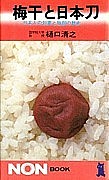江戸時代には武士の人口は約7%だったので、現在も武士の子孫は7%程度と推測できよう。国民の大多数は農民だったはずだが、武士道は本当に、日本精神を代表するものなのだろうか。
武士道というと葉隠を連想する人が多い。「武士道とは死ぬことと見つけたり」のくだりは有名だが、武家政権が確立された江戸時代には、戦のない世となり、武士の存在意義はかえって失われたから、武士の偉大さはその役割ではなく、むしろ観念論的に論じられたことだろう。江戸時代中期にはすでに、葉隠的武士道は現実にまるでそぐわず(戦死する可能性がないから)建前とみなされていたのではないかと思われる。このころ出た生類哀れみの令は、軍事政権でありながら生命尊重が謳われ、将軍綱吉自身も学問を愛しており、葉隠的武士道とは相容れないものである。ちなみにこの政令は、人の間の身分差別が放置され、人権思想が成熟しないうちに一足飛びに動物愛護が謳われ、しかも将軍自身が子に恵まれないのは前世の行いが原因とする迷信に基づいているなど、当時の庶民は全くついて行くことはできなかっであろうことは想像に難くない。
近代戦争では兵の多寡が決定的要素となり、徴兵制による近代軍隊創設のためには、武士だけが戦士であるという思想はかえって邪魔であるから、明治新政府が武士階級を解体したのは当然であろう。徴兵制に先だち長州藩も奇兵隊を創設している。葉隠的武士道が強調されるようになったのは、かえって武士階級が廃止された後の、軍人精神が国民に広く行きとどいた軍国主義の時代ではなかろうか。「生きて虜囚の辱めを受けず」で有名な戦陣訓は、現実の戦では兵力の消耗は戒められるから、精神論の色彩が非常に強いと言えるだろう。
今日軍国主義も過去のものとなったが、現在では時代劇が大きな影響を与えている。国民の大多数は農民のはずだが、時代劇では確実に武士が主人公で、設定はたいてい江戸時代である。主人公においては葉隠的な架空の武士の美学が誇張され、代官はたいてい腐敗していて、商人は強欲で屋号はたいてい越後屋であり、農民は無力・無学で一方的に搾取され、領主の慈悲を希うばかりで自分たちが主体的に政治を変えようとは決して思わない存在として描かれている。実際には一揆はたびたび起こったし、寺子屋では武士とともに庄屋・有力商人の子弟が机を並べて学んだ。武士が町人を斬り捨てても警察の追求を受けないというのもフィクションである。このようなステロタイプから視聴者は、政治家は腹黒く、企業は腐敗し、庶民は無力で無抵抗だというメッセージしか受け取らないだろう。時代劇の予定調和的ワンパターンも問題だが、特にラストに見られる印籠とジェノサイドは、権力と暴力が絶対だという印象を視聴者に与えかねない。助さん格さんは大量殺戮兵器であり、ジュネーブ協定違反である。
日本人の国民性は江戸時代に形成されたと言われているから、それ以前の国民性・文化性は失われたことになる。江戸時代の日本人も時代劇を愛していた。ここでいう「時代劇」とは江戸時代の現代劇のことであり、いかなる時代の題材であってもその通念、慣習、風俗、衣装、言語などは江戸時代のものである。曽我兄弟仇討ちは鎌倉時代の事件だが、江戸時代にはすでにこの時代劇があった。もちろん江戸時代の「(観念論的)武士道」精神に基づいたものであり、決して当時の通念に基づくものではない。
細川内閣が成立した1993年、私はカナダに在住していた。細川首相は就任にあたり「商人政治を排し、武家政治を行う」と語っていた。その意味は、自民党の利権政治を「商人政治」と捉え批判し、気品と節制ある政治を「武家政治」と捉えたのだろうが、これも時代劇という名のフィクションに幻惑されているだろう。細川首相はかつて時代劇に殿様役で出演したことがあったが、ニューズウィーク北米版にちょんまげ姿の写真が掲載され「武家政治」などと語られたのでは、失政があったらハラキリでもするのではないかと読者が誤解しかねないと心配したものである。
武士道というと葉隠を連想する人が多い。「武士道とは死ぬことと見つけたり」のくだりは有名だが、武家政権が確立された江戸時代には、戦のない世となり、武士の存在意義はかえって失われたから、武士の偉大さはその役割ではなく、むしろ観念論的に論じられたことだろう。江戸時代中期にはすでに、葉隠的武士道は現実にまるでそぐわず(戦死する可能性がないから)建前とみなされていたのではないかと思われる。このころ出た生類哀れみの令は、軍事政権でありながら生命尊重が謳われ、将軍綱吉自身も学問を愛しており、葉隠的武士道とは相容れないものである。ちなみにこの政令は、人の間の身分差別が放置され、人権思想が成熟しないうちに一足飛びに動物愛護が謳われ、しかも将軍自身が子に恵まれないのは前世の行いが原因とする迷信に基づいているなど、当時の庶民は全くついて行くことはできなかっであろうことは想像に難くない。
近代戦争では兵の多寡が決定的要素となり、徴兵制による近代軍隊創設のためには、武士だけが戦士であるという思想はかえって邪魔であるから、明治新政府が武士階級を解体したのは当然であろう。徴兵制に先だち長州藩も奇兵隊を創設している。葉隠的武士道が強調されるようになったのは、かえって武士階級が廃止された後の、軍人精神が国民に広く行きとどいた軍国主義の時代ではなかろうか。「生きて虜囚の辱めを受けず」で有名な戦陣訓は、現実の戦では兵力の消耗は戒められるから、精神論の色彩が非常に強いと言えるだろう。
今日軍国主義も過去のものとなったが、現在では時代劇が大きな影響を与えている。国民の大多数は農民のはずだが、時代劇では確実に武士が主人公で、設定はたいてい江戸時代である。主人公においては葉隠的な架空の武士の美学が誇張され、代官はたいてい腐敗していて、商人は強欲で屋号はたいてい越後屋であり、農民は無力・無学で一方的に搾取され、領主の慈悲を希うばかりで自分たちが主体的に政治を変えようとは決して思わない存在として描かれている。実際には一揆はたびたび起こったし、寺子屋では武士とともに庄屋・有力商人の子弟が机を並べて学んだ。武士が町人を斬り捨てても警察の追求を受けないというのもフィクションである。このようなステロタイプから視聴者は、政治家は腹黒く、企業は腐敗し、庶民は無力で無抵抗だというメッセージしか受け取らないだろう。時代劇の予定調和的ワンパターンも問題だが、特にラストに見られる印籠とジェノサイドは、権力と暴力が絶対だという印象を視聴者に与えかねない。助さん格さんは大量殺戮兵器であり、ジュネーブ協定違反である。
日本人の国民性は江戸時代に形成されたと言われているから、それ以前の国民性・文化性は失われたことになる。江戸時代の日本人も時代劇を愛していた。ここでいう「時代劇」とは江戸時代の現代劇のことであり、いかなる時代の題材であってもその通念、慣習、風俗、衣装、言語などは江戸時代のものである。曽我兄弟仇討ちは鎌倉時代の事件だが、江戸時代にはすでにこの時代劇があった。もちろん江戸時代の「(観念論的)武士道」精神に基づいたものであり、決して当時の通念に基づくものではない。
細川内閣が成立した1993年、私はカナダに在住していた。細川首相は就任にあたり「商人政治を排し、武家政治を行う」と語っていた。その意味は、自民党の利権政治を「商人政治」と捉え批判し、気品と節制ある政治を「武家政治」と捉えたのだろうが、これも時代劇という名のフィクションに幻惑されているだろう。細川首相はかつて時代劇に殿様役で出演したことがあったが、ニューズウィーク北米版にちょんまげ姿の写真が掲載され「武家政治」などと語られたのでは、失政があったらハラキリでもするのではないかと読者が誤解しかねないと心配したものである。
|
|
|
|
コメント(12)
こんにちは
武士の子孫、かつ、被差別部落の子孫です。
これは父方と母方の江戸時代の身分なんですが、本当は曾祖父母だけで32通りの身分があるんでしょうね。なので、武士の子孫は7%よりもう少し多いんでないかと…文明開化バンザイ(笑)
さて、本題ですが、うちの曾祖父の前の代に姓が一度変わったそうです。
理由は、境港の田舎侍でしたが、ある霧の深い日に曾曾祖父の前を塞ぐように歩く人影があり「無礼な!」と斬り付けたところ、目の不自由な身分の高い僧侶で、お家取り潰しの騒動になりかけて慌てて名字を変えたとか。その後明治維新になり、元の姓に戻ることができ、今は私が名乗ってます。
これって、身分の高い僧侶じゃなくて普通の町人だったらお咎めなしだったんですよね?
だから、私は江戸時代ってなんてバイオレンス!と思ってしまいます。
でも、汚職する商人がいつも『越後屋』なのはステレオタイプですよね。
ヨーロッパにおけるユダヤ人差別と同じ臭いを感じてしまいます。
でも、どうしても越後人=田中角栄とイメージしてしまうことをお許しください。
武士の子孫、かつ、被差別部落の子孫です。
これは父方と母方の江戸時代の身分なんですが、本当は曾祖父母だけで32通りの身分があるんでしょうね。なので、武士の子孫は7%よりもう少し多いんでないかと…文明開化バンザイ(笑)
さて、本題ですが、うちの曾祖父の前の代に姓が一度変わったそうです。
理由は、境港の田舎侍でしたが、ある霧の深い日に曾曾祖父の前を塞ぐように歩く人影があり「無礼な!」と斬り付けたところ、目の不自由な身分の高い僧侶で、お家取り潰しの騒動になりかけて慌てて名字を変えたとか。その後明治維新になり、元の姓に戻ることができ、今は私が名乗ってます。
これって、身分の高い僧侶じゃなくて普通の町人だったらお咎めなしだったんですよね?
だから、私は江戸時代ってなんてバイオレンス!と思ってしまいます。
でも、汚職する商人がいつも『越後屋』なのはステレオタイプですよね。
ヨーロッパにおけるユダヤ人差別と同じ臭いを感じてしまいます。
でも、どうしても越後人=田中角栄とイメージしてしまうことをお許しください。
すみません、問題提起をよく見ずにコメントしていたようです。
まず、問題として
〇『武士』というものの実際と『武士道』が乖離している。
〇しかも『武士道』は日本人の精神と言われているがそれでよいのか。
という議論をすればよいのですよね?
それでもって
凸よしよし横槍叩け!さんが、武士の実情にあわせた武士道の解釈と、明治期の武士道の由来『新渡戸武士道』を指摘されています。
はちみつさんは、『武士』と一括りにされているものを掘り下げておられます。
思うに、『武士道』イデオロギーは明治期に新渡戸によりまとめられましたが、明治政府に都合がよいから教育などの場面でも採用された…と考えたらスッキリするのではないでしょうか?
当時の天皇中心の中央集権国家を(江戸時代までの領主による封建的体制を解体して)全国民を直接支配下に置くには、官僚武士の建前を元にした『武士道イデオロギー』を日本人の精神として教えるのが近道です。
本来の武士の姿に則した『武士道』は…私は史料にあまりあたったことありませんが、官僚的側面と封建領主的な側面があったんでしょうね。
一つ言えるのは、昔は現代と違って社会的身分を決定する第一条件が『血統』でした。現代でも全くなくなったわけではありませんが、少なくとも学歴や能力など別の条件がより上位に来ています。
支配階級に就く権利があたえられていた血統を持つ人々…これが貴族と武士であって、ただそのチャンスを使っていた人、いなかった人それぞれですが、現代みたいな人権意識はないし、人口のほとんど大多数の人々はそんな権利などなくて全然別の原理で生活していたんでしょうね。
まず、問題として
〇『武士』というものの実際と『武士道』が乖離している。
〇しかも『武士道』は日本人の精神と言われているがそれでよいのか。
という議論をすればよいのですよね?
それでもって
凸よしよし横槍叩け!さんが、武士の実情にあわせた武士道の解釈と、明治期の武士道の由来『新渡戸武士道』を指摘されています。
はちみつさんは、『武士』と一括りにされているものを掘り下げておられます。
思うに、『武士道』イデオロギーは明治期に新渡戸によりまとめられましたが、明治政府に都合がよいから教育などの場面でも採用された…と考えたらスッキリするのではないでしょうか?
当時の天皇中心の中央集権国家を(江戸時代までの領主による封建的体制を解体して)全国民を直接支配下に置くには、官僚武士の建前を元にした『武士道イデオロギー』を日本人の精神として教えるのが近道です。
本来の武士の姿に則した『武士道』は…私は史料にあまりあたったことありませんが、官僚的側面と封建領主的な側面があったんでしょうね。
一つ言えるのは、昔は現代と違って社会的身分を決定する第一条件が『血統』でした。現代でも全くなくなったわけではありませんが、少なくとも学歴や能力など別の条件がより上位に来ています。
支配階級に就く権利があたえられていた血統を持つ人々…これが貴族と武士であって、ただそのチャンスを使っていた人、いなかった人それぞれですが、現代みたいな人権意識はないし、人口のほとんど大多数の人々はそんな権利などなくて全然別の原理で生活していたんでしょうね。
「葉隠」の著者山本常朝は、1659年に生まれた。山本の祖父と父は島原の乱(1637年)に出征した。常朝は父が70歳の時に成した子で、体が弱く20歳までは生きられないだろうと言われていた。彼は11歳のときに父を亡くし、小姓として仕官した。
民衆は元禄の太平を謳歌し、時代は町人の世になりつつあった。武士が命を賭けて戦う時代はとっくに終わり、武士階級は有名無実の存在になりつつあった。藩主鍋島光茂が亡くなったとき、山本は名誉ある殉死を遂げようとするが、光茂が追腹を禁止していたため果たせず、出家した。「葉隠」は彼が晩年に著した、彼の理想とする武士道を論じたものである。彼は実戦経験はなく、彼の武士としてのキャリアの全ては、側用人であった。
「武士道」精神は、江戸期以降とそれ以前では大きく異なる。鎌倉期には武士は平時には田畑を耕し、有事には所領を守るためがむしゃらに働いた。戦国期には戦が日常化し、生き残るためには手段を選ぶ余裕はなく、裏切り、寝返り、主殺しすら行われた。弱い主君は見捨てられて当然の時代だった。
だが江戸時代になると武士と農民が完全に分離し、戦がなくなった。藩主は戦のない時代に新規の雇用を行わないから、武士に必要とされたのは戦うノウハウではなく忠誠心である。朱子学の影響を受け林羅山や山鹿素行らによって作り上げられた江戸期の武士道は、特に「士道」と呼ばれている(狭義の武士道)が、それは存在意義を失った武士階級に、観念論的立場から新たな存在理由を与えるものだった。
昭和初期は、日本人が文字通り命を懸けて戦っていた時代であり、山本が生きた太平の時代でもなければ、兵法が観念論で語られることが許された時代でもない。実戦では戦力の浪費は厳に戒められる。勝てる見込みがなければ後退し、兵を補強して勝てる体制にしてから再び決戦を挑むのが兵法の常道である。江戸時代二百数十年は軍事政権とはいえ、実戦経験もなければそのノウハウも失われていた。日本軍に誤った形で導入された「狭義の武士道」がどれほどの災難をもたらしたか、国民は真剣に考えるべきであろう。
民衆は元禄の太平を謳歌し、時代は町人の世になりつつあった。武士が命を賭けて戦う時代はとっくに終わり、武士階級は有名無実の存在になりつつあった。藩主鍋島光茂が亡くなったとき、山本は名誉ある殉死を遂げようとするが、光茂が追腹を禁止していたため果たせず、出家した。「葉隠」は彼が晩年に著した、彼の理想とする武士道を論じたものである。彼は実戦経験はなく、彼の武士としてのキャリアの全ては、側用人であった。
「武士道」精神は、江戸期以降とそれ以前では大きく異なる。鎌倉期には武士は平時には田畑を耕し、有事には所領を守るためがむしゃらに働いた。戦国期には戦が日常化し、生き残るためには手段を選ぶ余裕はなく、裏切り、寝返り、主殺しすら行われた。弱い主君は見捨てられて当然の時代だった。
だが江戸時代になると武士と農民が完全に分離し、戦がなくなった。藩主は戦のない時代に新規の雇用を行わないから、武士に必要とされたのは戦うノウハウではなく忠誠心である。朱子学の影響を受け林羅山や山鹿素行らによって作り上げられた江戸期の武士道は、特に「士道」と呼ばれている(狭義の武士道)が、それは存在意義を失った武士階級に、観念論的立場から新たな存在理由を与えるものだった。
昭和初期は、日本人が文字通り命を懸けて戦っていた時代であり、山本が生きた太平の時代でもなければ、兵法が観念論で語られることが許された時代でもない。実戦では戦力の浪費は厳に戒められる。勝てる見込みがなければ後退し、兵を補強して勝てる体制にしてから再び決戦を挑むのが兵法の常道である。江戸時代二百数十年は軍事政権とはいえ、実戦経験もなければそのノウハウも失われていた。日本軍に誤った形で導入された「狭義の武士道」がどれほどの災難をもたらしたか、国民は真剣に考えるべきであろう。
三島由紀夫は生来病弱だったが、祖母夏子は常陸松平家の血を引き、三島に貴族趣味を仕込み男の子らしい遊びは一切禁止した。痩身で背も低かった三島の学習院時代の綽名は「アオジロ」。1945年入隊通知を受け取り、遺書を書くが、入隊試験のとき風邪をひいたのを肺浸潤と誤診され、入隊を免れる。東京大学卒業後、日本勧業銀行の入行試験を受験するが健康上の理由により不採用となる。虚弱体質は彼の大きなコンプレックスであり、強さに憧れた彼は1960年頃からボディビルを始め、見違えるように筋肉をつけると、進んで映画に出演したり写真集を出したりするなど、その鍛え上げられた肉体を積極的に披露しするようになった。
1970年、盾の会メンバーとともに陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地を訪れた三島は、総監を人質にとり自衛官に「諸君は武士だろう、武士ならば自分を否定する憲法をどうして守るんだ」と叫び決起を促したが、総監を騙して人質に取った三島に「バカヤロー」の野次が浴びせられ、三島は総監室で切腹した。腹部に13センチ、深さ5センチにわたって切り裂いたため腸が露出し、弟子の森田必勝が介錯したものの二度も失敗して刀を曲げてしまい、有段者の古賀浩靖に交代してやっと果たせた。
三島は作家であり、国の改革を訴えるならまさにペンを握りメディアを通して訴えるべきところを、なぜ武力クーデターによって実行しようとしたのだろうか。また自殺するなら頭部を銃で撃てば楽に死ねるものを、なぜこれほど壮絶な死に方を選んだのか。三島はその理由を、おそらく自覚できなかっただろう。
このごろインターネットを見ていると、口先だけ威勢のいいことを言って、それを実現する裏づけを欠いた安易な感情論が多いことに気づく。「今の若者はたるんでいるから徴兵制で鍛え直すべきだ」などと言う人に実際会ってみると、戦争も軍隊も知らない、線の細い青二才だったりするのだ。安倍首相のフレーズ「美しい国」「戦後レジームからの脱却」もまた観念論的で、現実感を欠いていた。彼もまた健康上の理由で、その任を辞した。
新撰組も多摩の農民出身が多く、剣術でのし上がり武士になることに憧れたが、局長の近藤が大名になる約束を得たとき、武士の時代は終わろうとしていた。局中法度が「士道ニ背キ間敷事」で始まり、これに反したときは切腹せねばならないことは広く知られている。
世の中には女・子供・老人が必ずおり、病人・障害者の類も存在する。皆が健康でもなければ、優秀なわけでもなく、持病を抱えて日々暮らしている者もあるだろう。何でも得意な人はいないのだから、人は内にある弱さを受け容れねばならない。国も皆が大国ではなく小国もあるから、小国には小国なりの身の処し方もあるだろう。それを蔑むようなやり方は、愛のある態度と言えるだろか。己の弱さを頑なに拒絶し、マッチョな生き方に徹することは、本当の強さだろうか。
己の弱さを直視し、受け容れていくことで、他者の弱さも受け容れることができる。騎士道精神とは本来そのようなものであり、何事も力に訴えることでもなければ、人の内にある弱さを蔑むことでもなかっただろう。
1970年、盾の会メンバーとともに陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地を訪れた三島は、総監を人質にとり自衛官に「諸君は武士だろう、武士ならば自分を否定する憲法をどうして守るんだ」と叫び決起を促したが、総監を騙して人質に取った三島に「バカヤロー」の野次が浴びせられ、三島は総監室で切腹した。腹部に13センチ、深さ5センチにわたって切り裂いたため腸が露出し、弟子の森田必勝が介錯したものの二度も失敗して刀を曲げてしまい、有段者の古賀浩靖に交代してやっと果たせた。
三島は作家であり、国の改革を訴えるならまさにペンを握りメディアを通して訴えるべきところを、なぜ武力クーデターによって実行しようとしたのだろうか。また自殺するなら頭部を銃で撃てば楽に死ねるものを、なぜこれほど壮絶な死に方を選んだのか。三島はその理由を、おそらく自覚できなかっただろう。
このごろインターネットを見ていると、口先だけ威勢のいいことを言って、それを実現する裏づけを欠いた安易な感情論が多いことに気づく。「今の若者はたるんでいるから徴兵制で鍛え直すべきだ」などと言う人に実際会ってみると、戦争も軍隊も知らない、線の細い青二才だったりするのだ。安倍首相のフレーズ「美しい国」「戦後レジームからの脱却」もまた観念論的で、現実感を欠いていた。彼もまた健康上の理由で、その任を辞した。
新撰組も多摩の農民出身が多く、剣術でのし上がり武士になることに憧れたが、局長の近藤が大名になる約束を得たとき、武士の時代は終わろうとしていた。局中法度が「士道ニ背キ間敷事」で始まり、これに反したときは切腹せねばならないことは広く知られている。
世の中には女・子供・老人が必ずおり、病人・障害者の類も存在する。皆が健康でもなければ、優秀なわけでもなく、持病を抱えて日々暮らしている者もあるだろう。何でも得意な人はいないのだから、人は内にある弱さを受け容れねばならない。国も皆が大国ではなく小国もあるから、小国には小国なりの身の処し方もあるだろう。それを蔑むようなやり方は、愛のある態度と言えるだろか。己の弱さを頑なに拒絶し、マッチョな生き方に徹することは、本当の強さだろうか。
己の弱さを直視し、受け容れていくことで、他者の弱さも受け容れることができる。騎士道精神とは本来そのようなものであり、何事も力に訴えることでもなければ、人の内にある弱さを蔑むことでもなかっただろう。
●相撲と武士道
相撲は興行であり、武道ではない。かつて庶民による草相撲と、武士が戦場での組み打ちの鍛錬で行う武家相撲があり、現在の大相撲は庶民の見世物が発展したものである。
19代横綱常陸山谷右エ門は、水戸藩の上級武士の家に生まれた。子供のころから怪力を発揮した常陸山は、力士入門を志したが、父は猛反対した。明治の初めに武士は廃止されたが、相撲は芝居や狂言と同じ見世物であり、身分の低い者のすることで上級士族のすることではなかったからである。常陸山の弟は、東京朝日新聞で「力だけの商売をしている芸人のことですから、私共も肩身が狭い」と語っている。
文明開化が本格化すると、いまだに髷を結いまわしを巻いて興行する相撲は前時代の遺物とみなされ、相撲廃止論が当然のように起こった。このような時代に、角界では異例の士族出身力士である常陸山は「力士は武士であれ」と説いた。タニマチがいて八百長もあったと思われる時代のことである。このように相撲は、歴史的に武士道とは無関係である。
古くからの伝統と思われている大部屋方式もちゃんこ鍋も後援会も国技館も、みな常陸山がルーツであり、彼は角界中興の祖として「角聖」と呼ばれている。明治42年に両国に完成した相撲常設館は、「国技館」の名称で呼ばれたが、それは見世物小屋としてデザインされていた。
なお横綱土俵入りに露払いと太刀持ちを従える習慣は、寛政期に谷風と小野川が初めて横綱土俵入りを行ったときに考案され、今日に続いているものである。
相撲は興行であり、武道ではない。かつて庶民による草相撲と、武士が戦場での組み打ちの鍛錬で行う武家相撲があり、現在の大相撲は庶民の見世物が発展したものである。
19代横綱常陸山谷右エ門は、水戸藩の上級武士の家に生まれた。子供のころから怪力を発揮した常陸山は、力士入門を志したが、父は猛反対した。明治の初めに武士は廃止されたが、相撲は芝居や狂言と同じ見世物であり、身分の低い者のすることで上級士族のすることではなかったからである。常陸山の弟は、東京朝日新聞で「力だけの商売をしている芸人のことですから、私共も肩身が狭い」と語っている。
文明開化が本格化すると、いまだに髷を結いまわしを巻いて興行する相撲は前時代の遺物とみなされ、相撲廃止論が当然のように起こった。このような時代に、角界では異例の士族出身力士である常陸山は「力士は武士であれ」と説いた。タニマチがいて八百長もあったと思われる時代のことである。このように相撲は、歴史的に武士道とは無関係である。
古くからの伝統と思われている大部屋方式もちゃんこ鍋も後援会も国技館も、みな常陸山がルーツであり、彼は角界中興の祖として「角聖」と呼ばれている。明治42年に両国に完成した相撲常設館は、「国技館」の名称で呼ばれたが、それは見世物小屋としてデザインされていた。
なお横綱土俵入りに露払いと太刀持ちを従える習慣は、寛政期に谷風と小野川が初めて横綱土俵入りを行ったときに考案され、今日に続いているものである。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=35048905&comm_id=87326&page=all
>9 ゆうじ(山本)
>軽薄なサムライ・ファッションを持ち出す人は、自分のルーツを真剣に考えたことがあるのかな、とときどき思います。「農民」はかっこよくない被支配階級だ、という意識があるのでしょうか。先祖が農家という人は、相当多いはずなのに。私もそうですが。今や土とは縁のない生活をしている以上、もはや農民がルーツというにはおこがましいかもしれませんけどね。
>アメリカの黒人の意識のめざめと比較すると興味深いです。白人へのアンビヴァレントな感情を乗り越えて、魅力的な文化を創ってきたのではないでしょうか。サムライ・ファッションに憧れる人は、「白人文化をひたすら礼賛する黒人」がそうでない黒人からどう見えたかについて考えてほしいと思います。
>9 ゆうじ(山本)
>軽薄なサムライ・ファッションを持ち出す人は、自分のルーツを真剣に考えたことがあるのかな、とときどき思います。「農民」はかっこよくない被支配階級だ、という意識があるのでしょうか。先祖が農家という人は、相当多いはずなのに。私もそうですが。今や土とは縁のない生活をしている以上、もはや農民がルーツというにはおこがましいかもしれませんけどね。
>アメリカの黒人の意識のめざめと比較すると興味深いです。白人へのアンビヴァレントな感情を乗り越えて、魅力的な文化を創ってきたのではないでしょうか。サムライ・ファッションに憧れる人は、「白人文化をひたすら礼賛する黒人」がそうでない黒人からどう見えたかについて考えてほしいと思います。
ヨーロッパ人がアメリカのイロコイ族と出遭ったとき、そこには女系社会があった。遺産は母から娘へと相続され、子は母の氏族に属した。子を産むのは母親だから、男系相続では他人の子に財産を奪われる可能性があるからである。
イロコイ族の政治のユニークな点として、女性参政権が挙げられる。各部族はまず女性だけの選挙で族母を選出し、族母が族長を指名した。族長が「偉大なる平和憲章」に違反した場合、族母はこれを罷免することができた。
旧世界もおそらく、昔は女系社会だったと思われる。これが男系社会に転換するのは、軍国主義の影響だろう。弓や槍などの武芸は、力のある男性にしかできず、外敵の侵略から村を守りあるいは不作の年に隣村から略奪する必要から、男性の発言力が拡大していったのではないだろうか。
時代が後になるほど女性の権利が拡大していったと考えるのは、必ずしも正しくない。かつて商家や農家の女性は家業に従事しており、専業主婦はまだ存在していなかった。ゆえに農家の女性が他家に嫁ぎ、その家になじめない場合は、実家に帰ってまた家業に従事すればよかったのだ。ところが武家の女性は、戦の役に立たない。というより、江戸時代は戦がない。武家の女性は家業に従事することなく、登城して務めを果たす夫の「留守を守る」のみであった。商家や農家に比べると、離縁された武家の女性には居場所はなく、その悲惨さは四谷怪談などで語られているとおりである。
日本の離婚率は1883年3.38%、1890年2.73%だったのが、明治民法施行の1898年を境に激減した。1900年1.46%、1910年1.21%と推移して、1920年には0.9%とついに0%台に落ち込み、再び1%台に上昇する1980年まで続くことになる。江戸時代の離婚率に至っては、陸奥国某村では4.8%と、現代のアメリカをも上回っていた。時代が後に行くほど離婚率が高くなると思うのは誤りで、離婚率減少は明治民法と深い関係にあると考えざるをえない。
明治政府が武士階級を解体したのは、国民皆兵を実施するには武士だけが戦士だという思想はかえって邪魔になるからだ。逆接的だが、武士階級の解体によって武士道精神はかえって国民に広く伝播した。徴兵は男子のみに実施されたので、参政権は男性のみ認められ、遺産の相続もほとんど男性の専権事項となった。
1920年には労働人口の半分・総人口の25%もいた農業は、1960年には労働人口の30% 、総人口の15%にまで減少した。代わって増加したのはサラリーマンで、1975年には労働人口の70%を占めるに至った。彼らは家業ではなく通勤したので、登城して務める武家のスタイルを模倣した。こうして女性たちは家業を失い、夫の留守を守る身となった。現に、機械化以前の炊事・洗濯は重労働だったので、この時代に女性の社会進出は考えにくく、政府も主婦のため所得税の配偶者控除を行った。
北欧では増加する老人人口を支えていくために、女性も就業している。少子化が進行し、家事が重労働でなくなった今、「女は家にいるもの」という価値観には何の合理性も見出せないように思う。女性はもともと仕事をもっていたのであり、「女は家を守るもの」「男は女を養うもの」という発想は、歪曲された武士道精神に由来する誤伝であろう。
イロコイ族の政治のユニークな点として、女性参政権が挙げられる。各部族はまず女性だけの選挙で族母を選出し、族母が族長を指名した。族長が「偉大なる平和憲章」に違反した場合、族母はこれを罷免することができた。
旧世界もおそらく、昔は女系社会だったと思われる。これが男系社会に転換するのは、軍国主義の影響だろう。弓や槍などの武芸は、力のある男性にしかできず、外敵の侵略から村を守りあるいは不作の年に隣村から略奪する必要から、男性の発言力が拡大していったのではないだろうか。
時代が後になるほど女性の権利が拡大していったと考えるのは、必ずしも正しくない。かつて商家や農家の女性は家業に従事しており、専業主婦はまだ存在していなかった。ゆえに農家の女性が他家に嫁ぎ、その家になじめない場合は、実家に帰ってまた家業に従事すればよかったのだ。ところが武家の女性は、戦の役に立たない。というより、江戸時代は戦がない。武家の女性は家業に従事することなく、登城して務めを果たす夫の「留守を守る」のみであった。商家や農家に比べると、離縁された武家の女性には居場所はなく、その悲惨さは四谷怪談などで語られているとおりである。
日本の離婚率は1883年3.38%、1890年2.73%だったのが、明治民法施行の1898年を境に激減した。1900年1.46%、1910年1.21%と推移して、1920年には0.9%とついに0%台に落ち込み、再び1%台に上昇する1980年まで続くことになる。江戸時代の離婚率に至っては、陸奥国某村では4.8%と、現代のアメリカをも上回っていた。時代が後に行くほど離婚率が高くなると思うのは誤りで、離婚率減少は明治民法と深い関係にあると考えざるをえない。
明治政府が武士階級を解体したのは、国民皆兵を実施するには武士だけが戦士だという思想はかえって邪魔になるからだ。逆接的だが、武士階級の解体によって武士道精神はかえって国民に広く伝播した。徴兵は男子のみに実施されたので、参政権は男性のみ認められ、遺産の相続もほとんど男性の専権事項となった。
1920年には労働人口の半分・総人口の25%もいた農業は、1960年には労働人口の30% 、総人口の15%にまで減少した。代わって増加したのはサラリーマンで、1975年には労働人口の70%を占めるに至った。彼らは家業ではなく通勤したので、登城して務める武家のスタイルを模倣した。こうして女性たちは家業を失い、夫の留守を守る身となった。現に、機械化以前の炊事・洗濯は重労働だったので、この時代に女性の社会進出は考えにくく、政府も主婦のため所得税の配偶者控除を行った。
北欧では増加する老人人口を支えていくために、女性も就業している。少子化が進行し、家事が重労働でなくなった今、「女は家にいるもの」という価値観には何の合理性も見出せないように思う。女性はもともと仕事をもっていたのであり、「女は家を守るもの」「男は女を養うもの」という発想は、歪曲された武士道精神に由来する誤伝であろう。
例えば武士が、朝廷からの使者に出した食事が腐っていたというような、重大なチョンボを犯した場合は、切腹しなければならない。本人が死にたくなくて逃亡(逐電という)した場合、その家はお役御免となる。責任を取って腹を切れば、罪は許され、息子がまた取り立てられることになる。どうやら、人間誰でも失敗はするから、最も大切な命をもって贖えば許されたようだ。また個人の人命より、家の存続や体面の方が重んじられた。
高貴な身分の人が一人で出歩くことは考えられず、供の者を必ず連れている。さて供の者を連れて歩いている二人組が、刀を持った暴漢5人に襲われた場合、どうすべきだろうか。
2対5では勝ち目がないからと主人を見捨てて逃亡するのは、絶対に不可であり、間違いなく手討ちにされる。供の者の務めは、主人を護衛することだからだ。では戦闘中に主人が殺害された場合、任務が消滅するため逃亡してもよいのだろうか。答えは不可である。主人を殺めた敵には、仇を討たなければならない。供の者が家に帰っていいのは、敵が全員逃亡した場合と、敵の全員を倒した場合のみである。
絶望的な状況でも、最後まで戦って死ねば「武士らしく最後まで立派に戦った」と賞賛され、その子が再び取り立てられる。たとえ主人が殺され、護衛の任務を果たせなかったとしてもである。そうなると、供の者は武士道をわきまえてさえいればよいのであって、武芸に秀でていることは必ずしも重要ではないことになる。
近代戦争では、兵力の浪費は厳に戒められる。しかし、絶望的な状況で無理な決戦をせず、いったん退却し兵力増強してから決戦を挑むというような兵法の常識は、日本軍では考慮されなかった。それぞれに守るべき拠点があり、絶望的状況でも逃げずに最後まで戦うことが求められた。玉砕は常に賞賛され、勝ち負けはあまり重視されなかったようだ。
国民皆兵実施のためには、武士だけが戦士であるという思想はじゃまになるので武士階級は解体されたが、武士道はかえって国民の間に浸透した。だが勝ち負けを冷徹に追求するのではなく、精神性を極度に重視する体質が、この国を悲惨な敗戦へと導いたのではないだろうか。
高貴な身分の人が一人で出歩くことは考えられず、供の者を必ず連れている。さて供の者を連れて歩いている二人組が、刀を持った暴漢5人に襲われた場合、どうすべきだろうか。
2対5では勝ち目がないからと主人を見捨てて逃亡するのは、絶対に不可であり、間違いなく手討ちにされる。供の者の務めは、主人を護衛することだからだ。では戦闘中に主人が殺害された場合、任務が消滅するため逃亡してもよいのだろうか。答えは不可である。主人を殺めた敵には、仇を討たなければならない。供の者が家に帰っていいのは、敵が全員逃亡した場合と、敵の全員を倒した場合のみである。
絶望的な状況でも、最後まで戦って死ねば「武士らしく最後まで立派に戦った」と賞賛され、その子が再び取り立てられる。たとえ主人が殺され、護衛の任務を果たせなかったとしてもである。そうなると、供の者は武士道をわきまえてさえいればよいのであって、武芸に秀でていることは必ずしも重要ではないことになる。
近代戦争では、兵力の浪費は厳に戒められる。しかし、絶望的な状況で無理な決戦をせず、いったん退却し兵力増強してから決戦を挑むというような兵法の常識は、日本軍では考慮されなかった。それぞれに守るべき拠点があり、絶望的状況でも逃げずに最後まで戦うことが求められた。玉砕は常に賞賛され、勝ち負けはあまり重視されなかったようだ。
国民皆兵実施のためには、武士だけが戦士であるという思想はじゃまになるので武士階級は解体されたが、武士道はかえって国民の間に浸透した。だが勝ち負けを冷徹に追求するのではなく、精神性を極度に重視する体質が、この国を悲惨な敗戦へと導いたのではないだろうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ここが変だよ比較文化論 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-