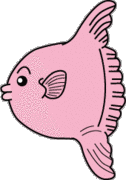|
|
|
|
コメント(1000)
吉本隆明「『四季』派の本質〜三好達治を中心に」『全著作集 5 』勁草書房 所収
「四季」派の詩人たちが、詩形と詩意識との先祖かえりを敢行したとき、必然的につきあたったのは、日本の恒常民衆の独特な残忍感覚と、やさしい美意識との共存という現象であった。このような伝統感性への先祖かえりが、現実社会からの逃亡によってはじめておこなわれたとかんがえるのはまちがっている。むしろ、三好が、本来的に強靭な生活者であり、リアルな日常生活感覚の把握者であることが、このような恒常民的な感性につきあたるおおきな原因をなしていることは、これらの戦争詩を、背後からささえている強い論理的感覚によって推定できるとおもう。
初出→『文学』昭和三十三年四月号
「四季」派の詩人たちが、詩形と詩意識との先祖かえりを敢行したとき、必然的につきあたったのは、日本の恒常民衆の独特な残忍感覚と、やさしい美意識との共存という現象であった。このような伝統感性への先祖かえりが、現実社会からの逃亡によってはじめておこなわれたとかんがえるのはまちがっている。むしろ、三好が、本来的に強靭な生活者であり、リアルな日常生活感覚の把握者であることが、このような恒常民的な感性につきあたるおおきな原因をなしていることは、これらの戦争詩を、背後からささえている強い論理的感覚によって推定できるとおもう。
初出→『文学』昭和三十三年四月号
奥野健男『歴史の斜面に立つ女たち〜文学のなかに女性像を追う』毎日新聞社
花子のモデルにされた武田百合子こそ、もっとも貞淑でもっとも淫乱に見える、しかも過去と未来とをつなぐ現在に生きる、可愛い、したたかな女性なのである。この花子的な女性によって文学者武田泰淳の後人生は発奮し刺激され、さまざまな秀作を書き、入れ歯もはめないまま、酒をのみのみあの世に行ってしまった。
大宅壮一が平林たい子は日本の女性で唯一人総理大臣にしたい人物だと絶賛していたが、からりとして私情をさしはさまない公平な観察、判断、実行など、いずれも男まさりで頼もしい感じがあった。…『自伝的交友録・実感的作家論』というエッセイをぼくはいつも座右に置いている。
花子のモデルにされた武田百合子こそ、もっとも貞淑でもっとも淫乱に見える、しかも過去と未来とをつなぐ現在に生きる、可愛い、したたかな女性なのである。この花子的な女性によって文学者武田泰淳の後人生は発奮し刺激され、さまざまな秀作を書き、入れ歯もはめないまま、酒をのみのみあの世に行ってしまった。
大宅壮一が平林たい子は日本の女性で唯一人総理大臣にしたい人物だと絶賛していたが、からりとして私情をさしはさまない公平な観察、判断、実行など、いずれも男まさりで頼もしい感じがあった。…『自伝的交友録・実感的作家論』というエッセイをぼくはいつも座右に置いている。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
マンボウ広場 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
マンボウ広場のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 38357人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209252人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28045人