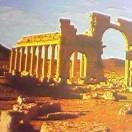12月1日、ユング心理学研究会セミナー「絵画をみる経験をめぐって」の講義が、東京大学駒場キャンパス ファカルティハウスにて開催されました。講師は、東海大学の田中彰吾先生です。
とても興味深い講義だったので、その内容をまとめておきたいと思いました。
○忘れられない経験
田中先生が、フランスで絵画の鑑賞三昧の日々を送られていたある時期、ゴッホの3枚の絵をみた瞬間、衝撃に打たれて足がピタッと止まり、15分くらい動けなくなったことがあったそうです。その3枚の絵とは、『二人の少女』『オーヴェールの教会』『自我像(オルセー美術館)』の絵でした。
(絵を探してみました http://
その絵をみた時、先生は、「絵をみているのは自分じゃない」という感じがしたそうです。「絵が向こうから見ることを要求してくるような感じ」「絵の魔力に捕らえられて、動けなくなっている感じ」がしたとおっしゃっていました。
ユング心理学的な言葉を使えば、ヌミノースな感情が沸き起こり、どうしようもなく惹きつけられる感覚と、それでいて、おいそれとは近づけない畏怖を感じたということです。おそらく元型が活発に動いていた瞬間だったのだろう、と先生はおっしゃっていました。
さて、メルロ・ポンティは、その著『眼と精神』の中で、こんなことを言っているそうです。
「森のなかで、私は幾度も私が森を見ているのではないと感じた。樹が私を見つめ、私に語りかけているように感じた日もある」
(アンドレ・マルシャンの言葉)P266
「山そのものがあちらから、自らを画家によって見られるようにするのであり、この山に向かって画家はその眼なざしで問いかけるのである」P264
これはつまり、「主体と客体が逆転した視覚経験」である、ということでした。
○見ることの誤解
私達はふつう、「見る」と言えば、“光がものに当たって反射した光を目で知覚している”と考えます。現実の姿が眼球と視神経を通じて脳へと伝達され、脳の内部(または心の内部)で現実のコピーを映し出している、と思っているのです。この考え方を「鏡モデル」と言うそうです。
しかし、ここで、「視覚」を捉えなおしてみよう、ということになりました。
?猫を用いた視覚実験(Held & Hein 1963)
(実験の内容について探してみたら、http://
この実験では、ゴンドラに入れられ自力歩行を奪われた猫は(外界の視覚は成立しているはずだが)「奥行き」の次元が欠けていることがわかりました。そして、このことから、「正常な知覚は運動と対になって成立している」ことが推測されました。
?開眼手術のあとで最初に見える世界
「ヴァージルはこの最初の瞬間のことを、何を見ているのかよくわからなかったと語った。光があり、動きがあり、色があったが、すべてがごっちゃになっていて、意味をなさず、ぼうっとしていた。そのぼんやりした塊のひとつが動いて、声がした。『どんなぐあいですか?』そこで初めて、この光と影の混沌とした塊が顔だと気づいた」O.サックス著『火星の人類学』P162
・生後14カ月で失明(赤の他2種類の色が分かる状態)、11歳で開眼手術したある人は、
↓
開眼手術後、黄色がとても鮮明に感じられた、ということでした。
・生後10カ月で失明(明暗はわかるが色はわからない状態)、12歳で開眼手術したある人は、
↓
開眼手術後、まぶしい。明るさは分かるが色はわからない、ということでした。
つまり、ゴンドラの中の猫も、開眼手術後の患者も、視覚世界が混沌としていて、「奥行き」や「形」がわからなかった、ということです。つまり、「見えているのに見えない」状態だったのです。
視覚は成立していますが、通常の意味では見えていない。彼らの見えの世界は、切れ目がなく、物も背景も分離しておらず、遠近感もない、というカオスの状態であることがわかります。
つまり、ここでも、「通常の視覚(見えの世界)は、運動や身体の動きと結びつくことで、意味のある視覚が成立している」ということがわかるのです。
○動きのシュミレーション
・G.アルチンボルド(1527-1593)の『春』
http://
(近くで見るか、遠くで見るかで、見え方が変わる)
・逆さ絵
http://
(まっすぐだと蛙が見えるが、絵を左に転がすと馬が見える)
・隠し絵
http://
(海と女性の横顔が見える)
以上の絵からわかることは、「ある対象(絵画・物・風景)を見るには、それを見るのにふさわしい距離・向き・角度がある」ということです。もっといえば、ふだん「私たちは、身体の動きを通じて対象を見るうえで適切な位置を探し当てている」のです。この身体の動きには、眼球の運動も含まれています(眼球の運動を止めると何も見えなくなるそうです。
Ex.エニグマ錯視 http://
真ん中の円一点をじっと見つめているつもりでも、チラチラするのは、眼球が動いているからなのだそうです)。
○「見る」ことの身体性
以上のことからわかることは、
・見る側の身体の動き・眼球の動きに伴って、見える世界は姿を変えること
・身体の運動があることで、形・奥行き・動きなどの意味をもつ視覚世界が成立すること
です。
つまり、「視覚」は、眼などの感覚器官があり、脳があるから見えている(鏡モデル)わけではないのです。
メルロ・ポンティは『眼と精神』でこのように言っているそうです。
「画家はその身体を世界に貸すことによって、世界を絵に変える。この化体を理解するためには、働いている現実の身体・・・視覚と運動のより糸であるような身体を取りもどさなくてはならない」P257
絵にかえる 見る
画家 ⇄ 世界 身体 ⇄ 世界
身体を貸す 動く
[画家の場合] [私たちの場合]
※画家は、この「見る」ことを鋭く意識している
・ラファエロの『アテネの学堂』
http://
・エッシャーの『滝』
http://
(「眼球だけを動かす時と身体を動かした時との“見え”の違い」「その空間に身体を入れた時と入れない時の“見え”の違い」を示唆しているのか?)
・ピカソの『ドラ・マールの肖像』http://
(キュビズム;正面や横から見た(アングルを変えた時の)世界の見え方の違いを示唆)
○「見る」とはどういうことか
?「見る」ことは、所与の客観的な世界のコピーを脳の内部(または心の内部)に表象することではありません。
?他方、「見る」ことは、主観的な心(または脳)の作用が世界の像を現出させることでもありません。
?世界像 ← 視覚 ?世界像 ← 心
眼球・視神経 想像
[客観][表象] [主観][表象]
??は夢や幻想とどこが違うの?
「見る」ことは、見る主体に身体があり、身体が世界の中で動き、行動することと共に生じてくるのです。(世界内存在モデル)
−−−−−−−−−−−−−−−
│ 身体 → 行動 │
│ 身体 ← 視覚 │
│ (世界) │
│ 色・形・奥行き・動き │
−−−−−−−−−−−−−−−
夢も、眼球の動きによって見ています。「REM(Rapid Eye Movement)睡眠」の時に、私たちは夢を見ていると言われています。
「見る」とは、
「まず、ある知覚があってそれにつづいてある運動がおこるといったものではなく、知覚と運動とはひとつの体系を形成し、それがひとつの全体として変容してゆくものだ」『知覚の現象学(1)』P192
「私の見るすべてのものは・・・「私がなしうる」ことの地図の上に定位されるのだ」『眼と精神』P257
ということです。
このように、私たちは、自分の身体をより深く世界に入れることで、対象とシンクロし、インタラクション(相互作用)し、世界を「見て」いるのです。
以上が、講義の内容でした。
○ ○ ○ ○ ○
そして、私はこの講義を聞いたあと、次のようなことを考えました。
?身体性(特に身体図式)とコンプレックスの関係
身体図式とは、誕生以来、個人の生活環境の中で身につけてきた行動様式とでもいったらよいのでしょうか。ある状態にさらされた時、瞬間的に思わずとってしまう行動の枠組み(スキーマ)のようなものだと、私個人は解釈しています。
これを認知面に置きかえれば、認知療法の「自動思考」と「スキーマ」という考え方になるのでしょうか。自動思考は(みんなが同じ状況下で同じ考え方や反応をするわけではなく)それぞれの成育歴や経験などによって習慣化され形づくられていくものと言われます。
で、この部分、ユング心理学的に考えると、私には、「個人的無意識」に属する概念のように思えてきたりするのですよね。
また、認知心理学には、「活性化拡散モデル」や「意味ネットワーク」とい考え方があり、ある単語が提示された時、その言葉と意味的につながっている言葉や記憶が同時に活性化され想起されやすくなる、という考え方があります。で、これを「情動」と「記憶」に置きかえると、ユングの言うコンプレックスとそっくりだな、と私は思うのです。
そうした個人個人がそれぞれ持つ身体図式(身体性)と対象が出会い、シンクロし、インタラクションする時、その個人独特の対象との出会い(「見る」体験)―衝撃―が生まれることもあるのではないか、と講義を聞きながら、考えました。
?身体性(特に身体図式)と元型の関係
一方、人間には、ヒトという「種」に特有の身体の動かし方もあります。ピアジェは、2歳までの子供は手を伸ばしてものに触ったり舐めたりして対象に働きかけ、その作用をうけることで感覚運動的知能を獲得する、というようなことを言っていたと思うのですが、そのような社会的対人的相互作用によって、私たちは、ヒト特有の身体性・身体図式を形作っている部分もあると思うのです。これは、「本能」といっても良い部分だと思います。
そして、この「本能的なもの」は、ユング心理学でいえば、「元型」にあたるのではないかと、私は思ったのです。
元型とは、太古の昔から人間がとってきた行動パターンの集積のようなものです。その行動パターンは「無意識」のうちに全ての人に繰り返されていきます。つまり、「種に特有の行動パターンを生じさせるもの=身体図式」は集合的無意識の部分に属するもののように私には感じられたのですよね。
そして、この元型的な行動パターンを生み出す身体図式と対象が共鳴しあうと、ヌミノースな「見る」体験が生まれるのではないか・・・とも考えました。
?夢と眼球運動の関係は、無意識と眼球運動(身体性)の関係を明らかにする?
フロイトは、「夢は無意識への王道である」と言いました。
考えてみれば、「夢」という現象は、とても不思議な現象です。瞼を閉じ、眼という感覚器官は何も見ていないはずなのに、私たちは映像(視覚)を認知するからです。そして、この「夢の映像・視覚」は「眼球運動」によって生まれるということでした。
以上のようなことを考えているうちに、夢と眼球運動、そして無意識と眼球運動、ひいては無意識と身体性との関連が、今後どんどん明らかになればいいな・・・なんて思い始め、とてもワクワクした気持ちになったのでした。
とても興味深い講義だったので、その内容をまとめておきたいと思いました。
○忘れられない経験
田中先生が、フランスで絵画の鑑賞三昧の日々を送られていたある時期、ゴッホの3枚の絵をみた瞬間、衝撃に打たれて足がピタッと止まり、15分くらい動けなくなったことがあったそうです。その3枚の絵とは、『二人の少女』『オーヴェールの教会』『自我像(オルセー美術館)』の絵でした。
(絵を探してみました http://
その絵をみた時、先生は、「絵をみているのは自分じゃない」という感じがしたそうです。「絵が向こうから見ることを要求してくるような感じ」「絵の魔力に捕らえられて、動けなくなっている感じ」がしたとおっしゃっていました。
ユング心理学的な言葉を使えば、ヌミノースな感情が沸き起こり、どうしようもなく惹きつけられる感覚と、それでいて、おいそれとは近づけない畏怖を感じたということです。おそらく元型が活発に動いていた瞬間だったのだろう、と先生はおっしゃっていました。
さて、メルロ・ポンティは、その著『眼と精神』の中で、こんなことを言っているそうです。
「森のなかで、私は幾度も私が森を見ているのではないと感じた。樹が私を見つめ、私に語りかけているように感じた日もある」
(アンドレ・マルシャンの言葉)P266
「山そのものがあちらから、自らを画家によって見られるようにするのであり、この山に向かって画家はその眼なざしで問いかけるのである」P264
これはつまり、「主体と客体が逆転した視覚経験」である、ということでした。
○見ることの誤解
私達はふつう、「見る」と言えば、“光がものに当たって反射した光を目で知覚している”と考えます。現実の姿が眼球と視神経を通じて脳へと伝達され、脳の内部(または心の内部)で現実のコピーを映し出している、と思っているのです。この考え方を「鏡モデル」と言うそうです。
しかし、ここで、「視覚」を捉えなおしてみよう、ということになりました。
?猫を用いた視覚実験(Held & Hein 1963)
(実験の内容について探してみたら、http://
この実験では、ゴンドラに入れられ自力歩行を奪われた猫は(外界の視覚は成立しているはずだが)「奥行き」の次元が欠けていることがわかりました。そして、このことから、「正常な知覚は運動と対になって成立している」ことが推測されました。
?開眼手術のあとで最初に見える世界
「ヴァージルはこの最初の瞬間のことを、何を見ているのかよくわからなかったと語った。光があり、動きがあり、色があったが、すべてがごっちゃになっていて、意味をなさず、ぼうっとしていた。そのぼんやりした塊のひとつが動いて、声がした。『どんなぐあいですか?』そこで初めて、この光と影の混沌とした塊が顔だと気づいた」O.サックス著『火星の人類学』P162
・生後14カ月で失明(赤の他2種類の色が分かる状態)、11歳で開眼手術したある人は、
↓
開眼手術後、黄色がとても鮮明に感じられた、ということでした。
・生後10カ月で失明(明暗はわかるが色はわからない状態)、12歳で開眼手術したある人は、
↓
開眼手術後、まぶしい。明るさは分かるが色はわからない、ということでした。
つまり、ゴンドラの中の猫も、開眼手術後の患者も、視覚世界が混沌としていて、「奥行き」や「形」がわからなかった、ということです。つまり、「見えているのに見えない」状態だったのです。
視覚は成立していますが、通常の意味では見えていない。彼らの見えの世界は、切れ目がなく、物も背景も分離しておらず、遠近感もない、というカオスの状態であることがわかります。
つまり、ここでも、「通常の視覚(見えの世界)は、運動や身体の動きと結びつくことで、意味のある視覚が成立している」ということがわかるのです。
○動きのシュミレーション
・G.アルチンボルド(1527-1593)の『春』
http://
(近くで見るか、遠くで見るかで、見え方が変わる)
・逆さ絵
http://
(まっすぐだと蛙が見えるが、絵を左に転がすと馬が見える)
・隠し絵
http://
(海と女性の横顔が見える)
以上の絵からわかることは、「ある対象(絵画・物・風景)を見るには、それを見るのにふさわしい距離・向き・角度がある」ということです。もっといえば、ふだん「私たちは、身体の動きを通じて対象を見るうえで適切な位置を探し当てている」のです。この身体の動きには、眼球の運動も含まれています(眼球の運動を止めると何も見えなくなるそうです。
Ex.エニグマ錯視 http://
真ん中の円一点をじっと見つめているつもりでも、チラチラするのは、眼球が動いているからなのだそうです)。
○「見る」ことの身体性
以上のことからわかることは、
・見る側の身体の動き・眼球の動きに伴って、見える世界は姿を変えること
・身体の運動があることで、形・奥行き・動きなどの意味をもつ視覚世界が成立すること
です。
つまり、「視覚」は、眼などの感覚器官があり、脳があるから見えている(鏡モデル)わけではないのです。
メルロ・ポンティは『眼と精神』でこのように言っているそうです。
「画家はその身体を世界に貸すことによって、世界を絵に変える。この化体を理解するためには、働いている現実の身体・・・視覚と運動のより糸であるような身体を取りもどさなくてはならない」P257
絵にかえる 見る
画家 ⇄ 世界 身体 ⇄ 世界
身体を貸す 動く
[画家の場合] [私たちの場合]
※画家は、この「見る」ことを鋭く意識している
・ラファエロの『アテネの学堂』
http://
・エッシャーの『滝』
http://
(「眼球だけを動かす時と身体を動かした時との“見え”の違い」「その空間に身体を入れた時と入れない時の“見え”の違い」を示唆しているのか?)
・ピカソの『ドラ・マールの肖像』http://
(キュビズム;正面や横から見た(アングルを変えた時の)世界の見え方の違いを示唆)
○「見る」とはどういうことか
?「見る」ことは、所与の客観的な世界のコピーを脳の内部(または心の内部)に表象することではありません。
?他方、「見る」ことは、主観的な心(または脳)の作用が世界の像を現出させることでもありません。
?世界像 ← 視覚 ?世界像 ← 心
眼球・視神経 想像
[客観][表象] [主観][表象]
??は夢や幻想とどこが違うの?
「見る」ことは、見る主体に身体があり、身体が世界の中で動き、行動することと共に生じてくるのです。(世界内存在モデル)
−−−−−−−−−−−−−−−
│ 身体 → 行動 │
│ 身体 ← 視覚 │
│ (世界) │
│ 色・形・奥行き・動き │
−−−−−−−−−−−−−−−
夢も、眼球の動きによって見ています。「REM(Rapid Eye Movement)睡眠」の時に、私たちは夢を見ていると言われています。
「見る」とは、
「まず、ある知覚があってそれにつづいてある運動がおこるといったものではなく、知覚と運動とはひとつの体系を形成し、それがひとつの全体として変容してゆくものだ」『知覚の現象学(1)』P192
「私の見るすべてのものは・・・「私がなしうる」ことの地図の上に定位されるのだ」『眼と精神』P257
ということです。
このように、私たちは、自分の身体をより深く世界に入れることで、対象とシンクロし、インタラクション(相互作用)し、世界を「見て」いるのです。
以上が、講義の内容でした。
○ ○ ○ ○ ○
そして、私はこの講義を聞いたあと、次のようなことを考えました。
?身体性(特に身体図式)とコンプレックスの関係
身体図式とは、誕生以来、個人の生活環境の中で身につけてきた行動様式とでもいったらよいのでしょうか。ある状態にさらされた時、瞬間的に思わずとってしまう行動の枠組み(スキーマ)のようなものだと、私個人は解釈しています。
これを認知面に置きかえれば、認知療法の「自動思考」と「スキーマ」という考え方になるのでしょうか。自動思考は(みんなが同じ状況下で同じ考え方や反応をするわけではなく)それぞれの成育歴や経験などによって習慣化され形づくられていくものと言われます。
で、この部分、ユング心理学的に考えると、私には、「個人的無意識」に属する概念のように思えてきたりするのですよね。
また、認知心理学には、「活性化拡散モデル」や「意味ネットワーク」とい考え方があり、ある単語が提示された時、その言葉と意味的につながっている言葉や記憶が同時に活性化され想起されやすくなる、という考え方があります。で、これを「情動」と「記憶」に置きかえると、ユングの言うコンプレックスとそっくりだな、と私は思うのです。
そうした個人個人がそれぞれ持つ身体図式(身体性)と対象が出会い、シンクロし、インタラクションする時、その個人独特の対象との出会い(「見る」体験)―衝撃―が生まれることもあるのではないか、と講義を聞きながら、考えました。
?身体性(特に身体図式)と元型の関係
一方、人間には、ヒトという「種」に特有の身体の動かし方もあります。ピアジェは、2歳までの子供は手を伸ばしてものに触ったり舐めたりして対象に働きかけ、その作用をうけることで感覚運動的知能を獲得する、というようなことを言っていたと思うのですが、そのような社会的対人的相互作用によって、私たちは、ヒト特有の身体性・身体図式を形作っている部分もあると思うのです。これは、「本能」といっても良い部分だと思います。
そして、この「本能的なもの」は、ユング心理学でいえば、「元型」にあたるのではないかと、私は思ったのです。
元型とは、太古の昔から人間がとってきた行動パターンの集積のようなものです。その行動パターンは「無意識」のうちに全ての人に繰り返されていきます。つまり、「種に特有の行動パターンを生じさせるもの=身体図式」は集合的無意識の部分に属するもののように私には感じられたのですよね。
そして、この元型的な行動パターンを生み出す身体図式と対象が共鳴しあうと、ヌミノースな「見る」体験が生まれるのではないか・・・とも考えました。
?夢と眼球運動の関係は、無意識と眼球運動(身体性)の関係を明らかにする?
フロイトは、「夢は無意識への王道である」と言いました。
考えてみれば、「夢」という現象は、とても不思議な現象です。瞼を閉じ、眼という感覚器官は何も見ていないはずなのに、私たちは映像(視覚)を認知するからです。そして、この「夢の映像・視覚」は「眼球運動」によって生まれるということでした。
以上のようなことを考えているうちに、夢と眼球運動、そして無意識と眼球運動、ひいては無意識と身体性との関連が、今後どんどん明らかになればいいな・・・なんて思い始め、とてもワクワクした気持ちになったのでした。
|
|
|
|
コメント(29)
見るということに関して、私が常々不思議に思うのは、…普通のひととは反対かも知れませんが、鏡に映った自分のルックスのほうが、写真に写った自分のルックスのほうよりはるかにイケメンに見えることです。
写真のほうが、何か心霊的で悪魔的な悪意ある何者かの念写のようなデフォルメにすら感じるのですが、…なんぼ不平を言っても、間違いなく写真のほうが客観的な像なのだと結論する他ないわけですよね。
すると、むしろ、私が直に現実に見ている生の世界のほうがかなり主観的に歪んでいる、…と考えるほかないわけです!
あと、ホームヴィデオになどに映った、他者の視線の延長上にある自分の、客観的映像は、まるで死霊のように不気味に感じられるし、声なども、とてもイヤなおぞましい声に聞こえます。
このことと、田中彰吾さんの講義の内容を関連させて考えてみたかったのですが、まだ、うまくまとまりません 。
。
写真のほうが、何か心霊的で悪魔的な悪意ある何者かの念写のようなデフォルメにすら感じるのですが、…なんぼ不平を言っても、間違いなく写真のほうが客観的な像なのだと結論する他ないわけですよね。
すると、むしろ、私が直に現実に見ている生の世界のほうがかなり主観的に歪んでいる、…と考えるほかないわけです!
あと、ホームヴィデオになどに映った、他者の視線の延長上にある自分の、客観的映像は、まるで死霊のように不気味に感じられるし、声なども、とてもイヤなおぞましい声に聞こえます。
このことと、田中彰吾さんの講義の内容を関連させて考えてみたかったのですが、まだ、うまくまとまりません
本文のリポートは、3日のミネルヴァさんの日記にアップされたものです。お願して今回コミュニティーにアップしもらいました。
なお、同日記での私のコメントを以下コピペします。
------------------------------------------------
素晴らしい感想文ですね! 1年半ぶりに出席され、今年の「芸術のことば」シリーズではもっともアカデミックなお話の内容を、これだけ正確に把握されたミネルヴァさんの理解力と感性に、正直驚嘆しました。
朝外出前に拝見し、今改めて拝読し一層その感を強くしました。
折角ですので本文をコミュニティーに、別トピでアップしてくれませんか?
そして多分ミクシィは見ていられない講師の田中先生にも送ってみてください。
ところで今回の駆け足東京ステイ、ほんとうにお疲れさまでした。
来期は今回のセミナーの流れのシリーズになりますので、機会がありましたら是非またいらしてください。
------------------------------------------------
なお、同日記での私のコメントを以下コピペします。
------------------------------------------------
素晴らしい感想文ですね! 1年半ぶりに出席され、今年の「芸術のことば」シリーズではもっともアカデミックなお話の内容を、これだけ正確に把握されたミネルヴァさんの理解力と感性に、正直驚嘆しました。
朝外出前に拝見し、今改めて拝読し一層その感を強くしました。
折角ですので本文をコミュニティーに、別トピでアップしてくれませんか?
そして多分ミクシィは見ていられない講師の田中先生にも送ってみてください。
ところで今回の駆け足東京ステイ、ほんとうにお疲れさまでした。
来期は今回のセミナーの流れのシリーズになりますので、機会がありましたら是非またいらしてください。
------------------------------------------------
僕も日記へのコメントをコピペしますね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ミネルバさん
こんばんわ。読みましたよ〜
臨場感ある文章で、田中先生の話が蘇りましたよ。ありがとう。
<画家と世界の関係について>
僕の理解では、
画家が世界に働きかける。
その結果として、世界が画家を通して絵として現れる
という構図だったと思います。
一般の人の場合は、
人が、身体を動かす
その結果として、世界が身体を通して視覚として現れる。
という理解です。
これは、そのまんま現代の量子力学のいうところの観測による影響とまったく同じだなと思って聞いてました。
そして通常我々は、常に身体を(眼球などの微細運動から、もっと細やかなな心理的働きかけも含めて)世界に対して投げかけることで、世界(他者)と私の間の境界を作りだしていて、その境界を作る活動によって、見えたり、聞こえたり、匂ったりしているのだなという理解です。
そして、ゴッホの絵を見た時になにが起こったかというと、絵を見ることで、その境界を揺り動かされ、主客身分化な境地になったと。
つまりゴッホと、自分のその時の身体性の状況が非常に共鳴して、私と世界の境界線に大きな揺らぎが生じて、それによって既存の主客関係が崩れた意識状態になったということだろうなと思いました。
<身体性とコンプレクスについて>
身体性とは、個人というより宇宙誕生から人類が誕生し、ここまでの進化の過程で構築された「構造」「かたち」であり、近くは行動様式という理解です。
←この辺は身体性をどこまの次元で捉えるかで違って来ますが。
ちなみに、ウィルバーの言っている万物の歴史とはそういうことで、つまり時間軸としてはビッグバンから今までが全て進化として繋がっていて、元型のような普遍的といわれるものも進化の途中の産物なわけです。
以前白田さんに確認したら、ユングもその時間スケールでは普遍とは言ってないと言ってました。
それと全象限ですね。つまり個の外面、個の内面、集団の外面、内面全てをくるめて身体性と考えるのが僕の考え方です。
←この辺、限定した肉体だけや個の内面外面だけを身体性とした議論でもある程度は大丈夫なんですが、深く掘り下げると必ず4象限は影響しあうので、切り離せないので、4象限全体で身体性といった方が話しが早いという考えです。
つまりこの身体性によって、肉体の形から、心のかたち、言語や解釈といったことまでが、限定されているという理解です。
ミネルバさんが指摘されている
>認知心理学には、「活性化拡散モデル」や「意味ネットワーク」とい考え方があり、ある単語
>が提示された時、その言葉と意味的につながっている言葉や記憶が同時に活性化され想
>起されやすくなる、という考え方があります。
上記の4象限全体の構造・かたちを身体性として理解すると、とてもよく当てはまると思います。
コンプレクスと元型と身体性について、以上のことからどう考えているかというと、
まずユング的には、
・コンプレクスは、現れたものであり、現象です。
・元型は、現れないものであり現象(コンプレクスなど)化させるなにか
なわけです。
つまりここには、現象と現象化せしまるなにかという階層構造があるわけです。そして、この階層構造は、多分単純に二階層ということではなく、もっと複雑に多階層なのだと思っています。
そしてこの多階層な構造は、万物の歴史の中で作られた構造であり、先に述べた身体性なわけです。
ですから結論としては、ミネルバさんが言わんとしていることとほぼ同じで、身体性のある階層がコンプレクスであり、さらに深いレベルが元型だと思っているわけです。
//
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ミネルバさん
こんばんわ。読みましたよ〜
臨場感ある文章で、田中先生の話が蘇りましたよ。ありがとう。
<画家と世界の関係について>
僕の理解では、
画家が世界に働きかける。
その結果として、世界が画家を通して絵として現れる
という構図だったと思います。
一般の人の場合は、
人が、身体を動かす
その結果として、世界が身体を通して視覚として現れる。
という理解です。
これは、そのまんま現代の量子力学のいうところの観測による影響とまったく同じだなと思って聞いてました。
そして通常我々は、常に身体を(眼球などの微細運動から、もっと細やかなな心理的働きかけも含めて)世界に対して投げかけることで、世界(他者)と私の間の境界を作りだしていて、その境界を作る活動によって、見えたり、聞こえたり、匂ったりしているのだなという理解です。
そして、ゴッホの絵を見た時になにが起こったかというと、絵を見ることで、その境界を揺り動かされ、主客身分化な境地になったと。
つまりゴッホと、自分のその時の身体性の状況が非常に共鳴して、私と世界の境界線に大きな揺らぎが生じて、それによって既存の主客関係が崩れた意識状態になったということだろうなと思いました。
<身体性とコンプレクスについて>
身体性とは、個人というより宇宙誕生から人類が誕生し、ここまでの進化の過程で構築された「構造」「かたち」であり、近くは行動様式という理解です。
←この辺は身体性をどこまの次元で捉えるかで違って来ますが。
ちなみに、ウィルバーの言っている万物の歴史とはそういうことで、つまり時間軸としてはビッグバンから今までが全て進化として繋がっていて、元型のような普遍的といわれるものも進化の途中の産物なわけです。
以前白田さんに確認したら、ユングもその時間スケールでは普遍とは言ってないと言ってました。
それと全象限ですね。つまり個の外面、個の内面、集団の外面、内面全てをくるめて身体性と考えるのが僕の考え方です。
←この辺、限定した肉体だけや個の内面外面だけを身体性とした議論でもある程度は大丈夫なんですが、深く掘り下げると必ず4象限は影響しあうので、切り離せないので、4象限全体で身体性といった方が話しが早いという考えです。
つまりこの身体性によって、肉体の形から、心のかたち、言語や解釈といったことまでが、限定されているという理解です。
ミネルバさんが指摘されている
>認知心理学には、「活性化拡散モデル」や「意味ネットワーク」とい考え方があり、ある単語
>が提示された時、その言葉と意味的につながっている言葉や記憶が同時に活性化され想
>起されやすくなる、という考え方があります。
上記の4象限全体の構造・かたちを身体性として理解すると、とてもよく当てはまると思います。
コンプレクスと元型と身体性について、以上のことからどう考えているかというと、
まずユング的には、
・コンプレクスは、現れたものであり、現象です。
・元型は、現れないものであり現象(コンプレクスなど)化させるなにか
なわけです。
つまりここには、現象と現象化せしまるなにかという階層構造があるわけです。そして、この階層構造は、多分単純に二階層ということではなく、もっと複雑に多階層なのだと思っています。
そしてこの多階層な構造は、万物の歴史の中で作られた構造であり、先に述べた身体性なわけです。
ですから結論としては、ミネルバさんが言わんとしていることとほぼ同じで、身体性のある階層がコンプレクスであり、さらに深いレベルが元型だと思っているわけです。
//
先日、なかひらさんと甲田さんのコラボによる、「魔法とモノノケの裏表〜『スプーの日記』の世界で遊ぶ〜」
http://nakahiramai.blogspot.com/2011/12/blog-post_09.html
に参加しました。代々木上原も金壺堂も、なんかとっていい街で良い感じの場所でした。
創作活動の裏側の話は、とても面白くて、最近のユング研のテーマである語りかけてくるもの、背後にあるヌミノースな世界から身体性を通して現れてくるものに対して、とても緻密に戦略をもって、創作しているんだなぁという印象で面白かったですよ。
芸術家(創作者)にとっては、そういった背後にある何ものかというのは、当たり前の存在で、具体的にそれとどう向き合うかというのが、課題なんだな〜と思いました。
あえて元型的なものを使わないように避けているという話もとても面白かったです。
現れてくるものを、ひらりとかわして、少しひねって味付けしているようなそんな感じですかね。
とっても参考になりました。
http://nakahiramai.blogspot.com/2011/12/blog-post_09.html
に参加しました。代々木上原も金壺堂も、なんかとっていい街で良い感じの場所でした。
創作活動の裏側の話は、とても面白くて、最近のユング研のテーマである語りかけてくるもの、背後にあるヌミノースな世界から身体性を通して現れてくるものに対して、とても緻密に戦略をもって、創作しているんだなぁという印象で面白かったですよ。
芸術家(創作者)にとっては、そういった背後にある何ものかというのは、当たり前の存在で、具体的にそれとどう向き合うかというのが、課題なんだな〜と思いました。
あえて元型的なものを使わないように避けているという話もとても面白かったです。
現れてくるものを、ひらりとかわして、少しひねって味付けしているようなそんな感じですかね。
とっても参考になりました。
けろりんさん、清志朗さん
東京でお会いした時も、“TV版の「ちびまるこちゃん」や「クレヨンしんちゃん」には元型が出てこない”というお話をされていましたよね。
でも、それが映画になると一転、元型的な登場人物が出てくるお話になる、ということでした
さて、元型がコンステレーションするとき、深く情動が揺り動かされる、つまりヌミノースな体験がもたらされる・・・と言いますよね。
ところで、そうした体験は、人為的につくれるものなのでしょうか・・・? ついつい、そんな疑問が浮かんできます
そして、この疑問に対するひとつの答えとして、『スタートレック』があげられることがありますよね。
この宇宙物語は、意識的にユング理論をベースにして創られたものなのだ、と何かで読んだことがあります。そして、この番組はたいへん人気を博したそうです。
また、物語の形式についても、私は、元型的なパターンがあるのではないか、と考えています。(河合隼雄氏もフォルマリズムのことを書いてらっしゃったと記憶していますが・・・)
たとえば、自我確立のプロセスや青春小説には、一つの定型的な型があるように思えるのですよね。そのストーリの流れ(型)そのものが、ある時期特有の心の動きを反映しているように思えるのです。(たとえば、英雄神話には、その背後にたいてい母親元型がコンステレーションしていて、「自立」がテーマになっているとか・・・)
ところで、けろりんさんは、女性の素足を見ると元型的な体験をされるようですが( )、もしかしたら、その背後には、アニマという元型がコンステレーションされているのかもしれませんよ
)、もしかしたら、その背後には、アニマという元型がコンステレーションされているのかもしれませんよ
東京でお会いした時も、“TV版の「ちびまるこちゃん」や「クレヨンしんちゃん」には元型が出てこない”というお話をされていましたよね。
でも、それが映画になると一転、元型的な登場人物が出てくるお話になる、ということでした
さて、元型がコンステレーションするとき、深く情動が揺り動かされる、つまりヌミノースな体験がもたらされる・・・と言いますよね。
ところで、そうした体験は、人為的につくれるものなのでしょうか・・・? ついつい、そんな疑問が浮かんできます
そして、この疑問に対するひとつの答えとして、『スタートレック』があげられることがありますよね。
この宇宙物語は、意識的にユング理論をベースにして創られたものなのだ、と何かで読んだことがあります。そして、この番組はたいへん人気を博したそうです。
また、物語の形式についても、私は、元型的なパターンがあるのではないか、と考えています。(河合隼雄氏もフォルマリズムのことを書いてらっしゃったと記憶していますが・・・)
たとえば、自我確立のプロセスや青春小説には、一つの定型的な型があるように思えるのですよね。そのストーリの流れ(型)そのものが、ある時期特有の心の動きを反映しているように思えるのです。(たとえば、英雄神話には、その背後にたいてい母親元型がコンステレーションしていて、「自立」がテーマになっているとか・・・)
ところで、けろりんさんは、女性の素足を見ると元型的な体験をされるようですが(
> ミネルヴァの戦士さん
ちなみに、盆踊りとアレクサンダー・テクニーク、…という拡充も可能な気がする。
もとより、盆踊りもまたアクティング・アウトを用いた変成意識の誘発を狙う、不可視の何かを“視る”ためのメチエなのかも知れない。つまり、ハレの時空へのイニシエーションにしてプロモーション!
だからたぶん、不可視の何かとは、“彼岸”なのかも。
盆踊り、それは、懐かしい異人たちの幻影を出現させ“視る”ための“彼岸の時間”を“魅させる”、シオドア・スタージョン的な、ホモ・ゲシュタルトによる、ミクロコスモス的な有機宇宙時計でもあったりして。
そういえば、シオドア・スタージョンの“墓読み”も、通常では不可視の何かを“視て”いるわけだが、“視る”とは、“読む”ことでもあるのかも知れない。
子どもの頃には、まるで、紅茶に浸したマドレーヌがプルーストに魅せたような、…クリスマスの時間、…正月の時間、…夏休みの時間、…など、あの“特別な時間”が視え、体感されたものだが、オトナになってしまった今では、それが、まるで、ダブリナーズ同様の“パラリシス”により視えなくなってしまってる、…。
つまり、盲目にさせるため迫り来る日常(ケ)のパラリシスを祓うための盆踊りなのかも知れない。
ということは、盆踊りもまた、ウィン(グ)ド・クロッシングだったのである!
いや、盆踊りを深読みしてしまったか!?
ちなみに、盆踊りとアレクサンダー・テクニーク、…という拡充も可能な気がする。
もとより、盆踊りもまたアクティング・アウトを用いた変成意識の誘発を狙う、不可視の何かを“視る”ためのメチエなのかも知れない。つまり、ハレの時空へのイニシエーションにしてプロモーション!
だからたぶん、不可視の何かとは、“彼岸”なのかも。
盆踊り、それは、懐かしい異人たちの幻影を出現させ“視る”ための“彼岸の時間”を“魅させる”、シオドア・スタージョン的な、ホモ・ゲシュタルトによる、ミクロコスモス的な有機宇宙時計でもあったりして。
そういえば、シオドア・スタージョンの“墓読み”も、通常では不可視の何かを“視て”いるわけだが、“視る”とは、“読む”ことでもあるのかも知れない。
子どもの頃には、まるで、紅茶に浸したマドレーヌがプルーストに魅せたような、…クリスマスの時間、…正月の時間、…夏休みの時間、…など、あの“特別な時間”が視え、体感されたものだが、オトナになってしまった今では、それが、まるで、ダブリナーズ同様の“パラリシス”により視えなくなってしまってる、…。
つまり、盲目にさせるため迫り来る日常(ケ)のパラリシスを祓うための盆踊りなのかも知れない。
ということは、盆踊りもまた、ウィン(グ)ド・クロッシングだったのである!
いや、盆踊りを深読みしてしまったか!?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ユング心理学研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ユング心理学研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 相棒
- 59356人
- 2位
- 福岡 ソフトバンクホークス
- 42963人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75883人