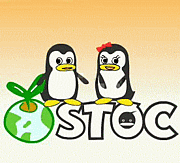初めまして!!温暖化を憂う一人です。
最近特に危機感を持っています。以下に最近感じていることを書き込みます。みなさんのご意見をお待ちしています。
---------------------------------
今のCO2レベルは 産業革命以前の280ppmより増えて、360-370ppmですが、2100年にはそのレベルは今のまま排出を続けた場合、1000ppm程度にまで 達すると予想している報告 (予想に幅があり、その一番高いケース)もあります。
過去の地球の歴史の中で今から5600万年〜4900万年前の地球のCO2濃度が 1125ppmだったということが明らかになっています。
その時の地球はどうだったのか?
その時の地球には 氷、雪の類は全くなく、南極大陸は深い緑に覆われていたそうです。 海面は今よりも相当高かったそうです。
2100年にそうなるとは言えませんが、そうなる条件が整ってしまうわけです。2100年からは地球は南極が緑に覆われていた姿に向かって進んでいき、数世紀後にはそのときに似た姿になるのでは、と思われます。
そうなる前に一日も早く人類がその防止に立ち上がることを望みます。
(Hot "Prehistoric" Conditions May Return by 2100, Study Says National Geographic News 9/28より引用)
追)生物の絶滅と温暖化
上の南極が緑に覆われる程度で落ち着けばいいのですが、過去の地球の歴史は『それでは終わらないよ!!』と行っています。
今までの長い地球の歴史(地球が出来て50億年、生命誕生から38億年)の中で、地球上の生物の 96%が死滅したとされている『PT絶滅』というのがあります。
まだ、原因ははっきりしているわけではありませんが、仮説として 以下のストーリーが提唱されています。
これにも 『メタンハイドレート』の分解が大きく関わっているようです。
その仮説を紹介します。
そのPT絶滅が起こったのは約2億5000万年前とされています。その頃の地球は今のような大陸の配置ではなくて、すべての大陸が集まってくっついた パンゲア大陸 が出来たところでした。
これは大陸移動と呼ばれ、今のような7大陸に分かれたり、また 集まって一緒になったりというのを 数億年周期で繰り返しているようです。2億5000万年前はその大陸がひとつになった時期でした。この大陸移動は地下のマントルの対流によって起こっています。したがって、火山活動と密接な関係があるわけです。
ということで PT絶滅 の引き金になったのは
シベリア高原で起こった大噴火だと言われています。その痕跡が残っているようです。
この大噴火で大量のCO2(現在の大気中のCO2量の15倍の量)が大気中に放出されたとされています。
そして、そのCO2は地球の温室効果をもたらし、その温暖化により地中の メタンハイドレート をとかし、大量のメタンガスが大気中に放出されたとしています。
その結果、温暖化が加速され、赤道付近で平均気温が+8-9℃の上昇、極付近で +20-25℃の上昇が起こり地球上の生物の殆どが絶滅したとされています。
メタンは特定の微生物によって作られ、C12を好む微生物でこのPT地層では C12が通常よりも多いことが分かっています。
また、今の海では、極付近が冷たいためその付近の海水が海底に沈みこみ、南から暖かい海水が流れ込む(海流)ことによって海水が循環し海水中の酸素濃度が保たれていますが、この大気の高温化により極付近も暖かくなり、この海水の循環が起こらなくなり、海水中の酸素がなくなり、海中の生物も絶滅したと考えられています。
PT絶滅の地層(1000万年間)には それまで大量にいたプランクトンの化石が全くなく、絶滅したことの証拠とされています。
このときの絶滅は約1000万年という長い時間をかけて起こったことです。
でも、今の地球上でもこれと同じ絶滅が進行しています。この急激な気候の変化についていけない生物種は 2050年までに全体の約40%いて それが絶滅してしまうであろうと言われています。この間高々200-300年です。ものすごいスピードです。
PT絶滅以上のすさまじいスピードの変化です。
自然の絶滅スピードの100倍のスピードといわれています。
かけがえのない種が失われつつあります。
今、地球は最初のCO2が増える引き金が人為的なものであるだけで 上のPT絶滅と同じシナリオを進むのではと危惧されます。
最近特に危機感を持っています。以下に最近感じていることを書き込みます。みなさんのご意見をお待ちしています。
---------------------------------
今のCO2レベルは 産業革命以前の280ppmより増えて、360-370ppmですが、2100年にはそのレベルは今のまま排出を続けた場合、1000ppm程度にまで 達すると予想している報告 (予想に幅があり、その一番高いケース)もあります。
過去の地球の歴史の中で今から5600万年〜4900万年前の地球のCO2濃度が 1125ppmだったということが明らかになっています。
その時の地球はどうだったのか?
その時の地球には 氷、雪の類は全くなく、南極大陸は深い緑に覆われていたそうです。 海面は今よりも相当高かったそうです。
2100年にそうなるとは言えませんが、そうなる条件が整ってしまうわけです。2100年からは地球は南極が緑に覆われていた姿に向かって進んでいき、数世紀後にはそのときに似た姿になるのでは、と思われます。
そうなる前に一日も早く人類がその防止に立ち上がることを望みます。
(Hot "Prehistoric" Conditions May Return by 2100, Study Says National Geographic News 9/28より引用)
追)生物の絶滅と温暖化
上の南極が緑に覆われる程度で落ち着けばいいのですが、過去の地球の歴史は『それでは終わらないよ!!』と行っています。
今までの長い地球の歴史(地球が出来て50億年、生命誕生から38億年)の中で、地球上の生物の 96%が死滅したとされている『PT絶滅』というのがあります。
まだ、原因ははっきりしているわけではありませんが、仮説として 以下のストーリーが提唱されています。
これにも 『メタンハイドレート』の分解が大きく関わっているようです。
その仮説を紹介します。
そのPT絶滅が起こったのは約2億5000万年前とされています。その頃の地球は今のような大陸の配置ではなくて、すべての大陸が集まってくっついた パンゲア大陸 が出来たところでした。
これは大陸移動と呼ばれ、今のような7大陸に分かれたり、また 集まって一緒になったりというのを 数億年周期で繰り返しているようです。2億5000万年前はその大陸がひとつになった時期でした。この大陸移動は地下のマントルの対流によって起こっています。したがって、火山活動と密接な関係があるわけです。
ということで PT絶滅 の引き金になったのは
シベリア高原で起こった大噴火だと言われています。その痕跡が残っているようです。
この大噴火で大量のCO2(現在の大気中のCO2量の15倍の量)が大気中に放出されたとされています。
そして、そのCO2は地球の温室効果をもたらし、その温暖化により地中の メタンハイドレート をとかし、大量のメタンガスが大気中に放出されたとしています。
その結果、温暖化が加速され、赤道付近で平均気温が+8-9℃の上昇、極付近で +20-25℃の上昇が起こり地球上の生物の殆どが絶滅したとされています。
メタンは特定の微生物によって作られ、C12を好む微生物でこのPT地層では C12が通常よりも多いことが分かっています。
また、今の海では、極付近が冷たいためその付近の海水が海底に沈みこみ、南から暖かい海水が流れ込む(海流)ことによって海水が循環し海水中の酸素濃度が保たれていますが、この大気の高温化により極付近も暖かくなり、この海水の循環が起こらなくなり、海水中の酸素がなくなり、海中の生物も絶滅したと考えられています。
PT絶滅の地層(1000万年間)には それまで大量にいたプランクトンの化石が全くなく、絶滅したことの証拠とされています。
このときの絶滅は約1000万年という長い時間をかけて起こったことです。
でも、今の地球上でもこれと同じ絶滅が進行しています。この急激な気候の変化についていけない生物種は 2050年までに全体の約40%いて それが絶滅してしまうであろうと言われています。この間高々200-300年です。ものすごいスピードです。
PT絶滅以上のすさまじいスピードの変化です。
自然の絶滅スピードの100倍のスピードといわれています。
かけがえのない種が失われつつあります。
今、地球は最初のCO2が増える引き金が人為的なものであるだけで 上のPT絶滅と同じシナリオを進むのではと危惧されます。
|
|
|
|
コメント(90)
改名しました。前の名前はDayanです。
ややこしくしてすいません。
nihaodaxi さん
ご意見、ありがとうございました。
私も、今世界中の人間が団結して温暖化を防がなければならないと思います。
でも、やっぱり個人や団体の力には限度があるので
政府が動いてくれないことには苦しいですね。。。
なので、nihaodaxi さんが載せてくださった
安部さんの記事には驚きでした。
やっと政府も動いてくれるのかなと。
温室効果ガスの固定・隔離技術が完成するまで、
私達はなんとか時間を稼がなければなりませんね。
できる限り多くの人に温暖化の状況を知ってもらい、
一人一人が資源を大切に使っていかなければならないと思います。
あの、ここで質問です。
今、私は税務署でアルバイトをしています。
税務署には「温暖化防止にご協力ください」というポスターが貼ってあり、
電気のスイッチがある所には必ず「節電!」などの文字があります。
トイレは、昼間誰もいなかったら自動的に電気が消え、
人が入ってきたら自動的に電気が入る仕組みになっていました。
私はとても驚いたのですが、これはやっぱり公的機関だからなのでしょうか?
一般の企業や会社ではこのようなことをしてるのでしょうか?
ややこしくしてすいません。
nihaodaxi さん
ご意見、ありがとうございました。
私も、今世界中の人間が団結して温暖化を防がなければならないと思います。
でも、やっぱり個人や団体の力には限度があるので
政府が動いてくれないことには苦しいですね。。。
なので、nihaodaxi さんが載せてくださった
安部さんの記事には驚きでした。
やっと政府も動いてくれるのかなと。
温室効果ガスの固定・隔離技術が完成するまで、
私達はなんとか時間を稼がなければなりませんね。
できる限り多くの人に温暖化の状況を知ってもらい、
一人一人が資源を大切に使っていかなければならないと思います。
あの、ここで質問です。
今、私は税務署でアルバイトをしています。
税務署には「温暖化防止にご協力ください」というポスターが貼ってあり、
電気のスイッチがある所には必ず「節電!」などの文字があります。
トイレは、昼間誰もいなかったら自動的に電気が消え、
人が入ってきたら自動的に電気が入る仕組みになっていました。
私はとても驚いたのですが、これはやっぱり公的機関だからなのでしょうか?
一般の企業や会社ではこのようなことをしてるのでしょうか?
まゆさん
こちらこそコメントありがとうございます。
●安部さんの記事には驚きでした。
やっと政府も動いてくれるのかなと。
<----これもアル・ゴアさんの影響による世論の盛り上がりがあるかもしれませんね。でも、まだまだ政府には危機感がないですね。
もうすこし緊迫感が欲しいですね。
●「温暖化防止にご協力ください」
<---電気が自動的に切れるのは 公的機関だからでしょうね!! まだ 一般の会社ではそれにかけるコストの方がでかいんだと思います。そういうのは見たことがないです。でも、当社の工場ではコスト意識が高くて 使わない電気は人がちゃんと消す習慣がついています。どこの企業でも『温暖化防止』の目的ではなく、『コスト低減』の目的で節電・節水をしていると思います。
たた゜、事務所ではまだ そういう意識が薄いですね。
という感じです。
こちらこそコメントありがとうございます。
●安部さんの記事には驚きでした。
やっと政府も動いてくれるのかなと。
<----これもアル・ゴアさんの影響による世論の盛り上がりがあるかもしれませんね。でも、まだまだ政府には危機感がないですね。
もうすこし緊迫感が欲しいですね。
●「温暖化防止にご協力ください」
<---電気が自動的に切れるのは 公的機関だからでしょうね!! まだ 一般の会社ではそれにかけるコストの方がでかいんだと思います。そういうのは見たことがないです。でも、当社の工場ではコスト意識が高くて 使わない電気は人がちゃんと消す習慣がついています。どこの企業でも『温暖化防止』の目的ではなく、『コスト低減』の目的で節電・節水をしていると思います。
たた゜、事務所ではまだ そういう意識が薄いですね。
という感じです。
nihaodaxi さん
そうですね。政府にはもっと温暖化に関心を持ってほしいです。
そういえば、ゴアさんは次の大統領選挙に出はるんでしょうか?
私はゴアさんに大統領になってほしいです。
そしたらアメリカも日本も、もっと変わっていくような気がしてます。
やっぱり公的機関だからなんですね。
でも、『コスト低減』という目的でも節電・節水をしていくのは結果的に温暖化防止につながるので、良いことですね。
この前、テレビで
環境に良い製品を作ったり、エコに力を入れている企業や会社が売り上げを伸ばしている。
と言っていました。
これってやっぱり本当なんですか?
あと、CMでPanasonicが個人の家用の、自家発電電池(やったっけ?)を売り出してるみたいです。
これを使えば、家から出るCO2が年間約45%カットと言ってました。
これは期待できると思っていいのでしょうか?
そうですね。政府にはもっと温暖化に関心を持ってほしいです。
そういえば、ゴアさんは次の大統領選挙に出はるんでしょうか?
私はゴアさんに大統領になってほしいです。
そしたらアメリカも日本も、もっと変わっていくような気がしてます。
やっぱり公的機関だからなんですね。
でも、『コスト低減』という目的でも節電・節水をしていくのは結果的に温暖化防止につながるので、良いことですね。
この前、テレビで
環境に良い製品を作ったり、エコに力を入れている企業や会社が売り上げを伸ばしている。
と言っていました。
これってやっぱり本当なんですか?
あと、CMでPanasonicが個人の家用の、自家発電電池(やったっけ?)を売り出してるみたいです。
これを使えば、家から出るCO2が年間約45%カットと言ってました。
これは期待できると思っていいのでしょうか?
まゆさん
アル・ゴアさんは出ないと思いますよ。本人がそう言っているようです。多分、ヒラリー・クリントンが次の大統領だと思います。
そうですね。アル・コアさんが大統領になったらかなり変わると思います。
でも、ヒラリーのブレーンに入りそうな気がするけど.......
『コスト低減』
目的は違っても結果は同じだから、それで いいですよね。
でも、緊迫感はないですね。
●エコに力を入れている企業や会社が売り上げを伸ばしている。
今はエコをうたうと消費者に受け入れられるようです。なんかブームみたいなものでしょうね。
実際どれだけ環境を考えているか?は別問題ですけど....
●自家発電電池
これは『太陽電池』のこと?
だったら ちょっと問題があります。太陽電池も半導体のひとつなんですが、この半導体というのは 作るときにものすごくエネルギーを使うようです。消費者が使うときには CO2は出ないけど その太陽電池を作る過程でものすごくたくさんCO2を出しているので必ずしもいいとは言えませんね。
まゆさんの言ってるものと違うかも知れないけど.....
アル・ゴアさんは出ないと思いますよ。本人がそう言っているようです。多分、ヒラリー・クリントンが次の大統領だと思います。
そうですね。アル・コアさんが大統領になったらかなり変わると思います。
でも、ヒラリーのブレーンに入りそうな気がするけど.......
『コスト低減』
目的は違っても結果は同じだから、それで いいですよね。
でも、緊迫感はないですね。
●エコに力を入れている企業や会社が売り上げを伸ばしている。
今はエコをうたうと消費者に受け入れられるようです。なんかブームみたいなものでしょうね。
実際どれだけ環境を考えているか?は別問題ですけど....
●自家発電電池
これは『太陽電池』のこと?
だったら ちょっと問題があります。太陽電池も半導体のひとつなんですが、この半導体というのは 作るときにものすごくエネルギーを使うようです。消費者が使うときには CO2は出ないけど その太陽電池を作る過程でものすごくたくさんCO2を出しているので必ずしもいいとは言えませんね。
まゆさんの言ってるものと違うかも知れないけど.....
ちょっと古い記事ですが、わかりやすい記事ですので ここにのっけます。
--------------------------------------------
総論 温暖化 地球のシグナル
温暖化がハイペースで進む地球が警鐘を鳴らし始めている。本特集は3部構成により、様々な視点から温暖化の現状を探る(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
地球温暖化の影響が出るのは遠い将来のことで、今から心配する必要はないように思える。来週の天気予報もあてにならないのに、長期的な気候変動など予測できそうにない。寒い冬の日には、少しくらい暖かくなってもいいと思う。環境保護活動家は温暖化の危機を叫び、「車に乗るな」「つましい生活をしろ」と、私たちを脅しているだけに違いない……。
そう考えれば、気が楽かもしれない。だが、この特集の第1部「大地と海のシグナル」を読んでいただきたい。様々な場所で起こっている異変は、地球からの警告だ。
米国のアラスカ州から南米アンデス山脈の雪峰まで、今この瞬間にも温暖化は急速に進んでいる。過去100年の地球の気温上昇は平均で0.6℃だが、現在、高緯度地方ではもっと大幅に上昇している。氷は解け、河川の水量は減り、海岸の浸食が進み、人々の生活圏を脅かしているのだ。
第2部「生き物たちのシグナル」で紹介するのは、動植物に及びつつある温暖化の影響。それらはすでに起きている事実だ。変化の多くは、私たちの知らない所で進んでいる。だからと言って、無視することはできない。それらは、ほかの地域での今後の変化を予告しているからだ。
「ちょっと待ってほしい」と、懐疑的な人たちは言うだろう。気候は変わりやすい。1000年前、ヨーロッパは温暖で、英国でもワイン用のブドウが栽培できた。だが400年前までにテムズ川が何度も凍結するほど寒冷化が進んだ。今の気温上昇も自然の変動にすぎず、一時的なものではないか。
気候の専門家に言わせれば、それは甘い考えだ。確かに、これから紹介する温暖化の兆候のなかには、自然の気候リズムで説明できるものもあるだろう。だが地球規模で進む異常な気温上昇は、別の要因によるものだ。
人類は長年、森林を伐採し、石炭・石油・天然ガスを燃やし、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスを大気中に放出してきた。人為的な活動による二酸化炭素の排出量は、植物の光合成や海水中に溶け込むことによる吸収量を上回っている(2004年2月号の特集「炭素の行方」参照)。
現在、大気中の二酸化炭素濃度は過去数十万年のどの時期よりも高い。「今や気候変動への人間の影響は無視できない」と、米国プリンストン大学の気候専門家ジョージ・フィランダーは話す。
国連の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が2001年に報告した内容によると、過去100年間の気温上昇が人間の活動に起因することはほぼ確実だ。地球の気温はこの1000年のうちで最も急速に上昇している。火山爆発や太陽の活動などの自然要因だけでは気温上昇を説明できない。
IPCCは、地球の気温が今世紀末までにさらに1.4?5.8℃上がると予測している。だが、温暖化は一定のペースで進むとは限らない。第3部「過去からのシグナル」で紹介するように、過去を調べると、地球の温度調節機能は遅れて反応するようだ。初めはゆっくり上がる気温が、ある時急に上昇し、大災害を招きかねないと一部の専門家は懸念する。地球の温度調節機能をいじり続けるのは「賢明とは言えない」と、フィランダーは警告する。
(national Geographic より)
--------------------------------------------
総論 温暖化 地球のシグナル
温暖化がハイペースで進む地球が警鐘を鳴らし始めている。本特集は3部構成により、様々な視点から温暖化の現状を探る(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
地球温暖化の影響が出るのは遠い将来のことで、今から心配する必要はないように思える。来週の天気予報もあてにならないのに、長期的な気候変動など予測できそうにない。寒い冬の日には、少しくらい暖かくなってもいいと思う。環境保護活動家は温暖化の危機を叫び、「車に乗るな」「つましい生活をしろ」と、私たちを脅しているだけに違いない……。
そう考えれば、気が楽かもしれない。だが、この特集の第1部「大地と海のシグナル」を読んでいただきたい。様々な場所で起こっている異変は、地球からの警告だ。
米国のアラスカ州から南米アンデス山脈の雪峰まで、今この瞬間にも温暖化は急速に進んでいる。過去100年の地球の気温上昇は平均で0.6℃だが、現在、高緯度地方ではもっと大幅に上昇している。氷は解け、河川の水量は減り、海岸の浸食が進み、人々の生活圏を脅かしているのだ。
第2部「生き物たちのシグナル」で紹介するのは、動植物に及びつつある温暖化の影響。それらはすでに起きている事実だ。変化の多くは、私たちの知らない所で進んでいる。だからと言って、無視することはできない。それらは、ほかの地域での今後の変化を予告しているからだ。
「ちょっと待ってほしい」と、懐疑的な人たちは言うだろう。気候は変わりやすい。1000年前、ヨーロッパは温暖で、英国でもワイン用のブドウが栽培できた。だが400年前までにテムズ川が何度も凍結するほど寒冷化が進んだ。今の気温上昇も自然の変動にすぎず、一時的なものではないか。
気候の専門家に言わせれば、それは甘い考えだ。確かに、これから紹介する温暖化の兆候のなかには、自然の気候リズムで説明できるものもあるだろう。だが地球規模で進む異常な気温上昇は、別の要因によるものだ。
人類は長年、森林を伐採し、石炭・石油・天然ガスを燃やし、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスを大気中に放出してきた。人為的な活動による二酸化炭素の排出量は、植物の光合成や海水中に溶け込むことによる吸収量を上回っている(2004年2月号の特集「炭素の行方」参照)。
現在、大気中の二酸化炭素濃度は過去数十万年のどの時期よりも高い。「今や気候変動への人間の影響は無視できない」と、米国プリンストン大学の気候専門家ジョージ・フィランダーは話す。
国連の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が2001年に報告した内容によると、過去100年間の気温上昇が人間の活動に起因することはほぼ確実だ。地球の気温はこの1000年のうちで最も急速に上昇している。火山爆発や太陽の活動などの自然要因だけでは気温上昇を説明できない。
IPCCは、地球の気温が今世紀末までにさらに1.4?5.8℃上がると予測している。だが、温暖化は一定のペースで進むとは限らない。第3部「過去からのシグナル」で紹介するように、過去を調べると、地球の温度調節機能は遅れて反応するようだ。初めはゆっくり上がる気温が、ある時急に上昇し、大災害を招きかねないと一部の専門家は懸念する。地球の温度調節機能をいじり続けるのは「賢明とは言えない」と、フィランダーは警告する。
(national Geographic より)
続きです、
---------------------------
温暖化1 大地と海のシグナル
急速に後退する山岳地帯の氷河、年々薄くなる北極圏の海氷。海面上昇で海に没しそうな小島がある一方で、水源が枯渇して干上がった湖もある。大地、そして海で起こっている異変をリポート。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
装備は最小限でいい。氷河の研究者ダニエル・フェイグレはバックパックをかつぐ私を見て言った。ここは米国モンタナ州のグレイシャー(氷河)国立公園。フェイグレと二人の研究者、それに私の一行は、アイゼンにピッケル、クマよけスプレーなどを持って同公園内のスペリー氷河を目指す。フェイグレたちは10年以上、この公園の氷河が後退していく様子を計測している。
これまでに得られた結果は驚くべき内容だ。1910年当時、ここには推定150の氷河があったが、今では30足らず。しかも、その大半は面積が3分の2ほどに縮小している。フェイグレは、公園内の氷河のほとんど、もしくはすべてが30年以内に消えると予測、グレイシャー国立公園とは名ばかりになるのでは、と話す。
「本来なら何十万年もかけて徐々に進行する変化が、わずか何十年という短い時間で起きている」と、フェイグレは言う。
地球の温暖化は進んでいる。人間の活動が原因だ。科学者たちは様々な兆候から、そう確信している。特に石油やガソリンなどの化石燃料を燃やすと、大気中に二酸化炭素などの温室効果ガスが蓄積されて温暖化が進行すると、大半の科学者が考えている。
急速に進む温暖化
「以前はもっとそばまで氷河が来ていた」と、フェイグレは氷河の急勾配を登りながら言った。歩道脇の標識には、スペリー氷河が1901年の325ヘクタールから現在120ヘクタールに縮小したと書いてある。「この標識はもう古い。今では100ヘクタール足らずだ」と、彼は話す。
地球上のあらゆる場所で、氷に異変が起きている。アフリカの有名なキリマンジャロの雪は1912年以降、80%以上が解けた。インドのガルワル・ヒマラヤ氷河も急速に後退し、この調子だとヒマラヤ中部と東部の氷河は2035年までにほとんど消えてしまうかもしれない。北極の海氷もこの半世紀で大幅に薄くなり、氷が浮かぶ海域は過去30年間で約10%縮まった。NASA(米航空宇宙局)の調査で、グリーンランドをおおう氷床の融解も確認されている。
北半球では、春に氷の割れる時期が150年前に比べて9日早まり、秋の結氷は10日遅くなった。スイスの山から、赤道にあるインドネシアのイリアン・ジャヤ氷河まで、氷原や氷河、海氷が急速に消えようとしている。
気温が上がると氷河や万年雪が解け、大量の水が海に流れ込む。海水温が上がると海水は膨張する。こうした変化が組み合わさって、この100年間に世界の海面は平均10〜20センチ上昇したと、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)は報告している。
46億年の地球の歴史で、海面は大幅な上昇と下降を繰り返してきたという。だが、最近は過去2000〜3000年の平均上昇率を上回る、年に2ミリの割合で世界の海面が上昇している。この傾向が続けば、世界の海岸線は驚くほど変わりかねない。
(national Geographic より)
---------------------------
温暖化1 大地と海のシグナル
急速に後退する山岳地帯の氷河、年々薄くなる北極圏の海氷。海面上昇で海に没しそうな小島がある一方で、水源が枯渇して干上がった湖もある。大地、そして海で起こっている異変をリポート。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
装備は最小限でいい。氷河の研究者ダニエル・フェイグレはバックパックをかつぐ私を見て言った。ここは米国モンタナ州のグレイシャー(氷河)国立公園。フェイグレと二人の研究者、それに私の一行は、アイゼンにピッケル、クマよけスプレーなどを持って同公園内のスペリー氷河を目指す。フェイグレたちは10年以上、この公園の氷河が後退していく様子を計測している。
これまでに得られた結果は驚くべき内容だ。1910年当時、ここには推定150の氷河があったが、今では30足らず。しかも、その大半は面積が3分の2ほどに縮小している。フェイグレは、公園内の氷河のほとんど、もしくはすべてが30年以内に消えると予測、グレイシャー国立公園とは名ばかりになるのでは、と話す。
「本来なら何十万年もかけて徐々に進行する変化が、わずか何十年という短い時間で起きている」と、フェイグレは言う。
地球の温暖化は進んでいる。人間の活動が原因だ。科学者たちは様々な兆候から、そう確信している。特に石油やガソリンなどの化石燃料を燃やすと、大気中に二酸化炭素などの温室効果ガスが蓄積されて温暖化が進行すると、大半の科学者が考えている。
急速に進む温暖化
「以前はもっとそばまで氷河が来ていた」と、フェイグレは氷河の急勾配を登りながら言った。歩道脇の標識には、スペリー氷河が1901年の325ヘクタールから現在120ヘクタールに縮小したと書いてある。「この標識はもう古い。今では100ヘクタール足らずだ」と、彼は話す。
地球上のあらゆる場所で、氷に異変が起きている。アフリカの有名なキリマンジャロの雪は1912年以降、80%以上が解けた。インドのガルワル・ヒマラヤ氷河も急速に後退し、この調子だとヒマラヤ中部と東部の氷河は2035年までにほとんど消えてしまうかもしれない。北極の海氷もこの半世紀で大幅に薄くなり、氷が浮かぶ海域は過去30年間で約10%縮まった。NASA(米航空宇宙局)の調査で、グリーンランドをおおう氷床の融解も確認されている。
北半球では、春に氷の割れる時期が150年前に比べて9日早まり、秋の結氷は10日遅くなった。スイスの山から、赤道にあるインドネシアのイリアン・ジャヤ氷河まで、氷原や氷河、海氷が急速に消えようとしている。
気温が上がると氷河や万年雪が解け、大量の水が海に流れ込む。海水温が上がると海水は膨張する。こうした変化が組み合わさって、この100年間に世界の海面は平均10〜20センチ上昇したと、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)は報告している。
46億年の地球の歴史で、海面は大幅な上昇と下降を繰り返してきたという。だが、最近は過去2000〜3000年の平均上昇率を上回る、年に2ミリの割合で世界の海面が上昇している。この傾向が続けば、世界の海岸線は驚くほど変わりかねない。
(national Geographic より)
続きです、
---------------------------
温暖化2 生き物たちのシグナル
地球の生態系は地球温暖化によって大きな影響を受ける。サンゴ礁の白化、枯れる森林、動物の渡りの時期の変化はその一例。南極の「南極半島」周辺にスポットを当て、その劇的な変化を報告する。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
南極大陸の一角にある南極半島は、南米大陸に向かって1300キロほど細長く延びる。過去30年のうち23年間、ここで調査を続けている環境問題の専門家ビル・フレーザーによれば、以前と変わっていないものはただ一つ、壮大な眺めだけだ。ここでは陸も海も、そしてそこで暮らす生き物たちも、すべてが変化の波にさらされている。この一帯は地球上で最も急速に温暖化が進んでいる地域の一つで、冬の平均気温は過去50年間で5℃ほど上昇した。
最も目立つ変化はマール山麓氷河の後退だが、フレーザーが気にかけているのは、温暖化がアデリーペンギンに与える影響だ。孤独と冒険を楽しみながら、極地に生息する鳥類に関する博士論文を書こうと南極へやって来た彼は現在、アデリーペンギンの研究をライフワークにしている。
南極の真夏に当たる1月のある日、彼と私は南極圏外に位置するビスコー諸島の繁殖コロニーの個体数を調べるため、近くの高台に登った。小石を集めて作ったペンギンの巣が、斑点のように散らばっている。赤レンガ色の染みのように見えるのは、糞が堆積して固まったグアノ(鳥糞石)だ。アデリーペンギンは海とコロニーの間を行き来して、食べ物のオキアミを運ぶ。陸では、体を綿毛でおおわれた数百羽のヒナが鳴き声を上げて食べ物を待っている。南極の氷の上を生活の場にしているペンギンは、アデリーペンギンを含めて2種類だけ(もう1種類はエンペラペンギン)。20年前のビスコー諸島には、子育て中のアデリーペンギンのつがいが2800組いたが、今では1000組前後まで減った。
付近の島々でも30年間で3万2000組から1万1000組に減り、以前の3分の1程度になった。フレーザーの調査によれば、アデリーペンギンの数が減る代わりに、本来もっと温暖な亜南極地方にすむジェンツーペンギンが増えている。10数組のジェンツーペンギンのつがいがビスコー諸島にやって来たのは1990年代初め。今では660組まで増えた。
「まったく信じられません。アデリーペンギンはもうすぐビスコー諸島から姿を消してしまうでしょう。彼らは滅びゆく運命にある」と、米国のパーマー基地の研究チームを率いるフレーザーは言う。
「100年ほど前、ここは基本的には極地と同じ環境で、気候的にこの地域は南極大陸とほぼ一体化していました。それが今は、亜南極性の気候がどんどん強まっている。私は30年前から二つの気候のせめぎ合いを目の当たりにしてきたけれど、パーマー基地はもはや極地性の気候とは言えない。このような変化がきわめて短期間で起きたことは、恐るべきことだ」
南極半島西部で急速に温暖化が進んだ理由は、地球規模の気温上昇だけでなく、局地的な海流や気流の変化も関係している。世界全体でみれば、温暖化のペースはもっと緩やかで、過去100年間で平均気温が0.6℃上昇したにすぎない。とはいえ、この程度の比較的小さな気候の変化でも、影響は自然界全体に広がっている。フレーザーが心血を注いできた南極半島の調査は、温暖化が地球全体の生態系に与える深刻な影響を解明する手がかりを与えてくれる。
すでに動植物や昆虫は温暖化に適応するため、渡りや移動の時期を早めたり、交尾や開花の時期を変えたりしている。ヨーロッパでは最近の数十年間で、定住型のチョウのうち35種が、生息地域を30〜240キロ北へ拡大させたことが分かった。また、多くの植物の開花期が50年前より1週間ほど早まり、秋の紅葉が5日ほど遅くなった。
英国の鳥は20世紀半ばに比べて卵の孵化の時期が平均9日早くなり、カエルの交尾期は最高で7週間も早まった。北米のジュドウアオツバメは25年前に比べ、春に北へ移動するのが12日早くなった。カナダのアカギツネの生息地域は数百キロ北極寄りに移り、ホッキョクギツネのテリトリーに入り込んでいる。
高山植物は自生地をじりじりと標高の高いところに移し、山頂近くの希少種を脅かしつつある。地球の気候はこれまで常に自然の変動を繰り返し、温暖化と寒冷化の間で揺れ動いてきた。それでも環境問題の専門家が現在の温暖化に懸念を抱くのには、いくつかの理由がある。まず、今回の温暖化は人間が気候の変化を加速させている可能性があること。そして温暖化のペースが早すぎて、生き物たちが変化に適応して絶滅を逃れるための時間的余裕がないことだ。
さらに、生き物の種によって、それぞれ環境の変化への対応の仕方が違うため、相互依存の関係にある生き物同士の生活サイクルにズレが生じかねない。そして、個体数の減少を引き起こす可能性もある。
今のところは世界の多くの地域で温暖化が進んでも、動植物は高緯度地方や高地に移って暑さから逃れることができる。だが、このような退避ルートには限りがあり、なかには人間の手で道がふさがれているケースもある。これまでの数千年間と異なり、動植物が適応しなければならない現在の世界は、温暖化問題に加えて、63億人に増えた人類の存在という別の問題も抱えているのだ。
「過去の大規模な気候変動の際には、人類の存在は大きな障害ではなかったので、生き物たちは自由に移動できました。今は生き物たちが生息地を変えようとすると、トウモロコシ畑やシカゴのような大都会に突き当たってしまうおそれがあります」と、環境問題専門家のカミール・パーメザンは言う。
(national Geographic より)
---------------------------
温暖化2 生き物たちのシグナル
地球の生態系は地球温暖化によって大きな影響を受ける。サンゴ礁の白化、枯れる森林、動物の渡りの時期の変化はその一例。南極の「南極半島」周辺にスポットを当て、その劇的な変化を報告する。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
南極大陸の一角にある南極半島は、南米大陸に向かって1300キロほど細長く延びる。過去30年のうち23年間、ここで調査を続けている環境問題の専門家ビル・フレーザーによれば、以前と変わっていないものはただ一つ、壮大な眺めだけだ。ここでは陸も海も、そしてそこで暮らす生き物たちも、すべてが変化の波にさらされている。この一帯は地球上で最も急速に温暖化が進んでいる地域の一つで、冬の平均気温は過去50年間で5℃ほど上昇した。
最も目立つ変化はマール山麓氷河の後退だが、フレーザーが気にかけているのは、温暖化がアデリーペンギンに与える影響だ。孤独と冒険を楽しみながら、極地に生息する鳥類に関する博士論文を書こうと南極へやって来た彼は現在、アデリーペンギンの研究をライフワークにしている。
南極の真夏に当たる1月のある日、彼と私は南極圏外に位置するビスコー諸島の繁殖コロニーの個体数を調べるため、近くの高台に登った。小石を集めて作ったペンギンの巣が、斑点のように散らばっている。赤レンガ色の染みのように見えるのは、糞が堆積して固まったグアノ(鳥糞石)だ。アデリーペンギンは海とコロニーの間を行き来して、食べ物のオキアミを運ぶ。陸では、体を綿毛でおおわれた数百羽のヒナが鳴き声を上げて食べ物を待っている。南極の氷の上を生活の場にしているペンギンは、アデリーペンギンを含めて2種類だけ(もう1種類はエンペラペンギン)。20年前のビスコー諸島には、子育て中のアデリーペンギンのつがいが2800組いたが、今では1000組前後まで減った。
付近の島々でも30年間で3万2000組から1万1000組に減り、以前の3分の1程度になった。フレーザーの調査によれば、アデリーペンギンの数が減る代わりに、本来もっと温暖な亜南極地方にすむジェンツーペンギンが増えている。10数組のジェンツーペンギンのつがいがビスコー諸島にやって来たのは1990年代初め。今では660組まで増えた。
「まったく信じられません。アデリーペンギンはもうすぐビスコー諸島から姿を消してしまうでしょう。彼らは滅びゆく運命にある」と、米国のパーマー基地の研究チームを率いるフレーザーは言う。
「100年ほど前、ここは基本的には極地と同じ環境で、気候的にこの地域は南極大陸とほぼ一体化していました。それが今は、亜南極性の気候がどんどん強まっている。私は30年前から二つの気候のせめぎ合いを目の当たりにしてきたけれど、パーマー基地はもはや極地性の気候とは言えない。このような変化がきわめて短期間で起きたことは、恐るべきことだ」
南極半島西部で急速に温暖化が進んだ理由は、地球規模の気温上昇だけでなく、局地的な海流や気流の変化も関係している。世界全体でみれば、温暖化のペースはもっと緩やかで、過去100年間で平均気温が0.6℃上昇したにすぎない。とはいえ、この程度の比較的小さな気候の変化でも、影響は自然界全体に広がっている。フレーザーが心血を注いできた南極半島の調査は、温暖化が地球全体の生態系に与える深刻な影響を解明する手がかりを与えてくれる。
すでに動植物や昆虫は温暖化に適応するため、渡りや移動の時期を早めたり、交尾や開花の時期を変えたりしている。ヨーロッパでは最近の数十年間で、定住型のチョウのうち35種が、生息地域を30〜240キロ北へ拡大させたことが分かった。また、多くの植物の開花期が50年前より1週間ほど早まり、秋の紅葉が5日ほど遅くなった。
英国の鳥は20世紀半ばに比べて卵の孵化の時期が平均9日早くなり、カエルの交尾期は最高で7週間も早まった。北米のジュドウアオツバメは25年前に比べ、春に北へ移動するのが12日早くなった。カナダのアカギツネの生息地域は数百キロ北極寄りに移り、ホッキョクギツネのテリトリーに入り込んでいる。
高山植物は自生地をじりじりと標高の高いところに移し、山頂近くの希少種を脅かしつつある。地球の気候はこれまで常に自然の変動を繰り返し、温暖化と寒冷化の間で揺れ動いてきた。それでも環境問題の専門家が現在の温暖化に懸念を抱くのには、いくつかの理由がある。まず、今回の温暖化は人間が気候の変化を加速させている可能性があること。そして温暖化のペースが早すぎて、生き物たちが変化に適応して絶滅を逃れるための時間的余裕がないことだ。
さらに、生き物の種によって、それぞれ環境の変化への対応の仕方が違うため、相互依存の関係にある生き物同士の生活サイクルにズレが生じかねない。そして、個体数の減少を引き起こす可能性もある。
今のところは世界の多くの地域で温暖化が進んでも、動植物は高緯度地方や高地に移って暑さから逃れることができる。だが、このような退避ルートには限りがあり、なかには人間の手で道がふさがれているケースもある。これまでの数千年間と異なり、動植物が適応しなければならない現在の世界は、温暖化問題に加えて、63億人に増えた人類の存在という別の問題も抱えているのだ。
「過去の大規模な気候変動の際には、人類の存在は大きな障害ではなかったので、生き物たちは自由に移動できました。今は生き物たちが生息地を変えようとすると、トウモロコシ畑やシカゴのような大都会に突き当たってしまうおそれがあります」と、環境問題専門家のカミール・パーメザンは言う。
(national Geographic より)
続きです、
---------------------------
温暖化3 未来を予測する
氷河や洞窟、サンゴ礁などから過去何十万年分もの気候データが読み取れる。それを基に将来の気候を予測すれば、どんな未来が待ち受けているかが導き出せるが、さて、未来はどうなるのだろうか。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
花粉化石を調べて過去の植生を研究している、米国オレゴン大学の古気候学者キャシー・ホイットロックが大きな声をかける。「1、2の3、それっ!」。米国北西部、オレゴン州のコースト山脈中部にあるリトル湖の岸辺でのこと。ホイットロックと学生2人、私の計4人はコア採取機を握る手に力を入れ、引っ張り上げた。「もう一回」と彼女が指示する。粉化石を調べて過去の植生を研究している、米国オレゴン大学の古気候学者キャシー・ホイットロックが大きな声をかける。「1、2の3、それっ!」。米国北西部、オレゴン州のコースト山脈中部にあるリトル湖の岸辺でのこと。ホイットロックと学生2人、私の計4人はコア採取機を握る手に力を入れ、引っ張り上げた。「もう一回」と彼女が指示する。
岸辺のぬかるんだ泥土の中に彼女らが埋めておいた筒形の試料採取容器が、ゆっくりと上がってきた。
「あと、もう一回」というホイットロックの掛け声に合わせて再び引っ張り上げると、やっと容器を抜き取ることができた。
ホイットロックは子供がプレゼントをもらった時のような笑顔で、直径5センチ、長さ1メートルほどの古い泥土のコア試料を取り出した。
「素晴らしい試料です」。彼女はそう話すと、泥土の試料の内部を調べるため、ポケットナイフで縦に切り込みを入れた。
「この深みのある茶色の部分は有機物、特に花粉がたくさん含まれているための色でしょう。顕微鏡で見ないと花粉の存在は分からないけど、間違いなく含まれているはずです」
この花粉にこそ、ホイットロックら研究者が取り組んでいる難問を解く手がかりがある。それは、周期的に起こる「急激な気候変動」の原因は何かということだ。
ここで言う気候変動は、過去約100万年の間に10万年ぐらいの周期で氷期(寒冷期)と間氷期(温暖期)が交互に訪れた「緩やかな気候変動」のことではない。寒冷期から温暖期へと急激に移行し、また逆戻りした変動のことだ。こうした急激な変動はどれくらいの頻度とスピードで起こったのか。そして、おそらく最も重要なことは、過去に起きた急激な気候変動から、現在および今後の地球の気候が変わっていく様子を読み取れるか、だ。
こうした疑問を解明しようとして、研究者は過去の気候を知るための材料を、驚くほど様々なところから集めている。氷河の氷やモレーン(氷河が運んだ岩屑)、鍾乳洞の床にできた石筍(石灰質のタケノコ状の塊)、年輪、サンゴ、砂丘、それに深海底の堆積物に埋まる動物性プランクトンの微化石……。さらに、古代の碑文からワイン醸造業者や園芸家の日記、航海日誌にいたるまで、人間の残した記録に手がかりを求める研究者もいる。
「人間の記録と自然の記録の両方が必要だ」と、米国オハイオ州立大学の氷河学者ロニー・トンプソンは言う。彼は、熱帯の高山地帯で解けつつある氷河から雪氷のコア試料を採取して研究している。「人類誕生の時代の前と後の気候のメカニズムについて調べている。そうやって前後を比較して初めて、人間が気候にどんな影響を与えるかが解明できるのです」
気候変動のスピードについては、ホイットロックがリトル湖の泥土のコア試料を使った研究で明らかになっている。ここで採取した試料には、1メートル当たりで約2300年分の樹木や草花の花粉の粒が含まれる。試料から花粉を見つけるには、まず各標本からごく少量の土を取り、それを化学物質の溶液に浸して花粉以外のものをすべて取り除く。そうして残った花粉をほんの一滴スライドに載せ、そこに含まれる300粒ほどの花粉がどんな植物の花粉かを一つずつ特定していく。この作業によって、コースト山脈の植生が過去の気候変動によってどう変化したかが解明できる。
「ここでは深さ18.25メートルで湖底の岩盤に突き当たります」と、ホイットロックは試料を載せたスライドを顕微鏡にセットしながら言う。「その深さから採取した花粉は、4万2000年前のものになります」
リトル湖は、最終氷期(約7万年前から約1万1500年前)が訪れる前に起きた地滑りで小さな川がせき止められてできた湖だ。泥土に含まれる花粉を調べれば、「最終氷期に入る前と、約2万1000年前の最も寒冷な時期にオレゴン州の沿岸地方がどんな環境だったかが分かる。そして約1万3000年前に温暖化が進んだ時期に、環境が大きく変化したのが読み取れる」とホイットロックは言う。「最終氷期のピークだった2万1000年前のこの辺りの森の様子がよく分かるのです」
私が顕微鏡をのぞくと、ホイットロックはスライドを動かし、花粉をいくつも見せてくれた。でも実際には花粉の種類は二つしかなかったので、思いのほか分かりやすかった。エンゲルマントウヒとメルテンスツガの2種類だ。
「現代のコースト山脈にエンゲルマントウヒは生えていません。今見られる針葉樹の多くはダグラスモミです。でもこのスライドの上に、その花粉はない。ダグラスモミの花粉が現れるのは、最終氷期が終わりに近づいた頃です。そしていったん現れると一気に増え、トウヒの森は消えてしまう。それがたった200年から500年の間に起きた。そんな短い期間のうちに森がまるごと消え、違う樹種の森にとって代わられたのです」
ホイットロックはひと呼吸おいてから続けた。「それほど劇的な変化がなぜ、どのようにして起きたのかを突き止めたい。もし、また地球に氷期が訪れたとしたら、あるいは今以上に温暖化が進んだとしたら、どんなことが起きるのか。その時、私たちはどう対応するのでしょう」
(national Geographic より)
---------------------------
温暖化3 未来を予測する
氷河や洞窟、サンゴ礁などから過去何十万年分もの気候データが読み取れる。それを基に将来の気候を予測すれば、どんな未来が待ち受けているかが導き出せるが、さて、未来はどうなるのだろうか。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
花粉化石を調べて過去の植生を研究している、米国オレゴン大学の古気候学者キャシー・ホイットロックが大きな声をかける。「1、2の3、それっ!」。米国北西部、オレゴン州のコースト山脈中部にあるリトル湖の岸辺でのこと。ホイットロックと学生2人、私の計4人はコア採取機を握る手に力を入れ、引っ張り上げた。「もう一回」と彼女が指示する。粉化石を調べて過去の植生を研究している、米国オレゴン大学の古気候学者キャシー・ホイットロックが大きな声をかける。「1、2の3、それっ!」。米国北西部、オレゴン州のコースト山脈中部にあるリトル湖の岸辺でのこと。ホイットロックと学生2人、私の計4人はコア採取機を握る手に力を入れ、引っ張り上げた。「もう一回」と彼女が指示する。
岸辺のぬかるんだ泥土の中に彼女らが埋めておいた筒形の試料採取容器が、ゆっくりと上がってきた。
「あと、もう一回」というホイットロックの掛け声に合わせて再び引っ張り上げると、やっと容器を抜き取ることができた。
ホイットロックは子供がプレゼントをもらった時のような笑顔で、直径5センチ、長さ1メートルほどの古い泥土のコア試料を取り出した。
「素晴らしい試料です」。彼女はそう話すと、泥土の試料の内部を調べるため、ポケットナイフで縦に切り込みを入れた。
「この深みのある茶色の部分は有機物、特に花粉がたくさん含まれているための色でしょう。顕微鏡で見ないと花粉の存在は分からないけど、間違いなく含まれているはずです」
この花粉にこそ、ホイットロックら研究者が取り組んでいる難問を解く手がかりがある。それは、周期的に起こる「急激な気候変動」の原因は何かということだ。
ここで言う気候変動は、過去約100万年の間に10万年ぐらいの周期で氷期(寒冷期)と間氷期(温暖期)が交互に訪れた「緩やかな気候変動」のことではない。寒冷期から温暖期へと急激に移行し、また逆戻りした変動のことだ。こうした急激な変動はどれくらいの頻度とスピードで起こったのか。そして、おそらく最も重要なことは、過去に起きた急激な気候変動から、現在および今後の地球の気候が変わっていく様子を読み取れるか、だ。
こうした疑問を解明しようとして、研究者は過去の気候を知るための材料を、驚くほど様々なところから集めている。氷河の氷やモレーン(氷河が運んだ岩屑)、鍾乳洞の床にできた石筍(石灰質のタケノコ状の塊)、年輪、サンゴ、砂丘、それに深海底の堆積物に埋まる動物性プランクトンの微化石……。さらに、古代の碑文からワイン醸造業者や園芸家の日記、航海日誌にいたるまで、人間の残した記録に手がかりを求める研究者もいる。
「人間の記録と自然の記録の両方が必要だ」と、米国オハイオ州立大学の氷河学者ロニー・トンプソンは言う。彼は、熱帯の高山地帯で解けつつある氷河から雪氷のコア試料を採取して研究している。「人類誕生の時代の前と後の気候のメカニズムについて調べている。そうやって前後を比較して初めて、人間が気候にどんな影響を与えるかが解明できるのです」
気候変動のスピードについては、ホイットロックがリトル湖の泥土のコア試料を使った研究で明らかになっている。ここで採取した試料には、1メートル当たりで約2300年分の樹木や草花の花粉の粒が含まれる。試料から花粉を見つけるには、まず各標本からごく少量の土を取り、それを化学物質の溶液に浸して花粉以外のものをすべて取り除く。そうして残った花粉をほんの一滴スライドに載せ、そこに含まれる300粒ほどの花粉がどんな植物の花粉かを一つずつ特定していく。この作業によって、コースト山脈の植生が過去の気候変動によってどう変化したかが解明できる。
「ここでは深さ18.25メートルで湖底の岩盤に突き当たります」と、ホイットロックは試料を載せたスライドを顕微鏡にセットしながら言う。「その深さから採取した花粉は、4万2000年前のものになります」
リトル湖は、最終氷期(約7万年前から約1万1500年前)が訪れる前に起きた地滑りで小さな川がせき止められてできた湖だ。泥土に含まれる花粉を調べれば、「最終氷期に入る前と、約2万1000年前の最も寒冷な時期にオレゴン州の沿岸地方がどんな環境だったかが分かる。そして約1万3000年前に温暖化が進んだ時期に、環境が大きく変化したのが読み取れる」とホイットロックは言う。「最終氷期のピークだった2万1000年前のこの辺りの森の様子がよく分かるのです」
私が顕微鏡をのぞくと、ホイットロックはスライドを動かし、花粉をいくつも見せてくれた。でも実際には花粉の種類は二つしかなかったので、思いのほか分かりやすかった。エンゲルマントウヒとメルテンスツガの2種類だ。
「現代のコースト山脈にエンゲルマントウヒは生えていません。今見られる針葉樹の多くはダグラスモミです。でもこのスライドの上に、その花粉はない。ダグラスモミの花粉が現れるのは、最終氷期が終わりに近づいた頃です。そしていったん現れると一気に増え、トウヒの森は消えてしまう。それがたった200年から500年の間に起きた。そんな短い期間のうちに森がまるごと消え、違う樹種の森にとって代わられたのです」
ホイットロックはひと呼吸おいてから続けた。「それほど劇的な変化がなぜ、どのようにして起きたのかを突き止めたい。もし、また地球に氷期が訪れたとしたら、あるいは今以上に温暖化が進んだとしたら、どんなことが起きるのか。その時、私たちはどう対応するのでしょう」
(national Geographic より)
つづき
--------------------------
温暖化4 日本の取り組み
地球温暖化の進行を抑えるため、日本はどんな手を打っているのか。政府がその柱にすえているのが、「京都議定書」で決めた温室効果ガスの削減目標の達成だ。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
京都議定書は1997年12月、京都で開催された国際会議「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」で採択された。世界各国で分担して、二酸化炭素やメタン、代替フロンなど6種類の温室効果ガスを減らそうという取り決めだ。最初の目標として、先進国全体で2008?12年までの年平均排出量を90年比(代替フロン等3ガスは95年を基準にできる)で5%以上削減することが掲げられた。
各国・地域の削減目標はEUが8%、米国が7%、ロシアが0%。日本は6%減で合意した。すでに欧州や日本などが議定書を批准しており、ロシアの批准を待って発効する予定。発効しなければ法的拘束力はないが、それでも日本政府は温室効果ガスの削減に取り組む。
国内排出削減分は0.5%
日本にとって、増え続けている温室効果ガスの排出をマイナスに転ずるのは容易ではない。政府は、どのような方法で6%減を達成するのかを細かく示した「地球温暖化対策推進大綱」を1998年に策定、2002年3月に改訂した。たとえば、自動車の燃費改善で約1390万トン(二酸化炭素換算)を削減、各家庭でシャワーを1日1分、家族全員が減らして93万トン(同)を削減するといった具合だ。
大綱が掲げる削減策は、議定書の本来の目的である国内での排出削減と、それ以外の対策に分けられる。6%のうち前者で0.5%分を、後者で5.5%分を削減する。
国内での排出削減目標は次の通り。化石燃料の利用で生じる「エネルギー起源の二酸化炭素」は90年レベルに維持。「非エネルギー起源の二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素の3ガス」は基準年の総排出量の0.5%分削減する。「代替フロン等3ガス」は同2.0%分の増加に抑える。さらに、技術開発や国民の努力で2.0%分削減する。合わせて0.5%分だ。
残り5.5%の達成方法は以下の二つ。一つは、既存の森林を管理すれば削減分とみなすことができる「森林吸収源」の適用。国際交渉の末に認められたこの手段で、日本は目標削減量の6割以上に当たる3.9%分をまかなう。
そしてもう一つの手段は、海外で削減分を補える「京都メカニズム」。外国の余った削減分(排出権)を買ったり、外国と共同で植林など排出削減の取り組みをして、その削減分を両国で分配することが認められている。すでに政府はブータンでの水力発電プロジェクトなど八つの案件を承認しているが、本格的な活用はこれからだ。日本はこの京都メカニズムで6%のうち1.6%分を補う算段だ。
森林吸収源と京都メカニズムは達成が見込めるが、問題は国内での排出削減だ。2002年の国内の温室効果ガス排出量は13億3100万トン(二酸化炭素換算)で、基準年に比べて減るどころか、7.6%も増加している。
なかには、すでに目標が達成できそうな分野がある。たとえばオゾン層を破壊するフロンの代わりに冷媒などへの利用が増えている代替フロン等3ガスは、エアコンなどからの回収率を高めるなどの対策が進み、排出量を大幅に減らしている。ところが一方で、総排出量の90%近くを占めるエネルギー起源の二酸化炭素の排出が12%も増えている。
なかでも運輸部門が90年比20%増、民生部門(家庭)が29%増と著しい。ハイブリッド自動車など燃費のよい自動車や省エネ住宅、省エネ家電の開発が進み、普及しつつあるものの、それ以上に世帯数や自家用車の台数の増加が大きい。2000年の人口は90年比で2.7%増なのに対し、世帯数は15%、自家用車保有台数は29%といずれも二桁の伸びだ。一人ひとりが積極的に生活を変えていかなければ、温暖化は抑えられなくなっている。
こうした背景を受け現在、環境省や経済産業省が大綱の2度目の見直しを進めている。最大の焦点になっているのが温暖化対策税だ。家庭や自動車などで排出される温室効果ガスの量に応じて課税する政策で、「炭素税」などとも呼ばれる。すでに欧州などでは導入が進んでいる。
この税制を導入すれば、化石燃料の価格などエネルギー消費のコストが上昇し、省エネ効果があると環境省は期待する。現在提案されているのは温室効果ガス1トン(炭素換算)当たり3000円程度の税率で、ガソリン1リットル当たり約2円の価格上昇となる見込みだ。
これに対し、産業界は一貫して反対している。日本経済団体連合会(経団連)は「景気回復に水を差す」と猛反発し、経済産業省も否定的な立場だ。「課税によって海外との競争力が落ちれば、その産業は打撃を受ける。生産が減って温室効果ガスの国内排出は減るだろうが、減った生産を海外から輸入するのであれば、その分排出を海外に移しただけで、日本にとって単なる痛みでしかない」と、経済産業省の岸本吉生環境経済室長は話す。
6%減の目標を達成できなければ、次の約束期間にさらに高い目標値が設定されるうえ、国際交渉でもマイナスになる。結局は強引にでも帳尻を合わせることになるだろう。
とても小さな一歩だが
しかし、京都議定書はわずかな一歩でしかない。温暖化を止めるには温室効果ガスの排出量を現在の50%以下に減らす必要がある。2012年までの取り組みを2150年まで何度も繰り返してやっと、気温が今より2〜5℃上昇したところで安定すると考えられている。
さらに、米国やオーストラリアといった温室効果ガスの排出大国が京都議定書から離脱したため、京都議定書の実効性はさらに小さくなってしまった。
米国は世界全体の二酸化炭素排出量のうち、最も多い約24%を排出する(右ページ)。議定書の策定時には7%削減で合意したものの、途上国の削減目標がないことや、自国の経済に悪影響を及ぼすなどの理由で2001年に議定書を離脱した。この動きに追従するように、オーストラリアも離脱してしまった。
一方で、途上国が温室効果ガスの削減に消極的なことも今後の温暖化対策に影を落としている。途上国にしてみれば、膨大な化石燃料を消費して地球温暖化を引き起こしたのは先進国であるとの思いが強い。そのため2012年までの第一約束期間では、これらの国々の経済発展を妨げないよう削減の約束は見送られた。しかし、そこには世界第2位の排出国である中国も含まれており、その排出量は年々増えている。先進国が排出削減の努力をするほど、途上国の総排出量に占める比率が高くなる。次の約束期間でこうした国々を参加させることが課題だ。
京都議定書に距離を置く国がある一方で、積極的にさらに高い目標を掲げる国もある。
たとえば、ドイツはEU内の目標で2008?12年に温室効果ガスを21%削減することを約束、2002年までに18.9%減らした。英国もEU内で12.5%の削減を約束し、すでに14.9%の削減に成功している。
両国とも京都メカニズムを利用せずに目標を達成できる見込みだ。ドイツは旧東ドイツのエネルギー効率の低い環境を改善することで大幅に排出量を削減した。英国では、先進国の責任として2050年までに自国の排出量を60%削減するという大目標を掲げ、対策に取り組んでいる。すでに温暖化対策税を導入しているほか、火力発電から天然ガスによる発電へとエネルギー転換を急速に進めている。
環境省の清水康弘地球温暖化対策課長はこう話す。「日本も目の前の6%削減だけにとらわれず、50年、100年先を見すえた対策が必要です。現状では社会制度が温暖化に対応したものになっていない。たとえば電力を使うほど使用料が高くなるとか、渋滞の激しい地域で料金を徴収して交通量を抑制するなど社会システム自体を変えていくことが必要です」
(national Geographic より)
--------------------------
温暖化4 日本の取り組み
地球温暖化の進行を抑えるため、日本はどんな手を打っているのか。政府がその柱にすえているのが、「京都議定書」で決めた温室効果ガスの削減目標の達成だ。(この記事は2004年9月号に掲載されたものです。)
京都議定書は1997年12月、京都で開催された国際会議「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」で採択された。世界各国で分担して、二酸化炭素やメタン、代替フロンなど6種類の温室効果ガスを減らそうという取り決めだ。最初の目標として、先進国全体で2008?12年までの年平均排出量を90年比(代替フロン等3ガスは95年を基準にできる)で5%以上削減することが掲げられた。
各国・地域の削減目標はEUが8%、米国が7%、ロシアが0%。日本は6%減で合意した。すでに欧州や日本などが議定書を批准しており、ロシアの批准を待って発効する予定。発効しなければ法的拘束力はないが、それでも日本政府は温室効果ガスの削減に取り組む。
国内排出削減分は0.5%
日本にとって、増え続けている温室効果ガスの排出をマイナスに転ずるのは容易ではない。政府は、どのような方法で6%減を達成するのかを細かく示した「地球温暖化対策推進大綱」を1998年に策定、2002年3月に改訂した。たとえば、自動車の燃費改善で約1390万トン(二酸化炭素換算)を削減、各家庭でシャワーを1日1分、家族全員が減らして93万トン(同)を削減するといった具合だ。
大綱が掲げる削減策は、議定書の本来の目的である国内での排出削減と、それ以外の対策に分けられる。6%のうち前者で0.5%分を、後者で5.5%分を削減する。
国内での排出削減目標は次の通り。化石燃料の利用で生じる「エネルギー起源の二酸化炭素」は90年レベルに維持。「非エネルギー起源の二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素の3ガス」は基準年の総排出量の0.5%分削減する。「代替フロン等3ガス」は同2.0%分の増加に抑える。さらに、技術開発や国民の努力で2.0%分削減する。合わせて0.5%分だ。
残り5.5%の達成方法は以下の二つ。一つは、既存の森林を管理すれば削減分とみなすことができる「森林吸収源」の適用。国際交渉の末に認められたこの手段で、日本は目標削減量の6割以上に当たる3.9%分をまかなう。
そしてもう一つの手段は、海外で削減分を補える「京都メカニズム」。外国の余った削減分(排出権)を買ったり、外国と共同で植林など排出削減の取り組みをして、その削減分を両国で分配することが認められている。すでに政府はブータンでの水力発電プロジェクトなど八つの案件を承認しているが、本格的な活用はこれからだ。日本はこの京都メカニズムで6%のうち1.6%分を補う算段だ。
森林吸収源と京都メカニズムは達成が見込めるが、問題は国内での排出削減だ。2002年の国内の温室効果ガス排出量は13億3100万トン(二酸化炭素換算)で、基準年に比べて減るどころか、7.6%も増加している。
なかには、すでに目標が達成できそうな分野がある。たとえばオゾン層を破壊するフロンの代わりに冷媒などへの利用が増えている代替フロン等3ガスは、エアコンなどからの回収率を高めるなどの対策が進み、排出量を大幅に減らしている。ところが一方で、総排出量の90%近くを占めるエネルギー起源の二酸化炭素の排出が12%も増えている。
なかでも運輸部門が90年比20%増、民生部門(家庭)が29%増と著しい。ハイブリッド自動車など燃費のよい自動車や省エネ住宅、省エネ家電の開発が進み、普及しつつあるものの、それ以上に世帯数や自家用車の台数の増加が大きい。2000年の人口は90年比で2.7%増なのに対し、世帯数は15%、自家用車保有台数は29%といずれも二桁の伸びだ。一人ひとりが積極的に生活を変えていかなければ、温暖化は抑えられなくなっている。
こうした背景を受け現在、環境省や経済産業省が大綱の2度目の見直しを進めている。最大の焦点になっているのが温暖化対策税だ。家庭や自動車などで排出される温室効果ガスの量に応じて課税する政策で、「炭素税」などとも呼ばれる。すでに欧州などでは導入が進んでいる。
この税制を導入すれば、化石燃料の価格などエネルギー消費のコストが上昇し、省エネ効果があると環境省は期待する。現在提案されているのは温室効果ガス1トン(炭素換算)当たり3000円程度の税率で、ガソリン1リットル当たり約2円の価格上昇となる見込みだ。
これに対し、産業界は一貫して反対している。日本経済団体連合会(経団連)は「景気回復に水を差す」と猛反発し、経済産業省も否定的な立場だ。「課税によって海外との競争力が落ちれば、その産業は打撃を受ける。生産が減って温室効果ガスの国内排出は減るだろうが、減った生産を海外から輸入するのであれば、その分排出を海外に移しただけで、日本にとって単なる痛みでしかない」と、経済産業省の岸本吉生環境経済室長は話す。
6%減の目標を達成できなければ、次の約束期間にさらに高い目標値が設定されるうえ、国際交渉でもマイナスになる。結局は強引にでも帳尻を合わせることになるだろう。
とても小さな一歩だが
しかし、京都議定書はわずかな一歩でしかない。温暖化を止めるには温室効果ガスの排出量を現在の50%以下に減らす必要がある。2012年までの取り組みを2150年まで何度も繰り返してやっと、気温が今より2〜5℃上昇したところで安定すると考えられている。
さらに、米国やオーストラリアといった温室効果ガスの排出大国が京都議定書から離脱したため、京都議定書の実効性はさらに小さくなってしまった。
米国は世界全体の二酸化炭素排出量のうち、最も多い約24%を排出する(右ページ)。議定書の策定時には7%削減で合意したものの、途上国の削減目標がないことや、自国の経済に悪影響を及ぼすなどの理由で2001年に議定書を離脱した。この動きに追従するように、オーストラリアも離脱してしまった。
一方で、途上国が温室効果ガスの削減に消極的なことも今後の温暖化対策に影を落としている。途上国にしてみれば、膨大な化石燃料を消費して地球温暖化を引き起こしたのは先進国であるとの思いが強い。そのため2012年までの第一約束期間では、これらの国々の経済発展を妨げないよう削減の約束は見送られた。しかし、そこには世界第2位の排出国である中国も含まれており、その排出量は年々増えている。先進国が排出削減の努力をするほど、途上国の総排出量に占める比率が高くなる。次の約束期間でこうした国々を参加させることが課題だ。
京都議定書に距離を置く国がある一方で、積極的にさらに高い目標を掲げる国もある。
たとえば、ドイツはEU内の目標で2008?12年に温室効果ガスを21%削減することを約束、2002年までに18.9%減らした。英国もEU内で12.5%の削減を約束し、すでに14.9%の削減に成功している。
両国とも京都メカニズムを利用せずに目標を達成できる見込みだ。ドイツは旧東ドイツのエネルギー効率の低い環境を改善することで大幅に排出量を削減した。英国では、先進国の責任として2050年までに自国の排出量を60%削減するという大目標を掲げ、対策に取り組んでいる。すでに温暖化対策税を導入しているほか、火力発電から天然ガスによる発電へとエネルギー転換を急速に進めている。
環境省の清水康弘地球温暖化対策課長はこう話す。「日本も目の前の6%削減だけにとらわれず、50年、100年先を見すえた対策が必要です。現状では社会制度が温暖化に対応したものになっていない。たとえば電力を使うほど使用料が高くなるとか、渋滞の激しい地域で料金を徴収して交通量を抑制するなど社会システム自体を変えていくことが必要です」
(national Geographic より)
『温暖化関連ニュース』
-----------------------
CNET Japan - 2007年2月22日
水源がまず枯渇--地球温暖化で専門家が警告
文:Michael Kanellos(CNET News.com)
地球温暖化で最初に影響を受けるのは、水かもしれない。
Lawrence Berkeley National Laboratoryのディレクターであり、代替エネルギーの研究費増額に奮闘する世界有数の科学者、Steven Chu氏をはじめ、多くの識者が、地球の温度上昇によって氷河や湖などの水源が急速に枯渇すると予測している。
Chu氏は、水の供給が激減すれば、その影響は甚大かつ深刻なものになると述べ、一部ではそうした影響がすでに見られていると話す。同氏は、1997年にノーベル物理学賞を共同受賞した人物だ。
今週に入りサンフランシスコで開催された「Cleantech Forum」の講演で、Chu氏は「夏期には黄河が干上がるようになった」と語った。
ヒマラヤ山脈の氷河や融雪を水源とする黄河は今、水量を減らしつつある。世界人口の多くがヒマラヤ山脈から生み出される水を利用していることから、こうした兆候は一般的にもよいものとは言えない。
米国では、カリフォルニア州およびネバダ州にかけて広がるシエラネバダ山脈の積雪量が、2100年までに30〜70%減少する見込みだという。
減少率が20%にとどまった場合でも、芝生に水をやったり、トイレを頻繁に流したりすることを止めねばならないだろう。50%以上の減少率なら、カリフォルニア州の人口までもが減る可能性がある。積雪量が大幅に減少すれば農業も大打撃を受け、州外への移出はさらに加速すると、Chu氏は述べている。
もっとも、世界のある地域の山脈や山岳では、積雪はむしろ増えている。乾燥地帯はより乾燥し、湿潤地帯では降雨量が増えていくというのが、大半の専門家の見方だ。だが、降雪および降雨量が増えても、温暖化のせいで山脈は水を確保できず、ほとんどが使用される前に流出してしまうのだという。
「温暖化の影響を家庭で最初に受けるのは、おそらく水だ。貯水に関する問題は、日に日に深刻化している」(Chu氏)
複数の新興企業やGeneral Electricなどの一部大手企業は、海水や廃水を浄化し、人間が利用できるようにするシステムへの投資を増強し始めている。
Cleantech Venture Networkの会長Nicholas Parker氏は、「水問題はさらに顕著化するだろう」と予想している。
-----------------------
CNET Japan - 2007年2月22日
水源がまず枯渇--地球温暖化で専門家が警告
文:Michael Kanellos(CNET News.com)
地球温暖化で最初に影響を受けるのは、水かもしれない。
Lawrence Berkeley National Laboratoryのディレクターであり、代替エネルギーの研究費増額に奮闘する世界有数の科学者、Steven Chu氏をはじめ、多くの識者が、地球の温度上昇によって氷河や湖などの水源が急速に枯渇すると予測している。
Chu氏は、水の供給が激減すれば、その影響は甚大かつ深刻なものになると述べ、一部ではそうした影響がすでに見られていると話す。同氏は、1997年にノーベル物理学賞を共同受賞した人物だ。
今週に入りサンフランシスコで開催された「Cleantech Forum」の講演で、Chu氏は「夏期には黄河が干上がるようになった」と語った。
ヒマラヤ山脈の氷河や融雪を水源とする黄河は今、水量を減らしつつある。世界人口の多くがヒマラヤ山脈から生み出される水を利用していることから、こうした兆候は一般的にもよいものとは言えない。
米国では、カリフォルニア州およびネバダ州にかけて広がるシエラネバダ山脈の積雪量が、2100年までに30〜70%減少する見込みだという。
減少率が20%にとどまった場合でも、芝生に水をやったり、トイレを頻繁に流したりすることを止めねばならないだろう。50%以上の減少率なら、カリフォルニア州の人口までもが減る可能性がある。積雪量が大幅に減少すれば農業も大打撃を受け、州外への移出はさらに加速すると、Chu氏は述べている。
もっとも、世界のある地域の山脈や山岳では、積雪はむしろ増えている。乾燥地帯はより乾燥し、湿潤地帯では降雨量が増えていくというのが、大半の専門家の見方だ。だが、降雪および降雨量が増えても、温暖化のせいで山脈は水を確保できず、ほとんどが使用される前に流出してしまうのだという。
「温暖化の影響を家庭で最初に受けるのは、おそらく水だ。貯水に関する問題は、日に日に深刻化している」(Chu氏)
複数の新興企業やGeneral Electricなどの一部大手企業は、海水や廃水を浄化し、人間が利用できるようにするシステムへの投資を増強し始めている。
Cleantech Venture Networkの会長Nicholas Parker氏は、「水問題はさらに顕著化するだろう」と予想している。
Japan News Network。(27日11:03)
NASA学者、米政権の温暖化政策批判
アメリカのNASA=航空宇宙局を代表する科学者が、ブッシュ政権の温暖化政策を公然と批判し、石炭による火力発電所の建設の即時凍結などを訴えしました。
「(地球温暖化の)証拠が明白なのに、我々はすべきことを何もしていない」(米航空宇宙局・ゴッダード宇宙科学研究所、ジェームズ・ハンセン博士)
NASAのジェームズ・ハンセン博士はこのように述べ、この10年に変化を起こさなければ、人類の滅亡につながる恐れがあると警告しました。
その上で、ハンセン氏は、石炭を使った火力発電所の建設を即時凍結することなど、緊急の対策が必要だと述べました。
ブッシュ政権は、過去に温暖化に関する科学者の報告書を都合のいいように書き換えていたことがわかっていますが、ハンセン氏も、発言をめぐってNASAの上層部から圧力をかけられたことがあるということです。
「30年間働いてきたが、現在は(情報統制が)ひどい状況だ」(米航空宇宙局・ゴッダード宇宙科学研究所、ジェームズ・ハンセン博士)
NASAとは関係なく個人的な立場で発言したことについて、ハンセン氏は、地球温暖化の真実が国民にきちんと伝わっていないことが理由だとしています。(27日11:03)
NASA学者、米政権の温暖化政策批判
アメリカのNASA=航空宇宙局を代表する科学者が、ブッシュ政権の温暖化政策を公然と批判し、石炭による火力発電所の建設の即時凍結などを訴えしました。
「(地球温暖化の)証拠が明白なのに、我々はすべきことを何もしていない」(米航空宇宙局・ゴッダード宇宙科学研究所、ジェームズ・ハンセン博士)
NASAのジェームズ・ハンセン博士はこのように述べ、この10年に変化を起こさなければ、人類の滅亡につながる恐れがあると警告しました。
その上で、ハンセン氏は、石炭を使った火力発電所の建設を即時凍結することなど、緊急の対策が必要だと述べました。
ブッシュ政権は、過去に温暖化に関する科学者の報告書を都合のいいように書き換えていたことがわかっていますが、ハンセン氏も、発言をめぐってNASAの上層部から圧力をかけられたことがあるということです。
「30年間働いてきたが、現在は(情報統制が)ひどい状況だ」(米航空宇宙局・ゴッダード宇宙科学研究所、ジェームズ・ハンセン博士)
NASAとは関係なく個人的な立場で発言したことについて、ハンセン氏は、地球温暖化の真実が国民にきちんと伝わっていないことが理由だとしています。(27日11:03)
温暖化は海水も着実にあっためています。海流の変化、漁業への影響が危惧されています。
私もこのまま進んだ場合の改定のメタンハイドレートの崩壊が恐ろしいです。
今回の水温が上がっているのが 200-1200mの深さということですから、メタンハイドレートのあるところも含まれています。このまま気温、海水温が上昇していく危険を感じます。
以下、昨日の記事です。
-------------------------------------
流氷の“ふるさと”も温暖化
流氷の「ふるさと」、オホーツク海から遠く北太平洋にかけての水深約200〜1200メートルに横たわる「中層水」の水温が過去50年間に最大約0・7度上昇したことを、北海道大低温科学研究所の若土正曉教授らのグループが突き止めた。
地球温暖化が原因とみられ、オホーツク海や親潮域の豊かな漁場に悪影響を及ぼす可能性がある重大な変化とみられる。
同グループは、北太平洋やオホーツク海の計6万3000カ所の水温と海中の酸素量について、1955〜2004年のデータを解析。その結果、オホーツク海で水温が最大約0・7度上昇、生物の呼吸に必要な酸素量は最大で1リットル当たり0・7ミリリットル減と変化が見られた。こうした傾向は親潮域や、北太平洋北西部にも広がっていた。
海氷は氷点下30〜40度の強風がシベリアから吹き付けるオホーツク海北西部の沿岸域でできる。一部は流氷となり北海道まで到達する。海氷ができる際に重く冷たい「ブライン」という水が作り出されて深く潜り、中層水を形成。鉄分などプランクトンや魚に必要な栄養分は中層水の流れによって北太平洋まで運ばれ、親潮域を豊かな海にしているとされる。
今回、中層水の長期的な温度上昇が確認されたことで、オホーツク海の海氷を作るシステムが温暖化で弱まっていることが裏付けられる上、栄養分の運搬力も低下しつつあると推測できる。
若土教授は「温暖化の影響が海の深い層にまで及び、大きな広がりをみせていたことに驚いている。この海域を海洋資源の宝庫といえる海にしている特有の海洋循環システムが、温暖化によって大きく狂い始めている」と警鐘を鳴らしている。
[mikkansprts.com 2007年2月26日20時16分]
私もこのまま進んだ場合の改定のメタンハイドレートの崩壊が恐ろしいです。
今回の水温が上がっているのが 200-1200mの深さということですから、メタンハイドレートのあるところも含まれています。このまま気温、海水温が上昇していく危険を感じます。
以下、昨日の記事です。
-------------------------------------
流氷の“ふるさと”も温暖化
流氷の「ふるさと」、オホーツク海から遠く北太平洋にかけての水深約200〜1200メートルに横たわる「中層水」の水温が過去50年間に最大約0・7度上昇したことを、北海道大低温科学研究所の若土正曉教授らのグループが突き止めた。
地球温暖化が原因とみられ、オホーツク海や親潮域の豊かな漁場に悪影響を及ぼす可能性がある重大な変化とみられる。
同グループは、北太平洋やオホーツク海の計6万3000カ所の水温と海中の酸素量について、1955〜2004年のデータを解析。その結果、オホーツク海で水温が最大約0・7度上昇、生物の呼吸に必要な酸素量は最大で1リットル当たり0・7ミリリットル減と変化が見られた。こうした傾向は親潮域や、北太平洋北西部にも広がっていた。
海氷は氷点下30〜40度の強風がシベリアから吹き付けるオホーツク海北西部の沿岸域でできる。一部は流氷となり北海道まで到達する。海氷ができる際に重く冷たい「ブライン」という水が作り出されて深く潜り、中層水を形成。鉄分などプランクトンや魚に必要な栄養分は中層水の流れによって北太平洋まで運ばれ、親潮域を豊かな海にしているとされる。
今回、中層水の長期的な温度上昇が確認されたことで、オホーツク海の海氷を作るシステムが温暖化で弱まっていることが裏付けられる上、栄養分の運搬力も低下しつつあると推測できる。
若土教授は「温暖化の影響が海の深い層にまで及び、大きな広がりをみせていたことに驚いている。この海域を海洋資源の宝庫といえる海にしている特有の海洋循環システムが、温暖化によって大きく狂い始めている」と警鐘を鳴らしている。
[mikkansprts.com 2007年2月26日20時16分]
まゆさん
ああ 自家発電電池というのは 燃料電池ですね。水素と酸素を使って発電できるようです。水の電気分解の逆ですね。これは小型でいいので 各家庭にも置けるようです。でも、まだ あまり普及していませんね。
まず、自動車が燃料電池になると思います。これは試作品が出来ています。その次に家庭用の発電機だと思います。
ただ、問題は水素を作るのにエネルギーが要るようです。ですから 自動車や家庭用で使う場合はCO2が出ませんが、水素を作るときにCO2が出るわけです。そのトータルがどうなるかですね。私も まだそこまでよく分からないです。
温暖化対策; CO2の排出量の多い、?アメリカ、中国、ロシア、日本、インドが積極的にやらないと効果が上がりません。
特に急速に経済発展している中国に一日も早く対策をとってもらわないといけませんね。
アメリカは クリントン大統領のときは積極的だったんですがねブッシュ大統領になってから 変わりました。アメリカの石油、軍需産業がその支持母体で 多くの政治献金が出ていたようです。ですから 癒着ですね。NASAの研究者の論文もブッシュの命令で改ざんされていたようです。
http://tanakanews.com/070227warming.htm
アメリカの温暖化に対する世論はかなり盛り上がっていますよ。50%ぐらいが危機感を持っているとどこかでみました。そのため、ブッシュは消極的ですが、あのシュワちゃんが知事やってるところ、LAだったかな? そこは 温暖化関連の法案を作っているようです。
もう少しですよ!!
ああ 自家発電電池というのは 燃料電池ですね。水素と酸素を使って発電できるようです。水の電気分解の逆ですね。これは小型でいいので 各家庭にも置けるようです。でも、まだ あまり普及していませんね。
まず、自動車が燃料電池になると思います。これは試作品が出来ています。その次に家庭用の発電機だと思います。
ただ、問題は水素を作るのにエネルギーが要るようです。ですから 自動車や家庭用で使う場合はCO2が出ませんが、水素を作るときにCO2が出るわけです。そのトータルがどうなるかですね。私も まだそこまでよく分からないです。
温暖化対策; CO2の排出量の多い、?アメリカ、中国、ロシア、日本、インドが積極的にやらないと効果が上がりません。
特に急速に経済発展している中国に一日も早く対策をとってもらわないといけませんね。
アメリカは クリントン大統領のときは積極的だったんですがねブッシュ大統領になってから 変わりました。アメリカの石油、軍需産業がその支持母体で 多くの政治献金が出ていたようです。ですから 癒着ですね。NASAの研究者の論文もブッシュの命令で改ざんされていたようです。
http://tanakanews.com/070227warming.htm
アメリカの温暖化に対する世論はかなり盛り上がっていますよ。50%ぐらいが危機感を持っているとどこかでみました。そのため、ブッシュは消極的ですが、あのシュワちゃんが知事やってるところ、LAだったかな? そこは 温暖化関連の法案を作っているようです。
もう少しですよ!!
愛さん
まだ、あきらめないで 最後まで努力しましょう!!
光、熱、回転などのエネルギーの節約はすべてCO2の削減につながりますよ!!
いろいろなことをいう人がいますが、私はアル・ゴアさんの言うことが概ね正しいと思います。世の中の殆どの科学者が支持しています。それを信じて行動すればいいと思います。
都立高校の冷房−−− これ私も『ん?』と思いましたが、勉強する学生のことを思うと『やめなさい!!』といいにくいですね。その冷房を使う際の温度設定において 温暖化を意識してくれることを期待します。
石原知事は意識が薄いのかな?
今、日本のCO2の排出量は 産業部門は4−5%削減されているようです。しかし、運輸と一般の家庭が 20-30%と大幅に増えています。この民生部門の削減を急がないといけないですね。
餝この数字正確ではないですが、企業の削減努力はかなり数字に現れていましたが、運輸業とわれわれの生活でのCO2の排出量が増えています。⇒ 後で調べます。
まだ、あきらめないで 最後まで努力しましょう!!
光、熱、回転などのエネルギーの節約はすべてCO2の削減につながりますよ!!
いろいろなことをいう人がいますが、私はアル・ゴアさんの言うことが概ね正しいと思います。世の中の殆どの科学者が支持しています。それを信じて行動すればいいと思います。
都立高校の冷房−−− これ私も『ん?』と思いましたが、勉強する学生のことを思うと『やめなさい!!』といいにくいですね。その冷房を使う際の温度設定において 温暖化を意識してくれることを期待します。
石原知事は意識が薄いのかな?
今、日本のCO2の排出量は 産業部門は4−5%削減されているようです。しかし、運輸と一般の家庭が 20-30%と大幅に増えています。この民生部門の削減を急がないといけないですね。
餝この数字正確ではないですが、企業の削減努力はかなり数字に現れていましたが、運輸業とわれわれの生活でのCO2の排出量が増えています。⇒ 後で調べます。
アメリカの温暖化問題に対する最近の動き
----------------------------------------
アメリカ 温暖化対策、機運が急騰 政権も翻意、支持率回復狙う 北海道新聞2007/02/21 08:25
米国内で地球温暖化対策を求める政治的な動きが、これまでになく盛り上がってきた。リベラル派だけでなく、保守派にも対策強化の機運が広がってきたことが大きな要因。ブッシュ政権も、低迷する支持率回復を見込んで積極姿勢を見せている。(ワシントン・西村卓也)
二月中旬、米上院を会場に、地球温暖化対策の議員フォーラムが開かれた。米国の上下両院議員のほか、ドイツのメルケル首相ら主要八カ国(G8)の代表、中国、インドなど経済が急成長する五カ国も参加した。
フォーラムで米共和党のマケイン上院議員は「私たちは限界点まで来た。米国議会は政府とともに行動しなければならない」と訴えた。民主党系無所属のリーバーマン上院議員は、マケイン氏とともに米国の排出削減目標を設定する新法案を提出する考えを表明した。
両氏とも、イラクからの米軍撤退論に反発する保守派だが、温暖化問題では積極姿勢が目立つ。
米国は二○○一年に京都議定書離脱を表明、「途上国に温暖化ガスの排出削減義務がない」などと議定書批判を繰り返してきた。背景にはブッシュ政権の新保守主義派(ネオコン)が主導した「単独行動主義」があり、米国内保守派は総じて温暖化対策に消極的だった。
しかし、昨年秋の中間選挙敗北後、政権内のネオコンは一掃され、石油業界と近いチェイニー副大統領の影響力も低下。政権一期目で国防副長官を務め、ネオコンの中心人物だったウルフォウィッツ世銀総裁は、同フォーラムで「対応が遅れれば結果は高くつく」と、温暖化対策に積極姿勢を示してみせた。
ブッシュ大統領は一月の一般教書演説でガソリン消費の削減目標を明示するなど、これまでになく温暖化対策に力点を置いた。批判が集中するイラク政策から目をそらせ、支持率回復につなげたい本音が見え隠れする。
もともと温暖化問題の米国での火付け役は、映画「不都合な真実」で温暖化の実態を訴えた民主党のゴア前副大統領。映画はアカデミー賞候補となり、ゴア氏は今年のノーベル平和賞候補にも名が挙がった。○八年の大統領選立候補を求める声も上がっている。
マケイン氏のほか、民主党のヒラリー・クリントン、オバマ両氏ら、来年の大統領選有力候補はいずれも地球温暖化問題を重要視しており、政治的関心はさらに強まることが予想される。
----------------------------------------
アメリカ 温暖化対策、機運が急騰 政権も翻意、支持率回復狙う 北海道新聞2007/02/21 08:25
米国内で地球温暖化対策を求める政治的な動きが、これまでになく盛り上がってきた。リベラル派だけでなく、保守派にも対策強化の機運が広がってきたことが大きな要因。ブッシュ政権も、低迷する支持率回復を見込んで積極姿勢を見せている。(ワシントン・西村卓也)
二月中旬、米上院を会場に、地球温暖化対策の議員フォーラムが開かれた。米国の上下両院議員のほか、ドイツのメルケル首相ら主要八カ国(G8)の代表、中国、インドなど経済が急成長する五カ国も参加した。
フォーラムで米共和党のマケイン上院議員は「私たちは限界点まで来た。米国議会は政府とともに行動しなければならない」と訴えた。民主党系無所属のリーバーマン上院議員は、マケイン氏とともに米国の排出削減目標を設定する新法案を提出する考えを表明した。
両氏とも、イラクからの米軍撤退論に反発する保守派だが、温暖化問題では積極姿勢が目立つ。
米国は二○○一年に京都議定書離脱を表明、「途上国に温暖化ガスの排出削減義務がない」などと議定書批判を繰り返してきた。背景にはブッシュ政権の新保守主義派(ネオコン)が主導した「単独行動主義」があり、米国内保守派は総じて温暖化対策に消極的だった。
しかし、昨年秋の中間選挙敗北後、政権内のネオコンは一掃され、石油業界と近いチェイニー副大統領の影響力も低下。政権一期目で国防副長官を務め、ネオコンの中心人物だったウルフォウィッツ世銀総裁は、同フォーラムで「対応が遅れれば結果は高くつく」と、温暖化対策に積極姿勢を示してみせた。
ブッシュ大統領は一月の一般教書演説でガソリン消費の削減目標を明示するなど、これまでになく温暖化対策に力点を置いた。批判が集中するイラク政策から目をそらせ、支持率回復につなげたい本音が見え隠れする。
もともと温暖化問題の米国での火付け役は、映画「不都合な真実」で温暖化の実態を訴えた民主党のゴア前副大統領。映画はアカデミー賞候補となり、ゴア氏は今年のノーベル平和賞候補にも名が挙がった。○八年の大統領選立候補を求める声も上がっている。
マケイン氏のほか、民主党のヒラリー・クリントン、オバマ両氏ら、来年の大統領選有力候補はいずれも地球温暖化問題を重要視しており、政治的関心はさらに強まることが予想される。
はじめまして。「しげ」と言います。
先の石油高騰もあって、やっと、
アメリカも本腰を入れる気配ですね。
良いことと思います。
代替エネルギーも所詮延命策にすぎず、
人間の感覚の時間で議論するのではなく、
地球創造の時間で議論し、些細なことでも、
早急にやれることは、やらねばいけないと思います。
どなたか、以下のことは、可能か、理論的に正しいか?
検証してもらえませんか?
エネルギーをできるだけ使わないで、温度を下げることが、
望ましいと思いますが、夏に「打ち水」をしますが、
寒いときに、バケツに水を貯めて、氷を作ることで、
気温は下がるのでしょうか?
「Yes」だとすれば、たとえば、北極や南極のような地域で、
自然にまかせ、凍らせると、温暖化はとまりますか?
「Yes」だとすれば、オイルフェンスのようなもので、
海流の流れを止めて、海水温が早く低下するようにすれば、
氷が多くできる。この考えは、正しいか?
どなたか、ご教示ください。
先の石油高騰もあって、やっと、
アメリカも本腰を入れる気配ですね。
良いことと思います。
代替エネルギーも所詮延命策にすぎず、
人間の感覚の時間で議論するのではなく、
地球創造の時間で議論し、些細なことでも、
早急にやれることは、やらねばいけないと思います。
どなたか、以下のことは、可能か、理論的に正しいか?
検証してもらえませんか?
エネルギーをできるだけ使わないで、温度を下げることが、
望ましいと思いますが、夏に「打ち水」をしますが、
寒いときに、バケツに水を貯めて、氷を作ることで、
気温は下がるのでしょうか?
「Yes」だとすれば、たとえば、北極や南極のような地域で、
自然にまかせ、凍らせると、温暖化はとまりますか?
「Yes」だとすれば、オイルフェンスのようなもので、
海流の流れを止めて、海水温が早く低下するようにすれば、
氷が多くできる。この考えは、正しいか?
どなたか、ご教示ください。
しげさん
<寒いときに、バケツに水を貯めて、氷を作ることで、
気温は下がるのでしょうか?>
水を氷にするということは 水から熱を奪っているということで 実際には大気中に熱が逃げ、わずかですが温まっているわけです。
北極海の氷を作るというのは フェンスを作った水を冷やすということが必要です。冬の北極は冷えるでしょうけど、問題は夏です。今の予想では 2040年ぐらいの夏に すべての氷が融けてしまうと言うわけです。
冬には多少元に戻ると思いますが、年々暖かくなり冬に出来る氷も少なくなっていくと思います。
実際は海流がものすごく深海の海水も動かしていて それを止めるのは難しいですし、海水ですし それを十分な氷を作るために冷やすということも難しいと思います。
この程度しか分かりませんが、地球物理に詳しい方に説明していただきたいと思います。
<寒いときに、バケツに水を貯めて、氷を作ることで、
気温は下がるのでしょうか?>
水を氷にするということは 水から熱を奪っているということで 実際には大気中に熱が逃げ、わずかですが温まっているわけです。
北極海の氷を作るというのは フェンスを作った水を冷やすということが必要です。冬の北極は冷えるでしょうけど、問題は夏です。今の予想では 2040年ぐらいの夏に すべての氷が融けてしまうと言うわけです。
冬には多少元に戻ると思いますが、年々暖かくなり冬に出来る氷も少なくなっていくと思います。
実際は海流がものすごく深海の海水も動かしていて それを止めるのは難しいですし、海水ですし それを十分な氷を作るために冷やすということも難しいと思います。
この程度しか分かりませんが、地球物理に詳しい方に説明していただきたいと思います。
ヨーロッパでも記録的な暖冬となっているようです。
-------------------------------------
欧州も記録的暖冬 EU首脳会議で温暖化対策 ('07/3/3 中国新聞)
--------------------------------------------
日本を含め世界各地で暖冬傾向となった今冬は、欧州でも記録的な暖かさとなった。欧州連合(EU)は気候変動問題への危機感を強めており、八日からの首脳会議の主要議題で地球温暖化対策を取り上げるが、既に「暖かい冬」が普通となるとの見方も出ている。
英国は今冬の平均気温が暫定値で五・四七度と、一九一四年の観測開始以来、二番目の暖かさ。英気象専門家はBBC放送(電子版)に対し、気候変動の影響で英国の今後の気候が「暖かく湿度の高い冬、乾燥しより暑い夏」に向かって行く可能性があると指摘した。
過去五十年で最も暖かい冬だったといわれるイタリアでは、野菜や果物に影響も。南部プーリア州では豊作で一部の野菜価格が下落。オレンジの収穫量が半分となる見込みのシチリア島は、農協が「農業の危機」と発表した。イタリア全体の降水量が少なく、早くも夏の水不足が懸念されている。
ドイツでは、冬の平均気温を四度上回り、一九〇一年からの観測史上、最も暖かい冬となった。政府は温室効果ガスの二酸化炭素の排出を、植林などによる吸収で結果的に相殺する「カーボン・ニュートラル」に注目。二月末に、政府関係者の出張の際に移動手段となる飛行機などの二酸化炭素排出量に適用する閣議決定をしたが、具体策の明言を避けており、難しさを示している。(ロンドン、ベルリン、ブリュッセル、ローマ共同)
-------------------------------------
欧州も記録的暖冬 EU首脳会議で温暖化対策 ('07/3/3 中国新聞)
--------------------------------------------
日本を含め世界各地で暖冬傾向となった今冬は、欧州でも記録的な暖かさとなった。欧州連合(EU)は気候変動問題への危機感を強めており、八日からの首脳会議の主要議題で地球温暖化対策を取り上げるが、既に「暖かい冬」が普通となるとの見方も出ている。
英国は今冬の平均気温が暫定値で五・四七度と、一九一四年の観測開始以来、二番目の暖かさ。英気象専門家はBBC放送(電子版)に対し、気候変動の影響で英国の今後の気候が「暖かく湿度の高い冬、乾燥しより暑い夏」に向かって行く可能性があると指摘した。
過去五十年で最も暖かい冬だったといわれるイタリアでは、野菜や果物に影響も。南部プーリア州では豊作で一部の野菜価格が下落。オレンジの収穫量が半分となる見込みのシチリア島は、農協が「農業の危機」と発表した。イタリア全体の降水量が少なく、早くも夏の水不足が懸念されている。
ドイツでは、冬の平均気温を四度上回り、一九〇一年からの観測史上、最も暖かい冬となった。政府は温室効果ガスの二酸化炭素の排出を、植林などによる吸収で結果的に相殺する「カーボン・ニュートラル」に注目。二月末に、政府関係者の出張の際に移動手段となる飛行機などの二酸化炭素排出量に適用する閣議決定をしたが、具体策の明言を避けており、難しさを示している。(ロンドン、ベルリン、ブリュッセル、ローマ共同)
琵琶湖の話題です。琵琶湖が死にかけていますね!!
魚がいなくなるのは 時間の問題ですね!!
また、これと同じことが早晩太平洋、大西洋でも起こります。海洋の酸欠が.... 大食料問題ですね!!
-----------------------------------
滋賀・琵琶湖:北湖の深層「富栄養化」、温暖化で循環不完全 生態系、急変の恐れ
滋賀県・琵琶湖の北湖(琵琶湖大橋以北、最大水深約104メートル)の深層でこの半世紀の間に、富栄養化をもたらす栄養塩の濃度が数倍上昇したことが分かった。
分析した県琵琶湖・環境科学研究センターの専門家は、地球温暖化の影響で表層と深層の水循環が不完全となり、栄養塩が蓄積している可能性を指摘。気候変動などで生態系が急激に変化する「レジームシフト」の兆候の恐れもあるという。
同センターの熊谷道夫・琵琶湖研究部門長らが水深80〜90メートルの観測データを精査した。栄養塩の一種「硝酸態窒素」の濃度平均値は、55年ごろ0・05ppm以下だったが、00年ごろには0・25〜0・30ppm程度に上昇。さらに「リン酸態リン」は、75年以前には0・005ppm以下だったが、00年ごろ0・015〜0・025ppm程度に上昇し、現在に至っている。【服部正法】
毎日新聞 2006年9月10日 東京朝刊
魚がいなくなるのは 時間の問題ですね!!
また、これと同じことが早晩太平洋、大西洋でも起こります。海洋の酸欠が.... 大食料問題ですね!!
-----------------------------------
滋賀・琵琶湖:北湖の深層「富栄養化」、温暖化で循環不完全 生態系、急変の恐れ
滋賀県・琵琶湖の北湖(琵琶湖大橋以北、最大水深約104メートル)の深層でこの半世紀の間に、富栄養化をもたらす栄養塩の濃度が数倍上昇したことが分かった。
分析した県琵琶湖・環境科学研究センターの専門家は、地球温暖化の影響で表層と深層の水循環が不完全となり、栄養塩が蓄積している可能性を指摘。気候変動などで生態系が急激に変化する「レジームシフト」の兆候の恐れもあるという。
同センターの熊谷道夫・琵琶湖研究部門長らが水深80〜90メートルの観測データを精査した。栄養塩の一種「硝酸態窒素」の濃度平均値は、55年ごろ0・05ppm以下だったが、00年ごろには0・25〜0・30ppm程度に上昇。さらに「リン酸態リン」は、75年以前には0・005ppm以下だったが、00年ごろ0・015〜0・025ppm程度に上昇し、現在に至っている。【服部正法】
毎日新聞 2006年9月10日 東京朝刊
オーストラリアも始動?
---------------------------
照明替え明るい未来
温暖化抑止へ豪政府が運動
(Chunichi Web press 20070311)
地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの削減はなかなか進まない。そんな中、オーストラリア政府は先月、白熱電球を電球形蛍光灯に切り替える国家では世界初のキャンペーンを始めた。照明を切り替える省エネ効果は一体、どれほどあるのか?
(岩岡千景)
同政府は医療用などを除き、家庭や商業施設で使われている白熱電球の販売を段階的に規制。電球形蛍光灯への切り替えを進め、五年後の二〇一二年までに四百万トンの温室効果ガスを削減することを目指す。
温室効果ガスは、石炭や重油などを燃やして電力をつくるときに排出される。このため電力の消費を減らせば、地球環境への負荷も減らすことになる。
では、消費電力はどれだけ違うのか。松下電器産業によると、六〇ワット形の場合、従来の白熱電球が五四ワットなのに対し、最新の電球形蛍光灯は一〇ワットと、五分の一以下=図参照。
ただ、価格は白熱電球が百円前後と安く、電球形蛍光灯は千二百円前後と十二倍も高い。だが「意外に気づきにくいのが、長期的な経費」と、同社の加瀬秀樹照明・管球商品チームリーダーは説明する。
寿命も十倍違うため、切り替えると消費電力は電気代にして約一万円の節約になるという。
日本では、照明が一般家庭の消費電力に占める割合は、エアコンの次に多く、冷蔵庫と並ぶ16・1%(二〇〇五年度)。照明の中身をみると、ほぼ三分の一に当たる九・三個が電球だ。このうち省エネ型の電球形蛍光灯は三・二個にすぎず、白熱電球が六・一個とまだまだ多い。
このため、消費者団体「地球温暖化防止・省エネ東京連絡会」が照明の切り替えによる節電効果を消費者セミナーで伝えるなど、草の根で切り替え運動は広がっている。
同連絡会の田嶋いずみさんは「電球を切り替えるだけで、照明の消費電力の80%を減らすことができ、電気代も五分の一にできる。白熱電球と変わらない色や形の製品もある。このことを、もっと知ってほしい」と話す。
環境経済に詳しい永井進法政大教授も「省エネ型の商品選びは有効な温暖化対策。日本も掛け声だけでなく、具体的な目標や規制を決めて国民的な動きにする契機をつくるべきだ」と語る。
世界自然保護基金(WWF)オーストラリアによると、地球温暖化で気温が一度上がると同国ニューサウスウェールズ州で干ばつが70%増え、一−二度上がると世界最大の珊瑚(さんご)礁「グレートバリアリーフ」の珊瑚の60−80%が白化する恐れがあるという。
同国における家庭のCO2排出量の中で、照明が占める割合は5%。車や冷暖房、他の電化製品が占める割合の方が圧倒的に多いが、商業施設では27%に上る。
電力生産は主に火力発電で、CO2を多く排出する石炭に依存する割合が多く、国民一人当たりのCO2排出量は世界トップ級。CO2排出削減について定めた「京都議定書」は、米国と同じく批准していない。
WWFジャパン自然保護室の山岸尚之さんは「照明の切り替えは有効な一策で前進だが、温暖化防止には総合的な対策と世界の協調が必要。議定書を批准しそれらを進めていくべきだ」と指摘している。
---------------------------
照明替え明るい未来
温暖化抑止へ豪政府が運動
(Chunichi Web press 20070311)
地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの削減はなかなか進まない。そんな中、オーストラリア政府は先月、白熱電球を電球形蛍光灯に切り替える国家では世界初のキャンペーンを始めた。照明を切り替える省エネ効果は一体、どれほどあるのか?
(岩岡千景)
同政府は医療用などを除き、家庭や商業施設で使われている白熱電球の販売を段階的に規制。電球形蛍光灯への切り替えを進め、五年後の二〇一二年までに四百万トンの温室効果ガスを削減することを目指す。
温室効果ガスは、石炭や重油などを燃やして電力をつくるときに排出される。このため電力の消費を減らせば、地球環境への負荷も減らすことになる。
では、消費電力はどれだけ違うのか。松下電器産業によると、六〇ワット形の場合、従来の白熱電球が五四ワットなのに対し、最新の電球形蛍光灯は一〇ワットと、五分の一以下=図参照。
ただ、価格は白熱電球が百円前後と安く、電球形蛍光灯は千二百円前後と十二倍も高い。だが「意外に気づきにくいのが、長期的な経費」と、同社の加瀬秀樹照明・管球商品チームリーダーは説明する。
寿命も十倍違うため、切り替えると消費電力は電気代にして約一万円の節約になるという。
日本では、照明が一般家庭の消費電力に占める割合は、エアコンの次に多く、冷蔵庫と並ぶ16・1%(二〇〇五年度)。照明の中身をみると、ほぼ三分の一に当たる九・三個が電球だ。このうち省エネ型の電球形蛍光灯は三・二個にすぎず、白熱電球が六・一個とまだまだ多い。
このため、消費者団体「地球温暖化防止・省エネ東京連絡会」が照明の切り替えによる節電効果を消費者セミナーで伝えるなど、草の根で切り替え運動は広がっている。
同連絡会の田嶋いずみさんは「電球を切り替えるだけで、照明の消費電力の80%を減らすことができ、電気代も五分の一にできる。白熱電球と変わらない色や形の製品もある。このことを、もっと知ってほしい」と話す。
環境経済に詳しい永井進法政大教授も「省エネ型の商品選びは有効な温暖化対策。日本も掛け声だけでなく、具体的な目標や規制を決めて国民的な動きにする契機をつくるべきだ」と語る。
世界自然保護基金(WWF)オーストラリアによると、地球温暖化で気温が一度上がると同国ニューサウスウェールズ州で干ばつが70%増え、一−二度上がると世界最大の珊瑚(さんご)礁「グレートバリアリーフ」の珊瑚の60−80%が白化する恐れがあるという。
同国における家庭のCO2排出量の中で、照明が占める割合は5%。車や冷暖房、他の電化製品が占める割合の方が圧倒的に多いが、商業施設では27%に上る。
電力生産は主に火力発電で、CO2を多く排出する石炭に依存する割合が多く、国民一人当たりのCO2排出量は世界トップ級。CO2排出削減について定めた「京都議定書」は、米国と同じく批准していない。
WWFジャパン自然保護室の山岸尚之さんは「照明の切り替えは有効な一策で前進だが、温暖化防止には総合的な対策と世界の協調が必要。議定書を批准しそれらを進めていくべきだ」と指摘している。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ストップ*ザ*温暖化キャンペーン 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-