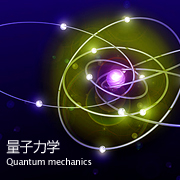?量子力学における「決定論」
ある時点tでの,要素の位置とシステムが完全に把握できれば,それ以後の時点t´でのあらゆる要素の位置とシステムを完全に演繹し予測し,未来を【決定できる】。その意味での(確率論的)決定論。
?広義の「決定論」
すべての要素の位置とシステムを完全に把握できないため,未来を演繹し予測し「決定」できないということと,実際に未来が【決定されている】かどうかということは無関係である。未来を予測・決定できなくても,我々はあらゆる要素の振る舞いの結果であり【決定されている】。その意味での(論理的)決定論。
量子力学は?を否定することに成功した。つまり「未来は予測・決定できない」と。しかし,だからといって,我々が【決定されている】かどうかについて量子力学は否定できていない。そのことはウィキペディア「量子力学」の項目にも書かれているくらいの「解釈問題」としての大きな論点であり,「量子力学」をもって「決定論」のすべてが否定されたとは言い得ない。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
この解釈(ことに?に関しての)突っ込んだ意見をお待ちしてます
ある時点tでの,要素の位置とシステムが完全に把握できれば,それ以後の時点t´でのあらゆる要素の位置とシステムを完全に演繹し予測し,未来を【決定できる】。その意味での(確率論的)決定論。
?広義の「決定論」
すべての要素の位置とシステムを完全に把握できないため,未来を演繹し予測し「決定」できないということと,実際に未来が【決定されている】かどうかということは無関係である。未来を予測・決定できなくても,我々はあらゆる要素の振る舞いの結果であり【決定されている】。その意味での(論理的)決定論。
量子力学は?を否定することに成功した。つまり「未来は予測・決定できない」と。しかし,だからといって,我々が【決定されている】かどうかについて量子力学は否定できていない。そのことはウィキペディア「量子力学」の項目にも書かれているくらいの「解釈問題」としての大きな論点であり,「量子力学」をもって「決定論」のすべてが否定されたとは言い得ない。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
この解釈(ことに?に関しての)突っ込んだ意見をお待ちしてます
|
|
|
|
コメント(42)
まず、?について。
確率論的決定論といってぼやかしているような気がするんですが、
確率的な未来予測を認めるならば、量子力学は?を否定していないと考えます。
不確定性によるゆらぎも、
さらには非実在性による確率的な振る舞いも、
ひっくるめて考えれば確率的な未来予測は可能です。
ここでの決定論が、
アインシュタインが述べているところの実在性を言っているのであれば、それは確かに量子論は否定しています。
しかし、それにしても局所性か実在性のどちらかを捨てれば良いと言っているだけで、ここでの話とは少しズレてくると思います。
「確率論的」という言葉をなんともなしに使ったのがその誤解であると考えるわけですが、いかがお考えでしょうか。
確率論的決定論といってぼやかしているような気がするんですが、
確率的な未来予測を認めるならば、量子力学は?を否定していないと考えます。
不確定性によるゆらぎも、
さらには非実在性による確率的な振る舞いも、
ひっくるめて考えれば確率的な未来予測は可能です。
ここでの決定論が、
アインシュタインが述べているところの実在性を言っているのであれば、それは確かに量子論は否定しています。
しかし、それにしても局所性か実在性のどちらかを捨てれば良いと言っているだけで、ここでの話とは少しズレてくると思います。
「確率論的」という言葉をなんともなしに使ったのがその誤解であると考えるわけですが、いかがお考えでしょうか。
すこーし考えてみた感じだと、
post selection
に近いのかもしれません。
なんだかよく分からない系に対して、測定をすることによって過去を決定することができます。
対して、いわゆる古典系での測定は未来をも決定します。
量子力学によれば、未来は確率的な予測になります。
しかし測定によって、過去・現在の事を決定することができます。
このように系を決定することは、波束の収縮という形で理解をすることができます。
つまり、今現在すべての測定されたことによる事象(網膜にイメージがうつり、脳が認識したetc...)は決定していると考えることができます。
これで話は済むのかとも考えられますが、ひとつ問題があります。
これは物理の方面からの苦情ですが、
量子力学の解釈に古典力学が必要であることです。
上で話している測定は古典的な測定を考えているので、量子力学の解釈の上で古典的な考えが必要なのはちょっと嫌なわけです。
そこでそれを回避する解釈として、多世界解釈があるわけです。
そこでは、上で言っている「決定」の雰囲気が少し変わります。
ですが・・・、
この解釈についてはなにぶん勉強中でして、私もまだよくは分かってない状態です。
と、いうのが私の?への意見です。
まとめると、
波束の収縮という観点で量子力学の測定を考えた場合、?で主張なさっている、すべての要素が決定的であるというのはある意味自然である。
否定されたいうよりはむしろ肯定している。
と考えます。
隠れた変数理論を知っているとは通ですね。
物理学科の学生でも知らない人もいそうですから。
(noccoさんが物理専門でしたら失礼^^;)
ついでに言うと、隠れた変数理論はベルの不等式という式にまとめられるんですが、
ベルの不等式は既に実験的に破れているので、隠れた変数理論はもう破れています。
アインシュタインの主張はEPRの論文で読むことが出来ますよ。
上でいろいろ書きましたが、
決定論的というのがまだしっかり理解できていない気がするので、
反応待ってます。
長文&連投失礼
post selection
に近いのかもしれません。
なんだかよく分からない系に対して、測定をすることによって過去を決定することができます。
対して、いわゆる古典系での測定は未来をも決定します。
量子力学によれば、未来は確率的な予測になります。
しかし測定によって、過去・現在の事を決定することができます。
このように系を決定することは、波束の収縮という形で理解をすることができます。
つまり、今現在すべての測定されたことによる事象(網膜にイメージがうつり、脳が認識したetc...)は決定していると考えることができます。
これで話は済むのかとも考えられますが、ひとつ問題があります。
これは物理の方面からの苦情ですが、
量子力学の解釈に古典力学が必要であることです。
上で話している測定は古典的な測定を考えているので、量子力学の解釈の上で古典的な考えが必要なのはちょっと嫌なわけです。
そこでそれを回避する解釈として、多世界解釈があるわけです。
そこでは、上で言っている「決定」の雰囲気が少し変わります。
ですが・・・、
この解釈についてはなにぶん勉強中でして、私もまだよくは分かってない状態です。
と、いうのが私の?への意見です。
まとめると、
波束の収縮という観点で量子力学の測定を考えた場合、?で主張なさっている、すべての要素が決定的であるというのはある意味自然である。
否定されたいうよりはむしろ肯定している。
と考えます。
隠れた変数理論を知っているとは通ですね。
物理学科の学生でも知らない人もいそうですから。
(noccoさんが物理専門でしたら失礼^^;)
ついでに言うと、隠れた変数理論はベルの不等式という式にまとめられるんですが、
ベルの不等式は既に実験的に破れているので、隠れた変数理論はもう破れています。
アインシュタインの主張はEPRの論文で読むことが出来ますよ。
上でいろいろ書きましたが、
決定論的というのがまだしっかり理解できていない気がするので、
反応待ってます。
長文&連投失礼
>noccoさん
?は実在論ではないということですね。なんか難しい話ですね。(実は量子力学の観測問題とかはあまり詳しくないのですが、興味があるので書き込ませてもらってます。宜しくお願いします)
>?..未来を予測・決定できなくても,我々はあらゆる要素の振る舞いの結果であり【決定されている】。その意味での(論理的)決定論。
我々はあらゆる要素の振る舞いの結果ということは、、
(論理的)決定論というよりも、むしろ(因果的)決定論ということでしょうか??
つまり、我々にとって未来は予測できないが、背後に何らかの因果法則が働いて、我々の未来は決定してるということでしょうか?
もしそうだとすれば、その「因果法則」というのは量子力学を超えたものをさすのでしょうか?それともあくまで量子力学の範囲内で考えればよいのでしょうか?
?は実在論ではないということですね。なんか難しい話ですね。(実は量子力学の観測問題とかはあまり詳しくないのですが、興味があるので書き込ませてもらってます。宜しくお願いします)
>?..未来を予測・決定できなくても,我々はあらゆる要素の振る舞いの結果であり【決定されている】。その意味での(論理的)決定論。
我々はあらゆる要素の振る舞いの結果ということは、、
(論理的)決定論というよりも、むしろ(因果的)決定論ということでしょうか??
つまり、我々にとって未来は予測できないが、背後に何らかの因果法則が働いて、我々の未来は決定してるということでしょうか?
もしそうだとすれば、その「因果法則」というのは量子力学を超えたものをさすのでしょうか?それともあくまで量子力学の範囲内で考えればよいのでしょうか?
>>11(takekujira氏)
>post selection
これは聞いたことのないタームです。簡単にググってみたけどHITしなかったので、概略を取ってください。
>なんだかよく分からない系に対して、測定をすることによって過去を決定することができます。
つなんだかよく分からない系ってw
>いわゆる古典系での測定は未来をも決定します。
ニュートン力学の因果的決定論ね。
>まとめると、波束の収縮という観点で量子力学の測定を考えた場合、?で主張なさっている、すべての要素が決定的であるというのはある意味自然である。否定されたいうよりはむしろ肯定している。と考えます。
っていうことは、 未来を予測・決定できなくても,我々はあらゆる要素の振る舞いの結果であり【(未来は)決定されている】っていうことですか??
>noccoさんが物理専門でしたら失礼^^;
物理学は門外漢だお
>ベルの不等式は既に実験的に破れているので、隠れた変数理論はもう破れています。
わたしの知ってる限りでは全面的には破れてみたいだけど、もう完全に破れたってことでいいのかしら??
>post selection
これは聞いたことのないタームです。簡単にググってみたけどHITしなかったので、概略を取ってください。
>なんだかよく分からない系に対して、測定をすることによって過去を決定することができます。
つなんだかよく分からない系ってw
>いわゆる古典系での測定は未来をも決定します。
ニュートン力学の因果的決定論ね。
>まとめると、波束の収縮という観点で量子力学の測定を考えた場合、?で主張なさっている、すべての要素が決定的であるというのはある意味自然である。否定されたいうよりはむしろ肯定している。と考えます。
っていうことは、 未来を予測・決定できなくても,我々はあらゆる要素の振る舞いの結果であり【(未来は)決定されている】っていうことですか??
>noccoさんが物理専門でしたら失礼^^;
物理学は門外漢だお
>ベルの不等式は既に実験的に破れているので、隠れた変数理論はもう破れています。
わたしの知ってる限りでは全面的には破れてみたいだけど、もう完全に破れたってことでいいのかしら??
>>12(くらべん氏)
>?は実在論ではないということですね。なんか難しい話ですね。
そうなんです。難しいお話なんです。どこまで物理学が噛んでいけるかも(射程も)はっきりしてないし。。
>つまり、我々にとって未来は予測できないが、背後に何らかの因果法則が働いて、我々の未来は決定してるということでしょうか?
因果的決定論じゃないと思うんですけど、”我々があらゆる要素の振る舞いの結果”であるなら、←(未来)が予測できなくても、また背後に因果法則が働いているかどうかっていうことでもなく、ただ”我々があらゆる要素の振る舞いの結果”であることによって未来は決定してるっていうことだと思うんだけど、うまく説明できないなぁ。。
>もしそうだとすれば、その「因果法則」というのは量子力学を超えたものをさすのでしょうか?
量子力学を超えたものを指しそうです(原理的に量子力学を超えられるかどうかは別にして)。で、わたしとして量子力学によって?を完全に否定してほしいんです。
>?は実在論ではないということですね。なんか難しい話ですね。
そうなんです。難しいお話なんです。どこまで物理学が噛んでいけるかも(射程も)はっきりしてないし。。
>つまり、我々にとって未来は予測できないが、背後に何らかの因果法則が働いて、我々の未来は決定してるということでしょうか?
因果的決定論じゃないと思うんですけど、”我々があらゆる要素の振る舞いの結果”であるなら、←(未来)が予測できなくても、また背後に因果法則が働いているかどうかっていうことでもなく、ただ”我々があらゆる要素の振る舞いの結果”であることによって未来は決定してるっていうことだと思うんだけど、うまく説明できないなぁ。。
>もしそうだとすれば、その「因果法則」というのは量子力学を超えたものをさすのでしょうか?
量子力学を超えたものを指しそうです(原理的に量子力学を超えられるかどうかは別にして)。で、わたしとして量子力学によって?を完全に否定してほしいんです。
post selection
は量子情報を扱う人が使っている方言みたいなものなのかな^^;
これは系を決定する方法として、測定によって過去そうであったと決定するやり方です。
つまり、この決定によって未来は「まったく」予測されません。
「なんだかよく分からない」というのは「未知」という意味しかないですw
あぁ。まだまだnoccoさんとの間に認識の差があったようです。
私は、
「今私たちがいるこの世界が決定されているかどうかが不安なんだ!」
という提起だと理解していました。
ひとつまえのnoccoさんの書き込みを見ると、
また戻ってしまいますが、「実在性」と同じだと感じてしまうのですが・・・。
「あらゆる要素の帰結として未来は決定される」
という主張はまさに実在性そのものです。
実在性と量子力学については、何個か上でちょっと書きました。
隠れた変数というのは、量子論におけるアインシュタインの言う不完全性を克服するために、実在性を否定するのではなく、隠れた変数を導入して解決しよう!
という考えです。
しかし、これにしたがって計算すると「ある量」の最大値が2と計算されてしまうのです。これがベルの不等式です。
しかし、この不等式は実験によって否定されました。
つまり
「隠れた変数理論が成立」 ⇒ 「ベルの不等式が成立」
後者が否定されたので、対偶によって、前者は否定されます。
こんな感じでどうでしょ?
は量子情報を扱う人が使っている方言みたいなものなのかな^^;
これは系を決定する方法として、測定によって過去そうであったと決定するやり方です。
つまり、この決定によって未来は「まったく」予測されません。
「なんだかよく分からない」というのは「未知」という意味しかないですw
あぁ。まだまだnoccoさんとの間に認識の差があったようです。
私は、
「今私たちがいるこの世界が決定されているかどうかが不安なんだ!」
という提起だと理解していました。
ひとつまえのnoccoさんの書き込みを見ると、
また戻ってしまいますが、「実在性」と同じだと感じてしまうのですが・・・。
「あらゆる要素の帰結として未来は決定される」
という主張はまさに実在性そのものです。
実在性と量子力学については、何個か上でちょっと書きました。
隠れた変数というのは、量子論におけるアインシュタインの言う不完全性を克服するために、実在性を否定するのではなく、隠れた変数を導入して解決しよう!
という考えです。
しかし、これにしたがって計算すると「ある量」の最大値が2と計算されてしまうのです。これがベルの不等式です。
しかし、この不等式は実験によって否定されました。
つまり
「隠れた変数理論が成立」 ⇒ 「ベルの不等式が成立」
後者が否定されたので、対偶によって、前者は否定されます。
こんな感じでどうでしょ?
>>13(takekujira氏)
「あらゆる要素の帰結として未来は決定される」っていうのは、わたしの感覚では論理的(可能性的な)決定論みたいなものなのかなぁ。これは実在(決定されて既にある)を意味してるんじゃなくて、論理的可能性として未来は決定されているっていうことだと思うの。わたしはあらゆる要素、このあらゆる要素が定まっていないからあらゆる要素の帰結って言うことの不可能さ(言えなさ)によって?を否定できるんじゃないかって考えてるんだけど。。
隠れた変数に関しては、アラン・アスペさんとかポール・クヴィアトさんの検証実験は局所的な隠れた変数理論を否定したけど、非局所的なものは否定されていないって聞いたけど、非局所的っていうの自体が的外れなのかな??
「あらゆる要素の帰結として未来は決定される」っていうのは、わたしの感覚では論理的(可能性的な)決定論みたいなものなのかなぁ。これは実在(決定されて既にある)を意味してるんじゃなくて、論理的可能性として未来は決定されているっていうことだと思うの。わたしはあらゆる要素、このあらゆる要素が定まっていないからあらゆる要素の帰結って言うことの不可能さ(言えなさ)によって?を否定できるんじゃないかって考えてるんだけど。。
隠れた変数に関しては、アラン・アスペさんとかポール・クヴィアトさんの検証実験は局所的な隠れた変数理論を否定したけど、非局所的なものは否定されていないって聞いたけど、非局所的っていうの自体が的外れなのかな??
>takekujiraさん
post selection という話は興味深いと思いました。我々が網膜を通して何かを見るということも、そういうことになるんでしょうか?
11でのtakekujiraさんの決定論は、僕がイメージした実在論に近いと思います。(つまり「実際に何が起ったか」ということ)。
ただ、僕は「因果性」までは実在論に含めていませんでした。
>noccoさん
>「あらゆる要素の帰結として未来は決定される」っていうのは、わたしの感覚では論理的(可能性的な)決定論みたいなものなのかなぁ。
ひょっとして哲学の問題とかですか??物理での決定論しかイメージしてませんでしたが、哲学的には「自由意志はあるか?」とか、そういう問題にもなりますよね。。もう少し説明お願いします。
post selection という話は興味深いと思いました。我々が網膜を通して何かを見るということも、そういうことになるんでしょうか?
11でのtakekujiraさんの決定論は、僕がイメージした実在論に近いと思います。(つまり「実際に何が起ったか」ということ)。
ただ、僕は「因果性」までは実在論に含めていませんでした。
>noccoさん
>「あらゆる要素の帰結として未来は決定される」っていうのは、わたしの感覚では論理的(可能性的な)決定論みたいなものなのかなぁ。
ひょっとして哲学の問題とかですか??物理での決定論しかイメージしてませんでしたが、哲学的には「自由意志はあるか?」とか、そういう問題にもなりますよね。。もう少し説明お願いします。
>>20(くらべん氏)
そぉですね(わたしの専門は物理学じゃなくて哲学方面なので)で、決定論のお話になると自由意思(自由選択)が必ずと言っていいほど噛んでくるものです。
ところで、決定論自体は科学的なもの(物理的な世界記述に関する)なので、自由意思(自由選択)があるかどうかじゃなくて(自由意思がある→非決定論、自由意思がない→決定論っていう論証方法は保留しておいて)、科学(量子力学)的に世界は決定論的であるかどうかってことが争点になってると思います。(例えば、この世界が古典力学によって完全に記述できるような世界だった場合、自由意思の有無に拘らずこの世界は決定論的です。もちろん、自由意思があるにもかかわらず決定論的な世界っていうのは変な感じですけど、とりま最初に論証されるべきは自由意思の有無じゃなくて科学的な決定論の是非です。
そして、>>17で書いた「わたしはあらゆる要素、このあらゆる要素が定まっていないからあらゆる要素の帰結って言うことの不可能さ(言えなさ)によって?を否定できるんじゃないか」っていう”事後”から見たら確かに定まっている(いた)ように見える要素が、現実的には定まっていない(要素足りえない)ってことを対象の重ねあわせ状態っていう考え方とその実験検証(二重スリット実験??)で証明できるんじゃないかっていう。
そぉですね(わたしの専門は物理学じゃなくて哲学方面なので)で、決定論のお話になると自由意思(自由選択)が必ずと言っていいほど噛んでくるものです。
ところで、決定論自体は科学的なもの(物理的な世界記述に関する)なので、自由意思(自由選択)があるかどうかじゃなくて(自由意思がある→非決定論、自由意思がない→決定論っていう論証方法は保留しておいて)、科学(量子力学)的に世界は決定論的であるかどうかってことが争点になってると思います。(例えば、この世界が古典力学によって完全に記述できるような世界だった場合、自由意思の有無に拘らずこの世界は決定論的です。もちろん、自由意思があるにもかかわらず決定論的な世界っていうのは変な感じですけど、とりま最初に論証されるべきは自由意思の有無じゃなくて科学的な決定論の是非です。
そして、>>17で書いた「わたしはあらゆる要素、このあらゆる要素が定まっていないからあらゆる要素の帰結って言うことの不可能さ(言えなさ)によって?を否定できるんじゃないか」っていう”事後”から見たら確かに定まっている(いた)ように見える要素が、現実的には定まっていない(要素足りえない)ってことを対象の重ねあわせ状態っていう考え方とその実験検証(二重スリット実験??)で証明できるんじゃないかっていう。
>noccoさん
つまり、量子力学の場合、実は"因果"の"果"が生じる前に"因"の方が定まっておらず、つまり因自体が本質的に定まっていない(重ね合わせという形でしか存在しえない)という時点で決定論の枠組みから外れてしまっているということでしょうか。。
確かに、位置や運動量などの"観測可能量(observable)"というパラメータの値を"因"とみなせば、宇宙はそれらの"因"の重ねあわせになってしまうと思います。
でも"観測可能量"を"因"とみなすより、"波動関数"自体を因とみなせば、量子力学においても因は定まったものと考えることが出来ると思います。(量子力学の性質上、因として波動関数が与えられても果としての測定結果は確率論的にしか得られないので、この場合も不完全な決定論になると思いますが)。
つまり、"あらゆる要素"="波動関数自体"とすれば、決定論は完全には覆されないと思うのですが、、問題はこういう等式を成り立たせても良いのかということですかね(波動関数は物理的実在というよりも、観測者の知識を表している?)。。
つまり、量子力学の場合、実は"因果"の"果"が生じる前に"因"の方が定まっておらず、つまり因自体が本質的に定まっていない(重ね合わせという形でしか存在しえない)という時点で決定論の枠組みから外れてしまっているということでしょうか。。
確かに、位置や運動量などの"観測可能量(observable)"というパラメータの値を"因"とみなせば、宇宙はそれらの"因"の重ねあわせになってしまうと思います。
でも"観測可能量"を"因"とみなすより、"波動関数"自体を因とみなせば、量子力学においても因は定まったものと考えることが出来ると思います。(量子力学の性質上、因として波動関数が与えられても果としての測定結果は確率論的にしか得られないので、この場合も不完全な決定論になると思いますが)。
つまり、"あらゆる要素"="波動関数自体"とすれば、決定論は完全には覆されないと思うのですが、、問題はこういう等式を成り立たせても良いのかということですかね(波動関数は物理的実在というよりも、観測者の知識を表している?)。。
>>23(くらべん氏)
大体そんな感じで考えてます。>つまり、量子力学の場合、実は"因果"の"果"が生じる前に"因"の方が定まっておらず、つまり因自体が本質的に定まっていない(重ね合わせという形でしか存在しえない)という時点で決定論の枠組みから外れてしまっている。
>量子力学の性質上、因として波動関数が与えられても果としての測定結果は確率論的にしか得られないので、この場合も不完全な決定論になると思いますが)。
>"あらゆる要素"="波動関数自体"とすれば、決定論は完全には覆されないと思うのですが、
えーっと、ここでいわれてる不完全な決定論(=確率的決定論)は決定論として妥当じゃないって考えます。やっぱり決定論っていうのは、ニュートン力学における完全記述と関わってこなきゃなので。
>問題はこういう等式を成り立たせても良いのかということですかね(波動関数は物理的実在というよりも、観測者の知識を表している?)。。
意思説ですか??(最先端の研究者間の認知が知りたいなぁ)
大体そんな感じで考えてます。>つまり、量子力学の場合、実は"因果"の"果"が生じる前に"因"の方が定まっておらず、つまり因自体が本質的に定まっていない(重ね合わせという形でしか存在しえない)という時点で決定論の枠組みから外れてしまっている。
>量子力学の性質上、因として波動関数が与えられても果としての測定結果は確率論的にしか得られないので、この場合も不完全な決定論になると思いますが)。
>"あらゆる要素"="波動関数自体"とすれば、決定論は完全には覆されないと思うのですが、
えーっと、ここでいわれてる不完全な決定論(=確率的決定論)は決定論として妥当じゃないって考えます。やっぱり決定論っていうのは、ニュートン力学における完全記述と関わってこなきゃなので。
>問題はこういう等式を成り立たせても良いのかということですかね(波動関数は物理的実在というよりも、観測者の知識を表している?)。。
意思説ですか??(最先端の研究者間の認知が知りたいなぁ)
>noccoさん
23>>波動関数は物理的実在というよりも、観測者の知識を表している?
wikiで「波動関数」なんかを調べると、波動関数の収縮は光速度をこえるため、波動関数を物理的実在とみなすと深刻なパラドックスを引き起こすとかかれてました。。観測者の知識だったら意思説になるのかも知れませんが、観測する人間が存在しないと量子状態が決まらないのも不自然ですね。
いずれにせよ、確率的決定論ではなくて、完全な決定論について考えておられる様なので、23ではだめですね。。
ところで問題をもう少し整理すると、結局、観測によって結果が得られた時点で原因も事後的に決定するということが決定論(=あらゆる出来事は、その出来事に先行する出来事のみによって決定していること)とずれているということですよね。原因は常に結果の前になければならないのに、量子力学的には両者が同時発生的になっているということですね(本当にそうなっているのかな??)。
エヴェレットの多世界解釈の観点から考えるのも面白いかと思いました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%A4%9A%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%A7%A3%E9%87%88
wikiから引用。。
>多世界解釈は決定論であると主張する者もいる。しかし、決定論であるためには、干渉性の消失が生じる前に、その結果が既に決定している必要がある。つまり、どの状態が自世界となるのかや、その過程が決定論的に記述出来なければならない。そのためには、自世界と多世界の区別を示す変数と、世界の干渉の度合いを示す時間関数が必要となる。
23>>波動関数は物理的実在というよりも、観測者の知識を表している?
wikiで「波動関数」なんかを調べると、波動関数の収縮は光速度をこえるため、波動関数を物理的実在とみなすと深刻なパラドックスを引き起こすとかかれてました。。観測者の知識だったら意思説になるのかも知れませんが、観測する人間が存在しないと量子状態が決まらないのも不自然ですね。
いずれにせよ、確率的決定論ではなくて、完全な決定論について考えておられる様なので、23ではだめですね。。
ところで問題をもう少し整理すると、結局、観測によって結果が得られた時点で原因も事後的に決定するということが決定論(=あらゆる出来事は、その出来事に先行する出来事のみによって決定していること)とずれているということですよね。原因は常に結果の前になければならないのに、量子力学的には両者が同時発生的になっているということですね(本当にそうなっているのかな??)。
エヴェレットの多世界解釈の観点から考えるのも面白いかと思いました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%A4%9A%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%A7%A3%E9%87%88
wikiから引用。。
>多世界解釈は決定論であると主張する者もいる。しかし、決定論であるためには、干渉性の消失が生じる前に、その結果が既に決定している必要がある。つまり、どの状態が自世界となるのかや、その過程が決定論的に記述出来なければならない。そのためには、自世界と多世界の区別を示す変数と、世界の干渉の度合いを示す時間関数が必要となる。
>noccoさん
あぁ。私の話はすべて局所性は仮定していたので、隠れた変数理論も(局所性を仮定した)とでも付け加えておいてください。ベルの不等式は局所性を仮定しています。
EPRの話をごくごく簡単に書きます。
EPRでは位置と運動量ですが、簡単のためにスピンにします。
エンタングルド状態といって、粒子Aが↑なら粒子Bが↓のような相関を任意の軸において持つような状態が量子力学ではあります。
これはAさんが粒子Aに対してx軸で↑と測定したならば、Bさんは粒子Bに対して絶対にx軸で↓と測定される。ということです。
ここで、局所実在性を仮定します。すると、局所性でAさんの測定はBさんへは光速を超えて影響することができません。
しかし、Aさんは測定の軸を選ぶ自由度を持っていますので、実在性によってなんらかのパラメーターによってその測定結果が決定されていたと考えると、Aでの測定は粒子Bのパラメータへ影響したと考える必要があります。
これは矛盾します。つまり、局所実在性は否定されます。
↑でくらべんさんの述べている「深刻なパラドックス」の一例ですね。
こんな感じです。EPRの論文では実在性をもう少しちゃんと定義してから使っていますが、イメージとしては良いと思います。
少しずつ話が見えてきたような気がします。
まず、確率的と言う点に関しては、「確率的な予測は決定ではない」とされる立場からは量子力学はなにも決定はしてくれません。
これはつまり波動関数自身をそういった観点からは、その要素として認めることができないことを意味していると思います。
私がpost selectionを挙げたのがまずかったのかもしれません。
しかし、一方で弱い測定と呼ばれる手法を用いて、ある変数に関する波動関数というのは作ることができます。つまり、post selectionという考え方を用いずに波動関数を実現することができます。
よって、そういった波動関数を要素として考えるとき、量子状態−量子状態間での「因果律」が保たれ、決定論は肯定されていると考えられると思います。
しかし、その量子状態間での因果律は人間の感覚からは確率的にしか表現されていないというのが、現在までの実験事実です。
人間の感覚に本質的に捕らえることができない量子状態をいうものを”因”とみなしうるかどうかと言う話にまとめることができるのではないでしょうか。
あぁ。私の話はすべて局所性は仮定していたので、隠れた変数理論も(局所性を仮定した)とでも付け加えておいてください。ベルの不等式は局所性を仮定しています。
EPRの話をごくごく簡単に書きます。
EPRでは位置と運動量ですが、簡単のためにスピンにします。
エンタングルド状態といって、粒子Aが↑なら粒子Bが↓のような相関を任意の軸において持つような状態が量子力学ではあります。
これはAさんが粒子Aに対してx軸で↑と測定したならば、Bさんは粒子Bに対して絶対にx軸で↓と測定される。ということです。
ここで、局所実在性を仮定します。すると、局所性でAさんの測定はBさんへは光速を超えて影響することができません。
しかし、Aさんは測定の軸を選ぶ自由度を持っていますので、実在性によってなんらかのパラメーターによってその測定結果が決定されていたと考えると、Aでの測定は粒子Bのパラメータへ影響したと考える必要があります。
これは矛盾します。つまり、局所実在性は否定されます。
↑でくらべんさんの述べている「深刻なパラドックス」の一例ですね。
こんな感じです。EPRの論文では実在性をもう少しちゃんと定義してから使っていますが、イメージとしては良いと思います。
少しずつ話が見えてきたような気がします。
まず、確率的と言う点に関しては、「確率的な予測は決定ではない」とされる立場からは量子力学はなにも決定はしてくれません。
これはつまり波動関数自身をそういった観点からは、その要素として認めることができないことを意味していると思います。
私がpost selectionを挙げたのがまずかったのかもしれません。
しかし、一方で弱い測定と呼ばれる手法を用いて、ある変数に関する波動関数というのは作ることができます。つまり、post selectionという考え方を用いずに波動関数を実現することができます。
よって、そういった波動関数を要素として考えるとき、量子状態−量子状態間での「因果律」が保たれ、決定論は肯定されていると考えられると思います。
しかし、その量子状態間での因果律は人間の感覚からは確率的にしか表現されていないというのが、現在までの実験事実です。
人間の感覚に本質的に捕らえることができない量子状態をいうものを”因”とみなしうるかどうかと言う話にまとめることができるのではないでしょうか。
>>25(くらべん氏)
>波動関数の収縮は光速度をこえるため
トピずれだけど、光速度の絶対性は、、
>観測する人間が存在しないと量子状態が決まらないのも不自然ですね。
〜〜量子コンピュータにおいて、外部から侵入した光子や電子の影響によって量子ビットの状態が確定してしまう量子エラーは人間の意思とは無関係に生じる。また、量子テレポーテーションでも同様のエラーが実験の障害となる。これら意思とは無関係に状態が確定する現象は、意思説を否定する有力な証拠となるだろう〜〜ですね。
>原因は常に結果の前になければならないのに、量子力学的には両者が同時発生的になっているということですね(本当にそうなっているのかな??)。
その本当のところを知りたいんです。
>エヴェレットの多世界解釈の観点から考えるのも面白いかと思いました。
Wikiはあんまり信用できないから、もう少し学術的なソースがほしいお
>波動関数の収縮は光速度をこえるため
トピずれだけど、光速度の絶対性は、、
>観測する人間が存在しないと量子状態が決まらないのも不自然ですね。
〜〜量子コンピュータにおいて、外部から侵入した光子や電子の影響によって量子ビットの状態が確定してしまう量子エラーは人間の意思とは無関係に生じる。また、量子テレポーテーションでも同様のエラーが実験の障害となる。これら意思とは無関係に状態が確定する現象は、意思説を否定する有力な証拠となるだろう〜〜ですね。
>原因は常に結果の前になければならないのに、量子力学的には両者が同時発生的になっているということですね(本当にそうなっているのかな??)。
その本当のところを知りたいんです。
>エヴェレットの多世界解釈の観点から考えるのも面白いかと思いました。
Wikiはあんまり信用できないから、もう少し学術的なソースがほしいお
26>takekujiraさん
>よって、そういった波動関数を要素として考えるとき、量子状態−量子状態間での「因果律」が保たれ、決定論は肯定されていると考えられると思います。
波動関数の収縮さえなければ、シュレディンガー方程式に従った量子状態の時間発展は決定論的であるという意味だと単純に理解したのですが、でもやはり「観測行為」を行なうと波動関数は収縮するわけで、こうなると因の波動関数と果の波動関数の関係は、確率的にしか定まらないので、結局決定論にならないのではと思うのですが。。
やはり量子力学で決定論的な解釈を行なおうとすれば、takekujiraさんが指摘しておられた様に局所性を否定するか、エヴェレットの解釈の様に波動関数の収縮が起らないような解釈を導入するしかないとも思えてきます。
>takekujiraさん
>人間の感覚に本質的に捕らえることができない量子状態をいうものを”因”とみなしうるかどうかと言う話にまとめることができるのではないでしょうか。
>noccoさん
>っていうことは、もう量子力学からも、決定論からも離れて、認識論の話になるっていうことですか
post selectionにせよ、弱い測定にせよ、波動関数(量子状態)は実験者が実験において有る程度セッティングするものだと思うので、それほど非感覚的なものでもないと思います。それに因だけでなく、果(収縮した波動関数)も、勿論波動関数で表せます。なので、波動関数に物理的実在性をゆるせるならば(←これが良くわからんのですが)、認識論の話にはならないと思います。
noccoさんは予測可能性としての決定論ではなく、とにかく「我々があらゆる要素の結果として【決定されているか】」ということを問題にされているので、因の波動関数が与えられたとき(←予測可能性は必要とされていないので、我々がこの波動関数の値を実際に知っている必要はない)、果としての波動関数が何らかの因果法則によって決定されていれば良いと思います。
>全充さん
ウォルボーンの実験教えて頂きありがとうございます。二重スリットで干渉したかしなかったの光子の経路が、時間的に送れたPdの計測の有無で事後的に決まるということですね。波動関数の収縮はどの時点で起ったのか?むしろ、そう考えることも間違ってるんでしょうか?
最後に、僕の意見をまとめると、
☆量子力学を決定論で扱うにはエヴェレットの解釈を使わなければならないような気がする。
☆そもそも決定論であるためには量子力学が実在論でなければ難しいのではないかと思う(宇宙の歴史(未来も含めて)は認識者に拘らず同一であり、客観的でなければならない)。
です。
>よって、そういった波動関数を要素として考えるとき、量子状態−量子状態間での「因果律」が保たれ、決定論は肯定されていると考えられると思います。
波動関数の収縮さえなければ、シュレディンガー方程式に従った量子状態の時間発展は決定論的であるという意味だと単純に理解したのですが、でもやはり「観測行為」を行なうと波動関数は収縮するわけで、こうなると因の波動関数と果の波動関数の関係は、確率的にしか定まらないので、結局決定論にならないのではと思うのですが。。
やはり量子力学で決定論的な解釈を行なおうとすれば、takekujiraさんが指摘しておられた様に局所性を否定するか、エヴェレットの解釈の様に波動関数の収縮が起らないような解釈を導入するしかないとも思えてきます。
>takekujiraさん
>人間の感覚に本質的に捕らえることができない量子状態をいうものを”因”とみなしうるかどうかと言う話にまとめることができるのではないでしょうか。
>noccoさん
>っていうことは、もう量子力学からも、決定論からも離れて、認識論の話になるっていうことですか
post selectionにせよ、弱い測定にせよ、波動関数(量子状態)は実験者が実験において有る程度セッティングするものだと思うので、それほど非感覚的なものでもないと思います。それに因だけでなく、果(収縮した波動関数)も、勿論波動関数で表せます。なので、波動関数に物理的実在性をゆるせるならば(←これが良くわからんのですが)、認識論の話にはならないと思います。
noccoさんは予測可能性としての決定論ではなく、とにかく「我々があらゆる要素の結果として【決定されているか】」ということを問題にされているので、因の波動関数が与えられたとき(←予測可能性は必要とされていないので、我々がこの波動関数の値を実際に知っている必要はない)、果としての波動関数が何らかの因果法則によって決定されていれば良いと思います。
>全充さん
ウォルボーンの実験教えて頂きありがとうございます。二重スリットで干渉したかしなかったの光子の経路が、時間的に送れたPdの計測の有無で事後的に決まるということですね。波動関数の収縮はどの時点で起ったのか?むしろ、そう考えることも間違ってるんでしょうか?
最後に、僕の意見をまとめると、
☆量子力学を決定論で扱うにはエヴェレットの解釈を使わなければならないような気がする。
☆そもそも決定論であるためには量子力学が実在論でなければ難しいのではないかと思う(宇宙の歴史(未来も含めて)は認識者に拘らず同一であり、客観的でなければならない)。
です。
少し間があいてしまいました。
>nootz.w.tさん
ニックネーム変えたのですねw
私が書いたのは、認識論というよりは、決定論における各要素の定義の話です。
波動関数に実在を持たせれば普通の意味での要素足りえるというのは、くらべんさんの仰るとおりだと考えます。
しかし、古典力学の手助けを借りずに多世界解釈のような方法で考えたとき、実在を伴わずに量子力学のみで決定論(のようなもの)を話せるのではないかという提案でした。しかし、決定した未来に必ずしも到達するわけではないというのは、決定論としては致命的であるのは確かです。なので、そのようなものを決定論として認めるかどうかという話も書いた次第です。
>全充さん
遅延選択の実験と同じような不思議さを感じますね。非常に魅力的な実験です。
この実験を見るだけで、相対論との相性の悪さをヒシヒシと感じます。
アタリマエですが、今さらっと計算して、式の上でもDpの測定で偏光を測定すると干渉が消えることが確認できました。DpとDsが偏光を識別するか如何によって結果に位相項を含むかどうかが変わりました。
Dpでの測定のtraceを取っても干渉が消えるのに驚きました。Dpの結果を知る云々ではなくて、Dpで偏光を測定することの効果がそのまま表れるのですね。
この方法で、コヒーレント長の充分長いエンタングルドペアによる超光速通信を一瞬思い浮かべましたが、無理ですね^^;
この実験の単一ペアに対する成功確率が1/4しかありません。Zeilingerのテレポーテーションを古典情報なしで行うのと同じ状態ですね><
ともかく、なかなか面白い情報ありがとうございます。
>くらべんさん
>noccoさんは予測可能性としての決定論ではなく、とにかく「我々があらゆる要素の
>結果として【決定されているか】」ということを問題にされているので、因の波動
>関数が与えられたとき(←予測可能性は必要とされていないので、我々がこの波動
>関数の値を実際に知っている必要はない)、果としての波動関数が何らかの因果法
>則によって決定されていれば良いと思います。
私もまさにこの意味で述べました。
ただ、この書き込みの上の方で書いたとおり、実在性を入れなくても、認識論を回避する方法はあると考えてます。
とにかく、現在の古典力学の助けを借りている量子力学では完全な決定論を形成するのは不可能であるという点では同感です。
>時空堂さん
そういう因果律を考えるのは可能だとは思います。
繰り返しになりますが、post selectionはまさにその考え方です。
しかし、そこは完全な因果律Bではなくて、波動関数という大きな意味での因を考え、その上で果を考えることによって狭い意味での因が決定します。
完全な因果律Bの成立は因果律Aを否定しそうな気がするのですが、どうでしょうか。
ですが、そうして局所性が破れ(=因果律Aの崩壊)、波動関数が実在を持ちめでたしめでたしとなる可能性もありますね。
興味のつきない世界です。
>nootz.w.tさん
ニックネーム変えたのですねw
私が書いたのは、認識論というよりは、決定論における各要素の定義の話です。
波動関数に実在を持たせれば普通の意味での要素足りえるというのは、くらべんさんの仰るとおりだと考えます。
しかし、古典力学の手助けを借りずに多世界解釈のような方法で考えたとき、実在を伴わずに量子力学のみで決定論(のようなもの)を話せるのではないかという提案でした。しかし、決定した未来に必ずしも到達するわけではないというのは、決定論としては致命的であるのは確かです。なので、そのようなものを決定論として認めるかどうかという話も書いた次第です。
>全充さん
遅延選択の実験と同じような不思議さを感じますね。非常に魅力的な実験です。
この実験を見るだけで、相対論との相性の悪さをヒシヒシと感じます。
アタリマエですが、今さらっと計算して、式の上でもDpの測定で偏光を測定すると干渉が消えることが確認できました。DpとDsが偏光を識別するか如何によって結果に位相項を含むかどうかが変わりました。
Dpでの測定のtraceを取っても干渉が消えるのに驚きました。Dpの結果を知る云々ではなくて、Dpで偏光を測定することの効果がそのまま表れるのですね。
この方法で、コヒーレント長の充分長いエンタングルドペアによる超光速通信を一瞬思い浮かべましたが、無理ですね^^;
この実験の単一ペアに対する成功確率が1/4しかありません。Zeilingerのテレポーテーションを古典情報なしで行うのと同じ状態ですね><
ともかく、なかなか面白い情報ありがとうございます。
>くらべんさん
>noccoさんは予測可能性としての決定論ではなく、とにかく「我々があらゆる要素の
>結果として【決定されているか】」ということを問題にされているので、因の波動
>関数が与えられたとき(←予測可能性は必要とされていないので、我々がこの波動
>関数の値を実際に知っている必要はない)、果としての波動関数が何らかの因果法
>則によって決定されていれば良いと思います。
私もまさにこの意味で述べました。
ただ、この書き込みの上の方で書いたとおり、実在性を入れなくても、認識論を回避する方法はあると考えてます。
とにかく、現在の古典力学の助けを借りている量子力学では完全な決定論を形成するのは不可能であるという点では同感です。
>時空堂さん
そういう因果律を考えるのは可能だとは思います。
繰り返しになりますが、post selectionはまさにその考え方です。
しかし、そこは完全な因果律Bではなくて、波動関数という大きな意味での因を考え、その上で果を考えることによって狭い意味での因が決定します。
完全な因果律Bの成立は因果律Aを否定しそうな気がするのですが、どうでしょうか。
ですが、そうして局所性が破れ(=因果律Aの崩壊)、波動関数が実在を持ちめでたしめでたしとなる可能性もありますね。
興味のつきない世界です。
>> #32 takekujiraさん、
> 繰り返しになりますが、post selectionはまさにその考え方です。
済みません、モロに既出でしたね。1ページ目を読んでいなかった・・・
ともあれ近しい考え方が既に存在していることを知れてうれしく思います。
> 完全な因果律Bの成立は因果律Aを否定しそうな気がするのですが、どうでしょうか。
同感です。
明確に論理的な言語化はできていないのですが、直観として何か矛盾しそうな印象は持っています。
ユンギアンなので思考だけでなく直観も同レベルで信頼しています
ところでtakekujiraさんの言われている「局所性」なのですが、定義するとなるとどんな感じで使われていますか?
よろしければ教えていただけると幸いです。読み落としていたら済みません。
> 繰り返しになりますが、post selectionはまさにその考え方です。
済みません、モロに既出でしたね。1ページ目を読んでいなかった・・・
ともあれ近しい考え方が既に存在していることを知れてうれしく思います。
> 完全な因果律Bの成立は因果律Aを否定しそうな気がするのですが、どうでしょうか。
同感です。
明確に論理的な言語化はできていないのですが、直観として何か矛盾しそうな印象は持っています。
ユンギアンなので思考だけでなく直観も同レベルで信頼しています
ところでtakekujiraさんの言われている「局所性」なのですが、定義するとなるとどんな感じで使われていますか?
よろしければ教えていただけると幸いです。読み落としていたら済みません。
>takekujiraさん
僕は多世界解釈は決定論だと思います(とはいえあくまで素人の意見ですが)。
確かに分岐した世界のどちらに行くのか自分自身では予測できないけれども、実際には世界が分岐すると同時に自分自身も分岐するわけで、たまたまそのうちの一つの世界に意識が向いたときにはその世界のことしか認識できないがゆえに、自身が現在認識している世界だけが実在だと思い込んでいると考えることができるのではないかと思います。
実際には分岐した全ての世界が実在しているわけですから。。
でも、多世界解釈とかじゃなく、通常の解釈でも"あらゆる要素が事後に定まる"ということについて、考えてみると面白いんじゃないかと思います。
違うコミュのトピックですが、少し似てるところがあるかと思ったので(時間はどちらに流れているか)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=22441421&comment_count=54&comm_id=155397
僕は多世界解釈は決定論だと思います(とはいえあくまで素人の意見ですが)。
確かに分岐した世界のどちらに行くのか自分自身では予測できないけれども、実際には世界が分岐すると同時に自分自身も分岐するわけで、たまたまそのうちの一つの世界に意識が向いたときにはその世界のことしか認識できないがゆえに、自身が現在認識している世界だけが実在だと思い込んでいると考えることができるのではないかと思います。
実際には分岐した全ての世界が実在しているわけですから。。
でも、多世界解釈とかじゃなく、通常の解釈でも"あらゆる要素が事後に定まる"ということについて、考えてみると面白いんじゃないかと思います。
違うコミュのトピックですが、少し似てるところがあるかと思ったので(時間はどちらに流れているか)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=22441421&comment_count=54&comm_id=155397
自分は素人なんですが…
考えれば考える程、多世界解釈は非現実的なように思います。
仮にそうだったとして、誰も確かめようが無いし…可能性のある全ての事象が実現するなら、小数点以下何桁までの確率が実現しますか?無限に小さい小数点まで?
と言う事は今この瞬間には無限に宇宙が存在していると…。
改めて考えてみると、究極に投げやりな解釈だと思いますよ。
昔、初めてこの解釈について本で読んだ時は感心しちゃったりしましたが、
これを最初に編み出した科学者?の、学問に対する姿勢を疑います。
以上の理由から、多世界解釈を出来の悪い決定論と認識しております。
なので自分はこの種の問題についてこれ以上考える時間が勿体無いです。
皆さんはどう思いますか?
なんかおかしい部分があれば御指摘願います。
考えれば考える程、多世界解釈は非現実的なように思います。
仮にそうだったとして、誰も確かめようが無いし…可能性のある全ての事象が実現するなら、小数点以下何桁までの確率が実現しますか?無限に小さい小数点まで?
と言う事は今この瞬間には無限に宇宙が存在していると…。
改めて考えてみると、究極に投げやりな解釈だと思いますよ。
昔、初めてこの解釈について本で読んだ時は感心しちゃったりしましたが、
これを最初に編み出した科学者?の、学問に対する姿勢を疑います。
以上の理由から、多世界解釈を出来の悪い決定論と認識しております。
なので自分はこの種の問題についてこれ以上考える時間が勿体無いです。
皆さんはどう思いますか?
なんかおかしい部分があれば御指摘願います。
>ごはんかけごはん さん
私は多世界解釈の証拠となる実験があるは書いていません。そのように読めてしまったなら申し訳ありませんでした。
ですが、ご存知ではあると思いますが、局所的な隠れた変数論は実験で否定されました。この理論も最初は、確かめようがない認識の問題だという扱いだったはずです。
ですが、ベルの理論とアスペの実験によって見事否定されました。
同じことが多世界解釈やそのほかの量子力学の解釈問題におきてもいいですし、確かめようがない問題なんだと決め付けるのはまずいのではないかという問題提起が主題でした。
現に、量子コンピューティングの実現が多世界解釈の証拠となると言っている人もいますね。私はすこしそれには同意しかねますが・・・。
私は多世界解釈の証拠となる実験があるは書いていません。そのように読めてしまったなら申し訳ありませんでした。
ですが、ご存知ではあると思いますが、局所的な隠れた変数論は実験で否定されました。この理論も最初は、確かめようがない認識の問題だという扱いだったはずです。
ですが、ベルの理論とアスペの実験によって見事否定されました。
同じことが多世界解釈やそのほかの量子力学の解釈問題におきてもいいですし、確かめようがない問題なんだと決め付けるのはまずいのではないかという問題提起が主題でした。
現に、量子コンピューティングの実現が多世界解釈の証拠となると言っている人もいますね。私はすこしそれには同意しかねますが・・・。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
量子力学 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-