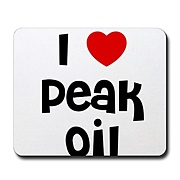ちょっとブレイク。
【運営方針08 10/24 更新】
■レポートorトピック構想(仮題)と今の関心度(***)
「ピークオイル総論(埋蔵量評価、昨今の価格分析)」*
「反ピークオイル派について(楽観、懐疑、市場経済・技術信仰」**
「輸送問題」*
「省エネ技術・省エネ生活について」*
「燃料電池と水素社会」**
「代替エネルギー開発(バイオ燃料、メタンハイドレート、太陽光発電、風力発電、波力・潮力発電、核融合、高速増殖炉、石炭ガス化・液化、小水力、地熱温度差発電等)」**
「アメリカの覇権戦略/中国の軍事戦略/EUの戦略」**
「東アジア経済圏構想/自由貿易体制の危機」**
「BRICs/TIPS/VISTA/NEXT11」
「人間の本性について(人類の歴史、人間行動学、マルチエージェント人工社会シュミレーション)」
「日本の核武装論(憲法、自衛隊、MD構想)/独自の諜報機関(J-CIA、NSC、情報省、外務調査庁構想など)」**
「教育の問題/啓蒙活動の方法(TV、映画、書籍)/意志決定」
「日本の生き抜く道の提言」←目標
これらのテーマについて構想中です。トピックたては自由ですが、私が構想中のものとかぶっている場合がありますので、出来たら事前に一言下さると助かります。または、要望があれば優先的に作ります。
【その他】
・用語集トピを作るか検討中。→要望あり→怠け中
■管理人作成のトピック頭文について
著作権は管理人にあります。利害が発生する場合がありますので、無断でばら撒かないでください。
■人数の推移
3/25 255人
4/12 267人
4/20 274人
5/ 6 294人
5/24 311人
5/26 313人
7/13 350人
8/ 3 367人
8/20 372人
9/15 396人
10/15 428人
11/8 456人
11/18 470人
11/26 483人
11/29 519人
11/30 564人
1/1 581人
3/1 606人
4/2 614人
5/1 634人
5/26 669人
5/27 674人
6/10 695人
8/8 750人
10/8 770人
10/24 779人
そろそろピークか?!
■近況&ぼやき
管理人就職活動中につき、更新が滞り気味。
ちなみにコミュ画像はASPOのサイトより、ピークオイルマウスパッドの画像。ここのは同Get readyマグカップ(L)ですw。ロゴ等は自由に使ってよいとの事です。
管理人の日々のピークオイルに関する(or関しないw)雑感を書いていきます。コメント歓迎です。このコミュに対する意見・提案・ぼやき、私へのメッセージなどあればご自由にここでどうぞ。
■主な雑記目次(意外と気合が入っているので整理)
1あいさつ
7エンデの話(Mizoさん)
14-15バイオエタノールについて(るるーさん)
21このコミュの名前について
27ピークオイルに対する勘違いについて
28ビジョンの大切さについて
31-35反ピークオイル論への反論
39改めてコミュ方針について
43-44宣伝活動について(osamu in gardenさん)
46理系・文系の分析(nariさん)
49もうぬりです
50ブルース氏からのメール
51-53アンケートの提案とmixiプレミアム(おぐおぐさん)
52ぬりの由来
54-55あるNPOの話
61-65,68ソーラーカーについて
67独自URL
69副管理人任命
70二人こぎと7人乗り
70-72温暖化懐疑論
73-74輸送問題(おぐおぐさん)
75商品紹介について
76,78ピークオイル委員会について(スーパーTSさん)
78年頭にあたって
79台湾新幹線開通
【運営方針08 10/24 更新】
■レポートorトピック構想(仮題)と今の関心度(***)
「ピークオイル総論(埋蔵量評価、昨今の価格分析)」*
「反ピークオイル派について(楽観、懐疑、市場経済・技術信仰」**
「輸送問題」*
「省エネ技術・省エネ生活について」*
「燃料電池と水素社会」**
「代替エネルギー開発(バイオ燃料、メタンハイドレート、太陽光発電、風力発電、波力・潮力発電、核融合、高速増殖炉、石炭ガス化・液化、小水力、地熱温度差発電等)」**
「アメリカの覇権戦略/中国の軍事戦略/EUの戦略」**
「東アジア経済圏構想/自由貿易体制の危機」**
「BRICs/TIPS/VISTA/NEXT11」
「人間の本性について(人類の歴史、人間行動学、マルチエージェント人工社会シュミレーション)」
「日本の核武装論(憲法、自衛隊、MD構想)/独自の諜報機関(J-CIA、NSC、情報省、外務調査庁構想など)」**
「教育の問題/啓蒙活動の方法(TV、映画、書籍)/意志決定」
「日本の生き抜く道の提言」←目標
これらのテーマについて構想中です。トピックたては自由ですが、私が構想中のものとかぶっている場合がありますので、出来たら事前に一言下さると助かります。または、要望があれば優先的に作ります。
【その他】
・用語集トピを作るか検討中。→要望あり→怠け中
■管理人作成のトピック頭文について
著作権は管理人にあります。利害が発生する場合がありますので、無断でばら撒かないでください。
■人数の推移
3/25 255人
4/12 267人
4/20 274人
5/ 6 294人
5/24 311人
5/26 313人
7/13 350人
8/ 3 367人
8/20 372人
9/15 396人
10/15 428人
11/8 456人
11/18 470人
11/26 483人
11/29 519人
11/30 564人
1/1 581人
3/1 606人
4/2 614人
5/1 634人
5/26 669人
5/27 674人
6/10 695人
8/8 750人
10/8 770人
10/24 779人
そろそろピークか?!
■近況&ぼやき
管理人就職活動中につき、更新が滞り気味。
ちなみにコミュ画像はASPOのサイトより、ピークオイルマウスパッドの画像。ここのは同Get readyマグカップ(L)ですw。ロゴ等は自由に使ってよいとの事です。
管理人の日々のピークオイルに関する(or関しないw)雑感を書いていきます。コメント歓迎です。このコミュに対する意見・提案・ぼやき、私へのメッセージなどあればご自由にここでどうぞ。
■主な雑記目次(意外と気合が入っているので整理)
1あいさつ
7エンデの話(Mizoさん)
14-15バイオエタノールについて(るるーさん)
21このコミュの名前について
27ピークオイルに対する勘違いについて
28ビジョンの大切さについて
31-35反ピークオイル論への反論
39改めてコミュ方針について
43-44宣伝活動について(osamu in gardenさん)
46理系・文系の分析(nariさん)
49もうぬりです
50ブルース氏からのメール
51-53アンケートの提案とmixiプレミアム(おぐおぐさん)
52ぬりの由来
54-55あるNPOの話
61-65,68ソーラーカーについて
67独自URL
69副管理人任命
70二人こぎと7人乗り
70-72温暖化懐疑論
73-74輸送問題(おぐおぐさん)
75商品紹介について
76,78ピークオイル委員会について(スーパーTSさん)
78年頭にあたって
79台湾新幹線開通
|
|
|
|
コメント(1000)
IEEJ(日本エネルギー経済研究所)の「アジア/世界エネルギーアウトルック2009」の報告会(2009年10月23日)での質問と回答の一つ、
Q:エネルギー需要増に対し、石油の供給能力は対応できるのか(ピークオイルが近いと言われているが)?
A:石油の供給サイドでは、2030年まで石油資源制約は発生しないが、欧州、米国での既存油田n減退率上昇が進む中、十分かつタイムリーな投資確保が困難化し、供給制約が徐々に顕在化し、Easy Oilはピークアウトすると想定しています。IEAによると、世界全体での既存油田の減退率は6〜7%程度でm、将来は8〜9%に上昇する見通しであり、既存油田減退を補うための探鉱開発が重要であるとしています。
☆
資源制約は発生しないが、ピークアウトするって、なんか苦しい気がしますが(笑)
本文中でも、
「2010年を過ぎる頃から、相対的にコストの高い中小規模油田、あるいは深海油田等へのシフトが見込まれ、また、既存油田の減退率上昇、投資停滞による供給制約が徐々に顕在化し、これに連動して原油価格は徐々に上昇する。非在来型石油の生産量も増加するが、(中略)必要とされる需要増を担うのは、中東を中心とするOPEC諸国やロシアである。」
と述べられています。採掘コストが高い油田にシフトしていくことは、資源的制約・地質的制約と言っていいと思うんですけど。
どうしても、「ピークオイル」(=狭い意味での地質学的ピークというレッテル)という単語は受け入れることは出来んようです。もし、認めてしまうと、ものすごい悲観的なことを発信しているということになってしまうからでしょうか。
Q:エネルギー需要増に対し、石油の供給能力は対応できるのか(ピークオイルが近いと言われているが)?
A:石油の供給サイドでは、2030年まで石油資源制約は発生しないが、欧州、米国での既存油田n減退率上昇が進む中、十分かつタイムリーな投資確保が困難化し、供給制約が徐々に顕在化し、Easy Oilはピークアウトすると想定しています。IEAによると、世界全体での既存油田の減退率は6〜7%程度でm、将来は8〜9%に上昇する見通しであり、既存油田減退を補うための探鉱開発が重要であるとしています。
☆
資源制約は発生しないが、ピークアウトするって、なんか苦しい気がしますが(笑)
本文中でも、
「2010年を過ぎる頃から、相対的にコストの高い中小規模油田、あるいは深海油田等へのシフトが見込まれ、また、既存油田の減退率上昇、投資停滞による供給制約が徐々に顕在化し、これに連動して原油価格は徐々に上昇する。非在来型石油の生産量も増加するが、(中略)必要とされる需要増を担うのは、中東を中心とするOPEC諸国やロシアである。」
と述べられています。採掘コストが高い油田にシフトしていくことは、資源的制約・地質的制約と言っていいと思うんですけど。
どうしても、「ピークオイル」(=狭い意味での地質学的ピークというレッテル)という単語は受け入れることは出来んようです。もし、認めてしまうと、ものすごい悲観的なことを発信しているということになってしまうからでしょうか。
2002年の鳩山由紀夫「秘書が脱税容疑ならば、議員バッジ外します」
http://www.youtube.com/watch?v=wnGcufFL7ys
鳩山首相 「国というものがなんだかよくわからない」
http://www.youtube.com/watch?v=Pqwb_d8bBIQ
ユッキー鳩山愛のテーマ「宇宙ができて137億年」
http://www.youtube.com/watch?v=rRKSVNGBpNk
ここまで酷い巨額脱税首相を据えてしまい、未だ68%もの支持を続けている我々も情けないが、国際市場にも見放され、これまで唯一の強みだった産業も日本一人負け状態になりつつある(図は、政権交代後のNYダウと日経平均の乖離)。
http://www.sc.mufg.jp/inv_info/ii_report/fj_report/pdf/fj20091124.pdf
唯一通った法案は、返済猶予という正気とは思えない制度で、温暖化の試算は都合が悪いから却下。
高速道路無料化すればCO2は減るといい、2020年までに100%電気自動車にするから大丈夫だって。
今から販売車両を100%EVにしたって、10年では入れ替わらないし、一般庶民に定価400万円で冬は50キロも走れない小型車を買えというのは、車を購入する権利をただ政府が奪うだけだ。まあ、それもよいのかもしれないけど。
基本毎日憂鬱だけれど、よいニュースも。
スパコンは、自主開発にこだわりすぎると利権の塊になるので、見直して大正解。スパコンは必要でも、開発方式に問題がありまくり。次世代ロケットも開発ありきだ。もっと、共同入札方式にして、採算を重視しないと。科学技術の発展と、巨額プロジェクトの実現はイコールではない。こういうときに、ノーベル賞学者が駆り出され、専門でもない技術に関して声を大にして意見するところなど、なんだか情けない。
そういえば、東京メトロのアナウンスは、クリステル・チアリ(クロード・チアリの娘)がやっているらしい。なぜに?英語オンチの私からすれば下手とはいえないが、決してうまいともいえない気がする。
トヨタ、ホンダがF1を撤退し、F1が世界の一大スポーツとはいえなくなっていく気がするが、トヨタはモータースポーツをあきらめたわけではない気がする。レクサスブランドのスーパーカーLFAや、FT-86コンセプトなど、ホンダがNSXやS2000の開発をやめたのと対照的だ。
他にも、2010年に閉鎖予定のお台場「パレットタウン」の土地を、森ビルと814億円で去年買収したが、そこにミニサーキットを作るのではという噂も聞いた。
内燃機関エンジンの未来はどうなっていくんだろう。
http://www.youtube.com/watch?v=wnGcufFL7ys
鳩山首相 「国というものがなんだかよくわからない」
http://www.youtube.com/watch?v=Pqwb_d8bBIQ
ユッキー鳩山愛のテーマ「宇宙ができて137億年」
http://www.youtube.com/watch?v=rRKSVNGBpNk
ここまで酷い巨額脱税首相を据えてしまい、未だ68%もの支持を続けている我々も情けないが、国際市場にも見放され、これまで唯一の強みだった産業も日本一人負け状態になりつつある(図は、政権交代後のNYダウと日経平均の乖離)。
http://www.sc.mufg.jp/inv_info/ii_report/fj_report/pdf/fj20091124.pdf
唯一通った法案は、返済猶予という正気とは思えない制度で、温暖化の試算は都合が悪いから却下。
高速道路無料化すればCO2は減るといい、2020年までに100%電気自動車にするから大丈夫だって。
今から販売車両を100%EVにしたって、10年では入れ替わらないし、一般庶民に定価400万円で冬は50キロも走れない小型車を買えというのは、車を購入する権利をただ政府が奪うだけだ。まあ、それもよいのかもしれないけど。
基本毎日憂鬱だけれど、よいニュースも。
スパコンは、自主開発にこだわりすぎると利権の塊になるので、見直して大正解。スパコンは必要でも、開発方式に問題がありまくり。次世代ロケットも開発ありきだ。もっと、共同入札方式にして、採算を重視しないと。科学技術の発展と、巨額プロジェクトの実現はイコールではない。こういうときに、ノーベル賞学者が駆り出され、専門でもない技術に関して声を大にして意見するところなど、なんだか情けない。
そういえば、東京メトロのアナウンスは、クリステル・チアリ(クロード・チアリの娘)がやっているらしい。なぜに?英語オンチの私からすれば下手とはいえないが、決してうまいともいえない気がする。
トヨタ、ホンダがF1を撤退し、F1が世界の一大スポーツとはいえなくなっていく気がするが、トヨタはモータースポーツをあきらめたわけではない気がする。レクサスブランドのスーパーカーLFAや、FT-86コンセプトなど、ホンダがNSXやS2000の開発をやめたのと対照的だ。
他にも、2010年に閉鎖予定のお台場「パレットタウン」の土地を、森ビルと814億円で去年買収したが、そこにミニサーキットを作るのではという噂も聞いた。
内燃機関エンジンの未来はどうなっていくんだろう。
daiさん
うーん。いろいろ考えたのですが、このグラフのインパクトをまだ感じられないでいます。
貿易赤字に突入しそうなのは、自動車などの工業製品が売れなくなったことに、円高が拍車をかけていることが主因であって、エネルギー価格はあまり大きくないというのが私の認識です。
それに、日本の化石燃料輸入費用は、総額でもGDP比でも、他国と比べて突出しているものではありませんし、経済活動へ価格のインパクトもかなり小さくなっています。これが国民の暮らしを圧迫している主な原因とは思えません。
2009年はもうちょっと下がるはずだし。
火力発電は高いと桜井さんは主張していらっしゃるようですが、昔は6割こえてましたが、原油炊きはここ10年は6%から11%程度で推移している程度で、ベースは石炭とLNGです。本当は電力会社とすれば、安い原発と石炭を増やしたいところですが、需要変動幅がどんどん拡大していることと、調整用のLNGスポット買い(去年は高かった)が増えたため、昨年は高くつきました。現在、LNGは値崩れしていて、パイプラインガスよりもはるかに安くなってます。
家庭用太陽光発電の発電単価が20円を切ると書かれていますが、引用されているNEDOの計算は「用地費、人件費、一般管理費、公租公課は無とする。」となっていて、コストのほとんどを占めている工事費(工務店の人工費)を無視しているようなので、ちょっとどうなんだろうと思ってしまいます。
First Solar社のCd-Te系は、かつて公害問題になったカドミウムを屋根に載せることに対する抵抗感との戦いという面もありますし、First Solar社の架台はとても弱く安っぽいので、台風の多い日本の家庭の屋根に向いていないんじゃないかなとも思い、単純に比較していいものかと。
電力の質も含め、コスト面で対抗しようとするのはまだまだおかしい気がします。
やはり、導入すればするほど光熱費は上がる。スペインなどでの失敗はどうとらえているんでしょうか。
高価格のエネルギーに対するコンセンサスが取れている程度において、導入には賛成なのですが。
うーん。いろいろ考えたのですが、このグラフのインパクトをまだ感じられないでいます。
貿易赤字に突入しそうなのは、自動車などの工業製品が売れなくなったことに、円高が拍車をかけていることが主因であって、エネルギー価格はあまり大きくないというのが私の認識です。
それに、日本の化石燃料輸入費用は、総額でもGDP比でも、他国と比べて突出しているものではありませんし、経済活動へ価格のインパクトもかなり小さくなっています。これが国民の暮らしを圧迫している主な原因とは思えません。
2009年はもうちょっと下がるはずだし。
火力発電は高いと桜井さんは主張していらっしゃるようですが、昔は6割こえてましたが、原油炊きはここ10年は6%から11%程度で推移している程度で、ベースは石炭とLNGです。本当は電力会社とすれば、安い原発と石炭を増やしたいところですが、需要変動幅がどんどん拡大していることと、調整用のLNGスポット買い(去年は高かった)が増えたため、昨年は高くつきました。現在、LNGは値崩れしていて、パイプラインガスよりもはるかに安くなってます。
家庭用太陽光発電の発電単価が20円を切ると書かれていますが、引用されているNEDOの計算は「用地費、人件費、一般管理費、公租公課は無とする。」となっていて、コストのほとんどを占めている工事費(工務店の人工費)を無視しているようなので、ちょっとどうなんだろうと思ってしまいます。
First Solar社のCd-Te系は、かつて公害問題になったカドミウムを屋根に載せることに対する抵抗感との戦いという面もありますし、First Solar社の架台はとても弱く安っぽいので、台風の多い日本の家庭の屋根に向いていないんじゃないかなとも思い、単純に比較していいものかと。
電力の質も含め、コスト面で対抗しようとするのはまだまだおかしい気がします。
やはり、導入すればするほど光熱費は上がる。スペインなどでの失敗はどうとらえているんでしょうか。
高価格のエネルギーに対するコンセンサスが取れている程度において、導入には賛成なのですが。
ぬりさん
基本的には緻密な分析というより、政治的インパクトを意図した図解です。今は政治フェーズのタイミングなので。
言い替えると「高価格のエネルギーに対するコンセンサスが取れている程度において」ではなく「高価格のエネルギーに対するコンセンサスを取るための便法」といった位置づけ。
ただ、内需主導の経済成長を標榜する場合、輸入と国内での代替についての視点が議論から漏れるのは問題だろうと思います。これまでは、「出る(輸入)をはかりて入る(輸出)を増やす」という発送というか、輸入が増えるのは当然でそれを上回る輸出ドライブ、という発想だったと思います。
「入るをはかりて出るを制す」の視点を導入する必要があるというのが私の意見。
(はい、縮小均衡志向です)
太陽光のコスト構成を議論するつもりではなかったのだけれど
> 用地費、人件費、一般管理費、公租公課
これは運転費の話ではないでしょうか?(建設人件費は建設費)
(調べてないけど)
屋根のカドミウムを気にするなら、自動車バッテリーの鉛は?
雨水が浸透したら、即性能が出なくなるので、修理に回ると思います=浸出は微々たるものかと。
むしろ、廃棄費用をケチって庭にバッテリーを積んでいる住宅の方が問題ではないでしょうか。
架台の話は、風力の落雷・地震や、水力の土砂災害と一緒で、日本がコストアップになるのもやむを得ないと私も思います。
基本的には緻密な分析というより、政治的インパクトを意図した図解です。今は政治フェーズのタイミングなので。
言い替えると「高価格のエネルギーに対するコンセンサスが取れている程度において」ではなく「高価格のエネルギーに対するコンセンサスを取るための便法」といった位置づけ。
ただ、内需主導の経済成長を標榜する場合、輸入と国内での代替についての視点が議論から漏れるのは問題だろうと思います。これまでは、「出る(輸入)をはかりて入る(輸出)を増やす」という発送というか、輸入が増えるのは当然でそれを上回る輸出ドライブ、という発想だったと思います。
「入るをはかりて出るを制す」の視点を導入する必要があるというのが私の意見。
(はい、縮小均衡志向です)
太陽光のコスト構成を議論するつもりではなかったのだけれど
> 用地費、人件費、一般管理費、公租公課
これは運転費の話ではないでしょうか?(建設人件費は建設費)
(調べてないけど)
屋根のカドミウムを気にするなら、自動車バッテリーの鉛は?
雨水が浸透したら、即性能が出なくなるので、修理に回ると思います=浸出は微々たるものかと。
むしろ、廃棄費用をケチって庭にバッテリーを積んでいる住宅の方が問題ではないでしょうか。
架台の話は、風力の落雷・地震や、水力の土砂災害と一緒で、日本がコストアップになるのもやむを得ないと私も思います。
daiさん
そうですね。政治フェーズというのはよく理解しています。
他の方法があるのに、あえて高額なものを使用するならば、被る経済非効率の損害に見合うメリットの提示こそが必要であると思います(もちろん、メリットはよく理解しています)。
であるのに、石油より安く済む、というようなイメージを与えるやりかたは、啓蒙戦略としてどうなのかなと。
私は縮小均衡志向ではなくて、どちらかというと縮小均衡甘受といった感じでしょうかね。
だからといって、輸出を減らすことが良いことみたいな話になるのは変だなと思いますし(これまで
それで飯を食っといてそりゃないだろって)、内需といっても、本気で先進国で内需主導にしようとしたら、ほとんど不動産バブルにするしかないというのが、過去の主要国経済を分析した結果かなと。
ま、自主的に縮小するのは簡単ですね。ただ、経済が圧迫していく中では一般庶民は金の亡者なので、コミュニティや社会の秩序は崩壊の圧力にさらされるでしょう。それをいかに緩和するのかが政治と思うのですが、縮小を後押しするのは間違っていると考えます。
というか、産業発展を無視して内需喚起なんてバカげてます。
http://www.nedo.go.jp/nedata/17fy/01/g/0001g003.html
には
「修繕・保守費は年当たり建設費総額の1%とする。」
とあります。
家庭用向けの太陽光発電のコストで、一般的にいわれている48円/kWhとかという数字のほとんど(24円くらい)は、工務店に流れると聞いてます。既築住宅に3.5kWを取り付ける費用の220万円のうち、30万円が工務店の人件費と聞きました(新エネ部会長の柏木氏談)。
技術開発でどんなにモジュールコストを押さえても、日本の家庭向けで20円を切るのは無理じゃんと思ってもおかしくないと思いますが。
カドミウムは気にしすぎと私も思いますが、現に日本ではほとんど売れていないのが現実。実際の環境問題というより、気持ちの問題でしょうね。
ドイツでは、Q-CellsをFast Solarが駆逐しつつある(今年の発注の7割がFast Solar)。
大量に導入しようとすれば、安い海外製品の方に流れるのは当然ですが、それでは貿易赤字を拡大させるだけになるのでは。
日本にはコスト高の事情があるので、海外の販売事例の平均値を上げて、安いと表現するのはフェアではない気がします。
東南アジアではサツマイモがキロ3円なんだから、サツマイモをもっと食えと言っているような感じでしょうか。
そうですね。政治フェーズというのはよく理解しています。
他の方法があるのに、あえて高額なものを使用するならば、被る経済非効率の損害に見合うメリットの提示こそが必要であると思います(もちろん、メリットはよく理解しています)。
であるのに、石油より安く済む、というようなイメージを与えるやりかたは、啓蒙戦略としてどうなのかなと。
私は縮小均衡志向ではなくて、どちらかというと縮小均衡甘受といった感じでしょうかね。
だからといって、輸出を減らすことが良いことみたいな話になるのは変だなと思いますし(これまで
それで飯を食っといてそりゃないだろって)、内需といっても、本気で先進国で内需主導にしようとしたら、ほとんど不動産バブルにするしかないというのが、過去の主要国経済を分析した結果かなと。
ま、自主的に縮小するのは簡単ですね。ただ、経済が圧迫していく中では一般庶民は金の亡者なので、コミュニティや社会の秩序は崩壊の圧力にさらされるでしょう。それをいかに緩和するのかが政治と思うのですが、縮小を後押しするのは間違っていると考えます。
というか、産業発展を無視して内需喚起なんてバカげてます。
http://www.nedo.go.jp/nedata/17fy/01/g/0001g003.html
には
「修繕・保守費は年当たり建設費総額の1%とする。」
とあります。
家庭用向けの太陽光発電のコストで、一般的にいわれている48円/kWhとかという数字のほとんど(24円くらい)は、工務店に流れると聞いてます。既築住宅に3.5kWを取り付ける費用の220万円のうち、30万円が工務店の人件費と聞きました(新エネ部会長の柏木氏談)。
技術開発でどんなにモジュールコストを押さえても、日本の家庭向けで20円を切るのは無理じゃんと思ってもおかしくないと思いますが。
カドミウムは気にしすぎと私も思いますが、現に日本ではほとんど売れていないのが現実。実際の環境問題というより、気持ちの問題でしょうね。
ドイツでは、Q-CellsをFast Solarが駆逐しつつある(今年の発注の7割がFast Solar)。
大量に導入しようとすれば、安い海外製品の方に流れるのは当然ですが、それでは貿易赤字を拡大させるだけになるのでは。
日本にはコスト高の事情があるので、海外の販売事例の平均値を上げて、安いと表現するのはフェアではない気がします。
東南アジアではサツマイモがキロ3円なんだから、サツマイモをもっと食えと言っているような感じでしょうか。
ぬりさん
> 被る経済非効率の損害
いつもながら、論理的に適切な言い回し、いいなぁ、、、 こういう言葉で議論が進めば必要以上に政治的なプレゼンをしなくていいのですけどね。
なんとなく噛み合っていないように感じたのだけれど、それは多分、私が他人の引用に乗っかって書いているからでしょう。
恐縮ですが、太陽光の話はこの辺で降ろさせてください。(金額はその辺であっていると思いますよ)
小水力も「放っておくと海外製に席捲されてしまいますよ」と主張しているのだけれど、なかなか聞いてもらえないように感じています。そういう意味で、櫻井さんのグラフも引用しながら、国産再生可能エネルギーの重要性を説いているところです。
> 被る経済非効率の損害
いつもながら、論理的に適切な言い回し、いいなぁ、、、 こういう言葉で議論が進めば必要以上に政治的なプレゼンをしなくていいのですけどね。
なんとなく噛み合っていないように感じたのだけれど、それは多分、私が他人の引用に乗っかって書いているからでしょう。
恐縮ですが、太陽光の話はこの辺で降ろさせてください。(金額はその辺であっていると思いますよ)
小水力も「放っておくと海外製に席捲されてしまいますよ」と主張しているのだけれど、なかなか聞いてもらえないように感じています。そういう意味で、櫻井さんのグラフも引用しながら、国産再生可能エネルギーの重要性を説いているところです。
daiさん
そうですね。PVの話はひとまずやめましょう。
再生可能エネルギーの中では、私は小水力と地熱あたりに最大の活路を見出したいと思っているのですが、いかんせん家庭向けPVの余剰電力買取に偏りすぎていて危機感を感じます。方向性としてかなり真逆。かといって、再生可能エネルギーならば何でも全量高額買取みたいなことは、ちょっと極端過ぎる気がする。
もともと解けない問題を解こうとしているわけで。政治が介入すればするほど、ろくなことがないです。自然に増えないものは仕方がない。
なんとか国産で頑張りたいですね。やはり、コンパクトで高効率で壊れなくて安心感があってシステム統合性の高い、というあたりの強みを活かしてもらいたいものです。
トイレと小水力といえば日本製みたいな。
そうですね。PVの話はひとまずやめましょう。
再生可能エネルギーの中では、私は小水力と地熱あたりに最大の活路を見出したいと思っているのですが、いかんせん家庭向けPVの余剰電力買取に偏りすぎていて危機感を感じます。方向性としてかなり真逆。かといって、再生可能エネルギーならば何でも全量高額買取みたいなことは、ちょっと極端過ぎる気がする。
もともと解けない問題を解こうとしているわけで。政治が介入すればするほど、ろくなことがないです。自然に増えないものは仕方がない。
なんとか国産で頑張りたいですね。やはり、コンパクトで高効率で壊れなくて安心感があってシステム統合性の高い、というあたりの強みを活かしてもらいたいものです。
トイレと小水力といえば日本製みたいな。
ぬりさん
> トイレと小水力といえば日本製みたいな。
おしっこで回すから小水力、ってこと? (^^)
そうそう、便器や洗面台のフラッシュ用赤外線センサーの電源に小水力発電が使われているのはご存じでしたでしょうか?
http://www.inax.co.jp/company/seeds/tech/hatsuden.html
こういうのも日本独特のような気がします(違うかもしれないけど)。
全量固定買取に関しては、パブコメを出し、ヒアリングも受けてきました。ご参考。
http://energy-decentral.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/fit-3ad1.html
> トイレと小水力といえば日本製みたいな。
おしっこで回すから小水力、ってこと? (^^)
そうそう、便器や洗面台のフラッシュ用赤外線センサーの電源に小水力発電が使われているのはご存じでしたでしょうか?
http://www.inax.co.jp/company/seeds/tech/hatsuden.html
こういうのも日本独特のような気がします(違うかもしれないけど)。
全量固定買取に関しては、パブコメを出し、ヒアリングも受けてきました。ご参考。
http://energy-decentral.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/fit-3ad1.html
面白い!
ただ、水流で発電しても、結局水圧は水道側のポンプのエネルギーな訳で、電線を引っ張るコストが高い場合以外は微妙な気がしますね。こういうケースの小型バッテリーは、存在そのものが全体に対して無駄になる場合が多いです。
上下水道で発電するアイディアの研究は前からありますが、無駄になっている部分はごく一部ですしね。地下鉄の駅で発生する風で発電するなんていう研究のありましたが、風車がついてるタクシーみたいなアイディアですね。
日本のトイレは、以前は一度に流すのに必要な水量の規制がなかったためか、諸外国に比べて大量の水をつかっていましたけど、最近のハイエンドモデルはかなり少ない水でフラシュしている気がします。ああいう、少量の水で最大の効用を生み出すようなアイディアを、小水力発電の方にも生かせないかな、なんてちょっと思っただけです。
小水力じゃなくて少水力みたいな。日本らしいクールな水車が作れれば、海外でも売れるんじゃないかなと勝手に思ったりしてます。
パブコメみました。やはり安定出力は魅力ですよねー。
投資案件としてもそうですが、水利権等の規制緩和がネックなのかなとも思ったり。ペイするならみんなやるのに、そうしないのは・・・。
ただ、水流で発電しても、結局水圧は水道側のポンプのエネルギーな訳で、電線を引っ張るコストが高い場合以外は微妙な気がしますね。こういうケースの小型バッテリーは、存在そのものが全体に対して無駄になる場合が多いです。
上下水道で発電するアイディアの研究は前からありますが、無駄になっている部分はごく一部ですしね。地下鉄の駅で発生する風で発電するなんていう研究のありましたが、風車がついてるタクシーみたいなアイディアですね。
日本のトイレは、以前は一度に流すのに必要な水量の規制がなかったためか、諸外国に比べて大量の水をつかっていましたけど、最近のハイエンドモデルはかなり少ない水でフラシュしている気がします。ああいう、少量の水で最大の効用を生み出すようなアイディアを、小水力発電の方にも生かせないかな、なんてちょっと思っただけです。
小水力じゃなくて少水力みたいな。日本らしいクールな水車が作れれば、海外でも売れるんじゃないかなと勝手に思ったりしてます。
パブコメみました。やはり安定出力は魅力ですよねー。
投資案件としてもそうですが、水利権等の規制緩和がネックなのかなとも思ったり。ペイするならみんなやるのに、そうしないのは・・・。
お邪魔します、櫻井です。daiさんに引っ張られて来ました。
・私は経済には素人なのでむしろ教えを請いたいのですが、
化石燃料の輸入費用が10年で18兆円増えてる影響って、そんなに小さいでしょうか。
日本の2007年分の貿易黒字が10兆円ですから、企業で言うなら通常の利益分の2倍の余計な出費が増えるのはまずそう、と思うのですが如何でしょうか。しかもこの10年の累計だと、結構な額になってますけど。(^^;
・太陽光のコストですが、まずNEDOの計算法に関する誤解のご指摘:
・用地費…屋根ですから、いらんですがな。(^^;
・工事費…設備導入費用に含まれています。
そして20円/kWhを切るための方策ですが、モジュール製造コストはせいぜい価格の3〜4割ですので、それを下げるだけではダメですね。
http://unit.aist.go.jp/rcpv/ci/about_pv/economics/CostReduction.html
営業・流通費が4割ぐらい占めてるんで、政策使ってでもそこを下げないといかんです。日本がドイツに遅れを取ったのは、そこの部分です。
で、同じようなことはPV以外にも言えるんですわ。まず資源量やコストがまともに調査すらされてない。2月の環境省の報告書の検討会でも皆さん怒ってましたし、私自身も地熱の方々の会合に乗り込んで「そういうデータって無いんですか」って訊きに言ったぐらいです。
普段の講演でも、「太陽光と原発だけでは損なはずや」って言ってます。;)
かと言って何も考えずに助成すりゃいい訳でもなくて、去年のスペインはその典型ですわ。一昨年の段階で業界誌(Photon)の社説にまで「高すぎるから下げろ」って言われてたのに、問題の顕在化から実際に下げるまで1年以上かかって、それでああいうことに。
そのへんも私の本で解説してますから、良ければ読んだって下さい。
なおmixiは普段殆ど使ってませんので、太陽光とか政策について何かご質問ありましたら、適当にブログなりメールなりで頂ければ幸いです。
ではでは。
・私は経済には素人なのでむしろ教えを請いたいのですが、
化石燃料の輸入費用が10年で18兆円増えてる影響って、そんなに小さいでしょうか。
日本の2007年分の貿易黒字が10兆円ですから、企業で言うなら通常の利益分の2倍の余計な出費が増えるのはまずそう、と思うのですが如何でしょうか。しかもこの10年の累計だと、結構な額になってますけど。(^^;
・太陽光のコストですが、まずNEDOの計算法に関する誤解のご指摘:
・用地費…屋根ですから、いらんですがな。(^^;
・工事費…設備導入費用に含まれています。
そして20円/kWhを切るための方策ですが、モジュール製造コストはせいぜい価格の3〜4割ですので、それを下げるだけではダメですね。
http://unit.aist.go.jp/rcpv/ci/about_pv/economics/CostReduction.html
営業・流通費が4割ぐらい占めてるんで、政策使ってでもそこを下げないといかんです。日本がドイツに遅れを取ったのは、そこの部分です。
で、同じようなことはPV以外にも言えるんですわ。まず資源量やコストがまともに調査すらされてない。2月の環境省の報告書の検討会でも皆さん怒ってましたし、私自身も地熱の方々の会合に乗り込んで「そういうデータって無いんですか」って訊きに言ったぐらいです。
普段の講演でも、「太陽光と原発だけでは損なはずや」って言ってます。;)
かと言って何も考えずに助成すりゃいい訳でもなくて、去年のスペインはその典型ですわ。一昨年の段階で業界誌(Photon)の社説にまで「高すぎるから下げろ」って言われてたのに、問題の顕在化から実際に下げるまで1年以上かかって、それでああいうことに。
そのへんも私の本で解説してますから、良ければ読んだって下さい。
なおmixiは普段殆ど使ってませんので、太陽光とか政策について何かご質問ありましたら、適当にブログなりメールなりで頂ければ幸いです。
ではでは。
東大の宮田秀明教授が主導する「二次電池による社会システム・イノベーション」のプロジェクトが、年内にも「一般社団法人 二次電池社会システム研究会」を設立させ、会員(有料)を募集しているようです。
http://www.nijidenchi.org/
なんか、この構想、どんどん劣化していっている気がする。一線の専門家の関心はどんどんうすれ、中途半端に首を突っ込んでいるひとや、騙されやすい人が集まっていくような予感がします。だいじょうぶかー。最近は先生の日経BPのコラムもとてもつまらなくなってしまったし。
10ヶ月も前ですが、ここの第2回フォーラムでの渡辺さん(たぶんマスター)の発表で、
http://www.nijidenchi.org/up_image/090223_5_watanabe.pdf
PV(太陽電池)やEV、住宅用バッテリーをどれだけ導入すればよいかという試算を行ったところ、結論は、18kWhのバッテリーを家におき、車はガソリン車のままというのがベストになってます。これって、フォーラムの方向性からいくとまずい結論・・・。
おまけに、宮地氏の研究をみると、
http://www.nijidenchi.org/up_image/5.miyachi.pdf
結局分散導入より集中導入の方がいいとなっていて、渡辺氏の結論さえ無意味となってしまう・・・。
ま、PVやEVの導入をコスト計算でメリットを出そうとする事自体無謀。
家庭用PVに合わせたバッテリーの分散導入は、集中導入よりも二桁くらい無駄が多いことが、いろんな研究でいわれているので、当然といえば当然なんですよね。
頑張れ東大生。指導教官にまけず、自分の頭で考えるんだ!!お前らいくら税金かかってるかわかってんのか。
http://www.nijidenchi.org/
なんか、この構想、どんどん劣化していっている気がする。一線の専門家の関心はどんどんうすれ、中途半端に首を突っ込んでいるひとや、騙されやすい人が集まっていくような予感がします。だいじょうぶかー。最近は先生の日経BPのコラムもとてもつまらなくなってしまったし。
10ヶ月も前ですが、ここの第2回フォーラムでの渡辺さん(たぶんマスター)の発表で、
http://www.nijidenchi.org/up_image/090223_5_watanabe.pdf
PV(太陽電池)やEV、住宅用バッテリーをどれだけ導入すればよいかという試算を行ったところ、結論は、18kWhのバッテリーを家におき、車はガソリン車のままというのがベストになってます。これって、フォーラムの方向性からいくとまずい結論・・・。
おまけに、宮地氏の研究をみると、
http://www.nijidenchi.org/up_image/5.miyachi.pdf
結局分散導入より集中導入の方がいいとなっていて、渡辺氏の結論さえ無意味となってしまう・・・。
ま、PVやEVの導入をコスト計算でメリットを出そうとする事自体無謀。
家庭用PVに合わせたバッテリーの分散導入は、集中導入よりも二桁くらい無駄が多いことが、いろんな研究でいわれているので、当然といえば当然なんですよね。
頑張れ東大生。指導教官にまけず、自分の頭で考えるんだ!!お前らいくら税金かかってるかわかってんのか。
最近思うことなど。
マックで携帯から打てるだけ(笑)
VSTO(東シベリアパイプライン)は、大慶への分岐ルートから30キロまで溶接が進んだ。
昨年夏、プーチンが北京に行った際には、アルタイルートの方が先に繋がるかのような発言(2013年か2014年と具体的な時期まで示した)をしたが、アルタイルートは2006年から2007年の欧州との価格交渉の際の見せ玉というのがもっぱらの噂で、実際価格を吊り上げた後に破談になっている。アルタイルートは標高もたかく、需要地とも遠いので実現性は低いという評価もある。ある筋の話では、当局者の意見を無視して、プーチンの趣味という話もある。
一昨年ごろ、李明博大統領が北朝鮮経由のパイプラインに意欲を見せて世界を驚かせたが、これも専門家同士の雑談レベルでは、大統領の趣味的発言で、いまだにその考えは捨てていないらしい。
昨年4月のパイプライン爆発事故を口実に、ガスプロムはトルクメニスタンからのガス供給を断っていた。理由は、昨年度前半は欧州ガス市場が急激に落ち込み、価格も大幅に下がっていたのにも関わらず、トルクメニスタンからの買い取り価格はかなり高く設定されていた。これは、トルクメニスタンが欧州に直接ガスを販売したいという構想(トランスカスピ海パイプライン構想)や、中国向け販売のメリットを削ぐためと言われていたが、ここにきてあだに。
結果、欧州ガス市場が回復するまではできるだけ買いたくないということに。10月に再開という報道が出たが、価格で折り合わずということで延期。12月23日にようやく合意し、1月9日に再開。価格はどうなったのだろう。
トルクメニスタンは、昨年来から中国向けのガス供給を開始したが、こちらはなんと価格が決まっていない。ロシアに先行してリードという見方もあるが、ロシア以外の販売ルート開拓を焦って、価格面で苦しい状況になるかも。石炭地帯を経由するので、中国側はかならず石炭価格リンクを要求してくるだろう。一方のロシアは、アルタイルートでの交渉で、石炭価格リンクを拒絶し、昨年は石油価格バスケットにすることを提案し、今年中に価格システムでの合意を目指すという。
日本は、三井物産、三菱商事念願のサハリン2からのLNG輸入が、なんと昨年の麻生首相の頃に開始され、昨年のLNG供給の3.5%をまかない、中東依存率は87%程度まで下がった。サハリン2の供給能力は今年およそ倍になるので、昨年同様に供給能力の6割程度を輸入するとすれば、8%程度まで到達するかもしれない。石狩への供給も始まった。
輸入先の多様化という点や、間にシーレーンのチョークポイントがないことを考えても、よい傾向だろう。
マックで携帯から打てるだけ(笑)
VSTO(東シベリアパイプライン)は、大慶への分岐ルートから30キロまで溶接が進んだ。
昨年夏、プーチンが北京に行った際には、アルタイルートの方が先に繋がるかのような発言(2013年か2014年と具体的な時期まで示した)をしたが、アルタイルートは2006年から2007年の欧州との価格交渉の際の見せ玉というのがもっぱらの噂で、実際価格を吊り上げた後に破談になっている。アルタイルートは標高もたかく、需要地とも遠いので実現性は低いという評価もある。ある筋の話では、当局者の意見を無視して、プーチンの趣味という話もある。
一昨年ごろ、李明博大統領が北朝鮮経由のパイプラインに意欲を見せて世界を驚かせたが、これも専門家同士の雑談レベルでは、大統領の趣味的発言で、いまだにその考えは捨てていないらしい。
昨年4月のパイプライン爆発事故を口実に、ガスプロムはトルクメニスタンからのガス供給を断っていた。理由は、昨年度前半は欧州ガス市場が急激に落ち込み、価格も大幅に下がっていたのにも関わらず、トルクメニスタンからの買い取り価格はかなり高く設定されていた。これは、トルクメニスタンが欧州に直接ガスを販売したいという構想(トランスカスピ海パイプライン構想)や、中国向け販売のメリットを削ぐためと言われていたが、ここにきてあだに。
結果、欧州ガス市場が回復するまではできるだけ買いたくないということに。10月に再開という報道が出たが、価格で折り合わずということで延期。12月23日にようやく合意し、1月9日に再開。価格はどうなったのだろう。
トルクメニスタンは、昨年来から中国向けのガス供給を開始したが、こちらはなんと価格が決まっていない。ロシアに先行してリードという見方もあるが、ロシア以外の販売ルート開拓を焦って、価格面で苦しい状況になるかも。石炭地帯を経由するので、中国側はかならず石炭価格リンクを要求してくるだろう。一方のロシアは、アルタイルートでの交渉で、石炭価格リンクを拒絶し、昨年は石油価格バスケットにすることを提案し、今年中に価格システムでの合意を目指すという。
日本は、三井物産、三菱商事念願のサハリン2からのLNG輸入が、なんと昨年の麻生首相の頃に開始され、昨年のLNG供給の3.5%をまかない、中東依存率は87%程度まで下がった。サハリン2の供給能力は今年およそ倍になるので、昨年同様に供給能力の6割程度を輸入するとすれば、8%程度まで到達するかもしれない。石狩への供給も始まった。
輸入先の多様化という点や、間にシーレーンのチョークポイントがないことを考えても、よい傾向だろう。
しかし、これからの数年間は、カタール、オーストラリア、ロシア三つ巴のLNG供給過剰となるだろう。理由は、目当てにしていた北米ガス市場が、米国内のシェールガスなどの非在来型ガスの生産の伸びによって、LNG輸入量が激減したからだ。米国のLNG基地の設備過剰問題も深刻で、新規計画の中止や、再輸出ポイントとして申請しなおすなどの動きが起きていた。ただし、シェールガスは開発サイクルが短いため、金融危機後に開発投資が急激し、徐々に供給は苦しくなる。空前のガス在庫を抱えた2009年だったが、状況は徐々に変化しつつある。
欧州ガス市場は、需要の急激後、LNG価格がパイプラインガスよりも落ち込んだことや、輸入先の脱ロシアの思惑もあって(前々回のウクライナガス供給危機の教訓で、LNG基地を増設していた)、需要回復の多くをLNGで賄った。
ガスプロムは、LNGの独自技術をもっていないのでLNG市場に乗り遅れたが、今後急速に供給能力を高めていくだろう。しかしそれは、世界のLNG需給を緩和させ、価格を下落に導き、これまで築いてきたパイプライン輸出の権益を自ら損なうことになるというジレンマも抱えている。
そうなれば、多額の開発費用が必要なヤマル半島のガス田開発(ボバネンコなど)はさらに遅れるだろう。その先にある巨大海洋ガス田シュトックマンはさらに遅れる。ロシアが誇るガス埋蔵量の実力が活かされるのは、どんどん先延ばされる。
また、LNG市場の拡大と価格低下は、パイプライン需要を低下させる。連立を絶った新ドイツ政権は、原発の停止を延期させることができれば、ロシアからの直接のパイプラインであるノルドストリーム建設を急ぐ必要はなくなる。そうでなくとも、反対国は多く、いくらでも延期要因はある。
同様に、ナブッコVSサウスストリームなどのパイプライン構想も、急ぐ必要が減れば、計画競争は沈静化し、特にナブッコ構想は頓挫する可能性が高い。
米国ではすでにそうだが、今後数年間、ガス供給がだぶつき、IEAの警告のように石油供給が再びタイトになっていけば、アジアでもガス価格を石油価格から切り離すべきという議論がかならず起こるだろう。現在はアジアでのLNG価格は…
はう!半分消えた(笑)
欧州ガス市場は、需要の急激後、LNG価格がパイプラインガスよりも落ち込んだことや、輸入先の脱ロシアの思惑もあって(前々回のウクライナガス供給危機の教訓で、LNG基地を増設していた)、需要回復の多くをLNGで賄った。
ガスプロムは、LNGの独自技術をもっていないのでLNG市場に乗り遅れたが、今後急速に供給能力を高めていくだろう。しかしそれは、世界のLNG需給を緩和させ、価格を下落に導き、これまで築いてきたパイプライン輸出の権益を自ら損なうことになるというジレンマも抱えている。
そうなれば、多額の開発費用が必要なヤマル半島のガス田開発(ボバネンコなど)はさらに遅れるだろう。その先にある巨大海洋ガス田シュトックマンはさらに遅れる。ロシアが誇るガス埋蔵量の実力が活かされるのは、どんどん先延ばされる。
また、LNG市場の拡大と価格低下は、パイプライン需要を低下させる。連立を絶った新ドイツ政権は、原発の停止を延期させることができれば、ロシアからの直接のパイプラインであるノルドストリーム建設を急ぐ必要はなくなる。そうでなくとも、反対国は多く、いくらでも延期要因はある。
同様に、ナブッコVSサウスストリームなどのパイプライン構想も、急ぐ必要が減れば、計画競争は沈静化し、特にナブッコ構想は頓挫する可能性が高い。
米国ではすでにそうだが、今後数年間、ガス供給がだぶつき、IEAの警告のように石油供給が再びタイトになっていけば、アジアでもガス価格を石油価格から切り離すべきという議論がかならず起こるだろう。現在はアジアでのLNG価格は…
はう!半分消えた(笑)
最近の懸念
日産の将来
iMiEVへの過剰な補助
一般のEVへの過剰な期待
(低速&低安全のゴーカートなら成り立つ)
今年度燃料電池関連予算、2000億の憂鬱
エネファーム5000機まで間近(補助金あまり気味)
FCV(燃料電池自動車)業界が、2015年実用化目標に向けばく進中
他のエコカーブームに余計に焦ってる模様
相変わらずの破壊的な民主党政権。国体が壊れていくってこういうことなんですね。
脱石油社会、エネルギー供給の限界を見据えた社会経済を考えつつ、最新のエネルギー情報をみつめる当コミュニティは、双方に興味のある方には奇妙に思われるかも知れませんが、これからもこんなスタイルでいこうかなと思う今日この頃。
日産の将来
iMiEVへの過剰な補助
一般のEVへの過剰な期待
(低速&低安全のゴーカートなら成り立つ)
今年度燃料電池関連予算、2000億の憂鬱
エネファーム5000機まで間近(補助金あまり気味)
FCV(燃料電池自動車)業界が、2015年実用化目標に向けばく進中
他のエコカーブームに余計に焦ってる模様
相変わらずの破壊的な民主党政権。国体が壊れていくってこういうことなんですね。
脱石油社会、エネルギー供給の限界を見据えた社会経済を考えつつ、最新のエネルギー情報をみつめる当コミュニティは、双方に興味のある方には奇妙に思われるかも知れませんが、これからもこんなスタイルでいこうかなと思う今日この頃。
daiさん
ニュースのコピペは確かに多いかもしれませんね。考え物です・・・。
EVの低安全と書いてしまいましたが、誤解を与えてしまったかもしれません。決してEVが安全でないということが言いたかったのではありません。
現行のガソリン車とは、特性が異なるので、現行の自動車安全基準を満たすようにEVを作ってしまうと、余計に競争に勝てなくなってしまうのではないかということです。
つまり、現在の小型車と、二輪車の間に、EV専用の基準を設け、最高スピードを制限する代わりに、衝突安全基準を下げたほうが、EVの市場投入には有利ではないかと考えます。
その意義や細かい根拠は、daiさんなら理解していただけるのではないでしょうか。
中国の農村部で、激安で安全基準ムシのEVがどんどん走っているのを見ると、日本でも農村部や都市部コミューターなどに限定して、激安EVがもっと走ってもいいような気がします。
と、いうわけです。
民主党に関して、環境・エネルギー政策で拒否感を感じるのは、-25%という目標に関するところと、高速道路無料化の部分の2点です。
温暖化に関しては、私は懐疑派ではありませんが、今後のCO2濃度上昇の殆どを中国とアメリカが担うであろうことを考えると、日本が減らそうが増やそうが大して関係ないので、その2国を制御できない以上、無理するくらいなら、温暖化した後の対策を考える方が現実的ではないかと考えます。幸か不幸か、気候変動による影響は、日本は他の国より小さいはずです。また、被害の多くは、局所的に発生する干ばつがかなり大きな部分を占めると考えられますが、水文学の専門家沖大幹先生によりますと、被害人口拡大の因子の殆どは、開発途上国の人口増加によるもので、温暖化の影響はむしろプラスになる場合もあると聞きました。IPCC3で採用された(水資源に関する)2度ラインのようなものは、さすがに恣意的だと。
頑張って、再計算をさせているようですが、殆ど結果が変わらないとみえて、数日前外務副大臣の福山氏と話した人の話だと、あまり話したがらなかったようなので、よい結果は得られていないと思います。今日も、モデル計算を行っている日本の権威数名の話を聞きましたが、正気とは思えません。
まあ、経済成長戦略が大失敗することは誰の眼にみても明らかなので、あれはわざと日本経済を衰退させて、CO2排出量を減少させようという政策なのかもと、意地悪な目で見ています。結果的に、短期の目標設定でウソをつき、マニフェストは実現させると。ただし、経済が衰退すれば誰も支持しなくなるので、マニフェスト実現の意味はないですけど。
高速道路無料化に関しては、言うまでもなく、モータリゼーションを加速させ、財政を悪化し、今後さらに困難になるであろうインフラのメンテナンスの潮流と逆行するまさに愚策と思います。理解不能。
新エネ政策に関して、全量買い取りへの方向や、太陽光以外の新エネへの拡大など、新エネ普及の観点からプラスの部分もあるかと思います。まだ、中間報告も上がっていないので評価できませんが、風力、小水力、地熱等の高価買い取りの認可が降りれば、一定に評価はしていいと思います。細かいところでは反対もあるのですが。
主たるエネルギー政策は、現状ではないと言ってよいと思うので、政治的な不確定要素を増大させているという意味で、民主党政権の存在はマイナスでしかないと考えています。
ニュースのコピペは確かに多いかもしれませんね。考え物です・・・。
EVの低安全と書いてしまいましたが、誤解を与えてしまったかもしれません。決してEVが安全でないということが言いたかったのではありません。
現行のガソリン車とは、特性が異なるので、現行の自動車安全基準を満たすようにEVを作ってしまうと、余計に競争に勝てなくなってしまうのではないかということです。
つまり、現在の小型車と、二輪車の間に、EV専用の基準を設け、最高スピードを制限する代わりに、衝突安全基準を下げたほうが、EVの市場投入には有利ではないかと考えます。
その意義や細かい根拠は、daiさんなら理解していただけるのではないでしょうか。
中国の農村部で、激安で安全基準ムシのEVがどんどん走っているのを見ると、日本でも農村部や都市部コミューターなどに限定して、激安EVがもっと走ってもいいような気がします。
と、いうわけです。
民主党に関して、環境・エネルギー政策で拒否感を感じるのは、-25%という目標に関するところと、高速道路無料化の部分の2点です。
温暖化に関しては、私は懐疑派ではありませんが、今後のCO2濃度上昇の殆どを中国とアメリカが担うであろうことを考えると、日本が減らそうが増やそうが大して関係ないので、その2国を制御できない以上、無理するくらいなら、温暖化した後の対策を考える方が現実的ではないかと考えます。幸か不幸か、気候変動による影響は、日本は他の国より小さいはずです。また、被害の多くは、局所的に発生する干ばつがかなり大きな部分を占めると考えられますが、水文学の専門家沖大幹先生によりますと、被害人口拡大の因子の殆どは、開発途上国の人口増加によるもので、温暖化の影響はむしろプラスになる場合もあると聞きました。IPCC3で採用された(水資源に関する)2度ラインのようなものは、さすがに恣意的だと。
頑張って、再計算をさせているようですが、殆ど結果が変わらないとみえて、数日前外務副大臣の福山氏と話した人の話だと、あまり話したがらなかったようなので、よい結果は得られていないと思います。今日も、モデル計算を行っている日本の権威数名の話を聞きましたが、正気とは思えません。
まあ、経済成長戦略が大失敗することは誰の眼にみても明らかなので、あれはわざと日本経済を衰退させて、CO2排出量を減少させようという政策なのかもと、意地悪な目で見ています。結果的に、短期の目標設定でウソをつき、マニフェストは実現させると。ただし、経済が衰退すれば誰も支持しなくなるので、マニフェスト実現の意味はないですけど。
高速道路無料化に関しては、言うまでもなく、モータリゼーションを加速させ、財政を悪化し、今後さらに困難になるであろうインフラのメンテナンスの潮流と逆行するまさに愚策と思います。理解不能。
新エネ政策に関して、全量買い取りへの方向や、太陽光以外の新エネへの拡大など、新エネ普及の観点からプラスの部分もあるかと思います。まだ、中間報告も上がっていないので評価できませんが、風力、小水力、地熱等の高価買い取りの認可が降りれば、一定に評価はしていいと思います。細かいところでは反対もあるのですが。
主たるエネルギー政策は、現状ではないと言ってよいと思うので、政治的な不確定要素を増大させているという意味で、民主党政権の存在はマイナスでしかないと考えています。
ただし、何よりも私が民主党の存在を受け入れられないのは、政府の最低限の機能である外交と金融政策があまりに危険ということであり、はっきり言って、それ以外はあってもなくても、人気を維持することによって政権を安定させる程度の効果しかないと考えています。
米国への裏切りや、サウジへの失態、中国・韓国に対する謎の態度、外国人地方参政権の付与、幹事長による天皇陛下の扱いや数々の公然の暴挙、首相・財務大臣の無能さ、などなどです。
サウジアラビアの新聞には、日本の政権交代は民主党が政権担当能力が無いことを証明するために行われたと書かれたそうですが、全くその通りで、あまりにおぼつかなくてとても政権とは呼べないと思います。
ま、政府がそんな程度でも、一時的にはなんとかなるのですが、民主党が行っていることは単なる国体の破壊作業みたいなものなので、それが吉とでる可能性は否定はしません。
ただし、これからの将来は、エネルギー資源を巡って、かなりギクシャクした国際関係になると私は考えているので、その為の長期的な準備としては、逆行してしまっていると思います。
かといって、引き返すのが自民党?といわれると、つらいところです。
まともな選択肢を失ってしまったことが、日本の不孝であり、日本人が育てるところの政治の限界ということなんでしょう。
SOFCに関しては、海外では定置型FCの主流はSOFCであり、日本のようにPEFCに偏っているのは、FCV開発に先行的に偏りすぎていたという事情があるのではないかとにらんでいます。
PEFCの大規模実証事業であるエネファームは、今年もうすぐ5000基になろうというところですが、海外から非常に注目されています。
「なぜ、SOFCじゃなくて日本はPEFCなんだ。理解できない。でも、日本人が本気ということだから、なにか勝算があるのかもしれない。我々は、日本の結果をよく見ることにしよう。でも、外に出てくる数字を見る限り、大失敗に終わるんじゃないだろうか。」
IEAの定置型FCの部会に何度か出席したのですが、これが大方の海外の見方だと思います。
daiさんが仰っておられるのは、京セラや日本ガイシ、三菱重工の動きのことでしょうか。
米国への裏切りや、サウジへの失態、中国・韓国に対する謎の態度、外国人地方参政権の付与、幹事長による天皇陛下の扱いや数々の公然の暴挙、首相・財務大臣の無能さ、などなどです。
サウジアラビアの新聞には、日本の政権交代は民主党が政権担当能力が無いことを証明するために行われたと書かれたそうですが、全くその通りで、あまりにおぼつかなくてとても政権とは呼べないと思います。
ま、政府がそんな程度でも、一時的にはなんとかなるのですが、民主党が行っていることは単なる国体の破壊作業みたいなものなので、それが吉とでる可能性は否定はしません。
ただし、これからの将来は、エネルギー資源を巡って、かなりギクシャクした国際関係になると私は考えているので、その為の長期的な準備としては、逆行してしまっていると思います。
かといって、引き返すのが自民党?といわれると、つらいところです。
まともな選択肢を失ってしまったことが、日本の不孝であり、日本人が育てるところの政治の限界ということなんでしょう。
SOFCに関しては、海外では定置型FCの主流はSOFCであり、日本のようにPEFCに偏っているのは、FCV開発に先行的に偏りすぎていたという事情があるのではないかとにらんでいます。
PEFCの大規模実証事業であるエネファームは、今年もうすぐ5000基になろうというところですが、海外から非常に注目されています。
「なぜ、SOFCじゃなくて日本はPEFCなんだ。理解できない。でも、日本人が本気ということだから、なにか勝算があるのかもしれない。我々は、日本の結果をよく見ることにしよう。でも、外に出てくる数字を見る限り、大失敗に終わるんじゃないだろうか。」
IEAの定置型FCの部会に何度か出席したのですが、これが大方の海外の見方だと思います。
daiさんが仰っておられるのは、京セラや日本ガイシ、三菱重工の動きのことでしょうか。
ぬりさん
重要な問題点がたくさん出ていると思います。
ぬりさんの日記に対応して書かせていただいた部分は、このコミュでの議論とは別と思うので、とりあえずそこへの書込みを議論の場としておきます。
> つまり、現在の小型車と、二輪車の間に、EV専用の基準を設け、最高スピードを制限する代わりに、衝突安全基準を下げたほうが、EVの市場投入には有利ではないかと考えます。
これは了解、合意です。もっと言えばモビリティーの再定義が必要だと考えています。たとえば、東京で大部分の戸別住宅の門前では40k,/hくらいで自動車が走っていますが、田舎だといきなり国道に面していて80km/hで走る車の前に幼稚園児が飛び出したりとか、、、東京では家の周囲で子どもが遊べるけれど、田舎では子どもは家の中で遊ばなければいけない、、、
温暖化に関する中国とアメリカについては、私もできれば昨年中にマイブログに書きたかったのですが、時間が取れません。2月中旬くらいまでにはなんとか。
結論だけ言うと、2050年に90年比半減を達成し、その全人類の排出量を近年の世界人口で割った上で各国の人口で割り振る。これを目標値として、現状の排出量との差を「要求削減量」と定義すると、annex1(EUは27国)合計と、アメリカと、中国がほぼ同量の削減が要求されており、かつ、世界全体の要求削減量の82%をこの3グループで占めています。
(そもそも温暖化の議論をするときに、インドを持ち出すこと自体中国を利する発言だ、ということを理解する人がとても少ないのが悲しい。現時点でインドは2050年適正値にいますから)
その上で、25%目標は、あくまでもアメリカ、中国を巻き込むための外交カード、プラス、グリーンニューディールに関する産業目標のチャレンジングな提言、という意味で私は評価しています。
高速道路関係は私も大反対。前政権もやっていた近距離の通勤割引こそ地域経済にも温暖化対策にもプラスだと思うのですが(たとえば、地方路線の平日の50km以下を無料化)
> 主たるエネルギー政策は、現状ではないと言ってよいと思うので、政治的な不確定要素を増大させているという意味で、民主党政権の存在はマイナスでしかないと考えています。
自民党政権との比較においては、少なくとも政権交代がプラスだったと考えています。少なくとも、次に自民党政権になったとして、政権交代なしでそのまま自民党政権になった場合より、政権交代を2回やって自民党政権になった方がプラスだろうと。
(字数制限で、一旦切ります)
重要な問題点がたくさん出ていると思います。
ぬりさんの日記に対応して書かせていただいた部分は、このコミュでの議論とは別と思うので、とりあえずそこへの書込みを議論の場としておきます。
> つまり、現在の小型車と、二輪車の間に、EV専用の基準を設け、最高スピードを制限する代わりに、衝突安全基準を下げたほうが、EVの市場投入には有利ではないかと考えます。
これは了解、合意です。もっと言えばモビリティーの再定義が必要だと考えています。たとえば、東京で大部分の戸別住宅の門前では40k,/hくらいで自動車が走っていますが、田舎だといきなり国道に面していて80km/hで走る車の前に幼稚園児が飛び出したりとか、、、東京では家の周囲で子どもが遊べるけれど、田舎では子どもは家の中で遊ばなければいけない、、、
温暖化に関する中国とアメリカについては、私もできれば昨年中にマイブログに書きたかったのですが、時間が取れません。2月中旬くらいまでにはなんとか。
結論だけ言うと、2050年に90年比半減を達成し、その全人類の排出量を近年の世界人口で割った上で各国の人口で割り振る。これを目標値として、現状の排出量との差を「要求削減量」と定義すると、annex1(EUは27国)合計と、アメリカと、中国がほぼ同量の削減が要求されており、かつ、世界全体の要求削減量の82%をこの3グループで占めています。
(そもそも温暖化の議論をするときに、インドを持ち出すこと自体中国を利する発言だ、ということを理解する人がとても少ないのが悲しい。現時点でインドは2050年適正値にいますから)
その上で、25%目標は、あくまでもアメリカ、中国を巻き込むための外交カード、プラス、グリーンニューディールに関する産業目標のチャレンジングな提言、という意味で私は評価しています。
高速道路関係は私も大反対。前政権もやっていた近距離の通勤割引こそ地域経済にも温暖化対策にもプラスだと思うのですが(たとえば、地方路線の平日の50km以下を無料化)
> 主たるエネルギー政策は、現状ではないと言ってよいと思うので、政治的な不確定要素を増大させているという意味で、民主党政権の存在はマイナスでしかないと考えています。
自民党政権との比較においては、少なくとも政権交代がプラスだったと考えています。少なくとも、次に自民党政権になったとして、政権交代なしでそのまま自民党政権になった場合より、政権交代を2回やって自民党政権になった方がプラスだろうと。
(字数制限で、一旦切ります)
(989からのつづきです)
> 米国への裏切り
日本ほど米軍を大量に駐在させている国は他にない、という分析を読んだことがあります。フィリピンは駐留米軍に全部出ていってもらったけれど、アメリカとの友好関係に傷はついていない、とか。
> サウジへの失態
これが何を指すのか、わかりません、ごめんなさい。
> 中国・韓国に対する謎の態度
何が謎か、これも分かりません。
> 、外国人地方参政権の付与
私はもともと賛成です。日本の地政学敵意値を考えると、多様な人の意見が重要と思います。たとえばイビチャ=オシムとか、ピーター=フランクルとか。
また、人は責任を与えられると役割を果たすようになるというのが私の持論です。石原都知事のように「選挙権を行使したければ先に日本国籍を取れ」というのも一方の意見としてありだと思いますが、むしろ、選挙で投票する責任を与えることで日本社会に住んでいる(事情はともかく国籍のある国に住まない)人たちが社会的責任を感じて日本社会のあるべきすがたをより強く考え、その結果日本国籍を取得する人が増える、というのが、現実的かつ望ましいストーリーだと私は考えます。
小沢問題はぬりさんの日記にコメント入れました。
首相が無能かどうかは、そう見られても仕方ない面jがあるとは思いますが、記者クラブメディアが誇張している部分も大きいし、過去5代の首相との比較では、小泉をどう評価するかを除けば、森・;福田・阿部・麻生と比べて無能とは言えないと思います。
ちなみに、無能な首相、ということについて、私は森さん(か宇野さん)が戦後史上最悪だったと考えています。
> まともな選択肢を失ってしまったことが、日本の不孝であり、日本人が育てるところの政治の限界ということなんでしょう。
冷戦崩壊後にまともな選択肢を持ってこなかったのが失敗だったと思っています。今となっては日本にソフトランディングの選択肢はないと。
私は民主党政権はそれほど悪くないと思っていますが、多分、ずるずる何もできずに終わるよりは民主党政権を経てハードランディングする方がまだまし、というところまで幅広く考えれば、ぬりさんとも合意できるのではないかと考えています。
> SOFCに関しては、海外では定置型FCの主流はSOFCであり、日本のようにPEFCに偏っているのは、FCV開発に先行的に偏りすぎていたという事情があるのではないかとにらんでいます。
この情報、とても勉強になります。
京セラや日本ガイシのSOFC技術は、世界的に見て、遅れているのでしょうか? 期待していたのですが。(三菱重工が関わっていることは知りませんでした)
> サウジアラビアの新聞には、日本の政権交代は民主党が政権担当能力が無いことを証明するために行われたと書かれたそうですが
それを認めたとしても、同時に、もはや自民党政権に政権担当能力がないことも照明されていると思います。多分ぬりさんも同意でしょう。
現状を経て、何を作り出すかが大切。後ろ向きの批判はすべて無視し、前向きの批判の上に未来を作る以外に、日本の道はないと思います。民主党がやっている事の是非を語る場合も、その批判を通して何を生み出すかを考えないと。
(少なくとも検察庁は日本の未来に責任を負っていないと思います。そういう人たちに日本の未来を左右させてはいけない)
> 米国への裏切り
日本ほど米軍を大量に駐在させている国は他にない、という分析を読んだことがあります。フィリピンは駐留米軍に全部出ていってもらったけれど、アメリカとの友好関係に傷はついていない、とか。
> サウジへの失態
これが何を指すのか、わかりません、ごめんなさい。
> 中国・韓国に対する謎の態度
何が謎か、これも分かりません。
> 、外国人地方参政権の付与
私はもともと賛成です。日本の地政学敵意値を考えると、多様な人の意見が重要と思います。たとえばイビチャ=オシムとか、ピーター=フランクルとか。
また、人は責任を与えられると役割を果たすようになるというのが私の持論です。石原都知事のように「選挙権を行使したければ先に日本国籍を取れ」というのも一方の意見としてありだと思いますが、むしろ、選挙で投票する責任を与えることで日本社会に住んでいる(事情はともかく国籍のある国に住まない)人たちが社会的責任を感じて日本社会のあるべきすがたをより強く考え、その結果日本国籍を取得する人が増える、というのが、現実的かつ望ましいストーリーだと私は考えます。
小沢問題はぬりさんの日記にコメント入れました。
首相が無能かどうかは、そう見られても仕方ない面jがあるとは思いますが、記者クラブメディアが誇張している部分も大きいし、過去5代の首相との比較では、小泉をどう評価するかを除けば、森・;福田・阿部・麻生と比べて無能とは言えないと思います。
ちなみに、無能な首相、ということについて、私は森さん(か宇野さん)が戦後史上最悪だったと考えています。
> まともな選択肢を失ってしまったことが、日本の不孝であり、日本人が育てるところの政治の限界ということなんでしょう。
冷戦崩壊後にまともな選択肢を持ってこなかったのが失敗だったと思っています。今となっては日本にソフトランディングの選択肢はないと。
私は民主党政権はそれほど悪くないと思っていますが、多分、ずるずる何もできずに終わるよりは民主党政権を経てハードランディングする方がまだまし、というところまで幅広く考えれば、ぬりさんとも合意できるのではないかと考えています。
> SOFCに関しては、海外では定置型FCの主流はSOFCであり、日本のようにPEFCに偏っているのは、FCV開発に先行的に偏りすぎていたという事情があるのではないかとにらんでいます。
この情報、とても勉強になります。
京セラや日本ガイシのSOFC技術は、世界的に見て、遅れているのでしょうか? 期待していたのですが。(三菱重工が関わっていることは知りませんでした)
> サウジアラビアの新聞には、日本の政権交代は民主党が政権担当能力が無いことを証明するために行われたと書かれたそうですが
それを認めたとしても、同時に、もはや自民党政権に政権担当能力がないことも照明されていると思います。多分ぬりさんも同意でしょう。
現状を経て、何を作り出すかが大切。後ろ向きの批判はすべて無視し、前向きの批判の上に未来を作る以外に、日本の道はないと思います。民主党がやっている事の是非を語る場合も、その批判を通して何を生み出すかを考えないと。
(少なくとも検察庁は日本の未来に責任を負っていないと思います。そういう人たちに日本の未来を左右させてはいけない)
daiさん
ろくに外交力もない日本が、単なる自虐的数字で、アメリカや中国を巻き込もうなんて甘過ぎと思います。はっきりいって対外的なインパクトはすでにゼロですね。
アメリカとは一緒に基準年を2005年にしようと足並みを揃えていたのに、ろくに話もせず90年比に変えてしまったのは、信頼の意味で巻き込むのには大きく後退したと聞きます。中国はもとより日本の言うことを聞く国ではありません。
環境分野での経済牽引は大切ですが、グリーンニューディールと銘打ってばらまきを行ってしまっては、ただ産業を潰す方に働いてしまうでしょう。
政権交代を二回やって戻った方がよいというのは賛成です。
はなから期待していませんでしたが、一応しばらくは静観していました。しかし、試しにやらせてみるには余りに危険が大き過ぎて取り返しがつかない、自民党や国民の勉強代としては高くつきすぎるように思います。
そりゃフィリピンの現在のアロヨ政権は小泉と並んでイラク戦争を支持したほどの親米政権ですから。
米軍を撤退させたのは、現地の中国人による反米世論の高まりの影響が大きくありました。しかし、米軍を撤退させた直後、自国軍画未整備だったため、中国軍が南沙諸島(天然ガスが出る)を実行支配したため、フィリピン内で今度は対中国不安がつのり、親米政権が誕生したわけです。現在はテロ対策の名目で一部呼び戻しており、再び長期駐屯できるように法整備を進めています。
民主党はもとより大した外交政策を持っていなかったのですが、最初の外交ブレーンに寺島実郎氏を採用したのが大きなまちがいでした。
岡田外相がいろいろ外交交渉を行っても、毎朝官邸に届く「寺島メモ」と呼ばれるFAXを真に受けたのか、鳩山首相がとんちんかんなことを言って打ち壊してしまいます。
最初は米国は首相がバカなのだと思い、国務省は首相を相手にしないことを決めます。しかし、次第に寺島氏の影響があると考えるようになり、米国の関係者の寺島氏との接触を禁止。干された寺島氏は12月18日あたりでブレーンを首になり、代わりに小泉政権で外交顧問をしていた岡本行夫氏に交代します。
米軍にでて行ってもらうのはよいですが、その前に憲法を改正して自衛軍をもつ準備をしないと。
普天間問題は、約束の履行が筋です。
ろくに外交力もない日本が、単なる自虐的数字で、アメリカや中国を巻き込もうなんて甘過ぎと思います。はっきりいって対外的なインパクトはすでにゼロですね。
アメリカとは一緒に基準年を2005年にしようと足並みを揃えていたのに、ろくに話もせず90年比に変えてしまったのは、信頼の意味で巻き込むのには大きく後退したと聞きます。中国はもとより日本の言うことを聞く国ではありません。
環境分野での経済牽引は大切ですが、グリーンニューディールと銘打ってばらまきを行ってしまっては、ただ産業を潰す方に働いてしまうでしょう。
政権交代を二回やって戻った方がよいというのは賛成です。
はなから期待していませんでしたが、一応しばらくは静観していました。しかし、試しにやらせてみるには余りに危険が大き過ぎて取り返しがつかない、自民党や国民の勉強代としては高くつきすぎるように思います。
そりゃフィリピンの現在のアロヨ政権は小泉と並んでイラク戦争を支持したほどの親米政権ですから。
米軍を撤退させたのは、現地の中国人による反米世論の高まりの影響が大きくありました。しかし、米軍を撤退させた直後、自国軍画未整備だったため、中国軍が南沙諸島(天然ガスが出る)を実行支配したため、フィリピン内で今度は対中国不安がつのり、親米政権が誕生したわけです。現在はテロ対策の名目で一部呼び戻しており、再び長期駐屯できるように法整備を進めています。
民主党はもとより大した外交政策を持っていなかったのですが、最初の外交ブレーンに寺島実郎氏を採用したのが大きなまちがいでした。
岡田外相がいろいろ外交交渉を行っても、毎朝官邸に届く「寺島メモ」と呼ばれるFAXを真に受けたのか、鳩山首相がとんちんかんなことを言って打ち壊してしまいます。
最初は米国は首相がバカなのだと思い、国務省は首相を相手にしないことを決めます。しかし、次第に寺島氏の影響があると考えるようになり、米国の関係者の寺島氏との接触を禁止。干された寺島氏は12月18日あたりでブレーンを首になり、代わりに小泉政権で外交顧問をしていた岡本行夫氏に交代します。
米軍にでて行ってもらうのはよいですが、その前に憲法を改正して自衛軍をもつ準備をしないと。
普天間問題は、約束の履行が筋です。
サウジアラビアの件は、昨年11月に、サウジへの特使に、当初は長年のつながりのある福田氏が予定されていましたが、鳩山首相は自身の友人の岩國氏を派遣。それを知ったサウジアラビア国王はがっかりして、式典の出席を取り止めたというものです。
中国と韓国へのナゾの態度とは、
マニフェストにも載せられず、内閣でも不一致、最高裁で違憲判決が出ていて、国民に認知すらされていない外交人地方参政権の問題を、与党のいち幹事長が中韓に対して「お待たせしました」と言って約束をしてきたこと。
もう1つは、いくら中国とパイプをつくるためだとはいえ、一国の国会議員があれだけ大挙して一国の元首に挨拶に行き握手して帰ってくる(それも税金で)という異常さです。そんな国聞いたことがありません。あれで、パイプができたんでしょうか。
おまけに、あの握手会と引き換えに天皇陛下と習近平副主席の会談を、天皇陛下のご予定を確認する前に約束してきたことです。完全に他国を優先するなんて異常です。習近平氏は、後継者候補ナンバーワンなんて言われていますが、最近失態続きで遠退いていたので、天皇陛下と会談をして既成事実化し、挽回をはかるため、中国側から要望が出たのだと推測します。
これはどう考えても異常です。
オシムもピーターフランクルも参政権がほしくて日本にきたわけではありません。
私も多様性の増加は鍵だと思いますが、それは移民政策であって参政権ではありません。
責任を与えられると役割を果たすようになることには賛成ですが、外国籍の方は自国の利益の為に働くために日本に来ているわけでもあるので、そんな役割を果たされる必要はありません。外国人に参政権がないのは世界の常識です。
日本に住んでいる外国人で参政権を求めているのは特定永住外国人である韓国系の方々が主であり、朝鮮系や台湾系はむしろ反対しています。彼らは、韓国籍を持ちながら祖国に帰る意志のない人々なわけで、それを在日特権というかたちでコンプロマイズさせて日本政府もごまかしてきたわけですが、そのような罪深い枠を、参政権を与えることでさらに固定化してしまう恐れがあります。帰国支援と帰化策を推し進めればいいはずで、中途半端でいることに押し留めるのはもっと罪深いと思います。
しかし、韓国系の方々は減少傾向にあるので、これからの外国人はまちがいなくほとんどが中国人です。この法案が通ればまず中国人が大挙してくることになります。自国には選挙はないのに日本では持っているという奇妙な状態も問題かも知れませんが、中国人だけでなく、本当に多様な人々を受け入れたいのであれば、特区を設けて税制優遇し、外資を呼び込むのが普通の感覚ではないでしょうか。
憲法違反の問題も含め、このやり方による多様化政策は絶対反対です。
鳩山、管の両氏に関しては、野党時代から一貫して無能の政治家だと考えていたので、マスメディアの誇張は関係ありません。daiさんの挙げられた歴代首相4人は、決して優秀だったとは思いませんが、鳩山、管に比べたら比較にならないほどまともな感覚を持っていると思います。二人ともただ小沢という男に担がれただけの存在ですよ。
今の日本の状況に追い込んだ根本的な問題を、自民党時代の小沢がいくつもたらしたかを考えれば、到底いまの民主党には任せられるとは考えられないはずなんですが。小沢が嫌で民主党に入ったという議員さんもたくさんおられますが、不憫でなりません。
SOFCの技術が海外より遅れているということはないと思います。大々的に推進されていないのは、業界内の特殊な構造があるからと思います。海外でもSOFCの大規模な導入はまだありません。
後ろ向きに考えたくはありませんが、少なくとも現在の首相、幹事長にはおやめになって頂く以外に、前向きな選択はありません。
この状態がつづけば、どんどんと見るも無残な状況に追い込まれ、悪い反動が起きてしまうでしょう。
中国と韓国へのナゾの態度とは、
マニフェストにも載せられず、内閣でも不一致、最高裁で違憲判決が出ていて、国民に認知すらされていない外交人地方参政権の問題を、与党のいち幹事長が中韓に対して「お待たせしました」と言って約束をしてきたこと。
もう1つは、いくら中国とパイプをつくるためだとはいえ、一国の国会議員があれだけ大挙して一国の元首に挨拶に行き握手して帰ってくる(それも税金で)という異常さです。そんな国聞いたことがありません。あれで、パイプができたんでしょうか。
おまけに、あの握手会と引き換えに天皇陛下と習近平副主席の会談を、天皇陛下のご予定を確認する前に約束してきたことです。完全に他国を優先するなんて異常です。習近平氏は、後継者候補ナンバーワンなんて言われていますが、最近失態続きで遠退いていたので、天皇陛下と会談をして既成事実化し、挽回をはかるため、中国側から要望が出たのだと推測します。
これはどう考えても異常です。
オシムもピーターフランクルも参政権がほしくて日本にきたわけではありません。
私も多様性の増加は鍵だと思いますが、それは移民政策であって参政権ではありません。
責任を与えられると役割を果たすようになることには賛成ですが、外国籍の方は自国の利益の為に働くために日本に来ているわけでもあるので、そんな役割を果たされる必要はありません。外国人に参政権がないのは世界の常識です。
日本に住んでいる外国人で参政権を求めているのは特定永住外国人である韓国系の方々が主であり、朝鮮系や台湾系はむしろ反対しています。彼らは、韓国籍を持ちながら祖国に帰る意志のない人々なわけで、それを在日特権というかたちでコンプロマイズさせて日本政府もごまかしてきたわけですが、そのような罪深い枠を、参政権を与えることでさらに固定化してしまう恐れがあります。帰国支援と帰化策を推し進めればいいはずで、中途半端でいることに押し留めるのはもっと罪深いと思います。
しかし、韓国系の方々は減少傾向にあるので、これからの外国人はまちがいなくほとんどが中国人です。この法案が通ればまず中国人が大挙してくることになります。自国には選挙はないのに日本では持っているという奇妙な状態も問題かも知れませんが、中国人だけでなく、本当に多様な人々を受け入れたいのであれば、特区を設けて税制優遇し、外資を呼び込むのが普通の感覚ではないでしょうか。
憲法違反の問題も含め、このやり方による多様化政策は絶対反対です。
鳩山、管の両氏に関しては、野党時代から一貫して無能の政治家だと考えていたので、マスメディアの誇張は関係ありません。daiさんの挙げられた歴代首相4人は、決して優秀だったとは思いませんが、鳩山、管に比べたら比較にならないほどまともな感覚を持っていると思います。二人ともただ小沢という男に担がれただけの存在ですよ。
今の日本の状況に追い込んだ根本的な問題を、自民党時代の小沢がいくつもたらしたかを考えれば、到底いまの民主党には任せられるとは考えられないはずなんですが。小沢が嫌で民主党に入ったという議員さんもたくさんおられますが、不憫でなりません。
SOFCの技術が海外より遅れているということはないと思います。大々的に推進されていないのは、業界内の特殊な構造があるからと思います。海外でもSOFCの大規模な導入はまだありません。
後ろ向きに考えたくはありませんが、少なくとも現在の首相、幹事長にはおやめになって頂く以外に、前向きな選択はありません。
この状態がつづけば、どんどんと見るも無残な状況に追い込まれ、悪い反動が起きてしまうでしょう。
ぬりさん
温暖化交渉に関するアメリカとの「信頼関係」については、京都議定書からアメリカが一方的に離脱した時点で終わっているように思うのですが。
フィリピンの件。
中国を意識した安全保障という意味で言うと、尖閣諸島に中国が軍事侵攻するスキを与えない、というテーマが具体性のある最重点検討課題かと考えているので、フィリピンとの比較は重要と思っています。
中国の視点を想定して、尖閣諸島軍事侵攻に必要な軍事的コストと、得るもの、失うものを考えると、結構ハードルが高いのではないかと考えています。他国の海上警察が警備する「領土」への軍事侵攻は、一定以上の力のある国同士では結構たいへんだろうと。
逆に言えば、日本にとって尖閣諸島を直接防衛する想定での安全保障対策よりも、東アジア全体の枠組み(当然外交も含めて)の強化に力点をおくべきだと思っています。海兵隊がどこにいるかはそれほど重要とは思っていません。
中国は核保有国であり、日本の核武装は現実的でないので、核の威嚇に対する対策は必要。そのためには、アメリカが「日本に対する核攻撃はアメリカ本土に対する核攻撃と見なす」と本気で主張する状況は必要だと思います。
一方、アメリカが海兵隊のグアム移転を合理的選択肢として検討したことは間違いないと思っています。だとしたら、無理に海兵隊を沖縄に留めてもらう必要性は低いのではないでしょうか。
小沢一郎さんが言う「第七艦隊のみの日本駐留」は合理的選択肢の一つだと考えます。
一方、鳩山さんの言う「駐留無き」は、核に関する上記文脈のもとでは不可能でしょう。東アジアにおける安全保障の枠組みを大きく変える必要がある。
「修学旅行外交」については、私はいいアイディアだったと思います。もちろん「あれで、パイプができた」はずもありませんが、一年生議員が中国の政治家と接触したことで、20年後にパイプになるような人脈づくりのきっかけになれば充分な成果でしょう。
大使館員が観光ガイドを務める「外遊」と違って、税金を使う価値がある。
> あの握手会と引き換えに天皇陛下と習近平副主席の会談を、天皇陛下のご予定を確認する前に約束してきた
これは事実認識の相違ですね。
胡錦濤氏が副主席だった時代に天皇と会見した前例に倣ったという報道の方が事実だと私は判断しています。事務方がそれを軽視したために天皇のアポが取れず、その(事務方の)ミスを政治家の決断でフォローしたのだろうと。
議論したい内容がてんこ盛りですが、時間が許さないので、この辺で失礼します。
温暖化交渉に関するアメリカとの「信頼関係」については、京都議定書からアメリカが一方的に離脱した時点で終わっているように思うのですが。
フィリピンの件。
中国を意識した安全保障という意味で言うと、尖閣諸島に中国が軍事侵攻するスキを与えない、というテーマが具体性のある最重点検討課題かと考えているので、フィリピンとの比較は重要と思っています。
中国の視点を想定して、尖閣諸島軍事侵攻に必要な軍事的コストと、得るもの、失うものを考えると、結構ハードルが高いのではないかと考えています。他国の海上警察が警備する「領土」への軍事侵攻は、一定以上の力のある国同士では結構たいへんだろうと。
逆に言えば、日本にとって尖閣諸島を直接防衛する想定での安全保障対策よりも、東アジア全体の枠組み(当然外交も含めて)の強化に力点をおくべきだと思っています。海兵隊がどこにいるかはそれほど重要とは思っていません。
中国は核保有国であり、日本の核武装は現実的でないので、核の威嚇に対する対策は必要。そのためには、アメリカが「日本に対する核攻撃はアメリカ本土に対する核攻撃と見なす」と本気で主張する状況は必要だと思います。
一方、アメリカが海兵隊のグアム移転を合理的選択肢として検討したことは間違いないと思っています。だとしたら、無理に海兵隊を沖縄に留めてもらう必要性は低いのではないでしょうか。
小沢一郎さんが言う「第七艦隊のみの日本駐留」は合理的選択肢の一つだと考えます。
一方、鳩山さんの言う「駐留無き」は、核に関する上記文脈のもとでは不可能でしょう。東アジアにおける安全保障の枠組みを大きく変える必要がある。
「修学旅行外交」については、私はいいアイディアだったと思います。もちろん「あれで、パイプができた」はずもありませんが、一年生議員が中国の政治家と接触したことで、20年後にパイプになるような人脈づくりのきっかけになれば充分な成果でしょう。
大使館員が観光ガイドを務める「外遊」と違って、税金を使う価値がある。
> あの握手会と引き換えに天皇陛下と習近平副主席の会談を、天皇陛下のご予定を確認する前に約束してきた
これは事実認識の相違ですね。
胡錦濤氏が副主席だった時代に天皇と会見した前例に倣ったという報道の方が事実だと私は判断しています。事務方がそれを軽視したために天皇のアポが取れず、その(事務方の)ミスを政治家の決断でフォローしたのだろうと。
議論したい内容がてんこ盛りですが、時間が許さないので、この辺で失礼します。
daiさん
お互いに時間がないでしょうから、議論仕切れない部分はまたいつの日か。
信頼というか、ある意味ではテーブルにつかせるために同調できる部分で研究者同士が同調してきたのだと思いますが。巻き込もうというときに、それを裏切ったのは大きいですよ。とんだ笑いものです。
現在尖閣諸島は、一応海上保安庁が警備していますが、海自は出ていけないので、してないにも等しいです。本当はそうでもないようですが、それはどうも国家機密っぽい。
普天間基地がグアムにいったくらいでは、尖閣にせめて来ることはないと思いますが、日本の軍法が整備されないまま、米軍が引き上げてしまったら、ほとんどリスクなしかと。
それに、外国人地方参政権が付与された状態で、石垣市に中国人をごく一部送り込むだけで、新しい石垣市長が尖閣諸島の中国領有を宣言するなんてこともありえますよ。まあ、実際そういうことが目的の一つなわけですが。
私は、海兵隊が絶対に沖縄にいなければならないとは全然思いませんが、普天間は一度約束したことですから、それは相手の気が変わらない限り、履行すべきです。ただそれだけです。だれも留めたいと思っているひとは少ないはずです。
グアム移転を合理的選択肢として捉えているということは、単なる日本を重要な補給基地から、lフロントとしてしか捉えなくなったという意味で、本来は強い危機感を持たねばならんのですがね。すでに、米軍の太平洋戦略は大きく変わりつつあります。おそらく、グアム中心の潜水艦戦略が変わってきた。
大使館外交が機能していないとしても、「修学旅行」を評価することは到底できませんね。世界の笑いものですと言いたいところですが、既に関心の対象ですらありませんね。
習副主席に関しては、タイミングが重要です。日本では次期国家主席のような扱いをされていますが、あの頃は習副主席はポスト競争から脱落しそうになっていたので、点数稼ぎに過去の事例をもちだして天皇陛下を利用したに過ぎません。少なくとも、中国側のリクエストであることには間違いないでしょう。
前例に倣うのであれば、中国政府と日本政府の間で日程を調整して会合を設定すればいいのに、小沢氏が仲介して、さらに小沢氏があれほどムキになってねじ込んだのは、天皇陛下のアポをとる前に、胡錦濤主席との約束をしてしまい、握手会もやってしまったからに他ならないと思います。
お互いに時間がないでしょうから、議論仕切れない部分はまたいつの日か。
信頼というか、ある意味ではテーブルにつかせるために同調できる部分で研究者同士が同調してきたのだと思いますが。巻き込もうというときに、それを裏切ったのは大きいですよ。とんだ笑いものです。
現在尖閣諸島は、一応海上保安庁が警備していますが、海自は出ていけないので、してないにも等しいです。本当はそうでもないようですが、それはどうも国家機密っぽい。
普天間基地がグアムにいったくらいでは、尖閣にせめて来ることはないと思いますが、日本の軍法が整備されないまま、米軍が引き上げてしまったら、ほとんどリスクなしかと。
それに、外国人地方参政権が付与された状態で、石垣市に中国人をごく一部送り込むだけで、新しい石垣市長が尖閣諸島の中国領有を宣言するなんてこともありえますよ。まあ、実際そういうことが目的の一つなわけですが。
私は、海兵隊が絶対に沖縄にいなければならないとは全然思いませんが、普天間は一度約束したことですから、それは相手の気が変わらない限り、履行すべきです。ただそれだけです。だれも留めたいと思っているひとは少ないはずです。
グアム移転を合理的選択肢として捉えているということは、単なる日本を重要な補給基地から、lフロントとしてしか捉えなくなったという意味で、本来は強い危機感を持たねばならんのですがね。すでに、米軍の太平洋戦略は大きく変わりつつあります。おそらく、グアム中心の潜水艦戦略が変わってきた。
大使館外交が機能していないとしても、「修学旅行」を評価することは到底できませんね。世界の笑いものですと言いたいところですが、既に関心の対象ですらありませんね。
習副主席に関しては、タイミングが重要です。日本では次期国家主席のような扱いをされていますが、あの頃は習副主席はポスト競争から脱落しそうになっていたので、点数稼ぎに過去の事例をもちだして天皇陛下を利用したに過ぎません。少なくとも、中国側のリクエストであることには間違いないでしょう。
前例に倣うのであれば、中国政府と日本政府の間で日程を調整して会合を設定すればいいのに、小沢氏が仲介して、さらに小沢氏があれほどムキになってねじ込んだのは、天皇陛下のアポをとる前に、胡錦濤主席との約束をしてしまい、握手会もやってしまったからに他ならないと思います。
その条件で選挙権を与えるならば、帰化すればよいと思ってしまうのですが。
母国にも参政権があるのに、日本でも選挙権があるというのでは、過剰利権な気がします。普通に考えて。別に、日本に来ていただいているわけではないので。来たいと思われるような国にした方がよいというに過ぎません。
そう状況になってから対処するのでは、国民の排外意識にいたずらに火をつけることになってしまうと思います。
「くさ」の種類にもよりますが、北朝鮮系だけで2万人くらいはいると聞いていますが。
少なくとも、多様化政策の手法として、参政権付与は適当な手段とは思えませんね。
スウェーデンでも、既に大量の移民を受け入れたために、社会では大きな問題を抱えています。
どうしても、移民は固まって居住するので、いくつかの都市では人口の4割にも達し、ますます地方自治がゆがめられていくという事態になっています。現地の友人に聞いても、深刻に受け止めている人は多いです。労働人口の確保という側面もあるでしょうが、リスクもしっかりと考えた上で決断しなければなりません。
母国にも参政権があるのに、日本でも選挙権があるというのでは、過剰利権な気がします。普通に考えて。別に、日本に来ていただいているわけではないので。来たいと思われるような国にした方がよいというに過ぎません。
そう状況になってから対処するのでは、国民の排外意識にいたずらに火をつけることになってしまうと思います。
「くさ」の種類にもよりますが、北朝鮮系だけで2万人くらいはいると聞いていますが。
少なくとも、多様化政策の手法として、参政権付与は適当な手段とは思えませんね。
スウェーデンでも、既に大量の移民を受け入れたために、社会では大きな問題を抱えています。
どうしても、移民は固まって居住するので、いくつかの都市では人口の4割にも達し、ますます地方自治がゆがめられていくという事態になっています。現地の友人に聞いても、深刻に受け止めている人は多いです。労働人口の確保という側面もあるでしょうが、リスクもしっかりと考えた上で決断しなければなりません。
先日、JOGMEC主催のセミナーで、前のEIA長官だったGuy Caruso氏とEnergy Policy Research Foundation , IncのLucian Pugliaresi氏の講演を聞いてきました。
Caruso氏はオバマ政権の環境政策について、Pugliaresi氏はシェールガスについてです。
Caruso氏によれば米国でのキャップアンドトレードを定める、ACESA(American Clean Energy and Security Act)法案は、数カ月前に下院を通過したが、オバマ政権の人気の陰りや、反対派の活動の影響もあって、今年中に上院を通過するのは難しいとの見解でした。
EIAによる分析によると、国際オフセットをいれないと、CO2削減原単位はある場合のおよそ$40/CO2-tの5倍の約$200/CO2-tになる(2030年時点)と予測。2025年頃から電気料金が急騰し、17セント/kWhまで上昇するとしている。
こちらの講演はあまり面白いことはなかった、講演後に個別に話をすることが出来たので、EIAのことについていろいろ聞いてみた。
Pugliaresi氏のシェールガスの話は、特に専門的な知見を得ることもなかったが、
・2009年のガス生産量は、米国が世界一だった
・非在来ガスの生産量は、ほぼLNGの生産量と同じ成長量で推移している
・LNG事業は長期契約がないと成立しないプロジェクトであるが、スポット買いの割合が増えている
・今後、価格のインデックスが変わる可能性がある
・天然ガスが安くなれば、GTLの可能性が広がるが、現時点では設備投資の高さがネック
・CNG自動車は、航続距離が短いのでアメリカでは普及しない
会場からは、良い質問がたくさん出た。Climategateの質問もあったけど(笑)。
結局、ガスは発電向けであり、安い石炭や原子力と競合する限り、需要の伸びには限度がある。
価格スキームが変わっていくとして、輸送用燃料への代替弾力性がどれほどなのかということがキーになると感じた。
ただし、この世界はエネルギー効率ではなく、「便利さ」がより重要であるので、安いだけでは変わることはないだろう。
Caruso氏はオバマ政権の環境政策について、Pugliaresi氏はシェールガスについてです。
Caruso氏によれば米国でのキャップアンドトレードを定める、ACESA(American Clean Energy and Security Act)法案は、数カ月前に下院を通過したが、オバマ政権の人気の陰りや、反対派の活動の影響もあって、今年中に上院を通過するのは難しいとの見解でした。
EIAによる分析によると、国際オフセットをいれないと、CO2削減原単位はある場合のおよそ$40/CO2-tの5倍の約$200/CO2-tになる(2030年時点)と予測。2025年頃から電気料金が急騰し、17セント/kWhまで上昇するとしている。
こちらの講演はあまり面白いことはなかった、講演後に個別に話をすることが出来たので、EIAのことについていろいろ聞いてみた。
Pugliaresi氏のシェールガスの話は、特に専門的な知見を得ることもなかったが、
・2009年のガス生産量は、米国が世界一だった
・非在来ガスの生産量は、ほぼLNGの生産量と同じ成長量で推移している
・LNG事業は長期契約がないと成立しないプロジェクトであるが、スポット買いの割合が増えている
・今後、価格のインデックスが変わる可能性がある
・天然ガスが安くなれば、GTLの可能性が広がるが、現時点では設備投資の高さがネック
・CNG自動車は、航続距離が短いのでアメリカでは普及しない
会場からは、良い質問がたくさん出た。Climategateの質問もあったけど(笑)。
結局、ガスは発電向けであり、安い石炭や原子力と競合する限り、需要の伸びには限度がある。
価格スキームが変わっていくとして、輸送用燃料への代替弾力性がどれほどなのかということがキーになると感じた。
ただし、この世界はエネルギー効率ではなく、「便利さ」がより重要であるので、安いだけでは変わることはないだろう。
東大 茅陽一先生のコメント
・コペンハーゲン合意では、途上国に2020年まで毎年1000億ドル援助す
ることになっており、これはとんでもないことだ。日本も毎年2兆円程度負担す
ることになるだろう。
2兆円で途上国に環境援助したら、乗数効果で6兆円くらいの経済効果になって
逆にCO2増えてしまうだろう。米中の削減合意が出来なかったことも考えれば、皮肉にもコペンハーゲンは、CO2排出増に加担してしまったことになるのかもしれない。
財政リスクをとってまでして日本国債で新興国の経済発展にお金をだし、二酸化炭素の排出量は増えて、エネルギー価格は上がる。なかなか最悪の合意だと改めて思う。
そして、-25%に向けた行程表の中身が一部報じられた。
真水部分を10%にしてしまうと、麻生政権の目標との違いをアピールしにくいから、15%と言いたいが、それも数字がかぶるから、「6割を真水」という表現にしたということか。
2020年に1000戸の住宅に太陽光パネルを設置とある。福田ビジョンでは2005年比10倍、2009年6月の麻生政権の決断では20倍。これは530戸を想定。鳩山政権ではさらに倍だから40倍といったところか。
3年間で、毎年目標が倍々になって、一気に8倍になったわけだ。クイズダービーじゃないんだし・・・。
昨年の新築戸建ては30%減少して、約80万戸。あと10年で1000戸に導入するには、新築のすべてに取り付けても足りない。現在の導入スピードをすぐにでも10倍くらいにしても厳しいくらい。
批評する価値すらない。実に愚かだ。福山議員はこの内容に本当に考えて納得しているのだろうか。
予感していたとはいえ、検察が小沢不起訴に終り、すっかりテストステロン値が下がり、民主党政権メランコリーから、小沢不起訴の2番底を迎えている。
【参考】
選挙結果に左右されるテストステロン
http://urologist.jp/modules/newdb3/detail.php?id=14
一部、マルサ(東京国税局査察部)も動き出し、所得税法違反容疑での捜査も動いていると聞くが、これだけの巨悪を裁くことのできない日本の司法と日本全体の問題を感じざるをえません。
・コペンハーゲン合意では、途上国に2020年まで毎年1000億ドル援助す
ることになっており、これはとんでもないことだ。日本も毎年2兆円程度負担す
ることになるだろう。
2兆円で途上国に環境援助したら、乗数効果で6兆円くらいの経済効果になって
逆にCO2増えてしまうだろう。米中の削減合意が出来なかったことも考えれば、皮肉にもコペンハーゲンは、CO2排出増に加担してしまったことになるのかもしれない。
財政リスクをとってまでして日本国債で新興国の経済発展にお金をだし、二酸化炭素の排出量は増えて、エネルギー価格は上がる。なかなか最悪の合意だと改めて思う。
そして、-25%に向けた行程表の中身が一部報じられた。
真水部分を10%にしてしまうと、麻生政権の目標との違いをアピールしにくいから、15%と言いたいが、それも数字がかぶるから、「6割を真水」という表現にしたということか。
2020年に1000戸の住宅に太陽光パネルを設置とある。福田ビジョンでは2005年比10倍、2009年6月の麻生政権の決断では20倍。これは530戸を想定。鳩山政権ではさらに倍だから40倍といったところか。
3年間で、毎年目標が倍々になって、一気に8倍になったわけだ。クイズダービーじゃないんだし・・・。
昨年の新築戸建ては30%減少して、約80万戸。あと10年で1000戸に導入するには、新築のすべてに取り付けても足りない。現在の導入スピードをすぐにでも10倍くらいにしても厳しいくらい。
批評する価値すらない。実に愚かだ。福山議員はこの内容に本当に考えて納得しているのだろうか。
予感していたとはいえ、検察が小沢不起訴に終り、すっかりテストステロン値が下がり、民主党政権メランコリーから、小沢不起訴の2番底を迎えている。
【参考】
選挙結果に左右されるテストステロン
http://urologist.jp/modules/newdb3/detail.php?id=14
一部、マルサ(東京国税局査察部)も動き出し、所得税法違反容疑での捜査も動いていると聞くが、これだけの巨悪を裁くことのできない日本の司法と日本全体の問題を感じざるをえません。
いよいよコミュ開設以来のこのトピックも、3年と4ヶ月をもって、ラストの書き込みになろうとしています。
久しぶりに序盤の頃の書き込みを読み返していました。
たびたび、コミュの歴史を振り返っていますが、最近は議論というよりもニュースや話題の紹介がずいぶんと増えましたね。
開設当時は、ピークオイルという概念をいかに多くの人に周知できるか、ということに専念していたわけですが、ある程度人数が増えてきて、またポジティブにもネガティブにも関心のある方と話をするにつれ、単に知らしめることに専念することの意味に疑問を持つようになったような気がします。
米国では、温暖化に関する関心度が雇用問題によって大きく下がったと報じられていましたが、まあ人間そんなもんだし。世の中の真実を暴き、いくら声高に叫んだところで、全体に対する問題意識を共有できるかいなかは、その時その時の状況に強く依存してしまう。
mixiの会員数の増加率が停滞したことも影響していると思いますが、石油価格が上昇トレンドにある時代は、コミュの人数もずっと増加し、下落してからはほとんど増えなくなりました。
CO2排出量も、頑張って減らしても結局経済の停滞の効果には遠く及ばなかった。
そう考えると、草の根の周知活動とは、極めて政治的なものを除き、概して虚しいものです。
ピークオイルという現象ひとつをとっても、極めて人間的、否、動物的な現象であり、経済活動や人間の欲望も、人為的に変えられるようでいて、本質的な部分は変えられるものではない。
社会の問題を考えるとき、人は何が変更可能で、何が変更不可能かを、自身の感覚で見極めた上で、人為的に変更可能性の高い部分(いわゆる物理的に可能な変更)を理想的に変更し(たとえば”教育”の改革とか)、それによってその人が考える理想な社会に近づける、と考えるわけですが。
実際は、往々にして変更不可能な場合がほとんど。そうした思考実験に、はたしてどれだけの意味があるのかと、ふと思ったりしてしまいます。
開設時に強く意識していたことは、こうした問題に拘泥することなく、変えられるものは何かを見極めた上で、自分が最低限守りたいと思えるものを守ろうというものでした。
そして、Eric Shmitの言葉ではないですが、Just do it, if you really, really care about it.ってな感じで、ピークオイルがもたらすであろう社会構造変革に自分自身がとても関心があり、それを通じて世の中と関わり合うということが、自分の人生なのかもな、なんて思ったりしています。
ここ数年は、ピークオイルの情報と言えば、Energy BulletinとThe Oil Drum(とそのコメント)だったわけですが、Energy Bulletinは最近はあまり注目されなくなってきた気がします。The Oil Drumは、依然としてホットではありますが、たまに?というネタもあります。その後、FacebookなどのSNSでも活発な議論が起き始めましたが、最近は、ピークオイルコミュのメンバーに限らず、関連する情報がTwitterやTumblrを通じで行われるようになりました。
これからの情報の中心地はどこをさまよって行くんでしょうね。
久しぶりに序盤の頃の書き込みを読み返していました。
たびたび、コミュの歴史を振り返っていますが、最近は議論というよりもニュースや話題の紹介がずいぶんと増えましたね。
開設当時は、ピークオイルという概念をいかに多くの人に周知できるか、ということに専念していたわけですが、ある程度人数が増えてきて、またポジティブにもネガティブにも関心のある方と話をするにつれ、単に知らしめることに専念することの意味に疑問を持つようになったような気がします。
米国では、温暖化に関する関心度が雇用問題によって大きく下がったと報じられていましたが、まあ人間そんなもんだし。世の中の真実を暴き、いくら声高に叫んだところで、全体に対する問題意識を共有できるかいなかは、その時その時の状況に強く依存してしまう。
mixiの会員数の増加率が停滞したことも影響していると思いますが、石油価格が上昇トレンドにある時代は、コミュの人数もずっと増加し、下落してからはほとんど増えなくなりました。
CO2排出量も、頑張って減らしても結局経済の停滞の効果には遠く及ばなかった。
そう考えると、草の根の周知活動とは、極めて政治的なものを除き、概して虚しいものです。
ピークオイルという現象ひとつをとっても、極めて人間的、否、動物的な現象であり、経済活動や人間の欲望も、人為的に変えられるようでいて、本質的な部分は変えられるものではない。
社会の問題を考えるとき、人は何が変更可能で、何が変更不可能かを、自身の感覚で見極めた上で、人為的に変更可能性の高い部分(いわゆる物理的に可能な変更)を理想的に変更し(たとえば”教育”の改革とか)、それによってその人が考える理想な社会に近づける、と考えるわけですが。
実際は、往々にして変更不可能な場合がほとんど。そうした思考実験に、はたしてどれだけの意味があるのかと、ふと思ったりしてしまいます。
開設時に強く意識していたことは、こうした問題に拘泥することなく、変えられるものは何かを見極めた上で、自分が最低限守りたいと思えるものを守ろうというものでした。
そして、Eric Shmitの言葉ではないですが、Just do it, if you really, really care about it.ってな感じで、ピークオイルがもたらすであろう社会構造変革に自分自身がとても関心があり、それを通じて世の中と関わり合うということが、自分の人生なのかもな、なんて思ったりしています。
ここ数年は、ピークオイルの情報と言えば、Energy BulletinとThe Oil Drum(とそのコメント)だったわけですが、Energy Bulletinは最近はあまり注目されなくなってきた気がします。The Oil Drumは、依然としてホットではありますが、たまに?というネタもあります。その後、FacebookなどのSNSでも活発な議論が起き始めましたが、最近は、ピークオイルコミュのメンバーに限らず、関連する情報がTwitterやTumblrを通じで行われるようになりました。
これからの情報の中心地はどこをさまよって行くんでしょうね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ピークオイル 更新情報
ピークオイルのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75480人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6458人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208290人