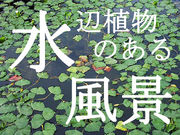流れの中で見つけた 一株移植したら こんな川です
コウホネ 花が咲いた
はじめまして。。
去年、たまたまコウホネを一株見つけてしまいました。
そこは、どぶ川と呼ばれているような川で、誰も
見向きもしないところなのですが、調べてみると、
40年前は川一面コウホネが多い尽くすほどの群生地でした。
奇跡的に生き延びたようです。
川は水深5センチから40センチ。
流れも緩急さまざま。
川底は、砂利底(流れあり)と泥底(流れなし)
このコウホネを株分けし、川に増やそうと
地元の人と考えているのですが、
株分けのよい方法や、流れのある川への植え方が
いまいち自信ありません。
(鉢植え経験者は多いのですが・・・)
どなたかよい方法をご存知でしたら教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
コウホネ 花が咲いた
はじめまして。。
去年、たまたまコウホネを一株見つけてしまいました。
そこは、どぶ川と呼ばれているような川で、誰も
見向きもしないところなのですが、調べてみると、
40年前は川一面コウホネが多い尽くすほどの群生地でした。
奇跡的に生き延びたようです。
川は水深5センチから40センチ。
流れも緩急さまざま。
川底は、砂利底(流れあり)と泥底(流れなし)
このコウホネを株分けし、川に増やそうと
地元の人と考えているのですが、
株分けのよい方法や、流れのある川への植え方が
いまいち自信ありません。
(鉢植え経験者は多いのですが・・・)
どなたかよい方法をご存知でしたら教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
|
|
|
|
コメント(16)
オグラコウホネやヒメコウホネほどではないですが、コウホネもずいぶん減ってきているようですね。
残念ながら、僕にはコウホネ栽培の経験はなく、具体的なアドバイスは出来ません。
ただ、思うのは移植する前にコウホネが減少した理由をしっかりと分析し、取り除く必要があるのではないでしょうか。
そうでなければ宝蔵寺沼のムジナモやガシャモク再生池のガシャモクのように思うような成果が得られないかもしれません。
それがはっきりするまでは、栽培してふやすのがいいと思いますが、一株というのは痛いですね。
生産性はもちろん、栄養繁殖しか増やす手がなさそうですので。
参考になるかどうかはわかりませんが、コウホネについては、こちらの方が詳しいと思います。
ttp://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiga/
個人的に応援してますので、こうすけさん、ぜひコウホネを増やしてください。
残念ながら、僕にはコウホネ栽培の経験はなく、具体的なアドバイスは出来ません。
ただ、思うのは移植する前にコウホネが減少した理由をしっかりと分析し、取り除く必要があるのではないでしょうか。
そうでなければ宝蔵寺沼のムジナモやガシャモク再生池のガシャモクのように思うような成果が得られないかもしれません。
それがはっきりするまでは、栽培してふやすのがいいと思いますが、一株というのは痛いですね。
生産性はもちろん、栄養繁殖しか増やす手がなさそうですので。
参考になるかどうかはわかりませんが、コウホネについては、こちらの方が詳しいと思います。
ttp://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiga/
個人的に応援してますので、こうすけさん、ぜひコウホネを増やしてください。
アドバイス、ありがとうございます。
基本的にこの川は高度経済成長期、生活廃水による水質の悪化で、
いったん死の川となりました。しかし、その後、下水完備により、
水質だけはやや取り戻し、ヘドロもなくなり、いまでは魚もずいぶん戻ってきています。
実はこのコウホネも、長年堆積した土の下に眠っていたもののようです。
各地の川を歩いていると、護岸工事などにより一度はダメになった川が、
自力で再生しく姿をよく見かけます。ただ、人の意識は、「あんな川」
「昔はよかった」そんな声ばかり。
そんな足元の自然に気づかない人たちに、川ってすごいんだぞって知ってほしくて、
コウホネをシンボル的存在にしたいと思ったのです。
僕は魚専門なので、またアドバイスお願いしますね。
基本的にこの川は高度経済成長期、生活廃水による水質の悪化で、
いったん死の川となりました。しかし、その後、下水完備により、
水質だけはやや取り戻し、ヘドロもなくなり、いまでは魚もずいぶん戻ってきています。
実はこのコウホネも、長年堆積した土の下に眠っていたもののようです。
各地の川を歩いていると、護岸工事などにより一度はダメになった川が、
自力で再生しく姿をよく見かけます。ただ、人の意識は、「あんな川」
「昔はよかった」そんな声ばかり。
そんな足元の自然に気づかない人たちに、川ってすごいんだぞって知ってほしくて、
コウホネをシンボル的存在にしたいと思ったのです。
僕は魚専門なので、またアドバイスお願いしますね。
では、大阪自然史博物館さんの解答を転載する前に私の出した質問の要点を書き込みます。
こうすけさんの質問は、
1.株へのダメージを最小限にするとり方
2.元の大きさになるのに何年くらいかかるか。
でしたが、両方とも実物を見ていない学芸員さんには、明確な答えを出せないだろうと考えましたので、以下のように変更しました。
1.栽培にあたってどのくらいの根茎を取る必要があるか?
※これがわかれば、残すべき量も、予想できると思います。
2.1年にどの程度成長するか
※これがわかれば、こうすけさんの2の疑問の答えも予想できると考えました。
加えて
3.栽培についてのアドバイス
4.移植についての「アドバイス
をお願いしました。
次に書く、大阪自然史博物館さんの答えが、こうすけさんの質問の意図から、ずれていると感じるかもしれませんが、だとしたらそれは私の責任であり、学芸員さんはこちらの質問へ、的確な答えを出してくれているということを書いておきます。
こうすけさんの質問は、
1.株へのダメージを最小限にするとり方
2.元の大きさになるのに何年くらいかかるか。
でしたが、両方とも実物を見ていない学芸員さんには、明確な答えを出せないだろうと考えましたので、以下のように変更しました。
1.栽培にあたってどのくらいの根茎を取る必要があるか?
※これがわかれば、残すべき量も、予想できると思います。
2.1年にどの程度成長するか
※これがわかれば、こうすけさんの2の疑問の答えも予想できると考えました。
加えて
3.栽培についてのアドバイス
4.移植についての「アドバイス
をお願いしました。
次に書く、大阪自然史博物館さんの答えが、こうすけさんの質問の意図から、ずれていると感じるかもしれませんが、だとしたらそれは私の責任であり、学芸員さんはこちらの質問へ、的確な答えを出してくれているということを書いておきます。
大阪自然史博物館の学芸員の志賀さんの回答を引用します。
(以下全文引用です。)
以下、幾つかに分けてお答えします。少し長いですがご容赦下
さい。
【どのくらいの根茎が必要か】
コウホネの仲間は根茎を地下に縦横に走らせて、分枝して下部
が増えます。まず、野生地から株を採集してきて、ちゃんと根付
かせるには根茎が20-30cm程度あれば十分でしょう。10cm程度でも
根付きますが、葉など株全体が極端に矮小化します。コウホネ属
のサイズや根茎の分枝までの期間は根茎のサイズに依存していま
す。
【1年にどの程度成長するか】
おおよそ河川などの流水環境や礫があって成長が難しい場所で
はだいたい10-20cm程度。ため池や湖沼などでは30-50cm程度根茎
が伸長します。ちなみに分枝は成長量に依存しますが1-2年に1回
程度します。
【栽培について】
育成については、大きなコンテナが必要です。土は赤玉に鹿沼
土、肥料を混ぜるとよく育ちます。3年に1回は植え替えをしてや
るとよいでしょう。
【移植について】
移植については、生育地の管理者から許可を得ることを前提で
す。まず、非常に難しいことがわかっていて、多くの産地では失
敗しています。根茎から根が伸びて土にしっかり根付く前に、流
されてしまったりするためです。移植する場所は慎重に選ぶ必要
があるでしょう。
【植生の保全、復元の仕方について】
最後に保全についてです。取ってきた株を増やして、川に戻し
てもそれは遺伝的に1個体です。これでは、元に戻ったとは言え
ません。もともと40年前にあった時は、たくさんの個体で構成さ
れてたと考えられるからです。
根茎からの増殖と並行して、その集団(他の集団から取ってく
るのはNGです)から種子を取ってきて、発芽させて新しい株を育
てるのをお勧めします。
(以下全文引用です。)
以下、幾つかに分けてお答えします。少し長いですがご容赦下
さい。
【どのくらいの根茎が必要か】
コウホネの仲間は根茎を地下に縦横に走らせて、分枝して下部
が増えます。まず、野生地から株を採集してきて、ちゃんと根付
かせるには根茎が20-30cm程度あれば十分でしょう。10cm程度でも
根付きますが、葉など株全体が極端に矮小化します。コウホネ属
のサイズや根茎の分枝までの期間は根茎のサイズに依存していま
す。
【1年にどの程度成長するか】
おおよそ河川などの流水環境や礫があって成長が難しい場所で
はだいたい10-20cm程度。ため池や湖沼などでは30-50cm程度根茎
が伸長します。ちなみに分枝は成長量に依存しますが1-2年に1回
程度します。
【栽培について】
育成については、大きなコンテナが必要です。土は赤玉に鹿沼
土、肥料を混ぜるとよく育ちます。3年に1回は植え替えをしてや
るとよいでしょう。
【移植について】
移植については、生育地の管理者から許可を得ることを前提で
す。まず、非常に難しいことがわかっていて、多くの産地では失
敗しています。根茎から根が伸びて土にしっかり根付く前に、流
されてしまったりするためです。移植する場所は慎重に選ぶ必要
があるでしょう。
【植生の保全、復元の仕方について】
最後に保全についてです。取ってきた株を増やして、川に戻し
てもそれは遺伝的に1個体です。これでは、元に戻ったとは言え
ません。もともと40年前にあった時は、たくさんの個体で構成さ
れてたと考えられるからです。
根茎からの増殖と並行して、その集団(他の集団から取ってく
るのはNGです)から種子を取ってきて、発芽させて新しい株を育
てるのをお勧めします。
僭越ながら、蛇足かもしれませんが、少し補足させていただきます。
>【栽培について】
用土ですが、鹿沼土は比重が軽く、水に浮きやすいのでやや使いにくい側面があります。
ですので単用事は避け、志賀さんのお薦めどおり、赤玉に混ぜる形が良いかと思います(私は鹿沼を使ったことがありませんが)。
また、肥料は、睡蓮鉢で栽培されている方ですと、マグァンプKや発酵油粕(発酵でないとダメ)を使っている人が多いようです。
私は発酵油粕を使ってます。
>【植生の保全、復元の仕方について】
メダカなどでもそうなので、釈迦に説法とは思いますが、特定地域の種の保存は、同じ集団内での遺伝子の同一性と多様性の両立が必要です。
やはり栄養繁殖での保全は厳しいものがあるようです。
私も志賀さん同様、栄養繁殖とともに種子繁殖の可能性を模索したほうが、いいと思います。
40年間失われていたものです。
結果を急がず、長いスパンで見たほうがいいのではないでしょうか。
こうすけさんが、急がずとも周りが結果を早く出したいと思うことは、往々にしてあります。
>【栽培について】
用土ですが、鹿沼土は比重が軽く、水に浮きやすいのでやや使いにくい側面があります。
ですので単用事は避け、志賀さんのお薦めどおり、赤玉に混ぜる形が良いかと思います(私は鹿沼を使ったことがありませんが)。
また、肥料は、睡蓮鉢で栽培されている方ですと、マグァンプKや発酵油粕(発酵でないとダメ)を使っている人が多いようです。
私は発酵油粕を使ってます。
>【植生の保全、復元の仕方について】
メダカなどでもそうなので、釈迦に説法とは思いますが、特定地域の種の保存は、同じ集団内での遺伝子の同一性と多様性の両立が必要です。
やはり栄養繁殖での保全は厳しいものがあるようです。
私も志賀さん同様、栄養繁殖とともに種子繁殖の可能性を模索したほうが、いいと思います。
40年間失われていたものです。
結果を急がず、長いスパンで見たほうがいいのではないでしょうか。
こうすけさんが、急がずとも周りが結果を早く出したいと思うことは、往々にしてあります。
>>D★さん
アサザは遺伝子的にはかなりやばいらしいですね。
ほとんどの生息地は、栄養繁殖のみで、1〜2種のクローンで構成されているとか。
そもそも、アサザの種ってわがままなんですよね。
水生植物の癖に水中でも土中でも発芽せず、波打ち際でもダメ。
つまり、光のあたる地表で、水の来ないところってことで、春に水位が著しく下がる場所でないと、実生は定着しないようです。
>>こうすけさん
僕は大したことしてないので、お礼は大阪自然史博物館さんに言うのが適当かと思います。
コウホネの実は白っぽい横から見ると涙滴型の袋に入った状態で水面に浮かび、流れに乗って散布されます。
流れ着いた土の上で発芽となるので、想像ですが水はヒタヒタかまたは湿っているくらいがいいかもしれません。
子孫繁栄の戦略は、うちで保護観察中のアギナシと似てますね。
アサザは遺伝子的にはかなりやばいらしいですね。
ほとんどの生息地は、栄養繁殖のみで、1〜2種のクローンで構成されているとか。
そもそも、アサザの種ってわがままなんですよね。
水生植物の癖に水中でも土中でも発芽せず、波打ち際でもダメ。
つまり、光のあたる地表で、水の来ないところってことで、春に水位が著しく下がる場所でないと、実生は定着しないようです。
>>こうすけさん
僕は大したことしてないので、お礼は大阪自然史博物館さんに言うのが適当かと思います。
コウホネの実は白っぽい横から見ると涙滴型の袋に入った状態で水面に浮かび、流れに乗って散布されます。
流れ着いた土の上で発芽となるので、想像ですが水はヒタヒタかまたは湿っているくらいがいいかもしれません。
子孫繁栄の戦略は、うちで保護観察中のアギナシと似てますね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
水辺植物のある風景★ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
水辺植物のある風景★のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37839人
- 2位
- 酒好き
- 170669人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89536人