初めまして。
行動経済学に興味を持ち独学で学んでるボブといいます。
ちょっと疑問に思ったことがあったんでトピックを立てさせて頂きました。
もし、解明されている内容でしたらすみませんm(__)m
疑問に思ったことは『損失回避性は先天的か後天的か』です。
自分の考えを先に述べさせて頂くと、損失回避性は後天的なものだと思います。
人がある種の後悔した経験が強い記憶として残り、こういった傾向が起こるのではと考えています。
けれど、同じぐらいの効用というか絶対値が同じぐらいの喜んだ経験をしていて、後悔した記憶の方が強い記憶として残ったとしたら先天的ということになってしまいますよね?
皆さんの意見を是非ともお聞かせ下さい。
行動経済学に興味を持ち独学で学んでるボブといいます。
ちょっと疑問に思ったことがあったんでトピックを立てさせて頂きました。
もし、解明されている内容でしたらすみませんm(__)m
疑問に思ったことは『損失回避性は先天的か後天的か』です。
自分の考えを先に述べさせて頂くと、損失回避性は後天的なものだと思います。
人がある種の後悔した経験が強い記憶として残り、こういった傾向が起こるのではと考えています。
けれど、同じぐらいの効用というか絶対値が同じぐらいの喜んだ経験をしていて、後悔した記憶の方が強い記憶として残ったとしたら先天的ということになってしまいますよね?
皆さんの意見を是非ともお聞かせ下さい。
|
|
|
|
コメント(3)
私は"たろぬこ"さんの意見、「両方が補完的に機能している」に賛成ですが、shorebirdさんのブログ<http://d.hatena.ne.jp/shorebird/>で知りました「リスク知性」に関する本を紹介します。
Risk Intelligence: How to Live with Uncertainty. 作者: Dylan Evans 出版社/メーカー: Free Press 発売日: 2012/04/17
これは、進化心理学からみた「感情」の本を書いたりしている、ディラン・エヴァンズによるヒトのリスク認知に関する本です。この中で、彼は、ヒトは不確実なことを扱うのを好まないし、またヒトは確率的に物事を考えるのがいやがるのは何故だろうかと考え、それ故なぜリスク知性(エヴァンズによるその定義は「確率を正確に見積もることのできる能力」)が問題になるのか(専門家だからといってリスク知性が高いわけではない)について問い、、その背後のインセンティブ構造にも大きな要因の問題があるように考えています。ヒトの認知には様々なバイアスがあることが知られているが--具体的には以下のようなバイアスがある:利用可能性バイアス、自分が望むことは起きやすいと考えるバイアス、証拠の強さと証拠の信頼性の混同、確証バイアス(まず結論に飛びつき、その後はそれを支持する証拠だけ探すバイアス)、後知恵バイアス(一旦信念を形成した後、それ以前から一貫してそう考えていたと信じてしまう傾向)、読心幻想(自分はヒトの嘘が見抜けると信じる傾向)--、これが確率の見積もりをそれぞれ阻害する。また、より速く反応した方がスマートに見えるので深く考える前に反応する傾向や、周りの大勢にはとりあえず従っておくという群集心理も証拠を見定めて不確実性を評価する妨げとなる。これらの認知バイアスにはカーネマンとトヴァルスキーが指摘したヒューリスティックス由来のバイアスも含まれているし、自己欺瞞傾向から生じたバイアスのように思われるものもある。さらに制度要因という点からも、リスク知性への至近要因を指摘している。--以上、shorebirdさんの書評「Risk Intelligence」<http://d.hatena.ne.jp/shorebird/20130901>及び「Risk Intelligence その1〜その20<完>」<http://d.hatena.ne.jp/shorebird/searchdiary?word=Risk+Intelligence&.submit=%B8%A1%BA%F7&type=detail>を参考にしました。
また、リスク知性をどう測るのかについて、エヴァンズとジャコバスにより開発された手法--RQテストページhttp://www.projectionpoint.comにおいて無料で測定することが可能--が紹介されています。そのリスク知性の測定リサーチによって得られた重要な知見として、彼はリスク知性は一般知性IQと相関しない独立の認知特性らしいこと、そしてそれはトレーニングによって上昇させることができることをあげています。
彼は、ラカニアン精神分析のトレーニングを受けて1995年頃精神分析医になりましたが、それを実践を通じて考えるうちに、ラカニアン精神分析は実証的ではないのではないかとの懐疑を抱き、精神分析医を辞めました。(これに関しては、ディラン・エヴァンズ著『ラカンは間違っている―精神分析から進化論へ』学樹書院 2010/03/01がある。) その後、LSEの哲学のドクターコースに入り直し、ヘレナ・クローニンの影響を受けて進化心理学を学び、2000年に哲学の博士号を取って感情の研究を行います。(翻訳されたものとして、ディラン・エヴァンズス著『感情 (〈1冊でわかる〉シリーズ) 』岩波書店 2005/12/22がある。) 2008年からは意思決定理論やリスクマネジメントをリサーチしはじめます。そして、リスクインテリジェンスをリサーチし、企業や個人相手にリスクインテリジェンスにかかるアドバイスやトレーニングを行うビジネスを立ち上げたりもしています。
なを、先天的というか進化論的に獲得したリスク回避性質に関しては、昆虫の捕食回避戦略を中心に書かれた一版向けの啓蒙書である、ギルバート・ウォルドバウアー著『食べられないために―― 逃げる虫、だます虫、戦う虫』みすず書房 2013/07/24 という本もあります。
Risk Intelligence: How to Live with Uncertainty. 作者: Dylan Evans 出版社/メーカー: Free Press 発売日: 2012/04/17
これは、進化心理学からみた「感情」の本を書いたりしている、ディラン・エヴァンズによるヒトのリスク認知に関する本です。この中で、彼は、ヒトは不確実なことを扱うのを好まないし、またヒトは確率的に物事を考えるのがいやがるのは何故だろうかと考え、それ故なぜリスク知性(エヴァンズによるその定義は「確率を正確に見積もることのできる能力」)が問題になるのか(専門家だからといってリスク知性が高いわけではない)について問い、、その背後のインセンティブ構造にも大きな要因の問題があるように考えています。ヒトの認知には様々なバイアスがあることが知られているが--具体的には以下のようなバイアスがある:利用可能性バイアス、自分が望むことは起きやすいと考えるバイアス、証拠の強さと証拠の信頼性の混同、確証バイアス(まず結論に飛びつき、その後はそれを支持する証拠だけ探すバイアス)、後知恵バイアス(一旦信念を形成した後、それ以前から一貫してそう考えていたと信じてしまう傾向)、読心幻想(自分はヒトの嘘が見抜けると信じる傾向)--、これが確率の見積もりをそれぞれ阻害する。また、より速く反応した方がスマートに見えるので深く考える前に反応する傾向や、周りの大勢にはとりあえず従っておくという群集心理も証拠を見定めて不確実性を評価する妨げとなる。これらの認知バイアスにはカーネマンとトヴァルスキーが指摘したヒューリスティックス由来のバイアスも含まれているし、自己欺瞞傾向から生じたバイアスのように思われるものもある。さらに制度要因という点からも、リスク知性への至近要因を指摘している。--以上、shorebirdさんの書評「Risk Intelligence」<http://d.hatena.ne.jp/shorebird/20130901>及び「Risk Intelligence その1〜その20<完>」<http://d.hatena.ne.jp/shorebird/searchdiary?word=Risk+Intelligence&.submit=%B8%A1%BA%F7&type=detail>を参考にしました。
また、リスク知性をどう測るのかについて、エヴァンズとジャコバスにより開発された手法--RQテストページhttp://www.projectionpoint.comにおいて無料で測定することが可能--が紹介されています。そのリスク知性の測定リサーチによって得られた重要な知見として、彼はリスク知性は一般知性IQと相関しない独立の認知特性らしいこと、そしてそれはトレーニングによって上昇させることができることをあげています。
彼は、ラカニアン精神分析のトレーニングを受けて1995年頃精神分析医になりましたが、それを実践を通じて考えるうちに、ラカニアン精神分析は実証的ではないのではないかとの懐疑を抱き、精神分析医を辞めました。(これに関しては、ディラン・エヴァンズ著『ラカンは間違っている―精神分析から進化論へ』学樹書院 2010/03/01がある。) その後、LSEの哲学のドクターコースに入り直し、ヘレナ・クローニンの影響を受けて進化心理学を学び、2000年に哲学の博士号を取って感情の研究を行います。(翻訳されたものとして、ディラン・エヴァンズス著『感情 (〈1冊でわかる〉シリーズ) 』岩波書店 2005/12/22がある。) 2008年からは意思決定理論やリスクマネジメントをリサーチしはじめます。そして、リスクインテリジェンスをリサーチし、企業や個人相手にリスクインテリジェンスにかかるアドバイスやトレーニングを行うビジネスを立ち上げたりもしています。
なを、先天的というか進化論的に獲得したリスク回避性質に関しては、昆虫の捕食回避戦略を中心に書かれた一版向けの啓蒙書である、ギルバート・ウォルドバウアー著『食べられないために―― 逃げる虫、だます虫、戦う虫』みすず書房 2013/07/24 という本もあります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
行動経済学 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
行動経済学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77419人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209453人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19956人
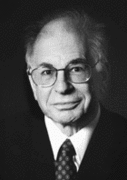

















![[NHK]100分de名著](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/22/92/6082292_141s.jpg)





