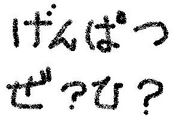|
|
|
|
コメント(15)
結構初心的な質問だと思いますが、
好意に甘えこちらで質問させてください。
Puが入ると制御棒の効きが悪いのはなぜですか?
ATOMICAによると、
プルトニウムの核特性の主な特徴は以下のとおりである。
1)プルトニウムの熱中性子の吸収断面積がウランより大きい。これにより熱中性子束が小さくなる。
2)核分裂性プルトニウム(Pu−239、Pu−241)の熱中性子核分裂断面積がU−235より大きい。
3)プルトニウムによる中性子の共鳴吸収がウランより大きい。特にPu−240が熱中性子領域に近いところで大きな吸収断面積を持つ。
4)プルトニウムの遅発中性子割合がウランよりも小さい。
a.制御棒の中性子吸収効果が相対的に低下する。[ 1)、 2)により]
b.ボイド反応度係数がより負となる。[ 1)、 2)、 3)により]
c.ドップラ反応度係数がより負となる。[ 1)、 2)、 3)により]
d.即発中性子寿命が短くなる。[ 1)により]
e.反応度投入時の出力上昇が早く、かつ、大きくなる。[ 4)により]
1)〜3)、a.〜cとeまでは理解できます。(感覚的に)
4)は未確認、d.が理解できませんが。
一般的に、制御棒の効きが悪くなる理由として、
1)の理由が挙げられています。
でも、熱中性子束がへったら、核分裂の量が減っていい気がするし・・・
あ、吸収断面積がでかいってことは制御棒に吸収される前に
Puが中性子をくっちゃって、核分裂しちゃうってことでしょうか?
でも、Puの方が1核分裂あたりの発熱量が多いから、
Uよりもドップラーが利きやすいような気がするし・・・
熱中性子の核分裂が増えてもνもηも小さいから
中性子がそんなに増しないような気もするし、
総合的になんだか良いような気がする・・・
と、いったもやもやした感じなんです。
質問も明確じゃなくて申し訳ないのですが、
どなたか、すっきり説明していただけるとうれしいです。
好意に甘えこちらで質問させてください。
Puが入ると制御棒の効きが悪いのはなぜですか?
ATOMICAによると、
プルトニウムの核特性の主な特徴は以下のとおりである。
1)プルトニウムの熱中性子の吸収断面積がウランより大きい。これにより熱中性子束が小さくなる。
2)核分裂性プルトニウム(Pu−239、Pu−241)の熱中性子核分裂断面積がU−235より大きい。
3)プルトニウムによる中性子の共鳴吸収がウランより大きい。特にPu−240が熱中性子領域に近いところで大きな吸収断面積を持つ。
4)プルトニウムの遅発中性子割合がウランよりも小さい。
a.制御棒の中性子吸収効果が相対的に低下する。[ 1)、 2)により]
b.ボイド反応度係数がより負となる。[ 1)、 2)、 3)により]
c.ドップラ反応度係数がより負となる。[ 1)、 2)、 3)により]
d.即発中性子寿命が短くなる。[ 1)により]
e.反応度投入時の出力上昇が早く、かつ、大きくなる。[ 4)により]
1)〜3)、a.〜cとeまでは理解できます。(感覚的に)
4)は未確認、d.が理解できませんが。
一般的に、制御棒の効きが悪くなる理由として、
1)の理由が挙げられています。
でも、熱中性子束がへったら、核分裂の量が減っていい気がするし・・・
あ、吸収断面積がでかいってことは制御棒に吸収される前に
Puが中性子をくっちゃって、核分裂しちゃうってことでしょうか?
でも、Puの方が1核分裂あたりの発熱量が多いから、
Uよりもドップラーが利きやすいような気がするし・・・
熱中性子の核分裂が増えてもνもηも小さいから
中性子がそんなに増しないような気もするし、
総合的になんだか良いような気がする・・・
と、いったもやもやした感じなんです。
質問も明確じゃなくて申し訳ないのですが、
どなたか、すっきり説明していただけるとうれしいです。
上級者ではないですが、口をはさみます!
炉心に熱中性子の吸収断面積が大きいPuが多いと、即発中性子から熱中性子へ遷移した後に吸収確率が高いから、寿命が短いと言ってるのではないですか?
あと、”制御棒の効きが悪くなる”という言葉がやっぱり引っかかるのですが、燃料棒の設計の際に稼動後ある程度まで行くとPuが増えて熱中性子断面積が増えてしまうとか考慮されているものなのでしょうか?やっぱりしてるんでしょうね。
でも、制御棒の周りの燃料棒だけは、U富化率をあげてやっているんでしょうか。
実際のLWRの稼働中の制御は殆どケミカルシムを使用しているし、制御棒を使うのは起動、停止、負荷変動の大きい時や、スクラム時ですよね。
別話ですが、
熱中性子領域を1K-10KeVという範囲に限定すれば、
ηはU233が一番大きいんですね。
Pu239とU235だけの比較にすれば、1eV以下だとU235の方がηが大きいんですね。
そんな所の中性子の話題は出ないにせよ。
いろいろ勉強になります、有難うございます。
炉心に熱中性子の吸収断面積が大きいPuが多いと、即発中性子から熱中性子へ遷移した後に吸収確率が高いから、寿命が短いと言ってるのではないですか?
あと、”制御棒の効きが悪くなる”という言葉がやっぱり引っかかるのですが、燃料棒の設計の際に稼動後ある程度まで行くとPuが増えて熱中性子断面積が増えてしまうとか考慮されているものなのでしょうか?やっぱりしてるんでしょうね。
でも、制御棒の周りの燃料棒だけは、U富化率をあげてやっているんでしょうか。
実際のLWRの稼働中の制御は殆どケミカルシムを使用しているし、制御棒を使うのは起動、停止、負荷変動の大きい時や、スクラム時ですよね。
別話ですが、
熱中性子領域を1K-10KeVという範囲に限定すれば、
ηはU233が一番大きいんですね。
Pu239とU235だけの比較にすれば、1eV以下だとU235の方がηが大きいんですね。
そんな所の中性子の話題は出ないにせよ。
いろいろ勉強になります、有難うございます。
吸収断面積(σa)=核分裂断面積(σf)+捕獲断面積(σc)
ですよね?
どれをみても吸収断面積とかいてあるので、
どちらか(σf、σc)に言及していないので、
なんらかの意味や意図があるのかな?と考えたりします。
ドップラー効果は共鳴吸収領域でしたね・・・
あ、共鳴吸収領域は熱領域より高いので即発中性子寿命が減るんですかね?
U233は熱領域の核分裂断面積が高いんですよね?
だからηが大きくなるんじゃないかと・・・
η=ν*σf/σa
教科書では、熱中性子に対するσが下記のようにありました。
U-235 Pu-235 U-233
σf 577 741 515
σa 678 1015 573
これをみるとPuの捕獲断面積が多いってことですよね・・・
じゃぁ、より熱中性子が減るってことは良いことのような・・・
ケミカルシムって良くわかってないですけど、
PWRの冷却中のボロンのことですよね??
確かにBWRも通常運転時は制御棒よりもボイドで出力調整していると聞くので、
MOX燃料の場合ボイド係数も負になるのであれば、なんかいいような・・・。
ですよね?
どれをみても吸収断面積とかいてあるので、
どちらか(σf、σc)に言及していないので、
なんらかの意味や意図があるのかな?と考えたりします。
ドップラー効果は共鳴吸収領域でしたね・・・
あ、共鳴吸収領域は熱領域より高いので即発中性子寿命が減るんですかね?
U233は熱領域の核分裂断面積が高いんですよね?
だからηが大きくなるんじゃないかと・・・
η=ν*σf/σa
教科書では、熱中性子に対するσが下記のようにありました。
U-235 Pu-235 U-233
σf 577 741 515
σa 678 1015 573
これをみるとPuの捕獲断面積が多いってことですよね・・・
じゃぁ、より熱中性子が減るってことは良いことのような・・・
ケミカルシムって良くわかってないですけど、
PWRの冷却中のボロンのことですよね??
確かにBWRも通常運転時は制御棒よりもボイドで出力調整していると聞くので、
MOX燃料の場合ボイド係数も負になるのであれば、なんかいいような・・・。
>吸収断面積(σa)=核分裂断面積(σf)+捕獲断面積(σc)
>U233は熱領域の核分裂断面積が高いんですよね?
>だからηが大きくなるんじゃないかと・・・
>η=ν*σf/σa
式で示されるとすっきりです。有難うございます。<ゆさん
>ケミカルシムって良くわかってないですけど、
>PWRの冷却中のボロンのことですよね??
>確かにBWRも通常運転時は制御棒よりもボイドで出力調整していると聞くので、
その通りです!冷却材中のボロン濃度です。
PWR稼働中に、U235減少に伴って、ボロン濃度低下でfission数を維持。
だから、初回起動中などは、ボロン濃度が高いんですよね。
Pだとケミカルシムで炉出力制御するのが支配的でしたよね。
BWRだと再循環流量でボイド発生度調整で、炉出力制御でしたよね。
ふむふむ。勉強になります。
>燃料設計の際には稼働後燃料取り出しまでの核特性の変化を予測しています。
>更に、燃料配置も考慮して可能な限り平均的に燃えるようにPu冨化率も考慮しています。
そうですか!有難うございます。
燃料配置調整で、炉燃焼度を出来る限り平滑化してあげてるんですよね。
>PWRでもBWRでも燃料のボイド係数は負の値になるように炉心設計が義務づけら>れています。
燃料のボイド係数というよりも、温度が上がればボイドが出るって理解してしまっているんですが、燃料自体にもボイド係数を考慮しているんですか?
ボイドがあると、中性子が熱中性子化されにくくなるから、核分裂が起こりにくくなって、反応度が低くなるんでしたよね。
ふむふむ、朝から勉強になります。有難うございました。
>U233は熱領域の核分裂断面積が高いんですよね?
>だからηが大きくなるんじゃないかと・・・
>η=ν*σf/σa
式で示されるとすっきりです。有難うございます。<ゆさん
>ケミカルシムって良くわかってないですけど、
>PWRの冷却中のボロンのことですよね??
>確かにBWRも通常運転時は制御棒よりもボイドで出力調整していると聞くので、
その通りです!冷却材中のボロン濃度です。
PWR稼働中に、U235減少に伴って、ボロン濃度低下でfission数を維持。
だから、初回起動中などは、ボロン濃度が高いんですよね。
Pだとケミカルシムで炉出力制御するのが支配的でしたよね。
BWRだと再循環流量でボイド発生度調整で、炉出力制御でしたよね。
ふむふむ。勉強になります。
>燃料設計の際には稼働後燃料取り出しまでの核特性の変化を予測しています。
>更に、燃料配置も考慮して可能な限り平均的に燃えるようにPu冨化率も考慮しています。
そうですか!有難うございます。
燃料配置調整で、炉燃焼度を出来る限り平滑化してあげてるんですよね。
>PWRでもBWRでも燃料のボイド係数は負の値になるように炉心設計が義務づけら>れています。
燃料のボイド係数というよりも、温度が上がればボイドが出るって理解してしまっているんですが、燃料自体にもボイド係数を考慮しているんですか?
ボイドがあると、中性子が熱中性子化されにくくなるから、核分裂が起こりにくくなって、反応度が低くなるんでしたよね。
ふむふむ、朝から勉強になります。有難うございました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
是か?否か?原子力発電 更新情報
-
最新のアンケート
是か?否か?原子力発電のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- マイミク募集はここで。
- 89583人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208275人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90041人