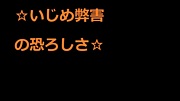犯罪犯した者勝ち
殺した者勝ち
騙したもの勝ち
虐めたもの勝ち
の世の中にしてはならない。
そういった、個人の尊重を無視した犯罪を軽んじてはならない。
と思います。
日本国憲法第13条とは、日本国憲法の第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
http://
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第3章は「国民の権利と義務」について定めた条文であるが、更に三分することができる。
第10条から第12条までが人権に関する総則規定、第13条から第30条までは各種の権利・義務に関する個別・総括規定、第31条から第40条までは刑事訴訟に関する規定となる。
この第13条は、以後第30条まで続く各種の権利・義務規定を包括する条文であり、「基本的人権の尊重」を三大原則の一つとして定める憲法の根幹といえる存在である。
また他の大原則、具体的には第9条が定める「平和主義」、第1条が定める「国民主権」も大元はこの「個人の尊重」、「生命・自由・幸福追求権の尊重」を達成するために存在すると見做されているため、
第13条は日本国憲法で最も重要な条文といわれることがある。
第14条〜第30条に規定されず、憲法制定後の社会変遷の中で「新しい人権」として保護されるべきだとされるようになったことについては、この第13条を根拠に認められることがある(日本国憲法が制定以来、一度も改正されていないため)。また「幸福追求権」もこの条文を根拠に保護されている。
殺した者勝ち
騙したもの勝ち
虐めたもの勝ち
の世の中にしてはならない。
そういった、個人の尊重を無視した犯罪を軽んじてはならない。
と思います。
日本国憲法第13条とは、日本国憲法の第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
http://
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第3章は「国民の権利と義務」について定めた条文であるが、更に三分することができる。
第10条から第12条までが人権に関する総則規定、第13条から第30条までは各種の権利・義務に関する個別・総括規定、第31条から第40条までは刑事訴訟に関する規定となる。
この第13条は、以後第30条まで続く各種の権利・義務規定を包括する条文であり、「基本的人権の尊重」を三大原則の一つとして定める憲法の根幹といえる存在である。
また他の大原則、具体的には第9条が定める「平和主義」、第1条が定める「国民主権」も大元はこの「個人の尊重」、「生命・自由・幸福追求権の尊重」を達成するために存在すると見做されているため、
第13条は日本国憲法で最も重要な条文といわれることがある。
第14条〜第30条に規定されず、憲法制定後の社会変遷の中で「新しい人権」として保護されるべきだとされるようになったことについては、この第13条を根拠に認められることがある(日本国憲法が制定以来、一度も改正されていないため)。また「幸福追求権」もこの条文を根拠に保護されている。
|
|
|
|
コメント(2)
http://www.mirukenpou.net/kenpou_kyouiku/backnumber/100517.html
「すべて国民は、個人として尊重される」。憲法13条にうたわれたこの「個人の尊重」ということこそが、憲法のいちばん基底にある原理である。憲法の基本原理が人権尊重、国民主権、平和主義であるということは、いまや、中学生や高校生にも常識となっているであろう。では、なぜ、人権尊重であり、国民主権であり、平和主義なのであろうか。その答えがこの「個人の尊重」なのである。すなわち、一人ひとりをかけがえのない個人として尊重しなければならないからこそ、一人ひとりの自由・人権を守らなければならない(人権尊重)。一人ひとりの個人の政治に対する考え方も、それぞれ等しく同じ価値あるものとして政治に反映されなければならない(国民主権)。そして、一人ひとりを個人として尊重するということは、なによりも、人間を「数」としてしかとらえない軍隊や戦争とは相容れないし、誰もが「平和」な生活を送れるということが大前提として必要である(平和主義)。つまり、憲法の三大原理といわれている人権尊重、国民主権、平和主義は、いずれも、「個人の尊重」という同じ根っこから派生しているものなのである。
「個人の尊重」とは、一人ひとりの人間を自立した人格的存在として尊重するということであり、一人ひとりがそれぞれに固有の価値をもっているという認識を前提に、それぞれの人がもっている価値を等しく尊重しようというものである。平たくいえば、一人ひとりの人間を大事にする、ということである。それは、一人ひとりが「違う」存在であるということを認め合い、その「違い」をそれぞれに尊重するということでもある。日本では、しばしば、「平等」ということを、「みな同じ」という意味合いで語ることが多いが、「平等」とは、本来、「人はみな同じだから平等でなければならない」のではなく、「人はみなそれぞれに違うからこそ平等でなければならない」というものとしてとらえられるべきものである。つまり、一人ひとりの人間は、みな、それぞれに違うのであり、一人ひとりが他者とは違った価値をもっている、だから、それぞれの人がもっているそれぞれに異なった価値を等しく尊重しよう、というのが「個人の尊重」原理のうえにたった「平等」の考え方なのである。
学校は集団生活の場である。そのため、ややもすれば、自分を抑えてでも周りと同調することが良いことだとされがちであるが、それは「個人の尊重」に反する。集団生活には、一定のルールは当然必要である。しかし、それは、集団のために必要なのではない。お互いを個人として尊重するということから、一定のルールが必要とされるわけである。「学校のためなんだから、クラスのためなんだから、みんなのためなんだから、我慢すべきだ」というのでなく、自分自身も他者も一個の人格的存在として尊重するという観点から自分の好き勝手にはできない場合もある、ということを生徒が理解できれば、集団生活のルールをつうじて「個人の尊重」ということの意味を実感できるのではないだろうか。
「個人の尊重」は、「個人主義」の社会を前提としている。「個人主義」は、これも日本では誤解されやすいが、「利己主義」ではない。「個人主義」の社会とは、「自立した個人」を構成単位とする社会のことで、そこでは、当然、他者もまた「自立した個人」として存在することが自明の前提となっているから、自分のことだけで他人のことは考えない「利己主義」は通用しない。西欧においては、封建社会が崩壊していく過程のなかで、自然発生的に「自立した個人」が生まれ、そういう「個人」が主体となって近代社会を形成してきたという歴史があるが、日本の場合には、「個人」が成熟することなく「上からの近代化」が推し進められ、「個人主義」の社会になりきらないままに、こんにちまできている。したがって、「個人主義」社会を前提とする「個人の尊重」原理も、なかなか理解されにくい面があることは否定できない。しかし、人権、平和、国民主権という価値を是とする以上は、その共通の根っこともいうべき「個人の尊重」原理の理解を深めることは必要不可欠だといえよう。次代を担う中学生・高校生に「個人の尊重」ということの意味を正しく伝えることが、憲法教育の重要な意義だと考える。
「すべて国民は、個人として尊重される」。憲法13条にうたわれたこの「個人の尊重」ということこそが、憲法のいちばん基底にある原理である。憲法の基本原理が人権尊重、国民主権、平和主義であるということは、いまや、中学生や高校生にも常識となっているであろう。では、なぜ、人権尊重であり、国民主権であり、平和主義なのであろうか。その答えがこの「個人の尊重」なのである。すなわち、一人ひとりをかけがえのない個人として尊重しなければならないからこそ、一人ひとりの自由・人権を守らなければならない(人権尊重)。一人ひとりの個人の政治に対する考え方も、それぞれ等しく同じ価値あるものとして政治に反映されなければならない(国民主権)。そして、一人ひとりを個人として尊重するということは、なによりも、人間を「数」としてしかとらえない軍隊や戦争とは相容れないし、誰もが「平和」な生活を送れるということが大前提として必要である(平和主義)。つまり、憲法の三大原理といわれている人権尊重、国民主権、平和主義は、いずれも、「個人の尊重」という同じ根っこから派生しているものなのである。
「個人の尊重」とは、一人ひとりの人間を自立した人格的存在として尊重するということであり、一人ひとりがそれぞれに固有の価値をもっているという認識を前提に、それぞれの人がもっている価値を等しく尊重しようというものである。平たくいえば、一人ひとりの人間を大事にする、ということである。それは、一人ひとりが「違う」存在であるということを認め合い、その「違い」をそれぞれに尊重するということでもある。日本では、しばしば、「平等」ということを、「みな同じ」という意味合いで語ることが多いが、「平等」とは、本来、「人はみな同じだから平等でなければならない」のではなく、「人はみなそれぞれに違うからこそ平等でなければならない」というものとしてとらえられるべきものである。つまり、一人ひとりの人間は、みな、それぞれに違うのであり、一人ひとりが他者とは違った価値をもっている、だから、それぞれの人がもっているそれぞれに異なった価値を等しく尊重しよう、というのが「個人の尊重」原理のうえにたった「平等」の考え方なのである。
学校は集団生活の場である。そのため、ややもすれば、自分を抑えてでも周りと同調することが良いことだとされがちであるが、それは「個人の尊重」に反する。集団生活には、一定のルールは当然必要である。しかし、それは、集団のために必要なのではない。お互いを個人として尊重するということから、一定のルールが必要とされるわけである。「学校のためなんだから、クラスのためなんだから、みんなのためなんだから、我慢すべきだ」というのでなく、自分自身も他者も一個の人格的存在として尊重するという観点から自分の好き勝手にはできない場合もある、ということを生徒が理解できれば、集団生活のルールをつうじて「個人の尊重」ということの意味を実感できるのではないだろうか。
「個人の尊重」は、「個人主義」の社会を前提としている。「個人主義」は、これも日本では誤解されやすいが、「利己主義」ではない。「個人主義」の社会とは、「自立した個人」を構成単位とする社会のことで、そこでは、当然、他者もまた「自立した個人」として存在することが自明の前提となっているから、自分のことだけで他人のことは考えない「利己主義」は通用しない。西欧においては、封建社会が崩壊していく過程のなかで、自然発生的に「自立した個人」が生まれ、そういう「個人」が主体となって近代社会を形成してきたという歴史があるが、日本の場合には、「個人」が成熟することなく「上からの近代化」が推し進められ、「個人主義」の社会になりきらないままに、こんにちまできている。したがって、「個人主義」社会を前提とする「個人の尊重」原理も、なかなか理解されにくい面があることは否定できない。しかし、人権、平和、国民主権という価値を是とする以上は、その共通の根っこともいうべき「個人の尊重」原理の理解を深めることは必要不可欠だといえよう。次代を担う中学生・高校生に「個人の尊重」ということの意味を正しく伝えることが、憲法教育の重要な意義だと考える。
http://www.ayame-law.jp/article/14368445.html
「個人の尊重」とは、一人ひとりをかけがえのない存在として大切にするということです。一人ひとりをかけがえのない存在として大切にするということは、人を人として大切にするということであり、誰もが、国家や力の強い者、多数者から、何かの目的のための道具や手段、モノ扱いをされないということです。
「一人ひとり」には、他者のみならず、自分も含まれます。だから自分も大切にし、他者も大切にするということです。一人ひとりの人、誰もがこの世に意味があって生まれてきています。ぞんざいに扱われてよい命なんてどこにもありません。どの命も大切な命です。そして、誰もが、一人の人間として、自由に自分の幸せを求めて生きていけることが保障されなければなりません。
私は、幸せの前提は、人として大切に扱われることであり、人と争わずに温かくつながることだと思います。その上で、自分が自分らしく自由に生きるということです。きっと誰もが、人として大切に扱われたい、そしてできることならば、人とは争わずに温かくつながりたいと思っているのではないでしょうか。そして、型にはめられた幸せではなく、自分らしく自由に生きてみたいと心の底では誰もが思っているのではないでしょうか。
私は、仙台弁護士会の人権擁護委員会に所属していたのですが、そこでは、刑務所受刑者からの処遇に関する人権救済申立が多数よせられていました。その申立ての背後には、「自分を人として扱ってくれない」というような哀しみをよく感じます。また、弁護士の仕事をして、人と人との紛争の中に身をおいてみると、多くの紛争の背景には、相手が自分を人として大切に扱われなかったことについての相手への怒りや哀しみがあることをよく感じます。
誰かから、人として、自分のありのままの存在を大切にされたとき、人は、とても深い喜びを感じますよね。大切にしてくれた人のことは、きっと自分も大切にしようと思いますし、感謝の気持ちを抱き、信頼もするでしょう。お互いがお互いを人として大切にする社会は、信頼を基底にする社会であり、他者という存在は、攻撃したり、利用したりする対象ではなく助け合うもの、支え合う対象として捉えられ、優しく寛容な社会になるのではないでしょうか。
「人を人として大切にする」という意識を一人ひとりに浸透させることが重要です。人を何かの手段や道具にしてはならないことを伝えることが必要です
人は誰もが「自分フィルター」を通して世の中を見ているということです。自分は、どんなに客観的に物事を見ていると思っていても、それはあくまで自分が選んだ情報をもとに、自分の価値観を通して、事実を認識し評価しているのです。あくまで自分個人の「主観的な」ものの見方・考え方であり、自分は「偏っているかもしれない」、「間違っているかも知れない」ということを踏まえておかなければなりません。
つい人は、自分が思っているように人も思うべきだ、自分は正しい、間違っているのは相手の方だと思ってしまいがちなのですね。自分中心に物事を考えてしまいがちなのです。
弱い立場の人、少数の人、自分とは正反対の他者の意見や価値観も尊重にするということです。尊重するとは、自分と考え方や価値観の違う誰かの意見を、排斥したり、無視したり自分の考えを押しつけたりすることなく、受けとめるということです。
一つは「想像力」です。相手が大切にしているものを知ろうと想像することです。
自分とは違う考え方の人がいるということ、自分の考えだけが絶対ではないということをふまえて、相手の立場に立って考え、相手にも大切に思っている何かがあるということを想像することです。
二つめは、しっかりと相手の意見に耳を傾けることです。言葉を通じてお互いの考えをよく知り合うということです。
人はみな違っていること、自分の考えとは違う考え方があること、そして違う考え方の人の立場を想像することが大切であるということを
それぞれの立場があり、価値観があり、意見があります
自分と違う価値観、特に相手の考えが少数なものであったとき、その価値観の存在を受け入れることは、本当に難しいものです。想像力を一生懸命働かせる必要があります。相手の言葉に意識的に耳を傾け、分かろうと努力する必要があるのです
「個人の尊重」とは、一人ひとりをかけがえのない存在として大切にするということです。一人ひとりをかけがえのない存在として大切にするということは、人を人として大切にするということであり、誰もが、国家や力の強い者、多数者から、何かの目的のための道具や手段、モノ扱いをされないということです。
「一人ひとり」には、他者のみならず、自分も含まれます。だから自分も大切にし、他者も大切にするということです。一人ひとりの人、誰もがこの世に意味があって生まれてきています。ぞんざいに扱われてよい命なんてどこにもありません。どの命も大切な命です。そして、誰もが、一人の人間として、自由に自分の幸せを求めて生きていけることが保障されなければなりません。
私は、幸せの前提は、人として大切に扱われることであり、人と争わずに温かくつながることだと思います。その上で、自分が自分らしく自由に生きるということです。きっと誰もが、人として大切に扱われたい、そしてできることならば、人とは争わずに温かくつながりたいと思っているのではないでしょうか。そして、型にはめられた幸せではなく、自分らしく自由に生きてみたいと心の底では誰もが思っているのではないでしょうか。
私は、仙台弁護士会の人権擁護委員会に所属していたのですが、そこでは、刑務所受刑者からの処遇に関する人権救済申立が多数よせられていました。その申立ての背後には、「自分を人として扱ってくれない」というような哀しみをよく感じます。また、弁護士の仕事をして、人と人との紛争の中に身をおいてみると、多くの紛争の背景には、相手が自分を人として大切に扱われなかったことについての相手への怒りや哀しみがあることをよく感じます。
誰かから、人として、自分のありのままの存在を大切にされたとき、人は、とても深い喜びを感じますよね。大切にしてくれた人のことは、きっと自分も大切にしようと思いますし、感謝の気持ちを抱き、信頼もするでしょう。お互いがお互いを人として大切にする社会は、信頼を基底にする社会であり、他者という存在は、攻撃したり、利用したりする対象ではなく助け合うもの、支え合う対象として捉えられ、優しく寛容な社会になるのではないでしょうか。
「人を人として大切にする」という意識を一人ひとりに浸透させることが重要です。人を何かの手段や道具にしてはならないことを伝えることが必要です
人は誰もが「自分フィルター」を通して世の中を見ているということです。自分は、どんなに客観的に物事を見ていると思っていても、それはあくまで自分が選んだ情報をもとに、自分の価値観を通して、事実を認識し評価しているのです。あくまで自分個人の「主観的な」ものの見方・考え方であり、自分は「偏っているかもしれない」、「間違っているかも知れない」ということを踏まえておかなければなりません。
つい人は、自分が思っているように人も思うべきだ、自分は正しい、間違っているのは相手の方だと思ってしまいがちなのですね。自分中心に物事を考えてしまいがちなのです。
弱い立場の人、少数の人、自分とは正反対の他者の意見や価値観も尊重にするということです。尊重するとは、自分と考え方や価値観の違う誰かの意見を、排斥したり、無視したり自分の考えを押しつけたりすることなく、受けとめるということです。
一つは「想像力」です。相手が大切にしているものを知ろうと想像することです。
自分とは違う考え方の人がいるということ、自分の考えだけが絶対ではないということをふまえて、相手の立場に立って考え、相手にも大切に思っている何かがあるということを想像することです。
二つめは、しっかりと相手の意見に耳を傾けることです。言葉を通じてお互いの考えをよく知り合うということです。
人はみな違っていること、自分の考えとは違う考え方があること、そして違う考え方の人の立場を想像することが大切であるということを
それぞれの立場があり、価値観があり、意見があります
自分と違う価値観、特に相手の考えが少数なものであったとき、その価値観の存在を受け入れることは、本当に難しいものです。想像力を一生懸命働かせる必要があります。相手の言葉に意識的に耳を傾け、分かろうと努力する必要があるのです
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
★いじめの弊害の恐ろしさ ★ 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-