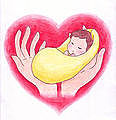ikasumi0 さん
http://
による分析が的を得ていると思ったので、皆さんとも共有したいと思い
転記許可をいただきました。
また、今後も継続的に自分達の置かれている現状を書き込んでいただければ
この、先の見えない不安の突破口も見つかるかもしれません。
どうぞよろしくお願いいたします。












【動かないのか動けないのか動く必要がないのか動かしたくないのか現状分析】
twitter上で避難に関する重要な声をいただいたのでとぅぎゃろうと思ったのですが、避難した方に誹謗中傷がいく可能性もあるのでブログにまとめました。
1.ある声
動きたいのに動けない
福島からの避難についてネット上でこんな声をみた。最初は仕事とお金の問題だろうと思った。しかし、調べたり話を聞いていくと様々な要因が複雑に絡まっていることに気づいた。そこで5月初旬「福島のいま( http://
動きたいのに動けない。色んなひずみの間からかすかに漏れでてきた声のようで、チラシ作成が終わった後も自分の中で強く残った。
2福島への手紙
「福島のいま」というチラシは、渋谷デモや京都デモで配布したりネット上からダウンロードしていただく形で拡散した。その中で「私も住んでいる福島で配ります」と言う方が何人もいて不思議だった。首都圏が原発事故に無関心なのは分かるけど、なぜ福島の中でなにかを配らなきゃいけないのか。
5月末、木下黄太さんのご厚意で、「福島のいま」チラシを福島の講演会で配っていただけることが決まった。京都で避難支援をしている方に「とにかく呼んでも避難してきてくれない。一時的に滞在しても帰ってしまう」と聞いていたので、どのように語りかけるか迷っていた。
はじめは首都圏向けチラシの「罪悪感・恐怖感にふれないように」と同じ方針にした。しかしtwitterで福島在住の方を含む様々な人達からの反応は違った。
「福島市などでも行政のデマを信じている人がいるからもっと厳しい言葉で。ネット使えるかどうかが情報の分かれ目。」
「もっと数字を細かく書いたほうがいい。比較して自分で判断できるように。」
そのような多くのアドバイスをいただいた。「危険」性を伝える言葉を書かなきゃだめだだといわれたが、私は自分が分からないことは書きたくなかったので、それを加えることはできないと断った。
「専門家でなければ「危険」と言えませんか?法律できまってるんですかね?専門家が「安全だ」だと言う以上誰が真実を教えてくれるんでしょうか。」
なぜ、私が分かることしか言わないか。それは本当に単純に責任が取りたくないからだ。話しながら今福島の人がどのような状況に置かれているかますます分からなくなった。動きたいのに動けない。それは高齢者が情報が足りず思考停止しているという簡単な問題ではないのか。
思いきってtwitterで問いかけてみた。
「福島のかたが「動きたいのに動けない」と感じるのは、福島に情報が足りないことが原因ですか?それとも思考停止してしまっている人が多いことが原因ですか?」
3避難する人々の葛藤
その問いへの反応をいくつか分類してまとめてみる。
(i)地域社会の中の圧力
「私は、小さな子どもを連れて一時避難したら、嫁ぎ先の義理家族、義理姉、部落の人たちに非難されています。嫁のくせに土地を捨てるのか、自分の子どもだけ助かればいいのか、と責められまくってます。精神的にすごく辛い。」
「いろんな情報を集めて危険を話しても理解してもらえない。福島はニュースや政府を信じてる中高年層ばかりで危険をわかってない。そして部落や親戚の繋がりでがんじがらめ。避難した私は非県民と責められるわけです。」
この声に対する反応が一番大きかった。「そんな家族捨てればよい」「全体主義」「ひどい土地だな」そういう声もあった。
また、「私もそうです。全部捨てて避難しました」という福島の方からの共感の声も多く届いた。
私はただ福島県民がひどい人達であるということで済むのかと疑問を持った。
(ii)福島の多重な姿
「福島市は原発に近い相馬方面からの避難受け入れ先です。それが思考を混乱させている一因かと。避難しなければいけない場所に避難してくる人がいる。外とネット上の温度差がありすぎてどうしたらいいか。」
「市内の学校予定地に大量の仮設住宅の建設も始まっている。福島市の人には津波被災者への遠慮もあるかも。津波被災者と原発被害者が混ざって複雑に混乱があるかも。」
この点は首都圏に住んでいる私には見えない部分だった。福島もまた津波被害を受けたのだ。そして原発事故で様々な段階で避難区域や対応が分かれた。いきなり現れた、その多重な姿に多くの人は戸惑い迷っているのかもしれない。
(iii)それでも続く「日常」
ここまでは、計画的避難区域外(年20msv内)である福島市や郡山市の話をしてきた。計画的避難区域(年20msv超)に指定された飯舘村では、会社が操業しているので、若い人達が隣の町に移り住んで通ってこないといけないという情報もあった。
一方で5月はじめにあったTBSの報道特集では、事故後一斉に避難させた葛尾村を「取り残された村民、牛、馬」などの形で非難し、そんなに簡単に避難できるものではないとする飯舘村の村長を「村民と向き合っている」と賞賛していた。どの視点からものをみるか、優先順位をどうするかによって世界の把握は一変する。この報道は、放射線量が高いところでも「日常」を続けようとすることの方が良いという姿勢にみえた。
仕事がそのまま続くように、学校もまた変わらぬ体制のまま進もうとする。校庭の土を削るかどうかから始まって、「風評」被害を防ぐためにいわき市の給食に福島産の食べ物をつかうといわき市長が宣言し疑問の声があがることもあった。不登校をするしかないという福島市の保護者の声もあった。
二本松市は独自にホールボディカンターを利用して内部被曝検査を行うらしい。自治体によっても対応がちがい、放射線量も同心円上ではなくホットスポットがあることも分かっている。
政府の政策を別として考えてみたとき、今回チェルノブイリのようにはじめ大きな爆発があるのではなくて、ゆるやかにじわじわと続く危機だから、自治体・個人なども時間があって迷いや差が生じやすいのかもしれない。
そしてその複雑な状況の中で、放射性物質を取り込みやすい子ども達は生活をしている。安全か危険かの二者択一は意味がない。とにかくリスクを上げないようにしなければというのが私の立場である。
(iv)避難した後の罪悪感
避難先へ向かうバスの中で泣いたという方もいた。きっと将来への不安感、解放された安堵などあると思う。一方で自分だけ逃げる罪悪感みたいなものも含んでいるのではないかと思った。
「気持ちとして子供を避難させたい人は実際福島にはたくさんいると思います。」
そう言って、福島に残してきた人を気にかける方が多かった。
自分はリスクが高いと思うから避難する。それはつまり、リスクが高いと思うところに誰かを残していくことなのだ。近所の人、子どもの友達、親戚。いろんな人の顔が浮かぶ。その中で避難先から戻る人もいるのかもしれない。
(v)絶望感
福島では、自主避難は何も補償されない、義援金も来ないという噂があるという意見もあった。避難区域の外にある福島市や郡山市は被災・罹災証明書がでない。そうすると避難受け入れ先も限られてくる。「親が責任もって逃がせ」と外から言う人がいる。しかし将来どうなるか一切分からない状態で、自分のせいでこの事態が起きたわけでもないのに、すべて捨てて子供だけ連れて逃げろというのは、酷な要望のようにも感じた。
自分達は補償されない。それが原発のあった自治体に対する怒りにつながっているような気もした。
色も味もにおいもないってことがネックと言う方もいた。将来不透明な絶望感のなかで、見えない何かにだんだん慣れてしまうということはあり得ることだと思った。
4.土地や関わりを失うこと
避難区域内でも帰ってくることを念頭においた支援をしてほしいという方に対して「なぜわざわざ危ないところに帰るのだ」と返す方がいた。
私は、放射線量が高い土地の人が帰るか帰らないか自問自答し続けたり、なにか症状に表れるかもと不安に思い続けたりしなきゃいけないこの先を想像した。そしてそもそもなぜこういう状況になったかがすごくおかしいし、ひどいことだと感じた。
私は福島にいて「避難するな」と言う人たちもまた被害者であると思う。家族内の力関係や学校・職場の組織の問題も多い。しかし、避難するなという人たちもまた極度の不安の中にいるのだ。
首都圏の人に「田舎でぎりぎりの生活してる人達にとっては放射性物質など遠い存在なんだ。仕方ない」と言われたことがある。なぜ何も聞いていないのに、外部が勝手に「仕方ない」と諦めるのだろうか。なぜ語りかけず勝手に「福島の人」をつくりだして代弁しようとするのだろうか。そもそも日本に住む多くの人が、危ないところからは皆逃げているだろう大丈夫だろうと漠然と認識していると思う。
私個人としては本当は、一時的でもいいので行政が主導して学童疎開をしてほしい。なぜなら自主避難だと、貧困の子ども、養護施設の子どもや養護学校の寮に入っている子どもが取り残されるからだ。人生は不平等なものだけれど、生存に関わることまで自分の生まれた境遇に左右されるのは私は納得できない。
しかし、福島県内の放射線量の高い地域でプールに入るか入らないかというニュースが流れているのをみてあきらめた。今は動きたい人は動けるようにする自主避難支援と20mSv撤回が急ぎで取り組まなきゃいけない課題として少しずつ活動している。撤回や自主避難の拡大が行政を動かすかもしれないと期待しながら。
5.大きな溝
「福島への手紙」のほかに避難名簿を作成を手伝わせていただいた経験も含めて気づいたことがある。それはいくつかの大きな溝があるということだ。
(i)情報源や世代による情報や危機意識の格差
放射能に対する情報や危機意識の溝があることは確かなようだ。家族内でも大きく意見が分かれ、離婚を決意して避難された方もいる。人間がほとんど経験したことがない事態であるからこそ、「食中毒を起こす生肉」のようにとっさに恐怖心が湧いてこない。見えないから何が怖いのか分からないという問題もあるようだ。
その溝が家族や地域の中で「避難するな」という雰囲気に繋がっている。また今がどこか危機の状況であることは分かっているので、「日常を乱すな」という圧力が起きやすいのかもしれない。
(私の考え「マスクとプラカード」http://
(ii)被災・罹災証明
避難先一覧をお手伝いして気づいたことは、被災・罹災証明がないと避難先の対象が限られるということだ。福島市や郡山市などは避難区域に指定されていないので被災・罹災証明がでない。(20km圏内の警戒区域においてすら、「家が壊れているか確認できない」と罹災証明が発効されないケースもあるようだ)相対的に条件がよい公的機関の避難先を利用できないケースも多い。しかし、避難区域外でも子どもはできるだけ避難させた方がいいという情報が多くあり、その溝の中で保護者や子どもは苦しんでいる。
(iii)受け入れ側の体制
Portal311( http://
また、受入れ先の自治体によって待遇が異なる。かなり生活に不便な場所に避難先がある場合や、その後のケアがほとんどない場合もあるようで、そのことが避難先全体に対する不安をもたらしているのかもしれない。(避難一覧 http://
(iv)補償・責任の問題
東電の下っ端しか補償に関する説明にこないと言う方がいた。これから補償がどうなるのかどれほど長い裁判があるのか分からない。責任をどこがどう取るのかも分からない。誰かが責任を取る気があるかさえ分からない。その中で新しい土地に移り住むという選択を取るというのは厳しい。
自己判断で逃げろと言われる。しかし選択肢というのは選択できてはじめて選択肢になる。寿司を二貫並べられて、明らかに片方に大量のわさびが入っていたら、それを選ぶ人は少ない。わさびを取り除く努力もしないで「あなたはそれを選びました」と自己判断・自己責任というのは無理があるのではないだろうか。
6.いま
私は東電原発事故による被ばくの問題について「いま」考えたい。歴史の教科書ででてくる「社会問題」ははっきりと手に掴めたけれど、現在進行形の物事はこんなに簡単に手をすりぬけていくのだと気づいた。何が問題なのか分からない。それがいま起こっていることの大きさを表しているようにも思う。
これから放射線量が高い土地に生きている人たちの「いま」は、何重にも重なっていく。被ばくを可能な限り少なくすること、食べ物による内部被ばくできるだけおさえること、差別が起きてくる前に正しい知識を広めて予防することなど沢山しなければならないことがある。
「フクシマ」という触れてはいけない過去の問題にさせないために、私は「いま」何かを語りかけたり行動したりしたい。他の人にはそれを強要しないけど、せめて関心をできるだけ長く持ち続けてくれたら嬉しい。
最終的に「福島への手紙」( http://
☆「福島への手紙」→( http://
セブンイレブンネットプリント→予約番号 FUCZT2ED (6月7日更新予定)です。
☆「福島のいま〔最新版〕」→( http://
セブンイレブンネットプリント→予約番号 7PE4U3AK (6月7日更新予定)です。
このままの形でご自由に拡散、配布下さい。
http://
による分析が的を得ていると思ったので、皆さんとも共有したいと思い
転記許可をいただきました。
また、今後も継続的に自分達の置かれている現状を書き込んでいただければ
この、先の見えない不安の突破口も見つかるかもしれません。
どうぞよろしくお願いいたします。
【動かないのか動けないのか動く必要がないのか動かしたくないのか現状分析】
twitter上で避難に関する重要な声をいただいたのでとぅぎゃろうと思ったのですが、避難した方に誹謗中傷がいく可能性もあるのでブログにまとめました。
1.ある声
動きたいのに動けない
福島からの避難についてネット上でこんな声をみた。最初は仕事とお金の問題だろうと思った。しかし、調べたり話を聞いていくと様々な要因が複雑に絡まっていることに気づいた。そこで5月初旬「福島のいま( http://
動きたいのに動けない。色んなひずみの間からかすかに漏れでてきた声のようで、チラシ作成が終わった後も自分の中で強く残った。
2福島への手紙
「福島のいま」というチラシは、渋谷デモや京都デモで配布したりネット上からダウンロードしていただく形で拡散した。その中で「私も住んでいる福島で配ります」と言う方が何人もいて不思議だった。首都圏が原発事故に無関心なのは分かるけど、なぜ福島の中でなにかを配らなきゃいけないのか。
5月末、木下黄太さんのご厚意で、「福島のいま」チラシを福島の講演会で配っていただけることが決まった。京都で避難支援をしている方に「とにかく呼んでも避難してきてくれない。一時的に滞在しても帰ってしまう」と聞いていたので、どのように語りかけるか迷っていた。
はじめは首都圏向けチラシの「罪悪感・恐怖感にふれないように」と同じ方針にした。しかしtwitterで福島在住の方を含む様々な人達からの反応は違った。
「福島市などでも行政のデマを信じている人がいるからもっと厳しい言葉で。ネット使えるかどうかが情報の分かれ目。」
「もっと数字を細かく書いたほうがいい。比較して自分で判断できるように。」
そのような多くのアドバイスをいただいた。「危険」性を伝える言葉を書かなきゃだめだだといわれたが、私は自分が分からないことは書きたくなかったので、それを加えることはできないと断った。
「専門家でなければ「危険」と言えませんか?法律できまってるんですかね?専門家が「安全だ」だと言う以上誰が真実を教えてくれるんでしょうか。」
なぜ、私が分かることしか言わないか。それは本当に単純に責任が取りたくないからだ。話しながら今福島の人がどのような状況に置かれているかますます分からなくなった。動きたいのに動けない。それは高齢者が情報が足りず思考停止しているという簡単な問題ではないのか。
思いきってtwitterで問いかけてみた。
「福島のかたが「動きたいのに動けない」と感じるのは、福島に情報が足りないことが原因ですか?それとも思考停止してしまっている人が多いことが原因ですか?」
3避難する人々の葛藤
その問いへの反応をいくつか分類してまとめてみる。
(i)地域社会の中の圧力
「私は、小さな子どもを連れて一時避難したら、嫁ぎ先の義理家族、義理姉、部落の人たちに非難されています。嫁のくせに土地を捨てるのか、自分の子どもだけ助かればいいのか、と責められまくってます。精神的にすごく辛い。」
「いろんな情報を集めて危険を話しても理解してもらえない。福島はニュースや政府を信じてる中高年層ばかりで危険をわかってない。そして部落や親戚の繋がりでがんじがらめ。避難した私は非県民と責められるわけです。」
この声に対する反応が一番大きかった。「そんな家族捨てればよい」「全体主義」「ひどい土地だな」そういう声もあった。
また、「私もそうです。全部捨てて避難しました」という福島の方からの共感の声も多く届いた。
私はただ福島県民がひどい人達であるということで済むのかと疑問を持った。
(ii)福島の多重な姿
「福島市は原発に近い相馬方面からの避難受け入れ先です。それが思考を混乱させている一因かと。避難しなければいけない場所に避難してくる人がいる。外とネット上の温度差がありすぎてどうしたらいいか。」
「市内の学校予定地に大量の仮設住宅の建設も始まっている。福島市の人には津波被災者への遠慮もあるかも。津波被災者と原発被害者が混ざって複雑に混乱があるかも。」
この点は首都圏に住んでいる私には見えない部分だった。福島もまた津波被害を受けたのだ。そして原発事故で様々な段階で避難区域や対応が分かれた。いきなり現れた、その多重な姿に多くの人は戸惑い迷っているのかもしれない。
(iii)それでも続く「日常」
ここまでは、計画的避難区域外(年20msv内)である福島市や郡山市の話をしてきた。計画的避難区域(年20msv超)に指定された飯舘村では、会社が操業しているので、若い人達が隣の町に移り住んで通ってこないといけないという情報もあった。
一方で5月はじめにあったTBSの報道特集では、事故後一斉に避難させた葛尾村を「取り残された村民、牛、馬」などの形で非難し、そんなに簡単に避難できるものではないとする飯舘村の村長を「村民と向き合っている」と賞賛していた。どの視点からものをみるか、優先順位をどうするかによって世界の把握は一変する。この報道は、放射線量が高いところでも「日常」を続けようとすることの方が良いという姿勢にみえた。
仕事がそのまま続くように、学校もまた変わらぬ体制のまま進もうとする。校庭の土を削るかどうかから始まって、「風評」被害を防ぐためにいわき市の給食に福島産の食べ物をつかうといわき市長が宣言し疑問の声があがることもあった。不登校をするしかないという福島市の保護者の声もあった。
二本松市は独自にホールボディカンターを利用して内部被曝検査を行うらしい。自治体によっても対応がちがい、放射線量も同心円上ではなくホットスポットがあることも分かっている。
政府の政策を別として考えてみたとき、今回チェルノブイリのようにはじめ大きな爆発があるのではなくて、ゆるやかにじわじわと続く危機だから、自治体・個人なども時間があって迷いや差が生じやすいのかもしれない。
そしてその複雑な状況の中で、放射性物質を取り込みやすい子ども達は生活をしている。安全か危険かの二者択一は意味がない。とにかくリスクを上げないようにしなければというのが私の立場である。
(iv)避難した後の罪悪感
避難先へ向かうバスの中で泣いたという方もいた。きっと将来への不安感、解放された安堵などあると思う。一方で自分だけ逃げる罪悪感みたいなものも含んでいるのではないかと思った。
「気持ちとして子供を避難させたい人は実際福島にはたくさんいると思います。」
そう言って、福島に残してきた人を気にかける方が多かった。
自分はリスクが高いと思うから避難する。それはつまり、リスクが高いと思うところに誰かを残していくことなのだ。近所の人、子どもの友達、親戚。いろんな人の顔が浮かぶ。その中で避難先から戻る人もいるのかもしれない。
(v)絶望感
福島では、自主避難は何も補償されない、義援金も来ないという噂があるという意見もあった。避難区域の外にある福島市や郡山市は被災・罹災証明書がでない。そうすると避難受け入れ先も限られてくる。「親が責任もって逃がせ」と外から言う人がいる。しかし将来どうなるか一切分からない状態で、自分のせいでこの事態が起きたわけでもないのに、すべて捨てて子供だけ連れて逃げろというのは、酷な要望のようにも感じた。
自分達は補償されない。それが原発のあった自治体に対する怒りにつながっているような気もした。
色も味もにおいもないってことがネックと言う方もいた。将来不透明な絶望感のなかで、見えない何かにだんだん慣れてしまうということはあり得ることだと思った。
4.土地や関わりを失うこと
避難区域内でも帰ってくることを念頭においた支援をしてほしいという方に対して「なぜわざわざ危ないところに帰るのだ」と返す方がいた。
私は、放射線量が高い土地の人が帰るか帰らないか自問自答し続けたり、なにか症状に表れるかもと不安に思い続けたりしなきゃいけないこの先を想像した。そしてそもそもなぜこういう状況になったかがすごくおかしいし、ひどいことだと感じた。
私は福島にいて「避難するな」と言う人たちもまた被害者であると思う。家族内の力関係や学校・職場の組織の問題も多い。しかし、避難するなという人たちもまた極度の不安の中にいるのだ。
首都圏の人に「田舎でぎりぎりの生活してる人達にとっては放射性物質など遠い存在なんだ。仕方ない」と言われたことがある。なぜ何も聞いていないのに、外部が勝手に「仕方ない」と諦めるのだろうか。なぜ語りかけず勝手に「福島の人」をつくりだして代弁しようとするのだろうか。そもそも日本に住む多くの人が、危ないところからは皆逃げているだろう大丈夫だろうと漠然と認識していると思う。
私個人としては本当は、一時的でもいいので行政が主導して学童疎開をしてほしい。なぜなら自主避難だと、貧困の子ども、養護施設の子どもや養護学校の寮に入っている子どもが取り残されるからだ。人生は不平等なものだけれど、生存に関わることまで自分の生まれた境遇に左右されるのは私は納得できない。
しかし、福島県内の放射線量の高い地域でプールに入るか入らないかというニュースが流れているのをみてあきらめた。今は動きたい人は動けるようにする自主避難支援と20mSv撤回が急ぎで取り組まなきゃいけない課題として少しずつ活動している。撤回や自主避難の拡大が行政を動かすかもしれないと期待しながら。
5.大きな溝
「福島への手紙」のほかに避難名簿を作成を手伝わせていただいた経験も含めて気づいたことがある。それはいくつかの大きな溝があるということだ。
(i)情報源や世代による情報や危機意識の格差
放射能に対する情報や危機意識の溝があることは確かなようだ。家族内でも大きく意見が分かれ、離婚を決意して避難された方もいる。人間がほとんど経験したことがない事態であるからこそ、「食中毒を起こす生肉」のようにとっさに恐怖心が湧いてこない。見えないから何が怖いのか分からないという問題もあるようだ。
その溝が家族や地域の中で「避難するな」という雰囲気に繋がっている。また今がどこか危機の状況であることは分かっているので、「日常を乱すな」という圧力が起きやすいのかもしれない。
(私の考え「マスクとプラカード」http://
(ii)被災・罹災証明
避難先一覧をお手伝いして気づいたことは、被災・罹災証明がないと避難先の対象が限られるということだ。福島市や郡山市などは避難区域に指定されていないので被災・罹災証明がでない。(20km圏内の警戒区域においてすら、「家が壊れているか確認できない」と罹災証明が発効されないケースもあるようだ)相対的に条件がよい公的機関の避難先を利用できないケースも多い。しかし、避難区域外でも子どもはできるだけ避難させた方がいいという情報が多くあり、その溝の中で保護者や子どもは苦しんでいる。
(iii)受け入れ側の体制
Portal311( http://
また、受入れ先の自治体によって待遇が異なる。かなり生活に不便な場所に避難先がある場合や、その後のケアがほとんどない場合もあるようで、そのことが避難先全体に対する不安をもたらしているのかもしれない。(避難一覧 http://
(iv)補償・責任の問題
東電の下っ端しか補償に関する説明にこないと言う方がいた。これから補償がどうなるのかどれほど長い裁判があるのか分からない。責任をどこがどう取るのかも分からない。誰かが責任を取る気があるかさえ分からない。その中で新しい土地に移り住むという選択を取るというのは厳しい。
自己判断で逃げろと言われる。しかし選択肢というのは選択できてはじめて選択肢になる。寿司を二貫並べられて、明らかに片方に大量のわさびが入っていたら、それを選ぶ人は少ない。わさびを取り除く努力もしないで「あなたはそれを選びました」と自己判断・自己責任というのは無理があるのではないだろうか。
6.いま
私は東電原発事故による被ばくの問題について「いま」考えたい。歴史の教科書ででてくる「社会問題」ははっきりと手に掴めたけれど、現在進行形の物事はこんなに簡単に手をすりぬけていくのだと気づいた。何が問題なのか分からない。それがいま起こっていることの大きさを表しているようにも思う。
これから放射線量が高い土地に生きている人たちの「いま」は、何重にも重なっていく。被ばくを可能な限り少なくすること、食べ物による内部被ばくできるだけおさえること、差別が起きてくる前に正しい知識を広めて予防することなど沢山しなければならないことがある。
「フクシマ」という触れてはいけない過去の問題にさせないために、私は「いま」何かを語りかけたり行動したりしたい。他の人にはそれを強要しないけど、せめて関心をできるだけ長く持ち続けてくれたら嬉しい。
最終的に「福島への手紙」( http://
☆「福島への手紙」→( http://
セブンイレブンネットプリント→予約番号 FUCZT2ED (6月7日更新予定)です。
☆「福島のいま〔最新版〕」→( http://
セブンイレブンネットプリント→予約番号 7PE4U3AK (6月7日更新予定)です。
このままの形でご自由に拡散、配布下さい。
|
|
|
|
コメント(6)
福島郡山から@savefukushimaaさんの手紙
外で子ども達の遊ぶ声がしない。この一ヶ月で人々の意識は大きく変わった。「皆大丈夫といっている」から「皆不安を抱えている」への変化。不安を抱えながらも動けない、これが現状。
一ヶ月ほど前までは、放射線がどれほど子ども達の体に害があるのか、周囲の人々はあまり理解していなかった。だからこそ情報を繋いでいただき、安全論をねじ曲げようとした。そしてそのおかげで今、安全論はほぼ消え去った。皆不安を口にできる状況になった。
危険を感じていない人には声高に危険を叫ぶ必要がある。しかし、今周囲にいる人は明らかに不安は感じているが動けない人である。その方々に声高に危険を叫んでも何も生まれない。危険は十分理解しているのだから。
避難に対する支援ももちろん大切。しかし、大半の人々が動けない以上そちらにも目を向けなければならない。動けない子ども達への支援もしなくてはならない。蓄積を避けながらも、原発事故前の生活に近づけられるよう何ができるだろうか?
子ども達の集団疎開はぜひ実現してほしい。しかし、それを実現するのは現実的にかなり厳しいだろう。お金の面でも、時間の面でも。避難区域の線引きも難しい。
残っている子ども達のためにセーフスポットを創り出したい。完璧に放射線管理がされていて、子ども達が思い切り遊べる場がほしい。県全体を除染するのは難しくても、セーフスポットを創り出すことはできるはずだ。そこが親達が思いを吐き出す場にもなる。
目的は「子ども達の命を繋ぐ」子ども達の中には、「動いた子ども」も、「動く子ども」も、「動けない子ども」も含まれる。そして大半は「動けない子ども達」動けない子ども達に何ができるか。考えなければいけない時期にきている。
外で子ども達の遊ぶ声がしない。この一ヶ月で人々の意識は大きく変わった。「皆大丈夫といっている」から「皆不安を抱えている」への変化。不安を抱えながらも動けない、これが現状。
一ヶ月ほど前までは、放射線がどれほど子ども達の体に害があるのか、周囲の人々はあまり理解していなかった。だからこそ情報を繋いでいただき、安全論をねじ曲げようとした。そしてそのおかげで今、安全論はほぼ消え去った。皆不安を口にできる状況になった。
危険を感じていない人には声高に危険を叫ぶ必要がある。しかし、今周囲にいる人は明らかに不安は感じているが動けない人である。その方々に声高に危険を叫んでも何も生まれない。危険は十分理解しているのだから。
避難に対する支援ももちろん大切。しかし、大半の人々が動けない以上そちらにも目を向けなければならない。動けない子ども達への支援もしなくてはならない。蓄積を避けながらも、原発事故前の生活に近づけられるよう何ができるだろうか?
子ども達の集団疎開はぜひ実現してほしい。しかし、それを実現するのは現実的にかなり厳しいだろう。お金の面でも、時間の面でも。避難区域の線引きも難しい。
残っている子ども達のためにセーフスポットを創り出したい。完璧に放射線管理がされていて、子ども達が思い切り遊べる場がほしい。県全体を除染するのは難しくても、セーフスポットを創り出すことはできるはずだ。そこが親達が思いを吐き出す場にもなる。
目的は「子ども達の命を繋ぐ」子ども達の中には、「動いた子ども」も、「動く子ども」も、「動けない子ども」も含まれる。そして大半は「動けない子ども達」動けない子ども達に何ができるか。考えなければいけない時期にきている。
ikasumi0 さん
http://d.hatena.ne.jp/ikasumi0/20110608/1307519947
被ばくしたくないなら避難をすればいいじゃない【現状分析】
この状況では逃げたい人が逃げてくださいとしか言えない
よく聞く言葉です。私もそう思います。
しかし、「動きたくても動けない」そういう声も福島(宮城の一部)から漏れてきます。
福島(宮城の一部)からの避難の現状について自分なりに分析してみました。乱暴なまとめですが、自分が情報共有したり、福島の人と話したり、避難支援活動しながら考えたことです。正確な分析ではないかもしれませんが、何かの参考にしていただければ嬉しいです。
1.「動きたいのに動けない」福島の複雑な現状
i.情報ソースの違いによる危機感の溝
・世代の違い・子育ての担い手かどうかの違いで目にするメディアが違う。
・福島県のアドバイザー山下俊一氏は当初、100msvまで安全と講演会で発言。
・郡山市で12万部配られたタウン誌
(特別寄稿・福島への手紙1「長崎から」の画像←九州工業大学学長・宮里達郎による安全デマ)
ii.同調しろという圧力
・共同体のつながりがしっかりしているゆえの「逃げるな」という雰囲気があるらしい。しかしそれは福島の方が全体主義とかいうわけではなくて、危機的状況なのに何もできない極度の不安感からではないか。
iii.被災・罹災証明
・被災・罹災証明書が発行されない自主避難は避難先条件が悪い。
・警戒区域ないでさえ発行も統一的ではない。
iv.補償・責任が不明確なことへの不安・諦め
・福島では、どうせ補償はしてもらえないと裁判を諦めている生産者も多いよう。
・何も補償されないかもしれないのに、土地・家・関わり全部捨てて「自主避難すればいいじゃない」というのは酷な気がする。
v.受け入れ態勢の不整備
・避難先一覧すらボランティアが作成。 http://bit.ly/isTsZ
・6月3付けで厚労省はさらに雇用促進住宅の受入れ制限の指導を行った。
・各自治体によって対応も受け入れ態勢も異なる。
vi.様々な被害者
・津波被害者と避難区域内外被害者が入り乱れ、福島市内には仮設住宅が建設始まっている。
・より大変な状況の人に対する遠慮で不安を口に出せない。
vii.つづく「日常」
・会社・学校が日常通り続き、親は子がいるから、子は親がいるから動けない。
viii.罪悪感・絶望感
・誰かをリスクの高いところに残していく罪悪感。
・他の地域に見捨てられたという絶望感。
(ここまでの思考過程:「動かないのか動けないのか動く必要がないのか動かしたくないのか」 http://d.hatena.ne.jp/ikasumi0/20110530/1306802044」)
☆実態はもっと複雑です。私はこの状況に対して自分が何ができるだろうかという答えとして、チラシを二枚つくりました。
♪「福島のいま 首都圏向け〔最新版〕」→( http://xfs.jp/3RWUd )
♪「福島のいま 全国向け」→( http://xfs.jp/fySry )
♪「福島への手紙」→( http://xfs.jp/STDB4 )
デモの横や街頭などで配布したりネットからダウンロードして各々配布中。
☆とにかく状況が複雑すぎて、福島の人達が福島の中で相談したりできないんじゃないかと思い、福島向けの電話相談窓口がつくれないかと考えています。できれば行政に無理ならフリーダイヤルで。もし何か教えていただけることなどありましたらお願いします。
2.行政の対応
・6月3日付けで厚生労働省が雇用促進住宅の受入れを福島県内住民に限るという指導をだしました。それを受けてとくにv.受け入れ態勢の不整備について考えてました。
厚生労働省職業安定局へ電話願います。0335025352。罹災証明なし自主避難を各自治体の雇用促進住宅で受け入れていたのに、6月3日付で第一原発事故の被害を受けた福島県内住民に限るという制限。事態は深刻で範囲を狭める意図が不明です
こういう趣旨のツイートをみて思い切って電話をかけてみました。
厚生労働省職業安定局の方(かわいそうなので名前は伏せます)
・事故当初は広く受け入れることにしていたのだが、4月28日付けで雇用開発機構や出先機関には「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」を中心に福島県にかぎると知らせていた。
・広く受け入れるまま運用は続いていた。入居手続のため問い合わせた人には、口頭で全員に説明していた。HPに記載や文書では出していない。福島県以外の自主避難者の受付は6月12日まで、家賃無料期間は9月(すでに入っている人も)までという指導を6月3日にだしたことに問題ないという認識。厚労省HPで今週中に公開する。
・6月3日に指導を入れたのは、国からの通達ではない。決定の責任は、総務省職業安定局 総務課 宮川課長 0335026768(対応は最初の窓口でのみ受け付ける)
http://d.hatena.ne.jp/ikasumi0/20110608/1307519947
被ばくしたくないなら避難をすればいいじゃない【現状分析】
この状況では逃げたい人が逃げてくださいとしか言えない
よく聞く言葉です。私もそう思います。
しかし、「動きたくても動けない」そういう声も福島(宮城の一部)から漏れてきます。
福島(宮城の一部)からの避難の現状について自分なりに分析してみました。乱暴なまとめですが、自分が情報共有したり、福島の人と話したり、避難支援活動しながら考えたことです。正確な分析ではないかもしれませんが、何かの参考にしていただければ嬉しいです。
1.「動きたいのに動けない」福島の複雑な現状
i.情報ソースの違いによる危機感の溝
・世代の違い・子育ての担い手かどうかの違いで目にするメディアが違う。
・福島県のアドバイザー山下俊一氏は当初、100msvまで安全と講演会で発言。
・郡山市で12万部配られたタウン誌
(特別寄稿・福島への手紙1「長崎から」の画像←九州工業大学学長・宮里達郎による安全デマ)
ii.同調しろという圧力
・共同体のつながりがしっかりしているゆえの「逃げるな」という雰囲気があるらしい。しかしそれは福島の方が全体主義とかいうわけではなくて、危機的状況なのに何もできない極度の不安感からではないか。
iii.被災・罹災証明
・被災・罹災証明書が発行されない自主避難は避難先条件が悪い。
・警戒区域ないでさえ発行も統一的ではない。
iv.補償・責任が不明確なことへの不安・諦め
・福島では、どうせ補償はしてもらえないと裁判を諦めている生産者も多いよう。
・何も補償されないかもしれないのに、土地・家・関わり全部捨てて「自主避難すればいいじゃない」というのは酷な気がする。
v.受け入れ態勢の不整備
・避難先一覧すらボランティアが作成。 http://bit.ly/isTsZ
・6月3付けで厚労省はさらに雇用促進住宅の受入れ制限の指導を行った。
・各自治体によって対応も受け入れ態勢も異なる。
vi.様々な被害者
・津波被害者と避難区域内外被害者が入り乱れ、福島市内には仮設住宅が建設始まっている。
・より大変な状況の人に対する遠慮で不安を口に出せない。
vii.つづく「日常」
・会社・学校が日常通り続き、親は子がいるから、子は親がいるから動けない。
viii.罪悪感・絶望感
・誰かをリスクの高いところに残していく罪悪感。
・他の地域に見捨てられたという絶望感。
(ここまでの思考過程:「動かないのか動けないのか動く必要がないのか動かしたくないのか」 http://d.hatena.ne.jp/ikasumi0/20110530/1306802044」)
☆実態はもっと複雑です。私はこの状況に対して自分が何ができるだろうかという答えとして、チラシを二枚つくりました。
♪「福島のいま 首都圏向け〔最新版〕」→( http://xfs.jp/3RWUd )
♪「福島のいま 全国向け」→( http://xfs.jp/fySry )
♪「福島への手紙」→( http://xfs.jp/STDB4 )
デモの横や街頭などで配布したりネットからダウンロードして各々配布中。
☆とにかく状況が複雑すぎて、福島の人達が福島の中で相談したりできないんじゃないかと思い、福島向けの電話相談窓口がつくれないかと考えています。できれば行政に無理ならフリーダイヤルで。もし何か教えていただけることなどありましたらお願いします。
2.行政の対応
・6月3日付けで厚生労働省が雇用促進住宅の受入れを福島県内住民に限るという指導をだしました。それを受けてとくにv.受け入れ態勢の不整備について考えてました。
厚生労働省職業安定局へ電話願います。0335025352。罹災証明なし自主避難を各自治体の雇用促進住宅で受け入れていたのに、6月3日付で第一原発事故の被害を受けた福島県内住民に限るという制限。事態は深刻で範囲を狭める意図が不明です
こういう趣旨のツイートをみて思い切って電話をかけてみました。
厚生労働省職業安定局の方(かわいそうなので名前は伏せます)
・事故当初は広く受け入れることにしていたのだが、4月28日付けで雇用開発機構や出先機関には「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」を中心に福島県にかぎると知らせていた。
・広く受け入れるまま運用は続いていた。入居手続のため問い合わせた人には、口頭で全員に説明していた。HPに記載や文書では出していない。福島県以外の自主避難者の受付は6月12日まで、家賃無料期間は9月(すでに入っている人も)までという指導を6月3日にだしたことに問題ないという認識。厚労省HPで今週中に公開する。
・6月3日に指導を入れたのは、国からの通達ではない。決定の責任は、総務省職業安定局 総務課 宮川課長 0335026768(対応は最初の窓口でのみ受け付ける)
疑問に思ったことをきいてみた。
1・最初の避難区域は同心円状に設定
2.その後「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」は放射線量を考慮して同心円状ではない。
3.なのにまた今回「福島県」という行政区域で区切るのか。宮城の一部で会津より放射線量が高いところがある。
避難する人達は仕事をやめたりローンを残しままワラにもすがる思いで避難している。それを口頭の周知のみで公的機関の受入れの条件を急に変えて良いのか。
国方針に従っているのでなんとも申しようがない。
また国の方針に従って変わる可能性もある。
と回答してくださいました。
3.避難(津波被害含む)に関するここまでの対応
i.生活保護は避難先自治体に責任
3月18日の時点で厚労省は、震災の被災者が、他の市町村に避難して生活保護を申請した場合、避難先の都道府県や市町村が保護費を支給し、費用も負担するよう求める通知。
http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201103180014.html
この時点で、各自治体が受入れ萎縮に向かう可能性を示唆する方が多かったです。
ii.罹災・被災証明書
浪江町などははじめは簡単に「罹災証明書」がでたのに、後半は「家の損壊が現地調査できないから」と罹災証明書がでなかった。
南相馬市では津波で壊滅した集落等は航空写真で認定という特例で認めたという話も。
それ以外の人には自宅に被害がないという理由で「被災証明」が発行されることが多い。
おそらく今後の補償にどの証明書がでたのかが影響するので、自治体の対応が慎重になったのではないかなと個人的に思います。
iii.生活保護打ち切り
生活保護受給中の被災者に対し、避難所生活で住居費がかからないことや、義援金を受け取ったことを理由にした保護の廃止や停止が相次ぐ。
http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CN/main/457419.html
これは他の自治体に避難した方ではないですが、国ではなく各自治体が生活保護を出しているために財政問題で停止を急いでいるのかもしれません。
1・最初の避難区域は同心円状に設定
2.その後「計画的避難区域」「緊急時避難準備区域」は放射線量を考慮して同心円状ではない。
3.なのにまた今回「福島県」という行政区域で区切るのか。宮城の一部で会津より放射線量が高いところがある。
避難する人達は仕事をやめたりローンを残しままワラにもすがる思いで避難している。それを口頭の周知のみで公的機関の受入れの条件を急に変えて良いのか。
国方針に従っているのでなんとも申しようがない。
また国の方針に従って変わる可能性もある。
と回答してくださいました。
3.避難(津波被害含む)に関するここまでの対応
i.生活保護は避難先自治体に責任
3月18日の時点で厚労省は、震災の被災者が、他の市町村に避難して生活保護を申請した場合、避難先の都道府県や市町村が保護費を支給し、費用も負担するよう求める通知。
http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201103180014.html
この時点で、各自治体が受入れ萎縮に向かう可能性を示唆する方が多かったです。
ii.罹災・被災証明書
浪江町などははじめは簡単に「罹災証明書」がでたのに、後半は「家の損壊が現地調査できないから」と罹災証明書がでなかった。
南相馬市では津波で壊滅した集落等は航空写真で認定という特例で認めたという話も。
それ以外の人には自宅に被害がないという理由で「被災証明」が発行されることが多い。
おそらく今後の補償にどの証明書がでたのかが影響するので、自治体の対応が慎重になったのではないかなと個人的に思います。
iii.生活保護打ち切り
生活保護受給中の被災者に対し、避難所生活で住居費がかからないことや、義援金を受け取ったことを理由にした保護の廃止や停止が相次ぐ。
http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CN/main/457419.html
これは他の自治体に避難した方ではないですが、国ではなく各自治体が生活保護を出しているために財政問題で停止を急いでいるのかもしれません。
iv.各地の雇用促進住宅に対して制限
今回電話で問い合わせてみても、自主避難可能の情報が広がって、多くの人が行政の制度を利用することで行政負担が増えることを懸念しているのか目的がよく分かりませんでした。
もしくは人口流出を抑えたいという意思があるのかもしれません。
省によるかもしれませんが、原発事故被災者に対するここまでの行政の対応はとにかく避難区域外の人を動かしたくないというように見えます。「自衛」という指導をしながらそこに住み続けてくれれば、補償もしなくて済むし経済活動も滞らない。一番経済的損失は少ないという判断ではないかと思います。
体の疾病については証明するのがかなり難しいですし、裁判は長い時間かかるのでそれが全体としては得策という判断なのだと思います。
悪意があるないではなく、統治機構は「大多数の利益」と判断したものを採用するものなんじゃないかなと思います。でもそれが「医療費」「不安感」「少子化」「差別」「日本全体が誠実に対応をしていないことによる他国からの不信感」などを含めれば本当に利益につながるのか私はひじょうに疑問です。
人口流出や経済の停滞が問題であるならば、放射性物質をとりこみやすいとされている成長期の子どもだけでも一時的でいいので学童疎開させる方向はいかがでしょうか。
自主避難だと親が動けないと子どもが動けない、子どもが動けないと親が動けないとなるし、生まれた環境の経済力で子どもの生存に関する権利が左右されるという問題がでてきます。
私は理想論をいうつもりはないです。でもホットスポットがある、放射性物質に対する感受性が年代で異なるのだから、画一的に対応するのではなく、せめて効率的に対応してほしいです。不平等をおそれているのかもしれないですが、放射性物質は原発推進してきたおじさま達にはあまり取り込まれない不平等なものなんですもの。
おそらく学童疎開は学校が関わってくるので、厚労省と文科省で管轄が違うのだと思います。でもそんなこと言っている場合ではないと思います。
百歩譲って「まじむり。危ないけどそこで我慢して生きて」というなら、できるかぎりリスクを下げると思われる情報の周知徹底と自衛手段を行政がお金をだしてするべきだと思います。
私はアナーキストでもコミュニストでも反体制ですらありません。ただこの前代未聞の状況に行政も何が正しいか分からないんじゃないかと思います。それなら考えたことはそれぞれ声を上げて伝えてあげるべきなのではないでしょうか。もちろんそれが他の人の声の排除にならないよう気をつけながら。
福島の学校では夏も窓を閉めて扇風機で授業をするのだそうです。窓際は放射線量が高いから、週に一回席替えをして不平等にならないようにしている学校もあるそうです。小さな子どもにマスクをさせるのは本当に難しいしN95は無理です。
このまま何も変えなくてよいのでしょうか。もうすぐ梅雨がきます。
文責 疋田香澄
☆「福島のいま 首都圏向け〔最新版〕」→( http://xfs.jp/3RWUd )
セブンイレブンネットプリント→予約番号 DXRYUC72 (6月14日更新予定)
☆「福島のいま 全国向け」→( http://xfs.jp/fySry )
セブンイレブンネットプリント→予約番号 9CDR6KBZ (6月14日更新予定)
☆「福島への手紙」→( http://xfs.jp/STDB4 )
セブンイレブンネットプリント→予約番号 M8SGLJF7 (6月14日更新予定)
このままの形でご自由に拡散、配布下さい。
今回電話で問い合わせてみても、自主避難可能の情報が広がって、多くの人が行政の制度を利用することで行政負担が増えることを懸念しているのか目的がよく分かりませんでした。
もしくは人口流出を抑えたいという意思があるのかもしれません。
省によるかもしれませんが、原発事故被災者に対するここまでの行政の対応はとにかく避難区域外の人を動かしたくないというように見えます。「自衛」という指導をしながらそこに住み続けてくれれば、補償もしなくて済むし経済活動も滞らない。一番経済的損失は少ないという判断ではないかと思います。
体の疾病については証明するのがかなり難しいですし、裁判は長い時間かかるのでそれが全体としては得策という判断なのだと思います。
悪意があるないではなく、統治機構は「大多数の利益」と判断したものを採用するものなんじゃないかなと思います。でもそれが「医療費」「不安感」「少子化」「差別」「日本全体が誠実に対応をしていないことによる他国からの不信感」などを含めれば本当に利益につながるのか私はひじょうに疑問です。
人口流出や経済の停滞が問題であるならば、放射性物質をとりこみやすいとされている成長期の子どもだけでも一時的でいいので学童疎開させる方向はいかがでしょうか。
自主避難だと親が動けないと子どもが動けない、子どもが動けないと親が動けないとなるし、生まれた環境の経済力で子どもの生存に関する権利が左右されるという問題がでてきます。
私は理想論をいうつもりはないです。でもホットスポットがある、放射性物質に対する感受性が年代で異なるのだから、画一的に対応するのではなく、せめて効率的に対応してほしいです。不平等をおそれているのかもしれないですが、放射性物質は原発推進してきたおじさま達にはあまり取り込まれない不平等なものなんですもの。
おそらく学童疎開は学校が関わってくるので、厚労省と文科省で管轄が違うのだと思います。でもそんなこと言っている場合ではないと思います。
百歩譲って「まじむり。危ないけどそこで我慢して生きて」というなら、できるかぎりリスクを下げると思われる情報の周知徹底と自衛手段を行政がお金をだしてするべきだと思います。
私はアナーキストでもコミュニストでも反体制ですらありません。ただこの前代未聞の状況に行政も何が正しいか分からないんじゃないかと思います。それなら考えたことはそれぞれ声を上げて伝えてあげるべきなのではないでしょうか。もちろんそれが他の人の声の排除にならないよう気をつけながら。
福島の学校では夏も窓を閉めて扇風機で授業をするのだそうです。窓際は放射線量が高いから、週に一回席替えをして不平等にならないようにしている学校もあるそうです。小さな子どもにマスクをさせるのは本当に難しいしN95は無理です。
このまま何も変えなくてよいのでしょうか。もうすぐ梅雨がきます。
文責 疋田香澄
☆「福島のいま 首都圏向け〔最新版〕」→( http://xfs.jp/3RWUd )
セブンイレブンネットプリント→予約番号 DXRYUC72 (6月14日更新予定)
☆「福島のいま 全国向け」→( http://xfs.jp/fySry )
セブンイレブンネットプリント→予約番号 9CDR6KBZ (6月14日更新予定)
☆「福島への手紙」→( http://xfs.jp/STDB4 )
セブンイレブンネットプリント→予約番号 M8SGLJF7 (6月14日更新予定)
このままの形でご自由に拡散、配布下さい。
みなさまこんにちはm(_ _)m
もしコチラへの書き込みが適切でない場合はどうぞ削除してください。
もうすぐ震災から9ヶ月。年も暮れに近づいてきました。
今だからこそ、放射能問題だけではなく、防災・医療・などなど
「暮らしの中の科学」についてわかりやすく学び考えていこうというコミュを作りました。
子育て中のパパ・ママ中心の関心事について取り扱って生きたいと思います。
「ママの勉強部屋」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5862191
危険・安全の判断ではなく
自分で考えるための材料を集めることが主旨です。
どうぞ皆さまのご参加をお待ちしております。
もしコチラへの書き込みが適切でない場合はどうぞ削除してください。
もうすぐ震災から9ヶ月。年も暮れに近づいてきました。
今だからこそ、放射能問題だけではなく、防災・医療・などなど
「暮らしの中の科学」についてわかりやすく学び考えていこうというコミュを作りました。
子育て中のパパ・ママ中心の関心事について取り扱って生きたいと思います。
「ママの勉強部屋」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5862191
危険・安全の判断ではなく
自分で考えるための材料を集めることが主旨です。
どうぞ皆さまのご参加をお待ちしております。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人