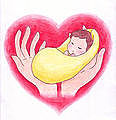|
|
|
|
コメント(7)
ニュースではありませんが、今朝、郡山市の保育園に
今のご事情をお伺いするために、
電話させていただきました。
以下、私の日記の一部をそのまま転載させていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「郡山市の園長さん」
今朝、福島の赤ちゃん、乳幼児が気になって
個別に保育園の先生に御事情を
伺ってみようと、電話した。
私がお電話した保育園の園長さんは
包容力のある経験豊富なドンとしたお母さん的な
印象だった。
以下、園長さんからお伺いした概要。
・この園では、ガイガーカウンターが支給されている。
ただし、ガンマ線しか測れない機種。
他園では、ガイガーを持っておられないところもあるので、
定期的に貸し出し、個別に測定をしている。
…基本的には、自分たちで測定し、その推移を
見守りながら、身の周りを気をつけてすごしている。
・今朝の放射能濃度は、外で1.17マイクロシーベルト(時間あたり)、
屋内で0.2マイクロシーベルト。
…これは、4月5日〜7日に測定した濃度より、
半分以下になっている。
危険性も認識しているが、こうして少しづつ
濃度が下がっている面も大事に見守って過ごしたい。
・避難しようというお母さんは、もう避難されている。
一方で、不安に思いながらも、ここで過ごすことを
選択しているお母さんもおり、
…そこは、お母さんたち一人ひとりの判断を
尊重するしかないということがある。
・園としては、子どもにとっては不満なところもあろうけど、
外遊びを控えめにしつつ、マスクをつけさせたりして
過ごしている。
水道水は、今は大丈夫とのこと。
…私の印象としては、
地元に根差したしっかり者の包容力あふれるお母さんが
その場で暮らす中で、できるだけ懸命に善処されている
様子がうかがえた。
ただ、片方で、
腰が重いんだな、という印象もあった。
「どうしてこの人たちは、
もっと放射能汚染について調べて
もっと危険性を認識して
もっと子どもたちに安全なために
実際に動こうとしないのか?」
…という私の個人的な疑問はとけはしなかったな。。。
危険ばかりに着目して、慌てさせようというのではない。
小さい子供たちがいるからこそ、
危険可能性をできる限り避けるセレクトをすべきと思うのだ。
ちなみに、
園長さんが説明してくださった、本日の放射能濃度
『外:1.17マイクロシーベルト
屋内:0.2マイクロシーベルト
(4月5日〜7日より半分以下)』
…は、もしこれが今後一定して続くという仮想のもとで計算すると、
『外:10ミリシーベルト
屋内:1.75ミリシーベルト(1年あたり)』
…ということになる。
これに加えて、3月中の放射能汚染が蓄積されているだろうから、
もう少し、年間被ばく量は増えるんちゃうかな…?
武田先生によると、成人の年間許容被ばく量は1ミリシーベルト、
0.1マイクロシーベルト以下なら安全に暮らしてよい、
0.6マイクロシーベルトを超えたら、そこは避けたほうがよい、
とのことだから。
…やっぱ、ちょっと、小さい子供には負担が大きすぎると思うんやけど。。
…私が現地にいたら、
間違いなく、できるだけ早く避難していたことだろう。
親や友達、あるいは園の先生方を説得して、
できるだけ知り合い、友達も一緒に避難するよう勧めていただろう。
今のご事情をお伺いするために、
電話させていただきました。
以下、私の日記の一部をそのまま転載させていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「郡山市の園長さん」
今朝、福島の赤ちゃん、乳幼児が気になって
個別に保育園の先生に御事情を
伺ってみようと、電話した。
私がお電話した保育園の園長さんは
包容力のある経験豊富なドンとしたお母さん的な
印象だった。
以下、園長さんからお伺いした概要。
・この園では、ガイガーカウンターが支給されている。
ただし、ガンマ線しか測れない機種。
他園では、ガイガーを持っておられないところもあるので、
定期的に貸し出し、個別に測定をしている。
…基本的には、自分たちで測定し、その推移を
見守りながら、身の周りを気をつけてすごしている。
・今朝の放射能濃度は、外で1.17マイクロシーベルト(時間あたり)、
屋内で0.2マイクロシーベルト。
…これは、4月5日〜7日に測定した濃度より、
半分以下になっている。
危険性も認識しているが、こうして少しづつ
濃度が下がっている面も大事に見守って過ごしたい。
・避難しようというお母さんは、もう避難されている。
一方で、不安に思いながらも、ここで過ごすことを
選択しているお母さんもおり、
…そこは、お母さんたち一人ひとりの判断を
尊重するしかないということがある。
・園としては、子どもにとっては不満なところもあろうけど、
外遊びを控えめにしつつ、マスクをつけさせたりして
過ごしている。
水道水は、今は大丈夫とのこと。
…私の印象としては、
地元に根差したしっかり者の包容力あふれるお母さんが
その場で暮らす中で、できるだけ懸命に善処されている
様子がうかがえた。
ただ、片方で、
腰が重いんだな、という印象もあった。
「どうしてこの人たちは、
もっと放射能汚染について調べて
もっと危険性を認識して
もっと子どもたちに安全なために
実際に動こうとしないのか?」
…という私の個人的な疑問はとけはしなかったな。。。
危険ばかりに着目して、慌てさせようというのではない。
小さい子供たちがいるからこそ、
危険可能性をできる限り避けるセレクトをすべきと思うのだ。
ちなみに、
園長さんが説明してくださった、本日の放射能濃度
『外:1.17マイクロシーベルト
屋内:0.2マイクロシーベルト
(4月5日〜7日より半分以下)』
…は、もしこれが今後一定して続くという仮想のもとで計算すると、
『外:10ミリシーベルト
屋内:1.75ミリシーベルト(1年あたり)』
…ということになる。
これに加えて、3月中の放射能汚染が蓄積されているだろうから、
もう少し、年間被ばく量は増えるんちゃうかな…?
武田先生によると、成人の年間許容被ばく量は1ミリシーベルト、
0.1マイクロシーベルト以下なら安全に暮らしてよい、
0.6マイクロシーベルトを超えたら、そこは避けたほうがよい、
とのことだから。
…やっぱ、ちょっと、小さい子供には負担が大きすぎると思うんやけど。。
…私が現地にいたら、
間違いなく、できるだけ早く避難していたことだろう。
親や友達、あるいは園の先生方を説得して、
できるだけ知り合い、友達も一緒に避難するよう勧めていただろう。
たんぽぽ舎より転記:
福島県教職員組合の教育委員会宛要請書と「放射線による健康被害から
子どもたちを守るための具体的措置の要請」と「放射線による健康被害から
子どもたちを守る県教組声明」を送ります。
2011年4月26日
福島県教育委員会
教育委員長 鈴木 芳喜 様
教育長 遠藤 俊博 様
福島県教職員組合
中央執行委員長 竹中 柳一
放射線による健康被害から子どもたちを守るための具体的措置の要請
東日本大震災及び原発事故から、子どもたち及び教職員の安全確保に努力され
ていることに感謝申し上げます。
文部科学省は4月19日、「学校等の校舎・校庭等の利用判断に係る暫定的考え方」
を示しました。学校現場及び保護者からは、「本当にこの基準で大丈夫なのか」
「これでは子どもたちの健康を守れない」といった不安の声が多く出されています。
県教組は20日「放射線による健康被害から子どもたちを守るための県教組声明」
を発し、今回の基準を直ちに撤回し、子どもの健康を第一にした安全策を示すと
ともに、子どもたちの受ける線量を減らすための具体的な対策を示し早急に実施
することを訴えています。
現在、多くの子どもたちは、通常値を大きく超える放射線量の中での生活しています。
県教育委員会は、福島県内の学校現場の実態を直視し、文科省の示した基準よりも
厳しく状況を受け止め、将来にわたり、子どもたちの健康に絶対に影響がないと
いいきれる安全策を示し、具体的措置を早急に講ずるよう以下の点について強く
要請します。
福島県教職員組合の教育委員会宛要請書と「放射線による健康被害から
子どもたちを守るための具体的措置の要請」と「放射線による健康被害から
子どもたちを守る県教組声明」を送ります。
2011年4月26日
福島県教育委員会
教育委員長 鈴木 芳喜 様
教育長 遠藤 俊博 様
福島県教職員組合
中央執行委員長 竹中 柳一
放射線による健康被害から子どもたちを守るための具体的措置の要請
東日本大震災及び原発事故から、子どもたち及び教職員の安全確保に努力され
ていることに感謝申し上げます。
文部科学省は4月19日、「学校等の校舎・校庭等の利用判断に係る暫定的考え方」
を示しました。学校現場及び保護者からは、「本当にこの基準で大丈夫なのか」
「これでは子どもたちの健康を守れない」といった不安の声が多く出されています。
県教組は20日「放射線による健康被害から子どもたちを守るための県教組声明」
を発し、今回の基準を直ちに撤回し、子どもの健康を第一にした安全策を示すと
ともに、子どもたちの受ける線量を減らすための具体的な対策を示し早急に実施
することを訴えています。
現在、多くの子どもたちは、通常値を大きく超える放射線量の中での生活しています。
県教育委員会は、福島県内の学校現場の実態を直視し、文科省の示した基準よりも
厳しく状況を受け止め、将来にわたり、子どもたちの健康に絶対に影響がないと
いいきれる安全策を示し、具体的措置を早急に講ずるよう以下の点について強く
要請します。
記
1. 福島県として子どもを放射線の健康被害から守るため、より厳しい基準と、
子どもたちの受ける線量を減らすための具体的な対策を早急に示すこと。
(1) 年間20mSv、毎時3.8μSvとした文部科学省の基準を撤回するよう上申すること。
(2) 子どもたちは、学習で土をいじり校庭を走り回ります。舞い上がった砂ぼこりを
吸い込むことは避けられません。また、転んで皮膚をすりむけば、そこに
放射性物質が付着します。このような場合の科学的データを示すこと。
子どもたちの行動を具体的に捉え、外部被ばく、内部被ばくの危険性を回避し
将来にわたる健康を守る観点から、県独自でより低い基準値を定め、子どもたちの
受ける線量を減らすための具体的な対策を早急に講ずること。
(3) 各学校毎に、専門的機関による敷地内及び通学路の詳しい放射線量の測定
と、「福島第一原発汚染マップ」同様の学校版放射線量マップを早急に作成し、
保護者・地域に公表すること。
(4) 放射線量の高い土壌の入れ替え、除染措置を行うなど、放射線量を減らす
万全の対策を講ずること。
(5) 放射線量の高い学校での授業は行わず、休校もしくは、放射線量の低い地
域への移転など、子どもたちの受ける線量を減らすため具体策を講じること。
2. 全ての学校に放射線量測定器を早急に配布すること。各学校における
放射線量測定についての統一的な測定マニュアルを示すこと。
(1) 学校版放射線量マップを基に、子どもの活動場所、及び敷地内の放射線量
が高い箇所で定時に測定し、結果を掲示し公表すること。また、積算値も公表す
ること。その場合、空間線量のみならず、地面から1cmの放射線量も測定すること。
(2) たとえば、地面から1cmでの放射線量が3.8μSv/hを越えるホットスポット
を立ち入り禁止区域とし、子どもたちが放射線を受けない対策を講じること。
3. 子どもたちを放射線による健康被害から守るため、教職員が指導し
行うべき安全対応マニュアルを早急に示すこと。
(1) 県教委がこれまでに示している、日常生活における注意事項を徹底させること。
(2) 放射線量の高いところでの活動は絶対行わないこと。
(3) 花壇の整備、栽培活動を行う場合は、直接土に触れないよう、全員にゴム
手袋の着用させること。
(4) 屋外活動では、内部被ばくの危険性を無くすため、マスクを着用させること。
また、活動時間の制限をし、受ける線量を減らすための具体的対策を講ずること。
(5) 屋外での部活動及び体育の学習活動では、土埃の上がらないように配慮す
ること、土埃が上がる状況の中では活動を中止し退避するなど、具体的な対応を
取ること。
(6) マスク及びゴム手袋等は公費で負担すること。
4. 放射線量が高くなる危険性が生じたときの対応について、明確にすること。
(1) 学校現場にすみやかな情報が送られるように、情報網を整備すること。
(2) 緊急時にすみやかな対応ができるよう、指示系統を明確にすること。
(3) 緊急時に、教職員が子どもたちに行う安全対策について明確にすること。
(4) 緊急時に、保護者との連絡、対応について明確にすること。
(5) 安全確認、学校からの退避についての判断、指示系統を明確にすること。
5. 子ども、教職員を放射能による健康被害から守るため、福島県教職員組合
との協議を継続して行うこと。また、子どもたちの安全を守るために、県教育委
員会に寄せられる意見・要望について公開し、県民が安心できる対応策について
様々な観点から専門家の意見も踏まえなから検討し具体策を講ずること。
以上
1. 福島県として子どもを放射線の健康被害から守るため、より厳しい基準と、
子どもたちの受ける線量を減らすための具体的な対策を早急に示すこと。
(1) 年間20mSv、毎時3.8μSvとした文部科学省の基準を撤回するよう上申すること。
(2) 子どもたちは、学習で土をいじり校庭を走り回ります。舞い上がった砂ぼこりを
吸い込むことは避けられません。また、転んで皮膚をすりむけば、そこに
放射性物質が付着します。このような場合の科学的データを示すこと。
子どもたちの行動を具体的に捉え、外部被ばく、内部被ばくの危険性を回避し
将来にわたる健康を守る観点から、県独自でより低い基準値を定め、子どもたちの
受ける線量を減らすための具体的な対策を早急に講ずること。
(3) 各学校毎に、専門的機関による敷地内及び通学路の詳しい放射線量の測定
と、「福島第一原発汚染マップ」同様の学校版放射線量マップを早急に作成し、
保護者・地域に公表すること。
(4) 放射線量の高い土壌の入れ替え、除染措置を行うなど、放射線量を減らす
万全の対策を講ずること。
(5) 放射線量の高い学校での授業は行わず、休校もしくは、放射線量の低い地
域への移転など、子どもたちの受ける線量を減らすため具体策を講じること。
2. 全ての学校に放射線量測定器を早急に配布すること。各学校における
放射線量測定についての統一的な測定マニュアルを示すこと。
(1) 学校版放射線量マップを基に、子どもの活動場所、及び敷地内の放射線量
が高い箇所で定時に測定し、結果を掲示し公表すること。また、積算値も公表す
ること。その場合、空間線量のみならず、地面から1cmの放射線量も測定すること。
(2) たとえば、地面から1cmでの放射線量が3.8μSv/hを越えるホットスポット
を立ち入り禁止区域とし、子どもたちが放射線を受けない対策を講じること。
3. 子どもたちを放射線による健康被害から守るため、教職員が指導し
行うべき安全対応マニュアルを早急に示すこと。
(1) 県教委がこれまでに示している、日常生活における注意事項を徹底させること。
(2) 放射線量の高いところでの活動は絶対行わないこと。
(3) 花壇の整備、栽培活動を行う場合は、直接土に触れないよう、全員にゴム
手袋の着用させること。
(4) 屋外活動では、内部被ばくの危険性を無くすため、マスクを着用させること。
また、活動時間の制限をし、受ける線量を減らすための具体的対策を講ずること。
(5) 屋外での部活動及び体育の学習活動では、土埃の上がらないように配慮す
ること、土埃が上がる状況の中では活動を中止し退避するなど、具体的な対応を
取ること。
(6) マスク及びゴム手袋等は公費で負担すること。
4. 放射線量が高くなる危険性が生じたときの対応について、明確にすること。
(1) 学校現場にすみやかな情報が送られるように、情報網を整備すること。
(2) 緊急時にすみやかな対応ができるよう、指示系統を明確にすること。
(3) 緊急時に、教職員が子どもたちに行う安全対策について明確にすること。
(4) 緊急時に、保護者との連絡、対応について明確にすること。
(5) 安全確認、学校からの退避についての判断、指示系統を明確にすること。
5. 子ども、教職員を放射能による健康被害から守るため、福島県教職員組合
との協議を継続して行うこと。また、子どもたちの安全を守るために、県教育委
員会に寄せられる意見・要望について公開し、県民が安心できる対応策について
様々な観点から専門家の意見も踏まえなから検討し具体策を講ずること。
以上
放射線による健康被害から子どもたちを守る県教組声明
福島原発の大事故以降、放射線量が極めて高い状態が続いています。私たちは、
放射線による健康被害から子どもたちを守るために、福島県教育委員会及び文部
科学省に対し、安全対策についての指針とマニュアルの提示を強く求めてきました。
大事故から一ヶ月が経過した4月19日、ようやく文部科学省は「学校等の校舎・
校庭等の利用判断に係る暫定的考え方」を示しました。学校現場及び保護者からは、
「本当にこの基準で大丈夫なのか」「子どもたちに影響はないのか」といった
不安の声が多く出されています。
文部科学省は、原子力災害対策本部の示した「ICRP(国際放射線防護委員会)の
示す『非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル』1 - 20mSv/yを
暫定的な目安」を、一般公衆レベルのまま学校での判断基準としました。ICRPが
示している現行の規制値は1mSv/yです。これをはるかに超え、一般公衆レベルの
上限でとされる20mSv/yは、計画的避難地域を設定する基準量でもあり、放射線
業務従事者の年間平均許容量(ICRP 1990年勧告)に匹敵します。放射線に対する
リスクが大きい子どもたちにこの基準を適用することは、長年の生活の中での
累積値は相当に大きくなり、子どもたちの命と健康を守ることはできません。
また、子どもたちが校庭等で活動できる制限値を3.8μSv/h未満としていますが、
学校等の敷地内の放射線量は一定ではなく、側溝や雨樋の下、塵や木の葉などが
集まる吹きだまり、水たまりなどの窪地などは比較的高く、校庭など地面は空間
放射線量より高くなっています。子どもたちは、学習で土をいじり、校庭を走り
回ります。舞い上がった砂ぼこりを吸い込むことは避けられません。また、転んで
皮膚をすりむけば、そこに放射性物質が付着します。空間線量が3.8μSv/h未満で
あっても、実際は空間線量より高い放射線を浴びることとなります。さらに、
内部被ばくの危険性もあります。
文部科学省の示した暫定基準は、子どもたちが学校生活をする上では極めて
危険な基準といわざるを得ません。文部科学省は、今回の基準を直ちに撤回し、
子どもの健康を第一にした安全策を示すべきです。また、福島県災害対策本部
及び福島県教育委員会は、子ども及び保護者が安心できるように、全ての学校
施設及び通学路において放射線量の高いところを明確にした放射線量マップを
作成し、立ち入り禁止区域を設けるなど万全の対策を講ずることを強く要求します。
さらに、子どもたちの受ける線量を減らすための具体的な対策を示し、土壌の
入れ替え等の措置を早急に講ずることを要求します。
私たちは、子どもたちを放射線による健康被害から守るため、一刻も早い原発
事故の収束と安全確認を強く求めると共に、現在の通常値を大きく超える中での
子どもたちの生活について、「直ちに健康に影響がない」というのではなく、
絶対に健康に影響がないといいきれる安全策を早急に示し実施することを強く
要求するものです。
2011年4月20日
福島県教職員組合
中央執行委員長 竹中 柳一
福島原発の大事故以降、放射線量が極めて高い状態が続いています。私たちは、
放射線による健康被害から子どもたちを守るために、福島県教育委員会及び文部
科学省に対し、安全対策についての指針とマニュアルの提示を強く求めてきました。
大事故から一ヶ月が経過した4月19日、ようやく文部科学省は「学校等の校舎・
校庭等の利用判断に係る暫定的考え方」を示しました。学校現場及び保護者からは、
「本当にこの基準で大丈夫なのか」「子どもたちに影響はないのか」といった
不安の声が多く出されています。
文部科学省は、原子力災害対策本部の示した「ICRP(国際放射線防護委員会)の
示す『非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル』1 - 20mSv/yを
暫定的な目安」を、一般公衆レベルのまま学校での判断基準としました。ICRPが
示している現行の規制値は1mSv/yです。これをはるかに超え、一般公衆レベルの
上限でとされる20mSv/yは、計画的避難地域を設定する基準量でもあり、放射線
業務従事者の年間平均許容量(ICRP 1990年勧告)に匹敵します。放射線に対する
リスクが大きい子どもたちにこの基準を適用することは、長年の生活の中での
累積値は相当に大きくなり、子どもたちの命と健康を守ることはできません。
また、子どもたちが校庭等で活動できる制限値を3.8μSv/h未満としていますが、
学校等の敷地内の放射線量は一定ではなく、側溝や雨樋の下、塵や木の葉などが
集まる吹きだまり、水たまりなどの窪地などは比較的高く、校庭など地面は空間
放射線量より高くなっています。子どもたちは、学習で土をいじり、校庭を走り
回ります。舞い上がった砂ぼこりを吸い込むことは避けられません。また、転んで
皮膚をすりむけば、そこに放射性物質が付着します。空間線量が3.8μSv/h未満で
あっても、実際は空間線量より高い放射線を浴びることとなります。さらに、
内部被ばくの危険性もあります。
文部科学省の示した暫定基準は、子どもたちが学校生活をする上では極めて
危険な基準といわざるを得ません。文部科学省は、今回の基準を直ちに撤回し、
子どもの健康を第一にした安全策を示すべきです。また、福島県災害対策本部
及び福島県教育委員会は、子ども及び保護者が安心できるように、全ての学校
施設及び通学路において放射線量の高いところを明確にした放射線量マップを
作成し、立ち入り禁止区域を設けるなど万全の対策を講ずることを強く要求します。
さらに、子どもたちの受ける線量を減らすための具体的な対策を示し、土壌の
入れ替え等の措置を早急に講ずることを要求します。
私たちは、子どもたちを放射線による健康被害から守るため、一刻も早い原発
事故の収束と安全確認を強く求めると共に、現在の通常値を大きく超える中での
子どもたちの生活について、「直ちに健康に影響がない」というのではなく、
絶対に健康に影響がないといいきれる安全策を早急に示し実施することを強く
要求するものです。
2011年4月20日
福島県教職員組合
中央執行委員長 竹中 柳一
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90060人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人