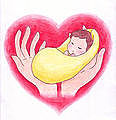|
|
|
|
コメント(57)
(これは、むしろ東海の原発からの放射能を監視する目的で設置されたようですが)を除いて、あまりに観測地点の密度が低すぎます。特に、放射性降下物の測定地点は全く不足しており、体内被曝の影響を正確に評価するのは不可能です。II章で議論したように、新宿でかなり高い値が出ていますが、これは新宿がたまたまホットスポットだったのかもしれませんし、逆に首都圏でももっと汚染が激しいところがあるのかもしれません。自分が住んでいるところがたまたまホットスポットになってしまうと、発表されたデータが低くても被曝が大きくなってしまいます。原発事故による健康被害のリスクの評価は、観測地点の密度を増やさないと本当のところは何も言えないのではないかと思います。(距離が離れるほど拡散が効いてくるので、たとえば首都圏あたりでは数キロおきに計測する必要は無いかもしれません。しかし、いずれにせよ現在の体制では観測地点があまりに少なすぎます。)
一方で、首都圏でも農作物からの放射能の検出がいくつも報告されています。農作物が汚染されているということは、上で議論したように、放射性降下物があったと言うことですから、これからしても広い地域で汚染が進んでいることがわかります。(少なくとも、たまたま新宿だけが汚染されているということはあり得ない。もちろん、もともとそういう事は非常に考えづらいわけですが。)逆に、放射性降下物があれば、農作物の被害は当然予想されるはずですから、出荷してから検出して騒動になるより、放射性降下物観測の密度を増やし、先手を打って農作物の検査と対策をすべきです。
逆に、たとえば福島県内でも、会津地方は現時点では比較的被害が少ないと思われます。むしろ首都圏より汚染が小さいくらいではないでしょうか?(単なる私の想像で、データはありません。ご存知の方、教えてください。)会津地方の農作物が、もし汚染がないのに出荷停止等されるとすれば、それこそ風評被害ではないでしょうか。(実際に汚染されているものについては、「風評被害」とは言えません。)ともかく観測地点の増加による正確な汚染状況の把握と、農作物のスクリーニングの厳格化、および両者の連携を行うべきだと考えます。
一方で、首都圏でも農作物からの放射能の検出がいくつも報告されています。農作物が汚染されているということは、上で議論したように、放射性降下物があったと言うことですから、これからしても広い地域で汚染が進んでいることがわかります。(少なくとも、たまたま新宿だけが汚染されているということはあり得ない。もちろん、もともとそういう事は非常に考えづらいわけですが。)逆に、放射性降下物があれば、農作物の被害は当然予想されるはずですから、出荷してから検出して騒動になるより、放射性降下物観測の密度を増やし、先手を打って農作物の検査と対策をすべきです。
逆に、たとえば福島県内でも、会津地方は現時点では比較的被害が少ないと思われます。むしろ首都圏より汚染が小さいくらいではないでしょうか?(単なる私の想像で、データはありません。ご存知の方、教えてください。)会津地方の農作物が、もし汚染がないのに出荷停止等されるとすれば、それこそ風評被害ではないでしょうか。(実際に汚染されているものについては、「風評被害」とは言えません。)ともかく観測地点の増加による正確な汚染状況の把握と、農作物のスクリーニングの厳格化、および両者の連携を行うべきだと考えます。
IV. 現時点での被害が事故の全貌か?
原発事故は現在も進行中です。放水作業の一応の成功で事態は収まったかに見えるかもしれませんが、それは単に「差し迫った危機の一部を回避した」だけで、事故全体が収束したとはとても言えない状況です。実際、II章で議論したように、放射能汚染の拡大と言う点では、東京消防庁の放水作業後の 3/21から、むしろ悪化しています。原子炉がコントロールされたと言えない状況で、また高濃度の放射能の排出が防げていない現状では、今後も放射能汚染が拡大する可能性がかなりあります。それがどの程度深刻かはわかりません。たとえ、ある地点での現時点までの汚染が大したことないとしても、今後についてはわかりません。
科学者による事故の分析としては、たとえば、カリフォルニア大学サンタバーバラ校におけるMonreal氏の講演スライド
http://online.itp.ucsb.edu/online/plecture/bmonreal11/
が有志科学者によって和訳もされ、多くの方に広まっています。
http://ribf.riken.jp/~koji/jishin/zhen_zai.html
この内容には私個人としてはいくつか異論がありますが、少なくとも現時点で明らかなこととして、講演での被害の見積は楽観的に過ぎたということは言えると思います。仮に講演時点での見積は正しかったとしても、講演ではその後の被害の拡大について予見していません。たとえば、17ページ(ページ数は翻訳版に準拠)で茨城県東海村での放射線強度がすぐに下がった記述がありますが、21日以後は空気中線量もなかなか下がりませんでした。この際にはII節で新宿について議論した以上に、この地域は放射性降下物によって汚染され、農作物や水道にも被害が出ています。翻訳された方々は研究者として尊敬できる方ばかりで、また善意からなさったことだと思いますが、敢えて申し上げますと、結果的には楽観的すぎる見方を広めてしまったことにはならないでしょうか。(もちろん、翻訳は翻訳であり、翻訳者の意見と内容は別であること、また仮に内容が間違っていたとしても一つの情報提供として意味があること、などは理解しています。)現状では(まだ)チェルノブイリ未満であると私も思いますが、スリーマイルアイランドよりはむしろチェルノブイリに近い状況ではないかと考えます。[4/12 追記:原子力安全・保安院もついに福島原発事故がINESレベル7相当の事故であることを認めました。過去にレベル7とされた事故はチェルノブイリのみです。4/12現在ではまだチェルノブイリより小規模とは言え、チェルノブイリと大きく異なるとは既に言えません。]スリーマイルアイランドだと思って油断するよりは、チェルノブイリの可能性を覚悟して準備し、それが空振りであれば笑って喜ぶ、方が良いのではないでしょうか。
V. LNT・ICRP勧告で十分か? リスクの見積もり
I節で議論したように、現在のところ、放射線防護は国際的にもICRP勧告をベースに行われており、その背景にはLNTモデルがあります。原発事故等の場合にも、これらを基準にリスクを見積もるのが標準的ですが、それで正しいことが立証されているわけではありません。楽観的・悲観的なさまざまな見方があるようです。
1.) 低線量被曝と発がんリスク
2009年の時点で、ほぼ中立的な立場と思われるレビュー記事が以下にあります。
Assessing cancer risks of low-dose radiation
L. Mullenders et al. Nature Reviews Cancer 9, 596-604 (August 2009)
http://www.nature.com/nrc/journal/v9/n8/abs/nrc2677.html
このレビューの内容を一言でまとめると、結局いろいろな議論があり、低線量被曝による発がんリスクについては現状では良くわからない部分が多い。LNTを放棄するほどの強い材料はない、ということのようです。安全サイドに立つなら、やはり最低限LNTは仮定するべきでしょう。
原発事故は現在も進行中です。放水作業の一応の成功で事態は収まったかに見えるかもしれませんが、それは単に「差し迫った危機の一部を回避した」だけで、事故全体が収束したとはとても言えない状況です。実際、II章で議論したように、放射能汚染の拡大と言う点では、東京消防庁の放水作業後の 3/21から、むしろ悪化しています。原子炉がコントロールされたと言えない状況で、また高濃度の放射能の排出が防げていない現状では、今後も放射能汚染が拡大する可能性がかなりあります。それがどの程度深刻かはわかりません。たとえ、ある地点での現時点までの汚染が大したことないとしても、今後についてはわかりません。
科学者による事故の分析としては、たとえば、カリフォルニア大学サンタバーバラ校におけるMonreal氏の講演スライド
http://online.itp.ucsb.edu/online/plecture/bmonreal11/
が有志科学者によって和訳もされ、多くの方に広まっています。
http://ribf.riken.jp/~koji/jishin/zhen_zai.html
この内容には私個人としてはいくつか異論がありますが、少なくとも現時点で明らかなこととして、講演での被害の見積は楽観的に過ぎたということは言えると思います。仮に講演時点での見積は正しかったとしても、講演ではその後の被害の拡大について予見していません。たとえば、17ページ(ページ数は翻訳版に準拠)で茨城県東海村での放射線強度がすぐに下がった記述がありますが、21日以後は空気中線量もなかなか下がりませんでした。この際にはII節で新宿について議論した以上に、この地域は放射性降下物によって汚染され、農作物や水道にも被害が出ています。翻訳された方々は研究者として尊敬できる方ばかりで、また善意からなさったことだと思いますが、敢えて申し上げますと、結果的には楽観的すぎる見方を広めてしまったことにはならないでしょうか。(もちろん、翻訳は翻訳であり、翻訳者の意見と内容は別であること、また仮に内容が間違っていたとしても一つの情報提供として意味があること、などは理解しています。)現状では(まだ)チェルノブイリ未満であると私も思いますが、スリーマイルアイランドよりはむしろチェルノブイリに近い状況ではないかと考えます。[4/12 追記:原子力安全・保安院もついに福島原発事故がINESレベル7相当の事故であることを認めました。過去にレベル7とされた事故はチェルノブイリのみです。4/12現在ではまだチェルノブイリより小規模とは言え、チェルノブイリと大きく異なるとは既に言えません。]スリーマイルアイランドだと思って油断するよりは、チェルノブイリの可能性を覚悟して準備し、それが空振りであれば笑って喜ぶ、方が良いのではないでしょうか。
V. LNT・ICRP勧告で十分か? リスクの見積もり
I節で議論したように、現在のところ、放射線防護は国際的にもICRP勧告をベースに行われており、その背景にはLNTモデルがあります。原発事故等の場合にも、これらを基準にリスクを見積もるのが標準的ですが、それで正しいことが立証されているわけではありません。楽観的・悲観的なさまざまな見方があるようです。
1.) 低線量被曝と発がんリスク
2009年の時点で、ほぼ中立的な立場と思われるレビュー記事が以下にあります。
Assessing cancer risks of low-dose radiation
L. Mullenders et al. Nature Reviews Cancer 9, 596-604 (August 2009)
http://www.nature.com/nrc/journal/v9/n8/abs/nrc2677.html
このレビューの内容を一言でまとめると、結局いろいろな議論があり、低線量被曝による発がんリスクについては現状では良くわからない部分が多い。LNTを放棄するほどの強い材料はない、ということのようです。安全サイドに立つなら、やはり最低限LNTは仮定するべきでしょう。
2.) 原発とリスク
今回の福島原発事故も含め、リスクの見積もりは、被曝線量を推定してそれに基づいて行われています。この文書でも、その枠組の中で議論して来ました。(それ以外に定量的なリスク推定の手法がないからでもありますが。)
事故がない場合の通常運転時の原発では、空気中線量が定められた環境基準以下であることになっています。その環境基準は、健康に影響を与えないはずである水準に設定されています。たとえば、ドイツでは、原発による一般市民の被曝は 0.3 mSv/年以下に規制されています。これは、自然に存在する 1.4 mSv/年(ドイツの平均)よりも小さく、ICRP勧告による一般公衆の被曝限度(1 mSv/年)よりも小さい値で、何の問題もなさそうです。また、実際には、この基準値よりも被曝ははるかに小さいと見積もられています。そうすると、「理論的」には原発が健康に与える影響は無視できるはずです。(もちろん、事故の無い場合の話です。)しかし、ドイツでの大規模な研究の結果、原発付近では子供の発がん率が有意に上昇したと言う統計的な結果が得られています。これは一つの原発についてではなく、いくつもの原発についての統計データの綿密な解析です。
Case-control study on childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants in Germany 1980-2003.
C. Spix et al., Eur J Cancer 44(2):275-84 (2008).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18082395
Leukaemia in young children living in the vicinity of German nuclear power plants.
P. Kaatsch et al., Int. J. Cancer 122(4):721-6 (2008).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18067131
後者の Kaatch et al., Int J. Cancer より主要な結果を示す TABLE IV と TABLE V を以下に引用します。原発から5km以内に住んでいる子供の白血病(leukaemia)の発症率が2倍程度に増加し、95%の信頼区間でも1.5倍以上になると言う結論です。
この結果からは、標準的な被曝リスクの見積もりは不十分であることが懸念されます。何故このような影響が生じるかは良くわかりません。個人的には、空気中線量が小さくても、放出された微量の放射性物質を体内に取り込んだ内部被曝の効果によるものではないかと想像します。II節で、実効線量係数を用いた内部被曝の推定を紹介しましたが、これもある種の仮説であって、実際のリスクはそれ以上である可能性もあります。いずれにせよ、理由がよくわからないからと言ってリスクの存在が否定されるわけではありません。
もちろん、これは一つの報告(論文)であって、それだけで何かが確定するわけではないことは研究者ならば誰でも知っていることです。しかし、リスクを考える上では見過ごせない報告です。この結果を見ても、「◯◯ mSv以下の被曝なら無害」とは簡単には言えません。
3.) チェルノブイリ事故の健康被害
史上最悪のチェルノブイリ事故の健康被害について、WHO・IAEA等の公式見解では、事故による死者数の増加は、せいぜい数千人のオーダーだと言うことになっているようです。
2003-2005の調査に基づく“Chernobyl Forum”のレポート:
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf
2008年のUNSCEARのレポート:
http://www.unscear.org/docs/reports/2008/Advance_copy_Annex_D_Chernobyl_Report.pdf
今回の福島原発事故も含め、リスクの見積もりは、被曝線量を推定してそれに基づいて行われています。この文書でも、その枠組の中で議論して来ました。(それ以外に定量的なリスク推定の手法がないからでもありますが。)
事故がない場合の通常運転時の原発では、空気中線量が定められた環境基準以下であることになっています。その環境基準は、健康に影響を与えないはずである水準に設定されています。たとえば、ドイツでは、原発による一般市民の被曝は 0.3 mSv/年以下に規制されています。これは、自然に存在する 1.4 mSv/年(ドイツの平均)よりも小さく、ICRP勧告による一般公衆の被曝限度(1 mSv/年)よりも小さい値で、何の問題もなさそうです。また、実際には、この基準値よりも被曝ははるかに小さいと見積もられています。そうすると、「理論的」には原発が健康に与える影響は無視できるはずです。(もちろん、事故の無い場合の話です。)しかし、ドイツでの大規模な研究の結果、原発付近では子供の発がん率が有意に上昇したと言う統計的な結果が得られています。これは一つの原発についてではなく、いくつもの原発についての統計データの綿密な解析です。
Case-control study on childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants in Germany 1980-2003.
C. Spix et al., Eur J Cancer 44(2):275-84 (2008).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18082395
Leukaemia in young children living in the vicinity of German nuclear power plants.
P. Kaatsch et al., Int. J. Cancer 122(4):721-6 (2008).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18067131
後者の Kaatch et al., Int J. Cancer より主要な結果を示す TABLE IV と TABLE V を以下に引用します。原発から5km以内に住んでいる子供の白血病(leukaemia)の発症率が2倍程度に増加し、95%の信頼区間でも1.5倍以上になると言う結論です。
この結果からは、標準的な被曝リスクの見積もりは不十分であることが懸念されます。何故このような影響が生じるかは良くわかりません。個人的には、空気中線量が小さくても、放出された微量の放射性物質を体内に取り込んだ内部被曝の効果によるものではないかと想像します。II節で、実効線量係数を用いた内部被曝の推定を紹介しましたが、これもある種の仮説であって、実際のリスクはそれ以上である可能性もあります。いずれにせよ、理由がよくわからないからと言ってリスクの存在が否定されるわけではありません。
もちろん、これは一つの報告(論文)であって、それだけで何かが確定するわけではないことは研究者ならば誰でも知っていることです。しかし、リスクを考える上では見過ごせない報告です。この結果を見ても、「◯◯ mSv以下の被曝なら無害」とは簡単には言えません。
3.) チェルノブイリ事故の健康被害
史上最悪のチェルノブイリ事故の健康被害について、WHO・IAEA等の公式見解では、事故による死者数の増加は、せいぜい数千人のオーダーだと言うことになっているようです。
2003-2005の調査に基づく“Chernobyl Forum”のレポート:
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf
2008年のUNSCEARのレポート:
http://www.unscear.org/docs/reports/2008/Advance_copy_Annex_D_Chernobyl_Report.pdf
しかし、実際の被害ははるかに大きいと言う議論もいくつもあります。その代表例として、
Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment
Alexey V. Yablokov (Center for Russian Environmental Policy, Moscow, Russia), Vassily B. Nesterenko, and Alexey V. Nesterenko (Institute of Radiation Safety, Minsk, Belarus). Consulting Editor Janette D. Sherman-Nevinger (Environmental Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan).
Annals of the New York Academy of Sciences
Volume 1181, December 2009
http://www.nyas.org/publications/annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1
を挙げておきます。これは、ロシアと白ロシアの研究者が現地での研究をまとめたものです。WHO/IAEAの推定の問題点としていくつもの指摘がされています。たとえば、実際の被曝量、特に内部被曝の推定が難しく、WHO/IAEAの議論が準拠している仮定の正当性は全く明らかでないことが指摘されています。また、放射性物質を体内に取り込んだ場合の内部被曝の影響は科学的に明らかになっていないことも指摘されています。II節で紹介した実効線量係数による議論は、あくまでも一つの仮説です。同じ放射線量であれば体外被曝も体内被曝も影響は同じはずだと言う議論もありますが、これも乱暴な議論と言うべきです。たとえば、体内に取り込まれた放射性物質が特定の組織に固定されてしまった場合、その周囲の細胞は非常に強く被曝すると考えられます。このような場合の健康への影響は十分理解されているとは言えません。
そこで、上記文献で Yablokovらは、実際に各地域でどのような病気や健康問題が生じたか、そしてそれが放射性物質による汚染状況やタイミングとどのように相関しているか、を調べ事故による健康被害を推定しています。(状況は大きく異なりますが、上記 2.)節のドイツの原発周囲における小児の発がん確率の調査とアプローチとしては似ています。)
いくつかの例を以下にあげます。
(引用図)
経済的・社会的状況が同様の地域で、汚染状況により事故後の子どもの疾病率が大きく異なることが示されています。
また、現地の研究ではありませんが、上記文献で紹介されている興味深い結果をちあげておきます。チェルノブイリから2000km以上離れた英国ウェールズで、Sr-90による土壌汚染が確認されています。この土壌汚染の経年変化と、1500g以下の低体重児の出産率の変化をプロットしたものが以下です。二つのデータが相関していることは明らかに見えます。
(引用図)
Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment
Alexey V. Yablokov (Center for Russian Environmental Policy, Moscow, Russia), Vassily B. Nesterenko, and Alexey V. Nesterenko (Institute of Radiation Safety, Minsk, Belarus). Consulting Editor Janette D. Sherman-Nevinger (Environmental Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan).
Annals of the New York Academy of Sciences
Volume 1181, December 2009
http://www.nyas.org/publications/annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1
を挙げておきます。これは、ロシアと白ロシアの研究者が現地での研究をまとめたものです。WHO/IAEAの推定の問題点としていくつもの指摘がされています。たとえば、実際の被曝量、特に内部被曝の推定が難しく、WHO/IAEAの議論が準拠している仮定の正当性は全く明らかでないことが指摘されています。また、放射性物質を体内に取り込んだ場合の内部被曝の影響は科学的に明らかになっていないことも指摘されています。II節で紹介した実効線量係数による議論は、あくまでも一つの仮説です。同じ放射線量であれば体外被曝も体内被曝も影響は同じはずだと言う議論もありますが、これも乱暴な議論と言うべきです。たとえば、体内に取り込まれた放射性物質が特定の組織に固定されてしまった場合、その周囲の細胞は非常に強く被曝すると考えられます。このような場合の健康への影響は十分理解されているとは言えません。
そこで、上記文献で Yablokovらは、実際に各地域でどのような病気や健康問題が生じたか、そしてそれが放射性物質による汚染状況やタイミングとどのように相関しているか、を調べ事故による健康被害を推定しています。(状況は大きく異なりますが、上記 2.)節のドイツの原発周囲における小児の発がん確率の調査とアプローチとしては似ています。)
いくつかの例を以下にあげます。
(引用図)
経済的・社会的状況が同様の地域で、汚染状況により事故後の子どもの疾病率が大きく異なることが示されています。
また、現地の研究ではありませんが、上記文献で紹介されている興味深い結果をちあげておきます。チェルノブイリから2000km以上離れた英国ウェールズで、Sr-90による土壌汚染が確認されています。この土壌汚染の経年変化と、1500g以下の低体重児の出産率の変化をプロットしたものが以下です。二つのデータが相関していることは明らかに見えます。
(引用図)
チェルノブイリ事故の後、周辺地域で多くの疾病や健康問題が報告されました. IAEA/WHO等の見解では、これらの問題の大部分は、放射線・放射性物質による直接の被害ではなく、ソ連崩壊に伴う社会の混乱や、「心理的問題」によるものとされています。しかし、標準的な放射線のリスク評価は、チェルノブイリ事故に関しては不明点が大きい「被曝線量の推定」と、主に広島・長崎での調査に立脚した「被曝線量と発がん率の相関」の両者に依存しています。後者の相関についても、さまざまな核種の内部被曝によるリスクを十分評価していない可能性があります。この問題は、2.)節で議論したドイツでの原発周囲の小児発がん率の上昇にも関係します。また、社会の混乱や「心理的問題」が健康被害をもたらしたと言う因果関係の定量的な検証は全く無いようです。私には、Yablokovらの議論の方がはるかに説得力を持っているように思えます。少なくとも、放射線被曝による健康被害には不確定性が大きく、下限はWHO/IAEAの評価で与えられるにせよ、上限は例えばYablokovらの推定に相当するのではないでしょうか?不確定性が大きく、また社会への影響が非常に巨大な問題で、リスクの下限のみに着目して上限を無視すると言うのは極めて無責任であると考えます。
このように、原発事故の際のリスクの評価には、標準的な被曝線量の推定とLNTの組み合わせでも十分ではない(それから示唆されるよりも実際のリスクが大きい)可能性があります。2.)節や3.)節の議論が完全に確立していないとしても、このような指摘があって完全に否定できないならば、安全サイドに立って被爆量、特に内部被曝を最小限にするよう可能な限りの対策を取るべきと考えます。
このように、原発事故の際のリスクの評価には、標準的な被曝線量の推定とLNTの組み合わせでも十分ではない(それから示唆されるよりも実際のリスクが大きい)可能性があります。2.)節や3.)節の議論が完全に確立していないとしても、このような指摘があって完全に否定できないならば、安全サイドに立って被爆量、特に内部被曝を最小限にするよう可能な限りの対策を取るべきと考えます。
VI. まとめ ー科学者として―
今回の原発事故は、私個人にとってもいろいろと衝撃的なできごとでした。(過去形と言うより、現在進行形ですね。)私自身や、私の家族にとっての直接の健康被害も正直なところ心配です。(これは、ここまで議論したような私なりの考察に基づいていますので、間違いがあれば是非指摘して安心させて頂きたいと思います。ただ、仮に私の住所に飛来する放射性物質の影響が無視できて、また水道水の汚染も無視できるとしても、農作物について厳格な管理がなされない限り、食卓での不安を完全に払拭することはできないでしょう。)また、私の悲観論が間違っていて、仮に首都圏における直接被害が無視できる程度で収まったとしても、少なくとも原発の周辺地域に多大の損害を与えたことは既に争いようのない事実でしょう。私自身は今まで原発に直接関わったことはありませんが、科学、そして物理に携わる者としても、大変な衝撃を受けています。科学技術が福島の、日本の、そして世界の人々を裏切ったことは事実です。
今回の事故の大きな要因として、もちろん地震や津波はありますが、過度の楽観論があったことは否定しようがありません。地震や津波の際の危険性は、過去に何度も指摘があったようですが、「まあ、そんなことはまず起こらないでしょう」ということで、コスト優先の論理で無視されてしまったようです。設計段階での想定の甘さについては、たとえば元東芝で原子力発電所の設計をされていた後藤政志さんのレクチャーが大変参考になります。
http://www.ustream.tv/recorded/13509182
事故が起こった後も、当初は「軽水型の原子炉なので原子炉の構造からスリーマイルアイランド事故以下の規模で収まるはずだ」と言った楽観論が多かったように思いますが、現実は既にスリーマイルアイランド事故を大きく超える規模になってしまっています。事故発生後、東京電力や政府がどのように判断し対応して来たのかは明らかでない点も多いですが、少なくとも、当初事態を甘く見てしまったために対応が後手後手になってしまったことは確かだと思います。
そもそも、放射能がダダ漏れと言う現状は、既に「起こってはならない、起こらないはずだった」事態です。(あまりにいろいろなことが起きて、皆さん感覚もマヒしているようですが。。。。)専門家や政府が今まで「このようなことは決して起こらない」と国民に言い続けて来て、その保証が裏切られたことは科学者として深刻に受け止めるべきです。
このことの反省に立てば、現状での被害や、今後の危険性についても、過小評価することなく、むしろあらゆる可能性を考慮し、最悪の事態も考え、慎重に(=むしろ悲観的に)考察し、その結果を率直に一般社会の方々にも伝えることこそ科学者の責務ではないかと私は考えます。「社会の不安をしずめる」というのは善意ではあると思いますし、政治的な判断としてはあり得るかもしれません。しかし、そのような判断は少なくとも科学者の仕事では無いように思います。(私個人の感想を言えば、むしろ、大変なことが起きているのに皆さんの受け止め方がのんびりし過ぎているような気がします。)科学者の役割は、事実を的確にとらえ、それを伝えることではないかと思います。それが悲観的なものであっても、その根拠やいろいろな可能性をきちんと伝えれば、無用なパニックを起こすほど、日本人の知的水準は低くないと私は考えます。
今回の原発事故は、私個人にとってもいろいろと衝撃的なできごとでした。(過去形と言うより、現在進行形ですね。)私自身や、私の家族にとっての直接の健康被害も正直なところ心配です。(これは、ここまで議論したような私なりの考察に基づいていますので、間違いがあれば是非指摘して安心させて頂きたいと思います。ただ、仮に私の住所に飛来する放射性物質の影響が無視できて、また水道水の汚染も無視できるとしても、農作物について厳格な管理がなされない限り、食卓での不安を完全に払拭することはできないでしょう。)また、私の悲観論が間違っていて、仮に首都圏における直接被害が無視できる程度で収まったとしても、少なくとも原発の周辺地域に多大の損害を与えたことは既に争いようのない事実でしょう。私自身は今まで原発に直接関わったことはありませんが、科学、そして物理に携わる者としても、大変な衝撃を受けています。科学技術が福島の、日本の、そして世界の人々を裏切ったことは事実です。
今回の事故の大きな要因として、もちろん地震や津波はありますが、過度の楽観論があったことは否定しようがありません。地震や津波の際の危険性は、過去に何度も指摘があったようですが、「まあ、そんなことはまず起こらないでしょう」ということで、コスト優先の論理で無視されてしまったようです。設計段階での想定の甘さについては、たとえば元東芝で原子力発電所の設計をされていた後藤政志さんのレクチャーが大変参考になります。
http://www.ustream.tv/recorded/13509182
事故が起こった後も、当初は「軽水型の原子炉なので原子炉の構造からスリーマイルアイランド事故以下の規模で収まるはずだ」と言った楽観論が多かったように思いますが、現実は既にスリーマイルアイランド事故を大きく超える規模になってしまっています。事故発生後、東京電力や政府がどのように判断し対応して来たのかは明らかでない点も多いですが、少なくとも、当初事態を甘く見てしまったために対応が後手後手になってしまったことは確かだと思います。
そもそも、放射能がダダ漏れと言う現状は、既に「起こってはならない、起こらないはずだった」事態です。(あまりにいろいろなことが起きて、皆さん感覚もマヒしているようですが。。。。)専門家や政府が今まで「このようなことは決して起こらない」と国民に言い続けて来て、その保証が裏切られたことは科学者として深刻に受け止めるべきです。
このことの反省に立てば、現状での被害や、今後の危険性についても、過小評価することなく、むしろあらゆる可能性を考慮し、最悪の事態も考え、慎重に(=むしろ悲観的に)考察し、その結果を率直に一般社会の方々にも伝えることこそ科学者の責務ではないかと私は考えます。「社会の不安をしずめる」というのは善意ではあると思いますし、政治的な判断としてはあり得るかもしれません。しかし、そのような判断は少なくとも科学者の仕事では無いように思います。(私個人の感想を言えば、むしろ、大変なことが起きているのに皆さんの受け止め方がのんびりし過ぎているような気がします。)科学者の役割は、事実を的確にとらえ、それを伝えることではないかと思います。それが悲観的なものであっても、その根拠やいろいろな可能性をきちんと伝えれば、無用なパニックを起こすほど、日本人の知的水準は低くないと私は考えます。
いつもTwitterではお世話になっております。また、被曝対策コミュの管理人をしております。よろしくお願いいたします。
「重松逸造」を逆に一度調べてみないといけないという発想もあるかと。重松逸造の研究により世界中の研究が歪められています。最初の結核研究だけは水俣病、イタイイタイ病、スモン、HTLV、ヒロシマ、チェルノブイリ、すべてをなかったことや過小評価しています。チェルノブイリでは甲状腺癌以外がなかった事になったままです。
チェルノブイリを経験したヨーロッパでは0.1mSv/yを基準としていますが、1mSv/yは甘い、改悪してきたという非難があり、これは重松逸造の研究から来ています。一度、どうか検索してみて、様々な動画や本の情報を得て見てください。
私見ですが、0.1mSv/yの方を親御さんたちは目指すべきと思うようになってきました。
「重松逸造」を逆に一度調べてみないといけないという発想もあるかと。重松逸造の研究により世界中の研究が歪められています。最初の結核研究だけは水俣病、イタイイタイ病、スモン、HTLV、ヒロシマ、チェルノブイリ、すべてをなかったことや過小評価しています。チェルノブイリでは甲状腺癌以外がなかった事になったままです。
チェルノブイリを経験したヨーロッパでは0.1mSv/yを基準としていますが、1mSv/yは甘い、改悪してきたという非難があり、これは重松逸造の研究から来ています。一度、どうか検索してみて、様々な動画や本の情報を得て見てください。
私見ですが、0.1mSv/yの方を親御さんたちは目指すべきと思うようになってきました。
「なぜ子どもの被曝をさけなければならないか。」
http://blog.livedoor.jp/tokiko1003/archives/2701962.html
原子力発電政治結論から先に書きます。お子さんを持つ方がいらっしゃったら、絶対に守ってほしいです。
子どもは絶対に被曝から守らないといけない。
その理由が漠然としていたと思いますが、被曝するその子どもの病気だけではなく、その子どもが将来、子どもを授かれるかどうかが、決定してしまう可能性があるからです。
生物学的に説明しますが、理由は以下の通りです。
【女の子の場合】---------------------------------------
女の子は生まれる前から、卵子のもとになる卵母細胞という細胞をもっており、
母親のお腹の中でまだ胎児でいる時期には600万〜700万個
↓(徐々に減少)
出世時に100万〜200万個
↓(さらに減少)
思春期までに約30万個
とその数を減らしていきます。
女性は、初潮から閉経までに平均で約400個排卵すると言われています。(閉経後は残った卵母細胞は退化していきます。)
さて、卵母細胞は、毎月1個成熟し、卵子となって排卵され、受精を待ちます。
その他の排卵されない待機中の卵母細胞は、卵母細胞のまま細胞分裂を止めた状態で卵胞内に存在し続けています。その待機中には、DNAの修復は行われない為、年齢を重ねるごとに卵子の損傷の可能性が大きくなり、同時に不妊の可能性も高まるわけです。
つまり、ここでみなさんに注意していただきたいことは、女性は生まれたときから卵母細胞を持っていて、出世後に自分で新たに生成することができないということです。
・・・わかりますか?
幼少期に被曝して、卵母細胞にダメージを受けた女の子がどうなるか・・・。
一度被曝してしまったら、取り返しがきかないんです。
被曝をしてしまった卵母細胞がどうなってしまうか、想像できると思います。
ICRPの発表しているしきい値をご紹介します。
------------------------------------------
急性被曝 慢性被曝
一時不妊 0.65-1.5 Gy -----
永久不妊 2.5-6.0 Gy 0.2 Gy/年
------------------------------------------
(Gy=Svでいいと思います)
【男の子の場合】---------------------------------------
男の子の場合、精母細胞は放射線の感受性が高く、低線量でも細胞死が起こり一時不妊になってしまいます。また、0.15Sv以上浴びると精子の元になる精母細胞がダメージを受けて細胞死し、永久不妊となると言われています。
こちらでも具体的にしきい値をご紹介します。
--------------------------------------------
急性被曝 慢性被曝
一時不妊 0.15 Gy 0.4 Gy/年
永久不妊 3.5-6.0 Gy 2.0 Gy/年
--------------------------------------------
(Gy=Svでいいと思います)
※すいません。ICRPの数値のソースを探したのですが、どうしても本文が見つからなかった為、関連するURLを貼らせていただきます。
?人体に対する放射線の確定的影響と確率的影響
http://www.rada.or.jp/database/home4/normal/ht-docs/member/synopsis/030065.html
?日高振興局(放射線を生殖腺に受けると子供はできなくなるの?)
http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hfc/homepage/q-16.htm
さて、これを読んだ後もあなたは汚染地域で子どもを遊ばせることを許せますか?
福島の子ども達に20mSVを許容する政府が一体何をしているかわかりますか・・・?
実はこの話、昔、高校の生物の先生が授業で話してくれていました。その時は子どもが被曝するなんて想像していなかったため、なかなか実感できませんでした。本当ならもっと早くにこの記事をUPすべきだったと思い、とても後悔しています。自分の知識や数値に自信がなかったというのが本音です。でも、自分の持っている知識で、少しでも子ども達が助けられるのなら・・・と思い、思い切ってUPしました。
※幾分高校時代の授業をベースにし、ネットで足りない箇所を補ったため、間違っている箇所があるかと思います。ご指摘いただければ訂正しますので、気づかれた方はコメントを入れていただけると助かります。
今まさに、子ども達の未来が奪われようとしています。
どうか、この記事を読んで、思うところがあったのなら、これをお子さんを持つお友達に伝えてください。そして、子ども達を守ってください。
・・・・・お願いします。
一刻も早く、子ども達を避難させてください。お願いします。政府の人・・・。
http://blog.livedoor.jp/tokiko1003/archives/2701962.html
原子力発電政治結論から先に書きます。お子さんを持つ方がいらっしゃったら、絶対に守ってほしいです。
子どもは絶対に被曝から守らないといけない。
その理由が漠然としていたと思いますが、被曝するその子どもの病気だけではなく、その子どもが将来、子どもを授かれるかどうかが、決定してしまう可能性があるからです。
生物学的に説明しますが、理由は以下の通りです。
【女の子の場合】---------------------------------------
女の子は生まれる前から、卵子のもとになる卵母細胞という細胞をもっており、
母親のお腹の中でまだ胎児でいる時期には600万〜700万個
↓(徐々に減少)
出世時に100万〜200万個
↓(さらに減少)
思春期までに約30万個
とその数を減らしていきます。
女性は、初潮から閉経までに平均で約400個排卵すると言われています。(閉経後は残った卵母細胞は退化していきます。)
さて、卵母細胞は、毎月1個成熟し、卵子となって排卵され、受精を待ちます。
その他の排卵されない待機中の卵母細胞は、卵母細胞のまま細胞分裂を止めた状態で卵胞内に存在し続けています。その待機中には、DNAの修復は行われない為、年齢を重ねるごとに卵子の損傷の可能性が大きくなり、同時に不妊の可能性も高まるわけです。
つまり、ここでみなさんに注意していただきたいことは、女性は生まれたときから卵母細胞を持っていて、出世後に自分で新たに生成することができないということです。
・・・わかりますか?
幼少期に被曝して、卵母細胞にダメージを受けた女の子がどうなるか・・・。
一度被曝してしまったら、取り返しがきかないんです。
被曝をしてしまった卵母細胞がどうなってしまうか、想像できると思います。
ICRPの発表しているしきい値をご紹介します。
------------------------------------------
急性被曝 慢性被曝
一時不妊 0.65-1.5 Gy -----
永久不妊 2.5-6.0 Gy 0.2 Gy/年
------------------------------------------
(Gy=Svでいいと思います)
【男の子の場合】---------------------------------------
男の子の場合、精母細胞は放射線の感受性が高く、低線量でも細胞死が起こり一時不妊になってしまいます。また、0.15Sv以上浴びると精子の元になる精母細胞がダメージを受けて細胞死し、永久不妊となると言われています。
こちらでも具体的にしきい値をご紹介します。
--------------------------------------------
急性被曝 慢性被曝
一時不妊 0.15 Gy 0.4 Gy/年
永久不妊 3.5-6.0 Gy 2.0 Gy/年
--------------------------------------------
(Gy=Svでいいと思います)
※すいません。ICRPの数値のソースを探したのですが、どうしても本文が見つからなかった為、関連するURLを貼らせていただきます。
?人体に対する放射線の確定的影響と確率的影響
http://www.rada.or.jp/database/home4/normal/ht-docs/member/synopsis/030065.html
?日高振興局(放射線を生殖腺に受けると子供はできなくなるの?)
http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hfc/homepage/q-16.htm
さて、これを読んだ後もあなたは汚染地域で子どもを遊ばせることを許せますか?
福島の子ども達に20mSVを許容する政府が一体何をしているかわかりますか・・・?
実はこの話、昔、高校の生物の先生が授業で話してくれていました。その時は子どもが被曝するなんて想像していなかったため、なかなか実感できませんでした。本当ならもっと早くにこの記事をUPすべきだったと思い、とても後悔しています。自分の知識や数値に自信がなかったというのが本音です。でも、自分の持っている知識で、少しでも子ども達が助けられるのなら・・・と思い、思い切ってUPしました。
※幾分高校時代の授業をベースにし、ネットで足りない箇所を補ったため、間違っている箇所があるかと思います。ご指摘いただければ訂正しますので、気づかれた方はコメントを入れていただけると助かります。
今まさに、子ども達の未来が奪われようとしています。
どうか、この記事を読んで、思うところがあったのなら、これをお子さんを持つお友達に伝えてください。そして、子ども達を守ってください。
・・・・・お願いします。
一刻も早く、子ども達を避難させてください。お願いします。政府の人・・・。
29.記載文へのトラックバックも一応記載しておきます。
2. kakeri2011年05月17日 01:20
「福島の子ども達に20mSVを許容する政府が一体何をしているかわかりますか・・・?」とのことでしたが、誤解されているようですので、お知らせ致します。
20mSv/yは、暫定値ですし、ICRPの基準値まで余裕があります。
また、半減期により放射線量は低下していきますので、
年間トータルで20mSvまで行きません。(実際に下がっています)
表の前半の急性被曝の数値は、瞬間的な放射線量の値です。
放射線は、光の一種ですので、放射線量は光の強さと思って下さい。一定以上の強さ(=放射線量)を超えないと、細胞に影響を及ぼさないのです。
もし、20mSv/yが暫定値と本当に危険ならば、ユニセフやWHOが必ず、修正勧告してきます。欧米だけでなく、アフリカ、南米諸国、世界中が注視しています。
3. Bochibochi2011年05月17日 03:16
>>kakeriさん
コメントありがとうございます。
私は科学的な知識に乏しいので、ご指摘いただきありがとうございます。
それを踏まえた上で、言わせていただきます。
自分のDNAがどれくらい修復能力があるのかは、誰にもわからない。もしかしたら、ダメージを受けても全部修復できるかもしれない。けれど、その逆だったら?
子どもの放射能の感受性は、大人と比較しても桁違いに大きいと言われています。特に卵母細胞は、ダメージを受ければ卵子になるときまでそのダメージの修復はされずにあるのです。取り返しのつかない細胞にダメージがあった場合、どう責任を取れますか?
私がいいたいのは、そういうことなんです。
感情的になりやすいので、こういう書き方しかできなくて申し訳ありません。でもkakeriさんのコメントを読んで安心してしまう方がいらっしゃると、私も困るので、返信させていただきました。
でも、是非、今後ともいろいろとご指摘いただければと思います。
4. kakeri2011年05月17日 04:07
ご心配、ごもっともです。私は、学生時に国際保健を学んでいた者です。1990年代にチェルノブイリ被曝被害に関心があり、WHOの報告書や英文の論文を読んでおりました。当時は、今ほど放射線に関して解明されていないことが多く、広島長崎の原爆の調査研究、診察記録(カルテ)などが世界の参考資料でありました。
チェルノブイリ事故では、世界中の科学者が調査研究をし、25年経た今日、多くの事が分かって参りました。その結果、放射能の被曝に関しては、主に医学部の「放射線医学」という分野で扱うのですが、20年前のテキストと現在のテキストでは、内容が随分変わりました。古い知識しか持っていない学者と最新の知識を学んでいる学者とでは、異なる見解が出てくることになります。
胎児の被曝に関する資料(現在、世界中で認められている知見です)がありますので参考にしてみて下さい。不明な点があれば、お知らせ下さい。私も全て分かるわけではないのですが、できる限りお答えしたく思っております。
「胎児の被曝に関する資料」
http://www.jaog.or.jp/japanese/jigyo/SENTEN/kouhou/hibaku.htm
2. kakeri2011年05月17日 01:20
「福島の子ども達に20mSVを許容する政府が一体何をしているかわかりますか・・・?」とのことでしたが、誤解されているようですので、お知らせ致します。
20mSv/yは、暫定値ですし、ICRPの基準値まで余裕があります。
また、半減期により放射線量は低下していきますので、
年間トータルで20mSvまで行きません。(実際に下がっています)
表の前半の急性被曝の数値は、瞬間的な放射線量の値です。
放射線は、光の一種ですので、放射線量は光の強さと思って下さい。一定以上の強さ(=放射線量)を超えないと、細胞に影響を及ぼさないのです。
もし、20mSv/yが暫定値と本当に危険ならば、ユニセフやWHOが必ず、修正勧告してきます。欧米だけでなく、アフリカ、南米諸国、世界中が注視しています。
3. Bochibochi2011年05月17日 03:16
>>kakeriさん
コメントありがとうございます。
私は科学的な知識に乏しいので、ご指摘いただきありがとうございます。
それを踏まえた上で、言わせていただきます。
自分のDNAがどれくらい修復能力があるのかは、誰にもわからない。もしかしたら、ダメージを受けても全部修復できるかもしれない。けれど、その逆だったら?
子どもの放射能の感受性は、大人と比較しても桁違いに大きいと言われています。特に卵母細胞は、ダメージを受ければ卵子になるときまでそのダメージの修復はされずにあるのです。取り返しのつかない細胞にダメージがあった場合、どう責任を取れますか?
私がいいたいのは、そういうことなんです。
感情的になりやすいので、こういう書き方しかできなくて申し訳ありません。でもkakeriさんのコメントを読んで安心してしまう方がいらっしゃると、私も困るので、返信させていただきました。
でも、是非、今後ともいろいろとご指摘いただければと思います。
4. kakeri2011年05月17日 04:07
ご心配、ごもっともです。私は、学生時に国際保健を学んでいた者です。1990年代にチェルノブイリ被曝被害に関心があり、WHOの報告書や英文の論文を読んでおりました。当時は、今ほど放射線に関して解明されていないことが多く、広島長崎の原爆の調査研究、診察記録(カルテ)などが世界の参考資料でありました。
チェルノブイリ事故では、世界中の科学者が調査研究をし、25年経た今日、多くの事が分かって参りました。その結果、放射能の被曝に関しては、主に医学部の「放射線医学」という分野で扱うのですが、20年前のテキストと現在のテキストでは、内容が随分変わりました。古い知識しか持っていない学者と最新の知識を学んでいる学者とでは、異なる見解が出てくることになります。
胎児の被曝に関する資料(現在、世界中で認められている知見です)がありますので参考にしてみて下さい。不明な点があれば、お知らせ下さい。私も全て分かるわけではないのですが、できる限りお答えしたく思っております。
「胎児の被曝に関する資料」
http://www.jaog.or.jp/japanese/jigyo/SENTEN/kouhou/hibaku.htm
続)
5. sunnydolph2011年05月17日 06:34
kakeriさんは誤解しています。
> 放射線は、光の一種ですので、.......
放射線には、高エネルギーを有するヘリウム4原子核(アルファ線)、高エネルギーを有する電子(ベータ線)、高エネルギーを有する電磁波(ガンマ線)などがあり、ガンマ線は光の一種と言ってもいいかも知れませんが、他のものは違います。
> 一定以上の強さ(=放射線量)を超えないと、細胞に影響を及ぼさないのです。
何か閾値のようなものがあるものと勘違いされているようですが、閾値のようなものはありません。たくさん放射線を浴びると、その分だけ細胞やDNAが壊れる確率が高くなるだけです。
20mSv/yなら、まだ癌になる確率が低いから、それで我慢してくれ.....と言っているのに過ぎないのです。
しかも、癌になるにしてもほとんどの場合は「ただちに」癌になるわけではありません。
たとえば、ストロンチウム90などの放射性物質を体内に取り込んでしまった場合は、何十年も内部被曝し続けることになります。そして何十年後かに癌になっても原発との因果関係の確認はほぼ不可能になります。
6. kurikinD2011年05月17日 09:45
はじめまして、twitterからリンクを辿って参りました。
転載させて頂きますね。
kakeriさんのおっしゃっていることが私にはよくわかりません。
今すぐ原発事故が収束するのなら、確かに半減していくでしょうけれど、収束の目処は立っていませんし、現在も毎日放射性物質が出続けているのですから、安心などできないと思います。
7. taro2011年05月17日 10:06
すごくいい記事なんですけど、この不妊になる閾値を出してしまったら、論理が破綻しています。
永久不妊のしきい値となる 0.2 Gy/年= 200ミリSv/year です。
それならば、安全幅を十分に取っている20ミリSv/yearは安全。と言えてしまうわけです。累積もそれぐらいです。
しかし、卵母細胞に対するダメージなど分からないことが多く、より分からないもの危険には保守的になるべきなのは同意します
10. Bochibochi2011年05月17日 11:19
>>taroさん
そうでしょうか。閾値は実際発表されている数値なので、嘘は書けません。しかも閾値は、あくまで許容値ではなく、我慢して欲しい数値です。
どの数値で卵母細胞や精母細胞にダメージが実際に出るかは、本当に誰にもわかりません。。。
20mSVの閾値を与え、そのリスクを福島の子ども達に負わせることが私達国民の意志ですか?それが安全だと考えられるのでしょうか。。。
私には絶対そんなことは言えないです。
でも、根本の考え方はtaroさんと同じだと信じています。
コメントありがとうございました。
11. taro2011年05月17日 12:15
念のために、
閾値とは、ギリギリ許容値できる値です。しかし、ちょっとでも超えてしまうとリスクが出てきます。言い換えてみれば、「影響がないからガマンできる」とも言えます。
閾値は、「影響はあるけど我慢して」ではないです。
そして、安全の為に余裕を作って規制値を決めます。
今回の20mSvは規制値です。
これだけなら20mSvだと少しは余裕はあります。化学物質規制と比べるとかなり余裕は少ないですけど。
私は、20mSVは全く分からないことが多いためリスクが大きく、人体実験のようなことをすべきではないと考えています。その点は同意しています。
影響が分かっている範囲(5〜8ミリ程度/年)で運用すべきじゃないかなと考えています。
12. Bochibochi2011年05月17日 12:27
>>taroさん
閾値設定についての見解の相違だと思います。
私は、子どもに対して、20msvを許容している点を最も重視しています。この数値は、子どもの放射能の感受性を加味されているでしょうか。
さらに、これから子どもを生む世代にこの閾値を同様に要求していいのでしょうか。
成人(できれば子育て終了世代以降)に対しては、taroさんのおっしゃるとおりでもいいと思います。
見直されるべき閾値については、私は専門家ではないですし、まだ勉強不足でなんとも申し上げられません。
再度のコメントありがとうございます。
13. seacat2011年05月17日 13:22
Twitterからたどり着きました
一言コメさせていただきます
私は親として、
20msvが危険と言われる方がいらっしゃるなら、
危険だと認識します
特に知識のある方に多く見られますが
今この時点の出来事が、とてつもなく不自然でありえないのに
安全だの危険でないなど断定されますけど
将来もし万一のことがあったら、あなた方が責任を取ってくれるんですか?
少しでも疑いがあれば被曝は避けたい、それが子を思う親心というものです
Bochibochiさん、この記事を上げてくださって、本当にありがとうございます
5. sunnydolph2011年05月17日 06:34
kakeriさんは誤解しています。
> 放射線は、光の一種ですので、.......
放射線には、高エネルギーを有するヘリウム4原子核(アルファ線)、高エネルギーを有する電子(ベータ線)、高エネルギーを有する電磁波(ガンマ線)などがあり、ガンマ線は光の一種と言ってもいいかも知れませんが、他のものは違います。
> 一定以上の強さ(=放射線量)を超えないと、細胞に影響を及ぼさないのです。
何か閾値のようなものがあるものと勘違いされているようですが、閾値のようなものはありません。たくさん放射線を浴びると、その分だけ細胞やDNAが壊れる確率が高くなるだけです。
20mSv/yなら、まだ癌になる確率が低いから、それで我慢してくれ.....と言っているのに過ぎないのです。
しかも、癌になるにしてもほとんどの場合は「ただちに」癌になるわけではありません。
たとえば、ストロンチウム90などの放射性物質を体内に取り込んでしまった場合は、何十年も内部被曝し続けることになります。そして何十年後かに癌になっても原発との因果関係の確認はほぼ不可能になります。
6. kurikinD2011年05月17日 09:45
はじめまして、twitterからリンクを辿って参りました。
転載させて頂きますね。
kakeriさんのおっしゃっていることが私にはよくわかりません。
今すぐ原発事故が収束するのなら、確かに半減していくでしょうけれど、収束の目処は立っていませんし、現在も毎日放射性物質が出続けているのですから、安心などできないと思います。
7. taro2011年05月17日 10:06
すごくいい記事なんですけど、この不妊になる閾値を出してしまったら、論理が破綻しています。
永久不妊のしきい値となる 0.2 Gy/年= 200ミリSv/year です。
それならば、安全幅を十分に取っている20ミリSv/yearは安全。と言えてしまうわけです。累積もそれぐらいです。
しかし、卵母細胞に対するダメージなど分からないことが多く、より分からないもの危険には保守的になるべきなのは同意します
10. Bochibochi2011年05月17日 11:19
>>taroさん
そうでしょうか。閾値は実際発表されている数値なので、嘘は書けません。しかも閾値は、あくまで許容値ではなく、我慢して欲しい数値です。
どの数値で卵母細胞や精母細胞にダメージが実際に出るかは、本当に誰にもわかりません。。。
20mSVの閾値を与え、そのリスクを福島の子ども達に負わせることが私達国民の意志ですか?それが安全だと考えられるのでしょうか。。。
私には絶対そんなことは言えないです。
でも、根本の考え方はtaroさんと同じだと信じています。
コメントありがとうございました。
11. taro2011年05月17日 12:15
念のために、
閾値とは、ギリギリ許容値できる値です。しかし、ちょっとでも超えてしまうとリスクが出てきます。言い換えてみれば、「影響がないからガマンできる」とも言えます。
閾値は、「影響はあるけど我慢して」ではないです。
そして、安全の為に余裕を作って規制値を決めます。
今回の20mSvは規制値です。
これだけなら20mSvだと少しは余裕はあります。化学物質規制と比べるとかなり余裕は少ないですけど。
私は、20mSVは全く分からないことが多いためリスクが大きく、人体実験のようなことをすべきではないと考えています。その点は同意しています。
影響が分かっている範囲(5〜8ミリ程度/年)で運用すべきじゃないかなと考えています。
12. Bochibochi2011年05月17日 12:27
>>taroさん
閾値設定についての見解の相違だと思います。
私は、子どもに対して、20msvを許容している点を最も重視しています。この数値は、子どもの放射能の感受性を加味されているでしょうか。
さらに、これから子どもを生む世代にこの閾値を同様に要求していいのでしょうか。
成人(できれば子育て終了世代以降)に対しては、taroさんのおっしゃるとおりでもいいと思います。
見直されるべき閾値については、私は専門家ではないですし、まだ勉強不足でなんとも申し上げられません。
再度のコメントありがとうございます。
13. seacat2011年05月17日 13:22
Twitterからたどり着きました
一言コメさせていただきます
私は親として、
20msvが危険と言われる方がいらっしゃるなら、
危険だと認識します
特に知識のある方に多く見られますが
今この時点の出来事が、とてつもなく不自然でありえないのに
安全だの危険でないなど断定されますけど
将来もし万一のことがあったら、あなた方が責任を取ってくれるんですか?
少しでも疑いがあれば被曝は避けたい、それが子を思う親心というものです
Bochibochiさん、この記事を上げてくださって、本当にありがとうございます
Newton7月号、明日発売です。
http://www.newtonpress.co.jp/science/newton/index.html
6月号もかなり充実した内容でしたが、
今度は「きちんと知りたい 原発と放射能」に絞っているようです。
予告から抜粋
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
また,放射能汚染問題についても,
今月号とはちがった視点からくわしく考えていきます。
広島・長崎に投下された原爆による被ばく,
過去の核実験による放射能の影響,
1999年におきた茨城県東海村JCO臨界事故など,
被ばく被害が生じた過去の事例をひもとき,
福島第一原発事故での被害と比較していきます。
自分自身,家族,仲間を守るため,放射能の怖さは知っておくべきです。
しかし怖がりすぎも,原発周辺地域の農作物,水産物などの風評被害を生みますから,
避けるべきでしょう。
軽く考えすぎない一方で,怖がりすぎもしない,
放射能の“適切な怖がり方”を探っていきます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www.newtonpress.co.jp/science/newton/index.html
6月号もかなり充実した内容でしたが、
今度は「きちんと知りたい 原発と放射能」に絞っているようです。
予告から抜粋
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
また,放射能汚染問題についても,
今月号とはちがった視点からくわしく考えていきます。
広島・長崎に投下された原爆による被ばく,
過去の核実験による放射能の影響,
1999年におきた茨城県東海村JCO臨界事故など,
被ばく被害が生じた過去の事例をひもとき,
福島第一原発事故での被害と比較していきます。
自分自身,家族,仲間を守るため,放射能の怖さは知っておくべきです。
しかし怖がりすぎも,原発周辺地域の農作物,水産物などの風評被害を生みますから,
避けるべきでしょう。
軽く考えすぎない一方で,怖がりすぎもしない,
放射能の“適切な怖がり方”を探っていきます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n✡☮さんが立ててくださった【年間20mSvの意味 2011年05月14日 12:45】
申しわけありませんが、こちらと【過去の原発事故による被害】【非難しない避難の呼びかけ】のトピへ転載させていただきます。悪しからずご了承くださいませm(__)m
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『嶋橋さんの白血病との闘いは終わった。発症から2年1カ月。浜岡原発で約9年働き、29歳1カ月の人生だった。その間の被曝線量は、50.6mSv。年間では最多の年でも9.8mSv」|2000/3/22中国新聞:ある原発作業員の死 http://p.tl/gmXU
実際に福島県内各地で20mSvを超えるであろう状況になっています。
子供たちのポケットは小さい。
しかし、手遅れはないと思います。
避難に迷っている方、現状に危機感を持っている方お母さんたちは、
是非避難してみて下さい。
そこにはあなた方と同じ状況から避難して来た、他のお母さん家族がいます。
申しわけありませんが、こちらと【過去の原発事故による被害】【非難しない避難の呼びかけ】のトピへ転載させていただきます。悪しからずご了承くださいませm(__)m
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『嶋橋さんの白血病との闘いは終わった。発症から2年1カ月。浜岡原発で約9年働き、29歳1カ月の人生だった。その間の被曝線量は、50.6mSv。年間では最多の年でも9.8mSv」|2000/3/22中国新聞:ある原発作業員の死 http://p.tl/gmXU
実際に福島県内各地で20mSvを超えるであろう状況になっています。
子供たちのポケットは小さい。
しかし、手遅れはないと思います。
避難に迷っている方、現状に危機感を持っている方お母さんたちは、
是非避難してみて下さい。
そこにはあなた方と同じ状況から避難して来た、他のお母さん家族がいます。
風評被害という言葉を利用されて、子供たちが被ばくしていくことを食い止めなければいけませんね。
政府や東電が風評という言葉を利用して、補償しなくてもよい方向に勧めているようです。
 とにかく、原発推進の立場にある機関や人物の言葉を信用しないことが、大切な子供達を守るポイントです。
とにかく、原発推進の立場にある機関や人物の言葉を信用しないことが、大切な子供達を守るポイントです。
もうすでに3号機の核爆発と見られる現象からウラン、プルトニウムまで重いから飛散しないと思われていたものが、細かい粒子は気体エアロゾルとなってアメリカでも検出されていたくらいです。ハワイの牛乳からストロンチウム検出など。
サンデー毎日でも取り上げています。
http://onihutari.blog60.fc2.com/blog-entry-52.html
6月3日 低線量でも安全な被曝は存在しない 小出裕章氏 (zakzak)
小出裕章氏は、私にとって信頼できる研究者です。
http://hiroakikoide.wordpress.com/2011/06/03/zakzak-jun3/
信頼できる人か情報かなどは、だいたいその人の生き様、信念としているものが何かや、大切にしているもの、話し方や言葉で見分けがつくと思います。
原発推進者たちから子供達を守りましょう!
政府や東電が風評という言葉を利用して、補償しなくてもよい方向に勧めているようです。
もうすでに3号機の核爆発と見られる現象からウラン、プルトニウムまで重いから飛散しないと思われていたものが、細かい粒子は気体エアロゾルとなってアメリカでも検出されていたくらいです。ハワイの牛乳からストロンチウム検出など。
サンデー毎日でも取り上げています。
http://onihutari.blog60.fc2.com/blog-entry-52.html
6月3日 低線量でも安全な被曝は存在しない 小出裕章氏 (zakzak)
小出裕章氏は、私にとって信頼できる研究者です。
http://hiroakikoide.wordpress.com/2011/06/03/zakzak-jun3/
信頼できる人か情報かなどは、だいたいその人の生き様、信念としているものが何かや、大切にしているもの、話し方や言葉で見分けがつくと思います。
原発推進者たちから子供達を守りましょう!
参考までにこんな資料が出ています。
日本共産党が、専門家と一緒に東京都内の放射線量をまとめました。
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904.html
日本共産党都議団は、5月6日より25日までの間、専門家の協力も得て、都内全域で放射線量測定を行いました。
調査の特徴
都内全域を約10km四方メッシュに区切り、山間部を除き、ほぼ全域でのべ128カ所を測定した。
放射線量が高かった東部地域については、約5km四方メッシュに区切り、延べ55ヵ所を測定した。
マスコミ報道で「やや高い」と報道された新宿区で8ヵ所、豊洲周辺地域で23ヵ所測定した。
■資料?
東京都全体
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_1.pdf
■資料?
足立区、葛飾区、江戸川区など
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_2.pdf
■資料?
江東区から練馬区
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_3.pdf
■資料?
新宿区内
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_4.pdf
■測定結果一覧表
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_5.pdf
■2011年5月26日付「しんぶん赤旗」
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_6.pdf
■東京都内各地の空中放射線量測定結果について(PDF)
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_7.pdf
役所が学校や幼稚園等への説明に使えるかと思います。
日本共産党が、専門家と一緒に東京都内の放射線量をまとめました。
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904.html
日本共産党都議団は、5月6日より25日までの間、専門家の協力も得て、都内全域で放射線量測定を行いました。
調査の特徴
都内全域を約10km四方メッシュに区切り、山間部を除き、ほぼ全域でのべ128カ所を測定した。
放射線量が高かった東部地域については、約5km四方メッシュに区切り、延べ55ヵ所を測定した。
マスコミ報道で「やや高い」と報道された新宿区で8ヵ所、豊洲周辺地域で23ヵ所測定した。
■資料?
東京都全体
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_1.pdf
■資料?
足立区、葛飾区、江戸川区など
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_2.pdf
■資料?
江東区から練馬区
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_3.pdf
■資料?
新宿区内
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_4.pdf
■測定結果一覧表
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_5.pdf
■2011年5月26日付「しんぶん赤旗」
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_6.pdf
■東京都内各地の空中放射線量測定結果について(PDF)
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2011/20110525195904_7.pdf
役所が学校や幼稚園等への説明に使えるかと思います。
本日東北、関東注意です!
twitter より
@save_child 子供を守ろう[save child]
【早ければ14日から2号機の水蒸気を放出するということなので、念のためご用心を!6月14日午前9時からの放射能拡散予報 福島原発から南へ流れ、関東を覆う予測です[*風向き画像あり] http://p.tl/Zrt2 】
このつぶやきのURL
https://twitter.com/#!/save_child/status/80242690016555009
!!本日6/14深夜、福島第一原発から大量の煙。特に4号機 !
2011.06.14 00:00-01:00 / 福島原発ライブカメラ
http://t.co/gg7wXl5
ヨウ素、セシウムなど揮発性物質が増えそう。お母さん達注意してください
●風向きチェック
●ヨウ素を含む食品、昆布だしなどをあらかじめ飲ませる(とろろ昆布、昆布茶、粉末昆布の粉でもOK)
●保育園、学校休ませて引きこもる
●外出時は露出度の低い衣類とマスク、防止着用
などなど出来る限りのご注意を。
http://t.co/gg7wXl5
twitter より
@save_child 子供を守ろう[save child]
【早ければ14日から2号機の水蒸気を放出するということなので、念のためご用心を!6月14日午前9時からの放射能拡散予報 福島原発から南へ流れ、関東を覆う予測です[*風向き画像あり] http://p.tl/Zrt2 】
このつぶやきのURL
https://twitter.com/#!/save_child/status/80242690016555009
!!本日6/14深夜、福島第一原発から大量の煙。特に4号機 !
2011.06.14 00:00-01:00 / 福島原発ライブカメラ
http://t.co/gg7wXl5
ヨウ素、セシウムなど揮発性物質が増えそう。お母さん達注意してください
●風向きチェック
●ヨウ素を含む食品、昆布だしなどをあらかじめ飲ませる(とろろ昆布、昆布茶、粉末昆布の粉でもOK)
●保育園、学校休ませて引きこもる
●外出時は露出度の低い衣類とマスク、防止着用
などなど出来る限りのご注意を。
http://t.co/gg7wXl5
お勧めの著書『子ども達を放射能から守るために』
政府の「ただちに害が出るものではない」「基準値以内だから安全」という見解は内部被爆を考慮してない発言。実際チェルノブイリでは5年後に影響がでてきた。内部被爆は食物からも影響するので原発から離れた地域の人 も注意することが必要です。
乳幼児や14歳までの子供、妊娠中や授乳中の女性は基準値以下でも汚染されている可能性があるものは口にしないほうが良い。水道水の場合、乳幼児のセシウムの基準値は100ベクレル/kgだが、少量でも体内に入ると、そこから放射線がでて細胞を傷つけガンを誘発する。
気をつけたい食物: 半減期が30年のセシウムの影響が出やすい根菜。チェルノブイリではジャガイモがセシウムに高度に汚染された。日本でも人参、大根、イモ類など土の中で育つ食材に要注意。
出所『子どもたちを放射能から守るために』http://a.r10.to/hBM7aS
松本市長の菅谷昭
政府の「ただちに害が出るものではない」「基準値以内だから安全」という見解は内部被爆を考慮してない発言。実際チェルノブイリでは5年後に影響がでてきた。内部被爆は食物からも影響するので原発から離れた地域の人 も注意することが必要です。
乳幼児や14歳までの子供、妊娠中や授乳中の女性は基準値以下でも汚染されている可能性があるものは口にしないほうが良い。水道水の場合、乳幼児のセシウムの基準値は100ベクレル/kgだが、少量でも体内に入ると、そこから放射線がでて細胞を傷つけガンを誘発する。
気をつけたい食物: 半減期が30年のセシウムの影響が出やすい根菜。チェルノブイリではジャガイモがセシウムに高度に汚染された。日本でも人参、大根、イモ類など土の中で育つ食材に要注意。
出所『子どもたちを放射能から守るために』http://a.r10.to/hBM7aS
松本市長の菅谷昭
一般社団法人 サイエンス・メディアセンター
http://smc-japan.org/?p=2026
【低線量被ばくによるがんリスク】論文解題:調麻佐志・東工大准教授
低線量被ばくの発がんリスクに関して、議論が続いています。一つの鍵となりうる2003年に米科学アカデミー紀要に掲載された論文に関し、解説を寄稿して頂きましたので掲載致します。
調 麻佐志(しらべ・まさし)准教授
東京工業大学 大学院理工学研究科 工学基礎科学講座(科学計量学)
1. はじめに
ここに紹介した論文注1は、2003年11月の『米国科学アカデミー紀要(通称:PNAS)』に掲載された論文です。
この中では、現在我が国で最も注目されている問題の一つ、「低線量被ばくの発がんリスクへの影響」について、多くの研究を比較しながら議論が行われています。出版後、多数の引用(300超)がなされ、しかも、(私に理解できる範囲では)極度に否定的な反論はないので、現時点では内容の科学的妥当性は損なわれていないと判断しました注2。
この論文が掲載された学術誌『PNAS』は、多くの方々が名前を聞いたことがある『Nature』や『Science』に比べると一般の知名度では劣りますが、様々な専門分野の学術論文が掲載される学術誌の中では、この二大巨頭に準じる権威が認められている学術誌です。
もちろん、掲載された学術誌に権威があるからといって、当該論文の内容が正しいとは限りません。しかし、それだけ多くの科学者から注目されやすく、内容には批判的な目が向けられる機会が多い中で、ある意味生き残っている論文であることから、私は現時点での専門家の間での信ぴょう性は高いと受け止めております。
この論文は科学論文ですので専門知識がなければ読みにくいところは多々あると思いますが、要求される専門知識は少なめで、議論もシンプルです(門外漢の私が読んでも理解できる程度です)。
しかも、原論文の英語は比較的わかり易いと思われます。詳しい内容が気になる方は、原論文に直接あたっていただければと思います。
論文紹介(要旨の翻訳)
"低線量被ばくによる がんリスク:私たちが確かにわかっていることは何かを評価する"
原題:Cancer risks attributable to low doses of ionizing radiation: Assessing what we really know
著者:David J. Brenner(米国コロンビア大学)他
書誌情報:PNAS November 25, 2003 vol. 100 no. 24 13761-13766
http://www.pnas.org/content/100/24/13761
【要旨(筆者による日本語訳)】
高レベルの放射線被ばくは、発がんを含む、しかし、がんに限らない有害な影響を疑いなくもたらす。低線量被ばくに関してはずっと明確でないとはいえ、低線量被ばくのリスクは、がん検診、原子力発電の将来、職業的な放射線被ばく、頻繁に航空機を利用する乗客のリスク、有人宇宙探査、核テロリズムといった幅広い問題と関連しており社会的に重要である。私たちは、低線量被曝のリスクを定量することの難しさについてレビューを行い、二つの問題に取り組んだ。第一の問題は、ヒトの発がんリスクの増加について良い証拠が得られるx線あるいはγ線被ばくの最低値はいくつか?という問いである。疫学的データは、急性(短期)被ばくで約10〜50mSv、長期被ばくで約50〜100mSvをその最低値の範囲として示す。第二の問題は、さらに低い線量の被ばくによるがんのリスクを推定して評価するのに最適な手法は何か?というものである。実験的な根拠のある、定量的かつ生物物理学的な議論で支持され得るものとしては、中レベルから極低レベルの被ばくの発がんリスクの定量には線形推定が最も適切な手法であるようだ。この線形仮説は必ずしも最も保守的なアプローチなわけではない。また、いくつかの放射線による発がんリスクを過小評価し、またいくつかを過大評価する可能性が高い。
http://smc-japan.org/?p=2026
【低線量被ばくによるがんリスク】論文解題:調麻佐志・東工大准教授
低線量被ばくの発がんリスクに関して、議論が続いています。一つの鍵となりうる2003年に米科学アカデミー紀要に掲載された論文に関し、解説を寄稿して頂きましたので掲載致します。
調 麻佐志(しらべ・まさし)准教授
東京工業大学 大学院理工学研究科 工学基礎科学講座(科学計量学)
1. はじめに
ここに紹介した論文注1は、2003年11月の『米国科学アカデミー紀要(通称:PNAS)』に掲載された論文です。
この中では、現在我が国で最も注目されている問題の一つ、「低線量被ばくの発がんリスクへの影響」について、多くの研究を比較しながら議論が行われています。出版後、多数の引用(300超)がなされ、しかも、(私に理解できる範囲では)極度に否定的な反論はないので、現時点では内容の科学的妥当性は損なわれていないと判断しました注2。
この論文が掲載された学術誌『PNAS』は、多くの方々が名前を聞いたことがある『Nature』や『Science』に比べると一般の知名度では劣りますが、様々な専門分野の学術論文が掲載される学術誌の中では、この二大巨頭に準じる権威が認められている学術誌です。
もちろん、掲載された学術誌に権威があるからといって、当該論文の内容が正しいとは限りません。しかし、それだけ多くの科学者から注目されやすく、内容には批判的な目が向けられる機会が多い中で、ある意味生き残っている論文であることから、私は現時点での専門家の間での信ぴょう性は高いと受け止めております。
この論文は科学論文ですので専門知識がなければ読みにくいところは多々あると思いますが、要求される専門知識は少なめで、議論もシンプルです(門外漢の私が読んでも理解できる程度です)。
しかも、原論文の英語は比較的わかり易いと思われます。詳しい内容が気になる方は、原論文に直接あたっていただければと思います。
論文紹介(要旨の翻訳)
"低線量被ばくによる がんリスク:私たちが確かにわかっていることは何かを評価する"
原題:Cancer risks attributable to low doses of ionizing radiation: Assessing what we really know
著者:David J. Brenner(米国コロンビア大学)他
書誌情報:PNAS November 25, 2003 vol. 100 no. 24 13761-13766
http://www.pnas.org/content/100/24/13761
【要旨(筆者による日本語訳)】
高レベルの放射線被ばくは、発がんを含む、しかし、がんに限らない有害な影響を疑いなくもたらす。低線量被ばくに関してはずっと明確でないとはいえ、低線量被ばくのリスクは、がん検診、原子力発電の将来、職業的な放射線被ばく、頻繁に航空機を利用する乗客のリスク、有人宇宙探査、核テロリズムといった幅広い問題と関連しており社会的に重要である。私たちは、低線量被曝のリスクを定量することの難しさについてレビューを行い、二つの問題に取り組んだ。第一の問題は、ヒトの発がんリスクの増加について良い証拠が得られるx線あるいはγ線被ばくの最低値はいくつか?という問いである。疫学的データは、急性(短期)被ばくで約10〜50mSv、長期被ばくで約50〜100mSvをその最低値の範囲として示す。第二の問題は、さらに低い線量の被ばくによるがんのリスクを推定して評価するのに最適な手法は何か?というものである。実験的な根拠のある、定量的かつ生物物理学的な議論で支持され得るものとしては、中レベルから極低レベルの被ばくの発がんリスクの定量には線形推定が最も適切な手法であるようだ。この線形仮説は必ずしも最も保守的なアプローチなわけではない。また、いくつかの放射線による発がんリスクを過小評価し、またいくつかを過大評価する可能性が高い。
2. この論文が指摘したこと、およびその意味について
2−1.論文が指摘したこと
なんらかの要因について、それがヒトの体に与える影響が明確でないとき(とくに影響の発生の仕方が大きなロシアンルーレットのようにランダムな場合、その影響を確率的影響と呼びます)、その要因が健康に与える影響(端的な例は病気に罹ることですが、逆に良い影響も含みます)を科学的に分析するのに、疫学と呼ばれる科学の専門分野の様々なアプローチが使われます。
この「低線量被ばくによるがんのリスク」論文(以下、単に「リスク論文」と記述します)は、そのようなアプローチの特性を下敷きに、先行する研究のレビュー(検討・整理・(再)配置)を行いました。その結果から、この論文で指摘している重要な事項は次の3つです:
1.あるレベル以下の低線量被ばくによるがんリスクの存在は、検証が必要とするサンプルのサイズ(調査の対象となる被ばくされた方の人数)があまりにも巨大になるため注3、科学(疫学)における標準的かつ最も厳密なアプローチ(リスクの直接推計)によって検証することができない。しかし、科学的にみても、直接推計により検証できないことがリスクの不在を意味するわけではない。
2.これまで、直接推計によってがんのリスクの存在が証明された長期被ばく量の最小値は(年単位ではなく生涯で)50〜100mSvである。
3.2)の最低値未満の被ばく量によるがんリスクを科学的に明らかにするためには、何らかのモデル/仮説を前提として採用する必要があり、現時点では比例モデル(線形閾値無しモデル/仮説;LNT)が科学的に最も適切なモデルと考えられる。
それぞれをもう少し詳しく説明してみましょう。
2−1.論文が指摘したこと
なんらかの要因について、それがヒトの体に与える影響が明確でないとき(とくに影響の発生の仕方が大きなロシアンルーレットのようにランダムな場合、その影響を確率的影響と呼びます)、その要因が健康に与える影響(端的な例は病気に罹ることですが、逆に良い影響も含みます)を科学的に分析するのに、疫学と呼ばれる科学の専門分野の様々なアプローチが使われます。
この「低線量被ばくによるがんのリスク」論文(以下、単に「リスク論文」と記述します)は、そのようなアプローチの特性を下敷きに、先行する研究のレビュー(検討・整理・(再)配置)を行いました。その結果から、この論文で指摘している重要な事項は次の3つです:
1.あるレベル以下の低線量被ばくによるがんリスクの存在は、検証が必要とするサンプルのサイズ(調査の対象となる被ばくされた方の人数)があまりにも巨大になるため注3、科学(疫学)における標準的かつ最も厳密なアプローチ(リスクの直接推計)によって検証することができない。しかし、科学的にみても、直接推計により検証できないことがリスクの不在を意味するわけではない。
2.これまで、直接推計によってがんのリスクの存在が証明された長期被ばく量の最小値は(年単位ではなく生涯で)50〜100mSvである。
3.2)の最低値未満の被ばく量によるがんリスクを科学的に明らかにするためには、何らかのモデル/仮説を前提として採用する必要があり、現時点では比例モデル(線形閾値無しモデル/仮説;LNT)が科学的に最も適切なモデルと考えられる。
それぞれをもう少し詳しく説明してみましょう。
1) 低線量被ばく(つまり、××mSvあるいは◯◯μSvといった単位で測られる放射線被ばくの量が相対的に少ない被ばく)によるがんのリスク評価は、疫学の研究対象の一つです。
しかし、疫学において標準的かつ最も厳密なアプローチ(リスクの直接推計とその検定注4)を採用すると、ある一定レベル以下の低線量被ばくのリスクの有無を決定することは原理的に不可能になります。しかし、「一般に」だけではなく、この問題に限定しての科学的な理解においても、リスクの直接推計によって検証できないことがリスクの無いことを(暫定的にでも)意味するわけではありません。これは、単にそのアプローチを採用することに科学として無理があることを意味します。
2) リスクの直接推計に基づいた先行する科学研究によってがんのリスクが検証された被ばくのレベルは、原爆の犠牲者・被害者が受けたような限られた短時間で被爆する場合(急性被ばくといいます)で10〜50mSv、原発事故による被ばく(環境に放出された放射性物質による被ばく)や原発作業従事者の被ばくのように長期にわたって少しずつ被ばくする場合(長期被ばくといいます)で50〜100mSvです。
福島第1原子力発電所の事故に伴い大きく懸念されるのが、後者の長期被ばくです。なお、ここでは、以下の点には十分な注意を払ってください。
(ア) 被ばく量の単位(mSvやμSvなど)は年間の被ばく量をあらわす単位(たとえば、mSV/年)でなく、長期(多くの研究で5〜10年以上、理論上は生涯)に渡り蓄積された被ばく量を表します。
(イ) これまで行われてきた長期被ばくのリスクに関する研究では、必ずしも内部被ばくの影響が明示的には考慮されておりません(データの性質により考慮できなかったのです)。
(ウ) 同じく、これまでの長期被ばくのリスクに関する研究において、厳密にリスクが証明された被ばく量の最小値は、科学的に放射線の影響を受け易いとされているグループ(お腹の赤ちゃん、赤ん坊、こどもなど)にとっての最小値では必ずしもありません。
3) 前項で、長期被ばくに関しては、少なくとも50〜100mSvの被ばく量でがんのリスクがあることが検証されたと述べました。それでは、50〜100mSv以下の被ばくにはがんのリスクがないのでしょうか。そのようなリスクを科学的(疫学的)に検討するためには、1)で述べた最も厳密なアプローチを使うことができません。
(逆に、2)で示した値は、厳密なアプローチで明らかになった疑いの余地が実質ゼロな値ともいえます)
リスクの直接推計に代わって使われる科学的なアプローチは、推定ないしは外挿といわれるアプローチです。単純化して説明しますと、影響が科学的にわかる範囲(つまり、50〜100mSv以上)の被ばくとがんリスクの関係をプロットし(とりあえず横軸に被ばく量、縦軸に発がん率をとって、グラフに点を打つことを想像してください)注5、プロットされた点を上手くつないでわからないところまで延長してやることでリスクの見積もりを行うものです(小さいですが、リスク論文にあるこちらの模式図(http://p.tl/Vvl3)を参照してください注6。横軸は被ばく量、縦軸が放射線被ばくによるがんのリスクを表します)。
データから点を上手くつなぎ、さらに延長する作業には様々な可能性があり、極論すれば好きなように線を引くことができてしまいます。しかし、それでは科学にはなりません。この作業を科学的に行うためには、検討している現象(ここでは、放射線被ばくによってがんが発生するという現象)の背後に想定されるメカニズムに基づいて、曲線の形状をモデル化(仮定)する必要があります。
残念ながら、現在(そしておそらく今後も)、科学が持ち合わせる証拠から判断して、科学的に異論がほとんどないだろうと断言できる程度の厳密さでこの曲線の形状を決めることはできません。1)で述べたことと同じ問題があるからです(つまり、厳密なアプローチで曲線の形状を決定することができないのです)。
そこで、いくつかの数値データや放射線被ばくによるがん発生のメカニズムに関する実験的および理論的研究に基づいて、現在の科学水準から最も妥当な曲線の形状はどのようなものかを推測する必要が生じます。
この形状に関連する様々な研究の成果に基づき、リスク論文は、科学的に最も妥当な曲線の形状は直線であるようだと結論しています。このような曲線の形状を採用するモデルは、専門的には閾値無し線形モデル(LNT)と呼ばれていますが、わかりやすさを優先して以下では比例モデル注7と呼ぶことにします。
しかし、疫学において標準的かつ最も厳密なアプローチ(リスクの直接推計とその検定注4)を採用すると、ある一定レベル以下の低線量被ばくのリスクの有無を決定することは原理的に不可能になります。しかし、「一般に」だけではなく、この問題に限定しての科学的な理解においても、リスクの直接推計によって検証できないことがリスクの無いことを(暫定的にでも)意味するわけではありません。これは、単にそのアプローチを採用することに科学として無理があることを意味します。
2) リスクの直接推計に基づいた先行する科学研究によってがんのリスクが検証された被ばくのレベルは、原爆の犠牲者・被害者が受けたような限られた短時間で被爆する場合(急性被ばくといいます)で10〜50mSv、原発事故による被ばく(環境に放出された放射性物質による被ばく)や原発作業従事者の被ばくのように長期にわたって少しずつ被ばくする場合(長期被ばくといいます)で50〜100mSvです。
福島第1原子力発電所の事故に伴い大きく懸念されるのが、後者の長期被ばくです。なお、ここでは、以下の点には十分な注意を払ってください。
(ア) 被ばく量の単位(mSvやμSvなど)は年間の被ばく量をあらわす単位(たとえば、mSV/年)でなく、長期(多くの研究で5〜10年以上、理論上は生涯)に渡り蓄積された被ばく量を表します。
(イ) これまで行われてきた長期被ばくのリスクに関する研究では、必ずしも内部被ばくの影響が明示的には考慮されておりません(データの性質により考慮できなかったのです)。
(ウ) 同じく、これまでの長期被ばくのリスクに関する研究において、厳密にリスクが証明された被ばく量の最小値は、科学的に放射線の影響を受け易いとされているグループ(お腹の赤ちゃん、赤ん坊、こどもなど)にとっての最小値では必ずしもありません。
3) 前項で、長期被ばくに関しては、少なくとも50〜100mSvの被ばく量でがんのリスクがあることが検証されたと述べました。それでは、50〜100mSv以下の被ばくにはがんのリスクがないのでしょうか。そのようなリスクを科学的(疫学的)に検討するためには、1)で述べた最も厳密なアプローチを使うことができません。
(逆に、2)で示した値は、厳密なアプローチで明らかになった疑いの余地が実質ゼロな値ともいえます)
リスクの直接推計に代わって使われる科学的なアプローチは、推定ないしは外挿といわれるアプローチです。単純化して説明しますと、影響が科学的にわかる範囲(つまり、50〜100mSv以上)の被ばくとがんリスクの関係をプロットし(とりあえず横軸に被ばく量、縦軸に発がん率をとって、グラフに点を打つことを想像してください)注5、プロットされた点を上手くつないでわからないところまで延長してやることでリスクの見積もりを行うものです(小さいですが、リスク論文にあるこちらの模式図(http://p.tl/Vvl3)を参照してください注6。横軸は被ばく量、縦軸が放射線被ばくによるがんのリスクを表します)。
データから点を上手くつなぎ、さらに延長する作業には様々な可能性があり、極論すれば好きなように線を引くことができてしまいます。しかし、それでは科学にはなりません。この作業を科学的に行うためには、検討している現象(ここでは、放射線被ばくによってがんが発生するという現象)の背後に想定されるメカニズムに基づいて、曲線の形状をモデル化(仮定)する必要があります。
残念ながら、現在(そしておそらく今後も)、科学が持ち合わせる証拠から判断して、科学的に異論がほとんどないだろうと断言できる程度の厳密さでこの曲線の形状を決めることはできません。1)で述べたことと同じ問題があるからです(つまり、厳密なアプローチで曲線の形状を決定することができないのです)。
そこで、いくつかの数値データや放射線被ばくによるがん発生のメカニズムに関する実験的および理論的研究に基づいて、現在の科学水準から最も妥当な曲線の形状はどのようなものかを推測する必要が生じます。
この形状に関連する様々な研究の成果に基づき、リスク論文は、科学的に最も妥当な曲線の形状は直線であるようだと結論しています。このような曲線の形状を採用するモデルは、専門的には閾値無し線形モデル(LNT)と呼ばれていますが、わかりやすさを優先して以下では比例モデル注7と呼ぶことにします。
すこし補足しますと、この三つの指摘のうち最初の二つについては疫学の専門家の間ではかなり高いレベルで合意がなされているはずです。そこには、データや理論の恣意的な解釈や当てはめの余地がほぼ無いからです。
一方、三つ目注8については、あるいは反論・対案を持つ専門家がいるかもしれません。ただし、その専門家が対案として持つ可能性のある別の考え方(つまり曲線形状と背後のメカニズム)に対しては、リスク論文の中でそれぞれ問題点や限界が指摘されています。したがって、これらの指摘に対する合理的な反論、ないしはそのモデルが適用される範囲の合理的な限定なしに別のモデルを主張する専門家はまずいないはずです(根拠なく対案が提出されたとすれば、その主張を少なくとも科学的主張として受け止める必要はありません)。
たとえば、代表的な対案である閾値モデルは、メカニズムとデータの両面から適用できる範囲が比例モデルよりもかなり限られていることが指摘されています注9。つまり、反論の内容とその論理、またそれが意味するところをよく検討する必要があるのです。
参考までに、原子力安全委員会がホームページに公開した資料(『低線量放射線の健康影響について』(平成23年5月26日改訂版、http://www.nsc.go.jp/info/20110526.html)に、つぎのように書かれていることを確認してください(下線は筆者による)。リスク論文とおおむね整合的なことがおわかりいただけると思います。
標記に関する原子力安全委員会の考え方について説明いたします。
(中略)
一方、「確率的影響」には、被ばくから一定の期間を経た後にある確率で、固形がん、白血病等を発症することが含まれます。がんのリスクの評価は、疫学的手法によるものが基礎となっています。広島や長崎で原子爆弾に起因する放射線を受けた方々の追跡調査の結果からは、100mSvを超える被ばく線量では被ばく量とその影響の発生率との間に比例性があると認められております。一方、100mSv以下の被ばく線量では、がんリスクが見込まれるものの、統計的な不確かさが大きく疫学的手法によってがん等の確率的影響のリスクを直接明らかに示すことはできない、とされております。このように、100mSv以下の被ばく線量による確率的影響の存在は見込まれるものの不確かさがあります。
そこでICRPは、100mSv以下の被ばく線量域を含め、線量とその影響の発生率に比例関係があるというモデルに基づいて放射線防護を行うことを推奨しています。またICRPは、このモデルに基づき、全世代を通じたがんのリスク係数を示しています。それは100mSvあたり0.0055(100mSvの被ばくは生涯のがん死亡リスクを0.55%上乗せする。)に相当します。
ー『低線量放射線の健康影響について』(平成23年5月26日改訂版)http://www.nsc.go.jp/info/20110526.html
[Retrieved 6.20.2011]
一方、三つ目注8については、あるいは反論・対案を持つ専門家がいるかもしれません。ただし、その専門家が対案として持つ可能性のある別の考え方(つまり曲線形状と背後のメカニズム)に対しては、リスク論文の中でそれぞれ問題点や限界が指摘されています。したがって、これらの指摘に対する合理的な反論、ないしはそのモデルが適用される範囲の合理的な限定なしに別のモデルを主張する専門家はまずいないはずです(根拠なく対案が提出されたとすれば、その主張を少なくとも科学的主張として受け止める必要はありません)。
たとえば、代表的な対案である閾値モデルは、メカニズムとデータの両面から適用できる範囲が比例モデルよりもかなり限られていることが指摘されています注9。つまり、反論の内容とその論理、またそれが意味するところをよく検討する必要があるのです。
参考までに、原子力安全委員会がホームページに公開した資料(『低線量放射線の健康影響について』(平成23年5月26日改訂版、http://www.nsc.go.jp/info/20110526.html)に、つぎのように書かれていることを確認してください(下線は筆者による)。リスク論文とおおむね整合的なことがおわかりいただけると思います。
標記に関する原子力安全委員会の考え方について説明いたします。
(中略)
一方、「確率的影響」には、被ばくから一定の期間を経た後にある確率で、固形がん、白血病等を発症することが含まれます。がんのリスクの評価は、疫学的手法によるものが基礎となっています。広島や長崎で原子爆弾に起因する放射線を受けた方々の追跡調査の結果からは、100mSvを超える被ばく線量では被ばく量とその影響の発生率との間に比例性があると認められております。一方、100mSv以下の被ばく線量では、がんリスクが見込まれるものの、統計的な不確かさが大きく疫学的手法によってがん等の確率的影響のリスクを直接明らかに示すことはできない、とされております。このように、100mSv以下の被ばく線量による確率的影響の存在は見込まれるものの不確かさがあります。
そこでICRPは、100mSv以下の被ばく線量域を含め、線量とその影響の発生率に比例関係があるというモデルに基づいて放射線防護を行うことを推奨しています。またICRPは、このモデルに基づき、全世代を通じたがんのリスク係数を示しています。それは100mSvあたり0.0055(100mSvの被ばくは生涯のがん死亡リスクを0.55%上乗せする。)に相当します。
ー『低線量放射線の健康影響について』(平成23年5月26日改訂版)http://www.nsc.go.jp/info/20110526.html
[Retrieved 6.20.2011]
2−2.リスク論文が指摘したことの意味
「(外部被曝が)100mSV/年(≒10μSV/時)を超さなければ健康に影響を及ぼさない」といった趣旨の発言や記述をニュース等で目にし、あるいは耳にすることが多いでしょう。また、その根拠として100mSv未満の放射線被ばくの健康影響を厳密に科学的に検証した研究が存在しないことを挙げる発言もたまに目にします。
ここで紹介したリスク論文は、科学の範囲内でも、このような考えにいくつもの重大な誤りがあることを明らかにしてくれます。
もちろん、低線量被ばくの影響は短期的に現れにくいことは科学的な合意事項ですので、「直ちに影響はない」といったレトリックの意味についてここで議論するつもりはありません注10。主な問題点は以下のとおりです。
A) 100mSv程度以上の被ばくによる健康リスクを科学的に証明した調査・研究が用いる単位は、一年あたりの被ばく量を表すmSV/年ではなく、(一生涯にオーダーが近い長期に)累積された被ばく量を表すmSvです。
したがって、現状で20mSV/年の外部被ばくが見込まれる注11のであれば、そこに5年程度以上住むことを前提とすると(セシウムの半減期が約30年と長いこともあって)、既存の科学的な調査研究の結果は「健康に影響を及ぼすこと」をむしろ証明しています。
B) 100mSv(あるいは50mSv)未満の低線量被ばくのリスク(影響)が「厳密に」証明できないのは、リスクがないからではなく、「厳密」という旗印の下で使われたアプローチが適切でないためです(追加的な説明は別に行うので、関心のある方は3節をご覧ください)。
つまり、「リスクが証明できない」ことが、あらかじめわかっているアプローチをあてはめて導かれた「リスクが無いこと」の証明には、科学的な価値が全くありません。(なお、低線量被ばくのリスクに関する研究論文や調査報告では、多重比較などの言葉をつかって詳細な検定/下位検定を行うなどと書かれることがありえます。そのときには、同様の不思議なアプローチが取られている可能性もあるので、注意する必要があります。)
C) 長期被ばくに関する有力なデータの多くは原発作業従事者に関するデータです。したがって、そのデータに基づいて今回の事故の影響を考えようとしても、データが主に成人男性に関するデータであるため必然的に生じる限界があります。
子供の健康が放射線による影響を受け易いことについては(影響の受けやすさの程度については別としても)科学者間で合意があり、それを考慮しないで100mSvという数字が取り上げられてしまうと、科学的な意味で明らかに子供の健康に対するリスクを過小評価することにつながってしまいます。
D) (若干議論の余地はありますが)現状で科学的に最も妥当と考えられる比例 モデルを適用すれば、たとえば、20mSvの被ばくによるがんリスクはある程度合 理的に見積もることができます。たとえば、100mSvの被ばくをされた方の生涯の がん死確率(「絶対リスク」)がこの被ばくによって0.5%増えるのであれば、 20mSvでは「絶対リスク」が0.1%と見積もられます。
あるいは、放射線影響協会の報告書(『原子力発電施設等 放射線業務従事者 等に係る疫学的調査』(平成22年3月))から数字を借りれば、全悪性新生物に よる死亡が50〜100mSvの累積被ばく量で「相対リスク注12」は9%ほど増えていま すので、20mSvの累積被ばくではがんによる死亡の「相対リスク」の増加分は2% 近いと見積もれます注13。
いずれも例として行った雑な議論ですので、科学的に適切な見積もりを実行するには注意すべき点が多数あります。しかし、比例モデルによって、見積もりが可能であることのイメージは掴めたのではないでしょうか。つまり、(それが確実に正しいことの証明となるわけではないものの)現状で最適と考えられる科学的なアプローチによって、低線量被ばくのリスクの有無が議論できるに留まらず、どの程度のリスクがあるかについても検討できるのです。
以上に挙げた問題点によって、(リスクががんに限定されており、そのこと自体健康リスクの過小評価につながりますが)低線量被ばくによるガンのリスクに関して、リスク論文が指摘したことの意味をお伝えできたのではないかと思います。
「(外部被曝が)100mSV/年(≒10μSV/時)を超さなければ健康に影響を及ぼさない」といった趣旨の発言や記述をニュース等で目にし、あるいは耳にすることが多いでしょう。また、その根拠として100mSv未満の放射線被ばくの健康影響を厳密に科学的に検証した研究が存在しないことを挙げる発言もたまに目にします。
ここで紹介したリスク論文は、科学の範囲内でも、このような考えにいくつもの重大な誤りがあることを明らかにしてくれます。
もちろん、低線量被ばくの影響は短期的に現れにくいことは科学的な合意事項ですので、「直ちに影響はない」といったレトリックの意味についてここで議論するつもりはありません注10。主な問題点は以下のとおりです。
A) 100mSv程度以上の被ばくによる健康リスクを科学的に証明した調査・研究が用いる単位は、一年あたりの被ばく量を表すmSV/年ではなく、(一生涯にオーダーが近い長期に)累積された被ばく量を表すmSvです。
したがって、現状で20mSV/年の外部被ばくが見込まれる注11のであれば、そこに5年程度以上住むことを前提とすると(セシウムの半減期が約30年と長いこともあって)、既存の科学的な調査研究の結果は「健康に影響を及ぼすこと」をむしろ証明しています。
B) 100mSv(あるいは50mSv)未満の低線量被ばくのリスク(影響)が「厳密に」証明できないのは、リスクがないからではなく、「厳密」という旗印の下で使われたアプローチが適切でないためです(追加的な説明は別に行うので、関心のある方は3節をご覧ください)。
つまり、「リスクが証明できない」ことが、あらかじめわかっているアプローチをあてはめて導かれた「リスクが無いこと」の証明には、科学的な価値が全くありません。(なお、低線量被ばくのリスクに関する研究論文や調査報告では、多重比較などの言葉をつかって詳細な検定/下位検定を行うなどと書かれることがありえます。そのときには、同様の不思議なアプローチが取られている可能性もあるので、注意する必要があります。)
C) 長期被ばくに関する有力なデータの多くは原発作業従事者に関するデータです。したがって、そのデータに基づいて今回の事故の影響を考えようとしても、データが主に成人男性に関するデータであるため必然的に生じる限界があります。
子供の健康が放射線による影響を受け易いことについては(影響の受けやすさの程度については別としても)科学者間で合意があり、それを考慮しないで100mSvという数字が取り上げられてしまうと、科学的な意味で明らかに子供の健康に対するリスクを過小評価することにつながってしまいます。
D) (若干議論の余地はありますが)現状で科学的に最も妥当と考えられる比例 モデルを適用すれば、たとえば、20mSvの被ばくによるがんリスクはある程度合 理的に見積もることができます。たとえば、100mSvの被ばくをされた方の生涯の がん死確率(「絶対リスク」)がこの被ばくによって0.5%増えるのであれば、 20mSvでは「絶対リスク」が0.1%と見積もられます。
あるいは、放射線影響協会の報告書(『原子力発電施設等 放射線業務従事者 等に係る疫学的調査』(平成22年3月))から数字を借りれば、全悪性新生物に よる死亡が50〜100mSvの累積被ばく量で「相対リスク注12」は9%ほど増えていま すので、20mSvの累積被ばくではがんによる死亡の「相対リスク」の増加分は2% 近いと見積もれます注13。
いずれも例として行った雑な議論ですので、科学的に適切な見積もりを実行するには注意すべき点が多数あります。しかし、比例モデルによって、見積もりが可能であることのイメージは掴めたのではないでしょうか。つまり、(それが確実に正しいことの証明となるわけではないものの)現状で最適と考えられる科学的なアプローチによって、低線量被ばくのリスクの有無が議論できるに留まらず、どの程度のリスクがあるかについても検討できるのです。
以上に挙げた問題点によって、(リスクががんに限定されており、そのこと自体健康リスクの過小評価につながりますが)低線量被ばくによるガンのリスクに関して、リスク論文が指摘したことの意味をお伝えできたのではないかと思います。
2−3.リスク論文についてまとめ
リスクの大小(また、そのリスクをどう受け止めるべきか)については議論の余地が多分にありますが、科学の議論に忠実であれば、低線量であっても長期の放射線被ばくによるがんのリスクがあることが検証されていると認めるべきだと考えられます。
さらに、そのリスクがどの程度であるかについても、(リスクの存在自体ほど強い証拠と論理によって肯定するのは難しいとはいえ)現状で最も科学的に妥当と考えられるアプローチがあり、がんのリスクに限っては、その具体的な見積もりを得ることができます。これがリスク論文の指摘することでした。
しかし、この科学的に検証されたリスクの存在、および科学的に妥当と考えられる具体的なリスクに関する数字を前にしても、個人あるいは家族、共同体、自治体、国がどのような判断をすべきかについては、科学的に議論することはできません。
したがって、現状の放射性物質の飛散状況があり、どのような観点からも福島県内の多くの地点で外部被ばくのレベルは長期的ながんリスクが存在するレベルに達していると科学が結論しても、直ちに域外へと避難しなければならないことを科学が教えてくれるわけではありません。判断には、科学的に適切な証拠が非常に大切ですが、さらに重要な別種の(社会的)議論も必要です。
3. 一定レベル以下の低線量被ばくのリスクの有無が
直接推計アプローチでは検証できない理由
(以下は、乱暴な説明であることをご理解の上、気になる方だけお読みください。)
リスクの直接推計アプローチの手続きは、簡単にいえば、たとえば50mSv未満の被ばくを受けた場合にがんリスクが存在するかを確認するために、「その被ばくしたヒトの集団と、自然放射線による被ばくしか受けていないとみなせるヒトの集団をとりあげて、その違いを推計し、その推計値が意味のあるものかを統計学的に検証する」ものです。
なぜこのアプローチが低線量被ばくでは使えないかを(乱暴なやり方で)説明したいと思います。詳しくかつ正確に理解したい方は統計学の教科書にあたってください。
目の前にコインがあります。このコインには歪みがあることが疑われていて、その歪み具合は、表(オモテ)のでる確率が正常なコインよりも0.5%だけ多い程度と予想されています。つまり、50.5%が表のでる確率で、49.5%が裏のでる確率であると見込まれています。このコインを100回投げた結果を観察すれば、コインの歪みの存在を証明できるでしょうか。
仮に、歪みを確認するコインが正常なコインであると仮定しますと、100回投げて50回表がでる確率は:
100!/(50!×(100-50)!)×0.5100≒0.079589237(つまり約7.96%)
となります(これは、確率の計算に慣れてない方にとって意外に小さく感じられるかもしれません)。
一方、50.5%表が出るコインを100回投げて50回表がでる確率は:
100!/(50!×(100-50)!)×0.50550×0.49550≒0.079192265(約7.92%)
となります。上の値よりも小さいですが、二つの差はごくわずかです注14。
おおむね同じ傾向(二つの確率の差が非常に小さいという傾向)が表のでる回数が50回にある程度近いところで見られます。そのため、正常なコインとわずかに歪んだコインとの間では、100回程度投げただけでは二つの表が出る回数に、検出できる差が生じない可能性が非常に高いわけです。
低線量被ばくのがんリスクは、このようにわずかに歪んだコインの表裏のようなもので、被ばくのない状態と結果の出方には統計的に断言できる程度の大きな差がみられない可能性が高いと事前に想定されます(とはいえ、たとえば0.5%のがん死リスクの増加は、大きな人口を想像すれば軽々に無視できるものではありません)。
したがって、このような二種のコインの差を科学的に検討するためにはコインを投げる回数を増やす、すなわち、調査対象となる被ばくされた方々の数を非常に大きく増やす必要がありますが、その人数は確保できない規模に到達しています。
差の検出力をザルの目にたとえてこのことの意味を考えますと、現在は(おそらく今後とも)、実施可能な調査研究で使える最小のザルの目が5cm角であるのに対して、すくおうとする低線量被ばくのリスクは体長1mm以下の小魚であるといった状況であると想定できます注15。
このザルを使って小魚がいるかもしれない池の水をいかに念入りにさらっても小魚がかかることはまずありえませんが、大きな魚(高線量の被ばくリスク)がいれば、かかります。この結果から、池には小魚(とくに、大きな魚がかかった場合の稚魚)がいないと結論するのは、あまりにも馬鹿げた話です。残念ながら、科学とは程遠い世界の話注16だと思います。
(了)
リスクの大小(また、そのリスクをどう受け止めるべきか)については議論の余地が多分にありますが、科学の議論に忠実であれば、低線量であっても長期の放射線被ばくによるがんのリスクがあることが検証されていると認めるべきだと考えられます。
さらに、そのリスクがどの程度であるかについても、(リスクの存在自体ほど強い証拠と論理によって肯定するのは難しいとはいえ)現状で最も科学的に妥当と考えられるアプローチがあり、がんのリスクに限っては、その具体的な見積もりを得ることができます。これがリスク論文の指摘することでした。
しかし、この科学的に検証されたリスクの存在、および科学的に妥当と考えられる具体的なリスクに関する数字を前にしても、個人あるいは家族、共同体、自治体、国がどのような判断をすべきかについては、科学的に議論することはできません。
したがって、現状の放射性物質の飛散状況があり、どのような観点からも福島県内の多くの地点で外部被ばくのレベルは長期的ながんリスクが存在するレベルに達していると科学が結論しても、直ちに域外へと避難しなければならないことを科学が教えてくれるわけではありません。判断には、科学的に適切な証拠が非常に大切ですが、さらに重要な別種の(社会的)議論も必要です。
3. 一定レベル以下の低線量被ばくのリスクの有無が
直接推計アプローチでは検証できない理由
(以下は、乱暴な説明であることをご理解の上、気になる方だけお読みください。)
リスクの直接推計アプローチの手続きは、簡単にいえば、たとえば50mSv未満の被ばくを受けた場合にがんリスクが存在するかを確認するために、「その被ばくしたヒトの集団と、自然放射線による被ばくしか受けていないとみなせるヒトの集団をとりあげて、その違いを推計し、その推計値が意味のあるものかを統計学的に検証する」ものです。
なぜこのアプローチが低線量被ばくでは使えないかを(乱暴なやり方で)説明したいと思います。詳しくかつ正確に理解したい方は統計学の教科書にあたってください。
目の前にコインがあります。このコインには歪みがあることが疑われていて、その歪み具合は、表(オモテ)のでる確率が正常なコインよりも0.5%だけ多い程度と予想されています。つまり、50.5%が表のでる確率で、49.5%が裏のでる確率であると見込まれています。このコインを100回投げた結果を観察すれば、コインの歪みの存在を証明できるでしょうか。
仮に、歪みを確認するコインが正常なコインであると仮定しますと、100回投げて50回表がでる確率は:
100!/(50!×(100-50)!)×0.5100≒0.079589237(つまり約7.96%)
となります(これは、確率の計算に慣れてない方にとって意外に小さく感じられるかもしれません)。
一方、50.5%表が出るコインを100回投げて50回表がでる確率は:
100!/(50!×(100-50)!)×0.50550×0.49550≒0.079192265(約7.92%)
となります。上の値よりも小さいですが、二つの差はごくわずかです注14。
おおむね同じ傾向(二つの確率の差が非常に小さいという傾向)が表のでる回数が50回にある程度近いところで見られます。そのため、正常なコインとわずかに歪んだコインとの間では、100回程度投げただけでは二つの表が出る回数に、検出できる差が生じない可能性が非常に高いわけです。
低線量被ばくのがんリスクは、このようにわずかに歪んだコインの表裏のようなもので、被ばくのない状態と結果の出方には統計的に断言できる程度の大きな差がみられない可能性が高いと事前に想定されます(とはいえ、たとえば0.5%のがん死リスクの増加は、大きな人口を想像すれば軽々に無視できるものではありません)。
したがって、このような二種のコインの差を科学的に検討するためにはコインを投げる回数を増やす、すなわち、調査対象となる被ばくされた方々の数を非常に大きく増やす必要がありますが、その人数は確保できない規模に到達しています。
差の検出力をザルの目にたとえてこのことの意味を考えますと、現在は(おそらく今後とも)、実施可能な調査研究で使える最小のザルの目が5cm角であるのに対して、すくおうとする低線量被ばくのリスクは体長1mm以下の小魚であるといった状況であると想定できます注15。
このザルを使って小魚がいるかもしれない池の水をいかに念入りにさらっても小魚がかかることはまずありえませんが、大きな魚(高線量の被ばくリスク)がいれば、かかります。この結果から、池には小魚(とくに、大きな魚がかかった場合の稚魚)がいないと結論するのは、あまりにも馬鹿げた話です。残念ながら、科学とは程遠い世界の話注16だと思います。
(了)
注1:原論文について日本語への暫定訳は終えております。さらに、筆頭著者であるBrenner博士から大変なご好意により訳文およびオリジナルの図表の公開の許諾を得ておりますが、公開には出版社からの許諾も必要です。6月10日に許諾をお願いする連絡をメールでさせていただき、6月20日付で出版社から許諾のメールをいただきましたので、翻訳を公開いたします。
通常であれば、出版社側の規定にしたがって原文一ページにつき20ドル(計120ドル)および頒布一部毎に0.1ドルを支払わなければならないのですが、今回は現状にご配慮くださった出版社の寛大なお取り計らいにより、すべて無償で配布することが実現できました。ここに改めて感謝申し上げます。
注2:この点についてこの重要な査読付論文が明確に反論しているといった例があれば、ご指摘いただければ幸いです。(SMCより:このサイト上部の「問い合わせ」からお寄せ下さい)
注3:リスク論文では10mSvの被ばくリスクを検証するためには500万人が必要とされています。なお、なぜそうなってしまうかについての乱暴な説明が3節にあります。
注4:リスクの直接推計の方法自体やその有意性の検定(直接推計の方法や内容に応じた推計された値を統計学的にみて意味があるかどうかを確認するテスト)のやり方にはバリエーションがあります。
注5:正確には、通常、50〜100mSvより低い被ばく量におけるがんリスクのデータもあわせて利用します。
注6:PNAS論文フルテキストにアクセスできる環境にある方は、http://p.tl/JWrFから大きな図が見られます。
注7:つまり、追加的な被ばく量と超過リスクが正比例するというモデルです。
注8:国際放射線防護委員会(ICRP)もおおよその意味ではこの考え方(LNT)に沿っています。
注9:つまり、閾値モデルが妥当でないわけではなく、特定のがんではない全般的ながんのリスクを推定するには向かないだけとも言えます。
注10:もちろん、緊急事態における避難の手続き・困難さを考慮すると、一時的であれば「直ちに影響はない」という考え方には頷ける余地がないわけではありません。
注11:注11:ちなみに、近隣の公的機関が測定した放射線量が2μSV/時であるからといって、年間の外部被ばく量が約20mSV(つまり約20mSv/年)になるわけではありません。生活パタンや被ばく対策、あるいは局所的な放射性物質の分布状況によって、実際に被ばくする放射線量は変化するからです。
注12:数字は同報告書の表3.4−1より。ちなみに、このケースのように、リスクの増加分0.5%という数字は、何も無い時のがんによる死亡の可能性がたとえば x%(ベースラインあるいは期待死亡率ともいえます)であれば、発がんリスクが x・0.5/100増えることを意味する「相対リスク」を指す場合がありますので、資料を読む際には注意が必要です。
本稿の公開後、「専門家以外を対象としたリスク情報の提供に際しては、ベースラインに影響を受ける相対リスク表記ではな く、パーセンテージを計算するときに使われる分母として当該の集団全体を使う絶対リスクで表記し、読者の混同をさけるべきである」という旨のご指摘を受けました。
筆者はこのご指摘に対して全面的に賛成であり、ご指摘を受けて本稿の修正を行いました。ここに反省するとともに、ご指摘に対して感謝させていただきます。なお、このケースでも「相対リスク」ではなく「絶対リスク」による表記を採用すべきところではありますが、補正等に関する煩雑な議論を避けるため、そのまま「相対リスク」での表記を残してしまいました。申し訳ありませんが、その点には十分ご注意ください。
注13:数字を借りてはいますが、このような見積もりを適切に行うには、いくつかの前提について慎重な吟味が必要です。また、割り算ではなく、すくなくとも統計学的に直線を引く作業(回帰)を行わなければ、比例モデルの枠組みにおいても妥当なリスクの推定にはなりません。
注14:有効数字などにツッコミをいれるのはご遠慮いただきたいところであります。
注15:福島第一原子力発電所の事故によって、とくにこのまま抜本的な放射線対策の遅れが続けば、このザルの目が従来よりも細かくなることが予想されます。痛ましい、そして戦慄せざるを得ない状況であります。
注16:この点に興味をいだいた方は、ポパーの反証可能性の議論について一読されることをお勧めします。たとえば、チャルマーズ著『新版 科学論の展開―科学と呼ばれているのは何なのか?』恒星社厚生閣(1985)が入門書として取っつき易いでしょう。
※SMCでは本寄稿に関し、専門家/研究者の方からの異論・反論もお待ちしています。サイト上部の「ご質問・お問い合わせ」欄からご連絡下さい。
通常であれば、出版社側の規定にしたがって原文一ページにつき20ドル(計120ドル)および頒布一部毎に0.1ドルを支払わなければならないのですが、今回は現状にご配慮くださった出版社の寛大なお取り計らいにより、すべて無償で配布することが実現できました。ここに改めて感謝申し上げます。
注2:この点についてこの重要な査読付論文が明確に反論しているといった例があれば、ご指摘いただければ幸いです。(SMCより:このサイト上部の「問い合わせ」からお寄せ下さい)
注3:リスク論文では10mSvの被ばくリスクを検証するためには500万人が必要とされています。なお、なぜそうなってしまうかについての乱暴な説明が3節にあります。
注4:リスクの直接推計の方法自体やその有意性の検定(直接推計の方法や内容に応じた推計された値を統計学的にみて意味があるかどうかを確認するテスト)のやり方にはバリエーションがあります。
注5:正確には、通常、50〜100mSvより低い被ばく量におけるがんリスクのデータもあわせて利用します。
注6:PNAS論文フルテキストにアクセスできる環境にある方は、http://p.tl/JWrFから大きな図が見られます。
注7:つまり、追加的な被ばく量と超過リスクが正比例するというモデルです。
注8:国際放射線防護委員会(ICRP)もおおよその意味ではこの考え方(LNT)に沿っています。
注9:つまり、閾値モデルが妥当でないわけではなく、特定のがんではない全般的ながんのリスクを推定するには向かないだけとも言えます。
注10:もちろん、緊急事態における避難の手続き・困難さを考慮すると、一時的であれば「直ちに影響はない」という考え方には頷ける余地がないわけではありません。
注11:注11:ちなみに、近隣の公的機関が測定した放射線量が2μSV/時であるからといって、年間の外部被ばく量が約20mSV(つまり約20mSv/年)になるわけではありません。生活パタンや被ばく対策、あるいは局所的な放射性物質の分布状況によって、実際に被ばくする放射線量は変化するからです。
注12:数字は同報告書の表3.4−1より。ちなみに、このケースのように、リスクの増加分0.5%という数字は、何も無い時のがんによる死亡の可能性がたとえば x%(ベースラインあるいは期待死亡率ともいえます)であれば、発がんリスクが x・0.5/100増えることを意味する「相対リスク」を指す場合がありますので、資料を読む際には注意が必要です。
本稿の公開後、「専門家以外を対象としたリスク情報の提供に際しては、ベースラインに影響を受ける相対リスク表記ではな く、パーセンテージを計算するときに使われる分母として当該の集団全体を使う絶対リスクで表記し、読者の混同をさけるべきである」という旨のご指摘を受けました。
筆者はこのご指摘に対して全面的に賛成であり、ご指摘を受けて本稿の修正を行いました。ここに反省するとともに、ご指摘に対して感謝させていただきます。なお、このケースでも「相対リスク」ではなく「絶対リスク」による表記を採用すべきところではありますが、補正等に関する煩雑な議論を避けるため、そのまま「相対リスク」での表記を残してしまいました。申し訳ありませんが、その点には十分ご注意ください。
注13:数字を借りてはいますが、このような見積もりを適切に行うには、いくつかの前提について慎重な吟味が必要です。また、割り算ではなく、すくなくとも統計学的に直線を引く作業(回帰)を行わなければ、比例モデルの枠組みにおいても妥当なリスクの推定にはなりません。
注14:有効数字などにツッコミをいれるのはご遠慮いただきたいところであります。
注15:福島第一原子力発電所の事故によって、とくにこのまま抜本的な放射線対策の遅れが続けば、このザルの目が従来よりも細かくなることが予想されます。痛ましい、そして戦慄せざるを得ない状況であります。
注16:この点に興味をいだいた方は、ポパーの反証可能性の議論について一読されることをお勧めします。たとえば、チャルマーズ著『新版 科学論の展開―科学と呼ばれているのは何なのか?』恒星社厚生閣(1985)が入門書として取っつき易いでしょう。
※SMCでは本寄稿に関し、専門家/研究者の方からの異論・反論もお待ちしています。サイト上部の「ご質問・お問い合わせ」欄からご連絡下さい。
このたび個人主催のコミュニティを公開することにしましたので、
こちらでも紹介させて頂きます。
興味持たれた方はご覧になってみて下さい。
公開情報図書館
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5690894
−−−−−−−コミュトップより抜粋−−−−−−−
【目的】
放射線・原子力・心理面に関するWEB公開情報についての収集と整理。
内容の信憑性を検証するような性質のものではなく、
法人や研究所名義で公開している情報や
信頼できそうな研究者等が公開している情報を淡々と集約し、
管理人と参加者が情報を共有すること。
解説サイトおよび電子書籍
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63329164&comm_id=5690894
法人系ホームページ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63328922&comm_id=5690894
調査報告書等
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63329409&comm_id=5690894
データベースまたはリンク集
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63343684&comm_id=5690894
原子力発電所および事故に関する解説
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63359066&comm_id=5690894
こちらでも紹介させて頂きます。
興味持たれた方はご覧になってみて下さい。
公開情報図書館
http://mixi.jp/view_community.pl?id=5690894
−−−−−−−コミュトップより抜粋−−−−−−−
【目的】
放射線・原子力・心理面に関するWEB公開情報についての収集と整理。
内容の信憑性を検証するような性質のものではなく、
法人や研究所名義で公開している情報や
信頼できそうな研究者等が公開している情報を淡々と集約し、
管理人と参加者が情報を共有すること。
解説サイトおよび電子書籍
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63329164&comm_id=5690894
法人系ホームページ
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63328922&comm_id=5690894
調査報告書等
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63329409&comm_id=5690894
データベースまたはリンク集
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63343684&comm_id=5690894
原子力発電所および事故に関する解説
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63359066&comm_id=5690894
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人