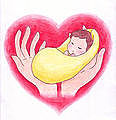|
|
|
|
コメント(11)
ツイッターの方からこれをmixiに掲載して欲しいというご依頼がありました。
色々な方が以下の記事を見てブログに原発被爆労災認定者が実名で被爆量と共に載せられています。
やっと見つけた…元記事
 校庭活動に放射線基準…文科省、福島県に提示へ
校庭活動に放射線基準…文科省、福島県に提示へ
文部科学省は、校庭など、幼稚園や学校の屋外で子供が活動する際の放射線量の基準を近く福島県に示す方針を固めた。
同県内では、一部の学校で比較的高い濃度の放射線量や放射性物質が検出されており、体育など屋外活動の実施可否について早期に基準を示す必要があると判断した。
同省などによると、基準は、児童生徒の年間被曝(ひばく)許容量を20ミリ・シーベルト(2万マイクロ・シーベルト)として、一般的な校庭の使用時間などを勘案して算定する方針。原子力安全委員会の助言を得た上で、大気中の線量基準などを同県に示す。基準を超えた場合、校庭を使用禁止にし、授業を屋内だけに限るなどの措置をとる案も出ている。
(2011年4月10日03時19分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110409-OYT1T00912.htm
以下は『karinnkarinのコーヒーブレイク』より転記
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1480429/1493461/68797994?page=1
この基準によれば、児童生徒の年間被曝許容量を20ミリシーベルト(2万マイクロ・シーベルト)としている。
20ミリシーベルトといえば、原発労働者の年間の許容被曝量。この数値に驚愕した人も多いのではないだろうか。
手もとに、一つの資料がある。
原発被曝労災が明らかになった人の被曝線量だ。
実名で公表されているので紹介したい。
□嶋橋 伸之
1993年5月、静岡県労働基準局磐田署に労災申請。
実名での最初の認定。(認定2件目)。
中部電力浜岡原発勤務、計測装置点検作業。81年3月から89年12月まで8年10ヶ月勤務して、50.63ミリシーベルト被曝。
慢性骨髄性白血病により91年10月20日死亡。29才。94年7月労災支給。
□大内 久
1999年9月30日、JCO東海事業所臨界事故。
16〜20シーベルト(16,000〜20,000ミリシーベルト)被曝。35歳。死亡。
□篠原 理人
同上。6〜10シーベルト被曝。39歳。死亡。
□横山 豊
同上。1〜4.5シーベルト被曝。54歳。生存。
JCO東海事業所臨界事故で水抜きの突撃隊が作られたが、当時、「針が振り切れた」というのは100ミリーシーベルトを超えたことをさした。
□長尾 光明
2003年1月、福島県富岡署に労災申請
福島第一、浜岡原発、ふげんで被曝労働。
77年10月から82年1月まで4年3ヶ月従事。70ミリシーベルト被曝。
多発性骨髄腫。2004年1月労災支給。
すべての情報開示と完全な補償を求め雇用主の石川島プラントや東電に話し合いを申し入れたが拒否され、04年10月7日、「原子力損害の賠償に関する法律」に基づき4400万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に提訴。
2007年12月死亡。82歳。2010年 2月、最高裁上告棄却。敗訴確定。
□喜友名 正(きゆな ただし)
淀川労働基準監督署に労災申請。
泊、敦賀原発など全国7ヶ所の原発で97年9月から6年4ヶ月間、非破壊検査に従事。99.76ミリシーベルト被曝。
悪性リンパ腫により2005年3月死亡。53歳。
2005年10月、遺族は労災を申請。2006年9月却下。2007年、不服申し立てにより厚生労働省で「りん伺」(上級官庁に伺いを立てる)決定。 2008年10月労災認定。
一度に大量の被曝をしない限り急性障害は現れない。しかし、この資料によれば、累計50〜70ミリシーベルトで、何年か経ってから障害が現れているのだ。被曝労働者も、おおむね50ミリシーベルトを超えたあたりから体調が悪くなると言われている。
子どもに年間許容被曝量が20ミリシーベルトという基準は、考えられない。この数字にワタシ達大人が向き合い、一歩を踏み出さなければ。
(転記完)
色々な方が以下の記事を見てブログに原発被爆労災認定者が実名で被爆量と共に載せられています。
やっと見つけた…元記事
文部科学省は、校庭など、幼稚園や学校の屋外で子供が活動する際の放射線量の基準を近く福島県に示す方針を固めた。
同県内では、一部の学校で比較的高い濃度の放射線量や放射性物質が検出されており、体育など屋外活動の実施可否について早期に基準を示す必要があると判断した。
同省などによると、基準は、児童生徒の年間被曝(ひばく)許容量を20ミリ・シーベルト(2万マイクロ・シーベルト)として、一般的な校庭の使用時間などを勘案して算定する方針。原子力安全委員会の助言を得た上で、大気中の線量基準などを同県に示す。基準を超えた場合、校庭を使用禁止にし、授業を屋内だけに限るなどの措置をとる案も出ている。
(2011年4月10日03時19分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110409-OYT1T00912.htm
以下は『karinnkarinのコーヒーブレイク』より転記
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1480429/1493461/68797994?page=1
この基準によれば、児童生徒の年間被曝許容量を20ミリシーベルト(2万マイクロ・シーベルト)としている。
20ミリシーベルトといえば、原発労働者の年間の許容被曝量。この数値に驚愕した人も多いのではないだろうか。
手もとに、一つの資料がある。
原発被曝労災が明らかになった人の被曝線量だ。
実名で公表されているので紹介したい。
□嶋橋 伸之
1993年5月、静岡県労働基準局磐田署に労災申請。
実名での最初の認定。(認定2件目)。
中部電力浜岡原発勤務、計測装置点検作業。81年3月から89年12月まで8年10ヶ月勤務して、50.63ミリシーベルト被曝。
慢性骨髄性白血病により91年10月20日死亡。29才。94年7月労災支給。
□大内 久
1999年9月30日、JCO東海事業所臨界事故。
16〜20シーベルト(16,000〜20,000ミリシーベルト)被曝。35歳。死亡。
□篠原 理人
同上。6〜10シーベルト被曝。39歳。死亡。
□横山 豊
同上。1〜4.5シーベルト被曝。54歳。生存。
JCO東海事業所臨界事故で水抜きの突撃隊が作られたが、当時、「針が振り切れた」というのは100ミリーシーベルトを超えたことをさした。
□長尾 光明
2003年1月、福島県富岡署に労災申請
福島第一、浜岡原発、ふげんで被曝労働。
77年10月から82年1月まで4年3ヶ月従事。70ミリシーベルト被曝。
多発性骨髄腫。2004年1月労災支給。
すべての情報開示と完全な補償を求め雇用主の石川島プラントや東電に話し合いを申し入れたが拒否され、04年10月7日、「原子力損害の賠償に関する法律」に基づき4400万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に提訴。
2007年12月死亡。82歳。2010年 2月、最高裁上告棄却。敗訴確定。
□喜友名 正(きゆな ただし)
淀川労働基準監督署に労災申請。
泊、敦賀原発など全国7ヶ所の原発で97年9月から6年4ヶ月間、非破壊検査に従事。99.76ミリシーベルト被曝。
悪性リンパ腫により2005年3月死亡。53歳。
2005年10月、遺族は労災を申請。2006年9月却下。2007年、不服申し立てにより厚生労働省で「りん伺」(上級官庁に伺いを立てる)決定。 2008年10月労災認定。
一度に大量の被曝をしない限り急性障害は現れない。しかし、この資料によれば、累計50〜70ミリシーベルトで、何年か経ってから障害が現れているのだ。被曝労働者も、おおむね50ミリシーベルトを超えたあたりから体調が悪くなると言われている。
子どもに年間許容被曝量が20ミリシーベルトという基準は、考えられない。この数字にワタシ達大人が向き合い、一歩を踏み出さなければ。
(転記完)
チェルノブイリ25年ドキュメンタリー
『見えない敵』chernobyl:The invisuible Thief
制作:BAUM-FILM Production(ドイツ 2006年)
報告:クリストフ・ポーケル/ドキュメンタリー作家
石川洋一解説員
「このドキュメンタリーでは語り部の妻の女性やチェルノブイリの除染作業に携わった画家がガンで亡くなっていきます。
しかし、それとチェルノブイリとの関連は証明されていません。
国家は常に「心配はない」「直ちに健康への影響は無い」と話します。原子力エネルギーの背後には常に巨大な国家があった、1986年のチェルノブイリ事故直後、ウクライナのキエフでは、何事も無かったかのように、子どもも参加したメーデーの行進が行われました。
2011.3.15、チェルノブイリの10分の1の放射能が福島第一原発から放出されました。国がこのことを発表したのは、1ヶ月近く経ってからでした。
このドキュメンタリー作家が追う、「見えない敵」とは、何だったのでしょうか?
(本編)
作家・クリストフ:1986年、旧ソビエト、ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所で起きた爆発事故。
その1年後ドイツ人の私は2ヶ月間ウクライナに入り、その時通訳をしていたマリーナと知り合い、2年後に結婚。
しかしマリーナは放射線障害と思われる病気で死亡。私はチェルノブイリ原発事故に深くかかわった人たちから話を聞いて、被害の真相を追う決意をした。
私たちは第二次大戦中、ナチスドイツがソビエトを攻撃した作戦について、ドキュメンタリーを制作していた。
私の父も携わっていた作戦の足跡を辿り、チェルノブイリの南を流れるドニエプル川を渡り、北へ向かった。
今になって思えば、私たちは高濃度の放射能で汚染された地域で仕事をしていたのだ。
共に行動していた音声のミーシャ、彼はチェルノブイリで原発が爆発した数週間後、事故処理の様子を撮影したチームの一員として仕事をした。私と知り合う1年前のことだった。
ミーシャはあの時使用した機材や車両などは全て放射能に汚染されていたので、埋めなければならなかった、と言っていた。
しかし、自分の健康のことなどは心配していなかったようだ。
今回、私は18年ぶりにミーシャに会った。同僚のカメラマン、コースチャも一緒に。
(1986.4.26未明に事故があり、「5月末から9月にかけて撮影された映像」が流れる)
カメラマン・コースチャ:
チェルノブイリの原発事故が発生した時、アフガニスタンにいて、大惨事があったという話を聞いた。直ちに帰国して赤の広場でメーデーのパレードを撮影した後、チェルノブイリ行きを命じられた。
自分から志願する形で派遣されたが、実際には選択の余地はなかった。事故の重大さをわかっていなかった。
音声担当・ミーシャ:
1986.5.28にチェルノブイリ事故現場に行くように命令を受け、5日後現地到着。前任の担当者と交代する為だった。上司から言われたら仕方がない。行かなければならなかったから、行ったまでだ。強制されたわけではないが、とにかく行った。
作家・クリストフ:
1986.4.26未明 操作ミスと設計上の欠陥から炉心が溶融し、爆発が生じた。爆発により、大量の放射能が放出され、周囲を汚染。東からの風が放射性粒子の雲をウクライナ、ソビエト全土、更にはヨーロッパまで運んだ。その結果、国境を越えた放射能被害をもたらすことになった。
「200万年に1度しか起こり得ない事故」これは、当時統計学者がはじき出した確率だ。
『見えない敵』chernobyl:The invisuible Thief
制作:BAUM-FILM Production(ドイツ 2006年)
報告:クリストフ・ポーケル/ドキュメンタリー作家
石川洋一解説員
「このドキュメンタリーでは語り部の妻の女性やチェルノブイリの除染作業に携わった画家がガンで亡くなっていきます。
しかし、それとチェルノブイリとの関連は証明されていません。
国家は常に「心配はない」「直ちに健康への影響は無い」と話します。原子力エネルギーの背後には常に巨大な国家があった、1986年のチェルノブイリ事故直後、ウクライナのキエフでは、何事も無かったかのように、子どもも参加したメーデーの行進が行われました。
2011.3.15、チェルノブイリの10分の1の放射能が福島第一原発から放出されました。国がこのことを発表したのは、1ヶ月近く経ってからでした。
このドキュメンタリー作家が追う、「見えない敵」とは、何だったのでしょうか?
(本編)
作家・クリストフ:1986年、旧ソビエト、ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所で起きた爆発事故。
その1年後ドイツ人の私は2ヶ月間ウクライナに入り、その時通訳をしていたマリーナと知り合い、2年後に結婚。
しかしマリーナは放射線障害と思われる病気で死亡。私はチェルノブイリ原発事故に深くかかわった人たちから話を聞いて、被害の真相を追う決意をした。
私たちは第二次大戦中、ナチスドイツがソビエトを攻撃した作戦について、ドキュメンタリーを制作していた。
私の父も携わっていた作戦の足跡を辿り、チェルノブイリの南を流れるドニエプル川を渡り、北へ向かった。
今になって思えば、私たちは高濃度の放射能で汚染された地域で仕事をしていたのだ。
共に行動していた音声のミーシャ、彼はチェルノブイリで原発が爆発した数週間後、事故処理の様子を撮影したチームの一員として仕事をした。私と知り合う1年前のことだった。
ミーシャはあの時使用した機材や車両などは全て放射能に汚染されていたので、埋めなければならなかった、と言っていた。
しかし、自分の健康のことなどは心配していなかったようだ。
今回、私は18年ぶりにミーシャに会った。同僚のカメラマン、コースチャも一緒に。
(1986.4.26未明に事故があり、「5月末から9月にかけて撮影された映像」が流れる)
カメラマン・コースチャ:
チェルノブイリの原発事故が発生した時、アフガニスタンにいて、大惨事があったという話を聞いた。直ちに帰国して赤の広場でメーデーのパレードを撮影した後、チェルノブイリ行きを命じられた。
自分から志願する形で派遣されたが、実際には選択の余地はなかった。事故の重大さをわかっていなかった。
音声担当・ミーシャ:
1986.5.28にチェルノブイリ事故現場に行くように命令を受け、5日後現地到着。前任の担当者と交代する為だった。上司から言われたら仕方がない。行かなければならなかったから、行ったまでだ。強制されたわけではないが、とにかく行った。
作家・クリストフ:
1986.4.26未明 操作ミスと設計上の欠陥から炉心が溶融し、爆発が生じた。爆発により、大量の放射能が放出され、周囲を汚染。東からの風が放射性粒子の雲をウクライナ、ソビエト全土、更にはヨーロッパまで運んだ。その結果、国境を越えた放射能被害をもたらすことになった。
「200万年に1度しか起こり得ない事故」これは、当時統計学者がはじき出した確率だ。
画家:ディミトリー・グティン、通称ディーマ
2000年夏、友人の紹介で彼のアパートを訪ねた。彼は何日も食事をしていなかったが、有り金をはたいて私の為にワインの小瓶を用意してくれた。ロシアでは、初めての来客とは酒を飲むのが習わしだったからだ。当時彼は38歳だった。
ディーマは原発事故の処理をする為に動員された80万人のうちの1人だ。
1986.8初め、汚染地帯に派遣された。軍を正式に除隊するわずか数日前のことだった。
画家・ディーマ:
1984-86まで軍に所属していた。2年間の兵役は法律で決められていた。’86に最初の任地だったチェルニゴフに戻された。まさに運命の巡り合わせ。そこからチェルノブイリまでは80kmの距離だった。
作家・クリストフ:
ディーマは放射能汚染地帯で兵役を終えた。入隊する前の彼は絵の勉強をしていた。母親の元には入隊前に描いた陽気で明るい絵が残っている。
ディーマ・母:
ディーマが兵役に就いて1年半が過ぎ、まもなく除隊、という時のこと、中尉に昇進することになり、最初の就任場所チェルニゴフに戻された。
息子はチェルノブイリの原発の事故のことを何も知らされていなかった。次の任地を聞くと、「チェルニゴフだ」という。驚くと何故かと聞かれたが、息子を恐がらせたくなかった為、「チェルノブイリで事故があった」とだけ話すと、息子は「関係無いよ」と、どういうわけかとても冷静で穏やかだった。
作家・クリストフ:
数年前私はモスクワで、有名なジャーナリストのウラジーミル・ステファノビッチ・グバレフに会った。ソビエト時代は共産党の機関紙だったプラウダ?の科学欄担当の編集者だった。
政権内の人間とも懇意だった彼は、第一線のジャーナリストとして、核実験にも立ち会った。
グバレフは、チェルノブイリの原発事故の後、高濃度の放射能汚染地帯で働いた人達、いわゆる「チェルノブイリ被災者」の1人でもある。爆発した原子炉に近づくことを許された、最初のジャーナリストだった。
ジャーナリスト・グバレフ:
チェルノブイリの原発事故で何より重要だったのは、何が起きているのか、正確に知ることだった。自分はあらゆる方面に通じていて、軍・軍民・情報機関のKGBなどあらゆる人から十分な情報を得ることができた。
当時プラウダの編集者だった観点から確かだと思ったのは、ゴルバチョフ書記長をはじめ政府は、チェルノブイリが何らかの理由で自分たちに向けられた“敵対行為”だと思い込んでいた。ゴルバチョフは全てが自分に向けられた攻撃と受け止め、一度もチェルノブイリには来なかった。人間とはそういうもの。
自分は3日後こう書いた。「チェルノブイリは20世紀の戦争だ。これまでとは姿を変えた戦争だ。その為に人々が死に、これからも死に続けるだろう…」と。
画家・ディーマ:
「人体には何も影響は無い」とのことだった。我々がもらった文書には、“軍事行動への参加”とだけ書かれていた。
冷戦時代のソビエト軍の基本訓練がどのようなものだったか、恐らくあなたも想像がつくだろう。
核爆発が起きた時に取る行動も、実におかしなものだった。爆発が起きたら、その方向にかかとを向け、うつ伏せになる。襟を立てて首を隠し、手をわきの下にいれる。
しかし現実には核爆発、とりわけあのような原子炉事故で放出される放射性物質は一つではない。実に様々な放射性物質が含まれていて、半減期も異なる。
現実は遥かに恐ろしい、それは間違いない。
2000年夏、友人の紹介で彼のアパートを訪ねた。彼は何日も食事をしていなかったが、有り金をはたいて私の為にワインの小瓶を用意してくれた。ロシアでは、初めての来客とは酒を飲むのが習わしだったからだ。当時彼は38歳だった。
ディーマは原発事故の処理をする為に動員された80万人のうちの1人だ。
1986.8初め、汚染地帯に派遣された。軍を正式に除隊するわずか数日前のことだった。
画家・ディーマ:
1984-86まで軍に所属していた。2年間の兵役は法律で決められていた。’86に最初の任地だったチェルニゴフに戻された。まさに運命の巡り合わせ。そこからチェルノブイリまでは80kmの距離だった。
作家・クリストフ:
ディーマは放射能汚染地帯で兵役を終えた。入隊する前の彼は絵の勉強をしていた。母親の元には入隊前に描いた陽気で明るい絵が残っている。
ディーマ・母:
ディーマが兵役に就いて1年半が過ぎ、まもなく除隊、という時のこと、中尉に昇進することになり、最初の就任場所チェルニゴフに戻された。
息子はチェルノブイリの原発の事故のことを何も知らされていなかった。次の任地を聞くと、「チェルニゴフだ」という。驚くと何故かと聞かれたが、息子を恐がらせたくなかった為、「チェルノブイリで事故があった」とだけ話すと、息子は「関係無いよ」と、どういうわけかとても冷静で穏やかだった。
作家・クリストフ:
数年前私はモスクワで、有名なジャーナリストのウラジーミル・ステファノビッチ・グバレフに会った。ソビエト時代は共産党の機関紙だったプラウダ?の科学欄担当の編集者だった。
政権内の人間とも懇意だった彼は、第一線のジャーナリストとして、核実験にも立ち会った。
グバレフは、チェルノブイリの原発事故の後、高濃度の放射能汚染地帯で働いた人達、いわゆる「チェルノブイリ被災者」の1人でもある。爆発した原子炉に近づくことを許された、最初のジャーナリストだった。
ジャーナリスト・グバレフ:
チェルノブイリの原発事故で何より重要だったのは、何が起きているのか、正確に知ることだった。自分はあらゆる方面に通じていて、軍・軍民・情報機関のKGBなどあらゆる人から十分な情報を得ることができた。
当時プラウダの編集者だった観点から確かだと思ったのは、ゴルバチョフ書記長をはじめ政府は、チェルノブイリが何らかの理由で自分たちに向けられた“敵対行為”だと思い込んでいた。ゴルバチョフは全てが自分に向けられた攻撃と受け止め、一度もチェルノブイリには来なかった。人間とはそういうもの。
自分は3日後こう書いた。「チェルノブイリは20世紀の戦争だ。これまでとは姿を変えた戦争だ。その為に人々が死に、これからも死に続けるだろう…」と。
画家・ディーマ:
「人体には何も影響は無い」とのことだった。我々がもらった文書には、“軍事行動への参加”とだけ書かれていた。
冷戦時代のソビエト軍の基本訓練がどのようなものだったか、恐らくあなたも想像がつくだろう。
核爆発が起きた時に取る行動も、実におかしなものだった。爆発が起きたら、その方向にかかとを向け、うつ伏せになる。襟を立てて首を隠し、手をわきの下にいれる。
しかし現実には核爆発、とりわけあのような原子炉事故で放出される放射性物質は一つではない。実に様々な放射性物質が含まれていて、半減期も異なる。
現実は遥かに恐ろしい、それは間違いない。
ジャーナリスト・グバレフ:
(溶融したウラン238の写真を見せ)チェルノブイリの4号炉が臨界に達し、爆発が起きる危険があると非常に心配した人がいた。自分は、核実験を自分の目で見ていたので、危険の程度を理解していた人間の1人である。
それはまさに地獄。ひと言で言って、地獄だ。自分は15km離れた所から核兵器の実験を見てそう実感した。
残念ながらソビエトでもアメリカでも、原子力の実験は軍の主導の元で行われていた。核爆発の実験場には、実験に使う動物と、当然のことながら、軍事施設があった。軍は大規模な実験を行い、放射能の影響に関して貴重なデータを得ていた。それで人体にはどの程度の被曝が許されるのか、わかっていた。
そうした基準は全てチェルノブイリにも適用されるはずだった。自分もどの程度被曝しても大丈夫か、大まかなことは知っていた。もちろんそこにあった物には一切触れず、常に防護服を着用し、終わったらすぐに廃棄処分した。
(撮影風景)
「あそこの照射線量は200レントゲンだろう」「爆発で飛ばされたパイプは約1000レントゲン」「ここは約200レントゲンだ」
ジャーナリスト・グバレフ:
最大の課題はヨーロッパ全域が放射能に汚染されるのを、いかに防ぐかということだった。そして、いかにして新たな爆発を防ぐか、更には大量の放射能を含んだ瓦礫を1箇所に集めるという作業もあった。
爆発した原子炉の火を消す最も単純な方法は、放っておくことだった。放っておけば1ヶ月後にはチェルノブイリの4号原子炉は燃えて無くなっただろう。
しかし、そうなれば、大気中にウランが放出され、ウラル地方から大西洋までヨーロッパ全域に拡散することになり、放射能レベルは通常の10倍から20倍になる。
画家・ディーマ:
放射能の拡散を防ぐには、原子炉を鋼鉄とコンクリートの構造物、石棺で覆うしかない。
しかし、そのような大きなものを作るには大量のコンクリートが必要だ。そこでコンクリート工場を作り、現場でコンクリートを生産することになった。
我々は鉄道工兵だったので、我々の部隊の仕事は線路の敷設だった。コンクリート工場から原子炉までを線路で繋いだ。これでコンクリートを大型車両に搭載して運ぶことができた。そしてそのコンクリートが全ての上に流し込まれた。
ジャーナリスト・グバレフ:
事故後すぐに放射能被害の広がりを抑える作業が始まった。原子炉の下にまだ冷却用の水が残っていて危険だったからだ。また、炉心も溶融していた。炉心が冷却水に触れたら、新たな大規模爆発が起きかねない。そうなれば、ウクライナの大都市キエフ全域も放射能に汚染される。何としてもこの水を抜く必要があった。真っ暗な中で二人の若者が原子炉の水を抜く為中に入った。彼らは大量の放射能を浴びたが、水を抜くことには成功した。
(モスクワ郊外・ミチノ墓地)
作家・クリストフ:
ここにはチェルノブイリの原発事故で早い時期に処理にあたった人たちが埋葬されている。彼らは被爆から僅か数週間のうちに無残な死に方で亡くなったのだ。
私は慰霊碑を見て衝撃を受けた。死者の名誉を讃えると同時に人間が作り出した原子力に対して、人間がいかに無力であるかを訴えているようだ。
(人間の像は皮膚が焼けただれたような像)
(溶融したウラン238の写真を見せ)チェルノブイリの4号炉が臨界に達し、爆発が起きる危険があると非常に心配した人がいた。自分は、核実験を自分の目で見ていたので、危険の程度を理解していた人間の1人である。
それはまさに地獄。ひと言で言って、地獄だ。自分は15km離れた所から核兵器の実験を見てそう実感した。
残念ながらソビエトでもアメリカでも、原子力の実験は軍の主導の元で行われていた。核爆発の実験場には、実験に使う動物と、当然のことながら、軍事施設があった。軍は大規模な実験を行い、放射能の影響に関して貴重なデータを得ていた。それで人体にはどの程度の被曝が許されるのか、わかっていた。
そうした基準は全てチェルノブイリにも適用されるはずだった。自分もどの程度被曝しても大丈夫か、大まかなことは知っていた。もちろんそこにあった物には一切触れず、常に防護服を着用し、終わったらすぐに廃棄処分した。
(撮影風景)
「あそこの照射線量は200レントゲンだろう」「爆発で飛ばされたパイプは約1000レントゲン」「ここは約200レントゲンだ」
ジャーナリスト・グバレフ:
最大の課題はヨーロッパ全域が放射能に汚染されるのを、いかに防ぐかということだった。そして、いかにして新たな爆発を防ぐか、更には大量の放射能を含んだ瓦礫を1箇所に集めるという作業もあった。
爆発した原子炉の火を消す最も単純な方法は、放っておくことだった。放っておけば1ヶ月後にはチェルノブイリの4号原子炉は燃えて無くなっただろう。
しかし、そうなれば、大気中にウランが放出され、ウラル地方から大西洋までヨーロッパ全域に拡散することになり、放射能レベルは通常の10倍から20倍になる。
画家・ディーマ:
放射能の拡散を防ぐには、原子炉を鋼鉄とコンクリートの構造物、石棺で覆うしかない。
しかし、そのような大きなものを作るには大量のコンクリートが必要だ。そこでコンクリート工場を作り、現場でコンクリートを生産することになった。
我々は鉄道工兵だったので、我々の部隊の仕事は線路の敷設だった。コンクリート工場から原子炉までを線路で繋いだ。これでコンクリートを大型車両に搭載して運ぶことができた。そしてそのコンクリートが全ての上に流し込まれた。
ジャーナリスト・グバレフ:
事故後すぐに放射能被害の広がりを抑える作業が始まった。原子炉の下にまだ冷却用の水が残っていて危険だったからだ。また、炉心も溶融していた。炉心が冷却水に触れたら、新たな大規模爆発が起きかねない。そうなれば、ウクライナの大都市キエフ全域も放射能に汚染される。何としてもこの水を抜く必要があった。真っ暗な中で二人の若者が原子炉の水を抜く為中に入った。彼らは大量の放射能を浴びたが、水を抜くことには成功した。
(モスクワ郊外・ミチノ墓地)
作家・クリストフ:
ここにはチェルノブイリの原発事故で早い時期に処理にあたった人たちが埋葬されている。彼らは被爆から僅か数週間のうちに無残な死に方で亡くなったのだ。
私は慰霊碑を見て衝撃を受けた。死者の名誉を讃えると同時に人間が作り出した原子力に対して、人間がいかに無力であるかを訴えているようだ。
(人間の像は皮膚が焼けただれたような像)
カメラマン・コースチャ:
(写真を指差し)マロディア・フローレンコ、カメラマンだったが死んだ。脚本家・照明技師・運転手・プロデューサーのシャブリー。カメラマンで生きているのは自分だけだ。
(撮影映像:軍上官から作業員への説明)
「具体的に説明しよう。ここから階段を上り、突き当たりまでまっすぐ行け。手押し車に瓦礫を載せろ。1人が載せて、他の2人が運ぶ。向こうに着いたら、すぐに数え始めろ。90まで数えたら駆け足で戻る。」
Q現場に入ったら、90まで数えることが決まっていたのか?
カメラマン・コースチャ:とにかく、撮影することしか考えていなかった。
Q制限時間があることに恐ろしさを感じなかったのか?
カメラマン・コースチャ:もう一度行くことを考えたら、危険を我慢して1回で終わらせる方がマシだった。
音声担当・ミーシャ:上官が命令する。向こうへ行ったら数を数えながらシャベルで瓦礫を掬え。90まで数え終えたら、全てを捨てて走って外に出ろ。戻ったら次の班が行け、と。
しかし映像で見せたように、カメラマンはあらかじめ向こうで待機している。ドアが開いて兵士が入って来て、出る所まで撮影するので、更に20秒居残ることになる。カメラマンとはそういうものだ。
カメラマン・コースチャ:
チェルノブイリの原発事故現場を去る時、持って行った全ての撮影機材を置いてこなくてはならなかった。
音声担当・ミーシャ:テープレコーダー2台、同時録音ができるきカメラが1台、手持ちカメラが2台、三脚。
Q撮りだめしたフィルムは?
音声担当・ミーシャ:フィルムは持って帰ったが、撮影機材は全て向こうに棄ててきた。
ジャーナリスト・グバレフ:
どこが危険な場所かというと、原子炉のすぐ隣でも、プルトニウムが無い限り、危険では無かった。しかし、放射能レベルを調べると、10km先でも非常に危険な場所があった。あのような大災害ではどこが危険で、どこが危険でないのかはわからないのだ。
作家・クリストフ:
どこが危険の境界線なのか。放射能に対する反応は、人それぞれ異なる。
放射性の小さなチリでさえも、死をもたらすことがあるのだ。
1987年我々はチェルノブイリの立ち入り禁止区域に近い場所で放射能汚染を無視して撮影を続けた。
ドイツ軍の占領時代に覚えていることを何か話してもらえないかと民家を訪ね、自分の父が闘った戦争について、ドキュメンタリーの撮影に夢中だった私は、ここで新たな戦争が起きていることに気づいていなかった。
人間が作った目に見えない敵との戦いだ。
ディーマ曰く、「チェルノブイリは人間が自然、そして自分自身を敵に回した戦争だ」と私に言った。
画家・ディーマ:
軍当局は私達が実際にどこにいるのか、原子炉から何km離れた所にいるのかを発表するつもりなど無かった。その頃にはすでに道路は閉鎖され、パトロールが行われ、「半径30km以内立ち入り禁止」という標識が立てられていた。
30km圏内には空気中に大量の放射性物質が排出されていた。辺りの土の多量の放射性物質を含んでいたのだ。もちろん、野営テントを張って作業している我々には、知る由もなかった。
毎朝、我々はミネラルウォーターを飲み、片手一杯ほどの白い粉が支給された。その粉が何なのかは知らなかったが、主の祈りを信じるように、この粉が自分達を救ってくれる、と信じていた。そう信じていたから作業を続けられたのだと思う。皆明るい雰囲気で特に夜は楽しかった。ちょうどその頃、サッカーのワールドカップ、メキシコ大会が行われていたので、皆大声をあげて応援していた。
兵士達は、汚染物質を除去する作業を10時間以上も行った後で、這うようにしてテレビのある部屋へ行き、ワールドカップの試合を見ていたのだ。
(写真を指差し)マロディア・フローレンコ、カメラマンだったが死んだ。脚本家・照明技師・運転手・プロデューサーのシャブリー。カメラマンで生きているのは自分だけだ。
(撮影映像:軍上官から作業員への説明)
「具体的に説明しよう。ここから階段を上り、突き当たりまでまっすぐ行け。手押し車に瓦礫を載せろ。1人が載せて、他の2人が運ぶ。向こうに着いたら、すぐに数え始めろ。90まで数えたら駆け足で戻る。」
Q現場に入ったら、90まで数えることが決まっていたのか?
カメラマン・コースチャ:とにかく、撮影することしか考えていなかった。
Q制限時間があることに恐ろしさを感じなかったのか?
カメラマン・コースチャ:もう一度行くことを考えたら、危険を我慢して1回で終わらせる方がマシだった。
音声担当・ミーシャ:上官が命令する。向こうへ行ったら数を数えながらシャベルで瓦礫を掬え。90まで数え終えたら、全てを捨てて走って外に出ろ。戻ったら次の班が行け、と。
しかし映像で見せたように、カメラマンはあらかじめ向こうで待機している。ドアが開いて兵士が入って来て、出る所まで撮影するので、更に20秒居残ることになる。カメラマンとはそういうものだ。
カメラマン・コースチャ:
チェルノブイリの原発事故現場を去る時、持って行った全ての撮影機材を置いてこなくてはならなかった。
音声担当・ミーシャ:テープレコーダー2台、同時録音ができるきカメラが1台、手持ちカメラが2台、三脚。
Q撮りだめしたフィルムは?
音声担当・ミーシャ:フィルムは持って帰ったが、撮影機材は全て向こうに棄ててきた。
ジャーナリスト・グバレフ:
どこが危険な場所かというと、原子炉のすぐ隣でも、プルトニウムが無い限り、危険では無かった。しかし、放射能レベルを調べると、10km先でも非常に危険な場所があった。あのような大災害ではどこが危険で、どこが危険でないのかはわからないのだ。
作家・クリストフ:
どこが危険の境界線なのか。放射能に対する反応は、人それぞれ異なる。
放射性の小さなチリでさえも、死をもたらすことがあるのだ。
1987年我々はチェルノブイリの立ち入り禁止区域に近い場所で放射能汚染を無視して撮影を続けた。
ドイツ軍の占領時代に覚えていることを何か話してもらえないかと民家を訪ね、自分の父が闘った戦争について、ドキュメンタリーの撮影に夢中だった私は、ここで新たな戦争が起きていることに気づいていなかった。
人間が作った目に見えない敵との戦いだ。
ディーマ曰く、「チェルノブイリは人間が自然、そして自分自身を敵に回した戦争だ」と私に言った。
画家・ディーマ:
軍当局は私達が実際にどこにいるのか、原子炉から何km離れた所にいるのかを発表するつもりなど無かった。その頃にはすでに道路は閉鎖され、パトロールが行われ、「半径30km以内立ち入り禁止」という標識が立てられていた。
30km圏内には空気中に大量の放射性物質が排出されていた。辺りの土の多量の放射性物質を含んでいたのだ。もちろん、野営テントを張って作業している我々には、知る由もなかった。
毎朝、我々はミネラルウォーターを飲み、片手一杯ほどの白い粉が支給された。その粉が何なのかは知らなかったが、主の祈りを信じるように、この粉が自分達を救ってくれる、と信じていた。そう信じていたから作業を続けられたのだと思う。皆明るい雰囲気で特に夜は楽しかった。ちょうどその頃、サッカーのワールドカップ、メキシコ大会が行われていたので、皆大声をあげて応援していた。
兵士達は、汚染物質を除去する作業を10時間以上も行った後で、這うようにしてテレビのある部屋へ行き、ワールドカップの試合を見ていたのだ。
作家・クリストフ:
1989年5月、マリーナと私は結婚した。2年前に一緒にロケをしていた頃の幸せがずっと続いて欲しいと思った。撮影中は行く先々でとても温かいもてなしを受けた。素晴らしい転機にも恵まれた。田舎道を車で走り、森に入って崩れた地下壕を探した。
チェルノブイリから80kmほど離れたチェルニゴフで、地元の市場の管理者達がロケ機材のメーターを見て、放射能数値の抜き打ち検査だと勘違いした。ロケは中断するしかなかった。
画家・ディーマ:
水は十分にあった。巨大な貯水タンクがあったし、給水トラックも来ていた。おかげで汚れはちゃんと洗い流すことができた。
それに、熱いお湯やぬるめのお湯が利用できるシャワーもあった。だから、安全対策が不十分だとは思わなかった。
作家・クリストフ:
水は全ての命に欠かせないもの。水は放射性のチリは洗い流すが、放射性物質を破壊するわけではない。どんなに進んだ技術があっても、結局最後に役に立つのは水だけだ。しかし、汚染された水はどこへ流れて行くのだろうか。
画家・ディーマ:
チリには放射性物質が含まれている、という説明は受けたが、放射性のチリが何なのか、また、それがどのような悪影響を与えるのかは教えられなかった。チリは放射能で汚染されていると考えられていたので、防護マスクは絶対必要っだった。マスクをすれば、チリを吸い込まずに済む。あらゆる放射性粒子が気管支に入らないようにする為だった。我々は我慢できる限り、あのマスクをして作業をしたが、気温が30℃になる中、長時間付けているのはとても辛かった。
画家・ディーマの姉 タチアナ:
私たちの祖父母は当時のレニングラードから少し離れたプシュケに住んでいた。私と弟のディーマは子どもの頃、ずっとそこで休暇を過ごした。
祖父母の家には見事な庭があって、様々な花が咲いていた。祖母は花が大好きだったので、私も花の手入れを手伝った。ディーマは美術学校に通っていた頃、よく花の絵を描いていた。
子どもの頃の私達はとても仲が良かったが、大きくなってからは別々の道を進んでも、心はいつも繋がっていた。
しかし弟がチェルノブイリに行ってから、とても内向的になった。自分の世界に引きこもってしまった。
恐らくあまりに多くのことを経験した為、昔と同じようには生きられなくなってしまったのだろう。
彼の気持ちを綴った、最後の詩がある。
「不吉なカラスの鳴き声のように
広がるチェルノブイリの病、見えない敵。
それが私達の若々しい歌を汚す」
この数行が全てを言い表している。
チェルノブイリで浴びた放射能が目に見えない敵のように若者を蝕んでいくのだ。
ディーマの描く世界は、元々とても明るくてカラフルだった。チェルノブイリは、それに黒い絵の具を塗りたくったのだ。
画家・ディーマ:
(絵を見せながら)これら3つの絵はダイナミックな構図を用いて描いてみた。黙示録をテーマにしたもので、ダンテが叙事詩「新曲」の中で書いた「地獄編」の世界をモチーフにしている。ダンテの描いた地獄は、決して熱いものではなかった。疎外感に満ちた、寒い所なのだ。だから自分は、赤やオレンジなどの色を選ばなかった。疎外感を示す、冷たい色を選んだ。恐らくとても主観的な解釈だが、この人たちは葉っぱを思い起こさせる。枝から引きちぎられ、ぐるぐると円を描きながら舞ってどこかへ消えて行く葉っぱだ。彼らは触れ合いはするものの、互いにしっかり抱き合うほどの体力がないのだ。
1989年5月、マリーナと私は結婚した。2年前に一緒にロケをしていた頃の幸せがずっと続いて欲しいと思った。撮影中は行く先々でとても温かいもてなしを受けた。素晴らしい転機にも恵まれた。田舎道を車で走り、森に入って崩れた地下壕を探した。
チェルノブイリから80kmほど離れたチェルニゴフで、地元の市場の管理者達がロケ機材のメーターを見て、放射能数値の抜き打ち検査だと勘違いした。ロケは中断するしかなかった。
画家・ディーマ:
水は十分にあった。巨大な貯水タンクがあったし、給水トラックも来ていた。おかげで汚れはちゃんと洗い流すことができた。
それに、熱いお湯やぬるめのお湯が利用できるシャワーもあった。だから、安全対策が不十分だとは思わなかった。
作家・クリストフ:
水は全ての命に欠かせないもの。水は放射性のチリは洗い流すが、放射性物質を破壊するわけではない。どんなに進んだ技術があっても、結局最後に役に立つのは水だけだ。しかし、汚染された水はどこへ流れて行くのだろうか。
画家・ディーマ:
チリには放射性物質が含まれている、という説明は受けたが、放射性のチリが何なのか、また、それがどのような悪影響を与えるのかは教えられなかった。チリは放射能で汚染されていると考えられていたので、防護マスクは絶対必要っだった。マスクをすれば、チリを吸い込まずに済む。あらゆる放射性粒子が気管支に入らないようにする為だった。我々は我慢できる限り、あのマスクをして作業をしたが、気温が30℃になる中、長時間付けているのはとても辛かった。
画家・ディーマの姉 タチアナ:
私たちの祖父母は当時のレニングラードから少し離れたプシュケに住んでいた。私と弟のディーマは子どもの頃、ずっとそこで休暇を過ごした。
祖父母の家には見事な庭があって、様々な花が咲いていた。祖母は花が大好きだったので、私も花の手入れを手伝った。ディーマは美術学校に通っていた頃、よく花の絵を描いていた。
子どもの頃の私達はとても仲が良かったが、大きくなってからは別々の道を進んでも、心はいつも繋がっていた。
しかし弟がチェルノブイリに行ってから、とても内向的になった。自分の世界に引きこもってしまった。
恐らくあまりに多くのことを経験した為、昔と同じようには生きられなくなってしまったのだろう。
彼の気持ちを綴った、最後の詩がある。
「不吉なカラスの鳴き声のように
広がるチェルノブイリの病、見えない敵。
それが私達の若々しい歌を汚す」
この数行が全てを言い表している。
チェルノブイリで浴びた放射能が目に見えない敵のように若者を蝕んでいくのだ。
ディーマの描く世界は、元々とても明るくてカラフルだった。チェルノブイリは、それに黒い絵の具を塗りたくったのだ。
画家・ディーマ:
(絵を見せながら)これら3つの絵はダイナミックな構図を用いて描いてみた。黙示録をテーマにしたもので、ダンテが叙事詩「新曲」の中で書いた「地獄編」の世界をモチーフにしている。ダンテの描いた地獄は、決して熱いものではなかった。疎外感に満ちた、寒い所なのだ。だから自分は、赤やオレンジなどの色を選ばなかった。疎外感を示す、冷たい色を選んだ。恐らくとても主観的な解釈だが、この人たちは葉っぱを思い起こさせる。枝から引きちぎられ、ぐるぐると円を描きながら舞ってどこかへ消えて行く葉っぱだ。彼らは触れ合いはするものの、互いにしっかり抱き合うほどの体力がないのだ。
作家・クリストフ:
遠隔操作できる重機はすぐに使えなくなった。強い放射線が電子機器を壊してしまったのだ。
もはや頼りは人間の体しかない。シャベルと手押し車と水を使った作業だ。
ジャーナリスト・グバレフ:
一部の兵士や消防士たちは全く無意味な死に方をした。彼らは4号炉の建屋の火を消した。そして、再び発火しないかを規則に従って、その場に留まり監視していたのだ。
その為、致死量の10倍の放射線を浴びてしまった。火を消してすぐに立ち去っていれば、今も生きていられたかもしれない。
チェルノブイリではその他、汚染された屋上に上がってする作業もあった。3号炉の屋上から黒鉛の塊を落とす仕事だ。驚いたことに、必要な人数の10倍の志願者があった。彼らは危険を承知で引き受けた。これは賭けでもあり、人間の本質なのだ。
消火作業にあたった人たちは、致死量の放射線を1回ならず、10回分も浴びていた。
1ヶ月以内に死ぬことは明白だったので、自分はゴルバチョフに、彼らに国家英雄の名誉称号を贈るべきだと言った。そうすれば、国が讃えてくれたことを生きている間に知ることができる、と進言した。
ゴルバチョフは必ずそうすると約束してくれたが、実際に称号が贈られたのは6ヶ月後だった。
画家・ディーマ:
これはチェルノブイリの事故処理作業員に配られた一般的なバッヂ。表彰状と一緒にもらった。
芸術的に見れば、ロシアの伝統的な形の十字架を取り入れた極めて美しいデザインと言えるだろう。しかしこれは、勲章ではない。ご覧の通りだ。
作家・クリストフ:
1986年、モスクワへ向かう途中、ナタリアに会った。学校時代の友人、ディーマを紹介してくれたのはナタリアだ。
ディーマの友人・ナタリア:
ディーマとは、14歳の時、同じクラスだった。旧ソビエトでは7年生だ。
彼は他の生徒と違う感じがあった。自由な感じで、当時から芸術家タイプだった。
卒業後に2回ほど同窓会があった。ディーマも来ていて何の屈託もなく「チェルノブイリに行っていたんだ」と言っていた。
私は驚きを隠せなかった。同級生にあそこへ行っていた人がいたなんてショックだった。
「どうだった?」「なぜ行ったの?」と色々質問した。ディーマは愚痴や文句は一切言わなかった。身体が弱っているようにも見えず、見た目には何も変わっていなかったのだ。プライドがあって同情などされたくなかったのだろう。
画家・ディーマ:
除隊して、モスクワに戻ってから真っ先にしたのは買い物だった。車でスポーツ用品店に行って、ウェイトトレーニングの道具を買ったのだ。軍隊では楽しんでやっていたから。
ところが、ギョッとした。おもりを二つ付けただけで、バーベルを挙げられなくなっていたのだ。
軍隊ではもっと重いのを挙げて、私より体格の良い仲間を驚かせていた。
筋肉が弱くなっていたのだ。放射線によって、筋肉や神経など、繊細な組織が破壊されたのだ。
そういうふうに推測する以外、原因は考えられなかった。
この手元にある二つの文書は、いずれもチェルノブイリ被災者に関するものだ。
一つ目は1997年に出されたもので、我慢できるような普通の病気の人も「チェルノブイリ被災者」として認定された。命に別条のない肺の病気なども含まれる。
ところが状況が変化した。1999年に出された二つ目の文書には、「チェルノブイリ被災者の傷病手当は命にかかわる病気の人にのみ支払われる」、と書かれている。つまりはガンだけ、ということ。
遠隔操作できる重機はすぐに使えなくなった。強い放射線が電子機器を壊してしまったのだ。
もはや頼りは人間の体しかない。シャベルと手押し車と水を使った作業だ。
ジャーナリスト・グバレフ:
一部の兵士や消防士たちは全く無意味な死に方をした。彼らは4号炉の建屋の火を消した。そして、再び発火しないかを規則に従って、その場に留まり監視していたのだ。
その為、致死量の10倍の放射線を浴びてしまった。火を消してすぐに立ち去っていれば、今も生きていられたかもしれない。
チェルノブイリではその他、汚染された屋上に上がってする作業もあった。3号炉の屋上から黒鉛の塊を落とす仕事だ。驚いたことに、必要な人数の10倍の志願者があった。彼らは危険を承知で引き受けた。これは賭けでもあり、人間の本質なのだ。
消火作業にあたった人たちは、致死量の放射線を1回ならず、10回分も浴びていた。
1ヶ月以内に死ぬことは明白だったので、自分はゴルバチョフに、彼らに国家英雄の名誉称号を贈るべきだと言った。そうすれば、国が讃えてくれたことを生きている間に知ることができる、と進言した。
ゴルバチョフは必ずそうすると約束してくれたが、実際に称号が贈られたのは6ヶ月後だった。
画家・ディーマ:
これはチェルノブイリの事故処理作業員に配られた一般的なバッヂ。表彰状と一緒にもらった。
芸術的に見れば、ロシアの伝統的な形の十字架を取り入れた極めて美しいデザインと言えるだろう。しかしこれは、勲章ではない。ご覧の通りだ。
作家・クリストフ:
1986年、モスクワへ向かう途中、ナタリアに会った。学校時代の友人、ディーマを紹介してくれたのはナタリアだ。
ディーマの友人・ナタリア:
ディーマとは、14歳の時、同じクラスだった。旧ソビエトでは7年生だ。
彼は他の生徒と違う感じがあった。自由な感じで、当時から芸術家タイプだった。
卒業後に2回ほど同窓会があった。ディーマも来ていて何の屈託もなく「チェルノブイリに行っていたんだ」と言っていた。
私は驚きを隠せなかった。同級生にあそこへ行っていた人がいたなんてショックだった。
「どうだった?」「なぜ行ったの?」と色々質問した。ディーマは愚痴や文句は一切言わなかった。身体が弱っているようにも見えず、見た目には何も変わっていなかったのだ。プライドがあって同情などされたくなかったのだろう。
画家・ディーマ:
除隊して、モスクワに戻ってから真っ先にしたのは買い物だった。車でスポーツ用品店に行って、ウェイトトレーニングの道具を買ったのだ。軍隊では楽しんでやっていたから。
ところが、ギョッとした。おもりを二つ付けただけで、バーベルを挙げられなくなっていたのだ。
軍隊ではもっと重いのを挙げて、私より体格の良い仲間を驚かせていた。
筋肉が弱くなっていたのだ。放射線によって、筋肉や神経など、繊細な組織が破壊されたのだ。
そういうふうに推測する以外、原因は考えられなかった。
この手元にある二つの文書は、いずれもチェルノブイリ被災者に関するものだ。
一つ目は1997年に出されたもので、我慢できるような普通の病気の人も「チェルノブイリ被災者」として認定された。命に別条のない肺の病気なども含まれる。
ところが状況が変化した。1999年に出された二つ目の文書には、「チェルノブイリ被災者の傷病手当は命にかかわる病気の人にのみ支払われる」、と書かれている。つまりはガンだけ、ということ。
ディーマの友人・ナタリア:
ディーマの病気はチェルノブイリに関係あると認定されるべきだった。そうすればもう少し多くの補助を受けられたはずだ。年金は物凄く少なくて、生活ぶりはご覧になったと思いますが、すっかり痩せ細り、満足に食事もしていなかった。
しかし、何より彼を苦しませたのは、不当な扱いだったと私は思っている。
なぜ国ではなく、自分の方から、病気の原因を証明しなくてはならないのか。
彼は私にこう言った。「僕は行列の最後尾の1人かもしれない」
既に多くの人が死んでいるので、自分もその列に並んでいるのを知っていたのだ。
作家・クリストフ:
1990年にマリーナは乳がんと診断された。35歳の誕生日を迎える2ヶ月前、結婚してから僅か9ヶ月後のことだ。
放射能レベルの高い地域でロケをしていたのが病気の原因ではないかと私は自分を責めた。
ところが後に別の事実がわかった。マリーナは子どもの頃、シベリアのクラスノカメンスク近郊で暮らしていたことがあったのだ。
近くには世界有数のウラン鉱山があった。軍医だった彼女の父親は、その地に赴任した3年後、脳腫瘍で亡くなっている。
東シベリアのクラスノカメンスク。ここでは核爆弾や原子力発電所に使う為、ウランが採掘されている。水は放射能で汚染され、鉱山からは天然の放射性ガスが大量に放出されている。周辺には、ウラン鉱山から掘り出された膨大な量の残土が積み上げられている。
マリーナは10代の頃、ここで暮らしていたのだ。
ジャーナリスト・グバレフ:
1954年には放射能について全てがわかっていた。どの程度放射能を浴びると、人体に危険を及ぼし、どの程度なら大丈夫なのかということが解明されていた。
1985年くらいまで、大気中の放射能は今より最高で3倍も高いレベルだった。
原因はソビエトとアメリカが大気中で行った核実験だ。
チェルノブイリの事故をきっかけに、我々は反軍国主義のプロパガンダを全面的に打ち出すことができた。チェルノブイリは核戦争がいかに恐ろしいかを見せてくれたからだ。
被曝の恐ろしいところは、どんな影響があるのか、想像しにくいことだ。
放射性物質のストロンチウムは、骨や顎に蓄積され、やがて歯が抜け落ちる。しかし痛みを感じるものではないので、だからこそ、兵士たちはどんな仕事でも引き受けたのだ。
そして、後になって代償を支払わされた。それが、「チェルノブイリの悲劇」なのだ。
作家・クリストフ:
1991年9月、私の妻、マリーナは亡くなった。まもなく36歳になるところだった。
放射線が病気の原因だと思っているが、証明することはできない…
画家・ディーマ:
体に多少の痛みと不快感がある。そう感じるのは、放射能の影響が波のように体に入り、出て行くからだと考えるようにしている。
何とも言いようのない状態になって、そのたびに「自分はもう、これでお終いだ」と思ってしまう。これが1回戦、2回戦、3回戦とずっと続いて、まるで自分は知らない土地で風車と闘う…ドンキホーテみたいだ…
ディーマの友人・ナタリア:
1995年か96年のことだったと思うが、ディーマが病院から電話をしてきて「僕のことを覚えているかい?迎えに来て欲しい」と言われた。
モスクワは大きな町なので病院までの道がわからなくて、時間がかかった。
彼は大きな病院のロビーで座っていて、付き添っている人はいなかった。
痩せ細って青白い顔をしていた。まるで老人のようで、見るからにかわいそうな姿だった。
ディーマは何回か頭の手術を受けていて、本当に気の毒な姿だった。同窓会の時と比べたら、恐ろしいほどの変わりようだ。もはや廃人同様になっていた。
ディーマの病気はチェルノブイリに関係あると認定されるべきだった。そうすればもう少し多くの補助を受けられたはずだ。年金は物凄く少なくて、生活ぶりはご覧になったと思いますが、すっかり痩せ細り、満足に食事もしていなかった。
しかし、何より彼を苦しませたのは、不当な扱いだったと私は思っている。
なぜ国ではなく、自分の方から、病気の原因を証明しなくてはならないのか。
彼は私にこう言った。「僕は行列の最後尾の1人かもしれない」
既に多くの人が死んでいるので、自分もその列に並んでいるのを知っていたのだ。
作家・クリストフ:
1990年にマリーナは乳がんと診断された。35歳の誕生日を迎える2ヶ月前、結婚してから僅か9ヶ月後のことだ。
放射能レベルの高い地域でロケをしていたのが病気の原因ではないかと私は自分を責めた。
ところが後に別の事実がわかった。マリーナは子どもの頃、シベリアのクラスノカメンスク近郊で暮らしていたことがあったのだ。
近くには世界有数のウラン鉱山があった。軍医だった彼女の父親は、その地に赴任した3年後、脳腫瘍で亡くなっている。
東シベリアのクラスノカメンスク。ここでは核爆弾や原子力発電所に使う為、ウランが採掘されている。水は放射能で汚染され、鉱山からは天然の放射性ガスが大量に放出されている。周辺には、ウラン鉱山から掘り出された膨大な量の残土が積み上げられている。
マリーナは10代の頃、ここで暮らしていたのだ。
ジャーナリスト・グバレフ:
1954年には放射能について全てがわかっていた。どの程度放射能を浴びると、人体に危険を及ぼし、どの程度なら大丈夫なのかということが解明されていた。
1985年くらいまで、大気中の放射能は今より最高で3倍も高いレベルだった。
原因はソビエトとアメリカが大気中で行った核実験だ。
チェルノブイリの事故をきっかけに、我々は反軍国主義のプロパガンダを全面的に打ち出すことができた。チェルノブイリは核戦争がいかに恐ろしいかを見せてくれたからだ。
被曝の恐ろしいところは、どんな影響があるのか、想像しにくいことだ。
放射性物質のストロンチウムは、骨や顎に蓄積され、やがて歯が抜け落ちる。しかし痛みを感じるものではないので、だからこそ、兵士たちはどんな仕事でも引き受けたのだ。
そして、後になって代償を支払わされた。それが、「チェルノブイリの悲劇」なのだ。
作家・クリストフ:
1991年9月、私の妻、マリーナは亡くなった。まもなく36歳になるところだった。
放射線が病気の原因だと思っているが、証明することはできない…
画家・ディーマ:
体に多少の痛みと不快感がある。そう感じるのは、放射能の影響が波のように体に入り、出て行くからだと考えるようにしている。
何とも言いようのない状態になって、そのたびに「自分はもう、これでお終いだ」と思ってしまう。これが1回戦、2回戦、3回戦とずっと続いて、まるで自分は知らない土地で風車と闘う…ドンキホーテみたいだ…
ディーマの友人・ナタリア:
1995年か96年のことだったと思うが、ディーマが病院から電話をしてきて「僕のことを覚えているかい?迎えに来て欲しい」と言われた。
モスクワは大きな町なので病院までの道がわからなくて、時間がかかった。
彼は大きな病院のロビーで座っていて、付き添っている人はいなかった。
痩せ細って青白い顔をしていた。まるで老人のようで、見るからにかわいそうな姿だった。
ディーマは何回か頭の手術を受けていて、本当に気の毒な姿だった。同窓会の時と比べたら、恐ろしいほどの変わりようだ。もはや廃人同様になっていた。
ディーマの母:
チェルノブイリはひと言で言って、「この国の恥」だ。私はそう思っている。
兵士たちは全てを犠牲にしてあそこへ行ったのだから、少なくとも人並みの生活は補償されるべきだ。病気を治せるように、医療面の援助をすることは当然なのに、何一つ、行われない。
息子はごく普通の健康な少年だった。そして、入隊して最初に検査を受けた時、健康そのものだった。
でも除隊して戻って来てからは、どんどん衰弱していったのだ。何の原因もないのに、あんなふうに体が弱るはずはない。チェルノブイリは本当にこの国の恥だ。
作家・クリストフ:
2002年の夏、モスクワ近郊の森の中でディーマは遺体で発見された。彼が子ども時代、休暇を過ごした別荘の近くだ。4日後には40歳の誕生日を迎えるはずだった。
ディーマの墓の近くには、モスクワの北東300kmのヤロスラボリに繋がる道路が走っている。除隊を目前にした1986年、ディーマはヤロスラボリからチェルノブイリに動員された。
墓はわかりづらい所にあるので、ディーマの義理の弟ヴィトルが案内してくれた。遺体が見つかった時、当局は親族を見つけ出すことができなかった。ディーマは身元不明者の一角にひっそりと埋葬されている…
完
チェルノブイリはひと言で言って、「この国の恥」だ。私はそう思っている。
兵士たちは全てを犠牲にしてあそこへ行ったのだから、少なくとも人並みの生活は補償されるべきだ。病気を治せるように、医療面の援助をすることは当然なのに、何一つ、行われない。
息子はごく普通の健康な少年だった。そして、入隊して最初に検査を受けた時、健康そのものだった。
でも除隊して戻って来てからは、どんどん衰弱していったのだ。何の原因もないのに、あんなふうに体が弱るはずはない。チェルノブイリは本当にこの国の恥だ。
作家・クリストフ:
2002年の夏、モスクワ近郊の森の中でディーマは遺体で発見された。彼が子ども時代、休暇を過ごした別荘の近くだ。4日後には40歳の誕生日を迎えるはずだった。
ディーマの墓の近くには、モスクワの北東300kmのヤロスラボリに繋がる道路が走っている。除隊を目前にした1986年、ディーマはヤロスラボリからチェルノブイリに動員された。
墓はわかりづらい所にあるので、ディーマの義理の弟ヴィトルが案内してくれた。遺体が見つかった時、当局は親族を見つけ出すことができなかった。ディーマは身元不明者の一角にひっそりと埋葬されている…
完
n✡☮さんが立ててくださった【年間20mSvの意味 2011年05月14日 12:45】
申しわけありませんが、こちらと【放射能とその影響についての基礎知識】【非難しない避難の呼びかけ】のトピへ転載させていただきます。悪しからずご了承くださいませm(__)m
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『嶋橋さんの白血病との闘いは終わった。発症から2年1カ月。浜岡原発で約9年働き、29歳1カ月の人生だった。その間の被曝線量は、50.6mSv。年間では最多の年でも9.8mSv」|2000/3/22中国新聞:ある原発作業員の死 http://p.tl/gmXU
実際に福島県内各地で20mSvを超えるであろう状況になっています。
子供たちのポケットは小さい。
しかし、手遅れはないと思います。
避難に迷っている方、現状に危機感を持っている方お母さんたちは、
是非避難してみて下さい。
そこにはあなた方と同じ状況から避難して来た、他のお母さん家族がいます。
申しわけありませんが、こちらと【放射能とその影響についての基礎知識】【非難しない避難の呼びかけ】のトピへ転載させていただきます。悪しからずご了承くださいませm(__)m
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『嶋橋さんの白血病との闘いは終わった。発症から2年1カ月。浜岡原発で約9年働き、29歳1カ月の人生だった。その間の被曝線量は、50.6mSv。年間では最多の年でも9.8mSv」|2000/3/22中国新聞:ある原発作業員の死 http://p.tl/gmXU
実際に福島県内各地で20mSvを超えるであろう状況になっています。
子供たちのポケットは小さい。
しかし、手遅れはないと思います。
避難に迷っている方、現状に危機感を持っている方お母さんたちは、
是非避難してみて下さい。
そこにはあなた方と同じ状況から避難して来た、他のお母さん家族がいます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
被曝から子供達を守れ〜繋ぐ命〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90055人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人