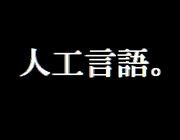|
|
|
|
コメント(42)
初めまして。
発音に関する議論に音の表記が必要であり、それに当面ローマン・アルファベットを使用するという点、基本規定事項として諒解です。
さて。ここの参加者の大多数は日本語ネイティヴの話者になるであろうと思われますので、日本語に含まれる母音・子音は全て有する言語にすることを提案します。
・ただし/l/と/r/の別を加える。
・/v/音と/b/音も弁別。
・『ん』に相当するn, ng, gn(n~), m を、それぞれ独立の子音として書き分けられるように。
・英語のthのような、世界の言語で見ても比較的特殊な音は採用しない。
――という辺りを叩き台にしてはどうでしょう。
> 個人的になじみがあるのは音表記したカイロ方言ですが
> そこでは
> 短母音は/a/ /i/ /u/
> 長母音は/aa/ /ii/ /uu/としてました。
インド系の言語に似てますね。
ちなみにヒンディーやサンスクリットの場合は/e/ /o/は必ず長母音。他に母音扱いの/R/ /L/なんてのもあったりします。
発音に関する議論に音の表記が必要であり、それに当面ローマン・アルファベットを使用するという点、基本規定事項として諒解です。
さて。ここの参加者の大多数は日本語ネイティヴの話者になるであろうと思われますので、日本語に含まれる母音・子音は全て有する言語にすることを提案します。
・ただし/l/と/r/の別を加える。
・/v/音と/b/音も弁別。
・『ん』に相当するn, ng, gn(n~), m を、それぞれ独立の子音として書き分けられるように。
・英語のthのような、世界の言語で見ても比較的特殊な音は採用しない。
――という辺りを叩き台にしてはどうでしょう。
> 個人的になじみがあるのは音表記したカイロ方言ですが
> そこでは
> 短母音は/a/ /i/ /u/
> 長母音は/aa/ /ii/ /uu/としてました。
インド系の言語に似てますね。
ちなみにヒンディーやサンスクリットの場合は/e/ /o/は必ず長母音。他に母音扱いの/R/ /L/なんてのもあったりします。
ご参加ありがとうございます!
さっそく貴重なご意見を聞かせていただき、感謝感激です。
今後ともよろしくお願いいたします。
>rothkofanさま
ご参加&ご意見どうもありがとうございます。
私は基本的には、中国語畑(とくに古典漢語)の者です。 アラビア語、ペルシア語、トルコ語など中東の言語も好きでかじっています。スラブ諸語にも興味があり、どうやらこういった言語のあいだを周期的にさまよっている状況です(笑)
>カイロ方言
アーンミーヤですね。私はアラビア語はフスハー(正則語)しか学んでいないのですが、アラビア語は世界的に見ても母音が少なめな言語ですね。
>そのへんを正確に表現するために
なるほど、アラビア語の長母音を表記するさいに母音を並べるのはそうした理由があったのですか。
>
こちらこそ、いろいろと教えてくださいませ。
>死郎さま
はじめまして。ご参加とご提案ありがとうございます。
日本語よりも音素を多くすること。/l/と/r/、/b/と/v/の弁別。世界の主要言語の多くでみられる特徴ということを考えても、リーズナブルな設定かと思います。鼻音の書き分け、特殊な音の不採用など、以上を叩き台にすることに賛成です。
どの音素を採用するかしないか、
おいおい決めていきましょう。
*ところで、文字はローマ字アルファベットによる表記
ということで決定したいと思います。さてこの際に、
?1文字1音主義でいくべきか、
?またたとえばch,ll,dzs,tsch,nyみたいに
必要があれば複数の文字で1音をあらわすべきか、
?あるいはš,č,ő,é,ö,şみたいにアルファベットに
符号をつけて1音を表すようにするか
といった問題も出てきますね。
採用する音素が決定していない段階ではわかりませんが、
これについても話し合っていきましょう。
さっそく貴重なご意見を聞かせていただき、感謝感激です。
今後ともよろしくお願いいたします。
>rothkofanさま
ご参加&ご意見どうもありがとうございます。
私は基本的には、中国語畑(とくに古典漢語)の者です。 アラビア語、ペルシア語、トルコ語など中東の言語も好きでかじっています。スラブ諸語にも興味があり、どうやらこういった言語のあいだを周期的にさまよっている状況です(笑)
>カイロ方言
アーンミーヤですね。私はアラビア語はフスハー(正則語)しか学んでいないのですが、アラビア語は世界的に見ても母音が少なめな言語ですね。
>そのへんを正確に表現するために
なるほど、アラビア語の長母音を表記するさいに母音を並べるのはそうした理由があったのですか。
>
こちらこそ、いろいろと教えてくださいませ。
>死郎さま
はじめまして。ご参加とご提案ありがとうございます。
日本語よりも音素を多くすること。/l/と/r/、/b/と/v/の弁別。世界の主要言語の多くでみられる特徴ということを考えても、リーズナブルな設定かと思います。鼻音の書き分け、特殊な音の不採用など、以上を叩き台にすることに賛成です。
どの音素を採用するかしないか、
おいおい決めていきましょう。
*ところで、文字はローマ字アルファベットによる表記
ということで決定したいと思います。さてこの際に、
?1文字1音主義でいくべきか、
?またたとえばch,ll,dzs,tsch,nyみたいに
必要があれば複数の文字で1音をあらわすべきか、
?あるいはš,č,ő,é,ö,şみたいにアルファベットに
符号をつけて1音を表すようにするか
といった問題も出てきますね。
採用する音素が決定していない段階ではわかりませんが、
これについても話し合っていきましょう。
>死郎さま
どうもありがとうございます。肝心なことを忘れておりました。どのような人工言語にするかをまず話し合っておかないといけませんよね。
(3)はたしかに作るのが大変そうですね。言語の研究としてやる分にはいいのでしょうけど。(1)と(2)は、国際補助語などの実用向きか、必ずしもそうではないという違いなのでしょうか。どうせ作るならコミュニケーションに使えたほうがいいと思います。
また簡便性ということなら、後からコミュに参加された方や見学される方が、過去ログを見るだけでじゅうぶん文法を了解・習得でき、後からでも言語創作に参加できるほどのものを目指す、というのはいかがでしょうか?
あまり複雑なものではなく、誰でも利用できて、かつ創作に携われるということで、(1)の定義する方針がいちばん適切かなあ、と考えているのですが。皆様のご意見はいかがでしょうか。
どうもありがとうございます。肝心なことを忘れておりました。どのような人工言語にするかをまず話し合っておかないといけませんよね。
(3)はたしかに作るのが大変そうですね。言語の研究としてやる分にはいいのでしょうけど。(1)と(2)は、国際補助語などの実用向きか、必ずしもそうではないという違いなのでしょうか。どうせ作るならコミュニケーションに使えたほうがいいと思います。
また簡便性ということなら、後からコミュに参加された方や見学される方が、過去ログを見るだけでじゅうぶん文法を了解・習得でき、後からでも言語創作に参加できるほどのものを目指す、というのはいかがでしょうか?
あまり複雑なものではなく、誰でも利用できて、かつ創作に携われるということで、(1)の定義する方針がいちばん適切かなあ、と考えているのですが。皆様のご意見はいかがでしょうか。
> a, e, i, o, u
エスペラントでも五母音ですし、普遍的でよろしいのではないでしょうか。
そうなると次の段階として、
●母音の長短の別を採用するか否か。
●曖昧母音 /@/(IPAだと、eをひっくり返した形)をどのように扱うか。
といった辺りですか。
母音の長短についてはrothkofanさまも挙げてらっしゃいますが。しかし、これがない言語の話者にとっては、けっこう区別が難しいという問題もあります。
それに日本語のようなモーラに基づく言語と、印欧語の多くがそうであるようにシラブルで把握される発音体系の言語とでは、同じ長短でも扱いが違うような。
つまり日本語では『アー』は『アア』に等しいわけですが、/a/ と /a:/ を独立した別の音として扱う言語なら、a〜uで五母音ではなく十母音の扱いになってきます。
そうなれば二重母音などというものも考えなければならなくなって参りまして。例えば /ai/ という音を /a/ + /i/ として扱うのか、別の一音と考えるのか――。
●音節をどのような構造にするか。
――という辺りも重要になってきますね。
さて。曖昧母音 /@/ については、マレー語/インドネシア語あたりでは五母音に加えてこれを区別しています。表記ではeのところを /e/ と読んだり /@/ と読ませたり。
またサンスクリットで短母音の /a/ だったものが、ヒンディーでは前後の音により /@/ になっていく傾向にあるようです。
そのへんを日本語の耳で聞くと、ウ段辺りの音に変換される。ということは /@/ は /u/(場合によっては /o/)と弁別されない、ということになりますね。
問題提起ばかりですが。上記それぞれの点、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
エスペラントでも五母音ですし、普遍的でよろしいのではないでしょうか。
そうなると次の段階として、
●母音の長短の別を採用するか否か。
●曖昧母音 /@/(IPAだと、eをひっくり返した形)をどのように扱うか。
といった辺りですか。
母音の長短についてはrothkofanさまも挙げてらっしゃいますが。しかし、これがない言語の話者にとっては、けっこう区別が難しいという問題もあります。
それに日本語のようなモーラに基づく言語と、印欧語の多くがそうであるようにシラブルで把握される発音体系の言語とでは、同じ長短でも扱いが違うような。
つまり日本語では『アー』は『アア』に等しいわけですが、/a/ と /a:/ を独立した別の音として扱う言語なら、a〜uで五母音ではなく十母音の扱いになってきます。
そうなれば二重母音などというものも考えなければならなくなって参りまして。例えば /ai/ という音を /a/ + /i/ として扱うのか、別の一音と考えるのか――。
●音節をどのような構造にするか。
――という辺りも重要になってきますね。
さて。曖昧母音 /@/ については、マレー語/インドネシア語あたりでは五母音に加えてこれを区別しています。表記ではeのところを /e/ と読んだり /@/ と読ませたり。
またサンスクリットで短母音の /a/ だったものが、ヒンディーでは前後の音により /@/ になっていく傾向にあるようです。
そのへんを日本語の耳で聞くと、ウ段辺りの音に変換される。ということは /@/ は /u/(場合によっては /o/)と弁別されない、ということになりますね。
問題提起ばかりですが。上記それぞれの点、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
いやー話が進んできて議論が精緻になってきましたねえ。
rothkofanさま
>前後にくる子音によって前で発音したり後ろで発音したり
アラビア語は3母音が基本ですが、前後に来る子音によって
あきらかに音色がちがうばあいがありますね。aが前よりに
なったり後ろよりになったり。インドネシア人がアラビア語
を学ぶさいに、それを真似て喉音のあとにつづく母音aを
/o/に変えて読むことがあります。
>母音はこの5つに抑えて、
ローマ字アルファベットに入っている母音は
この5つだけですし、それもいいかもしれませんね。
>死郎さま
5母音体系は安定しているためか、
この体系をとる言語は多いですよね。
>●母音の長短の別を採用するか否か
>日本語では『アー』は『アア』に等しいわけですが、
/a/ と /a:/ を独立した別の音として扱う言語なら、
a〜uで五母音ではなく十母音の扱いになってきます。
これはたしかにそうですね。英語では「長母音」を
別の音として捉えていますね。
>二重母音
これもなかなかむずかしい問題ですね。
2個の母音の連続か、あるいは
/-i//-u/を子音とみなすかどうか。
うーん長母音・二重母音についてはあまり深く考えて
いませんでした。
>音節
私案では
V CV VC CVC (C=子音、V=母音)
という基本的なところだけ考えています。
語頭や語尾に複数の子音連続が立ちうるかどうかは
決めていませんが、閉音節(子音終わり)はありの
方向で行きたいと思います。
>●曖昧母音 /@/(IPAだと、eをひっくり返した形)
をどのように扱うか
非常に多くの言語がこの母音をもっていますが、
?独立した1音素として/@/を持っている
?アクセントの位置など一定条件下で他の母音が弱化して
生まれた異音として、持っている
という違いがあるように思います。
マレー語などは?のほうでしょうか。
ヒンディー語のばあいは?のように異音として持っている
という理解でよろしいでしょうか?
(間違っていましたらご指摘願います)
/@/を独立した母音として扱っている言語であっても
表記上特定の字を割り当てている言語は少ないですね。
マレー語は仰るように/e/と/@/の両方を"e"で表しますね。
いっぽうウェールズ語では"Y,y"の文字でこの曖昧母音を
表していたと思います。
5母音+曖昧母音という体系も、多くの言語で見られるもの
です。もし曖昧母音を採用するなら、
・異音として採用する(表記に反映させる)
・異音として採用する(表記には反映させない)
・独立した母音として(表記に反映させる)
・独立した母音として(表記に反映させない)
という選択肢が出てくるでしょうか。
rothkofanさま
>前後にくる子音によって前で発音したり後ろで発音したり
アラビア語は3母音が基本ですが、前後に来る子音によって
あきらかに音色がちがうばあいがありますね。aが前よりに
なったり後ろよりになったり。インドネシア人がアラビア語
を学ぶさいに、それを真似て喉音のあとにつづく母音aを
/o/に変えて読むことがあります。
>母音はこの5つに抑えて、
ローマ字アルファベットに入っている母音は
この5つだけですし、それもいいかもしれませんね。
>死郎さま
5母音体系は安定しているためか、
この体系をとる言語は多いですよね。
>●母音の長短の別を採用するか否か
>日本語では『アー』は『アア』に等しいわけですが、
/a/ と /a:/ を独立した別の音として扱う言語なら、
a〜uで五母音ではなく十母音の扱いになってきます。
これはたしかにそうですね。英語では「長母音」を
別の音として捉えていますね。
>二重母音
これもなかなかむずかしい問題ですね。
2個の母音の連続か、あるいは
/-i//-u/を子音とみなすかどうか。
うーん長母音・二重母音についてはあまり深く考えて
いませんでした。
>音節
私案では
V CV VC CVC (C=子音、V=母音)
という基本的なところだけ考えています。
語頭や語尾に複数の子音連続が立ちうるかどうかは
決めていませんが、閉音節(子音終わり)はありの
方向で行きたいと思います。
>●曖昧母音 /@/(IPAだと、eをひっくり返した形)
をどのように扱うか
非常に多くの言語がこの母音をもっていますが、
?独立した1音素として/@/を持っている
?アクセントの位置など一定条件下で他の母音が弱化して
生まれた異音として、持っている
という違いがあるように思います。
マレー語などは?のほうでしょうか。
ヒンディー語のばあいは?のように異音として持っている
という理解でよろしいでしょうか?
(間違っていましたらご指摘願います)
/@/を独立した母音として扱っている言語であっても
表記上特定の字を割り当てている言語は少ないですね。
マレー語は仰るように/e/と/@/の両方を"e"で表しますね。
いっぽうウェールズ語では"Y,y"の文字でこの曖昧母音を
表していたと思います。
5母音+曖昧母音という体系も、多くの言語で見られるもの
です。もし曖昧母音を採用するなら、
・異音として採用する(表記に反映させる)
・異音として採用する(表記には反映させない)
・独立した母音として(表記に反映させる)
・独立した母音として(表記に反映させない)
という選択肢が出てくるでしょうか。
では斯波左衛門尉さまのご意見を受けまして。
> うーん長母音・二重母音についてはあまり深く考えて
> いませんでした。
であるならば、とりあえず保留で。
ちなみに、エスペラントだと長短の別ナシでしたよね。“シンプルな言語”を指向するなら、その線でも構わないとも思います……が、個人的にはエス語とは出来る限り差別化を図りたい気がします(笑)。
参考までに、マレー語だと長短の別がなく、先述した通り六母音。プラス、ai、au、oiの三つの二重母音があります。
タミル語の例だと五母音にそれぞれ長短があり、aiとauの二重母音を持ちます。サンスクリットからの借用語には母音の /R/ もありますが、これはこの際考えないとして。
> >音節
> 私案では
>
> V CV VC CVC (C=子音、V=母音)
>
> という基本的なところだけ考えています。
諒解しました。そうなるとやはり、以後モーラよりもシラブルで考えたほうが都合良さそうですね。
> マレー語などは(1)のほうでしょうか。
> ヒンディー語のばあいは(2)のように異音として持っている
> という理解でよろしいでしょうか?
それで正しいと思います。
あるいはヒンディーの場合、事実上母音 /a/ が消滅するのですが、無母音の筈の子音にも /@/ が補われる傾向にある(これはインド英語でも同じく)ので、そうした発音になるとも言えます。
※引用部分、マル数字は機種依存なので置換させていただきました。
> ・異音として採用する(表記に反映させる)
> ・異音として採用する(表記には反映させない)
> ・独立した母音として(表記に反映させる)
> ・独立した母音として(表記に反映させない)
これも個人的な意見ですが、特に独立した母音として採用する必要は感じません。
表記にも反映しなくて良いとは思うのですが、さて /@/ という音が発せられた時に /a/ と同一の音として捉えるのか、/u/ か、あるいは /o/ なのか……という点は最低決めておくべきなのかな、と。
> うーん長母音・二重母音についてはあまり深く考えて
> いませんでした。
であるならば、とりあえず保留で。
ちなみに、エスペラントだと長短の別ナシでしたよね。“シンプルな言語”を指向するなら、その線でも構わないとも思います……が、個人的にはエス語とは出来る限り差別化を図りたい気がします(笑)。
参考までに、マレー語だと長短の別がなく、先述した通り六母音。プラス、ai、au、oiの三つの二重母音があります。
タミル語の例だと五母音にそれぞれ長短があり、aiとauの二重母音を持ちます。サンスクリットからの借用語には母音の /R/ もありますが、これはこの際考えないとして。
> >音節
> 私案では
>
> V CV VC CVC (C=子音、V=母音)
>
> という基本的なところだけ考えています。
諒解しました。そうなるとやはり、以後モーラよりもシラブルで考えたほうが都合良さそうですね。
> マレー語などは(1)のほうでしょうか。
> ヒンディー語のばあいは(2)のように異音として持っている
> という理解でよろしいでしょうか?
それで正しいと思います。
あるいはヒンディーの場合、事実上母音 /a/ が消滅するのですが、無母音の筈の子音にも /@/ が補われる傾向にある(これはインド英語でも同じく)ので、そうした発音になるとも言えます。
※引用部分、マル数字は機種依存なので置換させていただきました。
> ・異音として採用する(表記に反映させる)
> ・異音として採用する(表記には反映させない)
> ・独立した母音として(表記に反映させる)
> ・独立した母音として(表記に反映させない)
これも個人的な意見ですが、特に独立した母音として採用する必要は感じません。
表記にも反映しなくて良いとは思うのですが、さて /@/ という音が発せられた時に /a/ と同一の音として捉えるのか、/u/ か、あるいは /o/ なのか……という点は最低決めておくべきなのかな、と。
rothkofanさま、ご指摘ありがとうございます。たしかに母音と語形変化が関連しているとしたら、気になる点ですよね。
最初に音韻論を決めておくことにしたのは、どのような語形変化がある(あるいは無いか)言語をめざすにしても基本的な音韻だけでも考えておかないと、あとで文法を設定したりボキャブラリを増やしたさいに、どの音素が使えるあるいは使えないかが決まっていないことになり、かえって混乱すると思ったからなのです。
音素や音節を先に決めても、じっさいに語を作るときの音の組み合わせは無数なので、まだまだ語形の自由選択の余地はじゅうぶん残されていると考えているのですが・・・
しかし文法的なことも少しは決めておくべきかもしれませんね。「どのような類型の言語をめざすか」という点についても、今から考えておきましょうか?語形変化があるのかないのか、あるとしたら印欧語やセム語のような屈折語なのか、トルコ語やモンゴル語、日本語のような膠着語をめざすのか、などについて、大まかな特徴だけでも考えておくというのはどうでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせください。
>長母音、二重母音
死郎さま、すみませぬ。どちらでもいいやと思っていましたので。しかし長短の区別についてご要望があればおっしゃってください。どちらかといえば、私もエスペラントより音韻が複雑なほうが面白いのではないか、また長母音などがあったほうが個人的には「楽しい」という気がいたします。まあ好みの問題かもしれませんが。
曖昧母音については、死郎さま、rothkofanさまのご意見を受けまして、独立した母音として扱わないということでよろしいでしょうか。
最初に音韻論を決めておくことにしたのは、どのような語形変化がある(あるいは無いか)言語をめざすにしても基本的な音韻だけでも考えておかないと、あとで文法を設定したりボキャブラリを増やしたさいに、どの音素が使えるあるいは使えないかが決まっていないことになり、かえって混乱すると思ったからなのです。
音素や音節を先に決めても、じっさいに語を作るときの音の組み合わせは無数なので、まだまだ語形の自由選択の余地はじゅうぶん残されていると考えているのですが・・・
しかし文法的なことも少しは決めておくべきかもしれませんね。「どのような類型の言語をめざすか」という点についても、今から考えておきましょうか?語形変化があるのかないのか、あるとしたら印欧語やセム語のような屈折語なのか、トルコ語やモンゴル語、日本語のような膠着語をめざすのか、などについて、大まかな特徴だけでも考えておくというのはどうでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせください。
>長母音、二重母音
死郎さま、すみませぬ。どちらでもいいやと思っていましたので。しかし長短の区別についてご要望があればおっしゃってください。どちらかといえば、私もエスペラントより音韻が複雑なほうが面白いのではないか、また長母音などがあったほうが個人的には「楽しい」という気がいたします。まあ好みの問題かもしれませんが。
曖昧母音については、死郎さま、rothkofanさまのご意見を受けまして、独立した母音として扱わないということでよろしいでしょうか。
三人だけで話が進んでしまって、他の方が入りづらくなってしまうのではないかと心配してみたり。現在当コミュには、ほかお二方が参加してらっしゃるようですが。読んではいらっしゃるのかな。
rothkofanさまの挙げられた、母音交代による意味変化というのは僕も非常に興味深く感じています。仰るアラビア語やヘブライ語などでは、そうしたシステムが重要な位置を占めていますよね。
サンスクリットの文法中にも僅かながらそうしたものがありますし、よく考えれば日本語にも含まれていますし(『当たる』→『当てる』とか、『hito(一)』→『huta(二)』、『mi(三)』→『mu(六)』、『yo(四)』→『ya(八』……)。
ただし、そういったものを採用するならそれだけで徹底して、例外を極力排除するべきでしょうね。最初に決めた『シンプルな言語』を、という原則からすると。
さて。ということで、こののち文法的な話まで進んだ時点で、それに合わせて音素・音韻のほうも調節していくほうが良いでしょうか。
> しかし文法的なことも少しは決めておくべきかもしれませんね。「どのような類型の言語をめざすか」という点についても、今から考えておきましょうか?語形変化があるのかないのか、あるとしたら印欧語やセム語のような屈折語なのか、トルコ語やモンゴル語、日本語のような膠着語をめざすのか、などについて、大まかな特徴だけでも考えておくというのはどうでしょうか。
屈折語は、面白いとは思うんですが、あまり学習し易くはならないかも知れませんね。それに単純化していくと、結局は膠着語とそう変わらないことになりそうです。
他の選択肢として、中国語や英語、マレー語のような孤立語というのもありますが。その場合の弱点としては『単語の品詞が区別しづらく、一つの文が複数の意味に取れる場合がある』辺りですか。
もう一つ抱合語というのもあるようですけど、これはどうなんでしょう。面白そうですけど、ちょっと手に負えない感じも(笑)。
> ご要望があればおっしゃってください。
長母音、二重母音に関しては、僕も多少のバリエーションがあったほうが良いかなと思いました。ですので、長母音はアリの方向で、二重母音も幾つか――という辺りを個人的希望として出しておきます。内訳はまた検討するとして。
曖昧母音は区別しない点、諒解です。
> >長母音
> アクセント記号を別途つけるのも表記上大変なので、
> 長母音には必ずアクセントが付く
> という使い方もあるかと思いました。
> カイロ方言だと、一呼吸で発声できる長さの文ならその1文全体を、1つのアクセント構造として母音調整してました。そのため、正則アラビア語では短母音のところを長母音化したり、長母音のところを短母音化したり、条件によって短母音を脱落させたりしてました。アクセントの規則と長母音とを関連付けた例です。
サンスクリットでは、後ろから二つ目の音節から数えていって最初に長母音に当たると、そこにアクセントが来ます。ただし後ろから四つ目より前へは遡りません。また二重母音や後に子音連続が続く音節は『位置で長い』と言って長母音の扱いです。
こう書くと難しいようですけど、馴れると考えなくてもすんなり音として出てきます。
しかし単純化を考えるならば、全く無アクセントで文全体で緩やかな抑揚があるというのでも良いかも知れません。仏語、ヒンディー、それから日本の北関東方言みたいな感じで。
rothkofanさまの挙げられた、母音交代による意味変化というのは僕も非常に興味深く感じています。仰るアラビア語やヘブライ語などでは、そうしたシステムが重要な位置を占めていますよね。
サンスクリットの文法中にも僅かながらそうしたものがありますし、よく考えれば日本語にも含まれていますし(『当たる』→『当てる』とか、『hito(一)』→『huta(二)』、『mi(三)』→『mu(六)』、『yo(四)』→『ya(八』……)。
ただし、そういったものを採用するならそれだけで徹底して、例外を極力排除するべきでしょうね。最初に決めた『シンプルな言語』を、という原則からすると。
さて。ということで、こののち文法的な話まで進んだ時点で、それに合わせて音素・音韻のほうも調節していくほうが良いでしょうか。
> しかし文法的なことも少しは決めておくべきかもしれませんね。「どのような類型の言語をめざすか」という点についても、今から考えておきましょうか?語形変化があるのかないのか、あるとしたら印欧語やセム語のような屈折語なのか、トルコ語やモンゴル語、日本語のような膠着語をめざすのか、などについて、大まかな特徴だけでも考えておくというのはどうでしょうか。
屈折語は、面白いとは思うんですが、あまり学習し易くはならないかも知れませんね。それに単純化していくと、結局は膠着語とそう変わらないことになりそうです。
他の選択肢として、中国語や英語、マレー語のような孤立語というのもありますが。その場合の弱点としては『単語の品詞が区別しづらく、一つの文が複数の意味に取れる場合がある』辺りですか。
もう一つ抱合語というのもあるようですけど、これはどうなんでしょう。面白そうですけど、ちょっと手に負えない感じも(笑)。
> ご要望があればおっしゃってください。
長母音、二重母音に関しては、僕も多少のバリエーションがあったほうが良いかなと思いました。ですので、長母音はアリの方向で、二重母音も幾つか――という辺りを個人的希望として出しておきます。内訳はまた検討するとして。
曖昧母音は区別しない点、諒解です。
> >長母音
> アクセント記号を別途つけるのも表記上大変なので、
> 長母音には必ずアクセントが付く
> という使い方もあるかと思いました。
> カイロ方言だと、一呼吸で発声できる長さの文ならその1文全体を、1つのアクセント構造として母音調整してました。そのため、正則アラビア語では短母音のところを長母音化したり、長母音のところを短母音化したり、条件によって短母音を脱落させたりしてました。アクセントの規則と長母音とを関連付けた例です。
サンスクリットでは、後ろから二つ目の音節から数えていって最初に長母音に当たると、そこにアクセントが来ます。ただし後ろから四つ目より前へは遡りません。また二重母音や後に子音連続が続く音節は『位置で長い』と言って長母音の扱いです。
こう書くと難しいようですけど、馴れると考えなくてもすんなり音として出てきます。
しかし単純化を考えるならば、全く無アクセントで文全体で緩やかな抑揚があるというのでも良いかも知れません。仏語、ヒンディー、それから日本の北関東方言みたいな感じで。
返信が遅れ申し訳ありません。
しばらく間が空いてしまいました。
とりあえず決まっていることはシラブルと、
短母音が5つあるということだけですよね。
まあ気長にやりましょう(笑)
>アクセントは無しで
私も基本的にアクセントは無しでもいいと思いますが、
後ろから2音節目にアクセントが来るという法則も
捨てがたいと同時に思ったり…
>長母音、二重母音
長母音を採用するとしたら、
すでに決まっている短母音5種に対して、
それぞれに対応する長母音があるというのは
どうでしょうか?
/a:/ /e:/ /i:/ /o:/ /u:/
やはり表記をどうするかというのが問題ですね。
二重母音はいくつかの種類を採用する方向で行きたいと
思いますが、/ai/ /au/あたりは普遍的ですよね。この他に
・広母音+狭母音 /ei/ /eu/ /oi/ /ou/
・狭母音+広母音 /ia/ /ie/ /io/ /ua/ /ue/ /uo/
・その他 /ui/ /iu/ /ea/ /oa/
を考えてみましたが、じっさいこんなにたくさん
要らないだろうと思っています。この中から淘汰して
いきましょうか?他になにか二重母音の例があれば
教えてください。
>死郎さま
>抱合語
アイヌ語やイヌイト語などの類型ですよね。
これは難しそうですね〜。私も学んだことはなく、
人工言語として作ったこともありません。
個人的な体験では、わりと作りやすかったのは
語順がSOVの膠着語とSVOの屈折語でした。
これは日本語と印欧語に親しんできたので
自然なことかもしれません。
しばらく間が空いてしまいました。
とりあえず決まっていることはシラブルと、
短母音が5つあるということだけですよね。
まあ気長にやりましょう(笑)
>アクセントは無しで
私も基本的にアクセントは無しでもいいと思いますが、
後ろから2音節目にアクセントが来るという法則も
捨てがたいと同時に思ったり…
>長母音、二重母音
長母音を採用するとしたら、
すでに決まっている短母音5種に対して、
それぞれに対応する長母音があるというのは
どうでしょうか?
/a:/ /e:/ /i:/ /o:/ /u:/
やはり表記をどうするかというのが問題ですね。
二重母音はいくつかの種類を採用する方向で行きたいと
思いますが、/ai/ /au/あたりは普遍的ですよね。この他に
・広母音+狭母音 /ei/ /eu/ /oi/ /ou/
・狭母音+広母音 /ia/ /ie/ /io/ /ua/ /ue/ /uo/
・その他 /ui/ /iu/ /ea/ /oa/
を考えてみましたが、じっさいこんなにたくさん
要らないだろうと思っています。この中から淘汰して
いきましょうか?他になにか二重母音の例があれば
教えてください。
>死郎さま
>抱合語
アイヌ語やイヌイト語などの類型ですよね。
これは難しそうですね〜。私も学んだことはなく、
人工言語として作ったこともありません。
個人的な体験では、わりと作りやすかったのは
語順がSOVの膠着語とSVOの屈折語でした。
これは日本語と印欧語に親しんできたので
自然なことかもしれません。
●アクセント
rothkofanさまが挙げてくださったカイロ方言の例も興味深いのですが、やはり余り複雑にしないほうが良いかも知れません。
そうなると無アクセントか定位置ということで、
> 後ろから2音節目にアクセントが来るという法則も
> 捨てがたいと同時に思ったり…
斯波左衛門尉さまの仰るこれは、エスペラントと同じですか。
ただし母音の長短を弁別する場合は、アクセント部位を伸ばすわけにはいきませんね。
ということで必然的に『強弱アクセント』なのか『高低アクセント』なのか、という選択肢になると思います。これはどちらが良いでしょうか。
ついでに前回の書込みの訂正。仏語は無アクセントと書いてしまいましたが、正確には語末にアクセントが来るのでした(文全体になだらかな抑揚があるというのは正しいのですが)。
ということでアクセントが定位置の場合は、最後か最後から二番目か、という先例があることになります。
●長母音
> すでに決まっている短母音5種に対して、
> それぞれに対応する長母音があるというのは
> どうでしょうか?
異義ありません。
> やはり表記をどうするかというのが問題ですね。
案としては、
○単純に文字を重ねる
aa, ee, ii, oo, uu
○大文字を使う(サンスクリットのローマナイズの一方式)
A, E, I, O, U
○ラテン語の長音符号を流用(便宜的に後置)
a^, e^, i^, o^, u^
――それぞれ一長一短あると思いますが。
●二重母音
> この中から淘汰していきましょうか?
当方で考えたのは、/ai/ /au/ の他に /ei/ /eu/ /oi/ /ou/ の六つです。さらに絞るなら /ei/ を /e:/ と、/ou/ を /o:/ と統合してしまうことで、/ai/ /au/ /eu/ /oi/ の計四種でしょうか。
/i-/ に関しては /j-/ に、/u-/ は /w-/ に変化し易いということと、/i/ と /e/、/u/ と /o/ は混じり易いという辺りを鑑みましての試案です。
●文法
> 個人的な体験では、わりと作りやすかったのは
> 語順がSOVの膠着語とSVOの屈折語でした。
ごもっとも。
ところで、この両者については語順は割と自由にできますが、孤立語になるときっちり決めないといけませんね。
で。アラビア語・ヘブライ語のように母音交替によって単語が変化する、というのも未だ気になっています。
rothkofanさまが挙げてくださったカイロ方言の例も興味深いのですが、やはり余り複雑にしないほうが良いかも知れません。
そうなると無アクセントか定位置ということで、
> 後ろから2音節目にアクセントが来るという法則も
> 捨てがたいと同時に思ったり…
斯波左衛門尉さまの仰るこれは、エスペラントと同じですか。
ただし母音の長短を弁別する場合は、アクセント部位を伸ばすわけにはいきませんね。
ということで必然的に『強弱アクセント』なのか『高低アクセント』なのか、という選択肢になると思います。これはどちらが良いでしょうか。
ついでに前回の書込みの訂正。仏語は無アクセントと書いてしまいましたが、正確には語末にアクセントが来るのでした(文全体になだらかな抑揚があるというのは正しいのですが)。
ということでアクセントが定位置の場合は、最後か最後から二番目か、という先例があることになります。
●長母音
> すでに決まっている短母音5種に対して、
> それぞれに対応する長母音があるというのは
> どうでしょうか?
異義ありません。
> やはり表記をどうするかというのが問題ですね。
案としては、
○単純に文字を重ねる
aa, ee, ii, oo, uu
○大文字を使う(サンスクリットのローマナイズの一方式)
A, E, I, O, U
○ラテン語の長音符号を流用(便宜的に後置)
a^, e^, i^, o^, u^
――それぞれ一長一短あると思いますが。
●二重母音
> この中から淘汰していきましょうか?
当方で考えたのは、/ai/ /au/ の他に /ei/ /eu/ /oi/ /ou/ の六つです。さらに絞るなら /ei/ を /e:/ と、/ou/ を /o:/ と統合してしまうことで、/ai/ /au/ /eu/ /oi/ の計四種でしょうか。
/i-/ に関しては /j-/ に、/u-/ は /w-/ に変化し易いということと、/i/ と /e/、/u/ と /o/ は混じり易いという辺りを鑑みましての試案です。
●文法
> 個人的な体験では、わりと作りやすかったのは
> 語順がSOVの膠着語とSVOの屈折語でした。
ごもっとも。
ところで、この両者については語順は割と自由にできますが、孤立語になるときっちり決めないといけませんね。
で。アラビア語・ヘブライ語のように母音交替によって単語が変化する、というのも未だ気になっています。
◆アクセント
>> 後ろから2音節目にアクセントが来るという法則も
はい、エスペラントとそれの基になったヨーロッパ諸言語で採られているアクセント方式です。ロマンス諸語やスラブ諸語などに多いですね。
>『強弱アクセント』なのか『高低アクセント』なのか
そうですね。長短母音の区別があるから、アクセントのある母音とて伸ばすわけにはいかないですね。強弱か長短か。これも悩ましい(というかあんまり考えていなかったりする)のですが、自然言語を例にとるとスペイン語、イタリア語などは強弱。高低アクセントはセルビア・クロアチア語に見られます。が、はっきり言って後者はかなり発音しづらい気がします。アクセントありとしたら強弱のほうが便利だと考えているところです。
>正確には語末にアクセントが来る
そうですね。フランス語、トルコ語、ペルシア語などは最後にアクセントが来て語尾上がりな感じになっていたと思います。(私の個人的な好みでは最後にアクセントが来て、文がのったり(?)している言語が美しいと感じます。)
◆長母音
教えていただいた案の中では「単純に文字を重ねる」のがいちばん簡単なように思います。じっさいの例ではオランダ語、フィンランド語、モンゴル語が同じ母音を重ねて長母音を表しています。個人的にはこれが書きやすくて良いのでは?と思います。
◆二重母音
>/ai/ /au/ の他に /ei/ /eu/ /oi/ /ou/ の六つ
私もこの6種あたりが妥当な線かと思っていました。
/i//u/始まりはたしかに半母音(子音)と解釈できますね。
/ei//ou/は仰るように微妙ですね。
長母音化してしまうのもアリかと思います。
◆文法
孤立語のばあいは語順の自由度はかなり狭まりますね。
あるていど語順の柔軟性がある類型が良いのではと
思ったり。
>母音交代
もし採用するならば例外は極力排除すべきとのご意見に
賛成です。アラビア語の母音交代ってけっこう例外が
多いんです(とくに複数形の作り方)。
というより母音交代のタイプが多すぎるのかもしれません。
>> 後ろから2音節目にアクセントが来るという法則も
はい、エスペラントとそれの基になったヨーロッパ諸言語で採られているアクセント方式です。ロマンス諸語やスラブ諸語などに多いですね。
>『強弱アクセント』なのか『高低アクセント』なのか
そうですね。長短母音の区別があるから、アクセントのある母音とて伸ばすわけにはいかないですね。強弱か長短か。これも悩ましい(というかあんまり考えていなかったりする)のですが、自然言語を例にとるとスペイン語、イタリア語などは強弱。高低アクセントはセルビア・クロアチア語に見られます。が、はっきり言って後者はかなり発音しづらい気がします。アクセントありとしたら強弱のほうが便利だと考えているところです。
>正確には語末にアクセントが来る
そうですね。フランス語、トルコ語、ペルシア語などは最後にアクセントが来て語尾上がりな感じになっていたと思います。(私の個人的な好みでは最後にアクセントが来て、文がのったり(?)している言語が美しいと感じます。)
◆長母音
教えていただいた案の中では「単純に文字を重ねる」のがいちばん簡単なように思います。じっさいの例ではオランダ語、フィンランド語、モンゴル語が同じ母音を重ねて長母音を表しています。個人的にはこれが書きやすくて良いのでは?と思います。
◆二重母音
>/ai/ /au/ の他に /ei/ /eu/ /oi/ /ou/ の六つ
私もこの6種あたりが妥当な線かと思っていました。
/i//u/始まりはたしかに半母音(子音)と解釈できますね。
/ei//ou/は仰るように微妙ですね。
長母音化してしまうのもアリかと思います。
◆文法
孤立語のばあいは語順の自由度はかなり狭まりますね。
あるていど語順の柔軟性がある類型が良いのではと
思ったり。
>母音交代
もし採用するならば例外は極力排除すべきとのご意見に
賛成です。アラビア語の母音交代ってけっこう例外が
多いんです(とくに複数形の作り方)。
というより母音交代のタイプが多すぎるのかもしれません。
すみません、すっかり遅くなってしまいました。
>rothkofanさま
記号のこと了解です。
>アクセント
>後ろから2音節目に固定
>強弱アクセントでOKです。
ふと思ったのですが、語形変化によってアクセントが移動することもあるのだろうかと。文法のほうでおいおい議論することになると思いますので、とりあえず今はこれでいきましょうか。
>二重母音
>設定を規則的にするなら6つ残しておいたほうが良いような
そうですね。残しておいてもいいでしょうね。/ei//ou/と揃っていたほうが体系的で規則的かと思います。
>母音交代
アラビア語の母音による格変化っていうのはずいぶん規則的なシステムですよね。格が必要最小限の3種類であり、それぞれ3つの母音を割りふっているというのも規則的です。さて格をどのようにするか、まず屈折語か膠着語かという類型を決めることが前提になってきます。ですので母音交代の話題は、文法トピックのほうへ移動して継続することに致しましょう。
さて、母音がある程度決まりましたので、このへんで「発音を決めよう」トピックの話題は「子音」を決めることにしたいと思いますが、いかがでしょうか?
>rothkofanさま
記号のこと了解です。
>アクセント
>後ろから2音節目に固定
>強弱アクセントでOKです。
ふと思ったのですが、語形変化によってアクセントが移動することもあるのだろうかと。文法のほうでおいおい議論することになると思いますので、とりあえず今はこれでいきましょうか。
>二重母音
>設定を規則的にするなら6つ残しておいたほうが良いような
そうですね。残しておいてもいいでしょうね。/ei//ou/と揃っていたほうが体系的で規則的かと思います。
>母音交代
アラビア語の母音による格変化っていうのはずいぶん規則的なシステムですよね。格が必要最小限の3種類であり、それぞれ3つの母音を割りふっているというのも規則的です。さて格をどのようにするか、まず屈折語か膠着語かという類型を決めることが前提になってきます。ですので母音交代の話題は、文法トピックのほうへ移動して継続することに致しましょう。
さて、母音がある程度決まりましたので、このへんで「発音を決めよう」トピックの話題は「子音」を決めることにしたいと思いますが、いかがでしょうか?
> さて、母音がある程度決まりましたので、このへんで「発音を決めよう」トピックの話題は「子音」を決めることにしたいと思いますが、いかがでしょうか?
諒解です。では率先して。
このトピの最初のほうで書いた通り、日本語(共通語)に含まれる子音に幾つか補ってと考えると:
| /r/ /h/ /k/ /g/ /ŋ/
| _______ /p/ /b/ /m/
| /l/ /s/ /t/ /d/ /n/
| _______ /ts/ /z/
| /y/ /ʃ/ /tʃ/ /ʒ/ /ɲ/
| /w/ /f/ ____ /v/
――で23ですか。環境によって一部の文字が読めないかも知れませんので、aを加えて日本語のア段でも示してみます。
ラ ハ カ ガ (ン)ガ
パ バ マ
ラ サ タ ダ ナ
ツァ ザ
ヤ シャ チャ ジャ ニャ
ワ ファ ヴァ
という感じで(間隔が上手く開きませんけれど)。
さらに加えるべき音など、ご意見ありましたらお願いします。
諒解です。では率先して。
このトピの最初のほうで書いた通り、日本語(共通語)に含まれる子音に幾つか補ってと考えると:
| /r/ /h/ /k/ /g/ /ŋ/
| _______ /p/ /b/ /m/
| /l/ /s/ /t/ /d/ /n/
| _______ /ts/ /z/
| /y/ /ʃ/ /tʃ/ /ʒ/ /ɲ/
| /w/ /f/ ____ /v/
――で23ですか。環境によって一部の文字が読めないかも知れませんので、aを加えて日本語のア段でも示してみます。
ラ ハ カ ガ (ン)ガ
パ バ マ
ラ サ タ ダ ナ
ツァ ザ
ヤ シャ チャ ジャ ニャ
ワ ファ ヴァ
という感じで(間隔が上手く開きませんけれど)。
さらに加えるべき音など、ご意見ありましたらお願いします。
どうもどうも。ちょっと戻ってしまうようで恐縮ですが、母音についてふたつほど。
1.
長母音と、短母音にアクセントが付いたものの区別が、世界中の話者にとって簡単に身につけられるかというと、かなり難しいと思います。実際に、日本語でモーラの長さを比較する実験に関わりましたが、前後の子音やアクセントの有る無しにより、モーラの物理的な長さは一定ではありませんでした。
それでも、日本人はモーラの長さを認識して、「固持」「工事」は母音の長さの違いとして区別ができます。しかし、英・韓・中の日本語学習者の発話を聞くと、きちんと区別できている人は稀です。また、日本人であっても、「病院」と「美容院」は母音の長さだけではなく、助詞につながる音のアクセントの違いで認識しているような感想を持っています。
単語のデザインのとき、品詞が異なるように配置すれば、認めても構わないと思います。例えばsakaは動詞「歩く」で、saakaは「歩行」など。または、あえて関連を持たせず、sakaは「歩く」で、saakaは「塩」など。そうすると、/a/と/aa/は文法・正書法の問題にとどまり、[a]と[aa]を区別する訓練が不要になります。
2.
追って書きます。
1.
長母音と、短母音にアクセントが付いたものの区別が、世界中の話者にとって簡単に身につけられるかというと、かなり難しいと思います。実際に、日本語でモーラの長さを比較する実験に関わりましたが、前後の子音やアクセントの有る無しにより、モーラの物理的な長さは一定ではありませんでした。
それでも、日本人はモーラの長さを認識して、「固持」「工事」は母音の長さの違いとして区別ができます。しかし、英・韓・中の日本語学習者の発話を聞くと、きちんと区別できている人は稀です。また、日本人であっても、「病院」と「美容院」は母音の長さだけではなく、助詞につながる音のアクセントの違いで認識しているような感想を持っています。
単語のデザインのとき、品詞が異なるように配置すれば、認めても構わないと思います。例えばsakaは動詞「歩く」で、saakaは「歩行」など。または、あえて関連を持たせず、sakaは「歩く」で、saakaは「塩」など。そうすると、/a/と/aa/は文法・正書法の問題にとどまり、[a]と[aa]を区別する訓練が不要になります。
2.
追って書きます。
2.
単語の中心となる母音1個ないし数個を除く母音は、[ə]になる傾向がある言語が多いと思います。
英語はその傾向が強く、第一・第二アクセント以外は、半分以上が[ə]と言っても過言ではありません。話者・方言によっては、ほとんど[ə]という例もあると思います。標準語でもaffectとeffectは、先頭にアクセントがないので、通常は区別不可能です。単語の意味も似ているし、お手上げです。
さて、そういう話者にとって、単語の中に2つ以上の母音があり、母音の区別が重要だとすると、学習は困難だと思います。例えば、英語話者が日本語の地名「北坂」「北崎」「片坂」(架空です)などの区別をすることは、実際に困難を極めているようです。
この点、母音調和が見られるトルコ語やモンゴル語は、単語内の母音が統一されている例が多く見られ、学習者には敷居が低いと思います。
粗く原則をまとめてみます。不正確かもしれませんが。
日本語:母音の区別をする。音素ごとに区別する。
トルコ語:母音の区別をする。単語・語尾つき単語ごとに区別する。
英語:母音の区別をする。アクセント位置の音素だけ区別する。
これをふまえて、架空言語話者の訛を見てみます。
架空言語には、
asaka saki saku sake sako
sika siki siku sike siko
...以下略
の単語があるとします。
英語訛の架空言語話者は、以下のようになります。(実際は3音節以上で観測されますが、見にくいので、2音節語にしました)
saka /sakə/
saki /sakə/
saku /sakə/
...以下略
sika /sikə/
siki /sikə/
siku /sikə/
...以下略
このように、英語訛では、アクセント位置以外の母音の発音は/ə/になってしまうので、区別できません。もしこの架空言語の標準語が、英語訛で定着すると、5つ同じ発音なのに表記は区別しなければならない、という矛盾が生まれます。
トルコ語訛の学習者は、母音の区別がわかり、しかも学習にそれほど抵抗がないと思います。
トルコ語式の母音調和を、語尾変化に導入することは、それほど必要を感じません。まったく同じ意味の語尾が、母音調和の規則のために複数用意されることになり、すっきりしたエスペラント語のような文法体系にはなりません。
これを少し緩和し、形態素ごとに母音調和させる原則なら、たとえ英語訛の人であっても、アクセント位置以外にも注目して、正しい母音を区別できるはずです。
つまり、こうなります。
nata-saka nata-siki nata-suku nata-seke nata-soko
niti-saka niti-siki niti-suku niti-seke niti-soko
...以下略
さらに、
ha-niti-saka ...
hi-niti-saka ...
hu-niti-saka ...
...以下略
この場合、基本的には、sikaのような母音が揃っていない単語は、存在してはいけないことになります。存在すると、複合語で、以下のような単語を区別しなければならなくなります。
ha-nata-saka
ha-nita-saka
ha-nati-saka
そこで、効果的に英語式の母音を導入したら、どうでしょうか。次の原則になります。
(1)形態素内の母音は、すべて同じ母音で調和すること。
例
dazaga /dazaga/
dizigi /dizigi/
duzugu /duzugu/
dezege /dezege/
dozogo /dozogo/
(2)ただし、アクセント位置を除く母音がすべてaなら、アクセント位置の母音は調和しなくてもよい。
例
daziga /daziga/または/dazigə/
dazuga /dazuga/または/dazugə/
dazega /dazega/または/dazegə/
dazoga /dazoga/または/dazogə/
ということで、英語訛の人でも、最初の母音さえ/a/と発音することに気をつければ、4つの区別ができます。
これで、3音節の単語のデザインでは、同じ子音で最大9個の単語を作ることができます。
もちろん9個フルに使うと覚えにくいですから、デザインのときは、同じ子音の組で3個から5個くらいですね。
単語の中心となる母音1個ないし数個を除く母音は、[ə]になる傾向がある言語が多いと思います。
英語はその傾向が強く、第一・第二アクセント以外は、半分以上が[ə]と言っても過言ではありません。話者・方言によっては、ほとんど[ə]という例もあると思います。標準語でもaffectとeffectは、先頭にアクセントがないので、通常は区別不可能です。単語の意味も似ているし、お手上げです。
さて、そういう話者にとって、単語の中に2つ以上の母音があり、母音の区別が重要だとすると、学習は困難だと思います。例えば、英語話者が日本語の地名「北坂」「北崎」「片坂」(架空です)などの区別をすることは、実際に困難を極めているようです。
この点、母音調和が見られるトルコ語やモンゴル語は、単語内の母音が統一されている例が多く見られ、学習者には敷居が低いと思います。
粗く原則をまとめてみます。不正確かもしれませんが。
日本語:母音の区別をする。音素ごとに区別する。
トルコ語:母音の区別をする。単語・語尾つき単語ごとに区別する。
英語:母音の区別をする。アクセント位置の音素だけ区別する。
これをふまえて、架空言語話者の訛を見てみます。
架空言語には、
asaka saki saku sake sako
sika siki siku sike siko
...以下略
の単語があるとします。
英語訛の架空言語話者は、以下のようになります。(実際は3音節以上で観測されますが、見にくいので、2音節語にしました)
saka /sakə/
saki /sakə/
saku /sakə/
...以下略
sika /sikə/
siki /sikə/
siku /sikə/
...以下略
このように、英語訛では、アクセント位置以外の母音の発音は/ə/になってしまうので、区別できません。もしこの架空言語の標準語が、英語訛で定着すると、5つ同じ発音なのに表記は区別しなければならない、という矛盾が生まれます。
トルコ語訛の学習者は、母音の区別がわかり、しかも学習にそれほど抵抗がないと思います。
トルコ語式の母音調和を、語尾変化に導入することは、それほど必要を感じません。まったく同じ意味の語尾が、母音調和の規則のために複数用意されることになり、すっきりしたエスペラント語のような文法体系にはなりません。
これを少し緩和し、形態素ごとに母音調和させる原則なら、たとえ英語訛の人であっても、アクセント位置以外にも注目して、正しい母音を区別できるはずです。
つまり、こうなります。
nata-saka nata-siki nata-suku nata-seke nata-soko
niti-saka niti-siki niti-suku niti-seke niti-soko
...以下略
さらに、
ha-niti-saka ...
hi-niti-saka ...
hu-niti-saka ...
...以下略
この場合、基本的には、sikaのような母音が揃っていない単語は、存在してはいけないことになります。存在すると、複合語で、以下のような単語を区別しなければならなくなります。
ha-nata-saka
ha-nita-saka
ha-nati-saka
そこで、効果的に英語式の母音を導入したら、どうでしょうか。次の原則になります。
(1)形態素内の母音は、すべて同じ母音で調和すること。
例
dazaga /dazaga/
dizigi /dizigi/
duzugu /duzugu/
dezege /dezege/
dozogo /dozogo/
(2)ただし、アクセント位置を除く母音がすべてaなら、アクセント位置の母音は調和しなくてもよい。
例
daziga /daziga/または/dazigə/
dazuga /dazuga/または/dazugə/
dazega /dazega/または/dazegə/
dazoga /dazoga/または/dazogə/
ということで、英語訛の人でも、最初の母音さえ/a/と発音することに気をつければ、4つの区別ができます。
これで、3音節の単語のデザインでは、同じ子音で最大9個の単語を作ることができます。
もちろん9個フルに使うと覚えにくいですから、デザインのときは、同じ子音の組で3個から5個くらいですね。
>拙者さん
こんにちは。
私の意見2は、文法的なルールにするのではなく、単語デザインの時に、避けるべき、または推奨されるべきルールという、設計者向けの補足のようなものと認識していただければいいと思います。
例えば、dezigaという単語を思いついて、それが1つの形態素であれば、なるべくdazigaかdizigiという単語に決定する、というようなことです。deとzigaが、すでにある形態素ならdezigaは許容されますが、アクセントがないので/dəziga/と発音さる可能性があるので、そうした例においても対策を考える必要は依然としてあります。例えばdeというアクセントなしの前置の語幹を作ったら、daは作らない、とか。
「[ə]化による混同が予測される形態素を作らない」というのが原則です。
こんにちは。
私の意見2は、文法的なルールにするのではなく、単語デザインの時に、避けるべき、または推奨されるべきルールという、設計者向けの補足のようなものと認識していただければいいと思います。
例えば、dezigaという単語を思いついて、それが1つの形態素であれば、なるべくdazigaかdizigiという単語に決定する、というようなことです。deとzigaが、すでにある形態素ならdezigaは許容されますが、アクセントがないので/dəziga/と発音さる可能性があるので、そうした例においても対策を考える必要は依然としてあります。例えばdeというアクセントなしの前置の語幹を作ったら、daは作らない、とか。
「[ə]化による混同が予測される形態素を作らない」というのが原則です。
> (それで、死郎さまと斯波左衛門尉良弼さまのレス待ちにしてるとこです)
ええと。すみません、お待たせしました(笑)。
チーズケーキ様のご意見を拝見していたところです。
なるほど、複雑な話になるのかと思いましたが、要するに単語設定の際の注意点ですか。たしかに(可能であれば)留意すべきかも知れません。
しかし、もしかするとその制約によって、同じ音節数に於ける単語のバリエーションが減ってしまうかもですね。
このへんはチーズケーキ様ご自身が『単語を決めよう』トピックでご提案されている内容とも絡んできそうな……必然的に長い単語にならざるを得なくなりそうな予感がします。これについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
拙者様も、ご参入ようこそです☆
ええと。すみません、お待たせしました(笑)。
チーズケーキ様のご意見を拝見していたところです。
なるほど、複雑な話になるのかと思いましたが、要するに単語設定の際の注意点ですか。たしかに(可能であれば)留意すべきかも知れません。
しかし、もしかするとその制約によって、同じ音節数に於ける単語のバリエーションが減ってしまうかもですね。
このへんはチーズケーキ様ご自身が『単語を決めよう』トピックでご提案されている内容とも絡んできそうな……必然的に長い単語にならざるを得なくなりそうな予感がします。これについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
拙者様も、ご参入ようこそです☆
>思いついた人が随時作成するというのでどうでしょう
そのほうがいいかもしれませんね。
トピ主がひとりだけですと更新が遅れてしまいますので。
思いついた方が随時トピックを作成するということで
いきましょうか。
ただし混乱を避けるためにトピック名の「形式」を定めて
おいて必ずそれに従った名前のトピックを立てることに
しましょう。
たとえば、発音関連の話題なら
”【発音/子音】子音の表記について”
”【文法】動詞の完了形について”
などなど。
アタマに「発音」(音韻論でもいいですが)とか
「文法」といった語を必ず付けて、なんのトピック
であるのか分かりやすいようにしておくのです。
というのはいかがでしょう?
*上のはあくまで一例です。
そのほうがいいかもしれませんね。
トピ主がひとりだけですと更新が遅れてしまいますので。
思いついた方が随時トピックを作成するということで
いきましょうか。
ただし混乱を避けるためにトピック名の「形式」を定めて
おいて必ずそれに従った名前のトピックを立てることに
しましょう。
たとえば、発音関連の話題なら
”【発音/子音】子音の表記について”
”【文法】動詞の完了形について”
などなど。
アタマに「発音」(音韻論でもいいですが)とか
「文法」といった語を必ず付けて、なんのトピック
であるのか分かりやすいようにしておくのです。
というのはいかがでしょう?
*上のはあくまで一例です。
>このへんはチーズケーキ様ご自身が
>『単語を決めよう』トピックでご提案されている内容とも絡んできそうな
発音のバリエーションと、同音異義語の解決についてですね。
確かに、私の意見は、発音のバリエーションを少なくする方向ですので、同音異義語を防ぐのに有効な「発音のバリエーションを確保する」を使えませんから、必然的に「音節数を多くする」になりますね。
>同じ音節数に於ける単語のバリエーションが減ってしまうかもですね。
おっしゃる通り、かなりの確率で、減ると思います。言語における形態素の数が一定だと仮定すると、単語の平均の音節数が増えますね。
ただ、死郎さんがまとめられているように、母音11、子音23を使うとすると、
V = 11C1
CV = 23C1 * 11C1 = 253
CVC = 23C1 * 11C1 * 23C1 = 5819
計6083で、発音しにくい音節を省くために20%を実際に使うとすると、1音節語では1216形態素の表記が可能です。
ここで、開音節か閉音節か、分けて考えます。
そして、2音節以上では母音調和をすると仮定します
VとCVとCVCV'とCVCV'CV''の場合
V = 11C1
CV = 23C1 * 11C1 = 253
CVCV' = 23C1 * 11C1 * 23C1 = 5819
CVCV'CV'' = 23C1 * 11C1 * 23C1 * 23C1 = 133837
計139920で、20%は27984形態素。
VとCVとCVCとCVCCV'CとCVCCV'CCV''Cの場合
なんか、計算がめんどくなってきましたが、要は開音節の23倍の23*23倍の23*23*23倍です。かなり多いです。
という感じで、母音調和を考慮しても、2音節あれば万単位の形態素を表せそうです。
でも、これは机上の空論ですので、なにか実際の言語を調査したり、架空言語でシミュレーションしたりしないと、現実的かどうか、わからないですね。
>『単語を決めよう』トピックでご提案されている内容とも絡んできそうな
発音のバリエーションと、同音異義語の解決についてですね。
確かに、私の意見は、発音のバリエーションを少なくする方向ですので、同音異義語を防ぐのに有効な「発音のバリエーションを確保する」を使えませんから、必然的に「音節数を多くする」になりますね。
>同じ音節数に於ける単語のバリエーションが減ってしまうかもですね。
おっしゃる通り、かなりの確率で、減ると思います。言語における形態素の数が一定だと仮定すると、単語の平均の音節数が増えますね。
ただ、死郎さんがまとめられているように、母音11、子音23を使うとすると、
V = 11C1
CV = 23C1 * 11C1 = 253
CVC = 23C1 * 11C1 * 23C1 = 5819
計6083で、発音しにくい音節を省くために20%を実際に使うとすると、1音節語では1216形態素の表記が可能です。
ここで、開音節か閉音節か、分けて考えます。
そして、2音節以上では母音調和をすると仮定します
VとCVとCVCV'とCVCV'CV''の場合
V = 11C1
CV = 23C1 * 11C1 = 253
CVCV' = 23C1 * 11C1 * 23C1 = 5819
CVCV'CV'' = 23C1 * 11C1 * 23C1 * 23C1 = 133837
計139920で、20%は27984形態素。
VとCVとCVCとCVCCV'CとCVCCV'CCV''Cの場合
なんか、計算がめんどくなってきましたが、要は開音節の23倍の23*23倍の23*23*23倍です。かなり多いです。
という感じで、母音調和を考慮しても、2音節あれば万単位の形態素を表せそうです。
でも、これは机上の空論ですので、なにか実際の言語を調査したり、架空言語でシミュレーションしたりしないと、現実的かどうか、わからないですね。
> という感じで、母音調和を考慮しても、2音節あれば万単位の形態素を表せそうです。
こうして数字で出てくると説得力がありますねえ。
たしかにこれだけあれば不足はなさそうな。
> でも、これは机上の空論ですので、なにか実際の言語を調査したり、架空言語でシミュレーションしたりしないと、現実的かどうか、わからないですね。
御意。挙げられたような英語話者の問題だけでなく、他の母語の場合も勘案すると、なんだかもっと制約がつきそうです。
……というか立ち戻って、(イギリス)英語や米語のネイティヴにだけそこまで配慮する必要があるのか、とも思えて来ました。
一応現在の事実上の世界標準の言語は英語ですが、そうではあっても内訳で“標準的な”英語を話すのは一握りですし。だいたい話者人口だけで見ると最大なのはインド英語だったりしますし。
まあもちろん、それに類した母語を持つ人たち、というところが主旨だとは思いますけれど。それでも彼らが世界の中で多数派だったり特に重要だったりするのかと言えば……どうなのでしょうか。
このへん、もうちょっと考えたほうがいいのかも知れませんね。
それはそれとして。
> >ただし混乱を避けるためにトピック名の「形式」を定めて
> >おいて必ずそれに従った名前のトピックを立てることに
異存ありません。よろしくー。
こうして数字で出てくると説得力がありますねえ。
たしかにこれだけあれば不足はなさそうな。
> でも、これは机上の空論ですので、なにか実際の言語を調査したり、架空言語でシミュレーションしたりしないと、現実的かどうか、わからないですね。
御意。挙げられたような英語話者の問題だけでなく、他の母語の場合も勘案すると、なんだかもっと制約がつきそうです。
……というか立ち戻って、(イギリス)英語や米語のネイティヴにだけそこまで配慮する必要があるのか、とも思えて来ました。
一応現在の事実上の世界標準の言語は英語ですが、そうではあっても内訳で“標準的な”英語を話すのは一握りですし。だいたい話者人口だけで見ると最大なのはインド英語だったりしますし。
まあもちろん、それに類した母語を持つ人たち、というところが主旨だとは思いますけれど。それでも彼らが世界の中で多数派だったり特に重要だったりするのかと言えば……どうなのでしょうか。
このへん、もうちょっと考えたほうがいいのかも知れませんね。
それはそれとして。
> >ただし混乱を避けるためにトピック名の「形式」を定めて
> >おいて必ずそれに従った名前のトピックを立てることに
異存ありません。よろしくー。
>まあもちろん、それに類した母語を持つ人たち、
>というところが主旨だとは思いますけれど。
そうなんです、特に英語話者というわけではないです。
>それでも彼らが世界の中で多数派だったり特に重要だったりする
>のかと言えば……どうなのでしょうか。
英語話者に限らず、誰にとっても、発音が似ている単語の多い言語は、難しいと思うのです。
繰り返しになりますが、
「[ə]化による混同が予測される形態素を作らない」というのが原則です。
母音による屈折を作るとか、接頭辞・接尾辞・語幹の案もないので、まだ未知数ですね。他の部分が決まるまで、この母音に関する補足の議論は、お休みしようと思いますが、いかがでしょうか。
議論再開のタイミングとしては、屈折や接尾辞のリストを、音声を含めて作り始めて、仮のリストができたときだと思います。
>というところが主旨だとは思いますけれど。
そうなんです、特に英語話者というわけではないです。
>それでも彼らが世界の中で多数派だったり特に重要だったりする
>のかと言えば……どうなのでしょうか。
英語話者に限らず、誰にとっても、発音が似ている単語の多い言語は、難しいと思うのです。
繰り返しになりますが、
「[ə]化による混同が予測される形態素を作らない」というのが原則です。
母音による屈折を作るとか、接頭辞・接尾辞・語幹の案もないので、まだ未知数ですね。他の部分が決まるまで、この母音に関する補足の議論は、お休みしようと思いますが、いかがでしょうか。
議論再開のタイミングとしては、屈折や接尾辞のリストを、音声を含めて作り始めて、仮のリストができたときだと思います。
上記トピック内であまり的を射ないコメントをした者ですが、まとめると:
基本母音は: a e i o u
それぞれに長母音あり: aa ee ii oo uu
二重母音は基本的に: ai au ei eu oi ou
音環境によっては各母音は曖昧化:@
語を作る時には混同しそうな語を避けるように心がける(aka ekaのような)
音節は「(C)V(C)」 ( )内は必須要素ではないことを表わす
(Vが長母音や二重母音のときも同様?)
アクセント位置は固定
(ひとまず後ろから二番目に)
強弱アクセント
母音交替による語形成とかも視野に
子音についての議論は別のトピックに
(uの音価は?ei ou は ee oo に合流する可能性あり?)
基本母音は: a e i o u
それぞれに長母音あり: aa ee ii oo uu
二重母音は基本的に: ai au ei eu oi ou
音環境によっては各母音は曖昧化:@
語を作る時には混同しそうな語を避けるように心がける(aka ekaのような)
音節は「(C)V(C)」 ( )内は必須要素ではないことを表わす
(Vが長母音や二重母音のときも同様?)
アクセント位置は固定
(ひとまず後ろから二番目に)
強弱アクセント
母音交替による語形成とかも視野に
子音についての議論は別のトピックに
(uの音価は?ei ou は ee oo に合流する可能性あり?)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
mixi発・人工言語を作ろう 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
mixi発・人工言語を作ろうのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90040人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6420人
- 3位
- 独り言
- 9045人