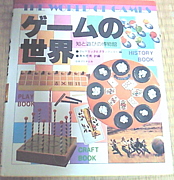|
|
|
|
コメント(92)
なるほど64マスチェッカーはオープニングを籤で選択ですか。確かに連珠の珠型選択と似ていますね。
しかしこういうやり方は先手後手の優劣をなくすには有力でしょうが、まずますオープニングを各形ごとに暗記しなければならなくなり、“研究”量で勝負がついてしまいそうです。いやそれこそがそのゲームの本質・醍醐味なのだという考え方もあるでしょうが、もっと自由に出たとこ勝負にはできないか?
そこでランダム配置という発想になるわけですが、ランダム配置もオープニングの選択の1種ではないかという疑問に対しては、すべての形(または類型)が研究可能(例えば連珠の26形)な範囲に収まっているのがオープニングの選択であって、それが不可能なほど膨大な量であるのがランダム配置であると使い分けましょうか。
そう考えたとき、ランダム配置が難しいゲームもありその典型例が連珠だと思います。そこで石(駒)だけでなくビッディングと組み合わせて盤もランダム配置にしたらどうかという前にも云った発想になってくるわけです。
実は囲碁でもランダム盤(http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16061995&comm_id=1857406)というのを考えたことがあります。これは盤端の攻防を予測不能なものにすることにより、従来の定石・布石理論を役に立たなくして、本質的に囲碁というものを理解しているかどうかを競おうというものです。9路盤程度の大きさなら、通常の盤だとそれこそ初手から終局までの研究が必要になりそうなので(それが面白いという考え方もあるでしょうが)、このルールなら興深くなると思います。
しかしこういうやり方は先手後手の優劣をなくすには有力でしょうが、まずますオープニングを各形ごとに暗記しなければならなくなり、“研究”量で勝負がついてしまいそうです。いやそれこそがそのゲームの本質・醍醐味なのだという考え方もあるでしょうが、もっと自由に出たとこ勝負にはできないか?
そこでランダム配置という発想になるわけですが、ランダム配置もオープニングの選択の1種ではないかという疑問に対しては、すべての形(または類型)が研究可能(例えば連珠の26形)な範囲に収まっているのがオープニングの選択であって、それが不可能なほど膨大な量であるのがランダム配置であると使い分けましょうか。
そう考えたとき、ランダム配置が難しいゲームもありその典型例が連珠だと思います。そこで石(駒)だけでなくビッディングと組み合わせて盤もランダム配置にしたらどうかという前にも云った発想になってくるわけです。
実は囲碁でもランダム盤(http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16061995&comm_id=1857406)というのを考えたことがあります。これは盤端の攻防を予測不能なものにすることにより、従来の定石・布石理論を役に立たなくして、本質的に囲碁というものを理解しているかどうかを競おうというものです。9路盤程度の大きさなら、通常の盤だとそれこそ初手から終局までの研究が必要になりそうなので(それが面白いという考え方もあるでしょうが)、このルールなら興深くなると思います。
>54 Stephen Cabotさん: 囲碁でもランダム盤
ランダム盤、いい考えですね。どこにも特異点がない盤というのを四一郎さんが紹介していました。(円筒形だったかな?でも、円筒形だと特異点があるな?)
この議論に四一郎さんを引っ張り込みましょうか?
↓
改めて、当該の日記を探してみたら、四一郎さんが言ってたのは「ナイトから見て正方形の盤」(つまりチェスの話でした。すみません。その話の過程で「円筒形の盤」の話も出たのでした。)
でも、引っ張り込むと面白そうなので、一度話をしてみます。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1241094035&owner_id=19185299&org_id=1226763988
ランダム盤、いい考えですね。どこにも特異点がない盤というのを四一郎さんが紹介していました。(円筒形だったかな?でも、円筒形だと特異点があるな?)
この議論に四一郎さんを引っ張り込みましょうか?
↓
改めて、当該の日記を探してみたら、四一郎さんが言ってたのは「ナイトから見て正方形の盤」(つまりチェスの話でした。すみません。その話の過程で「円筒形の盤」の話も出たのでした。)
でも、引っ張り込むと面白そうなので、一度話をしてみます。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1241094035&owner_id=19185299&org_id=1226763988
囲碁なら六角形よりむしろ三角形にして、三方を囲めばとれるようにすれば激しい戦いになっていいかもしれません。
あるいは2次元から3次元・4次元と拡げていくとか(http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16030039&comm_id=1857406)。1次元だって自明かというとそうでもありません。
いずれにせよ盤端の特異点がなければ退屈なゲームでしょうから、特異点をめぐる攻防になりそうです。
2次元の話に戻って、盤(というかマス)の形はすべてのマスを盤端の特異点を除いて等価にしようとすると3角形・4角形・6角形の3種類しかないのに、99.9%のゲームは4角形というのは不思議ですね。
囲碁・オセロ・連珠では3角形・6角形にすると根本的にゲームの性格が変わってしまうので面白くなるかどうかわかりませんが、将棋系ならゲームの本質が変わるわけではないので面白いゲームが作れそうな気がします。
ナッシュと云えばビューティフルマインド冒頭のプリンストンキャンパスのシーンで、ヘックスではなく(笑)囲碁を打っているシーンが思い浮かびます。あの映画では美化されていますが実際はとんでもない人物だったらしく、“ゲーム”というものの魔性を考えさせます。
あるいは2次元から3次元・4次元と拡げていくとか(http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16030039&comm_id=1857406)。1次元だって自明かというとそうでもありません。
いずれにせよ盤端の特異点がなければ退屈なゲームでしょうから、特異点をめぐる攻防になりそうです。
2次元の話に戻って、盤(というかマス)の形はすべてのマスを盤端の特異点を除いて等価にしようとすると3角形・4角形・6角形の3種類しかないのに、99.9%のゲームは4角形というのは不思議ですね。
囲碁・オセロ・連珠では3角形・6角形にすると根本的にゲームの性格が変わってしまうので面白くなるかどうかわかりませんが、将棋系ならゲームの本質が変わるわけではないので面白いゲームが作れそうな気がします。
ナッシュと云えばビューティフルマインド冒頭のプリンストンキャンパスのシーンで、ヘックスではなく(笑)囲碁を打っているシーンが思い浮かびます。あの映画では美化されていますが実際はとんでもない人物だったらしく、“ゲーム”というものの魔性を考えさせます。
>61
六角形のマス(ヘックス)に打てば六角碁ですが、交点(六角形の頂点)に打てば三角碁になり(つまり双対関係にある)、すでに沢山プレーされています。それなりに面白いです。更に、三次元、四次元、五次元などへの拡張もなされています。三次元碁すなわち立体碁は、面と面の戦いになって面白いです。もっとも石は切れにくく、敵地への侵入は簡単で、「地」の囲いにくい碁(互いに荒らしあう碁)になりがちですが。
特異点のないトーラス碁もそれはそれで面白いです。フェアリー盤にはほかにアニュラス盤、クライン盤、クロスキャップ盤、三次元トーラス盤(四次元内で実現するもの)など、多数試みられています。
また、99.9%のゲームが4角形ということは全くなく、ヘックス盤のゲームは、非常にたくさんあります。シミュレーションゲームを入れれば、4角形より6角形のゲームのほうが、むしろ種類はずっと多いでしょう。
六角形のマス(ヘックス)に打てば六角碁ですが、交点(六角形の頂点)に打てば三角碁になり(つまり双対関係にある)、すでに沢山プレーされています。それなりに面白いです。更に、三次元、四次元、五次元などへの拡張もなされています。三次元碁すなわち立体碁は、面と面の戦いになって面白いです。もっとも石は切れにくく、敵地への侵入は簡単で、「地」の囲いにくい碁(互いに荒らしあう碁)になりがちですが。
特異点のないトーラス碁もそれはそれで面白いです。フェアリー盤にはほかにアニュラス盤、クライン盤、クロスキャップ盤、三次元トーラス盤(四次元内で実現するもの)など、多数試みられています。
また、99.9%のゲームが4角形ということは全くなく、ヘックス盤のゲームは、非常にたくさんあります。シミュレーションゲームを入れれば、4角形より6角形のゲームのほうが、むしろ種類はずっと多いでしょう。
アブストラクトゲームや一般ボードゲームのヘックスもとても多いですよ。
例えばクニツィアの「頭脳絶好調」とか、カワサキさんの「ガウス」とか、「ロボトリー」などもそうです。有名な「カタン」もそうですし、「テイクイットイージー」や「穴掘り土竜」や「レイルウェイライバルズ」もそうです。さらにギプフシリーズにはヘックス盤が沢山ありますし、盤はないけど、「ハイヴ」もそうです。かっきりしたスクウェア盤は案外少ないので、恐らくスクウェア盤のゲームよりヘックス盤のゲームの方が多いでしょう。更にこれにシュミレーションゲームを入れたら、種類だけで数えれば6角形の方が圧倒的に多いということになると思います。
例えばクニツィアの「頭脳絶好調」とか、カワサキさんの「ガウス」とか、「ロボトリー」などもそうです。有名な「カタン」もそうですし、「テイクイットイージー」や「穴掘り土竜」や「レイルウェイライバルズ」もそうです。さらにギプフシリーズにはヘックス盤が沢山ありますし、盤はないけど、「ハイヴ」もそうです。かっきりしたスクウェア盤は案外少ないので、恐らくスクウェア盤のゲームよりヘックス盤のゲームの方が多いでしょう。更にこれにシュミレーションゲームを入れたら、種類だけで数えれば6角形の方が圧倒的に多いということになると思います。
アブストラクトゲームや一般ボードゲームでも六角形は多数派である…
確かにそうかもしれません。ただ残念ながらメジャーになったゲームがないですね。メジャーという言い方がおかしければ文化として認められた存在といいましょうか。
あるいはあげられているゲームのどれかが時間がたてばそういう存在になるのかもしれません。そのゲームにそれだけの魅力があれば…
ゲームの魅力は逆説的ですが、“人間にとって”易しいことではないでしょうか。易しいというのは“ヨミやすい”ということであって、思考回路がつながって電流が流れるように手がひらめくときに、人は面白いと感じるのだと思います。
私が一番面白いと思うのは囲碁ですが、これは人間にとって非常に易しいゲームであり、最も難しい(変化が広い)とされているのは19路と盤が広いからだけです。8路にすればオセロの方がはるかに難しいことは自明でしょう。
これはオセロが一手で多くの石がひっくり返るため人間にとって非常に読みにくいからであり、コンピューターにとっては囲碁の一手もオセロの一手も同じですが、人間にとっては囲碁は非常に読みやすくそのために筋のひらめきのようなものを感じやすく面白いと感じるのだと思います。オセロではコンピュターは人間などでは相手にならず、チェスはいい勝負、囲碁はコンピューターなど論外というのはコンピューターの強弱ではなく、人間にとって囲碁は易しいから人間が強すぎるのでしょう。逆に云えば易しいゲームだからこそ19路まで広げても興を削ぐことなく、特異点の盤全体に占めるバランスがちょうどいいところまで盤を広げることができたのかもしれません。オセロでこれ以上盤を広くすると人間にとっては難しすぎて興を削いでしまいますし、将棋系のメジャーなゲームが8路・9路であって、大将棋などが廃れてしまったというのも、これが人間が愉しめるちょうどいい大きさなのでしょう。
そういう意味では“易しい”ゲームを創ることが重要だと思います。
道路図から原稿用紙のマス目に至るまで世の中はスクエアにあふれており、我々はスクエアの世界に慣れ親しんでいます。そこにヘックスの世界を持ち込むのは何か違和感があって難しく感じるのかもしれません。
そういう意味ではシミュレーションゲームに慣れ親しんだ若い世代はヘックスに抵抗がないでしょうから、文化にまで成長する偉大なヘックスボードゲームが生まれるかもしれません…いやもう生まれているのだが宣伝不足の問題で汎く知られていないだけなのか? 近年メジャーになったゲームとしてはオセロがありますが、このゲームの普及宣伝活動は実に戦略的で見事だったと思います。
着手放棄は“着手”と認められるかどうかは囲碁の終局ルール上の重要な問題であり、中国ルールではその点が問題にならないのは大きな利点です。ただ地を数えるのではなく石を数えるというのは、コンピューターに教え込むには好適かもしれませんが、人間の感性にはちょっとひっかかる部分があります。
もっとも1次元碁の着手放棄の問題については中国ルールも日本ルールも関係ないみたいですが。
国際ルールの動きについては私もよく知りません。現在のところ韓国(日本ルール)が最強だし、日本が中心に国際普及を図った歴史的事情から中国(中国ルールのバリエーションの台湾を含む)以外で中国ルールを積極的に採用する国はないと思うので、日本ルールを基本に細部を厳密に定義していくというのが常識的だと思いますが…
チベットルールのトリアトには直接ナカデできず、一度コウダテ?を打ってからというのは確かシッキムルールといわれてなかったかな。シッキムはチベット人の王国でインド―英国とチベット―中国の緩衝地帯として数百年存在しましたが近年インドに併合されました。国王(皇太子だったかも)が来日したときに日本棋院を訪問しこのルールで対戦したという大昔の棋道の記事を読んだ覚えがあります。
大石はソバコウが多いので、ナカデになっても実質的にははイキみたいなものですから死活の感覚がまるきり違うゲームになりますね。
確かにそうかもしれません。ただ残念ながらメジャーになったゲームがないですね。メジャーという言い方がおかしければ文化として認められた存在といいましょうか。
あるいはあげられているゲームのどれかが時間がたてばそういう存在になるのかもしれません。そのゲームにそれだけの魅力があれば…
ゲームの魅力は逆説的ですが、“人間にとって”易しいことではないでしょうか。易しいというのは“ヨミやすい”ということであって、思考回路がつながって電流が流れるように手がひらめくときに、人は面白いと感じるのだと思います。
私が一番面白いと思うのは囲碁ですが、これは人間にとって非常に易しいゲームであり、最も難しい(変化が広い)とされているのは19路と盤が広いからだけです。8路にすればオセロの方がはるかに難しいことは自明でしょう。
これはオセロが一手で多くの石がひっくり返るため人間にとって非常に読みにくいからであり、コンピューターにとっては囲碁の一手もオセロの一手も同じですが、人間にとっては囲碁は非常に読みやすくそのために筋のひらめきのようなものを感じやすく面白いと感じるのだと思います。オセロではコンピュターは人間などでは相手にならず、チェスはいい勝負、囲碁はコンピューターなど論外というのはコンピューターの強弱ではなく、人間にとって囲碁は易しいから人間が強すぎるのでしょう。逆に云えば易しいゲームだからこそ19路まで広げても興を削ぐことなく、特異点の盤全体に占めるバランスがちょうどいいところまで盤を広げることができたのかもしれません。オセロでこれ以上盤を広くすると人間にとっては難しすぎて興を削いでしまいますし、将棋系のメジャーなゲームが8路・9路であって、大将棋などが廃れてしまったというのも、これが人間が愉しめるちょうどいい大きさなのでしょう。
そういう意味では“易しい”ゲームを創ることが重要だと思います。
道路図から原稿用紙のマス目に至るまで世の中はスクエアにあふれており、我々はスクエアの世界に慣れ親しんでいます。そこにヘックスの世界を持ち込むのは何か違和感があって難しく感じるのかもしれません。
そういう意味ではシミュレーションゲームに慣れ親しんだ若い世代はヘックスに抵抗がないでしょうから、文化にまで成長する偉大なヘックスボードゲームが生まれるかもしれません…いやもう生まれているのだが宣伝不足の問題で汎く知られていないだけなのか? 近年メジャーになったゲームとしてはオセロがありますが、このゲームの普及宣伝活動は実に戦略的で見事だったと思います。
着手放棄は“着手”と認められるかどうかは囲碁の終局ルール上の重要な問題であり、中国ルールではその点が問題にならないのは大きな利点です。ただ地を数えるのではなく石を数えるというのは、コンピューターに教え込むには好適かもしれませんが、人間の感性にはちょっとひっかかる部分があります。
もっとも1次元碁の着手放棄の問題については中国ルールも日本ルールも関係ないみたいですが。
国際ルールの動きについては私もよく知りません。現在のところ韓国(日本ルール)が最強だし、日本が中心に国際普及を図った歴史的事情から中国(中国ルールのバリエーションの台湾を含む)以外で中国ルールを積極的に採用する国はないと思うので、日本ルールを基本に細部を厳密に定義していくというのが常識的だと思いますが…
チベットルールのトリアトには直接ナカデできず、一度コウダテ?を打ってからというのは確かシッキムルールといわれてなかったかな。シッキムはチベット人の王国でインド―英国とチベット―中国の緩衝地帯として数百年存在しましたが近年インドに併合されました。国王(皇太子だったかも)が来日したときに日本棋院を訪問しこのルールで対戦したという大昔の棋道の記事を読んだ覚えがあります。
大石はソバコウが多いので、ナカデになっても実質的にははイキみたいなものですから死活の感覚がまるきり違うゲームになりますね。
>66
もし「メジャーなゲーム」が歴史の長いゲームと言う意味なら、確かに六角形のマスはメジャーではありません。理由は簡単で、六角形のマスは作りにくいからです。四角形は縦横に線を引けばいいので、昔からあるということです。これから将来は六角形も四角形以上に作られるでしょう。
マスが四角形(スクエア盤)のアブストラクトの新作も結構あります。マグベス、タンボ、ニュートロン、フットボールなどで、中でもアマゾンはなかなかの傑作です。
「易しい」ゲームというのは、「そのルールを成立させる最小の複雑さ」と言い換えていいのではないかと私は思います。囲碁の19路は私には広すぎます。17路あるいは15路でいいのではないかと思います。もちろんいわゆる大局観は損なわれますが、大局観が難しいのです。面白いとも言えますが。21路や23路で打ったこともありますが、流石に大局観が難しくなりすぎ、時間もかかりすぎます。
リバーシ(オセロ)は、6路盤は解かれました。後手勝ちです。
8路盤はまだ当分とけそうもないですが、既にコンピュータに勝てる人はいないでしょう。仰る通り、リバーシは人間には難しく相対的に機械には簡単なゲームです。
10路盤リバーシ(グランドオセロ)の大会も何度か行われているのですが、やはり8路盤の強い人が強いものの、面白いことに「感覚」の要素が出てきて、8路盤の中級者でも10路盤を研究すると、8路盤の上級者相手に結構戦えます。
三次元リバーシ(立体オセロ)は、もう人間の手に負えないゲームで、最後まで打ち切るだけでも大変でした。
囲碁のルールは当然合理的な中国・台湾ルールであるべきで、日本ルールは初級者には難しすぎます。終ったか終らないかすら、技量によって判断が異なるのでは、ゲームとしては失格です。
また囲碁のコミが日本式に数えて7目半もあるのは、まだまだ人間が弱すぎるからで、神様の目から見れば、19路盤の本質的なコミは1目半か2目半でしょう。コミは今後も増えるかも知れませんが、将来的に見れば(もし人間の技量がずっと上がれば)今度は減少傾向に転じると私は考えています。
もし「メジャーなゲーム」が歴史の長いゲームと言う意味なら、確かに六角形のマスはメジャーではありません。理由は簡単で、六角形のマスは作りにくいからです。四角形は縦横に線を引けばいいので、昔からあるということです。これから将来は六角形も四角形以上に作られるでしょう。
マスが四角形(スクエア盤)のアブストラクトの新作も結構あります。マグベス、タンボ、ニュートロン、フットボールなどで、中でもアマゾンはなかなかの傑作です。
「易しい」ゲームというのは、「そのルールを成立させる最小の複雑さ」と言い換えていいのではないかと私は思います。囲碁の19路は私には広すぎます。17路あるいは15路でいいのではないかと思います。もちろんいわゆる大局観は損なわれますが、大局観が難しいのです。面白いとも言えますが。21路や23路で打ったこともありますが、流石に大局観が難しくなりすぎ、時間もかかりすぎます。
リバーシ(オセロ)は、6路盤は解かれました。後手勝ちです。
8路盤はまだ当分とけそうもないですが、既にコンピュータに勝てる人はいないでしょう。仰る通り、リバーシは人間には難しく相対的に機械には簡単なゲームです。
10路盤リバーシ(グランドオセロ)の大会も何度か行われているのですが、やはり8路盤の強い人が強いものの、面白いことに「感覚」の要素が出てきて、8路盤の中級者でも10路盤を研究すると、8路盤の上級者相手に結構戦えます。
三次元リバーシ(立体オセロ)は、もう人間の手に負えないゲームで、最後まで打ち切るだけでも大変でした。
囲碁のルールは当然合理的な中国・台湾ルールであるべきで、日本ルールは初級者には難しすぎます。終ったか終らないかすら、技量によって判断が異なるのでは、ゲームとしては失格です。
また囲碁のコミが日本式に数えて7目半もあるのは、まだまだ人間が弱すぎるからで、神様の目から見れば、19路盤の本質的なコミは1目半か2目半でしょう。コミは今後も増えるかも知れませんが、将来的に見れば(もし人間の技量がずっと上がれば)今度は減少傾向に転じると私は考えています。
偶数路盤はコミが小さいことが知られています。それで奇数路盤について考えます。
7路盤以下の奇数路盤はコミは大きいでしょう。5路盤の天元に打たれると、後手は対抗しようがないように思います。コミは24なのかな。9路盤は私には難しくて分かりませんが、どうなのでしょうか。9から上は全て同じという説は、本当かなあと思います。大きくなるほど先手の有利が薄まりそうだから、わずかずつでもコミは小さくなりそうですが、違うのでしょうか。
19路盤はある意味特殊です。9路盤などは全てが局地戦なので、大局観が成立しにくいです。15路まではそんな感じが付きまといます。21路は19路とあまり変わりませんが、23路以上になると、再び大局観が薄まります。25路だと、隅と他の隅の関連はなくなり、再び局地戦の集合のようになる感じです。
19路だと三連星が成立します。三連星の間に打ち込むのは、もちろん死にはしませんが、先手にいじめられてそれなりに大変です。ところが25路以上だと星と星が遠すぎて、三連星を打っても先手の有利が生きない感じがします。勢力が張れていないので、布石の意味が薄らぐと思われます。
19路は流石に歴史の洗礼を潜り抜けただけあって、最も大局観の必要な大きさに思われます。私のように技量のないものには広すぎますが。
あとは長方形版ですが、偶数×偶数はコミが小さいでしょう。あとはどうなのでしょうか。一次元盤は長方形番の極端な例と考えられます。奇数×n盤ですね。
7路盤以下の奇数路盤はコミは大きいでしょう。5路盤の天元に打たれると、後手は対抗しようがないように思います。コミは24なのかな。9路盤は私には難しくて分かりませんが、どうなのでしょうか。9から上は全て同じという説は、本当かなあと思います。大きくなるほど先手の有利が薄まりそうだから、わずかずつでもコミは小さくなりそうですが、違うのでしょうか。
19路盤はある意味特殊です。9路盤などは全てが局地戦なので、大局観が成立しにくいです。15路まではそんな感じが付きまといます。21路は19路とあまり変わりませんが、23路以上になると、再び大局観が薄まります。25路だと、隅と他の隅の関連はなくなり、再び局地戦の集合のようになる感じです。
19路だと三連星が成立します。三連星の間に打ち込むのは、もちろん死にはしませんが、先手にいじめられてそれなりに大変です。ところが25路以上だと星と星が遠すぎて、三連星を打っても先手の有利が生きない感じがします。勢力が張れていないので、布石の意味が薄らぐと思われます。
19路は流石に歴史の洗礼を潜り抜けただけあって、最も大局観の必要な大きさに思われます。私のように技量のないものには広すぎますが。
あとは長方形版ですが、偶数×偶数はコミが小さいでしょう。あとはどうなのでしょうか。一次元盤は長方形番の極端な例と考えられます。奇数×n盤ですね。
19路盤が一番大局観が要求され、したがって(少なくとも私にとっては)一番おもしろそうというのは、そのサイズがちょうど盤端の特異点の盤全体に占める割合がちょうどいいのでしょう。それ以下だとヨミキリの世界になってくるし、大きな盤というのはお互いに勝手なことがやれるでしょうから。
それぞれのサイズの“真の”コミについては良く判りません。
5路盤の24目など後手全滅の場合等は別にして、ある程度の大きさの盤のコミはどの程度が正解なのか…
19路盤のコミはこれまでの経験から80%以上の確率で7目だと思います。そのプラスマイナス1目もあわせればで99%以上の確率になるでしょう。神の眼から見れば…という可能性も完全に否定はできませんが、今後白番の打ち方だけが進歩していくとは考えにくいと思います。神の能力を100として人間の能力が5だとしても、それは白も黒も5でしょう。
そして9路盤のコミが19路盤と同じ程度であるらしいということから、9路盤以上は変わらないのかどうか…
私は9路盤はかなり読み切れる世界ですから、コミが19路盤とほぼ同じらしいというのは単なる偶然だと考えています。ですから10路盤11路盤などは増減があると思います。
問題はある程度大きな盤、例えば19路盤以上になったときにコミは(おそらく7目で)変わらないのか、それともある目数に向けて暫減・または暫増していくのか、それとも偶数盤はコミが小さいといった理屈があって上がったり下がったりしていくのかということですね。
これは正直さっぱりわかりません。無限大に近くなれば先手後手はあまり関係ないような気がするので、1目またはゼロ目に向けて収束するような気がしますが、収束はゆっくりとしたペースなので100路盤くらいまでは7目プラスマイナス1目で変わらないのではないかというのが何の根拠もない私の直感です。
中国ルールというのは囲碁が考案されたときのルールだったのでしょうし、“地”というものの定義は難しいので、石の存在可能性を争う方が厳密に定義できて優れたルールだという考え方は当然あると思います。入門者やコンピューターに教えるには適したルールかもしれません。
しかしながら入門者が初心者のクラスまで上達すると地の概念がすぐ理解できるようになるので、日本ルールの方がわかりやすくなります。そして何よりも地を囲う・荒らすといった概念が感覚的にわかりやすくなるので、一局にストーリー性が出てきます。オセロのように石数が多い方が勝ちというのでは感覚的にピンとこないし、中国人だって終局時以外は日本風に思考しているはずです。おまけに中国ルールでは終局時の整地が面倒だし、中国ルールの中でも最も合理的といわれるバリエーションでは、専門の石を数える道具まで必要でとても普及可能なルールとは思えません。
もちろん日本ルールには終局の定義がはっきりしない部分があり、その部分は厳密にルールを決めておく必要があるでしょう。しかしながらそれは明文化しておけばいいというだけの話であり、ここが面倒だからとか、あるいは厳密なルール化というのはルールは単純な方が優れているので好ましくないとかいう理由で中国ルールというのではゲームの本質を損なってしまうでしょう。
1次元碁、あるいは短辺が1路の長方形盤というのは案外変化があります。2×2の4路盤というのは考えるまでもありませんが、1×4の1次元4路盤はどう決着するか? 結局はルール問題として何らかの取り決めをする必要がありますが、これは中国ルールでも日本ルールでも同様であり、中国ルールだから実戦に即して解決できるというものではありません。
それぞれのサイズの“真の”コミについては良く判りません。
5路盤の24目など後手全滅の場合等は別にして、ある程度の大きさの盤のコミはどの程度が正解なのか…
19路盤のコミはこれまでの経験から80%以上の確率で7目だと思います。そのプラスマイナス1目もあわせればで99%以上の確率になるでしょう。神の眼から見れば…という可能性も完全に否定はできませんが、今後白番の打ち方だけが進歩していくとは考えにくいと思います。神の能力を100として人間の能力が5だとしても、それは白も黒も5でしょう。
そして9路盤のコミが19路盤と同じ程度であるらしいということから、9路盤以上は変わらないのかどうか…
私は9路盤はかなり読み切れる世界ですから、コミが19路盤とほぼ同じらしいというのは単なる偶然だと考えています。ですから10路盤11路盤などは増減があると思います。
問題はある程度大きな盤、例えば19路盤以上になったときにコミは(おそらく7目で)変わらないのか、それともある目数に向けて暫減・または暫増していくのか、それとも偶数盤はコミが小さいといった理屈があって上がったり下がったりしていくのかということですね。
これは正直さっぱりわかりません。無限大に近くなれば先手後手はあまり関係ないような気がするので、1目またはゼロ目に向けて収束するような気がしますが、収束はゆっくりとしたペースなので100路盤くらいまでは7目プラスマイナス1目で変わらないのではないかというのが何の根拠もない私の直感です。
中国ルールというのは囲碁が考案されたときのルールだったのでしょうし、“地”というものの定義は難しいので、石の存在可能性を争う方が厳密に定義できて優れたルールだという考え方は当然あると思います。入門者やコンピューターに教えるには適したルールかもしれません。
しかしながら入門者が初心者のクラスまで上達すると地の概念がすぐ理解できるようになるので、日本ルールの方がわかりやすくなります。そして何よりも地を囲う・荒らすといった概念が感覚的にわかりやすくなるので、一局にストーリー性が出てきます。オセロのように石数が多い方が勝ちというのでは感覚的にピンとこないし、中国人だって終局時以外は日本風に思考しているはずです。おまけに中国ルールでは終局時の整地が面倒だし、中国ルールの中でも最も合理的といわれるバリエーションでは、専門の石を数える道具まで必要でとても普及可能なルールとは思えません。
もちろん日本ルールには終局の定義がはっきりしない部分があり、その部分は厳密にルールを決めておく必要があるでしょう。しかしながらそれは明文化しておけばいいというだけの話であり、ここが面倒だからとか、あるいは厳密なルール化というのはルールは単純な方が優れているので好ましくないとかいう理由で中国ルールというのではゲームの本質を損なってしまうでしょう。
1次元碁、あるいは短辺が1路の長方形盤というのは案外変化があります。2×2の4路盤というのは考えるまでもありませんが、1×4の1次元4路盤はどう決着するか? 結局はルール問題として何らかの取り決めをする必要がありますが、これは中国ルールでも日本ルールでも同様であり、中国ルールだから実戦に即して解決できるというものではありません。
> ホイジンガのホモ・ルーデンス
増川さんの「将棋の起源」平凡社1996 p150から抜粋
1990年にザルツブルグのモツアルテウム音楽外学のギュンター・バウアー教授の提唱により、同大学内に「遊戯研究と遊戯教育のための研究所」が設立された。・・・最大の功績は93年以来、学術書「ホモルーデンス」シリーズを毎年ザルツブルグとミュンヘンから出版、各国の研究者の最新の発表とキコウ本の復刻とをおこなっている。
最近、翻訳ツールが発達しているので、英語以外も内容の見当つようになることを期待しています。
米国の大手書店ではねっとでの立ち読みが可能になてきたらしい。国会図書館の電子化の進展もあるようです。
増川さんの「将棋の起源」平凡社1996 p150から抜粋
1990年にザルツブルグのモツアルテウム音楽外学のギュンター・バウアー教授の提唱により、同大学内に「遊戯研究と遊戯教育のための研究所」が設立された。・・・最大の功績は93年以来、学術書「ホモルーデンス」シリーズを毎年ザルツブルグとミュンヘンから出版、各国の研究者の最新の発表とキコウ本の復刻とをおこなっている。
最近、翻訳ツールが発達しているので、英語以外も内容の見当つようになることを期待しています。
米国の大手書店ではねっとでの立ち読みが可能になてきたらしい。国会図書館の電子化の進展もあるようです。
ホイジンガは本国以上に日本で人気があるのではないでしょうか。欧米ではどちらかというと中世の秋に代表される歴史家扱いですが、日本では何といっても遊戯を取り上げたホモ・ルーデンスです。もっとも私は中世の秋は大傑作だと思うのですが、ホモ・ルーデンスの方は途中で退屈になって放り出してしまいました(笑)。
食事やSEXといった本来生命維持活動であるものまで遊戯にしてしまったのがヒトであるならば、最も純粋な?遊戯というべき盤上競技は最も人間らしい活動かもしれません。
大型ネット書店(私が利用しているのは主にe−books)では、ネット上での立ち読み?として2ページアップしては1ページ非公開にするのを繰り返す方式を採用している場合があり、なかなかいいアイデアだと思います。
食事やSEXといった本来生命維持活動であるものまで遊戯にしてしまったのがヒトであるならば、最も純粋な?遊戯というべき盤上競技は最も人間らしい活動かもしれません。
大型ネット書店(私が利用しているのは主にe−books)では、ネット上での立ち読み?として2ページアップしては1ページ非公開にするのを繰り返す方式を採用している場合があり、なかなかいいアイデアだと思います。
なぜ「コミ碁」は碁にあらずという言葉があったのでしょうか?
大手合ではコミなし、コミは勝負を早く付けたいとの要求から始まりました。記事などには締め切りがありますので。
コミなしは明らかに先手有利。それでも古来から続いてきたルールです。
連珠は禁手なしならほぼ先手必勝。
現在、連珠には19道四四非禁と15道の四四禁ルールと2種目あり、19道連珠はごく少数の人たちが行っています。(五目並べは連珠とやや異なりルールに各種ある)
19道の場合、先手有利のはず、だが公式対局が行われてきており、定石もあります。
草場さんから、先手有利なのであるから、19道でも四四禁にしてもよいのではないかとの疑問がありました。盤上ゲームとして先手後手すこしでも均等に近づけばよいはずです。しかし、19道四四非禁は存続しています。
コミ碁は碁にあらず・・・先手有利でも白は横綱相撲をとればよいとの趣旨なのでしょう。
先手後手、両方を持って対局すれば公平です、しかし、時間がかかります。
ドラフツの場合、引き分けがあると、再度持ち時間を少なくして対戦し、1日のうちで勝負の決着をつけています。囲碁ではそぐわない方式です。将棋の千日手は再対局を行っています。コミのルールが世界的に普及したのも無理はありません
大手合ではコミなし、コミは勝負を早く付けたいとの要求から始まりました。記事などには締め切りがありますので。
コミなしは明らかに先手有利。それでも古来から続いてきたルールです。
連珠は禁手なしならほぼ先手必勝。
現在、連珠には19道四四非禁と15道の四四禁ルールと2種目あり、19道連珠はごく少数の人たちが行っています。(五目並べは連珠とやや異なりルールに各種ある)
19道の場合、先手有利のはず、だが公式対局が行われてきており、定石もあります。
草場さんから、先手有利なのであるから、19道でも四四禁にしてもよいのではないかとの疑問がありました。盤上ゲームとして先手後手すこしでも均等に近づけばよいはずです。しかし、19道四四非禁は存続しています。
コミ碁は碁にあらず・・・先手有利でも白は横綱相撲をとればよいとの趣旨なのでしょう。
先手後手、両方を持って対局すれば公平です、しかし、時間がかかります。
ドラフツの場合、引き分けがあると、再度持ち時間を少なくして対戦し、1日のうちで勝負の決着をつけています。囲碁ではそぐわない方式です。将棋の千日手は再対局を行っています。コミのルールが世界的に普及したのも無理はありません
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
盤上ゲーム図書資料館 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
盤上ゲーム図書資料館のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77276人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209398人
- 3位
- 福岡 ソフトバンクホークス
- 42914人