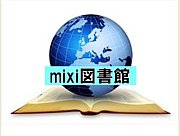レビューに掲載している本の中から、
私の心に響いた言葉を残しています。
ご参加は、いつもどおり自由です



mixi図書館入り口へ
http://
私の心に響いた言葉を残しています。
ご参加は、いつもどおり自由です
mixi図書館入り口へ
http://
|
|
|
|
コメント(70)
あいさんの日記より〜
京セラ会長・稲盛和夫その1
以前、ドツボのとき通勤で秋葉原から乗り換えた山手線の車内広告で「生き方」という文字が目に入り、本屋に直行してこの本を購入しました。
いまだに本屋さんで売れてます
京セラ会長・稲盛和夫、氏は得度(出家)してます。
『生き方−人間として一番大切なこと』(稲盛和夫)より
一生懸命に働くこと、感謝の心を忘れないこと、善き思い、正しい行いに努めること、素直な反省真でいつも自分を律すること、日々の暮らしの中で心を磨き、人格を高めつづけること。すなわち、そのような当たり前のことを一生懸命行っていくことに、まさに生きる意義があるし、それ以外に、人間としての「生き方」はないように思います。
抜粋です
・ 幸福人生の方程式
人生をよりよく生き、幸福という果実を得るには、どうすればよいか。そのことを私は一つの方程式で表現しています。
人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力
最初の「考え方」。三つの要素のなかではもっとも大事なもので、この考え方次第で人生は決まってしまうといっても過言ではありません。この考え方が大事なのは、これにはマイナスポイントがあるからです。
・明るい未来の姿を描く
私たちはいくつになっても夢を語り、明るい未来の姿を描ける人間でありたいものです。
夢が大きければ大きいほど、その実現までの距離は遠いものになる。しかし、それでもそれが成就したときの姿や、そこへ至るプロセスを幾度もシミュレーションし、眼前に「見える」までに濃密にイメージしていると、実現への道筋がしだいに明らかに見えてくるとともに、そこへ一歩でも近づくためのさまざまなヒントが、何げない日常生活からも得られるようになっていくものです。
・わずかでも前進する
昨日の努力に少しの工夫と改良を上乗せして、今日は昨日よりもわずかながらでも前進する。
その、よりよくしようという姿勢を怠らないことが、のちに大きな差となって表れてくる。
けっして通い慣れた同じ道は通らないということが、成功に近づく秘訣なのです。
・ 今日一日を充実させる
いたずらに明日を煩ったり、将来の見通しを立てることに汲々とするよりも、まずは今日一日を充実させることに力を注いだほうがいい。それが結局、夢を現実のものとする最善の道なのです。
因果が応報するには時間がかかる。このことを心して、結果をあせらず、日ごろから倦まず弛まず、地道に善行を積み重ねるよう努力することが大切なのです。
・「好き」と「打ち込む」の好循環
「好き」と「打ち込む」はコインの表と裏のようなもので、その因果関係は循環しています。好きだから仕事に打ち込めるし、打ち込むうちに好きになってくるものです。
どんな仕事であっても、それに全力で打ち込んでやり遂げれば、大きな達成感と自信が生まれ、また次の目標へ挑戦する意欲が生まれてきます。そのくり返しの中で、さらに仕事が好きになります。そうなれば、どんな努力も苦にならなくなり、すばらしい成果を上げることができるのです。
つまり、「好き」こそが最大のモチベーションであり、意欲も努力も、ひいては成功への道筋も、みんな「好き」であることがその母体になるということです。
・ 生きる意味は魂を磨いていくこと
この世のことはこの世限りでいったん清算しなくてはならない。
そのなかでたった一つ滅びないものがあるとすれば、それは、「魂」というものではないでしょうか。死を迎えるときには、現世でつくり上げた地位も名誉も財産もすべて脱ぎ捨て、魂だけ携えて新しい旅立ちをしなくてはならないのです。
ですから、「この世へ何しにきたのか」と問われたら、私は迷いもてらいもなく、生まれたときより少しでもましな人間になる、すなわちわずかなりとも美しく崇高な魂をもって死んでいくためだと答えます。
京セラ会長・稲盛和夫その1
以前、ドツボのとき通勤で秋葉原から乗り換えた山手線の車内広告で「生き方」という文字が目に入り、本屋に直行してこの本を購入しました。
いまだに本屋さんで売れてます
京セラ会長・稲盛和夫、氏は得度(出家)してます。
『生き方−人間として一番大切なこと』(稲盛和夫)より
一生懸命に働くこと、感謝の心を忘れないこと、善き思い、正しい行いに努めること、素直な反省真でいつも自分を律すること、日々の暮らしの中で心を磨き、人格を高めつづけること。すなわち、そのような当たり前のことを一生懸命行っていくことに、まさに生きる意義があるし、それ以外に、人間としての「生き方」はないように思います。
抜粋です
・ 幸福人生の方程式
人生をよりよく生き、幸福という果実を得るには、どうすればよいか。そのことを私は一つの方程式で表現しています。
人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力
最初の「考え方」。三つの要素のなかではもっとも大事なもので、この考え方次第で人生は決まってしまうといっても過言ではありません。この考え方が大事なのは、これにはマイナスポイントがあるからです。
・明るい未来の姿を描く
私たちはいくつになっても夢を語り、明るい未来の姿を描ける人間でありたいものです。
夢が大きければ大きいほど、その実現までの距離は遠いものになる。しかし、それでもそれが成就したときの姿や、そこへ至るプロセスを幾度もシミュレーションし、眼前に「見える」までに濃密にイメージしていると、実現への道筋がしだいに明らかに見えてくるとともに、そこへ一歩でも近づくためのさまざまなヒントが、何げない日常生活からも得られるようになっていくものです。
・わずかでも前進する
昨日の努力に少しの工夫と改良を上乗せして、今日は昨日よりもわずかながらでも前進する。
その、よりよくしようという姿勢を怠らないことが、のちに大きな差となって表れてくる。
けっして通い慣れた同じ道は通らないということが、成功に近づく秘訣なのです。
・ 今日一日を充実させる
いたずらに明日を煩ったり、将来の見通しを立てることに汲々とするよりも、まずは今日一日を充実させることに力を注いだほうがいい。それが結局、夢を現実のものとする最善の道なのです。
因果が応報するには時間がかかる。このことを心して、結果をあせらず、日ごろから倦まず弛まず、地道に善行を積み重ねるよう努力することが大切なのです。
・「好き」と「打ち込む」の好循環
「好き」と「打ち込む」はコインの表と裏のようなもので、その因果関係は循環しています。好きだから仕事に打ち込めるし、打ち込むうちに好きになってくるものです。
どんな仕事であっても、それに全力で打ち込んでやり遂げれば、大きな達成感と自信が生まれ、また次の目標へ挑戦する意欲が生まれてきます。そのくり返しの中で、さらに仕事が好きになります。そうなれば、どんな努力も苦にならなくなり、すばらしい成果を上げることができるのです。
つまり、「好き」こそが最大のモチベーションであり、意欲も努力も、ひいては成功への道筋も、みんな「好き」であることがその母体になるということです。
・ 生きる意味は魂を磨いていくこと
この世のことはこの世限りでいったん清算しなくてはならない。
そのなかでたった一つ滅びないものがあるとすれば、それは、「魂」というものではないでしょうか。死を迎えるときには、現世でつくり上げた地位も名誉も財産もすべて脱ぎ捨て、魂だけ携えて新しい旅立ちをしなくてはならないのです。
ですから、「この世へ何しにきたのか」と問われたら、私は迷いもてらいもなく、生まれたときより少しでもましな人間になる、すなわちわずかなりとも美しく崇高な魂をもって死んでいくためだと答えます。
「人生の意味とは」その1 あいさんの日記より〜
少し長いですが、ご紹介いたします。
ひろさちやさんのお話です。
「人生の意味とは
ひろさちやのサラリーマン生き方塾
困難こそがいい」
今の世の中は、なかなか困難な時代だといいます。バブルが崩壊し構造的な不景気が続いて、多くの人が、いつリストラに遭うのだろうか、再就職ができるのだろうか、老後はどうなるのだろうか、と不安をかかえて生きています。
しかし、よく考えてみれば、今という時代が、とり立てて困難な時代でもないのです。そして、自分だけが困難な人生でもないのです。
困難というものは、なくなることはありません。
いったい困難のない人生なんて、どこに意味があるのでしょうか。そもそも困難のない人生を生きようというところに、問題があるのです。困難こそがいいのです。
苦しみというものは、自分自身で苦しみにしているのです。
仏教でいう「苦」の本来の意味は、「思うがままにならない」ということです。
わたしたちは、
---思うがままにならない事を思うままにしようとしたときに、苦しむ---
のです。
ですから、思うままにならないことは、思うままにならないことだと諦(あきら)めればいい。明らかにすればいいのです。するとそれは、苦にならないのです。
「苦しみ」がなくなることはありませんが、
---苦しみでなくなる---
のです。それがお釈迦さまの説いた教えでした。
人は「生まれ、苦しみ、死ぬ」
サマセット・モームの『人間の絆』という本にこんな話があります。
東方のある王さまが、人間の歴史を知ろうとして、学者に命じて本を集めさせますと、それは五百巻になりました。ところが王さまは国事に忙しくて、とても五百巻も本を読むわけにはいきません。もっと要約するように命じます。
そこで学者は二十年かけて五百巻の本を五十巻に要約して、王のもとに持参しました。しかし、王さまはすでに年をとってしまいました。とても五十巻も読めません。再び学者に要約するように命じました。
学者はまた二十年かけて、わずか一巻に要約して持参しました。ところが、王はすでに、横たわってまさに死に就こうとしていました。
結局学者は、人間の歴史をわずか一行にして、死に逝かんとする王の耳元でささやきました。
「人は、生まれ、苦しみ、そして死ぬ。それが、人間の歴史でございます」
どんな時代でも、どんなにお金があってもなくても、地位が違っても、人間の本質というものは同じです。
それは、「人は、生まれ、苦しみ、そして死ぬ」ということなのです。
乱暴な言い方ですが、そもそも「人生には生きがいがある」と思っていることが、大間違いかもしれません。人生はつきつめてみれば、「生まれ、苦しみ、そして死ぬ」ということだけでしょう。
わたしたちは、人生に何か大きな意味があると思っています。飢え死にするような人生より、美味いものを食べる人生の方が意味があると思っています。
わたしたちは、一所懸命に働いて、ぜいたくするとか、大きな仕事をするとか、出世するとか、それが値打ちのある人生だと思っています。
少し長いですが、ご紹介いたします。
ひろさちやさんのお話です。
「人生の意味とは
ひろさちやのサラリーマン生き方塾
困難こそがいい」
今の世の中は、なかなか困難な時代だといいます。バブルが崩壊し構造的な不景気が続いて、多くの人が、いつリストラに遭うのだろうか、再就職ができるのだろうか、老後はどうなるのだろうか、と不安をかかえて生きています。
しかし、よく考えてみれば、今という時代が、とり立てて困難な時代でもないのです。そして、自分だけが困難な人生でもないのです。
困難というものは、なくなることはありません。
いったい困難のない人生なんて、どこに意味があるのでしょうか。そもそも困難のない人生を生きようというところに、問題があるのです。困難こそがいいのです。
苦しみというものは、自分自身で苦しみにしているのです。
仏教でいう「苦」の本来の意味は、「思うがままにならない」ということです。
わたしたちは、
---思うがままにならない事を思うままにしようとしたときに、苦しむ---
のです。
ですから、思うままにならないことは、思うままにならないことだと諦(あきら)めればいい。明らかにすればいいのです。するとそれは、苦にならないのです。
「苦しみ」がなくなることはありませんが、
---苦しみでなくなる---
のです。それがお釈迦さまの説いた教えでした。
人は「生まれ、苦しみ、死ぬ」
サマセット・モームの『人間の絆』という本にこんな話があります。
東方のある王さまが、人間の歴史を知ろうとして、学者に命じて本を集めさせますと、それは五百巻になりました。ところが王さまは国事に忙しくて、とても五百巻も本を読むわけにはいきません。もっと要約するように命じます。
そこで学者は二十年かけて五百巻の本を五十巻に要約して、王のもとに持参しました。しかし、王さまはすでに年をとってしまいました。とても五十巻も読めません。再び学者に要約するように命じました。
学者はまた二十年かけて、わずか一巻に要約して持参しました。ところが、王はすでに、横たわってまさに死に就こうとしていました。
結局学者は、人間の歴史をわずか一行にして、死に逝かんとする王の耳元でささやきました。
「人は、生まれ、苦しみ、そして死ぬ。それが、人間の歴史でございます」
どんな時代でも、どんなにお金があってもなくても、地位が違っても、人間の本質というものは同じです。
それは、「人は、生まれ、苦しみ、そして死ぬ」ということなのです。
乱暴な言い方ですが、そもそも「人生には生きがいがある」と思っていることが、大間違いかもしれません。人生はつきつめてみれば、「生まれ、苦しみ、そして死ぬ」ということだけでしょう。
わたしたちは、人生に何か大きな意味があると思っています。飢え死にするような人生より、美味いものを食べる人生の方が意味があると思っています。
わたしたちは、一所懸命に働いて、ぜいたくするとか、大きな仕事をするとか、出世するとか、それが値打ちのある人生だと思っています。
「人生の意味とは」その2 あいさんの日記より〜
しかし、仕事にどれほどの価値があるのでしょうか。
この社会では、「世の中の役に立つ」ことが、大きな価値のようになっています。
この資本主義社会では、大量生産・大量消費で資源の無駄遣いをしています。期限が切れたコンビニのお弁当は、みんな捨ててしまうように、せっかくの資源をムダに捨ててしまう社会です。資源・エネルギーの無駄遣いをして、環境汚染を進めて地球を痛めつけています。役に立つというのは、そういうことを活発にやっていることにもなります。
人生に値打ちがあるのか
インドを旅しますと、路上生活者がいっぱいいます。彼らは路上で生まれて、路上で育ち、物乞いをして、路上で死んでいくのです。
そういう人々を見ると「こういう人たちにとって、生きている値打ちがあるだろうか」と、つい思ってしまうのが、誰もが持つ正直な感想でしょう。
けれども、そう思った途端に、はっと気がつきます。では、自分の人生と、この人たちの人生とでは、いったいどれだけ値打ちに差があるというのでしょうか?
インドの路上生活者の人生に値打ちがないとしたら、私たちの人生だって、値打ちなどないのです。
生まれてすぐに死んでしまう子どももいる。すると、何のために生まれてきたんだろう、生きる値打ちがあったのだろうかと思います。では、百歳まで生きた方が人間の値打ちがあるのでしょうか?
わたしたちは元気に仕事をして、長生きをして安楽な生活をすることに、価値があると思っています。そして、知らず知らず、他人と比べてわたしのほうが値打ちがあるのだと思っています。そういう考え方そのものが、慢心だと思うのです。
ほとけさまは、「すべての衆生は、わたしの子どもだ」と言っておられます。『法華経』には「この三界はわたしのものなんだよ。その三界の一切の衆生はことごとくわたしの子である」(譬喩品(ひゆほん))と説かれています。
ほとけさまからみれば、すべての衆生が等しくわが子です。路上生活者であろうが、生まれてすぐに死んでしまう子であろうが、ほとけさまからみたら、どんな人も等しい価値を持っているのです。
徹底して自由人であれ
わたしたちは、生きている間にしか、人生に値打ちがないと思っています。これはまさに、宗教を持たないから、そういう考え方になるわけです。
「死んで花見が咲くものか」とか、「二度とない人生だから」とか「生きてる間が花よ」とか言いますが、生きてる間にしか価値をおいてないのが現代人です。
死んでしまえば価値がなくなるというわけです。死ねばスクラップ同然で無価値というわけです。自動車は走れる間だけしか、値打ちがありません。動かなくなれば、まったく価値がありません。それと同じです。
生きている間にしか、人生に値打ちがないという思想は、かけがえのない人生を、「商品価値」としてとらえることです。
商品価値とは、別の言い方をすれば「機能価値」です。人間は「働く」機能で評価されます。働けなくなったら、価値が下がります。年齢が高くなるほど次第にゴミに近づいていって、定年退職したら粗大ゴミになるというわけです。
わたしたちは、人生を、そういう価値観でとらえているのではないでしょうか。
この人生を、商品価値でとらえていると、自分を商品として高く買ってもらうことが、幸せな生き方と思ってしまいます。さらには、自分自身を商品として、会社に売り渡すことにもなるのです。
自分という人格そのものを、会社に売り渡してしまうと、自分の人生はまったく会社に従属してしまいます。そうなると、会社がどんなに悪いことをしても、逆らうことはできなくなります。
会社に見捨てられることを恐れ、リストラされたらどうしよう。妻子がいる、子どもの教育もある、家のローンもあると、先の不安をかかえています。仕方がないから、会社に従属し続けることになります。
それでは、まるで「会社の奴隷」です。
自分を商品として売り渡してしまったら、幸せな生き方はできなくなります。ほんとうの自分を大事にするのであれば、自分自身を商品として売り渡してはいけないのです。
会社を離れて、万が一、食べていけなくなれば、そのときはそのときだと、腹をくくればいいのです。腹をくくったときから、道が開けてくるのです。
しかし、仕事にどれほどの価値があるのでしょうか。
この社会では、「世の中の役に立つ」ことが、大きな価値のようになっています。
この資本主義社会では、大量生産・大量消費で資源の無駄遣いをしています。期限が切れたコンビニのお弁当は、みんな捨ててしまうように、せっかくの資源をムダに捨ててしまう社会です。資源・エネルギーの無駄遣いをして、環境汚染を進めて地球を痛めつけています。役に立つというのは、そういうことを活発にやっていることにもなります。
人生に値打ちがあるのか
インドを旅しますと、路上生活者がいっぱいいます。彼らは路上で生まれて、路上で育ち、物乞いをして、路上で死んでいくのです。
そういう人々を見ると「こういう人たちにとって、生きている値打ちがあるだろうか」と、つい思ってしまうのが、誰もが持つ正直な感想でしょう。
けれども、そう思った途端に、はっと気がつきます。では、自分の人生と、この人たちの人生とでは、いったいどれだけ値打ちに差があるというのでしょうか?
インドの路上生活者の人生に値打ちがないとしたら、私たちの人生だって、値打ちなどないのです。
生まれてすぐに死んでしまう子どももいる。すると、何のために生まれてきたんだろう、生きる値打ちがあったのだろうかと思います。では、百歳まで生きた方が人間の値打ちがあるのでしょうか?
わたしたちは元気に仕事をして、長生きをして安楽な生活をすることに、価値があると思っています。そして、知らず知らず、他人と比べてわたしのほうが値打ちがあるのだと思っています。そういう考え方そのものが、慢心だと思うのです。
ほとけさまは、「すべての衆生は、わたしの子どもだ」と言っておられます。『法華経』には「この三界はわたしのものなんだよ。その三界の一切の衆生はことごとくわたしの子である」(譬喩品(ひゆほん))と説かれています。
ほとけさまからみれば、すべての衆生が等しくわが子です。路上生活者であろうが、生まれてすぐに死んでしまう子であろうが、ほとけさまからみたら、どんな人も等しい価値を持っているのです。
徹底して自由人であれ
わたしたちは、生きている間にしか、人生に値打ちがないと思っています。これはまさに、宗教を持たないから、そういう考え方になるわけです。
「死んで花見が咲くものか」とか、「二度とない人生だから」とか「生きてる間が花よ」とか言いますが、生きてる間にしか価値をおいてないのが現代人です。
死んでしまえば価値がなくなるというわけです。死ねばスクラップ同然で無価値というわけです。自動車は走れる間だけしか、値打ちがありません。動かなくなれば、まったく価値がありません。それと同じです。
生きている間にしか、人生に値打ちがないという思想は、かけがえのない人生を、「商品価値」としてとらえることです。
商品価値とは、別の言い方をすれば「機能価値」です。人間は「働く」機能で評価されます。働けなくなったら、価値が下がります。年齢が高くなるほど次第にゴミに近づいていって、定年退職したら粗大ゴミになるというわけです。
わたしたちは、人生を、そういう価値観でとらえているのではないでしょうか。
この人生を、商品価値でとらえていると、自分を商品として高く買ってもらうことが、幸せな生き方と思ってしまいます。さらには、自分自身を商品として、会社に売り渡すことにもなるのです。
自分という人格そのものを、会社に売り渡してしまうと、自分の人生はまったく会社に従属してしまいます。そうなると、会社がどんなに悪いことをしても、逆らうことはできなくなります。
会社に見捨てられることを恐れ、リストラされたらどうしよう。妻子がいる、子どもの教育もある、家のローンもあると、先の不安をかかえています。仕方がないから、会社に従属し続けることになります。
それでは、まるで「会社の奴隷」です。
自分を商品として売り渡してしまったら、幸せな生き方はできなくなります。ほんとうの自分を大事にするのであれば、自分自身を商品として売り渡してはいけないのです。
会社を離れて、万が一、食べていけなくなれば、そのときはそのときだと、腹をくくればいいのです。腹をくくったときから、道が開けてくるのです。
「人生の意味とは」その3 あいさんの日記より〜
ほとけさまの教えは、
---奴隷になるな。自由人であれ---
ということです。お釈迦さまが、わたしたちに教えられたことは、徹底して「奴隷になるな」ということでした。
自分らしく生きるとは
だから、会社から離れて自分という存在をうち立てることです。「わたしはわたしなんだ。会社はわたしの労働する時間に対して給料を払っているだけで、会社とわたしとは違うんだ」という意識にならなくてはいけません。
自分らしく生きるとは、自分の権限内にあることを努力すればいいのです。
自分の権限の外にあるものは、努力したって仕方ないのです。
音楽家がうまく歌おうというのは、それは自分の権限の中で努力できることです。しかし、聴衆の拍手喝采を浴びようとするのは、自分の思うままにならないことなのです。カメラマンがいい写真を撮ろうというのは、自分で努力できるけれど、入賞しようというのは、これは思うままにならないことです。
わたしはよく講演するのですが、自分がよかったなと思える講演をしようとは思います。でも、聴衆が喜んでくれるようにとは思いません。それは聴衆の勝手だからです。
サラリーマンだったら、上司に気に入られるかどうかではなく、自分でやれる仕事だけをやればいいのです。デパートの販売員は、お客さんによく説明すればいい、それは自分の努力でできることなのです。しかし客がそれを買ってくれるかどうかは客の勝手です。
だから、自分なりに一所懸命に仕事をして、もしもクビになるときは、クビになったでいいのです。そうタカをくくって仕事をすればいい。クビになったら困ると不安に思っているほうが、苦痛なのです。
歯医者に行く前は、歯を削られる恐ろしさを思うと行きたくない。でも、行ってしまえば、なんだこんなものかと思うのです。
ある人が資金繰りができなくて、手形の不渡りを出しました。それまで会社倒産の危機で何とか不渡りを出さないようにと金策に駆けずり回って、血尿まで出て死ぬ思いだった。しかし、会社が倒産してしまったら、「なーんだ、こんなもんか・・・」と逆に明るくなったという体験を聞いたことがあります。
人生は無限の中のヒトコマ
インドで、食うや食わずの路上生活者の人々を見るとそんな生活をするくらいなら、泥棒して捕まって刑務所に入ったら、さぞかし楽な生活ができるのにと思ったこともあります。でも、彼らはそうしないのです。
生活に困っても、悪いことをしないのは、インド人にとって、この世は輪廻転生のわずかヒトコマだからなのです。
インドの人たちは、この人生を一回限りではなく、無限に輪廻すると思っています。
だから、今の世で泥棒をやったら、次の世は地獄に堕ちると考えています。地獄に堕ちればとてつもない長い間、苦しむことになります。わずかな安楽のために、一兆六千二百億年という長い苦しみを受ける。それでは割に合いません。だから、彼らは悪いことをしないで、慎ましやかに生きているわけです。
「輪廻転生」とは、死んで生まれることを、無限に繰り返すわけです。
無限の人生があるのですから、無限の可能性があるわけです。ところが、「この人生だけがすべて」という考えに立つと、人生を商品価値として見るような生き方になってしまうのです。
徹底した自由人であるためには、人生は一回限りではなく、無限に輪廻があるのだということを知らねばなりません。
倶会一処(くえいっしょ)
ほとけさまの教えは、
---奴隷になるな。自由人であれ---
ということです。お釈迦さまが、わたしたちに教えられたことは、徹底して「奴隷になるな」ということでした。
自分らしく生きるとは
だから、会社から離れて自分という存在をうち立てることです。「わたしはわたしなんだ。会社はわたしの労働する時間に対して給料を払っているだけで、会社とわたしとは違うんだ」という意識にならなくてはいけません。
自分らしく生きるとは、自分の権限内にあることを努力すればいいのです。
自分の権限の外にあるものは、努力したって仕方ないのです。
音楽家がうまく歌おうというのは、それは自分の権限の中で努力できることです。しかし、聴衆の拍手喝采を浴びようとするのは、自分の思うままにならないことなのです。カメラマンがいい写真を撮ろうというのは、自分で努力できるけれど、入賞しようというのは、これは思うままにならないことです。
わたしはよく講演するのですが、自分がよかったなと思える講演をしようとは思います。でも、聴衆が喜んでくれるようにとは思いません。それは聴衆の勝手だからです。
サラリーマンだったら、上司に気に入られるかどうかではなく、自分でやれる仕事だけをやればいいのです。デパートの販売員は、お客さんによく説明すればいい、それは自分の努力でできることなのです。しかし客がそれを買ってくれるかどうかは客の勝手です。
だから、自分なりに一所懸命に仕事をして、もしもクビになるときは、クビになったでいいのです。そうタカをくくって仕事をすればいい。クビになったら困ると不安に思っているほうが、苦痛なのです。
歯医者に行く前は、歯を削られる恐ろしさを思うと行きたくない。でも、行ってしまえば、なんだこんなものかと思うのです。
ある人が資金繰りができなくて、手形の不渡りを出しました。それまで会社倒産の危機で何とか不渡りを出さないようにと金策に駆けずり回って、血尿まで出て死ぬ思いだった。しかし、会社が倒産してしまったら、「なーんだ、こんなもんか・・・」と逆に明るくなったという体験を聞いたことがあります。
人生は無限の中のヒトコマ
インドで、食うや食わずの路上生活者の人々を見るとそんな生活をするくらいなら、泥棒して捕まって刑務所に入ったら、さぞかし楽な生活ができるのにと思ったこともあります。でも、彼らはそうしないのです。
生活に困っても、悪いことをしないのは、インド人にとって、この世は輪廻転生のわずかヒトコマだからなのです。
インドの人たちは、この人生を一回限りではなく、無限に輪廻すると思っています。
だから、今の世で泥棒をやったら、次の世は地獄に堕ちると考えています。地獄に堕ちればとてつもない長い間、苦しむことになります。わずかな安楽のために、一兆六千二百億年という長い苦しみを受ける。それでは割に合いません。だから、彼らは悪いことをしないで、慎ましやかに生きているわけです。
「輪廻転生」とは、死んで生まれることを、無限に繰り返すわけです。
無限の人生があるのですから、無限の可能性があるわけです。ところが、「この人生だけがすべて」という考えに立つと、人生を商品価値として見るような生き方になってしまうのです。
徹底した自由人であるためには、人生は一回限りではなく、無限に輪廻があるのだということを知らねばなりません。
倶会一処(くえいっしょ)
「人生の意味とは」その4 あいさんの日記より〜
『阿弥陀経(あみだきょう)』に倶会一処(くえいっしょ)という言葉があります。
「倶会一処」とは「ともに一つのところで出会う」ということです。「一つのところ」とは、ほとけさまの浄土です。
ほとけさまの浄土は、宗派によってそれぞれ呼び方が違います。浄土宗や浄土真宗では「極楽浄土」、真言宗では「密厳浄土(みつごんじょうど)」、日蓮宗では「霊山浄土(りょうぜんじょうど)」と呼びます。
呼び名は違いますが、それぞれがほとけさまの浄土なのです。
この浄土という考えは、わたしたちはこの人生だけでおしまいではない、わたしたちは死ねば、ほとけさまのもとに生まれることができるということです。
ある女性に聞かれました。
「お浄土が倶会一処というのは、ほんとうですか?」
「ほんとうですよ」
「それじゃあ、わたしはお浄土なんか行きたくありません」
わたしは、その方がどうしてそんなことを言うのか、ピンときました。
「いじめられたお姑さんに、またお浄土で会わなくてはいけないのだったら、わたしは地獄に行きたい」
彼女はそう言うのです。それで、わたしは言いました。
「では、あなたは地獄に行けばいい。地獄では、お姑さんには会わないけれど、同時に旦那にも会えないよ。自分の子どもにも会うこともできない。親しいお友達にも会うことができないよ」
「どうしてですか?」
「あんな人には会いたくないと憎む心が、まさに地獄の心です。だから、あなたの堕ちる地獄は、孤独地獄なのです。誰もいないところで、一兆六千二百億年じっといるんだよ」
そう言ったら、彼女は真っ青になりました。
この娑婆世界では、いろいろな縁で、ともすれば憎しみあう関係になることもあります。二度と会いたくない、という人もいることでしょう。
しかし、それは互いに、ただ縁があって対立したのです。縁によって対立しているということに気がつかないで、人を恨んだり憎み続けるとしたら、その心がまさに地獄なのです。
けれども、浄土とはそうした縁を超越した世界です。死んでお浄土へ往けば、対立した者同士が再会して、「あのときはつらかったね」と許しあえる仲になるのです。
互いに許し合える心が、お浄土と言うことができます。許し合えるのは、縁というものがよくよくわかっているからなのです。
美しい思い出とは
人生とはこの一回限りだけではないのです。無限の人生の繰り返しがあります。また別の言い方をすれば、お浄土があるのです。
そうすると、人生の意味は世の中に役に立つとか、楽しいことをやるとか、そういうことではないということになります。
わたしたちがお浄土に往って、もっていけるものがあるとしたら、それはなんでしょうか。それは形あるものではありません。財産やお金、地位だとか名誉だとか、そんなものは持っていけません。
『阿弥陀経(あみだきょう)』に倶会一処(くえいっしょ)という言葉があります。
「倶会一処」とは「ともに一つのところで出会う」ということです。「一つのところ」とは、ほとけさまの浄土です。
ほとけさまの浄土は、宗派によってそれぞれ呼び方が違います。浄土宗や浄土真宗では「極楽浄土」、真言宗では「密厳浄土(みつごんじょうど)」、日蓮宗では「霊山浄土(りょうぜんじょうど)」と呼びます。
呼び名は違いますが、それぞれがほとけさまの浄土なのです。
この浄土という考えは、わたしたちはこの人生だけでおしまいではない、わたしたちは死ねば、ほとけさまのもとに生まれることができるということです。
ある女性に聞かれました。
「お浄土が倶会一処というのは、ほんとうですか?」
「ほんとうですよ」
「それじゃあ、わたしはお浄土なんか行きたくありません」
わたしは、その方がどうしてそんなことを言うのか、ピンときました。
「いじめられたお姑さんに、またお浄土で会わなくてはいけないのだったら、わたしは地獄に行きたい」
彼女はそう言うのです。それで、わたしは言いました。
「では、あなたは地獄に行けばいい。地獄では、お姑さんには会わないけれど、同時に旦那にも会えないよ。自分の子どもにも会うこともできない。親しいお友達にも会うことができないよ」
「どうしてですか?」
「あんな人には会いたくないと憎む心が、まさに地獄の心です。だから、あなたの堕ちる地獄は、孤独地獄なのです。誰もいないところで、一兆六千二百億年じっといるんだよ」
そう言ったら、彼女は真っ青になりました。
この娑婆世界では、いろいろな縁で、ともすれば憎しみあう関係になることもあります。二度と会いたくない、という人もいることでしょう。
しかし、それは互いに、ただ縁があって対立したのです。縁によって対立しているということに気がつかないで、人を恨んだり憎み続けるとしたら、その心がまさに地獄なのです。
けれども、浄土とはそうした縁を超越した世界です。死んでお浄土へ往けば、対立した者同士が再会して、「あのときはつらかったね」と許しあえる仲になるのです。
互いに許し合える心が、お浄土と言うことができます。許し合えるのは、縁というものがよくよくわかっているからなのです。
美しい思い出とは
人生とはこの一回限りだけではないのです。無限の人生の繰り返しがあります。また別の言い方をすれば、お浄土があるのです。
そうすると、人生の意味は世の中に役に立つとか、楽しいことをやるとか、そういうことではないということになります。
わたしたちがお浄土に往って、もっていけるものがあるとしたら、それはなんでしょうか。それは形あるものではありません。財産やお金、地位だとか名誉だとか、そんなものは持っていけません。
「人生の意味とは」その5 あいさんの日記より〜
お浄土に持っていけるものは、
---この世の中での美しい思い出---
ではないでしょうか。しかし、旅行してきて「あんなところへ行ったよ、景色がすばらしかったよ」というようなものが、美しい思い出ではありません。
苦しんで、つらくて、涙を流したことが美しい思い出になるのです。この世の中で苦しみのたうちまわって、傷つきあって生きたこと、それが美しい思い出になるのです。
イエスは、有名な「山上の垂訓」でこう言っています。
「幸福(さいわい)なるかな、心の貧しき者。天国はその人のものなり。
幸福(さいわい)なるかな、悲しむ者。その人は慰められん。」(マタイによる福音書)
幸せなのは、貧しい者、泣く者である。神の国においてあなた方は必ず慰めを受ける。そうして、不幸なのは、今、笑う者である。あなた方はすでに慰めを受けているから、というのです。
イエスのこんなパラドックス的なことばが、真実をついていると思うわけです。かといってわたしは「苦しみなさい、泣きなさい」ということを言っているのではありません。
楽しむときには、楽しめばいいのです。笑うときには、笑えばいいのです。そして、くるしまないといけないとき、苦しめばいいのです。
今こうして生きていて、なんでもいただいたものを、あるがままに受け取ればいいのです。
自分の本来の姿とは、ほとけさまの赤ん坊なのです。仏子です。
ほとけさまは、「この三界の衆生は皆、わが子なり」と言われています。蛙の子は蛙であるように、仏の子は仏なのです。
だから、わたしたちは仏なのです。無限の価値を持っているのです。
でも、まだ赤ん坊なわけです。赤ちゃんは赤ちゃんなりの楽しみを味わえばいいのです。
わたしたちは高度経済成長の時代や、バブルの時代に浮かれきっていました。そのような体験は、美しい思い出になることはありません。
この不況で停滞して、不安で苦しんでいる今こそ、美しい思い出をつくることができるときなのです。
ひろさちやさんプロファイル
1936年、大阪に生まれる。東京大学文学部インド哲学科を卒業後、同大学院博士課程を修了。気象大学校では、講師、助教授、教授として20年間教壇に立つ。宗教思想の研究、講演など、仏教を中心に宗教をわかりやすく説き、多くの人々の支持を得る。現在、大正大学客員教授。主な著書に、『仏教初歩』(すずき出版)、『ひろさちやの般若心経88講』(新潮社)、『こころの歳時記』(徳間書店)、『タテマエとホンネ』(講談社現代新書)など。
(2004年7月現在)
お浄土に持っていけるものは、
---この世の中での美しい思い出---
ではないでしょうか。しかし、旅行してきて「あんなところへ行ったよ、景色がすばらしかったよ」というようなものが、美しい思い出ではありません。
苦しんで、つらくて、涙を流したことが美しい思い出になるのです。この世の中で苦しみのたうちまわって、傷つきあって生きたこと、それが美しい思い出になるのです。
イエスは、有名な「山上の垂訓」でこう言っています。
「幸福(さいわい)なるかな、心の貧しき者。天国はその人のものなり。
幸福(さいわい)なるかな、悲しむ者。その人は慰められん。」(マタイによる福音書)
幸せなのは、貧しい者、泣く者である。神の国においてあなた方は必ず慰めを受ける。そうして、不幸なのは、今、笑う者である。あなた方はすでに慰めを受けているから、というのです。
イエスのこんなパラドックス的なことばが、真実をついていると思うわけです。かといってわたしは「苦しみなさい、泣きなさい」ということを言っているのではありません。
楽しむときには、楽しめばいいのです。笑うときには、笑えばいいのです。そして、くるしまないといけないとき、苦しめばいいのです。
今こうして生きていて、なんでもいただいたものを、あるがままに受け取ればいいのです。
自分の本来の姿とは、ほとけさまの赤ん坊なのです。仏子です。
ほとけさまは、「この三界の衆生は皆、わが子なり」と言われています。蛙の子は蛙であるように、仏の子は仏なのです。
だから、わたしたちは仏なのです。無限の価値を持っているのです。
でも、まだ赤ん坊なわけです。赤ちゃんは赤ちゃんなりの楽しみを味わえばいいのです。
わたしたちは高度経済成長の時代や、バブルの時代に浮かれきっていました。そのような体験は、美しい思い出になることはありません。
この不況で停滞して、不安で苦しんでいる今こそ、美しい思い出をつくることができるときなのです。
ひろさちやさんプロファイル
1936年、大阪に生まれる。東京大学文学部インド哲学科を卒業後、同大学院博士課程を修了。気象大学校では、講師、助教授、教授として20年間教壇に立つ。宗教思想の研究、講演など、仏教を中心に宗教をわかりやすく説き、多くの人々の支持を得る。現在、大正大学客員教授。主な著書に、『仏教初歩』(すずき出版)、『ひろさちやの般若心経88講』(新潮社)、『こころの歳時記』(徳間書店)、『タテマエとホンネ』(講談社現代新書)など。
(2004年7月現在)
〜* 逆説的な戒律…ダイア―博士の本から *〜 マザー・ホワイトさんの日記から
【逆説的な戒律】
*人はしばしば理不尽で愚かで利己的になる。
それでも相手を許しなさい。
*親切にすると、下心があると責められるかもしれない。
それでも親切にしなさい。
*成功すると、うわべだけの友人や真の敵ができる。
それでも成功しなさい。
*正直で率直な人間は、人に騙されるかもしれない。
それでも正直で率直な人間でいなさい。
*何年もかけて築いたものを、誰かが一夜にして壊すかもしれない。
それでも築きなさい。
*心が安らかで幸せだと、嫉妬されるかもしれない。
それでも幸せでいなさい。
*今日よいことをしても、明日には忘れられることがよくある。
それでもよいことをしなさい。
*自分が持っている最高のものを世界に与えても、十分ではないかもしれない。
それでも、持っている最高のものを世界に与えなさい。
【逆説的な戒律】
*人はしばしば理不尽で愚かで利己的になる。
それでも相手を許しなさい。
*親切にすると、下心があると責められるかもしれない。
それでも親切にしなさい。
*成功すると、うわべだけの友人や真の敵ができる。
それでも成功しなさい。
*正直で率直な人間は、人に騙されるかもしれない。
それでも正直で率直な人間でいなさい。
*何年もかけて築いたものを、誰かが一夜にして壊すかもしれない。
それでも築きなさい。
*心が安らかで幸せだと、嫉妬されるかもしれない。
それでも幸せでいなさい。
*今日よいことをしても、明日には忘れられることがよくある。
それでもよいことをしなさい。
*自分が持っている最高のものを世界に与えても、十分ではないかもしれない。
それでも、持っている最高のものを世界に与えなさい。
「男女のすれ違う理由」 あいさんの日記から〜
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=49889358&comm_id=753938
※真夜中に妻から起こされて
夫:なんだ、どうした?
妻:ベットを独り占めしないでくださいな。
夫:そりゃすまん。
妻:あなたときたら、いつだってそうなんですから。
夫:なんだって?
妻:いつだって割を食らうのは私のほうだって言ってるんですよ。
夫:ちょっと待った。わしは眠っていたんだよ。
お前はわしが眠っているときの行動にまで責任をもてというのか。
妻:それじゃ言わせていただいきますけど、この前だって……
とこのあと、妻は過去のことをあれこれほじくり出して責めたてた。
デボラ・タネン著「わかりあえない理由」より
*・゜゜・*:.。..。.:*・゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*
男と女では「伝えたいこと」が違うし、「伝わり方」も根本的に異なるようです。
・夫は単にメッセージレベル(ベットにおける自分の寝方)で受け取っていますが、
・妻はそれをメタメッセージ(ふたりの関係における夫のふるまい方)から見ています。
妻の夫に対する不満を調査したところ、
「子育て(または妊娠)のたいへんさを分かってくれないこと」
「話を聞いてくれない」「褒めてくれない」
などがトップを占めたそうです。
夫が「いつも家族旅行をしている」「充分なお金を稼いできてやっている」と満足していたとしても、それは すべてDoingであり、奥さんのBeingを無視し続けているのかもしれません。
“Doing”よりも 根底にあるのが“Being”です。
僕達は、どんなにたくさんのDoingがあっても、Beingが満たされない限り、本当の満足は得られないのです。
相手は Doing(行為)によって解決してほしいのではなく、自分が感じていること(=Being)を受けとめてほしいのです。
▼.男女のすれ違う理由
□男は「正しく」なりたがる(正当化) 女は「いい子」になりたがる
□ほめられたい男 愛されたい女
□男性は考えがまとまったら話し、女性は考えがまとまらないからこそ話す
□女は男が変わってくれることを望み、男は女がそのままでいること望む
□会話は男にとっては情報のやりとり、女にとっては心のやりとり
□男「問題を解決すればいいんだろ?」
女「解決してほしいんじゃない。わかってほしいだけなの」
□男⇒愛しているからこそ話をして弱みを見せたくない、迷惑をかけたくない
女⇒愛しているからこそ、何でも聞いて欲しい。何でも話して欲しい。
□女「理由を説明してほしかったのに」
男「そんなことまで説明する必要はない」
□男は、「女性が何も言わないのは不満がないからだ」と思い込みがちだが、
女は「言わなくてもわかってほしい」と思って言わないだけ
□男性はセックスしてからでないと、自分の感情や気持をありのまま表すことができない。
女性は、まず男に気持ちを整理してもらってからでないと、セックスする気になれない
□多くの男性は、弱みを見せるのは男として失格で、弱みを見せてはいけないと思い込んでいる
□男「本当に自分の支えを必要としているのであれば、彼女の方から頼んでくるべきだ」と思っている。女はコチラから言わなければ 何もしてくれようとしない男性側へ不満を持つ
♀:女にとっての良い関係「深い心の交流から生まれる一体感を持てること」と捉え、無意識に「いつもそばにいてくれない男性へのさびしさ」につながっていく。
♂:男にとっての良い関係「一緒にいても義務感なしに、一人でいられる自由な間柄」と捉え、無意識に「いつも女性に飲み込まれてしまうのではないかという恐怖感」を起こす。
□相手の癖にイライラするとしたら、大ごとにする前に「変な癖はお互いさま」と自分に言い聞かせると気が楽になる
□あなたの受け取る愛の質は、あなたが自分に置いている価値を映し出す
(※男(左脳:Meタイプ)と女(右脳:Weタイプ)という分け方をしていますが、
男が「Weタイプ」女が「Meタイプ」であれば、立場は逆になります)
相手を批判する前に、お互いが自分を省みて、気づき、歩み寄ることが、男女の調和の鍵なんですね。
『音楽は言葉を探している愛である』--シドニー・ラリエ
の言葉通り、男女の調和の旅は永遠に続く音楽なのかもしれません。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=49889358&comm_id=753938
※真夜中に妻から起こされて
夫:なんだ、どうした?
妻:ベットを独り占めしないでくださいな。
夫:そりゃすまん。
妻:あなたときたら、いつだってそうなんですから。
夫:なんだって?
妻:いつだって割を食らうのは私のほうだって言ってるんですよ。
夫:ちょっと待った。わしは眠っていたんだよ。
お前はわしが眠っているときの行動にまで責任をもてというのか。
妻:それじゃ言わせていただいきますけど、この前だって……
とこのあと、妻は過去のことをあれこれほじくり出して責めたてた。
デボラ・タネン著「わかりあえない理由」より
*・゜゜・*:.。..。.:*・゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*
男と女では「伝えたいこと」が違うし、「伝わり方」も根本的に異なるようです。
・夫は単にメッセージレベル(ベットにおける自分の寝方)で受け取っていますが、
・妻はそれをメタメッセージ(ふたりの関係における夫のふるまい方)から見ています。
妻の夫に対する不満を調査したところ、
「子育て(または妊娠)のたいへんさを分かってくれないこと」
「話を聞いてくれない」「褒めてくれない」
などがトップを占めたそうです。
夫が「いつも家族旅行をしている」「充分なお金を稼いできてやっている」と満足していたとしても、それは すべてDoingであり、奥さんのBeingを無視し続けているのかもしれません。
“Doing”よりも 根底にあるのが“Being”です。
僕達は、どんなにたくさんのDoingがあっても、Beingが満たされない限り、本当の満足は得られないのです。
相手は Doing(行為)によって解決してほしいのではなく、自分が感じていること(=Being)を受けとめてほしいのです。
▼.男女のすれ違う理由
□男は「正しく」なりたがる(正当化) 女は「いい子」になりたがる
□ほめられたい男 愛されたい女
□男性は考えがまとまったら話し、女性は考えがまとまらないからこそ話す
□女は男が変わってくれることを望み、男は女がそのままでいること望む
□会話は男にとっては情報のやりとり、女にとっては心のやりとり
□男「問題を解決すればいいんだろ?」
女「解決してほしいんじゃない。わかってほしいだけなの」
□男⇒愛しているからこそ話をして弱みを見せたくない、迷惑をかけたくない
女⇒愛しているからこそ、何でも聞いて欲しい。何でも話して欲しい。
□女「理由を説明してほしかったのに」
男「そんなことまで説明する必要はない」
□男は、「女性が何も言わないのは不満がないからだ」と思い込みがちだが、
女は「言わなくてもわかってほしい」と思って言わないだけ
□男性はセックスしてからでないと、自分の感情や気持をありのまま表すことができない。
女性は、まず男に気持ちを整理してもらってからでないと、セックスする気になれない
□多くの男性は、弱みを見せるのは男として失格で、弱みを見せてはいけないと思い込んでいる
□男「本当に自分の支えを必要としているのであれば、彼女の方から頼んでくるべきだ」と思っている。女はコチラから言わなければ 何もしてくれようとしない男性側へ不満を持つ
♀:女にとっての良い関係「深い心の交流から生まれる一体感を持てること」と捉え、無意識に「いつもそばにいてくれない男性へのさびしさ」につながっていく。
♂:男にとっての良い関係「一緒にいても義務感なしに、一人でいられる自由な間柄」と捉え、無意識に「いつも女性に飲み込まれてしまうのではないかという恐怖感」を起こす。
□相手の癖にイライラするとしたら、大ごとにする前に「変な癖はお互いさま」と自分に言い聞かせると気が楽になる
□あなたの受け取る愛の質は、あなたが自分に置いている価値を映し出す
(※男(左脳:Meタイプ)と女(右脳:Weタイプ)という分け方をしていますが、
男が「Weタイプ」女が「Meタイプ」であれば、立場は逆になります)
相手を批判する前に、お互いが自分を省みて、気づき、歩み寄ることが、男女の調和の鍵なんですね。
『音楽は言葉を探している愛である』--シドニー・ラリエ
の言葉通り、男女の調和の旅は永遠に続く音楽なのかもしれません。
「しん友(新友・真友・心友)探しの旅に出よう」 あいさんの日記より〜
☆人間関係が豊かな時間を作る
これからのあなたは、どんな人とつきあいたいとかんがえるだろうか。
人の幸せの総量と言うのは、あなたを支える心強いしん友(新友・真友・心友)と心豊かに共有する時間の総量ではないかと思う。
実際、人生で一番充実感を味わえるものは、モノやカネの豊かさよりも人間関係を通して得られるタイムリッチなのではあるまいか。
従って、人生後半はふつうのつきあいで済む人には肩の力を抜いてさらりとした対応で流していって、しん友にしたいと思えるような人に対しては、ひと味違う楽しい工夫をしてみるのがいい。
だれとでも公平につきあうことを考えて行動していると、時としてエネルギーにふり回されてしまうからだ。
さほど大切でない人間関係にスタンス(距離)を広げておくといったメリハリをつけた人付き合うの知恵が必要なのである。
☆自らの人生哲学に照らしてアンテナを
人を見る目は、物心ついてから今日まで積み上げてきた人間関係から得た判断力の集大成であって、いってみればあなたの人生哲学そのものであろう。
だから、げんじてんにおけるあなたの総力をあげて一人でも二人でもしん友を求めて、日ごろから目を光らせておくことである。
そこで、これからの人生行路にどういう人物をしん友にしたいのか、あいまいであっては、いつになってもそんな人との触れ合いは期待できない。
筆者の場合、今後もつきあうしん友となるのは、次の五つのイメージのうち二つ以上身につけている人物を受けとめて、中身の濃い人間関係を心がけている。
☆つきあいを深めたい人の人間像
�いくらつきあっても疲れない人−自然体でつきあえる人だ。余計なことまでやって相手を疲れさせることをしないケジメと心くばりがあって、つきあうことが楽しいというムードがお互いの間にある。
�いくらつきあっても退屈しない人−つきあいの中に心に残る演出、楽しい仕掛けを心がけていて飽きさせない。いつも何かに燃えていて快い刺激の相互交流が常にある。さらに、ユーモアやウィットを理解する心の持ち主であることだ。
�共存共栄をはかって伸びていく人−自分だけでなく、相手と一緒になって明日へ向かって伸びて行こうとする、そんな熱い心づかいがそこにあるのでゆさぶられてしまう。お互い主体性を持ってつき合うのがいい関係を持続させていく。
�度量が広い人−さりげなさの中に変わらぬ友情(包容力ある大きなやさしさ)が感じられる。また人の話によく耳を傾ける心の広さがある。そして、エクボ(長所)には両目をあけて、アバタ(短所)には片目をつぶるという、ゆとりある姿勢があることもいい。
�ヒューマニティのある人−人間がとても温かい。勇気、判断力、明るさ、思いやり、親しみやすさ、謙虚さといったようなプラスの人格を身につけている。心の冷たい人は、とかく自分の都合で相手を動かそうとする傾向が強く、相手の心にアレルギーを惹き起こしがちである。
上記に述べたような教養に裏づけられた豊かな情感で、人の心に爽やかな印象を残してくれる人物、こんな魅力ある個性の持ち主(しん友)を一人でも多く捜し求めるように努めている。
限りある人生においては望ましい人間像を明確にして、しん友とのつきあいを大切に育てながらともに大きく成長したい。
ちなみにここで、日ごろ遠慮したい人物像をいくつか挙げてみよう。
その場の雰囲気をわきまえずに自分の話に酔って、周囲に口害を与えていく「自己陶酔(ナルシス)型」、いつもグチやボヤキぶしで人生に対して逃げの姿勢でいる「逃避型」、何かにつけこちらの能力や人脈を利用しようとする図々しい「打算型」そして過去の世界にどっぷり浸って引きこもってしまう「郷愁型」の人物には、こちらから積極的な働きかけをせず、接触されれば応えるといった受身の対応になりがちである。
我々はこういう人欲しますが、逆に自分がこういう人間になろうと努力すれば自然としん友は集まってくるものだと思います。
☆人間関係が豊かな時間を作る
これからのあなたは、どんな人とつきあいたいとかんがえるだろうか。
人の幸せの総量と言うのは、あなたを支える心強いしん友(新友・真友・心友)と心豊かに共有する時間の総量ではないかと思う。
実際、人生で一番充実感を味わえるものは、モノやカネの豊かさよりも人間関係を通して得られるタイムリッチなのではあるまいか。
従って、人生後半はふつうのつきあいで済む人には肩の力を抜いてさらりとした対応で流していって、しん友にしたいと思えるような人に対しては、ひと味違う楽しい工夫をしてみるのがいい。
だれとでも公平につきあうことを考えて行動していると、時としてエネルギーにふり回されてしまうからだ。
さほど大切でない人間関係にスタンス(距離)を広げておくといったメリハリをつけた人付き合うの知恵が必要なのである。
☆自らの人生哲学に照らしてアンテナを
人を見る目は、物心ついてから今日まで積み上げてきた人間関係から得た判断力の集大成であって、いってみればあなたの人生哲学そのものであろう。
だから、げんじてんにおけるあなたの総力をあげて一人でも二人でもしん友を求めて、日ごろから目を光らせておくことである。
そこで、これからの人生行路にどういう人物をしん友にしたいのか、あいまいであっては、いつになってもそんな人との触れ合いは期待できない。
筆者の場合、今後もつきあうしん友となるのは、次の五つのイメージのうち二つ以上身につけている人物を受けとめて、中身の濃い人間関係を心がけている。
☆つきあいを深めたい人の人間像
�いくらつきあっても疲れない人−自然体でつきあえる人だ。余計なことまでやって相手を疲れさせることをしないケジメと心くばりがあって、つきあうことが楽しいというムードがお互いの間にある。
�いくらつきあっても退屈しない人−つきあいの中に心に残る演出、楽しい仕掛けを心がけていて飽きさせない。いつも何かに燃えていて快い刺激の相互交流が常にある。さらに、ユーモアやウィットを理解する心の持ち主であることだ。
�共存共栄をはかって伸びていく人−自分だけでなく、相手と一緒になって明日へ向かって伸びて行こうとする、そんな熱い心づかいがそこにあるのでゆさぶられてしまう。お互い主体性を持ってつき合うのがいい関係を持続させていく。
�度量が広い人−さりげなさの中に変わらぬ友情(包容力ある大きなやさしさ)が感じられる。また人の話によく耳を傾ける心の広さがある。そして、エクボ(長所)には両目をあけて、アバタ(短所)には片目をつぶるという、ゆとりある姿勢があることもいい。
�ヒューマニティのある人−人間がとても温かい。勇気、判断力、明るさ、思いやり、親しみやすさ、謙虚さといったようなプラスの人格を身につけている。心の冷たい人は、とかく自分の都合で相手を動かそうとする傾向が強く、相手の心にアレルギーを惹き起こしがちである。
上記に述べたような教養に裏づけられた豊かな情感で、人の心に爽やかな印象を残してくれる人物、こんな魅力ある個性の持ち主(しん友)を一人でも多く捜し求めるように努めている。
限りある人生においては望ましい人間像を明確にして、しん友とのつきあいを大切に育てながらともに大きく成長したい。
ちなみにここで、日ごろ遠慮したい人物像をいくつか挙げてみよう。
その場の雰囲気をわきまえずに自分の話に酔って、周囲に口害を与えていく「自己陶酔(ナルシス)型」、いつもグチやボヤキぶしで人生に対して逃げの姿勢でいる「逃避型」、何かにつけこちらの能力や人脈を利用しようとする図々しい「打算型」そして過去の世界にどっぷり浸って引きこもってしまう「郷愁型」の人物には、こちらから積極的な働きかけをせず、接触されれば応えるといった受身の対応になりがちである。
我々はこういう人欲しますが、逆に自分がこういう人間になろうと努力すれば自然としん友は集まってくるものだと思います。
伊勢白山道さんのブログより。
志(こころざし)が大切
2010-08-19 11:11:22 | Weblog
折れそうな心細い心でも、必死に生きようともがく姿は美しいです。それが自分のための事でも、自分という生命を活かそうと責任を果たしているのです。
さらには他人も活かそうと、もがき努力する姿は、最高に美しいものです。
しかし、無理な人助けは、お金や時間も掛かる事が多く、自分自身をつぶしかねません。これでは、自分への責任も果たせないのでダメです。自分が出来る範囲で実行できれば、それで良いのです。
ただ、同じ勉強中の生きる人間を助けるのは難しいですが、この世を卒業した縁ある人々を思いやる事は、誰にでも出来ます。
もし、困っている卒業生(先祖)が居れば、助けてあげたいと思える気持ちは美しいです。これは、お金も物も必要ありませんので、自分の気持ち1つで出来ることです。
既に生きていない人々への思いやりですから、何の見返りも期待できません。それでも、困っていれば可哀想だ、という気持ちだけで行うのですから、尊く美しいのです。
利己主義の有料先生は、先祖供養をバカにして神ばかりを求めます。
本当の神様は、弱い者を見捨ててスリ寄る人間を相手にすると思いますか?絶対にしません。
困る者(先祖や縁ある霊)を助けようとしている人間には、神の方から寄ります。
なぜなら、神と同じ事をしようとするからです。その波長に引き寄るのです。
人の心は絶対に死ねない永遠不滅な存在です。でも、肉体は違います。期間限定で先祖と神様から借りている物です。自動車にガソリンを入れるように、肉体にも水や食事を供給し、定期検査も必要です。
医師にしても、人間を治す自信など本当はありません。
でも、なんとか困る人を「治したい」という志(こころざし)が在るだけなんです。この志が、他人を治しています。
ただ、この現実界の次元では、志だけでは医師も自信が持てないので、無数に選択できる薬や手段を併用します。やることはした、手段は尽くしたと思えれば、その気持ちが医師にも患者にも強い癒しの効果を起こさせます。
先祖供養や神様への感謝参拝も、まったく医師の気持ちと同じです。
信仰したからと言って、良くなる自信も本当はないのです。
ただ、困る存在が居れば癒してあげたい、見えない物事にも恩を感じて感謝をしたいという志が、その人に在るだけなのです。
この志が、大いなる存在には届いているのです。
この世のすべては、大いなる存在1つから産まれたのですから、私たちが持つ志は、自然と大いなる存在へと届きます。
この志を集合させた内容が、私たちの住む世界に反射して来ます。
「気合いだ〜」ではなく、この世は「こころざしだ〜〜」なのです。
生かして頂いて ありがとう御座位ます
志(こころざし)が大切
2010-08-19 11:11:22 | Weblog
折れそうな心細い心でも、必死に生きようともがく姿は美しいです。それが自分のための事でも、自分という生命を活かそうと責任を果たしているのです。
さらには他人も活かそうと、もがき努力する姿は、最高に美しいものです。
しかし、無理な人助けは、お金や時間も掛かる事が多く、自分自身をつぶしかねません。これでは、自分への責任も果たせないのでダメです。自分が出来る範囲で実行できれば、それで良いのです。
ただ、同じ勉強中の生きる人間を助けるのは難しいですが、この世を卒業した縁ある人々を思いやる事は、誰にでも出来ます。
もし、困っている卒業生(先祖)が居れば、助けてあげたいと思える気持ちは美しいです。これは、お金も物も必要ありませんので、自分の気持ち1つで出来ることです。
既に生きていない人々への思いやりですから、何の見返りも期待できません。それでも、困っていれば可哀想だ、という気持ちだけで行うのですから、尊く美しいのです。
利己主義の有料先生は、先祖供養をバカにして神ばかりを求めます。
本当の神様は、弱い者を見捨ててスリ寄る人間を相手にすると思いますか?絶対にしません。
困る者(先祖や縁ある霊)を助けようとしている人間には、神の方から寄ります。
なぜなら、神と同じ事をしようとするからです。その波長に引き寄るのです。
人の心は絶対に死ねない永遠不滅な存在です。でも、肉体は違います。期間限定で先祖と神様から借りている物です。自動車にガソリンを入れるように、肉体にも水や食事を供給し、定期検査も必要です。
医師にしても、人間を治す自信など本当はありません。
でも、なんとか困る人を「治したい」という志(こころざし)が在るだけなんです。この志が、他人を治しています。
ただ、この現実界の次元では、志だけでは医師も自信が持てないので、無数に選択できる薬や手段を併用します。やることはした、手段は尽くしたと思えれば、その気持ちが医師にも患者にも強い癒しの効果を起こさせます。
先祖供養や神様への感謝参拝も、まったく医師の気持ちと同じです。
信仰したからと言って、良くなる自信も本当はないのです。
ただ、困る存在が居れば癒してあげたい、見えない物事にも恩を感じて感謝をしたいという志が、その人に在るだけなのです。
この志が、大いなる存在には届いているのです。
この世のすべては、大いなる存在1つから産まれたのですから、私たちが持つ志は、自然と大いなる存在へと届きます。
この志を集合させた内容が、私たちの住む世界に反射して来ます。
「気合いだ〜」ではなく、この世は「こころざしだ〜〜」なのです。
生かして頂いて ありがとう御座位ます
マザー・ホワイトさんの日記から〜
江原啓之さんの『スピリチュアル夢百科』より…
夢とは、スピリチュアルワールドへの里帰りの記憶。…それは、エネルギーを補給するため。
夢には…大きく分けて3種類…それぞれ性質はまったく異なる。
・肉の夢…眠る環境を反映して見る夢
・魂の夢(思いぐせの夢)…遅刻してはいけないと言う精神的なプレッシャー(これも思いぐせの一種)を抱えて眠ると、遅刻する夢を見たりする。
・霊の夢(スピリチュアルドリーム)…大切な種類の夢で、さまざまなメッセージが込められ、具体的な自分の人生の指針を与えられたり、夢の中で素晴らしい体験をすることもある。
さて、見ている夢がどの種類の夢なのか…霊の夢かどうかを見分けるポイントは映像の鮮明度。
この世とは格段に違います。
文字通り、この世のものとは思えない美しさです。
(私もこれを基準にしています)
たましいの里帰りの夢は、霊の夢だけです。
幽界へ里帰りするわけですが、その幽界のどのあたりに行くかは、そのときの自分自身の波長の高さによって決まります。
波長が低ければ、幽界の下層界へ行き悪夢を。
波長が非常に高いときは、中層部から上層部にかけての「サマーランド」へ行き、神々しい夢、美しい夢を見ます。霊界にいるガ―ディアンスピリット(守護霊)からのメッセージを授かることができるのも、高い層へ行けたときなのです。
江原さんは、眠るときは一生懸命眠ること…とおっしゃいますが、こう言う理由なんですね♪(私も夢を見ることを楽しみに寝ています)
以上引用より。
暗い夢が続いていたのと、当分…本当に当分見ていなかった怖い夢を、今月に入り見ていたので…今朝の夢は久々のスピリチュアルドリームとメッセージでルンルンです♪
怖い夢は、潜在意識の底の底から浮上して来たな〜と自分自身の怖れを感じたのと、もう、その怖れもこうして姿を顕したと言うことは、出ていくときかな…とも勝手に解釈。
ある意味、その怖い夢は…良い出来事の前兆かも(*^^*)と、超ポジティブシンキングの私です♪あはは♪
さて、今朝の夢は、とても綺麗な流れの川に沿って山道を歩いているものでした。
明るい鮮明な夢で、木々の葉っぱ一枚一枚のきらめき、そして、透明度抜群の水の美しさ…
そして、目覚める前に、
聞こえて来たメッセージが、
歌うような声で…
『赦しに苦しみはあろうか〜』と、
弥勒菩薩さま?のお姿と共に頂きました。
それと…
『自分をつくり直してみませんか〜』
聞こえた言葉に、目覚めた時…はあ?と思えたりするんですが…^_^;
しばらく後で納得したり…
そうそう、私のHNの『マザー・ホワイト』も夢で聞こえた名前です。
マザーですか?と思わず声をあげたのを覚えています^_^;
夢って…不思議で楽しくて…自分のそのときの波長も判断できて…
同じ夢を見るなら…霊の夢を見たいですよね〜。
そこで、またまた引用。
「肉の夢」を見ないためには、寝室の環境を整えたり…就寝前に体調を整えたり…
そして、聡明な「大人のたましい」を持ち「魂の夢」を見ないための指針…
(霊の夢を見るための秘訣のようにも私は思うので、シェアしますね。)
【たましいを成長に導く10ヵ条】
・うぬぼれをもたない
・物質に貪欲にならない
・色欲はほどほどに
・怒りを持たない
・大食,美食に走らない
・嫉妬をしない
・怠惰にならない
・悪口を言わない,卑下をしない
・意地悪をしない
・傲慢にならない
これらを心がけることが「大人のたましい」への道です。たましいが成長すれば心が平和になり本当の幸せが得られるのです。
江原さんの言葉に深く納得です。
当たり前のことと言えば当たり前のこの10ヵ条…知ってる知ってるでなく、実行することを続けたいと思います(^-^)v
江原啓之さんの『スピリチュアル夢百科』より…
夢とは、スピリチュアルワールドへの里帰りの記憶。…それは、エネルギーを補給するため。
夢には…大きく分けて3種類…それぞれ性質はまったく異なる。
・肉の夢…眠る環境を反映して見る夢
・魂の夢(思いぐせの夢)…遅刻してはいけないと言う精神的なプレッシャー(これも思いぐせの一種)を抱えて眠ると、遅刻する夢を見たりする。
・霊の夢(スピリチュアルドリーム)…大切な種類の夢で、さまざまなメッセージが込められ、具体的な自分の人生の指針を与えられたり、夢の中で素晴らしい体験をすることもある。
さて、見ている夢がどの種類の夢なのか…霊の夢かどうかを見分けるポイントは映像の鮮明度。
この世とは格段に違います。
文字通り、この世のものとは思えない美しさです。
(私もこれを基準にしています)
たましいの里帰りの夢は、霊の夢だけです。
幽界へ里帰りするわけですが、その幽界のどのあたりに行くかは、そのときの自分自身の波長の高さによって決まります。
波長が低ければ、幽界の下層界へ行き悪夢を。
波長が非常に高いときは、中層部から上層部にかけての「サマーランド」へ行き、神々しい夢、美しい夢を見ます。霊界にいるガ―ディアンスピリット(守護霊)からのメッセージを授かることができるのも、高い層へ行けたときなのです。
江原さんは、眠るときは一生懸命眠ること…とおっしゃいますが、こう言う理由なんですね♪(私も夢を見ることを楽しみに寝ています)
以上引用より。
暗い夢が続いていたのと、当分…本当に当分見ていなかった怖い夢を、今月に入り見ていたので…今朝の夢は久々のスピリチュアルドリームとメッセージでルンルンです♪
怖い夢は、潜在意識の底の底から浮上して来たな〜と自分自身の怖れを感じたのと、もう、その怖れもこうして姿を顕したと言うことは、出ていくときかな…とも勝手に解釈。
ある意味、その怖い夢は…良い出来事の前兆かも(*^^*)と、超ポジティブシンキングの私です♪あはは♪
さて、今朝の夢は、とても綺麗な流れの川に沿って山道を歩いているものでした。
明るい鮮明な夢で、木々の葉っぱ一枚一枚のきらめき、そして、透明度抜群の水の美しさ…
そして、目覚める前に、
聞こえて来たメッセージが、
歌うような声で…
『赦しに苦しみはあろうか〜』と、
弥勒菩薩さま?のお姿と共に頂きました。
それと…
『自分をつくり直してみませんか〜』
聞こえた言葉に、目覚めた時…はあ?と思えたりするんですが…^_^;
しばらく後で納得したり…
そうそう、私のHNの『マザー・ホワイト』も夢で聞こえた名前です。
マザーですか?と思わず声をあげたのを覚えています^_^;
夢って…不思議で楽しくて…自分のそのときの波長も判断できて…
同じ夢を見るなら…霊の夢を見たいですよね〜。
そこで、またまた引用。
「肉の夢」を見ないためには、寝室の環境を整えたり…就寝前に体調を整えたり…
そして、聡明な「大人のたましい」を持ち「魂の夢」を見ないための指針…
(霊の夢を見るための秘訣のようにも私は思うので、シェアしますね。)
【たましいを成長に導く10ヵ条】
・うぬぼれをもたない
・物質に貪欲にならない
・色欲はほどほどに
・怒りを持たない
・大食,美食に走らない
・嫉妬をしない
・怠惰にならない
・悪口を言わない,卑下をしない
・意地悪をしない
・傲慢にならない
これらを心がけることが「大人のたましい」への道です。たましいが成長すれば心が平和になり本当の幸せが得られるのです。
江原さんの言葉に深く納得です。
当たり前のことと言えば当たり前のこの10ヵ条…知ってる知ってるでなく、実行することを続けたいと思います(^-^)v
伊勢ー白山 道さんのブログから〜
志(こころざし)が大切
折れそうな心細い心でも、必死に生きようともがく姿は美しいです。それが自分のための事でも、自分という生命を活かそうと責任を果たしているのです。
さらには他人も活かそうと、もがき努力する姿は、最高に美しいものです。
しかし、無理な人助けは、お金や時間も掛かる事が多く、自分自身をつぶしかねません。これでは、自分への責任も果たせないのでダメです。自分が出来る範囲で実行できれば、それで良いのです。
ただ、同じ勉強中の生きる人間を助けるのは難しいですが、この世を卒業した縁ある人々を思いやる事は、誰にでも出来ます。
もし、困っている卒業生(先祖)が居れば、助けてあげたいと思える気持ちは美しいです。これは、お金も物も必要ありませんので、自分の気持ち1つで出来ることです。
既に生きていない人々への思いやりですから、何の見返りも期待できません。それでも、困っていれば可哀想だ、という気持ちだけで行うのですから、尊く美しいのです。
利己主義の有料先生は、先祖供養をバカにして神ばかりを求めます。
本当の神様は、弱い者を見捨ててスリ寄る人間を相手にすると思いますか?絶対にしません。
困る者(先祖や縁ある霊)を助けようとしている人間には、神の方から寄ります。
なぜなら、神と同じ事をしようとするからです。その波長に引き寄るのです。
人の心は絶対に死ねない永遠不滅な存在です。でも、肉体は違います。期間限定で先祖と神様から借りている物です。自動車にガソリンを入れるように、肉体にも水や食事を供給し、定期検査も必要です。
医師にしても、人間を治す自信など本当はありません。
でも、なんとか困る人を「治したい」という志(こころざし)が在るだけなんです。この志が、他人を治しています。
ただ、この現実界の次元では、志だけでは医師も自信が持てないので、無数に選択できる薬や手段を併用します。やることはした、手段は尽くしたと思えれば、その気持ちが医師にも患者にも強い癒しの効果を起こさせます。
先祖供養や神様への感謝参拝も、まったく医師の気持ちと同じです。
信仰したからと言って、良くなる自信も本当はないのです。
ただ、困る存在が居れば癒してあげたい、見えない物事にも恩を感じて感謝をしたいという志が、その人に在るだけなのです。
この志が、大いなる存在には届いているのです。
この世のすべては、大いなる存在1つから産まれたのですから、私たちが持つ志は、自然と大いなる存在へと届きます。
この志を集合させた内容が、私たちの住む世界に反射して来ます。
「気合いだ〜」ではなく、この世は「こころざしだ〜〜」なのです。
志(こころざし)が大切
折れそうな心細い心でも、必死に生きようともがく姿は美しいです。それが自分のための事でも、自分という生命を活かそうと責任を果たしているのです。
さらには他人も活かそうと、もがき努力する姿は、最高に美しいものです。
しかし、無理な人助けは、お金や時間も掛かる事が多く、自分自身をつぶしかねません。これでは、自分への責任も果たせないのでダメです。自分が出来る範囲で実行できれば、それで良いのです。
ただ、同じ勉強中の生きる人間を助けるのは難しいですが、この世を卒業した縁ある人々を思いやる事は、誰にでも出来ます。
もし、困っている卒業生(先祖)が居れば、助けてあげたいと思える気持ちは美しいです。これは、お金も物も必要ありませんので、自分の気持ち1つで出来ることです。
既に生きていない人々への思いやりですから、何の見返りも期待できません。それでも、困っていれば可哀想だ、という気持ちだけで行うのですから、尊く美しいのです。
利己主義の有料先生は、先祖供養をバカにして神ばかりを求めます。
本当の神様は、弱い者を見捨ててスリ寄る人間を相手にすると思いますか?絶対にしません。
困る者(先祖や縁ある霊)を助けようとしている人間には、神の方から寄ります。
なぜなら、神と同じ事をしようとするからです。その波長に引き寄るのです。
人の心は絶対に死ねない永遠不滅な存在です。でも、肉体は違います。期間限定で先祖と神様から借りている物です。自動車にガソリンを入れるように、肉体にも水や食事を供給し、定期検査も必要です。
医師にしても、人間を治す自信など本当はありません。
でも、なんとか困る人を「治したい」という志(こころざし)が在るだけなんです。この志が、他人を治しています。
ただ、この現実界の次元では、志だけでは医師も自信が持てないので、無数に選択できる薬や手段を併用します。やることはした、手段は尽くしたと思えれば、その気持ちが医師にも患者にも強い癒しの効果を起こさせます。
先祖供養や神様への感謝参拝も、まったく医師の気持ちと同じです。
信仰したからと言って、良くなる自信も本当はないのです。
ただ、困る存在が居れば癒してあげたい、見えない物事にも恩を感じて感謝をしたいという志が、その人に在るだけなのです。
この志が、大いなる存在には届いているのです。
この世のすべては、大いなる存在1つから産まれたのですから、私たちが持つ志は、自然と大いなる存在へと届きます。
この志を集合させた内容が、私たちの住む世界に反射して来ます。
「気合いだ〜」ではなく、この世は「こころざしだ〜〜」なのです。
『目標達成する魔法の言葉』 おざりんさんの日記より。
「HOW?=どうすればできるか?」
なぜ、トップのリーダー達(=成功者)は、短期間で大きな目標を達成できるか?
彼らは、問題が起こるときや障害を乗り越えるときはいつも、前進するための
魔法の言葉を使ってました。
それは、「HOW?=どうすればできるか?」という言葉です。
人は、ほとんどの場合、自分が考える通りの人間になります。
トップの人々は、欲しい物について、
どうやったら手に入れることができるかを考えます。
どうやったら幸せになれるかを考えます。
彼らは、目標について、
どこへ向かっているか、どうやったら人生が豊かになるかに焦点を当てています。
彼らは、起こって欲しいことばかりを考えます。
「HOW?=どうすればできるか?」
あなたが一生前進し続ける魔法の言葉です。
さあ、声に出して言ってみましょう。
「HOW!?」
これからは、目標について考えるとき、問いかけることは、
「どうやったらできるか?」です。
何か問題を解決しなければいけないとき、問いかけることは、
「どうやったら解決できるか?」です。
乗り越えなければいけない障害があったら、問いかけることは、
「どうやったら乗り越えられるか?」 です。
トップの人々は常に、この「どうすればできるか?」について考えます。
「どうすれば?」と考えれば、
行動するためのアイディアが生まれます。やる気も沸いてきます。
成功者は常に行動中心で考えます。
彼らは、アイディアが浮かんだら、すぐに行動するのです!
そして、もう一つの発見が、このようなプラス思考は、
あなたに元気を与えるということ。あなたを強くします!
逆に、マイナス思考は、あなたを弱らせ、起こらせ、小さくします。
言い換えれば、欲しい物、欲しい結果について、常にプラス思考で考えれば、
もっと力強くなり、自信を得ることができます。
欲しくない結果や、怒らせること、不幸になることに焦点を当てて考えれば、
あなたはどんどん弱っていきます。
あなたの仕事は常に前向きになることです。
ただし、訓練が必要です。
何度も何度も、繰り返し繰り返し、実践します。
すると何が得られるでしょうか?!
そう!習慣です。
常に、起こって欲しい結果について考える習慣が身につきます。
それがトップに立つ人です。
それが、マーケットのリーダーであり、起業家、腕の良いビジネスマンなのです。
なぜなら、
欲しいものを「HOW?=どうすれば手に入れるか?」と常に継続して考えれば、
常にエネルギーが流れ込み、前へ進むアイディアがどんどん沸くからです!
<ブライアン・トレーシーさんのお話>
「HOW?=どうすればできるか?」
なぜ、トップのリーダー達(=成功者)は、短期間で大きな目標を達成できるか?
彼らは、問題が起こるときや障害を乗り越えるときはいつも、前進するための
魔法の言葉を使ってました。
それは、「HOW?=どうすればできるか?」という言葉です。
人は、ほとんどの場合、自分が考える通りの人間になります。
トップの人々は、欲しい物について、
どうやったら手に入れることができるかを考えます。
どうやったら幸せになれるかを考えます。
彼らは、目標について、
どこへ向かっているか、どうやったら人生が豊かになるかに焦点を当てています。
彼らは、起こって欲しいことばかりを考えます。
「HOW?=どうすればできるか?」
あなたが一生前進し続ける魔法の言葉です。
さあ、声に出して言ってみましょう。
「HOW!?」
これからは、目標について考えるとき、問いかけることは、
「どうやったらできるか?」です。
何か問題を解決しなければいけないとき、問いかけることは、
「どうやったら解決できるか?」です。
乗り越えなければいけない障害があったら、問いかけることは、
「どうやったら乗り越えられるか?」 です。
トップの人々は常に、この「どうすればできるか?」について考えます。
「どうすれば?」と考えれば、
行動するためのアイディアが生まれます。やる気も沸いてきます。
成功者は常に行動中心で考えます。
彼らは、アイディアが浮かんだら、すぐに行動するのです!
そして、もう一つの発見が、このようなプラス思考は、
あなたに元気を与えるということ。あなたを強くします!
逆に、マイナス思考は、あなたを弱らせ、起こらせ、小さくします。
言い換えれば、欲しい物、欲しい結果について、常にプラス思考で考えれば、
もっと力強くなり、自信を得ることができます。
欲しくない結果や、怒らせること、不幸になることに焦点を当てて考えれば、
あなたはどんどん弱っていきます。
あなたの仕事は常に前向きになることです。
ただし、訓練が必要です。
何度も何度も、繰り返し繰り返し、実践します。
すると何が得られるでしょうか?!
そう!習慣です。
常に、起こって欲しい結果について考える習慣が身につきます。
それがトップに立つ人です。
それが、マーケットのリーダーであり、起業家、腕の良いビジネスマンなのです。
なぜなら、
欲しいものを「HOW?=どうすれば手に入れるか?」と常に継続して考えれば、
常にエネルギーが流れ込み、前へ進むアイディアがどんどん沸くからです!
<ブライアン・トレーシーさんのお話>
『今日の水じゃよ』 おざりんさんの日記より。
目で 耳で 舌で
すべての感覚を開いて
世界を見てごらん
それが
瞬間 瞬間 一日 一日を
味わって生きることだよ
いつも大変お世話になっている日本メンタルヘルス協会の衛藤先生のお話です。
私が子供時代、近所に禅坊主がいました。
ある日、私が水道からコップに水を入れて飲んでいると、
和尚さんが帰って来て、
「きみが飲んでいるのはなんだね?」と声をかけられました。
私が「水だよ」と答えると、
「そうかなぁ。それはただの水じゃないぞ」と言います。
私は、自分で蛇口からコップに水を入れたのだから、
「水だよ」と自信を持って答えました。
すると、「いや、それはただの水じゃない。飲んでごらんよ」
と、和尚さんはニヤリと笑います。
私はもう一度口にコップの水を含みましたが、やっぱりただの水です。
「これ水だよ。ぼく自分で入れたんだもん」と言うと、
「いや、そうじゃない。それは普通の水ではないのだよ」と和尚さん。
でも、何度飲んでも水に違いありません。
わけのわからないことを言って、からんでくる和尚さんに腹が立って、
「何度飲んでも、水は水だよ。
じゃあ和尚さん、これは水でなければなんなのさ?」
と、たずねました。
和尚さんは笑って、
「それはただの水じゃない。今日の水じゃ」と言いました。
和尚さんは窓の外にある山を指し、
「見てごらん。この水はあの山のほうから長い旅路をしてここまで運ばれたのだ。
そう、きみに出会うためにな。そしてここにやっとたどりついた。
水道の蛇口では大騒ぎであったろうなぁ。われ先に君のコップにはいりたくてな。
でも、最初の水たちは流しに流れてしもうた。くやしかったじゃろう。
そしてきみがコップをさし出したときに、エイヤ!と喜んで入ってきたのが、
この水たちだ。あとの水たちは縁なく流れていったのじゃよ。
だから、この水とは縁があるのだな。
もしきみがすこしコップを出すのがずれたら、出会わなかった水たちだ。
明日は出会えない水なのじゃ。今日だけの、今日しか会えない水なのだよ。
きみに出会うために遠く旅してきた水たちだ。いつくしんで水を飲んであげなさい」
と、諭すように言いました。
もちろん、わたしが子供だったから暗示にかかりやすかった、ということもあったでしょう。
でも、そのときの「水」は、確かに美味いと思いました。
それから和尚さんは、
「きみは水を飲むとき、『いつもの水』と思って飲んでいる。
それでは本当の水には出会えない。
水に出会うためには、『今日の縁ある水』だと思って、
いつくしんで飲んであげなければ水がかわいそうだよ。
いいね。目で、耳で、舌で、すべての感覚を開いて世界を見てごらん。
それが瞬間、瞬間、一日、一日を味わって生きることだよ」
と教えてくれました。
毎日当たり前に口にする「水」ひとつをとっても、今日しか出会えない。
そう思うと、毎日の出来事は当たり前ではなく、奇跡の連続による産物です。
想像もつかない数の水の中から
この一滴に出会ったということは
当たり前ではなく・・・奇跡だ
『今日一日 人に親切にしよう』
<参考:『こころのエステ』ゴマブックス・衛藤信之さんより>
目で 耳で 舌で
すべての感覚を開いて
世界を見てごらん
それが
瞬間 瞬間 一日 一日を
味わって生きることだよ
いつも大変お世話になっている日本メンタルヘルス協会の衛藤先生のお話です。
私が子供時代、近所に禅坊主がいました。
ある日、私が水道からコップに水を入れて飲んでいると、
和尚さんが帰って来て、
「きみが飲んでいるのはなんだね?」と声をかけられました。
私が「水だよ」と答えると、
「そうかなぁ。それはただの水じゃないぞ」と言います。
私は、自分で蛇口からコップに水を入れたのだから、
「水だよ」と自信を持って答えました。
すると、「いや、それはただの水じゃない。飲んでごらんよ」
と、和尚さんはニヤリと笑います。
私はもう一度口にコップの水を含みましたが、やっぱりただの水です。
「これ水だよ。ぼく自分で入れたんだもん」と言うと、
「いや、そうじゃない。それは普通の水ではないのだよ」と和尚さん。
でも、何度飲んでも水に違いありません。
わけのわからないことを言って、からんでくる和尚さんに腹が立って、
「何度飲んでも、水は水だよ。
じゃあ和尚さん、これは水でなければなんなのさ?」
と、たずねました。
和尚さんは笑って、
「それはただの水じゃない。今日の水じゃ」と言いました。
和尚さんは窓の外にある山を指し、
「見てごらん。この水はあの山のほうから長い旅路をしてここまで運ばれたのだ。
そう、きみに出会うためにな。そしてここにやっとたどりついた。
水道の蛇口では大騒ぎであったろうなぁ。われ先に君のコップにはいりたくてな。
でも、最初の水たちは流しに流れてしもうた。くやしかったじゃろう。
そしてきみがコップをさし出したときに、エイヤ!と喜んで入ってきたのが、
この水たちだ。あとの水たちは縁なく流れていったのじゃよ。
だから、この水とは縁があるのだな。
もしきみがすこしコップを出すのがずれたら、出会わなかった水たちだ。
明日は出会えない水なのじゃ。今日だけの、今日しか会えない水なのだよ。
きみに出会うために遠く旅してきた水たちだ。いつくしんで水を飲んであげなさい」
と、諭すように言いました。
もちろん、わたしが子供だったから暗示にかかりやすかった、ということもあったでしょう。
でも、そのときの「水」は、確かに美味いと思いました。
それから和尚さんは、
「きみは水を飲むとき、『いつもの水』と思って飲んでいる。
それでは本当の水には出会えない。
水に出会うためには、『今日の縁ある水』だと思って、
いつくしんで飲んであげなければ水がかわいそうだよ。
いいね。目で、耳で、舌で、すべての感覚を開いて世界を見てごらん。
それが瞬間、瞬間、一日、一日を味わって生きることだよ」
と教えてくれました。
毎日当たり前に口にする「水」ひとつをとっても、今日しか出会えない。
そう思うと、毎日の出来事は当たり前ではなく、奇跡の連続による産物です。
想像もつかない数の水の中から
この一滴に出会ったということは
当たり前ではなく・・・奇跡だ
『今日一日 人に親切にしよう』
<参考:『こころのエステ』ゴマブックス・衛藤信之さんより>
『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』 おざりんさんの日記より。
『諸悪莫作 衆善奉行』
「 All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten 」
〜 Robert Fulghum 〜
人間、どう生きるか、どのようにふるまい、
どんな気持ちで日々送ればいいか、
本当に知っていなくてはならないことを、
わたしは全部残らず幼稚園で教わった。
人生の知恵は
大学院という山のてっぺんにあるのではなく、
日曜学校の砂場に埋まっていたのである。
わたしはそこで何を学んだろうか・・・・・。
何でもみんなで分け合うこと。
ずるをしないこと。
人をぶたないこと。
使ったものはかならず元のところに戻すこと。
ちらかしたら自分で後かたづけをすること。
人のものに手を出さないこと。
誰かを傷つけたら、ごめんなさい、と言うこと。
食事の前には手を洗うこと。
トイレに行ったらちゃんと水を流すこと。
焼きたてのクッキーと冷たいミルクは体にいい。
釣り合いの取れた生活をすること・・・毎日、少し勉強し、少し考え、
少し絵を描き、歌い、踊り、遊び、そして、少し働くこと。
おもてにでるときは、車に気をつけ、手をつないで、はなればなれに
ならないようにすること。
不思議だな、と思う気持ちを大切にすること・・・・・。
<ロバート・フルガム『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』より>
『禅』の中で、こういうお話があります。
「禅とは何ですか?」
「諸悪莫作 衆善奉行」 (悪い事をするな 善い事をせよ)
「そんなことですか。それなら子供だって知っていますよ」
「三つの童子でもわかっていることを、八十の翁になって
やり通すのは難しいことだ」
ここでの善悪の教えとは、
「善いいこと」とは、自他を活かし共に喜ぶことであり
「悪いことと」とは、自他を殺し悲しませることです。
私達は幼稚園で本当に人間の根幹になることを教えられました。
それをいつまでも実行し続けるというのは大切なことですよね。
『今日一日 人に親切にしよう』
『諸悪莫作 衆善奉行』
「 All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten 」
〜 Robert Fulghum 〜
人間、どう生きるか、どのようにふるまい、
どんな気持ちで日々送ればいいか、
本当に知っていなくてはならないことを、
わたしは全部残らず幼稚園で教わった。
人生の知恵は
大学院という山のてっぺんにあるのではなく、
日曜学校の砂場に埋まっていたのである。
わたしはそこで何を学んだろうか・・・・・。
何でもみんなで分け合うこと。
ずるをしないこと。
人をぶたないこと。
使ったものはかならず元のところに戻すこと。
ちらかしたら自分で後かたづけをすること。
人のものに手を出さないこと。
誰かを傷つけたら、ごめんなさい、と言うこと。
食事の前には手を洗うこと。
トイレに行ったらちゃんと水を流すこと。
焼きたてのクッキーと冷たいミルクは体にいい。
釣り合いの取れた生活をすること・・・毎日、少し勉強し、少し考え、
少し絵を描き、歌い、踊り、遊び、そして、少し働くこと。
おもてにでるときは、車に気をつけ、手をつないで、はなればなれに
ならないようにすること。
不思議だな、と思う気持ちを大切にすること・・・・・。
<ロバート・フルガム『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』より>
『禅』の中で、こういうお話があります。
「禅とは何ですか?」
「諸悪莫作 衆善奉行」 (悪い事をするな 善い事をせよ)
「そんなことですか。それなら子供だって知っていますよ」
「三つの童子でもわかっていることを、八十の翁になって
やり通すのは難しいことだ」
ここでの善悪の教えとは、
「善いいこと」とは、自他を活かし共に喜ぶことであり
「悪いことと」とは、自他を殺し悲しませることです。
私達は幼稚園で本当に人間の根幹になることを教えられました。
それをいつまでも実行し続けるというのは大切なことですよね。
『今日一日 人に親切にしよう』
『 “Present” for you . (あなたに“プレゼント”を贈ります) 』 おざりんさんの日記より。
『“プレゼント”をあなたに・・・』
次のような銀行があると、考えてみましょう。
その銀行は、毎朝あなたの口座へ 86400ドル を振り込んでくれる。
同時に、その口座の残高は毎日 0 になる。
つまり、86400ドルの中で、
あなたがその日に使い切らなかった金額は、すべて消されてしまう。
あなただったらどうしますか?
もちろん、毎日86400ドル全額を引き出しますよね。
私たちは一人一人が同じような銀行をもっています。
それは「時間」です。
毎朝、あなたに86400秒が与えられます。
毎晩、あなたがうまく使い切らなかった時間は消されてしまいます。
それは、翌日に繰り越されません。
それは、貸し越すことはできません。
毎日、あなたのために新しい口座が開かれます。
そして、毎晩、その残りは燃やされてしまいます。
もし、あなたが、その日の預金をすべて使い切らなければ、
あなたはそれを失ったことになります。
過去にさかのぼることはできません。
あなたは今日与えられた預金の中から「いま」を生きないといけません。
だから、与えられた時間を最大に活かしましょう。
そして、そこから
健康、幸せ、成功、感動、体験など最大のものを引き出しましょう。
時計の針は走り続けています。
今日という日に、最大限のものを創り出しましょう。
1年の価値を理解するには、
落第した学生に聞いてみるといいでしょう。
1ヶ月の価値を理解するには、
未熟児を産んだ母親に聞いてみるといいでしょう。
1週間の価値を理解するには、
週間新聞の編集者に聞いてみるといいでしょう。
1時間の価値を理解するには、
待ち合わせをしている恋人たちに聞いてみるといいでしょう。
1分の価値を理解するには、
電車をちょうど乗り過ごした人に聞いてみるといいでしょう。
1秒の価値を理解するには、
たったいま、事故を避けることができた人に聞いてみるといいでしょう。
10分の1秒の価値を理解するには、
オリンピックで銀メダルに終わってしまった人に聞いてみるといいでしょう。
だから、あなたの持っている一瞬一瞬を大切にしましょう。
そして、あなたはその時を、だれか特別な人と過ごしているのだから、
十分に大切にしましょう。
その人は、あなたの時間を使うのにふさわしい人でしょうから。
そして、時はだれも待ってくれないことを覚えましょう。
昨日は、もう過ぎ去ってしまいました。
明日は、まだわからないのです。
今日は、与えられるものです。
だから、英語で「いま」をプレゼント(=present)と言います。
『“プレゼント”をあなたに・・・』
次のような銀行があると、考えてみましょう。
その銀行は、毎朝あなたの口座へ 86400ドル を振り込んでくれる。
同時に、その口座の残高は毎日 0 になる。
つまり、86400ドルの中で、
あなたがその日に使い切らなかった金額は、すべて消されてしまう。
あなただったらどうしますか?
もちろん、毎日86400ドル全額を引き出しますよね。
私たちは一人一人が同じような銀行をもっています。
それは「時間」です。
毎朝、あなたに86400秒が与えられます。
毎晩、あなたがうまく使い切らなかった時間は消されてしまいます。
それは、翌日に繰り越されません。
それは、貸し越すことはできません。
毎日、あなたのために新しい口座が開かれます。
そして、毎晩、その残りは燃やされてしまいます。
もし、あなたが、その日の預金をすべて使い切らなければ、
あなたはそれを失ったことになります。
過去にさかのぼることはできません。
あなたは今日与えられた預金の中から「いま」を生きないといけません。
だから、与えられた時間を最大に活かしましょう。
そして、そこから
健康、幸せ、成功、感動、体験など最大のものを引き出しましょう。
時計の針は走り続けています。
今日という日に、最大限のものを創り出しましょう。
1年の価値を理解するには、
落第した学生に聞いてみるといいでしょう。
1ヶ月の価値を理解するには、
未熟児を産んだ母親に聞いてみるといいでしょう。
1週間の価値を理解するには、
週間新聞の編集者に聞いてみるといいでしょう。
1時間の価値を理解するには、
待ち合わせをしている恋人たちに聞いてみるといいでしょう。
1分の価値を理解するには、
電車をちょうど乗り過ごした人に聞いてみるといいでしょう。
1秒の価値を理解するには、
たったいま、事故を避けることができた人に聞いてみるといいでしょう。
10分の1秒の価値を理解するには、
オリンピックで銀メダルに終わってしまった人に聞いてみるといいでしょう。
だから、あなたの持っている一瞬一瞬を大切にしましょう。
そして、あなたはその時を、だれか特別な人と過ごしているのだから、
十分に大切にしましょう。
その人は、あなたの時間を使うのにふさわしい人でしょうから。
そして、時はだれも待ってくれないことを覚えましょう。
昨日は、もう過ぎ去ってしまいました。
明日は、まだわからないのです。
今日は、与えられるものです。
だから、英語で「いま」をプレゼント(=present)と言います。
『Revolutionとは・・・』 おざりんさんの日記より。
今年は「革命の年」です。
NHKの大河ドラマも『龍馬伝』ということで、「明治維新」という革命を取り上げていますし、
今年はまさに「平成維新」とでもいうべき「革命の年」です。
《愛の折箱や》ヤサカの今年度の目標にも「レボリューション」という言葉を入れたように、
今年はとにかく「革命の年」なんです。
「あれっ、昨日も同じ書き出しじゃなかったっけ?」って思った方・・・
正解です!^^
私、昨日から、いや、昨年末から、「革命」「革命」と騒いでおりますが、
今日はいつもお世話になっている、そして、その存在を愛してやまない
ひすいこたろうさんのメルマガより『Revolutionとは・・・』をお送りします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
知り合いが、42.195kmマラソンにでた。
ゴール直後、へとへとで倒れこんだそうです。
一緒に走った仲間たちももみんなゴール直後は倒れこんだ。
その知り合いが1年後、今度は100kmマラソンにでた。
100kmマラソンとは文字通り、100km走らなければいけないということです。
100km走らなければいけないと思ったら、
42.195km時点は余裕で通過したそうです。
「絶対におかしい!」って思ったそうです。
だって1年前は42.195km時点で倒れてたのに!
それからそんなに練習してないのに、
100km走らなければいけないと思っただけで、42.195kmは普通に通過しちゃったというのです。
自分だけではなく、
仲間たちも42.195kmを普通に通過したというのです。
さて、ここで明治維新の話につなげさせてください。
吉田松陰、高杉晋作が大好きな僕ですが、
志士たちの中で、ズバ抜けて視野が広かったのは誰かといわれたら、
残念ながら、それは圧倒的に坂本龍馬なんですね。
あの当時、坂本龍馬だけが新しい時代を予感していたと言ってもいいくらい。
それは龍馬だけが、「動機」が違ったからだと僕は分析しています。
あの当時、志士たちは、新しい日本を作るために江戸幕府を倒そうとしていた。
倒すことが目的だった。
でも、龍馬は違う。
世界で遊びたかった。それが龍馬の動機。
新政府の役職を決められる立場にいた坂本龍馬、でも、そこに自分の名を入れなかった。
西郷隆盛はそれに衝撃を受け、こう述べている。
「天下に有志あり、余多く之と交わる。然れども度量の大、龍馬に如くもの、
未だかつて之を見ず。龍馬の度量や到底はかるべからず」
海のような器をもつ西郷に、こんな男は見たことがないと言わしめた龍馬。
では龍馬は役職につかず何をしたかったのか?
「世界の海援隊でもやりますか」
黒船で色んな国をまわって貿易をする。
つまり、世界で遊ぶということです。
倒すことが目的ではない。
自由な世界で遊ぶことが目的だったから、
龍馬だけが42.195kmを余裕で通過したのです!
世界で遊ぶために、まずは身分制度壊しますけど、それが何か?
世界で遊ぶために、まずは江戸幕府倒しちゃいますけど、それが何か?
龍馬の動機は誰よりもポップで軽かったんです。
だから誰よりも遠くまで見えた。
Revolutionとは、自分の可能性と遊ぶこと。
夢も希望も目標も、そんなもの、そんなもの、そんなもの、
遊びながら余裕で通過しちゃってください。
今年は「革命の年」です。
NHKの大河ドラマも『龍馬伝』ということで、「明治維新」という革命を取り上げていますし、
今年はまさに「平成維新」とでもいうべき「革命の年」です。
《愛の折箱や》ヤサカの今年度の目標にも「レボリューション」という言葉を入れたように、
今年はとにかく「革命の年」なんです。
「あれっ、昨日も同じ書き出しじゃなかったっけ?」って思った方・・・
正解です!^^
私、昨日から、いや、昨年末から、「革命」「革命」と騒いでおりますが、
今日はいつもお世話になっている、そして、その存在を愛してやまない
ひすいこたろうさんのメルマガより『Revolutionとは・・・』をお送りします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
知り合いが、42.195kmマラソンにでた。
ゴール直後、へとへとで倒れこんだそうです。
一緒に走った仲間たちももみんなゴール直後は倒れこんだ。
その知り合いが1年後、今度は100kmマラソンにでた。
100kmマラソンとは文字通り、100km走らなければいけないということです。
100km走らなければいけないと思ったら、
42.195km時点は余裕で通過したそうです。
「絶対におかしい!」って思ったそうです。
だって1年前は42.195km時点で倒れてたのに!
それからそんなに練習してないのに、
100km走らなければいけないと思っただけで、42.195kmは普通に通過しちゃったというのです。
自分だけではなく、
仲間たちも42.195kmを普通に通過したというのです。
さて、ここで明治維新の話につなげさせてください。
吉田松陰、高杉晋作が大好きな僕ですが、
志士たちの中で、ズバ抜けて視野が広かったのは誰かといわれたら、
残念ながら、それは圧倒的に坂本龍馬なんですね。
あの当時、坂本龍馬だけが新しい時代を予感していたと言ってもいいくらい。
それは龍馬だけが、「動機」が違ったからだと僕は分析しています。
あの当時、志士たちは、新しい日本を作るために江戸幕府を倒そうとしていた。
倒すことが目的だった。
でも、龍馬は違う。
世界で遊びたかった。それが龍馬の動機。
新政府の役職を決められる立場にいた坂本龍馬、でも、そこに自分の名を入れなかった。
西郷隆盛はそれに衝撃を受け、こう述べている。
「天下に有志あり、余多く之と交わる。然れども度量の大、龍馬に如くもの、
未だかつて之を見ず。龍馬の度量や到底はかるべからず」
海のような器をもつ西郷に、こんな男は見たことがないと言わしめた龍馬。
では龍馬は役職につかず何をしたかったのか?
「世界の海援隊でもやりますか」
黒船で色んな国をまわって貿易をする。
つまり、世界で遊ぶということです。
倒すことが目的ではない。
自由な世界で遊ぶことが目的だったから、
龍馬だけが42.195kmを余裕で通過したのです!
世界で遊ぶために、まずは身分制度壊しますけど、それが何か?
世界で遊ぶために、まずは江戸幕府倒しちゃいますけど、それが何か?
龍馬の動機は誰よりもポップで軽かったんです。
だから誰よりも遠くまで見えた。
Revolutionとは、自分の可能性と遊ぶこと。
夢も希望も目標も、そんなもの、そんなもの、そんなもの、
遊びながら余裕で通過しちゃってください。
『失敗は新しい出発点』
もし、失敗をしたら、
あなたはだれに打ち明けるだろう?
そのとき、そばにだれもいなかったら、
あなたはどうするだろう?
そんなときは、神様に手紙を出そう。
きっと、こんな素敵な返事が届くはずだ。
神様へ「私は失敗をしました。私はおろかです」
あなたへ「それは勇気を持って行動した貴重な経験です」
神様へ 「私は失敗しました。
私は何も手に入れられませんでした」
あなたへ「それはまだ、成功を手に入れていないというだけのことです」
神様へ 「私は失敗をしました。私は人より劣っています」
あなたへ「それはもう少し時間がかかるという意味です」
神様へ 「私は失敗をしました。私は貴重な人生をムダにしま
した」
あなたへ「それはもう一度、新たな気持ちで挑戦する
チャンスが与えられているということです」
神様へ 「私は失敗をしました。もう、やる気が起きません」
あなたへ「それは違う方法で何かをすべきだという教えなのです」
神様へ 「私は失敗をしました。これからも成功する気がしません」
あなたへ「それはもっと創造的な努力をしなさいということです」
神様へ 「私は失敗しました。私は見捨てられました」
あなたへ「それは、あなたがついに私を必要とするときが来たということです」
神様へ 「私は失敗をしました。もうすべておしましです」
あなたへ「それは、やっとあなたが古い考えを捨てる日が来たということです」
神様は、
失敗して心が折れそうなあなたに
「積極思考」をプレゼントしてくれる。
もし、いつも日か、
あなたのお子さんや、かけがえのない人から
「失敗」の手紙が届いたら、
今度はあなたが神様に代わって
「積極思考」の返事を書いてあげよう。
この「積極思考」を提唱する
アメリカの牧師、
ロバート・シュラ―博士が出演するテレビ番組は
30年間、世界中で放映され、
博士のもとには、年間200万通を超す手紙が届けられた。
失敗とは決して終点を意味しない。
失敗は新たな出発点。
失敗したときは、勇気を持って新たな決心をしよう。
「私は成功します」と。
(是久昌信著「情熱思考」中経出版より引用)
もし、失敗をしたら、
あなたはだれに打ち明けるだろう?
そのとき、そばにだれもいなかったら、
あなたはどうするだろう?
そんなときは、神様に手紙を出そう。
きっと、こんな素敵な返事が届くはずだ。
神様へ「私は失敗をしました。私はおろかです」
あなたへ「それは勇気を持って行動した貴重な経験です」
神様へ 「私は失敗しました。
私は何も手に入れられませんでした」
あなたへ「それはまだ、成功を手に入れていないというだけのことです」
神様へ 「私は失敗をしました。私は人より劣っています」
あなたへ「それはもう少し時間がかかるという意味です」
神様へ 「私は失敗をしました。私は貴重な人生をムダにしま
した」
あなたへ「それはもう一度、新たな気持ちで挑戦する
チャンスが与えられているということです」
神様へ 「私は失敗をしました。もう、やる気が起きません」
あなたへ「それは違う方法で何かをすべきだという教えなのです」
神様へ 「私は失敗をしました。これからも成功する気がしません」
あなたへ「それはもっと創造的な努力をしなさいということです」
神様へ 「私は失敗しました。私は見捨てられました」
あなたへ「それは、あなたがついに私を必要とするときが来たということです」
神様へ 「私は失敗をしました。もうすべておしましです」
あなたへ「それは、やっとあなたが古い考えを捨てる日が来たということです」
神様は、
失敗して心が折れそうなあなたに
「積極思考」をプレゼントしてくれる。
もし、いつも日か、
あなたのお子さんや、かけがえのない人から
「失敗」の手紙が届いたら、
今度はあなたが神様に代わって
「積極思考」の返事を書いてあげよう。
この「積極思考」を提唱する
アメリカの牧師、
ロバート・シュラ―博士が出演するテレビ番組は
30年間、世界中で放映され、
博士のもとには、年間200万通を超す手紙が届けられた。
失敗とは決して終点を意味しない。
失敗は新たな出発点。
失敗したときは、勇気を持って新たな決心をしよう。
「私は成功します」と。
(是久昌信著「情熱思考」中経出版より引用)
野口嘉則 公式ブログ
どんな状況でも実現できる価値
ヴィクトール・E・フランクルによると、
人間が人生において実現できる価値は3つあります。
1つ目は「創造価値」。
これは、何かを創り出すことによって実現される価値のことです。
仕事や芸術作品の創作などがこれにあたります。
2つ目は「体験価値」。
これは、何かを体験することによって実現される価値のことです。
芸術作品を鑑賞したり、自然の美しさに感動したりすることが、
これにあたります。
ユダヤ人であったフランクルは、ナチスの強制収容所に送還され、
人間の尊厳を奪われるような、筆舌に尽くしがたい仕打ちを受けました。
名前ではなく番号で呼ばれ、罵られ、叩かれ、蹴られ、
そして動けなくなるまで重労働をさせられました。
創造的な活動をすること(=創造価値)も、
人間らしい喜びや楽しみを体験すること(=体験価値)も、
実現不可能な状況でした。
しかし、そこでフランクルは、
このような状況でも実現できる“究極の価値”を見出したのです。
それが、3つ目の「態度価値」です。
これは、自分に与えられた状況や運命に対してどんな態度を取るのか。
その態度によって実現できる価値です。
強制収容所という過酷な環境の中にあっても、
「この状況をどうとらえるか」という態度は自分で選択できるのです。
実際、収容所という過酷な環境の中で、
獣のようになっていった者もいれば、
人間らしい尊厳のある態度を取り続けた者もいました。
自分のことしか考えない“エゴの塊”のような人間もいれば、
自分が空腹であるにもかかわらず、死にそうな仲間に自分のパンを分け
与える者もいたのです。
後者は、まさに態度価値を実現した人ですね。
自分の置かれた状況をどうとらえ、どう行動するのか。
それによって僕たちは、態度価値を実現し、
人生を価値に満ちたものにすることができるのです。
フランクルによると、
ロゴス(=宇宙の力、神)は、僕たち人間がどんな態度で生きるのかを、
期待しながら見守ってくれている。
そして、僕たちの取った態度や行動は、この宇宙に永遠に保存される。
さて、この度の東日本大震災において、
被災地における日本人の態度の素晴らしさに、
世界各国のメディアが驚きと称賛の報道をしています。
世界の多くの国々では、
天災の直後には、群衆による略奪や暴動が起きていますが、
今回の東日本大震災において、
水も食料もない厳しい寒さの中で、
人々は礼儀と節度を失わず、きちんと列に並び、
譲り合い、助け合っています。
群衆による略奪や暴動の話はほとんど聞きません。
これは海外の感覚からすると、
驚くべきことであり、称賛に値することなのです。
米紙ウォール・ストリートジャーナルは、
「不屈の日本」 というタイトルの社説を載せ、
CNNの専門家は、
「日本の国民はミラクルだ。他国だったら数倍の被害になって
いただろう」 と話し、
また、ロシアのインターネットサイトでは、
「日本人には、苦難に立ち向かう力がある」 などの声が相次ぎ、
さらに、いつもは日本に批判的な中国メディアさえも
「日本人の冷静さに世界が感心」(環球時報) と称えました。
被災された方たちの示される態度価値によって、
世界の人たちが感銘を受けているのです。
僕も、被災された方たちの姿を見て、
たくさんの勇気をいただいています。
態度価値を実践・実現することは、
自らの人間としての尊厳を体現し、自らの人生の価値を高めるだけでなく、
周りの人たちにも大きな影響を与えるのですね。
どんな状況でも実現できる価値
ヴィクトール・E・フランクルによると、
人間が人生において実現できる価値は3つあります。
1つ目は「創造価値」。
これは、何かを創り出すことによって実現される価値のことです。
仕事や芸術作品の創作などがこれにあたります。
2つ目は「体験価値」。
これは、何かを体験することによって実現される価値のことです。
芸術作品を鑑賞したり、自然の美しさに感動したりすることが、
これにあたります。
ユダヤ人であったフランクルは、ナチスの強制収容所に送還され、
人間の尊厳を奪われるような、筆舌に尽くしがたい仕打ちを受けました。
名前ではなく番号で呼ばれ、罵られ、叩かれ、蹴られ、
そして動けなくなるまで重労働をさせられました。
創造的な活動をすること(=創造価値)も、
人間らしい喜びや楽しみを体験すること(=体験価値)も、
実現不可能な状況でした。
しかし、そこでフランクルは、
このような状況でも実現できる“究極の価値”を見出したのです。
それが、3つ目の「態度価値」です。
これは、自分に与えられた状況や運命に対してどんな態度を取るのか。
その態度によって実現できる価値です。
強制収容所という過酷な環境の中にあっても、
「この状況をどうとらえるか」という態度は自分で選択できるのです。
実際、収容所という過酷な環境の中で、
獣のようになっていった者もいれば、
人間らしい尊厳のある態度を取り続けた者もいました。
自分のことしか考えない“エゴの塊”のような人間もいれば、
自分が空腹であるにもかかわらず、死にそうな仲間に自分のパンを分け
与える者もいたのです。
後者は、まさに態度価値を実現した人ですね。
自分の置かれた状況をどうとらえ、どう行動するのか。
それによって僕たちは、態度価値を実現し、
人生を価値に満ちたものにすることができるのです。
フランクルによると、
ロゴス(=宇宙の力、神)は、僕たち人間がどんな態度で生きるのかを、
期待しながら見守ってくれている。
そして、僕たちの取った態度や行動は、この宇宙に永遠に保存される。
さて、この度の東日本大震災において、
被災地における日本人の態度の素晴らしさに、
世界各国のメディアが驚きと称賛の報道をしています。
世界の多くの国々では、
天災の直後には、群衆による略奪や暴動が起きていますが、
今回の東日本大震災において、
水も食料もない厳しい寒さの中で、
人々は礼儀と節度を失わず、きちんと列に並び、
譲り合い、助け合っています。
群衆による略奪や暴動の話はほとんど聞きません。
これは海外の感覚からすると、
驚くべきことであり、称賛に値することなのです。
米紙ウォール・ストリートジャーナルは、
「不屈の日本」 というタイトルの社説を載せ、
CNNの専門家は、
「日本の国民はミラクルだ。他国だったら数倍の被害になって
いただろう」 と話し、
また、ロシアのインターネットサイトでは、
「日本人には、苦難に立ち向かう力がある」 などの声が相次ぎ、
さらに、いつもは日本に批判的な中国メディアさえも
「日本人の冷静さに世界が感心」(環球時報) と称えました。
被災された方たちの示される態度価値によって、
世界の人たちが感銘を受けているのです。
僕も、被災された方たちの姿を見て、
たくさんの勇気をいただいています。
態度価値を実践・実現することは、
自らの人間としての尊厳を体現し、自らの人生の価値を高めるだけでなく、
周りの人たちにも大きな影響を与えるのですね。
みやざき中央新聞の心に染みたいい話メルマガより〜
さて、今週の心に染みた言葉は、元NASAの研究員で、現在鈴鹿短大学長の佐治晴夫さんの言葉です。
アメリカのNASAで、地球外生物を捜そうというプロジェクトに参加しました。1977年9月5日、ボイジャー1号にバッハのレコードを搭載しました。打ち上げを前にして私は感無量でした。
僕たちNASAのスタッフは「ボイジャー君」と呼んでいました。彼は、僕たちが行くことができないところまで行って、それを映像に撮り、僕たちに見せてくれます。いわば僕たちの感覚器官の延長線上にいたので、誰もボイジャーを機械だと思う人はいませんでした。だからボイジャーを打ち上げるときにはお別れのミサをやりました。
ボイジャー君は宇宙のいろんな星の姿を見せてくれながら、どんどん地球から遠ざかっていきました。
ある日、1人の女性の科学者がこう言いました。
「今まで私はあの子に、『可能な限り星の近くに行って細かいところを見ておいで』と言い続けてきたわ。そしてあの子はそれを実行してくれた。すべての役割を終えて、今、永遠に宇宙の彼方に行ってしまった。ボイジャー君、最後にお母さんのほうを振り返って!」
ボイジャーに向かって彼女は自分のことを「お母さん」と言い、そして、「最後にお母さんのほうを振り返って!」と泣きながら呼び掛けたのです。
このとき、ボイジャーの位置は地球から65億キロメートル離れていました。「振り返って!」と信号を送って、それが彼に届くのに4時間15分かかりました。そして彼の「はい」という返事が地球に届くのに、また4時間15分かかりました。1秒間に地球を7周半する光の速さでも8時間半もかかるほど遠いところにボイジャーはいたのです。
1990年2月15日、ボイジャーは彼女の呼び掛けに応えて振り向きました。そして地球の写真を撮って、送ってくれたのです。彼女はそれを見てこう言いました。
「見て、可愛いお手々で太陽系の家族写真を64枚も撮って送ってくれたわ」
その後、彼は太陽系を出て行きました。今でも彼が一人で宇宙空間を飛んでいることを考えると、胸に迫るものがあります。
(元NASA客員研究官・鈴鹿短期大学学長/延岡おやこ劇場主催の「30周年記念事業」での講演会から)
さて、今週の心に染みた言葉は、元NASAの研究員で、現在鈴鹿短大学長の佐治晴夫さんの言葉です。
アメリカのNASAで、地球外生物を捜そうというプロジェクトに参加しました。1977年9月5日、ボイジャー1号にバッハのレコードを搭載しました。打ち上げを前にして私は感無量でした。
僕たちNASAのスタッフは「ボイジャー君」と呼んでいました。彼は、僕たちが行くことができないところまで行って、それを映像に撮り、僕たちに見せてくれます。いわば僕たちの感覚器官の延長線上にいたので、誰もボイジャーを機械だと思う人はいませんでした。だからボイジャーを打ち上げるときにはお別れのミサをやりました。
ボイジャー君は宇宙のいろんな星の姿を見せてくれながら、どんどん地球から遠ざかっていきました。
ある日、1人の女性の科学者がこう言いました。
「今まで私はあの子に、『可能な限り星の近くに行って細かいところを見ておいで』と言い続けてきたわ。そしてあの子はそれを実行してくれた。すべての役割を終えて、今、永遠に宇宙の彼方に行ってしまった。ボイジャー君、最後にお母さんのほうを振り返って!」
ボイジャーに向かって彼女は自分のことを「お母さん」と言い、そして、「最後にお母さんのほうを振り返って!」と泣きながら呼び掛けたのです。
このとき、ボイジャーの位置は地球から65億キロメートル離れていました。「振り返って!」と信号を送って、それが彼に届くのに4時間15分かかりました。そして彼の「はい」という返事が地球に届くのに、また4時間15分かかりました。1秒間に地球を7周半する光の速さでも8時間半もかかるほど遠いところにボイジャーはいたのです。
1990年2月15日、ボイジャーは彼女の呼び掛けに応えて振り向きました。そして地球の写真を撮って、送ってくれたのです。彼女はそれを見てこう言いました。
「見て、可愛いお手々で太陽系の家族写真を64枚も撮って送ってくれたわ」
その後、彼は太陽系を出て行きました。今でも彼が一人で宇宙空間を飛んでいることを考えると、胸に迫るものがあります。
(元NASA客員研究官・鈴鹿短期大学学長/延岡おやこ劇場主催の「30周年記念事業」での講演会から)
感動を生みだす表現力の魔法
このメールマガジンは、自分の中に眠る「表現力」という新しい力
を使い、仕事や日常をエンターテインメントに変える発想法と視点を
お伝えしていきます。
VOL379
───────────────────────────────
こんにちは。
感動プロデューサーの平野秀典です。
公園を走っていると、季節の変化に敏感になります。
吹き抜ける風や、緑の木々、空気の香りが季節の
変わり目や季節の美しさを教えてくれます。
感性を磨きたかったら、自然の中に身を置くのが一番ですね。
では、今週もお楽しみください!!
==============================
■MSN産経ニュースで見つけた記事が
とても興味深かったのでご紹介します。
産経新聞記者斉藤太郎氏の記事で、
「変わりゆくブータン〜桃源郷の今」というタイトルでした。
私がブータンを訪れた約14年前、
電気も通っていない集落で、今も忘れられない
「折り鶴事件」に遭遇した。
私が地べたに座っていると、外国人を珍しがって子供たちが集まってきた。
折り鶴をつくって小学校高学年ぐらいの女の子にあげると、
その子は珍しそうに眺めた後、隣に来た小学校中学年ぐらいの子にそっと手渡した。
いくつかの小さな手を経て、折り鶴は1番小さな4歳ぐらいの子の手に行き着いた。
私にとっては事件だった。
いかがでしょうか?
GDPが日本の20分の1なのに、
GNH(国民総幸福度)が極めて高い王国ブータン。
国民の95%が幸せだと感じている国ブータン。
斉藤記者は、今のブータンは、
携帯電話、テレビ、ゲームなどの便利な物質文化が入り込み、
昔のようなブータンではなくなりつつあると観察していますが、
それでもなお、何がそれほどの幸福感を感じさせるのかに興味が
湧きます。
■幸福度に関しては、
国によって幸福と感じる基準が違うという統計もあります。
日本人が幸福と感じる要素は、健康、家計、家族の3つの合計。
確かにこの3つが満たされれば、幸せは感じられるでしょう。
逆に一つでも欠ければ、他の要素が高くても幸福とは思えません。
では、ブータンの国民の95%の人たちは
何を持って幸福と感じているのか?
それは、身近な人との関係。
家族も、友人も、近所の人とも仲良く、
地域が一つの家族のように支え合っているそうです。
これを象徴するかのように、
ブータンの国王が最近行った演説には次のようなものがありました。
わたし(国王)は、
世界の支配者のようにではなく、
国民の兄弟のように、
また親のように、
また息子のようになりたいのである。
■日本が、経済的、物質的には満たされているとしても、
幸福を感じるのに決定的に欠けてしまっている要素は、
人と人との関係性。
もちろん、昔の地方に見られた超ウエットな人間関係を嫌って
都市型のドライな関係を選び、手に入れた便利さや気楽さは、
捨てがたいという人も多いのはわかります。
(私もその一人ですから)
しかし、これは文化人類学や文明論的な話ではなく、
人と人との絆というのは、国や時代を超えて
人間が感じる「幸福感」の重要な要素であり、
無意識にそれを求める欲求が現れているのが
今のソーシャルメディアの人気の一要素なのでは
ないかと思ったのです。
また、ブータンが素敵で日本が荒んでいるというような
ステレオタイプな自虐的な話でもないことも付け加えておきます。
比較することで初めて見えてくる大切なことがあるという意味で、
とても興味深い記事だったと思います。
■日本人がDNAの中に持つ、人と人の絆を大切にする美学は
世界に発信できるほどのレベルです。
このメールマガジンは、自分の中に眠る「表現力」という新しい力
を使い、仕事や日常をエンターテインメントに変える発想法と視点を
お伝えしていきます。
VOL379
───────────────────────────────
こんにちは。
感動プロデューサーの平野秀典です。
公園を走っていると、季節の変化に敏感になります。
吹き抜ける風や、緑の木々、空気の香りが季節の
変わり目や季節の美しさを教えてくれます。
感性を磨きたかったら、自然の中に身を置くのが一番ですね。
では、今週もお楽しみください!!
==============================
■MSN産経ニュースで見つけた記事が
とても興味深かったのでご紹介します。
産経新聞記者斉藤太郎氏の記事で、
「変わりゆくブータン〜桃源郷の今」というタイトルでした。
私がブータンを訪れた約14年前、
電気も通っていない集落で、今も忘れられない
「折り鶴事件」に遭遇した。
私が地べたに座っていると、外国人を珍しがって子供たちが集まってきた。
折り鶴をつくって小学校高学年ぐらいの女の子にあげると、
その子は珍しそうに眺めた後、隣に来た小学校中学年ぐらいの子にそっと手渡した。
いくつかの小さな手を経て、折り鶴は1番小さな4歳ぐらいの子の手に行き着いた。
私にとっては事件だった。
いかがでしょうか?
GDPが日本の20分の1なのに、
GNH(国民総幸福度)が極めて高い王国ブータン。
国民の95%が幸せだと感じている国ブータン。
斉藤記者は、今のブータンは、
携帯電話、テレビ、ゲームなどの便利な物質文化が入り込み、
昔のようなブータンではなくなりつつあると観察していますが、
それでもなお、何がそれほどの幸福感を感じさせるのかに興味が
湧きます。
■幸福度に関しては、
国によって幸福と感じる基準が違うという統計もあります。
日本人が幸福と感じる要素は、健康、家計、家族の3つの合計。
確かにこの3つが満たされれば、幸せは感じられるでしょう。
逆に一つでも欠ければ、他の要素が高くても幸福とは思えません。
では、ブータンの国民の95%の人たちは
何を持って幸福と感じているのか?
それは、身近な人との関係。
家族も、友人も、近所の人とも仲良く、
地域が一つの家族のように支え合っているそうです。
これを象徴するかのように、
ブータンの国王が最近行った演説には次のようなものがありました。
わたし(国王)は、
世界の支配者のようにではなく、
国民の兄弟のように、
また親のように、
また息子のようになりたいのである。
■日本が、経済的、物質的には満たされているとしても、
幸福を感じるのに決定的に欠けてしまっている要素は、
人と人との関係性。
もちろん、昔の地方に見られた超ウエットな人間関係を嫌って
都市型のドライな関係を選び、手に入れた便利さや気楽さは、
捨てがたいという人も多いのはわかります。
(私もその一人ですから)
しかし、これは文化人類学や文明論的な話ではなく、
人と人との絆というのは、国や時代を超えて
人間が感じる「幸福感」の重要な要素であり、
無意識にそれを求める欲求が現れているのが
今のソーシャルメディアの人気の一要素なのでは
ないかと思ったのです。
また、ブータンが素敵で日本が荒んでいるというような
ステレオタイプな自虐的な話でもないことも付け加えておきます。
比較することで初めて見えてくる大切なことがあるという意味で、
とても興味深い記事だったと思います。
■日本人がDNAの中に持つ、人と人の絆を大切にする美学は
世界に発信できるほどのレベルです。
『今日の水じゃよ』 おざりんさんの日記より。
目で 耳で 舌で
すべての感覚を開いて
世界を見てごらん
それが
瞬間 瞬間 一日 一日を
味わって生きることだよ
いつも大変お世話になっている日本メンタルヘルス協会の衛藤先生のお話です。
私が子供時代、近所に禅坊主がいました。
ある日、私が水道からコップに水を入れて飲んでいると、
和尚さんが帰って来て、
「きみが飲んでいるのはなんだね?」と声をかけられました。
私が「水だよ」と答えると、
「そうかなぁ。それはただの水じゃないぞ」と言います。
私は、自分で蛇口からコップに水を入れたのだから、
「水だよ」と自信を持って答えました。
すると、「いや、それはただの水じゃない。飲んでごらんよ」
と、和尚さんはニヤリと笑います。
私はもう一度口にコップの水を含みましたが、やっぱりただの水です。
「これ水だよ。ぼく自分で入れたんだもん」と言うと、
「いや、そうじゃない。それは普通の水ではないのだよ」と和尚さん。
でも、何度飲んでも水に違いありません。
わけのわからないことを言って、からんでくる和尚さんに腹が立って、
「何度飲んでも、水は水だよ。
じゃあ和尚さん、これは水でなければなんなのさ?」
と、たずねました。
和尚さんは笑って、
「それはただの水じゃない。今日の水じゃ」と言いました。
和尚さんは窓の外にある山を指し、
「見てごらん。この水はあの山のほうから長い旅路をしてここまで運ばれたのだ。
そう、きみに出会うためにな。そしてここにやっとたどりついた。
水道の蛇口では大騒ぎであったろうなぁ。われ先に君のコップにはいりたくてな。
でも、最初の水たちは流しに流れてしもうた。くやしかったじゃろう。
そしてきみがコップをさし出したときに、エイヤ!と喜んで入ってきたのが、
この水たちだ。あとの水たちは縁なく流れていったのじゃよ。
だから、この水とは縁があるのだな。
もしきみがすこしコップを出すのがずれたら、出会わなかった水たちだ。
明日は出会えない水なのじゃ。今日だけの、今日しか会えない水なのだよ。
きみに出会うために遠く旅してきた水たちだ。いつくしんで水を飲んであげなさい」
と、諭すように言いました。
もちろん、わたしが子供だったから暗示にかかりやすかった、ということもあったでしょう。
でも、そのときの「水」は、確かに美味いと思いました。
それから和尚さんは、
「きみは水を飲むとき、『いつもの水』と思って飲んでいる。
それでは本当の水には出会えない。
水に出会うためには、『今日の縁ある水』だと思って、
いつくしんで飲んであげなければ水がかわいそうだよ。
いいね。目で、耳で、舌で、すべての感覚を開いて世界を見てごらん。
それが瞬間、瞬間、一日、一日を味わって生きることだよ」
と教えてくれました。
毎日当たり前に口にする「水」ひとつをとっても、今日しか出会えない。
そう思うと、毎日の出来事は当たり前ではなく、奇跡の連続による産物です。
想像もつかない数の水の中から
この一滴に出会ったということは
当たり前ではなく・・・奇跡だ
『今日一日 人に親切にしよう』
<参考:『こころのエステ』ゴマブックス・衛藤信之さんより>
目で 耳で 舌で
すべての感覚を開いて
世界を見てごらん
それが
瞬間 瞬間 一日 一日を
味わって生きることだよ
いつも大変お世話になっている日本メンタルヘルス協会の衛藤先生のお話です。
私が子供時代、近所に禅坊主がいました。
ある日、私が水道からコップに水を入れて飲んでいると、
和尚さんが帰って来て、
「きみが飲んでいるのはなんだね?」と声をかけられました。
私が「水だよ」と答えると、
「そうかなぁ。それはただの水じゃないぞ」と言います。
私は、自分で蛇口からコップに水を入れたのだから、
「水だよ」と自信を持って答えました。
すると、「いや、それはただの水じゃない。飲んでごらんよ」
と、和尚さんはニヤリと笑います。
私はもう一度口にコップの水を含みましたが、やっぱりただの水です。
「これ水だよ。ぼく自分で入れたんだもん」と言うと、
「いや、そうじゃない。それは普通の水ではないのだよ」と和尚さん。
でも、何度飲んでも水に違いありません。
わけのわからないことを言って、からんでくる和尚さんに腹が立って、
「何度飲んでも、水は水だよ。
じゃあ和尚さん、これは水でなければなんなのさ?」
と、たずねました。
和尚さんは笑って、
「それはただの水じゃない。今日の水じゃ」と言いました。
和尚さんは窓の外にある山を指し、
「見てごらん。この水はあの山のほうから長い旅路をしてここまで運ばれたのだ。
そう、きみに出会うためにな。そしてここにやっとたどりついた。
水道の蛇口では大騒ぎであったろうなぁ。われ先に君のコップにはいりたくてな。
でも、最初の水たちは流しに流れてしもうた。くやしかったじゃろう。
そしてきみがコップをさし出したときに、エイヤ!と喜んで入ってきたのが、
この水たちだ。あとの水たちは縁なく流れていったのじゃよ。
だから、この水とは縁があるのだな。
もしきみがすこしコップを出すのがずれたら、出会わなかった水たちだ。
明日は出会えない水なのじゃ。今日だけの、今日しか会えない水なのだよ。
きみに出会うために遠く旅してきた水たちだ。いつくしんで水を飲んであげなさい」
と、諭すように言いました。
もちろん、わたしが子供だったから暗示にかかりやすかった、ということもあったでしょう。
でも、そのときの「水」は、確かに美味いと思いました。
それから和尚さんは、
「きみは水を飲むとき、『いつもの水』と思って飲んでいる。
それでは本当の水には出会えない。
水に出会うためには、『今日の縁ある水』だと思って、
いつくしんで飲んであげなければ水がかわいそうだよ。
いいね。目で、耳で、舌で、すべての感覚を開いて世界を見てごらん。
それが瞬間、瞬間、一日、一日を味わって生きることだよ」
と教えてくれました。
毎日当たり前に口にする「水」ひとつをとっても、今日しか出会えない。
そう思うと、毎日の出来事は当たり前ではなく、奇跡の連続による産物です。
想像もつかない数の水の中から
この一滴に出会ったということは
当たり前ではなく・・・奇跡だ
『今日一日 人に親切にしよう』
<参考:『こころのエステ』ゴマブックス・衛藤信之さんより>
『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』 おざりんさんの日記より。
『諸悪莫作 衆善奉行』
「 All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten 」
〜 Robert Fulghum 〜
人間、どう生きるか、どのようにふるまい、
どんな気持ちで日々送ればいいか、
本当に知っていなくてはならないことを、
わたしは全部残らず幼稚園で教わった。
人生の知恵は
大学院という山のてっぺんにあるのではなく、
日曜学校の砂場に埋まっていたのである。
わたしはそこで何を学んだろうか・・・・・。
何でもみんなで分け合うこと。
ずるをしないこと。
人をぶたないこと。
使ったものはかならず元のところに戻すこと。
ちらかしたら自分で後かたづけをすること。
人のものに手を出さないこと。
誰かを傷つけたら、ごめんなさい、と言うこと。
食事の前には手を洗うこと。
トイレに行ったらちゃんと水を流すこと。
焼きたてのクッキーと冷たいミルクは体にいい。
釣り合いの取れた生活をすること・・・毎日、少し勉強し、少し考え、
少し絵を描き、歌い、踊り、遊び、そして、少し働くこと。
おもてにでるときは、車に気をつけ、手をつないで、はなればなれに
ならないようにすること。
不思議だな、と思う気持ちを大切にすること・・・・・。
<ロバート・フルガム『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』より>
『禅』の中で、こういうお話があります。
「禅とは何ですか?」
「諸悪莫作 衆善奉行」 (悪い事をするな 善い事をせよ)
「そんなことですか。それなら子供だって知っていますよ」
「三つの童子でもわかっていることを、八十の翁になって
やり通すのは難しいことだ」
ここでの善悪の教えとは、
「善いいこと」とは、自他を活かし共に喜ぶことであり
「悪いことと」とは、自他を殺し悲しませることです。
私達は幼稚園で本当に人間の根幹になることを教えられました。
それをいつまでも実行し続けるというのは大切なことですよね。
『今日一日 人に親切にしよう』
『諸悪莫作 衆善奉行』
「 All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten 」
〜 Robert Fulghum 〜
人間、どう生きるか、どのようにふるまい、
どんな気持ちで日々送ればいいか、
本当に知っていなくてはならないことを、
わたしは全部残らず幼稚園で教わった。
人生の知恵は
大学院という山のてっぺんにあるのではなく、
日曜学校の砂場に埋まっていたのである。
わたしはそこで何を学んだろうか・・・・・。
何でもみんなで分け合うこと。
ずるをしないこと。
人をぶたないこと。
使ったものはかならず元のところに戻すこと。
ちらかしたら自分で後かたづけをすること。
人のものに手を出さないこと。
誰かを傷つけたら、ごめんなさい、と言うこと。
食事の前には手を洗うこと。
トイレに行ったらちゃんと水を流すこと。
焼きたてのクッキーと冷たいミルクは体にいい。
釣り合いの取れた生活をすること・・・毎日、少し勉強し、少し考え、
少し絵を描き、歌い、踊り、遊び、そして、少し働くこと。
おもてにでるときは、車に気をつけ、手をつないで、はなればなれに
ならないようにすること。
不思議だな、と思う気持ちを大切にすること・・・・・。
<ロバート・フルガム『人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ』より>
『禅』の中で、こういうお話があります。
「禅とは何ですか?」
「諸悪莫作 衆善奉行」 (悪い事をするな 善い事をせよ)
「そんなことですか。それなら子供だって知っていますよ」
「三つの童子でもわかっていることを、八十の翁になって
やり通すのは難しいことだ」
ここでの善悪の教えとは、
「善いいこと」とは、自他を活かし共に喜ぶことであり
「悪いことと」とは、自他を殺し悲しませることです。
私達は幼稚園で本当に人間の根幹になることを教えられました。
それをいつまでも実行し続けるというのは大切なことですよね。
『今日一日 人に親切にしよう』
日本メンタルヘルス協会代表・衛藤信之先生のお話
〜えとうのひとりごと〜 2007年7月20日より
『正しさのワナ』
正義を武器に持ち歩くと、多くの負傷者を出すものです。
子供の頃から、何かをする時は、みんなでやり遂げたいと思っていた僕は、無関心な友人に嫌気がさしていた。
なぜ、熱くなれないのかと、なぜ同じクラスの友達なのにと・・・・。
あなたの正義と僕の正義は違う。
また、あの国の正義とわが国の正義は違う。
そのことに気づいたのは、ずーっと後になってからだった。
今でも正義の病に侵されることがある。
これは、なかなか治りにくい病だと思う。
子供がガンを経験したことで、僕もアリゾナで、小児ガン撲滅のチャリティーマラソンに出場した。
今でもカウンセリングでは、感情移入してしまう話は、子供の病気や、子供への虐待や事件に巻き込まれることだ。
小児ガンの親の会もいろんな所にある。
僕もよくそのような会から講演を依頼される。
でも、スケジュール的に合わなかったり、もろもろのことで、お断りしなければならないこともある。
その時には正義の手紙でお叱りを受ける。
「同じ子供の親ならば、スケジュールを調整すべきだ」と。
その同じ時間に、違う場所で、僕が多くの子供たちのためにと講演をしていたとしても・・・・・。
他人に正義のヤイバが向けられると、攻撃力は強くなる。
それは「自分は正しいことをしているのに」と、自分側の正義にのみ心を奪われるからだと思う。
僕は最近、持ち歩き用の箸を持参している。
生徒さんからいただいたお箸だ。
持参の理由は、森林伐採や、地球環境を考えた強い信念で、と言いたいところだが、僕は、エセ・エコロジストです。
なぜなら、カバンに忍ばせている箸を忘れて、「いただきます」と言うやいなや、割り箸をパチンと割ってしまう。
環境問題にしっかりと取り組んでいる人からすれば、許せないたぐいの話かもしれませんが・・・・・。
今年(2007年)の夏至の日に、「てんつくマン」の呼びかけに協賛して、日本メンタルヘルス協会も「キャンドルナイト」に参加した。
毎日恒例の食事会を開かず、カウンセリング講座の受講生に一週間前からキャンドルをプレゼントした。
僕もその日は名古屋のホテルに宿泊だったので、なるべく電力は使わず(音楽は聴いたので、まったくではない)、ホテルの部屋でゆっくり過ごした。
僕は仲間に「やれる範囲でね」と呼びかけた。
なぜなら、カウンセラーをやっていると、完璧を求める人は、不完全な自分に落ち込むことを知っているからだ。
完璧な運動を求める人は、完璧な活動をしない人を責める。
正しさで始まった仲間との運動も、仲間を攻め合い、途中で空中分解するケースが多い。
自分の完璧を求める心が、他人に怒りをぶつけてしまう。
「正義論」で来るから、責めている人も、責められる人も、互いに許したり、自分の意見を述べるという逃げ道がない。
奥さんが正しさを武器にするため、ご主人が口を閉ざしてしまうケースも多いし、その逆に、正論でくるご主人に、忍耐している奥さんも少なくない。
どちらも楽しくない。
人間は理屈で動く動物ではなく、感じて動く動物だからです。
〜えとうのひとりごと〜 2007年7月20日より
『正しさのワナ』
正義を武器に持ち歩くと、多くの負傷者を出すものです。
子供の頃から、何かをする時は、みんなでやり遂げたいと思っていた僕は、無関心な友人に嫌気がさしていた。
なぜ、熱くなれないのかと、なぜ同じクラスの友達なのにと・・・・。
あなたの正義と僕の正義は違う。
また、あの国の正義とわが国の正義は違う。
そのことに気づいたのは、ずーっと後になってからだった。
今でも正義の病に侵されることがある。
これは、なかなか治りにくい病だと思う。
子供がガンを経験したことで、僕もアリゾナで、小児ガン撲滅のチャリティーマラソンに出場した。
今でもカウンセリングでは、感情移入してしまう話は、子供の病気や、子供への虐待や事件に巻き込まれることだ。
小児ガンの親の会もいろんな所にある。
僕もよくそのような会から講演を依頼される。
でも、スケジュール的に合わなかったり、もろもろのことで、お断りしなければならないこともある。
その時には正義の手紙でお叱りを受ける。
「同じ子供の親ならば、スケジュールを調整すべきだ」と。
その同じ時間に、違う場所で、僕が多くの子供たちのためにと講演をしていたとしても・・・・・。
他人に正義のヤイバが向けられると、攻撃力は強くなる。
それは「自分は正しいことをしているのに」と、自分側の正義にのみ心を奪われるからだと思う。
僕は最近、持ち歩き用の箸を持参している。
生徒さんからいただいたお箸だ。
持参の理由は、森林伐採や、地球環境を考えた強い信念で、と言いたいところだが、僕は、エセ・エコロジストです。
なぜなら、カバンに忍ばせている箸を忘れて、「いただきます」と言うやいなや、割り箸をパチンと割ってしまう。
環境問題にしっかりと取り組んでいる人からすれば、許せないたぐいの話かもしれませんが・・・・・。
今年(2007年)の夏至の日に、「てんつくマン」の呼びかけに協賛して、日本メンタルヘルス協会も「キャンドルナイト」に参加した。
毎日恒例の食事会を開かず、カウンセリング講座の受講生に一週間前からキャンドルをプレゼントした。
僕もその日は名古屋のホテルに宿泊だったので、なるべく電力は使わず(音楽は聴いたので、まったくではない)、ホテルの部屋でゆっくり過ごした。
僕は仲間に「やれる範囲でね」と呼びかけた。
なぜなら、カウンセラーをやっていると、完璧を求める人は、不完全な自分に落ち込むことを知っているからだ。
完璧な運動を求める人は、完璧な活動をしない人を責める。
正しさで始まった仲間との運動も、仲間を攻め合い、途中で空中分解するケースが多い。
自分の完璧を求める心が、他人に怒りをぶつけてしまう。
「正義論」で来るから、責めている人も、責められる人も、互いに許したり、自分の意見を述べるという逃げ道がない。
奥さんが正しさを武器にするため、ご主人が口を閉ざしてしまうケースも多いし、その逆に、正論でくるご主人に、忍耐している奥さんも少なくない。
どちらも楽しくない。
人間は理屈で動く動物ではなく、感じて動く動物だからです。
ある講演会で、僕は幸せというのは、
「白亜の豪邸に住むことでも、豪華な五つ星のレストランで毎日食事することでも、六本木ヒルズでオフィスを構えることでもなく、」本当の幸せとは、今の日常の生活に幸せを感じ、 「陽が昇ることに、周囲や自分が健康なことに、今日も平和なことに、奥さんが作る何気ないお弁当に」 幸せを感じることですよ
と、話をしたことがあります。
数日後に届いた手紙に、女性解放運動家の方から、
「衛藤さんは、“奥様がお弁当を作る”と安易に言われましたが、奥さん=お弁当。そのような考えが日本の女性達を解放できないのです。お見受けしたところ講演者としては、お若いので仕方がないのでしょうが、人生勉強が足らないように思われます。」
僕はこれには、驚きました。
僕の話は「幸せとは」であって、「女性のあり方」を語った訳ではないのです。
もし僕が
「奥さんが、お弁当を作るべきです。ご主人にお弁当を作らせる女性は最低です!」
と語ったなら、この手紙の怒りは理解できるのですが・・・・。
まるで、重箱の隅をつついたような非難だった。
何かに怒っている人は、キッカケは何でもいい。
怒りをある人に向けることが目的だから。
不思議なのは怒っている人は、自分が正しいことを言っているという正義の側に立つので、自分が何に怒っているのかという、自分自身の感情には目を向けない。
ただ、私は正しい、相手が間違っているという気持ちが感情全体を支配する。
僕はあわてて「そんなつもりではない旨を伝えよう」と手紙を出そうとしたが、そんな人に限って、住所も氏名も無記なのです。
まるで、言いたいことを伝えて、苛立ちを一方的に発散したかったとでも言うように、こちらの意見は一切聞かない。
正義の権化になると問答無用になります。
僕としては、頭を突然殴られて、走って逃げられたような心境でした。なにより、女性解放を語りながら、「お若い」からとか、「お年寄り」だからと、ジェネレーション・ハラスメントをしている自分自身のことには気づいていない。
僕は、講演者が話す話は、一般論として聞いている。
僕の子供は一歳の時に、小児ガンで大学病院に入院したが、一般に「こんな生活はガンになる」と言う類の話はどこにいても、よく聞く話しだ。
テレビでも、講演会でも、「子供に、こんなジャンク・フードを食べさせると、子供はガンになります」とか、「親がこんな生活だと、子供はガンになります」と聞いても、それは、一般論として可能性があるということで、「そうなんだろうなぁ」と納得して聞いています。
僕は「子供にはそんな物は食べさせていないし、僕たちは、そんな不摂生な生活はしてはいなかった」と怒りの手紙を書くこともありません。
それは、僕に向けられた話ではなく、一般論としての話ですから。
また、テレビ局に「すべてのガンがそういう訳ではないでしょう」とクレームを言う気にもならない。
なぜなら、報道関係者も「そのお怒りは分かります。申し訳ありません。これは一般論としての話ですから・・・」とクレームを入れた人を肯定するしかない訳ですから。
それ以上には何もない。
もちろん、クレームを言う人が「私が正しい人だと認めてほしいの」「自分は立派な人だと認めさせたいの」と自覚しているのなら、話は変わります。
なぜなら、人にはいろんな楽しみ方があるからです。
問題なのは、苛立ちの本当の意味を知らないで、他人を裁く正義の権化と化した、その人のパーソナリティです。
一般にこのような人は、子供にも、恋人にも、部下にも正義をヨロイに容赦なく相手を責めます。
そのため、大切な仲間から「また、はじまった」と嫌われているか、その人が怖いから多くの人々は従順に服従し、その中でお山の大将になることが多い。
僕は思う。
人は正義で責めあうと、誰もが、不完全な存在だから、生きにくい人間社会になると。
もちろん、情報を出す側の配慮と気遣いは必要なのです。
「白亜の豪邸に住むことでも、豪華な五つ星のレストランで毎日食事することでも、六本木ヒルズでオフィスを構えることでもなく、」本当の幸せとは、今の日常の生活に幸せを感じ、 「陽が昇ることに、周囲や自分が健康なことに、今日も平和なことに、奥さんが作る何気ないお弁当に」 幸せを感じることですよ
と、話をしたことがあります。
数日後に届いた手紙に、女性解放運動家の方から、
「衛藤さんは、“奥様がお弁当を作る”と安易に言われましたが、奥さん=お弁当。そのような考えが日本の女性達を解放できないのです。お見受けしたところ講演者としては、お若いので仕方がないのでしょうが、人生勉強が足らないように思われます。」
僕はこれには、驚きました。
僕の話は「幸せとは」であって、「女性のあり方」を語った訳ではないのです。
もし僕が
「奥さんが、お弁当を作るべきです。ご主人にお弁当を作らせる女性は最低です!」
と語ったなら、この手紙の怒りは理解できるのですが・・・・。
まるで、重箱の隅をつついたような非難だった。
何かに怒っている人は、キッカケは何でもいい。
怒りをある人に向けることが目的だから。
不思議なのは怒っている人は、自分が正しいことを言っているという正義の側に立つので、自分が何に怒っているのかという、自分自身の感情には目を向けない。
ただ、私は正しい、相手が間違っているという気持ちが感情全体を支配する。
僕はあわてて「そんなつもりではない旨を伝えよう」と手紙を出そうとしたが、そんな人に限って、住所も氏名も無記なのです。
まるで、言いたいことを伝えて、苛立ちを一方的に発散したかったとでも言うように、こちらの意見は一切聞かない。
正義の権化になると問答無用になります。
僕としては、頭を突然殴られて、走って逃げられたような心境でした。なにより、女性解放を語りながら、「お若い」からとか、「お年寄り」だからと、ジェネレーション・ハラスメントをしている自分自身のことには気づいていない。
僕は、講演者が話す話は、一般論として聞いている。
僕の子供は一歳の時に、小児ガンで大学病院に入院したが、一般に「こんな生活はガンになる」と言う類の話はどこにいても、よく聞く話しだ。
テレビでも、講演会でも、「子供に、こんなジャンク・フードを食べさせると、子供はガンになります」とか、「親がこんな生活だと、子供はガンになります」と聞いても、それは、一般論として可能性があるということで、「そうなんだろうなぁ」と納得して聞いています。
僕は「子供にはそんな物は食べさせていないし、僕たちは、そんな不摂生な生活はしてはいなかった」と怒りの手紙を書くこともありません。
それは、僕に向けられた話ではなく、一般論としての話ですから。
また、テレビ局に「すべてのガンがそういう訳ではないでしょう」とクレームを言う気にもならない。
なぜなら、報道関係者も「そのお怒りは分かります。申し訳ありません。これは一般論としての話ですから・・・」とクレームを入れた人を肯定するしかない訳ですから。
それ以上には何もない。
もちろん、クレームを言う人が「私が正しい人だと認めてほしいの」「自分は立派な人だと認めさせたいの」と自覚しているのなら、話は変わります。
なぜなら、人にはいろんな楽しみ方があるからです。
問題なのは、苛立ちの本当の意味を知らないで、他人を裁く正義の権化と化した、その人のパーソナリティです。
一般にこのような人は、子供にも、恋人にも、部下にも正義をヨロイに容赦なく相手を責めます。
そのため、大切な仲間から「また、はじまった」と嫌われているか、その人が怖いから多くの人々は従順に服従し、その中でお山の大将になることが多い。
僕は思う。
人は正義で責めあうと、誰もが、不完全な存在だから、生きにくい人間社会になると。
もちろん、情報を出す側の配慮と気遣いは必要なのです。
ただ、一般論だと言う話もあるのです。
テレビで「日本のお父さんは・・・」と言う場合。
すべての日本のお父さんが“そう”だ、と言い切られるのは、「過度の一般化」だとは思うけれど、僕は苛立ちはしない。
なぜなら、それは一般論の話だろうからです。
でも、自分だけに意識が敏感に向く人は、自分が否定された気になります。
被害妄想も、このような心理状態の一種です。
そのような人が、正義の武器を手にすると、勢い感情的になるのです。
そして、テレビ局にクレームを入れる。
日常的に穏やかな人は、怒ることと、受け流すことが、ハッキリしている。
そして、いつも大らかに笑っているから、子供からも周囲からも嫌われはしない。
自分の正義にのみ意識が向くと、「相手はそんな気持ちで言ったのではなかったのかもしれないなぁ」という余裕がなくなる。
正義のために、国のために、愛のために、と大義名分を持つと「自分の正論」しか見えなくなる。
だから、それぞれの正しさを信じるテロも戦争も終わらない。
この怒りの連鎖を止める方法は、勝ち負けのゲームから降りるしかない。
和歌山のカレー混入事件の容疑者の自宅の塀に、おびただしく罵詈雑言が書かれていた。
「悪魔の住む家」「鬼畜!出てゆけ」などが所狭しと書かれていた。
そこには、当時、なんの罪のない容疑者の子供が住んでいたことや、子供たちの心の傷などは想像もしない。
松本サリン事件で、疑われた河野さんご夫妻の家に、「悪魔出て行け!」と石を投げたのは、正義の一般人です。
後に、それがカルト化したオウム真理教だと分かると、反省も無く、新聞が悪いと、自分の見方の偏りを反省することもしない。
中国の孔子も、このように良いとか悪いとかで人を決め付ける良識者や、一般的常識人の怖さを一番恐れた。
中世の魔女裁判の魔女狩りで一般の人々が多く血祭りにあげられた。
その恐怖も正義心から生まれた。
正義を叫ぶ人によって、誰かの心が傷つけられてゆく。
イラクで人質になった若者と家族に、罵声を浴びせたのも、マスコミに煽られ、国の正義を信じた人々です。
そして、戦争を始める人々も、自国の正義の御旗に集まるのです。
今、話題になっているモンスター・ペアレントと呼ばれ、学校に対して非常識なクレームを入れる親も、根っこのところではつながっています。
「卒業アルバムにのっているうちの子供の写真が、他の子供より少なくて傷ついている。学校教育は平等であるべきでしょう。すぐにアルバムをつくり直せ!」
「学校の呼び出しに応じたために、会社を休んだ。休業補償を請求します!」
「学校で子供の携帯電話を取りあげられた、その携帯が使えない時間帯の電話代は、先生に支払ってほしい」
などなど。
こんな話を聞くと、耳を疑うが、自分は間違っていない、自分は子供を守るために戦っていると、信じて疑わないのです。
近所の迷惑を考えないでゴミを収集する、ゴミ屋敷の問題。
近所に対して嫌がらせをする変わり者は、毎日のようにテレビに出てくる。
お騒がせの人々に共通するのは「自分は間違っていない!」と金切り声をあげるのだと警察の人は首をかしげていた。
共通するのは自分だけの見方。
自分だけの正義を疑わない人々です。
今、世界に起こっている戦争の問題も自分を疑っていない。
今の時代、大切なことは、自分の正しさを疑う時代なのかもしれません。
仏さまのおでこにあるチャクラは第三の目とも呼ばれています。
それは、自分を見つめる目だそうです。
最後に必要になるのは、自分が正しいと思っている正義のよりどころを客観的に見つめ、自分を疑ってみることです。
自分の正しさは絶対なのか?
自分も知らないで人を傷つけることはないか?
自分の間違いは許すけど、他人の間違いを許せないのは、人生を楽しんでいないからではないかと、自分に訊ねてみるのも良いでしょう。
洞察の目を向けることが大切なのです。
ただし、自分を疑い、自分を責めて、うつ病になっている人には必要ありませんが(重箱の隅の、読者のクレーム用のただし書き・・・・)、人を責めたくなった時には、自分を客観的に冷静に見つめる心の目を持ちたいですね。
ニーチェは世界が深いと言いました。
心の世界は、単純に「正義」と「悪」という二元論ではなく、自分も他人においても、人は複雑なしがらみの中で生きているという優しい眼差しを持ちたいですね。
テレビで「日本のお父さんは・・・」と言う場合。
すべての日本のお父さんが“そう”だ、と言い切られるのは、「過度の一般化」だとは思うけれど、僕は苛立ちはしない。
なぜなら、それは一般論の話だろうからです。
でも、自分だけに意識が敏感に向く人は、自分が否定された気になります。
被害妄想も、このような心理状態の一種です。
そのような人が、正義の武器を手にすると、勢い感情的になるのです。
そして、テレビ局にクレームを入れる。
日常的に穏やかな人は、怒ることと、受け流すことが、ハッキリしている。
そして、いつも大らかに笑っているから、子供からも周囲からも嫌われはしない。
自分の正義にのみ意識が向くと、「相手はそんな気持ちで言ったのではなかったのかもしれないなぁ」という余裕がなくなる。
正義のために、国のために、愛のために、と大義名分を持つと「自分の正論」しか見えなくなる。
だから、それぞれの正しさを信じるテロも戦争も終わらない。
この怒りの連鎖を止める方法は、勝ち負けのゲームから降りるしかない。
和歌山のカレー混入事件の容疑者の自宅の塀に、おびただしく罵詈雑言が書かれていた。
「悪魔の住む家」「鬼畜!出てゆけ」などが所狭しと書かれていた。
そこには、当時、なんの罪のない容疑者の子供が住んでいたことや、子供たちの心の傷などは想像もしない。
松本サリン事件で、疑われた河野さんご夫妻の家に、「悪魔出て行け!」と石を投げたのは、正義の一般人です。
後に、それがカルト化したオウム真理教だと分かると、反省も無く、新聞が悪いと、自分の見方の偏りを反省することもしない。
中国の孔子も、このように良いとか悪いとかで人を決め付ける良識者や、一般的常識人の怖さを一番恐れた。
中世の魔女裁判の魔女狩りで一般の人々が多く血祭りにあげられた。
その恐怖も正義心から生まれた。
正義を叫ぶ人によって、誰かの心が傷つけられてゆく。
イラクで人質になった若者と家族に、罵声を浴びせたのも、マスコミに煽られ、国の正義を信じた人々です。
そして、戦争を始める人々も、自国の正義の御旗に集まるのです。
今、話題になっているモンスター・ペアレントと呼ばれ、学校に対して非常識なクレームを入れる親も、根っこのところではつながっています。
「卒業アルバムにのっているうちの子供の写真が、他の子供より少なくて傷ついている。学校教育は平等であるべきでしょう。すぐにアルバムをつくり直せ!」
「学校の呼び出しに応じたために、会社を休んだ。休業補償を請求します!」
「学校で子供の携帯電話を取りあげられた、その携帯が使えない時間帯の電話代は、先生に支払ってほしい」
などなど。
こんな話を聞くと、耳を疑うが、自分は間違っていない、自分は子供を守るために戦っていると、信じて疑わないのです。
近所の迷惑を考えないでゴミを収集する、ゴミ屋敷の問題。
近所に対して嫌がらせをする変わり者は、毎日のようにテレビに出てくる。
お騒がせの人々に共通するのは「自分は間違っていない!」と金切り声をあげるのだと警察の人は首をかしげていた。
共通するのは自分だけの見方。
自分だけの正義を疑わない人々です。
今、世界に起こっている戦争の問題も自分を疑っていない。
今の時代、大切なことは、自分の正しさを疑う時代なのかもしれません。
仏さまのおでこにあるチャクラは第三の目とも呼ばれています。
それは、自分を見つめる目だそうです。
最後に必要になるのは、自分が正しいと思っている正義のよりどころを客観的に見つめ、自分を疑ってみることです。
自分の正しさは絶対なのか?
自分も知らないで人を傷つけることはないか?
自分の間違いは許すけど、他人の間違いを許せないのは、人生を楽しんでいないからではないかと、自分に訊ねてみるのも良いでしょう。
洞察の目を向けることが大切なのです。
ただし、自分を疑い、自分を責めて、うつ病になっている人には必要ありませんが(重箱の隅の、読者のクレーム用のただし書き・・・・)、人を責めたくなった時には、自分を客観的に冷静に見つめる心の目を持ちたいですね。
ニーチェは世界が深いと言いました。
心の世界は、単純に「正義」と「悪」という二元論ではなく、自分も他人においても、人は複雑なしがらみの中で生きているという優しい眼差しを持ちたいですね。
喜多川泰の徒然日記より。
無財の七施
ずっと前にこのブログでも紹介しましたが
お釈迦様の教えに
「無財の七施」というのがあります
自分にお金がなくても、物がなくても相手に喜びを与える方法があるという教えが
この「無財の七施」
一、眼施(やさしい眼で人に接する)
二、和顔施(にこやかな顔で接する)
三、言辞施(優しい言葉で接する)
四、身施(自分の身体でできることを奉仕する)
五、心施(相手の人の心になって思いやる)
六、床座施(席を譲る)
七、房舎施(自分の家を提供する)
あらゆるものごとがつながり合ってできているという
「縁起」という世界観においては
人間同士だけでなく、すべての生物において
助け合い、支え合いの中でしか生物は生きていられないということを
教えられます。
いま、「助け合い」という言葉が
多く聞かれます
被災地の方のために何ができるかを考えるのと同じくらい
今自分のいる場所で
自分の周りの人に何ができるのかを考えるのは
とても大切なこと。
あらゆるものはつながりあって生きているのだから
本当の助け合いとは
「あげた相手を忘れ、あげた品物も忘れ、あげたこの私自身を忘れ得ること」
だと言います。
たった一つでもいいから
実行してみようとする心が
少しだけこの国を明るくします。
それは小さな光だけど
みんなでやれば大きな光になります。
不安ではなく、安心を与える
そんな一隅を照らす人でいよう!
無財の七施
ずっと前にこのブログでも紹介しましたが
お釈迦様の教えに
「無財の七施」というのがあります
自分にお金がなくても、物がなくても相手に喜びを与える方法があるという教えが
この「無財の七施」
一、眼施(やさしい眼で人に接する)
二、和顔施(にこやかな顔で接する)
三、言辞施(優しい言葉で接する)
四、身施(自分の身体でできることを奉仕する)
五、心施(相手の人の心になって思いやる)
六、床座施(席を譲る)
七、房舎施(自分の家を提供する)
あらゆるものごとがつながり合ってできているという
「縁起」という世界観においては
人間同士だけでなく、すべての生物において
助け合い、支え合いの中でしか生物は生きていられないということを
教えられます。
いま、「助け合い」という言葉が
多く聞かれます
被災地の方のために何ができるかを考えるのと同じくらい
今自分のいる場所で
自分の周りの人に何ができるのかを考えるのは
とても大切なこと。
あらゆるものはつながりあって生きているのだから
本当の助け合いとは
「あげた相手を忘れ、あげた品物も忘れ、あげたこの私自身を忘れ得ること」
だと言います。
たった一つでもいいから
実行してみようとする心が
少しだけこの国を明るくします。
それは小さな光だけど
みんなでやれば大きな光になります。
不安ではなく、安心を与える
そんな一隅を照らす人でいよう!
心にビタミン「いい話」vol.001
『一流とはどういうことか』
ある人が、船井総合研究所の最高顧問船井幸雄さんに、「一流とはどういうことですか?」と尋ねました。船井さんは、こう答えられたといいます。
「例えば、飛行機に乗ったとき。ファーストクラスのトイレを覗いてご覧なさい。手洗いには、水滴一つ撥ねていません。使った人が後の人のことを考えて、丁寧に拭いてから出てくるからですね。エコノミー席のトイレと見比べてみるとよくわかります」
さらに、
「ホテルのスウィートルームでも同じです。チェックアウトする時、スウィートルームのお客さんは、まるで使っていないかのようにベッドの掛け布団を元通りにして部屋を出て行きます。それが、一流ということなのです」
この話を聞いて、ハッと思い当たることがありました。
飛行機のビジネスクラスを利用して、オーストラリアを旅した時のことです。帰りにシドニー空港の待合室で、出発までの時間を過ごしました。この空港には、ビジネスクラスとファーストクラスのお客様専用の待合室があります。そこには飲み物の他、サンドウィッチやフルーツ等の軽食が用意されていました。
(何か美味しそうなものはあるかな…)と、ビュッフェを見て回っていると、一人の女性がツカツカと私の方に向かって歩いて来ました。
正直、ドキッとしました。自慢じゃありませんが、英語はからきし自信がありません。
相手は、五〇歳くらいでしょうか。いかにもイギリスの貴婦人という出で立ちで、高級品を身にまとっていました。映画でいうなら、「マイフェアレディ」のオードリー・ヘップバーンのイメージです。歩き方一つとっても優雅な雰囲気を醸し出しています。
彼女は私の目の前で立ち止まりました。すると、テーブルのナプキンを一枚手に取るなり、スッと屈んだのです。そして、床に落ちいていた「何か」を拾ったのでした。その「何か」とはキウイフルーツでした。誰かが取りそこなって、落としてしまったのでしょう。驚いたのはその後です。
彼女は、床を何度もキュキュッと音をたてて拭いた後、そのべとべとしたナプキンを自分の上着のポケットに何気なく仕舞ったのです。一流とはそういうことなのですね。大企業の経営者だから一流なのではありません。お金持ちだから一流なのではないのです。日頃の振る舞いが一流だから、成功を手にしているのです。
呆然とする私の顔を見て微笑んで一言。
「イッツ・デンジェラス」
いくら英語オンチでもそのくらいは理解できました。目の前に落ちいていたキウイフルーツに気づかなかった私は、返す言葉もありませんでした。
『一流とはどういうことか』
ある人が、船井総合研究所の最高顧問船井幸雄さんに、「一流とはどういうことですか?」と尋ねました。船井さんは、こう答えられたといいます。
「例えば、飛行機に乗ったとき。ファーストクラスのトイレを覗いてご覧なさい。手洗いには、水滴一つ撥ねていません。使った人が後の人のことを考えて、丁寧に拭いてから出てくるからですね。エコノミー席のトイレと見比べてみるとよくわかります」
さらに、
「ホテルのスウィートルームでも同じです。チェックアウトする時、スウィートルームのお客さんは、まるで使っていないかのようにベッドの掛け布団を元通りにして部屋を出て行きます。それが、一流ということなのです」
この話を聞いて、ハッと思い当たることがありました。
飛行機のビジネスクラスを利用して、オーストラリアを旅した時のことです。帰りにシドニー空港の待合室で、出発までの時間を過ごしました。この空港には、ビジネスクラスとファーストクラスのお客様専用の待合室があります。そこには飲み物の他、サンドウィッチやフルーツ等の軽食が用意されていました。
(何か美味しそうなものはあるかな…)と、ビュッフェを見て回っていると、一人の女性がツカツカと私の方に向かって歩いて来ました。
正直、ドキッとしました。自慢じゃありませんが、英語はからきし自信がありません。
相手は、五〇歳くらいでしょうか。いかにもイギリスの貴婦人という出で立ちで、高級品を身にまとっていました。映画でいうなら、「マイフェアレディ」のオードリー・ヘップバーンのイメージです。歩き方一つとっても優雅な雰囲気を醸し出しています。
彼女は私の目の前で立ち止まりました。すると、テーブルのナプキンを一枚手に取るなり、スッと屈んだのです。そして、床に落ちいていた「何か」を拾ったのでした。その「何か」とはキウイフルーツでした。誰かが取りそこなって、落としてしまったのでしょう。驚いたのはその後です。
彼女は、床を何度もキュキュッと音をたてて拭いた後、そのべとべとしたナプキンを自分の上着のポケットに何気なく仕舞ったのです。一流とはそういうことなのですね。大企業の経営者だから一流なのではありません。お金持ちだから一流なのではないのです。日頃の振る舞いが一流だから、成功を手にしているのです。
呆然とする私の顔を見て微笑んで一言。
「イッツ・デンジェラス」
いくら英語オンチでもそのくらいは理解できました。目の前に落ちいていたキウイフルーツに気づかなかった私は、返す言葉もありませんでした。
「祝婚歌」
二人が睦(むつ)まじくいるためには
愚かでいるほうがいい
立派すぎないほうがいい
立派すぎることは
長持ちしないことだと気付いているほうがいい
完璧をめざさないほうがいい
完璧なんて不自然なことだと
うそぶいているほうがいい
二人のうちどちらかが
ふざけているほうがいい
ずっこけているほうがいい
互いに非難することがあっても
非難できる資格が自分にあったかどうか
あとで
疑わしくなるほうがいい
正しいことを言うときは
少しひかえめにするほうがいい
正しいことを言うときは
相手を傷つけやすいものだと
気付いているほうがいい
立派でありたいとか
正しくありたいとかいう
無理な緊張には
色目を使わず
ゆったり ゆたかに
光を浴びているほうがいい
健康で 風に吹かれながら
生きていることのなつかしさに
ふと 胸が熱くなる
そんな日があってもいい
そして
なぜ胸が熱くなるのか
黙っていても
二人にはわかるのであってほしい
(『吉野 弘 詩集』より)
二人が睦(むつ)まじくいるためには
愚かでいるほうがいい
立派すぎないほうがいい
立派すぎることは
長持ちしないことだと気付いているほうがいい
完璧をめざさないほうがいい
完璧なんて不自然なことだと
うそぶいているほうがいい
二人のうちどちらかが
ふざけているほうがいい
ずっこけているほうがいい
互いに非難することがあっても
非難できる資格が自分にあったかどうか
あとで
疑わしくなるほうがいい
正しいことを言うときは
少しひかえめにするほうがいい
正しいことを言うときは
相手を傷つけやすいものだと
気付いているほうがいい
立派でありたいとか
正しくありたいとかいう
無理な緊張には
色目を使わず
ゆったり ゆたかに
光を浴びているほうがいい
健康で 風に吹かれながら
生きていることのなつかしさに
ふと 胸が熱くなる
そんな日があってもいい
そして
なぜ胸が熱くなるのか
黙っていても
二人にはわかるのであってほしい
(『吉野 弘 詩集』より)
『悩める人々への銘』
大きなことを成し遂げる為に、
強さを求めたのに
謙遜を学ぶようにと弱さを授かった
偉大なことをできるようにと
健康を求めたのに
より良きことをするようにと病気を賜った
幸せになろうとして 富を求めたのに
賢明であるようにと 貧困を授かった
世に人々の賞賛を得ようと 成功を求めたのに
得意にならないようにと 失敗を授かった
人生を楽しむために あらゆるものを求めたのに
あらゆるものを慈しむために 人生を賜った
求めたものは一つとして与えられなかったが
願いはすべて聞き届けられた
私はもっとも豊かに祝福されたのだ
作者不詳
(加藤諦三著『無名兵士の言葉』より)
大きなことを成し遂げる為に、
強さを求めたのに
謙遜を学ぶようにと弱さを授かった
偉大なことをできるようにと
健康を求めたのに
より良きことをするようにと病気を賜った
幸せになろうとして 富を求めたのに
賢明であるようにと 貧困を授かった
世に人々の賞賛を得ようと 成功を求めたのに
得意にならないようにと 失敗を授かった
人生を楽しむために あらゆるものを求めたのに
あらゆるものを慈しむために 人生を賜った
求めたものは一つとして与えられなかったが
願いはすべて聞き届けられた
私はもっとも豊かに祝福されたのだ
作者不詳
(加藤諦三著『無名兵士の言葉』より)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
mixi図書館 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-