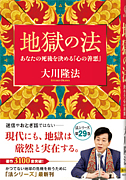幸福の法、第三章 人間を幸福にする四つの原理、四正道を紹介します。
副題として、――現代的四正道「愛」「知」「反省」「発展」となっております。
なお、幸福の法はこちら。
http://
副題として、――現代的四正道「愛」「知」「反省」「発展」となっております。
なお、幸福の法はこちら。
http://
|
|
|
|
コメント(9)
第3章 人間を幸福にする四つの原理――現代的四正道「愛」「知」「反省」「発展」
1 悩みから脱出するための四つの方法(P132)
本章では、「人間を幸福にする四つの原理」と題して、幸福の科学で説かれている「幸福の原理」についての話をします。
ただ、幸福の原理には、かなり数多くの教え、理論が派生しているので、ここではそのすべてについての話ではなく、初心者にも分かり、また、仏法真理を勉強してきた人にとっては伝道の切り口になるような、分かりやすい話をしたいと思います。
ここで述べる四つの原理は、単に頭で考えた空想的な話ではなく、私自身の実体験を踏まえたものです。そして、「人間を幸福にする四つの原理」と言いつつも、これは実は、「悟りに到る四つの道」でもあるのです。「悟りに到る四つの道」ということは、裏を返せば、「苦悩、悩みから脱出するための四つの方法」ということでもあります。
その代表的な事柄について述べてみたいと思います。
1 悩みから脱出するための四つの方法(P132)
本章では、「人間を幸福にする四つの原理」と題して、幸福の科学で説かれている「幸福の原理」についての話をします。
ただ、幸福の原理には、かなり数多くの教え、理論が派生しているので、ここではそのすべてについての話ではなく、初心者にも分かり、また、仏法真理を勉強してきた人にとっては伝道の切り口になるような、分かりやすい話をしたいと思います。
ここで述べる四つの原理は、単に頭で考えた空想的な話ではなく、私自身の実体験を踏まえたものです。そして、「人間を幸福にする四つの原理」と言いつつも、これは実は、「悟りに到る四つの道」でもあるのです。「悟りに到る四つの道」ということは、裏を返せば、「苦悩、悩みから脱出するための四つの方法」ということでもあります。
その代表的な事柄について述べてみたいと思います。
2 「奪う愛」の苦しみからの脱却(愛の原理)(P133)
「評価されていない」という苦しみ
一番目に、「『奪う愛』の苦しみからの脱却」ということを述べたいと思います。
世の中の人々の苦しみを見ていると、たいていの場合は、欲しいと思うものが手に入らないことによる苦しみです。
「欲しいと思うものが手に入らない」という苦しみは、結局「自分は他の人から愛されていない。評価されていない」という苦しみなのです。
精神的なものであれば、人の優しい言葉や気持ち、扱いであったり、名誉や肩書などであったりするでしょう。物質的なものであれば、食べる物、着る物から始まって、お金や、その他、車とか、家とか、いろいろあります。これらも、自分自身で手に入れるというよりは、まわりから与えられるという要素も多分にあるので、そういう点を強く見ていくと、苦しみのもとになっていきます。
そのように、現代人の苦しみを見てみると、その多くは、他から与えられていないことに苦しみなのです。
「これだけよく働いているのに、給料が安い」「これだけよく働いているのに、出世が遅い」ということもあれば、「汗水垂らして働いているのに、女房や子供からの評価が悪い」ということもあるでしょう。「こんなに一生懸命、勉強したのに女性にもてない」ということもあるかもしれません。あるいは、「こんなに一生懸命、仕事をしているのに、なかなか才能が生かしきれない」ということもあるでしょう。
苦しみの根源を探ってみると、結局、「自分はこんなにがんばっているのに、自分に対する、まわりの人の評価、あるいは、まわりの人の手を通じての扱いが、非常に悪い」ということに対する欲求不満、得られないことに対する欲求不満だと思うのです。
物質的な面については、ある程度、諦めがつくこともあるのですが、精神的な面、特に人間関係における精神的な面については、苦しみからの脱却は、なかなか難しいものがあります。なぜなら、他の人の気持ちというものは、なかなか自分の自由にならないからです。
ちょうど都合よく、自分が「この人に評価してほしい」と思う人が、自分を評価してくれたり、自分が「この人に愛されたい」と思う人が、自分を愛してくれたりはしないものです。その反対に、自分が「こんな人から評価を受けたくない」と思う人が、自分を評価してくれたり、自分が「こんな人は嫌いだ」と思う人が、自分を好きになってきたりするものです。これが世の中の常なのです。
こういうことがあって、なかなか思うようにいかないのです。
「評価されていない」という苦しみ
一番目に、「『奪う愛』の苦しみからの脱却」ということを述べたいと思います。
世の中の人々の苦しみを見ていると、たいていの場合は、欲しいと思うものが手に入らないことによる苦しみです。
「欲しいと思うものが手に入らない」という苦しみは、結局「自分は他の人から愛されていない。評価されていない」という苦しみなのです。
精神的なものであれば、人の優しい言葉や気持ち、扱いであったり、名誉や肩書などであったりするでしょう。物質的なものであれば、食べる物、着る物から始まって、お金や、その他、車とか、家とか、いろいろあります。これらも、自分自身で手に入れるというよりは、まわりから与えられるという要素も多分にあるので、そういう点を強く見ていくと、苦しみのもとになっていきます。
そのように、現代人の苦しみを見てみると、その多くは、他から与えられていないことに苦しみなのです。
「これだけよく働いているのに、給料が安い」「これだけよく働いているのに、出世が遅い」ということもあれば、「汗水垂らして働いているのに、女房や子供からの評価が悪い」ということもあるでしょう。「こんなに一生懸命、勉強したのに女性にもてない」ということもあるかもしれません。あるいは、「こんなに一生懸命、仕事をしているのに、なかなか才能が生かしきれない」ということもあるでしょう。
苦しみの根源を探ってみると、結局、「自分はこんなにがんばっているのに、自分に対する、まわりの人の評価、あるいは、まわりの人の手を通じての扱いが、非常に悪い」ということに対する欲求不満、得られないことに対する欲求不満だと思うのです。
物質的な面については、ある程度、諦めがつくこともあるのですが、精神的な面、特に人間関係における精神的な面については、苦しみからの脱却は、なかなか難しいものがあります。なぜなら、他の人の気持ちというものは、なかなか自分の自由にならないからです。
ちょうど都合よく、自分が「この人に評価してほしい」と思う人が、自分を評価してくれたり、自分が「この人に愛されたい」と思う人が、自分を愛してくれたりはしないものです。その反対に、自分が「こんな人から評価を受けたくない」と思う人が、自分を評価してくれたり、自分が「こんな人は嫌いだ」と思う人が、自分を好きになってきたりするものです。これが世の中の常なのです。
こういうことがあって、なかなか思うようにいかないのです。
親への欲求不満は、大人になっても根っことして残る。
特に、人との関係という意味での愛は、男女の愛もあれば、それ以外の人間関係での愛もあると思いますが、そこでの苦しみは、たいていの場合、仏教の根本に否定されている、喉の奥から手が出てくるような渇愛、妄執とでもいうような苦しみなのです。
それは、他の人に対する、「こうしてほしい。ああしてほしい」という思いです。それには、異性に対するものもあるでしょう。また、子供であれば、「自分の親に、こうしてほしい」という思いや、「自分の親に、もう少し力があったら、よかったのに」という思いもあるでしょう。
あるいは、すでに子供ではなく、十分、大人になっていても、「少なくとも、自分の現在の苦しみの原因は、子供時代に、自分の親に力がなかったことだ」というような場合もあります。
「親に経済力がなかった」「親が偉くなかった」「親が田舎者であった」ということもあれば、「親が、すでに年をとっていた」「親が病気であった」ということもあります。あるいは、「親が離婚していた」「親が別居していた」「親の片方が死んでいて、片親であった」「親が外に愛人をつくっていて、家庭に波風が立っていた」ということもあります。
そのようなことで、子供時代に、親に対する、いろいろな欲求不満があり、充足されなかったという場合もあるのです。大人になっても、それが根っこになって残っているわけです。
この部分は、埋められるかというと、なかなか埋められないのです。
たとえば、二十歳までの自分の育ち方について、「親に、こうであってほしかったのに」と思うかもしれません。しかし、親は親で、子供が二十歳になる時代には、すでに「有」の状態、固まった状態になっていて、人生が決まっているのです。子供が成長する過程で、親の人生は決まってしまいます。親だって、人生をやり直せるのだったら、やり直したいぐらいなのです。ところが、膠のように固まった人生になってしまっているのです。
親は子供に対して、「おれのところに生まれたのが不運だと思ってくれ」というぐらいのことは言えるかもしれませんが、すでに生まれ育った子供の育ち方を、いまさら変えることはできません。
したがって、子供のほうは、この部分について充足されたいと思っても、充足されることは、ほとんどないのです。
こういう、幼少時、子供時代に自分が満たされなかった欲求不満のようなものが、社会人になってから、違ったかたちで表れることがあります。本来は親に対して求めていたものを、たとえば、上司、上役に対して求めたりするのです。親に求めていたのと同じような評価を、親の代わりに、会社の部長や社長、役員などに求めたがるわけです。
ところが、そのような振り替えをしても、たいていの場合、親に対して、欲求不満を持ったのと同じように、また欲求不満になります。自分が思っているようには満たされないのです。
それは、そのはずなのです。会社には、たくさんの社員がいて、課長や部長、社長などは、数名、数十名、数百名、あるいは、それ以上の大勢の部下を養っています。そして、たとえば、子だくさんの家庭で、親が「子供を公平に扱わなくてはならない」と思っているのと同じように、会社で、上司はみな、「部下に対して、あまり好き嫌いをはっきりさせてはいけない」と思っているものです。上司が部下に対して、あまり好き嫌いをはっきりさせると、全体の士気が落ちるので、上司はなるべく、そうならないようにしようと努力しています。
そのため、ある人が、「自分だけが独占的に上司から愛されたい」と強く願っても、十中八九、その試みは失敗に終わります。たいてい成功しないのです。
上司が、その人だけを特別に持ち上げて、偉くしてくれるようなことは、あまりありません。また、たまたま、そういうことがあったとしても、その人は、まわりからの嫉妬や悪口など、いろいろなものを受けて挫折しがちなのです。
一人だけが非常に評価されると、その人は、だいたい、まわりから悪口や陰口を言われ、中傷されて、それに耐えきれなくなります。「こんなに悪口や陰口を言われるのだったら、もう、あまり上司の評価を受けない方がいいな」という感じになってくるのです。
特に、人との関係という意味での愛は、男女の愛もあれば、それ以外の人間関係での愛もあると思いますが、そこでの苦しみは、たいていの場合、仏教の根本に否定されている、喉の奥から手が出てくるような渇愛、妄執とでもいうような苦しみなのです。
それは、他の人に対する、「こうしてほしい。ああしてほしい」という思いです。それには、異性に対するものもあるでしょう。また、子供であれば、「自分の親に、こうしてほしい」という思いや、「自分の親に、もう少し力があったら、よかったのに」という思いもあるでしょう。
あるいは、すでに子供ではなく、十分、大人になっていても、「少なくとも、自分の現在の苦しみの原因は、子供時代に、自分の親に力がなかったことだ」というような場合もあります。
「親に経済力がなかった」「親が偉くなかった」「親が田舎者であった」ということもあれば、「親が、すでに年をとっていた」「親が病気であった」ということもあります。あるいは、「親が離婚していた」「親が別居していた」「親の片方が死んでいて、片親であった」「親が外に愛人をつくっていて、家庭に波風が立っていた」ということもあります。
そのようなことで、子供時代に、親に対する、いろいろな欲求不満があり、充足されなかったという場合もあるのです。大人になっても、それが根っこになって残っているわけです。
この部分は、埋められるかというと、なかなか埋められないのです。
たとえば、二十歳までの自分の育ち方について、「親に、こうであってほしかったのに」と思うかもしれません。しかし、親は親で、子供が二十歳になる時代には、すでに「有」の状態、固まった状態になっていて、人生が決まっているのです。子供が成長する過程で、親の人生は決まってしまいます。親だって、人生をやり直せるのだったら、やり直したいぐらいなのです。ところが、膠のように固まった人生になってしまっているのです。
親は子供に対して、「おれのところに生まれたのが不運だと思ってくれ」というぐらいのことは言えるかもしれませんが、すでに生まれ育った子供の育ち方を、いまさら変えることはできません。
したがって、子供のほうは、この部分について充足されたいと思っても、充足されることは、ほとんどないのです。
こういう、幼少時、子供時代に自分が満たされなかった欲求不満のようなものが、社会人になってから、違ったかたちで表れることがあります。本来は親に対して求めていたものを、たとえば、上司、上役に対して求めたりするのです。親に求めていたのと同じような評価を、親の代わりに、会社の部長や社長、役員などに求めたがるわけです。
ところが、そのような振り替えをしても、たいていの場合、親に対して、欲求不満を持ったのと同じように、また欲求不満になります。自分が思っているようには満たされないのです。
それは、そのはずなのです。会社には、たくさんの社員がいて、課長や部長、社長などは、数名、数十名、数百名、あるいは、それ以上の大勢の部下を養っています。そして、たとえば、子だくさんの家庭で、親が「子供を公平に扱わなくてはならない」と思っているのと同じように、会社で、上司はみな、「部下に対して、あまり好き嫌いをはっきりさせてはいけない」と思っているものです。上司が部下に対して、あまり好き嫌いをはっきりさせると、全体の士気が落ちるので、上司はなるべく、そうならないようにしようと努力しています。
そのため、ある人が、「自分だけが独占的に上司から愛されたい」と強く願っても、十中八九、その試みは失敗に終わります。たいてい成功しないのです。
上司が、その人だけを特別に持ち上げて、偉くしてくれるようなことは、あまりありません。また、たまたま、そういうことがあったとしても、その人は、まわりからの嫉妬や悪口など、いろいろなものを受けて挫折しがちなのです。
一人だけが非常に評価されると、その人は、だいたい、まわりから悪口や陰口を言われ、中傷されて、それに耐えきれなくなります。「こんなに悪口や陰口を言われるのだったら、もう、あまり上司の評価を受けない方がいいな」という感じになってくるのです。
そうすると、親に認められたかった気持の代償として上司に認められたかったのに、そういう「認められたい」という気持ちは、結局、自分自身で放棄しなければいけなくなってきます。それで、また欲求不満になるのです。
そのように、実社会において認められない場合があるわけですが、「実社会において認められたい」という気持ちは、かなり、父性原理、父親的原理とかかわるものです。「幼少期に、父親に認められなかった」という欲求不満を持っている人は、社会に出ると、会社の上司、あるいは、そういう立場に立つ人に認められたがります。父親に認められなかった部分を、社会での評価のほうに持っていこうとするのです。
しかし、それは、父親に認められなかったのと同じように、たいていなかなかうまくいかないものです。そのときに、どのようにするかというと、幼少時、子供時代において母親に求めていたもののほうへ欲求を移すのです。
たとえば、「子供時代、父は評価してくれなかったが、母は 無限にかわいがってくれた。それで、見事に充足されていた」という場合、救いはあります。子供時代に母の愛を十分に受けた人の場合は、社会に出て、仮に出世しなかったとしても、救いがあるのです。
そういう人の場合は、実社会で成功しなかったときに、家庭に幸福を見出していくことがよくあります。
ただ、「子供時代に、母親からも十分な愛を受けられなかった」という場合もあります。
子供も、一人でなく、二人、三人になってくると、どうしても、親の愛が二分の一、三分の一になってきます。そして、兄弟のなかに、親が特にかわいがる子がいたりすると、ほかの子のほうは、差別されているような気持ちになるのです。
そういう意味で、「子供時代に、父は自分に無関心であった」ということは多いのですが、「母も、自分をあまりかわいがってくれなかった」という場合もあります。「自分は母に、もっともっと、かわいがってほしかったのに、充分に、かわいがってもらえなかった。遊んでもらえなかった。ほめてもらえなかった。スキンシップをとってもらえなかった」ということです。
こういう人は、家庭的な面でも、やはり欲求不満を起こしていきがちです。
子供時代に母親から充分に愛された人は、そういう情愛の深い女性を伴侶として選びたがる傾向があり、そのため、社会において挫折しても、その部分について、傷口を埋めてもらえるというか、くるんでもらえることが多いのですが、子供時代に、家庭において、母の愛というものを充分に受けなかった人は、そういう優しい女性との結婚を、ほんとうは深層心理で望んでいながら、それができないことが多いのです。
そして、そういうタイプの女性ではなく、非常に棘のある、きついタイプ、自分がきずつけられるようなタイプの女性を、あえて好きになります。わざわざ、その正反対のほうの女性に惹かれていくのです。
それで、結婚できなくて傷つけられることも当然ありますが、結婚して傷つけられることもあります。家庭において、また挫折をくり返すのです。結局、幼少時に受けたのと同じような体験をくり返すわけです。
そのように、実社会において認められない場合があるわけですが、「実社会において認められたい」という気持ちは、かなり、父性原理、父親的原理とかかわるものです。「幼少期に、父親に認められなかった」という欲求不満を持っている人は、社会に出ると、会社の上司、あるいは、そういう立場に立つ人に認められたがります。父親に認められなかった部分を、社会での評価のほうに持っていこうとするのです。
しかし、それは、父親に認められなかったのと同じように、たいていなかなかうまくいかないものです。そのときに、どのようにするかというと、幼少時、子供時代において母親に求めていたもののほうへ欲求を移すのです。
たとえば、「子供時代、父は評価してくれなかったが、母は 無限にかわいがってくれた。それで、見事に充足されていた」という場合、救いはあります。子供時代に母の愛を十分に受けた人の場合は、社会に出て、仮に出世しなかったとしても、救いがあるのです。
そういう人の場合は、実社会で成功しなかったときに、家庭に幸福を見出していくことがよくあります。
ただ、「子供時代に、母親からも十分な愛を受けられなかった」という場合もあります。
子供も、一人でなく、二人、三人になってくると、どうしても、親の愛が二分の一、三分の一になってきます。そして、兄弟のなかに、親が特にかわいがる子がいたりすると、ほかの子のほうは、差別されているような気持ちになるのです。
そういう意味で、「子供時代に、父は自分に無関心であった」ということは多いのですが、「母も、自分をあまりかわいがってくれなかった」という場合もあります。「自分は母に、もっともっと、かわいがってほしかったのに、充分に、かわいがってもらえなかった。遊んでもらえなかった。ほめてもらえなかった。スキンシップをとってもらえなかった」ということです。
こういう人は、家庭的な面でも、やはり欲求不満を起こしていきがちです。
子供時代に母親から充分に愛された人は、そういう情愛の深い女性を伴侶として選びたがる傾向があり、そのため、社会において挫折しても、その部分について、傷口を埋めてもらえるというか、くるんでもらえることが多いのですが、子供時代に、家庭において、母の愛というものを充分に受けなかった人は、そういう優しい女性との結婚を、ほんとうは深層心理で望んでいながら、それができないことが多いのです。
そして、そういうタイプの女性ではなく、非常に棘のある、きついタイプ、自分がきずつけられるようなタイプの女性を、あえて好きになります。わざわざ、その正反対のほうの女性に惹かれていくのです。
それで、結婚できなくて傷つけられることも当然ありますが、結婚して傷つけられることもあります。家庭において、また挫折をくり返すのです。結局、幼少時に受けたのと同じような体験をくり返すわけです。
底なし沼のように、無限に奪い取る人
このように、子供時代に受けた心の傷が、大人になってから、別なかたちで展開することが多くあります。それで、結局、不幸な人生をつくるのです。
そのもとは、原点において「前半生、自分は不幸であった。充足されなかった。だから、誰か、これを充足してくれないだろうか。埋め合わせてくれないだろうか」と思うところにあります。
そういう思いで人生を生きている人は、実は底なし沼のようなもので、そういう人に対して、いくら与えても、その与えたものは消え去ってしまうのです。
会社での評価にしても、その人は、いくら評価されても足りないのです。「まだまだ、もっと評価してほしい。もっとほめてほしい。もっと早く偉くしてほしい。もっと給料を上げてほしい。もっと、みんなの前で表彰してほしい」というように、きりがないほど、ずっと求めつづけます。
そのため、その人に対する評価は、どこかで必ず打ち切られます。そうすると、その人は不機嫌になってしまい、満足しないのです。
家庭にあっても同じです。その満たされないタイプの人というのは、奥さんが、あるいは、ご主人が、いくら一生懸命、尽くしても、底なしで、満足しません。伴侶がいくら努力しても、それを評価しないで、「あれが足りない。これが足りない」と、足りないことばかりを言います。
伴侶が一生懸命やっていて、九十九パーセントのところまで来ていても、欠けている一パーセントのほうを重視して、「おまえは、ここが足りない。あそこが足りない」「あなたは、ここがだめよ。」と言うのです。
たとえば、夫がいくら、会社で戦って勝ち、同期より早く出世していても、その夫に対し、「帰りが遅い」ということだけを取り上げて、ずっと怒りつづける妻がいます。こういう人は、夫の帰りが早ければ満足するかというと、そうではなく、今度は、夫の出世が遅いことを怒るのは間違いありません。夫の帰りが遅い事を責める妻は、夫の帰りが早くなれば、今度は、夫の出世が遅いことを責めたり、夫の残業代が少ないことを責めたり、いろいろするのです。
これは、人間の性格であり、何か一部分を取って責める人というのは、そこが埋まっても、ほかの部分を、また必ず責めます。
そのようなことがあって、こういう人は、なかなか満足しないのです。
人間は、男であれ女であれ、自分自身を振り返ってみて、百パーセントではないはずです。したがって、「あなたは、他の人に対して、百パーセントを求めるほど完璧な人間なのですか」ということです。「では、百パーセント、完璧な男性とはどういう男性なのですか。百パーセント、完璧な女性とは、どのような女性なのですか。そういう人が、実際に、具体的にいるのでしょうか」ということです。
たとえ、有名人、タレントのような女性を自分の妻にしたとしても、とてもじゃないけれども、満足はいきません。テレビタレントのような女性を奥さんにしても、それはたいてい苦しみのもとです。そういう人は、全世界の男性から愛されたくてしょうがなく、ブラウン管に映ることばかりに関心があるので、亭主のことなどには関心がなく、構っている暇もなくて、家にいてもくれません。そのため、そういう女性を妻にしたからといって、幸福になれるわけではないのです。(一部例外はある。)
あるいは、全女性から慕われるような男性を夫にすれば、幸福になれるかというと、それもまた難しいのです。毎日毎日、夫の素行が心配になるからです。
そのように、自分自身も百パーセントではないのに、他の人が百パーセントでなければ気に入らない人、あるいは、「自分は完全主義者、完璧主義者なのだ。そういう完璧な人が現れないかぎりは、自分は幸福になれないのだ」というようなことを言っている人は、幸福になれる権利を永遠に放棄しているのと同じなのです。
こういう無限に奪い取る傾向を持っている人は、いくら、まわりの人から本当に愛を注がれていても、それが分からないことが多く、足りないことのほうに意識が行くのです。そのため、その人に対して、いくら愛を注いでもだめなので、結局は、愛を注いでいる人のほうが疲れてくるということがあります。
このように、子供時代に受けた心の傷が、大人になってから、別なかたちで展開することが多くあります。それで、結局、不幸な人生をつくるのです。
そのもとは、原点において「前半生、自分は不幸であった。充足されなかった。だから、誰か、これを充足してくれないだろうか。埋め合わせてくれないだろうか」と思うところにあります。
そういう思いで人生を生きている人は、実は底なし沼のようなもので、そういう人に対して、いくら与えても、その与えたものは消え去ってしまうのです。
会社での評価にしても、その人は、いくら評価されても足りないのです。「まだまだ、もっと評価してほしい。もっとほめてほしい。もっと早く偉くしてほしい。もっと給料を上げてほしい。もっと、みんなの前で表彰してほしい」というように、きりがないほど、ずっと求めつづけます。
そのため、その人に対する評価は、どこかで必ず打ち切られます。そうすると、その人は不機嫌になってしまい、満足しないのです。
家庭にあっても同じです。その満たされないタイプの人というのは、奥さんが、あるいは、ご主人が、いくら一生懸命、尽くしても、底なしで、満足しません。伴侶がいくら努力しても、それを評価しないで、「あれが足りない。これが足りない」と、足りないことばかりを言います。
伴侶が一生懸命やっていて、九十九パーセントのところまで来ていても、欠けている一パーセントのほうを重視して、「おまえは、ここが足りない。あそこが足りない」「あなたは、ここがだめよ。」と言うのです。
たとえば、夫がいくら、会社で戦って勝ち、同期より早く出世していても、その夫に対し、「帰りが遅い」ということだけを取り上げて、ずっと怒りつづける妻がいます。こういう人は、夫の帰りが早ければ満足するかというと、そうではなく、今度は、夫の出世が遅いことを怒るのは間違いありません。夫の帰りが遅い事を責める妻は、夫の帰りが早くなれば、今度は、夫の出世が遅いことを責めたり、夫の残業代が少ないことを責めたり、いろいろするのです。
これは、人間の性格であり、何か一部分を取って責める人というのは、そこが埋まっても、ほかの部分を、また必ず責めます。
そのようなことがあって、こういう人は、なかなか満足しないのです。
人間は、男であれ女であれ、自分自身を振り返ってみて、百パーセントではないはずです。したがって、「あなたは、他の人に対して、百パーセントを求めるほど完璧な人間なのですか」ということです。「では、百パーセント、完璧な男性とはどういう男性なのですか。百パーセント、完璧な女性とは、どのような女性なのですか。そういう人が、実際に、具体的にいるのでしょうか」ということです。
たとえ、有名人、タレントのような女性を自分の妻にしたとしても、とてもじゃないけれども、満足はいきません。テレビタレントのような女性を奥さんにしても、それはたいてい苦しみのもとです。そういう人は、全世界の男性から愛されたくてしょうがなく、ブラウン管に映ることばかりに関心があるので、亭主のことなどには関心がなく、構っている暇もなくて、家にいてもくれません。そのため、そういう女性を妻にしたからといって、幸福になれるわけではないのです。(一部例外はある。)
あるいは、全女性から慕われるような男性を夫にすれば、幸福になれるかというと、それもまた難しいのです。毎日毎日、夫の素行が心配になるからです。
そのように、自分自身も百パーセントではないのに、他の人が百パーセントでなければ気に入らない人、あるいは、「自分は完全主義者、完璧主義者なのだ。そういう完璧な人が現れないかぎりは、自分は幸福になれないのだ」というようなことを言っている人は、幸福になれる権利を永遠に放棄しているのと同じなのです。
こういう無限に奪い取る傾向を持っている人は、いくら、まわりの人から本当に愛を注がれていても、それが分からないことが多く、足りないことのほうに意識が行くのです。そのため、その人に対して、いくら愛を注いでもだめなので、結局は、愛を注いでいる人のほうが疲れてくるということがあります。
与えられているものに感謝を(P149)
大事なことは何であるかというと「もう、いい加減に、『人から貰うことで自分が幸福になれる』という考えは捨ててはどうか」ということです。
これは、きりがないのです。物質的な面、物やお金についても、あるいは、他の人からの社会的評価や名声、その他についても、健康についても、きりがありません。「これで最高。これで完璧」というものはないのです。
苦しみのもとは、たいていの場合、自分自身がつくり出しているものなのです。
したがって、「そういう傾向性を、いったん思いとどまってはどうか。相手は、一パーセント足りないかもしれない。あるいは、十パーセント足りないかもしれない。しかし、その十パーセントの足りないところを、一生懸命、責めるよりは、九十九パーセントのできているところに目を向けてあげてはどうか」ということです。
男性が奥さんに百パーセントを求めたら、家庭内は不和になるのが普通です。なかには、百パーセントを求めたら、それを達成すべく、がんばるような、よくできた奥さんもいるかもしれませんが、そういう人は、心身症になる気があります。
あるいは、舅や姑が嫁に百パーセントを求めたら、嫁は、一生懸命、仕えるものの、やはり、心のなかで、かなり鬱屈してくるということがあります。
そのため、やはり、他の人に対しては、百パーセントを求めるより、よくやっているところのほうに目を向けてあげるべきなのです。
そのようにすると、不思議なことに、世の中は変わってきます。「人から奪いたい。取りたい。貰いたい。貰わなければ幸福になれない」という思いをやめて、自分が現に与えられているものを発見し、あるいは、他の人の悪いところではなく、よいところを見ていこうとすると、そういう、評価を変えること、考え方を変えること自体が、実は人に与えていることになるのです。
一生懸命やっていて、九十九パーセントまでできていても、十パーセントがだめで、いつも怒られている奥さん、あるいは、ご主人がいます。相手から見て、「あなたは、いい人なのだけれども、この癖だけは、どうしても気に入らない」というようなものがあるわけです。
たとえば、「一生懸命やっていて、いい男なのだけれども、このポマードだけは嫌だ」「この髭だけは、どうも嫌だ」「この片方の目の目尻が吊り上っているのが、どうも嫌だ」「ときどき鼻を鳴らす癖がある」「夜中に歯ぎしりをする」など、いろいろあると思います。
しかし、「これだけは嫌だ」というものを取り上げて言っている人は、不幸になりたい人なのです。要するに、そういうことを言っている人は、実は、自分が不幸になりたくて、不幸になる理由を探しているのです。「これがあるから幸福になれない」という理由を探しているのです。
そうではなく、やはり、他の人のよいところを認めていき、自分が与えられているところについて、よく感謝し、考え方を変えなくてはなりません。
そして、人から取ることは、もう、この辺でやめましょう。人から与えられていることをよく見て、今度はちょっと、自分も人にあげるほう、お返しをするほうを考えましょう。
たとえば、ご主人は、いつも帰りが遅いかもしれませんが、遅いのには遅いだけの理由があるのでしょうから、奥さんは、そういうことに対して、ねぎらいの言葉をかけてあげることです。それだけでも、かなり違います。
いつも帰りの遅いご主人は、奥さんに対して、「言い訳しても、どうせ聴く耳を持たないのだから、もう、無駄なことは言うまい」と思い、「飯」「風呂」「寝る」だけで済ませ、それ以外は言わないわけです。ところが、奥さんが、ねぎらいの言葉をかけてあげたりすると、ご主人は、ふっと心を開くこともあるのです。
大事なことは何であるかというと「もう、いい加減に、『人から貰うことで自分が幸福になれる』という考えは捨ててはどうか」ということです。
これは、きりがないのです。物質的な面、物やお金についても、あるいは、他の人からの社会的評価や名声、その他についても、健康についても、きりがありません。「これで最高。これで完璧」というものはないのです。
苦しみのもとは、たいていの場合、自分自身がつくり出しているものなのです。
したがって、「そういう傾向性を、いったん思いとどまってはどうか。相手は、一パーセント足りないかもしれない。あるいは、十パーセント足りないかもしれない。しかし、その十パーセントの足りないところを、一生懸命、責めるよりは、九十九パーセントのできているところに目を向けてあげてはどうか」ということです。
男性が奥さんに百パーセントを求めたら、家庭内は不和になるのが普通です。なかには、百パーセントを求めたら、それを達成すべく、がんばるような、よくできた奥さんもいるかもしれませんが、そういう人は、心身症になる気があります。
あるいは、舅や姑が嫁に百パーセントを求めたら、嫁は、一生懸命、仕えるものの、やはり、心のなかで、かなり鬱屈してくるということがあります。
そのため、やはり、他の人に対しては、百パーセントを求めるより、よくやっているところのほうに目を向けてあげるべきなのです。
そのようにすると、不思議なことに、世の中は変わってきます。「人から奪いたい。取りたい。貰いたい。貰わなければ幸福になれない」という思いをやめて、自分が現に与えられているものを発見し、あるいは、他の人の悪いところではなく、よいところを見ていこうとすると、そういう、評価を変えること、考え方を変えること自体が、実は人に与えていることになるのです。
一生懸命やっていて、九十九パーセントまでできていても、十パーセントがだめで、いつも怒られている奥さん、あるいは、ご主人がいます。相手から見て、「あなたは、いい人なのだけれども、この癖だけは、どうしても気に入らない」というようなものがあるわけです。
たとえば、「一生懸命やっていて、いい男なのだけれども、このポマードだけは嫌だ」「この髭だけは、どうも嫌だ」「この片方の目の目尻が吊り上っているのが、どうも嫌だ」「ときどき鼻を鳴らす癖がある」「夜中に歯ぎしりをする」など、いろいろあると思います。
しかし、「これだけは嫌だ」というものを取り上げて言っている人は、不幸になりたい人なのです。要するに、そういうことを言っている人は、実は、自分が不幸になりたくて、不幸になる理由を探しているのです。「これがあるから幸福になれない」という理由を探しているのです。
そうではなく、やはり、他の人のよいところを認めていき、自分が与えられているところについて、よく感謝し、考え方を変えなくてはなりません。
そして、人から取ることは、もう、この辺でやめましょう。人から与えられていることをよく見て、今度はちょっと、自分も人にあげるほう、お返しをするほうを考えましょう。
たとえば、ご主人は、いつも帰りが遅いかもしれませんが、遅いのには遅いだけの理由があるのでしょうから、奥さんは、そういうことに対して、ねぎらいの言葉をかけてあげることです。それだけでも、かなり違います。
いつも帰りの遅いご主人は、奥さんに対して、「言い訳しても、どうせ聴く耳を持たないのだから、もう、無駄なことは言うまい」と思い、「飯」「風呂」「寝る」だけで済ませ、それ以外は言わないわけです。ところが、奥さんが、ねぎらいの言葉をかけてあげたりすると、ご主人は、ふっと心を開くこともあるのです。
人間関係をよくするには一円もいらない
「足りないところだけを見て、それを求め続けた場合、幸福になれる人間はいないのだ」ということを、まず悟らなくてはいけません。
すでに多くのものを与えられているのです。それに感謝することから出発すると、人はお返しをしなければいけなくなり、お返しの人生になります。実を言うと、お返しの人生においては、不幸になる道がありません。自分がお返しの人生に入ったときには、不幸はないのです。
これも、完璧に百パーセントのお返しができるわけではないのですが、一パーセントお返しできたら一パーセントだけ幸福になり、十パーセントお返しできたら十パーセント幸福になり、五十パーセントお返しできたら五十パーセントお返し幸福、九十パーセントできたら、九十パーセント幸福になります。
そのため、人を愛するほう、人に与えるほうに思いを切り替えたならば、その「観の転回」をすることによって、結局、人生において不幸が消えていくのです。むしろ、それは幸福の創造なのです。
したがって、他の人の幸福を自分の幸福としているほど、幸福な人はいないのです。「他の人の幸福を自分の不幸とする」というような、人は、なかなか幸福になれません。「少しでも他の人がよくなると、それを自分の幸福と思う」という人が、実は幸福的メンタリティー(心的傾向)を持っている人なのです。
「奪う愛」の苦しみは、たいてい、人間関係を中心としての欲求不満であり、それは、「自分は与えられていない」ということから来る不満だと思います。しかし、そういうものは、いくら求めても、ますます蟻地獄になっていく道なのだということを知らなければいけません。
その思いを捨てて、自分が認められているところについて感謝し、自分が他の人に求めていたことよりも、自分が他の人にしてあげていなかったことのほうを考えることです。
たとえば、「この上司は自分を評価してくれなかった」と、長い間、ずっと恨みつらみに思っているとします。そのときに、「自分は、その上司が出世できるように、それほど仕事でサポートしたことがあるか」と考えると、あまりしていなことがあります。それでいながら、自分が評価してもらっていないことだけは気になるわけです。
「足りないところだけを見て、それを求め続けた場合、幸福になれる人間はいないのだ」ということを、まず悟らなくてはいけません。
すでに多くのものを与えられているのです。それに感謝することから出発すると、人はお返しをしなければいけなくなり、お返しの人生になります。実を言うと、お返しの人生においては、不幸になる道がありません。自分がお返しの人生に入ったときには、不幸はないのです。
これも、完璧に百パーセントのお返しができるわけではないのですが、一パーセントお返しできたら一パーセントだけ幸福になり、十パーセントお返しできたら十パーセント幸福になり、五十パーセントお返しできたら五十パーセントお返し幸福、九十パーセントできたら、九十パーセント幸福になります。
そのため、人を愛するほう、人に与えるほうに思いを切り替えたならば、その「観の転回」をすることによって、結局、人生において不幸が消えていくのです。むしろ、それは幸福の創造なのです。
したがって、他の人の幸福を自分の幸福としているほど、幸福な人はいないのです。「他の人の幸福を自分の不幸とする」というような、人は、なかなか幸福になれません。「少しでも他の人がよくなると、それを自分の幸福と思う」という人が、実は幸福的メンタリティー(心的傾向)を持っている人なのです。
「奪う愛」の苦しみは、たいてい、人間関係を中心としての欲求不満であり、それは、「自分は与えられていない」ということから来る不満だと思います。しかし、そういうものは、いくら求めても、ますます蟻地獄になっていく道なのだということを知らなければいけません。
その思いを捨てて、自分が認められているところについて感謝し、自分が他の人に求めていたことよりも、自分が他の人にしてあげていなかったことのほうを考えることです。
たとえば、「この上司は自分を評価してくれなかった」と、長い間、ずっと恨みつらみに思っているとします。そのときに、「自分は、その上司が出世できるように、それほど仕事でサポートしたことがあるか」と考えると、あまりしていなことがあります。それでいながら、自分が評価してもらっていないことだけは気になるわけです。
続き。
「自分は、上司が出世できるようにサポートしたことがあるか。ほんとうに、一生懸命、協力したのか」と考えると、自分はしたつもりでいても、相手の立場から見れば、そうではないことがあります。上司は、「彼はいつも、ボーナスが支給される前の月になったら、一生懸命働き、ボーナス日を過ぎたら、また働かなくなる傾向がある」などと思っていたりします。そんなものです。
自分としては一生懸命やったつもりでいても、相手は、「彼は非常にエゴイストだ。自分の方に見返りがあるときだけは、やるのだけれども、そうでないときは、まったく何もしない」などと思っていたりするものなのです。ただ、それが分からないので、「自分としては一生懸命やったのに、評価してもらっていない」と思うわけです。
したがって、他の人の立場に立って、相手から与えられていないことよりも自分自身が相手に与えていないこと、なしていなことのほうを考え、それに対して、深い反省をし、行動することです。これが幸福への道なのです。
長年、夫婦で連れ添っていても、自分の妻、あるいは夫が、一生懸命、努力したことに対して、ほめ言葉一つ与えない人がいます。なぜ、そのようなことに躊躇するのでしょうか。それをするには一円も要らないのです。
たとえば、今日、頑張っていつもより素晴らしいお化粧を発明し、少しだけ、きれいになったら、ほめてあげればよいのです。
あるいは、ご主人が、今日は、いつもより十分早く帰ってきたら、ほめてあげればよいのです。十分早く帰っただけでも、「あなた、今日は早く帰って来たわね。お仕事、頑張ったのね。」と、一言、言ってあげれば、ご主人は、「そうか。やはり、段取りよく仕事をして、早く帰ったら、妻も喜ぶのだな」と思い、喜びます。
そういうちょっとした、些細なことでもよいのです。
それから、「おれが、おれが」と思って突っ張る人がいますが、やはり、突っ張っていて、それほど成功できる人は、世の中にはいないのです。それで、成功することもあるのですが、どこかでコロンと高転びをします。“高下駄”から転げ落ちるのが普通です。強気で行き、勝負して勝つこともありますが、どこかでは転ぶものなのです。
したがって、やはり、頭を下げることです。頭を下げることには一円もいらないのです。腰を低くし、頭を低くして、精進していくことが大事です。それをしないで突っ張りすぎると、高転びをしていきます。
人間関係をよくするには、基本的に、お金は一円も要りません。まったくいらないのです。単に心の態度を変え、口を開くぐらいです。少しエネルギーは使うので、エネルギーが一キロカロリーぐらい減るかも知れませんが、それほど大したことではありません。
人は、自分に対して言われた言葉は何十年でも覚えているものですが、ほめ言葉も、また、覚えているものです。少し怒られても、十年間ぐらい覚えているし、少しほめられても、十年ぐらい、ほめられた気になっているものです。その一瞬の効果は大きいわけです。
人間関係を良好にし、幸福な方向へ導くには、一円のお金も要らないし、汗水垂らして努力する必要もないのです。必要なのは、心の態度を変えること、そして、具体的な、ささやかな好意を示してあげることです。それが大事です。
世の中の人の苦しみを見ると、ほとんどは、この「奪う愛」のところの苦しみなのです。「欲しい、欲しい」と思って苦しんでいるので、「欲しい」と思うことをやめて、「どうしたら人に与えることができるのか」ということを考えてください。その時点で、すでに悩みは消えています。これも悟りの一転語です。
ここでは、「愛の原理」のなかで、いちばん基本的なところについて述べました。
「自分は、上司が出世できるようにサポートしたことがあるか。ほんとうに、一生懸命、協力したのか」と考えると、自分はしたつもりでいても、相手の立場から見れば、そうではないことがあります。上司は、「彼はいつも、ボーナスが支給される前の月になったら、一生懸命働き、ボーナス日を過ぎたら、また働かなくなる傾向がある」などと思っていたりします。そんなものです。
自分としては一生懸命やったつもりでいても、相手は、「彼は非常にエゴイストだ。自分の方に見返りがあるときだけは、やるのだけれども、そうでないときは、まったく何もしない」などと思っていたりするものなのです。ただ、それが分からないので、「自分としては一生懸命やったのに、評価してもらっていない」と思うわけです。
したがって、他の人の立場に立って、相手から与えられていないことよりも自分自身が相手に与えていないこと、なしていなことのほうを考え、それに対して、深い反省をし、行動することです。これが幸福への道なのです。
長年、夫婦で連れ添っていても、自分の妻、あるいは夫が、一生懸命、努力したことに対して、ほめ言葉一つ与えない人がいます。なぜ、そのようなことに躊躇するのでしょうか。それをするには一円も要らないのです。
たとえば、今日、頑張っていつもより素晴らしいお化粧を発明し、少しだけ、きれいになったら、ほめてあげればよいのです。
あるいは、ご主人が、今日は、いつもより十分早く帰ってきたら、ほめてあげればよいのです。十分早く帰っただけでも、「あなた、今日は早く帰って来たわね。お仕事、頑張ったのね。」と、一言、言ってあげれば、ご主人は、「そうか。やはり、段取りよく仕事をして、早く帰ったら、妻も喜ぶのだな」と思い、喜びます。
そういうちょっとした、些細なことでもよいのです。
それから、「おれが、おれが」と思って突っ張る人がいますが、やはり、突っ張っていて、それほど成功できる人は、世の中にはいないのです。それで、成功することもあるのですが、どこかでコロンと高転びをします。“高下駄”から転げ落ちるのが普通です。強気で行き、勝負して勝つこともありますが、どこかでは転ぶものなのです。
したがって、やはり、頭を下げることです。頭を下げることには一円もいらないのです。腰を低くし、頭を低くして、精進していくことが大事です。それをしないで突っ張りすぎると、高転びをしていきます。
人間関係をよくするには、基本的に、お金は一円も要りません。まったくいらないのです。単に心の態度を変え、口を開くぐらいです。少しエネルギーは使うので、エネルギーが一キロカロリーぐらい減るかも知れませんが、それほど大したことではありません。
人は、自分に対して言われた言葉は何十年でも覚えているものですが、ほめ言葉も、また、覚えているものです。少し怒られても、十年間ぐらい覚えているし、少しほめられても、十年ぐらい、ほめられた気になっているものです。その一瞬の効果は大きいわけです。
人間関係を良好にし、幸福な方向へ導くには、一円のお金も要らないし、汗水垂らして努力する必要もないのです。必要なのは、心の態度を変えること、そして、具体的な、ささやかな好意を示してあげることです。それが大事です。
世の中の人の苦しみを見ると、ほとんどは、この「奪う愛」のところの苦しみなのです。「欲しい、欲しい」と思って苦しんでいるので、「欲しい」と思うことをやめて、「どうしたら人に与えることができるのか」ということを考えてください。その時点で、すでに悩みは消えています。これも悟りの一転語です。
ここでは、「愛の原理」のなかで、いちばん基本的なところについて述べました。
2 頭の悪さを嘆く暇があれば勉強を(知の原理)
たいていの人は「頭が悪い」と悩んでいる。
二番目に、「頭の悪さを嘆く暇があれば勉強を」ということを述べたいと思います。これは、「知の原理」についての話です。知の原理も、難しく言えば、きりはないのですが、ここでは、分かりやすい話をします。
本章の2節では、「自分は人から愛が貰えなくて、不幸だ、不幸だ」と言っている人に対し、幸福になる道として、愛の原理を述べ、「実際は、人に愛を与えることにおいて幸福になれるのだ」という話をしましたが、「自分は頭が悪い、悪い」と嘆いてばかりいる人も多いのです。
これを自分だけのことだと思っている人が多いのですが、世の中を見てみると、そのうちの九九・九九九九九九九パーセントぐらいまでは、頭が悪いことで悩んでいます。不思議なもので、他の人のことは、心のなかを覗けないので分からないため、自分だけがそうだと思っているのですが、たいていの人は、「自分は頭が悪い、悪い」と悩んでいるのです。
たとえば、学歴だけを取って、「この人は大卒だ。それも、こういう一流大学を出ている」というようなことを言ったりしますが、それでは、一流大学へ行った人はみんな、「自分は頭がよい」と思って、うぬぼれ天狗になって喜んでいるのかといえば、そんなことはありません。実際には、成績のよい人ほど、劣等感を感じやすいのです。
あまり勉強をせず、遊び呆けている人は、劣等感の感じ方が少なく、むしろ、優秀な人というか、自分の能力ぎりぎりまで勉強した人が、それで差がついた場合に感じる劣等感のほうが、実はきついのです。
「あの人は、一流大学へ行っているから、劣等感がなくて、いいな。自分は二流大学だから、劣等感の塊だ」「自分は大学へ行っていないから、劣等感の塊だ」などと思っているかもしれませんが、ほんとうは、一流大学に入った人が、そのなかで、しのぎを削って敗れたときの劣等感のほうが激しいのです。
彼らは、非常にきわどい劣等感を強く持っています。点数の一点や二点の違いで、「あいつは天才だ。おれは凡才だ」などと言って、非常に苦しんだりしています。ばかばかしい話であり、そういうところに価値観を感じていない人にとっては何でもないことなのですが、そういうところに価値観を感じている人だからこそ、非常に敏感に反応するのです。
そのため、一流大学へ行った人ほど、実は劣等感を強く感じています。
そういう意味で、外面的な学歴などで、一律に評価するのは問題があります。
たいていの人は「頭が悪い」と悩んでいる。
二番目に、「頭の悪さを嘆く暇があれば勉強を」ということを述べたいと思います。これは、「知の原理」についての話です。知の原理も、難しく言えば、きりはないのですが、ここでは、分かりやすい話をします。
本章の2節では、「自分は人から愛が貰えなくて、不幸だ、不幸だ」と言っている人に対し、幸福になる道として、愛の原理を述べ、「実際は、人に愛を与えることにおいて幸福になれるのだ」という話をしましたが、「自分は頭が悪い、悪い」と嘆いてばかりいる人も多いのです。
これを自分だけのことだと思っている人が多いのですが、世の中を見てみると、そのうちの九九・九九九九九九九パーセントぐらいまでは、頭が悪いことで悩んでいます。不思議なもので、他の人のことは、心のなかを覗けないので分からないため、自分だけがそうだと思っているのですが、たいていの人は、「自分は頭が悪い、悪い」と悩んでいるのです。
たとえば、学歴だけを取って、「この人は大卒だ。それも、こういう一流大学を出ている」というようなことを言ったりしますが、それでは、一流大学へ行った人はみんな、「自分は頭がよい」と思って、うぬぼれ天狗になって喜んでいるのかといえば、そんなことはありません。実際には、成績のよい人ほど、劣等感を感じやすいのです。
あまり勉強をせず、遊び呆けている人は、劣等感の感じ方が少なく、むしろ、優秀な人というか、自分の能力ぎりぎりまで勉強した人が、それで差がついた場合に感じる劣等感のほうが、実はきついのです。
「あの人は、一流大学へ行っているから、劣等感がなくて、いいな。自分は二流大学だから、劣等感の塊だ」「自分は大学へ行っていないから、劣等感の塊だ」などと思っているかもしれませんが、ほんとうは、一流大学に入った人が、そのなかで、しのぎを削って敗れたときの劣等感のほうが激しいのです。
彼らは、非常にきわどい劣等感を強く持っています。点数の一点や二点の違いで、「あいつは天才だ。おれは凡才だ」などと言って、非常に苦しんだりしています。ばかばかしい話であり、そういうところに価値観を感じていない人にとっては何でもないことなのですが、そういうところに価値観を感じている人だからこそ、非常に敏感に反応するのです。
そのため、一流大学へ行った人ほど、実は劣等感を強く感じています。
そういう意味で、外面的な学歴などで、一律に評価するのは問題があります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
死後の世界は存在します。 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
死後の世界は存在します。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196505人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209195人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 76984人