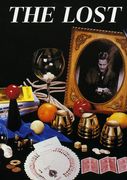|
|
|
|
コメント(89)
パーフェクト・リフルシャッフル(The Perfect Riffle Shuffle)
概要 カードマジックの達人たちは長年、1枚ずつ完全に噛み合わせるリフルシャッフルを目指してきたが、完全成功は難しい。ここで紹介される方法は、原理的な工夫(weaveの応用)により、見た目は完璧なリフルシャッフルでありながら、毎回確実に成功する。
方法 a
デックをテーブルに置き、両手の中指・薬指を外端角付近に、人差し指をトップに、親指を内端角付近に置く。
デックを2つにカットし、上半分(B)を右側に置く。BはAより約3/8インチ前に出す。
小指先端を外端角に当て、両手の中指・薬指・小指で外角を「箱状」に固定し、指先をテーブルに押し付ける。
親指で内端を持ち上げ、外角を固定したまま、親指で外方向に押して両パケットをわずかに外に回転させ、内角だけが接触する状態にする。
人差し指を離し、親指の圧を緩めると、下側からカードが噛み合い始める。
Aを外方向、Bを内方向に動かすことで、確実にカードが交互に噛み合う。
親指をカード側面に沿って上に滑らせ、リフル音を出しながらカードをテーブルに落とす。
ポイント
外角を3本の指で固定することで、内角にテンションがかかり、確実な噛み合わせが可能になる。
方法 b(チャールズ・ミラー使用)
基本は同じだが、親指位置を内端中央に置き、外方向に押し出して内角同士を接触させ、圧を緩めて角から噛み合わせる。
親指を上に動かしてリフル音を出す。
ストリップアウト・フォールスシャッフル(The Strip-Out False Shuffle – Charles Miller Method)
概要 チャールズ・ミラーによる改良型で、より自然かつ容易に行えるストリップアウト・シャッフル。
手順
デックを2つに分け、内角を合わせ、両手の親指と中指で側面をつかむ。薬指・小指はカールさせ、人差し指はトップを押さえる。
親指で角を持ち上げ、右手から数枚リフルし、その後両手で全カードを噛み合わせる。
外端を持ち替え、親指付け根を内端角付近に置く。
右パケットをテーブルに固定し、左パケットを右方向かつ斜め内側に押す。右親指付け根で角を押さえ、外側からは整った外観を保つ。
外端角を持ち、見た目は揃えるように見せつつ、実際は両パケットをわずかにずらし、右パケットを横に引き抜く(ストリップアウト)。
右パケットを左パケットの上に重ね、元の順序に戻す。
ポイント
外観は常に整って見えるため、観客に不自然さを与えない。
テレスコープ状態(重なり合い)で手を離しても怪しまれない。
ヒンドゥーシャッフル・バリエーション(Hindu Shuffle Variation)
概要 古くからあるヒンドゥーシャッフルの新しいハンドリングで、通常法を知っている人でも惑わされる。選ばれたカードをトップにコントロールする。
手順
ヒンドゥーシャッフルの持ち方でデックを持ち、左手に約1/3を落とす。
選ばれたカードを左手のカードの上に戻させる。
左手指で小パケットを取り、最初のパケットの上にインジョグして落とす(約1/2インチ内側)。
以降のパケットは外端を少し不揃いにして落とし、インジョグを隠す。
全体を右手で持ち上げ、右薬指先端でインジョグを持ち上げてブレイクを作り、親指と中指で保持。
通常のヒンドゥーシャッフルを続け、ブレイクまでパケットを落とし、最後のパケットをそのまま上に置くことで選ばれたカードがトップに来る。
ポイント
ブレイク作成は、デックを左手に戻す動作の中で完全にカバーされる。
概要 カードマジックの達人たちは長年、1枚ずつ完全に噛み合わせるリフルシャッフルを目指してきたが、完全成功は難しい。ここで紹介される方法は、原理的な工夫(weaveの応用)により、見た目は完璧なリフルシャッフルでありながら、毎回確実に成功する。
方法 a
デックをテーブルに置き、両手の中指・薬指を外端角付近に、人差し指をトップに、親指を内端角付近に置く。
デックを2つにカットし、上半分(B)を右側に置く。BはAより約3/8インチ前に出す。
小指先端を外端角に当て、両手の中指・薬指・小指で外角を「箱状」に固定し、指先をテーブルに押し付ける。
親指で内端を持ち上げ、外角を固定したまま、親指で外方向に押して両パケットをわずかに外に回転させ、内角だけが接触する状態にする。
人差し指を離し、親指の圧を緩めると、下側からカードが噛み合い始める。
Aを外方向、Bを内方向に動かすことで、確実にカードが交互に噛み合う。
親指をカード側面に沿って上に滑らせ、リフル音を出しながらカードをテーブルに落とす。
ポイント
外角を3本の指で固定することで、内角にテンションがかかり、確実な噛み合わせが可能になる。
方法 b(チャールズ・ミラー使用)
基本は同じだが、親指位置を内端中央に置き、外方向に押し出して内角同士を接触させ、圧を緩めて角から噛み合わせる。
親指を上に動かしてリフル音を出す。
ストリップアウト・フォールスシャッフル(The Strip-Out False Shuffle – Charles Miller Method)
概要 チャールズ・ミラーによる改良型で、より自然かつ容易に行えるストリップアウト・シャッフル。
手順
デックを2つに分け、内角を合わせ、両手の親指と中指で側面をつかむ。薬指・小指はカールさせ、人差し指はトップを押さえる。
親指で角を持ち上げ、右手から数枚リフルし、その後両手で全カードを噛み合わせる。
外端を持ち替え、親指付け根を内端角付近に置く。
右パケットをテーブルに固定し、左パケットを右方向かつ斜め内側に押す。右親指付け根で角を押さえ、外側からは整った外観を保つ。
外端角を持ち、見た目は揃えるように見せつつ、実際は両パケットをわずかにずらし、右パケットを横に引き抜く(ストリップアウト)。
右パケットを左パケットの上に重ね、元の順序に戻す。
ポイント
外観は常に整って見えるため、観客に不自然さを与えない。
テレスコープ状態(重なり合い)で手を離しても怪しまれない。
ヒンドゥーシャッフル・バリエーション(Hindu Shuffle Variation)
概要 古くからあるヒンドゥーシャッフルの新しいハンドリングで、通常法を知っている人でも惑わされる。選ばれたカードをトップにコントロールする。
手順
ヒンドゥーシャッフルの持ち方でデックを持ち、左手に約1/3を落とす。
選ばれたカードを左手のカードの上に戻させる。
左手指で小パケットを取り、最初のパケットの上にインジョグして落とす(約1/2インチ内側)。
以降のパケットは外端を少し不揃いにして落とし、インジョグを隠す。
全体を右手で持ち上げ、右薬指先端でインジョグを持ち上げてブレイクを作り、親指と中指で保持。
通常のヒンドゥーシャッフルを続け、ブレイクまでパケットを落とし、最後のパケットをそのまま上に置くことで選ばれたカードがトップに来る。
ポイント
ブレイク作成は、デックを左手に戻す動作の中で完全にカバーされる。
False Shuffle Retaining Top Stock
(トップストック保持型フォールスシャッフル)
概要 特定の順序でなくてもよい少数枚(例:同一スート13枚など)をトップに保持したままシャッフルする方法。 例として『The Mind Mirror』のような演目で、トップに13枚を残す場合を想定。
手順
デックの半分弱をアンダーカットし、最初のカードをインジョグして残りをシャッフルオフ。
インジョグ位置で再度アンダーカットし、下ろしたパケットの最初の6枚(保持したいカード)をラン。
このパケットをもう一方のパケットの上に重ね、約1.3cm(1/2インチ)外に突き出させる。
スクエア動作で右親指を内端に置き、指で上パケットを内側に押してブレイクを作り、右親指で保持。
デックを右手で持ち、ブレイクを保持したまま。
ブレイクまでの下半分を左手指上にリフルし、外側を右指先に乗せ、左手親指と指で端をつかみエンドリフルシャッフル。両パケットのトップ6枚は元のストックなので、これらを一緒にリフルすればストックはトップに戻る。
Gamblers’ False Shuffle
(ギャンブラーズ・フォールスシャッフル)
概要 非常に大胆なリフルシャッフルの偽装法。実際のギャンブルでは危険だが、マジック用途では有効。 見た目は通常のリフルシャッフルだが、順序は保持される。
手順
デック上半分を右手親指と中指で左角側面をつかみ、右側に置く。
残りを左手親指と中指で右角側面をつかみ、両手でパケットを覆い、人差し指で端中央を押さえる(Fig.1)。
左手親指からカードをリフルし、その直後に右手親指からリフルして重ねる。
両手でパケットを覆ったまま、手のひら外側で押し合わせ、テレスコープ動作を模倣(Fig.2)。
全体をためらいなく、会話しながら行うと自然。
Retaining Top Stock(トップストック保持型/ギャンブラーズ法)
概要 トップストックを一時的にデック中央に送ったように見せつつ、完全にコントロールする。 例:5枚の選ばれたカードをトップに保持したままシャッフル。
手順
デックの約2/3を右手でアンダーカットし、内角を合わせて逆V字型に構える。
リフルを左手パケットから始め、右手パケットより速く落とすことで、5枚のストックが右手パケットの最後の十数枚の下に固まるようにする(ストックに他のカードが噛まないよう注意)。
両パケットの端を親指と中指でつかみ、薬指を端中央に、人差し指先端を背面に置く。手をカード上にかぶせ、角度をつけて押し合わせる(Fig.1)。
パケットが揃ったら、左中指先端で右パケットの突き出た角(X)を押し、ストック上の内側を持ち上げる(Fig.3)。同時に左親指で押さえてブレイクを確保し、親指と薬指でスクエア(Fig.4)。
手の位置を保ったままデックを持ち上げ、人差し指先端で背面を押して外観を整える(Fig.4)。
右手でランニングカットを行い、ブレイクまで数枚ずつテーブルに落とし、最後に残りを上に置く。これでストックは再びトップに戻る。
ブレイク確保後は、ランニングカットの代わりにストレートカットや、中央からストックごと抜き出して上に置く方法も可能。
特徴と使い分け
False Shuffle Retaining Top Stock:比較的自然なエンドリフル型。トップの小パケットを保持。
Gamblers’ False Shuffle:大胆でスピーディ。順序保持はするが、観客の注意を会話や所作で逸らす必要あり。
Retaining Top Stock(ギャンブラーズ法):トップストックを一時的に中央に送ったように見せる心理的効果が強い。
(トップストック保持型フォールスシャッフル)
概要 特定の順序でなくてもよい少数枚(例:同一スート13枚など)をトップに保持したままシャッフルする方法。 例として『The Mind Mirror』のような演目で、トップに13枚を残す場合を想定。
手順
デックの半分弱をアンダーカットし、最初のカードをインジョグして残りをシャッフルオフ。
インジョグ位置で再度アンダーカットし、下ろしたパケットの最初の6枚(保持したいカード)をラン。
このパケットをもう一方のパケットの上に重ね、約1.3cm(1/2インチ)外に突き出させる。
スクエア動作で右親指を内端に置き、指で上パケットを内側に押してブレイクを作り、右親指で保持。
デックを右手で持ち、ブレイクを保持したまま。
ブレイクまでの下半分を左手指上にリフルし、外側を右指先に乗せ、左手親指と指で端をつかみエンドリフルシャッフル。両パケットのトップ6枚は元のストックなので、これらを一緒にリフルすればストックはトップに戻る。
Gamblers’ False Shuffle
(ギャンブラーズ・フォールスシャッフル)
概要 非常に大胆なリフルシャッフルの偽装法。実際のギャンブルでは危険だが、マジック用途では有効。 見た目は通常のリフルシャッフルだが、順序は保持される。
手順
デック上半分を右手親指と中指で左角側面をつかみ、右側に置く。
残りを左手親指と中指で右角側面をつかみ、両手でパケットを覆い、人差し指で端中央を押さえる(Fig.1)。
左手親指からカードをリフルし、その直後に右手親指からリフルして重ねる。
両手でパケットを覆ったまま、手のひら外側で押し合わせ、テレスコープ動作を模倣(Fig.2)。
全体をためらいなく、会話しながら行うと自然。
Retaining Top Stock(トップストック保持型/ギャンブラーズ法)
概要 トップストックを一時的にデック中央に送ったように見せつつ、完全にコントロールする。 例:5枚の選ばれたカードをトップに保持したままシャッフル。
手順
デックの約2/3を右手でアンダーカットし、内角を合わせて逆V字型に構える。
リフルを左手パケットから始め、右手パケットより速く落とすことで、5枚のストックが右手パケットの最後の十数枚の下に固まるようにする(ストックに他のカードが噛まないよう注意)。
両パケットの端を親指と中指でつかみ、薬指を端中央に、人差し指先端を背面に置く。手をカード上にかぶせ、角度をつけて押し合わせる(Fig.1)。
パケットが揃ったら、左中指先端で右パケットの突き出た角(X)を押し、ストック上の内側を持ち上げる(Fig.3)。同時に左親指で押さえてブレイクを確保し、親指と薬指でスクエア(Fig.4)。
手の位置を保ったままデックを持ち上げ、人差し指先端で背面を押して外観を整える(Fig.4)。
右手でランニングカットを行い、ブレイクまで数枚ずつテーブルに落とし、最後に残りを上に置く。これでストックは再びトップに戻る。
ブレイク確保後は、ランニングカットの代わりにストレートカットや、中央からストックごと抜き出して上に置く方法も可能。
特徴と使い分け
False Shuffle Retaining Top Stock:比較的自然なエンドリフル型。トップの小パケットを保持。
Gamblers’ False Shuffle:大胆でスピーディ。順序保持はするが、観客の注意を会話や所作で逸らす必要あり。
Retaining Top Stock(ギャンブラーズ法):トップストックを一時的に中央に送ったように見せる心理的効果が強い。
ストック・シャッフリングの体系(A System of Stock Shuffling)
背景
これまでオーバーハンドシャッフルでのストック法は、アードネス(Erdnase)法が唯一出版されていた。
アードネス法は有効だが、配る人数によって計算が変わるためパターンが一定せず、実戦では混乱しやすい。
本書の方法は配る人数(例:4人なら4)を基準に全てのラン数を決めるため、計算が不要で覚えやすい。
各カードのストック手順はパターン化されており、理解すれば高速かつ確実に行える。
例:4人配りの場合(数字4を基準にラン数を決定)
2枚ストック(トップ1枚+ボトム1枚)
半分アンダーカット → 3枚ラン → 4枚目をインジョグ → 残りをシャッフルオフ(元ボトムカードがトップへ)
インジョグでアンダーカット → 4枚ラン → 3枚ラン → 4枚目をインジョグ → シャッフルオフ
インジョグでアンダーカット → 上に投げる → 結果:目的カードが4番目と8番目に配置され、4人配りで同じ人に落ちる。
3枚ストック(トップ1枚+ボトム2枚)
上記手順を1ステップ延長し、インジョグとアウトジョグを組み合わせて3枚を4・8・12番目に配置。
4枚ストック(トップ1枚+ボトム3枚)
さらにステップを延長し、4・8・12・16番目に配置。
5枚ストック(トップ1枚+ボトム4枚)
同様に延長し、4・8・12・16・20番目に配置(複雑なため使用頻度は低い)。
特徴
配る人数がそのまま操作の基準数になるため、計算不要。
インジョグ/アウトジョグとブレイク保持を組み合わせ、カードを所定の位置に送る。
アードネス法よりもシンプルで再現性が高い。
オフザテーブル・フォールスリフルシャッフル(Off the Table False Riffle Shuffle)
用途 テーブルが使えない状況でのリフルシャッフルに見せかけたフォールスシャッフル。非常に欺瞞性が高い。
手順
右手でデックを端から持ち、右親指で半分をリフルして左手指上に落とす。
両パケットを持ち、外角をリフル。最初に左親指から6枚ほど落とし、その後は外角をわずかに噛ませる程度にリフル。最後の6枚ほどは右親指から落とす。
右親指で押し出したカードのファンがカバーとなり、外角を合わせてひねり、噛み合わせを外す。パケットは並行状態になるが、外見上はまだ噛み合っているように見える。
右パケット内端を持ち上げて左パケット上に置き、左親指で押さえながら右手で右側を軽く叩いてスクエア。
右手親指と指で端を揃える。
ポイント
動作テンポは通常のリフルシャッフルと同じにし、スクエア時の力加減も本物と同様にすることで自然さを保つ。
背景
これまでオーバーハンドシャッフルでのストック法は、アードネス(Erdnase)法が唯一出版されていた。
アードネス法は有効だが、配る人数によって計算が変わるためパターンが一定せず、実戦では混乱しやすい。
本書の方法は配る人数(例:4人なら4)を基準に全てのラン数を決めるため、計算が不要で覚えやすい。
各カードのストック手順はパターン化されており、理解すれば高速かつ確実に行える。
例:4人配りの場合(数字4を基準にラン数を決定)
2枚ストック(トップ1枚+ボトム1枚)
半分アンダーカット → 3枚ラン → 4枚目をインジョグ → 残りをシャッフルオフ(元ボトムカードがトップへ)
インジョグでアンダーカット → 4枚ラン → 3枚ラン → 4枚目をインジョグ → シャッフルオフ
インジョグでアンダーカット → 上に投げる → 結果:目的カードが4番目と8番目に配置され、4人配りで同じ人に落ちる。
3枚ストック(トップ1枚+ボトム2枚)
上記手順を1ステップ延長し、インジョグとアウトジョグを組み合わせて3枚を4・8・12番目に配置。
4枚ストック(トップ1枚+ボトム3枚)
さらにステップを延長し、4・8・12・16番目に配置。
5枚ストック(トップ1枚+ボトム4枚)
同様に延長し、4・8・12・16・20番目に配置(複雑なため使用頻度は低い)。
特徴
配る人数がそのまま操作の基準数になるため、計算不要。
インジョグ/アウトジョグとブレイク保持を組み合わせ、カードを所定の位置に送る。
アードネス法よりもシンプルで再現性が高い。
オフザテーブル・フォールスリフルシャッフル(Off the Table False Riffle Shuffle)
用途 テーブルが使えない状況でのリフルシャッフルに見せかけたフォールスシャッフル。非常に欺瞞性が高い。
手順
右手でデックを端から持ち、右親指で半分をリフルして左手指上に落とす。
両パケットを持ち、外角をリフル。最初に左親指から6枚ほど落とし、その後は外角をわずかに噛ませる程度にリフル。最後の6枚ほどは右親指から落とす。
右親指で押し出したカードのファンがカバーとなり、外角を合わせてひねり、噛み合わせを外す。パケットは並行状態になるが、外見上はまだ噛み合っているように見える。
右パケット内端を持ち上げて左パケット上に置き、左親指で押さえながら右手で右側を軽く叩いてスクエア。
右手親指と指で端を揃える。
ポイント
動作テンポは通常のリフルシャッフルと同じにし、スクエア時の力加減も本物と同様にすることで自然さを保つ。
フォールス・ランニング・カット(The False Running Cut)
目的 デックの異なる位置にバラバラに差し込まれた複数のカード(例:4枚のエース)を、観客に気づかれずにまとめる。
a. 裏向きで行う場合
デックを左手に持ち、4枚のエースを外端から異なる位置に差し込み、各カードを約1インチ突き出させる。
左人差し指でボトムカードを前方に押し出し、突き出たカードと揃える。
右手でデックを覆い、突き出た5枚を押し込むふりをして左方向に押し、斜めにデック内を通して内端側に約1.3cm(1/2インチ)ジョグさせる。この動作は右手で完全にカバー。
左手を返してデックを表向きにし、左小指第二関節と親指付け根でジョグされた5枚を挟み、右手でデックをつかんで左手で5枚を抜き取り、表向きでテーブルに置く(先頭はダミーカードでエースを隠す)。
残りのカードも同様に小パケットでテーブルに置き、最後にデックを揃えると4枚のエースがトップに揃う。
b. 表向きで行う場合
基本はaと同じだが、ボトムカードを押し出す工程を省く。
ジョグ後、左手でデックを保持し、右手でボトムから小パケットを抜き取ってテーブルに置くランニングカットを行い、最後にジョグされたカードをまとめてトップに置く。
特徴
動作は一瞬で、右手のカバーにより視覚的に完全に隠れる。
表向き・裏向きどちらでも可能。
ギャンブラーズ・フォールス・カット(Gamblers’ False Cut – “Up the Ladder”)
目的 デック全体の順序を完全に保持したまま、複雑なカットに見せる。ギャンブル由来の高度なフォールスカット。
手順
両手でデックを持ち、中央付近で分ける。
下半分(II)を右に引き、上半分(I)の上に約1.3cm(1/2インチ)右にジョグして置く。
右手で小パケットCを抜き取り、Iの上にフラッシュで置く。このときCとIの間に自動的にブレイクができ、左親指で保持。
IIから小パケットBを抜き取り、Cの上に置く。
同様にIから小パケットAを抜き取り、Bの上に置く。
最後にブレイク下のIを同じランニングカットで処理し、元の順序に戻す。
特徴
外見は複雑なカットだが、順序は完全保持。
Strip-Out False Shuffle(p.67)後に続けると、シャッフルとカットの両方を見せられる。
ギャンブラーズ・フォールス・カット(ボトムストック保持)
(Gamblers’ False Cut Retaining Bottom Stock)
目的 観客による本物のカット後でも、ボトムの特定カード群(例:4枚のエース)を保持する。
手順
リフルシャッフルを行い、角を噛ませつつ、各パケットの側面を人差し指で押さえて上向きに反らせる。エース4枚を最初に落とす。
カードをスクエアし、長辺方向に軽いクリンプを付けて背面をわずかに凹ませる。観客にカットさせる。
カット後、下パケットBを右手で持ち、ボトムから6枚ほどを右親指で滑らせて右指で保持(左側はテーブルに接地)。
BをAにスライドさせる際、左親指でAの左側を押し、右側をわずかに浮かせる。
Bの分離した6枚をAの下に滑り込ませ、残りを上に重ねる。
デックを揃えながら左手でクリンプを戻す。エースは依然としてボトムにある。
総評
False Running Cut:複数カードを瞬時にまとめる。
Gamblers’ False Cut(Up the Ladder):順序保持型の高度な見せカット。
Gamblers’ False Cut Retaining Bottom Stock:観客カット後でもボトムストックを保持。
目的 デックの異なる位置にバラバラに差し込まれた複数のカード(例:4枚のエース)を、観客に気づかれずにまとめる。
a. 裏向きで行う場合
デックを左手に持ち、4枚のエースを外端から異なる位置に差し込み、各カードを約1インチ突き出させる。
左人差し指でボトムカードを前方に押し出し、突き出たカードと揃える。
右手でデックを覆い、突き出た5枚を押し込むふりをして左方向に押し、斜めにデック内を通して内端側に約1.3cm(1/2インチ)ジョグさせる。この動作は右手で完全にカバー。
左手を返してデックを表向きにし、左小指第二関節と親指付け根でジョグされた5枚を挟み、右手でデックをつかんで左手で5枚を抜き取り、表向きでテーブルに置く(先頭はダミーカードでエースを隠す)。
残りのカードも同様に小パケットでテーブルに置き、最後にデックを揃えると4枚のエースがトップに揃う。
b. 表向きで行う場合
基本はaと同じだが、ボトムカードを押し出す工程を省く。
ジョグ後、左手でデックを保持し、右手でボトムから小パケットを抜き取ってテーブルに置くランニングカットを行い、最後にジョグされたカードをまとめてトップに置く。
特徴
動作は一瞬で、右手のカバーにより視覚的に完全に隠れる。
表向き・裏向きどちらでも可能。
ギャンブラーズ・フォールス・カット(Gamblers’ False Cut – “Up the Ladder”)
目的 デック全体の順序を完全に保持したまま、複雑なカットに見せる。ギャンブル由来の高度なフォールスカット。
手順
両手でデックを持ち、中央付近で分ける。
下半分(II)を右に引き、上半分(I)の上に約1.3cm(1/2インチ)右にジョグして置く。
右手で小パケットCを抜き取り、Iの上にフラッシュで置く。このときCとIの間に自動的にブレイクができ、左親指で保持。
IIから小パケットBを抜き取り、Cの上に置く。
同様にIから小パケットAを抜き取り、Bの上に置く。
最後にブレイク下のIを同じランニングカットで処理し、元の順序に戻す。
特徴
外見は複雑なカットだが、順序は完全保持。
Strip-Out False Shuffle(p.67)後に続けると、シャッフルとカットの両方を見せられる。
ギャンブラーズ・フォールス・カット(ボトムストック保持)
(Gamblers’ False Cut Retaining Bottom Stock)
目的 観客による本物のカット後でも、ボトムの特定カード群(例:4枚のエース)を保持する。
手順
リフルシャッフルを行い、角を噛ませつつ、各パケットの側面を人差し指で押さえて上向きに反らせる。エース4枚を最初に落とす。
カードをスクエアし、長辺方向に軽いクリンプを付けて背面をわずかに凹ませる。観客にカットさせる。
カット後、下パケットBを右手で持ち、ボトムから6枚ほどを右親指で滑らせて右指で保持(左側はテーブルに接地)。
BをAにスライドさせる際、左親指でAの左側を押し、右側をわずかに浮かせる。
Bの分離した6枚をAの下に滑り込ませ、残りを上に重ねる。
デックを揃えながら左手でクリンプを戻す。エースは依然としてボトムにある。
総評
False Running Cut:複数カードを瞬時にまとめる。
Gamblers’ False Cut(Up the Ladder):順序保持型の高度な見せカット。
Gamblers’ False Cut Retaining Bottom Stock:観客カット後でもボトムストックを保持。
フェードアウェイ・カードチェンジの概要
現象(観客の見え方)
マジシャンは右手に1枚のカード(例: 6)を持ち、表を見せる。
6)を持ち、表を見せる。
一瞬後、そのカードが観客の目の前で別のカード(例: 2)に変わる。
2)に変わる。
観客は「カードが消えて別のカードが現れた」ように錯覚する。
原理
実際には、右手のカードとデックのトップカードをトップチェンジで入れ替える。
特徴は、両手の動きと自然なモーションを利用して、入れ替えの瞬間を完全にカバーする点。
基本グリップとトップチェンジの動作
左手(デック):メカニクスグリップに近い持ち方。親指はトップに横たえ、人差し指は外端を斜め上に、残り3本は右側面。
右手(カード):内右角を親指(上)と人差し指(表側)でつまみ、中指側面を内端に当てる。
左手の動き
親指を引き、先端をトップカード左側付近に置く。
親指をまっすぐ伸ばし、トップカードを右側にスライドさせる。
親指は右方向やや上に向けたまま固定。
右手の動き
カードを持ったままデックに近づける。
親指付け根でカードを押し出すようにしてデック上に滑らせる(左親指の下を通す)。
同時に左親指で右に押し出されたトップカードを右手の指でつかむ。
→ 両動作を同時に行い、カード同士が一瞬で入れ替わる。
フェードアウェイ・チェンジとしての演出
右手に 6、左手デックのトップに
6、左手デックのトップに 2をセット。
2をセット。
両手を腰の高さで8インチほど離して構える。
右手カードを観客に見せ、水平に持つ。
右手を左上方向、左手を右上方向に弧を描くように動かし、手が交差する瞬間にトップチェンジ。
動きを続けて両手を顔の高さまで上げ、右手のカード( 2)を観客に見せる。
2)を観客に見せる。
左手で軽く右手カードを指先でタップし、「ほら、変わったでしょう」というジェスチャー。
錯覚を生む要因
動きの勢いとタイミング:両手が互いに近づく自然なモーションの中で高速にチェンジ。
視覚的カバー:右手カードがデックに滑り込む動きと、デックからカードが出てくる動きが同時に起こるため、入れ替えが見えない。
グリップの一貫性:観客には右手指がカードの角をずっと保持しているように見える。
応用
両方のカードを表向きにして行えば、観客に見せながら密かにカードを入れ替えられる。
チェンジ後のカードは伏せて置く、観客に持たせる、息を吹きかけて変化させるなど、演出の幅が広い。
現象(観客の見え方)
マジシャンは右手に1枚のカード(例:
一瞬後、そのカードが観客の目の前で別のカード(例:
観客は「カードが消えて別のカードが現れた」ように錯覚する。
原理
実際には、右手のカードとデックのトップカードをトップチェンジで入れ替える。
特徴は、両手の動きと自然なモーションを利用して、入れ替えの瞬間を完全にカバーする点。
基本グリップとトップチェンジの動作
左手(デック):メカニクスグリップに近い持ち方。親指はトップに横たえ、人差し指は外端を斜め上に、残り3本は右側面。
右手(カード):内右角を親指(上)と人差し指(表側)でつまみ、中指側面を内端に当てる。
左手の動き
親指を引き、先端をトップカード左側付近に置く。
親指をまっすぐ伸ばし、トップカードを右側にスライドさせる。
親指は右方向やや上に向けたまま固定。
右手の動き
カードを持ったままデックに近づける。
親指付け根でカードを押し出すようにしてデック上に滑らせる(左親指の下を通す)。
同時に左親指で右に押し出されたトップカードを右手の指でつかむ。
→ 両動作を同時に行い、カード同士が一瞬で入れ替わる。
フェードアウェイ・チェンジとしての演出
右手に
両手を腰の高さで8インチほど離して構える。
右手カードを観客に見せ、水平に持つ。
右手を左上方向、左手を右上方向に弧を描くように動かし、手が交差する瞬間にトップチェンジ。
動きを続けて両手を顔の高さまで上げ、右手のカード(
左手で軽く右手カードを指先でタップし、「ほら、変わったでしょう」というジェスチャー。
錯覚を生む要因
動きの勢いとタイミング:両手が互いに近づく自然なモーションの中で高速にチェンジ。
視覚的カバー:右手カードがデックに滑り込む動きと、デックからカードが出てくる動きが同時に起こるため、入れ替えが見えない。
グリップの一貫性:観客には右手指がカードの角をずっと保持しているように見える。
応用
両方のカードを表向きにして行えば、観客に見せながら密かにカードを入れ替えられる。
チェンジ後のカードは伏せて置く、観客に持たせる、息を吹きかけて変化させるなど、演出の幅が広い。
スライド・トップチェンジ(The Slide Top Change)
背景
「トップカードとセカンドカードを、トップカードをデックから離さずに入れ替える」実用的な方法は長らく存在しなかった。
従来の2つの方法は、いずれもオープンな操作が必要で、密かな交換には不向き。
この方法は、カードの表を見せずに完全にシークレットに交換できる。
手順
左手でディーリングポジションにデックを持ち、右手で軽くスクエアする動作を始める。
左親指でトップカードを右に約1インチ押し出し、右手小指第一関節と親指付け根の肉で挟む。
左親指をセカンドカードの表面に下ろし、右側を約1/4インチ持ち上げながら左に引き、トップカードから外す。
右手を左に動かしながら、トップカードの左側をセカンドカードの右側下に滑り込ませる。
両カードをスクエアしながら動作を終える。
特徴と用途
動作は1秒以内で完了し、右手の甲が常にトップカードを隠す。
アンビシャスカードの繰り返しダブルリフトのセットアップに有効。
スライド中に左小指でブレイクを作れば、次のダブルリフトの準備も同時にできる。
スロー・トップチェンジ(The Throw Top Change)
背景
基本動作はオーソドックスなトップチェンジに似ているが、カードを「投げる」動作を利用してカバーする。
テーブルを左後方に置いた状況で行うと効果的。
手順
右手に交換元カード(例: A)を持ち、左手にデック(トップに交換先カード、例:
A)を持ち、左手にデック(トップに交換先カード、例: A)を持つ。
A)を持つ。
左親指と人差し指・中指でトップカードを約1インチ押し出して保持。
右手をテーブル方向に振る直前に、左手トップカードをテーブルに「投げる」ように見せかけ、実際は右手カードと入れ替える。
左手は外側または上方に動かして観客の注意を引き、右手は投げたような動きを続ける。
特徴
タイミングが重要だが、動作に自然な理由があるため非常にカバーが効く。
テーブルや床にカードを投げる演出の中で行うと不可視性が高い。
チップオーバー・チェンジ(The Tip-Over Change)
背景
カードを表向きに見せた直後、伏せる動作の中で別カードを重ねて入れ替える。
マーリンの方法を改良し、同じカードで連続してチェンジを行えるようにした。
手順
左手でディーリングポジションにデックを持ち、小指で選ばれたカードの上にブレイクを作る。
ブレイク位置で右手パケットを持ち上げ、右人差し指と中指を外端左角付近に置く(Fig.1)。
左親指で下パケットのトップカード(選ばれたカード)を左に押し出し、右手パケットの左側で弾いて表向きに返す。
観客の注意が表向きカードに集中している間に、右中指第三関節で右手パケットのフェイスカードを押し出し、斜めに構えて右親指と中指で保持(Fig.2)。
左親指で表向きカードを押し出して伏せる動作の中で、右手パケットを左パケット上に重ね、保持していた別カードをそっと上に置く。
左パケットのトップカードをテーブルに送る。観客はこれが先ほどのカードだと思うが、実際は別カードで、選ばれたカードはまだ左パケットのトップにある。
特徴と応用
アンビシャスカードのフィナーレに最適。
同じカードで何度もチェンジを繰り返せる。
最後にデックを広げてダブりがないことを示すことで強いクリーンエンドが作れる。
背景
「トップカードとセカンドカードを、トップカードをデックから離さずに入れ替える」実用的な方法は長らく存在しなかった。
従来の2つの方法は、いずれもオープンな操作が必要で、密かな交換には不向き。
この方法は、カードの表を見せずに完全にシークレットに交換できる。
手順
左手でディーリングポジションにデックを持ち、右手で軽くスクエアする動作を始める。
左親指でトップカードを右に約1インチ押し出し、右手小指第一関節と親指付け根の肉で挟む。
左親指をセカンドカードの表面に下ろし、右側を約1/4インチ持ち上げながら左に引き、トップカードから外す。
右手を左に動かしながら、トップカードの左側をセカンドカードの右側下に滑り込ませる。
両カードをスクエアしながら動作を終える。
特徴と用途
動作は1秒以内で完了し、右手の甲が常にトップカードを隠す。
アンビシャスカードの繰り返しダブルリフトのセットアップに有効。
スライド中に左小指でブレイクを作れば、次のダブルリフトの準備も同時にできる。
スロー・トップチェンジ(The Throw Top Change)
背景
基本動作はオーソドックスなトップチェンジに似ているが、カードを「投げる」動作を利用してカバーする。
テーブルを左後方に置いた状況で行うと効果的。
手順
右手に交換元カード(例:
左親指と人差し指・中指でトップカードを約1インチ押し出して保持。
右手をテーブル方向に振る直前に、左手トップカードをテーブルに「投げる」ように見せかけ、実際は右手カードと入れ替える。
左手は外側または上方に動かして観客の注意を引き、右手は投げたような動きを続ける。
特徴
タイミングが重要だが、動作に自然な理由があるため非常にカバーが効く。
テーブルや床にカードを投げる演出の中で行うと不可視性が高い。
チップオーバー・チェンジ(The Tip-Over Change)
背景
カードを表向きに見せた直後、伏せる動作の中で別カードを重ねて入れ替える。
マーリンの方法を改良し、同じカードで連続してチェンジを行えるようにした。
手順
左手でディーリングポジションにデックを持ち、小指で選ばれたカードの上にブレイクを作る。
ブレイク位置で右手パケットを持ち上げ、右人差し指と中指を外端左角付近に置く(Fig.1)。
左親指で下パケットのトップカード(選ばれたカード)を左に押し出し、右手パケットの左側で弾いて表向きに返す。
観客の注意が表向きカードに集中している間に、右中指第三関節で右手パケットのフェイスカードを押し出し、斜めに構えて右親指と中指で保持(Fig.2)。
左親指で表向きカードを押し出して伏せる動作の中で、右手パケットを左パケット上に重ね、保持していた別カードをそっと上に置く。
左パケットのトップカードをテーブルに送る。観客はこれが先ほどのカードだと思うが、実際は別カードで、選ばれたカードはまだ左パケットのトップにある。
特徴と応用
アンビシャスカードのフィナーレに最適。
同じカードで何度もチェンジを繰り返せる。
最後にデックを広げてダブりがないことを示すことで強いクリーンエンドが作れる。
プッシュイン・チェンジ(The Push-In Change)
概要
ダブルリフトで2枚を1枚に見せ、下のカードを観客に覚えさせた状態でデックの外端に差し込み、下のカードだけを押し込み、残った上のカードを取り出して見せることでカードが変わったように見せる。
古典的で効果的なチェンジだが、従来法では下のカードが押し込まれる瞬間に端が見えてしまう弱点があった。
本書の方法は、その視覚的な欠点を解消している。
手順
ダブルリフトで2枚を完全に揃え、右手親指(上)と中指(表側)で外右角をつまみ、人差し指先端を外端に添えて保持。
下のカードの表を見せ、2枚をまとめて左手のデック外端に差し込む。左親指でブレイクを作り、デックを左指先に移動させる。
2枚を押し込み、外端から約3/4インチ残す。
右親指で上のカードを外かつ左方向に押し出し、同時に右中指先端で下のカードをわずかに右に引く。これにより下のカードの角は右親指の付け根で隠れ、左側や端からは見えない。
左人差し指先端で下のカード外端を押し込み、上のカードだけが突き出た状態にする。このカードを取り出して使う。
特徴
上下のカードの動きを同時に行うことで、下カードの押し込みが完全に隠れる。
表裏の組み合わせは自由(デックとカードの向きも問わない)。
ドロップ・スイッチ(The Drop Switch)
概要
観客が自由に選んだカードを密かに自分の手元に残し、別のカードを観客に渡すためのスイッチ。
シンプルで自然な動作の中で行える。
手順
左手でデックを持ち、観客にジョーカーをデック外端にクロスして差し込ませる。
右手をデック上に置き、親指を内端、中指を外端に置いてジョーカーより上の全カードを持ち上げる。上パケットの表を見せる(例: A)。
A)。
右親指からこのカードを内端で落とす。
上パケット内端を右方向に動かし、中指を支点にして斜めにずらす。この動きで A以外のカードが右に移動し、
A以外のカードが右に移動し、 Aは下パケット上に残る。
Aは下パケット上に残る。
右手で上パケットとジョーカーをつまみ、テーブルに置く。左手では小指を曲げて Aを下パケット上に保持。
Aを下パケット上に保持。
観客はテーブル上のパケットの表カードが Aだと思っているが、実際は
Aだと思っているが、実際は Aは左手デックのトップに残っている。
Aは左手デックのトップに残っている。
特徴
観客の選択や挿入動作を利用して自然にスイッチが行える。
概要
ダブルリフトで2枚を1枚に見せ、下のカードを観客に覚えさせた状態でデックの外端に差し込み、下のカードだけを押し込み、残った上のカードを取り出して見せることでカードが変わったように見せる。
古典的で効果的なチェンジだが、従来法では下のカードが押し込まれる瞬間に端が見えてしまう弱点があった。
本書の方法は、その視覚的な欠点を解消している。
手順
ダブルリフトで2枚を完全に揃え、右手親指(上)と中指(表側)で外右角をつまみ、人差し指先端を外端に添えて保持。
下のカードの表を見せ、2枚をまとめて左手のデック外端に差し込む。左親指でブレイクを作り、デックを左指先に移動させる。
2枚を押し込み、外端から約3/4インチ残す。
右親指で上のカードを外かつ左方向に押し出し、同時に右中指先端で下のカードをわずかに右に引く。これにより下のカードの角は右親指の付け根で隠れ、左側や端からは見えない。
左人差し指先端で下のカード外端を押し込み、上のカードだけが突き出た状態にする。このカードを取り出して使う。
特徴
上下のカードの動きを同時に行うことで、下カードの押し込みが完全に隠れる。
表裏の組み合わせは自由(デックとカードの向きも問わない)。
ドロップ・スイッチ(The Drop Switch)
概要
観客が自由に選んだカードを密かに自分の手元に残し、別のカードを観客に渡すためのスイッチ。
シンプルで自然な動作の中で行える。
手順
左手でデックを持ち、観客にジョーカーをデック外端にクロスして差し込ませる。
右手をデック上に置き、親指を内端、中指を外端に置いてジョーカーより上の全カードを持ち上げる。上パケットの表を見せる(例:
右親指からこのカードを内端で落とす。
上パケット内端を右方向に動かし、中指を支点にして斜めにずらす。この動きで
右手で上パケットとジョーカーをつまみ、テーブルに置く。左手では小指を曲げて
観客はテーブル上のパケットの表カードが
特徴
観客の選択や挿入動作を利用して自然にスイッチが行える。
レギュラー・クリンプ(The Regular Crimp)
目的 観客がカードを戻す際、そのカードの角を下向きに曲げてキーとして利用する。
方法
デックを両手で広げ、観客にカードを戻させる。
左手中指先端をカード表面の外右角(インデックス角)に押し当てる。
右手でスプレッドを閉じる動作の中で、右手中指先端でその角を押し下げ、左中指先端にかぶせるように曲げる。
デックを左手でスクエアし、外左角を持って観客に渡す。このときデックを前後逆にすることで、観客からクリンプが見えない位置に移動する。
シャッフル後、デックを縦に持つとクリンプは上内角に現れ、容易に位置を特定できる。
リトルフィンガー・クリンプ(The Little Finger Crimp)
目的 カードを持ち上げる自然な動作の中で、下左角を上向きに曲げる。
方法
右手でカードを縦に持ち、親指を表側、人差し指〜薬指を裏側に置き、小指中関節を下左角に当てて押し上げる。
カードを確認するふりをしてすぐに置くことで、瞬時に安全にクリンプを作れる。
ギャンブラーズ・クリンプ(The Gamblers’ Crimp)
目的 ギャンブル現場で好まれる上向きクリンプ。テーブル上に置いたときに目立ちにくい。
方法
左親指でトップカードを押し出し、右手人差し指と中指で表側、親指で裏側の内右角をつかむ。
カードを表向きに返す動作の中で、中指で表側を押し、親指で裏側を押し返して角を上向きに曲げる。
表示動作の中で自然にクリンプが作れるため、キーとして即利用可能。
ピーク・クリンプ(The Peek Crimp)
目的 観客がカードを覗いた直後、そのカードを上向きに曲げてマーキングする。
方法
観客がカードを覗いたら、左小指で内右角付近にブレイクを作る。
右手でデックを覆い、ブレイクを右親指で保持。
スクエア動作の中で、そのカードを右親指から左小指先端に滑らせ、小指を内側に曲げて角を上向きにクリンプする。
カードマーキング・クリンプ(Card Marking Crimp)
目的 通常の角曲げよりも目立たず、マーキングシステムのように光の反射で位置を確認できるクリンプ。
特徴
どんなに強く作っても外見上は目立たない。
デック上面やテーブルスプレッドでも、光の反射による「艶切れ」で位置を確認できる。
片角・対角・片端両角などに作れるが、片端両角が最も実用的で、カットや位置確認が容易。
目的 観客がカードを戻す際、そのカードの角を下向きに曲げてキーとして利用する。
方法
デックを両手で広げ、観客にカードを戻させる。
左手中指先端をカード表面の外右角(インデックス角)に押し当てる。
右手でスプレッドを閉じる動作の中で、右手中指先端でその角を押し下げ、左中指先端にかぶせるように曲げる。
デックを左手でスクエアし、外左角を持って観客に渡す。このときデックを前後逆にすることで、観客からクリンプが見えない位置に移動する。
シャッフル後、デックを縦に持つとクリンプは上内角に現れ、容易に位置を特定できる。
リトルフィンガー・クリンプ(The Little Finger Crimp)
目的 カードを持ち上げる自然な動作の中で、下左角を上向きに曲げる。
方法
右手でカードを縦に持ち、親指を表側、人差し指〜薬指を裏側に置き、小指中関節を下左角に当てて押し上げる。
カードを確認するふりをしてすぐに置くことで、瞬時に安全にクリンプを作れる。
ギャンブラーズ・クリンプ(The Gamblers’ Crimp)
目的 ギャンブル現場で好まれる上向きクリンプ。テーブル上に置いたときに目立ちにくい。
方法
左親指でトップカードを押し出し、右手人差し指と中指で表側、親指で裏側の内右角をつかむ。
カードを表向きに返す動作の中で、中指で表側を押し、親指で裏側を押し返して角を上向きに曲げる。
表示動作の中で自然にクリンプが作れるため、キーとして即利用可能。
ピーク・クリンプ(The Peek Crimp)
目的 観客がカードを覗いた直後、そのカードを上向きに曲げてマーキングする。
方法
観客がカードを覗いたら、左小指で内右角付近にブレイクを作る。
右手でデックを覆い、ブレイクを右親指で保持。
スクエア動作の中で、そのカードを右親指から左小指先端に滑らせ、小指を内側に曲げて角を上向きにクリンプする。
カードマーキング・クリンプ(Card Marking Crimp)
目的 通常の角曲げよりも目立たず、マーキングシステムのように光の反射で位置を確認できるクリンプ。
特徴
どんなに強く作っても外見上は目立たない。
デック上面やテーブルスプレッドでも、光の反射による「艶切れ」で位置を確認できる。
片角・対角・片端両角などに作れるが、片端両角が最も実用的で、カットや位置確認が容易。
スペクテイター・ピーク改良版(The Spectator Peek Improved)
概要
観客にカードを覗かせた後、その位置を密かにブレイクで保持する技法。
従来は人差し指先端でブレイクを保持する方法が一般的だったが、ここでは左小指を使う改良法が紹介されている。
手順
左手でディーリングポジションにデックを持ち、小指は内端と揃え、カードを右にベベルさせてフェイスカードができるだけ見えるようにする。
デックを垂直にし、観客に外右角からカードのインデックスを覗かせる。この動作で右側全体にブレイクができる。
観客が上パケットを離す瞬間、左小指先端を内右角側面に軽く押し当ててブレイクを保持。外端側は左親指の圧で閉じているため外見上は見えない。
デックを水平に戻し、右手でスクエアするふりをしながら、デックを右上方向に傾けて左指上に立てる。このときも小指ブレイクは保持。
再び左手のひらに戻し、ディーリングポジションに構える。
ポイント
ブレイク保持後はすぐに動かず、観客の注意が薄れるタイミング(約1分後)でサイドスリップなどを行うと効果的。
スペクテイター・ピーク — ザ・ラストワード(The Spectator Peek — The Last Word)
概要
小指ブレイク法よりもさらに自然で、指先が常に観客から見える状態でブレイクを保持できる方法。
一流カードマンの間で秘匿されてきたが、ここで初公開されたとされる。
手順
左手でデックを持ち、左薬指中節を内端角側面に押し当て、右にベベルさせる。
観客に外右角からカードを覗かせる。このとき右側全体にブレイクができる。
観客が上パケットを離すとブレイクは閉じるが、その直前に薬指中節の肉をブレイクに押し込み、内端で保持する。
後でスクエアする動作の中で右親指がこのブレイクを受け取り、サイドスリップ、パス、シャッフルなど任意の方法でカードをコントロールできる。
特徴
指先が常に見えているため、観客に「ブレイクを保持している」という疑念を与えにくい。
ブレイクは内端にあるため、外見上は完全に自然。
ピーク後のカードコントロール(After the Spectator Peek)
一般的な流れ
サイドスリップが最もよく使われる(ピーク後にトップへ移動)。
ただし状況によっては、オーバーハンドシャッフルやエンドリフルシャッフルでトップに送る方法も有効。
例
オーバーハンドシャッフル:右手でデックを端から持ち、親指で内端のブレイクを保持したままシャッフル。
エンドリフルシャッフル:右親指でブレイクまでカードをリフルし、残りを上に置く。
概要
観客にカードを覗かせた後、その位置を密かにブレイクで保持する技法。
従来は人差し指先端でブレイクを保持する方法が一般的だったが、ここでは左小指を使う改良法が紹介されている。
手順
左手でディーリングポジションにデックを持ち、小指は内端と揃え、カードを右にベベルさせてフェイスカードができるだけ見えるようにする。
デックを垂直にし、観客に外右角からカードのインデックスを覗かせる。この動作で右側全体にブレイクができる。
観客が上パケットを離す瞬間、左小指先端を内右角側面に軽く押し当ててブレイクを保持。外端側は左親指の圧で閉じているため外見上は見えない。
デックを水平に戻し、右手でスクエアするふりをしながら、デックを右上方向に傾けて左指上に立てる。このときも小指ブレイクは保持。
再び左手のひらに戻し、ディーリングポジションに構える。
ポイント
ブレイク保持後はすぐに動かず、観客の注意が薄れるタイミング(約1分後)でサイドスリップなどを行うと効果的。
スペクテイター・ピーク — ザ・ラストワード(The Spectator Peek — The Last Word)
概要
小指ブレイク法よりもさらに自然で、指先が常に観客から見える状態でブレイクを保持できる方法。
一流カードマンの間で秘匿されてきたが、ここで初公開されたとされる。
手順
左手でデックを持ち、左薬指中節を内端角側面に押し当て、右にベベルさせる。
観客に外右角からカードを覗かせる。このとき右側全体にブレイクができる。
観客が上パケットを離すとブレイクは閉じるが、その直前に薬指中節の肉をブレイクに押し込み、内端で保持する。
後でスクエアする動作の中で右親指がこのブレイクを受け取り、サイドスリップ、パス、シャッフルなど任意の方法でカードをコントロールできる。
特徴
指先が常に見えているため、観客に「ブレイクを保持している」という疑念を与えにくい。
ブレイクは内端にあるため、外見上は完全に自然。
ピーク後のカードコントロール(After the Spectator Peek)
一般的な流れ
サイドスリップが最もよく使われる(ピーク後にトップへ移動)。
ただし状況によっては、オーバーハンドシャッフルやエンドリフルシャッフルでトップに送る方法も有効。
例
オーバーハンドシャッフル:右手でデックを端から持ち、親指で内端のブレイクを保持したままシャッフル。
エンドリフルシャッフル:右親指でブレイクまでカードをリフルし、残りを上に置く。
1. 新しいグリンプス(A New Glimpse)
目的 トップから任意の枚数下のカード(例:5枚目)を自然な動作で覗き見る。
手順
トップ4枚を右手で取り、表向きにして「選ばれたカードは含まれていない」と見せる。
戻す際に左小指を5枚目の下に差し込みブレイクを作る。
デックを右手に持ち替え、右小指で外右角のブレイクを保持。
デックを表向きにし、左手でボトム4〜5枚を左にスプレッドして「下の方にもない」と見せる。このとき右小指のブレイクから5枚目のカードのインデックスを自然に確認できる。
特徴
「下の方にもない」という見せ方が覗きのカバーになる。
ブレイクは観客から見えない位置で保持。
2. カードのグリンプス(Glimpsing a Card)
目的 トップから2枚目のカードを、視線を向けたと悟られずに確認する。
手順
左小指でトップ2枚の下にブレイクを作る。
左親指でトップカードを押し出し、表向きに返して2枚目と揃える。
右手親指と中指で両端をつまみ、人差し指を表向きカードの表面に軽く置く。
2枚を垂直に持ち上げ、表向きカードについてコメントしながら、2枚目のカードを「視線の端」で確認する。
2枚を戻し、表向きカードだけを再び垂直に持ち上げ、スナップして裏向きに戻す。
特徴
視線を直接カードに向けず、視界の端で認識する訓練が必要。
観客に「覗いた」と思わせない。
3. トップカード・グリンプス(Top Card Glimpse)
目的 トップカードを自然なジェスチャーの中で確認する。
条件
片手トップパームとトップカードのリプレイスメントが正確にできること。
手順
右手で片手トップパームを行い、デックを左手に持たせる。
観客に話しかけながら、右手を体から離すジェスチャーを行い、その瞬間にパームしたカードを確認。
すぐにカードをトップに戻す。
特徴
視線を落とすタイミングは会話の流れで自然に作る。
慣れると数秒〜十数秒パームしたまま保持できる。
4. ギャンブラーズ・グリンプス(The Gamblers’ Glimpse)
目的 「カードの反りを直す」動作に見せかけてトップカードを覗く。ギャンブル由来の技法。
手順
左手でデックを水平に持ち、親指を上、示指を下にして内端を支える。
右手で両端をつかみ、左親指でトップカードを右に少し押し出し、右上角のインデックスを露出させる。
そのまま右指で外端を下に曲げる動作をし、右手親指と指の間のアーチ越しにインデックスを確認する。
特徴
観客の目の前で堂々とデックを見るが、動作の理由付けが自然。
チャールズ・ミラーがマジシャン相手にも通用させたとされる。
目的 トップから任意の枚数下のカード(例:5枚目)を自然な動作で覗き見る。
手順
トップ4枚を右手で取り、表向きにして「選ばれたカードは含まれていない」と見せる。
戻す際に左小指を5枚目の下に差し込みブレイクを作る。
デックを右手に持ち替え、右小指で外右角のブレイクを保持。
デックを表向きにし、左手でボトム4〜5枚を左にスプレッドして「下の方にもない」と見せる。このとき右小指のブレイクから5枚目のカードのインデックスを自然に確認できる。
特徴
「下の方にもない」という見せ方が覗きのカバーになる。
ブレイクは観客から見えない位置で保持。
2. カードのグリンプス(Glimpsing a Card)
目的 トップから2枚目のカードを、視線を向けたと悟られずに確認する。
手順
左小指でトップ2枚の下にブレイクを作る。
左親指でトップカードを押し出し、表向きに返して2枚目と揃える。
右手親指と中指で両端をつまみ、人差し指を表向きカードの表面に軽く置く。
2枚を垂直に持ち上げ、表向きカードについてコメントしながら、2枚目のカードを「視線の端」で確認する。
2枚を戻し、表向きカードだけを再び垂直に持ち上げ、スナップして裏向きに戻す。
特徴
視線を直接カードに向けず、視界の端で認識する訓練が必要。
観客に「覗いた」と思わせない。
3. トップカード・グリンプス(Top Card Glimpse)
目的 トップカードを自然なジェスチャーの中で確認する。
条件
片手トップパームとトップカードのリプレイスメントが正確にできること。
手順
右手で片手トップパームを行い、デックを左手に持たせる。
観客に話しかけながら、右手を体から離すジェスチャーを行い、その瞬間にパームしたカードを確認。
すぐにカードをトップに戻す。
特徴
視線を落とすタイミングは会話の流れで自然に作る。
慣れると数秒〜十数秒パームしたまま保持できる。
4. ギャンブラーズ・グリンプス(The Gamblers’ Glimpse)
目的 「カードの反りを直す」動作に見せかけてトップカードを覗く。ギャンブル由来の技法。
手順
左手でデックを水平に持ち、親指を上、示指を下にして内端を支える。
右手で両端をつかみ、左親指でトップカードを右に少し押し出し、右上角のインデックスを露出させる。
そのまま右指で外端を下に曲げる動作をし、右手親指と指の間のアーチ越しにインデックスを確認する。
特徴
観客の目の前で堂々とデックを見るが、動作の理由付けが自然。
チャールズ・ミラーがマジシャン相手にも通用させたとされる。
従来法(概要)
観客がカードを覗いた後、ブレイクを保持し、デックを表向きに返して下側インデックスを覗く。
手の位置でカバーするが、やや不自然さが残る場合がある。
新しい実用的な方法
a. 小指ブレイク+ジョグ利用法
観客がカードを覗いた後、左小指でブレイクを保持。
右手でデックを覆い、右親指でブレイクを受け取る。
上パケットのフェイスカード(観客のカード)を右親指から左小指先端に落とし、小指を左にずらしてカード内端を左側に斜めに突き出し、インデックスを露出。
右親指を離してブレイクを閉じ、右指でスクエアするふりをする。
左親指をデック表面外左角に当て、デックを内向きに回して垂直に立てると、ジョグされたインデックスが下端に現れる。
右手を掌上にしてデックを持ち替え、表向きから裏向きに戻す動作の中でインデックスを確認し、右小指でカードを押し込みフラッシュに戻す。
特徴
左右の手の甲でジョグ部分が完全に隠れる。
任意の位置のカードにも応用可能(サムカウントで位置を取ってから同様に処理)。
b. 「カード当て」的な演出を伴う方法
スペクテイター・ピークの持ち方で観客にカードを覗かせる(ボトムカードは選ばないよう強調)。
観客が覗いたら、左小指でブレイクを保持し、左親指をデック左側に沿わせ、人差し指を下にカールさせて右手でスクエア。
上パケットの縁を小指先端で左に動かし、デックを表向きにすると自動的に上パケットが右にジョグされ、フェイスカード(選ばれたカード)のインデックスが見える。
右手でフェイスカードを軽く叩き「このボトムカードじゃないですよね?」と言いながらインデックスを確認。
裏向きに戻し、少し離れて観客に「その 5、忘れないでくださいね」とオフハンドに告げると、観客は驚きの表情を見せる。
5、忘れないでくださいね」とオフハンドに告げると、観客は驚きの表情を見せる。
特徴
ミスディレクションが非常に強く、ジョグは自動的に作られるため失敗がない。
マリーニ(Max Malini)がサロン演技で名物的に使った演出。
カバー動作(Cover for the Glimpse)
a. ギャンブラーズ・メソッド(1枚)
選ばれたカードをトップから2枚目に置く。
右手でトップカードを取り、表向きに見せながら左手のデックを垂直に立て、右手カードで外右角を隠す。
左親指でトップカードを少し押し下げて外にずらし、中央を反らせてインデックスを覗く。
ブラックジャックの「ホールカード確認」動作が元。
b. 1枚(トップカード)
右手を観客側に見せ、左手でデックを垂直に持ち上げる。
両手の指先を合わせるジェスチャーをしながら、左親指でトップカードをバックルしてインデックスを覗く。
c. 複数枚(5カードルーティンなど)
各カードをトップに送るたびに、右手の指に順番を数えるジェスチャーをしながらバックルして覗く。
「1人目のカード」「2人目のカード」と数える動作が自然な視線移動の理由になる。
観客がカードを覗いた後、ブレイクを保持し、デックを表向きに返して下側インデックスを覗く。
手の位置でカバーするが、やや不自然さが残る場合がある。
新しい実用的な方法
a. 小指ブレイク+ジョグ利用法
観客がカードを覗いた後、左小指でブレイクを保持。
右手でデックを覆い、右親指でブレイクを受け取る。
上パケットのフェイスカード(観客のカード)を右親指から左小指先端に落とし、小指を左にずらしてカード内端を左側に斜めに突き出し、インデックスを露出。
右親指を離してブレイクを閉じ、右指でスクエアするふりをする。
左親指をデック表面外左角に当て、デックを内向きに回して垂直に立てると、ジョグされたインデックスが下端に現れる。
右手を掌上にしてデックを持ち替え、表向きから裏向きに戻す動作の中でインデックスを確認し、右小指でカードを押し込みフラッシュに戻す。
特徴
左右の手の甲でジョグ部分が完全に隠れる。
任意の位置のカードにも応用可能(サムカウントで位置を取ってから同様に処理)。
b. 「カード当て」的な演出を伴う方法
スペクテイター・ピークの持ち方で観客にカードを覗かせる(ボトムカードは選ばないよう強調)。
観客が覗いたら、左小指でブレイクを保持し、左親指をデック左側に沿わせ、人差し指を下にカールさせて右手でスクエア。
上パケットの縁を小指先端で左に動かし、デックを表向きにすると自動的に上パケットが右にジョグされ、フェイスカード(選ばれたカード)のインデックスが見える。
右手でフェイスカードを軽く叩き「このボトムカードじゃないですよね?」と言いながらインデックスを確認。
裏向きに戻し、少し離れて観客に「その
特徴
ミスディレクションが非常に強く、ジョグは自動的に作られるため失敗がない。
マリーニ(Max Malini)がサロン演技で名物的に使った演出。
カバー動作(Cover for the Glimpse)
a. ギャンブラーズ・メソッド(1枚)
選ばれたカードをトップから2枚目に置く。
右手でトップカードを取り、表向きに見せながら左手のデックを垂直に立て、右手カードで外右角を隠す。
左親指でトップカードを少し押し下げて外にずらし、中央を反らせてインデックスを覗く。
ブラックジャックの「ホールカード確認」動作が元。
b. 1枚(トップカード)
右手を観客側に見せ、左手でデックを垂直に持ち上げる。
両手の指先を合わせるジェスチャーをしながら、左親指でトップカードをバックルしてインデックスを覗く。
c. 複数枚(5カードルーティンなど)
各カードをトップに送るたびに、右手の指に順番を数えるジェスチャーをしながらバックルして覗く。
「1人目のカード」「2人目のカード」と数える動作が自然な視線移動の理由になる。
The Side Jog(サイド・ジョグ)
目的 選ばれたカードをデックに戻す際、自然な動作で右側にわずかにジョグさせ、後でコントロールできるようにする。
手順(概要)
左手でデックをサムカウントの持ち方に構え、親指を側面に沿わせる。
選ばれたカードを外端から3/4ほど差し込み、右手中指・薬指を外端左角付近、親指を内端左角付近に置く。右人差し指は爪と第3関節全体をデック上面に置く。
カードを押し込むと、自動的に内右側に約1/8インチのジョグができる。左小指で拾ってブレイクに移行可能。
The Jog at the Break(ブレイクからジョグへ)
目的 常に小指ブレイクを保持する必要はなく、ジョグに変換すればデックを自由に扱える。
手順(概要)
観客がカードを覗いた後、小指ブレイクを保持。右手でデックを覆いスクエアするふりをしながら、右親指で上パケット内端を押し上げ、小指をブレイクに差し込む。
小指でカードを右に押し、内端を約1/4インチ斜めにジョグさせる。親指を離してブレイクを閉じる。
小指をカード側面に移動し、左に押し戻して内端ジョグにする。
右手で内端側をつかみ、左手で外端をスクエアする。このとき右手の保持でジョグは維持される。
ジョグからの展開
右親指でジョグカードを持ち上げ、小指ブレイクに戻してサイドスリップでトップへ。
ジョグ上にブレイクを作り、シャッフルやパスでコントロール。
Alternative Method(代替法)
概要 ブレイクからジョグへの変換を、より一瞬で自然に行う方法。
手順(概要)
小指ブレイクを保持した状態で、右手親指と中指で上パケットをつかむ。
小指をブレイクから外し、上パケットをわずかに内側へ動かす。
上パケットのボトムカードを親指先から外し、すぐにパケットを前方に押し戻して揃える。
この動作で自然にジョグが作られ、見た目は完全にスクエアしているように見える。
演出上のポイント
ジョグを作った後、袖をまくる・テーブルに置くなどの自然な所作を挟むと、「カードは完全に失われた」という印象を強められる。
ジョグはブレイクよりも自由度が高く、デックを手渡したり置いたりできる。
目的 選ばれたカードをデックに戻す際、自然な動作で右側にわずかにジョグさせ、後でコントロールできるようにする。
手順(概要)
左手でデックをサムカウントの持ち方に構え、親指を側面に沿わせる。
選ばれたカードを外端から3/4ほど差し込み、右手中指・薬指を外端左角付近、親指を内端左角付近に置く。右人差し指は爪と第3関節全体をデック上面に置く。
カードを押し込むと、自動的に内右側に約1/8インチのジョグができる。左小指で拾ってブレイクに移行可能。
The Jog at the Break(ブレイクからジョグへ)
目的 常に小指ブレイクを保持する必要はなく、ジョグに変換すればデックを自由に扱える。
手順(概要)
観客がカードを覗いた後、小指ブレイクを保持。右手でデックを覆いスクエアするふりをしながら、右親指で上パケット内端を押し上げ、小指をブレイクに差し込む。
小指でカードを右に押し、内端を約1/4インチ斜めにジョグさせる。親指を離してブレイクを閉じる。
小指をカード側面に移動し、左に押し戻して内端ジョグにする。
右手で内端側をつかみ、左手で外端をスクエアする。このとき右手の保持でジョグは維持される。
ジョグからの展開
右親指でジョグカードを持ち上げ、小指ブレイクに戻してサイドスリップでトップへ。
ジョグ上にブレイクを作り、シャッフルやパスでコントロール。
Alternative Method(代替法)
概要 ブレイクからジョグへの変換を、より一瞬で自然に行う方法。
手順(概要)
小指ブレイクを保持した状態で、右手親指と中指で上パケットをつかむ。
小指をブレイクから外し、上パケットをわずかに内側へ動かす。
上パケットのボトムカードを親指先から外し、すぐにパケットを前方に押し戻して揃える。
この動作で自然にジョグが作られ、見た目は完全にスクエアしているように見える。
演出上のポイント
ジョグを作った後、袖をまくる・テーブルに置くなどの自然な所作を挟むと、「カードは完全に失われた」という印象を強められる。
ジョグはブレイクよりも自由度が高く、デックを手渡したり置いたりできる。
Automatic Jog No. I
用途:2枚のカード(選ばれたカードやセットトリック用カード)を中央に戻した後、1枚をトップ、もう1枚をボトム付近にコントロールする。
手順の流れ
右手で2枚を持ち、上のカードを左にずらして観客に表を見せる。
左手のデックを縦に持ち、左親指で中央にブレイクを作る。
右手の上のカード外端をブレイクに差し込み、左親指から1枚を離して2枚の間に挟み込む(インタリーブ)。
2枚をデック上から半分ほど突き出した状態にし、左小指先端を下右角に差し込む。
右親指でデック背面を押さえ、右人差し指で2枚をゆっくり押し込み、残り1/4インチで小指を抜くと、間に挟んだカードが内端にジョグされる。
小指でジョグを拾い、パスを行えば1枚がトップ、もう1枚がボトム2枚目に収まる。
特徴
2枚同時コントロールが可能。
インタリーブ構造を利用して自然にジョグを作る。
Automatic Jog No. II
用途:1枚のカードを中央に戻した後、ブレイク不要でジョグを作る。
手順の流れ
デックをアンダーカットし、選ばれたカードを左手パケット上に戻す。
右手パケットを上に重ね、外端を約1/2インチ突き出させる。
右手でデック内端をつかみ、左手は下から支える。
左手親指と指で「ミルキング」動作を行い、下パケットのカードを前方に押し出す。
下パケットのトップカードだけが内端にジョグされた状態になる。
特徴
ブレイク不要で、デックを自由に扱える。
そのままヒンドゥーシャッフルやディレイドパスに移行可能。
Automatic Jog No. III
用途:No.IIと似ているが、上パケットを押し戻す動作でジョグを作る。
手順の流れ
選ばれたカードを左手パケット上に戻す。
右手パケットを上に重ね、外端を約1/4インチ突き出させる。
右人差し指でデック上面を押さえ、左人差し指でパケットを押し戻して揃える。
下パケットのトップカード(選ばれたカード)が内端にジョグされる。
特徴
No.IIよりも動作がコンパクト。
スクエア動作の中でジョグが作られるため、視覚的に自然。
3つの方法に共通する利点
ジョグは非常に小さくでき、テーブルに置いても目立たない。
ブレイクを持たずにカード位置をマーキングできるため、デックを自由に扱える。
その後のパス、シャッフル、カットなどにスムーズに移行可能。
用途:2枚のカード(選ばれたカードやセットトリック用カード)を中央に戻した後、1枚をトップ、もう1枚をボトム付近にコントロールする。
手順の流れ
右手で2枚を持ち、上のカードを左にずらして観客に表を見せる。
左手のデックを縦に持ち、左親指で中央にブレイクを作る。
右手の上のカード外端をブレイクに差し込み、左親指から1枚を離して2枚の間に挟み込む(インタリーブ)。
2枚をデック上から半分ほど突き出した状態にし、左小指先端を下右角に差し込む。
右親指でデック背面を押さえ、右人差し指で2枚をゆっくり押し込み、残り1/4インチで小指を抜くと、間に挟んだカードが内端にジョグされる。
小指でジョグを拾い、パスを行えば1枚がトップ、もう1枚がボトム2枚目に収まる。
特徴
2枚同時コントロールが可能。
インタリーブ構造を利用して自然にジョグを作る。
Automatic Jog No. II
用途:1枚のカードを中央に戻した後、ブレイク不要でジョグを作る。
手順の流れ
デックをアンダーカットし、選ばれたカードを左手パケット上に戻す。
右手パケットを上に重ね、外端を約1/2インチ突き出させる。
右手でデック内端をつかみ、左手は下から支える。
左手親指と指で「ミルキング」動作を行い、下パケットのカードを前方に押し出す。
下パケットのトップカードだけが内端にジョグされた状態になる。
特徴
ブレイク不要で、デックを自由に扱える。
そのままヒンドゥーシャッフルやディレイドパスに移行可能。
Automatic Jog No. III
用途:No.IIと似ているが、上パケットを押し戻す動作でジョグを作る。
手順の流れ
選ばれたカードを左手パケット上に戻す。
右手パケットを上に重ね、外端を約1/4インチ突き出させる。
右人差し指でデック上面を押さえ、左人差し指でパケットを押し戻して揃える。
下パケットのトップカード(選ばれたカード)が内端にジョグされる。
特徴
No.IIよりも動作がコンパクト。
スクエア動作の中でジョグが作られるため、視覚的に自然。
3つの方法に共通する利点
ジョグは非常に小さくでき、テーブルに置いても目立たない。
ブレイクを持たずにカード位置をマーキングできるため、デックを自由に扱える。
その後のパス、シャッフル、カットなどにスムーズに移行可能。
Facing the Deck(デックを向かい合わせにする)
目的
デックの上半分と下半分を逆向きにして、中央に「表向きと裏向きの境界」を作る。
これにより、表向きカードが両側に存在する状態を作り出す。
古典的な「フェイスド・デック」の原理を利用する。
従来法
レギュラーパスを使い、上半分を抜き取り、表向きにして下半分の下に入れる。
改良法(本書の方法)
右半身を観客に向け、左手でデックをチャーリエパスの構え(裏面を観客側)に持つ。
右手でデック両端を軽くつかみ、甲を観客側に向ける。
チャーリエパスの要領で下半分を左手のひらに落とし、左人差し指で押し上げ、両パケットの上面を親指付け根下で逆V字に合わせる。
左人差し指を伸ばし、両手でパケットを直接合わせる。このとき下パケットが反転し、上パケットは裏面を観客側に保ったまま。
特徴
動作は一瞬で完了し、右手でカバーされる。
同じ手順で元の向きに戻すことも可能。
1793年のM. Decremps『Testament de Jerome Sharp』にも記載されている古典原理。
Righting the Faced Deck – New Method(フェイスド・デックを元に戻す新方法)
目的
フェイスド・デックを元の一方向に揃える。
ハーフパスを繰り返すよりも自然で効率的。
手順
左手でフェイスド・デックをチャーリエパスの構えに持ち、親指の圧を緩めると、表向きと裏向きの境界で自然に分かれる。
左人差し指で下パケット(表向き)を押し上げ、上パケット(裏向き)と逆V字に合わせる。
左人差し指を伸ばし、親指で両パケット上面を押さえたまま、左指を内側に曲げて上パケットを反転させ、下パケットに重ねる。
同時に左親指で元の下パケットを外側に押し出し、全体を左手のひらで表向きに揃える。
演出上の使い方
公然と行えば「デックの向きを見せる」動作に見える。
目的
デックの上半分と下半分を逆向きにして、中央に「表向きと裏向きの境界」を作る。
これにより、表向きカードが両側に存在する状態を作り出す。
古典的な「フェイスド・デック」の原理を利用する。
従来法
レギュラーパスを使い、上半分を抜き取り、表向きにして下半分の下に入れる。
改良法(本書の方法)
右半身を観客に向け、左手でデックをチャーリエパスの構え(裏面を観客側)に持つ。
右手でデック両端を軽くつかみ、甲を観客側に向ける。
チャーリエパスの要領で下半分を左手のひらに落とし、左人差し指で押し上げ、両パケットの上面を親指付け根下で逆V字に合わせる。
左人差し指を伸ばし、両手でパケットを直接合わせる。このとき下パケットが反転し、上パケットは裏面を観客側に保ったまま。
特徴
動作は一瞬で完了し、右手でカバーされる。
同じ手順で元の向きに戻すことも可能。
1793年のM. Decremps『Testament de Jerome Sharp』にも記載されている古典原理。
Righting the Faced Deck – New Method(フェイスド・デックを元に戻す新方法)
目的
フェイスド・デックを元の一方向に揃える。
ハーフパスを繰り返すよりも自然で効率的。
手順
左手でフェイスド・デックをチャーリエパスの構えに持ち、親指の圧を緩めると、表向きと裏向きの境界で自然に分かれる。
左人差し指で下パケット(表向き)を押し上げ、上パケット(裏向き)と逆V字に合わせる。
左人差し指を伸ばし、親指で両パケット上面を押さえたまま、左指を内側に曲げて上パケットを反転させ、下パケットに重ねる。
同時に左親指で元の下パケットを外側に押し出し、全体を左手のひらで表向きに揃える。
演出上の使い方
公然と行えば「デックの向きを見せる」動作に見える。
Automatic Reverse
目的 選ばれたカードをデック内で密かに反転させる。表向きに見せたカードがトップでも2番目でもないことを示す動作の中で行う。
手順概要
選ばれたカードをトップから2枚目に置く。
トップカードを押し出して表向きに返し、揃える。
トップ2枚の下にブレイクを作る(上は表向きの無関係カード、下は裏向きの選ばれたカード)。
左親指で次のカードを右に押し出し、右手の2枚を下から跳ね上げてそのカードを表向きにフリップさせる。
それも無関係カードだと示し、右手の2枚の下に置き、3枚を裏向きにしてトップに戻す。 → 選ばれたカードはトップから2枚目で反転状態になる。
Righting a Reversed Bottom Card
目的 デック底にある反転カードを密かに正位置に戻す。特にロケーターカードとして使った後の処理に有効。
手順概要
右手でデックを持ち、底カードが反転している状態から開始。
左手の指の根元にデック左側を当て、底カード以外を指先方向に約1.3cm(1/2インチ)引き出す。
右手で上のカード群を持ち上げ、左指を内側に曲げて底カードを裏向きに返す(指の根元をヒンジにする)。
同時に右手親指から残りのカードをリフルして左手に落とし、動作全体をリフルの一部に見せる。
複数枚の反転カードにも応用可能。
Facing the Bottom Card
目的 デック底の1枚を密かに反転させる。キー・カード作成や、反転デックのカバー、選ばれたカードの発見などに利用。
手順概要
右手でデックを持ち、左手を近づけて左指先をトップカード中央に当て、カードを約1インチ押し出す。
デック左側を持ち上げ、押し出したカードの上に裏向きで被せるように返す。
左指でカードを押し上げ、左親指をデック背面に置き、オーバーハンドシャッフルの構えにする。
そのままオーバーハンドシャッフルを行い、反転カードを底に送る。
シャッフルを省略すれば、トップカードの反転にも応用可能。
Faced Deck Turnover
目的 フェイスド・デック(上下で向きが逆の状態)を密かに全て同じ向きに揃える。従来法よりカバーが少なく、動作が自然。
手順概要
フェイスド・デックを右手で左角をつまむように持つ(親指は内角、人差し指は外角)。
薬指と小指を内側に曲げ、薬指の爪をトップカード背面に当てる。
薬指を伸ばしてデックを半回転させ、親指と人差し指を支点にして向きを揃える。
右手から左手にデックを渡す動作の中で行えば、一瞬で不可視に処理できる。
目的 選ばれたカードをデック内で密かに反転させる。表向きに見せたカードがトップでも2番目でもないことを示す動作の中で行う。
手順概要
選ばれたカードをトップから2枚目に置く。
トップカードを押し出して表向きに返し、揃える。
トップ2枚の下にブレイクを作る(上は表向きの無関係カード、下は裏向きの選ばれたカード)。
左親指で次のカードを右に押し出し、右手の2枚を下から跳ね上げてそのカードを表向きにフリップさせる。
それも無関係カードだと示し、右手の2枚の下に置き、3枚を裏向きにしてトップに戻す。 → 選ばれたカードはトップから2枚目で反転状態になる。
Righting a Reversed Bottom Card
目的 デック底にある反転カードを密かに正位置に戻す。特にロケーターカードとして使った後の処理に有効。
手順概要
右手でデックを持ち、底カードが反転している状態から開始。
左手の指の根元にデック左側を当て、底カード以外を指先方向に約1.3cm(1/2インチ)引き出す。
右手で上のカード群を持ち上げ、左指を内側に曲げて底カードを裏向きに返す(指の根元をヒンジにする)。
同時に右手親指から残りのカードをリフルして左手に落とし、動作全体をリフルの一部に見せる。
複数枚の反転カードにも応用可能。
Facing the Bottom Card
目的 デック底の1枚を密かに反転させる。キー・カード作成や、反転デックのカバー、選ばれたカードの発見などに利用。
手順概要
右手でデックを持ち、左手を近づけて左指先をトップカード中央に当て、カードを約1インチ押し出す。
デック左側を持ち上げ、押し出したカードの上に裏向きで被せるように返す。
左指でカードを押し上げ、左親指をデック背面に置き、オーバーハンドシャッフルの構えにする。
そのままオーバーハンドシャッフルを行い、反転カードを底に送る。
シャッフルを省略すれば、トップカードの反転にも応用可能。
Faced Deck Turnover
目的 フェイスド・デック(上下で向きが逆の状態)を密かに全て同じ向きに揃える。従来法よりカバーが少なく、動作が自然。
手順概要
フェイスド・デックを右手で左角をつまむように持つ(親指は内角、人差し指は外角)。
薬指と小指を内側に曲げ、薬指の爪をトップカード背面に当てる。
薬指を伸ばしてデックを半回転させ、親指と人差し指を支点にして向きを揃える。
右手から左手にデックを渡す動作の中で行えば、一瞬で不可視に処理できる。
Vesting a Card(カードのベスティング)
概要
「ベスティング」とは、カードをポケットではなくベストの中に密かに処分する技法。
30年以上ほとんど使われず、忘れられた技法になっていたが、実は非常に簡単で安全。
手順の流れ
カードを右手にパームした状態で、両手をベストの両端に持っていく。
右手がベスト端に近づく直前、右中指第一関節を曲げてカード端をつかみ、反対側をパームから解放。
カード端をズボンの布に当て、腹部をわずかに引き、手を上に動かしてベストの中へ滑り込ませる。
指先をベスト内に入れてカードを押し上げ、そのままベストの裾を軽く引き下げる動作でカバー。左手も同じ動作をして自然さを演出。
ポイント
動作はゆっくり自然に。素早く鋭い動きは視線を引きつけてしまう。
「ベストを整える」という自然な所作に見える。
The Zingone Thumbnail Gauge(ジンゴーン・サムネイル・ゲージ)
概要
サムネイル(親指の爪)を使って、同じ枚数のカードを2回連続で正確にカットする方法。
ほぼ不可能と思われる偽の「感覚的カット」を可能にする。
手順の流れ
デックをテーブルに横向き(外側が観客側)に置く。
右手指を遠い側に当て、右親指先を内側端に置き、爪をトップカードの縁にかける。
親指を強く押し込み、肉を圧縮して爪をデック側面に食い込ませる。
その位置でパケットを持ち上げてテーブルに置く。
残りのカードでも同じ動作を繰り返すと、2つのパケットは同じ枚数になる。
A Cutting Discovery(カッティング・ディスカバリー)
概要
上記サムネイル・ゲージを使ったカード当ての一例。
観客が選んだカードを、見た目は偶然のカットで当てる。
手順の流れ
観客にシャッフルさせたデックを受け取り、テーブルに置く。
サムネイル・ゲージで同じ枚数のパケットを2つ切り出し、右側に並べる。残りをA、最初のパケットをB、次をCとする。
観客にBまたはCからカードを選び、覚えてAの上に置かせる。その後BとCをAの上に重ねる。
デックを揃えて再びサムネイル・ゲージで2つにカットし、カード名を聞いて2回目のカットの下にそのカードを見せる。
応用
カードをBからCに移すなど、順序を変えても対応可能。
概要
「ベスティング」とは、カードをポケットではなくベストの中に密かに処分する技法。
30年以上ほとんど使われず、忘れられた技法になっていたが、実は非常に簡単で安全。
手順の流れ
カードを右手にパームした状態で、両手をベストの両端に持っていく。
右手がベスト端に近づく直前、右中指第一関節を曲げてカード端をつかみ、反対側をパームから解放。
カード端をズボンの布に当て、腹部をわずかに引き、手を上に動かしてベストの中へ滑り込ませる。
指先をベスト内に入れてカードを押し上げ、そのままベストの裾を軽く引き下げる動作でカバー。左手も同じ動作をして自然さを演出。
ポイント
動作はゆっくり自然に。素早く鋭い動きは視線を引きつけてしまう。
「ベストを整える」という自然な所作に見える。
The Zingone Thumbnail Gauge(ジンゴーン・サムネイル・ゲージ)
概要
サムネイル(親指の爪)を使って、同じ枚数のカードを2回連続で正確にカットする方法。
ほぼ不可能と思われる偽の「感覚的カット」を可能にする。
手順の流れ
デックをテーブルに横向き(外側が観客側)に置く。
右手指を遠い側に当て、右親指先を内側端に置き、爪をトップカードの縁にかける。
親指を強く押し込み、肉を圧縮して爪をデック側面に食い込ませる。
その位置でパケットを持ち上げてテーブルに置く。
残りのカードでも同じ動作を繰り返すと、2つのパケットは同じ枚数になる。
A Cutting Discovery(カッティング・ディスカバリー)
概要
上記サムネイル・ゲージを使ったカード当ての一例。
観客が選んだカードを、見た目は偶然のカットで当てる。
手順の流れ
観客にシャッフルさせたデックを受け取り、テーブルに置く。
サムネイル・ゲージで同じ枚数のパケットを2つ切り出し、右側に並べる。残りをA、最初のパケットをB、次をCとする。
観客にBまたはCからカードを選び、覚えてAの上に置かせる。その後BとCをAの上に重ねる。
デックを揃えて再びサムネイル・ゲージで2つにカットし、カード名を聞いて2回目のカットの下にそのカードを見せる。
応用
カードをBからCに移すなど、順序を変えても対応可能。
Separating the Colors(赤黒分離)
目的
観客に気づかれずに、赤札と黒札を完全に分ける。
表向き/裏向きのカードが混ざっているように見せる「小さなフラリッシュ」の中で行う。
手順概要
デックを左手で表向きに持ち、トップから赤札を数枚押し出して右手に表向きで取る。
次に黒札が来たら、左手を返してデックを裏向きにし、それらを右手のパケット上に裏向きで重ねる。
再び左手を返してデックを表向きにし、赤札が来たら右手パケットの底(既存の赤札の下)に表向きで入れる。
黒札が来たら再び左手を返して裏向きで右手パケット上に重ねる。
この動作を繰り返すと、右手パケットの底半分(表向き)が赤札、上半分(裏向き)が黒札になる。
最後にp.108の方法(Faced Deck Righting)で全てのカードの向きを揃えると、赤黒が分離された状態になる。
演出上の注意
わざと数枚、逆色のカードを表向き側に混ぜて外端から突き出させておくと、観客に「色が揃っている」と気づかれにくい。
最後にファンを作る際、それらを取り除き正しい色の山に加える。
Setting a Key Card(キーカードのセット)
目的
選ばれたカードの位置を、あらかじめ知っているカード(キーカード)の直下に置く。
シンプルかつ確実な方法で、古典的原理を自然な動作に隠す。
方法1(ブレイク+ジェスチャー法)
観客にシャッフルさせ、デックを広げて自由にカードを選ばせる。
スプレッドを閉じる際、中央付近で左小指にブレイクを作る。
左手を返して観客のカードを指差すジェスチャーをし、その動きで上パケットを右にずらし、下カードのインデックスを自分だけが確認。
左手を元に戻し、ブレイクを保持。
右手でデックを覆い、左親指で軽くリフルしてからブレイクでカット。
下半分を差し出して選ばれたカードを置かせ、上半分を重ねて揃える。 → 選ばれたカードはキーカードの直下に位置する。
方法2(サムカウント持ち+リフル法)
左手でサムカウントの持ち方、右手で軽くデックを覆う。
左親指で軽くリフルし、中央付近で止めてインデックスを確認。
右親指でブレイクを保持し、左親指のブレイクを解放してスクエア。
左小指で再びブレイクを取り、デックを右に返してもブレイクを保持。
右手でデックを持ち替え、左手を通常のディーリングポジションに戻す。
ブレイクを保持したままトップカードを広げて選ばせ、戻したら前述の方法1の後半と同様に処理。
目的
観客に気づかれずに、赤札と黒札を完全に分ける。
表向き/裏向きのカードが混ざっているように見せる「小さなフラリッシュ」の中で行う。
手順概要
デックを左手で表向きに持ち、トップから赤札を数枚押し出して右手に表向きで取る。
次に黒札が来たら、左手を返してデックを裏向きにし、それらを右手のパケット上に裏向きで重ねる。
再び左手を返してデックを表向きにし、赤札が来たら右手パケットの底(既存の赤札の下)に表向きで入れる。
黒札が来たら再び左手を返して裏向きで右手パケット上に重ねる。
この動作を繰り返すと、右手パケットの底半分(表向き)が赤札、上半分(裏向き)が黒札になる。
最後にp.108の方法(Faced Deck Righting)で全てのカードの向きを揃えると、赤黒が分離された状態になる。
演出上の注意
わざと数枚、逆色のカードを表向き側に混ぜて外端から突き出させておくと、観客に「色が揃っている」と気づかれにくい。
最後にファンを作る際、それらを取り除き正しい色の山に加える。
Setting a Key Card(キーカードのセット)
目的
選ばれたカードの位置を、あらかじめ知っているカード(キーカード)の直下に置く。
シンプルかつ確実な方法で、古典的原理を自然な動作に隠す。
方法1(ブレイク+ジェスチャー法)
観客にシャッフルさせ、デックを広げて自由にカードを選ばせる。
スプレッドを閉じる際、中央付近で左小指にブレイクを作る。
左手を返して観客のカードを指差すジェスチャーをし、その動きで上パケットを右にずらし、下カードのインデックスを自分だけが確認。
左手を元に戻し、ブレイクを保持。
右手でデックを覆い、左親指で軽くリフルしてからブレイクでカット。
下半分を差し出して選ばれたカードを置かせ、上半分を重ねて揃える。 → 選ばれたカードはキーカードの直下に位置する。
方法2(サムカウント持ち+リフル法)
左手でサムカウントの持ち方、右手で軽くデックを覆う。
左親指で軽くリフルし、中央付近で止めてインデックスを確認。
右親指でブレイクを保持し、左親指のブレイクを解放してスクエア。
左小指で再びブレイクを取り、デックを右に返してもブレイクを保持。
右手でデックを持ち替え、左手を通常のディーリングポジションに戻す。
ブレイクを保持したままトップカードを広げて選ばせ、戻したら前述の方法1の後半と同様に処理。
The Five Card Quibble(ファイブ・カード・クイブル)
想定状況
観客が自由にカードを見てデックを戻し、マジシャンが正確な位置を見失ったが、上位5枚のどれかであることは分かっている。
例:観客が勝手にカットしてカードを見た/ピークが失敗した/コントロールを失ったが位置はおおよそ把握している場合。
基本戦略
5枚を特定の配置に分け、観客の反応を観察しながら段階的に候補を絞り込む。
どのカードが選ばれても、演出上は「意図的にそうした」ように見せる。
手順概要
パスなどで選ばれたカードをトップ5枚に持ってくる(例:A, 2, 3, 4, 5)。
ファンにして5枚を確認。3枚目のランク+1の位置まで数えて、そのカード群を抜き、A, 2, 3を左側に置く。残りのデックの底から3枚目に5、その下に4がある状態にする。
左側の3枚から観客に1枚選ばせ、反応を観察。
違えば残り2枚から選ばせ、さらに反応を観察。
それでも違えば3枚をまとめて2枚伏せ+1枚表にして見せる。
まだ違えば「このカードは○○、つまりあなたのカードはデックの底から3枚目」と宣言し、デックを表向きにして底から数えて見せる。
反応がなければ次のカードを見せ、必ず的中させる。
ポイント
中央のカードはほぼ必ず選ばれるため、そこからの展開がメインルート。
どの段階でも「失敗」ではなく「演出の一部」に見せる話術と間合いが重要。
Emergency Card Stabbing(エマージェンシー・カード・スタビング)
想定状況
選ばれたカードが5枚のうちのどれかであることは分かっているが、どれかは不明。
その場で確実に突き止める必要がある。
基本戦略
5枚を覚えやすい並び(電話番号のように)で記憶し、観客に挿入させた「インジケーターカード」を使って位置を特定する。
手順概要
5枚をボトムに集め、ランクを覚える(例:2-5-3-J-7)。同ランクがあれば最初のスートも記憶。
パスで5枚を中央に移し、小指ブレイクを保持。
トップカードを観客に渡し、好きな位置に挿入させる。このときインジケーターカードがブレイク下に入るよう誘導。
観客がカード名を言ったら、記憶した並びから必要枚数を右親指から落として、そのカードを下パケットのトップに持ってくる。
デックを縦にし、ブレイク上のパケットを押し上げてインジケーターカードとその後ろのパケットを抜き取る。
残ったパケットのトップカードを観客に取らせると、それが選ばれたカード。
ポイント
「カードを好きな位置に挿入させる」動作が自然なカバーになる。
想定状況
観客が自由にカードを見てデックを戻し、マジシャンが正確な位置を見失ったが、上位5枚のどれかであることは分かっている。
例:観客が勝手にカットしてカードを見た/ピークが失敗した/コントロールを失ったが位置はおおよそ把握している場合。
基本戦略
5枚を特定の配置に分け、観客の反応を観察しながら段階的に候補を絞り込む。
どのカードが選ばれても、演出上は「意図的にそうした」ように見せる。
手順概要
パスなどで選ばれたカードをトップ5枚に持ってくる(例:A, 2, 3, 4, 5)。
ファンにして5枚を確認。3枚目のランク+1の位置まで数えて、そのカード群を抜き、A, 2, 3を左側に置く。残りのデックの底から3枚目に5、その下に4がある状態にする。
左側の3枚から観客に1枚選ばせ、反応を観察。
違えば残り2枚から選ばせ、さらに反応を観察。
それでも違えば3枚をまとめて2枚伏せ+1枚表にして見せる。
まだ違えば「このカードは○○、つまりあなたのカードはデックの底から3枚目」と宣言し、デックを表向きにして底から数えて見せる。
反応がなければ次のカードを見せ、必ず的中させる。
ポイント
中央のカードはほぼ必ず選ばれるため、そこからの展開がメインルート。
どの段階でも「失敗」ではなく「演出の一部」に見せる話術と間合いが重要。
Emergency Card Stabbing(エマージェンシー・カード・スタビング)
想定状況
選ばれたカードが5枚のうちのどれかであることは分かっているが、どれかは不明。
その場で確実に突き止める必要がある。
基本戦略
5枚を覚えやすい並び(電話番号のように)で記憶し、観客に挿入させた「インジケーターカード」を使って位置を特定する。
手順概要
5枚をボトムに集め、ランクを覚える(例:2-5-3-J-7)。同ランクがあれば最初のスートも記憶。
パスで5枚を中央に移し、小指ブレイクを保持。
トップカードを観客に渡し、好きな位置に挿入させる。このときインジケーターカードがブレイク下に入るよう誘導。
観客がカード名を言ったら、記憶した並びから必要枚数を右親指から落として、そのカードを下パケットのトップに持ってくる。
デックを縦にし、ブレイク上のパケットを押し上げてインジケーターカードとその後ろのパケットを抜き取る。
残ったパケットのトップカードを観客に取らせると、それが選ばれたカード。
ポイント
「カードを好きな位置に挿入させる」動作が自然なカバーになる。
The Drop Control
目的
観客がカードを戻す際、自然で「正直そう」に見える動作の中で、カードを特定の位置(例:トップから7枚目)にコントロールする。
手順概要
観客がカードを選んだらデックを揃え、左小指で中央付近にブレイクを作る。右親指で上半分の下から6枚をリフルし、左薬指で一時的にブレイクを保持。
左手を右手の下に構え、「どこでも戻してください」と言いながら右手から小パケットを落としていく。最初のブレイクまで落とし、そこにカードを置かせる。
さらに1〜2枚落とし、次のブレイクまで落とし、最後に残りを重ねる。左小指でブレイクを保持。
パスやオーバーハンドシャッフルで処理すれば、カードはトップから7枚目に。
特徴
トップやボトムを見せても安全。
「カードを混ぜている」印象を強く与える。
The Tap
目的
カードをデック側面から挿入し、軽いタップで反対側にごくわずかに突き出させ、ブレイクのきっかけにする。
手順概要
左手でデックを水平に持ち、観客のカードを側面から挿入。上辺を約1/4インチ突き出させる。
右手中指で軽くタップし、下辺を反対側からわずかに突き出させる。
右手でデック右上角をつかみ、左手ディーリングポジションに移す。
左小指で突き出た部分を引き下げてブレイクを作る。
特徴
外端は無傷に見えるため、観客からは痕跡が見えにくい。
ジョグは極小で十分。
The Single Card Bridge(チャールズ・ミラー)
目的
1枚だけを長辺方向にブリッジさせ、キー・カードとして利用する。
手順概要
左手でオーバーハンドシャッフルの構え、デック下辺を手のひら中央寄りに置く。
左指先をフェイスカード上辺付近に当て、右手でアンダーカットする際に押し下げてカードをブリッジさせる。
特徴
即座に、かつ不可視に作れるキー・カード。
位置確認やコントロールに応用可能。
A New Glide
目的
古典的グライドの代替。より自然で、知られていない方法でボトムから2枚目を抜き取る。
手順概要
左手でデックを端持ちし、中指第3関節をボトムカード表面に置く。
ボトムカードを見せた後、テーブル上方で中指で押し出し、左方向に斜め半インチずらす。
右手中指で2枚目の角を押し出し、人差し指を乗せて引き抜く。
左中指を戻してボトムカードを揃える。
特徴
動作が自然で、観客の視線を誘導しやすい。
古典的グライドよりも露見しにくい。
Establishing a Break from a Bridge
目的
ブリッジを利用してブレイクを再取得する。
手順概要
左小指でブレイクを作り、下半分を小指と親指付け根で挟んで内端だけをブリッジさせる。
デックを回転させたりテーブルに置いたりして「公正さ」を演出。
再び持ち上げ、右手で端を揃えるふりをしながら親指の腹を内端に軽く動かし、ブリッジを広げて小指を差し込む。
特徴
ごく小さなブリッジでも再利用可能。
観客に「カードは失われた」と思わせたままコントロールできる。
Transfer of Thumb-Count Break to the Little Finger
目的
サムカウントで数えた枚数の下に、右手を使わず左小指でブレイクを移す。特にテーブルワークで有効。
手順概要
左手でサムカウントの構え、前腕をテーブルに置き、内左角を親指付け根に押し当てる。
サムカウント後、親指の腹で外左角を押し、内左角を浮かせて親指付け根の肉をブレイクに食い込ませる。
親指を外左角背面に置き押し下げると、右下角が浮き、小指を差し込みやすくなる。
特徴
ダブル/トリプル/クアドラプルリフトのセットにも使える。
完全に手の形でカバーされ、視線を落とす必要がない。
目的
観客がカードを戻す際、自然で「正直そう」に見える動作の中で、カードを特定の位置(例:トップから7枚目)にコントロールする。
手順概要
観客がカードを選んだらデックを揃え、左小指で中央付近にブレイクを作る。右親指で上半分の下から6枚をリフルし、左薬指で一時的にブレイクを保持。
左手を右手の下に構え、「どこでも戻してください」と言いながら右手から小パケットを落としていく。最初のブレイクまで落とし、そこにカードを置かせる。
さらに1〜2枚落とし、次のブレイクまで落とし、最後に残りを重ねる。左小指でブレイクを保持。
パスやオーバーハンドシャッフルで処理すれば、カードはトップから7枚目に。
特徴
トップやボトムを見せても安全。
「カードを混ぜている」印象を強く与える。
The Tap
目的
カードをデック側面から挿入し、軽いタップで反対側にごくわずかに突き出させ、ブレイクのきっかけにする。
手順概要
左手でデックを水平に持ち、観客のカードを側面から挿入。上辺を約1/4インチ突き出させる。
右手中指で軽くタップし、下辺を反対側からわずかに突き出させる。
右手でデック右上角をつかみ、左手ディーリングポジションに移す。
左小指で突き出た部分を引き下げてブレイクを作る。
特徴
外端は無傷に見えるため、観客からは痕跡が見えにくい。
ジョグは極小で十分。
The Single Card Bridge(チャールズ・ミラー)
目的
1枚だけを長辺方向にブリッジさせ、キー・カードとして利用する。
手順概要
左手でオーバーハンドシャッフルの構え、デック下辺を手のひら中央寄りに置く。
左指先をフェイスカード上辺付近に当て、右手でアンダーカットする際に押し下げてカードをブリッジさせる。
特徴
即座に、かつ不可視に作れるキー・カード。
位置確認やコントロールに応用可能。
A New Glide
目的
古典的グライドの代替。より自然で、知られていない方法でボトムから2枚目を抜き取る。
手順概要
左手でデックを端持ちし、中指第3関節をボトムカード表面に置く。
ボトムカードを見せた後、テーブル上方で中指で押し出し、左方向に斜め半インチずらす。
右手中指で2枚目の角を押し出し、人差し指を乗せて引き抜く。
左中指を戻してボトムカードを揃える。
特徴
動作が自然で、観客の視線を誘導しやすい。
古典的グライドよりも露見しにくい。
Establishing a Break from a Bridge
目的
ブリッジを利用してブレイクを再取得する。
手順概要
左小指でブレイクを作り、下半分を小指と親指付け根で挟んで内端だけをブリッジさせる。
デックを回転させたりテーブルに置いたりして「公正さ」を演出。
再び持ち上げ、右手で端を揃えるふりをしながら親指の腹を内端に軽く動かし、ブリッジを広げて小指を差し込む。
特徴
ごく小さなブリッジでも再利用可能。
観客に「カードは失われた」と思わせたままコントロールできる。
Transfer of Thumb-Count Break to the Little Finger
目的
サムカウントで数えた枚数の下に、右手を使わず左小指でブレイクを移す。特にテーブルワークで有効。
手順概要
左手でサムカウントの構え、前腕をテーブルに置き、内左角を親指付け根に押し当てる。
サムカウント後、親指の腹で外左角を押し、内左角を浮かせて親指付け根の肉をブレイクに食い込ませる。
親指を外左角背面に置き押し下げると、右下角が浮き、小指を差し込みやすくなる。
特徴
ダブル/トリプル/クアドラプルリフトのセットにも使える。
完全に手の形でカバーされ、視線を落とす必要がない。
The Ruffle Return
目的
観客がカードを戻した直後に、左手だけで密かにブレイクを保持し、カードをコントロールする。
右手を使わず、自然な動作で行えるのが特徴。
手順概要
左手でデックを持ち、親指は左側面に沿わせ、内左角を親指付け根に押し当てる。
観客にカードを戻させる際、左親指の付け根からカードを“ラッフル”して差し込みやすくする。
カードが戻ったら、ラッフルでできた隙間に親指付け根の肉を押し込み、親指を上に倒して外端を閉じる。
観客のカードはまだ半分ほど突き出ているので、人差し指で押し込み揃える。
選ばれたカードはブレイク上のパケットの底に位置し、見た目は完全に揃っている。 → 以後、ヒンドゥーシャッフルやパスなどで自由にコントロール可能。
The Bridge Location
目的
観客が自由にカードを差し込んでも、その位置を特定できる古典的手法。
カードに曲げ癖をつけて物理的な“ブリッジ”を作る。
バートラムの方法
プレッシャーファンを作り、カード全体に下向きの曲げを与える。
観客のカードにも下向きの曲げがつく。
すぐにデック全体の端を上向きに曲げ、手から手へスプレッドしてカードを戻させる。
揃えてオーバーハンドシャッフル。曲げの違いでカード位置が分かる。
チャールズ・ミラーのバリエーション
エンドリフルシャッフルで上向きの曲げを与えた後、カードを戻させる。
以後はバートラム法と同様にコントロール。
The Mexican Turnover
目的
テーブル上のカードを表向きに返す動作の中で、密かに別のカードと入れ替える。
手順概要
右手のカードを内右角で持ち、左側をテーブルカードの右側下に差し込む。
両カードを垂直に立て、右中指でテーブルカードの内右角を押さえ、親指に持ち替える。
テーブルカードを左に引き抜き、右手のカードを表向きに返す。 改良点:左手中指先端をテーブルカードの内左角に置き、カードが滑らないようにしつつ素早く引き抜くことで、動作が安定し高速化。
The Spread Cull
目的
スプレッドの中で特定のカード群(例:4枚のエース)を密かにトップまたはボトムに集める。
手順概要
デックを表向きで左手に持ち、左親指でカードを右手に送る。
目的のカードが現れたら、左親指で引き戻し、右手指先で隣のカードを右に引いてカバー。
左親指で目的カードを右に滑らせ、右親指で拾ってデックのフェイス側に集める。
全て集めたら、ボトムから必要枚数をサムカウントし、ブレイクを保持してオーバーハンドシャッフルで所定位置に移動。
特徴
古い「1枚ずつ走らせる」方法よりもスムーズで、速度を落とさずに行える。
観客には単なるカードのスプレッドに見える。
目的
観客がカードを戻した直後に、左手だけで密かにブレイクを保持し、カードをコントロールする。
右手を使わず、自然な動作で行えるのが特徴。
手順概要
左手でデックを持ち、親指は左側面に沿わせ、内左角を親指付け根に押し当てる。
観客にカードを戻させる際、左親指の付け根からカードを“ラッフル”して差し込みやすくする。
カードが戻ったら、ラッフルでできた隙間に親指付け根の肉を押し込み、親指を上に倒して外端を閉じる。
観客のカードはまだ半分ほど突き出ているので、人差し指で押し込み揃える。
選ばれたカードはブレイク上のパケットの底に位置し、見た目は完全に揃っている。 → 以後、ヒンドゥーシャッフルやパスなどで自由にコントロール可能。
The Bridge Location
目的
観客が自由にカードを差し込んでも、その位置を特定できる古典的手法。
カードに曲げ癖をつけて物理的な“ブリッジ”を作る。
バートラムの方法
プレッシャーファンを作り、カード全体に下向きの曲げを与える。
観客のカードにも下向きの曲げがつく。
すぐにデック全体の端を上向きに曲げ、手から手へスプレッドしてカードを戻させる。
揃えてオーバーハンドシャッフル。曲げの違いでカード位置が分かる。
チャールズ・ミラーのバリエーション
エンドリフルシャッフルで上向きの曲げを与えた後、カードを戻させる。
以後はバートラム法と同様にコントロール。
The Mexican Turnover
目的
テーブル上のカードを表向きに返す動作の中で、密かに別のカードと入れ替える。
手順概要
右手のカードを内右角で持ち、左側をテーブルカードの右側下に差し込む。
両カードを垂直に立て、右中指でテーブルカードの内右角を押さえ、親指に持ち替える。
テーブルカードを左に引き抜き、右手のカードを表向きに返す。 改良点:左手中指先端をテーブルカードの内左角に置き、カードが滑らないようにしつつ素早く引き抜くことで、動作が安定し高速化。
The Spread Cull
目的
スプレッドの中で特定のカード群(例:4枚のエース)を密かにトップまたはボトムに集める。
手順概要
デックを表向きで左手に持ち、左親指でカードを右手に送る。
目的のカードが現れたら、左親指で引き戻し、右手指先で隣のカードを右に引いてカバー。
左親指で目的カードを右に滑らせ、右親指で拾ってデックのフェイス側に集める。
全て集めたら、ボトムから必要枚数をサムカウントし、ブレイクを保持してオーバーハンドシャッフルで所定位置に移動。
特徴
古い「1枚ずつ走らせる」方法よりもスムーズで、速度を落とさずに行える。
観客には単なるカードのスプレッドに見える。
The Double-Face
目的
デックのトップとボトムだけを裏向きにし、残り50枚を表向きにする特殊セットを素早く作る。
表向きに見えるデックの中に、両端だけ裏向きカードを仕込むことで、特定のトリックに利用できる。
手順概要
デックを表向きに持ち、Facing the Bottom Card(p.110)の方法でボトムカードを反転(オーバーハンドシャッフルは省略)。
ディーリングポジションで右手を上からかぶせ、左指先でボトムカードを内側に押してバクル(曲げる)。
左指先を次のカード(ボトムから2枚目)に置き、右に1インチほど突き出す。
再びFacing the Bottom Cardの動作を行うが、この突き出したカードを左指先で保持し、デックを返した際にそのカードの上にデックを置く。 → これでトップとボトムが裏向き、残りは表向きになる。
特徴と心理的効果
動作中、観客がトップカードを裏向きで見ても、前後で状態が変わらないように見えるため混乱を招く。
観客の注意がデックに集中していないタイミングで行うのが望ましい。
Gamblers’ Card Marking System
目的
カードの隅や辺にごく浅い「溝状のクリンプ」や小さな凹みを付け、ランクとスートを判別できるようにする。
元々はギャンブラーがゲーム中に高位カードをマーキングするために使った方法を、マジック用に応用。
マーキングの原理(ランク)
カードを特定の位置で軽く押し曲げ、光の反射で見える微細な凹凸を作る。
例(裏向き時の位置):
内左角:A(表向き時は2)
内端中央:3(表向き時は4)
内右角:5(表向き時は6)
内右角から1インチ上:7(表向き時は8)
右辺中央:9(表向き時は10)
外右角から1インチ下:J(表向き時はQ)
Kはマーキングしない。
スートの判別
スペード:裏面中央に爪で小さな凹み
ハート:表面中央に凹み
ダイヤ:裏向きでオフセンターに凹み
クラブ:無印
特徴
マークは非常に浅く、光の反射でのみ判別可能。
慣れれば顔を見ずに裏面からランクとスートを即座に読み取れる。
借りたデックでも短時間で数枚マーキングすれば即興で利用可能。
目的
デックのトップとボトムだけを裏向きにし、残り50枚を表向きにする特殊セットを素早く作る。
表向きに見えるデックの中に、両端だけ裏向きカードを仕込むことで、特定のトリックに利用できる。
手順概要
デックを表向きに持ち、Facing the Bottom Card(p.110)の方法でボトムカードを反転(オーバーハンドシャッフルは省略)。
ディーリングポジションで右手を上からかぶせ、左指先でボトムカードを内側に押してバクル(曲げる)。
左指先を次のカード(ボトムから2枚目)に置き、右に1インチほど突き出す。
再びFacing the Bottom Cardの動作を行うが、この突き出したカードを左指先で保持し、デックを返した際にそのカードの上にデックを置く。 → これでトップとボトムが裏向き、残りは表向きになる。
特徴と心理的効果
動作中、観客がトップカードを裏向きで見ても、前後で状態が変わらないように見えるため混乱を招く。
観客の注意がデックに集中していないタイミングで行うのが望ましい。
Gamblers’ Card Marking System
目的
カードの隅や辺にごく浅い「溝状のクリンプ」や小さな凹みを付け、ランクとスートを判別できるようにする。
元々はギャンブラーがゲーム中に高位カードをマーキングするために使った方法を、マジック用に応用。
マーキングの原理(ランク)
カードを特定の位置で軽く押し曲げ、光の反射で見える微細な凹凸を作る。
例(裏向き時の位置):
内左角:A(表向き時は2)
内端中央:3(表向き時は4)
内右角:5(表向き時は6)
内右角から1インチ上:7(表向き時は8)
右辺中央:9(表向き時は10)
外右角から1インチ下:J(表向き時はQ)
Kはマーキングしない。
スートの判別
スペード:裏面中央に爪で小さな凹み
ハート:表面中央に凹み
ダイヤ:裏向きでオフセンターに凹み
クラブ:無印
特徴
マークは非常に浅く、光の反射でのみ判別可能。
慣れれば顔を見ずに裏面からランクとスートを即座に読み取れる。
借りたデックでも短時間で数枚マーキングすれば即興で利用可能。
背景と位置づけ
リア・パームは、カードを手のひらの「後方」に保持するパームで、指を大きく開いてもカードが見えないのが特徴。
歴史的にはフラリッシュ的な使い方が多く、実用的な技法としては軽視されてきた。
マックス・マリーニ:小さな手で空中からカードをキャッチする演出に使用。
Larsen & Wright:カラー・チェンジへの応用を提案。
P.W. Miller(1938):ギャンブラーズ・ムーブ「capping the deck」研究中に同原理に到達。
M. Latapie:大きな手を活かし、カードを横向きにパーム。
1932年『La Prestidigitateur』誌にも掲載(帽子の中で隠す形)。
最大の課題は、通常のパームと同じくらい自然かつ密かにカードをリア・パーム位置に置くこと。これが解決すれば非常に応用範囲が広い。
基本形(The Nature of the Palm)
右手のひらを上に向け、カードを外端が指の付け根と平行、内端が手首のしわと平行になるように置く。
左手中指でカード中央を押さえ、右親指を内側に曲げ、小指付け根を押し出すようにしてカードを軽く湾曲させる(ビリヤードボールをパームする動きに似る)。
右手を反転させてもカードは後方に保持され、指を広げても見えない。
保持は親指付け根と小指付け根の肉の間の圧力で行い、親指で直接つかむわけではない。
内右角は親指付け根の下に軽く折れ込む形になる。
トップカードからのリア・パーム(Rear Palming the Top Card)
トップカードを通常のパーム(推奨は片手トップパーム)で右手に保持し、手のひらを下向きにする。
右手中指を内側に曲げ、中指と薬指でカードを後方に押しやる。外端は中指の第二・第三関節間に当たり、中指先端がカード表面を押さえて落下を防ぐ。
親指付け根と小指付け根を収縮させ、中指先端で外端中央を押し続けることでカードを固定。
指を自然に伸ばすと、カードはリア・パーム位置に保持される。
練習のコツ
初期は手のひらを上向きにして練習し、保持感覚を掴む。
慣れたら下向きでも音を立てず確実に行えるようにする。
左手の中指で補助しながらスクエアする動作で押し込む方法もあるが、最終的には右手単独で安定保持できるようにする。
リア・パームは、カードを手のひらの「後方」に保持するパームで、指を大きく開いてもカードが見えないのが特徴。
歴史的にはフラリッシュ的な使い方が多く、実用的な技法としては軽視されてきた。
マックス・マリーニ:小さな手で空中からカードをキャッチする演出に使用。
Larsen & Wright:カラー・チェンジへの応用を提案。
P.W. Miller(1938):ギャンブラーズ・ムーブ「capping the deck」研究中に同原理に到達。
M. Latapie:大きな手を活かし、カードを横向きにパーム。
1932年『La Prestidigitateur』誌にも掲載(帽子の中で隠す形)。
最大の課題は、通常のパームと同じくらい自然かつ密かにカードをリア・パーム位置に置くこと。これが解決すれば非常に応用範囲が広い。
基本形(The Nature of the Palm)
右手のひらを上に向け、カードを外端が指の付け根と平行、内端が手首のしわと平行になるように置く。
左手中指でカード中央を押さえ、右親指を内側に曲げ、小指付け根を押し出すようにしてカードを軽く湾曲させる(ビリヤードボールをパームする動きに似る)。
右手を反転させてもカードは後方に保持され、指を広げても見えない。
保持は親指付け根と小指付け根の肉の間の圧力で行い、親指で直接つかむわけではない。
内右角は親指付け根の下に軽く折れ込む形になる。
トップカードからのリア・パーム(Rear Palming the Top Card)
トップカードを通常のパーム(推奨は片手トップパーム)で右手に保持し、手のひらを下向きにする。
右手中指を内側に曲げ、中指と薬指でカードを後方に押しやる。外端は中指の第二・第三関節間に当たり、中指先端がカード表面を押さえて落下を防ぐ。
親指付け根と小指付け根を収縮させ、中指先端で外端中央を押し続けることでカードを固定。
指を自然に伸ばすと、カードはリア・パーム位置に保持される。
練習のコツ
初期は手のひらを上向きにして練習し、保持感覚を掴む。
慣れたら下向きでも音を立てず確実に行えるようにする。
左手の中指で補助しながらスクエアする動作で押し込む方法もあるが、最終的には右手単独で安定保持できるようにする。
Bottom Rear Palm
目的
デックのボトムカードを直接リア・パームに移す。
中間動作なしで素早く・確実・不可視に行える。
手順概要
左手でデックを裏向きに持ち、右手で端を揃える。
右手でデックをつかみ、指先をボトムカードのフェイス側に当て、右斜めに押し出す。
デックを左に引き抜くと、カードは右手の下に残る。
右中指先でカード表面を押し、親指付け根と小指付け根で挟んでリア・パームに保持。
必要なら左中指で押し込み固定。
特徴:右手の人差し指と中指を広げた状態でデックを持てるため、パームしていないように見える。
Rear Palm Side Slip
目的
観客が戻したカードをリア・パームに取り、トップにコントロールする。
手順概要
リフルしてカードを半分差し込ませる。
右手で押し込むふりをしつつ、左方向かつ斜めに通す(右人差し指で左角をコントロール)。
左指先でカードを右方向かつ内側にスイングしてリア・パーム位置へ。
左手でカードを押し上げて右手に保持。
左手でデックを前に動かし、右手は動かさずカードを受け取る。
デックを揃え、必要に応じてトップに戻す。
特徴:動作が非常に自然で、アンビシャスカードにも応用可能。
Little Finger Push-Out
目的
左小指ブレイク上のカードをリア・パーム経由でトップに送る。
Side Slipよりも幅広い場面で使用可能。
手順概要
左小指でブレイクを保持。
右手でデックを覆い、小指でカードを押し出す。
左指先でカードを右方向かつ内側にスイングしてリア・パーム位置へ。
Side Slipの後半(4〜6)と同様に処理。
Replacement
目的
リア・パームに保持したカードを自然にトップに戻す。
手順概要
左手でデックを持ち、右手(リア・パーム状態)で揃える。
デック外端を上げ、左親指を右手親指と人差し指の間に差し込み、カードをトップに置く(内端を1.5インチ突き出す)。
右親指で押し込み、完全に揃える。
特徴:音もなく数秒で完了し、視覚的にもパームやリプレイスの痕跡がない。
目的
デックのボトムカードを直接リア・パームに移す。
中間動作なしで素早く・確実・不可視に行える。
手順概要
左手でデックを裏向きに持ち、右手で端を揃える。
右手でデックをつかみ、指先をボトムカードのフェイス側に当て、右斜めに押し出す。
デックを左に引き抜くと、カードは右手の下に残る。
右中指先でカード表面を押し、親指付け根と小指付け根で挟んでリア・パームに保持。
必要なら左中指で押し込み固定。
特徴:右手の人差し指と中指を広げた状態でデックを持てるため、パームしていないように見える。
Rear Palm Side Slip
目的
観客が戻したカードをリア・パームに取り、トップにコントロールする。
手順概要
リフルしてカードを半分差し込ませる。
右手で押し込むふりをしつつ、左方向かつ斜めに通す(右人差し指で左角をコントロール)。
左指先でカードを右方向かつ内側にスイングしてリア・パーム位置へ。
左手でカードを押し上げて右手に保持。
左手でデックを前に動かし、右手は動かさずカードを受け取る。
デックを揃え、必要に応じてトップに戻す。
特徴:動作が非常に自然で、アンビシャスカードにも応用可能。
Little Finger Push-Out
目的
左小指ブレイク上のカードをリア・パーム経由でトップに送る。
Side Slipよりも幅広い場面で使用可能。
手順概要
左小指でブレイクを保持。
右手でデックを覆い、小指でカードを押し出す。
左指先でカードを右方向かつ内側にスイングしてリア・パーム位置へ。
Side Slipの後半(4〜6)と同様に処理。
Replacement
目的
リア・パームに保持したカードを自然にトップに戻す。
手順概要
左手でデックを持ち、右手(リア・パーム状態)で揃える。
デック外端を上げ、左親指を右手親指と人差し指の間に差し込み、カードをトップに置く(内端を1.5インチ突き出す)。
右親指で押し込み、完全に揃える。
特徴:音もなく数秒で完了し、視覚的にもパームやリプレイスの痕跡がない。
The Rear Palm Exchange
目的
2枚のカードを使い、自然な動作の中で1枚を密かにリア・パームに保持し、別のカードと入れ替えるスイッチ技法。
手順概要
トップ2枚を1枚のように右手に取り、第二関節と小指付け根で支え、親指は上端に置く(Fig.12)。
手のひらを下に向けながら、下のカード(フェイスカード)を指先で右に押し出す。
左手でそのカードを取り、観客に渡すかテーブルに置く。右手は自然にカールし、リア・パーム状態に(Fig.13)。
左手でデックを持ち、右手でFig.7のグリップに移行。
適切なタイミングでReplacementの方法でカードをデックに戻す。
In Lieu of the Double Lift(ダブルリフトの代替)
目的
ダブルリフトを使うトリックを、リア・パームを利用してより効果的に演じる。
手順概要
右手にリア・パームでカードを保持(トップまたはボトムから、後者推奨)。
左親指でトップカードを押し出し、右手人差し指と中指でつまみ、表向きに返す。
これを数回繰り返し、観客に「トップカードは1枚だけ」という印象を与える。
デックをスクエアしながら正面に持ってきて、リア・パームのカードを密かにトップに戻す。 → 観客はトップカードが同じだと思っているが、実際は2枚目に移動している。
Using the Rear Palm(リア・パームの使いどころ)
ポイント
通常のパームは「疑われていない時」に行うのが基本。
リア・パームは「指の間が見える=パーム不可能」に見えるため、特定の場面で強力な武器になる。
例:アンビシャスカードの中で1回だけ使うと、観客の推測を崩せる。
注意点
親指付け根の圧でカードの内角が下に反るため、右側から低い位置で見られる角度は避ける。
Fig.7のグリップで、観客に「パーム不可能」と思わせる時間を十分に取る。
「不可能に見える」ことが最大の武器なので、動作は急がず、ゆったり行う。
一度「手は空」と判断した観客は、その後のパームに警戒しなくなる。
目的
2枚のカードを使い、自然な動作の中で1枚を密かにリア・パームに保持し、別のカードと入れ替えるスイッチ技法。
手順概要
トップ2枚を1枚のように右手に取り、第二関節と小指付け根で支え、親指は上端に置く(Fig.12)。
手のひらを下に向けながら、下のカード(フェイスカード)を指先で右に押し出す。
左手でそのカードを取り、観客に渡すかテーブルに置く。右手は自然にカールし、リア・パーム状態に(Fig.13)。
左手でデックを持ち、右手でFig.7のグリップに移行。
適切なタイミングでReplacementの方法でカードをデックに戻す。
In Lieu of the Double Lift(ダブルリフトの代替)
目的
ダブルリフトを使うトリックを、リア・パームを利用してより効果的に演じる。
手順概要
右手にリア・パームでカードを保持(トップまたはボトムから、後者推奨)。
左親指でトップカードを押し出し、右手人差し指と中指でつまみ、表向きに返す。
これを数回繰り返し、観客に「トップカードは1枚だけ」という印象を与える。
デックをスクエアしながら正面に持ってきて、リア・パームのカードを密かにトップに戻す。 → 観客はトップカードが同じだと思っているが、実際は2枚目に移動している。
Using the Rear Palm(リア・パームの使いどころ)
ポイント
通常のパームは「疑われていない時」に行うのが基本。
リア・パームは「指の間が見える=パーム不可能」に見えるため、特定の場面で強力な武器になる。
例:アンビシャスカードの中で1回だけ使うと、観客の推測を崩せる。
注意点
親指付け根の圧でカードの内角が下に反るため、右側から低い位置で見られる角度は避ける。
Fig.7のグリップで、観客に「パーム不可能」と思わせる時間を十分に取る。
「不可能に見える」ことが最大の武器なので、動作は急がず、ゆったり行う。
一度「手は空」と判断した観客は、その後のパームに警戒しなくなる。
背景
マスケリンはファロー・シャッフルを「練習と忍耐で確実に交互にカードを飛び上がらせられるが、非常に習得が難しい」と評している。
古典的手法ではカードの両端を強く押して横方向にブリッジ(湾曲)させ、その反発力でカードを噛み合わせるため、コントロールが難しい。
本書の方法は横方向の強いブリッジを使わず、テンション要素を排して容易に習得できるのが特徴。
本書の方法(要約)
事前準備
右手指を片端、親指を反対端に置き、カードを横方向にわずかにブリッジさせて背面を凸状にする(目立たない程度)。
カットと持ち方
26枚ずつにカット。
両手で外端近くを持ち、親指は内側端、人差し指は上に浮かせて触れない。
位置合わせ
内端を合わせ、外端を約1.5インチ持ち上げ、浅いV字型にする。
内端は軽く触れ合わせる程度で、押し付けない。
噛み合わせ開始
両手の親指・中指・薬指で内向きに圧をかけ、縦方向にブリッジさせる。
これによりカードがまっすぐになり、内端がわずかに上がって自然に噛み合う。
右パケットのトップカードが左パケットのトップカードの上に乗る形で交互に入る。
進行と感覚
圧を維持しつつ内端を持ち上げ、外端を下げる。
親指の付け根でパケット側面に沿わせると、噛み合わせが進む感触が伝わる。
圧の強弱でスピードを自在に調整可能。
原理の理解
横方向のブリッジを縦方向のブリッジに変えることで、カードの内端がわずかに上がり、自然に噛み合う。
実験として:
パケットを持ち、1枚のカードを押し下げて離すと弱い力で戻る。
しかしパケット全体を横凸→縦凸に変えると、カードは強い力で戻り、全体が揃って噛み合う。
注意点
ブリッジサイズのカード(幅が狭いカード)でも可能だが、縦方向のブリッジに必要な指の力が増すため難易度が上がる。
新品または状態の良いカードが望ましい。
マスケリンはファロー・シャッフルを「練習と忍耐で確実に交互にカードを飛び上がらせられるが、非常に習得が難しい」と評している。
古典的手法ではカードの両端を強く押して横方向にブリッジ(湾曲)させ、その反発力でカードを噛み合わせるため、コントロールが難しい。
本書の方法は横方向の強いブリッジを使わず、テンション要素を排して容易に習得できるのが特徴。
本書の方法(要約)
事前準備
右手指を片端、親指を反対端に置き、カードを横方向にわずかにブリッジさせて背面を凸状にする(目立たない程度)。
カットと持ち方
26枚ずつにカット。
両手で外端近くを持ち、親指は内側端、人差し指は上に浮かせて触れない。
位置合わせ
内端を合わせ、外端を約1.5インチ持ち上げ、浅いV字型にする。
内端は軽く触れ合わせる程度で、押し付けない。
噛み合わせ開始
両手の親指・中指・薬指で内向きに圧をかけ、縦方向にブリッジさせる。
これによりカードがまっすぐになり、内端がわずかに上がって自然に噛み合う。
右パケットのトップカードが左パケットのトップカードの上に乗る形で交互に入る。
進行と感覚
圧を維持しつつ内端を持ち上げ、外端を下げる。
親指の付け根でパケット側面に沿わせると、噛み合わせが進む感触が伝わる。
圧の強弱でスピードを自在に調整可能。
原理の理解
横方向のブリッジを縦方向のブリッジに変えることで、カードの内端がわずかに上がり、自然に噛み合う。
実験として:
パケットを持ち、1枚のカードを押し下げて離すと弱い力で戻る。
しかしパケット全体を横凸→縦凸に変えると、カードは強い力で戻り、全体が揃って噛み合う。
注意点
ブリッジサイズのカード(幅が狭いカード)でも可能だが、縦方向のブリッジに必要な指の力が増すため難易度が上がる。
新品または状態の良いカードが望ましい。
1. 完全ファロー・シャッフルの前提
デックを正確に26枚ずつにカットし、右手に1〜26番カード、左手に27〜52番カードを持つ。
シャッフルは右手のトップカードが常に最初に来る形(アウトファロー)。
左手のトップカード(元の27番)は右手トップの下に入り、デックの2番目の位置に。
左手のボトムカード(元の52番)は常にデックの最下部に残る。
2. 各シャッフル後の「間隔(インターバル)」
1回目:元の順序で隣り合っていたカードの間に1枚入る(例:1, 27, 2, 28, 3, 29…)。
2回目:間隔は3枚。
3回目:間隔は7枚。
4回目:間隔は15枚。
5回目:間隔は31枚。
6回目:間隔は12枚。
7回目:間隔は25枚。
8回目:元の順序に完全復元。
3. 位置変化の計算式
各カードは「自分の番号×2−1」の位置に移動する。
例:10番カード → 10×2−1=19番位置。
計算結果が52を超える場合は52を引く。
例:44番カード → 44×2=88 → 88−52=36番位置。
4. エンドレスベルト(Endless Belts)の概念
52枚は6つの8枚グループ+4枚の固定カードに分かれる。
各グループはベルトコンベアのように順番に位置を入れ替えながら8回で元に戻る。
例:第1グループ(元の2, 3, 5, 9, 17, 33, 14, 27番カード)
1回目:2→3→5→9→17→33→14→27→2…
8回目で全員が元の位置に戻る。
残り4枚:
1番カード:常にトップ。
52番カード:常にボトム。
18番と35番カード:互いに入れ替わり、2回で元に戻る。
5. 実用的な意味
この理論を理解すると、完全ファローを繰り返したときのカードの位置を正確に予測できる。
位置制御やスタック構築、メモリーデックの一部操作に応用可能。
特に「8回で元に戻る」という周期性は、演技構成や複雑なコントロールに役立つ。
デックを正確に26枚ずつにカットし、右手に1〜26番カード、左手に27〜52番カードを持つ。
シャッフルは右手のトップカードが常に最初に来る形(アウトファロー)。
左手のトップカード(元の27番)は右手トップの下に入り、デックの2番目の位置に。
左手のボトムカード(元の52番)は常にデックの最下部に残る。
2. 各シャッフル後の「間隔(インターバル)」
1回目:元の順序で隣り合っていたカードの間に1枚入る(例:1, 27, 2, 28, 3, 29…)。
2回目:間隔は3枚。
3回目:間隔は7枚。
4回目:間隔は15枚。
5回目:間隔は31枚。
6回目:間隔は12枚。
7回目:間隔は25枚。
8回目:元の順序に完全復元。
3. 位置変化の計算式
各カードは「自分の番号×2−1」の位置に移動する。
例:10番カード → 10×2−1=19番位置。
計算結果が52を超える場合は52を引く。
例:44番カード → 44×2=88 → 88−52=36番位置。
4. エンドレスベルト(Endless Belts)の概念
52枚は6つの8枚グループ+4枚の固定カードに分かれる。
各グループはベルトコンベアのように順番に位置を入れ替えながら8回で元に戻る。
例:第1グループ(元の2, 3, 5, 9, 17, 33, 14, 27番カード)
1回目:2→3→5→9→17→33→14→27→2…
8回目で全員が元の位置に戻る。
残り4枚:
1番カード:常にトップ。
52番カード:常にボトム。
18番と35番カード:互いに入れ替わり、2回で元に戻る。
5. 実用的な意味
この理論を理解すると、完全ファローを繰り返したときのカードの位置を正確に予測できる。
位置制御やスタック構築、メモリーデックの一部操作に応用可能。
特に「8回で元に戻る」という周期性は、演技構成や複雑なコントロールに役立つ。
The Chart of Seventeen
概要
52枚のうち固定される4枚(1番・52番・18番・35番)を除く48枚は、3枚1組のセルに分けられる。
各セル内のカードは、元の順序で17枚間隔で並んでいる。
完全ファロー・シャッフルを繰り返しても、この「17枚間隔」の関係は崩れない。
例
元の順序で 2番・19番・36番のカードは、それぞれ17枚間隔で並んでいる。
1回目のシャッフル後:
2番位置 → 元の27番カード
19番位置 → 元の10番カード
36番位置 → 元の44番カード
2回目のシャッフル後も、それぞれの間隔は常に17枚のまま。
意味
この性質を理解すると、複数回の完全ファロー後でも特定カードの相対位置を追跡できる。
スタック構築や位置予測に応用可能。
Perfect Shuffle Stock
目的
特定のカード列を、間に1枚ずつ無関係カードを挟んだ形でトップ付近に配置する。
従来はオーバーハンドシャッフルで行っていたが、完全ファローを使えば1回のシャッフルでセットアップ可能。
例の設定
「An Indefectible Stop Trick」を演じるため、
9・7・5・3・A をトップから4・6・8・10・12番目に置きたい。
手順概要
セットアップ(9が先頭)をデックのトップに置き、ボトムカードの内左角を上向きにクリンプ。
デックを約40枚でカットし、セットアップを12〜18番目あたりに移動。
約26枚でカット(±2〜3枚の誤差は許容)、右手に上パケットを持つ(クリンプが右端)。
完全ファローを1回行う(最後の数枚は不規則にリフルしても可)。
デックを揃え、クリンプカードをトップにカット。
この時点で3・5・7・9・11番目に 9・7・5・3・A が並ぶ。
サイドスリップやクイック・オーバーハンドでトップに1枚加え、目的の4・6・8・10・12番目に配置。
偶数位置に置く場合
手順は同じだが、最後の「トップに1枚加える」工程は不要。
概要
52枚のうち固定される4枚(1番・52番・18番・35番)を除く48枚は、3枚1組のセルに分けられる。
各セル内のカードは、元の順序で17枚間隔で並んでいる。
完全ファロー・シャッフルを繰り返しても、この「17枚間隔」の関係は崩れない。
例
元の順序で 2番・19番・36番のカードは、それぞれ17枚間隔で並んでいる。
1回目のシャッフル後:
2番位置 → 元の27番カード
19番位置 → 元の10番カード
36番位置 → 元の44番カード
2回目のシャッフル後も、それぞれの間隔は常に17枚のまま。
意味
この性質を理解すると、複数回の完全ファロー後でも特定カードの相対位置を追跡できる。
スタック構築や位置予測に応用可能。
Perfect Shuffle Stock
目的
特定のカード列を、間に1枚ずつ無関係カードを挟んだ形でトップ付近に配置する。
従来はオーバーハンドシャッフルで行っていたが、完全ファローを使えば1回のシャッフルでセットアップ可能。
例の設定
「An Indefectible Stop Trick」を演じるため、
9・7・5・3・A をトップから4・6・8・10・12番目に置きたい。
手順概要
セットアップ(9が先頭)をデックのトップに置き、ボトムカードの内左角を上向きにクリンプ。
デックを約40枚でカットし、セットアップを12〜18番目あたりに移動。
約26枚でカット(±2〜3枚の誤差は許容)、右手に上パケットを持つ(クリンプが右端)。
完全ファローを1回行う(最後の数枚は不規則にリフルしても可)。
デックを揃え、クリンプカードをトップにカット。
この時点で3・5・7・9・11番目に 9・7・5・3・A が並ぶ。
サイドスリップやクイック・オーバーハンドでトップに1枚加え、目的の4・6・8・10・12番目に配置。
偶数位置に置く場合
手順は同じだが、最後の「トップに1枚加える」工程は不要。
The Eighteenth Card
性質
完全ファロー・シャッフルでは、18番目のカードは
1回目 → 35番目
2回目 → 18番目に戻る
3回目 → 再び35番目
以降、この2つの位置を交互に移動する。
この性質を利用し、選ばれたカードを18番目に戻すようコントロールしてから観客にシャッフルさせると、2回後にはほぼ同じ位置に戻る可能性が高い。
演出例
選ばれたカードを18番目にセット → 観客にシャッフルさせる → 2回後に18番付近を探す。
成功率は観客のカット精度に依存するため、ややリスクはあるが決まれば強い印象を与える。
Braue Poker Deal
効果
4枚のエース(またはロイヤルフラッシュ)を見せてデックに混ぜるが、4ハンドのポーカーを配ると自分の手に全て集まる。
方法概要
ボトムカードの内左角に下向きクリンプを作る。
エース4枚をトップに置き、クリンプが自分側右端になるようテーブルに置く。
約26枚でカット → さらにトップから15枚カット → クリンプは11番目付近に。
約23枚を右手に取り、完全ファロー1回。
クリンプ位置を確認し、トップからカットして10〜11番目に戻す。
再び約23枚を右手に取り、完全ファロー1回。
クリンプまでカットし、クリンプをボトムに。
4ハンド配ると、自分の手に4エースが揃う。
The Royal Flush Deal
上記Braue Poker Dealの手順を、トップにロイヤルフラッシュ5枚を置いて行うと、自分の手にロイヤルフラッシュが揃う。
Dishonesty at Its Apogee
効果
観客の自由なカット後、任意の人数のスタッドポーカーを配りながら、伏せられたホールカードやこれから配るカードの名前を言い当てる。
準備
トップに覚えやすい10枚のシーケンス(主にAや絵札)をセット。
方法概要
オーバーハンドで軽く混ぜつつトップ10枚を保持。
約23枚を右手に取り、完全ファロー1回(左パケット上部の数枚がまとめてトップに落ちる)。
ストリップアウト・フェイクシャッフル → 実際に26枚でカット。
この時点で、シーケンスはほぼトップ付近に特定間隔で配置されている。
観客にカットさせ(できれば26枚付近)、シーケンスをトップ近くに。
任意の人数でスタッドポーカーを配り、表向きカードからシーケンス内の位置を割り出し、伏せカードや次に配るカードを言い当てる。
必要に応じてインデックスを覗く(p.100の方法)を少しだけ使い、全てを知っているように見せる。
最後のシーケンスカードが出たら「私とカードゲームはしない方がいい」と締めて次の演目へ。
性質
完全ファロー・シャッフルでは、18番目のカードは
1回目 → 35番目
2回目 → 18番目に戻る
3回目 → 再び35番目
以降、この2つの位置を交互に移動する。
この性質を利用し、選ばれたカードを18番目に戻すようコントロールしてから観客にシャッフルさせると、2回後にはほぼ同じ位置に戻る可能性が高い。
演出例
選ばれたカードを18番目にセット → 観客にシャッフルさせる → 2回後に18番付近を探す。
成功率は観客のカット精度に依存するため、ややリスクはあるが決まれば強い印象を与える。
Braue Poker Deal
効果
4枚のエース(またはロイヤルフラッシュ)を見せてデックに混ぜるが、4ハンドのポーカーを配ると自分の手に全て集まる。
方法概要
ボトムカードの内左角に下向きクリンプを作る。
エース4枚をトップに置き、クリンプが自分側右端になるようテーブルに置く。
約26枚でカット → さらにトップから15枚カット → クリンプは11番目付近に。
約23枚を右手に取り、完全ファロー1回。
クリンプ位置を確認し、トップからカットして10〜11番目に戻す。
再び約23枚を右手に取り、完全ファロー1回。
クリンプまでカットし、クリンプをボトムに。
4ハンド配ると、自分の手に4エースが揃う。
The Royal Flush Deal
上記Braue Poker Dealの手順を、トップにロイヤルフラッシュ5枚を置いて行うと、自分の手にロイヤルフラッシュが揃う。
Dishonesty at Its Apogee
効果
観客の自由なカット後、任意の人数のスタッドポーカーを配りながら、伏せられたホールカードやこれから配るカードの名前を言い当てる。
準備
トップに覚えやすい10枚のシーケンス(主にAや絵札)をセット。
方法概要
オーバーハンドで軽く混ぜつつトップ10枚を保持。
約23枚を右手に取り、完全ファロー1回(左パケット上部の数枚がまとめてトップに落ちる)。
ストリップアウト・フェイクシャッフル → 実際に26枚でカット。
この時点で、シーケンスはほぼトップ付近に特定間隔で配置されている。
観客にカットさせ(できれば26枚付近)、シーケンスをトップ近くに。
任意の人数でスタッドポーカーを配り、表向きカードからシーケンス内の位置を割り出し、伏せカードや次に配るカードを言い当てる。
必要に応じてインデックスを覗く(p.100の方法)を少しだけ使い、全てを知っているように見せる。
最後のシーケンスカードが出たら「私とカードゲームはしない方がいい」と締めて次の演目へ。
A Bridge Deal
目的
ブリッジの達人を驚かせる「元の手札再現」デモンストレーション。
完全ファロー・シャッフルと正確な26枚カットを利用。
効果
4人分のブリッジハンドを配り、各プレイヤーに自分の手札を記憶させる。
デックを集め、2回の完全ファローと見せかけのシャッフル・カット後、再び配ると全員が元の手札を受け取る。
手順概要
4ハンド配り、時計回りに順番通りに回収。
正確に26枚でカット → 完全ファロー(右パケットのトップカードが常にトップに来る形)。
再び26枚でカット → 完全ファロー。
ストリップアウト・フェイクシャッフルとフェイクカット。
再配布すると元の手札が再現される。
カット精度を高める練習法として、26枚目のカードの側面を黒くして目印にする方法が紹介されている。
At the Top
目的
観客がシャッフルした後でも、選ばれたカードをトップ付近にコントロールする。
観客シャッフル時にも完全ファローの位置移動原理を応用。
効果
自由に選ばれたカードが、観客のシャッフル後にトップ付近に現れる。
手順概要
カード選択後、14枚目の位置に戻す。
観客にシャッフルさせる(1回目で15→約29番目、2回目で約6番目に移動)。
2回目のカット深さによってはボトム付近に行く場合もあるので注意。
4〜5枚の中に選ばれたカードがある状態にして、他の方法で特定する。
自分でシャッフルする場合はほぼ確実に位置を把握でき、2回目のシャッフル後に2番目に来るようにできる。
Double Less One
目的
完全ファローの位置移動原理とキーカードを組み合わせ、観客が選んだカードを不可能条件下で見つける。
効果
観客が自由に選んだカードを、混ぜられた状態から正確に当てる。
手順概要
観客シャッフル後、ボトムカード右内角を左小指で下向きにクリンプ(キーカード化)。
観客にカードを選ばせ、約18枚目に戻させる。キーカードはその上に位置。
約26枚でカット → 完全ファロー(キーカードと選択カードを含む中間部は正確にメッシュ、それより上はラフに)。
この時点でキーカードは約35番目、その2枚下が選択カード。
約18枚でカット → キーカードと選択カードを18枚目付近に戻す。
再び26枚でカット → 完全ファロー。
キーカードまでカットしてボトムに置くと、選択カードはトップから4枚目に。
3回目のシャッフルを行う場合は、事前にキーカードを15枚目付近にしてから同様の処理で、選択カードをトップから8枚目に。
特徴
カットは±数枚の誤差が許容され、メッシュは中間部のみ正確に行えばよい。
インプロンプトな「捕まえてみろ」系の演技に向く。
目的
ブリッジの達人を驚かせる「元の手札再現」デモンストレーション。
完全ファロー・シャッフルと正確な26枚カットを利用。
効果
4人分のブリッジハンドを配り、各プレイヤーに自分の手札を記憶させる。
デックを集め、2回の完全ファローと見せかけのシャッフル・カット後、再び配ると全員が元の手札を受け取る。
手順概要
4ハンド配り、時計回りに順番通りに回収。
正確に26枚でカット → 完全ファロー(右パケットのトップカードが常にトップに来る形)。
再び26枚でカット → 完全ファロー。
ストリップアウト・フェイクシャッフルとフェイクカット。
再配布すると元の手札が再現される。
カット精度を高める練習法として、26枚目のカードの側面を黒くして目印にする方法が紹介されている。
At the Top
目的
観客がシャッフルした後でも、選ばれたカードをトップ付近にコントロールする。
観客シャッフル時にも完全ファローの位置移動原理を応用。
効果
自由に選ばれたカードが、観客のシャッフル後にトップ付近に現れる。
手順概要
カード選択後、14枚目の位置に戻す。
観客にシャッフルさせる(1回目で15→約29番目、2回目で約6番目に移動)。
2回目のカット深さによってはボトム付近に行く場合もあるので注意。
4〜5枚の中に選ばれたカードがある状態にして、他の方法で特定する。
自分でシャッフルする場合はほぼ確実に位置を把握でき、2回目のシャッフル後に2番目に来るようにできる。
Double Less One
目的
完全ファローの位置移動原理とキーカードを組み合わせ、観客が選んだカードを不可能条件下で見つける。
効果
観客が自由に選んだカードを、混ぜられた状態から正確に当てる。
手順概要
観客シャッフル後、ボトムカード右内角を左小指で下向きにクリンプ(キーカード化)。
観客にカードを選ばせ、約18枚目に戻させる。キーカードはその上に位置。
約26枚でカット → 完全ファロー(キーカードと選択カードを含む中間部は正確にメッシュ、それより上はラフに)。
この時点でキーカードは約35番目、その2枚下が選択カード。
約18枚でカット → キーカードと選択カードを18枚目付近に戻す。
再び26枚でカット → 完全ファロー。
キーカードまでカットしてボトムに置くと、選択カードはトップから4枚目に。
3回目のシャッフルを行う場合は、事前にキーカードを15枚目付近にしてから同様の処理で、選択カードをトップから8枚目に。
特徴
カットは±数枚の誤差が許容され、メッシュは中間部のみ正確に行えばよい。
インプロンプトな「捕まえてみろ」系の演技に向く。
序文(Preface)
本書の目的は、カードマジックにおける高度な技法を、実用的かつ正確に記録すること。
著者は「自然さ」「確実さ」「無駄のない動作」を最重要視。
既知の技法も改良し、より実戦的な形で提示。
第1章:Secret Lift(シークレットリフト)
概要
観客に気づかれずに複数枚のカードを同時に持ち上げ、1枚のように扱う技法(ダブルリフト、トリプルリフトなど)。
One-Hand Double Lift:片手で2枚を持ち上げる。
Get-Ready:自然な動作でブレイクを作る準備法。
Turnover Variations:カードを返す際の自然な見せ方。
第2章:False Deal(フォールスディール)
概要
観客に配っているように見せかけて、実際にはトップやボトムのカードを配る技法。
Second Deal:トップカードを残し、2枚目を配る。
Bottom Deal:ボトムカードを配る。
Greek Deal:トップカードを残しつつ、下から配る特殊形。
Push-off / Strike Second:セカンドディールの2大方式。
第3章:Side Slip(サイドスリップ)
概要
ブレイク位置のカードを横に滑らせ、トップやボトムに移動させる。
Basic Side Slip:トップコントロール。
Reverse Side Slip:ボトムコントロール。
Multiple Side Slip:複数枚同時移動。
Side Slip Force:フォースとしての応用。
Side Slip Change:カード変化への応用。
Side Slip Palm:パームへの移行。
第4章:Pass(パス)
概要
デックを分割し、観客に気づかれずに上下を入れ替える。
Classic Pass:基本形。
Riffle Pass:リフル動作でカバー。
Spread Pass:スプレッド中に行う。
Turnover Pass:カードを返す動作でカバー。
Half Pass:一部のカードだけを反転。
第5章:Palming(パーミング)
概要
カードを手の中に隠し持つ技法。
Top Palm:トップからパーム。
Bottom Palm:ボトムからパーム。
One-Hand Top Palm:片手でトップパーム。
Diagonal Palm Shift:選ばれたカードを自然にパーム位置へ。
Palm Replacement:パームしたカードを自然に戻す。
第6章:False Shuffle(フォールスシャフル)
概要
混ぜているように見せかけて順序を保つ。
Overhand False Shuffle:オーバーハンド型。
Riffle False Shuffle:リフル型。
Strip-out Shuffle:ストリップアウトで順序保持。
Zarrow Shuffle:自然な見た目のリフル型フォールス。
第7章:False Cut(フォールスカット)
概要
カットしているように見せかけて順序を保つ。
Swing Cut False:スイングカット型。
Triple False Cut:3段階の見せかけカット。
Table False Cut:テーブル上でのカット。
第8章:Change(チェンジ)
概要
表示中のカードを瞬時に別のカードに変える。
Erdnase Change:古典的な指先での変化。
Bottom Change:手中でのカード交換。
Top Change:トップカードとの交換。
Mexican Turnover:テーブルカードとの交換。
第9章:Crimp(クリンプ)
概要
カードに微妙な曲げ癖をつけ、位置を特定する。
Corner Crimp:角を曲げる。
Side Crimp:側面を曲げる。
Bridge:デック全体を湾曲させる。
Gamblers’ Crimp:ギャンブル由来のマーキング。
第10章:Spectator Peek(スペクターピーク)
概要
観客にカードを覗かせ、その位置を保持する。
Basic Peek:小指ブレイクで保持。
Improved Peek:薬指や親指を使った改良。
After the Peek:ピーク後のコントロール法。
本書の目的は、カードマジックにおける高度な技法を、実用的かつ正確に記録すること。
著者は「自然さ」「確実さ」「無駄のない動作」を最重要視。
既知の技法も改良し、より実戦的な形で提示。
第1章:Secret Lift(シークレットリフト)
概要
観客に気づかれずに複数枚のカードを同時に持ち上げ、1枚のように扱う技法(ダブルリフト、トリプルリフトなど)。
One-Hand Double Lift:片手で2枚を持ち上げる。
Get-Ready:自然な動作でブレイクを作る準備法。
Turnover Variations:カードを返す際の自然な見せ方。
第2章:False Deal(フォールスディール)
概要
観客に配っているように見せかけて、実際にはトップやボトムのカードを配る技法。
Second Deal:トップカードを残し、2枚目を配る。
Bottom Deal:ボトムカードを配る。
Greek Deal:トップカードを残しつつ、下から配る特殊形。
Push-off / Strike Second:セカンドディールの2大方式。
第3章:Side Slip(サイドスリップ)
概要
ブレイク位置のカードを横に滑らせ、トップやボトムに移動させる。
Basic Side Slip:トップコントロール。
Reverse Side Slip:ボトムコントロール。
Multiple Side Slip:複数枚同時移動。
Side Slip Force:フォースとしての応用。
Side Slip Change:カード変化への応用。
Side Slip Palm:パームへの移行。
第4章:Pass(パス)
概要
デックを分割し、観客に気づかれずに上下を入れ替える。
Classic Pass:基本形。
Riffle Pass:リフル動作でカバー。
Spread Pass:スプレッド中に行う。
Turnover Pass:カードを返す動作でカバー。
Half Pass:一部のカードだけを反転。
第5章:Palming(パーミング)
概要
カードを手の中に隠し持つ技法。
Top Palm:トップからパーム。
Bottom Palm:ボトムからパーム。
One-Hand Top Palm:片手でトップパーム。
Diagonal Palm Shift:選ばれたカードを自然にパーム位置へ。
Palm Replacement:パームしたカードを自然に戻す。
第6章:False Shuffle(フォールスシャフル)
概要
混ぜているように見せかけて順序を保つ。
Overhand False Shuffle:オーバーハンド型。
Riffle False Shuffle:リフル型。
Strip-out Shuffle:ストリップアウトで順序保持。
Zarrow Shuffle:自然な見た目のリフル型フォールス。
第7章:False Cut(フォールスカット)
概要
カットしているように見せかけて順序を保つ。
Swing Cut False:スイングカット型。
Triple False Cut:3段階の見せかけカット。
Table False Cut:テーブル上でのカット。
第8章:Change(チェンジ)
概要
表示中のカードを瞬時に別のカードに変える。
Erdnase Change:古典的な指先での変化。
Bottom Change:手中でのカード交換。
Top Change:トップカードとの交換。
Mexican Turnover:テーブルカードとの交換。
第9章:Crimp(クリンプ)
概要
カードに微妙な曲げ癖をつけ、位置を特定する。
Corner Crimp:角を曲げる。
Side Crimp:側面を曲げる。
Bridge:デック全体を湾曲させる。
Gamblers’ Crimp:ギャンブル由来のマーキング。
第10章:Spectator Peek(スペクターピーク)
概要
観客にカードを覗かせ、その位置を保持する。
Basic Peek:小指ブレイクで保持。
Improved Peek:薬指や親指を使った改良。
After the Peek:ピーク後のコントロール法。
第11章:Glimpse(グリンプス)
概要
観客に気づかれずにカードを覗き見る。
A New Glimpse:任意位置のカードを確認。
Top Card Glimpse:トップカードを確認。
Gamblers’ Glimpse:自然な動作で覗く。
After the Peek:ピーク後の覗き取り。
Cover for the Glimpse:カバー動作の工夫。
第12章:Jog(ジョグ)
概要
カードをわずかに突き出して位置をマーキング。
Side Jog:側面ジョグ。
Jog at the Break:ブレイクからジョグへ。
Automatic Jog No.I〜III:自然な動作でジョグを作る。
第13章:Reverse(リバース)
概要
カードやデックの向きを反転させる。
Facing the Deck:上下半分を逆向きに。
Righting the Faced Deck:元に戻す。
Automatic Reverse:自然な見せ方で反転。
Facing the Bottom Card:ボトムカードを反転。
Faced Deck Turnover:デック全体の向きを揃える。
第14章:Sundry Sleights(サンドリー・スライト)
概要
その他の有用技法集。
Vesting a Card:カードをベスト内に処分。
Zingone Thumbnail Gauge:爪で同枚数カット。
Separating the Colors:赤黒分離。
Setting a Key Card:キーカードのセット。
Five Card Quibble:5枚中から特定。
Emergency Card Stabbing:突き刺して当てる。
Drop Control:自然なコントロール。
Tap:軽いタップでジョグ。
Single Card Bridge:1枚だけブリッジ。
New Glide:改良グライド。
Bridge Location:曲げ癖で位置特定。
Spread Cull:スプレッド中に集める。
Double-Face:トップとボトムだけ裏向き。
Gamblers’ Card Marking System:マーキング法。
第15章:Rear Palm(リアパーム)
概要
手の後方にカードを保持し、指を開いても見えないパーム。
Nature of the Palm:基本形。
Rear Palming the Top Card:トップから移行。
Bottom Rear Palm:ボトムから直接。
Rear Palm Side Slip:リターン時に移行。
Little Finger Push-Out:ブレイクから移行。
Replacement:トップへ戻す。
Rear Palm Exchange:カード交換。
In Lieu of the Double Lift:ダブルリフト代替。
第16章:Perfect Faro Shuffle(パーフェクト・ファロー・シャッフル)
概要
26枚ずつに正確にカットし、カードを完全に交互に噛み合わせる。
Shuffle Chart:8回で元に戻る位置変
概要
観客に気づかれずにカードを覗き見る。
A New Glimpse:任意位置のカードを確認。
Top Card Glimpse:トップカードを確認。
Gamblers’ Glimpse:自然な動作で覗く。
After the Peek:ピーク後の覗き取り。
Cover for the Glimpse:カバー動作の工夫。
第12章:Jog(ジョグ)
概要
カードをわずかに突き出して位置をマーキング。
Side Jog:側面ジョグ。
Jog at the Break:ブレイクからジョグへ。
Automatic Jog No.I〜III:自然な動作でジョグを作る。
第13章:Reverse(リバース)
概要
カードやデックの向きを反転させる。
Facing the Deck:上下半分を逆向きに。
Righting the Faced Deck:元に戻す。
Automatic Reverse:自然な見せ方で反転。
Facing the Bottom Card:ボトムカードを反転。
Faced Deck Turnover:デック全体の向きを揃える。
第14章:Sundry Sleights(サンドリー・スライト)
概要
その他の有用技法集。
Vesting a Card:カードをベスト内に処分。
Zingone Thumbnail Gauge:爪で同枚数カット。
Separating the Colors:赤黒分離。
Setting a Key Card:キーカードのセット。
Five Card Quibble:5枚中から特定。
Emergency Card Stabbing:突き刺して当てる。
Drop Control:自然なコントロール。
Tap:軽いタップでジョグ。
Single Card Bridge:1枚だけブリッジ。
New Glide:改良グライド。
Bridge Location:曲げ癖で位置特定。
Spread Cull:スプレッド中に集める。
Double-Face:トップとボトムだけ裏向き。
Gamblers’ Card Marking System:マーキング法。
第15章:Rear Palm(リアパーム)
概要
手の後方にカードを保持し、指を開いても見えないパーム。
Nature of the Palm:基本形。
Rear Palming the Top Card:トップから移行。
Bottom Rear Palm:ボトムから直接。
Rear Palm Side Slip:リターン時に移行。
Little Finger Push-Out:ブレイクから移行。
Replacement:トップへ戻す。
Rear Palm Exchange:カード交換。
In Lieu of the Double Lift:ダブルリフト代替。
第16章:Perfect Faro Shuffle(パーフェクト・ファロー・シャッフル)
概要
26枚ずつに正確にカットし、カードを完全に交互に噛み合わせる。
Shuffle Chart:8回で元に戻る位置変
『Expert Card Technique』序章(内容要約)
本書の目的 著者ジャン・ヒューガードとフレデリック・ブラウエは、カードマジックの技法を網羅的かつ実用的にまとめることを目的としている。 初心者から熟練者までが、より自然で効果的な演技を行えるようにするための「技法の百科事典」として構成されている。
技法の位置づけ 技法は目的のための手段であり、見せびらかすものではない。 観客に「技を見せた」と思わせずに、演技の中に溶け込ませることが理想である。
練習と習得 習得には反復練習が不可欠であり、速度よりも正確さと自然さを優先すべきだと強調している。 「ぎこちない速さ」よりも「滑らかな自然さ」が観客の信頼を生む。
本書の構成
フォース、パーム、パス、ディール系などの基礎から高度な技法までを体系的に解説。
各技法には複数のバリエーションや改良法を収録。
後半にはそれらの技法を活用した実践的なトリックやルーティンを掲載。
著者の姿勢 著者は「カードマジックの芸術性を高める」ことを使命とし、単なる手順解説ではなく、演技全体の流れや観客心理への配慮も含めて解説している。
印象的な一文(短い引用)
"The sleights described herein are not ends in themselves, but means to an end — the creation of mystery and entertainment." (本書で解説する技法は、それ自体が目的ではなく、神秘と楽しさを生み出すための手段である。)
本書の目的 著者ジャン・ヒューガードとフレデリック・ブラウエは、カードマジックの技法を網羅的かつ実用的にまとめることを目的としている。 初心者から熟練者までが、より自然で効果的な演技を行えるようにするための「技法の百科事典」として構成されている。
技法の位置づけ 技法は目的のための手段であり、見せびらかすものではない。 観客に「技を見せた」と思わせずに、演技の中に溶け込ませることが理想である。
練習と習得 習得には反復練習が不可欠であり、速度よりも正確さと自然さを優先すべきだと強調している。 「ぎこちない速さ」よりも「滑らかな自然さ」が観客の信頼を生む。
本書の構成
フォース、パーム、パス、ディール系などの基礎から高度な技法までを体系的に解説。
各技法には複数のバリエーションや改良法を収録。
後半にはそれらの技法を活用した実践的なトリックやルーティンを掲載。
著者の姿勢 著者は「カードマジックの芸術性を高める」ことを使命とし、単なる手順解説ではなく、演技全体の流れや観客心理への配慮も含めて解説している。
印象的な一文(短い引用)
"The sleights described herein are not ends in themselves, but means to an end — the creation of mystery and entertainment." (本書で解説する技法は、それ自体が目的ではなく、神秘と楽しさを生み出すための手段である。)
第1章:Secret Lift(シークレットリフト)概要
章の位置づけ
・カードマジックにおいて最も頻繁に使われる基本技法のひとつ。
・「Secret Lift」という名称は、観客に気づかれずに複数枚を一枚として持ち上げる(リフトする)ことを指す。
・代表的なものはDouble Lift(ダブルリフト)だが、本章ではTriple Lift(トリプルリフト)やQuadruple Lift(クアドラプルリフト)まで扱う。
主な内容
1.ダブルリフトの重要性
ほぼすべてのカードマジックのジャンルで応用可能。
「理想的なダブルリフト」は、左手親指で自然に2枚を押し出すだけで成立する形。
実際には事前の「ゲットレディ(準備動作)」が必要だが、それを自然なジェスチャーで隠す方法を解説。
2.ゲットレディの方法
左手小指でブレイクを作る方法。
右手でカードを扱う際に自然にブレイクを作る方法。
観客の注意を逸らすタイミングの取り方。
3.トリプルリフト/クアドラプルリフト
従来は不安定で実用的でないとされてきたが、本章では安定して行うための改良法を提示。
複数枚を押し出す際のエッジの揃え方、重なりを見せない保持法。
左手小指を自然に挿入するための準備動作。
4.持ち上げ方と見せ方
観客にカードを見せる際の角度と距離。
カードを返す動作を「見せ場」にせず、あくまで自然な一連の動作に溶け込ませる。
観客が「カードを見た」と思う瞬間をコントロールする。
5.心理的カバー
技法の直前・直後に観客の注意を別の方向に向ける。
視線や会話を利用して、手元への注視を避ける。
●技法の核となる考え方
「Secret Liftは、それ自体を見せるための技法ではなく、観客に“何もしていない”と思わせたまま、カードの同一性をコントロールするための手段である。」
●この章で得られるスキル
・ダブルリフトを自然に行うための準備と実行。
・トリプル/クアドラプルリフトを安定して行うための指使いと保持法。
・観客心理を利用したカバーの入れ方。
・技法を演技全体に溶け込ませるための動作設計。
章の位置づけ
・カードマジックにおいて最も頻繁に使われる基本技法のひとつ。
・「Secret Lift」という名称は、観客に気づかれずに複数枚を一枚として持ち上げる(リフトする)ことを指す。
・代表的なものはDouble Lift(ダブルリフト)だが、本章ではTriple Lift(トリプルリフト)やQuadruple Lift(クアドラプルリフト)まで扱う。
主な内容
1.ダブルリフトの重要性
ほぼすべてのカードマジックのジャンルで応用可能。
「理想的なダブルリフト」は、左手親指で自然に2枚を押し出すだけで成立する形。
実際には事前の「ゲットレディ(準備動作)」が必要だが、それを自然なジェスチャーで隠す方法を解説。
2.ゲットレディの方法
左手小指でブレイクを作る方法。
右手でカードを扱う際に自然にブレイクを作る方法。
観客の注意を逸らすタイミングの取り方。
3.トリプルリフト/クアドラプルリフト
従来は不安定で実用的でないとされてきたが、本章では安定して行うための改良法を提示。
複数枚を押し出す際のエッジの揃え方、重なりを見せない保持法。
左手小指を自然に挿入するための準備動作。
4.持ち上げ方と見せ方
観客にカードを見せる際の角度と距離。
カードを返す動作を「見せ場」にせず、あくまで自然な一連の動作に溶け込ませる。
観客が「カードを見た」と思う瞬間をコントロールする。
5.心理的カバー
技法の直前・直後に観客の注意を別の方向に向ける。
視線や会話を利用して、手元への注視を避ける。
●技法の核となる考え方
「Secret Liftは、それ自体を見せるための技法ではなく、観客に“何もしていない”と思わせたまま、カードの同一性をコントロールするための手段である。」
●この章で得られるスキル
・ダブルリフトを自然に行うための準備と実行。
・トリプル/クアドラプルリフトを安定して行うための指使いと保持法。
・観客心理を利用したカバーの入れ方。
・技法を演技全体に溶け込ませるための動作設計。
P157
Part 2 翻訳(FLOURISHES)
フラリッシュ カード大道芸人が演技に機知と輝きを添えるのはフラリッシュの用い方による。フラリッシュは曲芸師が一時の小悪魔的仕掛けに香りを添える香辛料のようなものであり、器用さと想像力を示す魅力的で優雅な即興の所作である。本当の魔術師は単にパックの中の失われたカードを探し出すだけで満足しない。その場でカードの表面をはじけば、どこからともなく失われたカードが現れる。あるいは皮肉たっぷりに、自分の手さばきが普通のデックであることを示すためにカードを滑らかにリボン状に弾き飛ばす。あるいは軽い手つきでカードを完全に対称の美しいファンに広げる。あるいはパック上を手でなぞりながら、必要なカードを空中から悠々と摘み取るのである。
以下のページには、曲芸師が演技に添えることのできる新しいフラリッシュが列挙されている。これらは単なる技巧の誇示として用いるのではなく、驚くべき力のさりげない実演として用いるべきである。そのように用いれば、観客に愛される非公式な手品の雰囲気作りに大いに寄与するであろう。
Part 2 翻訳(FLOURISHES)
フラリッシュ カード大道芸人が演技に機知と輝きを添えるのはフラリッシュの用い方による。フラリッシュは曲芸師が一時の小悪魔的仕掛けに香りを添える香辛料のようなものであり、器用さと想像力を示す魅力的で優雅な即興の所作である。本当の魔術師は単にパックの中の失われたカードを探し出すだけで満足しない。その場でカードの表面をはじけば、どこからともなく失われたカードが現れる。あるいは皮肉たっぷりに、自分の手さばきが普通のデックであることを示すためにカードを滑らかにリボン状に弾き飛ばす。あるいは軽い手つきでカードを完全に対称の美しいファンに広げる。あるいはパック上を手でなぞりながら、必要なカードを空中から悠々と摘み取るのである。
以下のページには、曲芸師が演技に添えることのできる新しいフラリッシュが列挙されている。これらは単なる技巧の誇示として用いるのではなく、驚くべき力のさりげない実演として用いるべきである。そのように用いれば、観客に愛される非公式な手品の雰囲気作りに大いに寄与するであろう。
P159
Part 2 翻訳(FLOURISHES:インターロック・プロダクション)
フラリッシュ カード曲芸師が演技に機知と輝きを添えるのはフラリッシュを用いるためである。フラリッシュは曲芸師が一時的な小悪魔的手品に香辛料を振りかけるようなものであり、熟練と想像力を示す魅力的で優雅な即興の所作である。真のネクロマンサーは単に山の中の失われたカードを探し出すだけでは満足せず、その表面を弾けばどこからともなく失せ物のカードが現れる。あるいは皮肉めいて、自分の山が普通であることを示すためにカードを滑らかにリボン状に弾いてみせる。あるいは軽い手つきでカードを完璧に対称なファンに広げる。あるいはパックの上を手でなぞるだけで、必要なカードを空中からさっと摘み取る。
以下のページには、曲芸師が演技に添えるための新しいフラリッシュが列挙されている。これらは単なる技巧の誇示として使うのではなく、むしろさりげない驚異の実演として用いるべきである。そのように使えば、観客に愛されるインフォーマルなホーカスポーカスの雰囲気作りに大いに寄与するだろう。
インターロック・プロダクション この非常に効果的なフラリッシュは約二十年前、当時アメリカのヴォードヴィルで活躍していたカードの名手クリフ・グリーン氏によって導入された。この妙技は、表と裏のパーム(back and front palm)の亜種と言えるもので、(乱用されがちなあのフラリッシュとは異なり)やり過ぎられていないため、これを習得した者にはなおさら価値がある。本稿で初めて詳述するこれらの動きは難しくはないが、完璧なタイミングを要する。
効果は次の通りである。両手の指を組み合わせた状態で、手の甲と手のひらを交互に空で見せると、単発のカードが次々と現れて手から床へ落ちてゆくように見える、というものである。
まずは単一のカードで習得を始め、カードを手の背から手のひらへ、またその逆へと受け渡す動作を完璧にしてから複数枚に取り掛かるのがよい。手順は次の通りである。
右手にパーム(掌底に隠し持つ)したカードを用意し、両手の指先を手の甲が外向きになるようにして体前で合わせる。
指先が触れたときに、パームしたカードの上の内角を右親指で押し込み、右手指の保持を解く。カードは図1のように右親指と指の間の溝(thumb crotch)から突き出す。
各手の指を開いて組み直し、右の人差し指を左の第一指と第二指の間に入れて指を組む。するとカードは両手の親指溝で上角を挟む形でしっかり保持され、カードの表面は観客側に向く(図2)。カードの下辺のエッジは右の小指の内側に当たり、上辺は左の第一指の側面に当たる。
左親指でカードの左上角をしっかり押してカードを掌から斜めに傾け、右親指の保持を解く。右親指をカードの下面の縦端に当て、親指でカードを押し上げて左親指溝の中をスライドさせる。同時に両手を上方へひっくり返して手のひらを前面に揃える。この手のひっくり返しはカードの動きを常に隠すようなタイミングで行わねばならない。動作の終わりにはカードは左親指溝から水平に突き出し(図3)、正面からは完全に隠れている。
カードと手を元の位置(図2)に戻すには、右親指と手の動きを単純に逆に行えば良い。手が下向きに回り始める瞬間に右親指を上げ、カードの上辺の縁に押し当てて左親指溝からカードを押し戻し、元の位置に戻す。
手の位置を正確に取り、指示に注意深く従えば、カードは手の前面から背面へ、背面から前面へと見えないまま楽に移動させられることが分かるだろう。
実際のフラリッシュ(複数枚の出現) カードを一枚ずつ出現させる実運用では、まず右手に6枚〜8枚ほどのパケットをパームしてから行う。
単一カードのときと同様に指を組み、パケットを図2の位置に持ってくる。
左の第一指先で最も内側にあるカードの外上角を押して内側に折り込み、それを他のカードから分離する。
単一カードで説明したとおりに右親指を下側へ落とし、残りのカードを左親指溝のほうへ押し通しながら両手を上方へ回す。こうして分離した内側の一枚を残す。動作の終わりには、その一枚は右親指と小指の側面で挟まれ、観客に向けて示される一方で、残りのパケットは左親指溝から手の背側に突出している。
その単枚を一瞬見せて落とし、直ちに手を反転して右親指で押し下げることでパケットを元の位置へ戻す。
出現させたい枚数だけ同じ動作を繰り返す。
このフラリッシュは一連のカード操作の締めくくりとして効果的であるが、やり過ぎてはならない。10〜12枚の出現で十分であろう。
Part 2 翻訳(FLOURISHES:インターロック・プロダクション)
フラリッシュ カード曲芸師が演技に機知と輝きを添えるのはフラリッシュを用いるためである。フラリッシュは曲芸師が一時的な小悪魔的手品に香辛料を振りかけるようなものであり、熟練と想像力を示す魅力的で優雅な即興の所作である。真のネクロマンサーは単に山の中の失われたカードを探し出すだけでは満足せず、その表面を弾けばどこからともなく失せ物のカードが現れる。あるいは皮肉めいて、自分の山が普通であることを示すためにカードを滑らかにリボン状に弾いてみせる。あるいは軽い手つきでカードを完璧に対称なファンに広げる。あるいはパックの上を手でなぞるだけで、必要なカードを空中からさっと摘み取る。
以下のページには、曲芸師が演技に添えるための新しいフラリッシュが列挙されている。これらは単なる技巧の誇示として使うのではなく、むしろさりげない驚異の実演として用いるべきである。そのように使えば、観客に愛されるインフォーマルなホーカスポーカスの雰囲気作りに大いに寄与するだろう。
インターロック・プロダクション この非常に効果的なフラリッシュは約二十年前、当時アメリカのヴォードヴィルで活躍していたカードの名手クリフ・グリーン氏によって導入された。この妙技は、表と裏のパーム(back and front palm)の亜種と言えるもので、(乱用されがちなあのフラリッシュとは異なり)やり過ぎられていないため、これを習得した者にはなおさら価値がある。本稿で初めて詳述するこれらの動きは難しくはないが、完璧なタイミングを要する。
効果は次の通りである。両手の指を組み合わせた状態で、手の甲と手のひらを交互に空で見せると、単発のカードが次々と現れて手から床へ落ちてゆくように見える、というものである。
まずは単一のカードで習得を始め、カードを手の背から手のひらへ、またその逆へと受け渡す動作を完璧にしてから複数枚に取り掛かるのがよい。手順は次の通りである。
右手にパーム(掌底に隠し持つ)したカードを用意し、両手の指先を手の甲が外向きになるようにして体前で合わせる。
指先が触れたときに、パームしたカードの上の内角を右親指で押し込み、右手指の保持を解く。カードは図1のように右親指と指の間の溝(thumb crotch)から突き出す。
各手の指を開いて組み直し、右の人差し指を左の第一指と第二指の間に入れて指を組む。するとカードは両手の親指溝で上角を挟む形でしっかり保持され、カードの表面は観客側に向く(図2)。カードの下辺のエッジは右の小指の内側に当たり、上辺は左の第一指の側面に当たる。
左親指でカードの左上角をしっかり押してカードを掌から斜めに傾け、右親指の保持を解く。右親指をカードの下面の縦端に当て、親指でカードを押し上げて左親指溝の中をスライドさせる。同時に両手を上方へひっくり返して手のひらを前面に揃える。この手のひっくり返しはカードの動きを常に隠すようなタイミングで行わねばならない。動作の終わりにはカードは左親指溝から水平に突き出し(図3)、正面からは完全に隠れている。
カードと手を元の位置(図2)に戻すには、右親指と手の動きを単純に逆に行えば良い。手が下向きに回り始める瞬間に右親指を上げ、カードの上辺の縁に押し当てて左親指溝からカードを押し戻し、元の位置に戻す。
手の位置を正確に取り、指示に注意深く従えば、カードは手の前面から背面へ、背面から前面へと見えないまま楽に移動させられることが分かるだろう。
実際のフラリッシュ(複数枚の出現) カードを一枚ずつ出現させる実運用では、まず右手に6枚〜8枚ほどのパケットをパームしてから行う。
単一カードのときと同様に指を組み、パケットを図2の位置に持ってくる。
左の第一指先で最も内側にあるカードの外上角を押して内側に折り込み、それを他のカードから分離する。
単一カードで説明したとおりに右親指を下側へ落とし、残りのカードを左親指溝のほうへ押し通しながら両手を上方へ回す。こうして分離した内側の一枚を残す。動作の終わりには、その一枚は右親指と小指の側面で挟まれ、観客に向けて示される一方で、残りのパケットは左親指溝から手の背側に突出している。
その単枚を一瞬見せて落とし、直ちに手を反転して右親指で押し下げることでパケットを元の位置へ戻す。
出現させたい枚数だけ同じ動作を繰り返す。
このフラリッシュは一連のカード操作の締めくくりとして効果的であるが、やり過ぎてはならない。10〜12枚の出現で十分であろう。
Part 2 FLOURISHES
P161
カラー・チェンジ これは、多くの教本に解説が載っている、有名なフランスの奇術師で影絵芸の名手トルウェイ(Trewey)が考案したとされる本来のカラー・チェンジである。不幸なことに、非常に重要な細部が省かれて伝わったため、この妙技の失敗率はひどいものとなった。掌底に隠したカードが、演者の手の底で露出してしまうという不可解な失敗が頻発し、この方法を用いる術者はたいてい自分だけを欺く結果になっている。 ここで初めて記す成功の秘訣は、親指を固くして掌側に押し付けて保持することである。必要な動作は次のとおり。
a. カードを盗む正しい方法
デックを左手で持ち、親指と第二・三・四指で側面を挟み、第一指は端に添える(図1参照)。
右手の指を密着させて表向きのカードの上へ置き、親指は背面に当て、パックの内端を親指の溝(crotch)にしっかり押し込む。右手の第一指の上面はデックの上面と揃っているべきである。
右手を表向きカードの上から引き、同時に左の人差し指先で掌底へパームする後部のカードを約1インチ内側へ押し込み、直ちに元の端に戻す。右親指を掌の側面に当てて固く保持し、その側面と掌の側面でこれらのカードを挟む(図2参照)。
すぐに固く押し付けた親指を掌の側面に押し当て、パケットを右手に平らに保持しつつ、そのパケットがパックから抜ける瞬間に指を屈曲させてカードを正しい掌底(orthodox palm)へ取り込む。
最後に屈めた右指の甲でパックの端を軽くたたいてスクエアにし、表向きカードが変わっていないことを改めて示す。
b. カラー・チェンジ グリップの機構が理解できれば、あとは実際にその動作をカードがデックから奪い取られたように見せない技巧で提示する方法だけである。手順は次の通り。
右手をデックよりやや下に平らに構え、表向きカードの上へ軽く上方に移動させる動作を一二回繰り返す。
左人差し指で後部のカードを約1インチ内側へ押し込み、前述のように右親指の溝に挟む。右手も同じ方向へ同じ距離だけ動かす。直ちに左の第三・第四指を下側から離し、左親指と第二指のみで外角近くを持ってパックを保持する。左人差し指はパックの背に沿わせて屈曲させる。
右手を真下に動かしてカードをパームする(図3参照)。屈めた右指の甲でパックの端をたたいてスクエアにし、少し後に右手を表向きカードの上へ戻す。パームしたカードをそこへ置き、これでカラー・チェンジは完了する。
この方法によれば、パームすべきカードは驚くほど容易かつ素早く確保でき、動作中にためらいのサインが出ない。 単にデックの後部からカードをパームするだけに使う場合も、同様にデックをスクエアにする覆いの下で盗みを行えばよい。
インポッシブル・カラー・チェンジ 滑らかに行えば、最も注意深い観客にも疑問を抱かせないカラー・チェンジである。
左側を前方に向けて立ち、背面を観客に向けたままオーバーハンドでシャッフルする。
右手でパックを、内端に親指、外端に四指を当てて持ち、ボトムカードは掌に向ける。
前方へ向きを変え、両手を体の両側に持ち上げて掌を見せる(指は上向き)。左へ回り、パックを左手に表向きで受け取る際に、右手でワンハンド・トップパームを行い、ボトムカードを表向き内側にパームする。
パックを左手で表向きに垂直に持ち、親指を表向きカードの中央に沿って押さえる(図1参照)。
右手の人差し指で表向きカードを示し、他の指は自然に掌に丸める。小指をパームしたカードの外右端の下へ滑り込ませ、第三指の側面に挟む。この動作は、指が掌の背の保護に隠れているため気づかれない。指を伸ばして、対角の角を押すことでカードを外向きに曲げ、手を直立で平らに保ったままデックの左数インチへ移動する。
右手をパックの上へ引き戻し、左親指をほんの少し持ち上げてパームしたカードの曲がった中央が下を通ることを許し、そのカードをきっちりとデックの表面に置く。右手の動きを左肩方向へためらいなく続けると、変化が明らかになる。さりげない仕草で右手が空であることを示す。
左親指の位置と右手の完全な平らさゆえに、手品の可能性はないように見える。変化は非常に驚かせるものである。
P161
カラー・チェンジ これは、多くの教本に解説が載っている、有名なフランスの奇術師で影絵芸の名手トルウェイ(Trewey)が考案したとされる本来のカラー・チェンジである。不幸なことに、非常に重要な細部が省かれて伝わったため、この妙技の失敗率はひどいものとなった。掌底に隠したカードが、演者の手の底で露出してしまうという不可解な失敗が頻発し、この方法を用いる術者はたいてい自分だけを欺く結果になっている。 ここで初めて記す成功の秘訣は、親指を固くして掌側に押し付けて保持することである。必要な動作は次のとおり。
a. カードを盗む正しい方法
デックを左手で持ち、親指と第二・三・四指で側面を挟み、第一指は端に添える(図1参照)。
右手の指を密着させて表向きのカードの上へ置き、親指は背面に当て、パックの内端を親指の溝(crotch)にしっかり押し込む。右手の第一指の上面はデックの上面と揃っているべきである。
右手を表向きカードの上から引き、同時に左の人差し指先で掌底へパームする後部のカードを約1インチ内側へ押し込み、直ちに元の端に戻す。右親指を掌の側面に当てて固く保持し、その側面と掌の側面でこれらのカードを挟む(図2参照)。
すぐに固く押し付けた親指を掌の側面に押し当て、パケットを右手に平らに保持しつつ、そのパケットがパックから抜ける瞬間に指を屈曲させてカードを正しい掌底(orthodox palm)へ取り込む。
最後に屈めた右指の甲でパックの端を軽くたたいてスクエアにし、表向きカードが変わっていないことを改めて示す。
b. カラー・チェンジ グリップの機構が理解できれば、あとは実際にその動作をカードがデックから奪い取られたように見せない技巧で提示する方法だけである。手順は次の通り。
右手をデックよりやや下に平らに構え、表向きカードの上へ軽く上方に移動させる動作を一二回繰り返す。
左人差し指で後部のカードを約1インチ内側へ押し込み、前述のように右親指の溝に挟む。右手も同じ方向へ同じ距離だけ動かす。直ちに左の第三・第四指を下側から離し、左親指と第二指のみで外角近くを持ってパックを保持する。左人差し指はパックの背に沿わせて屈曲させる。
右手を真下に動かしてカードをパームする(図3参照)。屈めた右指の甲でパックの端をたたいてスクエアにし、少し後に右手を表向きカードの上へ戻す。パームしたカードをそこへ置き、これでカラー・チェンジは完了する。
この方法によれば、パームすべきカードは驚くほど容易かつ素早く確保でき、動作中にためらいのサインが出ない。 単にデックの後部からカードをパームするだけに使う場合も、同様にデックをスクエアにする覆いの下で盗みを行えばよい。
インポッシブル・カラー・チェンジ 滑らかに行えば、最も注意深い観客にも疑問を抱かせないカラー・チェンジである。
左側を前方に向けて立ち、背面を観客に向けたままオーバーハンドでシャッフルする。
右手でパックを、内端に親指、外端に四指を当てて持ち、ボトムカードは掌に向ける。
前方へ向きを変え、両手を体の両側に持ち上げて掌を見せる(指は上向き)。左へ回り、パックを左手に表向きで受け取る際に、右手でワンハンド・トップパームを行い、ボトムカードを表向き内側にパームする。
パックを左手で表向きに垂直に持ち、親指を表向きカードの中央に沿って押さえる(図1参照)。
右手の人差し指で表向きカードを示し、他の指は自然に掌に丸める。小指をパームしたカードの外右端の下へ滑り込ませ、第三指の側面に挟む。この動作は、指が掌の背の保護に隠れているため気づかれない。指を伸ばして、対角の角を押すことでカードを外向きに曲げ、手を直立で平らに保ったままデックの左数インチへ移動する。
右手をパックの上へ引き戻し、左親指をほんの少し持ち上げてパームしたカードの曲がった中央が下を通ることを許し、そのカードをきっちりとデックの表面に置く。右手の動きを左肩方向へためらいなく続けると、変化が明らかになる。さりげない仕草で右手が空であることを示す。
左親指の位置と右手の完全な平らさゆえに、手品の可能性はないように見える。変化は非常に驚かせるものである。
Part 2 FLOURISHES
P164
The Covinous Color Change(コヴィナス・カラー・チェンジ)
効果は通常のカラー・チェンジと同じで、デックの表向きカードが変化するが、本手法はこのトリックのために考案された中でもおそらく最も滑らかなものの一つである。手順は以下の通り。
正面を向き、左手にデックを表向きでディールする姿勢で持ち、右人差し指で表向きカードを指し示し、右手が空であることを見せるように構える。
右手でデックを右端寄りの端持ちに取り、親指を内端、第二指を外端に置き、人差し指先端を表向きカードに当てたまま右へ回して右手の掌を前に向け、デックの背を外側に向ける。左人差し指は右手を指す位置に置き、その先端はデックの背から数インチ離しておく。
左へ戻してデックを左手に元の位置(左手で表向き)に移す動作のなかで、ここで(第51頁参照の)フェイスカード・パームを行い、右手でデックのトップカードを掌側にパームする。
右人差し指で表向きカードを指し示した後、右指を伸ばし、ギャンブラーのフラットパーム(第56頁参照)の方法でパームしたカードを保持する。すなわち、小指先と親指付け根をわずかに収縮させてカードを保持する。
右手をデックの表向きカードに平らに当て、パームしたカードをちょうどその上に重ね、指をできるだけ大きく開いてから手をゆっくり下へ引くことで、観客に変化を見せる。
デックを手から手へ移す動作は自然であり、左右の手が順に空であることを示すため、表向きカードの変化は観客にとって全くの不意打ちとなる。
The Pressure Fan(プレッシャー・ファン)
現代のカード曲芸師がカードの面を見せる際、左手で幅広くファンにして展示することが慣例となっている。各カードが等間隔で車輪のスポークのように放射状に並ぶ完璧なファンを作るには相当の練習を要するが、以下の細部に注意すれば習得は容易になる。ファンは正当なフラリッシュであり、観客に演者の器用さへの高い評価を与える。
左手をディールの保持法でデックを持ち、左親指で側面を右へ大きくそらしておく。右手は端を支えてカードを安定させる。
右親指を内端に、第二・第三指を外端に当て、ボトムカードの右隅付近で端をつかむ。これらの指の第二関節は曲げ、指先がボトムカードの端と一直線になるようにする。
デックを左親指の溝に斜めに置き、デックの左側が左親指にほぼ平行になるようにする。左人差し指の第一関節は内側の右隅に当たり、指はボトムカードの面を対角に横切る位置に来る(図1・2参照)。
右の第二・第三指の指先で軽く内側へ押してカードをわずかに曲げ、その指を右へスナップすることでファンを作る。右親指はトップカードの内端に軽く位置を保ち、右指が外端を右へ回すことでカードが先端から滑り出す(図3参照)。
本動作は文章で説明するのが難しく、練習によってコツを掴むしかない。上で述べた二点――デックを右へ傾けることと、右の第二・第三指の指先だけを外端に置くこと――が習得を大きく助け、スポーク状の美しい周辺形状を得る助けとなる。
プレッシャー・ファンの大きな利点は、デックの状態を問わず(新しいカードでも古いカードでも)同じようにファンを作れることである。
P164
The Covinous Color Change(コヴィナス・カラー・チェンジ)
効果は通常のカラー・チェンジと同じで、デックの表向きカードが変化するが、本手法はこのトリックのために考案された中でもおそらく最も滑らかなものの一つである。手順は以下の通り。
正面を向き、左手にデックを表向きでディールする姿勢で持ち、右人差し指で表向きカードを指し示し、右手が空であることを見せるように構える。
右手でデックを右端寄りの端持ちに取り、親指を内端、第二指を外端に置き、人差し指先端を表向きカードに当てたまま右へ回して右手の掌を前に向け、デックの背を外側に向ける。左人差し指は右手を指す位置に置き、その先端はデックの背から数インチ離しておく。
左へ戻してデックを左手に元の位置(左手で表向き)に移す動作のなかで、ここで(第51頁参照の)フェイスカード・パームを行い、右手でデックのトップカードを掌側にパームする。
右人差し指で表向きカードを指し示した後、右指を伸ばし、ギャンブラーのフラットパーム(第56頁参照)の方法でパームしたカードを保持する。すなわち、小指先と親指付け根をわずかに収縮させてカードを保持する。
右手をデックの表向きカードに平らに当て、パームしたカードをちょうどその上に重ね、指をできるだけ大きく開いてから手をゆっくり下へ引くことで、観客に変化を見せる。
デックを手から手へ移す動作は自然であり、左右の手が順に空であることを示すため、表向きカードの変化は観客にとって全くの不意打ちとなる。
The Pressure Fan(プレッシャー・ファン)
現代のカード曲芸師がカードの面を見せる際、左手で幅広くファンにして展示することが慣例となっている。各カードが等間隔で車輪のスポークのように放射状に並ぶ完璧なファンを作るには相当の練習を要するが、以下の細部に注意すれば習得は容易になる。ファンは正当なフラリッシュであり、観客に演者の器用さへの高い評価を与える。
左手をディールの保持法でデックを持ち、左親指で側面を右へ大きくそらしておく。右手は端を支えてカードを安定させる。
右親指を内端に、第二・第三指を外端に当て、ボトムカードの右隅付近で端をつかむ。これらの指の第二関節は曲げ、指先がボトムカードの端と一直線になるようにする。
デックを左親指の溝に斜めに置き、デックの左側が左親指にほぼ平行になるようにする。左人差し指の第一関節は内側の右隅に当たり、指はボトムカードの面を対角に横切る位置に来る(図1・2参照)。
右の第二・第三指の指先で軽く内側へ押してカードをわずかに曲げ、その指を右へスナップすることでファンを作る。右親指はトップカードの内端に軽く位置を保ち、右指が外端を右へ回すことでカードが先端から滑り出す(図3参照)。
本動作は文章で説明するのが難しく、練習によってコツを掴むしかない。上で述べた二点――デックを右へ傾けることと、右の第二・第三指の指先だけを外端に置くこと――が習得を大きく助け、スポーク状の美しい周辺形状を得る助けとなる。
プレッシャー・ファンの大きな利点は、デックの状態を問わず(新しいカードでも古いカードでも)同じようにファンを作れることである。
P166
Fan Flourish(ファン・フラリッシュ) カードの選択を促す場面での洒落たフラリッシュの一つに、デックを裏向きでファンにし、それをテーブルに置いてカードを引く人に自由な選択を保証する方法がある。このようにテーブル上に並べられたファンは見た目にも美しく映る。
Springing the Cards—A New Method(カードのスプリング — 新手法) 次に示す手法は、手から手へカードをスプリングする際に、より大きな安定性と容易さをもたらす。動作をややゆっくりにできるため効果的で、手を離してもカードをさらに遠くへ飛ばせるようになる。
右手にデックを、正統的な持ち方どおり内端に親指、外端に指を置いて持つが、親指を左内角に、右小指を右外角に斜め対角に配置し、残る三本の指は動作に関与させない。
親指と小指で内側へ圧をかけ、カードを右内角から左外角へ向けてたわませる(バuckleさせる)。
左手を右手から少し離して構え、カードの角を押さえ続けながら、親指の球(ball)からカードを滑らせて左手へ弾ませる。親指と小指の圧を増減することで、カードの飛び出す速度を調整できる(図1参照)。
The Top and Bottom Changes(トップおよびボトム・チェンジ) これらのチェンジは特定のトリック中の妙技として使われるだけでなく、独立しても効果的に用いることができる。
例えば、直前のトリックの結末が今ひとつで終わりの温度が足りないときに、赤いカードを手に持ち、デックのトップには黒、その次に赤が来ている状況だとする。演者は観客に向かって「実際はとても簡単です。赤いカードを袖でこすると…(こすると)黒に変わります」と語りつつ、動作に合わせて右半身をやや回して赤いカードの面を見せ、次に左へ回りながらボトム・チェンジを行う。手は前方で会合し、離れ、左へ回り切ったら左腕を伸ばしてカードを裏向きに持ち、手首から肘まで袖に沿わせてこする。再びカードの表を示すと、今は黒になっている。
さらに「赤が欲しいなら髪でこすると…」と言って両手を体の前で持ち上げながらトップ・チェンジを行い、その後右手を頭部へ運んで髪にこすり、変化を見せる。もし髪色が似合わないなら、同じ効果はカードを唇に近づけて吹きかける仕草でも得られる。
このように古典的なチェンジ(More Card Manipulations, No.1 の例)を組み合わせると、ファン、カラー・チェンジ、パーム、リカバリー等のメドレーに自然に収まる。
There It Is!(出てきた!) これは特に出所を特定できないちょっとした小粋な小技で、あまり知られていないようだ。ルーティンの合い間に遊びで入れると愉快である。
効果:演者が選ばれたカードを見つけられずに失敗するふりをするが、代わりに一風変わった方法でそれを見つける。
方法:
選ばれたカードをトップから2番目に持ってくる。右手の人差し指と親指でトップカードを端でつまみ、掌を上に向けて右へ回してカードの顔面を見せる。
次のカード(選ばれたカード)を左親指でパックから押し出す。右の第三指と小指で右外角をつまむ(図1参照)。
「違います」と告げられてトップカードを表向きにして元の位置に戻すと、この動作が自動的に所望のカードを(第三指と小指の間から)表向きに突き出させる。手はその時点で掌下向きになっている(図1参照)。
Fan Flourish(ファン・フラリッシュ) カードの選択を促す場面での洒落たフラリッシュの一つに、デックを裏向きでファンにし、それをテーブルに置いてカードを引く人に自由な選択を保証する方法がある。このようにテーブル上に並べられたファンは見た目にも美しく映る。
Springing the Cards—A New Method(カードのスプリング — 新手法) 次に示す手法は、手から手へカードをスプリングする際に、より大きな安定性と容易さをもたらす。動作をややゆっくりにできるため効果的で、手を離してもカードをさらに遠くへ飛ばせるようになる。
右手にデックを、正統的な持ち方どおり内端に親指、外端に指を置いて持つが、親指を左内角に、右小指を右外角に斜め対角に配置し、残る三本の指は動作に関与させない。
親指と小指で内側へ圧をかけ、カードを右内角から左外角へ向けてたわませる(バuckleさせる)。
左手を右手から少し離して構え、カードの角を押さえ続けながら、親指の球(ball)からカードを滑らせて左手へ弾ませる。親指と小指の圧を増減することで、カードの飛び出す速度を調整できる(図1参照)。
The Top and Bottom Changes(トップおよびボトム・チェンジ) これらのチェンジは特定のトリック中の妙技として使われるだけでなく、独立しても効果的に用いることができる。
例えば、直前のトリックの結末が今ひとつで終わりの温度が足りないときに、赤いカードを手に持ち、デックのトップには黒、その次に赤が来ている状況だとする。演者は観客に向かって「実際はとても簡単です。赤いカードを袖でこすると…(こすると)黒に変わります」と語りつつ、動作に合わせて右半身をやや回して赤いカードの面を見せ、次に左へ回りながらボトム・チェンジを行う。手は前方で会合し、離れ、左へ回り切ったら左腕を伸ばしてカードを裏向きに持ち、手首から肘まで袖に沿わせてこする。再びカードの表を示すと、今は黒になっている。
さらに「赤が欲しいなら髪でこすると…」と言って両手を体の前で持ち上げながらトップ・チェンジを行い、その後右手を頭部へ運んで髪にこすり、変化を見せる。もし髪色が似合わないなら、同じ効果はカードを唇に近づけて吹きかける仕草でも得られる。
このように古典的なチェンジ(More Card Manipulations, No.1 の例)を組み合わせると、ファン、カラー・チェンジ、パーム、リカバリー等のメドレーに自然に収まる。
There It Is!(出てきた!) これは特に出所を特定できないちょっとした小粋な小技で、あまり知られていないようだ。ルーティンの合い間に遊びで入れると愉快である。
効果:演者が選ばれたカードを見つけられずに失敗するふりをするが、代わりに一風変わった方法でそれを見つける。
方法:
選ばれたカードをトップから2番目に持ってくる。右手の人差し指と親指でトップカードを端でつまみ、掌を上に向けて右へ回してカードの顔面を見せる。
次のカード(選ばれたカード)を左親指でパックから押し出す。右の第三指と小指で右外角をつまむ(図1参照)。
「違います」と告げられてトップカードを表向きにして元の位置に戻すと、この動作が自動的に所望のカードを(第三指と小指の間から)表向きに突き出させる。手はその時点で掌下向きになっている(図1参照)。
第3版(1950年)巻頭謝辞・謝罪文 抜粋(原文英語)
“My most grateful thanks are due to Mr. George Stark, editor of the ‘Stars of Magic’ series, for his invaluable assistance in bringing this new edition to press. I would also express my sincere apologies to Mr. Dai Vernon, whose methods and material appear throughout this volume without proper acknowledgment in the first edition. The omission was not due to lack of appreciation, but to the unavoidable difficulties of compiling so vast a work by correspondence alone. I deeply regret any offence caused, and trust that the additions and corrections herein will prove sufficiently to compensate for the earlier oversight.”
— Jean Hugard, Preface to the Third Edition, Expert Card Technique (1950)
“My most grateful thanks are due to Mr. George Stark, editor of the ‘Stars of Magic’ series, for his invaluable assistance in bringing this new edition to press. I would also express my sincere apologies to Mr. Dai Vernon, whose methods and material appear throughout this volume without proper acknowledgment in the first edition. The omission was not due to lack of appreciation, but to the unavoidable difficulties of compiling so vast a work by correspondence alone. I deeply regret any offence caused, and trust that the additions and corrections herein will prove sufficiently to compensate for the earlier oversight.”
— Jean Hugard, Preface to the Third Edition, Expert Card Technique (1950)
「本改訂版を出版するにあたり、『Stars of Magic』シリーズの編集者ジョージ・スターク氏には計り知れないご助力を賜り、心より感謝申し上げます。また、本書初版において、ダイ・バーノン氏の手法や素材が十分な謝辞なく多数掲載されたことにつきましても、深くお詫び申し上げます。この省略は敬意を欠いたものではなく、これほど膨大な分量の原稿を書簡のみでまとめ上げるというやむを得ない困難によるものです。ご不快の念をおかけしたことを重ねてお詫びいたしますとともに、本改訂版における訂正および追記が、先の不備を十分に補うものとなることを願っております。 — ジーン・ヒューガード(1950年版『エキスパート・カード・テクニック』第3版 序文)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-