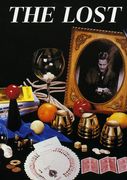KAPS, FRED(1926-1980)
オランダの生んだ偉大なマジシャン。
本名はアブラハム・ボンジャーズ(Abraham Bongers)。
9歳の頃にアマチュアマジシャンである美容師にちょっとしたクロースアップマジックを見せてもらった事でマジックに興味を持った。
青年の頃、ミスティカ(Mystica)という名前で軍隊などの慰問で活躍した頃もあったが、その後にフレッド・カップスと改名。
その高度なテクニックと洗練された演技は、一般客ばかりでなくマジシャン仲間からも尊敬された。
特に得意技であった塩の演技や、タバコの演技などはそれを模倣するものが現在でも後を絶えないほどである。
現在でもそうだが、ステージマジックとクロースアップマジックが、両方とも一流といえる希有な存在である。使用する道具やジャンルさえも様々なものを研究し、レパートリーとしていた。
マジックのオリンピックともいわれるFISMにおいてグランプリを三度(1950年、1955年、1961年)受賞している事は、彼自身の偉大さを物語るばかりではなく、FISMの権威を世界的にしたのも彼である、とも言えよう。
テレビ創世記においてはエド・サリバンショーに出演し、全米にその名を知られる事になった。当時はビートルズに匹敵するほどのエンターテイナーとも言われ、英国やオランダの王室にも招かれて演技を披露していたほどである。
日本においては1976年のJMA(日本奇術連盟)主催PCAMの大会に招かれ、マジック関係者に大きな衝撃を与えていった。
晩年の1979年にもJMS(力書房)の大会で来日をはたしている。
「何をやらせても彼があるトリックを手がけると、それは生き生きと光り輝くようであった。
オリジナルと呼べる作品は少なかったかもしれないが、本当に彼の特徴は選球眼のよさ(これはマジカルセンスといいかえてもいい)にあったともいえよう。
ある奇術の潜在的なよさ(長所)をみぬくと(あるいはそのトリックの弱点を見ぬくと)、徹底的にそのトリックを研究し、練習を重ねて自家薬籠中のものとし一級品にしたてあげた。」
松田道弘
ホーミング・カード
http://
トピット
http://
アスカニオ・スプレッド
http://
オランダの生んだ偉大なマジシャン。
本名はアブラハム・ボンジャーズ(Abraham Bongers)。
9歳の頃にアマチュアマジシャンである美容師にちょっとしたクロースアップマジックを見せてもらった事でマジックに興味を持った。
青年の頃、ミスティカ(Mystica)という名前で軍隊などの慰問で活躍した頃もあったが、その後にフレッド・カップスと改名。
その高度なテクニックと洗練された演技は、一般客ばかりでなくマジシャン仲間からも尊敬された。
特に得意技であった塩の演技や、タバコの演技などはそれを模倣するものが現在でも後を絶えないほどである。
現在でもそうだが、ステージマジックとクロースアップマジックが、両方とも一流といえる希有な存在である。使用する道具やジャンルさえも様々なものを研究し、レパートリーとしていた。
マジックのオリンピックともいわれるFISMにおいてグランプリを三度(1950年、1955年、1961年)受賞している事は、彼自身の偉大さを物語るばかりではなく、FISMの権威を世界的にしたのも彼である、とも言えよう。
テレビ創世記においてはエド・サリバンショーに出演し、全米にその名を知られる事になった。当時はビートルズに匹敵するほどのエンターテイナーとも言われ、英国やオランダの王室にも招かれて演技を披露していたほどである。
日本においては1976年のJMA(日本奇術連盟)主催PCAMの大会に招かれ、マジック関係者に大きな衝撃を与えていった。
晩年の1979年にもJMS(力書房)の大会で来日をはたしている。
「何をやらせても彼があるトリックを手がけると、それは生き生きと光り輝くようであった。
オリジナルと呼べる作品は少なかったかもしれないが、本当に彼の特徴は選球眼のよさ(これはマジカルセンスといいかえてもいい)にあったともいえよう。
ある奇術の潜在的なよさ(長所)をみぬくと(あるいはそのトリックの弱点を見ぬくと)、徹底的にそのトリックを研究し、練習を重ねて自家薬籠中のものとし一級品にしたてあげた。」
松田道弘
ホーミング・カード
http://
トピット
http://
アスカニオ・スプレッド
http://
|
|
|
|
コメント(62)
「私は正直なマジシャンです。」とフレッド氏は云う。
「私は本当に人をだました事はありません。だから、大人でさえも私の演技を楽しんでくれるのです。基本的には、人はマジックを信じていません。人はだまされているという事を認めたくないのです。好奇心を示すことはあっても、決してだまされているとは思いたくないのです。」
フレッド氏は、奇術を次のように説明しています。
「奇術というものは、単なる手の早業でもなければ、また、客の目をごまかせばよいというものでもない。奇術は、機転であり、すぐれた技術であり、そして何よりも、人間性の理解である。」といっている。
奇術界報413号(1976年1月)
「私は本当に人をだました事はありません。だから、大人でさえも私の演技を楽しんでくれるのです。基本的には、人はマジックを信じていません。人はだまされているという事を認めたくないのです。好奇心を示すことはあっても、決してだまされているとは思いたくないのです。」
フレッド氏は、奇術を次のように説明しています。
「奇術というものは、単なる手の早業でもなければ、また、客の目をごまかせばよいというものでもない。奇術は、機転であり、すぐれた技術であり、そして何よりも、人間性の理解である。」といっている。
奇術界報413号(1976年1月)
東海マジシャン第18号(昭和37年10月1日発行)
の記事です。
以下,無断引用です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジャック・ウォルトンの奇術
去る9月23目にNHKテレピで放送された世界のサーカスの中の奇術師ジャック・ウ
ォルトンの演技がマニアの間で評判になっている。映画と違い,再ぴ彼の演技が見られるか知れないので。ここに彼の現象を記録しておきたいと思う。
ケーンを新聞紙につつむ。これにコショーのぴんを取り出してふりかける。
びんを空中へ投げると消えてしまう。
新聞紙を拡げるとケーンが消えている。
新聞紙のかげから火のついたローソクが現われる。
ローソクをポケットに入れる。
さいふを出す中が空である。
一度とじてもう一度あけると紙幣が数枚入っている。
数える。
手でもむと小さくなる。
右手の中でコインになってしまう。
左手でハンカチを出す。
右手のコインが指間で4枚になる。
左手の上に拡げたハソカチにコイン入れてハンカチをとじる。
コインが消える。両手とも見せる。
ハンカチを袋状にして左手に持つ。
右手でエリから1枚のコインを取り出し,空中へ投げる。コインは空中で消えてハンカチの中へ落ち込む。
数枚のコインを同じ様にする。
コインをハンカチから出し箱に捨てる。
ハンカチから火のついたローソクが出る。
ローソクをポケットに入れる。
ポケットから紙幣を出す。
紙幣によるミリオンカード。
ハンカチをテーブルから取る。
瞬間右手にケーンが出現する。
ケーンを捨てる。
ハンカチからローソクが現れる。
ハンカチとローソクによる隠現
ローソクが数本に増加。増減。
ローソクが1本になる。
シルクがケーンになる。
以上スピーディで素晴しいテクニックを駆使した演技であった。
特に,パーム。パスの技巧が良い。
最近はハトの奇術が流行し。その他でパッとした奇術がないと思われているが,某氏曰く
「ハトでも出さないとかっこうがつかんと思っていたが,やる事は色々あるものだね」
−−−−−−−−引用ここまで−−−−−−−−−−−−−−−
演技内容から見て,フレッド・カップス師に間違いないと思うのですが,この名前は他では見たことがないので書き込みました。
それにしても,この時代,家庭用ビデオはまだないはずです。
これだけの演目を一度見ただけで書き留められるとは思えない。
8ミリにでも撮ってそれを見ながら書き記したのだろうか???
の記事です。
以下,無断引用です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ジャック・ウォルトンの奇術
去る9月23目にNHKテレピで放送された世界のサーカスの中の奇術師ジャック・ウ
ォルトンの演技がマニアの間で評判になっている。映画と違い,再ぴ彼の演技が見られるか知れないので。ここに彼の現象を記録しておきたいと思う。
ケーンを新聞紙につつむ。これにコショーのぴんを取り出してふりかける。
びんを空中へ投げると消えてしまう。
新聞紙を拡げるとケーンが消えている。
新聞紙のかげから火のついたローソクが現われる。
ローソクをポケットに入れる。
さいふを出す中が空である。
一度とじてもう一度あけると紙幣が数枚入っている。
数える。
手でもむと小さくなる。
右手の中でコインになってしまう。
左手でハンカチを出す。
右手のコインが指間で4枚になる。
左手の上に拡げたハソカチにコイン入れてハンカチをとじる。
コインが消える。両手とも見せる。
ハンカチを袋状にして左手に持つ。
右手でエリから1枚のコインを取り出し,空中へ投げる。コインは空中で消えてハンカチの中へ落ち込む。
数枚のコインを同じ様にする。
コインをハンカチから出し箱に捨てる。
ハンカチから火のついたローソクが出る。
ローソクをポケットに入れる。
ポケットから紙幣を出す。
紙幣によるミリオンカード。
ハンカチをテーブルから取る。
瞬間右手にケーンが出現する。
ケーンを捨てる。
ハンカチからローソクが現れる。
ハンカチとローソクによる隠現
ローソクが数本に増加。増減。
ローソクが1本になる。
シルクがケーンになる。
以上スピーディで素晴しいテクニックを駆使した演技であった。
特に,パーム。パスの技巧が良い。
最近はハトの奇術が流行し。その他でパッとした奇術がないと思われているが,某氏曰く
「ハトでも出さないとかっこうがつかんと思っていたが,やる事は色々あるものだね」
−−−−−−−−引用ここまで−−−−−−−−−−−−−−−
演技内容から見て,フレッド・カップス師に間違いないと思うのですが,この名前は他では見たことがないので書き込みました。
それにしても,この時代,家庭用ビデオはまだないはずです。
これだけの演目を一度見ただけで書き留められるとは思えない。
8ミリにでも撮ってそれを見ながら書き記したのだろうか???
最近、YouTubeの方にいくつかの氏の演技が出ていました。
マジックを行う上での自然さ、何度見てもほれぼれしてしまいます。
http://www.youtube.com/watch?v=UrYj5aV_K_8
http://www.youtube.com/watch?v=YIfElgVQyKs&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=in75bxS0PLE&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=KUp-cDgJs8M&mode=related&search=
マジックを行う上での自然さ、何度見てもほれぼれしてしまいます。
http://www.youtube.com/watch?v=UrYj5aV_K_8
http://www.youtube.com/watch?v=YIfElgVQyKs&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=in75bxS0PLE&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=KUp-cDgJs8M&mode=related&search=
フレッド・カップスのサロン用得意技の一つにサイドウォーク・シャッフルがあります。
私自身はマジックランド製を普段用いているのですが、トリックスでも同様の商品が販売されていました。タイトルは『エースをとらえよ!』です。
これの原文を読むとタイトルが"CONFUSIONE" di Fred Kapsとなっています。商品を作ったところはProposte Magicheです。一体どこの国なのでしょう。
元々このマジックは英国のケンブルクによって販売されていたJoe Piding"Three Card Trick with Four Cards"をもとにマーチン・ルイスが考案したと言われています。
ポール・ダニエルズも愛用していましたが、手順はどうもルイス版のような気がします。カップス氏はカップスらしく原案の良さを殺さずに独自の手順を考案したのでしょう。
私自身はマジックランド製を普段用いているのですが、トリックスでも同様の商品が販売されていました。タイトルは『エースをとらえよ!』です。
これの原文を読むとタイトルが"CONFUSIONE" di Fred Kapsとなっています。商品を作ったところはProposte Magicheです。一体どこの国なのでしょう。
元々このマジックは英国のケンブルクによって販売されていたJoe Piding"Three Card Trick with Four Cards"をもとにマーチン・ルイスが考案したと言われています。
ポール・ダニエルズも愛用していましたが、手順はどうもルイス版のような気がします。カップス氏はカップスらしく原案の良さを殺さずに独自の手順を考案したのでしょう。
フレッド・カップスのキャバレーアクトと呼ばれているのが有名なステージ手順かと思われます。
そのなかでハンカチと四枚のコインを使った地味でありながらも難易度が高く、いかにもカップスらしい手順が入っています。
複数枚のお札が,おまじないをかけると小さくなってゆき、しまいには4枚のコインになってしまいます。
その四枚のコインを使って演じているのがそのハンカチとコインの手順です。
簡単にいえば、四枚のコインが折り畳んだハンカチのなかに見えない状態で空中で飛行していく、というものです。
じつはこのマジック、巨匠ダイ・バーノン直伝であることは意外と知られていません。
バーノンの原案では3枚のコインを使ってハンカチに飛行するもので、一説には天海とディスカッションしているうちに完成したと言われています。
1960年代の半ばのヨーロッパレクチャーツアーにおいてバーノンはこのマジックを若きカップスに見せ、そして教えたそうです。
驚くべきことは天才カップスはたった一日でこの複雑なマジックを覚え、自分の手順としてその後に発展させていったのです。
そのなかでハンカチと四枚のコインを使った地味でありながらも難易度が高く、いかにもカップスらしい手順が入っています。
複数枚のお札が,おまじないをかけると小さくなってゆき、しまいには4枚のコインになってしまいます。
その四枚のコインを使って演じているのがそのハンカチとコインの手順です。
簡単にいえば、四枚のコインが折り畳んだハンカチのなかに見えない状態で空中で飛行していく、というものです。
じつはこのマジック、巨匠ダイ・バーノン直伝であることは意外と知られていません。
バーノンの原案では3枚のコインを使ってハンカチに飛行するもので、一説には天海とディスカッションしているうちに完成したと言われています。
1960年代の半ばのヨーロッパレクチャーツアーにおいてバーノンはこのマジックを若きカップスに見せ、そして教えたそうです。
驚くべきことは天才カップスはたった一日でこの複雑なマジックを覚え、自分の手順としてその後に発展させていったのです。
Fred Kapsの映像を視聴し、その技術と演出力に深く感銘を受けたことを石田氏に報告。映像内の複数の演目について具体的に分析し、Kapsの技術的巧妙さと演出の緩急、構成力、そして人間的魅力を高く評価している。
演目別の感想と分析
1. マッチングカード
シャフルを続けながら自然にフォースを行う手法に驚き
リボンスプレッド上でのフォースは後年タマリッツも使用しているが、Kapsは堂々と演じている
交互セットされた8枚から選ばせている可能性もあるが、いずれにせよ巧妙
オープナーとしての構成も見事で、伏線の張り方と緩急のつけ方が秀逸
2. トリプル・トランスポジション
宮中氏の解説と異なる印象を受けた(読み違えの可能性も示唆)
4枚のKをファンにして見せるタイミングや、エースとの入れ替えの見せ方が非常に洗練されている
今まで演じる気が起きなかったが、この演技を見てレパートリーに加えたいと感じた
3. ラストトリック
2枚のAと2枚のKで構成されていたのは白黒テレビ時代の制約か、あるいはKapsの通常スタイルか
カードの扱いが非常に巧妙で、2回繰り返せる構成にも驚き
4. ホーンテッドデック(コブラデック)
エースを差し込む際のブレークやコントロールが見抜けず、ティルトかと思っていたらホーンテッドデックだった
デックスイッチのタイミングが絶妙で、ラストトリックを挟むことでスイッチ感を消している
こうした演出上の配慮が名人芸と感じられる
その他の映像について
プレッシャーファンで1枚だけアウトジョグさせ、時計回りに回転させる動作が機械のように滑らか
ステージアクトでのお札の演技は知っていたが、カードでも十分に不思議で面白い
デックバニッシュでは完全に引っかかった
コインとタバコの演技も美しく、フレンチドロップの多用が意外だったが、Kapsが使うとまったく不自然に見えない
後半の映像はテレビ番組の一部かもしれず、角砂糖やタバコの演技がコント風で楽しい
レストランでの給仕役としての演技も印象的で、Kapsはどんなマジックにも応用が利く万能型だったと感じた
結び
Fred Kapsの演技は時代を超えて美しく、技術だけでなく気品と構成力に満ちている。改めてその偉大さを実感し、「長生きしてほしかった」と惜しむ気持ちで締めくくられている。
演目別の感想と分析
1. マッチングカード
シャフルを続けながら自然にフォースを行う手法に驚き
リボンスプレッド上でのフォースは後年タマリッツも使用しているが、Kapsは堂々と演じている
交互セットされた8枚から選ばせている可能性もあるが、いずれにせよ巧妙
オープナーとしての構成も見事で、伏線の張り方と緩急のつけ方が秀逸
2. トリプル・トランスポジション
宮中氏の解説と異なる印象を受けた(読み違えの可能性も示唆)
4枚のKをファンにして見せるタイミングや、エースとの入れ替えの見せ方が非常に洗練されている
今まで演じる気が起きなかったが、この演技を見てレパートリーに加えたいと感じた
3. ラストトリック
2枚のAと2枚のKで構成されていたのは白黒テレビ時代の制約か、あるいはKapsの通常スタイルか
カードの扱いが非常に巧妙で、2回繰り返せる構成にも驚き
4. ホーンテッドデック(コブラデック)
エースを差し込む際のブレークやコントロールが見抜けず、ティルトかと思っていたらホーンテッドデックだった
デックスイッチのタイミングが絶妙で、ラストトリックを挟むことでスイッチ感を消している
こうした演出上の配慮が名人芸と感じられる
その他の映像について
プレッシャーファンで1枚だけアウトジョグさせ、時計回りに回転させる動作が機械のように滑らか
ステージアクトでのお札の演技は知っていたが、カードでも十分に不思議で面白い
デックバニッシュでは完全に引っかかった
コインとタバコの演技も美しく、フレンチドロップの多用が意外だったが、Kapsが使うとまったく不自然に見えない
後半の映像はテレビ番組の一部かもしれず、角砂糖やタバコの演技がコント風で楽しい
レストランでの給仕役としての演技も印象的で、Kapsはどんなマジックにも応用が利く万能型だったと感じた
結び
Fred Kapsの演技は時代を超えて美しく、技術だけでなく気品と構成力に満ちている。改めてその偉大さを実感し、「長生きしてほしかった」と惜しむ気持ちで締めくくられている。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
クラシックマジック研究 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-