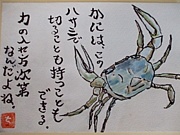|
|
|
|
コメント(15)
(第15話)
2036年10月15日、僕は29歳の誕生日をひばりに祝ってもらった。このところ、仕事も好調で、上司からは自分の仕事ぶりを高く評価してもらっている。でも、恋愛の方はまったくと言っていいほどダメな日々が続いていた。そんな中、彼女とは半年ほど前に看護師との合コンで出会った。
僕はあの日のことを一生忘れないだろう。今でも初めてであった日のことを鮮明に思い出すことができた。東芝ひばりという女性はわりときれいなのに、誰とも目を合わすことなく、一人で黙って料理を食べていた。まったく、合コン慣れしていない。きっと、頭数を合わせるために無理やり連れてこられたのだろう。他の三人の看護婦はいかにも合コン慣れしていて、僕達四人の男性から一人いい男を見つけ出して、そいつをどうやって自分のものにしようか、あれこれ策を実行しては一喜一憂をしていた。
僕は目の前に座っている合コン慣れしていない女性に興味を持った。僕は合コンでいい男はいないかなと厳しく品定めするような女性よりも、合コンに頭数そろえるために無理やり連れてこられたやる気のない女性のほうが好きだった。後者であれば、やり方次第では自分のものにできそうな気がしたからである。前者は身長が165しかない上、ぱっとしない顔の僕には見向きもしない。
「東芝さんでしたよね?」
「はい…。あなたは確か、夏目さんでしたよね」
「ここだけの話、私、実はこういうのダメなんですよね」
ここで僕はわざと小声で話して、彼女だけに話しているという雰囲気を強調した。彼女は耳に手を添えて、テーブル越しで少しだけ僕に近づいた。
「最近、もうすぐ三〇になるから、そろそろ結婚をしたいなあと思うようになってですね。それから、しぶしぶ合コン出るようになったんです。東芝さんも、あまり好きじゃないんではないですか?」
彼女は顔を赤らめながら、軽くうなずいた。そして、ジントニックを一口飲んで、のどを潤してから話し出した。
「実をいうと、ここにいる三人の後輩から、頭数をそろえるためにどうしても来て欲しいと言われたものですから…。本当は他の人が来るはずだったんですけど、急用で来られなくなったそうです。特に断る理由もなかったから、あまり好きではないんですが、顔を出してみたんです。そしたら、うまいこと彼女達の引き立て役をさせられてしまったみたいで…。だから、せめておいしいものだけはしっかりと食べて帰ろうと思ったわけですよ」
これはいけると思った。うまく説得することができれば、二人だけで抜け出すことができるのではないかと感じた。合コンなんて、その場のノリと勢いで成り立っているようなもの…。当たって砕けてみることにした。
「もし、よかったらこの後二人で抜け出しませんか?」
「えっ、それはまずいでしょ。だって、このあと二次会でカラオケでも行くでしょ。それで二人で抜け出すとなると誤解されますよ」
「いや、怪しまれずに二人で抜け出す方法が一つあります。それはですね…」
彼女と僕はこっそり店の外に出て、僕が彼女に作戦を話した。彼女が全てを理解すると僕らは何事もなかったかのように、席に戻った。そして、作戦は密かに実行された。
2036年10月15日、僕は29歳の誕生日をひばりに祝ってもらった。このところ、仕事も好調で、上司からは自分の仕事ぶりを高く評価してもらっている。でも、恋愛の方はまったくと言っていいほどダメな日々が続いていた。そんな中、彼女とは半年ほど前に看護師との合コンで出会った。
僕はあの日のことを一生忘れないだろう。今でも初めてであった日のことを鮮明に思い出すことができた。東芝ひばりという女性はわりときれいなのに、誰とも目を合わすことなく、一人で黙って料理を食べていた。まったく、合コン慣れしていない。きっと、頭数を合わせるために無理やり連れてこられたのだろう。他の三人の看護婦はいかにも合コン慣れしていて、僕達四人の男性から一人いい男を見つけ出して、そいつをどうやって自分のものにしようか、あれこれ策を実行しては一喜一憂をしていた。
僕は目の前に座っている合コン慣れしていない女性に興味を持った。僕は合コンでいい男はいないかなと厳しく品定めするような女性よりも、合コンに頭数そろえるために無理やり連れてこられたやる気のない女性のほうが好きだった。後者であれば、やり方次第では自分のものにできそうな気がしたからである。前者は身長が165しかない上、ぱっとしない顔の僕には見向きもしない。
「東芝さんでしたよね?」
「はい…。あなたは確か、夏目さんでしたよね」
「ここだけの話、私、実はこういうのダメなんですよね」
ここで僕はわざと小声で話して、彼女だけに話しているという雰囲気を強調した。彼女は耳に手を添えて、テーブル越しで少しだけ僕に近づいた。
「最近、もうすぐ三〇になるから、そろそろ結婚をしたいなあと思うようになってですね。それから、しぶしぶ合コン出るようになったんです。東芝さんも、あまり好きじゃないんではないですか?」
彼女は顔を赤らめながら、軽くうなずいた。そして、ジントニックを一口飲んで、のどを潤してから話し出した。
「実をいうと、ここにいる三人の後輩から、頭数をそろえるためにどうしても来て欲しいと言われたものですから…。本当は他の人が来るはずだったんですけど、急用で来られなくなったそうです。特に断る理由もなかったから、あまり好きではないんですが、顔を出してみたんです。そしたら、うまいこと彼女達の引き立て役をさせられてしまったみたいで…。だから、せめておいしいものだけはしっかりと食べて帰ろうと思ったわけですよ」
これはいけると思った。うまく説得することができれば、二人だけで抜け出すことができるのではないかと感じた。合コンなんて、その場のノリと勢いで成り立っているようなもの…。当たって砕けてみることにした。
「もし、よかったらこの後二人で抜け出しませんか?」
「えっ、それはまずいでしょ。だって、このあと二次会でカラオケでも行くでしょ。それで二人で抜け出すとなると誤解されますよ」
「いや、怪しまれずに二人で抜け出す方法が一つあります。それはですね…」
彼女と僕はこっそり店の外に出て、僕が彼女に作戦を話した。彼女が全てを理解すると僕らは何事もなかったかのように、席に戻った。そして、作戦は密かに実行された。
(第16話)
「先輩、大丈夫ですか?」
「ちょっと〜、飲み過ぎたみたい…」
これから二次会に行くというときに、東芝が酔いつぶれたことに他の女の子たちはすっかり困ってしまったようである。先輩を送っていくという貧乏くじのなすりつけ合いを始めてしまった。
「あのすみません。もし、よかったら私が送っていきましょうか? 私が彼女に飲ませすぎたみたいで…その責任を取らせて頂けませんか。せっかく、今から二次会に行くときに女の子が二人も抜けるとなると、残っている方に悪いですし…」
「夏目さんは大丈夫。新聞記事を書くのは早いけど、そっちの方は相当奥手だから、大丈夫でしゅよ」
後輩の富士はかなり飲んでいてろれつがうまく回らないようだった。一方で看護師達は東芝本人が「この人に送ってほしい」と言っているのもあって、私に彼女を任せることにしたようである。
その後、僕らがタクシーに乗るのを確認した後、彼らは何事もなかったかのように、集団でタクシーとは逆方向に動き出した。
「いやぁ、まさかここまでうまくいくとは…東芝さん、見事な酔っぱらいの演技でしたね」
「夏目さんこそ、店の人に頼んで焼酎ではなく、白湯を持ってこさせておきながら、みんなには焼酎と偽って、私に何杯も飲ませるんだから…」
それから、2人は顔を見合わせ笑った。さっきまでのことがおかしくてたまらない。もしかしたら、あっちの方だって、僕らのことが邪魔だったから、わざと見え見えの演技に乗ってくれたのかもしれない。女性の方はわからないが、男性の方は一応、トイレで打ち合わせをしておいた。たぶん、女性も同じようなことをやっているとは思うのだが…。それは僕が男性側の手の内を見せないように、彼女だって女性側の手の内は見せないからわからない。
あくまで、2人でみんなをだましたということに、なっていることが重要なのである。
「せっかくだから、この後2人で飲みませんか?」
彼女はこっちを一瞬向いてくれたが、すぐに窓に目を向けた。外が暗いので、窓にうっすら顔が映る。その顔は少しはにかんでいるようだった。しばらく、彼女は外を眺めて続けた。
「それとも今日はこのまま…帰りますか?」
僕はいい印象を与えようと、わざと一歩引いた。すると、彼女が突然、こっちを向いた。
「あなた、自分で誘っておいて、自分から舞台を降りるなんて…。それでいい男でも演じたつもり? あなたがずる賢い人ということはもうわかっていますから…。今日はとことん付き合ってもらいますよ。あっ、運転手さん、ここで降ろしてください」
突然、彼女が言うものだから、運転手はあわてて急ブレーキをかけた。僕らは前の席に頭から突っ込んだ。でも、しかたない。彼はお客の要求に応えただけである。
タクシーを降りて、彼女の行きつけの店「魔の力」に入った。普段、彼女はこの店に一人でしか行かないということであった。
「先輩、大丈夫ですか?」
「ちょっと〜、飲み過ぎたみたい…」
これから二次会に行くというときに、東芝が酔いつぶれたことに他の女の子たちはすっかり困ってしまったようである。先輩を送っていくという貧乏くじのなすりつけ合いを始めてしまった。
「あのすみません。もし、よかったら私が送っていきましょうか? 私が彼女に飲ませすぎたみたいで…その責任を取らせて頂けませんか。せっかく、今から二次会に行くときに女の子が二人も抜けるとなると、残っている方に悪いですし…」
「夏目さんは大丈夫。新聞記事を書くのは早いけど、そっちの方は相当奥手だから、大丈夫でしゅよ」
後輩の富士はかなり飲んでいてろれつがうまく回らないようだった。一方で看護師達は東芝本人が「この人に送ってほしい」と言っているのもあって、私に彼女を任せることにしたようである。
その後、僕らがタクシーに乗るのを確認した後、彼らは何事もなかったかのように、集団でタクシーとは逆方向に動き出した。
「いやぁ、まさかここまでうまくいくとは…東芝さん、見事な酔っぱらいの演技でしたね」
「夏目さんこそ、店の人に頼んで焼酎ではなく、白湯を持ってこさせておきながら、みんなには焼酎と偽って、私に何杯も飲ませるんだから…」
それから、2人は顔を見合わせ笑った。さっきまでのことがおかしくてたまらない。もしかしたら、あっちの方だって、僕らのことが邪魔だったから、わざと見え見えの演技に乗ってくれたのかもしれない。女性の方はわからないが、男性の方は一応、トイレで打ち合わせをしておいた。たぶん、女性も同じようなことをやっているとは思うのだが…。それは僕が男性側の手の内を見せないように、彼女だって女性側の手の内は見せないからわからない。
あくまで、2人でみんなをだましたということに、なっていることが重要なのである。
「せっかくだから、この後2人で飲みませんか?」
彼女はこっちを一瞬向いてくれたが、すぐに窓に目を向けた。外が暗いので、窓にうっすら顔が映る。その顔は少しはにかんでいるようだった。しばらく、彼女は外を眺めて続けた。
「それとも今日はこのまま…帰りますか?」
僕はいい印象を与えようと、わざと一歩引いた。すると、彼女が突然、こっちを向いた。
「あなた、自分で誘っておいて、自分から舞台を降りるなんて…。それでいい男でも演じたつもり? あなたがずる賢い人ということはもうわかっていますから…。今日はとことん付き合ってもらいますよ。あっ、運転手さん、ここで降ろしてください」
突然、彼女が言うものだから、運転手はあわてて急ブレーキをかけた。僕らは前の席に頭から突っ込んだ。でも、しかたない。彼はお客の要求に応えただけである。
タクシーを降りて、彼女の行きつけの店「魔の力」に入った。普段、彼女はこの店に一人でしか行かないということであった。
(第17話)
「太郎、ねぇ、太郎ったら…何、考えているの? 早くろうそくの火を消さないとケーキにろうが付くよ」
はっと僕は我に返って、あわててろうそくの火を消す。ひばりは「太郎、誕生日おめでとう」と言いながら、手作りのレアチーズケーキを切り分けて、小皿についでくれた。
「いや、ろうそくの火をみていたら、ひばりと初めてあった日に『魔の力』に行ったときのことを思い出してしまってね」
そう言いながら僕はケーキを食べる。すごくあっさりしていておいしい。甘いものがだめな僕でもレモンがよく効いた彼女の手作りチーズケーキだけは食べることができる。
「あの店はろうそくの光だけしか使わない店だから、すごく雰囲気がいいのよねぇ。あのときはまさか、こうして付き合うことになるとは思わなかったけど…」
ひばりもチーズケーキを食べている。一緒に同じものを食べ、一緒に同じ会話をしている。今回はたまたま2人で誕生日を一緒に過ごすことができたが、クリスマスも同じように一緒に過ごせるかは全くわからなかった。新聞記者も看護師も休みが不規則でなかかな一緒に休みを取ることができない。
「そうだよね。あの日はお互いに仕事の愚痴を言い合っただけだし…。でも、取りたいときに休みが取れないとかさ、みんなが休んでいるときも働かないといけないところとか不思議と共通していたから、お互いに共感できたんだよね」
自分の皿のケーキを食べ終わったので、ケーキを新しく小皿にのせた。それをまた食べる。
「確かにそれもあったと思うけど、2人の気があうというところが一番大きかったと思うよ。お互いに奥手だし、本当は合コンとかの華やかなところがすごく苦手…。そのなのに、私たちみたいなタイプの人間ってすごく少ないから、同じタイプの人間を見つけるのに苦労するのよ。でも、だからこそ、同じタイプの人間を見つけるための嗅覚がとても発達してるよね。あの日、太郎の合コンで浮いた姿を見たとき、自分と同じタイプをやっと見つけたと思った」
ひばりもケーキのおかわりをする。8等分されたケーキはあっという間に半分なくなった。僕はもう一つケーキをおかわりした。
「そうだね。僕もそう思った。だから、2人で一緒に抜けようなんて普段なら絶対に言えないことをさらりと言えたと思う」
彼女の紅茶がなくなっていることに気づき、僕は紅茶を入れてあげた。ついでに自分の紅茶も入れた。いつの間にかケーキはあと2切れになった。
「あっ、ありがとう。そう考えると私たち、運がいいよね。太郎に出会えて本当によかった」
僕はうなずいた。この偶然に感謝しないといけないと思った。そう考えている間にケーキは一切れとなってしまったので、僕は最後の一切れを食べた。こうして、二人の休みが重なった貴重な日は過ぎていった。
「太郎、ねぇ、太郎ったら…何、考えているの? 早くろうそくの火を消さないとケーキにろうが付くよ」
はっと僕は我に返って、あわててろうそくの火を消す。ひばりは「太郎、誕生日おめでとう」と言いながら、手作りのレアチーズケーキを切り分けて、小皿についでくれた。
「いや、ろうそくの火をみていたら、ひばりと初めてあった日に『魔の力』に行ったときのことを思い出してしまってね」
そう言いながら僕はケーキを食べる。すごくあっさりしていておいしい。甘いものがだめな僕でもレモンがよく効いた彼女の手作りチーズケーキだけは食べることができる。
「あの店はろうそくの光だけしか使わない店だから、すごく雰囲気がいいのよねぇ。あのときはまさか、こうして付き合うことになるとは思わなかったけど…」
ひばりもチーズケーキを食べている。一緒に同じものを食べ、一緒に同じ会話をしている。今回はたまたま2人で誕生日を一緒に過ごすことができたが、クリスマスも同じように一緒に過ごせるかは全くわからなかった。新聞記者も看護師も休みが不規則でなかかな一緒に休みを取ることができない。
「そうだよね。あの日はお互いに仕事の愚痴を言い合っただけだし…。でも、取りたいときに休みが取れないとかさ、みんなが休んでいるときも働かないといけないところとか不思議と共通していたから、お互いに共感できたんだよね」
自分の皿のケーキを食べ終わったので、ケーキを新しく小皿にのせた。それをまた食べる。
「確かにそれもあったと思うけど、2人の気があうというところが一番大きかったと思うよ。お互いに奥手だし、本当は合コンとかの華やかなところがすごく苦手…。そのなのに、私たちみたいなタイプの人間ってすごく少ないから、同じタイプの人間を見つけるのに苦労するのよ。でも、だからこそ、同じタイプの人間を見つけるための嗅覚がとても発達してるよね。あの日、太郎の合コンで浮いた姿を見たとき、自分と同じタイプをやっと見つけたと思った」
ひばりもケーキのおかわりをする。8等分されたケーキはあっという間に半分なくなった。僕はもう一つケーキをおかわりした。
「そうだね。僕もそう思った。だから、2人で一緒に抜けようなんて普段なら絶対に言えないことをさらりと言えたと思う」
彼女の紅茶がなくなっていることに気づき、僕は紅茶を入れてあげた。ついでに自分の紅茶も入れた。いつの間にかケーキはあと2切れになった。
「あっ、ありがとう。そう考えると私たち、運がいいよね。太郎に出会えて本当によかった」
僕はうなずいた。この偶然に感謝しないといけないと思った。そう考えている間にケーキは一切れとなってしまったので、僕は最後の一切れを食べた。こうして、二人の休みが重なった貴重な日は過ぎていった。
(第18話)
2037年6月6日、この日の福岡はとてもからっとしたいい天気で過ごしやすかった。少し暑かったけど、結婚式をするには最適であった。もうすぐ、梅雨を迎えるとは思えないほどの5月晴れであった。この日、僕らは結婚した。
ここまで来るのは、あっという間であった。少し早いかなと思ったが、ひばりがもう妊娠3ヵ月を迎えていたので、おなかが目立たないうちに結婚することとなった。できちゃった婚というのに、ひばりの両親はかなり抵抗を見せた。しかし、子供ができるようなことがなかったとしても、2人とも結婚願望が強かったことがわかってもらえたので、最後は納得してくれたようである。僕が大手新聞社で勤めていることもプラスに働いたとひばりが言っていた。
しかし、世間体にこだわるわりには、僕には片親しかいないことや、僕の出生については何も言わなかった。ひばりが言うにはそのようなことは太郎に対していっても、どうにかなる問題はないという考え方らしい。つまり、ある人が努力して変えることができること(就職や進学など)に対しては厳しいが、ある人に言ってもどうにもならないこと(身長とか親のことなど)に対してはとても寛容である。
かつて、看護師の仕事は産前休暇や産休などを取るのが大変難しい仕事であった。しかし、21世紀入ってからは看護師不足を解消するためにそのような環境が整えられたようである。
それにしても結婚式というのが、こんなにめんどくさいとは思わなかった。それ自体はとても華やかであるが、その日を迎えるためにいろいろな準備をしないといけないので本当に大変であった。特に誰を呼ぶかを決めるのは大変であった。ひばりには久万にも連絡すべきではないかと言われたが、僕は彼のことを他人だと認識していたので、結婚について何も連絡しなかった。
結婚式が終わったからと言って、劇的に何かが変わるわけではなかった。結婚する前からすでに同棲していたし、2人ともそれぞれの仕事があった。僕らは子供が生まれる直前まで、それまでと変わらない生活を続けていた。
2037年6月6日、この日の福岡はとてもからっとしたいい天気で過ごしやすかった。少し暑かったけど、結婚式をするには最適であった。もうすぐ、梅雨を迎えるとは思えないほどの5月晴れであった。この日、僕らは結婚した。
ここまで来るのは、あっという間であった。少し早いかなと思ったが、ひばりがもう妊娠3ヵ月を迎えていたので、おなかが目立たないうちに結婚することとなった。できちゃった婚というのに、ひばりの両親はかなり抵抗を見せた。しかし、子供ができるようなことがなかったとしても、2人とも結婚願望が強かったことがわかってもらえたので、最後は納得してくれたようである。僕が大手新聞社で勤めていることもプラスに働いたとひばりが言っていた。
しかし、世間体にこだわるわりには、僕には片親しかいないことや、僕の出生については何も言わなかった。ひばりが言うにはそのようなことは太郎に対していっても、どうにかなる問題はないという考え方らしい。つまり、ある人が努力して変えることができること(就職や進学など)に対しては厳しいが、ある人に言ってもどうにもならないこと(身長とか親のことなど)に対してはとても寛容である。
かつて、看護師の仕事は産前休暇や産休などを取るのが大変難しい仕事であった。しかし、21世紀入ってからは看護師不足を解消するためにそのような環境が整えられたようである。
それにしても結婚式というのが、こんなにめんどくさいとは思わなかった。それ自体はとても華やかであるが、その日を迎えるためにいろいろな準備をしないといけないので本当に大変であった。特に誰を呼ぶかを決めるのは大変であった。ひばりには久万にも連絡すべきではないかと言われたが、僕は彼のことを他人だと認識していたので、結婚について何も連絡しなかった。
結婚式が終わったからと言って、劇的に何かが変わるわけではなかった。結婚する前からすでに同棲していたし、2人ともそれぞれの仕事があった。僕らは子供が生まれる直前まで、それまでと変わらない生活を続けていた。
(第19話)
2037年12月20日、最初の子供が生まれた。初めての子供はかわいい女の子であったので、ひばりの喜び方はとてもすごかった。名前は二人であれこれ考えた結果、花月(かげつ)と名づけることとなった。ひばりが言うには、この子には月が何度でも満月を迎えるように、何度でも幸福に満たされるように。また、花のように何度でも人から愛されるように、という気持ちをこめて名付けた。
これを境にして僕らの生活は大きく変わった。ひばりは産休を取り、僕も会社の育児支援制度を利用して、育児に専念した。結婚よりも子供の方が生活に与える影響が大きい。
「次の子供は男の子がいいなぁ。息子とキャッチボールをしたり、サッカーの練習相手とかしてあげたいなぁ…父親として…」
僕は花月をあやしながら、そっとつぶやいた。子供が生まれてからまだ半年しか経ってないのに、もう次の子供のことを考えていた。隣の台所ではひばりが夕食を作っていた。
「そうねぇ。やっぱりあと一人ぐらいは欲しいよね。でも、せめて花月が五歳になるまではじっくりと育ててあげたいなぁ。私、年子の妹がいたから、親にほとんど甘えることができなかったのよね。物心がついたときからずっとお姉ちゃんだった。この子にはそんな思いをさせたくないのよ。」
ひばりは僕がボソッとつぶやいた言葉をひばりはしっかり聞いていたようだった。彼女は今、一年間の産休を取っているため、生後半年たった花月の育児に楽しく取り組んでいた。
「へぇ、そうなんだ。僕は一人っ子だったから、そう言った思いをしたことがないなぁ。むしろ、兄弟や姉妹がいるということにすごく憧れていたよ。母さんが女手一つで僕を育てないといけなかったから、一人でいることが多くてね…。そんなときは特に姉がいたらよかったのに…と思ったもん。」
また、僕も会社の育児支援制度を使って、毎日残業せずに家に帰ることができた。また、普段の休みとは別に月に二回は育児休暇を取ることが義務付けられていた。そのため、僕らは花月にたくさんの愛情を注いで上げることができた。二人で一緒に育児することで花月への愛情と関心をどんどん強めていくことが出来た。
「確かに私達は共働きだから、この子が一歳になれば、私は再び看護師として働き出すし、太郎だってかつての休みがほとんど取れない状態に戻る。そうすると、花月は保育園に預けないといけなくなる。でも、今、あなたの稼ぎだけで子供を二人も育てることはできないじゃない。そうなったら、子供にしわ寄せが行くんだよ。」
もう、彼女は作ったご飯をリビングにあるテーブルに並べ終わっていた。僕はテーブルに座りながら、考えていた。僕らの子供に対する価値観は全く異なっているが、どちらも子供を思うが故の発言である。それがわかっていたから、僕はひばりの考えを認めていたし、彼女も僕の考えを認めてくれたと思う。人というのは自分の経験を超えて物事を共感できないから、せめて言葉を使って少しでも相手のことを分かってあげられるようにと僕は心がけていた。
2037年12月20日、最初の子供が生まれた。初めての子供はかわいい女の子であったので、ひばりの喜び方はとてもすごかった。名前は二人であれこれ考えた結果、花月(かげつ)と名づけることとなった。ひばりが言うには、この子には月が何度でも満月を迎えるように、何度でも幸福に満たされるように。また、花のように何度でも人から愛されるように、という気持ちをこめて名付けた。
これを境にして僕らの生活は大きく変わった。ひばりは産休を取り、僕も会社の育児支援制度を利用して、育児に専念した。結婚よりも子供の方が生活に与える影響が大きい。
「次の子供は男の子がいいなぁ。息子とキャッチボールをしたり、サッカーの練習相手とかしてあげたいなぁ…父親として…」
僕は花月をあやしながら、そっとつぶやいた。子供が生まれてからまだ半年しか経ってないのに、もう次の子供のことを考えていた。隣の台所ではひばりが夕食を作っていた。
「そうねぇ。やっぱりあと一人ぐらいは欲しいよね。でも、せめて花月が五歳になるまではじっくりと育ててあげたいなぁ。私、年子の妹がいたから、親にほとんど甘えることができなかったのよね。物心がついたときからずっとお姉ちゃんだった。この子にはそんな思いをさせたくないのよ。」
ひばりは僕がボソッとつぶやいた言葉をひばりはしっかり聞いていたようだった。彼女は今、一年間の産休を取っているため、生後半年たった花月の育児に楽しく取り組んでいた。
「へぇ、そうなんだ。僕は一人っ子だったから、そう言った思いをしたことがないなぁ。むしろ、兄弟や姉妹がいるということにすごく憧れていたよ。母さんが女手一つで僕を育てないといけなかったから、一人でいることが多くてね…。そんなときは特に姉がいたらよかったのに…と思ったもん。」
また、僕も会社の育児支援制度を使って、毎日残業せずに家に帰ることができた。また、普段の休みとは別に月に二回は育児休暇を取ることが義務付けられていた。そのため、僕らは花月にたくさんの愛情を注いで上げることができた。二人で一緒に育児することで花月への愛情と関心をどんどん強めていくことが出来た。
「確かに私達は共働きだから、この子が一歳になれば、私は再び看護師として働き出すし、太郎だってかつての休みがほとんど取れない状態に戻る。そうすると、花月は保育園に預けないといけなくなる。でも、今、あなたの稼ぎだけで子供を二人も育てることはできないじゃない。そうなったら、子供にしわ寄せが行くんだよ。」
もう、彼女は作ったご飯をリビングにあるテーブルに並べ終わっていた。僕はテーブルに座りながら、考えていた。僕らの子供に対する価値観は全く異なっているが、どちらも子供を思うが故の発言である。それがわかっていたから、僕はひばりの考えを認めていたし、彼女も僕の考えを認めてくれたと思う。人というのは自分の経験を超えて物事を共感できないから、せめて言葉を使って少しでも相手のことを分かってあげられるようにと僕は心がけていた。
(第20話)
「今日の料理はすごく豪華だね」
3人の前には刺身やら肉やらケーキやらが乗っていた。そして、普段の食卓ではまずお目にかかれない上等のスパークリングワインが置いてあることがこの日が特別な日であることを示していた。
「そりゃそうよ。今日は2人にとって最初の記念日なんだから!」
2038年6月6日、初めての結婚記念日を僕らは迎えた。花月はまだ小さくて、まだ離乳食しか食べれないのに、ここにおいしいものが並んでいるがわかるのか、しれっと皿の上にある食べ物をつかんでは口の中に入れようとしていた。
「花月ちゃん、ダメでしょう。花月はまだ食べれないの」
それにダダをこねる花月。離乳食を全て食べさせようとスプーンですくって花月の口に持って行くひばり。それを僕はとてもほほえましく思った。
「はい、花月ちゃん、あーんして。はい、もぐもぐね。もぐもぐ…もぐもぐ…はい、ごっくんして。はい、よくできました。よしよし…。はい、もう一回、あーんして。……。」
ご飯を食べ終わってから、ひばりに変わって花月に離乳食を食べさせてみたが、この日もひばりみたいにうまくはいかなかった。ひひばりは自分のご飯を食べながら、僕らの様子をたえず見守っているようだった。このとき、ワインは1口も飲めなかった。
その後、ひばりは花月を風呂に入れて寝かしつけて、僕は皿を洗っていた。どちらも仕事を終えて、再びテーブルに着くことができたのはもう10時を過ぎていた。2人はワインをグラスに注ぎ、そっと乾杯をした。まず、お互いにプレゼントを用意していたので、それをそれぞれに渡した。それから、ご飯前の話の続きをした。様々なことを考えた結果、花月が3歳になるまでは次の子供を待つという結論になった。
今の世の中、子供を育てていくのはとても大変なことだった。僕は新聞社では社会部に属しているせいかその問題については詳しかった。21世紀に入ってからいろんな少子化対策がなされているというのに、未だに出生率が1.4から数値が上がらない。近いうち政府が新しい少子化対策を実施するらしいが、また同じことの繰り返しになると社説に書いてあった。
「今日の料理はすごく豪華だね」
3人の前には刺身やら肉やらケーキやらが乗っていた。そして、普段の食卓ではまずお目にかかれない上等のスパークリングワインが置いてあることがこの日が特別な日であることを示していた。
「そりゃそうよ。今日は2人にとって最初の記念日なんだから!」
2038年6月6日、初めての結婚記念日を僕らは迎えた。花月はまだ小さくて、まだ離乳食しか食べれないのに、ここにおいしいものが並んでいるがわかるのか、しれっと皿の上にある食べ物をつかんでは口の中に入れようとしていた。
「花月ちゃん、ダメでしょう。花月はまだ食べれないの」
それにダダをこねる花月。離乳食を全て食べさせようとスプーンですくって花月の口に持って行くひばり。それを僕はとてもほほえましく思った。
「はい、花月ちゃん、あーんして。はい、もぐもぐね。もぐもぐ…もぐもぐ…はい、ごっくんして。はい、よくできました。よしよし…。はい、もう一回、あーんして。……。」
ご飯を食べ終わってから、ひばりに変わって花月に離乳食を食べさせてみたが、この日もひばりみたいにうまくはいかなかった。ひひばりは自分のご飯を食べながら、僕らの様子をたえず見守っているようだった。このとき、ワインは1口も飲めなかった。
その後、ひばりは花月を風呂に入れて寝かしつけて、僕は皿を洗っていた。どちらも仕事を終えて、再びテーブルに着くことができたのはもう10時を過ぎていた。2人はワインをグラスに注ぎ、そっと乾杯をした。まず、お互いにプレゼントを用意していたので、それをそれぞれに渡した。それから、ご飯前の話の続きをした。様々なことを考えた結果、花月が3歳になるまでは次の子供を待つという結論になった。
今の世の中、子供を育てていくのはとても大変なことだった。僕は新聞社では社会部に属しているせいかその問題については詳しかった。21世紀に入ってからいろんな少子化対策がなされているというのに、未だに出生率が1.4から数値が上がらない。近いうち政府が新しい少子化対策を実施するらしいが、また同じことの繰り返しになると社説に書いてあった。
(第21話)
2040年4月8日、久万英雄の長男・英一の結婚式が山形で行われた。これは実にめでたいことであった。久万家ではいいことがずっと続いていた。長女・すみれは婚約の話がまとまって、秋に結婚することになっていたし、次女・奈美はこの春、法科大学院を卒業した。英雄は妻・彩と共にこのことを喜びながらも、子供が家から出て行くことを寂しがっていた。
結婚式が終わってから、久万は仙台で仕事があったので、もう一晩泊まっていくことにした。しかし、すみれと奈美は仕事があったため、その日のうちに綾と一緒に車で東京に帰った。
この日の夜、4月にしては珍しく雪が降っていた。雪は次第に激しさを増してきた。そして、時折吹雪いていた。久万は3人のことをしきりに心配していた。テレビをつけてみると関東でも雪が降っていて、積もる可能性があると言っていた。そうだとすると、3人はずっと雪の中帰らないといけないことになる。雪に慣れていないものにとって、雪の中を走り続けることはチェーンを巻いていても危険な行為である。彼は心配でたまらなかった。
翌日は朝早くから仕事があるので、早く寝ようとテレビを消そうとしたときであった。もうすぐ、日付が変わろうとしているときに「東北道で雪によるスリップ、30台ほどの玉突き事故」という臨時ニュースのテロップが流れた。彼はもしかしてと思ったが、そんなことをいちいち気にしていたら、心臓がいくつあっても足りないと思った。ふとんに入ったらあっという間に寝てしまった。
翌朝、起きてすぐにテレビをつけた。すると、信じられない光景が目に飛び込んできた。東北道・福島付近で起きた玉突き事故現場ではその中にあったタンクローリー車から漏れたガソリンに引火したため、ほとんどの車が燃えてようである。朝になって、ようやく火は消し止められたものの、黒焦げた固まりが30台ほどあった。なかには車の原型をほとんどとどめていないものもあった。まだ、事故に巻き込まれた人の安否はまったくわかっておらず、雪も依然として強く降り続いていた。
それは山形も同じであった。しかし、雪が強く降っているからといって、裁判が中止になることはない。久万はホテルを出て、タクシーで山形地裁に向かった。裁判はいかなることがあっても予定された日に必ず行われる。この日は児童虐待に関する刑事裁判であった。この裁判はどう考えても勝ち目がないと思った。それは親が何度も警察や児童相談所から注意を受けたにも関わらず、子供に対して虐待を加えていたからである。そこで裁判所はこの親に対して「親権剥奪命令」を出して、子供を保護しようとしたが、それに逆上して子供を殺してしまったのである。
それでも弁護士は弁護人として雇われた以上は、被告の無罪を勝ち取るためにいろいろと手を尽くす。しかし、今回のような事件だとどうやってもダメなことがわかっているので、やる気がいまいち起きない。むしろ、個人的には己の過ちに気付かせるために検察官と一緒になって重刑を要求したいぐらいだった。
たとえ、この人が重刑を言い渡されて、己の罪を償ったとしても、殺された子供は2度と帰ってこない。そんなことを考えるといくら生活のためといっても、弁護したくない人の弁護人になるのは気が進まなかった。久万はタクシーを降りて裁判所に入っていった。
2040年4月8日、久万英雄の長男・英一の結婚式が山形で行われた。これは実にめでたいことであった。久万家ではいいことがずっと続いていた。長女・すみれは婚約の話がまとまって、秋に結婚することになっていたし、次女・奈美はこの春、法科大学院を卒業した。英雄は妻・彩と共にこのことを喜びながらも、子供が家から出て行くことを寂しがっていた。
結婚式が終わってから、久万は仙台で仕事があったので、もう一晩泊まっていくことにした。しかし、すみれと奈美は仕事があったため、その日のうちに綾と一緒に車で東京に帰った。
この日の夜、4月にしては珍しく雪が降っていた。雪は次第に激しさを増してきた。そして、時折吹雪いていた。久万は3人のことをしきりに心配していた。テレビをつけてみると関東でも雪が降っていて、積もる可能性があると言っていた。そうだとすると、3人はずっと雪の中帰らないといけないことになる。雪に慣れていないものにとって、雪の中を走り続けることはチェーンを巻いていても危険な行為である。彼は心配でたまらなかった。
翌日は朝早くから仕事があるので、早く寝ようとテレビを消そうとしたときであった。もうすぐ、日付が変わろうとしているときに「東北道で雪によるスリップ、30台ほどの玉突き事故」という臨時ニュースのテロップが流れた。彼はもしかしてと思ったが、そんなことをいちいち気にしていたら、心臓がいくつあっても足りないと思った。ふとんに入ったらあっという間に寝てしまった。
翌朝、起きてすぐにテレビをつけた。すると、信じられない光景が目に飛び込んできた。東北道・福島付近で起きた玉突き事故現場ではその中にあったタンクローリー車から漏れたガソリンに引火したため、ほとんどの車が燃えてようである。朝になって、ようやく火は消し止められたものの、黒焦げた固まりが30台ほどあった。なかには車の原型をほとんどとどめていないものもあった。まだ、事故に巻き込まれた人の安否はまったくわかっておらず、雪も依然として強く降り続いていた。
それは山形も同じであった。しかし、雪が強く降っているからといって、裁判が中止になることはない。久万はホテルを出て、タクシーで山形地裁に向かった。裁判はいかなることがあっても予定された日に必ず行われる。この日は児童虐待に関する刑事裁判であった。この裁判はどう考えても勝ち目がないと思った。それは親が何度も警察や児童相談所から注意を受けたにも関わらず、子供に対して虐待を加えていたからである。そこで裁判所はこの親に対して「親権剥奪命令」を出して、子供を保護しようとしたが、それに逆上して子供を殺してしまったのである。
それでも弁護士は弁護人として雇われた以上は、被告の無罪を勝ち取るためにいろいろと手を尽くす。しかし、今回のような事件だとどうやってもダメなことがわかっているので、やる気がいまいち起きない。むしろ、個人的には己の過ちに気付かせるために検察官と一緒になって重刑を要求したいぐらいだった。
たとえ、この人が重刑を言い渡されて、己の罪を償ったとしても、殺された子供は2度と帰ってこない。そんなことを考えるといくら生活のためといっても、弁護したくない人の弁護人になるのは気が進まなかった。久万はタクシーを降りて裁判所に入っていった。
(第22話)
夕方、裁判が終ってから携帯を見ると、履歴に英一から着信がたくさん残っていた。久万は嫌な予感がした。携帯を持つ手が震えていた。それでも久万は英一に電話をかけた。
「あっ、もしもし、どうした? 何かあったのか?」
「やっと裁判が終わったのか…。さっき、テレビを見たら…母さんとすみれと奈美は、東京に帰る途中で事故にあって、大けがをしたって…。今からそっちに迎えに行くから、待ってて」
悪い予感は見事に的中してしまった。せめて、出発を1日遅らせることができれば、こんなことにはならなかったはずなのに…。今更、雪が止んでも意味がないと久万は思っていた。まん丸として、光っている月が憎らしく思えた。
車で福島に向かう途中、栄一は自分を責めていた。栄一は何も悪くないのに、自分の結婚式の帰りに家族が事故にあったことを責めていた。
「英一の結婚式に大雪が降ったことは偶然だったんだ。そんな偶然にまでおまえが責任を持つ必要はない。一度、予定が決まれば、雪が降ろうが、台風が来ようが、結婚式も裁判も仕事も予定通り行うしかないんだ。誰もこんな事故が起こることなんて予測できないんだから…」
久万は自分に言い聞かせるように英一をなぐさめるしかなかった。昨日の吹雪が嘘のように、きれいな月が出ていたのがうらめしかった。車はどんどん福島に近づいていた。
出発から2時間半ほどで、月明かりに照らされた事故現場に着いた。現場は福島と栃木の県境に近い白河付近であった。そこは事故からもう1日しか経っておらず、まだ黒焦げた車、焼けた鉄とガソリンの混じったにおいが事故の凄惨さを物語っていた。
それから、久万と英一は事故現場にいた警官に3人が運ばれた病院の場所を教えてもらい、病院に急行した。
病院には多くの人が運ばれているようで医者や看護師が忙しそうに走り回っていた。彼らは3人の名前を告げて、病室を案内してもらおうと思った。しかし、看護師は何も言わずに、立ち去った。しばらくして、医者が2人の下にやってきた。
「久万英雄さんと息子さんですよね」
「はい」
「こちらへ来てください…」
医者は2人を人気のない所へと連れて行った。久万と英一はお互いに顔を見合わせた。しかし、とても言葉を交わせるような雰囲気ではなかった。着いた先は霊安室であった。2人は最悪の結果を覚悟した。ドアを開けて入ると10体近くの遺体があった。その中に「久万すみれ」「久万奈美」と書いてある遺体があった。2人はそれを見て、ただ泣くことしかできなかった。
「大変申し訳ありません。手は尽くしましたが、すでに手遅れでした。本当に申し訳ありませんでした」
医者は深々と頭を下げていた。どんなに医者の腕がよかったとしても、治せるものと治せないものがある。それはとても悲しかった。だが、遺体が2体しかない。
「ここに妻がいないということは…妻は…久万彩は生きているということですよね」
医者は黙ってうなずき、今度は二人を集中治療室に連れて行った。二人は集中治療室には入れなかったけど、それでも廊下に面したガラス越しから彩の生存を確認できて、ほっとしていた。一人でも生きていてくれてありがとう…二人はそう思うことで、あまりにも残酷な現実と少しずつ向き合うしかなかった。
夕方、裁判が終ってから携帯を見ると、履歴に英一から着信がたくさん残っていた。久万は嫌な予感がした。携帯を持つ手が震えていた。それでも久万は英一に電話をかけた。
「あっ、もしもし、どうした? 何かあったのか?」
「やっと裁判が終わったのか…。さっき、テレビを見たら…母さんとすみれと奈美は、東京に帰る途中で事故にあって、大けがをしたって…。今からそっちに迎えに行くから、待ってて」
悪い予感は見事に的中してしまった。せめて、出発を1日遅らせることができれば、こんなことにはならなかったはずなのに…。今更、雪が止んでも意味がないと久万は思っていた。まん丸として、光っている月が憎らしく思えた。
車で福島に向かう途中、栄一は自分を責めていた。栄一は何も悪くないのに、自分の結婚式の帰りに家族が事故にあったことを責めていた。
「英一の結婚式に大雪が降ったことは偶然だったんだ。そんな偶然にまでおまえが責任を持つ必要はない。一度、予定が決まれば、雪が降ろうが、台風が来ようが、結婚式も裁判も仕事も予定通り行うしかないんだ。誰もこんな事故が起こることなんて予測できないんだから…」
久万は自分に言い聞かせるように英一をなぐさめるしかなかった。昨日の吹雪が嘘のように、きれいな月が出ていたのがうらめしかった。車はどんどん福島に近づいていた。
出発から2時間半ほどで、月明かりに照らされた事故現場に着いた。現場は福島と栃木の県境に近い白河付近であった。そこは事故からもう1日しか経っておらず、まだ黒焦げた車、焼けた鉄とガソリンの混じったにおいが事故の凄惨さを物語っていた。
それから、久万と英一は事故現場にいた警官に3人が運ばれた病院の場所を教えてもらい、病院に急行した。
病院には多くの人が運ばれているようで医者や看護師が忙しそうに走り回っていた。彼らは3人の名前を告げて、病室を案内してもらおうと思った。しかし、看護師は何も言わずに、立ち去った。しばらくして、医者が2人の下にやってきた。
「久万英雄さんと息子さんですよね」
「はい」
「こちらへ来てください…」
医者は2人を人気のない所へと連れて行った。久万と英一はお互いに顔を見合わせた。しかし、とても言葉を交わせるような雰囲気ではなかった。着いた先は霊安室であった。2人は最悪の結果を覚悟した。ドアを開けて入ると10体近くの遺体があった。その中に「久万すみれ」「久万奈美」と書いてある遺体があった。2人はそれを見て、ただ泣くことしかできなかった。
「大変申し訳ありません。手は尽くしましたが、すでに手遅れでした。本当に申し訳ありませんでした」
医者は深々と頭を下げていた。どんなに医者の腕がよかったとしても、治せるものと治せないものがある。それはとても悲しかった。だが、遺体が2体しかない。
「ここに妻がいないということは…妻は…久万彩は生きているということですよね」
医者は黙ってうなずき、今度は二人を集中治療室に連れて行った。二人は集中治療室には入れなかったけど、それでも廊下に面したガラス越しから彩の生存を確認できて、ほっとしていた。一人でも生きていてくれてありがとう…二人はそう思うことで、あまりにも残酷な現実と少しずつ向き合うしかなかった。
(第23話)
2041年4月9日、あの日から1年が経った。久万英一は思った。結婚記念日を迎えるたびに一緒に迎える2人の命日。栄一の妻・文(ふみ)は彼に優しく寄り添っていた。それを久万英雄と彩が優しく見守っていた。偶然とは言え、1年前、自分の結婚式の帰り、すみれと奈美は事故で帰らぬ人となった。それはとてもつらい。それは久万英雄も同じだった。
でも、綾が生きていてくれたからよかった。彼女は左足を切断したものの、現在はBS細胞から作った新しい足のおかげで元気に過ごしている。ようやく、記憶を取り戻してくれた。つい最近まで彼女は家族に関する記憶を全く思い出せずにいた。
事故後初めて久万と英一の2人が彩と再会したとき、彩が最初に出した言葉に2人は凍り付いた。
「あなた方は誰ですか? そして、私は誰ですか? わからないのです。教えてください」
このとき、彩が記憶喪失になっていることに2人は気付いた。それから、2人は彼女の記憶を取り戻すため、仕事の合間をぬっては病院に駆けつけた。久万は東京の家と事務所を売り払って、福島に移るほどであった。そして、彼女のことや自分のこと、家族のこと、どうして事故にあったのかとか、事故で2人が亡くなったことなどを丁寧に何回も何回も教えた。そうすることで、彩は少しずつ記憶を取り戻していった。
彩の記憶を取り戻させること…それが3人にとっての新しい生き甲斐であり、帰らぬ人となった2人の無念を晴らすものであった。
そのためであれば、21世紀初頭のねつ造事件によって、開発が遅れた上に未だに安全性がきちんと確認されていないBS細胞を使っても大して気にならなかった。久万も英一もそれでいいと思っていた。切断した左足が元に戻るなら…と彩も納得していた。
ただ、どうしてここに配偶子管理バンクが出てくるのかはよくわからなかった。話によれば、BS細胞を作るためには核を抜いた卵に、BS細胞を必要としている人の体細胞核を入れることが必要であり、その卵は配偶子管理バンクで保管されたものを利用しているとのことだった。
2041年4月9日、あの日から1年が経った。久万英一は思った。結婚記念日を迎えるたびに一緒に迎える2人の命日。栄一の妻・文(ふみ)は彼に優しく寄り添っていた。それを久万英雄と彩が優しく見守っていた。偶然とは言え、1年前、自分の結婚式の帰り、すみれと奈美は事故で帰らぬ人となった。それはとてもつらい。それは久万英雄も同じだった。
でも、綾が生きていてくれたからよかった。彼女は左足を切断したものの、現在はBS細胞から作った新しい足のおかげで元気に過ごしている。ようやく、記憶を取り戻してくれた。つい最近まで彼女は家族に関する記憶を全く思い出せずにいた。
事故後初めて久万と英一の2人が彩と再会したとき、彩が最初に出した言葉に2人は凍り付いた。
「あなた方は誰ですか? そして、私は誰ですか? わからないのです。教えてください」
このとき、彩が記憶喪失になっていることに2人は気付いた。それから、2人は彼女の記憶を取り戻すため、仕事の合間をぬっては病院に駆けつけた。久万は東京の家と事務所を売り払って、福島に移るほどであった。そして、彼女のことや自分のこと、家族のこと、どうして事故にあったのかとか、事故で2人が亡くなったことなどを丁寧に何回も何回も教えた。そうすることで、彩は少しずつ記憶を取り戻していった。
彩の記憶を取り戻させること…それが3人にとっての新しい生き甲斐であり、帰らぬ人となった2人の無念を晴らすものであった。
そのためであれば、21世紀初頭のねつ造事件によって、開発が遅れた上に未だに安全性がきちんと確認されていないBS細胞を使っても大して気にならなかった。久万も英一もそれでいいと思っていた。切断した左足が元に戻るなら…と彩も納得していた。
ただ、どうしてここに配偶子管理バンクが出てくるのかはよくわからなかった。話によれば、BS細胞を作るためには核を抜いた卵に、BS細胞を必要としている人の体細胞核を入れることが必要であり、その卵は配偶子管理バンクで保管されたものを利用しているとのことだった。
(第24話)
2041年10月27日、僕はすごいスクープを手に入れた。配偶子管理バンクで一定期間、利用されなかった精子や卵は本来、医療廃棄物として処理することが義務付けられている。ところが、それらは一切、廃棄処分されておらず、全て医療機関や研究機関に売り渡されていたことが発覚したのである。
本来、配偶子管理バンクは結婚せず子供を産もうとする女性に対して精子を提供することや、卵巣腫瘍などで自分の卵を使って子供が産めない女性に対して卵を提供することを目的に作られた施設である。そのため、ここで採取された配偶子はそれ以外の目的で利用することが法律で決められていた。そうすることで提供者の遺伝情報と、利用者の尊厳が守られるはずであった。
しかし、それが破られた今、医療機関や研究機関で遺伝情報を解析されることにより、遺伝情報が外部から漏れ、新たな差別が生まれる危険性があった。また、それがBS細胞やクローン人間の開発に使われる危険性があった。
僕はこのとき、過去の実績から遊軍記者として自由に取材をすることを許されていた。そこで社会部の編集会議において、このスクープとその背景・社会的影響を伝え、これを特集で大きく取り上げていくこと提案した。それは満場一致で受け入れられた。
このようなことを生み出した背景には、管理バンクが独立行政法人になり、独自採算で収益を上げないといけないことが背景にあった。2011年に少子化対策の切り札として国の管理下に置かれてから14年間は国立の施設であったが、2025年には独立行政法人化された。当時、管理バンクを利用した振り込め詐欺によって作られた悪いイメージによって利用者が大幅に減った。そのため、多額の赤字を生み出すようになったので、管理バンクは国から切り離された。それからしばらくは国からの補助金ももらえたが、2030年には完全に補助金が打ち切られてしまった。その頃から、少しでも収益を上げるため、医療機関や研究機関に精子や卵を転売するようになったと考えられる。
2041年10月27日、僕はすごいスクープを手に入れた。配偶子管理バンクで一定期間、利用されなかった精子や卵は本来、医療廃棄物として処理することが義務付けられている。ところが、それらは一切、廃棄処分されておらず、全て医療機関や研究機関に売り渡されていたことが発覚したのである。
本来、配偶子管理バンクは結婚せず子供を産もうとする女性に対して精子を提供することや、卵巣腫瘍などで自分の卵を使って子供が産めない女性に対して卵を提供することを目的に作られた施設である。そのため、ここで採取された配偶子はそれ以外の目的で利用することが法律で決められていた。そうすることで提供者の遺伝情報と、利用者の尊厳が守られるはずであった。
しかし、それが破られた今、医療機関や研究機関で遺伝情報を解析されることにより、遺伝情報が外部から漏れ、新たな差別が生まれる危険性があった。また、それがBS細胞やクローン人間の開発に使われる危険性があった。
僕はこのとき、過去の実績から遊軍記者として自由に取材をすることを許されていた。そこで社会部の編集会議において、このスクープとその背景・社会的影響を伝え、これを特集で大きく取り上げていくこと提案した。それは満場一致で受け入れられた。
このようなことを生み出した背景には、管理バンクが独立行政法人になり、独自採算で収益を上げないといけないことが背景にあった。2011年に少子化対策の切り札として国の管理下に置かれてから14年間は国立の施設であったが、2025年には独立行政法人化された。当時、管理バンクを利用した振り込め詐欺によって作られた悪いイメージによって利用者が大幅に減った。そのため、多額の赤字を生み出すようになったので、管理バンクは国から切り離された。それからしばらくは国からの補助金ももらえたが、2030年には完全に補助金が打ち切られてしまった。その頃から、少しでも収益を上げるため、医療機関や研究機関に精子や卵を転売するようになったと考えられる。
(第25話)
一方、医療機関や研究機関はそれを大いに歓迎した。21世紀初頭に韓国でBS細胞のデータを捏造したときに、研究員の女性から同意をえずに卵を取り出したことが大きな問題となった。それ以降、研究目的で人の精子や卵を使用する際には、第三者が作る倫理委員会と厚生労働省の許可を取ることや、提供者とその家族には必ず研究目的や使用理由を説明すること、提供者の健康に十分配慮することなどが義務付けられた。
これにより、日本では配偶子を研究機関などに提供する人が大きく減り、遺伝子技術の研究は停滞してしまった。それを補うために外国から配偶子を取り寄せることもなされたが、このような研究は誰からに発見されたら、もうその研究は意味がなさないような世界である。そのため、研究に必要な量を確保するには至らなかった。
そんな中での配偶子管理バンクで利用されていなかった精子や卵に目がつけられるようになった。そこで彼らは管理バンクが独立法人化されたことにより、経営がうまくいっていないことに目をつけた。ここに両者の利害は一致したのである。それから発覚するまでの10年間、管理バンクで使用されなかった精子や卵は高値で彼らに買い取られていったのである。彼らはあたかも外国からの取引量が増えたかのように偽装工作までしていた。
この事件には多くの弁護士も関与しているとされていた。そのリストを見たとき、僕は目を疑った。その中に久万英雄の名前があったからである。早速、真相を調べるための取材を始めた。
すると、彼は2040年4月8日に起きた白河玉突き事故で娘2人を亡くし、また、妻も左足を切断するような大ケガをしていた。そのときにBS細胞から妻の左足を再生するために配偶子管理バンクから人の卵を取り寄せたとされていた。そのほかにも弁護士の立場を利用して、このような手引きをいくつも行ったらしい。
一方、医療機関や研究機関はそれを大いに歓迎した。21世紀初頭に韓国でBS細胞のデータを捏造したときに、研究員の女性から同意をえずに卵を取り出したことが大きな問題となった。それ以降、研究目的で人の精子や卵を使用する際には、第三者が作る倫理委員会と厚生労働省の許可を取ることや、提供者とその家族には必ず研究目的や使用理由を説明すること、提供者の健康に十分配慮することなどが義務付けられた。
これにより、日本では配偶子を研究機関などに提供する人が大きく減り、遺伝子技術の研究は停滞してしまった。それを補うために外国から配偶子を取り寄せることもなされたが、このような研究は誰からに発見されたら、もうその研究は意味がなさないような世界である。そのため、研究に必要な量を確保するには至らなかった。
そんな中での配偶子管理バンクで利用されていなかった精子や卵に目がつけられるようになった。そこで彼らは管理バンクが独立法人化されたことにより、経営がうまくいっていないことに目をつけた。ここに両者の利害は一致したのである。それから発覚するまでの10年間、管理バンクで使用されなかった精子や卵は高値で彼らに買い取られていったのである。彼らはあたかも外国からの取引量が増えたかのように偽装工作までしていた。
この事件には多くの弁護士も関与しているとされていた。そのリストを見たとき、僕は目を疑った。その中に久万英雄の名前があったからである。早速、真相を調べるための取材を始めた。
すると、彼は2040年4月8日に起きた白河玉突き事故で娘2人を亡くし、また、妻も左足を切断するような大ケガをしていた。そのときにBS細胞から妻の左足を再生するために配偶子管理バンクから人の卵を取り寄せたとされていた。そのほかにも弁護士の立場を利用して、このような手引きをいくつも行ったらしい。
(第26話)
スクープ発見から一週間が経った。11月3日、朝一で僕は久万英雄がいる福島に着いた。早いもので、初めて彼と会った日から10年の月日が経っていた。しかし、彼はそれほど変わっていなかった。それでも、彼はすでに56歳になっていて、頭をよく見ると薄くなっているのがわかった。そこに10年の歳月が確実に流れていることを実感させられた。
もちろん、それだけではなかった。外の景色もまるで違った。以前は東京のごちゃごちゃした街中にあった事務所が、今はのどかな風景が広がる福島の郊外に移った。あのときは1月で雪が降っていたが、今回はまだ11月であったので、日差しがとても穏やかであった。
早速、僕は今まで調べた資料を元にして、彼に迫った。ところが彼は黙って僕の話を聞いているだけで、何も反論してこなかった。彼には弁護士としてのプライドはあるのだろうか…。一人でずっと話す僕と、ずっと黙り込んでいる久万…これは昼過ぎになっても何も変わらなかった。
「サリドマイド製剤の光と陰の話はご存じですか?」
僕はあっけに取られた。この日、久万が初めて話した言葉は、自分の疑惑を否定するでもなく、自分の疑惑を肯定するものでもなかったのだから…。
「知ってますよ。この薬によって、1960年代に日本を初め、世界各地で腕や足のない子供や耳が聞こえない子供がたくさん生まれました。ドイツやアメリカが早い段階でサリドマイド製剤の回収に踏み切ったのに対して、日本は『代わりの薬が見あたらない』として、製剤の回収が半年も遅れましたし、回収が不十分であったため、被害が大きく拡大しました。」
どうして、彼はこんなことを聞いてくるのだろうか? 自分の問題をごまかすためにわざとこんなことをしているのだろうか…。
「それはサリドマイド製剤の陰の部分ですね。光の部分は、あなたもご存じだと思いますが、この薬は多発性骨髄腫の特効薬であり、多発性骨髄腫の患者にとっては…なくてはならない薬です。」
そんなこと、医療関係の取材をする新聞記者であれば知らない者はいない。21世紀初頭からもう40年近くにわたって、サリドマイド製剤の被害者と多発性骨髄腫の患者は、サリドマイド製剤の保険適応再認可を巡って対立を続けてきた。被害者にとっていかなる理由があろうとも、自分たちの手足を奪った薬を薬として認めることはできなかった。また、骨のガンと呼ばれる多発性骨髄腫の患者にとって、サリドマイド製剤は取り扱いに細心の注意をしっかりすれば、これほどよく効く薬はない。事実、妊婦や出産を考えている夫婦以外であれば、この薬は何も問題を引き起こさないことが確認されている。
「すみません。このお話と今回の疑惑は何か関係があるのですか? ないのなら、今すぐ、本題に移ってください。私は明日の朝には福岡に帰らないといけないのです」
久万の顔が少しにやけたのを僕は見逃さなかった。
スクープ発見から一週間が経った。11月3日、朝一で僕は久万英雄がいる福島に着いた。早いもので、初めて彼と会った日から10年の月日が経っていた。しかし、彼はそれほど変わっていなかった。それでも、彼はすでに56歳になっていて、頭をよく見ると薄くなっているのがわかった。そこに10年の歳月が確実に流れていることを実感させられた。
もちろん、それだけではなかった。外の景色もまるで違った。以前は東京のごちゃごちゃした街中にあった事務所が、今はのどかな風景が広がる福島の郊外に移った。あのときは1月で雪が降っていたが、今回はまだ11月であったので、日差しがとても穏やかであった。
早速、僕は今まで調べた資料を元にして、彼に迫った。ところが彼は黙って僕の話を聞いているだけで、何も反論してこなかった。彼には弁護士としてのプライドはあるのだろうか…。一人でずっと話す僕と、ずっと黙り込んでいる久万…これは昼過ぎになっても何も変わらなかった。
「サリドマイド製剤の光と陰の話はご存じですか?」
僕はあっけに取られた。この日、久万が初めて話した言葉は、自分の疑惑を否定するでもなく、自分の疑惑を肯定するものでもなかったのだから…。
「知ってますよ。この薬によって、1960年代に日本を初め、世界各地で腕や足のない子供や耳が聞こえない子供がたくさん生まれました。ドイツやアメリカが早い段階でサリドマイド製剤の回収に踏み切ったのに対して、日本は『代わりの薬が見あたらない』として、製剤の回収が半年も遅れましたし、回収が不十分であったため、被害が大きく拡大しました。」
どうして、彼はこんなことを聞いてくるのだろうか? 自分の問題をごまかすためにわざとこんなことをしているのだろうか…。
「それはサリドマイド製剤の陰の部分ですね。光の部分は、あなたもご存じだと思いますが、この薬は多発性骨髄腫の特効薬であり、多発性骨髄腫の患者にとっては…なくてはならない薬です。」
そんなこと、医療関係の取材をする新聞記者であれば知らない者はいない。21世紀初頭からもう40年近くにわたって、サリドマイド製剤の被害者と多発性骨髄腫の患者は、サリドマイド製剤の保険適応再認可を巡って対立を続けてきた。被害者にとっていかなる理由があろうとも、自分たちの手足を奪った薬を薬として認めることはできなかった。また、骨のガンと呼ばれる多発性骨髄腫の患者にとって、サリドマイド製剤は取り扱いに細心の注意をしっかりすれば、これほどよく効く薬はない。事実、妊婦や出産を考えている夫婦以外であれば、この薬は何も問題を引き起こさないことが確認されている。
「すみません。このお話と今回の疑惑は何か関係があるのですか? ないのなら、今すぐ、本題に移ってください。私は明日の朝には福岡に帰らないといけないのです」
久万の顔が少しにやけたのを僕は見逃さなかった。
(第27話)
「大いに関係がありますよ。サリドマイド製剤は国がその安全性を認めていたからこそ、被害が大きく拡大しました。また、薬害エイズのときも、国が非加熱製剤は安全だと言っていました。その結果、多くの血友病患者がエイズにかかりました。薬害C型肝炎のときも、国はフィブリノーゲンを安全だと言っていました。その結果、多くの人がC型肝炎にかかりました。日本の医療行政は失敗ばかりなのに、どうして法律を守る必要があるんですか? そこに立派な技術があって、それを使うことで自分の愛する人の体が元通りになるのに、法律があるからと言って何もしない人がどこにいるんですか?」
確かに国は21世紀初頭まで、医療行政でたくさんの失策を犯してきた。その結果、多くの命が奪われ、多くの人の健康が奪われた。しかし、だからと言って、愛する人のために事故で失った左足を元通りにするために、法律で禁止されている配偶子管理バンクで保管されている卵を使ってBS細胞を利用して左足を元通りにすることが許されていいのだろうか?
「久万さん、あなたは間違っています。そんなことは許されるはずがないじゃないですか? 愛する人のためだったら、何をやっても許されるとでも思っているのですか…」
そこで久万が間髪入れずに話し出した。さっきまで黙り込んでいたのが嘘のように彼は話し続けた。
「確かにそうかもしれません。でも、そのことを海外でやっていたらどうなりますか? 何も問題ありませんよね…。それはかつての臓器移植でも同じでした。移植すれば助かるのに…法律が邪魔してそれができない。アメリカや西欧では移植が20世紀の頃から普通にできていました。だから、多くの人はみんなからお金をカンパしてもらって、アメリカなどで臓器移植をしてもらっていました。今でこそ日本でも普通に臓器移植ができますけど…」
確かにそうである。実際、日本で臓器提供が年齢に関係なくできるようになったのは2026年のことであった。20世紀末には15歳以上に限って移植が認められたが、子供の臓器移植は国内では長いこと認められていなかったため、21世紀に入ってからも多くの子供が海外で臓器移植を受けるしかなかった。彼は僕に反論の余地も与えることなく話し続けた。
「中にはお金を集めることができなくて、移植ができずに亡くなった人もいます。日本は昔から臓器移植ができるだけの高い技術があったのに、長いこと、それを使ってきませんでした。それは今回の遺伝子技術でも同じです。日本には世界に負けない高い技術があるのに…これでは宝の持ち腐れです。だから、前衛的な医者グループと弁護士が手を組んで法律を変えるためにいろいろとやってきたわけです」
「大いに関係がありますよ。サリドマイド製剤は国がその安全性を認めていたからこそ、被害が大きく拡大しました。また、薬害エイズのときも、国が非加熱製剤は安全だと言っていました。その結果、多くの血友病患者がエイズにかかりました。薬害C型肝炎のときも、国はフィブリノーゲンを安全だと言っていました。その結果、多くの人がC型肝炎にかかりました。日本の医療行政は失敗ばかりなのに、どうして法律を守る必要があるんですか? そこに立派な技術があって、それを使うことで自分の愛する人の体が元通りになるのに、法律があるからと言って何もしない人がどこにいるんですか?」
確かに国は21世紀初頭まで、医療行政でたくさんの失策を犯してきた。その結果、多くの命が奪われ、多くの人の健康が奪われた。しかし、だからと言って、愛する人のために事故で失った左足を元通りにするために、法律で禁止されている配偶子管理バンクで保管されている卵を使ってBS細胞を利用して左足を元通りにすることが許されていいのだろうか?
「久万さん、あなたは間違っています。そんなことは許されるはずがないじゃないですか? 愛する人のためだったら、何をやっても許されるとでも思っているのですか…」
そこで久万が間髪入れずに話し出した。さっきまで黙り込んでいたのが嘘のように彼は話し続けた。
「確かにそうかもしれません。でも、そのことを海外でやっていたらどうなりますか? 何も問題ありませんよね…。それはかつての臓器移植でも同じでした。移植すれば助かるのに…法律が邪魔してそれができない。アメリカや西欧では移植が20世紀の頃から普通にできていました。だから、多くの人はみんなからお金をカンパしてもらって、アメリカなどで臓器移植をしてもらっていました。今でこそ日本でも普通に臓器移植ができますけど…」
確かにそうである。実際、日本で臓器提供が年齢に関係なくできるようになったのは2026年のことであった。20世紀末には15歳以上に限って移植が認められたが、子供の臓器移植は国内では長いこと認められていなかったため、21世紀に入ってからも多くの子供が海外で臓器移植を受けるしかなかった。彼は僕に反論の余地も与えることなく話し続けた。
「中にはお金を集めることができなくて、移植ができずに亡くなった人もいます。日本は昔から臓器移植ができるだけの高い技術があったのに、長いこと、それを使ってきませんでした。それは今回の遺伝子技術でも同じです。日本には世界に負けない高い技術があるのに…これでは宝の持ち腐れです。だから、前衛的な医者グループと弁護士が手を組んで法律を変えるためにいろいろとやってきたわけです」
(第28話)
僕はあきれてしまった。法律を変えるためにはもっと周囲の賛同を得る方法があったはずである。それなのに現行の法律に納得がいかないからと言って法律で認められていない手術をすることは到底認められない。これでは1968年、日本初の心臓移植で起きた札幌和田事件と全く変わらない。法による根拠がないと、問題が起きたとき、手術の妥当性やその責任を大きく問われる。ここでも過去の教訓は生かされなかった。
「久万さん、そんなのタダの独りよがりですよ。多くの人がどう思っているかということに耳を傾けないとダメですよ。誰がなんと言おうとも私はこのことを新聞に書きますからね。それと、このことを警察と検察に告発します。残念ですが…仕方ありません」
彼のやろうとしていたことは方法さえ間違わなければ、いずれ世間から認められることであったかもしれない。彼ほどの人間がどうして、こんな簡単な過ちを犯してしまったのだろうか…。弁護士としての経験も十分積んでいる。現実と理想の折り合いのつけ方ぐらいわかっていたはずだ。
「何もわかっていませんね。あなた方、マスコミは第三者の視点から大衆受けのいいことを新聞やテレビで垂れ流していけばいいんですから…。当事者はそんな訳にはいかないんです。どんなにダメだと言われていても、愛する人の体が、ケガや病気をする前の体に戻る方法があれば、家族はそれにすがりつきますよ。それは使ってはダメだと誰に言われようと…。治る確率がわずかしかなくても…それにすがりつくしかないんです。その結果、全てを失うことになったとしても、やるでしょう…。理屈で人を助けることはできるなら、みんな法律や常識を守りますよ。でも、違うんです…」
彼の気持ちはわかる。確かに目の前に事故で左足を失った家族がいれば、どうにかしてそれを元通りしてあげたいと思うだろう。そして、その方法があれば、どんなに許されない方法であっても、それを実施するに違いない。目の前に臓器移植をしないと死ぬかもしれない子供がいれば、いかなる手を使っても臓器移植を受けさせてあげようとするのが、親心かもしれない。
しかし、世の中に当事者はわずかしかいなくて、大部分は第三者である以上、新聞記者として、第三者を無視するわけにはいけないのである。
「やっぱり、このことが公になる前に久万さん自らが警察に行くべきです。今から一緒に警察に行きましょう」
「どうして、悪いこともしてないのに警察に行かないといけないんですか? お願いだ。もう何も言わずに帰ってください」
僕は黙って会釈をして、彼の事務所を出た。そして、電車と飛行機を使って、夜遅く福岡に帰り着いた。
僕はあきれてしまった。法律を変えるためにはもっと周囲の賛同を得る方法があったはずである。それなのに現行の法律に納得がいかないからと言って法律で認められていない手術をすることは到底認められない。これでは1968年、日本初の心臓移植で起きた札幌和田事件と全く変わらない。法による根拠がないと、問題が起きたとき、手術の妥当性やその責任を大きく問われる。ここでも過去の教訓は生かされなかった。
「久万さん、そんなのタダの独りよがりですよ。多くの人がどう思っているかということに耳を傾けないとダメですよ。誰がなんと言おうとも私はこのことを新聞に書きますからね。それと、このことを警察と検察に告発します。残念ですが…仕方ありません」
彼のやろうとしていたことは方法さえ間違わなければ、いずれ世間から認められることであったかもしれない。彼ほどの人間がどうして、こんな簡単な過ちを犯してしまったのだろうか…。弁護士としての経験も十分積んでいる。現実と理想の折り合いのつけ方ぐらいわかっていたはずだ。
「何もわかっていませんね。あなた方、マスコミは第三者の視点から大衆受けのいいことを新聞やテレビで垂れ流していけばいいんですから…。当事者はそんな訳にはいかないんです。どんなにダメだと言われていても、愛する人の体が、ケガや病気をする前の体に戻る方法があれば、家族はそれにすがりつきますよ。それは使ってはダメだと誰に言われようと…。治る確率がわずかしかなくても…それにすがりつくしかないんです。その結果、全てを失うことになったとしても、やるでしょう…。理屈で人を助けることはできるなら、みんな法律や常識を守りますよ。でも、違うんです…」
彼の気持ちはわかる。確かに目の前に事故で左足を失った家族がいれば、どうにかしてそれを元通りしてあげたいと思うだろう。そして、その方法があれば、どんなに許されない方法であっても、それを実施するに違いない。目の前に臓器移植をしないと死ぬかもしれない子供がいれば、いかなる手を使っても臓器移植を受けさせてあげようとするのが、親心かもしれない。
しかし、世の中に当事者はわずかしかいなくて、大部分は第三者である以上、新聞記者として、第三者を無視するわけにはいけないのである。
「やっぱり、このことが公になる前に久万さん自らが警察に行くべきです。今から一緒に警察に行きましょう」
「どうして、悪いこともしてないのに警察に行かないといけないんですか? お願いだ。もう何も言わずに帰ってください」
僕は黙って会釈をして、彼の事務所を出た。そして、電車と飛行機を使って、夜遅く福岡に帰り着いた。
(第29話)
福島での取材から一ヶ月過ぎた12月5日、久万英雄とBS細胞を使って手術を行った医師・茨城克夫は多産促進法及び遺伝子技術使用倫理法違反で逮捕された。また、配偶子管理バンクで処分しないといけない卵を、研究機関などに横流しした疑いで、管理バンク所長・吉本寿太郎も逮捕された。
東京地検特捜部は今後も事件について詳しく調べた上で、事件に関係した人を全て逮捕する方針だとニュースで言っていた。このきっかけとなったのは、11月10日に我が九州日々新聞社が掲載したスクープであった。それから、事態を重く見た東京地検が動き出した。
一方でこの事件は人々に「医療とは一体何だ?」という問題を突きつけてきた。例えば、風邪にかかったときに病院に行くのは風邪を治すためであって、風邪を悪化させるためでない。
しかし、病院に行ったことで病気を悪化させることだってある。それはサリドマイド製剤事件、薬害エイズ、薬害肝炎などを見ればわかることである。そこまで極端な例を挙げなくても、すでに手遅れの末期ガン患者を医者は助けることができない。医者も人間である以上、限界がある。だから、人間はそれを補う形で医学を発達させてきた。しかし、限界の壁をどんどん遠くにやる作業をしているにすぎない。医者も医学も、けして万能にはなれない。
また、臓器移植や遺伝子技術などが発達したことにより、医学はより多くの人を救えるようになったのと同時に、新たな問題も抱えるようになった。それまでの医療は医者と患者の対話だけだったのに、その間に提供者が割って入ってくるようになった。医者は患者と提供者の板挟みに苦しむことになった。ときに
「臓器移植のために私の息子は殺された」
と言って、裁判になることが未だにある。もう、21世紀も半ばにさしかかったというのに…。
また、遺伝子技術や生殖技術の発達は、子供の産み方を大きく変えた。配偶子管理バンクで精子を購入さえすれば、女性は一人で子供を作ることができる。また、長いこと不妊に悩んでいた夫婦も、配偶子管理バンクで精子と卵を購入して、体外受精させたものを女性の体に入れてやれば、子供ができる。多くの人が喜んだ。
しかし、それと同じぐらいの人が悲しんだし、苦しんだ。僕だって、母の死の直前に聞いた話に大きなショックを受けた。どこの誰だかわからない人が自分の父親というのもショックだし、自分が機械のように作り出されたのがショックだった。地球に生命が生まれてから、ずっと続いていた子は親の遺伝形質を受け継ぐという大前提が根底から破壊された。
また、クローン技術は一卵性双生児以外で自分とまったく同じ遺伝子を持つものはいないという大原則をぶち壊した。BS細胞もクローン技術を応用したようなものであるから、問題が多い。
だとしたら、医学が発展したことで新たに人が幸せになっている一方で、医学が発展したことで新たに不幸を生み出しているのではないか? だったら、医学の発展が無条件に人を幸せにするわけではない…。それでも医学は発展していく。医学の発展に意味はあるのだろうか?
その疑問と向き合うために、僕は医学・医療の問題を様々な視点から考えるために文化部などと連携して長期にわたる特集を組むことにした。
「第3部 終了」
福島での取材から一ヶ月過ぎた12月5日、久万英雄とBS細胞を使って手術を行った医師・茨城克夫は多産促進法及び遺伝子技術使用倫理法違反で逮捕された。また、配偶子管理バンクで処分しないといけない卵を、研究機関などに横流しした疑いで、管理バンク所長・吉本寿太郎も逮捕された。
東京地検特捜部は今後も事件について詳しく調べた上で、事件に関係した人を全て逮捕する方針だとニュースで言っていた。このきっかけとなったのは、11月10日に我が九州日々新聞社が掲載したスクープであった。それから、事態を重く見た東京地検が動き出した。
一方でこの事件は人々に「医療とは一体何だ?」という問題を突きつけてきた。例えば、風邪にかかったときに病院に行くのは風邪を治すためであって、風邪を悪化させるためでない。
しかし、病院に行ったことで病気を悪化させることだってある。それはサリドマイド製剤事件、薬害エイズ、薬害肝炎などを見ればわかることである。そこまで極端な例を挙げなくても、すでに手遅れの末期ガン患者を医者は助けることができない。医者も人間である以上、限界がある。だから、人間はそれを補う形で医学を発達させてきた。しかし、限界の壁をどんどん遠くにやる作業をしているにすぎない。医者も医学も、けして万能にはなれない。
また、臓器移植や遺伝子技術などが発達したことにより、医学はより多くの人を救えるようになったのと同時に、新たな問題も抱えるようになった。それまでの医療は医者と患者の対話だけだったのに、その間に提供者が割って入ってくるようになった。医者は患者と提供者の板挟みに苦しむことになった。ときに
「臓器移植のために私の息子は殺された」
と言って、裁判になることが未だにある。もう、21世紀も半ばにさしかかったというのに…。
また、遺伝子技術や生殖技術の発達は、子供の産み方を大きく変えた。配偶子管理バンクで精子を購入さえすれば、女性は一人で子供を作ることができる。また、長いこと不妊に悩んでいた夫婦も、配偶子管理バンクで精子と卵を購入して、体外受精させたものを女性の体に入れてやれば、子供ができる。多くの人が喜んだ。
しかし、それと同じぐらいの人が悲しんだし、苦しんだ。僕だって、母の死の直前に聞いた話に大きなショックを受けた。どこの誰だかわからない人が自分の父親というのもショックだし、自分が機械のように作り出されたのがショックだった。地球に生命が生まれてから、ずっと続いていた子は親の遺伝形質を受け継ぐという大前提が根底から破壊された。
また、クローン技術は一卵性双生児以外で自分とまったく同じ遺伝子を持つものはいないという大原則をぶち壊した。BS細胞もクローン技術を応用したようなものであるから、問題が多い。
だとしたら、医学が発展したことで新たに人が幸せになっている一方で、医学が発展したことで新たに不幸を生み出しているのではないか? だったら、医学の発展が無条件に人を幸せにするわけではない…。それでも医学は発展していく。医学の発展に意味はあるのだろうか?
その疑問と向き合うために、僕は医学・医療の問題を様々な視点から考えるために文化部などと連携して長期にわたる特集を組むことにした。
「第3部 終了」
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
あまやま想のひねくれ者文学 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-