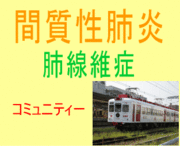|
|
|
|
コメント(5)
急性間質性肺炎(特発性間質性肺炎の急性型)
Acute Interstitial Pneumonia(AIP)
石坂彰敏 東京電力病院・臨床検査科科長(東京)
--------------------------------------------------
急性間質性肺炎(AIP)は1986年にKatzensteinらによって提唱された疾患概念であるが,従来はHamman‐Rich症候群と呼ばれていた.わが国では特発性間質性肺炎の急性型と同義語として用いられている.乾性咳嗽,発熱などの感冒様症状にひき続く労作時呼吸困難で発症し,胸部X線写真上びまん性の粒状・スリガラス状陰影を認める.数日程度で呼吸不全状態を呈する.
原因の有無を推定するために,詳細な病歴聴取(粉塵曝露歴・薬剤使用状況など)と肺感染症(クラミジア・マイコプラズマなど)の検索が重要である.死亡率60%以上と予後不良であるが,肺機能障害を残さない完全回復例も存在する.病理学的には種々の原因疾患(敗血症,重症外傷など)によって発症する,急性呼吸促迫症候群(ARDS)にみられるびまん性肺胞傷害(diffuse alveolar damage)に類似するが,硝子膜形成が軽いとされる.
◆治療方針
ステロイド薬,免疫抑制薬の効果は明らかではなく,ARDSと同様に急性呼吸不全に対する保存的な治療が中心となる.
A.呼吸管理
PaO2を70Torrに維持できるように酸素を投与する.挿管のうえ人工呼吸管理を余儀なくされる場合が多いが,近年挿管を要しないNIPPV(非侵襲的陽圧呼吸)が注目されている.10cmH2O程度の呼気終末陽圧呼吸(PEEP)は積極的に用いるが,心拍出量・血圧の低下に注意し,最大気道内圧は30cmH2O以下を維持する.低1回換気量(8ml/kg体重)で換気するが,このために生じるPaCO2の上昇は,pHが7.15以上に保てれば80Torrまでは許容される(permissive hypercapnea).ただし,頭蓋内占拠病変や致命的不整脈を有しないことが前提である.吸入気の酸素分圧(FIO2)はむやみに高くせず,できうる限り低く保つように努力する(0.6以下).
B.薬物療法
1.ステロイド単独もしくは免疫抑制薬との併用
処方例 下記のいずれかを用いる
1)パルス療法:ソル・メドロール⇒注 1g(生理食塩水⇒100mlに溶解)点滴投与(30‐60分)3日間
維持療法:プレドニゾロン⇒錠(5mg)12錠 分1 朝食後 連日 または
プレドニゾロン⇒錠(5mg)6‐12錠+エンドキサン⇒P錠(50mg)(保険適用外)1‐2錠 分1 朝食後 連日
パルス療法1クールで改善が認められた場合には維持療法を続け,プレドニゾロン⇒を2−4週間ごとに漸減する.1クールで無効な場合でもくり返しにより効果が現われることがある.
2)ソル・メドロール⇒注1g(生理食塩水⇒100mlに溶解)点滴投与+エンドキサン⇒注(保険適用外)200‐500mg(5%ブドウ糖⇒液500mlに溶解)ゆっくりと点滴投与 3日間
維持療法は上記と同じ
2.注意すべき副作用 上部消化管潰瘍,糖尿病,骨髄抑制,出血傾向,感染症.
3.その他の薬物療法 多臓器障害(上部消化管潰瘍,DIC,肝障害,腎障害)や二次感染を高頻度で認めるため,それらに対する薬物投与を行う.口腔内を清潔に保つことが二次感染予防上重要である.
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
Acute Interstitial Pneumonia(AIP)
石坂彰敏 東京電力病院・臨床検査科科長(東京)
--------------------------------------------------
急性間質性肺炎(AIP)は1986年にKatzensteinらによって提唱された疾患概念であるが,従来はHamman‐Rich症候群と呼ばれていた.わが国では特発性間質性肺炎の急性型と同義語として用いられている.乾性咳嗽,発熱などの感冒様症状にひき続く労作時呼吸困難で発症し,胸部X線写真上びまん性の粒状・スリガラス状陰影を認める.数日程度で呼吸不全状態を呈する.
原因の有無を推定するために,詳細な病歴聴取(粉塵曝露歴・薬剤使用状況など)と肺感染症(クラミジア・マイコプラズマなど)の検索が重要である.死亡率60%以上と予後不良であるが,肺機能障害を残さない完全回復例も存在する.病理学的には種々の原因疾患(敗血症,重症外傷など)によって発症する,急性呼吸促迫症候群(ARDS)にみられるびまん性肺胞傷害(diffuse alveolar damage)に類似するが,硝子膜形成が軽いとされる.
◆治療方針
ステロイド薬,免疫抑制薬の効果は明らかではなく,ARDSと同様に急性呼吸不全に対する保存的な治療が中心となる.
A.呼吸管理
PaO2を70Torrに維持できるように酸素を投与する.挿管のうえ人工呼吸管理を余儀なくされる場合が多いが,近年挿管を要しないNIPPV(非侵襲的陽圧呼吸)が注目されている.10cmH2O程度の呼気終末陽圧呼吸(PEEP)は積極的に用いるが,心拍出量・血圧の低下に注意し,最大気道内圧は30cmH2O以下を維持する.低1回換気量(8ml/kg体重)で換気するが,このために生じるPaCO2の上昇は,pHが7.15以上に保てれば80Torrまでは許容される(permissive hypercapnea).ただし,頭蓋内占拠病変や致命的不整脈を有しないことが前提である.吸入気の酸素分圧(FIO2)はむやみに高くせず,できうる限り低く保つように努力する(0.6以下).
B.薬物療法
1.ステロイド単独もしくは免疫抑制薬との併用
処方例 下記のいずれかを用いる
1)パルス療法:ソル・メドロール⇒注 1g(生理食塩水⇒100mlに溶解)点滴投与(30‐60分)3日間
維持療法:プレドニゾロン⇒錠(5mg)12錠 分1 朝食後 連日 または
プレドニゾロン⇒錠(5mg)6‐12錠+エンドキサン⇒P錠(50mg)(保険適用外)1‐2錠 分1 朝食後 連日
パルス療法1クールで改善が認められた場合には維持療法を続け,プレドニゾロン⇒を2−4週間ごとに漸減する.1クールで無効な場合でもくり返しにより効果が現われることがある.
2)ソル・メドロール⇒注1g(生理食塩水⇒100mlに溶解)点滴投与+エンドキサン⇒注(保険適用外)200‐500mg(5%ブドウ糖⇒液500mlに溶解)ゆっくりと点滴投与 3日間
維持療法は上記と同じ
2.注意すべき副作用 上部消化管潰瘍,糖尿病,骨髄抑制,出血傾向,感染症.
3.その他の薬物療法 多臓器障害(上部消化管潰瘍,DIC,肝障害,腎障害)や二次感染を高頻度で認めるため,それらに対する薬物投与を行う.口腔内を清潔に保つことが二次感染予防上重要である.
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
特発性肺線維症(特発性間質性肺炎の慢性型)
Idiopathic Pulmonary Fibrosis(IPF)
貫和敏博 東北大学加齢医学研究所教授・呼吸器腫瘍研究分野
--------------------------------------------------
本疾患名は肺線維症という多様な肺の線維化病態のうち,専門医の見解として,病理組織学的にusual interstitial pneumonia(UIP)像を示すものを指す.肺胞部の肺胞隔壁を場とする慢性炎症で,肺胞上皮脱落・肺胞虚脱による組織再構築が全肺野に斑状にみられ,臨床的には咳嗽,やがて労作時呼吸困難を自覚し,慢性呼吸不全となる.冬期呼吸器感染症を契機とする急性増悪(急性間質性肺炎病態)が多くは致命的となる.背景に重喫煙習慣がみられる例が多く,このような例は肺癌合併が死因となる.肺癌診断時に肺線維症を診断されることもまれでない.高齢男性に多く,呼吸器臨床症状出現後の5年生存率は約50%という予後不良の疾患で,厚生省特定疾患に指定されている(http://www.nanbyou.or.jp).特発性とは,膠原病合併性,薬剤性,職業性などを除外した原因不明のものを指す.
◆治療方針
A.診断確定と重要度把握
両側びまん性線状網状陰影で胸部CT写真で背側,下肺野中心の線維化である.アレルギー機序の炎症性疾患(ステロイド薬著効)や感染症との鑑別が必要であり,また動脈血酸素分圧(PaO2),肺機能検査,労作時酸素飽和度(SaO2)変化,血中指標(KL‐6,SP‐D:肺胞上皮由来のマーカー)などによる重症度把握のため,可能なら近隣の呼吸器専門医へ定期的に受診するよう紹介するのが望ましい.厚生省特定疾患として,安静時室内気吸入下PaO2<70Torrは医療費公費負担を申請しうる.
B.慢性・亜急性・急性増悪の3期の管理と治療方針
1.慢性安定期(ほとんど自覚症状なし)
(a)定期的な専門医受診.病態推移の把握:PaO2,KL‐6など.
(b)喫煙例は肺癌早期診断のための検査:細胞診,胸部CTは年1‐2回.
(c)この時期はステロイド薬は原則不投与:効果評価の臨床試験がなされていない.
(d)冬期感冒時は慎重に受診を指導.早期に経口抗生物質使用.
2.亜急性進展期(咳嗽,労作時呼吸困難出現)
(a)安静時室内気吸入下PaO2,労作時酸素飽和度低下を実測.それにより在宅酸素療法を開始.
(b)必要な場合,経口ステロイド薬使用開始.
処方例 下記のいずれかを用いる
1)プレドニゾロン⇒錠(5mg)2‐4錠 朝食後
外来での咳嗽などの自覚症状改善が目安.2週以上数か月間.
2)プレドニゾロン⇒錠(5mg)6‐8錠 朝食後など1ないし2回
プレドニゾロン⇒錠0.5mg/kgを目安に治療を始め,4週ごとに5‐10mgずつ減量.25mg前後からは症状をみながら隔日減量などの細かい工夫が必要.短期間に減量すると,再発悪化,致死の可能性もあるので専門医管理が望ましい.
3.急性増悪期(感染症など契機に急性間質性肺炎の病態になる)
ステロイドパルス療法
処方例
ソル・メドロール⇒注 0.5g 1日2回
生理食塩水⇒100mlに溶解して点滴投与 通常3日間
パルス終了後は以下の維持療法へ.呼吸器感染が併存することが多いので,抗生物質点滴,利尿なども管理する.もちろん必要な場合は酸素マスク,テントなど補助が必要.
プレドニゾロン⇒錠(5mg)8‐12錠 朝食後など1ないし2回
プレドニゾロン⇒錠1mg/kgを原則に.症状の推移を胸部CT,動脈血酸素分圧,CRP,LDHなどで追跡しながら,再パルスを考慮する場合もある.減量は10mg/月を目安にゆっくり.減量25mg前後は再増悪に十分注意が必要.
C.最近の治療法開発動向
1.肺移植 難治性・致死性疾患である肺線維症に対しては,欧米では肺移植がなされている.日本では脳死肺移植,生体肺移植が可能となったが,まだ肺のドナーは十分でない.
2.ステロイド薬以外の免疫抑制薬 日本では多数例における臨床試験がなされていないので,専門医にconsultationが必要.
処方例 下記のいずれかを用いる
1)エンドキサン⇒注 500‐750mg/m2 隔週 点滴静注
白血球2,000‐3,000/μl 以上を目安に増減(保険適用外)
2)サンディミュン⇒あるいはネオーラル⇒ 開始量3mg/kg/日(150‐200mg)
トラフ値100‐150μg/Lに調節
3.抗酸化薬 N‐acetylcysteine⇒(NAC)が以前より吸入薬として,慢性気管支炎の去痰薬であったが,軽症の肺線維症に対して,超音波ネブライザーによる吸入が試験されている.ヨーロッパでは経口薬の臨床試験が進行中である.
処方例
ムコフィリン⇒液(20%)1回2ml 1日2回 生理食塩水⇒10mlを加えて超音波ネブライザー
4.抗線維化薬
(a)従来,痛風治療薬であるコルヒチン⇒に,新たに増殖因子抑制作用が見出されたので,最近米国メイヨー・クリニックを中心に臨床試験がなされている.ステロイド減量に併用し,再燃防止効果も期待される.日本では保険適用外となる.
処方例
コルヒチン⇒錠(0.5mg)1回1錠 1日1ないし2回
(b)インターフェロンγ‐lb:最近,ヨーロッパより少数例の治療成績が報告された.作用機序に対する十分な理論がない.多数施設よりの報告を待つ必要がある.
(c)ピルフェニドン:米国において臨床試験が進行中.
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
Idiopathic Pulmonary Fibrosis(IPF)
貫和敏博 東北大学加齢医学研究所教授・呼吸器腫瘍研究分野
--------------------------------------------------
本疾患名は肺線維症という多様な肺の線維化病態のうち,専門医の見解として,病理組織学的にusual interstitial pneumonia(UIP)像を示すものを指す.肺胞部の肺胞隔壁を場とする慢性炎症で,肺胞上皮脱落・肺胞虚脱による組織再構築が全肺野に斑状にみられ,臨床的には咳嗽,やがて労作時呼吸困難を自覚し,慢性呼吸不全となる.冬期呼吸器感染症を契機とする急性増悪(急性間質性肺炎病態)が多くは致命的となる.背景に重喫煙習慣がみられる例が多く,このような例は肺癌合併が死因となる.肺癌診断時に肺線維症を診断されることもまれでない.高齢男性に多く,呼吸器臨床症状出現後の5年生存率は約50%という予後不良の疾患で,厚生省特定疾患に指定されている(http://www.nanbyou.or.jp).特発性とは,膠原病合併性,薬剤性,職業性などを除外した原因不明のものを指す.
◆治療方針
A.診断確定と重要度把握
両側びまん性線状網状陰影で胸部CT写真で背側,下肺野中心の線維化である.アレルギー機序の炎症性疾患(ステロイド薬著効)や感染症との鑑別が必要であり,また動脈血酸素分圧(PaO2),肺機能検査,労作時酸素飽和度(SaO2)変化,血中指標(KL‐6,SP‐D:肺胞上皮由来のマーカー)などによる重症度把握のため,可能なら近隣の呼吸器専門医へ定期的に受診するよう紹介するのが望ましい.厚生省特定疾患として,安静時室内気吸入下PaO2<70Torrは医療費公費負担を申請しうる.
B.慢性・亜急性・急性増悪の3期の管理と治療方針
1.慢性安定期(ほとんど自覚症状なし)
(a)定期的な専門医受診.病態推移の把握:PaO2,KL‐6など.
(b)喫煙例は肺癌早期診断のための検査:細胞診,胸部CTは年1‐2回.
(c)この時期はステロイド薬は原則不投与:効果評価の臨床試験がなされていない.
(d)冬期感冒時は慎重に受診を指導.早期に経口抗生物質使用.
2.亜急性進展期(咳嗽,労作時呼吸困難出現)
(a)安静時室内気吸入下PaO2,労作時酸素飽和度低下を実測.それにより在宅酸素療法を開始.
(b)必要な場合,経口ステロイド薬使用開始.
処方例 下記のいずれかを用いる
1)プレドニゾロン⇒錠(5mg)2‐4錠 朝食後
外来での咳嗽などの自覚症状改善が目安.2週以上数か月間.
2)プレドニゾロン⇒錠(5mg)6‐8錠 朝食後など1ないし2回
プレドニゾロン⇒錠0.5mg/kgを目安に治療を始め,4週ごとに5‐10mgずつ減量.25mg前後からは症状をみながら隔日減量などの細かい工夫が必要.短期間に減量すると,再発悪化,致死の可能性もあるので専門医管理が望ましい.
3.急性増悪期(感染症など契機に急性間質性肺炎の病態になる)
ステロイドパルス療法
処方例
ソル・メドロール⇒注 0.5g 1日2回
生理食塩水⇒100mlに溶解して点滴投与 通常3日間
パルス終了後は以下の維持療法へ.呼吸器感染が併存することが多いので,抗生物質点滴,利尿なども管理する.もちろん必要な場合は酸素マスク,テントなど補助が必要.
プレドニゾロン⇒錠(5mg)8‐12錠 朝食後など1ないし2回
プレドニゾロン⇒錠1mg/kgを原則に.症状の推移を胸部CT,動脈血酸素分圧,CRP,LDHなどで追跡しながら,再パルスを考慮する場合もある.減量は10mg/月を目安にゆっくり.減量25mg前後は再増悪に十分注意が必要.
C.最近の治療法開発動向
1.肺移植 難治性・致死性疾患である肺線維症に対しては,欧米では肺移植がなされている.日本では脳死肺移植,生体肺移植が可能となったが,まだ肺のドナーは十分でない.
2.ステロイド薬以外の免疫抑制薬 日本では多数例における臨床試験がなされていないので,専門医にconsultationが必要.
処方例 下記のいずれかを用いる
1)エンドキサン⇒注 500‐750mg/m2 隔週 点滴静注
白血球2,000‐3,000/μl 以上を目安に増減(保険適用外)
2)サンディミュン⇒あるいはネオーラル⇒ 開始量3mg/kg/日(150‐200mg)
トラフ値100‐150μg/Lに調節
3.抗酸化薬 N‐acetylcysteine⇒(NAC)が以前より吸入薬として,慢性気管支炎の去痰薬であったが,軽症の肺線維症に対して,超音波ネブライザーによる吸入が試験されている.ヨーロッパでは経口薬の臨床試験が進行中である.
処方例
ムコフィリン⇒液(20%)1回2ml 1日2回 生理食塩水⇒10mlを加えて超音波ネブライザー
4.抗線維化薬
(a)従来,痛風治療薬であるコルヒチン⇒に,新たに増殖因子抑制作用が見出されたので,最近米国メイヨー・クリニックを中心に臨床試験がなされている.ステロイド減量に併用し,再燃防止効果も期待される.日本では保険適用外となる.
処方例
コルヒチン⇒錠(0.5mg)1回1錠 1日1ないし2回
(b)インターフェロンγ‐lb:最近,ヨーロッパより少数例の治療成績が報告された.作用機序に対する十分な理論がない.多数施設よりの報告を待つ必要がある.
(c)ピルフェニドン:米国において臨床試験が進行中.
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
特発性間質性肺炎*〜**
Idiopathic Interstitial Pneumonia(IIP)
安藤正幸 熊本大学教授・第1内科
--------------------------------------------------
特発性間質性肺炎(IIP)は原因不明の間質性肺炎で,急性型と慢性型に分けられる.大半は慢性型で,緩徐に進行するが,しばしば急性増悪をきたして死に至る.慢性型は欧米の特発性肺線維症(idiopathic pulmonary fibrosis:IPF)と同意語である.急性型はHamman‐Rich症候群に相当し,欧米では急性間質性肺炎(AIP)として別の概念の疾患として取り扱われている.
診断のポイント
【1】緩徐に進行する労作時の息切れと乾性咳嗽を主症状とする.
【2】両側下肺野に吸気終末時に捻髪音(fine crackles,ベルクロラ音)を聴取する.進行例ではバチ指を認める.
【3】胸部X線写真にて両側びまん性に間質性陰影を認める.
【4】肺機能検査にて拘束性換気機能障害と拡散障害がみられ,低酸素血症を認める.
移送の判断基準
急性増悪時や末期に高度の呼吸不全を認める場合には,設備の整った医療機関へ移送する.
症候の診かた
坂道や階段の上昇などの労作に際し,息切れや乾性咳嗽を覚える場合には本症を疑う.聴診上,両側肺底部に吸気終末時に捻髪音を聴取すれば疑いはさらに強くなる.病期の進行したものでは頻呼吸,バチ指,チアノーゼがみられる.そのほか,全身倦怠感,発熱,寝汗,体重減少,関節痛を伴うことがある.しばしば病気の発症や増悪時に上気道炎症状が先行する.
検査とその所見の読みかた
【1】一般検査所見:赤沈値亢進,LDH上昇,γグロブリン上昇がみられる.RA,抗核抗体,免疫複合体がみられることがある.
【2】胸部単純X線写真:典型例では,粒状影,網状影が両側びまん性に,はじめ下肺に,やがて外側から上肺野へと分布し,肺は縮小する.横隔膜は挙上し,下肺野に蜂窩肺を認める.しかし,陰影の分布が不均等であったり,上中肺野に優位であったり,またブラbullaなどの気腫化を伴うなど非定型例もみられる.
【3】高分解能CT(HRCT):肥厚した小葉間隔壁,蜂窩肺,牽引性細気管支拡張,胸膜直下の線維化所見などがみられる.
【4】肺機能・動脈血ガス検査所見:肺活量(VC),全肺気量(TLC),残気量(RV)の減少,DLcoの低下,単位肺胞気量(VA)あたりの拡散能力(DLco/VA)の低下など,拘束性換気機能障害と拡散障害がみられる.Pao2は病期の進行とともに低下し,A‐aDO2の開大を認める.
【5】気管支肺胞洗浄回収液(BALF)所見:肺胞マクロファージの増加が認められる.リンパ球の増加は通常みられない.多核白血球や好酸球の増加は病勢の悪化時や進行した症例にみられる.
【6】血清中のサーファクタントプロテインA(SP‐A),ムチン成分であるKL‐6,単球遊走因子(MCP‐1)などが,活動性に一致して,高値を示す.
確定診断のポイント
臨床症候,検査所見に加えて,病理組織学的にUIP(usual interstitial pneumonia)の所見が得られれば確定診断できる.病理診断のためには胸腔鏡下肺生検もしくは開胸肺生検が必要である.わが国では厚生省特定疾患「びまん性肺疾患」調査研究班により診断基準が作成されている(表1[表]).
鑑別すべき疾患と鑑別のポイント
【1】膠原病性間質性肺炎⇒
?各種自己抗体が陽性である.
?膠原病に特有な身体所見がみられる.
【2】慢性過敏性肺炎⇒
?発症は生活環境(居住や職場)と関連がある.
?血清中に原因抗原に対する特異抗体が検出される.
?BALFリンパ球の著増がみられる.
【3】サルコイドーシス⇒
?両側肺門リンパ節腫大.
?血清ACEが高値を示す.
?眼・皮膚・筋肉・神経・心臓など他臓器に病変を認める.
【4】薬剤性間質性肺炎⇒
?発症は薬剤使用と関連がある.
?薬剤中止により改善することが多い.
【5】じん肺⇒
?職歴と関連性がある.
【6】BOOP⇒
?HRCTにて浸潤影を認める.
?BALFリンパ球の増加がみられる.
予後判定の基準
平均生存年数は初発症状から4〜6年である.高齢,呼吸困難Hugh‐Johnes3度以上,胸部X線像上病変の広範な広がり,%VC減少,%DLco減少,Pao2 60Torr以下,ステロイド無効,肺性心,肺癌合併の症例は予後が悪い.
重症度分類(厚生省特定疾患「びまん性肺疾患」調査研究班,1996年)を以下に示す.
?度:Pao2 80Torr以上
?度:Pao2 70〜79Torr
?度:Pao2 60〜69Torr
?度:Pao2 59Torr以下
合併症・続発症の診断
心不全,呼吸器感染症,肺癌,気胸が主なものである.心不全は右心室肥大,肺性心が原因となる.呼吸器感染症はステロイドや免疫抑制剤の使用時に増加する.肺癌は本症の19.2%にみられ明らかに多い.本症に合併した気胸は再膨張しにくく,治療が困難なことが多い.
治療法ワンポイント・メモ
慢性に緩徐に進行する場合には無治療で経過をみる.明らかな進行をみる場合にはステロイド剤が用いられるが,あまり有効ではない.急性増悪時にパルス療法が行われるが,効果がないことが多い.ステロイドが無効な場合には免疫抑制剤も使用される.
生活管理,ことにかぜをひかないように感染対策を講じることが大切である.その他,心不全対策,在宅酸素療法(HOT)などが行われる.
欧米では,症例によっては,肺移植が行われる.
さらに知っておくと役立つこと
【1】頻度は人口10万対3程度.40〜60歳の発症が多く,男女比は1.5:1ないし2:1で男性に多い.
【2】重症度?度以上の症例は厚生省特定疾患治療研究対象患者として治療費の公費負担が行われている.
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
Idiopathic Interstitial Pneumonia(IIP)
安藤正幸 熊本大学教授・第1内科
--------------------------------------------------
特発性間質性肺炎(IIP)は原因不明の間質性肺炎で,急性型と慢性型に分けられる.大半は慢性型で,緩徐に進行するが,しばしば急性増悪をきたして死に至る.慢性型は欧米の特発性肺線維症(idiopathic pulmonary fibrosis:IPF)と同意語である.急性型はHamman‐Rich症候群に相当し,欧米では急性間質性肺炎(AIP)として別の概念の疾患として取り扱われている.
診断のポイント
【1】緩徐に進行する労作時の息切れと乾性咳嗽を主症状とする.
【2】両側下肺野に吸気終末時に捻髪音(fine crackles,ベルクロラ音)を聴取する.進行例ではバチ指を認める.
【3】胸部X線写真にて両側びまん性に間質性陰影を認める.
【4】肺機能検査にて拘束性換気機能障害と拡散障害がみられ,低酸素血症を認める.
移送の判断基準
急性増悪時や末期に高度の呼吸不全を認める場合には,設備の整った医療機関へ移送する.
症候の診かた
坂道や階段の上昇などの労作に際し,息切れや乾性咳嗽を覚える場合には本症を疑う.聴診上,両側肺底部に吸気終末時に捻髪音を聴取すれば疑いはさらに強くなる.病期の進行したものでは頻呼吸,バチ指,チアノーゼがみられる.そのほか,全身倦怠感,発熱,寝汗,体重減少,関節痛を伴うことがある.しばしば病気の発症や増悪時に上気道炎症状が先行する.
検査とその所見の読みかた
【1】一般検査所見:赤沈値亢進,LDH上昇,γグロブリン上昇がみられる.RA,抗核抗体,免疫複合体がみられることがある.
【2】胸部単純X線写真:典型例では,粒状影,網状影が両側びまん性に,はじめ下肺に,やがて外側から上肺野へと分布し,肺は縮小する.横隔膜は挙上し,下肺野に蜂窩肺を認める.しかし,陰影の分布が不均等であったり,上中肺野に優位であったり,またブラbullaなどの気腫化を伴うなど非定型例もみられる.
【3】高分解能CT(HRCT):肥厚した小葉間隔壁,蜂窩肺,牽引性細気管支拡張,胸膜直下の線維化所見などがみられる.
【4】肺機能・動脈血ガス検査所見:肺活量(VC),全肺気量(TLC),残気量(RV)の減少,DLcoの低下,単位肺胞気量(VA)あたりの拡散能力(DLco/VA)の低下など,拘束性換気機能障害と拡散障害がみられる.Pao2は病期の進行とともに低下し,A‐aDO2の開大を認める.
【5】気管支肺胞洗浄回収液(BALF)所見:肺胞マクロファージの増加が認められる.リンパ球の増加は通常みられない.多核白血球や好酸球の増加は病勢の悪化時や進行した症例にみられる.
【6】血清中のサーファクタントプロテインA(SP‐A),ムチン成分であるKL‐6,単球遊走因子(MCP‐1)などが,活動性に一致して,高値を示す.
確定診断のポイント
臨床症候,検査所見に加えて,病理組織学的にUIP(usual interstitial pneumonia)の所見が得られれば確定診断できる.病理診断のためには胸腔鏡下肺生検もしくは開胸肺生検が必要である.わが国では厚生省特定疾患「びまん性肺疾患」調査研究班により診断基準が作成されている(表1[表]).
鑑別すべき疾患と鑑別のポイント
【1】膠原病性間質性肺炎⇒
?各種自己抗体が陽性である.
?膠原病に特有な身体所見がみられる.
【2】慢性過敏性肺炎⇒
?発症は生活環境(居住や職場)と関連がある.
?血清中に原因抗原に対する特異抗体が検出される.
?BALFリンパ球の著増がみられる.
【3】サルコイドーシス⇒
?両側肺門リンパ節腫大.
?血清ACEが高値を示す.
?眼・皮膚・筋肉・神経・心臓など他臓器に病変を認める.
【4】薬剤性間質性肺炎⇒
?発症は薬剤使用と関連がある.
?薬剤中止により改善することが多い.
【5】じん肺⇒
?職歴と関連性がある.
【6】BOOP⇒
?HRCTにて浸潤影を認める.
?BALFリンパ球の増加がみられる.
予後判定の基準
平均生存年数は初発症状から4〜6年である.高齢,呼吸困難Hugh‐Johnes3度以上,胸部X線像上病変の広範な広がり,%VC減少,%DLco減少,Pao2 60Torr以下,ステロイド無効,肺性心,肺癌合併の症例は予後が悪い.
重症度分類(厚生省特定疾患「びまん性肺疾患」調査研究班,1996年)を以下に示す.
?度:Pao2 80Torr以上
?度:Pao2 70〜79Torr
?度:Pao2 60〜69Torr
?度:Pao2 59Torr以下
合併症・続発症の診断
心不全,呼吸器感染症,肺癌,気胸が主なものである.心不全は右心室肥大,肺性心が原因となる.呼吸器感染症はステロイドや免疫抑制剤の使用時に増加する.肺癌は本症の19.2%にみられ明らかに多い.本症に合併した気胸は再膨張しにくく,治療が困難なことが多い.
治療法ワンポイント・メモ
慢性に緩徐に進行する場合には無治療で経過をみる.明らかな進行をみる場合にはステロイド剤が用いられるが,あまり有効ではない.急性増悪時にパルス療法が行われるが,効果がないことが多い.ステロイドが無効な場合には免疫抑制剤も使用される.
生活管理,ことにかぜをひかないように感染対策を講じることが大切である.その他,心不全対策,在宅酸素療法(HOT)などが行われる.
欧米では,症例によっては,肺移植が行われる.
さらに知っておくと役立つこと
【1】頻度は人口10万対3程度.40〜60歳の発症が多く,男女比は1.5:1ないし2:1で男性に多い.
【2】重症度?度以上の症例は厚生省特定疾患治療研究対象患者として治療費の公費負担が行われている.
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
特発性間質性肺炎(IIP)
森川 哲行 横浜労災病院・呼吸器科
--------------------------------------------------
病態
肺胞領域における胞隔炎に始まり,肺胞領域から末梢気道の構築の乱れをきたし最終的に肺の線維化と嚢胞形成に至る原因不明の疾患
異常値
・胸部X線 下肺野を中心とするびまん性粒状網状陰影.進行した場合蜂巣状陰影,横隔膜挙上などを呈する
・胸部CT スリガラス陰影,胸膜直下に分布する粒状網状陰影,進行するに従い蜂巣状陰影
・肺機能検査,血液ガス 拘束性換気障害,拡散能低下,低酸素血症,A-aDO2の開大
・血液検査 赤沈亢進,CRP上昇,LDH上昇,KL-6上昇,時にCA19-9上昇
経過観察のための検査項目とその測定頻度
●胸部X線 [急性期]急性(増悪)期には連日〜隔日ごとに撮影.回復に従い撮影間隔をあける [安定期]経過観察のため2〜3カ月ごとに撮影
●血液ガス [急性期]人工呼吸管理を含めた酸素療法が必要となり連日〜隔日ごとに測定 [安定期]経過観察のため2〜3カ月ごとに測定
●胸部CT [急性期]病状を把握するためなるべく早い時期に撮影 [安定期]1年に1回撮影
●血液検査 [急性期]白血球数,CRP,LDHなどを週に1〜2回以上測定 [安定期]1年に1〜2回測定
診断・経過観察上のポイント
?薬剤性肺臓炎,過敏性肺臓炎,膠原病肺,塵肺,放射線肺臓炎など他に間質性肺炎をきたしうる疾患を除外する必要がある.
?肺癌を合併するリスクが高いため,喀痰細胞診などの検査を定期的に行う.
?上気道炎,気管支鏡検査などを契機に急性増悪をきたす場合があるので注意を要する.
(森川 哲行)
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
森川 哲行 横浜労災病院・呼吸器科
--------------------------------------------------
病態
肺胞領域における胞隔炎に始まり,肺胞領域から末梢気道の構築の乱れをきたし最終的に肺の線維化と嚢胞形成に至る原因不明の疾患
異常値
・胸部X線 下肺野を中心とするびまん性粒状網状陰影.進行した場合蜂巣状陰影,横隔膜挙上などを呈する
・胸部CT スリガラス陰影,胸膜直下に分布する粒状網状陰影,進行するに従い蜂巣状陰影
・肺機能検査,血液ガス 拘束性換気障害,拡散能低下,低酸素血症,A-aDO2の開大
・血液検査 赤沈亢進,CRP上昇,LDH上昇,KL-6上昇,時にCA19-9上昇
経過観察のための検査項目とその測定頻度
●胸部X線 [急性期]急性(増悪)期には連日〜隔日ごとに撮影.回復に従い撮影間隔をあける [安定期]経過観察のため2〜3カ月ごとに撮影
●血液ガス [急性期]人工呼吸管理を含めた酸素療法が必要となり連日〜隔日ごとに測定 [安定期]経過観察のため2〜3カ月ごとに測定
●胸部CT [急性期]病状を把握するためなるべく早い時期に撮影 [安定期]1年に1回撮影
●血液検査 [急性期]白血球数,CRP,LDHなどを週に1〜2回以上測定 [安定期]1年に1〜2回測定
診断・経過観察上のポイント
?薬剤性肺臓炎,過敏性肺臓炎,膠原病肺,塵肺,放射線肺臓炎など他に間質性肺炎をきたしうる疾患を除外する必要がある.
?肺癌を合併するリスクが高いため,喀痰細胞診などの検査を定期的に行う.
?上気道炎,気管支鏡検査などを契機に急性増悪をきたす場合があるので注意を要する.
(森川 哲行)
今日の診療Vol.11 (C)2001 IGAKU-SHOIN Tokyo
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
間質性肺炎・肺線維症 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
間質性肺炎・肺線維症のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90024人
- 2位
- 酒好き
- 170668人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人