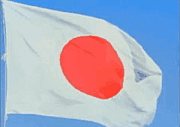はじめまして。太平洋戦争については昔から興味があり、色々と書籍を読んでおります。太平洋戦争を無謀としている本も多いですが、必敗と断定している本はあまり多くありません。
実は日本の兵力、国力は強大であり、戦略次第では引き分けは可能だったと思われます。もちろんアメリカの兵力、国力もすさまじいですが、日本のものも一般に言われている程は脆弱でなく、海軍の自滅作戦の展開さえなければアメリカもかなり苦戦を強いられたことでしょう。
また、日本は戦略なしに戦争を開始したわけではなく、戦略を立てていたのですが、海軍の真珠湾攻撃により大規模な戦略転換を余儀なくされた事実があります。この作戦は陸軍にはほとんど知らされていませんでした。
敗因は官僚統治機構、陸海軍の統帥権独立、海軍の隠ぺい体質、科学技術軽視など現在の日本と同じような弊害によるものだと思われます。これらの問題を抱えたまま戦争を行えばたとえ日米の立場が逆だったとしても、大勝利は難しかったでしょう。
私たちは戦争を防ぐことの可否を検証するよりも、敗因を検証し、今の日本の弊害を除去することが必要だと思います。過去の戦争を全て無謀とし、思考を停止してしまうことは進歩になりません。我々がそこから何かを学び、同じことを繰り返さないことが何よりも戦争の犠牲者たちへの供養になると思います。
以上、新参者のくせに生意気を言って申し訳ございませんでしたが、よろしくお願いいたします。
実は日本の兵力、国力は強大であり、戦略次第では引き分けは可能だったと思われます。もちろんアメリカの兵力、国力もすさまじいですが、日本のものも一般に言われている程は脆弱でなく、海軍の自滅作戦の展開さえなければアメリカもかなり苦戦を強いられたことでしょう。
また、日本は戦略なしに戦争を開始したわけではなく、戦略を立てていたのですが、海軍の真珠湾攻撃により大規模な戦略転換を余儀なくされた事実があります。この作戦は陸軍にはほとんど知らされていませんでした。
敗因は官僚統治機構、陸海軍の統帥権独立、海軍の隠ぺい体質、科学技術軽視など現在の日本と同じような弊害によるものだと思われます。これらの問題を抱えたまま戦争を行えばたとえ日米の立場が逆だったとしても、大勝利は難しかったでしょう。
私たちは戦争を防ぐことの可否を検証するよりも、敗因を検証し、今の日本の弊害を除去することが必要だと思います。過去の戦争を全て無謀とし、思考を停止してしまうことは進歩になりません。我々がそこから何かを学び、同じことを繰り返さないことが何よりも戦争の犠牲者たちへの供養になると思います。
以上、新参者のくせに生意気を言って申し訳ございませんでしたが、よろしくお願いいたします。
|
|
|
|
コメント(93)
陸軍と海軍が別々の志向をしている限り、太平洋戦争は途中で挫折すると思います。
陸海軍が別々の統帥権を持つことは予算などに関する利権を常に軍部の中で争っていることになります。例えば陸上攻撃機と艦載用の戦闘機は別々の場所で別々に生産されました。そのため陸海軍の航空機の仕様が違うので、それ自体で大量生産できないので物量が劣り。また陸海軍の立体作戦にも支障が出たりしました。島の基地から陸攻をとばしたりしても航続範囲は微々たるものでしたし。
陸海軍で航空機等の設計基準を統一し、生産体制もネジ1本から規格化すれば、生産体制の劣後と航空作戦上の支障を減らせると思います。また小さい経済の中での予算の奪い合いは結構戦況に響いたと思いますし。
南方資源作戦についてはそれ自体は日本の生存をかけた進出だと思いますが、大艦巨砲主義の影響で輸送船やタンカーはあまり優先して作られなかったことと、海軍が護衛艦隊の重要性を認識していなかったので護衛艦隊が組まれるのが遅れて、また護衛艦隊はなけなしの戦力をやりくりして作られていったので、結果として敵の潜水艦や艦隊、航空機にことごとく輸送船団は沈められてしまい、結果としては意味がなかったと言えると思います。
陸海軍が別々の統帥権を持つことは予算などに関する利権を常に軍部の中で争っていることになります。例えば陸上攻撃機と艦載用の戦闘機は別々の場所で別々に生産されました。そのため陸海軍の航空機の仕様が違うので、それ自体で大量生産できないので物量が劣り。また陸海軍の立体作戦にも支障が出たりしました。島の基地から陸攻をとばしたりしても航続範囲は微々たるものでしたし。
陸海軍で航空機等の設計基準を統一し、生産体制もネジ1本から規格化すれば、生産体制の劣後と航空作戦上の支障を減らせると思います。また小さい経済の中での予算の奪い合いは結構戦況に響いたと思いますし。
南方資源作戦についてはそれ自体は日本の生存をかけた進出だと思いますが、大艦巨砲主義の影響で輸送船やタンカーはあまり優先して作られなかったことと、海軍が護衛艦隊の重要性を認識していなかったので護衛艦隊が組まれるのが遅れて、また護衛艦隊はなけなしの戦力をやりくりして作られていったので、結果として敵の潜水艦や艦隊、航空機にことごとく輸送船団は沈められてしまい、結果としては意味がなかったと言えると思います。
確かに戦争理論としては大艦巨砲主義はあながち間違ってはいないと思います。戦力の高さは戦艦や空母の戦力に直接起因しますし。ただ、経営学の視点から見ると、いかんせん資源が足りないのに無理して背伸びをし過ぎていると言えると思います。大艦巨砲主義それ自体を維持するためにも、輸送や護衛艦隊の整備など資源管理を適切に行う必要がありますし。
物量不足で絶対的に力が足りないといえば、それまでなんですけどね。
大東亜共栄圏の提唱や満洲国の成立が日本の軍事思想を物語っていますよね。しかし米英の利権と次第に対立するようになり、中国も今度は頑強な抵抗を見せるようになっていきました。やはり各国同士の利権の対立、トレードオフの罠にまんまとはまっていってしまったような気がします。
物量不足で絶対的に力が足りないといえば、それまでなんですけどね。
大東亜共栄圏の提唱や満洲国の成立が日本の軍事思想を物語っていますよね。しかし米英の利権と次第に対立するようになり、中国も今度は頑強な抵抗を見せるようになっていきました。やはり各国同士の利権の対立、トレードオフの罠にまんまとはまっていってしまったような気がします。
バクチの好きな山本五十六だったので日本を勝利に導く為には漸減作戦では長期消耗戦に引き込まれていずれジリ貧になるので、短期で一気に片付ける攻勢一辺倒の大博打に賭けたんだと思います。作戦は防御よりも攻勢の方がイニシアティブを取りやすいですから。しかし攻勢攻撃があらかじめ暗号解読、レーダーで把握されれば攻勢有利の戦略は逆に待ち受けに合い、恰好の餌食となります。山本としてもそれは想像外だったでしょう。日本海軍お得意の奇襲、夜襲はレーダーと情報解析で逆に作用し日本に勝機はなくなったどころかわざわざ殺られに行くようなもので、、、
テクノロジー戦で負けたと言えばそれまでですが海軍それ自体、テクノロジーの固まりみたいなものなので、やはり航空エンジンや軍艦の動力タービンをようやくギリギリ国産化出来るぐらいの工業レベルではまだまだ対米戦は早すぎたと思います。
テクノロジー戦で負けたと言えばそれまでですが海軍それ自体、テクノロジーの固まりみたいなものなので、やはり航空エンジンや軍艦の動力タービンをようやくギリギリ国産化出来るぐらいの工業レベルではまだまだ対米戦は早すぎたと思います。
アメリカは確かに強いですが、日本も軍事大国でした。
陸海軍は精強であり、米軍としても日本軍の自滅のおかげでかなり救われています。
日本海軍がもっとまともな軍隊であれば、米軍とて侵攻できなかったでしょう。あれだけ無秩序に兵力を分散し、海軍は自滅し、それでも3年8ヵ月かかったのですから。しかも日本陸軍にいたっては健在でしたし。
最近の著書でも、過去の著書でも「太平洋戦争=必敗」としているものは意外に少なく、何らかの形で「和平」、「引き分け」が可能だったと定義しているものが多いです。
もっとも史実のポツダム宣言でも「無条件降伏」ではないですけどね。あれだけの戦争で条件付き講和を勝ち取ったのは日本ぐらいでしょうかね。
陸海軍は精強であり、米軍としても日本軍の自滅のおかげでかなり救われています。
日本海軍がもっとまともな軍隊であれば、米軍とて侵攻できなかったでしょう。あれだけ無秩序に兵力を分散し、海軍は自滅し、それでも3年8ヵ月かかったのですから。しかも日本陸軍にいたっては健在でしたし。
最近の著書でも、過去の著書でも「太平洋戦争=必敗」としているものは意外に少なく、何らかの形で「和平」、「引き分け」が可能だったと定義しているものが多いです。
もっとも史実のポツダム宣言でも「無条件降伏」ではないですけどね。あれだけの戦争で条件付き講和を勝ち取ったのは日本ぐらいでしょうかね。
ここは海軍悪玉論が多いですね。
たしかに海軍の戦線拡大はあまり良い判断とは思えませんが、
しかし洋上に一切航空機を出さなかった陸軍はどうなのでしょうか?
米軍は陸軍機もガダルカナルなどに進出し、あるいは空母から日本本土空襲を行ったりもしており、山本長官気を撃墜したのも陸軍機でした。
が、陸軍は、洋上を飛ぶことが出来ないからと言って海軍の要請を拒否し続け、しかし航空機生産の資源取りあいはしっかりと行っていました。
陸軍が海軍の指導で雷撃訓練を行い、洋上で実戦参加したのは、もはや負けが決まってからではなかったでしょうか?
海軍がガダルカナルで力尽きたのは、戦線拡大ももちろんのことですが、陸軍の協力を得られずに孤軍奮闘し、最後には空母艦載機まで陸上基地にあげて壊滅させたことにも原因があります。
最初から戦線を縮小していたら?
結局通商破壊線で南方からの資源供給を断たれた日本は負けていたのではないでしょうか?
米国との国力差はそれほどなかった、などという書き込みもありますが、エセックス級空母の増産体制を見ても、日本が米国に対抗できる国力があったとは思えません。
山本長官の短期決戦の判断が間違っていたとは、必ずしも言えないと私は思います。
たしかに海軍の戦線拡大はあまり良い判断とは思えませんが、
しかし洋上に一切航空機を出さなかった陸軍はどうなのでしょうか?
米軍は陸軍機もガダルカナルなどに進出し、あるいは空母から日本本土空襲を行ったりもしており、山本長官気を撃墜したのも陸軍機でした。
が、陸軍は、洋上を飛ぶことが出来ないからと言って海軍の要請を拒否し続け、しかし航空機生産の資源取りあいはしっかりと行っていました。
陸軍が海軍の指導で雷撃訓練を行い、洋上で実戦参加したのは、もはや負けが決まってからではなかったでしょうか?
海軍がガダルカナルで力尽きたのは、戦線拡大ももちろんのことですが、陸軍の協力を得られずに孤軍奮闘し、最後には空母艦載機まで陸上基地にあげて壊滅させたことにも原因があります。
最初から戦線を縮小していたら?
結局通商破壊線で南方からの資源供給を断たれた日本は負けていたのではないでしょうか?
米国との国力差はそれほどなかった、などという書き込みもありますが、エセックス級空母の増産体制を見ても、日本が米国に対抗できる国力があったとは思えません。
山本長官の短期決戦の判断が間違っていたとは、必ずしも言えないと私は思います。
初のコメント失礼します。
まず、太平洋戦争の始まりについてですが、当初日本のもくろみは、日独伊三国同盟を締結した後、ソ連とも同盟を結んで最終的には、日独伊ソ四ヵ国同盟にする構想だったそうです。
事実、独ソ不可侵条約と日ソ中立条約が存在しましたし、国際連盟を脱退し、除名された国々でしたから立場は同じと。
そうすれば、ドイツの技術や資源をなどをシベリア鉄道で日本に運べると。
日本からも送れると。
しかし、アメリカが横槍を入れた。
ルーズベルト大統領はソ連は仲間だと演説した。
しかも、ドイツが突如ソ連に侵攻して構想は破綻した。
その時、内閣下にあった、国家総力戦研究所でも対米戦の研究をした結果、敗戦は濃厚との結論に至った。
しかし、対米交渉がハルノートによって破綻し、南方資源地帯と日本本土の交通路の安全確保の観点からアメリカ太平洋艦隊を叩いておかなければ長期的な資源確保は難しいとの結論に至った。
アメリカの戦意を喪失させるため、前代未聞の航空機のみによる真珠湾攻撃をアメリカ事情に詳しい山本五十六元帥は考案した。
短期決戦を目標に。
こんな感じだと思います。
まず、太平洋戦争の始まりについてですが、当初日本のもくろみは、日独伊三国同盟を締結した後、ソ連とも同盟を結んで最終的には、日独伊ソ四ヵ国同盟にする構想だったそうです。
事実、独ソ不可侵条約と日ソ中立条約が存在しましたし、国際連盟を脱退し、除名された国々でしたから立場は同じと。
そうすれば、ドイツの技術や資源をなどをシベリア鉄道で日本に運べると。
日本からも送れると。
しかし、アメリカが横槍を入れた。
ルーズベルト大統領はソ連は仲間だと演説した。
しかも、ドイツが突如ソ連に侵攻して構想は破綻した。
その時、内閣下にあった、国家総力戦研究所でも対米戦の研究をした結果、敗戦は濃厚との結論に至った。
しかし、対米交渉がハルノートによって破綻し、南方資源地帯と日本本土の交通路の安全確保の観点からアメリカ太平洋艦隊を叩いておかなければ長期的な資源確保は難しいとの結論に至った。
アメリカの戦意を喪失させるため、前代未聞の航空機のみによる真珠湾攻撃をアメリカ事情に詳しい山本五十六元帥は考案した。
短期決戦を目標に。
こんな感じだと思います。
太平洋戦争が無謀な戦争であったかと問われれば
無謀であったと言わざる負えませんねぇ。
日中戦争の戦いは四年の長きに渡り
勝利も和平交渉のメドもたたず
戦いが一杯々の状態も一切考慮されず
陸軍自慢の関東軍が旧満州近辺のノモンハン事変でコテンパンにやられ…
緊張状態の中での睨みが続き
結果ハルノートの提出により兼ねてより反対派の多かった海軍が
石油輸出禁止で開戦にならざるおえなくなり
数多くの連合国を敵にまわして戦う羽目に陥り
何とか二年程度は善戦出来る兵器や人材は揃えて居たものの
連合国の方針で、まずヨーロッパ戦線でドイツ、イタリアを叩き
日本はヨーロッパが安定するまで長期戦と方針が決まってたので
早期決着を付けて和平交渉に持ち込むには無理があり
結果、長期消耗戦と言う日本の一番の弱点を突かれ
また陸海両軍共に多方面に多数の敵国と同時に対峙する事は
孫師の兵法からも外れる愚策と言わざるおえず
到底、勝見込みの無い戦いで有った事は事実だと思います。
無謀であったと言わざる負えませんねぇ。
日中戦争の戦いは四年の長きに渡り
勝利も和平交渉のメドもたたず
戦いが一杯々の状態も一切考慮されず
陸軍自慢の関東軍が旧満州近辺のノモンハン事変でコテンパンにやられ…
緊張状態の中での睨みが続き
結果ハルノートの提出により兼ねてより反対派の多かった海軍が
石油輸出禁止で開戦にならざるおえなくなり
数多くの連合国を敵にまわして戦う羽目に陥り
何とか二年程度は善戦出来る兵器や人材は揃えて居たものの
連合国の方針で、まずヨーロッパ戦線でドイツ、イタリアを叩き
日本はヨーロッパが安定するまで長期戦と方針が決まってたので
早期決着を付けて和平交渉に持ち込むには無理があり
結果、長期消耗戦と言う日本の一番の弱点を突かれ
また陸海両軍共に多方面に多数の敵国と同時に対峙する事は
孫師の兵法からも外れる愚策と言わざるおえず
到底、勝見込みの無い戦いで有った事は事実だと思います。
> ヒロシ☆さん
総論としては賛成なのですが、三点質問させて下さい。
ノモンハンでは、むしろ日本陸軍が寡兵をもって善戦したというのが近年の定説ではないですか?
1941年8月に石油禁輸措置、同年11月にハル・ノートですから、時系列が違うと思うのですが…
どちらかというとハル・ノートが陸軍の飲みがたい通告であり、海軍は石油禁輸措置で腹を決めざるを得なくなったのだと思います。
>連合国の方針で、まずヨーロッパ戦線でドイツ、イタリアを叩き
>日本はヨーロッパが安定するまで長期戦と方針が決まってた
恥ずかしながらこの件、2ちゃんの書き込みで読んだことがあるだけで、一次資料が何なのかを知りません。ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
米国で対日反抗作戦が発令されたのが42年7月、翌月にはガダルカナルに上陸しているわけですが、ノルマンディー上陸作戦の立案が始まったのがその翌年、作戦実行が二年後で、42年当時の西ヨーロッパ戦線は本格的反抗ではない作戦が立案されたのみに止まります。東部戦線でもドイツが再び攻勢に出て、スターリングラード攻防戦が始まった頃です。
現象だけを見ていると、どちらかというと連合国の反抗は太平洋が先だったという感じがするのですが…
総論としては賛成なのですが、三点質問させて下さい。
ノモンハンでは、むしろ日本陸軍が寡兵をもって善戦したというのが近年の定説ではないですか?
1941年8月に石油禁輸措置、同年11月にハル・ノートですから、時系列が違うと思うのですが…
どちらかというとハル・ノートが陸軍の飲みがたい通告であり、海軍は石油禁輸措置で腹を決めざるを得なくなったのだと思います。
>連合国の方針で、まずヨーロッパ戦線でドイツ、イタリアを叩き
>日本はヨーロッパが安定するまで長期戦と方針が決まってた
恥ずかしながらこの件、2ちゃんの書き込みで読んだことがあるだけで、一次資料が何なのかを知りません。ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
米国で対日反抗作戦が発令されたのが42年7月、翌月にはガダルカナルに上陸しているわけですが、ノルマンディー上陸作戦の立案が始まったのがその翌年、作戦実行が二年後で、42年当時の西ヨーロッパ戦線は本格的反抗ではない作戦が立案されたのみに止まります。東部戦線でもドイツが再び攻勢に出て、スターリングラード攻防戦が始まった頃です。
現象だけを見ていると、どちらかというと連合国の反抗は太平洋が先だったという感じがするのですが…
〉大陸帰りさん
ご質問ありがとうです。
ちょっと文章を短く纏めてしまった為に解りにくい部分や誤解を招いてしまったかも知れません。
先にお詫びしておきます。
ご質問のノモンハンでの日本軍の善戦の件ですが
私が調べた文献及びテレビのドキュメンタリー番組等の内容を参考とした私的な意見ですが
確かに航空隊や下士官以下の歩兵は善戦したと思います。
特に歩兵による夜戦は将兵が戦いの中から即座に学び対応し
対戦したジューコブ元帥に下士官以下は大変優秀だと言わせた程でした。
ただ軍上層部及び参謀達の指揮のまずさから二万の将兵を失うは
ジューコブ元帥の言葉を借りれば日本軍の装備及び作戦指揮は前時代的で近代の戦争には対応出来ないとの評価だそうです。
また石油輸出禁止措置とハルノートの件ですが
石油輸出禁止の前に精密工作機械の輸出禁止があり
日本では生産出来ない工作機械が入手不能になると兵器の生産に多大な影響を与え
米国が日本の首を真綿で絞めて居たのも意外と知られてない事実です。
海軍は兵器を主に戦う軍ですので発想は合理的にならざるおえず
石油輸出禁止になって国内の石油備蓄量により(民間及び訓練等でも消費されていくので)作戦行動出来る限界は決まっており
またハルノートが突きつけた中国からの無条件撤退は当時の日本陸軍にしては
絶対に呑める条件では無かったので…
時の米国が日本に戦争を仕掛けて来る事を望んでいた事は多数の文献から伺えます。
只今、私的な事情により泊まり込みの仕事に入って居まして
詳しい文献等が知りたいとの事ですので
仕事が終わる23日以降までお待ち頂けますか?
ご質問ありがとうです。
ちょっと文章を短く纏めてしまった為に解りにくい部分や誤解を招いてしまったかも知れません。
先にお詫びしておきます。
ご質問のノモンハンでの日本軍の善戦の件ですが
私が調べた文献及びテレビのドキュメンタリー番組等の内容を参考とした私的な意見ですが
確かに航空隊や下士官以下の歩兵は善戦したと思います。
特に歩兵による夜戦は将兵が戦いの中から即座に学び対応し
対戦したジューコブ元帥に下士官以下は大変優秀だと言わせた程でした。
ただ軍上層部及び参謀達の指揮のまずさから二万の将兵を失うは
ジューコブ元帥の言葉を借りれば日本軍の装備及び作戦指揮は前時代的で近代の戦争には対応出来ないとの評価だそうです。
また石油輸出禁止措置とハルノートの件ですが
石油輸出禁止の前に精密工作機械の輸出禁止があり
日本では生産出来ない工作機械が入手不能になると兵器の生産に多大な影響を与え
米国が日本の首を真綿で絞めて居たのも意外と知られてない事実です。
海軍は兵器を主に戦う軍ですので発想は合理的にならざるおえず
石油輸出禁止になって国内の石油備蓄量により(民間及び訓練等でも消費されていくので)作戦行動出来る限界は決まっており
またハルノートが突きつけた中国からの無条件撤退は当時の日本陸軍にしては
絶対に呑める条件では無かったので…
時の米国が日本に戦争を仕掛けて来る事を望んでいた事は多数の文献から伺えます。
只今、私的な事情により泊まり込みの仕事に入って居まして
詳しい文献等が知りたいとの事ですので
仕事が終わる23日以降までお待ち頂けますか?
> ヒロシ☆さん
ありがとうございます。
ううむ。ノモンハンで歩兵の援護なしに戦車を突出させて大損害を出し航空戦でも日本よりはるかに大きな損害を受けたジューコフ准将の「前時代的」という評価って正しいんでしょうか。
彼の指揮スタイルは、相手より損害受けることを気にしない人海戦術ですし…ある意味もっとも原始的。
ノモンハンは戦術レベルの話ではなく、ドイツ戦に備えて背後の脅威を取り除くべく本腰を入れたソ連中枢と、事態を軽く見た東京大本営の、戦略レベルの姿勢の差だったように思います。
米国に対日戦の意図があったかどうかは話題から外れますし、日米交渉史に関しては資料は豊富で流れは把握していると思っているので構いません。
が、連合国の戦争遂行の全体方針については資料は目に入りにくいのです。
なので、
「連合国の方針で、まずヨーロッパ戦線でドイツ、イタリアを叩き、日本はヨーロッパが安定するまで長期戦と方針が決まってた」
が今一つ理解出来ないのです。
お時間出来ました時に、この件についての資料のご紹介をお願いします。
ありがとうございます。
ううむ。ノモンハンで歩兵の援護なしに戦車を突出させて大損害を出し航空戦でも日本よりはるかに大きな損害を受けたジューコフ准将の「前時代的」という評価って正しいんでしょうか。
彼の指揮スタイルは、相手より損害受けることを気にしない人海戦術ですし…ある意味もっとも原始的。
ノモンハンは戦術レベルの話ではなく、ドイツ戦に備えて背後の脅威を取り除くべく本腰を入れたソ連中枢と、事態を軽く見た東京大本営の、戦略レベルの姿勢の差だったように思います。
米国に対日戦の意図があったかどうかは話題から外れますし、日米交渉史に関しては資料は豊富で流れは把握していると思っているので構いません。
が、連合国の戦争遂行の全体方針については資料は目に入りにくいのです。
なので、
「連合国の方針で、まずヨーロッパ戦線でドイツ、イタリアを叩き、日本はヨーロッパが安定するまで長期戦と方針が決まってた」
が今一つ理解出来ないのです。
お時間出来ました時に、この件についての資料のご紹介をお願いします。
〉大陸帰りさん
まだ仕事中では有りますので
資料本の方は未だ確認は出来てないのですが…
ちょっとした携帯からの検索でも沢山の情報が集まりましたので…
〉ヨーロッパの独伊戦を最重要とし日本に対しては長期消耗戦とする…の件ですが
Wikipediaより抜粋
(アルカディア会談)
真珠湾攻撃が起きたばかりであるが、アメリカ合衆国は戦争に勝利することを約束し、最初の目標はナチス・ドイツであるとした(ヨーロッパを最初の戦略目標とした)。また、ヨーロッパ作戦戦域において軍事的資源を統一して運用することにも同意した。 それ以外の会議の結果として、連合国共同宣言を1942年1月1日に行い、連合国(現在の国際連合)の結成に同意した。
似た内容はアルカディア会談で検索すれば幾らでも出てきます。
また長期消耗戦とは書いてないと思われる場合…
真珠湾攻撃以後の米国の建鑑計画とその後の戦略を調べれば簡単に答えは出ます。
エセックス級空母とF6FヘルキャットにVT信管が揃う昭和19年まで
大攻勢を掛ける手駒が揃っていませんでしたので。
〉ノモンハン事変で日本陸軍は善戦したのかの件ですが…
当時のソ連軍の現状を調べれば
逆に善戦し勝利を勝ち取ったのはソ連軍だとお分かりいただけると思います。
また石油禁輸処置とハルノートの関係ですが…
最後通牒のハルノートばかりが際立って目立っておりますが
日米の外交交渉は石油禁輸処置以前から幾度もやり取りがなされた結果
米国が石油と言う時間制限を付け、開戦か撤兵かを迫ったものです。
因みに石油が無ければ陸軍も軍事行動が出来なくて困るのは同じ事ですよ。(笑)
詳しくは開戦前の御前会議にて検索して下さいね!
まだ仕事中では有りますので
資料本の方は未だ確認は出来てないのですが…
ちょっとした携帯からの検索でも沢山の情報が集まりましたので…
〉ヨーロッパの独伊戦を最重要とし日本に対しては長期消耗戦とする…の件ですが
Wikipediaより抜粋
(アルカディア会談)
真珠湾攻撃が起きたばかりであるが、アメリカ合衆国は戦争に勝利することを約束し、最初の目標はナチス・ドイツであるとした(ヨーロッパを最初の戦略目標とした)。また、ヨーロッパ作戦戦域において軍事的資源を統一して運用することにも同意した。 それ以外の会議の結果として、連合国共同宣言を1942年1月1日に行い、連合国(現在の国際連合)の結成に同意した。
似た内容はアルカディア会談で検索すれば幾らでも出てきます。
また長期消耗戦とは書いてないと思われる場合…
真珠湾攻撃以後の米国の建鑑計画とその後の戦略を調べれば簡単に答えは出ます。
エセックス級空母とF6FヘルキャットにVT信管が揃う昭和19年まで
大攻勢を掛ける手駒が揃っていませんでしたので。
〉ノモンハン事変で日本陸軍は善戦したのかの件ですが…
当時のソ連軍の現状を調べれば
逆に善戦し勝利を勝ち取ったのはソ連軍だとお分かりいただけると思います。
また石油禁輸処置とハルノートの関係ですが…
最後通牒のハルノートばかりが際立って目立っておりますが
日米の外交交渉は石油禁輸処置以前から幾度もやり取りがなされた結果
米国が石油と言う時間制限を付け、開戦か撤兵かを迫ったものです。
因みに石油が無ければ陸軍も軍事行動が出来なくて困るのは同じ事ですよ。(笑)
詳しくは開戦前の御前会議にて検索して下さいね!
> ヒロシ☆さん
失礼ながらその程度の知識ならば、検索をかけるまでもなくあります。問題はそれをどう考察するか、なのです。
アルカディア会談当時日本軍はシンガポールも落としていません。フィリピンではその後バターン半島に立てこもった米軍が抵抗している時期です。ラバウルジャワビルマはまだ勢力圏外です。それでも日本の侵攻は計画以上の早さでした。
つまり状況は、アルカディア会談当時の1-2ヶ月後には全く違うものになっていたのです。
「ウォッチタワー作戦」「ノルマンディー上陸作戦」についても検索かけてみて下さい。現実に、ヨーロッパ戦線での反抗作戦の企画が始まる前に、対日反抗作戦は始まったのです。
ちなみに1942年7月に発令されたウォッチタワー作戦では、南方島嶼部からの反抗が計画されており、必ずしも空母群は不要です。むしろ大量の空母を利用する海域が小さすぎるかと。それに、ウォッチタワー作戦発令当時は、米軍もエンタープライズ級二隻、サラトガ、ワスプを保有していました。
>当時のソ連軍の現状を調べれば
逆に善戦し勝利を勝ち取ったのはソ連軍だとお分かりいただけると思います。
具体的な話でお願いします。
ヒロシ☆さんが参考になさっているwikiには
「元ソ連参謀本部故Василий Новобранецノヴォブラネツ大佐の手記では、『ノモンハンで勝ったのは、兵力と武器類の面で優位に立っていたからであり、戦闘能力で勝利したのではない』と書いている」
とありますが…?
>最後通牒のハルノートばかりが際立って目立っておりますが
私は始めから、ハルノートよりも石油禁輸の件を、海軍が腹を決めた原因として重視した書き込みをしているので、もう少し主旨を絞った書き込みをお願い出来ないでしょうか?
失礼ながらその程度の知識ならば、検索をかけるまでもなくあります。問題はそれをどう考察するか、なのです。
アルカディア会談当時日本軍はシンガポールも落としていません。フィリピンではその後バターン半島に立てこもった米軍が抵抗している時期です。ラバウルジャワビルマはまだ勢力圏外です。それでも日本の侵攻は計画以上の早さでした。
つまり状況は、アルカディア会談当時の1-2ヶ月後には全く違うものになっていたのです。
「ウォッチタワー作戦」「ノルマンディー上陸作戦」についても検索かけてみて下さい。現実に、ヨーロッパ戦線での反抗作戦の企画が始まる前に、対日反抗作戦は始まったのです。
ちなみに1942年7月に発令されたウォッチタワー作戦では、南方島嶼部からの反抗が計画されており、必ずしも空母群は不要です。むしろ大量の空母を利用する海域が小さすぎるかと。それに、ウォッチタワー作戦発令当時は、米軍もエンタープライズ級二隻、サラトガ、ワスプを保有していました。
>当時のソ連軍の現状を調べれば
逆に善戦し勝利を勝ち取ったのはソ連軍だとお分かりいただけると思います。
具体的な話でお願いします。
ヒロシ☆さんが参考になさっているwikiには
「元ソ連参謀本部故Василий Новобранецノヴォブラネツ大佐の手記では、『ノモンハンで勝ったのは、兵力と武器類の面で優位に立っていたからであり、戦闘能力で勝利したのではない』と書いている」
とありますが…?
>最後通牒のハルノートばかりが際立って目立っておりますが
私は始めから、ハルノートよりも石油禁輸の件を、海軍が腹を決めた原因として重視した書き込みをしているので、もう少し主旨を絞った書き込みをお願い出来ないでしょうか?
そもそものヒロシ☆さんの書き込みですが…
>陸軍自慢の関東軍が旧満州近辺のノモンハン事変でコテンパンにやられ…
>緊張状態の中での睨みが続き
>結果ハルノートの提出により兼ねてより反対派の多かった海軍が
>石油輸出禁止で開戦にならざるおえなくなり
とありますが、この書き込みではハルノートのあとに石油禁輸措置が記述されているのがおかしいのではないか?
というのが、当初の私の書き込んだ意図です。
また、ノモンハンでやられてにらみ合いになったことの結果としてハルノート、というのも、流れとしてはおかしくはないですか?
にらみ合いの末のハルノートを結果に持って来るならば、原因は南部仏印進駐にすべきかと。
それと、
>連合国の方針で〜中略
>と方針が決まってたので
>早期決着を付けて和平交渉に持ち込むには無理があり
と書かれていますが、日本は開戦後に日独伊単独不講和協定を締結しておりますから、早期講和が出来なかった原因を連合国の作戦だけに求めるというご趣旨にも無理があるかと思います。
>陸軍自慢の関東軍が旧満州近辺のノモンハン事変でコテンパンにやられ…
>緊張状態の中での睨みが続き
>結果ハルノートの提出により兼ねてより反対派の多かった海軍が
>石油輸出禁止で開戦にならざるおえなくなり
とありますが、この書き込みではハルノートのあとに石油禁輸措置が記述されているのがおかしいのではないか?
というのが、当初の私の書き込んだ意図です。
また、ノモンハンでやられてにらみ合いになったことの結果としてハルノート、というのも、流れとしてはおかしくはないですか?
にらみ合いの末のハルノートを結果に持って来るならば、原因は南部仏印進駐にすべきかと。
それと、
>連合国の方針で〜中略
>と方針が決まってたので
>早期決着を付けて和平交渉に持ち込むには無理があり
と書かれていますが、日本は開戦後に日独伊単独不講和協定を締結しておりますから、早期講和が出来なかった原因を連合国の作戦だけに求めるというご趣旨にも無理があるかと思います。
〉大陸帰りさんへ追伸
国の存亡が掛かった英国はまだしも何故直接自国を攻撃された米国が対ヒトラーを優先したかと言えば
それはマンハッタン計画に起因します。
太平洋戦争開戦前に独国から亡命し永住権を獲得した原爆の母で有るアインシュタインは
ルーズベルト大統領にこう進言したといいます。
独国には原爆を造れるだけの技術と物資と頭脳が揃って居ます。
独国より少しでも早く原爆を開発するべきですと…
因みにさしたる戦略的価値も無い米国のガナルカナル上陸は米国の仕掛けた消耗戦で
上手く策略にハマった日本軍は大変貴重なベテランパイロットや航空機、艦船や歩兵など
取り返しの付かない多数の損害を出し、後の米国大反抗作戦に対応出来る兵力を備蓄する事が出来ず
また太平洋で稼働してる米空母がエンタープライズただ一隻と言う最大のチャンスすらも有効に事を運ぶ事すら出来ませんでした。
また欧州戦線において1943年頃まで米軍の目立った活躍がなされてない様に思われがちですが
U-ボートによる通商破壊戦への妨害や英国やソ連への物資の補給…
ソ連には大量の輸送トラックを供与し、
それによってソ連軍は戦車の生産に専念出来たと言われてます。
また英国飛行場よりB17による軍事施設への空爆やアフリカ戦線にも参戦して独軍を追い払っており
最後の極めつけはノルマンディー上陸作戦の前にイタリア上陸と占領作戦が上げられます。
それでも米国の攻勢が遅いと思われるならば
米国が独軍に対抗する機甲師団の配備及び訓練の遅れ
英国からの戦訓による独陸軍への過大評価から上陸戦に対する警戒感がもたらしたものだと思います。
国の存亡が掛かった英国はまだしも何故直接自国を攻撃された米国が対ヒトラーを優先したかと言えば
それはマンハッタン計画に起因します。
太平洋戦争開戦前に独国から亡命し永住権を獲得した原爆の母で有るアインシュタインは
ルーズベルト大統領にこう進言したといいます。
独国には原爆を造れるだけの技術と物資と頭脳が揃って居ます。
独国より少しでも早く原爆を開発するべきですと…
因みにさしたる戦略的価値も無い米国のガナルカナル上陸は米国の仕掛けた消耗戦で
上手く策略にハマった日本軍は大変貴重なベテランパイロットや航空機、艦船や歩兵など
取り返しの付かない多数の損害を出し、後の米国大反抗作戦に対応出来る兵力を備蓄する事が出来ず
また太平洋で稼働してる米空母がエンタープライズただ一隻と言う最大のチャンスすらも有効に事を運ぶ事すら出来ませんでした。
また欧州戦線において1943年頃まで米軍の目立った活躍がなされてない様に思われがちですが
U-ボートによる通商破壊戦への妨害や英国やソ連への物資の補給…
ソ連には大量の輸送トラックを供与し、
それによってソ連軍は戦車の生産に専念出来たと言われてます。
また英国飛行場よりB17による軍事施設への空爆やアフリカ戦線にも参戦して独軍を追い払っており
最後の極めつけはノルマンディー上陸作戦の前にイタリア上陸と占領作戦が上げられます。
それでも米国の攻勢が遅いと思われるならば
米国が独軍に対抗する機甲師団の配備及び訓練の遅れ
英国からの戦訓による独陸軍への過大評価から上陸戦に対する警戒感がもたらしたものだと思います。
> ヒロシ☆さん
私は欧州での反抗が遅かったと言っているのではなく、太平洋方面での反抗が早かった、と言っているのです。
ガダルカナルが米軍の仕掛けた消耗戦?
ウォッチタワー作戦の主旨とは違うようですが?
ガダルカナル方面では、空母の損害を怖れて早めの撤退をしたフレッチャー中将を、南雲中将とともにもっとも空母指揮経験が多いにも関わらず更迭しております。
「米軍の仕掛けた消耗戦」とはちょっと違う気がしますが。
1939年のアインシュタインの手紙から1942年9月(ウォッチタワー作戦の発令後)のマンハッタン計画着手まで時間がありすぎます。
アインシュタインの手紙と連合国の戦略を繋げるというのは、現時点で私が持っている情報では無理があるかと。
なぜヒロシ☆さんはウォッチタワー作戦には言及されないまま連合国の戦略やガダルカナル戦についての話を進めるのですか?
私は欧州での反抗が遅かったと言っているのではなく、太平洋方面での反抗が早かった、と言っているのです。
ガダルカナルが米軍の仕掛けた消耗戦?
ウォッチタワー作戦の主旨とは違うようですが?
ガダルカナル方面では、空母の損害を怖れて早めの撤退をしたフレッチャー中将を、南雲中将とともにもっとも空母指揮経験が多いにも関わらず更迭しております。
「米軍の仕掛けた消耗戦」とはちょっと違う気がしますが。
1939年のアインシュタインの手紙から1942年9月(ウォッチタワー作戦の発令後)のマンハッタン計画着手まで時間がありすぎます。
アインシュタインの手紙と連合国の戦略を繋げるというのは、現時点で私が持っている情報では無理があるかと。
なぜヒロシ☆さんはウォッチタワー作戦には言及されないまま連合国の戦略やガダルカナル戦についての話を進めるのですか?
既に終了したトピを復活させて申し訳ないのですが・・・
太平洋戦争の敗因は、
1.戦争終了の為の絵姿が無かった
2.当時の二大大国【米英】と戦争しつつ、日本軍主力(陸軍)は中国を主戦場としていた。
ことにあるのではないかと愚考します。
1について:戦争とは政治的解決の一手段である以上、政治的にいかに紛争を解決するかが重要であるにも関わらず、当時の日本の指導者にはこれへの明確な考えが無かったことが、根本的な敗因だと考えます。
一方、連合国(といってもアメリカですが)は枢軸国の無条件降伏というエンドステートがあり、それに向け軍事作戦を行っていました。
2について:国力が世界NO1、2位の国と戦争するにも関わらず、陸軍の主努力は中国大陸、海軍の主努力は太平洋と、軍事作戦の重点が股割き状態。
これでは総力戦・長期持久戦に勝てなくて当然
トピタイの結論として、太平洋戦争の敗因は戦略そのものに欠陥があった以上、太平洋戦争は無謀なものであったとしかいいようがないかと思います。
因みに、よく日露戦争との比較がでます。確かに、国力比的には日露戦争時の日本:ロシアの方が、太平洋戦争時の日本:アメリカより開いていたのでしょうが、大きな差異として、日露戦争時は
1.日本側は朝鮮半島におけるロシアの影響力排除ができればよいという明確な戦争目的があった
2.アメリカを通じた講和の努力が真面目になされていた。
3.日本は対露戦以外の戦争はしていなかった(他国、特に中国の中立化に成功)
という違いがあるので、余り日露戦争の時の話は参考にならないと思います(日米開戦時の日本人は、日露戦争の成功体験から勝利の可能性を信じていた人も少なからず存在したようですが)
太平洋戦争の敗因は、
1.戦争終了の為の絵姿が無かった
2.当時の二大大国【米英】と戦争しつつ、日本軍主力(陸軍)は中国を主戦場としていた。
ことにあるのではないかと愚考します。
1について:戦争とは政治的解決の一手段である以上、政治的にいかに紛争を解決するかが重要であるにも関わらず、当時の日本の指導者にはこれへの明確な考えが無かったことが、根本的な敗因だと考えます。
一方、連合国(といってもアメリカですが)は枢軸国の無条件降伏というエンドステートがあり、それに向け軍事作戦を行っていました。
2について:国力が世界NO1、2位の国と戦争するにも関わらず、陸軍の主努力は中国大陸、海軍の主努力は太平洋と、軍事作戦の重点が股割き状態。
これでは総力戦・長期持久戦に勝てなくて当然
トピタイの結論として、太平洋戦争の敗因は戦略そのものに欠陥があった以上、太平洋戦争は無謀なものであったとしかいいようがないかと思います。
因みに、よく日露戦争との比較がでます。確かに、国力比的には日露戦争時の日本:ロシアの方が、太平洋戦争時の日本:アメリカより開いていたのでしょうが、大きな差異として、日露戦争時は
1.日本側は朝鮮半島におけるロシアの影響力排除ができればよいという明確な戦争目的があった
2.アメリカを通じた講和の努力が真面目になされていた。
3.日本は対露戦以外の戦争はしていなかった(他国、特に中国の中立化に成功)
という違いがあるので、余り日露戦争の時の話は参考にならないと思います(日米開戦時の日本人は、日露戦争の成功体験から勝利の可能性を信じていた人も少なからず存在したようですが)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
太平洋戦争は防げたのか 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-