★集中力と脳波の関係
集中力を語る場合によく出てくるのが脳波の話である。脳波は集中力と関連があるが、世に流布している集中力と脳波の関係論の大部分は、短絡的な考え方が多く、無意味というより有害であるといったほうがいい。
その最たる例が「α波=集中力」論である。この論の骨子は、「α波が出ているときが集中している状態である。逆に集中力を開発すすにはα波が出るようにトレーニングをすればいい」というものである。この条件反射的な幼稚な単純な言説が大手をふってまかり通っていることに、私は驚きと疑念を禁じ得ない。 私の考えを述べよう。
脳波には、α波、β波、θ波、δ波の四つがある。それに対応する形で、α波集中、β波集中、θ波集中、δ波集中というわけである。
α波は、意識がめざめた状態で、落ち着き、安定した姿で集中している状態のときに出ている脳波である。
β波は、意識がはっきり目覚め、緊張し、めまぐるしく働いている、何かに集中している状態のときに出る脳波である。一日のうち、私たちが起きている時間中、出ている脳波である。θ波は眠りに入るときや、眠りから覚めるときに出やすい脳波である。そして、δ波は睡眠中に出ている脳波である。
集中ということで言えば、四六時中脳波が出ているわけだから、起きているときだけではなく、入眠覚醒時や睡眠中も私たちは集中力を高めることができると考えられる。
例えば、日本で最初にノーベル賞を受賞し湯川秀樹博士の中間子理論など優れたインスピレーションは、θ波集中時に出やすいと言われている。また、ホンダを世界的にメーカーに育てた本田宗一郎は、夢のなかで決定的なアイデアをつかんだと言われている。
つまり、人間の集中活動は二四時間、それぞれの異なる脳波を出して営まれ続けているといっても過言ではない。したがって、「α波=集中力」という一面的でかつ直線的な考え方や決めつけ方はよくない。そのこと端的にわかる次のようなケースがある。
最近、携帯電話をもっていない人を探すのが難しいぐらい、誰もが携帯電話をもつようになってきた。自動車の運転中でも平気で携帯電話をかけるのが原因の交通事故も増加していると言われている。それは無理もないことである。その要因を脳波を使って説明しよう。
ある専門家が自動車を運転しているとき脳波について調べた結果が手元にある。その実験結果によると、「視覚をつかさどる脳波が大きくふれ、眼球が左右にたえまなく動いて、周囲の状況に気を配っている」――これが運転に集中しているときの集中状態であることがわかった。
一方、自動車を運転しながら携帯電話をしているときは、「眼球が前方の一点を集中して見る傾向が顕著であり、脳波は平坦になっていた」という。
この結果から言えることが、自動車を運転しているときと、運転しながら携帯電話をしているときでは、まったく違う脳波が現れていることだ。波形から判断すると、運転しているときにはα波が、携帯電話をしながらではβ波が出ているようだ。「α波=集中力」の図式がもろくも崩れさったのである。
★集中力を高めるためのノウハウ
集中力を高めるもっともいい方法とし、考えつくままにいろいろな方法を提示してみたい。
?気持ちを落ち着かせるためのノウハウ
一、頭のなかでゆっくり数を数える。これをカウント法と呼んでいる。どんな数でもいいし、どこまでいってもいい。これを少なくとも五分間行う。
二、瞑想、黙想する。座禅でもいいし、座禅のような形にこだわることなく、どんな場所でもいいから、瞑想、黙想する。時間に制限はない。
三、腹式呼吸をする。この場合、息を吸うときは早く、吐くときにゆっくり時間をかけて行う。時間をかけて腹式呼吸を行うことで身体全体からよぶんな力が抜け、心がとても落ち着いた状態になる。
四、静かな音楽や自分の好きな音楽を聴く。あるいは楽器を弾いたりする。アインシュタインは、研究を行っている合間によくバイオリンを弾いて気分を落ち着かせたりしたそうである。音楽は気持ちを落ちつかせるのに有効な手段である。例えば、「1/fゆらぎ」がある。風のこずえや砂浜、そよ風、小川のせせらぎなどの音を電気振動に変え、その周波数を分類したものだが、この「1/fゆらぎ」が耳を通して脳内に入ったときに、心も身体もそのような音楽に没入させ、心をリラックスさせる。クラシックの名曲を聴くと心が落ち着くのは、「1/fゆらぎ」が要因である。
五、絵画を見る。できれば風景がや素朴な絵画がいい。場所は、静かな美術館でもいいし、画廊でもいい。
六、自立訓練法を実施する。これはドイツの精神医学者であるJ・H・シュルツが始めたもので、自己暗示によって精神の緊張を解きほぐす方法である。精神医療だけでなく、スポーツ選手のメンタル・トレーニングや能力開発学習などに使われている。ゆったり、くつろぎながら、愉快な情景を思い浮かべ、そして「手が重くなる」「身体が温かい」というような暗示をかける。
?思考を活発に働かせながら、考えを位置づけたり、順序づけたり、関係づけるためのノウハウ
一、走っている車など、目に入るものを片っ端から数える。
二、目に入るものを片っ端から分類する。三、見聞していることのなかで、何かテーマを決め手、固有名詞や数字などを正確に記憶するよう努める。
四、バラバラになっている考えのなかで、特に重要なものを特定化しようと試みる。そして、そのなかでどれか二つをくっつけ、因果関係で結んでみる。同じく、主従関係、並列関係、そのほかの論理で結んでみる。
五、一〜四までがうまくできたら、今度はもっと対象を広げて、同じようなことを行う。 六、考えのなかであいまいな点が出てきたら、すかさず辞書を引いて調べる、確認する。 七、抽象的な考え方をできるだけ排除し、具体的に考えて、その例をさがす。
八、自分のもっている具体的なエピソードを、今度は抽象化したり、概念化したり、理念化してみる。
これらの一連のことを繰り返すことによって、思考を活発化させることによって、集中力が一気に高まる。
?思考のベクトルを内側に向けるためのノウハウ
一、漠然と観察する。例えば、風呂をわかすために水を入れるときに、水がたまるまでじっと見続ける。
二、絶対に借り物でない自分だけの考え、過去の体験や記憶を思い出し、そこに注意を向ける。とくに幼児期の頃を振り返ってみる。というのも、幼児ほどあれこれいろんなことに無心に没頭できるのはなかなかいないからである。何がなくてもいつのまにか道具をみつけて遊んでいる。われわれ大人に比べれば、何かに夢中になる点でははるかにレベルが高く、ストレートな集中力がある。したがって、過去の体験を思い出しながら、子どもたちの言動を観察したり、ときにはいっしょに遊んだり、子ども心になろうと努めてみたり、自分のなかの子ども心を探してみる。そして、自分のなかに見つけた子ども心をプラス思考で肯定し、大切に守り続けていく。
三、眼の焦点を一メートル以内の近距離に結ぶ。難しければ、近くのものをみつめる。 四、両手の親指をほお骨の下にあて、残りの指は揃えて額にかざす。ちょうど、帽子のツバのようにして、前方を見つめる。
五、ラジオやCDの音を小さくして、それを聴きとろうと努力する。
六、目をつぶって考える。
?いちだんと集中のレベルをあげるノウハウ
一、鋭い緻密な観察をする。大きなものより小さなものを観察する。大きな動きより微妙な動きを観察する。
二、両耳の後ろに親指をあてる。昆虫学者ファーブルの方法。
三、奥歯をかみしめる。
四、マッチ棒を何本でも折りながら考える。囲碁で有名は趙治勲の方法。
五、手のなかでクルミの実など、手のひらに入る手頃の大きさのものを一定のリズムで転がす。
六、周囲の照明をいくぶん弱くする。
七、新聞記事の活字の数を五分間、ひたする数える。
?豊かな創造的なアウトプットを生むためのノウハウ
一、歩きながら考える。
二、頭に思い浮かんだこと、歩いていて気がついたことなど、何でもいいからとにかく、メモをする、ひたすら書く。これは左脳(言語脳)を活発化、集中化する。
三、頭に浮かんだイメージを図や絵にする。これは右脳(音楽脳)を活発化、集中化する。 四、二と三の両方を行う。それによって、右脳も左脳の集中がたやすくできるようになり、二つの脳の結合によるシナジー効果で創造的なアイデアが出やすくなる。
五、もう一度、自分が直面している課題や目的を強く意識する。
六、この段階で浮かんできた考えが、自分の満足のいくものかどうかを評価する。満足できなければさらに集中を継続する。
七、日頃から問題意識を広げ、深め、問題解決度の満足水準をさらに高めるよう努力する。集中によって生まれるアウトプットの量は、問題意識の広さや深さ、満足水準の高さに比例するからである。
★全身集中術をマスターする
本当に集中力を高めるためには、頭脳と身体の両方の集中が不可欠である。
まず、脳のほうから説明すると、「右脳集中術」がある。右脳はイメージを司る脳として知られているが、右脳を集中させるには、風景や絵画の観察もいいが、イメージを思い浮かべるときにできるだけ細部までくっきり思い浮かべる癖をつけることである。そうしないと肝心の点が意識のなかから欠落して、ミスやトラブルを起こしやすくなる。
次に、左脳集中術をマスターしよう。「こうだからこうなる」「これとこれはこんな関係になる」というように、まず言葉で文句や文章を考える、事柄の筋道をつける、言葉を整理する、いろんな考えのなかから理由をつけて一つを選ぶ、複数のものを頭のなかに並べて比較する、結論をだす――といったような頭を働かせる癖をつけること。
また、全身集中術については、身体を動かしながら「考える身体=集中する身体」をつくっていくことである。そのためには、仕事や趣味、スポーツで要求される身のこなし、動作、技能については、自分がポイントと意識したところを正確に理解し、実際に身体を動かし、納得するまで反復練習する。身体を動かさないときは筋肉だけでも動かす。単に知識として覚えるだけではなく、身体でも覚えるようにすれば、集中力はいちだんをアップする。
人間誰もが集中力をもっている。集中する知性がある。集中力は三〇分から一時間しかもたないという方もあるが、そんなことはない。一カ月でも二カ月でも集中力を持続することは可能である。しかし、そんなことを考えるより、ここで紹介したノウハウにまず取り組んでいただきたい。
集中力を語る場合によく出てくるのが脳波の話である。脳波は集中力と関連があるが、世に流布している集中力と脳波の関係論の大部分は、短絡的な考え方が多く、無意味というより有害であるといったほうがいい。
その最たる例が「α波=集中力」論である。この論の骨子は、「α波が出ているときが集中している状態である。逆に集中力を開発すすにはα波が出るようにトレーニングをすればいい」というものである。この条件反射的な幼稚な単純な言説が大手をふってまかり通っていることに、私は驚きと疑念を禁じ得ない。 私の考えを述べよう。
脳波には、α波、β波、θ波、δ波の四つがある。それに対応する形で、α波集中、β波集中、θ波集中、δ波集中というわけである。
α波は、意識がめざめた状態で、落ち着き、安定した姿で集中している状態のときに出ている脳波である。
β波は、意識がはっきり目覚め、緊張し、めまぐるしく働いている、何かに集中している状態のときに出る脳波である。一日のうち、私たちが起きている時間中、出ている脳波である。θ波は眠りに入るときや、眠りから覚めるときに出やすい脳波である。そして、δ波は睡眠中に出ている脳波である。
集中ということで言えば、四六時中脳波が出ているわけだから、起きているときだけではなく、入眠覚醒時や睡眠中も私たちは集中力を高めることができると考えられる。
例えば、日本で最初にノーベル賞を受賞し湯川秀樹博士の中間子理論など優れたインスピレーションは、θ波集中時に出やすいと言われている。また、ホンダを世界的にメーカーに育てた本田宗一郎は、夢のなかで決定的なアイデアをつかんだと言われている。
つまり、人間の集中活動は二四時間、それぞれの異なる脳波を出して営まれ続けているといっても過言ではない。したがって、「α波=集中力」という一面的でかつ直線的な考え方や決めつけ方はよくない。そのこと端的にわかる次のようなケースがある。
最近、携帯電話をもっていない人を探すのが難しいぐらい、誰もが携帯電話をもつようになってきた。自動車の運転中でも平気で携帯電話をかけるのが原因の交通事故も増加していると言われている。それは無理もないことである。その要因を脳波を使って説明しよう。
ある専門家が自動車を運転しているとき脳波について調べた結果が手元にある。その実験結果によると、「視覚をつかさどる脳波が大きくふれ、眼球が左右にたえまなく動いて、周囲の状況に気を配っている」――これが運転に集中しているときの集中状態であることがわかった。
一方、自動車を運転しながら携帯電話をしているときは、「眼球が前方の一点を集中して見る傾向が顕著であり、脳波は平坦になっていた」という。
この結果から言えることが、自動車を運転しているときと、運転しながら携帯電話をしているときでは、まったく違う脳波が現れていることだ。波形から判断すると、運転しているときにはα波が、携帯電話をしながらではβ波が出ているようだ。「α波=集中力」の図式がもろくも崩れさったのである。
★集中力を高めるためのノウハウ
集中力を高めるもっともいい方法とし、考えつくままにいろいろな方法を提示してみたい。
?気持ちを落ち着かせるためのノウハウ
一、頭のなかでゆっくり数を数える。これをカウント法と呼んでいる。どんな数でもいいし、どこまでいってもいい。これを少なくとも五分間行う。
二、瞑想、黙想する。座禅でもいいし、座禅のような形にこだわることなく、どんな場所でもいいから、瞑想、黙想する。時間に制限はない。
三、腹式呼吸をする。この場合、息を吸うときは早く、吐くときにゆっくり時間をかけて行う。時間をかけて腹式呼吸を行うことで身体全体からよぶんな力が抜け、心がとても落ち着いた状態になる。
四、静かな音楽や自分の好きな音楽を聴く。あるいは楽器を弾いたりする。アインシュタインは、研究を行っている合間によくバイオリンを弾いて気分を落ち着かせたりしたそうである。音楽は気持ちを落ちつかせるのに有効な手段である。例えば、「1/fゆらぎ」がある。風のこずえや砂浜、そよ風、小川のせせらぎなどの音を電気振動に変え、その周波数を分類したものだが、この「1/fゆらぎ」が耳を通して脳内に入ったときに、心も身体もそのような音楽に没入させ、心をリラックスさせる。クラシックの名曲を聴くと心が落ち着くのは、「1/fゆらぎ」が要因である。
五、絵画を見る。できれば風景がや素朴な絵画がいい。場所は、静かな美術館でもいいし、画廊でもいい。
六、自立訓練法を実施する。これはドイツの精神医学者であるJ・H・シュルツが始めたもので、自己暗示によって精神の緊張を解きほぐす方法である。精神医療だけでなく、スポーツ選手のメンタル・トレーニングや能力開発学習などに使われている。ゆったり、くつろぎながら、愉快な情景を思い浮かべ、そして「手が重くなる」「身体が温かい」というような暗示をかける。
?思考を活発に働かせながら、考えを位置づけたり、順序づけたり、関係づけるためのノウハウ
一、走っている車など、目に入るものを片っ端から数える。
二、目に入るものを片っ端から分類する。三、見聞していることのなかで、何かテーマを決め手、固有名詞や数字などを正確に記憶するよう努める。
四、バラバラになっている考えのなかで、特に重要なものを特定化しようと試みる。そして、そのなかでどれか二つをくっつけ、因果関係で結んでみる。同じく、主従関係、並列関係、そのほかの論理で結んでみる。
五、一〜四までがうまくできたら、今度はもっと対象を広げて、同じようなことを行う。 六、考えのなかであいまいな点が出てきたら、すかさず辞書を引いて調べる、確認する。 七、抽象的な考え方をできるだけ排除し、具体的に考えて、その例をさがす。
八、自分のもっている具体的なエピソードを、今度は抽象化したり、概念化したり、理念化してみる。
これらの一連のことを繰り返すことによって、思考を活発化させることによって、集中力が一気に高まる。
?思考のベクトルを内側に向けるためのノウハウ
一、漠然と観察する。例えば、風呂をわかすために水を入れるときに、水がたまるまでじっと見続ける。
二、絶対に借り物でない自分だけの考え、過去の体験や記憶を思い出し、そこに注意を向ける。とくに幼児期の頃を振り返ってみる。というのも、幼児ほどあれこれいろんなことに無心に没頭できるのはなかなかいないからである。何がなくてもいつのまにか道具をみつけて遊んでいる。われわれ大人に比べれば、何かに夢中になる点でははるかにレベルが高く、ストレートな集中力がある。したがって、過去の体験を思い出しながら、子どもたちの言動を観察したり、ときにはいっしょに遊んだり、子ども心になろうと努めてみたり、自分のなかの子ども心を探してみる。そして、自分のなかに見つけた子ども心をプラス思考で肯定し、大切に守り続けていく。
三、眼の焦点を一メートル以内の近距離に結ぶ。難しければ、近くのものをみつめる。 四、両手の親指をほお骨の下にあて、残りの指は揃えて額にかざす。ちょうど、帽子のツバのようにして、前方を見つめる。
五、ラジオやCDの音を小さくして、それを聴きとろうと努力する。
六、目をつぶって考える。
?いちだんと集中のレベルをあげるノウハウ
一、鋭い緻密な観察をする。大きなものより小さなものを観察する。大きな動きより微妙な動きを観察する。
二、両耳の後ろに親指をあてる。昆虫学者ファーブルの方法。
三、奥歯をかみしめる。
四、マッチ棒を何本でも折りながら考える。囲碁で有名は趙治勲の方法。
五、手のなかでクルミの実など、手のひらに入る手頃の大きさのものを一定のリズムで転がす。
六、周囲の照明をいくぶん弱くする。
七、新聞記事の活字の数を五分間、ひたする数える。
?豊かな創造的なアウトプットを生むためのノウハウ
一、歩きながら考える。
二、頭に思い浮かんだこと、歩いていて気がついたことなど、何でもいいからとにかく、メモをする、ひたすら書く。これは左脳(言語脳)を活発化、集中化する。
三、頭に浮かんだイメージを図や絵にする。これは右脳(音楽脳)を活発化、集中化する。 四、二と三の両方を行う。それによって、右脳も左脳の集中がたやすくできるようになり、二つの脳の結合によるシナジー効果で創造的なアイデアが出やすくなる。
五、もう一度、自分が直面している課題や目的を強く意識する。
六、この段階で浮かんできた考えが、自分の満足のいくものかどうかを評価する。満足できなければさらに集中を継続する。
七、日頃から問題意識を広げ、深め、問題解決度の満足水準をさらに高めるよう努力する。集中によって生まれるアウトプットの量は、問題意識の広さや深さ、満足水準の高さに比例するからである。
★全身集中術をマスターする
本当に集中力を高めるためには、頭脳と身体の両方の集中が不可欠である。
まず、脳のほうから説明すると、「右脳集中術」がある。右脳はイメージを司る脳として知られているが、右脳を集中させるには、風景や絵画の観察もいいが、イメージを思い浮かべるときにできるだけ細部までくっきり思い浮かべる癖をつけることである。そうしないと肝心の点が意識のなかから欠落して、ミスやトラブルを起こしやすくなる。
次に、左脳集中術をマスターしよう。「こうだからこうなる」「これとこれはこんな関係になる」というように、まず言葉で文句や文章を考える、事柄の筋道をつける、言葉を整理する、いろんな考えのなかから理由をつけて一つを選ぶ、複数のものを頭のなかに並べて比較する、結論をだす――といったような頭を働かせる癖をつけること。
また、全身集中術については、身体を動かしながら「考える身体=集中する身体」をつくっていくことである。そのためには、仕事や趣味、スポーツで要求される身のこなし、動作、技能については、自分がポイントと意識したところを正確に理解し、実際に身体を動かし、納得するまで反復練習する。身体を動かさないときは筋肉だけでも動かす。単に知識として覚えるだけではなく、身体でも覚えるようにすれば、集中力はいちだんをアップする。
人間誰もが集中力をもっている。集中する知性がある。集中力は三〇分から一時間しかもたないという方もあるが、そんなことはない。一カ月でも二カ月でも集中力を持続することは可能である。しかし、そんなことを考えるより、ここで紹介したノウハウにまず取り組んでいただきたい。
|
|
|
|
|
|
|
|
JAPAN ダーツスクール 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
JAPAN ダーツスクールのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 2位
- 広島東洋カープ
- 55343人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37148人
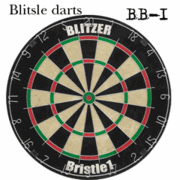







](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/93/34/659334_243s.jpg)















