これはHPからの抜粋です。
色々と参考文献はありますので、自分でも調べてみてください。
集中力を鍛える方法
★「集中力」は成功への最強アイテム
私たちは何かものごとを成し遂げようと努力した結果をふりかえって、「あの場面で集中力を発揮できなかったからうまくいかなかった」とか「〇〇にとても集中できたから良い成績が残せた」とよく言うことがよくある。とくに身体を使うスポーツ選手には、ここ一番のときに「集中力」を口にする人が多いようである。あるいは「自分は集中力を欠いている」と考えている人が世の中には意外に多いことに驚く。
では、この「集中力」とはいったい何か。どうやって身につけることができるのだろうか。
「集中力」を乱暴に表現してしまうと、「とても不思議な働きをする、生産性の高い、パワフルな能力」のことである。それは、仕事でも勉強でも一生懸命取り組んだときと、ダラダラと取り組んだときとでは、おのずとその成果に雲泥の差が出ることを私たちは体験上から知っている。
またその逆に、いったん集中力が途切れると気持ちがズタズタになり、元の集中状態へ戻るには相当な長い時間を必要とすることもよく知っている。
では、人が「集中している状態」とはどのような状態なのだろうか。そんな状態を表して、「一心不乱に」とか「忘我の境地」「ものに憑かれたように」と表現する。例えば、人間がある一点に集中したときにどうなるのかという例を二つあげよう。
一つは、日本囲碁史上において屈指の棋士と評された名人・碁所、第一二世本因坊丈和の話である。彼は、江戸時代後期に大活躍し棋士だが、御城碁で強敵と対戦したときに、難局を打開するための一手を一晩かけて考えぬき、翌未明、強敵を打破できる妙手を考え得たとき、丈和は糞尿にまみれていたそうである。相手を打ち負かす囲碁の手の発見に集中していたあまり、自分がいつ奪糞し、漏尿したかまったく気がつかなかったのである。 もう一つは、芸術の世界では大御所の北大路魯山人である。料理ばかりではなく、陶芸、絵画などに特異の才能を発揮した人として知られている。彼は、いったん集中しだすと「シュウシュウ」と鞴のような息を吐きながら、陶芸でも、料理でも絵画でもすごいスピードで仕上げていったと言われている。
わずかこの二人をみるだけでも、人がいったんものごとに集中したときの状態というのは計り知れない何かを生む可能性が高いことを伺い知ることができる。
つまり、人が本当に集中すると、ふだんの自分には絶対できなかったはずのことがいとも簡単にできてしまうのである。まさに自分の才能や身体的に機能をまったく凌駕した自分がそこに生まれてくるようなもので、これこそ集中力がもたらす驚くべき能力だと言ってよいだろう。
また、重要なことは、集中力はどんな人にも内在している能力で、集中力の引き出し方如何によっては、これもまた誰でも「集中人間」になることができる。
集中力は、スポーツでも勉強でも、創作活動でも対象の如何を問わず、普遍的に作用する能力で、計算力のように活用範囲が限定される能力ではないことである。
そして、集中力は誰にとっても有益不可欠な能力であり、ビジネスをはじめ社会生活のあらゆる場面で、豊かなアウトプットをもたらしてくれるものであり、自分が目標とする分野で成功するための最強の武器の一つになるといってもいいだろう。
★集中力のメカニズム
脳のソフトウエア理論である脳力学(ブレーンダイナミクス)と生理学の観点から集中(集中力)を分析すると、そのメカニズムは次のようなことが言える。
集中及び集中力の生理機構としては「第一次集中(第一次集中力)」と「第二次集中(第二次集中力)」の二つがある。第一次集中力の機構は首の後ろの延髄付近の脳幹部にあり、第二次集中力の機構は額の裏側を中心とする大脳新皮質部がある前頭葉部にある。 このように、集中力が二段階になっているのは、私が「ダム調節作用」と呼んでいる仕掛けと関連づけて説明するとわかりやすい。脳は、あらゆる情報をインプットあるいはキャッチしているわけではない。そんなことをしていると脳の情報処理機能はいっぺんにパンクしてしまう。
そうならないために、第一集中機能である延髄付近の脳幹部が、情報が入ってくる情報の量や質を規制する。ちょうど、電車のなかや喫茶店など、人の話し声をふつうは無視しているが、あるキーワードに敏感に反応することがある。つまり、私たちは無意識のうちに周囲の音や言葉を選択している。それを行うのが延髄付近にある脳幹部である。
第一次集中の特徴はもっとある。あくびを例にとって説明してみよう。
私たちがあくびをする状態というのは、とくに身体が疲れていたり、眠気を要求しているときである。しかしその一方で、あくびには、身体の疲れを解きほぐし、精神の集中を解除するという働きが含まれている。あくびをしたあとにフッと身体から気がぬけたような感じを覚えたことは何度もあるはずである。 あくびをつかさどる「あくび中枢」は、第一集中機能のある延髄付近にある。ということは、あくびには人間の身体の一番深い部分にある集中までも解除し、緊張を身体の底から芯まで取り除いてくれる働きをあることが言えるのである。
ということは「第一次集中」は、情報の総量規制をする一方で、潜在的、無意識的、身体的に、機能するといえる。
一方、第二次集中はどうか。第二次集中は、大脳新皮質の前頭葉部分にあり、集中が知的、顕在的、自覚的に進行していく。前頭葉は、思考活動を活発に行うと同時に、創造や意志、判断、構想、統制、自我、言語中枢をつかさどる大事な場所であある。
ここで大脳と小脳の機能の違いを少し述べておきたい。
大脳は、知的な思考活動が活発に行われる場である。例えば、野球選手が打てなくてスランプになったとしよう。どうやったら以前の打てる状態になるか、フォームはどうか、などを考える(思考する)のが大脳なのである。
そして、大脳がいったん決めたことを実行していくのが小脳である。例えば、投手が投げたボールを反射的に大脳で決めたフォームで打つのである。それを習慣づけたりする。このことから、大脳は思考の場だが、小脳は「習慣・反射の場」だと言われている。
したがって、思考の集中力を発揮するのは大脳で、反射や反復的な集中は小脳が発揮するというふうに、大脳と小脳における集中力の機能は、お互いに違うということがいえる。 大脳と小脳の間は繊維で連携しあっており、たえずコミュニケーションが行われている。大脳と小脳が完全に没交渉ということではありえない。
しかし、一流選手であればあるほど大脳と小脳の集中力とその機能をうまく交互に使いながら、スランプを克服したり、新しい技を発見したりしている。例えば、大脳右側半球(右脳)で集中的にイメージトレーニングした内容を、小脳を使って形にしたり、マニュアル化やプログラム化したりできるのは、大脳と小脳のコミュニケーションを頻繁に行っているからである。
したがって、私は集中力を次のように定義している。
「内発性または外発性の動機づけ要因により動機づけられ、ある課題の達成に向かって知的(あるいは身体的)なさまざまの個別能力を組織化するというソフトウエア(生理機制)を使って、より短時間内にアウトプット(生産性やサービス、プロダクツなど)を生み出す多産性の『超自的』ネットワーク能力であること」
集中力には、記憶力や計算力、想像力や分析力といったある特定の能力を組織化するのではなく、私たちがもっているありとあらゆる、言葉を変えればすべての能力を強力に顕在化させ、組み合わせ、統合する力が備わっているのである。
だからこそ、一+一が二ではなく、三にも四にも五にもなる相乗効果が現れるのは、集中力の効果がなのである。
ではどうやったら集中力を発動することができるのだろうか。集中力を発動するのは環境が要因なのか、動機なのかという点について述べてみよう。
★集中力の発動要因とは
ただ万遍なく毎日を過ごしていては集中力を短時間で発揮することはできない。一般に、集中力を発動させる要因には、内発性と外発性という二つの要因があると言われている。 内発性の要因は自分の心やあるいは身体的な欲求から発するもので、好奇心や興味、関心、問題意識、好きなこと、楽しいこと、愉快なこと、面白いこと、情熱、遊び心、研究、心などが要因となる。
昆虫学者として有名なアンリ・ファーブルは、幼い頃から一日中、道端にしゃがんで昆虫を観察していたと言われし、中国から日本に帰化し、昭和の天才棋士と言われた呉清源は、少年の頃から毎日数十時間かけて碁の勉強を熱心にしたという。
長い時間をかけて一つのことに集中できるのは、自分がそのことを心の底から好きでないとできるものではない。
一方、外発性の要因として考えられることは、社会的な評価が高いことや仕事上で必要性の高いこと、組織の一員として果たすべき役割が大変重要なこと、同僚や上司だけでなく家族からも期待されていること、報酬や待遇がべらぼうに高いことなどがある。それが集中力を発揮する要因となることは、日常生活で感じられている方も多いのではないだろか。
あるいは、逆境に自分がおかれたときに集中力を発揮することもある。
よく言われるのが「火事場の馬鹿力」である。人は災難に直面したときに思いがけない能力を発揮することがあるが、その発信源となるのが集中力である。
家が火事になったときに、小柄な女性が自分の体重の倍以上もあるタンスなどを抱えて運び出すことができるのは、集中力のポテンシャルが非常に高くなったためである。そして、火事騒ぎがおさまってから、「どうして自分の体重の倍もあるものを持ち出せたのだろうか」と不思議に思うのである。
「火事場の馬鹿力」に類似した話として次のような体験をした男性がいる。仙台市に住むこの男性はある日、中学生の息子と二人で近所の遊歩道を散歩していたら、突然、茂みからツキノワグマが襲いかかってきた。そのときその男性は息子と守らなければならないという親の使命感と「死んでたまるか」という切実な思いから、襲いかかるツキノワグマを無我夢中で払いのけていたら、熊を投げ飛ばしていたそうである。
これなども、極限状態におかれた人間の集中力のなせる技としかいいようがないが、言葉を変えれば、集中力によって限界と思われていた自分の能力を超えることができるし、集中力や人間をより成長、拡大、充実させる自己進化型の能力といってもいいだろう。
★集中状態とは何か
人間は集中力を最大限に発揮できたときに、精神的、身体的にどんな状態になるのだろうか。
よく武道やスポーツ、座禅などで言われるのが「無我の境地」「無心の境地」である。そうした状態に陥ったときに、実力以上の能力を発揮して、新記録やとんでもないプレーー(ゴルフでいうとホールインワンのようなのも)をやってのけることがある。そうしたスーパープレイを成し遂げたときというのは、精神状態は、一つは「ゾーンに入る」という。そのゾーンにはいると、バラバラになっていた精神や意識が目的に向かって統合する。そうすると精神的にすごく落ち着いて、エネルギーが身体にみなぎるという非常にパワフルな状態になる。
もう一つは、「フローになる」と言われる。感覚用語だが、フローとは「流れ」という意味だが、そうした感覚はある意味のやすらかさや落ち着き、静かな自信といったものが組合わさったような状態だと言われる。例えば、大観衆の前では緊張のあまり怖くなったり、逃げ出したいという気持ちに襲われることがあるが、「フロー」の状態に入ると、大観衆がすべて自分の味方をしている、応援しているというふうに思えてくるらしい。
したがって、オリンピックなどの大観衆が集まる大会などで、目標以上の成績がだせるかどうかは、「フロー」の状態に入れるかどうかである程度決まると言われている。一流の選手と言われる人たちは、ゾーンやフローの状態に自分を追い込むことができる人のことである。それは何もスポーツに限らず、文化、芸術やあるいは日常生活のさまざまな場面で、指摘されることである。
では、どうしたらゾーンやフローの状態に入れるのか。
よくメンタルトレーニングとかメンタル・コントロールと言われるが、そこには明確な問題意識や目的意識が必要である。そうした意識があれば、工夫したり、いろいろなことを試したり、そういったことを繰り返し取り組むことによってつくりあげていく自分自身のスキルや自信などが、背景にある。
また、一流選手になればなるほど、集中に入るために一連の儀式(手続き、集中儀式)をもっている。「集中儀式」を行うことで自分をもっともいい集中状態に、短時間でもっていくことができるのだ。それはある意味では集中へのプログラムといえる。そうした自信や技術に裏打ちされたプログラムを自分がもっているか否かで、ゾーンやフローへすばやく入れるかどうかが決まるし、それが一つの集中へのノウハウになっている。
集中儀式は、どんなみっともないものでもよい。徳川家康は、深く考えこむときには知らず知らずのうちに爪をかんでいたという。あの老獪な家康の集中儀式としは意外に感じるが、精神集中に欠かせない儀式は人それぞれであっていい。その集中儀式を発見するかぎは、過去の成功体験を思い浮かべ、そのときにどんな動作をしていたかを考えていけば発見できるだろう。
作家の渡辺淳一は、原稿の締め切りが迫っているのに書けないときは、目の前に大きな紙を広げ、その上に頭をもっていき、両手でごしごし頭をかく。フケが出、抜け毛が紙の上に落ちる。その動作を気のすむまで繰り返す。そのうち紙の上にフケや抜け毛がたまってこんもりした山をつくる。紙を両手で持ち上げ、左右にゆさゆさ傾ける。そうすると精神が原稿を書くことに集中し、構成や書き出しの文章が浮かんでくると、ものすごい速さで原稿を書いていくそうである。
渡辺淳一の精神集中法は、脳の生理にかなった方法である。よく作家が文章を書けなくなったときに「頭をむしる」という話を聞くが、頭をごしごしかけば大脳皮質が刺激され、活性化する。そうすると思考が活発にない、頭が非常にさえた状態になると、精神集中ができるのは当然なのである。
ところで、一般的には、集中状態にはそれぞれのレベル(七段階)があると言われている。
第一段階のレベルは、「そろそろ気持ちを引き締めて仕事にとりかかろう」とか「ぼちぼちシャキッとしなきゃ」といった気持ちが生まれることである。集中力への動機づけである。
第二段階になると、いらいらがなくなり、気が散らなくなり、気持ちが落ち着いてくる。 第三段階は、浮気感情や逃避感情がなくなり、「あれもやってみたい、これもやってみたい」とか「(プレッシャーが大きくて)この場から逃げ出したい」という気持ちが断ち切られる。
第四段階になってくると、考えや方向性が一つにまとまってくる。それまではバラバラだったがものがしだいに秩序や順序づけられ、関係性がはっきりしてくる。
第五段階は、これま外部に向かっていた思考のベクトルが内側に向かうようになる。外部から受けるプレッシャーなどが気にならなくなる。
第六段階は、対象あるいは課題といっていいが、それに対して没頭するようになる。
第七段階は集中の極限状態のことだが、先程説明したように「ゾーン」や「フロー」の状態に入る。最高の仕事ができたり、素晴らしいアウトプットが生まれるのが、第七段階の集中レベルに達したときである。
これらの七つの項目を、集中トレーニングのプログラムとして使用してもよいし、自分がどんな集中状態にあるかのチェックリストとして使ってもよい。
例えば、こんな体験をしたことはないだろうか。
喫茶店で本を読んでいるが、最初は周囲の景色や人の会話が気になって、ページをめくるのが遅いが、そのうちいつのまにか周囲のことが気にならなくなり、人の話し声が聞こえなくなるぐらい本に集中して、すごい速さでページをめくっているという状態になる。これが没頭している状態である。このことを知っておけば、自分がそういう状態になったときは、集中のレベルが第六段階にあるというわけで、そこまでいってなければ、もっと低い集中のレベルであることが理解できる。 ところが、第七段階の集中レベルになると、没頭レベルをはるかにしのぐ状態になる。
例えば、プロ野球の落合博満選手はかつて、全盛時代に常人離れした集中状態で試合にのぞんでいたことで知られる。彼は、試合が終わると、フロに入っても洗髪できないほど頭が痛んだそうだ。頭のてっぺんがぶよぶよになって、親指が頭のなかに入るような感じになったという。
そうした例は高度な精神集中の極致までいった人たち特有の共通症状らしい。チベットの高僧も、第七段階の集中に達した状態だと、頭のてっぺんがぐにゃぐにゃになり、指で押すといくらでも陥没したそうである。
また、大相撲五月場所で、横綱貴乃花が武蔵丸を優勝決定戦で敗った一番をみて、多くの人は貴乃花が現したものすごい集中力や気魄に感動したり、驚かれたかもしれない。それは、大相撲の最高位を守る横綱だけに備わる力なのかもしれない。
そられの例からもわかるように、集中するという活動は、大量のエネルギーを消費する。だから、集中した後は心身ともにぐったりす。また、集中はさまざまな能力を動員し、働かせるために、単純な脳活動よりもはるかにエネルギー(カロリーといってもよい)を食うのである。
したがって、自分の欲求や関心、好き、楽しいなどの感情や情熱自体がエネルギーやポテンシャルの高い、ハイテンションの能力とセンスが原動力となって、はじめて集中力が作動するのである。
こうした内発性能力やセンスが集中への根源的なパワーとなって、その強力なパワーが脳へ伝達されて、人は集中を高めていく。
しかし、より集中力を高め、やる気を引き出すために大切なことは、「睡眠」であり「休息」を必ずとることである。やる気があっても、集中力を高めていても、睡魔に襲われることがある。それは身体や精神が休息や安息を求めているという信号が脳から発信されているのである。そうした信号ができたときはその信号に素直に従うことが賢明である。
色々と参考文献はありますので、自分でも調べてみてください。
集中力を鍛える方法
★「集中力」は成功への最強アイテム
私たちは何かものごとを成し遂げようと努力した結果をふりかえって、「あの場面で集中力を発揮できなかったからうまくいかなかった」とか「〇〇にとても集中できたから良い成績が残せた」とよく言うことがよくある。とくに身体を使うスポーツ選手には、ここ一番のときに「集中力」を口にする人が多いようである。あるいは「自分は集中力を欠いている」と考えている人が世の中には意外に多いことに驚く。
では、この「集中力」とはいったい何か。どうやって身につけることができるのだろうか。
「集中力」を乱暴に表現してしまうと、「とても不思議な働きをする、生産性の高い、パワフルな能力」のことである。それは、仕事でも勉強でも一生懸命取り組んだときと、ダラダラと取り組んだときとでは、おのずとその成果に雲泥の差が出ることを私たちは体験上から知っている。
またその逆に、いったん集中力が途切れると気持ちがズタズタになり、元の集中状態へ戻るには相当な長い時間を必要とすることもよく知っている。
では、人が「集中している状態」とはどのような状態なのだろうか。そんな状態を表して、「一心不乱に」とか「忘我の境地」「ものに憑かれたように」と表現する。例えば、人間がある一点に集中したときにどうなるのかという例を二つあげよう。
一つは、日本囲碁史上において屈指の棋士と評された名人・碁所、第一二世本因坊丈和の話である。彼は、江戸時代後期に大活躍し棋士だが、御城碁で強敵と対戦したときに、難局を打開するための一手を一晩かけて考えぬき、翌未明、強敵を打破できる妙手を考え得たとき、丈和は糞尿にまみれていたそうである。相手を打ち負かす囲碁の手の発見に集中していたあまり、自分がいつ奪糞し、漏尿したかまったく気がつかなかったのである。 もう一つは、芸術の世界では大御所の北大路魯山人である。料理ばかりではなく、陶芸、絵画などに特異の才能を発揮した人として知られている。彼は、いったん集中しだすと「シュウシュウ」と鞴のような息を吐きながら、陶芸でも、料理でも絵画でもすごいスピードで仕上げていったと言われている。
わずかこの二人をみるだけでも、人がいったんものごとに集中したときの状態というのは計り知れない何かを生む可能性が高いことを伺い知ることができる。
つまり、人が本当に集中すると、ふだんの自分には絶対できなかったはずのことがいとも簡単にできてしまうのである。まさに自分の才能や身体的に機能をまったく凌駕した自分がそこに生まれてくるようなもので、これこそ集中力がもたらす驚くべき能力だと言ってよいだろう。
また、重要なことは、集中力はどんな人にも内在している能力で、集中力の引き出し方如何によっては、これもまた誰でも「集中人間」になることができる。
集中力は、スポーツでも勉強でも、創作活動でも対象の如何を問わず、普遍的に作用する能力で、計算力のように活用範囲が限定される能力ではないことである。
そして、集中力は誰にとっても有益不可欠な能力であり、ビジネスをはじめ社会生活のあらゆる場面で、豊かなアウトプットをもたらしてくれるものであり、自分が目標とする分野で成功するための最強の武器の一つになるといってもいいだろう。
★集中力のメカニズム
脳のソフトウエア理論である脳力学(ブレーンダイナミクス)と生理学の観点から集中(集中力)を分析すると、そのメカニズムは次のようなことが言える。
集中及び集中力の生理機構としては「第一次集中(第一次集中力)」と「第二次集中(第二次集中力)」の二つがある。第一次集中力の機構は首の後ろの延髄付近の脳幹部にあり、第二次集中力の機構は額の裏側を中心とする大脳新皮質部がある前頭葉部にある。 このように、集中力が二段階になっているのは、私が「ダム調節作用」と呼んでいる仕掛けと関連づけて説明するとわかりやすい。脳は、あらゆる情報をインプットあるいはキャッチしているわけではない。そんなことをしていると脳の情報処理機能はいっぺんにパンクしてしまう。
そうならないために、第一集中機能である延髄付近の脳幹部が、情報が入ってくる情報の量や質を規制する。ちょうど、電車のなかや喫茶店など、人の話し声をふつうは無視しているが、あるキーワードに敏感に反応することがある。つまり、私たちは無意識のうちに周囲の音や言葉を選択している。それを行うのが延髄付近にある脳幹部である。
第一次集中の特徴はもっとある。あくびを例にとって説明してみよう。
私たちがあくびをする状態というのは、とくに身体が疲れていたり、眠気を要求しているときである。しかしその一方で、あくびには、身体の疲れを解きほぐし、精神の集中を解除するという働きが含まれている。あくびをしたあとにフッと身体から気がぬけたような感じを覚えたことは何度もあるはずである。 あくびをつかさどる「あくび中枢」は、第一集中機能のある延髄付近にある。ということは、あくびには人間の身体の一番深い部分にある集中までも解除し、緊張を身体の底から芯まで取り除いてくれる働きをあることが言えるのである。
ということは「第一次集中」は、情報の総量規制をする一方で、潜在的、無意識的、身体的に、機能するといえる。
一方、第二次集中はどうか。第二次集中は、大脳新皮質の前頭葉部分にあり、集中が知的、顕在的、自覚的に進行していく。前頭葉は、思考活動を活発に行うと同時に、創造や意志、判断、構想、統制、自我、言語中枢をつかさどる大事な場所であある。
ここで大脳と小脳の機能の違いを少し述べておきたい。
大脳は、知的な思考活動が活発に行われる場である。例えば、野球選手が打てなくてスランプになったとしよう。どうやったら以前の打てる状態になるか、フォームはどうか、などを考える(思考する)のが大脳なのである。
そして、大脳がいったん決めたことを実行していくのが小脳である。例えば、投手が投げたボールを反射的に大脳で決めたフォームで打つのである。それを習慣づけたりする。このことから、大脳は思考の場だが、小脳は「習慣・反射の場」だと言われている。
したがって、思考の集中力を発揮するのは大脳で、反射や反復的な集中は小脳が発揮するというふうに、大脳と小脳における集中力の機能は、お互いに違うということがいえる。 大脳と小脳の間は繊維で連携しあっており、たえずコミュニケーションが行われている。大脳と小脳が完全に没交渉ということではありえない。
しかし、一流選手であればあるほど大脳と小脳の集中力とその機能をうまく交互に使いながら、スランプを克服したり、新しい技を発見したりしている。例えば、大脳右側半球(右脳)で集中的にイメージトレーニングした内容を、小脳を使って形にしたり、マニュアル化やプログラム化したりできるのは、大脳と小脳のコミュニケーションを頻繁に行っているからである。
したがって、私は集中力を次のように定義している。
「内発性または外発性の動機づけ要因により動機づけられ、ある課題の達成に向かって知的(あるいは身体的)なさまざまの個別能力を組織化するというソフトウエア(生理機制)を使って、より短時間内にアウトプット(生産性やサービス、プロダクツなど)を生み出す多産性の『超自的』ネットワーク能力であること」
集中力には、記憶力や計算力、想像力や分析力といったある特定の能力を組織化するのではなく、私たちがもっているありとあらゆる、言葉を変えればすべての能力を強力に顕在化させ、組み合わせ、統合する力が備わっているのである。
だからこそ、一+一が二ではなく、三にも四にも五にもなる相乗効果が現れるのは、集中力の効果がなのである。
ではどうやったら集中力を発動することができるのだろうか。集中力を発動するのは環境が要因なのか、動機なのかという点について述べてみよう。
★集中力の発動要因とは
ただ万遍なく毎日を過ごしていては集中力を短時間で発揮することはできない。一般に、集中力を発動させる要因には、内発性と外発性という二つの要因があると言われている。 内発性の要因は自分の心やあるいは身体的な欲求から発するもので、好奇心や興味、関心、問題意識、好きなこと、楽しいこと、愉快なこと、面白いこと、情熱、遊び心、研究、心などが要因となる。
昆虫学者として有名なアンリ・ファーブルは、幼い頃から一日中、道端にしゃがんで昆虫を観察していたと言われし、中国から日本に帰化し、昭和の天才棋士と言われた呉清源は、少年の頃から毎日数十時間かけて碁の勉強を熱心にしたという。
長い時間をかけて一つのことに集中できるのは、自分がそのことを心の底から好きでないとできるものではない。
一方、外発性の要因として考えられることは、社会的な評価が高いことや仕事上で必要性の高いこと、組織の一員として果たすべき役割が大変重要なこと、同僚や上司だけでなく家族からも期待されていること、報酬や待遇がべらぼうに高いことなどがある。それが集中力を発揮する要因となることは、日常生活で感じられている方も多いのではないだろか。
あるいは、逆境に自分がおかれたときに集中力を発揮することもある。
よく言われるのが「火事場の馬鹿力」である。人は災難に直面したときに思いがけない能力を発揮することがあるが、その発信源となるのが集中力である。
家が火事になったときに、小柄な女性が自分の体重の倍以上もあるタンスなどを抱えて運び出すことができるのは、集中力のポテンシャルが非常に高くなったためである。そして、火事騒ぎがおさまってから、「どうして自分の体重の倍もあるものを持ち出せたのだろうか」と不思議に思うのである。
「火事場の馬鹿力」に類似した話として次のような体験をした男性がいる。仙台市に住むこの男性はある日、中学生の息子と二人で近所の遊歩道を散歩していたら、突然、茂みからツキノワグマが襲いかかってきた。そのときその男性は息子と守らなければならないという親の使命感と「死んでたまるか」という切実な思いから、襲いかかるツキノワグマを無我夢中で払いのけていたら、熊を投げ飛ばしていたそうである。
これなども、極限状態におかれた人間の集中力のなせる技としかいいようがないが、言葉を変えれば、集中力によって限界と思われていた自分の能力を超えることができるし、集中力や人間をより成長、拡大、充実させる自己進化型の能力といってもいいだろう。
★集中状態とは何か
人間は集中力を最大限に発揮できたときに、精神的、身体的にどんな状態になるのだろうか。
よく武道やスポーツ、座禅などで言われるのが「無我の境地」「無心の境地」である。そうした状態に陥ったときに、実力以上の能力を発揮して、新記録やとんでもないプレーー(ゴルフでいうとホールインワンのようなのも)をやってのけることがある。そうしたスーパープレイを成し遂げたときというのは、精神状態は、一つは「ゾーンに入る」という。そのゾーンにはいると、バラバラになっていた精神や意識が目的に向かって統合する。そうすると精神的にすごく落ち着いて、エネルギーが身体にみなぎるという非常にパワフルな状態になる。
もう一つは、「フローになる」と言われる。感覚用語だが、フローとは「流れ」という意味だが、そうした感覚はある意味のやすらかさや落ち着き、静かな自信といったものが組合わさったような状態だと言われる。例えば、大観衆の前では緊張のあまり怖くなったり、逃げ出したいという気持ちに襲われることがあるが、「フロー」の状態に入ると、大観衆がすべて自分の味方をしている、応援しているというふうに思えてくるらしい。
したがって、オリンピックなどの大観衆が集まる大会などで、目標以上の成績がだせるかどうかは、「フロー」の状態に入れるかどうかである程度決まると言われている。一流の選手と言われる人たちは、ゾーンやフローの状態に自分を追い込むことができる人のことである。それは何もスポーツに限らず、文化、芸術やあるいは日常生活のさまざまな場面で、指摘されることである。
では、どうしたらゾーンやフローの状態に入れるのか。
よくメンタルトレーニングとかメンタル・コントロールと言われるが、そこには明確な問題意識や目的意識が必要である。そうした意識があれば、工夫したり、いろいろなことを試したり、そういったことを繰り返し取り組むことによってつくりあげていく自分自身のスキルや自信などが、背景にある。
また、一流選手になればなるほど、集中に入るために一連の儀式(手続き、集中儀式)をもっている。「集中儀式」を行うことで自分をもっともいい集中状態に、短時間でもっていくことができるのだ。それはある意味では集中へのプログラムといえる。そうした自信や技術に裏打ちされたプログラムを自分がもっているか否かで、ゾーンやフローへすばやく入れるかどうかが決まるし、それが一つの集中へのノウハウになっている。
集中儀式は、どんなみっともないものでもよい。徳川家康は、深く考えこむときには知らず知らずのうちに爪をかんでいたという。あの老獪な家康の集中儀式としは意外に感じるが、精神集中に欠かせない儀式は人それぞれであっていい。その集中儀式を発見するかぎは、過去の成功体験を思い浮かべ、そのときにどんな動作をしていたかを考えていけば発見できるだろう。
作家の渡辺淳一は、原稿の締め切りが迫っているのに書けないときは、目の前に大きな紙を広げ、その上に頭をもっていき、両手でごしごし頭をかく。フケが出、抜け毛が紙の上に落ちる。その動作を気のすむまで繰り返す。そのうち紙の上にフケや抜け毛がたまってこんもりした山をつくる。紙を両手で持ち上げ、左右にゆさゆさ傾ける。そうすると精神が原稿を書くことに集中し、構成や書き出しの文章が浮かんでくると、ものすごい速さで原稿を書いていくそうである。
渡辺淳一の精神集中法は、脳の生理にかなった方法である。よく作家が文章を書けなくなったときに「頭をむしる」という話を聞くが、頭をごしごしかけば大脳皮質が刺激され、活性化する。そうすると思考が活発にない、頭が非常にさえた状態になると、精神集中ができるのは当然なのである。
ところで、一般的には、集中状態にはそれぞれのレベル(七段階)があると言われている。
第一段階のレベルは、「そろそろ気持ちを引き締めて仕事にとりかかろう」とか「ぼちぼちシャキッとしなきゃ」といった気持ちが生まれることである。集中力への動機づけである。
第二段階になると、いらいらがなくなり、気が散らなくなり、気持ちが落ち着いてくる。 第三段階は、浮気感情や逃避感情がなくなり、「あれもやってみたい、これもやってみたい」とか「(プレッシャーが大きくて)この場から逃げ出したい」という気持ちが断ち切られる。
第四段階になってくると、考えや方向性が一つにまとまってくる。それまではバラバラだったがものがしだいに秩序や順序づけられ、関係性がはっきりしてくる。
第五段階は、これま外部に向かっていた思考のベクトルが内側に向かうようになる。外部から受けるプレッシャーなどが気にならなくなる。
第六段階は、対象あるいは課題といっていいが、それに対して没頭するようになる。
第七段階は集中の極限状態のことだが、先程説明したように「ゾーン」や「フロー」の状態に入る。最高の仕事ができたり、素晴らしいアウトプットが生まれるのが、第七段階の集中レベルに達したときである。
これらの七つの項目を、集中トレーニングのプログラムとして使用してもよいし、自分がどんな集中状態にあるかのチェックリストとして使ってもよい。
例えば、こんな体験をしたことはないだろうか。
喫茶店で本を読んでいるが、最初は周囲の景色や人の会話が気になって、ページをめくるのが遅いが、そのうちいつのまにか周囲のことが気にならなくなり、人の話し声が聞こえなくなるぐらい本に集中して、すごい速さでページをめくっているという状態になる。これが没頭している状態である。このことを知っておけば、自分がそういう状態になったときは、集中のレベルが第六段階にあるというわけで、そこまでいってなければ、もっと低い集中のレベルであることが理解できる。 ところが、第七段階の集中レベルになると、没頭レベルをはるかにしのぐ状態になる。
例えば、プロ野球の落合博満選手はかつて、全盛時代に常人離れした集中状態で試合にのぞんでいたことで知られる。彼は、試合が終わると、フロに入っても洗髪できないほど頭が痛んだそうだ。頭のてっぺんがぶよぶよになって、親指が頭のなかに入るような感じになったという。
そうした例は高度な精神集中の極致までいった人たち特有の共通症状らしい。チベットの高僧も、第七段階の集中に達した状態だと、頭のてっぺんがぐにゃぐにゃになり、指で押すといくらでも陥没したそうである。
また、大相撲五月場所で、横綱貴乃花が武蔵丸を優勝決定戦で敗った一番をみて、多くの人は貴乃花が現したものすごい集中力や気魄に感動したり、驚かれたかもしれない。それは、大相撲の最高位を守る横綱だけに備わる力なのかもしれない。
そられの例からもわかるように、集中するという活動は、大量のエネルギーを消費する。だから、集中した後は心身ともにぐったりす。また、集中はさまざまな能力を動員し、働かせるために、単純な脳活動よりもはるかにエネルギー(カロリーといってもよい)を食うのである。
したがって、自分の欲求や関心、好き、楽しいなどの感情や情熱自体がエネルギーやポテンシャルの高い、ハイテンションの能力とセンスが原動力となって、はじめて集中力が作動するのである。
こうした内発性能力やセンスが集中への根源的なパワーとなって、その強力なパワーが脳へ伝達されて、人は集中を高めていく。
しかし、より集中力を高め、やる気を引き出すために大切なことは、「睡眠」であり「休息」を必ずとることである。やる気があっても、集中力を高めていても、睡魔に襲われることがある。それは身体や精神が休息や安息を求めているという信号が脳から発信されているのである。そうした信号ができたときはその信号に素直に従うことが賢明である。
|
|
|
|
|
|
|
|
JAPAN ダーツスクール 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
JAPAN ダーツスクールのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37845人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31947人
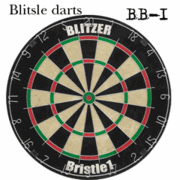







](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/93/34/659334_243s.jpg)















