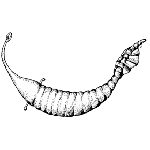- 詳細 2023年7月7日 10:00更新
-
タリモンストラム・グレガリウム(ツリモンストラム・グレガリウム 或いは ターリー・モンスター)
Tullimonstrum Gregarium(Tully Monster)
タリモンストラム・グレガリウムとは、1958年、北米イリノイ州のシカゴ近郊ある石炭紀後期のメゾンクリーク層のノジュールと呼ばれる石灰岩塊の中より(化石として)発見された奇妙な無脊椎動物である。
俗に“ターリーモンスター”(Tully Monster)と呼ばれる事もあり、これは発見者のフランシス・ターリー氏に因んで付けられたものである。
石炭紀後期(3億3300万年〜2億9000万年前)の汽水域(淡水と海水が混じる河口付近など)に群生していたとされ、その分類は諸説あるが、軟体動物門腹足綱異足目とされている。
『古生態図集・海の無脊椎動物』(福田芳夫 著・川島書店 刊)によると、ジョンソン氏とリチャードソン氏の両名は、タリモンストラム・グレガリウムは現在のカリナリア(ゾウクラゲ、軟体動物門腹足綱異足目)に最も近い存在と考えている。
体長は10cm〜30cm程度、骨格は無く、多数の節に分かれた長楕円形の身体からチューブ状の細長い吻部があり、その先端には小さな鋏(はさみ)があり、無脊椎動物であるにも係わらずこの鋏の中には八つの小さな歯が存在する。この部分で甲殻類や小魚、ケラゲ等を捕食していたものと想像される。
前出の『古生態図集・海の無脊椎動物』では、この鋏の基部中央辺りに口があり、そのまま体内を消化管が直行していると述べられているが、一説にはこの吻部は象の鼻のようなもので、この部分を使って捕獲した餌を口まで運んでいったのではないかとする説もある。
長く伸びた吻部の付け根辺りには、「バーオルガン」と呼ばれる一対の有柄の眼(或いはそれに相当する感覚器官)を有し、尾部には三角形の一対の鰭と、それらに垂直にややちいさめの鰭が付いており、これらの鰭が方向舵ど安定板の働きをしていたと考えられる。これらのことから、その柔らかな身体を縦に屈曲させながら水中を活発に泳ぎ回っていたものと考えられる。
捕獲されていたタリモンストラム・グレガリウム!
1988年4月、ネッシーで有名な英国ネス湖で、タリモンストラム・グレガリウムを思わせる生物が捕獲されていたというのだ。
4月某日、地元の漁師達がアーカード湾に船を出し漁をしていた。しかし、天候が悪化が悪化し、風も強く波m高くなってきたことから漁を中断し、移動することにした。漁師達は普段漁をしない比較的波の穏やかな南東の沿岸に網を打った。網が水深60mほどに達した頃、漁師達が網を引き上げてみると、予想外に多くの魚が掛かっていた。
しかし、網の中を良く見ると、そこにこれまで見たことの無い生物が三匹さかんに動いていることに気付く。
体長は30cmほど、全体に茶色がかった濃い灰色で、ヌメヌメと光る体表。長い首のようなものを持ち、頭部と思われる部分からは短く柔らかい触角のような物が二本、出たり引っ込んだりしている。その頭部?にある口はノコギリ状の鋭い歯があり、舌のようなものはなかった。
首の付け根には、一対の前肢のような突起物を持ち、首と同程度の長さの胴体は太く、いくつものリング状のくびれがあり、背中らしき部分のくびれのいくつかを膨らましている。尾と思われる部分には三角形の尾鰭のようなものがあった。
長い間漁師をしている彼らにもそれが何であるのか解らず、例えるなら、「太い一歩足のイカ」か「タコやナマコの仲間」のようだったと言う。
漁師達は地元の漁業組合に無線で連絡を取り、この生物の正体を確認しようとしたが、実物を見せないことには無線だけでは埒(らち)が開かないので、漁船の生簀にこの謎の生物を入れ、漁港に戻ることに。漁港に着くと漁業組合の関係者や漁師達が待っていて、問題の生物を見てもらったが、誰一人としてそれが何なのかさえ解らないという状態だった。
そこで、これは新種の生物かも知れないという事になり、英国科学庁に連絡をすることとなった。
連絡を入れて間もなく、政府の関係者と名乗る連中が港に現れた。彼らは、捕獲した謎の生物を見せるように漁師達に迫った。このような田舎町に政府の関係者が直々に来るものかと漁師達は不審に思いつつも、彼らをその生物が入った水槽まで案内した。
そこで、政府の関係者と名乗る連中は、しばらくその生物を興味深そうに観察すると、学者と思われる人物と何やら専門用語混じりで話し始めた。そして、おもむろに彼らは漁師達にこの生物を預からせて欲しいと言ってきた。
政府の関係者と名乗る以上、漁師達は無碍に拒むこともならなかった。
やがて、連中は手際よく水槽ごと運び出し車に載せると、何処へとも無く走り去っていった。
その後、政府からの連絡は無かったという・・・
この話には後日談がある。
真偽の程は定かではないが、この時捕獲された三匹の謎の生物は、後に英国政府関係のある研究者の手に渡ったという。
そして、三匹のうち一匹が英国政府により極秘裏に飼育。残り二匹は米国に空輸されたのだというが、その後の消息は不明である。
その後、英国によるものか米国によるものかは定かではないが、この謎の生物こそが。3億年近く前に絶滅したとされる「タリモンストラム・グレガリウム」だったというのである。
参考までに書くと、生きた化石と呼ばれる「シーラカンス」は6500万年前に絶滅したとされていた。
余談になるが、このタリモンストラム・グレガリウムが何らかの理由で巨大化したもの、或いはその近縁種がネッシーの正体だとする説を唱えた人物が居る。
最初にこの仮説を唱えたのは“怪獣ハンター”F・W・ホリディなる人物である。
この説はタリモンストラム・グレガリウムの生態がよく解らなかった事に加え、現存する化石は最大でも30cm程度だった事から珍説として一蹴され、現在ではこの仮説はほとんど支持されていない。
しかし、その反面、次の様な考察をされる方も居られる。
無脊椎動物のような原始的な器官構造をした生物はエネルギー消費量が少ないため、他の湖沼怪獣の候補よりも食事の量が少なくてすむかもしれない。また一部の軟体動物に見られるように環境に応じた性の転換が可能だとすれば、限定された湖という環境の中でも個体数は比較的少数に維持したまま種を存続することも可能ではないかというものである。参考まで書くと、地球上で最大の生物とされる無脊椎動物の「クダクラゲ」(刺胞動物門ヒドロ虫綱クダクラゲ目)は最大50m(一説には40mとも)にもなる。
古代生物の中では、ドイツで発見されたアンモナイト「Pachydiscus seppenradensis」の化石(白亜紀)のように直径2mに達する種もあった。それゆえ、古代から生き残ったタリモンストラム・グレガリウム或いはその近縁種が進化し巨大化したものではないかというのである。
その他、賛否両論かとは思うが、「タリモンストラム・グレガリウム=ネッシー」説の根拠として以下の様な理由が挙げられている。
太古、ネス湖は海と繋がり汽水湖状態であった。これは、河口の汽水域に棲んでいたとされるタリモンストラム・グレガリウムの生息条件と一致する。
無脊椎動物であるため、死後腐敗し水に溶けてしまうので、その死体はおろか骨一本も発見されない。
身体を縦に屈曲させて泳いでいたと想像されるその遊泳方法は、ネッシーの目撃例と酷似している。これが、チョウザメ等であれば身体を横に屈曲させて泳いでいるというのである。
胴体は節状になっており、湖面に浮かんだ時その姿があたかもコブが並んでいるように見える。
ネッシーの目撃情報には二本の角のようなものが生えていたという話もある。1988年4月にネス湖で捕獲されたタリモンストラム・グレガリウムと思われる生物にも頭部に二本の触角のような物があったという。
更に、巨大無脊椎動物の存在を裏付けるような事例も報告されている。
1998年1月、オーストラリア・タスマニア州フォーマルビーチで打ち上げられた奇怪な生物の死体は、胴体から首のような長い突起物があり、胴体側面には五枚のオール状の鰭のようなものがあったという。この死体には全く骨が無く、数日後腐敗して跡形無く消滅したという。
これらの事からも、ネッシーは進化し巨大化したタリモンストラム・グレガリウムの生き残り、或いはその近縁種ではないかというのである。
※トピックはご自由に作成下さい。
ただ、コミュニティの趣旨と全く違うトピや、誹謗中傷や管理人が不適切と判断した書き込みは事前の通知なく削除させて戴く場合が有ります。悪しからずご了承下さい。
【 参考 】
『古生態図集・海の無脊椎動物』
福田芳夫 著・川島書店 刊
ツリモンストラム・グレガリウムの実態
http://www2.pl ala.or. jp/dais injitu/ UMA/tur ly.html
川崎悟司イラスト集・ツリモンストラム
http://www.geo cities. co.jp/N atureLa nd/5218 /turimo nsutora mu.html
Tully Monster Wikipedia(英語)
http://en.wiki pedia.o rg/wiki /Tully_ Monster
Amphibian(英語)
http://www.mus eum.sta te.il.u s/exhib its/sym bols/fo ssil.ht ml
The Tully Monster(英語)
http://www.isg s.uiuc. edu/ser vs/pubs /geobit s-pub/g eobit5/ geobit5 .html
Illinois: Tullimonstrum gregarium (state fossil) (英語)
http://www.sta tefossi ls.com/ il/il.h tml
Aimals Past and Present-Learn about the Tully Monster(英語)
http://www.urb anext.u iuc.edu /animal s/tully .html
ミニ・ネッシー(ベビー・ネッシー)
http://umafan. blog72. fc2.com /blog-e ntry-21 0.html
古代生物/無脊椎動物/未確認生物/UMA/タリモンストラム・グレガリウム/ツリモンストラム・グレガリウム/ターリー・モンスター/Tullimonstrum Gregarium/Tully Monster/ネッシー/ゾウクラゲ/カリナリア/クダクラゲ/アンモナイト/
困ったときには