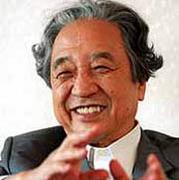大学の講義用に作成したものですが、梅原猛の日本文化論の概略的な理解にお役に立てばと思いまして掲載します。これをたたき台に活発な議論をお願いします。
◇◇◇◇◇◇梅原猛の日本文化論―異文化理解の前提としてー◇◇◇◇◇◇
日本人は何主義か?
倫理学の講義の時などに、「ギリシア人は主知主義で、中国人は道義主義と言われていますが、では日本人は何主義ですか?」と質問しますと、ほとんどの学生諸君は「わかりません」と応えます。これは大変困ったことですね。日本人の大学生までが、日本人の考え方、感じ方の特色、日本人の良さについて知らないで通しているのですから。つまり異文化理解をする前に、自文化理解ができていないのです。自文化理解も出来ていないのに異文化理解ができるはずはありません。というより、日本文化や日本思想自体が現在の日本人にとっては異文化だということなのかもしれませんね。
日本人の民族性は情を重んじる主情主義なのです。それは本居宣長が「もののあはれを知る心」を大和心として強調し、儒教や仏教の賢しらを退けようとしたことによって、定着したわけです。桜の花が咲き誇っているのを見て晴れやかな気持ちになったり、見たまま感じたまま物になりきって心が動くのがもののあはれです。ものに心が動くというのは、その対象はもちろん人間以外のものに限りません。人間に対する自然な情も入ります。宣長は『源氏物語』を最高傑作と評しましたが、それはもののあはれを文学的価値として確立して、作品全体に貫いているからです。
本居宣長の国文学的な国粋主義は、儒教や仏教伝来以前の日本が本来的な日本であったとして、儒教や仏教に汚染されていない日本を『古事記』『日本書紀』を通して明らかにしようとしました。宣長は、『日本書紀』は純然たる漢文で書かれているので、漢心(からごころ)が混ざっていると考え、『古事記』は古典中国語を基本に日本独特の表記を交えた、いわゆる「変体漢文」であり、漢文で表せない大和心を表そうと苦心しているので高く評価しています。
儒教や仏教に汚染されていない大和心といいましても、『古事記』の記述にも、海外の神話を下敷きにしているところもありますので、純国産を求めるのは無理があります。日本神道と呼ばれるものも、中国の道教の焼き直しの面もあり、道教との比較検討がもっと進まなければ、その独創性にはあいまいなところがあります。また逆に儒教や仏教思想も日本に定着して、人々の暮らしに大きな影響を与えていますので、日本文化からそれらを差し引くというのは、乱暴な議論です。それより定着した仏教や神道や儒教から日本文化を論じるという方が、日本文化を論じる場合に現実的だと思われます。
梅原猛の日本文化論への歩み
□梅原猛は1925年3月20日生まれで、現在84歳です。終戦の年1945年に京都大学文学部哲学専攻に合格したのですが、入学式から郷里の愛知県の実家に戻ると召集令状が来ていて、戦争が終わるまで、九州で軍隊生活でした。京大生の二等兵ですから格好のいじめの的だったかもしれません。でもなんとか生き残って9月に大学に戻ったのです。でも戦争で無意味な死を見ていたためか、虚無的な気分が抜けずに、ハイデッガーの実存哲学を死への哲学と捉えて、そこにのめりこんでいたわけです。そこで養母が心配して嫁を世話しまして、貧しいながらも家庭の幸福を築こうという生活の中で、生きる道を見出していったのです。
□哲学青年ですから死を見つめて哲学しているのが本当の自分で、小鳥が暖め合うような家庭の幸福は仮面の自分だと思っていたのに、仮面と自分の区別がなくなっていったわけです。それで哲学で身を立てなければならないのだけれど、西洋哲学はギリシア・ローマの古典古代からの伝統と、ユダヤ・キリスト教の伝統の下で出来上がっているわけでして、ニーチェやハイデッガーを研究しても、それを解釈、解説することに終わって独創的な哲学はできっこないと思ったわけですね。それで長いことスランプが続いたわけです。彼は独創的な哲学書が書けないのだったら、哲学書は出さないと決めていたので、なんとかしなければならなかったのです。
□そこで彼は理性より感情に注目したのです。落ち込んでばかりはいられないので、敗戦後の厳しい現実の中で、たくましく復興してくる時に庶民が求めていたのは笑いなのですね。それで笑いの研究をします。ちょうど戦後15年たって日米安全保障条約改定反対闘争が盛り上がったころです。京都から大阪の寄席に通ってノートをとっている哲学者がいるということで、面白がられて朝日新聞に「笑いの研究」を連載したわけです。これが梅原猛のマスコミデビューですね。
□笑いなどの感情にも民族性や宗教的背景があることに気付き、感情論を深めるためにも日本文化や日本の宗教を知らなければならないと思ったのです。つまり西洋哲学の研究ばかりやっていても、西洋人以上に西洋文化を知らない限り、そのエッセンスである西洋哲学が創造できるはずかないわけです。日本人は東洋文化や日本文化を研究し、日本の宗教を学んでこそ、それを土壌にした独創的な哲学が生まれるはずだということです。それで日本の伝統文化や宗教を学び始めたわけです。
□1960年代当時はいわゆる仏像ブームがありました。古寺を回りまして、そこの仏像を鑑賞しようというものです。私の高校は大阪府立泉尾高校でしたが、そこには国語に国文学を折口信夫に師事した堀内民一先生がおられまして、しきりに大和の寺と仏像の鑑賞を薦めておられました。敗戦国日本にとって日本にはこんな深い精神的な味わいのある伝統文化があるという事は、大きな心の支えだったわけです。
□梅原猛はNHKで1964年に「仏像―かたちとこころ」の総合司会をしました。仏像といえば釈迦如来像、薬師如来像、観世音菩薩像、大日如来像、阿弥陀如来像、地蔵菩薩像などが多いわけですね。仏像を理解しようとすれば当然、密教や顕教の深い理解が必要で、空海や最澄と必死で格闘したわけです。まあ日本仏教の世界にのめりこんでいったわけです。
近代知識人の宗教的痴呆を嘆く
□梅原猛は、当然近代日本の知識人たちの代表的な日本文化論に眼を通したわけですが、そこで彼は愕然としたわけですね。日本文化の伝統に仏教思想がきちんと位置づけられていないわけです。彼は廃仏毀釈後の日本は、「天皇制の内圧」によってまともに日本文化を評価できなくなっていると感じたのです。その状況を彼は「宗教的痴呆」とまで口を極めて喝破したのです。つまり「馬鹿野郎!」と叫んだわけですね。もちろん批評をするときに相手を「アホ馬鹿」呼ばわりしてはいけませんが、相手が超一流だけにその勇気は褒めるべきでしょう。
□1966年に病気で一ヶ月ほど入院したりして健康不安から、もうすぐ死ぬのではないかと思い、自暴自棄になって大胆な自説を展開するきっかけになったと言ってますが、6月に「明治百年における日本の自己誤認ー日本人の宗教的痴呆ー」を『日本』に8月に「日本文化論への批判的考察ー鈴木大拙・和辻哲郎の場合」を『展望』に発表しました。それらで、鈴木大拙、和辻哲郎、柳宗悦、丸山真男といった代表的な岩波文化人をなんと「宗教的痴呆」で一括したわけです。これらの論文は1967年に『美と宗教の発見-創造的日本文化論ー』として筑摩書房から出版されました。これが梅原猛の最初の単著です。
禅宗と浄土真宗以前に「日本的霊性」ないのかー鈴木大拙
□鈴木大拙(1870年 - 1966年)は『禅と日本文化』(岩波新書、正・続)『日本的霊性』(岩波文庫)で知られる、禅を世界に紹介した人です。西田幾多郎とは石川県立専門学校(後の第四高等学校)の頃からの親友でもあります。まさか96歳の禅の権威が、大往生を遂げる直前に、41歳の仏教研究を始めたばかりの青二才に「宗教的痴呆」呼ばわりされるとは世も末だと感じた人も多かったかもしれません。しかし学問の世界は年齢なんか関係ありませんよね、堂々と信じるところを語ればよろしい。
□鈴木大拙は、日本的霊性が目覚めたのは鎌倉新仏教においてである、特に禅こそが日本的霊性の代表だと論じたのです。つまり自分が研究している禅をこれこそが日本的霊性だと強調しすぎて、それ以前神道や最澄および天台思想、空海や浄土教文化などには日本的霊性までは認められないとしたわけです。
□その場合の霊性というのは無分別智に達しているということです。つまり主観・客観の合一の覚りに達したということですね。それで一つは禅で、無我の境地を覚ったことで、世界と自我の区別を去り、法と一つになるということです。もう一つは絶対他力の浄土真宗で自然法爾の境地ですね。あるがままで阿弥陀仏に抱擁されているという境地です。そこで初めて日本人は独自の霊性に達したというわけです。
□しかし梅原猛は、禅宗以前の日本の神道や仏教において、霊性に達していなかったということが果たして言えるのかということを問いただします。日本は元々自然に神奈備(かむなび)つまり神性を認めています。これが密教に取り入れられて、森羅万象は大日如来の現れだとされ、即身成仏つまりこの生身のままで成仏できるとされたわけです。この密教が天台宗に取り入れられて、天台本覚思想になるわけですが、一切衆生に仏性つまり元々仏だという本性があるとされます。つまりこの煩悩の苦悩に満ちた地獄の世界が、そのまま涅槃、つまり煩悩がかき消された静かな覚りの境地でもあるということです。そういうことを煩悩即菩提とかいうわけです。それが前提になっていて、禅の覚りや、阿弥陀仏の救いや、久遠の本仏が今この時に現れるということも言えるわけです。
□ですから鈴木大拙は、平安仏教の密教文化や浄土教文化に霊性まで至っていないというのなら、空海の著作や、密教の仏像や平安期の浄土庭園などにそういう覚りがないことを証明すべきなのですか、そういうことは一切せずに、密教を呪術的なレベルで捉え、浄土教も単なる阿弥陀仏に祈れば極楽に掬い取ってくれるという迷信的な信仰だと断定していることになります。
□禅宗が日本文化に霊性を与えているといわれ、美意識でも「わび・さび・しおり」などは禅の影響だといわれます。芭蕉の俳諧、たとえば
「しずけさや岩に染み入る蝉の声」とか
「古池や蛙飛び込む水の音」
などは有名ですね。しかし禅宗が入ってくる前の仏教的な無常観にもとづく美意識がありまして、西行などは旅を重ねて自然と融合した短歌を詠じていたのです。
「願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」(77)[続古今1527]「心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮」(470)[新古362]
霊性において芭蕉の方が深まっていると果たしていえるのか、鈴木大拙は何も論証できていないじゃないかというわけです。
祀る神と祀られる神ー和辻哲郎の天皇教
□梅原猛の自宅は現在左京区の若王子神社のすぐ近くにあります。そこは哲学の道の終点近くにあるわけです。実は旧和辻哲郎邸が現在の梅原猛邸なのです。和辻哲郎は西田幾多郎と並び称されるぐらいの代表的な京都学派の哲学者であり、『人間の学としての倫理学』(岩波書店)で日本の倫理学の代表者です。
□『古寺巡礼』(1919年) は和辻が30歳の時の出版です。これが古寺ブーム、仏像ブームの元になったということです。和辻の古寺や仏像への関心は、古美術としての価値の発見にあります。『法華経』や『観無量寿経』を美的ドラマの本だとしていると梅原は解説しています。『日本精神史研究』(1926年)でも奈良・平安の仏教をまじめな思想的問題として扱っていないそうです。和辻は仏教思想史の研究を計画していたのですが、頓挫してしまいます。
□結局和辻は1943(昭和18)年に『尊皇思想とその伝統』を著し、「尊皇思想」を日本精神史の軸に置く事になります。彼の倫理学は間柄として人間を捉える、『人間の学としての倫理学』(1934年)でしたが、間柄の中心に無の主体としての天皇を置く尊皇思想を日本の伝統の中心に据えたのです。天皇が中心あってこそその周りすべてが運行して秩序ができるという発想です。
□天皇は神性の中心であって、それが主体として神性を付与するのです。これが祀るという行為なのです。だから天皇は祀る神なのです。祀られることによって八百万の神々が神性を得て、自然や社会の秩序が保たれ、作物が稔り、生産力が発展し、国力が増強されて社稷が発展するということです。
□このような尊皇思想を日本思想の伝統の中心に置く発想自体は、戦後『尊皇思想とその伝統』を改訂した『日本倫理思想史』にも貫かれているということなのです。これでは戦争で青春を踏みにじられたと痛切に感じていた梅原猛にはとても納得できません。
□日本文化の中心に天皇が躍り出て来たのは、明治維新からではないのか、その時に天皇中心の国家神道を国教化する「大教宣布」を行い、仏教を支配的宗教から抹殺するために、神仏分離令を発し、廃仏毀釈を煽動したではなかったか、元々日本は仏教導入以来、仏教が主導的で神仏習合の文化が支配的ではなかったかと梅原は問いかけます。
木喰は八宗一見の僧か?―柳宗悦の木喰論
□木喰(もくじき1718年―1810年)は江戸時代後期の仏像彫刻家で、事細かに様式化した仏像彫刻の型を打破して、実に自由な仏像を作っています。「下ぶくれの田舎娘の顔をした薬師、カールに髪を結った釈迦、オドケた表情の山神、ダンゴ鼻の空海、女のような日蓮」などです。それで朝鮮の民芸の価値を見出した柳宗悦(1889年― 1961年)は、木喰は真言宗の僧だけれど、宗派にとらわれない八宗一見の僧だと解釈しました。しかし、梅原は木喰の痛烈な他宗を攻撃する短歌を示して、その解釈を否定します。
「念仏にこゑをからせどおともなし、みだとしやかとはひるねなりけり」
「ざぜんして ものをいはぬかあほうもの 己の心みつけざりけり」
そして木喰の真言阿字観の短歌を取り上げます。
「木喰の心のうちをたづぬれば、阿字観ならでたのしきはなし」
「念仏は真言阿字のふかみなし、ひげだいもくはにてもやいても」
真言阿字観というのは、阿字がaという音が万物の根源で、万物に宿り、万物として現れる無限の豊かさを持っているという信仰です。それが型に嵌った仏像では収まらないで生き生きとした人間性豊かな仏像表現になり、生命賛歌になっているということです。
つまり、梅原は、木喰の仏像を鑑賞するにあたって、木喰が文字で著したものも当然参考にするべきなのに、柳は白樺派的な普遍的一般性を尊重する自分の精神でだけ解釈してしまうのはおかしいというのです。木喰が真言僧で阿字観の信仰を強く持っていた以上、その思想、信仰の表現として捉えるべきではないかというわけです。それはやはり、奈良・平安の仏教が全く検討されなかった宗教的痴呆の現れではないかということです。
日本思想はタコツボ型か?―丸山真男の宗教的痴呆
□丸山真男(1914年― 1996年)は、『日本の思想』(岩波新書、1961年)で、日本思想は先天的にバラバラとツギハギの集まりだといいました。つまり日本は必要に応じて、諸外国から各時代に仏教や儒教やキリスト教などを輸入しましたが、それが日本に根付いて伝統思想となり精神史的に背骨となって発展するということはなかったといいます。それを日本思想を「タコツボ型」と表現しました。
これに対して梅原は、「大乗仏教という一つの大きな背骨が日本の精神の中核に通っている」と反論しています。
「奈良時代の法相から華厳、天台から密教へうつり、また浄土、禅や日蓮がでてきたあの精神の流れ、その流れに対して新しい反宗教の動き、そして儒教思想、国学思想の動き。日本の思想は、外来思想の影響を受けながら、それはそれとして一つの必然的な精神の動きをもち、またその宗教の発展が、文化のすみずみまで深く広く及んでいる」と梅原はみています。
大乗仏教が日本思想の伝統の背骨になっているかどうかを丸山が論じる際、はたして丸山は、その基本的文献を読んだのかどうかあやしいと言うのです。梅原猛は怒れる獅子となって咆哮したのです。
「私はもし丸山氏が、古事記を読み、日本書紀を読み、祝詞を読み、成唯識論を読み、華厳経を読み、法華経を読み、大日経を読み、浄土三部経を読み、空海を読み、最澄を読み、円仁を読み、源信を読み、法然を読み、親鸞を読み、日蓮を読み、一遍を読み、羅山を読み、宣長を読み、篤胤を読み、慈雲を読み、そして、日本の美術や文学や芸能や民俗の実際をしらべ、その上で、精神史は不可能だ、座標軸はないというのなら丸山氏を許してもよい。しかし、そういう本を読まず、またほとんど読もうともせず、日本の美術や文学や風俗について一向に調査しようともせずに、性急に、日本では精神史が書けない、日本の思想はツギハギだ、タコツボだというのは到底許しがたいのである。」(同上、91頁)
□この丸山批判は、梅原がそれらを読んだ上で、読んでいれば丸山は決してタコツボとは言えなかったはずだという確信の下で書いていますね。ですから大変この文章は説得力があります。
『地獄の思想』
□『地獄の思想―日本精神の一系譜―』(中公新書、1967年)は、梅原猛の最初の書き下ろし作品です。これはかなり話題作になりました。日本の宗教を次の三つの思想に分類したのです。「生命の思想」「心の思想」「地獄の思想」です。
□「生命の思想」を原理にする宗教は、日本神道と真言密教です。神道は自然生命を神として崇拝します。真言密教も、大日如来の現れとして森羅万象がそのまま神的な生命の発現なのです。この生命の思想は、鎌倉時代に日蓮宗に引き継がれていると言います。
□「心の思想」を原理する宗教は奈良仏教では、すべてを意識として展開する唯識論として展開されました。そして鎌倉時代には徹底的な内省の宗教である禅宗によって発展したのです。
□「地獄の思想」は、天台宗から始まりました。地獄にも仏を、仏にも地獄を観る「一念三千」の思想として展開し、浄土教の諸宗派が発展させることになります。梅原猛著『地獄の思想』は、この「地獄の思想」に絞って、日本の仏教と文学思想を見直したものであり、精神史の一つの試みです。
怨霊史観
□1969年に梅原猛は立命館大学を退職します。学園闘争が激しくなって、大学側の処理のやり方に不公正を感じたからです。二年間は専任のない時期を送ったのです。その間に法隆寺は聖徳太子の怨霊を封じ込めるために再建されたのだという『隠された十字架―法隆寺論』を発表しました。そしてさらに柿本人麿も持統天皇の逆鱗にふれて島根県に流され、水刑にされたという『水底の歌―柿本人麿論』を書いたのです。
□これは実は重要な日本文化論なのです。日本史では奈良時代の末期に、長岡京遷都をめぐって都作りの指揮をとっていた藤原種継が大伴氏の一族に殺されまして、早良皇太弟の指令だったとされ、早良皇太弟は淡路島に流される途中で憤死して、怨霊として大いに祟ったので、長岡京をやめて平安京にしたわけです。あとは最大の怨霊は菅原道真ですね。天皇家内部では崇徳上皇です。奈良時代の前期やそれ以前の怨霊はあまり問題になっていなかったのですが、梅原猛は最大の文化人である聖徳太子と柿本人麿まで怨霊にしてしまったわけです。
□『隠された十字架』に対して聖徳太子の頃には怨霊信仰はまだなかったという批判があったのですが、梅原によると大国主命から国譲りさせたときに、宮殿より大きな社を作って祀ってくれれば、朝廷を守ると言わせていて、それで最大の社が出雲大社なのです。明らかに敗者の祟りを恐れているわけですね。
□怨みを呑んで死んでいった人々の魂を鎮魂し、祀ることで、祟りを防ぎ、平安を守ってもらおうという信仰なのです。つまり祀られているのは政治的に陰謀で葬られた敗者なのですね。祀る方が勝者なのです。勝者が敗者の怨念を恐れ、祀り、敗者の夢を実現して霊を慰めるのです。聖徳太子の仏教国家の建設の夢を叶えたのは藤原氏と天皇家が叶え、柿本人麿や大伴家持の夢を実現して『万葉集』を仕上げたのは、平城天皇です。つまり祟られた側なのです。そこに日本独特の和の精神が生きているのです。
□ですから日本神道の精神から言えば、日本が侵略して被害を与えた東アジアの人々に対する鎮魂を、日本の為に戦って死んだ兵士たちの慰霊よりも優先すべきだということになります。そうすることによって東アジアの人々の平和友好の関係が築けるというのが、梅原猛の靖国神社の問題に対するスタンスです。
『湖の伝説』から縄文文化論さらにはアイヌ文化論へ
□怨霊を鎮めるというのは、実は土着していた人々を大陸から先進文化をもって渡って来た人々が支配する際に、数の上で多数の先住民と和解するために必要な和の儀式であったわけです。と同時に梅原猛だけが怨霊に気づくというのは、梅原自身の中に抑圧された無意識の世界に生母への思いがったわけです。それに向き合わざるを得なくしたきっかけが『湖の伝説』です。画家三橋節子が、癌で右腕を切断して、余命三年の間に、幼いが子を置いて死ななければならない哀しみを、左手で多くの作品の中に遺したという伝記です。書いている間は自分の生母のことは気づかなかったのですが、書き終わってから、堰を切ったように生母のことを語り始めます。それが『学問のすすめ』という自伝です。
□生母の面影と向き合うためにも、梅原は生誕の地仙台にいって東北地方の蝦夷文化を尋ね。そこに遮光器土器などに縄文人の怨霊を見出そうとします。そしてさらに蝦夷文化の名残を遺すアイヌ文化を尋ねて、そこにイオマンテ(熊送り)を見、この世とあの世の往還思想を改めて発見するのです。それは梅原の生母をあの世から取り戻したいという思いに寄り添ってくる信仰だったわけです。それでアイヌ文化こそ縄文人の文化を受け継いだものだと確信しまして、あの世を含む生命の循環と共生の生きていた縄文文化を見直し、そこに現代人が失った大切なものを発見し、甦らせようとします。
親鸞の二種回向
□この世とあの世の往還を含めて、大いなる生命の循環と共生の思想を縄文時代からの森の文化に由来する日本人の原思想のように捉えているのです。そこから親鸞の二種回向説の再評価に向かいます。
□浄土真宗の中心教義は『教行信証』という親鸞の主著では「往相回向と還相回向」の「二種回向」だとはっきり記されています。つまり阿弥陀仏によって阿弥陀浄土に救いとられる往相回向と、そこで修行して慈悲に目覚め、この世に煩悩に苦しむ衆生を救いに戻ってくる還相回向の二種回向説です。
□ところが近代の浄土真宗は唯円が親鸞の教えをまとめた『歎異抄』の悪人正機説が中心です。梅原猛も元々は『歎異抄入門』(PHP文庫)を書いていまして、1960年代の『仏教の思想』でも「二種回向」には触れてなかったのです。それが真髄は「二種回向」だと言い出したのです。
□近代真宗学は、霊を実体としては捉えません。浄土と言い、穢土といってもそれは魂(命)の境涯でして、阿弥陀仏と共に生きているのが浄土であり、阿弥陀仏を見失っているのが穢土あるいは地獄なのです。ですから二種回向は阿弥陀仏に向かうのが往相回向で、阿弥陀仏の慈悲を衆生に返すのが還相回向なのです。つまり死んでから阿弥陀浄土に行くなどというのは幻想だということですね。
□梅原猛はそれでは納得できないのです。あの世を実体化し、死後あの世に行って、また戻ってくるというのは、不死願望からくるわけですが、梅原の場合は自己の不死願望だけでなく、生母をあの世から取り戻したいという根源的な願望と結びついているだけに人一倍強いのかもしれません。
◇◇◇◇◇◇梅原猛の日本文化論―異文化理解の前提としてー◇◇◇◇◇◇
日本人は何主義か?
倫理学の講義の時などに、「ギリシア人は主知主義で、中国人は道義主義と言われていますが、では日本人は何主義ですか?」と質問しますと、ほとんどの学生諸君は「わかりません」と応えます。これは大変困ったことですね。日本人の大学生までが、日本人の考え方、感じ方の特色、日本人の良さについて知らないで通しているのですから。つまり異文化理解をする前に、自文化理解ができていないのです。自文化理解も出来ていないのに異文化理解ができるはずはありません。というより、日本文化や日本思想自体が現在の日本人にとっては異文化だということなのかもしれませんね。
日本人の民族性は情を重んじる主情主義なのです。それは本居宣長が「もののあはれを知る心」を大和心として強調し、儒教や仏教の賢しらを退けようとしたことによって、定着したわけです。桜の花が咲き誇っているのを見て晴れやかな気持ちになったり、見たまま感じたまま物になりきって心が動くのがもののあはれです。ものに心が動くというのは、その対象はもちろん人間以外のものに限りません。人間に対する自然な情も入ります。宣長は『源氏物語』を最高傑作と評しましたが、それはもののあはれを文学的価値として確立して、作品全体に貫いているからです。
本居宣長の国文学的な国粋主義は、儒教や仏教伝来以前の日本が本来的な日本であったとして、儒教や仏教に汚染されていない日本を『古事記』『日本書紀』を通して明らかにしようとしました。宣長は、『日本書紀』は純然たる漢文で書かれているので、漢心(からごころ)が混ざっていると考え、『古事記』は古典中国語を基本に日本独特の表記を交えた、いわゆる「変体漢文」であり、漢文で表せない大和心を表そうと苦心しているので高く評価しています。
儒教や仏教に汚染されていない大和心といいましても、『古事記』の記述にも、海外の神話を下敷きにしているところもありますので、純国産を求めるのは無理があります。日本神道と呼ばれるものも、中国の道教の焼き直しの面もあり、道教との比較検討がもっと進まなければ、その独創性にはあいまいなところがあります。また逆に儒教や仏教思想も日本に定着して、人々の暮らしに大きな影響を与えていますので、日本文化からそれらを差し引くというのは、乱暴な議論です。それより定着した仏教や神道や儒教から日本文化を論じるという方が、日本文化を論じる場合に現実的だと思われます。
梅原猛の日本文化論への歩み
□梅原猛は1925年3月20日生まれで、現在84歳です。終戦の年1945年に京都大学文学部哲学専攻に合格したのですが、入学式から郷里の愛知県の実家に戻ると召集令状が来ていて、戦争が終わるまで、九州で軍隊生活でした。京大生の二等兵ですから格好のいじめの的だったかもしれません。でもなんとか生き残って9月に大学に戻ったのです。でも戦争で無意味な死を見ていたためか、虚無的な気分が抜けずに、ハイデッガーの実存哲学を死への哲学と捉えて、そこにのめりこんでいたわけです。そこで養母が心配して嫁を世話しまして、貧しいながらも家庭の幸福を築こうという生活の中で、生きる道を見出していったのです。
□哲学青年ですから死を見つめて哲学しているのが本当の自分で、小鳥が暖め合うような家庭の幸福は仮面の自分だと思っていたのに、仮面と自分の区別がなくなっていったわけです。それで哲学で身を立てなければならないのだけれど、西洋哲学はギリシア・ローマの古典古代からの伝統と、ユダヤ・キリスト教の伝統の下で出来上がっているわけでして、ニーチェやハイデッガーを研究しても、それを解釈、解説することに終わって独創的な哲学はできっこないと思ったわけですね。それで長いことスランプが続いたわけです。彼は独創的な哲学書が書けないのだったら、哲学書は出さないと決めていたので、なんとかしなければならなかったのです。
□そこで彼は理性より感情に注目したのです。落ち込んでばかりはいられないので、敗戦後の厳しい現実の中で、たくましく復興してくる時に庶民が求めていたのは笑いなのですね。それで笑いの研究をします。ちょうど戦後15年たって日米安全保障条約改定反対闘争が盛り上がったころです。京都から大阪の寄席に通ってノートをとっている哲学者がいるということで、面白がられて朝日新聞に「笑いの研究」を連載したわけです。これが梅原猛のマスコミデビューですね。
□笑いなどの感情にも民族性や宗教的背景があることに気付き、感情論を深めるためにも日本文化や日本の宗教を知らなければならないと思ったのです。つまり西洋哲学の研究ばかりやっていても、西洋人以上に西洋文化を知らない限り、そのエッセンスである西洋哲学が創造できるはずかないわけです。日本人は東洋文化や日本文化を研究し、日本の宗教を学んでこそ、それを土壌にした独創的な哲学が生まれるはずだということです。それで日本の伝統文化や宗教を学び始めたわけです。
□1960年代当時はいわゆる仏像ブームがありました。古寺を回りまして、そこの仏像を鑑賞しようというものです。私の高校は大阪府立泉尾高校でしたが、そこには国語に国文学を折口信夫に師事した堀内民一先生がおられまして、しきりに大和の寺と仏像の鑑賞を薦めておられました。敗戦国日本にとって日本にはこんな深い精神的な味わいのある伝統文化があるという事は、大きな心の支えだったわけです。
□梅原猛はNHKで1964年に「仏像―かたちとこころ」の総合司会をしました。仏像といえば釈迦如来像、薬師如来像、観世音菩薩像、大日如来像、阿弥陀如来像、地蔵菩薩像などが多いわけですね。仏像を理解しようとすれば当然、密教や顕教の深い理解が必要で、空海や最澄と必死で格闘したわけです。まあ日本仏教の世界にのめりこんでいったわけです。
近代知識人の宗教的痴呆を嘆く
□梅原猛は、当然近代日本の知識人たちの代表的な日本文化論に眼を通したわけですが、そこで彼は愕然としたわけですね。日本文化の伝統に仏教思想がきちんと位置づけられていないわけです。彼は廃仏毀釈後の日本は、「天皇制の内圧」によってまともに日本文化を評価できなくなっていると感じたのです。その状況を彼は「宗教的痴呆」とまで口を極めて喝破したのです。つまり「馬鹿野郎!」と叫んだわけですね。もちろん批評をするときに相手を「アホ馬鹿」呼ばわりしてはいけませんが、相手が超一流だけにその勇気は褒めるべきでしょう。
□1966年に病気で一ヶ月ほど入院したりして健康不安から、もうすぐ死ぬのではないかと思い、自暴自棄になって大胆な自説を展開するきっかけになったと言ってますが、6月に「明治百年における日本の自己誤認ー日本人の宗教的痴呆ー」を『日本』に8月に「日本文化論への批判的考察ー鈴木大拙・和辻哲郎の場合」を『展望』に発表しました。それらで、鈴木大拙、和辻哲郎、柳宗悦、丸山真男といった代表的な岩波文化人をなんと「宗教的痴呆」で一括したわけです。これらの論文は1967年に『美と宗教の発見-創造的日本文化論ー』として筑摩書房から出版されました。これが梅原猛の最初の単著です。
禅宗と浄土真宗以前に「日本的霊性」ないのかー鈴木大拙
□鈴木大拙(1870年 - 1966年)は『禅と日本文化』(岩波新書、正・続)『日本的霊性』(岩波文庫)で知られる、禅を世界に紹介した人です。西田幾多郎とは石川県立専門学校(後の第四高等学校)の頃からの親友でもあります。まさか96歳の禅の権威が、大往生を遂げる直前に、41歳の仏教研究を始めたばかりの青二才に「宗教的痴呆」呼ばわりされるとは世も末だと感じた人も多かったかもしれません。しかし学問の世界は年齢なんか関係ありませんよね、堂々と信じるところを語ればよろしい。
□鈴木大拙は、日本的霊性が目覚めたのは鎌倉新仏教においてである、特に禅こそが日本的霊性の代表だと論じたのです。つまり自分が研究している禅をこれこそが日本的霊性だと強調しすぎて、それ以前神道や最澄および天台思想、空海や浄土教文化などには日本的霊性までは認められないとしたわけです。
□その場合の霊性というのは無分別智に達しているということです。つまり主観・客観の合一の覚りに達したということですね。それで一つは禅で、無我の境地を覚ったことで、世界と自我の区別を去り、法と一つになるということです。もう一つは絶対他力の浄土真宗で自然法爾の境地ですね。あるがままで阿弥陀仏に抱擁されているという境地です。そこで初めて日本人は独自の霊性に達したというわけです。
□しかし梅原猛は、禅宗以前の日本の神道や仏教において、霊性に達していなかったということが果たして言えるのかということを問いただします。日本は元々自然に神奈備(かむなび)つまり神性を認めています。これが密教に取り入れられて、森羅万象は大日如来の現れだとされ、即身成仏つまりこの生身のままで成仏できるとされたわけです。この密教が天台宗に取り入れられて、天台本覚思想になるわけですが、一切衆生に仏性つまり元々仏だという本性があるとされます。つまりこの煩悩の苦悩に満ちた地獄の世界が、そのまま涅槃、つまり煩悩がかき消された静かな覚りの境地でもあるということです。そういうことを煩悩即菩提とかいうわけです。それが前提になっていて、禅の覚りや、阿弥陀仏の救いや、久遠の本仏が今この時に現れるということも言えるわけです。
□ですから鈴木大拙は、平安仏教の密教文化や浄土教文化に霊性まで至っていないというのなら、空海の著作や、密教の仏像や平安期の浄土庭園などにそういう覚りがないことを証明すべきなのですか、そういうことは一切せずに、密教を呪術的なレベルで捉え、浄土教も単なる阿弥陀仏に祈れば極楽に掬い取ってくれるという迷信的な信仰だと断定していることになります。
□禅宗が日本文化に霊性を与えているといわれ、美意識でも「わび・さび・しおり」などは禅の影響だといわれます。芭蕉の俳諧、たとえば
「しずけさや岩に染み入る蝉の声」とか
「古池や蛙飛び込む水の音」
などは有名ですね。しかし禅宗が入ってくる前の仏教的な無常観にもとづく美意識がありまして、西行などは旅を重ねて自然と融合した短歌を詠じていたのです。
「願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」(77)[続古今1527]「心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮」(470)[新古362]
霊性において芭蕉の方が深まっていると果たしていえるのか、鈴木大拙は何も論証できていないじゃないかというわけです。
祀る神と祀られる神ー和辻哲郎の天皇教
□梅原猛の自宅は現在左京区の若王子神社のすぐ近くにあります。そこは哲学の道の終点近くにあるわけです。実は旧和辻哲郎邸が現在の梅原猛邸なのです。和辻哲郎は西田幾多郎と並び称されるぐらいの代表的な京都学派の哲学者であり、『人間の学としての倫理学』(岩波書店)で日本の倫理学の代表者です。
□『古寺巡礼』(1919年) は和辻が30歳の時の出版です。これが古寺ブーム、仏像ブームの元になったということです。和辻の古寺や仏像への関心は、古美術としての価値の発見にあります。『法華経』や『観無量寿経』を美的ドラマの本だとしていると梅原は解説しています。『日本精神史研究』(1926年)でも奈良・平安の仏教をまじめな思想的問題として扱っていないそうです。和辻は仏教思想史の研究を計画していたのですが、頓挫してしまいます。
□結局和辻は1943(昭和18)年に『尊皇思想とその伝統』を著し、「尊皇思想」を日本精神史の軸に置く事になります。彼の倫理学は間柄として人間を捉える、『人間の学としての倫理学』(1934年)でしたが、間柄の中心に無の主体としての天皇を置く尊皇思想を日本の伝統の中心に据えたのです。天皇が中心あってこそその周りすべてが運行して秩序ができるという発想です。
□天皇は神性の中心であって、それが主体として神性を付与するのです。これが祀るという行為なのです。だから天皇は祀る神なのです。祀られることによって八百万の神々が神性を得て、自然や社会の秩序が保たれ、作物が稔り、生産力が発展し、国力が増強されて社稷が発展するということです。
□このような尊皇思想を日本思想の伝統の中心に置く発想自体は、戦後『尊皇思想とその伝統』を改訂した『日本倫理思想史』にも貫かれているということなのです。これでは戦争で青春を踏みにじられたと痛切に感じていた梅原猛にはとても納得できません。
□日本文化の中心に天皇が躍り出て来たのは、明治維新からではないのか、その時に天皇中心の国家神道を国教化する「大教宣布」を行い、仏教を支配的宗教から抹殺するために、神仏分離令を発し、廃仏毀釈を煽動したではなかったか、元々日本は仏教導入以来、仏教が主導的で神仏習合の文化が支配的ではなかったかと梅原は問いかけます。
木喰は八宗一見の僧か?―柳宗悦の木喰論
□木喰(もくじき1718年―1810年)は江戸時代後期の仏像彫刻家で、事細かに様式化した仏像彫刻の型を打破して、実に自由な仏像を作っています。「下ぶくれの田舎娘の顔をした薬師、カールに髪を結った釈迦、オドケた表情の山神、ダンゴ鼻の空海、女のような日蓮」などです。それで朝鮮の民芸の価値を見出した柳宗悦(1889年― 1961年)は、木喰は真言宗の僧だけれど、宗派にとらわれない八宗一見の僧だと解釈しました。しかし、梅原は木喰の痛烈な他宗を攻撃する短歌を示して、その解釈を否定します。
「念仏にこゑをからせどおともなし、みだとしやかとはひるねなりけり」
「ざぜんして ものをいはぬかあほうもの 己の心みつけざりけり」
そして木喰の真言阿字観の短歌を取り上げます。
「木喰の心のうちをたづぬれば、阿字観ならでたのしきはなし」
「念仏は真言阿字のふかみなし、ひげだいもくはにてもやいても」
真言阿字観というのは、阿字がaという音が万物の根源で、万物に宿り、万物として現れる無限の豊かさを持っているという信仰です。それが型に嵌った仏像では収まらないで生き生きとした人間性豊かな仏像表現になり、生命賛歌になっているということです。
つまり、梅原は、木喰の仏像を鑑賞するにあたって、木喰が文字で著したものも当然参考にするべきなのに、柳は白樺派的な普遍的一般性を尊重する自分の精神でだけ解釈してしまうのはおかしいというのです。木喰が真言僧で阿字観の信仰を強く持っていた以上、その思想、信仰の表現として捉えるべきではないかというわけです。それはやはり、奈良・平安の仏教が全く検討されなかった宗教的痴呆の現れではないかということです。
日本思想はタコツボ型か?―丸山真男の宗教的痴呆
□丸山真男(1914年― 1996年)は、『日本の思想』(岩波新書、1961年)で、日本思想は先天的にバラバラとツギハギの集まりだといいました。つまり日本は必要に応じて、諸外国から各時代に仏教や儒教やキリスト教などを輸入しましたが、それが日本に根付いて伝統思想となり精神史的に背骨となって発展するということはなかったといいます。それを日本思想を「タコツボ型」と表現しました。
これに対して梅原は、「大乗仏教という一つの大きな背骨が日本の精神の中核に通っている」と反論しています。
「奈良時代の法相から華厳、天台から密教へうつり、また浄土、禅や日蓮がでてきたあの精神の流れ、その流れに対して新しい反宗教の動き、そして儒教思想、国学思想の動き。日本の思想は、外来思想の影響を受けながら、それはそれとして一つの必然的な精神の動きをもち、またその宗教の発展が、文化のすみずみまで深く広く及んでいる」と梅原はみています。
大乗仏教が日本思想の伝統の背骨になっているかどうかを丸山が論じる際、はたして丸山は、その基本的文献を読んだのかどうかあやしいと言うのです。梅原猛は怒れる獅子となって咆哮したのです。
「私はもし丸山氏が、古事記を読み、日本書紀を読み、祝詞を読み、成唯識論を読み、華厳経を読み、法華経を読み、大日経を読み、浄土三部経を読み、空海を読み、最澄を読み、円仁を読み、源信を読み、法然を読み、親鸞を読み、日蓮を読み、一遍を読み、羅山を読み、宣長を読み、篤胤を読み、慈雲を読み、そして、日本の美術や文学や芸能や民俗の実際をしらべ、その上で、精神史は不可能だ、座標軸はないというのなら丸山氏を許してもよい。しかし、そういう本を読まず、またほとんど読もうともせず、日本の美術や文学や風俗について一向に調査しようともせずに、性急に、日本では精神史が書けない、日本の思想はツギハギだ、タコツボだというのは到底許しがたいのである。」(同上、91頁)
□この丸山批判は、梅原がそれらを読んだ上で、読んでいれば丸山は決してタコツボとは言えなかったはずだという確信の下で書いていますね。ですから大変この文章は説得力があります。
『地獄の思想』
□『地獄の思想―日本精神の一系譜―』(中公新書、1967年)は、梅原猛の最初の書き下ろし作品です。これはかなり話題作になりました。日本の宗教を次の三つの思想に分類したのです。「生命の思想」「心の思想」「地獄の思想」です。
□「生命の思想」を原理にする宗教は、日本神道と真言密教です。神道は自然生命を神として崇拝します。真言密教も、大日如来の現れとして森羅万象がそのまま神的な生命の発現なのです。この生命の思想は、鎌倉時代に日蓮宗に引き継がれていると言います。
□「心の思想」を原理する宗教は奈良仏教では、すべてを意識として展開する唯識論として展開されました。そして鎌倉時代には徹底的な内省の宗教である禅宗によって発展したのです。
□「地獄の思想」は、天台宗から始まりました。地獄にも仏を、仏にも地獄を観る「一念三千」の思想として展開し、浄土教の諸宗派が発展させることになります。梅原猛著『地獄の思想』は、この「地獄の思想」に絞って、日本の仏教と文学思想を見直したものであり、精神史の一つの試みです。
怨霊史観
□1969年に梅原猛は立命館大学を退職します。学園闘争が激しくなって、大学側の処理のやり方に不公正を感じたからです。二年間は専任のない時期を送ったのです。その間に法隆寺は聖徳太子の怨霊を封じ込めるために再建されたのだという『隠された十字架―法隆寺論』を発表しました。そしてさらに柿本人麿も持統天皇の逆鱗にふれて島根県に流され、水刑にされたという『水底の歌―柿本人麿論』を書いたのです。
□これは実は重要な日本文化論なのです。日本史では奈良時代の末期に、長岡京遷都をめぐって都作りの指揮をとっていた藤原種継が大伴氏の一族に殺されまして、早良皇太弟の指令だったとされ、早良皇太弟は淡路島に流される途中で憤死して、怨霊として大いに祟ったので、長岡京をやめて平安京にしたわけです。あとは最大の怨霊は菅原道真ですね。天皇家内部では崇徳上皇です。奈良時代の前期やそれ以前の怨霊はあまり問題になっていなかったのですが、梅原猛は最大の文化人である聖徳太子と柿本人麿まで怨霊にしてしまったわけです。
□『隠された十字架』に対して聖徳太子の頃には怨霊信仰はまだなかったという批判があったのですが、梅原によると大国主命から国譲りさせたときに、宮殿より大きな社を作って祀ってくれれば、朝廷を守ると言わせていて、それで最大の社が出雲大社なのです。明らかに敗者の祟りを恐れているわけですね。
□怨みを呑んで死んでいった人々の魂を鎮魂し、祀ることで、祟りを防ぎ、平安を守ってもらおうという信仰なのです。つまり祀られているのは政治的に陰謀で葬られた敗者なのですね。祀る方が勝者なのです。勝者が敗者の怨念を恐れ、祀り、敗者の夢を実現して霊を慰めるのです。聖徳太子の仏教国家の建設の夢を叶えたのは藤原氏と天皇家が叶え、柿本人麿や大伴家持の夢を実現して『万葉集』を仕上げたのは、平城天皇です。つまり祟られた側なのです。そこに日本独特の和の精神が生きているのです。
□ですから日本神道の精神から言えば、日本が侵略して被害を与えた東アジアの人々に対する鎮魂を、日本の為に戦って死んだ兵士たちの慰霊よりも優先すべきだということになります。そうすることによって東アジアの人々の平和友好の関係が築けるというのが、梅原猛の靖国神社の問題に対するスタンスです。
『湖の伝説』から縄文文化論さらにはアイヌ文化論へ
□怨霊を鎮めるというのは、実は土着していた人々を大陸から先進文化をもって渡って来た人々が支配する際に、数の上で多数の先住民と和解するために必要な和の儀式であったわけです。と同時に梅原猛だけが怨霊に気づくというのは、梅原自身の中に抑圧された無意識の世界に生母への思いがったわけです。それに向き合わざるを得なくしたきっかけが『湖の伝説』です。画家三橋節子が、癌で右腕を切断して、余命三年の間に、幼いが子を置いて死ななければならない哀しみを、左手で多くの作品の中に遺したという伝記です。書いている間は自分の生母のことは気づかなかったのですが、書き終わってから、堰を切ったように生母のことを語り始めます。それが『学問のすすめ』という自伝です。
□生母の面影と向き合うためにも、梅原は生誕の地仙台にいって東北地方の蝦夷文化を尋ね。そこに遮光器土器などに縄文人の怨霊を見出そうとします。そしてさらに蝦夷文化の名残を遺すアイヌ文化を尋ねて、そこにイオマンテ(熊送り)を見、この世とあの世の往還思想を改めて発見するのです。それは梅原の生母をあの世から取り戻したいという思いに寄り添ってくる信仰だったわけです。それでアイヌ文化こそ縄文人の文化を受け継いだものだと確信しまして、あの世を含む生命の循環と共生の生きていた縄文文化を見直し、そこに現代人が失った大切なものを発見し、甦らせようとします。
親鸞の二種回向
□この世とあの世の往還を含めて、大いなる生命の循環と共生の思想を縄文時代からの森の文化に由来する日本人の原思想のように捉えているのです。そこから親鸞の二種回向説の再評価に向かいます。
□浄土真宗の中心教義は『教行信証』という親鸞の主著では「往相回向と還相回向」の「二種回向」だとはっきり記されています。つまり阿弥陀仏によって阿弥陀浄土に救いとられる往相回向と、そこで修行して慈悲に目覚め、この世に煩悩に苦しむ衆生を救いに戻ってくる還相回向の二種回向説です。
□ところが近代の浄土真宗は唯円が親鸞の教えをまとめた『歎異抄』の悪人正機説が中心です。梅原猛も元々は『歎異抄入門』(PHP文庫)を書いていまして、1960年代の『仏教の思想』でも「二種回向」には触れてなかったのです。それが真髄は「二種回向」だと言い出したのです。
□近代真宗学は、霊を実体としては捉えません。浄土と言い、穢土といってもそれは魂(命)の境涯でして、阿弥陀仏と共に生きているのが浄土であり、阿弥陀仏を見失っているのが穢土あるいは地獄なのです。ですから二種回向は阿弥陀仏に向かうのが往相回向で、阿弥陀仏の慈悲を衆生に返すのが還相回向なのです。つまり死んでから阿弥陀浄土に行くなどというのは幻想だということですね。
□梅原猛はそれでは納得できないのです。あの世を実体化し、死後あの世に行って、また戻ってくるというのは、不死願望からくるわけですが、梅原の場合は自己の不死願望だけでなく、生母をあの世から取り戻したいという根源的な願望と結びついているだけに人一倍強いのかもしれません。
|
|
|
|
コメント(1)
天台本覚思想
□最近は梅原の怨霊信仰の対象は、世阿弥に移っています。世阿弥に代表される能楽は、戦や飢饉、天変地異などによる災害などで、理不尽な死が蔓延していた時代に、死ぬに死に切れない怨霊たちを鎮魂するために誕生した宗教的な鎮魂劇なのです。ですから怨霊のスペシャリストとして梅原猛が取り組む必然性があったわけです。
□怨霊を鎮魂する場合に、あまりにも理不尽なだけに、その煩悩から簡単には脱却できませんね。ですからかえって逆説的に、その煩悩の深さにこそ、涅槃(煩悩が吹き消された覚りの境地)があるとするしかありません。これが煩悩即涅槃、煩悩即菩提という覚りです。つまり煩悩地獄の中にこそ煩悩を超えた悟りの世界があるということです。それを人間ドラマとして煩悩の舞を舞い、芸術に昇華することで、その華を見せ、その輝き(幽玄の美)が永遠であることを感じさせて鎮魂することで、成仏させられるというものなのです。
□そして仏教は大いなる生命の循環と共生を説きますが、その大いなる生命には人間だけでなく動物も植物も大地や大気も含まれます。それらが全体として生きていて、それが諸行無常、諸法無我の法を示しているのです。仏教の覚りとはその法と一体化することですから、法を示している森羅万象は法である本来の自己、つまり御仏の現れであるということになりますね。そうしますと、人間だけでなく、森羅万象が元々仏の現われなのだということになります。ということは人間だけでなく、森羅万象が元々仏の現れである以上、覚りを宿しているということになります。これを本覚というのです。梅原は近代西洋の人間中心主義に対して、大いなる生命の循環と共生という立場からアンチテーゼを出していくことが必要だ、天台本覚思想にはその中心になりうると考えています。これこそ日本的霊性だという立場です。
□しかし天台本覚思想には欠陥があると最近気付きまして、そこには太陽と水に対する信仰が欠けているというのです。それはエジプトに行きまして吉村作治さんの案内で、ギリシア・ローマ文明の前に太陽神信仰のエジプト文明があった。それはプラトン以降の形而上学に陥る前の存在の哲学があったのではないかというのです。この命の根源である熱と光と水の信仰を取り込めば、天台本覚信仰ももっと生き生きしたものになるのではないかというわけです。
□それで日本思想の研究と西洋哲学の研究も結合して、西洋哲学をトータルに超克できる梅原哲学がやっと書ける気がするというのです。しかし今すぐに書いたらすぐ死んでしまうので、90歳になってから十分準備してから、初めての本格的な哲学書を書きたいということです。でも90歳過ぎてから本格的な哲学書を書けたらそれこそギネスものですね。
□太陽信仰といえば、日本も天照大神を主神とする太陽信仰の国ですし、水信仰の国でもあります。天台本覚思想に農業の自然神信仰が融合したものが梅原猛の日本文化の根底にあるものだといえるでしょう。
□梅原は、プラトン以降の西洋形而上学を、人間の観念で作り上げた神やイデアの世界や主観的な理性を中心において世界を解釈する人間中心主義で、これは天動説だというのです。そこで天動説をひっくりかえして自然中心の地動説の哲学を創らなければならないといいます。
□それには自然の中心が要りますね。それは太陽神でしょうか、それともより根源的には宇宙の中心、天御中主命つまり北極星でしょうか。それは天皇の位置づけとも微妙にリンクするだけにむつかしい問題を孕んでいるようですね。
□梅原の日本文化論は、西洋の人間中心、理性中心の機械的文明に対して東洋の自然中心、生命中心、感情を重んじる文化を対置しするものですが、果たして両者を統合するような普遍性に到達できるかという問題も抱えているようですね。人類哲学を梅原は考えているようですから。
□最近は梅原の怨霊信仰の対象は、世阿弥に移っています。世阿弥に代表される能楽は、戦や飢饉、天変地異などによる災害などで、理不尽な死が蔓延していた時代に、死ぬに死に切れない怨霊たちを鎮魂するために誕生した宗教的な鎮魂劇なのです。ですから怨霊のスペシャリストとして梅原猛が取り組む必然性があったわけです。
□怨霊を鎮魂する場合に、あまりにも理不尽なだけに、その煩悩から簡単には脱却できませんね。ですからかえって逆説的に、その煩悩の深さにこそ、涅槃(煩悩が吹き消された覚りの境地)があるとするしかありません。これが煩悩即涅槃、煩悩即菩提という覚りです。つまり煩悩地獄の中にこそ煩悩を超えた悟りの世界があるということです。それを人間ドラマとして煩悩の舞を舞い、芸術に昇華することで、その華を見せ、その輝き(幽玄の美)が永遠であることを感じさせて鎮魂することで、成仏させられるというものなのです。
□そして仏教は大いなる生命の循環と共生を説きますが、その大いなる生命には人間だけでなく動物も植物も大地や大気も含まれます。それらが全体として生きていて、それが諸行無常、諸法無我の法を示しているのです。仏教の覚りとはその法と一体化することですから、法を示している森羅万象は法である本来の自己、つまり御仏の現れであるということになりますね。そうしますと、人間だけでなく、森羅万象が元々仏の現われなのだということになります。ということは人間だけでなく、森羅万象が元々仏の現れである以上、覚りを宿しているということになります。これを本覚というのです。梅原は近代西洋の人間中心主義に対して、大いなる生命の循環と共生という立場からアンチテーゼを出していくことが必要だ、天台本覚思想にはその中心になりうると考えています。これこそ日本的霊性だという立場です。
□しかし天台本覚思想には欠陥があると最近気付きまして、そこには太陽と水に対する信仰が欠けているというのです。それはエジプトに行きまして吉村作治さんの案内で、ギリシア・ローマ文明の前に太陽神信仰のエジプト文明があった。それはプラトン以降の形而上学に陥る前の存在の哲学があったのではないかというのです。この命の根源である熱と光と水の信仰を取り込めば、天台本覚信仰ももっと生き生きしたものになるのではないかというわけです。
□それで日本思想の研究と西洋哲学の研究も結合して、西洋哲学をトータルに超克できる梅原哲学がやっと書ける気がするというのです。しかし今すぐに書いたらすぐ死んでしまうので、90歳になってから十分準備してから、初めての本格的な哲学書を書きたいということです。でも90歳過ぎてから本格的な哲学書を書けたらそれこそギネスものですね。
□太陽信仰といえば、日本も天照大神を主神とする太陽信仰の国ですし、水信仰の国でもあります。天台本覚思想に農業の自然神信仰が融合したものが梅原猛の日本文化の根底にあるものだといえるでしょう。
□梅原は、プラトン以降の西洋形而上学を、人間の観念で作り上げた神やイデアの世界や主観的な理性を中心において世界を解釈する人間中心主義で、これは天動説だというのです。そこで天動説をひっくりかえして自然中心の地動説の哲学を創らなければならないといいます。
□それには自然の中心が要りますね。それは太陽神でしょうか、それともより根源的には宇宙の中心、天御中主命つまり北極星でしょうか。それは天皇の位置づけとも微妙にリンクするだけにむつかしい問題を孕んでいるようですね。
□梅原の日本文化論は、西洋の人間中心、理性中心の機械的文明に対して東洋の自然中心、生命中心、感情を重んじる文化を対置しするものですが、果たして両者を統合するような普遍性に到達できるかという問題も抱えているようですね。人類哲学を梅原は考えているようですから。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
梅原猛 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
梅原猛のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75488人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196034人
- 3位
- 独り言
- 9045人