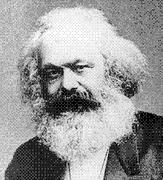最近、脱成長派がのざばり、経済成長は環境負荷になるので、経済は成長しない方がいい、定常経済で行きましょうという議論があるが、マルクスの労働価値説は、生身の労働者の労働だけが価値を生むことになっている。だとすれば、一日一人当たりの労働時間が24時間を超えることは有り得ないので、1人当たりの価値産出が24時間を上回ることは有り得ない。もちろん24時間労働は無理で、結局一人平均8時間働くとしたら、1人当たりのGDPは全員が働いたとしても8時間分の価値だということになり、経済成長という議論自体がナンセンスになってしまう。
労働の複雑度という観点を入れればどうか、確かに知的・文化的水準や、技能的水準において、平均の労働力の何倍もの複雑労働をする人がいる。そのように労働力の質を高めることによって、同じ8時間の労働が10時間あるいは20時間分の労働に当たることもある。しかしこれもその技能が平均化するとこまで普及すると8時間労働は8時間分の労働となる。だから長期的には経済成長しないことになる。
次に、生身の労働の複雑度は変わらないけれど、使う道具・機械・労働組織や分業の仕方などで随分時間当たりの生産量が違ってくる場合がある。マルクスはこれを特別剰余価値の生産と呼んだ、その場合同じ一時間の労働でも以前の10倍、100倍に成る場合がある。マルクスは、それを生産手段や組織などによって、「強められた」労働と呼び、確かに一時間の労働が10時間や100時間の価値を生むと認めたけれど、それもその機械や組織での労働が普及すれば、1時間の労働は1時間分の価値をうむことになる。
だから一人当たりのGDPを基準に経済成長を考える限り、人口と比例した経済成長しか考えられなくなり、人口増加率が0.8%だとすると超長期的な経済成長率も0.8%になってしまう。最近は人口が頭打ちになるという仮説が有力なので、経済成長率もやがてマイナスになってしまうことになる。
一方、物質的な生産力は科学技術の発展によってどんどん発達していくから、生み出される効用やサービスは人口増加率をはるかに上回る割合で増加していく。どれだけ増えたかは数量・効用量、サービス量などで計測できる。しかしそれは価格で測っていないので、GDP的な成長ではない。
マルクスの価値理論でいくと生産物全体の生産に費やされた現在及び過去の労働量になる。例えば、パソコン一台の生産に要した生身の労働者の労働時間が部品から完成品に至るまでで計10時間かかっているとする。その際に使用される原材料の価値も10時間分の価値に相当し、機械や道具の減価償却費も10時間分だとしたら計30時間分の労働時間の結晶だということになる。
もちろんこの労働時間は平均的な労働時間に換算されているので、その年の生産物とサービスの価値の総計はその年の労働者の総労働時間と等しいことになり、平均的労働時間が一日8時間なら、8時間×労働人口=GDPであることに変わりはない。
だとすると生身の労働者の労働だけが価値を生むことを前提にしたマルクス流の労働価値説では経済成長について議論すること自体成り立たないし、人口増加率以上の経済成長も目指すことはナンセンスにならないか。そうなると定常化経済論に相応しいということになるのか、ピケティは1.5%程度の経済成長率に落ち着くと見ているけれど。
私は価値論の大前提を考え直して、経済成長論を組み立て直すべきだと考えているが、マルクス研究者にはそれぞれ思うところがあると思うので、ご意見を陳述願います。ただしできるだけ論拠を上げて論証する形にしてください。
労働の複雑度という観点を入れればどうか、確かに知的・文化的水準や、技能的水準において、平均の労働力の何倍もの複雑労働をする人がいる。そのように労働力の質を高めることによって、同じ8時間の労働が10時間あるいは20時間分の労働に当たることもある。しかしこれもその技能が平均化するとこまで普及すると8時間労働は8時間分の労働となる。だから長期的には経済成長しないことになる。
次に、生身の労働の複雑度は変わらないけれど、使う道具・機械・労働組織や分業の仕方などで随分時間当たりの生産量が違ってくる場合がある。マルクスはこれを特別剰余価値の生産と呼んだ、その場合同じ一時間の労働でも以前の10倍、100倍に成る場合がある。マルクスは、それを生産手段や組織などによって、「強められた」労働と呼び、確かに一時間の労働が10時間や100時間の価値を生むと認めたけれど、それもその機械や組織での労働が普及すれば、1時間の労働は1時間分の価値をうむことになる。
だから一人当たりのGDPを基準に経済成長を考える限り、人口と比例した経済成長しか考えられなくなり、人口増加率が0.8%だとすると超長期的な経済成長率も0.8%になってしまう。最近は人口が頭打ちになるという仮説が有力なので、経済成長率もやがてマイナスになってしまうことになる。
一方、物質的な生産力は科学技術の発展によってどんどん発達していくから、生み出される効用やサービスは人口増加率をはるかに上回る割合で増加していく。どれだけ増えたかは数量・効用量、サービス量などで計測できる。しかしそれは価格で測っていないので、GDP的な成長ではない。
マルクスの価値理論でいくと生産物全体の生産に費やされた現在及び過去の労働量になる。例えば、パソコン一台の生産に要した生身の労働者の労働時間が部品から完成品に至るまでで計10時間かかっているとする。その際に使用される原材料の価値も10時間分の価値に相当し、機械や道具の減価償却費も10時間分だとしたら計30時間分の労働時間の結晶だということになる。
もちろんこの労働時間は平均的な労働時間に換算されているので、その年の生産物とサービスの価値の総計はその年の労働者の総労働時間と等しいことになり、平均的労働時間が一日8時間なら、8時間×労働人口=GDPであることに変わりはない。
だとすると生身の労働者の労働だけが価値を生むことを前提にしたマルクス流の労働価値説では経済成長について議論すること自体成り立たないし、人口増加率以上の経済成長も目指すことはナンセンスにならないか。そうなると定常化経済論に相応しいということになるのか、ピケティは1.5%程度の経済成長率に落ち着くと見ているけれど。
私は価値論の大前提を考え直して、経済成長論を組み立て直すべきだと考えているが、マルクス研究者にはそれぞれ思うところがあると思うので、ご意見を陳述願います。ただしできるだけ論拠を上げて論証する形にしてください。
|
|
|
|
|
|
|
|
カール・マルクス 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
カール・マルクスのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31947人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82527人