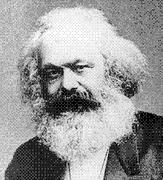以下の論稿は『ウェブマガジンプロメテウス』に掲載したものですが、マルクスの剰余価値理論の問題点を検討し、そこから21世紀の脱労働社会の新しい分配理論の基礎づけに脱構築できないか試みたものです。本当に脱労働社会になってしまえば、資本家ー労働者の搾取関係が社会の基本構造ではなくなってしまうので、剰余価値理論も分配理論に転化せざるを得ません。
これに対して脱労働社会化は理論的にあり得ないとか、労働者の労働だけが価値を生むという立場をあくまでまもるべきだとかいえるでしょうか?大いに議論して下さい。
https:/
21世紀の剰余価値論-搾取論から分配論への脱構築
文責 やすいゆたか
□石塚正英さんに拙稿「AIやロボットも剰余価値を生む可変資本か?」を慧眼と高い評価を頂いた。35年前の『人間観の転換ーマルクス物神性論批判』は学界ではシカトされ、本もほとんど売れなかったが石塚さんは高評価で、季刊クリティーク創刊にあたり、私を編集長にと推薦された。
https:/
□その時は初対面で、わけが分からず面食らった。それから長い付き合いで、随分彼の議論から啓発された。イエスの「聖餐復活仮説」も「歴史知」による日本古代史解明も彼の影響抜きには語れない。今回のAIも剰余価値を生むという議論も、石塚さんだけの高評価に終わってしまうのかどうか?
□我々の若い頃は、60年安保闘争後に高校生になり、社会科学を学習するというと『賃労働と資本』『共産党宣言』『空想から科学へ』と相場が決まっていた。要するに資本主義というのは、資本家が労働者の生み出した剰余価値を搾取する体制だということである。
□だから資本主義の矛盾の解決方法は、資本家が生産手段を独占して労働者を支配する体制をひっくりかえすことである。資本家は国家権力を握って、この体制を固めているから、国家権力を労働者が手に入れて、企業を国有化して労働者の支配下に置けばいいみたいに理解していた。
□価値を生み出しているのはあくまで労働者の労働であり、機械は富を生産する際の手段にすぎない。しかし産業革命以降機械の圧倒的な発展であたかも機械が価値を生み出しているかに倒錯視されているというのだ。
□マルクスは商品段階からフェティシズムを説くが、剰余価値理論としては実は機械が価値を生むのはフェティシズムであると言いたいのだ。生産過程で、機械は減価償却分だけ価値減耗するが、その分の価値を生産物に生み出すかに現象する。しかし機械だから価値を生んでいない筈である。
□マルクスはこれを「価値移転」として説明した。労働者の労働が生産手段の価値を生産物に移転させたという説明だ。つまり原材料・燃料・機械等の価値は生産物に変わる事で、生産物に移る事になるが、生産物を作ったのはあくまで労働者の労働だから価値移転させたのも具体的有用労働だという。
□生産の主体、労働の主体はあくまで労働者であって、機械は生産手段でしかない、機械がいかに生産の主役に見えても、機械を動かす労働者がいなければ生産できないという理屈である。新型コロナの流行で世界の工場である中国経済の麻痺で、世界経済がピンチになっていることも参考になる。
□しかしそれは電気が供給されないと人も機械も働けないということで相身互いである。やはり機械は生産過程で価値減耗分だけの価値を生産物に生み出していると見なしてもいい筈である。マルクスは人間が主体、機械は手段という図式にこだわっているからそうなってしまうだけである。
□むしろ機械制生産では人は機械に合わせて働かなくてはならないから、機械から切り離された人が主体とは言えないのである。つまり人間は機械を包摂して初めて主体なのである。つまりマン-マシンシステムが全体として人間なのであって、身体部分だけが主体で機械が手段とは言えくなっている。
□つまりもはや主体-手段という図式では捉えられなく成っているのに、マルクスは敢えて、資本主義を資本家対労働者の搾取関係に還元しようとしたために、主体-手段図式をもちだしたのである。それは分業の仕組みの導入や新鋭機の導入で生産量が飛躍することによる特別剰余価値生産ではより極端である。
□変化したのは労働の組織方法であったり、機械である。労働者の労働の強度・複雑度は単純化してむしろ減っている場合が多い。それでも単位時間あたりの生産量は何十倍、何百倍になる。この方法や機械が普及するまでの間、既成のやり方での生産も含めた平均として市場では通用する。
□だから一時間あたりこれまでの何十倍、何百倍の価値が生み出されるが、その価値を生み出したのはだれかということで、明らかに組織方法や新鋭機械だと思うのはマルクスに言わせると倒錯なのである。つまり労働しているのはあくまでも労働者であって機械ではない。
□だから新鋭機で強められた労働者の労働が価値を生んだとマルクスは啓蒙する。しかしこの説明は苦しい。複雑度が同じなら労働者は以前と同価値を対象化し、残りは新鋭機が生み出したとみなしても良いはずである。ここでも人間を生身の労働者に限定し、機械を手段に固定しているからだ。
□実際新鋭機の導入で、省力化が進む、労働者は機械に代替されて減っていく。機械の方が生産性が高ければ、代替させた方が利潤が大きくなる。とすると機械の発達は労働者から雇用を奪い、他に収入源がない労働者は餓死するしかなくなる。しかし実際は労働者階級は増加し、豊かになっている。
□それはそのイノベーションが新たな産業分野を興し、そこで雇用が拡大して失業を吸収したからである。それに生産力は膨れ上がったので、労働者は安価に生活必需品を入手できるようになる。しかしどの分野でも自動化が進むと、どの職場でも生身の労働力はほとんど要らない脱労働社会になる。
□その趨勢を人間の職場が機械に奪われると反発することはない。人間の方が低コストなら代替されることはない。つまり雇用の現場に活躍の場がなくなったとしても別の場で人間としての能力を実現すればいいのだ。ということは機械が人間に代わって労働し、価値を生む事もできているのである。
□つまりAIやロボットは生産や流通や販売の現場で自己の価格=生産費+平均利潤以上の価値つまり剰余価値を生み出す。その一部は企業利潤に、その他は直接間接に脱労働者に回される。この剰余価値を生み出したのは、ごく僅か残った労働者の強められた労働だと言うマルクス特有の理屈は説得力がない。
 AIやロボットが剰余価値を生むなら、その価格が剰余価値がゼロまで上昇して結局不変資本になるのではないかという批判が予想される。しかしでは何故生身の労働者の価格は上昇しなかったのか?マルクスは相対的過剰人口が原因だとした。つまり資本主義の発達は両極化に向かい大部分だった中間階級は没落して常に労働者階級は増え続ける。また技術革新は常に省力化を伴って、失業者を生み出す。この二つの理由が賃金が最低限度の生活費に抑え込まれる原因である。
AIやロボットが剰余価値を生むなら、その価格が剰余価値がゼロまで上昇して結局不変資本になるのではないかという批判が予想される。しかしでは何故生身の労働者の価格は上昇しなかったのか?マルクスは相対的過剰人口が原因だとした。つまり資本主義の発達は両極化に向かい大部分だった中間階級は没落して常に労働者階級は増え続ける。また技術革新は常に省力化を伴って、失業者を生み出す。この二つの理由が賃金が最低限度の生活費に抑え込まれる原因である。
 だとすると、AIやロボットも不断に続く開発競争で価格は生産費+平均利潤以上には上がらない。生産コストの低い途上国が教育の普及などで開発能力ができると、先進国の製品は「生産費+平均利潤」すら保てなくなって、撤退せざるを得なくなるかも知れない。つまりAIやロボットが剰余価値を生む条件はなくならない。
だとすると、AIやロボットも不断に続く開発競争で価格は生産費+平均利潤以上には上がらない。生産コストの低い途上国が教育の普及などで開発能力ができると、先進国の製品は「生産費+平均利潤」すら保てなくなって、撤退せざるを得なくなるかも知れない。つまりAIやロボットが剰余価値を生む条件はなくならない。
□だから機械に職場を奪われること反発しても虚しい抵抗だとしたら、脱労働者は何によって所得を得るのがよいか。資産や才覚次第で企業家やスポーツ文化、医師、弁護士などで活躍するのもいいが、その需要はごく一部である。大部分は雇用にありつけてもワークシェアでごく短時間である。
□そこで最低限度の生活費はベーシックインカムで国民全体に無条件で給付すればいいという意見が有力に成りつつある。しかし脱労働社会が実現すれば雇用は人口の一割未満だという。大部分はベーシックインカムだけが所得になり、最低限度が標準に成る。しかもそれで結構文化的に暮らせる。
□だとしたら怠惰な停滞した活気のない社会になりかねない。一国だけしか存在しないとしたらそれも或る種のユートピアだが、グローバル化は必然的なので、停滞していたら、発展し続ける国の商品に席巻されて、国内産業は空洞化してしまうことになる。発展的な社会を維持するためにはPI(参加型所得)を実施すべきである。
□PIとは、学習・文化・スポーツ・ボランティアなどの社会的に有意義な活動に対して、その量・質・貢献度を評定して、報酬する制度である。実はそれらの活動がなければ生産は維持・発展できないのだから、それらの活動も価値を生み出していると認定して、当然の報酬として国家が財政から支給する。
□もしそれを実施しなければ、所得がないので、ものは売れず経済はストップする。富はイノベーションの発展で増え続けているので、その増加の範囲内なら赤字国債で賄っても、うまく循環すれば償還でき、累積債務にはならない。つまり自動化によって剰余価値は増えているのだから大丈夫。
□だから21世紀の剰余価値理論は、資本家が労働者を搾取する理論から脱皮して、自動機械が生み出す剰余価値を社会的に有意義な活動する脱労働者に分配する理論へと脱構築される。その理論を構築する際にマルクスの『資本論』は批判的に克服されるべきものとして大いに意義があるのだ。
□蛇足だが『資本論』の剰余価値理論が資本主義の搾取構造を明解に示したことの意義を否定しているのではない。そのことを踏まえた上で、21世紀の脱労働社会化に伴って、新たな分配理論を構築する必要に迫られている今日、労働者の労働だけが価値を生み、価値を増殖する可変資本だという認識に留まっていては新時代の分配理論が築けない。脱労働者化した人々に所得が保証されないと未来はなくなってしまうということである。
これに対して脱労働社会化は理論的にあり得ないとか、労働者の労働だけが価値を生むという立場をあくまでまもるべきだとかいえるでしょうか?大いに議論して下さい。
https:/
21世紀の剰余価値論-搾取論から分配論への脱構築
文責 やすいゆたか
□石塚正英さんに拙稿「AIやロボットも剰余価値を生む可変資本か?」を慧眼と高い評価を頂いた。35年前の『人間観の転換ーマルクス物神性論批判』は学界ではシカトされ、本もほとんど売れなかったが石塚さんは高評価で、季刊クリティーク創刊にあたり、私を編集長にと推薦された。
https:/
□その時は初対面で、わけが分からず面食らった。それから長い付き合いで、随分彼の議論から啓発された。イエスの「聖餐復活仮説」も「歴史知」による日本古代史解明も彼の影響抜きには語れない。今回のAIも剰余価値を生むという議論も、石塚さんだけの高評価に終わってしまうのかどうか?
□我々の若い頃は、60年安保闘争後に高校生になり、社会科学を学習するというと『賃労働と資本』『共産党宣言』『空想から科学へ』と相場が決まっていた。要するに資本主義というのは、資本家が労働者の生み出した剰余価値を搾取する体制だということである。
□だから資本主義の矛盾の解決方法は、資本家が生産手段を独占して労働者を支配する体制をひっくりかえすことである。資本家は国家権力を握って、この体制を固めているから、国家権力を労働者が手に入れて、企業を国有化して労働者の支配下に置けばいいみたいに理解していた。
□価値を生み出しているのはあくまで労働者の労働であり、機械は富を生産する際の手段にすぎない。しかし産業革命以降機械の圧倒的な発展であたかも機械が価値を生み出しているかに倒錯視されているというのだ。
□マルクスは商品段階からフェティシズムを説くが、剰余価値理論としては実は機械が価値を生むのはフェティシズムであると言いたいのだ。生産過程で、機械は減価償却分だけ価値減耗するが、その分の価値を生産物に生み出すかに現象する。しかし機械だから価値を生んでいない筈である。
□マルクスはこれを「価値移転」として説明した。労働者の労働が生産手段の価値を生産物に移転させたという説明だ。つまり原材料・燃料・機械等の価値は生産物に変わる事で、生産物に移る事になるが、生産物を作ったのはあくまで労働者の労働だから価値移転させたのも具体的有用労働だという。
□生産の主体、労働の主体はあくまで労働者であって、機械は生産手段でしかない、機械がいかに生産の主役に見えても、機械を動かす労働者がいなければ生産できないという理屈である。新型コロナの流行で世界の工場である中国経済の麻痺で、世界経済がピンチになっていることも参考になる。
□しかしそれは電気が供給されないと人も機械も働けないということで相身互いである。やはり機械は生産過程で価値減耗分だけの価値を生産物に生み出していると見なしてもいい筈である。マルクスは人間が主体、機械は手段という図式にこだわっているからそうなってしまうだけである。
□むしろ機械制生産では人は機械に合わせて働かなくてはならないから、機械から切り離された人が主体とは言えないのである。つまり人間は機械を包摂して初めて主体なのである。つまりマン-マシンシステムが全体として人間なのであって、身体部分だけが主体で機械が手段とは言えくなっている。
□つまりもはや主体-手段という図式では捉えられなく成っているのに、マルクスは敢えて、資本主義を資本家対労働者の搾取関係に還元しようとしたために、主体-手段図式をもちだしたのである。それは分業の仕組みの導入や新鋭機の導入で生産量が飛躍することによる特別剰余価値生産ではより極端である。
□変化したのは労働の組織方法であったり、機械である。労働者の労働の強度・複雑度は単純化してむしろ減っている場合が多い。それでも単位時間あたりの生産量は何十倍、何百倍になる。この方法や機械が普及するまでの間、既成のやり方での生産も含めた平均として市場では通用する。
□だから一時間あたりこれまでの何十倍、何百倍の価値が生み出されるが、その価値を生み出したのはだれかということで、明らかに組織方法や新鋭機械だと思うのはマルクスに言わせると倒錯なのである。つまり労働しているのはあくまでも労働者であって機械ではない。
□だから新鋭機で強められた労働者の労働が価値を生んだとマルクスは啓蒙する。しかしこの説明は苦しい。複雑度が同じなら労働者は以前と同価値を対象化し、残りは新鋭機が生み出したとみなしても良いはずである。ここでも人間を生身の労働者に限定し、機械を手段に固定しているからだ。
□実際新鋭機の導入で、省力化が進む、労働者は機械に代替されて減っていく。機械の方が生産性が高ければ、代替させた方が利潤が大きくなる。とすると機械の発達は労働者から雇用を奪い、他に収入源がない労働者は餓死するしかなくなる。しかし実際は労働者階級は増加し、豊かになっている。
□それはそのイノベーションが新たな産業分野を興し、そこで雇用が拡大して失業を吸収したからである。それに生産力は膨れ上がったので、労働者は安価に生活必需品を入手できるようになる。しかしどの分野でも自動化が進むと、どの職場でも生身の労働力はほとんど要らない脱労働社会になる。
□その趨勢を人間の職場が機械に奪われると反発することはない。人間の方が低コストなら代替されることはない。つまり雇用の現場に活躍の場がなくなったとしても別の場で人間としての能力を実現すればいいのだ。ということは機械が人間に代わって労働し、価値を生む事もできているのである。
□つまりAIやロボットは生産や流通や販売の現場で自己の価格=生産費+平均利潤以上の価値つまり剰余価値を生み出す。その一部は企業利潤に、その他は直接間接に脱労働者に回される。この剰余価値を生み出したのは、ごく僅か残った労働者の強められた労働だと言うマルクス特有の理屈は説得力がない。
□だから機械に職場を奪われること反発しても虚しい抵抗だとしたら、脱労働者は何によって所得を得るのがよいか。資産や才覚次第で企業家やスポーツ文化、医師、弁護士などで活躍するのもいいが、その需要はごく一部である。大部分は雇用にありつけてもワークシェアでごく短時間である。
□そこで最低限度の生活費はベーシックインカムで国民全体に無条件で給付すればいいという意見が有力に成りつつある。しかし脱労働社会が実現すれば雇用は人口の一割未満だという。大部分はベーシックインカムだけが所得になり、最低限度が標準に成る。しかもそれで結構文化的に暮らせる。
□だとしたら怠惰な停滞した活気のない社会になりかねない。一国だけしか存在しないとしたらそれも或る種のユートピアだが、グローバル化は必然的なので、停滞していたら、発展し続ける国の商品に席巻されて、国内産業は空洞化してしまうことになる。発展的な社会を維持するためにはPI(参加型所得)を実施すべきである。
□PIとは、学習・文化・スポーツ・ボランティアなどの社会的に有意義な活動に対して、その量・質・貢献度を評定して、報酬する制度である。実はそれらの活動がなければ生産は維持・発展できないのだから、それらの活動も価値を生み出していると認定して、当然の報酬として国家が財政から支給する。
□もしそれを実施しなければ、所得がないので、ものは売れず経済はストップする。富はイノベーションの発展で増え続けているので、その増加の範囲内なら赤字国債で賄っても、うまく循環すれば償還でき、累積債務にはならない。つまり自動化によって剰余価値は増えているのだから大丈夫。
□だから21世紀の剰余価値理論は、資本家が労働者を搾取する理論から脱皮して、自動機械が生み出す剰余価値を社会的に有意義な活動する脱労働者に分配する理論へと脱構築される。その理論を構築する際にマルクスの『資本論』は批判的に克服されるべきものとして大いに意義があるのだ。
□蛇足だが『資本論』の剰余価値理論が資本主義の搾取構造を明解に示したことの意義を否定しているのではない。そのことを踏まえた上で、21世紀の脱労働社会化に伴って、新たな分配理論を構築する必要に迫られている今日、労働者の労働だけが価値を生み、価値を増殖する可変資本だという認識に留まっていては新時代の分配理論が築けない。脱労働者化した人々に所得が保証されないと未来はなくなってしまうということである。
|
|
|
|
コメント(50)
>>[18] 何か誤解していませんか、機械の活動ではありません。平均的な性能の機械は減価償却分だけ価値を製品に対象化しているということです。それだと不変資本ですね。だから減価償却費の何倍もの価値を対象化するような機械は剰余価値を生み出していると言える。
活動価値は生身の人間が脱労働者化して、社会的に有意義な活動をしている場合です。学習やスポーツ、文化活動、ボランティア活動はそのことによって商品やサービスを消費するだけではなく、文化を継承、発展させ、社会を良好に保ち活性化することで、生産活動をより活発にし、技術革新を促すので、その活動を量・質・貢献度で計算して報酬を支払うというものです。つまりそれらの活動も広い意味でのコストに組み込むという発想です。
活動価値は生身の人間が脱労働者化して、社会的に有意義な活動をしている場合です。学習やスポーツ、文化活動、ボランティア活動はそのことによって商品やサービスを消費するだけではなく、文化を継承、発展させ、社会を良好に保ち活性化することで、生産活動をより活発にし、技術革新を促すので、その活動を量・質・貢献度で計算して報酬を支払うというものです。つまりそれらの活動も広い意味でのコストに組み込むという発想です。
例えばです。
ボランティアは無償でやるからボランティアな訳です。
アマチュアスポーツやアマチュア文化はアマチュアでやることに意義があるわけですよね。
ここを有償化するには活動価値だからでは弱いんじゃないでしょうか。
一方でAIが主軸になるオートメーションでベーシックインカムは必須になります。
貨幣というのは必須性というのもポイントだと思います。
一方で活動的にするためになんらかのポイントをあげることには一つのアイディアとして意義があります。
変な話ですが私は一応プロの作家を目指してますが、その動機はお金が欲しいというより活動価値的な話でもあるからです。
他方でポイント化することで失われる活動の意義もあります。
例えば売れなくても良いから良いものを書きたいとか死んでからでも良いから認められたいとかです。
ボランティアは無償でやるからボランティアな訳です。
アマチュアスポーツやアマチュア文化はアマチュアでやることに意義があるわけですよね。
ここを有償化するには活動価値だからでは弱いんじゃないでしょうか。
一方でAIが主軸になるオートメーションでベーシックインカムは必須になります。
貨幣というのは必須性というのもポイントだと思います。
一方で活動的にするためになんらかのポイントをあげることには一つのアイディアとして意義があります。
変な話ですが私は一応プロの作家を目指してますが、その動機はお金が欲しいというより活動価値的な話でもあるからです。
他方でポイント化することで失われる活動の意義もあります。
例えば売れなくても良いから良いものを書きたいとか死んでからでも良いから認められたいとかです。
>>[30] AI時代は潜在的能力としては加速度的に生産力が発展する能力があるのですが、消費主体が雇用がなくなっていくので、所得がなく需要が冷え込んで、結局極端なデフレになり経済が衰退します。BIでは最低限度の生活水準に平準化します。
自由に事業を作って稼いだり、そこで働けばいいといいますが、元々不要になった労働力ですから、手作りやサービス業などである程度稼げても、そこにもAIゃロボットは進出しますから、それとの競争もありたいして稼げません。
つまり殆どが職をなくしますから、大部分はBIだけの収入になるということです。それならAIなどの先端技術の能力を引き出せません。それで生身の人間の活動を活気あるものにすることによって、需要を高めるのです。量・質・貢献度に応じて報酬すれば、活動はどんどん活発化し、AIはそれに呼応して能力を発揮できるということです。
自由に事業を作って稼いだり、そこで働けばいいといいますが、元々不要になった労働力ですから、手作りやサービス業などである程度稼げても、そこにもAIゃロボットは進出しますから、それとの競争もありたいして稼げません。
つまり殆どが職をなくしますから、大部分はBIだけの収入になるということです。それならAIなどの先端技術の能力を引き出せません。それで生身の人間の活動を活気あるものにすることによって、需要を高めるのです。量・質・貢献度に応じて報酬すれば、活動はどんどん活発化し、AIはそれに呼応して能力を発揮できるということです。
>>[31] お気持ちは十分分かります。私もマルクスの疎外論研究に情熱を燃やしたくちですから、お金のためではなく、自己実現として活動をしたいと言う気持をもっています。もし世界がBIを実施してあとは御自由にのんびりやってくださいということになれば、多少だらけてもそれはそれて一つのユートピアですが、商品経済、貨幣経済が続く中で、必ず競争原理でPIを採用する国がでてきますと、そこは勉強すればするほど、スポーツで頑張れば頑張るほど、ボランティアで活躍すればするほど報酬になるので、技術革新も進み、BIでのんびりやりたいひとだけやりなさいの国は空洞化してしますいます。私も若い頃は性善説で労働こそ本来は最大の喜びのはずだとか、勉強で怠けるなんて本来あり得ないと思っていましたが、自分を含めて人間の怠惰性、放置しておいたら腐ってしまうということが嫌というほど分かりました。貨幣経済の中ではやはり量・質・貢献度に貨幣で報いるという疎外された方法が一番効果的です。ですから貨幣のない社会を作って共同所有で一から原理的にどう活動を刺激するかを考えるなら、疎外されない方法も考えられると思いますが。
>>[35] それは井上智洋さんのBI論では、技術革新が進んでいくと、今までのBIの額では需要が追いつかなくなるから、ヘリコプターマネーで臨時給付したり、BIを引き上げていくという発想です。それは自動的に技術革新が進んでいくように考えられているわけです。そうではなくて、人間活動が沈滞化すれば、いろんな新しい便利なものができたり、高度な文化が生まれたりしても欲望や知性が発達しないとお金だけもらえても需要は増えません。つまり生身の人間も必死で頑張らないと、自分の限界に挑戦して学問を極めて、体力の限界に挑戦し、より高い文化を生み出そうと必死でもがかないすとだめなのです。BIを与えられてなんでもあげるよと機械に飼育されているようじゃ文明は衰退します。機械は決して人間の外部ではないのです。表裏一体、絶対矛盾的自己同一みたいなものです。
>>[38]
わかりましたなかなか興味深い主題です。
プロフェッショナルとは市場価値です。
アマチュアとは主体価値です。
ここに新人賞があります。話を簡単にするため思想の新人賞にしましょう。
例えばです。村上春樹が思想に挑戦します。売れます。ベストセラー。
ニーチェとマルクスが挑戦して落選
その後ニーチェとマルクスは死後認められます。
これは市場価値がニーチェとマルクスに追いついたのです。
村上春樹なんか問題になりません
このように市場価値は絶対ではありません。
もう一つ
では村上春樹は下らないのでしょうか
そういうことでもありません。
村上春樹より下な作家は山ほどいます。
ですからPIである程度のこともできるでしょう
でも絶対じゃないのです。
そこのところの使い道です。
わかりましたなかなか興味深い主題です。
プロフェッショナルとは市場価値です。
アマチュアとは主体価値です。
ここに新人賞があります。話を簡単にするため思想の新人賞にしましょう。
例えばです。村上春樹が思想に挑戦します。売れます。ベストセラー。
ニーチェとマルクスが挑戦して落選
その後ニーチェとマルクスは死後認められます。
これは市場価値がニーチェとマルクスに追いついたのです。
村上春樹なんか問題になりません
このように市場価値は絶対ではありません。
もう一つ
では村上春樹は下らないのでしょうか
そういうことでもありません。
村上春樹より下な作家は山ほどいます。
ですからPIである程度のこともできるでしょう
でも絶対じゃないのです。
そこのところの使い道です。
市場価値要するにプロフェッショナルな価値について考えてみましょう
私は貨幣を数として考えますが労働なのか熟練なのか流通なのか天然なのか
とにかく貨幣と数として現れる現象を投票する仕組みです。
良いものは売れると言いますが評価は完全ではありません。
例えば村上春樹<ニーチェ、マルクスと私は評価しましたが実は続きがあって
私は経済学レベルのマルクスをあまり評価してません。価値ということでも曖昧だし
論理も強引です。学会や市場では評価は高いですがこの先はわかりません。
そもそも市場価値で評価が正しいのかが自明ではありません。
村上春樹の方が優れてるんだという人もたくさんいると思いますし
ドストエフスキーより村上春樹は売れてるがそれってどうなのと思います。
一方で市場価値はそれなりに評価しなければやっていけません。
私は貨幣を数として考えますが労働なのか熟練なのか流通なのか天然なのか
とにかく貨幣と数として現れる現象を投票する仕組みです。
良いものは売れると言いますが評価は完全ではありません。
例えば村上春樹<ニーチェ、マルクスと私は評価しましたが実は続きがあって
私は経済学レベルのマルクスをあまり評価してません。価値ということでも曖昧だし
論理も強引です。学会や市場では評価は高いですがこの先はわかりません。
そもそも市場価値で評価が正しいのかが自明ではありません。
村上春樹の方が優れてるんだという人もたくさんいると思いますし
ドストエフスキーより村上春樹は売れてるがそれってどうなのと思います。
一方で市場価値はそれなりに評価しなければやっていけません。
>>[49]
私は思うんですがこれだけの話だと、AIへの移行の話を総合的にもっと論説だけじゃなくシミュレーションしないとPIだとか言ってる前にいろんな想定があってその想定をやっていかないといけないと思うんですよ。
同時にですねマルクスのモデルは変なところがあって、資本主義が滅ぶ原因は有機的構成の増大ですが、これは彼の等価交換のモデルが前提ですから、不等価交換している現実に近づけると、搾取のない安く買って高く売るだけがある理想的状態になるわけですね。
私はモデルとして経済学を考えることが重要だと思いますがよく不等価交換をモデルに入れることをマルクス経済学の人は拒む傾向にありますね。
私は思うんですがこれだけの話だと、AIへの移行の話を総合的にもっと論説だけじゃなくシミュレーションしないとPIだとか言ってる前にいろんな想定があってその想定をやっていかないといけないと思うんですよ。
同時にですねマルクスのモデルは変なところがあって、資本主義が滅ぶ原因は有機的構成の増大ですが、これは彼の等価交換のモデルが前提ですから、不等価交換している現実に近づけると、搾取のない安く買って高く売るだけがある理想的状態になるわけですね。
私はモデルとして経済学を考えることが重要だと思いますがよく不等価交換をモデルに入れることをマルクス経済学の人は拒む傾向にありますね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
カール・マルクス 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
カール・マルクスのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37840人
- 2位
- 酒好き
- 170672人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89537人