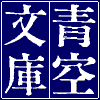|
|
|
|
コメント(5)
海野十三「十八時の音楽浴」を読みました。
小学生の頃、田舎の祖父母の家で、海野十三の「海底都市」という本を見つけ、読んだことがあります。なかなか面白かったです。
装丁からすると戦前の古い本で、おそらく父が少年時代、読んだ本だと思われます。
中高生になると星新一、筒井康隆、小松左京といった日本SF文学のパイオニアとされる作家にはまりました。
しかし彼らの先輩である海野十三の本はすべて絶版で本屋で見つかりません。本来、海野十三こそ日本SFのパイオニアでは、と思っていましたが海野の時代にはまだSFという語はなく、空想科学小説と呼ばれていたのかもしれません。
大学生の頃、早川文庫の復刻版で海野十三の「十八時の音楽浴」が出版されたのを記憶しておりますが、結局、そのときは読む機会がありませんでした。
おそらく海野の代表作が「十八時の音楽浴」だろうと思い、「海底都市」が面白かっただけに題名だけが記憶に長く残っていました。
青空文庫で無料で「十八時の音楽浴」が読めることを知り、早速ダウンロードして読んでみました。
人物描写が悪い意味で漫画的で、のめり込みづらかったですが、国民に音楽を聞かせて洗脳させるというアイデアが、この時代のSFとしては斬新だと思いました。
フィリップ・K・ディックの「電気羊はアンドロイドの夢を見るか」でも、冒頭で主人公夫婦が音楽を聴いて、感情をコントロールする、というストーリーが出てきます。
二つの小説とも、音楽を聴くことで人間の精神をコントロールされることに対して、それぞれの登場人物たちが、人間性を否定される行為だとして反発します。
海野もディックもお互いの小説を読んだことはないと推測しますが、両者が共通している点は驚くべきでしょう。
最後のオチもあり、「十八時の音楽浴」は少し古いが現代人が十分読むにあたいするSFと言えます。
小学生の頃、田舎の祖父母の家で、海野十三の「海底都市」という本を見つけ、読んだことがあります。なかなか面白かったです。
装丁からすると戦前の古い本で、おそらく父が少年時代、読んだ本だと思われます。
中高生になると星新一、筒井康隆、小松左京といった日本SF文学のパイオニアとされる作家にはまりました。
しかし彼らの先輩である海野十三の本はすべて絶版で本屋で見つかりません。本来、海野十三こそ日本SFのパイオニアでは、と思っていましたが海野の時代にはまだSFという語はなく、空想科学小説と呼ばれていたのかもしれません。
大学生の頃、早川文庫の復刻版で海野十三の「十八時の音楽浴」が出版されたのを記憶しておりますが、結局、そのときは読む機会がありませんでした。
おそらく海野の代表作が「十八時の音楽浴」だろうと思い、「海底都市」が面白かっただけに題名だけが記憶に長く残っていました。
青空文庫で無料で「十八時の音楽浴」が読めることを知り、早速ダウンロードして読んでみました。
人物描写が悪い意味で漫画的で、のめり込みづらかったですが、国民に音楽を聞かせて洗脳させるというアイデアが、この時代のSFとしては斬新だと思いました。
フィリップ・K・ディックの「電気羊はアンドロイドの夢を見るか」でも、冒頭で主人公夫婦が音楽を聴いて、感情をコントロールする、というストーリーが出てきます。
二つの小説とも、音楽を聴くことで人間の精神をコントロールされることに対して、それぞれの登場人物たちが、人間性を否定される行為だとして反発します。
海野もディックもお互いの小説を読んだことはないと推測しますが、両者が共通している点は驚くべきでしょう。
最後のオチもあり、「十八時の音楽浴」は少し古いが現代人が十分読むにあたいするSFと言えます。
織田作之助「夫婦善哉」を読みました。
作家、織田作之助の名前を初めて知ったのは、以前勤めた会社の上司が神田の古本屋で探している小説がいくつかあると言うので、何の本ですかと聞いたときでした。複数の作家の名の中に織田作之助がありました。
その後、ファミレス和食「さと」で冬に「夫婦善哉」を食べたとき、店のメニューにこれは織田作之助の同名小説に因んだスイーツだと解説がありました。
さらにその後、NHKでこの小説を解説していたのを見て、大まかなストーリーを知りました。番組によると、「夫婦善哉」は大阪B級グルメを紹介したグルメ小説。実は例の上司が無類のグルメ通なので、彼がこの小説に興味を持った理由がなんとなくわかった気がしました。
さて、名前だけ知ってるもののこれまで読む機会に恵まれなかった「夫婦善哉」。青空文庫で見つけ、早速ダウンロードしてみました。
読んだとき最初に感じたのは、グルメ小説というより、これは日本近代文学ーー純文学で模範とされる私小説的リアリティーを追及した小説だということです。
出会いから初老になるまでの夫婦の半生を描いた作品。主人公夫婦はヒロイックファンタジーに出てくるヒーローやヒロインとは真逆の、どこにでもいる平凡なダメ男とダメ女。既婚の柳吉が不倫し、うどん屋の娘で芸者の蝶子と駆け落ち。大阪に戻って、男は様々な商売を始めますが、どれも中途半端で店をつぶします。しかし悪い事ばかりでなく、親戚の遺産でまとまった金が入るなど、山あり谷ありの人生。
ラストシーンの蝶子の台詞「一人より女夫の方がええいうことでっしゃろ」は、倦怠期をとうに過ぎ、人生の酸いも甘いもかみ分けた熟年夫婦へのエールと読みました。
しかしながら、放蕩亭主にひたすら耐える女房の悲劇、といった単純な論評でおさまりきらない私小説ワールドのリアリズム。これが「夫婦善哉」執筆時の、作者、織田作之助の企みだったと推測します。
作家、織田作之助の名前を初めて知ったのは、以前勤めた会社の上司が神田の古本屋で探している小説がいくつかあると言うので、何の本ですかと聞いたときでした。複数の作家の名の中に織田作之助がありました。
その後、ファミレス和食「さと」で冬に「夫婦善哉」を食べたとき、店のメニューにこれは織田作之助の同名小説に因んだスイーツだと解説がありました。
さらにその後、NHKでこの小説を解説していたのを見て、大まかなストーリーを知りました。番組によると、「夫婦善哉」は大阪B級グルメを紹介したグルメ小説。実は例の上司が無類のグルメ通なので、彼がこの小説に興味を持った理由がなんとなくわかった気がしました。
さて、名前だけ知ってるもののこれまで読む機会に恵まれなかった「夫婦善哉」。青空文庫で見つけ、早速ダウンロードしてみました。
読んだとき最初に感じたのは、グルメ小説というより、これは日本近代文学ーー純文学で模範とされる私小説的リアリティーを追及した小説だということです。
出会いから初老になるまでの夫婦の半生を描いた作品。主人公夫婦はヒロイックファンタジーに出てくるヒーローやヒロインとは真逆の、どこにでもいる平凡なダメ男とダメ女。既婚の柳吉が不倫し、うどん屋の娘で芸者の蝶子と駆け落ち。大阪に戻って、男は様々な商売を始めますが、どれも中途半端で店をつぶします。しかし悪い事ばかりでなく、親戚の遺産でまとまった金が入るなど、山あり谷ありの人生。
ラストシーンの蝶子の台詞「一人より女夫の方がええいうことでっしゃろ」は、倦怠期をとうに過ぎ、人生の酸いも甘いもかみ分けた熟年夫婦へのエールと読みました。
しかしながら、放蕩亭主にひたすら耐える女房の悲劇、といった単純な論評でおさまりきらない私小説ワールドのリアリズム。これが「夫婦善哉」執筆時の、作者、織田作之助の企みだったと推測します。
コードウェイナー・スミスの「親友たち」を読了。
感想イコールネタバレになりそうなので、何を書いていいかわかりませんが、意外と面白かったこととショートショートのように最後のオチがすべての小説です。
病室で意識を取り戻す宇宙飛行士の主人公。仲間は無事かと医者に尋ねるが曖昧な返事。
医者たちは鎮静剤で主人公の興奮を和らげる。医師の告知は意外な結末に。
原文が読みやすいのか翻訳がよかったのか、昔の小説にしては一気に読めました。
コードウェイナー・スミスは名前だけ知ってるものの、これまで読む機会がありませんでした。
「人類補完機構シリーズ」で連作短編が有名とのことですが、アニメ、「新世紀エヴァンゲリオン」の「人類補完計画」はこれをパクったものでしょうか。
90年代初めぐらいに都内の大手書店で、コードウェイナー・スミスのフェア、または早川SF文庫の売れ筋フェアをやっていたような記憶があります。
その当時でも、コードウェイナー・スミスは昔の作家でしたが、昔の作品にしては面白い、という宣伝の仕方でした。
代表作「ノーストリリア」に羊の絵が書いてあり、早川SF文庫屈指のベストセラー「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」(フィリップ・K・ディック)とよく似た表紙のデザインにしていました。
感想イコールネタバレになりそうなので、何を書いていいかわかりませんが、意外と面白かったこととショートショートのように最後のオチがすべての小説です。
病室で意識を取り戻す宇宙飛行士の主人公。仲間は無事かと医者に尋ねるが曖昧な返事。
医者たちは鎮静剤で主人公の興奮を和らげる。医師の告知は意外な結末に。
原文が読みやすいのか翻訳がよかったのか、昔の小説にしては一気に読めました。
コードウェイナー・スミスは名前だけ知ってるものの、これまで読む機会がありませんでした。
「人類補完機構シリーズ」で連作短編が有名とのことですが、アニメ、「新世紀エヴァンゲリオン」の「人類補完計画」はこれをパクったものでしょうか。
90年代初めぐらいに都内の大手書店で、コードウェイナー・スミスのフェア、または早川SF文庫の売れ筋フェアをやっていたような記憶があります。
その当時でも、コードウェイナー・スミスは昔の作家でしたが、昔の作品にしては面白い、という宣伝の仕方でした。
代表作「ノーストリリア」に羊の絵が書いてあり、早川SF文庫屈指のベストセラー「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」(フィリップ・K・ディック)とよく似た表紙のデザインにしていました。
2018年1月11日、青空文庫に李箱(イ・サン)の詩が複数公開されました。
これまで李箱の存在は知らなかったのですが、韓国では有名な詩人、小説家とのこと。
本来、韓国語で作品を書いているようですが、今回公開されたのはすべて日本語で書かれた作品です。
一読した感想は、一言で言って、”抑制のきいた上質の前衛文学”といったところです。
ここで教科書的な解説です。
フランス文学史では前衛文学のムーヴメントは2回あります。1回目は19世紀末から20世紀初頭のアポリネールを中心とするシュールレアリズムやダダイズムのムーヴメント。2回目は戦後、サルトルおよびそれ以降のヌーボロマンのムーヴメント。
一方、アメリカ文学では戦後、バロウズなどのビートゼネレーションのムーヴメントがあります。
このうちフランス文学のシュールレアリズムとアメリカ文学のビートゼネレーションはいずれも文学というより、絵画、造形、音楽といった”非文学”のアーティストたちのムーヴメントで、その中にたまたま詩人が紛れ込んで前衛文学を発表しました。このため、これまでの文学の常識を逸脱した表現が特徴的と言えます。
一方、ヌーボロマンは文学を構造的に分析、研究した上で前衛を試みた、コテコテの活字メディアの前衛文学でした。
80年代のマルケスやボルヘスらの前衛ラテン文学は、どちらかと言えばこのヌーボロマンの系譜につながるものでしょう。
李箱は前者、つまりアポリネールやバロウズたちが試みた前衛文学に分類できると思います。つまり、前衛アートとしての文学です。
時代的にも戦前の詩人ですので、李箱自身もダダイズムを意識的に目指していたのかもしれません。
学生時代、現代詩手帖を購読し、寺山修司のアングラ芝居や実験映画にたしなみ、安部公房の前衛小説を読み、70年代のブリティッシュプログレを聴きまくり、エッシャーの展覧会に足を運び、さらにはカルトムービーのメッカ、四谷のイメージフォーラムの常連だった私は、筋金入りの前衛芸術オタクです。
その私から言わせれば、バブル時代にもてはやされた現代詩にくらべ、李箱の詩はいい意味で抑制がきいているように思えるのです。
完成度の高い前衛文学、というのとは少し違いますが、現代詩の悪い意味での支離滅裂やカオスがなく、虚無的または厭世的な基調低音で作品がまとめられています。
今回、公開された作品の中で一番注目したのは「AU MAGASIN DE NOUVEAUTES」でしょうか。
フランス語で「新しいお店にて」といった意味になるようです。詩は日本語で書かれますが、随所に中国語の単語が出てきます。
母国語が韓国語の李箱にとり、タイトルのフランス語も本文の日本語や中国語も外国語のはずです。
もしかしたら李箱は意図的に多国籍言語で作品を書いたのかもしれません。
作品を一貫して流れるトートロジー的表現もまた、言語を超越したところにある詩を目指していたのかもしれません。
李箱の詩を私は完全には理解していませんが、無意識のレベルで漠然と”好感”を持ちました。
日帝植民地時代の朝鮮に生きた李白。政治的抑圧感や反体制的メッセージをそこに読むことはできるでしょうが、前衛文学を志す以上、作者の関心は半分以上、文学上の方法論にあったのではないかと想像します。
これまで李箱の存在は知らなかったのですが、韓国では有名な詩人、小説家とのこと。
本来、韓国語で作品を書いているようですが、今回公開されたのはすべて日本語で書かれた作品です。
一読した感想は、一言で言って、”抑制のきいた上質の前衛文学”といったところです。
ここで教科書的な解説です。
フランス文学史では前衛文学のムーヴメントは2回あります。1回目は19世紀末から20世紀初頭のアポリネールを中心とするシュールレアリズムやダダイズムのムーヴメント。2回目は戦後、サルトルおよびそれ以降のヌーボロマンのムーヴメント。
一方、アメリカ文学では戦後、バロウズなどのビートゼネレーションのムーヴメントがあります。
このうちフランス文学のシュールレアリズムとアメリカ文学のビートゼネレーションはいずれも文学というより、絵画、造形、音楽といった”非文学”のアーティストたちのムーヴメントで、その中にたまたま詩人が紛れ込んで前衛文学を発表しました。このため、これまでの文学の常識を逸脱した表現が特徴的と言えます。
一方、ヌーボロマンは文学を構造的に分析、研究した上で前衛を試みた、コテコテの活字メディアの前衛文学でした。
80年代のマルケスやボルヘスらの前衛ラテン文学は、どちらかと言えばこのヌーボロマンの系譜につながるものでしょう。
李箱は前者、つまりアポリネールやバロウズたちが試みた前衛文学に分類できると思います。つまり、前衛アートとしての文学です。
時代的にも戦前の詩人ですので、李箱自身もダダイズムを意識的に目指していたのかもしれません。
学生時代、現代詩手帖を購読し、寺山修司のアングラ芝居や実験映画にたしなみ、安部公房の前衛小説を読み、70年代のブリティッシュプログレを聴きまくり、エッシャーの展覧会に足を運び、さらにはカルトムービーのメッカ、四谷のイメージフォーラムの常連だった私は、筋金入りの前衛芸術オタクです。
その私から言わせれば、バブル時代にもてはやされた現代詩にくらべ、李箱の詩はいい意味で抑制がきいているように思えるのです。
完成度の高い前衛文学、というのとは少し違いますが、現代詩の悪い意味での支離滅裂やカオスがなく、虚無的または厭世的な基調低音で作品がまとめられています。
今回、公開された作品の中で一番注目したのは「AU MAGASIN DE NOUVEAUTES」でしょうか。
フランス語で「新しいお店にて」といった意味になるようです。詩は日本語で書かれますが、随所に中国語の単語が出てきます。
母国語が韓国語の李箱にとり、タイトルのフランス語も本文の日本語や中国語も外国語のはずです。
もしかしたら李箱は意図的に多国籍言語で作品を書いたのかもしれません。
作品を一貫して流れるトートロジー的表現もまた、言語を超越したところにある詩を目指していたのかもしれません。
李箱の詩を私は完全には理解していませんが、無意識のレベルで漠然と”好感”を持ちました。
日帝植民地時代の朝鮮に生きた李白。政治的抑圧感や反体制的メッセージをそこに読むことはできるでしょうが、前衛文学を志す以上、作者の関心は半分以上、文学上の方法論にあったのではないかと想像します。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
青空文庫 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-