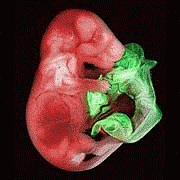ヒトゲノム:研究の長期戦略どこへ 理研の科学総合センター解散へ
http://
人間の全遺伝情報(ヒトゲノム)を解読する国際ヒトゲノム計画に貢献した「理化学研究所ゲノム科学総合研究センター」が3月末に解散する。産業への貢献が期待されたほど進まず、政府が独立行政法人の合理化を進める中で、見直し対象になった。欧米でも研究方針は頻繁に修正されるが、研究拠点の解散は珍しい。研究の一部は新組織で継続されるものの、センターとしての活動は10年間で終了することになり、ゲノム研究の長期戦略が論議を呼びそうだ。【田中泰義、青野由利】
◆10年間で1264億円投入
◇人材と資金を集中
ヒトゲノム計画は1980年代に提案され、米国を中心に国際協力で進められた。日本も90年代初めから参加し、98年にセンターが発足した。生物分野では初めて人材と資金を集中させた大規模研究機関で、10年間で約1264億円が投じられた。
この間、センターは21番染色体のゲノム解読で中心的な役割を果たし、チンパンジーやマウス、シロイヌナズナなどのゲノム解析でも成果をあげた。機能を持つ遺伝子のデータベースもマウスで作成した。榊佳之・同センター長は「新たな万能細胞である人工多能性幹細胞(iPS細胞)の開発も、われわれの基盤的な研究成果が支えた」と強調する。
◇学問的検討が不足
一方で、生物学における大型研究の戦略には課題も残した。
ゲノム解読では、使用機器の開発などに日本人が貢献した。しかし、日本の解読率はヒトゲノム全体の1割に満たなかった。このため「適切な時期に資金が投入されず、十分な国際貢献ができなかった」との批判が出た。
こうした声を踏まえ、政府は02年度以降、遺伝子から作られるたんぱく質の立体構造を決めるプロジェクト「タンパク3000」に積極的に予算を計上した。センターを中心に約578億円をつぎこみ、4187個の構造を決定したが、期待されたほど医薬品開発に直結しなかった。成果は見えにくく、再び研究戦略が問われた。
中村桂子・JT生命誌研究館長は「生物学は本質的に大型プロジェクトになじまない。ゲノム解読はプロジェクトに合う、まれな例だった。解読終了後は、それをどう展開するか考える必要があったのに、国際競争と称して学問的検討のないままタンパク3000などに資金を投じた」と指摘する。
結果的に組織は解散が決まった。センターを構成する5研究チームのうち1チームが研究を終了。他の4チームは理研の他組織と統合した新領域などとして再スタートする。
◇行革「見せしめ」の声も
合理化による研究拠点の改組を外部の専門家はどうみるか。
隅蔵(すみくら)康一・政策研究大学院大学准教授(科学技術政策)は「この分野の基盤は整備され、研究機関にとってゲノム解読装置やデータベースなどは普通のインフラになった。選択と集中の観点から発展的に研究体制を再編するのは妥当ではないか」と受け止める。
確かに、解読装置の機能向上は著しい。00年ごろにはヒトゲノムを1台で解読するには4年以上かかった。それが今では25〜40日で可能となり、10年にはわずか約2分に短縮される見通しだ。大量の機器を一研究機関に集中させる必要性は薄らいだ、との見方はセンター内にもある。
一方、吉岡斉・九州大教授(科学技術史)は「内外での評価を踏まえた上での判断と考えるが、行革のために見せしめ的に行った印象を受ける。研究機関に対し、短期間で成果を出せという風潮が強まるのではないか」と警戒する。
榊センター長は「10年間の成果が活用できるよう、国には今後も十分な対応を求めたい」と話している。
==============
■ことば
◇ヒトゲノム解読
人間の遺伝情報は細胞のDNAに、4種類の塩基を組み合わせた暗号文字で書き込まれている。ヒトゲノム計画は人間の全遺伝情報を担う約30億塩基対の配列を解読する国際プロジェクトとして90年代初頭に始まり、03年に終了した。その後、研究の焦点は、遺伝子の働きやたんぱく質の構造と機能、RNAの役割などに移ってきた。DNAなどの分子が細胞内で構成するネットワークの解明や、ゲノム解読で得られる大量データの情報処理も課題となっている。
==============
◇ゲノム計画の歴史◇
1988年 国際ヒトゲノム計画を推進する国際組織「HUGO」設立
90年 国際ヒトゲノム計画開始
96年 参加国が解読結果を直ちに公開することなどで合意
98年 理化学研究所ゲノム科学総合研究センター発足
2001年 ヒトゲノム解読概要発表
02年 タンパク3000計画開始
03年 ヒトゲノム解読完了
07年 タンパク3000計画終了
http://
人間の全遺伝情報(ヒトゲノム)を解読する国際ヒトゲノム計画に貢献した「理化学研究所ゲノム科学総合研究センター」が3月末に解散する。産業への貢献が期待されたほど進まず、政府が独立行政法人の合理化を進める中で、見直し対象になった。欧米でも研究方針は頻繁に修正されるが、研究拠点の解散は珍しい。研究の一部は新組織で継続されるものの、センターとしての活動は10年間で終了することになり、ゲノム研究の長期戦略が論議を呼びそうだ。【田中泰義、青野由利】
◆10年間で1264億円投入
◇人材と資金を集中
ヒトゲノム計画は1980年代に提案され、米国を中心に国際協力で進められた。日本も90年代初めから参加し、98年にセンターが発足した。生物分野では初めて人材と資金を集中させた大規模研究機関で、10年間で約1264億円が投じられた。
この間、センターは21番染色体のゲノム解読で中心的な役割を果たし、チンパンジーやマウス、シロイヌナズナなどのゲノム解析でも成果をあげた。機能を持つ遺伝子のデータベースもマウスで作成した。榊佳之・同センター長は「新たな万能細胞である人工多能性幹細胞(iPS細胞)の開発も、われわれの基盤的な研究成果が支えた」と強調する。
◇学問的検討が不足
一方で、生物学における大型研究の戦略には課題も残した。
ゲノム解読では、使用機器の開発などに日本人が貢献した。しかし、日本の解読率はヒトゲノム全体の1割に満たなかった。このため「適切な時期に資金が投入されず、十分な国際貢献ができなかった」との批判が出た。
こうした声を踏まえ、政府は02年度以降、遺伝子から作られるたんぱく質の立体構造を決めるプロジェクト「タンパク3000」に積極的に予算を計上した。センターを中心に約578億円をつぎこみ、4187個の構造を決定したが、期待されたほど医薬品開発に直結しなかった。成果は見えにくく、再び研究戦略が問われた。
中村桂子・JT生命誌研究館長は「生物学は本質的に大型プロジェクトになじまない。ゲノム解読はプロジェクトに合う、まれな例だった。解読終了後は、それをどう展開するか考える必要があったのに、国際競争と称して学問的検討のないままタンパク3000などに資金を投じた」と指摘する。
結果的に組織は解散が決まった。センターを構成する5研究チームのうち1チームが研究を終了。他の4チームは理研の他組織と統合した新領域などとして再スタートする。
◇行革「見せしめ」の声も
合理化による研究拠点の改組を外部の専門家はどうみるか。
隅蔵(すみくら)康一・政策研究大学院大学准教授(科学技術政策)は「この分野の基盤は整備され、研究機関にとってゲノム解読装置やデータベースなどは普通のインフラになった。選択と集中の観点から発展的に研究体制を再編するのは妥当ではないか」と受け止める。
確かに、解読装置の機能向上は著しい。00年ごろにはヒトゲノムを1台で解読するには4年以上かかった。それが今では25〜40日で可能となり、10年にはわずか約2分に短縮される見通しだ。大量の機器を一研究機関に集中させる必要性は薄らいだ、との見方はセンター内にもある。
一方、吉岡斉・九州大教授(科学技術史)は「内外での評価を踏まえた上での判断と考えるが、行革のために見せしめ的に行った印象を受ける。研究機関に対し、短期間で成果を出せという風潮が強まるのではないか」と警戒する。
榊センター長は「10年間の成果が活用できるよう、国には今後も十分な対応を求めたい」と話している。
==============
■ことば
◇ヒトゲノム解読
人間の遺伝情報は細胞のDNAに、4種類の塩基を組み合わせた暗号文字で書き込まれている。ヒトゲノム計画は人間の全遺伝情報を担う約30億塩基対の配列を解読する国際プロジェクトとして90年代初頭に始まり、03年に終了した。その後、研究の焦点は、遺伝子の働きやたんぱく質の構造と機能、RNAの役割などに移ってきた。DNAなどの分子が細胞内で構成するネットワークの解明や、ゲノム解読で得られる大量データの情報処理も課題となっている。
==============
◇ゲノム計画の歴史◇
1988年 国際ヒトゲノム計画を推進する国際組織「HUGO」設立
90年 国際ヒトゲノム計画開始
96年 参加国が解読結果を直ちに公開することなどで合意
98年 理化学研究所ゲノム科学総合研究センター発足
2001年 ヒトゲノム解読概要発表
02年 タンパク3000計画開始
03年 ヒトゲノム解読完了
07年 タンパク3000計画終了
|
|
|
|
コメント(23)
三菱化学、三菱化学生命科学研究所を解散・10年3月に
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080324AT1D2407G24032008.html
三菱化学は全額出資子会社の三菱化学生命科学研究所(東京・港)を2010年3月に解散する。約170人の研究所員は解雇する。研究員は現在の研究テーマを来年3月まで続けた後、同研究所の支援を受けて再就職先を探す。特許は三菱化学が引き継ぐ。
同研究所は病気の発症メカニズムなど生命現象の基礎研究を手掛けている。三菱ケミカルホールディングスは傘下に三菱化学に加えて田辺三菱製薬も持つが、同研究所の研究内容は事業につながりにくかったという。(22:01)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080324AT1D2407G24032008.html
三菱化学は全額出資子会社の三菱化学生命科学研究所(東京・港)を2010年3月に解散する。約170人の研究所員は解雇する。研究員は現在の研究テーマを来年3月まで続けた後、同研究所の支援を受けて再就職先を探す。特許は三菱化学が引き継ぐ。
同研究所は病気の発症メカニズムなど生命現象の基礎研究を手掛けている。三菱ケミカルホールディングスは傘下に三菱化学に加えて田辺三菱製薬も持つが、同研究所の研究内容は事業につながりにくかったという。(22:01)
脳科学総合研究センター次期センター長に利根川進MIT教授
平成20年3月27日
http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2008/080327_2/
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、利根川進マサチューセッツ工科大学(MIT)教授(理研フェロー※1/ハワード・ヒューズ医学研究所研究員※2)を脳科学総合研究センターの次期センター長に内定しました。任期は2009年4月1日から2013年3月末日までを予定しています。利根川教授はセンター長として、同センターの運営を担いますが、MIT教授として、今まで通りMITで研究を行います。
なお、甘利俊一現センター長は、2008年3月末日で任期を満了し、センター長職から退きます。2008年4月1日から利根川教授が就任するまでの1年間は、田中啓治領域ディレクターが副センター長としてセンター長の職務を代行します。また、利根川教授には引き続き、特別顧問を委嘱する予定です。
1. 脳科学総合研究センターの概要
理化学研究所脳科学総合研究センター(RIKEN Brain Science Institute、以下BSI)は、わが国の脳科学研究の中核的機関として、総合的かつ戦略的に脳科学研究を実施するため、1997年に国内外から優れた研究者・技術者を結集して発足しました。記憶・学習のメカニズムや臨界期の分子機構の解明、アルツハイマー病をはじめとする神経変成疾患の病因解明など、脳神経科学分野に世界的なインパクトを与える成果をあげるとともに、国内外の大学などに多くの優れた人材を送り出してきました。
BSIの初代センター長、伊藤正男前センター長(現BSI特別顧問)は、同センターを世界的に認められた国際的な研究機関とするため、すべて任期制の職員で構成され、厳しい評価制度を設け、外国人研究者を2割とするなど、わが国の科学技術システム改革の先導役を果たしてきました。
甘利俊一現センター長は、伊藤顧問の後を継いで2003年にセンター長に就任し、BSIの役割を明確化するとともに、研究員約300名を含む総勢500名を越えるスタッフを有する世界有数の脳科学の研究拠点へと成長させました。最近では、理研BSI−トヨタ連携センターをBSI内に設置する(2007年12月14日お知らせ)など、産業界との連携も積極的に推進しています。
利根川教授は、MITにおいて、理研-MIT脳科学研究センターのセンター長を務め、BSIとの共同研究の中で記憶・学習に関する研究を10年にわたり実施し、マウスの海馬の特定の神経回路を可逆的に制御する技術の開発など世界的な成果を上げています。この功績などから、理研は2007年に利根川教授に理研フェローを授与しています(2007年7月6日プレス発表)。
BSIは、1997年の設立から10年の間に、「脳を知る」、「脳を守る」、「脳を創る」、「脳を育む」の4領域の研究を展開してきました。2008年度からは、これらの各領域の融合性を高め、今後の脳科学で中心的な課題に取り組むため「心と知性への挑戦」、「回路機能メカニズム」、「疾患メカニズム」、「先端基盤技術研究」の4つのコアに組織を再編成し、MITをはじめとした国内外の研究機関と連携を深めつつ、先導的な研究を実施していく予定です。
2. 利根川進MIT教授略歴
< 略歴 >
1939年 愛知県生まれ
1963年 京都大学理学部卒業
1968年 カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程修了(Ph.D.)
1969年 ソーク研究所(ポスドク)
1971年 バーゼル研究所 主任研究員
1981年 マサチューセッツ工科大学(MIT) 教授
1988年 ハワード・ヒューズ医科学研究所 研究者
1998年 理研-MIT脳科学研究センター センター長
2002年 MITピカワ研究所 所長
2007年 理研フェロー/BSI特別顧問
< 業績 >
1984年 文化勲章
1987年 ノーベル生理学・医学賞 受賞
平成20年3月27日
http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2008/080327_2/
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、利根川進マサチューセッツ工科大学(MIT)教授(理研フェロー※1/ハワード・ヒューズ医学研究所研究員※2)を脳科学総合研究センターの次期センター長に内定しました。任期は2009年4月1日から2013年3月末日までを予定しています。利根川教授はセンター長として、同センターの運営を担いますが、MIT教授として、今まで通りMITで研究を行います。
なお、甘利俊一現センター長は、2008年3月末日で任期を満了し、センター長職から退きます。2008年4月1日から利根川教授が就任するまでの1年間は、田中啓治領域ディレクターが副センター長としてセンター長の職務を代行します。また、利根川教授には引き続き、特別顧問を委嘱する予定です。
1. 脳科学総合研究センターの概要
理化学研究所脳科学総合研究センター(RIKEN Brain Science Institute、以下BSI)は、わが国の脳科学研究の中核的機関として、総合的かつ戦略的に脳科学研究を実施するため、1997年に国内外から優れた研究者・技術者を結集して発足しました。記憶・学習のメカニズムや臨界期の分子機構の解明、アルツハイマー病をはじめとする神経変成疾患の病因解明など、脳神経科学分野に世界的なインパクトを与える成果をあげるとともに、国内外の大学などに多くの優れた人材を送り出してきました。
BSIの初代センター長、伊藤正男前センター長(現BSI特別顧問)は、同センターを世界的に認められた国際的な研究機関とするため、すべて任期制の職員で構成され、厳しい評価制度を設け、外国人研究者を2割とするなど、わが国の科学技術システム改革の先導役を果たしてきました。
甘利俊一現センター長は、伊藤顧問の後を継いで2003年にセンター長に就任し、BSIの役割を明確化するとともに、研究員約300名を含む総勢500名を越えるスタッフを有する世界有数の脳科学の研究拠点へと成長させました。最近では、理研BSI−トヨタ連携センターをBSI内に設置する(2007年12月14日お知らせ)など、産業界との連携も積極的に推進しています。
利根川教授は、MITにおいて、理研-MIT脳科学研究センターのセンター長を務め、BSIとの共同研究の中で記憶・学習に関する研究を10年にわたり実施し、マウスの海馬の特定の神経回路を可逆的に制御する技術の開発など世界的な成果を上げています。この功績などから、理研は2007年に利根川教授に理研フェローを授与しています(2007年7月6日プレス発表)。
BSIは、1997年の設立から10年の間に、「脳を知る」、「脳を守る」、「脳を創る」、「脳を育む」の4領域の研究を展開してきました。2008年度からは、これらの各領域の融合性を高め、今後の脳科学で中心的な課題に取り組むため「心と知性への挑戦」、「回路機能メカニズム」、「疾患メカニズム」、「先端基盤技術研究」の4つのコアに組織を再編成し、MITをはじめとした国内外の研究機関と連携を深めつつ、先導的な研究を実施していく予定です。
2. 利根川進MIT教授略歴
< 略歴 >
1939年 愛知県生まれ
1963年 京都大学理学部卒業
1968年 カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程修了(Ph.D.)
1969年 ソーク研究所(ポスドク)
1971年 バーゼル研究所 主任研究員
1981年 マサチューセッツ工科大学(MIT) 教授
1988年 ハワード・ヒューズ医科学研究所 研究者
1998年 理研-MIT脳科学研究センター センター長
2002年 MITピカワ研究所 所長
2007年 理研フェロー/BSI特別顧問
< 業績 >
1984年 文化勲章
1987年 ノーベル生理学・医学賞 受賞
<補足説明>
※1 理研フェロー
理研フェローは、世界的に傑出した実績と見識を有し、理研ブランドの創出にかけがえのない科学者に対して、研究所として敬意を表して授与する称号。利根川進MIT教授が第1号。
※2 ハワード・ヒューズ医学研究所研究員
ハワード・ヒューズ医学研究所(Howard Hughes Medical Institute, HHMI)は、非営利の医学研究機構であり、米国で最も大規模な慈善団体の1つとして、米国における生物医学分野の研究および科学教育の推進において主導的役割を果たしている。HHMIの第1の使命は、生物医学分野の基礎研究の推進である。その目的のために、60を超える全米の大学、医療センター、その他研究機関と連携している。また、約300名にのぼるHHMI研究員と2,000名を超える研究スタッフがこれらの連携研究機関に設けられたHHMIの研究室で働いている。中でもバージニア州ロウドン郡にあるHHMIのジャネリアファーム研究所は、多様な分野の研究者を結集するため特別に設計された研究施設で、ここでの研究プログラムでは、トップクラスの研究者達が、リスクは高いが、期待できる成果も大きい研究を行っている。HHMIの研究者は、その独創性と生産性の高さが有名で、全研究員のうち122名が全米科学アカデミーの会員。現在までに12名の研究者がノーベル賞を受賞している。
※1 理研フェロー
理研フェローは、世界的に傑出した実績と見識を有し、理研ブランドの創出にかけがえのない科学者に対して、研究所として敬意を表して授与する称号。利根川進MIT教授が第1号。
※2 ハワード・ヒューズ医学研究所研究員
ハワード・ヒューズ医学研究所(Howard Hughes Medical Institute, HHMI)は、非営利の医学研究機構であり、米国で最も大規模な慈善団体の1つとして、米国における生物医学分野の研究および科学教育の推進において主導的役割を果たしている。HHMIの第1の使命は、生物医学分野の基礎研究の推進である。その目的のために、60を超える全米の大学、医療センター、その他研究機関と連携している。また、約300名にのぼるHHMI研究員と2,000名を超える研究スタッフがこれらの連携研究機関に設けられたHHMIの研究室で働いている。中でもバージニア州ロウドン郡にあるHHMIのジャネリアファーム研究所は、多様な分野の研究者を結集するため特別に設計された研究施設で、ここでの研究プログラムでは、トップクラスの研究者達が、リスクは高いが、期待できる成果も大きい研究を行っている。HHMIの研究者は、その独創性と生産性の高さが有名で、全研究員のうち122名が全米科学アカデミーの会員。現在までに12名の研究者がノーベル賞を受賞している。
【 2008年3月25日 三菱化学生命科学研究所が解散へ 】
http://scienceportal.jp/news/daily/0803/0803251.html
生命科学研究で40年近い歴史を持つ三菱化学生命科学研究所が、再来年3月末で解散することが決まった。
同研究所は、1971年ライフサイエンスの基礎研究を目的に三菱化成生命科学研究所として発足した。初代所長は日本学術会議会長などを務めた江上不二男氏だった。94年に三菱化成が三菱油化と合併し、三菱化学となったのを機に三菱化学生命科学研究所と名称が変わったが、発足以来、企業が100%出資するライフサイエンスの基礎研究所として多くの成果を挙げている。特に、当初から生命現象の基礎研究だけでなく、環境や生命倫理も研究対象に含めるなどユニークな研究方針は、社会的にも大きな影響を与えた。
解散の理由について三菱化学は、「生命研を取り巻く環境は、設立当初とは大きく変わり、現在では、大学で生命科学の研究も盛んに行われるようになり、国、民間の同分野にかかわる研究所も多数設立されている」ことと、三菱スグループの医薬事業の発展で、創薬にかかわる研究も質・規模ともに大きく変化したことを挙げている。
研究所の在り方については、これまでも研究所内で何度も見直しが行われた経緯があり、2004年からは、「疾病治療の進歩に役立つ基礎研究」を新たな使命に掲げ、研究所内外から公募により採用された研究リーダーと研究テーマを軸とする新たな研究体制をスタートさせていた。
http://scienceportal.jp/news/daily/0803/0803251.html
生命科学研究で40年近い歴史を持つ三菱化学生命科学研究所が、再来年3月末で解散することが決まった。
同研究所は、1971年ライフサイエンスの基礎研究を目的に三菱化成生命科学研究所として発足した。初代所長は日本学術会議会長などを務めた江上不二男氏だった。94年に三菱化成が三菱油化と合併し、三菱化学となったのを機に三菱化学生命科学研究所と名称が変わったが、発足以来、企業が100%出資するライフサイエンスの基礎研究所として多くの成果を挙げている。特に、当初から生命現象の基礎研究だけでなく、環境や生命倫理も研究対象に含めるなどユニークな研究方針は、社会的にも大きな影響を与えた。
解散の理由について三菱化学は、「生命研を取り巻く環境は、設立当初とは大きく変わり、現在では、大学で生命科学の研究も盛んに行われるようになり、国、民間の同分野にかかわる研究所も多数設立されている」ことと、三菱スグループの医薬事業の発展で、創薬にかかわる研究も質・規模ともに大きく変化したことを挙げている。
研究所の在り方については、これまでも研究所内で何度も見直しが行われた経緯があり、2004年からは、「疾病治療の進歩に役立つ基礎研究」を新たな使命に掲げ、研究所内外から公募により採用された研究リーダーと研究テーマを軸とする新たな研究体制をスタートさせていた。
理研・脳科学総合研究センター長 利根川MIT教授内定
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200803280031a.nwc
理化学研究所は27日、日本の脳研究の中核である脳科学総合研究センター(BSI)の次期センター長に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進マサチューセッツ工科大学(MIT)教授(68)=写真=を内定した、と発表した。
1963年に京都大学を卒業後、45年間にわたり海外で研究生活を続けた利根川氏は、「科学技術基盤を強化できなければ日本にとって致命的なことになる」と将来に警鐘を鳴らした。その上で「脳センターは、実力主義で若い人を起用している。今後は人材を欧米の研究所から引き抜く努力を地道にやっていきたい」と抱負を語った。
また、さらに国際的研究所へ脱皮するには、「言語も英語に統一せざるを得ない」と、事務方まで英語を公用語とし、世界的な研究者を引き抜くには、子女のためのインターナショナルスクールを手配するなど環境整備を進める方針だ。
脳科学ではシステムとしてとらえることが世界的な潮流となっており「それが最終的に人間のシステムを理解することにつながる」と述べ、基礎研究に加えて社会や産業に役立つ応用研究を重視する方向性を示した。
利根川氏は、MITでの研究も続けるため、2009年4月に正式に就任する。
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200803280031a.nwc
理化学研究所は27日、日本の脳研究の中核である脳科学総合研究センター(BSI)の次期センター長に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進マサチューセッツ工科大学(MIT)教授(68)=写真=を内定した、と発表した。
1963年に京都大学を卒業後、45年間にわたり海外で研究生活を続けた利根川氏は、「科学技術基盤を強化できなければ日本にとって致命的なことになる」と将来に警鐘を鳴らした。その上で「脳センターは、実力主義で若い人を起用している。今後は人材を欧米の研究所から引き抜く努力を地道にやっていきたい」と抱負を語った。
また、さらに国際的研究所へ脱皮するには、「言語も英語に統一せざるを得ない」と、事務方まで英語を公用語とし、世界的な研究者を引き抜くには、子女のためのインターナショナルスクールを手配するなど環境整備を進める方針だ。
脳科学ではシステムとしてとらえることが世界的な潮流となっており「それが最終的に人間のシステムを理解することにつながる」と述べ、基礎研究に加えて社会や産業に役立つ応用研究を重視する方向性を示した。
利根川氏は、MITでの研究も続けるため、2009年4月に正式に就任する。
■「安全科学研究部門」を設立
−社会の安全と持続性の科学的な評価に向けて−
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2008/pr20080401_2/pr20080401_2.html
ポイント
安全に関わる研究課題へ融合的な取り組みを行う、「安全科学研究部門」を設立
市民・地域・産業・行政などの合理的な意思決定を助け、現実的で政策提言につながる研究を実施
社会へ導入されつつある新技術について影響評価を同時に行ない、便益を享受できるよう科学的に検討
概要
独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)は、4月1日付けで産総研つくばセンターに、安全や社会の持続可能性についての研究を実施する「安全科学研究部門」【研究部門長 中西 準子】を設立しました。
近年特に産業活動などにおける災害や安全問題や化学物質によるリスクの問題に加えて、地球環境や資源枯渇の問題に対する危機感が急速に増大しています。しかも、これらの問題は互いにトレードオフの関係にあることが多々あります。
このような困難な問題に取り組み、安全で持続可能な社会を構築するためには、従来のように爆発・安全、化学物質リスク、エネルギー効率も含めたライフサイクルアセスメントなどの分野での個別の評価研究を実施するだけでは不十分であり、これまでの研究分野の境界を越えた取り組みや研究体制作りが急務であると考えられます。
新しく設立される本研究部門では、これまで産総研内部の個別の研究組織で実施し得られた研究成果を融合させ統一的に考えることにより、持続可能性の高い生産や生活を選択するための指針や社会の要請に応じた最適の政策提示を科学的に行い、安全で、かつ持続可能性の高い社会の構築に大きく貢献することを目指します。
−社会の安全と持続性の科学的な評価に向けて−
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2008/pr20080401_2/pr20080401_2.html
ポイント
安全に関わる研究課題へ融合的な取り組みを行う、「安全科学研究部門」を設立
市民・地域・産業・行政などの合理的な意思決定を助け、現実的で政策提言につながる研究を実施
社会へ導入されつつある新技術について影響評価を同時に行ない、便益を享受できるよう科学的に検討
概要
独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)は、4月1日付けで産総研つくばセンターに、安全や社会の持続可能性についての研究を実施する「安全科学研究部門」【研究部門長 中西 準子】を設立しました。
近年特に産業活動などにおける災害や安全問題や化学物質によるリスクの問題に加えて、地球環境や資源枯渇の問題に対する危機感が急速に増大しています。しかも、これらの問題は互いにトレードオフの関係にあることが多々あります。
このような困難な問題に取り組み、安全で持続可能な社会を構築するためには、従来のように爆発・安全、化学物質リスク、エネルギー効率も含めたライフサイクルアセスメントなどの分野での個別の評価研究を実施するだけでは不十分であり、これまでの研究分野の境界を越えた取り組みや研究体制作りが急務であると考えられます。
新しく設立される本研究部門では、これまで産総研内部の個別の研究組織で実施し得られた研究成果を融合させ統一的に考えることにより、持続可能性の高い生産や生活を選択するための指針や社会の要請に応じた最適の政策提示を科学的に行い、安全で、かつ持続可能性の高い社会の構築に大きく貢献することを目指します。
医療研究の拠点新設 県が亜熱帯研を改編
ゲノム解析機活用
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200804031300_01.html
県は二日までに、医学や生物工学を活用した医療・健康ビジネスの集積を図るため、企画部が所管する亜熱帯総合研究所(那覇市)を組織改編し、産学官が連携する研究拠点として「県科学技術振興センター」(仮称)を二〇〇八年度中に新設する方針を固めた。〇七年度に導入したゲノム(全遺伝子情報)解析機器「次世代シーケンサー」を活用し、沖縄の生物資源などを生かした基礎研究に着手。並行して、県内医学界と連携した「りゅうきゅう臨床研究ネットワーク」を構築する。基礎・臨床の両研究の拠点を整備することで、製薬企業や創薬ベンチャーの誘致を目指す。
新センターは、亜熱帯総研の事業を医療を含めた科学技術全般に拡充し、産学官のコーディネート機関として機能を高度化。共同研究による創薬や知的財産の運用など、幅広い業務を一元的に担う。
事務局は当面、亜熱帯総研が入居している県南部合同庁舎(那覇市旭町)に置き、将来的には同総研が所有する沖縄科学技術研究・交流センター(うるま市)に移転する方針だ。
県は企業や大学などによる研究の意見や方向性を取りまとめる人材を育成するため、企画部科学技術振興課の職員を一日、東京大学に研修生として初めて派遣した。〇九年度以降も継続する。
基礎研究では、従来十六年かかっていたヒトゲノムの解析を三十日で処理する能力を持つ次世代シーケンサーを活用。県内の亜熱帯生物資源などの遺伝子を解析し、創薬に向けた有効性成分を探る。沖縄科学技術大学院大学とも連携し、生物科学分野の共同研究を視野に入れる。
シーケンサーの運用に伴い、県工業技術センターと県農業研究センターから各二人を担当者として配置する。臨床研究は琉球大学医学部附属病院や県医師会とネットワークを構築し、製薬企業や医療メーカーとの連携で治験(医薬品の承認を得るための臨床試験)に対応する。
琉大と連携し、被験者に試験目的などを説明する治験協力者(CRC)を育成して新センターに配置。説明責任を果たしながら、医薬品の承認を得やすい環境を整備する。(吉田央)
ゲノム解析機活用
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200804031300_01.html
県は二日までに、医学や生物工学を活用した医療・健康ビジネスの集積を図るため、企画部が所管する亜熱帯総合研究所(那覇市)を組織改編し、産学官が連携する研究拠点として「県科学技術振興センター」(仮称)を二〇〇八年度中に新設する方針を固めた。〇七年度に導入したゲノム(全遺伝子情報)解析機器「次世代シーケンサー」を活用し、沖縄の生物資源などを生かした基礎研究に着手。並行して、県内医学界と連携した「りゅうきゅう臨床研究ネットワーク」を構築する。基礎・臨床の両研究の拠点を整備することで、製薬企業や創薬ベンチャーの誘致を目指す。
新センターは、亜熱帯総研の事業を医療を含めた科学技術全般に拡充し、産学官のコーディネート機関として機能を高度化。共同研究による創薬や知的財産の運用など、幅広い業務を一元的に担う。
事務局は当面、亜熱帯総研が入居している県南部合同庁舎(那覇市旭町)に置き、将来的には同総研が所有する沖縄科学技術研究・交流センター(うるま市)に移転する方針だ。
県は企業や大学などによる研究の意見や方向性を取りまとめる人材を育成するため、企画部科学技術振興課の職員を一日、東京大学に研修生として初めて派遣した。〇九年度以降も継続する。
基礎研究では、従来十六年かかっていたヒトゲノムの解析を三十日で処理する能力を持つ次世代シーケンサーを活用。県内の亜熱帯生物資源などの遺伝子を解析し、創薬に向けた有効性成分を探る。沖縄科学技術大学院大学とも連携し、生物科学分野の共同研究を視野に入れる。
シーケンサーの運用に伴い、県工業技術センターと県農業研究センターから各二人を担当者として配置する。臨床研究は琉球大学医学部附属病院や県医師会とネットワークを構築し、製薬企業や医療メーカーとの連携で治験(医薬品の承認を得るための臨床試験)に対応する。
琉大と連携し、被験者に試験目的などを説明する治験協力者(CRC)を育成して新センターに配置。説明責任を果たしながら、医薬品の承認を得やすい環境を整備する。(吉田央)
DNA鑑定:精度向上へ「クリーンルーム」を増設−−県警 /富山
http://mainichi.jp/area/toyama/news/20080405ddlk16040673000c.html
◇計3室でスピードアップも
県警は、DNA鑑定の精度向上や迅速化のため、本部内に「クリーンルーム」を増設した。体に付着したちりやほこりを空気で払い落とす「エアーシャワー」も備える。総工費は約3200万円。県警科学捜査研究所は「より正確な捜査のために積極的に活用していく」としている。
従来の施設は1室のみで、広さも24平方メートルと全国でも最小規模だった。成分抽出や分析を同じ室内で行っており、試料に他の鑑定の試料が混入する可能性もゼロではなかった。
今回は、これに加え2室を増設した。3室の広さは合計で75平方メートルと、従来の約3倍。個々の作業を独立した場所で行えるため、鑑定精度が上がる上に、処理速度も約2倍に向上する。
DNA鑑定は、犯罪現場に残された血液や汗などの成分を鑑定することで容疑者を特定する捜査機関の有力な「武器」。県警が実施したDNA鑑定は、02年の48件から07年には約20倍の928件にまで急増した。鑑定のスピードアップと高精度の実現が急務だった。【茶谷亮】
http://mainichi.jp/area/toyama/news/20080405ddlk16040673000c.html
◇計3室でスピードアップも
県警は、DNA鑑定の精度向上や迅速化のため、本部内に「クリーンルーム」を増設した。体に付着したちりやほこりを空気で払い落とす「エアーシャワー」も備える。総工費は約3200万円。県警科学捜査研究所は「より正確な捜査のために積極的に活用していく」としている。
従来の施設は1室のみで、広さも24平方メートルと全国でも最小規模だった。成分抽出や分析を同じ室内で行っており、試料に他の鑑定の試料が混入する可能性もゼロではなかった。
今回は、これに加え2室を増設した。3室の広さは合計で75平方メートルと、従来の約3倍。個々の作業を独立した場所で行えるため、鑑定精度が上がる上に、処理速度も約2倍に向上する。
DNA鑑定は、犯罪現場に残された血液や汗などの成分を鑑定することで容疑者を特定する捜査機関の有力な「武器」。県警が実施したDNA鑑定は、02年の48件から07年には約20倍の928件にまで急増した。鑑定のスピードアップと高精度の実現が急務だった。【茶谷亮】
理化学研究所、韓国ハンヤン大学とポストナノテク分野で協定締結(理化学研究所)
[2008/04/10]
http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=3237
理化学研究所は9日、韓国のハンヤン大学とポストナノテク分野で協力協定を締結すると発表した。ハンヤン大学に建設中の「Fusion Tech Center(FTC)」に、研究拠点を設置。同大と協力しながら「ポスト」ナノテクノロジーの提案と確立を目指した研究開発を進める。研究者人工の減少や人材流出などアジア諸国共通の課題を解決するため、アジア諸国との研究ネットワークである「アジアリサーチネットワーク」を構築したい考え。理研が韓国に拠点を置くのは今回が初めて。
両者は共同研究や人材交流のほか、講演・共同セミナーなどを通じて情報交換などを実施。理研はハンヤン大学をはじめとするアジアリサーチネットワーク参加予定の研究機関と連携し、21世紀の革新的科学技術の創製を目指す。また、日本と韓国の連携を核に中国やインド、シンガポールなどのアジア諸国へ連携の和を広げるという。
[2008/04/10]
http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=3237
理化学研究所は9日、韓国のハンヤン大学とポストナノテク分野で協力協定を締結すると発表した。ハンヤン大学に建設中の「Fusion Tech Center(FTC)」に、研究拠点を設置。同大と協力しながら「ポスト」ナノテクノロジーの提案と確立を目指した研究開発を進める。研究者人工の減少や人材流出などアジア諸国共通の課題を解決するため、アジア諸国との研究ネットワークである「アジアリサーチネットワーク」を構築したい考え。理研が韓国に拠点を置くのは今回が初めて。
両者は共同研究や人材交流のほか、講演・共同セミナーなどを通じて情報交換などを実施。理研はハンヤン大学をはじめとするアジアリサーチネットワーク参加予定の研究機関と連携し、21世紀の革新的科学技術の創製を目指す。また、日本と韓国の連携を核に中国やインド、シンガポールなどのアジア諸国へ連携の和を広げるという。
理化学研究所、米国国立衛生研究所などと国際薬理遺伝学研究連合を創設
理研CGMと米国NIHが国際薬理遺伝学研究連合を創設
− オーダーメイド医療の実現に向け、個人ごとの最適な投薬法の確立へ −
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=187024&lindID=4
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)ゲノム医科学研究センター(CGM:中村祐輔センター長)と米国国立衛生研究所(NIH:エリアス・ザホーニ所長)薬理遺伝学研究ネットワーク(PGRN:スコット・ワイス議長)、NIHの3研究機関(国立一般医学研究所〔NIGMS〕、国立がん研究所〔NCI〕、国立心臓・肺・血液研究所〔NHLBI〕)は、2008年4月14日(日本時間4月15日)、米国癌学会 (AACR:サンディエゴ)の場において、薬剤の有効性や副作用と個人の遺伝的要因との関係を明らかにするため国際薬理遺伝学研究連合(Global Alliance for Pharmacogenomics:GAP)の創設に関し合意、中村センター長、ワイス議長および上記3研究機関の所長が合意書に署名しました。
理研CGMは、2008年4月1日、理研遺伝子多型研究センター(SRC)を改称し、SRCで取り組んできたヒトゲノムの多様性を示すSNP(Single Nucleotide Polymorphism:一塩基多型)を解析することで、遺伝子レベルで個人の体質の違いを把握し、個人の特性に合った診断・治療・予防や薬剤の投与が可能となるオーダーメイド医療の実現を目指した研究を、引き続き行っています。
米国NIHにおける研究グループの連合体であるPGRNは、NIH所属の3研究機関が協力し、体内における薬剤の作用や薬物動態と個人ごとの遺伝子の相違との関係について研究を行っています。
今回創設するGAPでは、CGM、PGRN双方の研究能力・資源を有効に活用し、共同研究やフォーラムの開催等を通じた連携・協力を行うこととしており、共同研究の第1弾として、遺伝的要因の乳がん治療剤への影響の研究等5件の共同研究を開始します。
GAPの創設により、薬剤の有効性や副作用に係る遺伝的要因の究明が加速し、その知見が臨床薬物治療に活用されることで、個々の患者の体質に適合した最適な薬剤の投与による国際的なヘルスケアの実現につながることが期待されます。
理研CGMと米国NIHが国際薬理遺伝学研究連合を創設
− オーダーメイド医療の実現に向け、個人ごとの最適な投薬法の確立へ −
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=187024&lindID=4
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)ゲノム医科学研究センター(CGM:中村祐輔センター長)と米国国立衛生研究所(NIH:エリアス・ザホーニ所長)薬理遺伝学研究ネットワーク(PGRN:スコット・ワイス議長)、NIHの3研究機関(国立一般医学研究所〔NIGMS〕、国立がん研究所〔NCI〕、国立心臓・肺・血液研究所〔NHLBI〕)は、2008年4月14日(日本時間4月15日)、米国癌学会 (AACR:サンディエゴ)の場において、薬剤の有効性や副作用と個人の遺伝的要因との関係を明らかにするため国際薬理遺伝学研究連合(Global Alliance for Pharmacogenomics:GAP)の創設に関し合意、中村センター長、ワイス議長および上記3研究機関の所長が合意書に署名しました。
理研CGMは、2008年4月1日、理研遺伝子多型研究センター(SRC)を改称し、SRCで取り組んできたヒトゲノムの多様性を示すSNP(Single Nucleotide Polymorphism:一塩基多型)を解析することで、遺伝子レベルで個人の体質の違いを把握し、個人の特性に合った診断・治療・予防や薬剤の投与が可能となるオーダーメイド医療の実現を目指した研究を、引き続き行っています。
米国NIHにおける研究グループの連合体であるPGRNは、NIH所属の3研究機関が協力し、体内における薬剤の作用や薬物動態と個人ごとの遺伝子の相違との関係について研究を行っています。
今回創設するGAPでは、CGM、PGRN双方の研究能力・資源を有効に活用し、共同研究やフォーラムの開催等を通じた連携・協力を行うこととしており、共同研究の第1弾として、遺伝的要因の乳がん治療剤への影響の研究等5件の共同研究を開始します。
GAPの創設により、薬剤の有効性や副作用に係る遺伝的要因の究明が加速し、その知見が臨床薬物治療に活用されることで、個々の患者の体質に適合した最適な薬剤の投与による国際的なヘルスケアの実現につながることが期待されます。
「オーダーメード医療」、日米研究機関がタッグ
2008年04月16日01時01分
http://www.asahi.com/science/update/0416/TKY200804150354.html
患者一人ひとりの遺伝子レベルの体質に応じて治療するオーダーメード医療の研究を、日米の研究機関が共同で始める。15日、理化学研究所(埼玉県和光市)ゲノム医科学研究センターと、米国立保健研究所(NIH)傘下の研究機関などが合意書に署名した。まず、乳がんの治療や脳梗塞(こうそく)の予防など5件の研究にとりかかる。
日米でトップの研究機関が、こうした共同研究を行うのは初めて。互いの能力や資源を効率的に利用した方が研究に無駄がなく、治療の標準化も図れると判断した。NIHの研究機関は、国立がん研究所など3機関で、これらが関与する薬理遺伝学研究ネットワークも参加する。
ゲノム医科学研究センターとともに国際薬理遺伝学研究連合を創設し、薬の効果や副作用にかかわる体質の研究を急ぎ、臨床への応用を早める。
5件の研究は第1弾。乳がんでは、標準的に使われながら心臓に毒性のある抗がん剤や、近年日本でも普及してきたホルモン療法の研究をする。脳梗塞では、研究組織が持つ5千人の患者データをもとに、脳梗塞や血管が詰まる病気の予防薬の効率的な使い方を探る。
米国は、オーダーメード医療に積極的で、一部の薬については米食品医薬品局が使用前の遺伝子検査を推奨している。研究には米国の有力大学や有名病院も加わる。
ゲノム医科学研究センターは、バイオバンクの30万症例のデータをもとに遺伝子レベルで体質を解析。病気を発症しやすい特徴も研究する。血液から45分で遺伝子のタイプを見分ける装置も企業と共同で開発している。
中村祐輔センター長(東大医科学研究所教授と併任)は「効果的な医療を米国のトップ研究機関と共同で実現させ、日本の患者さんに還元したい」と話す。
2008年04月16日01時01分
http://www.asahi.com/science/update/0416/TKY200804150354.html
患者一人ひとりの遺伝子レベルの体質に応じて治療するオーダーメード医療の研究を、日米の研究機関が共同で始める。15日、理化学研究所(埼玉県和光市)ゲノム医科学研究センターと、米国立保健研究所(NIH)傘下の研究機関などが合意書に署名した。まず、乳がんの治療や脳梗塞(こうそく)の予防など5件の研究にとりかかる。
日米でトップの研究機関が、こうした共同研究を行うのは初めて。互いの能力や資源を効率的に利用した方が研究に無駄がなく、治療の標準化も図れると判断した。NIHの研究機関は、国立がん研究所など3機関で、これらが関与する薬理遺伝学研究ネットワークも参加する。
ゲノム医科学研究センターとともに国際薬理遺伝学研究連合を創設し、薬の効果や副作用にかかわる体質の研究を急ぎ、臨床への応用を早める。
5件の研究は第1弾。乳がんでは、標準的に使われながら心臓に毒性のある抗がん剤や、近年日本でも普及してきたホルモン療法の研究をする。脳梗塞では、研究組織が持つ5千人の患者データをもとに、脳梗塞や血管が詰まる病気の予防薬の効率的な使い方を探る。
米国は、オーダーメード医療に積極的で、一部の薬については米食品医薬品局が使用前の遺伝子検査を推奨している。研究には米国の有力大学や有名病院も加わる。
ゲノム医科学研究センターは、バイオバンクの30万症例のデータをもとに遺伝子レベルで体質を解析。病気を発症しやすい特徴も研究する。血液から45分で遺伝子のタイプを見分ける装置も企業と共同で開発している。
中村祐輔センター長(東大医科学研究所教授と併任)は「効果的な医療を米国のトップ研究機関と共同で実現させ、日本の患者さんに還元したい」と話す。
理研の放射光施設「スプリング8」 06年181社 創薬開発向上を期待
http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200805020014a.nwc
■企業の活用増加
■専用ビーム設置の動き
理化学研究所播磨研究所(兵庫県佐用町)にある世界最大の放射光施設「SPring−8(スプリング8)」を、企業が研究開発に利用する動きが加速している。従来は、学術利用が大半だったが、利用企業数は、2006年には181社と01年に比べ約2倍に膨らみ、集計中の07年も前年を上回る勢いだ。
研究を本格化させるため、自前のビームラインを設置する動きも相次いでいる。放射光を物質に照射すると、原子レベルで物質特性を分析したり、構造解析できるため、タンパク質の構造解析や医薬品開発、新素材開発に利用する企業が増えている。
加えて2010年にはスプリング8の光より10億倍明るい光源を持つ「XFEL」(X線自由電子レーザー)も同所で稼働する見込み。より高解像度の高速分析が可能になり、国際競争力向上に一役買いそうだ。
スプリング8は当初は学術用途がほとんどだったが、研究成果の公表を前提に施設利用料の無料化で利用を促進した結果、06年の産業界利用は181社、約2300人と全体の約2割にのぼる。
主な研究成果では、ダイハツ工業が自動車の排ガスから有害物質を取り除く触媒解析に成功、新開発した触媒は従来使用されていた貴金属使用量を7割削減できた。P&Gは傷んだ頭髪の回復効果を分析し、ヘアケア製品の新開発につなげている。
より、具体的な成果を求め、放射光を取り出す施設、専用ビームラインを建設する動きも相次いでいる。トヨタグループの研究機関、豊田中央研究所は、今年度中に約10億円をかけてラインを設置し、燃料電池にからむ構造解析などに利用する計画。今年2月には住友化学など17社が新素材の共同開発に向けラインを建設している。
10年に併設する予定のXFEL計画では、日米欧間で熾烈な国際競争が繰り広げられている。
XFELは、スプリング8の10億倍の明るさを持ち、1000兆分の1秒単位で観察できるため、物質反応課程の分析に役立つ。
最も期待されるのが創薬分野だ。非常に短い波長のX線レーザーを作り出すことができるXFELを使えば、構造解析が不可能とされた膜タンパク質の解明も可能になる。細胞内外の情報伝達を担う膜タンパク質構造が解明できれば、画期的な創薬開発につながる。 創薬市場は数千億円規模とも試算され、XFELで先行することが、「国際競争力向上のカギを握る」(理研)とされている。
米国でもスタンフォード大で09年〜10年稼働を、欧州もEU(欧州連合)を中心に12カ国共同プロジェクトとして13年完成を目指す。日本は、スプリング8と同時照射することで、高光度を実現する計画。「世界最高性能の光」をフル活用して製品開発競争で差別化を図る。
◇
【用語解説】スプリング8
全長1400メートルの円形リングの中で、電子を光速近くまで加速させ、磁石などで進行方向を変えたときに出る放射光を利用し物質構造の解析などを行う施設。明るさは太陽光の約100億倍で原子レベルの物質を分析できる。昨年10月に稼働丸10年を迎えた。
http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200805020014a.nwc
■企業の活用増加
■専用ビーム設置の動き
理化学研究所播磨研究所(兵庫県佐用町)にある世界最大の放射光施設「SPring−8(スプリング8)」を、企業が研究開発に利用する動きが加速している。従来は、学術利用が大半だったが、利用企業数は、2006年には181社と01年に比べ約2倍に膨らみ、集計中の07年も前年を上回る勢いだ。
研究を本格化させるため、自前のビームラインを設置する動きも相次いでいる。放射光を物質に照射すると、原子レベルで物質特性を分析したり、構造解析できるため、タンパク質の構造解析や医薬品開発、新素材開発に利用する企業が増えている。
加えて2010年にはスプリング8の光より10億倍明るい光源を持つ「XFEL」(X線自由電子レーザー)も同所で稼働する見込み。より高解像度の高速分析が可能になり、国際競争力向上に一役買いそうだ。
スプリング8は当初は学術用途がほとんどだったが、研究成果の公表を前提に施設利用料の無料化で利用を促進した結果、06年の産業界利用は181社、約2300人と全体の約2割にのぼる。
主な研究成果では、ダイハツ工業が自動車の排ガスから有害物質を取り除く触媒解析に成功、新開発した触媒は従来使用されていた貴金属使用量を7割削減できた。P&Gは傷んだ頭髪の回復効果を分析し、ヘアケア製品の新開発につなげている。
より、具体的な成果を求め、放射光を取り出す施設、専用ビームラインを建設する動きも相次いでいる。トヨタグループの研究機関、豊田中央研究所は、今年度中に約10億円をかけてラインを設置し、燃料電池にからむ構造解析などに利用する計画。今年2月には住友化学など17社が新素材の共同開発に向けラインを建設している。
10年に併設する予定のXFEL計画では、日米欧間で熾烈な国際競争が繰り広げられている。
XFELは、スプリング8の10億倍の明るさを持ち、1000兆分の1秒単位で観察できるため、物質反応課程の分析に役立つ。
最も期待されるのが創薬分野だ。非常に短い波長のX線レーザーを作り出すことができるXFELを使えば、構造解析が不可能とされた膜タンパク質の解明も可能になる。細胞内外の情報伝達を担う膜タンパク質構造が解明できれば、画期的な創薬開発につながる。 創薬市場は数千億円規模とも試算され、XFELで先行することが、「国際競争力向上のカギを握る」(理研)とされている。
米国でもスタンフォード大で09年〜10年稼働を、欧州もEU(欧州連合)を中心に12カ国共同プロジェクトとして13年完成を目指す。日本は、スプリング8と同時照射することで、高光度を実現する計画。「世界最高性能の光」をフル活用して製品開発競争で差別化を図る。
◇
【用語解説】スプリング8
全長1400メートルの円形リングの中で、電子を光速近くまで加速させ、磁石などで進行方向を変えたときに出る放射光を利用し物質構造の解析などを行う施設。明るさは太陽光の約100億倍で原子レベルの物質を分析できる。昨年10月に稼働丸10年を迎えた。
田中さん、がんの研究へ本腰
島津製で会見、米と共同で
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008050700130&genre=F1&area=K00
ノーベル化学賞受賞者で島津製作所フェローの田中耕一さんが7日、京都市中京区の同社本社で記者会見し、米国の国際的ながん研究機関との共同研究を今秋から本格化、小型で高性能のタンパク質質量分析装置を開発する方針を明らかにした。従来より測定可能なタンパク質が増え、がん診断の向上につながる可能性があるという。
田中さんが所長を務める同社の「田中耕一記念質量分析研究所」の設立5周年を機に記者会見した。共同研究の相手は米フレッド・ハッチンソンがん研究センター(FHCRC)。田中さんが社内で開発中の新型質量分析装置を提供し、製品化に向けた評価をしてもらうと同時に、がんの早期診断につながるタンパク質を絞り込む。
国内の有力研究機関とも連携を予定。新型装置は3、4年後の製品化を目指しており、田中さんは「販売中の装置に比べて感度が一けた以上高く、質量が大きいタンパク質も分析できる。サイズで3分の2ぐらい、価格も半分程度に抑えたい」と意欲を示した。
田中さんはまた、5年間の研究活動で論文発表が約10件、特許出願が約20件に上ったことも明らかにし、「社内外での連携をさらに深め、役に立つ技術を世に送り出したい」と抱負を語った。
島津製で会見、米と共同で
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008050700130&genre=F1&area=K00
ノーベル化学賞受賞者で島津製作所フェローの田中耕一さんが7日、京都市中京区の同社本社で記者会見し、米国の国際的ながん研究機関との共同研究を今秋から本格化、小型で高性能のタンパク質質量分析装置を開発する方針を明らかにした。従来より測定可能なタンパク質が増え、がん診断の向上につながる可能性があるという。
田中さんが所長を務める同社の「田中耕一記念質量分析研究所」の設立5周年を機に記者会見した。共同研究の相手は米フレッド・ハッチンソンがん研究センター(FHCRC)。田中さんが社内で開発中の新型質量分析装置を提供し、製品化に向けた評価をしてもらうと同時に、がんの早期診断につながるタンパク質を絞り込む。
国内の有力研究機関とも連携を予定。新型装置は3、4年後の製品化を目指しており、田中さんは「販売中の装置に比べて感度が一けた以上高く、質量が大きいタンパク質も分析できる。サイズで3分の2ぐらい、価格も半分程度に抑えたい」と意欲を示した。
田中さんはまた、5年間の研究活動で論文発表が約10件、特許出願が約20件に上ったことも明らかにし、「社内外での連携をさらに深め、役に立つ技術を世に送り出したい」と抱負を語った。
脳科学 進む異分野連携
生理学研究所 多彩な専門家を育成
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20080625-OYT8T00207.htm
自然科学研究機構・生理学研究所(愛知県岡崎市)は、心理学や教育学など様々な分野と連携して、いじめ、ひきこもりなどの問題にも取り組む脳科学の専門家を育てる「多次元共同脳科学推進センター」を設立した。
4月の開設記念シンポジウムには、全国から脳科学の研究者や学生300人以上が集まった。世界的な脳科学者で、同センターの客員教授を務める国際電気通信基礎技術研究所脳情報研究所の川人光男所長は、サルの歩行時の脳情報をもとに、人型ロボットを動かすことに成功した自分たちの研究を紹介。「研究の発展には、幅広い分野の研究者の力が欠かせない。日本の脳科学は、フレッシュなアイデアを求めている」と若手への期待を語った。
霊長類を用いた脳科学研究の現状なども報告されたが、シンポジウムで強調されたのは、異分野との連携の重要性。例えば、心を解明する心理学も、脳科学が科学的な根拠を提供することで、教育や医療に安心して応用することができる。
日本の脳科学研究は世界のトップレベルを走る。生理研は、理化学研究所と並ぶ国内の拠点で、総合研究大学院大学として教育も担う。人の脳の働きを可視化する「脳磁計」「機能的磁気共鳴画像」の装置を使い、色覚や目の動かし方に関連する高次脳機能の解明などで国際的な成果を上げてきた。
しかし、これまで国内には、大学の脳神経科学科など脳科学の研究者を専門に育成する機関がなかった。さらに、複雑な脳を理解するには、生命科学だけでなく、哲学、心理学、工学など多分野の連携が欠かせなくなっている。
こうした現状を受け、設立されたのが脳科学推進センターだ。生理研の7人の併任教授に加え、全国から15人の客員教授を迎え、異分野の融合研究と若手の育成に取り組む。様々な病態モデルのニホンザルを供給する体制を整え、霊長類を活用した研究の拠点化も目指す。
センター長の池中一裕教授は、「研究中心の理研と役割分担して、人材育成に力を入れたい。異分野の知恵を集め、最後のフロンティアである脳の解明する拠点を作りたい」と話している。(長谷川聖治)
生理学研究所 多彩な専門家を育成
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20080625-OYT8T00207.htm
自然科学研究機構・生理学研究所(愛知県岡崎市)は、心理学や教育学など様々な分野と連携して、いじめ、ひきこもりなどの問題にも取り組む脳科学の専門家を育てる「多次元共同脳科学推進センター」を設立した。
4月の開設記念シンポジウムには、全国から脳科学の研究者や学生300人以上が集まった。世界的な脳科学者で、同センターの客員教授を務める国際電気通信基礎技術研究所脳情報研究所の川人光男所長は、サルの歩行時の脳情報をもとに、人型ロボットを動かすことに成功した自分たちの研究を紹介。「研究の発展には、幅広い分野の研究者の力が欠かせない。日本の脳科学は、フレッシュなアイデアを求めている」と若手への期待を語った。
霊長類を用いた脳科学研究の現状なども報告されたが、シンポジウムで強調されたのは、異分野との連携の重要性。例えば、心を解明する心理学も、脳科学が科学的な根拠を提供することで、教育や医療に安心して応用することができる。
日本の脳科学研究は世界のトップレベルを走る。生理研は、理化学研究所と並ぶ国内の拠点で、総合研究大学院大学として教育も担う。人の脳の働きを可視化する「脳磁計」「機能的磁気共鳴画像」の装置を使い、色覚や目の動かし方に関連する高次脳機能の解明などで国際的な成果を上げてきた。
しかし、これまで国内には、大学の脳神経科学科など脳科学の研究者を専門に育成する機関がなかった。さらに、複雑な脳を理解するには、生命科学だけでなく、哲学、心理学、工学など多分野の連携が欠かせなくなっている。
こうした現状を受け、設立されたのが脳科学推進センターだ。生理研の7人の併任教授に加え、全国から15人の客員教授を迎え、異分野の融合研究と若手の育成に取り組む。様々な病態モデルのニホンザルを供給する体制を整え、霊長類を活用した研究の拠点化も目指す。
センター長の池中一裕教授は、「研究中心の理研と役割分担して、人材育成に力を入れたい。異分野の知恵を集め、最後のフロンティアである脳の解明する拠点を作りたい」と話している。(長谷川聖治)
理研が、韓国に初の研究拠点(研究分室)を開設
- アジア諸国との研究ネットワーク構築を目指す -
平成20年7月1日
http://www.riken.jp/r-world/info/info/2008/080701/
独立行政法人理化学研究所(以下理研、野依良治理事長)の基幹研究所(玉尾皓平所長)は、韓国・漢陽(ハンヤン)大学(金鍾亮(キム・ジョンリャン)総長)のフュージョン・テクノロジー・センター(Fusion Technology Center:FTC)※1の5階に、国際連携研究グループ揺律※2機能アジア連携研究チーム(原正彦チームリーダー)の分室を設置しました。理研が韓国に研究拠点を置くのは、初めてのことです。
揺律機能アジア連携研究チームでは、漢陽大学の李海元(イ・ヘウォン)教授らと協力して、これまでエレクトロニクスデバイスの開発において障害とされてきた分子の「ゆらぎ」や「不安定性」を積極的に活用し、機能材料の開発や新規情報処理を行う「ポストナノテクノロジー」の確立を目指してきました。2008年4月10日には、研究協力を実施するとともに、人材交流や情報交換を行い、世界で活躍するアジア出身の次世代研究者を育成することを目指し、同大学と協力協定を締結しました(2008年4月9日お知らせ)。 今回の拠点開設により、両者の連携をより強化するとともに、それを核に、中国、インド、シンガポールなどのアジア諸国へ連携の和を広げて行く予定です。 2008年7月1日午前11時より、漢陽大学にてFTC開所式が開催され、理研をはじめ多くの関係者が出席しました。
- アジア諸国との研究ネットワーク構築を目指す -
平成20年7月1日
http://www.riken.jp/r-world/info/info/2008/080701/
独立行政法人理化学研究所(以下理研、野依良治理事長)の基幹研究所(玉尾皓平所長)は、韓国・漢陽(ハンヤン)大学(金鍾亮(キム・ジョンリャン)総長)のフュージョン・テクノロジー・センター(Fusion Technology Center:FTC)※1の5階に、国際連携研究グループ揺律※2機能アジア連携研究チーム(原正彦チームリーダー)の分室を設置しました。理研が韓国に研究拠点を置くのは、初めてのことです。
揺律機能アジア連携研究チームでは、漢陽大学の李海元(イ・ヘウォン)教授らと協力して、これまでエレクトロニクスデバイスの開発において障害とされてきた分子の「ゆらぎ」や「不安定性」を積極的に活用し、機能材料の開発や新規情報処理を行う「ポストナノテクノロジー」の確立を目指してきました。2008年4月10日には、研究協力を実施するとともに、人材交流や情報交換を行い、世界で活躍するアジア出身の次世代研究者を育成することを目指し、同大学と協力協定を締結しました(2008年4月9日お知らせ)。 今回の拠点開設により、両者の連携をより強化するとともに、それを核に、中国、インド、シンガポールなどのアジア諸国へ連携の和を広げて行く予定です。 2008年7月1日午前11時より、漢陽大学にてFTC開所式が開催され、理研をはじめ多くの関係者が出席しました。
科学技術振興の拠点に/沖縄センターが新看板
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200808121700_05.html
県所管の財団法人亜熱帯総合研究所から名称を変更し、一日に発足した沖縄科学技術振興センター(諸喜田茂充理事長)は十二日午前、那覇市の同センターで看板掲揚式を開いた。
諸喜田理事長と県企画部の上原良幸部長が新看板を掛けると、見守っていた職員から大きな拍手が起きた。
諸喜田理事長は「地域に根差した県民目線で産学官と連携し、社会貢献や沖縄の科学技術の振興発展に寄与したい」とあいさつ。上原部長は「沖縄21世紀ビジョンでも科学技術を沖縄振興の大きな柱に据えることになる。科学技術振興の中核機関として活躍してほしい」とエールを送った。
同センターは、県が所有するゲノム(全遺伝子情報)解析機器「次世代シーケンサー」を使い、沖縄の生物資源を生かした創薬研究や産業振興を目指す事業を七月に県から受託。大学や研究機関との共同研究で、今秋にも泡盛に使用する黒こうじ菌の解析に着手するほか、将来はがん治療薬の開発も視野に入れる。
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200808121700_05.html
県所管の財団法人亜熱帯総合研究所から名称を変更し、一日に発足した沖縄科学技術振興センター(諸喜田茂充理事長)は十二日午前、那覇市の同センターで看板掲揚式を開いた。
諸喜田理事長と県企画部の上原良幸部長が新看板を掛けると、見守っていた職員から大きな拍手が起きた。
諸喜田理事長は「地域に根差した県民目線で産学官と連携し、社会貢献や沖縄の科学技術の振興発展に寄与したい」とあいさつ。上原部長は「沖縄21世紀ビジョンでも科学技術を沖縄振興の大きな柱に据えることになる。科学技術振興の中核機関として活躍してほしい」とエールを送った。
同センターは、県が所有するゲノム(全遺伝子情報)解析機器「次世代シーケンサー」を使い、沖縄の生物資源を生かした創薬研究や産業振興を目指す事業を七月に県から受託。大学や研究機関との共同研究で、今秋にも泡盛に使用する黒こうじ菌の解析に着手するほか、将来はがん治療薬の開発も視野に入れる。
日本人標準ゲノム配列取得へ、次世代シーケンサー活用
【バイオ】発信:2008/09/09(火) 15:43:52
http://tech.braina.com/2008/0909/bio_20080909_001____.html
産業技術総合研究所と沖縄県、(財)沖縄科学技術振興センター、(株)トロピカルテクノセンターは、沖縄県所有の次世代ゲノムシーケンサーを用い、日本人の標準ゲノム配列の取得や、沖縄特有の微生物・酵素を産業利用するための研究開発等を9月から本格的に開始する。
2003年にヒトゲムノの全塩基配列の解析が完了したが、このゲノムデータは人種・個人が不明確だった。一方、産総研では、単一日本人ゲノム由来のゲノムデータであるBACライブラリーを確立しているものの、オーダーメイド医療をさらに推進するには、個人のゲノム情報を蓄積する必要があり、基準となる日本人の標準的ゲノム配列を解析することが不可欠だ。
今回の計画では、沖縄県が所有する次世代ゲノムシーケンサー3台などを活用することで、ゲノム配列等を効率的に高精度で解析する基盤技術の開発を進め、創薬に結びつくようなヒトゲノム情報、あるいは発酵産業など産業振興に結びつく有用な生物資源のゲノム情報の獲得や機能解析を行っていく。
今後、次世代ゲノムシーケンサーに関する技術体系を確立し、国内のゲノム拠点として国内外の大学や研究機関、企業などとの連携を目指す。
また、産総研や酒類総合研究所などが参加する『黒麹菌ゲノム解析コンソーシアム』と製品評価技術基盤機構(NITE)は共同で、泡盛の製造に用いられる黒麹菌の全ゲノムのドラフト塩基配列の解析に成功。同グループは2005年に醤油や味噌など用いられる黄麹菌のゲノム解析を完了しており、今回、日本を代表する麹菌2種の基準ゲノム情報が整備された。(科学、8月29日号2面)
【バイオ】発信:2008/09/09(火) 15:43:52
http://tech.braina.com/2008/0909/bio_20080909_001____.html
産業技術総合研究所と沖縄県、(財)沖縄科学技術振興センター、(株)トロピカルテクノセンターは、沖縄県所有の次世代ゲノムシーケンサーを用い、日本人の標準ゲノム配列の取得や、沖縄特有の微生物・酵素を産業利用するための研究開発等を9月から本格的に開始する。
2003年にヒトゲムノの全塩基配列の解析が完了したが、このゲノムデータは人種・個人が不明確だった。一方、産総研では、単一日本人ゲノム由来のゲノムデータであるBACライブラリーを確立しているものの、オーダーメイド医療をさらに推進するには、個人のゲノム情報を蓄積する必要があり、基準となる日本人の標準的ゲノム配列を解析することが不可欠だ。
今回の計画では、沖縄県が所有する次世代ゲノムシーケンサー3台などを活用することで、ゲノム配列等を効率的に高精度で解析する基盤技術の開発を進め、創薬に結びつくようなヒトゲノム情報、あるいは発酵産業など産業振興に結びつく有用な生物資源のゲノム情報の獲得や機能解析を行っていく。
今後、次世代ゲノムシーケンサーに関する技術体系を確立し、国内のゲノム拠点として国内外の大学や研究機関、企業などとの連携を目指す。
また、産総研や酒類総合研究所などが参加する『黒麹菌ゲノム解析コンソーシアム』と製品評価技術基盤機構(NITE)は共同で、泡盛の製造に用いられる黒麹菌の全ゲノムのドラフト塩基配列の解析に成功。同グループは2005年に醤油や味噌など用いられる黄麹菌のゲノム解析を完了しており、今回、日本を代表する麹菌2種の基準ゲノム情報が整備された。(科学、8月29日号2面)
ゲノム研究来月開始 医薬、健康の新産業を振興
2008年8月19日
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-135394-storytopic-3.html
【東京】県や産業技術総合研究所などは18日午後、都道府県会館で会見を開き、国内に数台しかないゲノム解析機「次世代シーケンサー」を用いた先端的ゲノム研究を9月から、うるま市で開始すると正式に発表した。
沖縄を国内の研究拠点として、ゲノム解析技術体系を確立し、沖縄に特有の微生物や酵素などを解析する。地域特性を生かした研究開発により、医薬品や健康食品産業など独自の産業振興を目指す。
研究するのは、県、産業技術総合研究所、沖縄科学技術振興センター、トロピカルテクノセンターの4者。うるま市の沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターで行う。
次世代シーケンサーは、国内に4台しかなく、うち3台が経済産業省の支援で2007年度に県内に導入された。3年事業で、本年度の予算は1億7700万円。
微生物からヒトに至る広範囲なゲノム研究を行うことにより、医薬・健康食品産業の新たな産業創出や発酵産業の高度化を加速する。国内の研究促進に寄与することも期待される。今後は沖縄科学技術大学院大学など国内外の大学や研究機関、企業とも連携し、ゲノム知識資源の集積を図る考えだ。
記者会見で県企画部の平良敏明科学技術統括監は「今回の取り組みで、県内の健康・医療産業や発酵産業等のバイオ産業の振興が促進することを期待する。世界的にも高い水準の次世代シーケンサーの研究開発拠点化を目指したい」と意欲を示した。
2008年8月19日
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-135394-storytopic-3.html
【東京】県や産業技術総合研究所などは18日午後、都道府県会館で会見を開き、国内に数台しかないゲノム解析機「次世代シーケンサー」を用いた先端的ゲノム研究を9月から、うるま市で開始すると正式に発表した。
沖縄を国内の研究拠点として、ゲノム解析技術体系を確立し、沖縄に特有の微生物や酵素などを解析する。地域特性を生かした研究開発により、医薬品や健康食品産業など独自の産業振興を目指す。
研究するのは、県、産業技術総合研究所、沖縄科学技術振興センター、トロピカルテクノセンターの4者。うるま市の沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターで行う。
次世代シーケンサーは、国内に4台しかなく、うち3台が経済産業省の支援で2007年度に県内に導入された。3年事業で、本年度の予算は1億7700万円。
微生物からヒトに至る広範囲なゲノム研究を行うことにより、医薬・健康食品産業の新たな産業創出や発酵産業の高度化を加速する。国内の研究促進に寄与することも期待される。今後は沖縄科学技術大学院大学など国内外の大学や研究機関、企業とも連携し、ゲノム知識資源の集積を図る考えだ。
記者会見で県企画部の平良敏明科学技術統括監は「今回の取り組みで、県内の健康・医療産業や発酵産業等のバイオ産業の振興が促進することを期待する。世界的にも高い水準の次世代シーケンサーの研究開発拠点化を目指したい」と意欲を示した。
みずほ銀、理研のシンポジウムを支援
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080916AT2C1201Z14092008.html
みずほ銀行は16日、理化学研究所が開く新技術の開発と実用化についてのシンポジウムを共催する。同行の本店を会場として提供するほか、行員がパネリストとして出席する。学術的なイベントを金融機関が支援するのは珍しい。優秀な研究者を抱える研究機関との関係を深めることで、将来の有望な取引先を確保することが狙いだ。
シンポジウムには先進的な技術を持つベンチャー企業なども参加する。みずほ銀は研究開発にかかる資金調達や販路の確保などで各企業を支援している。(15日 07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080916AT2C1201Z14092008.html
みずほ銀行は16日、理化学研究所が開く新技術の開発と実用化についてのシンポジウムを共催する。同行の本店を会場として提供するほか、行員がパネリストとして出席する。学術的なイベントを金融機関が支援するのは珍しい。優秀な研究者を抱える研究機関との関係を深めることで、将来の有望な取引先を確保することが狙いだ。
シンポジウムには先進的な技術を持つベンチャー企業なども参加する。みずほ銀は研究開発にかかる資金調達や販路の確保などで各企業を支援している。(15日 07:00)
「研究開発法人」の検討開始=来年2月に制度設計−大幅再編も・3府省チーム
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009121400911
内閣府と文部科学省、総務省の副大臣や政務官らで構成する「研究開発を担う法人の機能強化検討チーム」の初会合が14日、内閣府で開かれた。理化学研究所や産業技術総合研究所など現在は独立行政法人の組織を、「国立研究開発法人」(仮称)に移行させることを視野に、所管や予算、研究員人事、評価などの制度の在り方を来年2月ごろにまとめる方針を固めた。
同チームは、昨年議員立法で成立した「研究開発力強化法」を受けて設置され、同法で指定された32(来年度から38)の法人が対象。主査の1人の鈴木寛文部科学副大臣は、これらをそのまま新法人に移行させるのではなく、各省や民間が共同利用できるよう、大幅に再編する考えも示した。
政府は独立行政法人を国に戻すか、民営化する方針を示しているが、鈴木副大臣は、研究開発機関はどちらの道も取れないと説明。独立行政法人は中期目標・計画に対する達成度で評価し、企業的経営手法が求められるが、研究開発は予想外の発展があり得るため、違った評価・運営方法が必要と述べた。
初会合には、理研の野依良治理事長が招かれ、理研がスパコンなど国の基幹技術開発を任される一方で、人員削減も求められるのは整合性がないと指摘。世界最高水準の研究者を集められる待遇も必要と訴えた。(2009/12/14-21:26)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009121400911
内閣府と文部科学省、総務省の副大臣や政務官らで構成する「研究開発を担う法人の機能強化検討チーム」の初会合が14日、内閣府で開かれた。理化学研究所や産業技術総合研究所など現在は独立行政法人の組織を、「国立研究開発法人」(仮称)に移行させることを視野に、所管や予算、研究員人事、評価などの制度の在り方を来年2月ごろにまとめる方針を固めた。
同チームは、昨年議員立法で成立した「研究開発力強化法」を受けて設置され、同法で指定された32(来年度から38)の法人が対象。主査の1人の鈴木寛文部科学副大臣は、これらをそのまま新法人に移行させるのではなく、各省や民間が共同利用できるよう、大幅に再編する考えも示した。
政府は独立行政法人を国に戻すか、民営化する方針を示しているが、鈴木副大臣は、研究開発機関はどちらの道も取れないと説明。独立行政法人は中期目標・計画に対する達成度で評価し、企業的経営手法が求められるが、研究開発は予想外の発展があり得るため、違った評価・運営方法が必要と述べた。
初会合には、理研の野依良治理事長が招かれ、理研がスパコンなど国の基幹技術開発を任される一方で、人員削減も求められるのは整合性がないと指摘。世界最高水準の研究者を集められる待遇も必要と訴えた。(2009/12/14-21:26)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
生命科学研究ハイライト 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
生命科学研究ハイライトのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75489人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6452人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208290人