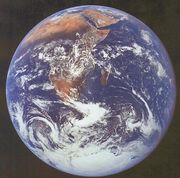|
|
|
|
コメント(20)
巨大隕石衝突は22億年前 豪州西部のクレーター
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012200129
オーストラリア西部にある「ヤラババ・クレーター」に巨大隕石が衝突したのは22億2900万年前と推定したと、同国のカーティン大などの研究チームが発表した。当時の大陸は氷で覆われていたが、衝突で大量の水蒸気が大気に放出され、気候が暖かく変化した可能性があるという。
ヤラババ・クレーターは地上の地形ではよく分からないが、航空機による磁気調査では楕円の形が浮かび上がる。巨大隕石が衝突した際にできたクレーターは直径約70kmとみられるが、年代がはっきりしていなかった。研究チームはクレーター内の鉱物を採取し、含まれる放射性元素のウランが鉛に変化する割合から年代を測定した。
「気候が“暖かく”変化した可能性」とあるので、ヒューロニアン氷河時代の終焉に結び付けたい考察ですかね?
衝突時にそこが氷に覆われていたことを示す証拠が無いのであくまでも“推測”らしいです。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012200129
オーストラリア西部にある「ヤラババ・クレーター」に巨大隕石が衝突したのは22億2900万年前と推定したと、同国のカーティン大などの研究チームが発表した。当時の大陸は氷で覆われていたが、衝突で大量の水蒸気が大気に放出され、気候が暖かく変化した可能性があるという。
ヤラババ・クレーターは地上の地形ではよく分からないが、航空機による磁気調査では楕円の形が浮かび上がる。巨大隕石が衝突した際にできたクレーターは直径約70kmとみられるが、年代がはっきりしていなかった。研究チームはクレーター内の鉱物を採取し、含まれる放射性元素のウランが鉛に変化する割合から年代を測定した。
「気候が“暖かく”変化した可能性」とあるので、ヒューロニアン氷河時代の終焉に結び付けたい考察ですかね?
衝突時にそこが氷に覆われていたことを示す証拠が無いのであくまでも“推測”らしいです。
こんな動画を見つけたので貼り付けぺたぺた♪
全地球史アトラス フルストーリー
https://www.youtube.com/watch?v=rTCXFuQSSNU
第1章から第12章までを1本にまとめた、地球誕生、生命誕生から地球の未来までを一気に見ることができる映像です。
第1章「地球誕生」
第2章「プレートテクトニクス」
第3章「原始生命誕生」
第4章「生命進化の第1ステージ」
第5章「生命進化の第2ステージ」
第6章「生命進化の第3ステージ」
第7章「生命大進化の夜明け前」
第8章「カンブリア紀の生命大進化」
第9章「古生代」
第10章「中生代から人類の誕生まで」
第11章「人類代〜人類誕生と文明の構築」
第12章「地球の未来」
全地球史アトラス フルストーリー
https://www.youtube.com/watch?v=rTCXFuQSSNU
第1章から第12章までを1本にまとめた、地球誕生、生命誕生から地球の未来までを一気に見ることができる映像です。
第1章「地球誕生」
第2章「プレートテクトニクス」
第3章「原始生命誕生」
第4章「生命進化の第1ステージ」
第5章「生命進化の第2ステージ」
第6章「生命進化の第3ステージ」
第7章「生命大進化の夜明け前」
第8章「カンブリア紀の生命大進化」
第9章「古生代」
第10章「中生代から人類の誕生まで」
第11章「人類代〜人類誕生と文明の構築」
第12章「地球の未来」
地球型惑星の形成とその材料物質の進化 始原的隕石と地球の化学組成が不一致
https://sorae.info/astronomy/20210619-terrestrial-planet-formation.html
微惑星から地球型惑星へ(地球型惑星の形成)
太陽が生まれて間もない頃、太陽の材料の残りである塵やガスからなる原始太陽系円盤が存在。
太陽系の惑星は、原始太陽系円盤が冷却するに従い、円盤中の塵がお互いの重力によって集まり、直径数キロメートルほどの微惑星が形成。
動画の前半では、塵から微惑星へ、微惑星から原始惑星へと天体が合体成長する様子を描いています。
動画の中盤では、赤くマークされた原始惑星に着目をするともう一つの原始惑星と衝突合体。
このような原始惑星同士の衝突は「巨大衝突」と呼ばれ、地球の衛星である月は、この巨大衝突によって形成されたとも考えられています。
動画の後半では、原始惑星の軌道の進化を描いています。原始惑星の軌道が他の原始惑星の重力により、しばしば大きく乱される様子が見て取れます。この時、原始惑星の軌道が交差したところで巨大衝突が起こります。
初期太陽系で形成された塵や微惑星のかけらが含まれている始原的隕石を分析することにより、惑星の形成過程や惑星を構成する物質の化学組成を実証的に知ることができます。多くの始原的隕石の分析研究により、地球などの岩石惑星は、原始太陽系円盤の木星より内側で形成された非炭素質型物質を主な材料として形成されたことが示されています。
とくに「エンスタタイト・コンドライト」と呼ばれる非炭素質型始原的隕石は、地球と月を形成した主要な材料物質と考えられてきました。
一方、「ユレイライト隕石」(主にケイ酸塩からなり、「コンドリュール」を含まない非炭素質型石質隕石の一種)の母天体に代表される一部の非炭素質型隕石と、さまざまな割合で炭素質コンドライト隕石母天体が混合した結果、地球型惑星が形成されたというモデルなども提案されてきました。
しかし、これらのモデルでは、地球の主要な成分であるケイ素の同位体組成などが地球の値と一致しないという矛盾点がありました。また、地球の岩石層(マントルと地殻)に含まれるケイ素の存在比が、太陽系全体の存在比より低いことも説明できていませんでした。
この謎を解明するため、岡山大学惑星物質研究所の田中亮吏教授たちのグループは、エンスタタイト・コンドライト隕石に含まれるコンドリュールおよびユレイライト隕石の酸素とケイ素の同位体組成分析を行うことにより、地球型惑星の約 50%を構成するこれらの元素の、原始太陽系円盤での進化過程を明らかにしました。
その結果、地球型惑星の化学組成は、原始太陽系円盤内の起源物質が形成された場における塵およびガス成分を反映しており、同時に始原的隕石の組成が必ずしも惑星の化学組成をそのまま反映しているものではないことが明らかになりました。このことは、地球型惑星の化学組成の再検討が必要であることを示唆しています。
画像
(上図)原始太陽系円盤の内側における微惑星形成モデル(Kruijer et al., 2017, PNAS, 114, 6712-6716 を改変)。太陽系が形成してから約100万年後までには、原始木星よりも内側の領域(地球型惑星が形成された領域)には、非炭素質型物質が卓越していたと考えられています。
(下図)岡山大学の研究グループが提案したモデル。非炭素質型物質が卓越していた領域で、急加熱され溶融したカンラン石に富むコンドリュール、蒸発した塵、初生ガスが反応することによってケイ素に富むコンドリュールが形成され、これらが集積して地球型惑星の起源となった微惑星が形成されました。
結論は画像(下図)の解説を読んだ方が早いかと。
材料
・急加熱で溶融したカンラン石に富むコンドリュール
・蒸発した塵と初生ガス
これ化学反応してケイ素に富むコンドリュールが形成ってことでしょうか。
↓
これらが集積して地球型惑星の起源となった微惑星が形成。
本研究成果は2021年5月20日、アメリカ天文学会の国際科学雑誌「The Planetary Science Journal」オンライン版に掲載されました。
https://sorae.info/astronomy/20210619-terrestrial-planet-formation.html
微惑星から地球型惑星へ(地球型惑星の形成)
太陽が生まれて間もない頃、太陽の材料の残りである塵やガスからなる原始太陽系円盤が存在。
太陽系の惑星は、原始太陽系円盤が冷却するに従い、円盤中の塵がお互いの重力によって集まり、直径数キロメートルほどの微惑星が形成。
動画の前半では、塵から微惑星へ、微惑星から原始惑星へと天体が合体成長する様子を描いています。
動画の中盤では、赤くマークされた原始惑星に着目をするともう一つの原始惑星と衝突合体。
このような原始惑星同士の衝突は「巨大衝突」と呼ばれ、地球の衛星である月は、この巨大衝突によって形成されたとも考えられています。
動画の後半では、原始惑星の軌道の進化を描いています。原始惑星の軌道が他の原始惑星の重力により、しばしば大きく乱される様子が見て取れます。この時、原始惑星の軌道が交差したところで巨大衝突が起こります。
初期太陽系で形成された塵や微惑星のかけらが含まれている始原的隕石を分析することにより、惑星の形成過程や惑星を構成する物質の化学組成を実証的に知ることができます。多くの始原的隕石の分析研究により、地球などの岩石惑星は、原始太陽系円盤の木星より内側で形成された非炭素質型物質を主な材料として形成されたことが示されています。
とくに「エンスタタイト・コンドライト」と呼ばれる非炭素質型始原的隕石は、地球と月を形成した主要な材料物質と考えられてきました。
一方、「ユレイライト隕石」(主にケイ酸塩からなり、「コンドリュール」を含まない非炭素質型石質隕石の一種)の母天体に代表される一部の非炭素質型隕石と、さまざまな割合で炭素質コンドライト隕石母天体が混合した結果、地球型惑星が形成されたというモデルなども提案されてきました。
しかし、これらのモデルでは、地球の主要な成分であるケイ素の同位体組成などが地球の値と一致しないという矛盾点がありました。また、地球の岩石層(マントルと地殻)に含まれるケイ素の存在比が、太陽系全体の存在比より低いことも説明できていませんでした。
この謎を解明するため、岡山大学惑星物質研究所の田中亮吏教授たちのグループは、エンスタタイト・コンドライト隕石に含まれるコンドリュールおよびユレイライト隕石の酸素とケイ素の同位体組成分析を行うことにより、地球型惑星の約 50%を構成するこれらの元素の、原始太陽系円盤での進化過程を明らかにしました。
その結果、地球型惑星の化学組成は、原始太陽系円盤内の起源物質が形成された場における塵およびガス成分を反映しており、同時に始原的隕石の組成が必ずしも惑星の化学組成をそのまま反映しているものではないことが明らかになりました。このことは、地球型惑星の化学組成の再検討が必要であることを示唆しています。
画像
(上図)原始太陽系円盤の内側における微惑星形成モデル(Kruijer et al., 2017, PNAS, 114, 6712-6716 を改変)。太陽系が形成してから約100万年後までには、原始木星よりも内側の領域(地球型惑星が形成された領域)には、非炭素質型物質が卓越していたと考えられています。
(下図)岡山大学の研究グループが提案したモデル。非炭素質型物質が卓越していた領域で、急加熱され溶融したカンラン石に富むコンドリュール、蒸発した塵、初生ガスが反応することによってケイ素に富むコンドリュールが形成され、これらが集積して地球型惑星の起源となった微惑星が形成されました。
結論は画像(下図)の解説を読んだ方が早いかと。
材料
・急加熱で溶融したカンラン石に富むコンドリュール
・蒸発した塵と初生ガス
これ化学反応してケイ素に富むコンドリュールが形成ってことでしょうか。
↓
これらが集積して地球型惑星の起源となった微惑星が形成。
本研究成果は2021年5月20日、アメリカ天文学会の国際科学雑誌「The Planetary Science Journal」オンライン版に掲載されました。
彩恵りり@お仕事募集中の科学ニュース解説者
6550万年前の白亜紀末の大量絶滅イベントは、北半球での春の後半から夏の前半にかけて発生した事が、化石の詳細な分析によって判明したよ!
https://twitter.com/Science_Release/status/1470317633006608386
今から6550万年前、地球に直径10kmの小惑星が衝突し、大量の塵が全地球を覆った結果、数年間の気温低下と光合成の停止により多くの生物が絶滅した。
ただ、この大量絶滅イベントはよく知られているけが、あの日に何が起きたのか細かい面については、これまであまりはっきりと分かってこなかった。
今回のマンチェスター大学などの研究チームは、この難しい課題に挑戦した。
6550万年前の小惑星衝突が起きた時代は、地質学的には中生代と新生代の間である事から、「K-Pg境界」と呼ばれる。K-Pg境界は世界中にあるけれど、アメリカ合衆国ノースダコタ州にある「タニス」という場所は特別だ。
タニスを含めたこの辺の広い地域には、K-Pg境界を含む「ヘルクリーク累層」という地層がある。ここは世界的にも非常に保存状態の良いK-Pg境界で、中生代に生息した、多数の恐竜を含む多種多様な生物化石が見つかる。
タニスでは、小惑星の衝突後約13分で細かい塵が降り積もり始め、その後粗い粒を含む激しいサージが到達して、1時間から2時間程度で堆積したと考えられる。今回の研究では、化石として見つかった魚類及び昆虫の季節的な影響の痕跡を調べて、小惑星が衝突したのはいつ頃の季節かを調べた。
分析に使用された魚の化石は全てチョウザメ目で、チョウザメ、ヘラチョウザメ、アミアに属する。この化石は詳細を分析する事ができて、例えば鰓に残った堆積物の証拠から、最初に塵が積もった頃は生きていて、その後のサージ到達で死亡した事が分かるほどの細やかさだ。
化石となった骨を見てみると、木の年輪のような線が観られる。これは成長の速い春夏と、成長が遅い秋冬の差でできるものだ。そしてこれを更に詳しく分析すると、炭素や酸素の同位体比率に違いがある事が分かる。同位体の比率は、周りの環境条件をよく反映するものとして知られている。
原子は陽子・中性子・電子でできていて、同じ元素は同じ陽子の数を持っている。ただし、同じ元素の中でも中性子の数が違うものがあって、これを同位体と言う。同位体によって原子の重さが微妙に違うので、生体内での化学反応や水の蒸発や凝固と言った物理的現象で移動のしやすさに差が出てくる。
すると、暖かい春夏と、寒い秋冬では、周りの水や餌などに同位体比率の差が出て、これを取り込んで成長するチョウザメの骨にも差が出てくる。だから逆に詳しく同位体比率を分析する事で、チョウザメの骨の成長線がどの季節に対応し、成長の末端部、つまり死亡時の季節を知る事が可能となる。
また、生まれて1年を経過していないチョウザメは、身体の大きさと季節に大体の関係性がある事がわかっている。骨の同位体比率から観た成長の末端部、及び1歳未満の個体の大きさを測ってみたところ、どちらも春の後半から夏の前半にかけて死亡した事を示すデータが得られた。
更に、これとは別に昆虫についても調べた。タニスから見つかった化石には大量の葉が含まれていて、中には枝についたままのも見つかっている。そしてこの葉のおよそ40%は、昆虫の幼虫によって食べられたであろう、大量の虫食い跡が見つかった。
幼虫が活発に活動し葉を食害するのは、主に春から夏にかけてで、これはチョウザメの分析と一致する。更に、カゲロウの成虫の化石も見つかった事で、更に絞る事が可能。はかないイメージの通り、カゲロウは成虫になってから数時間から数日しか活動する事ができない昆虫だ。
カゲロウの成虫は、この短い寿命の間に交尾と産卵をしないといけないから、しばしば大量発生して、それは春の終わりから夏にかけての数週間に限られる。そしてカゲロウの脆い身体が化石に残る事は、それを保存するだけの短時間の堆積イベントが起きた事を示している。
これらの結果から、6550万年前の大量絶滅イベントは、春の後半から夏の前半にかけての時期に起きた、という推定ができる。この点はとても重要だ。何故ならこの分析されたタニスは、白亜紀の時にも北半球にあった場所だからだ。そして、地球は全てが同じ季節じゃない。
実はこの大量絶滅イベントは、北半球と南半球では少し差がある事が分かっている。大量絶滅イベントが起きた時に北半球が春夏なら、南半球は秋冬という事になり、この元々の環境条件の差が、北半球と南半球で大量絶滅イベントの影響を多少なりとも変えてしまった可能性があるわけです。
字数制限のため感想は省略。
6550万年前の白亜紀末の大量絶滅イベントは、北半球での春の後半から夏の前半にかけて発生した事が、化石の詳細な分析によって判明したよ!
https://twitter.com/Science_Release/status/1470317633006608386
今から6550万年前、地球に直径10kmの小惑星が衝突し、大量の塵が全地球を覆った結果、数年間の気温低下と光合成の停止により多くの生物が絶滅した。
ただ、この大量絶滅イベントはよく知られているけが、あの日に何が起きたのか細かい面については、これまであまりはっきりと分かってこなかった。
今回のマンチェスター大学などの研究チームは、この難しい課題に挑戦した。
6550万年前の小惑星衝突が起きた時代は、地質学的には中生代と新生代の間である事から、「K-Pg境界」と呼ばれる。K-Pg境界は世界中にあるけれど、アメリカ合衆国ノースダコタ州にある「タニス」という場所は特別だ。
タニスを含めたこの辺の広い地域には、K-Pg境界を含む「ヘルクリーク累層」という地層がある。ここは世界的にも非常に保存状態の良いK-Pg境界で、中生代に生息した、多数の恐竜を含む多種多様な生物化石が見つかる。
タニスでは、小惑星の衝突後約13分で細かい塵が降り積もり始め、その後粗い粒を含む激しいサージが到達して、1時間から2時間程度で堆積したと考えられる。今回の研究では、化石として見つかった魚類及び昆虫の季節的な影響の痕跡を調べて、小惑星が衝突したのはいつ頃の季節かを調べた。
分析に使用された魚の化石は全てチョウザメ目で、チョウザメ、ヘラチョウザメ、アミアに属する。この化石は詳細を分析する事ができて、例えば鰓に残った堆積物の証拠から、最初に塵が積もった頃は生きていて、その後のサージ到達で死亡した事が分かるほどの細やかさだ。
化石となった骨を見てみると、木の年輪のような線が観られる。これは成長の速い春夏と、成長が遅い秋冬の差でできるものだ。そしてこれを更に詳しく分析すると、炭素や酸素の同位体比率に違いがある事が分かる。同位体の比率は、周りの環境条件をよく反映するものとして知られている。
原子は陽子・中性子・電子でできていて、同じ元素は同じ陽子の数を持っている。ただし、同じ元素の中でも中性子の数が違うものがあって、これを同位体と言う。同位体によって原子の重さが微妙に違うので、生体内での化学反応や水の蒸発や凝固と言った物理的現象で移動のしやすさに差が出てくる。
すると、暖かい春夏と、寒い秋冬では、周りの水や餌などに同位体比率の差が出て、これを取り込んで成長するチョウザメの骨にも差が出てくる。だから逆に詳しく同位体比率を分析する事で、チョウザメの骨の成長線がどの季節に対応し、成長の末端部、つまり死亡時の季節を知る事が可能となる。
また、生まれて1年を経過していないチョウザメは、身体の大きさと季節に大体の関係性がある事がわかっている。骨の同位体比率から観た成長の末端部、及び1歳未満の個体の大きさを測ってみたところ、どちらも春の後半から夏の前半にかけて死亡した事を示すデータが得られた。
更に、これとは別に昆虫についても調べた。タニスから見つかった化石には大量の葉が含まれていて、中には枝についたままのも見つかっている。そしてこの葉のおよそ40%は、昆虫の幼虫によって食べられたであろう、大量の虫食い跡が見つかった。
幼虫が活発に活動し葉を食害するのは、主に春から夏にかけてで、これはチョウザメの分析と一致する。更に、カゲロウの成虫の化石も見つかった事で、更に絞る事が可能。はかないイメージの通り、カゲロウは成虫になってから数時間から数日しか活動する事ができない昆虫だ。
カゲロウの成虫は、この短い寿命の間に交尾と産卵をしないといけないから、しばしば大量発生して、それは春の終わりから夏にかけての数週間に限られる。そしてカゲロウの脆い身体が化石に残る事は、それを保存するだけの短時間の堆積イベントが起きた事を示している。
これらの結果から、6550万年前の大量絶滅イベントは、春の後半から夏の前半にかけての時期に起きた、という推定ができる。この点はとても重要だ。何故ならこの分析されたタニスは、白亜紀の時にも北半球にあった場所だからだ。そして、地球は全てが同じ季節じゃない。
実はこの大量絶滅イベントは、北半球と南半球では少し差がある事が分かっている。大量絶滅イベントが起きた時に北半球が春夏なら、南半球は秋冬という事になり、この元々の環境条件の差が、北半球と南半球で大量絶滅イベントの影響を多少なりとも変えてしまった可能性があるわけです。
字数制限のため感想は省略。
一応、こちらにも貼り付けぺたぺた!
恐竜の滅亡に第2の小惑星衝突が関与していたか、痕跡を発見
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/081900386/
8月17日付けの科学誌「Science Advances」に発表された研究によると、海底の地震探査を行っていた科学者たちが直径8.5kmのクレーターらしき構造物を発見したという。近くの海底火山にちなんで「ナディール」と名付けられたこのクレーターは、直径400m以上の小惑星の衝突によって形成されたと考えられ、その形成時期はメキシコ、ユカタン半島の「チクシュルーブ・クレーター」と同時期である可能性がある。
研究チームはこの構造物の形と大きさを分析し、形成過程のモデルを作った。その結果、このクレーターは、直径400mの小惑星が大気圏を突き抜けて秒速20kmの猛スピードで海面に衝突してできたものであることがわかった。「海に飛び込んだ小惑星は、そこに何もないかのように水中を突進していったことでしょう」とブレイ氏は言う。
この衝突によりTNT火薬5000メガトン分のエネルギーが放出され、すぐ下の海水と海底の地層は一瞬にして蒸発しただろうと推測している。続いて衝撃波が海面に広がり、岩石は衝撃変性作用により液状に融解する。数分もしないうちに海底が再び盛り上がって中央に山を作り、崩れ落ちる。最終的に、真ん中にお椀のようなくぼみのある丘ができる。今回アフリカの西海岸で発見された構造物と同じ形だ。
ナディールの衝突は、すでに荒廃していた生態系に「追い打ちをかけた」可能性があるとブレイ氏は言う。今回のクレーターの他にも、ウクライナのボルティッシュ・クレーターという衝突クレーターは6540万年前のもので、チクシュルーブ・クレーターよりもわずかに新しいと、研究チームは指摘している。
小天体のワンツーパンチの可能性というお話です。
恐竜の滅亡に第2の小惑星衝突が関与していたか、痕跡を発見
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/081900386/
8月17日付けの科学誌「Science Advances」に発表された研究によると、海底の地震探査を行っていた科学者たちが直径8.5kmのクレーターらしき構造物を発見したという。近くの海底火山にちなんで「ナディール」と名付けられたこのクレーターは、直径400m以上の小惑星の衝突によって形成されたと考えられ、その形成時期はメキシコ、ユカタン半島の「チクシュルーブ・クレーター」と同時期である可能性がある。
研究チームはこの構造物の形と大きさを分析し、形成過程のモデルを作った。その結果、このクレーターは、直径400mの小惑星が大気圏を突き抜けて秒速20kmの猛スピードで海面に衝突してできたものであることがわかった。「海に飛び込んだ小惑星は、そこに何もないかのように水中を突進していったことでしょう」とブレイ氏は言う。
この衝突によりTNT火薬5000メガトン分のエネルギーが放出され、すぐ下の海水と海底の地層は一瞬にして蒸発しただろうと推測している。続いて衝撃波が海面に広がり、岩石は衝撃変性作用により液状に融解する。数分もしないうちに海底が再び盛り上がって中央に山を作り、崩れ落ちる。最終的に、真ん中にお椀のようなくぼみのある丘ができる。今回アフリカの西海岸で発見された構造物と同じ形だ。
ナディールの衝突は、すでに荒廃していた生態系に「追い打ちをかけた」可能性があるとブレイ氏は言う。今回のクレーターの他にも、ウクライナのボルティッシュ・クレーターという衝突クレーターは6540万年前のもので、チクシュルーブ・クレーターよりもわずかに新しいと、研究チームは指摘している。
小天体のワンツーパンチの可能性というお話です。
こちらにも貼り付けぺたぺた!
お題の通りの大陸の形成の一つの可能性。
彗星の衝突が地球の大陸を作る原動力になった可能性が判明
https://sorae.info/astronomy/20220901-comet-impact.html
彗星が地球表面に衝突すると、地殻を砕いて多数のひび割れを形成すると共に、その下にあるマントルにまで衝撃が伝播。
衝突した地点の下側では地球深部からの物質が地殻へと供給。
ひび割れた地殻には水が入り込み、岩石の融点を下げます。
この2つの作用によって花崗岩の塊が形成され、後に大陸地殻の “核” になったと推定。
理屈はこんな感じでしょうか?
個人的には好きなお話なので追記があると嬉しいですね。
お題の通りの大陸の形成の一つの可能性。
彗星の衝突が地球の大陸を作る原動力になった可能性が判明
https://sorae.info/astronomy/20220901-comet-impact.html
彗星が地球表面に衝突すると、地殻を砕いて多数のひび割れを形成すると共に、その下にあるマントルにまで衝撃が伝播。
衝突した地点の下側では地球深部からの物質が地殻へと供給。
ひび割れた地殻には水が入り込み、岩石の融点を下げます。
この2つの作用によって花崗岩の塊が形成され、後に大陸地殻の “核” になったと推定。
理屈はこんな感じでしょうか?
個人的には好きなお話なので追記があると嬉しいですね。
4億6600万年前、地球には環があったかもしれない
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13708_ring
古生代のオルドビス紀(約4億8540万年前〜4億4380万年前)には、地球への隕石衝突が急増した時期があったらしいことが知られている。その証拠の一つは地上に残されている衝突クレーターの年代で、オルドビス紀中期に衝突したことを示すクレーターが多く見つかっている。もう一つの証拠は、当時の石灰岩の地層に「L型コンドライト」と呼ばれる隕石の微小な破片が多く含まれているという事実だ。この地層の分析から、隕石衝突が増えたのは約4億6600万年前と推定されていて、この事象は「オルドビス衝突急増期」とも呼ばれる。
この時代に隕石衝突が急増した原因として、小惑星帯の中でL型コンドライトの母天体が分裂を起こし、その破片が太陽系の内側に降りそそいだために小天体の衝突が増えた、という説がこれまで考えられてきた。
小惑星が地球に衝突する場合、衝突地点は地球全体にランダムに分布するはずだ。実際、月や火星のクレーターの分布には偏りはみられない。
豪・モナシュ大学の研究チームは、この仮説を検証するために、オルドビス紀中期の21個の衝突クレーターが衝突当時に地球上のどこにあったのかを、プレートの移動をさかのぼって再現した。
オルドビス紀中期より古い岩石からなる安定陸塊に着目し、地理情報システム(GIS)のデータを使って、後の時代に堆積物や雪氷に覆われたり、侵食されたり、地殻変動を受けたりしていない領域の面積を計算した。さらに、プレート移動のモデルを使い、これらの地域がオルドビス紀中期にどこにあったかという「古緯度」を再現した。
その結果、これらの安定陸塊のうち、当時赤道付近にあったものは面積比で約30%しかなく、残り7割の安定陸塊は中・高緯度にあったことがわかった。にもかかわらず、21個のクレーターの古緯度は全て赤道から緯度で約30度以内の範囲に集中していた。
この結果から、これらのクレーターを作った隕石は小惑星帯から直接地球に降りそそいだのではなく、大型の小惑星が地球に接近して「ロッシュ限界」より内側に入り、潮汐力で破壊されてまず地球の周囲に「環」を形づくって、そこから落下したのだと考えている。
手間をかけて割り出した分布図は現在確認されているものだけのはずなので今後新たに発見されるクレーターも含めて精度を高めたいところですね。
とはいえ、オルドビス紀レベルのクレーターは風化も激しいでしょうから小さいものの発見は厳しそうかもしれません。
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13708_ring
古生代のオルドビス紀(約4億8540万年前〜4億4380万年前)には、地球への隕石衝突が急増した時期があったらしいことが知られている。その証拠の一つは地上に残されている衝突クレーターの年代で、オルドビス紀中期に衝突したことを示すクレーターが多く見つかっている。もう一つの証拠は、当時の石灰岩の地層に「L型コンドライト」と呼ばれる隕石の微小な破片が多く含まれているという事実だ。この地層の分析から、隕石衝突が増えたのは約4億6600万年前と推定されていて、この事象は「オルドビス衝突急増期」とも呼ばれる。
この時代に隕石衝突が急増した原因として、小惑星帯の中でL型コンドライトの母天体が分裂を起こし、その破片が太陽系の内側に降りそそいだために小天体の衝突が増えた、という説がこれまで考えられてきた。
小惑星が地球に衝突する場合、衝突地点は地球全体にランダムに分布するはずだ。実際、月や火星のクレーターの分布には偏りはみられない。
豪・モナシュ大学の研究チームは、この仮説を検証するために、オルドビス紀中期の21個の衝突クレーターが衝突当時に地球上のどこにあったのかを、プレートの移動をさかのぼって再現した。
オルドビス紀中期より古い岩石からなる安定陸塊に着目し、地理情報システム(GIS)のデータを使って、後の時代に堆積物や雪氷に覆われたり、侵食されたり、地殻変動を受けたりしていない領域の面積を計算した。さらに、プレート移動のモデルを使い、これらの地域がオルドビス紀中期にどこにあったかという「古緯度」を再現した。
その結果、これらの安定陸塊のうち、当時赤道付近にあったものは面積比で約30%しかなく、残り7割の安定陸塊は中・高緯度にあったことがわかった。にもかかわらず、21個のクレーターの古緯度は全て赤道から緯度で約30度以内の範囲に集中していた。
この結果から、これらのクレーターを作った隕石は小惑星帯から直接地球に降りそそいだのではなく、大型の小惑星が地球に接近して「ロッシュ限界」より内側に入り、潮汐力で破壊されてまず地球の周囲に「環」を形づくって、そこから落下したのだと考えている。
手間をかけて割り出した分布図は現在確認されているものだけのはずなので今後新たに発見されるクレーターも含めて精度を高めたいところですね。
とはいえ、オルドビス紀レベルのクレーターは風化も激しいでしょうから小さいものの発見は厳しそうかもしれません。
特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」
https://daizetsumetsu.jp/
生命の歴史の中で「進化」と「絶滅」は隣り合わせにある現象です。通常、100万年ごとに10%程度の種が絶滅すると考えられていますが、通常の絶滅とは異なって、短期間に75%以上もの分類群が絶滅したとされる現象(=大量絶滅)が過去に何度も起こっています。そのうち最も大きな5回の絶滅現象がビッグファイブです。ビッグファイブを境としてそれ以前と以降の生命の世界が大きく変わったため、それが次の新しい世界へと繋がる大きな原動力になったという考え方があります。
・オルドビス紀末 約4億4400万年前
・デボン紀後期 約3億7200万年前
・ペルム紀末 約2億5200万年前
・三畳紀末 約2億100万年前
・白亜紀末 約6600万年前
会期:2025年11月01日(土)〜2026年02月23日(月・祝)
会場:国立科学博物館
入場料や前売券の情報は確認することが出来ませんでした。
これは見に行くと思いますので個人的に要チェックですね。
https://daizetsumetsu.jp/
生命の歴史の中で「進化」と「絶滅」は隣り合わせにある現象です。通常、100万年ごとに10%程度の種が絶滅すると考えられていますが、通常の絶滅とは異なって、短期間に75%以上もの分類群が絶滅したとされる現象(=大量絶滅)が過去に何度も起こっています。そのうち最も大きな5回の絶滅現象がビッグファイブです。ビッグファイブを境としてそれ以前と以降の生命の世界が大きく変わったため、それが次の新しい世界へと繋がる大きな原動力になったという考え方があります。
・オルドビス紀末 約4億4400万年前
・デボン紀後期 約3億7200万年前
・ペルム紀末 約2億5200万年前
・三畳紀末 約2億100万年前
・白亜紀末 約6600万年前
会期:2025年11月01日(土)〜2026年02月23日(月・祝)
会場:国立科学博物館
入場料や前売券の情報は確認することが出来ませんでした。
これは見に行くと思いますので個人的に要チェックですね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
地球史 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のアンケート