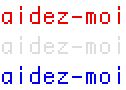定冠詞と不定冠詞の使い分けがなぜ大切なのか?
これはわかってきました。それだけでごろっといってる内容が違う事がありますから。
そこで、なぜ、複数形 と 単数形の使い分けが大切なのかわかってないです。
私は、単数形:1個か/複数形:2個から無限大 を なぜ情報として1文の中にいれるかわかっていません。この不必要と思える情報にどんな価値が潜んでいるのでしょうか?
音がきれい、マ!そういうものさ 2つで勉強していますが、心のそこからそれは素晴らしい事だと思ってないから、何年たたっても板につかないと思うのです(英語暦も入れて)
複数形 と 単数形は なぜそんなに大切なのか?
目から鱗!の考えを持ってる方はいませんか?
素晴らしい事だとわかったら、自然に使い分けに精を出すと思うのですが。。。よろしく。
これはわかってきました。それだけでごろっといってる内容が違う事がありますから。
そこで、なぜ、複数形 と 単数形の使い分けが大切なのかわかってないです。
私は、単数形:1個か/複数形:2個から無限大 を なぜ情報として1文の中にいれるかわかっていません。この不必要と思える情報にどんな価値が潜んでいるのでしょうか?
音がきれい、マ!そういうものさ 2つで勉強していますが、心のそこからそれは素晴らしい事だと思ってないから、何年たたっても板につかないと思うのです(英語暦も入れて)
複数形 と 単数形は なぜそんなに大切なのか?
目から鱗!の考えを持ってる方はいませんか?
素晴らしい事だとわかったら、自然に使い分けに精を出すと思うのですが。。。よろしく。
|
|
|
|
コメント(43)
たくさんの書き込みを有難う。
私、15年間英語も含めて、複数形 と 単数形をきちんと使おうとしてきたんですが、なんだかよく間違うんです。フランス語を勉強しだして、これはいかんなと思いました。英語と同じ間違いが!
それで なぜ板につかないかと考えると、複数形 と 単数形を愛してないんですよ。フランス語は英語より愛してるので、勉強は乗る気なんですが、複数形 と 単数形は、愛してないから、身体が拒否している。頭は、そうしようともがいてるのに。
ですから、このトピックは、複数形 と 単数形を愛するにはどうすればいいのでしょうか?に切り替えてもいいでしょう。
皆さんの意見の中で、複数形 と 単数形を愛していらっしゃる方がいますね。その方(たち)にお聞きしたい?
なぜ?
複数形 と 単数形で困ってる日本人って多いと思います。ロマン語の語学の先生何人にも聞いても、<冠詞は、日本人には難関らしい。ほかの文法は、ほかの民族より覚えが早くて、頭がいいのだけど、冠詞が駄目なのはなぜ?>と聞き返されます。
今までは<日本語にないから>といっていたのですが、このトピックを立てさせてもらって、わかりました。愛してないんですわ。
ということで、愛している方! 私たちに、なぜか、を教えてください。
もう一つの面白い局面は、歴史ですね。
土曜日の朝から、私の頭にはガロア人がうほうほう!と狩をしている映像が流れていました。
私の仮説:
狩り社会のとき、0と1がとても大切だったんではないか? 2からは、たくさんと言うことになってどうでもいい、又は困ったことではなかったか?
というのは、家族で狩りをする場合、獲物が0と1は死活問題。ところがたくさんになるとかえって困る。獲物をどうプリザーブするかの料理法の発達は、寒い地方のほうが発達してますね。フランスはそれほど寒くもないので、フィンランドとかに比べると少ない。でも、スモークでプリザーブする方法は古くからあみ出してたと思います。スモークするのが、おとうちゃんたちが3匹の巨大な動物を狩ってきちゃったら、おかあちゃんたちは、大変だったのでは? <あんたプリザーブする人手が足んないじゃない、こんなに取ってきてどうするのよ?>
0と1がことさら発達しているフランス語の背景にはまずこれがあるのではないか?0を示す言葉もフランス語にことさら多いですよね。
フランス地方では、早くから農牧農耕社会に変わってるんです。羊の頭数を数えてたのかというと、私は疑問に思います。群れだの、たくさんだの、少しだのの言葉が多いのは、正確に数を数えない文化だったんじゃないか?
ここは数文化が、早くに発達しなかった。エジプト、ギリシャから、数というもののコンセプトが伝わってきたときに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
という言葉が出来た。ちなみにギリシャは10進法だったので、このフランス地方も10進法だったんではないか? もちろんギリシャ象形文字の1,2,3,4,。
2からは、たくさんと言うことになってどうでもいいというコンセプトは、そのまま置き去りにされたのではないか? 数で代用すればいいわけだから。
ということで、
0−−−<食べる物ない!困った>
1−−−un une <お父ちゃんたちよくやったわね。>
2−−−des <こんなに取ってきてどうすんのよ!腐っちゃうじゃない。それに、来年どうすんのよ、この生物が減少したら、私たち飢えるわよ>
の名残に私は、翻弄されてるのではないか??
歴史は面白く、色々サイトであたって見ました。上の説にドンぴしゃりという細かい記述はないですが、全体の歴史の面白いサイトがありましたので、以下に貼り付けます。
http://history.husigi.com/
日本語だけだと思う。歴史雑学的で面白い。
http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/toguchi/links/histoire_fr.htm
リンク集。とぶとフランス語。上級フランス語学習者にとって面白いのでは?
複数形 と 単数形 愛している方! 私たちに、なぜか、を教えてください。
私、15年間英語も含めて、複数形 と 単数形をきちんと使おうとしてきたんですが、なんだかよく間違うんです。フランス語を勉強しだして、これはいかんなと思いました。英語と同じ間違いが!
それで なぜ板につかないかと考えると、複数形 と 単数形を愛してないんですよ。フランス語は英語より愛してるので、勉強は乗る気なんですが、複数形 と 単数形は、愛してないから、身体が拒否している。頭は、そうしようともがいてるのに。
ですから、このトピックは、複数形 と 単数形を愛するにはどうすればいいのでしょうか?に切り替えてもいいでしょう。
皆さんの意見の中で、複数形 と 単数形を愛していらっしゃる方がいますね。その方(たち)にお聞きしたい?
なぜ?
複数形 と 単数形で困ってる日本人って多いと思います。ロマン語の語学の先生何人にも聞いても、<冠詞は、日本人には難関らしい。ほかの文法は、ほかの民族より覚えが早くて、頭がいいのだけど、冠詞が駄目なのはなぜ?>と聞き返されます。
今までは<日本語にないから>といっていたのですが、このトピックを立てさせてもらって、わかりました。愛してないんですわ。
ということで、愛している方! 私たちに、なぜか、を教えてください。
もう一つの面白い局面は、歴史ですね。
土曜日の朝から、私の頭にはガロア人がうほうほう!と狩をしている映像が流れていました。
私の仮説:
狩り社会のとき、0と1がとても大切だったんではないか? 2からは、たくさんと言うことになってどうでもいい、又は困ったことではなかったか?
というのは、家族で狩りをする場合、獲物が0と1は死活問題。ところがたくさんになるとかえって困る。獲物をどうプリザーブするかの料理法の発達は、寒い地方のほうが発達してますね。フランスはそれほど寒くもないので、フィンランドとかに比べると少ない。でも、スモークでプリザーブする方法は古くからあみ出してたと思います。スモークするのが、おとうちゃんたちが3匹の巨大な動物を狩ってきちゃったら、おかあちゃんたちは、大変だったのでは? <あんたプリザーブする人手が足んないじゃない、こんなに取ってきてどうするのよ?>
0と1がことさら発達しているフランス語の背景にはまずこれがあるのではないか?0を示す言葉もフランス語にことさら多いですよね。
フランス地方では、早くから農牧農耕社会に変わってるんです。羊の頭数を数えてたのかというと、私は疑問に思います。群れだの、たくさんだの、少しだのの言葉が多いのは、正確に数を数えない文化だったんじゃないか?
ここは数文化が、早くに発達しなかった。エジプト、ギリシャから、数というもののコンセプトが伝わってきたときに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
という言葉が出来た。ちなみにギリシャは10進法だったので、このフランス地方も10進法だったんではないか? もちろんギリシャ象形文字の1,2,3,4,。
2からは、たくさんと言うことになってどうでもいいというコンセプトは、そのまま置き去りにされたのではないか? 数で代用すればいいわけだから。
ということで、
0−−−<食べる物ない!困った>
1−−−un une <お父ちゃんたちよくやったわね。>
2−−−des <こんなに取ってきてどうすんのよ!腐っちゃうじゃない。それに、来年どうすんのよ、この生物が減少したら、私たち飢えるわよ>
の名残に私は、翻弄されてるのではないか??
歴史は面白く、色々サイトであたって見ました。上の説にドンぴしゃりという細かい記述はないですが、全体の歴史の面白いサイトがありましたので、以下に貼り付けます。
http://history.husigi.com/
日本語だけだと思う。歴史雑学的で面白い。
http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/toguchi/links/histoire_fr.htm
リンク集。とぶとフランス語。上級フランス語学習者にとって面白いのでは?
複数形 と 単数形 愛している方! 私たちに、なぜか、を教えてください。
もしかして私愛してる組???麗子さんの文章楽しい。思わず大笑いしてしまいました。
これは単・複数形だけでなく、冠詞問題のような気がしますね。冠詞にはご存じの通り、3種類あってそれぞれ単数は男性女性、そして複数形がありますね。これを愛しているかと言われればあんまり愛してはいないと思う。てか、冠詞は絶対日本人学習者にはできない。理論的には完全に分析し使いこなすのは、”てにをは+が”のもっと手の込んだやつみたいなもんで、無理でしょう。それはほんとに悔しいです。
ただ、そこまで行かなくても、本とか読んでいても実に冠詞はきっちり意味を持って存在しているので、どの冠詞がついているかで、多くの文章を節約できます。
複数の冠詞がついているだけで日本語でだったらたくさんの言葉を費やさなければならないところ、lesで済むとか、そういうのグッと来ます(時々)。
一般的フランス人女性は全員・・・が、les francaisesですむ。
実際、4405さんが言っている様にこれをそのまま訳したら変な日本語だ。だから"普通フランスの女性は”という風にするだろう。しかし、lesの中には全員というニュアンスが確かに入っているのであって、この日本語訳には入っているようないないような微妙なところである。それは前後の文脈から感じ取るものなのであり、そこが日本語なのでしょう。
要はフランス語好きの人間は “めんどくさがりの理屈こき、しつこいわりにいい加減” が多く、それはつまり、フランス人の性質とも言えるのかもしれないけれど(あ、ここのフランス人と言う言葉のニュアンスにはlesが入ってますね)、それがフラ語を愛する理由なのかも知れません。もちろんそうじゃない方もたくさんいらっしゃると思いますが、私は結構そういう気質です。
3種類の冠詞+所有形容詞(mon,ton,son...)も加わり、どれを使っていいやら、でもどれでも良いと言うことも多く、そしてかすかに違いがある、そんなフラ語、、、愛しているのであろうか。
Je prends un bain.(入る前とか習慣を話すとき)
Je prends le bain.(今入っている)
J'ai pris mon bain.(入った後)
この上の三つ(記憶が間違ってなければ)を聞いたとき、目が点になりました。はい
これは単・複数形だけでなく、冠詞問題のような気がしますね。冠詞にはご存じの通り、3種類あってそれぞれ単数は男性女性、そして複数形がありますね。これを愛しているかと言われればあんまり愛してはいないと思う。てか、冠詞は絶対日本人学習者にはできない。理論的には完全に分析し使いこなすのは、”てにをは+が”のもっと手の込んだやつみたいなもんで、無理でしょう。それはほんとに悔しいです。
ただ、そこまで行かなくても、本とか読んでいても実に冠詞はきっちり意味を持って存在しているので、どの冠詞がついているかで、多くの文章を節約できます。
複数の冠詞がついているだけで日本語でだったらたくさんの言葉を費やさなければならないところ、lesで済むとか、そういうのグッと来ます(時々)。
一般的フランス人女性は全員・・・が、les francaisesですむ。
実際、4405さんが言っている様にこれをそのまま訳したら変な日本語だ。だから"普通フランスの女性は”という風にするだろう。しかし、lesの中には全員というニュアンスが確かに入っているのであって、この日本語訳には入っているようないないような微妙なところである。それは前後の文脈から感じ取るものなのであり、そこが日本語なのでしょう。
要はフランス語好きの人間は “めんどくさがりの理屈こき、しつこいわりにいい加減” が多く、それはつまり、フランス人の性質とも言えるのかもしれないけれど(あ、ここのフランス人と言う言葉のニュアンスにはlesが入ってますね)、それがフラ語を愛する理由なのかも知れません。もちろんそうじゃない方もたくさんいらっしゃると思いますが、私は結構そういう気質です。
3種類の冠詞+所有形容詞(mon,ton,son...)も加わり、どれを使っていいやら、でもどれでも良いと言うことも多く、そしてかすかに違いがある、そんなフラ語、、、愛しているのであろうか。
Je prends un bain.(入る前とか習慣を話すとき)
Je prends le bain.(今入っている)
J'ai pris mon bain.(入った後)
この上の三つ(記憶が間違ってなければ)を聞いたとき、目が点になりました。はい
いや!これ面白い。はまりました。有難う横断歩道さん
http://lapin.ic.h.kyoto-u.ac.jp/
まだ全部読んでないけど、東郷雄二と言う方、面白いフランス語を愛してる教授ですね。皆さん読んでみて! 面白いよ。
マリーさん
これやっぱ目が点でした。
Je prends un bain.(入る前とか習慣を話すとき)
Je prends le bain.(今入っている)
J'ai pris mon bain.(入った後)
旦那にどうだ!と試したら、そうだよ。ココ(私の愛称)と言ってました。ただ、みんなフランス人はそう思うのか、サンプル集めてきます。旦那はは私のいく千のフランス語の質問を避けようとするので、信用していいんだか疑問。やっぱ、フランス人はケチだぞ。(ただしうちの旦那だけ)
J'ai pris DES bainS
Je prenais des bains.
はさしずめ、
日本の風呂にも入ったことあるし、フランスの風呂も入ったことあるし、フィンランドの風呂にも入ったことがあるという感じなのかしら?
麗子
http://lapin.ic.h.kyoto-u.ac.jp/
まだ全部読んでないけど、東郷雄二と言う方、面白いフランス語を愛してる教授ですね。皆さん読んでみて! 面白いよ。
マリーさん
これやっぱ目が点でした。
Je prends un bain.(入る前とか習慣を話すとき)
Je prends le bain.(今入っている)
J'ai pris mon bain.(入った後)
旦那にどうだ!と試したら、そうだよ。ココ(私の愛称)と言ってました。ただ、みんなフランス人はそう思うのか、サンプル集めてきます。旦那はは私のいく千のフランス語の質問を避けようとするので、信用していいんだか疑問。やっぱ、フランス人はケチだぞ。(ただしうちの旦那だけ)
J'ai pris DES bainS
Je prenais des bains.
はさしずめ、
日本の風呂にも入ったことあるし、フランスの風呂も入ったことあるし、フィンランドの風呂にも入ったことがあるという感じなのかしら?
麗子
少しずれるかもしれませんが、金田一春彦さんの「日本語」(岩波新書)に面白いことが書いてありましたので引用します。
-----引用始まり-----
日本語の名詞は数の区別がないということがよく話題になる。(中略)この単複の区別は、世界の言語にかなり普遍的な現象で、インド・ヨーロッパ語はすべてもち、ウラル諸語・アルタイ諸語からビルマ語にまで及んでおり、ハム・セム諸語、アフリカの諸言語や太平洋の諸言語にも見られる。すなわち数の区別のない言語の方が珍しく、日本語のほかは朝鮮語・旧満州語・中国語・タイ語・ヴェトナム語(『安南語広文典』)から、インドネシア語(市河三喜ほか編『世界言語概説』下)などがそうで、大体、アジアの東南方にかたまっている。
日本語や中国語に数の区別がないことは、ヨーロッパ人を驚かせ、・・・
-----引用終わり-----
世界的にみれば、「なんで単数複数の区別をしないの?」と不思議に思う人のほうが多いってことになるのでしょうか。
また、金田一春彦さんの「日本語」によりますと、D・カーという中国語学者が中国語に名詞の数の区別のないことを知ったときの感想として
「われわれ西洋人は、数という範疇をもつためにいかに多くの不合理を犯させられているかと感得した」
と語ったそうです。
さらにこの「日本語」には双数という概念についても説明がされています。
双数というのは、対象を一つの場合、二つの場合、三つ以上場合と区別をすることです。この双数の概念を持つ代表的な言語はアラビア語で、ヨーロッパでは昔のギリシャ語、今のスロベニア語、リトアニア語にあるそうです。マオリ族の「さようなら」は、相手が一人、二人、三人以上によって使い分けられるそうですし、ミクロネシアのマーシャル群島のなかには、対象が三つ、四つの場合についても使い分けをする言語があるのだそうです。
おもしろいですね。
-----引用始まり-----
日本語の名詞は数の区別がないということがよく話題になる。(中略)この単複の区別は、世界の言語にかなり普遍的な現象で、インド・ヨーロッパ語はすべてもち、ウラル諸語・アルタイ諸語からビルマ語にまで及んでおり、ハム・セム諸語、アフリカの諸言語や太平洋の諸言語にも見られる。すなわち数の区別のない言語の方が珍しく、日本語のほかは朝鮮語・旧満州語・中国語・タイ語・ヴェトナム語(『安南語広文典』)から、インドネシア語(市河三喜ほか編『世界言語概説』下)などがそうで、大体、アジアの東南方にかたまっている。
日本語や中国語に数の区別がないことは、ヨーロッパ人を驚かせ、・・・
-----引用終わり-----
世界的にみれば、「なんで単数複数の区別をしないの?」と不思議に思う人のほうが多いってことになるのでしょうか。
また、金田一春彦さんの「日本語」によりますと、D・カーという中国語学者が中国語に名詞の数の区別のないことを知ったときの感想として
「われわれ西洋人は、数という範疇をもつためにいかに多くの不合理を犯させられているかと感得した」
と語ったそうです。
さらにこの「日本語」には双数という概念についても説明がされています。
双数というのは、対象を一つの場合、二つの場合、三つ以上場合と区別をすることです。この双数の概念を持つ代表的な言語はアラビア語で、ヨーロッパでは昔のギリシャ語、今のスロベニア語、リトアニア語にあるそうです。マオリ族の「さようなら」は、相手が一人、二人、三人以上によって使い分けられるそうですし、ミクロネシアのマーシャル群島のなかには、対象が三つ、四つの場合についても使い分けをする言語があるのだそうです。
おもしろいですね。
>麗子さん
亀レスですみませんが、最近ちょっと思っていることがあります。
日本にいる外国人を見ていると、日本語の格助詞が苦手な人が多い気がするのです。
会話していると気が付かないのですが、文章を書かせると、いわゆる「てにをは」の使い方がおかしいんです。
でも意味は通じるので、積極的に直そうとする人が周囲にいない。
すると、本人が気をつけない限り直らないのです。
一方で、完璧に格助詞を使いこなせる外国人も、もちろんいます。
助詞なんて、日本語の文法を習うときに、最初の方に出てくるはずです。
まともに日本語を習った人なら誰でも知ってる筈なのに、使いこなせる人とそうでない人がいる。
これは、もしかするとその人たちが「格助詞を愛しているかどうか」の違いかもしれませんね。
フランス語(英語)の単数・複数を日本人が使い分けられないのと、同じような現象、なのかもしれません。
亀レスですみませんが、最近ちょっと思っていることがあります。
日本にいる外国人を見ていると、日本語の格助詞が苦手な人が多い気がするのです。
会話していると気が付かないのですが、文章を書かせると、いわゆる「てにをは」の使い方がおかしいんです。
でも意味は通じるので、積極的に直そうとする人が周囲にいない。
すると、本人が気をつけない限り直らないのです。
一方で、完璧に格助詞を使いこなせる外国人も、もちろんいます。
助詞なんて、日本語の文法を習うときに、最初の方に出てくるはずです。
まともに日本語を習った人なら誰でも知ってる筈なのに、使いこなせる人とそうでない人がいる。
これは、もしかするとその人たちが「格助詞を愛しているかどうか」の違いかもしれませんね。
フランス語(英語)の単数・複数を日本人が使い分けられないのと、同じような現象、なのかもしれません。
横断歩道さん!
これはなるほど!です。
マリーさん!私昨日やっと風呂に入りました。
J'ai pris mon bain.(入った後)
です。
また考えたのですが。。。.(入った後)というのは、直後?それともずっとこう?
隣にいた旦那(フランス人)に聞いてみた。
昨日風呂に入ったわたしゃの場合はどうすんねん と聞いたら、
J'ai pris un bain
でも!これ(下記)にはそのとうりだと賛成してたのに。。。
Je prends un bain.(入る前とか習慣を話すとき)
Je prends le bain.(今入っている)
J'ai pris mon bain.(入った後)
ここちゃん、悪いけど、冠詞問題は非常に柔らかな考えで、次に来るセンテンス、話す内容で変わるんだからね。と言われました。フランス語は、私をなめなめ、なめなめ。
なめられても、不合理を愛せよ。
いわゆる「てにをは」の使い方は、日本語教師が、教えるのに一番困ります。大体、初級学習者は、最初はそんな事気にしてられない。だんだん話せるようになると、「てにをは」の煩雑さに頭にくる。怒っている。頭にくる。そこで2通りに分かれる。喋れれば間違っても気にしない人。きれいな日本語をと思い葛藤が何年にもわたる人。
まあ、お互い様と笑いつつ。
私の葛藤は続く。
これはなるほど!です。
マリーさん!私昨日やっと風呂に入りました。
J'ai pris mon bain.(入った後)
です。
また考えたのですが。。。.(入った後)というのは、直後?それともずっとこう?
隣にいた旦那(フランス人)に聞いてみた。
昨日風呂に入ったわたしゃの場合はどうすんねん と聞いたら、
J'ai pris un bain
でも!これ(下記)にはそのとうりだと賛成してたのに。。。
Je prends un bain.(入る前とか習慣を話すとき)
Je prends le bain.(今入っている)
J'ai pris mon bain.(入った後)
ここちゃん、悪いけど、冠詞問題は非常に柔らかな考えで、次に来るセンテンス、話す内容で変わるんだからね。と言われました。フランス語は、私をなめなめ、なめなめ。
なめられても、不合理を愛せよ。
いわゆる「てにをは」の使い方は、日本語教師が、教えるのに一番困ります。大体、初級学習者は、最初はそんな事気にしてられない。だんだん話せるようになると、「てにをは」の煩雑さに頭にくる。怒っている。頭にくる。そこで2通りに分かれる。喋れれば間違っても気にしない人。きれいな日本語をと思い葛藤が何年にもわたる人。
まあ、お互い様と笑いつつ。
私の葛藤は続く。
ばとんの王子さま☆丁寧なご説明ありがとうございました。
複数と単数から冠詞問題と冠詞問題の煩雑さから日本語の助詞問題へと発展してしまいました。
助詞も一つ一つのケースは説明できても、やはり使い方が重なる部分とか、修飾節に出て来るとなんか違ったりが出て来るので
外国の学習者には実際何を選んだら良いのか、私たちが冠詞を選ぶときの様に大変でしょうね。
冠詞も一回一回出来上がったものの説明を聞くと納得するものの、自分から選ぶのはハー大変。自分の中で理屈をこねても簡単に(>< )oダメーo( ><)oダメーo(><)oダメー!が出ますからね。
それにネイティブによっても言うことが違う事も多いし、それはその人やこっちのその度の説明で微妙なニュアンスや言い回しが変わることによって起きる事もあるので、なんともはや、何が正しいのか割り切れない事が多いです。もちろんこちらが言わんとしている事を相当近いところまで説明できれば、誤差も減って来るんでしょうが、そこまでつき合ってくれる人探すのも大変です。
なぜそんなに大切なのか、、、、
それはそれがフランス語で、今我々はそのフランス語を勉強しているから。
というなんとも素っ気ない答えに終始してしまうのかもしれません。それが魅力でもあり、それが苦悶でもあり、愛憎の並存関係みたいなものなのかもしれません。便利は便利だと思いますけどね。
なんか、ただでは転ばないようなフランス語好きですハイ(^-^)/。
複数と単数から冠詞問題と冠詞問題の煩雑さから日本語の助詞問題へと発展してしまいました。
助詞も一つ一つのケースは説明できても、やはり使い方が重なる部分とか、修飾節に出て来るとなんか違ったりが出て来るので
外国の学習者には実際何を選んだら良いのか、私たちが冠詞を選ぶときの様に大変でしょうね。
冠詞も一回一回出来上がったものの説明を聞くと納得するものの、自分から選ぶのはハー大変。自分の中で理屈をこねても簡単に(>< )oダメーo( ><)oダメーo(><)oダメー!が出ますからね。
それにネイティブによっても言うことが違う事も多いし、それはその人やこっちのその度の説明で微妙なニュアンスや言い回しが変わることによって起きる事もあるので、なんともはや、何が正しいのか割り切れない事が多いです。もちろんこちらが言わんとしている事を相当近いところまで説明できれば、誤差も減って来るんでしょうが、そこまでつき合ってくれる人探すのも大変です。
なぜそんなに大切なのか、、、、
それはそれがフランス語で、今我々はそのフランス語を勉強しているから。
というなんとも素っ気ない答えに終始してしまうのかもしれません。それが魅力でもあり、それが苦悶でもあり、愛憎の並存関係みたいなものなのかもしれません。便利は便利だと思いますけどね。
なんか、ただでは転ばないようなフランス語好きですハイ(^-^)/。
Je parle français
Je parle le français
parler は冠詞つけなくてもつけてもいい。
この、動詞だけですね、多分。
後は全部 le français
つけなくてもいいといわれると今度はびびりますね。
バトンの王子様:
その対比!それが困る(日本語学習者 が。私 は 困りませんが)とホホ、(日本語の先生やってたとき)
?希望を表す時 「野球がしたい」
?能力を表す時 「水泳ができる」「数学がわかる」
?好き嫌いを表す時 「君が好きだ」
が は、対比でもあるだろう!!と生徒から詰め寄られるわけです。
?希望を表す時 「野球がしたい」(ジャンケン は したくない)
?能力を表す時 「水泳ができる」「数学がわかる」(フランス語 は 出来ない)
?好き嫌いを表す時 「君が好きだ」
(ほかの人 は 好きではない)
ほらどうだ対比じゃないか、と例題はこれとは違いますが、私は生徒に詰め寄られました。ーーー私、ごめんねと可愛そうで謝ったしまった。確かにわかり難い。
この前、コロンビア人が、フランス人に
誰かが 冠詞を落としがちに喋っていたら、どういう感じに思う? 正直に言ってね、と詰め寄ってました。
フランス人は
喋ってる人がフランスで生まれた人であれば、教養がないと思う。外人であれば、しょうがないかと思う。
と言ってました。
何年まで、外人の範疇に入れてくれるのかなあ?
Je parle le français
parler は冠詞つけなくてもつけてもいい。
この、動詞だけですね、多分。
後は全部 le français
つけなくてもいいといわれると今度はびびりますね。
バトンの王子様:
その対比!それが困る(日本語学習者 が。私 は 困りませんが)とホホ、(日本語の先生やってたとき)
?希望を表す時 「野球がしたい」
?能力を表す時 「水泳ができる」「数学がわかる」
?好き嫌いを表す時 「君が好きだ」
が は、対比でもあるだろう!!と生徒から詰め寄られるわけです。
?希望を表す時 「野球がしたい」(ジャンケン は したくない)
?能力を表す時 「水泳ができる」「数学がわかる」(フランス語 は 出来ない)
?好き嫌いを表す時 「君が好きだ」
(ほかの人 は 好きではない)
ほらどうだ対比じゃないか、と例題はこれとは違いますが、私は生徒に詰め寄られました。ーーー私、ごめんねと可愛そうで謝ったしまった。確かにわかり難い。
この前、コロンビア人が、フランス人に
誰かが 冠詞を落としがちに喋っていたら、どういう感じに思う? 正直に言ってね、と詰め寄ってました。
フランス人は
喋ってる人がフランスで生まれた人であれば、教養がないと思う。外人であれば、しょうがないかと思う。
と言ってました。
何年まで、外人の範疇に入れてくれるのかなあ?
>麗子
a) 人間というものが 死すべき存在である
->それはあってると思います。
b) その人間は 死すべき存在である
->それは、ちょっと違う気がします。
Cet homme est mortelのほうが近いと思います。
L'homme est mortelって日本語にすれば。。。
a)にとても近いですよ。一般的に誰だって一人の人間が死すべき存在であるっていう意味です。あの場合は’Le’と’Un’は微妙に同じ意味ですよ。
ニュアンスは、多分
Un homme est mortel:微妙にちょっと主観的なきがする
誰かに自分が知ってること教えってるところ。
もちろんそういうことは、みんな知ってるからあまり強い意味でもないです
L'homme est mortel:微妙にちょっと客観的なきがする
一般的の現実としていうこと。誰でも知ってること。
c) 人間すべては 死すべき存在である
->それは合ってると思います。
a) 人間というものが 死すべき存在である
->それはあってると思います。
b) その人間は 死すべき存在である
->それは、ちょっと違う気がします。
Cet homme est mortelのほうが近いと思います。
L'homme est mortelって日本語にすれば。。。
a)にとても近いですよ。一般的に誰だって一人の人間が死すべき存在であるっていう意味です。あの場合は’Le’と’Un’は微妙に同じ意味ですよ。
ニュアンスは、多分
Un homme est mortel:微妙にちょっと主観的なきがする
誰かに自分が知ってること教えってるところ。
もちろんそういうことは、みんな知ってるからあまり強い意味でもないです
L'homme est mortel:微妙にちょっと客観的なきがする
一般的の現実としていうこと。誰でも知ってること。
c) 人間すべては 死すべき存在である
->それは合ってると思います。
>潮路さん、
よく分からないのでよかったら教えてください。
僕の理解が正しければ、潮路さんがおっしゃっているのは、総称文においては、
1) un N → 「Nであるどの個体をとっても」という意味を表す
2) le N → Nという名詞の意味そのものを指す
3) les N → 「Nであるすべての個体」を表す
ということですね。
まず2)の場合からですが、次の二つの発言は矛盾しているように思われます。
便宜上(i)(ii)と番号を振りました。
> (i) (l'hommeは)「世の中全てに存在する[homme]のこと」を言っているのではなくて、「[homme]と呼ばれるものが共通して持つ性質のこと」を言っているのです。つまりは、[homme]が持つ意味を指しているのです。
> (ii) (l'homme est mortelの意味=)人間という性質をもつものは、死すべき存在である。
なぜ矛盾かと言うと、(i)ではl'hommeが「性質」や「意味」を指すと言われているのに、
(ii)ではl'hommeが「〜性質を持つ*もの*」と訳されているからです。
(i)に厳密に従うならば、(ii)の訳は
「人間と呼ばれるものが持つ性質は死すべきものである」
「人間という言葉が持つ意味は死すべきものである」
といった奇妙なものになるはずです。
つまり、死ぬのは人間ではなく、人間の性質や人間という言葉の意味
ということになるはずです。
逆に、(ii)の訳に厳密に従うならば、(i)の説明は誤りで、
「l'hommeは[homme]という性質を持つものを表す」
となるはずです。平たく言えば、要するに人間を指すことになるはずです。
この矛盾はどう解決すればよいでしょうか。
次に3)のles Nの場合ですが、les hommesが「すべての人間の個体」
を指すと考えると、ちょっと困ったことが起きます。
この考え方だと、Les hommes sont mortelsは
太郎は死すべきものである。
次郎は死すべきものである。
花子は死すべきものである。
・・・
というように、すべての個体に対して「死すべきものである」
という述語が当てはまる、という意味を表しますね。
ここまではいいのですが、次のような場合はどうでしょう。
問題その1:
「人類は絶滅した」
○ Les hommes sont eteints.
は(意味が変なのはさておき)正しいフランス語だと思われます。
しかもこれは総称文の一種でしょう。
ところが、「絶滅した」というのは人間という種に対しては当てはまりますが、
個体に対しては当てはまりません。
×太郎は絶滅した。
×次郎は絶滅した。
×花子は絶滅した。
・・・
このように個体に還元できないケースはどうなのか、というのが一つの疑問です。
問題2: (hommesだと分かりにくいので例を変えます)
「日本人は親切だ」
○Les Japonais sont gentils.
これも正しいフランス語でしょう。
問題は、親切でない日本人が相当数いても、
この文は全く問題がない、ということです。
例外があっても全く問題がないのです。
したがって、
les Japonais = Japonaisであるすべての個体
とするのは誤りです。
これらの点で、les Nはun Nと異なります。
「人類は絶滅した」
×Un homme est eteint.
「日本人は親切だ」
Un Japonais est gentil.
(↑例外があってはいけない。すべての日本人がもれなく親切である必要がある。)
これらの事実は、上記のとおり、
1) un N → 「Nであるどの個体をとっても」という意味を表す
であることから自動的に出てきます。
×人間であるどの個体を取っても、その個体は絶滅した。
日本人であるどの個体を取っても、その個体は親切だ。(←例外禁止)
したがって、潮路さんのun Nに関するご説明には同意します。
le Nとles Nの場合について、何かお考えがおありでしたら、
ご説明いただけると嬉しいです。
よく分からないのでよかったら教えてください。
僕の理解が正しければ、潮路さんがおっしゃっているのは、総称文においては、
1) un N → 「Nであるどの個体をとっても」という意味を表す
2) le N → Nという名詞の意味そのものを指す
3) les N → 「Nであるすべての個体」を表す
ということですね。
まず2)の場合からですが、次の二つの発言は矛盾しているように思われます。
便宜上(i)(ii)と番号を振りました。
> (i) (l'hommeは)「世の中全てに存在する[homme]のこと」を言っているのではなくて、「[homme]と呼ばれるものが共通して持つ性質のこと」を言っているのです。つまりは、[homme]が持つ意味を指しているのです。
> (ii) (l'homme est mortelの意味=)人間という性質をもつものは、死すべき存在である。
なぜ矛盾かと言うと、(i)ではl'hommeが「性質」や「意味」を指すと言われているのに、
(ii)ではl'hommeが「〜性質を持つ*もの*」と訳されているからです。
(i)に厳密に従うならば、(ii)の訳は
「人間と呼ばれるものが持つ性質は死すべきものである」
「人間という言葉が持つ意味は死すべきものである」
といった奇妙なものになるはずです。
つまり、死ぬのは人間ではなく、人間の性質や人間という言葉の意味
ということになるはずです。
逆に、(ii)の訳に厳密に従うならば、(i)の説明は誤りで、
「l'hommeは[homme]という性質を持つものを表す」
となるはずです。平たく言えば、要するに人間を指すことになるはずです。
この矛盾はどう解決すればよいでしょうか。
次に3)のles Nの場合ですが、les hommesが「すべての人間の個体」
を指すと考えると、ちょっと困ったことが起きます。
この考え方だと、Les hommes sont mortelsは
太郎は死すべきものである。
次郎は死すべきものである。
花子は死すべきものである。
・・・
というように、すべての個体に対して「死すべきものである」
という述語が当てはまる、という意味を表しますね。
ここまではいいのですが、次のような場合はどうでしょう。
問題その1:
「人類は絶滅した」
○ Les hommes sont eteints.
は(意味が変なのはさておき)正しいフランス語だと思われます。
しかもこれは総称文の一種でしょう。
ところが、「絶滅した」というのは人間という種に対しては当てはまりますが、
個体に対しては当てはまりません。
×太郎は絶滅した。
×次郎は絶滅した。
×花子は絶滅した。
・・・
このように個体に還元できないケースはどうなのか、というのが一つの疑問です。
問題2: (hommesだと分かりにくいので例を変えます)
「日本人は親切だ」
○Les Japonais sont gentils.
これも正しいフランス語でしょう。
問題は、親切でない日本人が相当数いても、
この文は全く問題がない、ということです。
例外があっても全く問題がないのです。
したがって、
les Japonais = Japonaisであるすべての個体
とするのは誤りです。
これらの点で、les Nはun Nと異なります。
「人類は絶滅した」
×Un homme est eteint.
「日本人は親切だ」
Un Japonais est gentil.
(↑例外があってはいけない。すべての日本人がもれなく親切である必要がある。)
これらの事実は、上記のとおり、
1) un N → 「Nであるどの個体をとっても」という意味を表す
であることから自動的に出てきます。
×人間であるどの個体を取っても、その個体は絶滅した。
日本人であるどの個体を取っても、その個体は親切だ。(←例外禁止)
したがって、潮路さんのun Nに関するご説明には同意します。
le Nとles Nの場合について、何かお考えがおありでしたら、
ご説明いただけると嬉しいです。
Premisses
Tous les hommes sont mortels
(moyen /middle) (majeur / major)
Or les Grecs sont des hommes
(mineur / minor) (moyen / middle)
Conclusion
Donc Tous les Grecs sont mortels
(mineur / minor) (majeur / major)
Schema
なんですね。皆さんの書き込みを見て、サイトで遊びだしたら見つけたものです。
Les hommes sont mortels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syllogisme
L'homme est mortel.
http://www.iut-nantes.univ-nantes.fr/~habrias/spec1/attribut.html
色々想像したんですが、この後に続く文章が問題ではないかと。。。もし私なら、(今のレベルでの問題ですが)このあとどんな文章を書く想像してみました。
a) Un homme est mortel
エミースーの死はnyのダンスを愛するものにとって、降ってわいた悲劇であった。
病床にある彼女が、酸素ボンベと共に2人の看護婦に付き添われながら杮落としに現れたときには、会場はしんと静まりながらーーーーー
nyタイムズの記事みたいな感じ。
b) L'homme est mortel
この大前提を覆す新薬というものはーーー
メデイカル関係の論文。
c)Les hommes sont mortels
人間はいつかは死ぬものだ。
これが一番使い出があるような気がする。おばあちゃんが死んで嘆く人を慰めるときから、 カフェで 哲学っぽい論争をするときも。
Un homme est mortel が、一番使いにくいような匂いがします。
ただ単に勘ですが。。。変?
Tous les hommes sont mortels
(moyen /middle) (majeur / major)
Or les Grecs sont des hommes
(mineur / minor) (moyen / middle)
Conclusion
Donc Tous les Grecs sont mortels
(mineur / minor) (majeur / major)
Schema
なんですね。皆さんの書き込みを見て、サイトで遊びだしたら見つけたものです。
Les hommes sont mortels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syllogisme
L'homme est mortel.
http://www.iut-nantes.univ-nantes.fr/~habrias/spec1/attribut.html
色々想像したんですが、この後に続く文章が問題ではないかと。。。もし私なら、(今のレベルでの問題ですが)このあとどんな文章を書く想像してみました。
a) Un homme est mortel
エミースーの死はnyのダンスを愛するものにとって、降ってわいた悲劇であった。
病床にある彼女が、酸素ボンベと共に2人の看護婦に付き添われながら杮落としに現れたときには、会場はしんと静まりながらーーーーー
nyタイムズの記事みたいな感じ。
b) L'homme est mortel
この大前提を覆す新薬というものはーーー
メデイカル関係の論文。
c)Les hommes sont mortels
人間はいつかは死ぬものだ。
これが一番使い出があるような気がする。おばあちゃんが死んで嘆く人を慰めるときから、 カフェで 哲学っぽい論争をするときも。
Un homme est mortel が、一番使いにくいような匂いがします。
ただ単に勘ですが。。。変?
>ホリさん、
レス遅くなってスミマセン☆
どちらでもいいと思いますが、moins que〜の方は比較形なので、できればそばに置いておいてくれると口語体では耳が聞き取り易いです。書かれているものならば遠く離れていても元に戻って読み直して、そのqueが何処から如何にやってきたのかが確認できるのでいいのですけど。。。格好つけて口語体でもqueをあとで取ってつけたような形で使うフランス人もいますが、記憶力テストされているようで私はあまり好きでないです。実際、「え?」って聞き返すと、「ほら〜、やっぱり人の話しをちゃんと聞いていない!」と諭されることありますね ^ ^;)
嫌味に聞えてしまうのは、Parler francaisには、「きちんと明確に言いたいことを論理的に話す」といった第二の意味もあるので、しかもtoiではなくvousを使用されているので、さすが貴方様の論理には私は到底かないません、とも聞こえます。フランスでフランス語を話すのは当たり前のことなので、こちらの第二の意味で使われることが多々とあります。然し、これはあくまでも現代の若者がパリあたりで会話している場面を想定してます。文法上は全く問題ないです。
フランス語は勿論文法も大切ですが、リエゾンや韻などがあるように「音」も非常に大事な言語なので、ある程度文法の基礎を頭が理解したら、あとはどんどん耳や舌に覚えこませるようにされるとよろしいかと思います。
レス遅くなってスミマセン☆
どちらでもいいと思いますが、moins que〜の方は比較形なので、できればそばに置いておいてくれると口語体では耳が聞き取り易いです。書かれているものならば遠く離れていても元に戻って読み直して、そのqueが何処から如何にやってきたのかが確認できるのでいいのですけど。。。格好つけて口語体でもqueをあとで取ってつけたような形で使うフランス人もいますが、記憶力テストされているようで私はあまり好きでないです。実際、「え?」って聞き返すと、「ほら〜、やっぱり人の話しをちゃんと聞いていない!」と諭されることありますね ^ ^;)
嫌味に聞えてしまうのは、Parler francaisには、「きちんと明確に言いたいことを論理的に話す」といった第二の意味もあるので、しかもtoiではなくvousを使用されているので、さすが貴方様の論理には私は到底かないません、とも聞こえます。フランスでフランス語を話すのは当たり前のことなので、こちらの第二の意味で使われることが多々とあります。然し、これはあくまでも現代の若者がパリあたりで会話している場面を想定してます。文法上は全く問題ないです。
フランス語は勿論文法も大切ですが、リエゾンや韻などがあるように「音」も非常に大事な言語なので、ある程度文法の基礎を頭が理解したら、あとはどんどん耳や舌に覚えこませるようにされるとよろしいかと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
フランス語・助け合いの会 更新情報
-
最新のアンケート
フランス語・助け合いの会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77425人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209449人
- 3位
- 空を見上げるのが好き
- 139119人