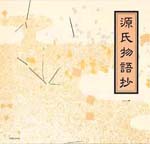視聴感想はこちらで
(投稿の際は何話かやタイトルも入れてもらうと助かります)
平安時代中期を舞台に紫式部(吉高由里子)が 藤原道長(柄本佑)への思いと秘めた情熱とたぐいまれな想像力で生を紡いでゆくNHK大河。
平安中期の藤原氏の権謀術数やこの時期謎の多い建物・調度・衣装・儀式等有識故実にも注目!
【キャスト】吉高由里子、柄本佑、黒木華、井浦新、吉田羊、ユースケ・サンタマリア、佐々木蔵之介、岸谷五朗、段田安則
【作】大石静(脚本家)
全体相関図(NHK)
https:/
【放送予定】
2024年1月7日(日) 放送スタート<初回15分拡大版>
[総合]日曜 午後8時00分 / 再放送 翌週土曜 午後1時05分
[BS・BSP4K]日曜 午後6時00分
[BSP4K]日曜 午後0時15分
(投稿の際は何話かやタイトルも入れてもらうと助かります)
平安時代中期を舞台に紫式部(吉高由里子)が 藤原道長(柄本佑)への思いと秘めた情熱とたぐいまれな想像力で生を紡いでゆくNHK大河。
平安中期の藤原氏の権謀術数やこの時期謎の多い建物・調度・衣装・儀式等有識故実にも注目!
【キャスト】吉高由里子、柄本佑、黒木華、井浦新、吉田羊、ユースケ・サンタマリア、佐々木蔵之介、岸谷五朗、段田安則
【作】大石静(脚本家)
全体相関図(NHK)
https:/
【放送予定】
2024年1月7日(日) 放送スタート<初回15分拡大版>
[総合]日曜 午後8時00分 / 再放送 翌週土曜 午後1時05分
[BS・BSP4K]日曜 午後6時00分
[BSP4K]日曜 午後0時15分
|
|
|
|
コメント(67)
第10回「月夜の陰謀」
正に陰謀…兼家の綿密な権謀術数が凄いっ!
暗躍する晴明も道兼も不気味…!
大鏡等の資料に基づく緊迫した事件の顛末が観ていてドキドキし愉しめた!
皇位継承の証明である剣と曲玉を合わせた「剣璽(けんじ)」も出てきましたね!
東宮の母としてついに国母に成った詮子(あきこ)の道長推しは後々大いに役に立つ!
哀れ花山天皇…しかし此の後法院となっても色々やってくれ北家に利用されるポイント高いユニークキャラですね!
更に哀れなのは職を失う為時…この後不遇の長い時期が続きます!
此の間の様々な体験はまひろ(紫式部)の創作造型活動に影響した様ですね!
色々な資料や物語等の文章では解り難い有識故実や官位や立場による違いの座の位置等も含め参考になる場面が多々ありますね!
道長とまひろの文のやりとりはいいですねぇ!
どんどん想いが深まっていきます!
古今集等古歌からとった道長の和歌と漢籍の漢詩まひろの歌の対比も面白い!
何故漢詩か?の道長への行成のアドバイスが流石能書家ぶりの回答でした!
道長とまひろのラブシーンは流石の大石脚本で濃厚でキュンキュン来る内容でした!
創作とは言えこの時代の文の遣り取りと逢瀬を体感出来うっとりでしたね(^_-)-☆
歓びと哀しみの融合した涙…美しい場面でしたね!
真面目で一本気な実資はいつも面白い!
正に陰謀…兼家の綿密な権謀術数が凄いっ!
暗躍する晴明も道兼も不気味…!
大鏡等の資料に基づく緊迫した事件の顛末が観ていてドキドキし愉しめた!
皇位継承の証明である剣と曲玉を合わせた「剣璽(けんじ)」も出てきましたね!
東宮の母としてついに国母に成った詮子(あきこ)の道長推しは後々大いに役に立つ!
哀れ花山天皇…しかし此の後法院となっても色々やってくれ北家に利用されるポイント高いユニークキャラですね!
更に哀れなのは職を失う為時…この後不遇の長い時期が続きます!
此の間の様々な体験はまひろ(紫式部)の創作造型活動に影響した様ですね!
色々な資料や物語等の文章では解り難い有識故実や官位や立場による違いの座の位置等も含め参考になる場面が多々ありますね!
道長とまひろの文のやりとりはいいですねぇ!
どんどん想いが深まっていきます!
古今集等古歌からとった道長の和歌と漢籍の漢詩まひろの歌の対比も面白い!
何故漢詩か?の道長への行成のアドバイスが流石能書家ぶりの回答でした!
道長とまひろのラブシーンは流石の大石脚本で濃厚でキュンキュン来る内容でした!
創作とは言えこの時代の文の遣り取りと逢瀬を体感出来うっとりでしたね(^_-)-☆
歓びと哀しみの融合した涙…美しい場面でしたね!
真面目で一本気な実資はいつも面白い!
第11回「まどう心」
兼家の謀略がまんまと成功し権力を掌握!
除目も北家をこれ見よがしに配する露骨な取扱いで着々と我が世の春が進行中!
袂を別っていた為時はまひろがどうあがこうが兼家の言う様に官職を得る事は無いのが政治経済の世界!
普段温厚な倫子にたしなめられ、更に注進されても兼家に直談判して政治の現実を知る事でこの世界の駆け引きの難しさをしる事になる!
その為の権力闘争と権謀術数であり、忖度であり贈答や寄付である時代でまひろや為時の様に実直で真面目に生きて行くのは今より辛い!
一条天皇の即位の様子が描かれており高御座や「大鏡」による生首事件等的確に描かれています!
恐いーっ( ;∀;)
倫子サロンでの倫子とまひろ二人の恋バナは、後々を知っている人にとっては、談笑し明るい二人だけに残酷感いっぱい!
宣孝のまひろへの婿取り話とリンクする道長からの妾(しょう)への誘いは純粋に愛する事と正妻(北の方)の扱いへの二人の想いの違いが顕れ哀しくも美しい場面でした!
二人の分岐点となる描写で音楽と映像の妙が表出されていて良かったですね☆
伊周や定子も現れいよいよ一条帝時代!
面白くなってきました!
紀行は晴明…現代も人気ですね(^_-)-☆
兼家の謀略がまんまと成功し権力を掌握!
除目も北家をこれ見よがしに配する露骨な取扱いで着々と我が世の春が進行中!
袂を別っていた為時はまひろがどうあがこうが兼家の言う様に官職を得る事は無いのが政治経済の世界!
普段温厚な倫子にたしなめられ、更に注進されても兼家に直談判して政治の現実を知る事でこの世界の駆け引きの難しさをしる事になる!
その為の権力闘争と権謀術数であり、忖度であり贈答や寄付である時代でまひろや為時の様に実直で真面目に生きて行くのは今より辛い!
一条天皇の即位の様子が描かれており高御座や「大鏡」による生首事件等的確に描かれています!
恐いーっ( ;∀;)
倫子サロンでの倫子とまひろ二人の恋バナは、後々を知っている人にとっては、談笑し明るい二人だけに残酷感いっぱい!
宣孝のまひろへの婿取り話とリンクする道長からの妾(しょう)への誘いは純粋に愛する事と正妻(北の方)の扱いへの二人の想いの違いが顕れ哀しくも美しい場面でした!
二人の分岐点となる描写で音楽と映像の妙が表出されていて良かったですね☆
伊周や定子も現れいよいよ一条帝時代!
面白くなってきました!
紀行は晴明…現代も人気ですね(^_-)-☆
第12回「思いの果て」
平安時代の恋愛模様の様子を垣間見、まひろと道長の方向性が決まる回!
紫式部集にも記載のある姉妹の契りを結ぶ女性の登場!
まひろの婿取り話を進める宣孝と実資エピソードが笑いを誘う!
後々奇しくもまひろと道長の大きなバックアップとなる倫子との縁談は倫子のおおらかさと積極性が出ていて面白い!
元々乗り気で無かった父である雅信がその積極性にタジタジで愛娘の縁談を進める気になる場面等良いですね!
しかしまひろが一大決心をし道長に逢いに行って聞いた衝撃の事実は青天の霹靂!
(妾(しょう)の辛さについては道長と道綱の会話で道綱の母の蜻蛉日記の内容が出てきます!)
そのショックも有り結局其々の想いを胸に、互いが決めた道を進む二人!
まひろの言う世の中を創る男に成長する為権謀術数も含め縁談に乗り婿入りする道長!
これから中枢に乗り込んでいく予感!
戻って来たまひろの様子を観ての弟の惟規とさわの声掛けが泣かせる!
片や親族の恨みを晴らす為、積極的に道長との縁談に乗る明子の怨念の深さにブルブル!
この時代の一般的な精神構造を巧く描き、恨みを創った側と恨む側の視点も入れて様々な思惑を描いていて面白いですね!
また呪詛が出て来そう!
いよいよ次回若き一条帝と定子更に彰子も登場!
紀行は庚申の夜 八坂庚申堂
60日に一度来るお腹に生息する虫(三尸虫(さんしちゆう))が悪さをしない様夜明かしする儀式
迷信だらけのこの時代は面白い!
平安時代の恋愛模様の様子を垣間見、まひろと道長の方向性が決まる回!
紫式部集にも記載のある姉妹の契りを結ぶ女性の登場!
まひろの婿取り話を進める宣孝と実資エピソードが笑いを誘う!
後々奇しくもまひろと道長の大きなバックアップとなる倫子との縁談は倫子のおおらかさと積極性が出ていて面白い!
元々乗り気で無かった父である雅信がその積極性にタジタジで愛娘の縁談を進める気になる場面等良いですね!
しかしまひろが一大決心をし道長に逢いに行って聞いた衝撃の事実は青天の霹靂!
(妾(しょう)の辛さについては道長と道綱の会話で道綱の母の蜻蛉日記の内容が出てきます!)
そのショックも有り結局其々の想いを胸に、互いが決めた道を進む二人!
まひろの言う世の中を創る男に成長する為権謀術数も含め縁談に乗り婿入りする道長!
これから中枢に乗り込んでいく予感!
戻って来たまひろの様子を観ての弟の惟規とさわの声掛けが泣かせる!
片や親族の恨みを晴らす為、積極的に道長との縁談に乗る明子の怨念の深さにブルブル!
この時代の一般的な精神構造を巧く描き、恨みを創った側と恨む側の視点も入れて様々な思惑を描いていて面白いですね!
また呪詛が出て来そう!
いよいよ次回若き一条帝と定子更に彰子も登場!
紀行は庚申の夜 八坂庚申堂
60日に一度来るお腹に生息する虫(三尸虫(さんしちゆう))が悪さをしない様夜明かしする儀式
迷信だらけのこの時代は面白い!
我が家には、地デジ化以降、TV受像機がなく、
テレビドラマをまったく見ていませんが、
中公新書ウェブサイト
https://www.chuko.co.jp/shinsho/portal/124610.html
榎村寛之(1959- )
「斎垣の歌」をめぐって
を読んでみました。
「『光る君へ』第6回「二人の才女」で、ついに清少納言が登場したが、
それはそれとして、藤原道長(柄本佑)がまひろ(吉高由里子)に
渡した手紙の
ちはやふる神の斎垣も越えぬべし恋しき人の見まくほしさに
に少し注目したい。
すでにネット上でいわれているように、この歌は『伊勢物語』第71段の
ちはやふる神の斎垣も越えぬべし大宮人の見まくほしさに
の「大宮人」を「恋しき人の」に変えたものである。
このころには定着していた本歌取り(元歌を匂わせて歌のイメージを
重層化させるテクニック。作者の腕の見せ所)とも言えない稚拙な歌だ。
まぁそこが『光る君へ』の道長らしい不器用さか。」
榎村寛之
『謎の平安前期 桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年』
中公新書 2023.12
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2023/12/102783.html
https://www.amazon.co.jp//dp/4121027833
も読んでみたくなりました。
テレビドラマをまったく見ていませんが、
中公新書ウェブサイト
https://www.chuko.co.jp/shinsho/portal/124610.html
榎村寛之(1959- )
「斎垣の歌」をめぐって
を読んでみました。
「『光る君へ』第6回「二人の才女」で、ついに清少納言が登場したが、
それはそれとして、藤原道長(柄本佑)がまひろ(吉高由里子)に
渡した手紙の
ちはやふる神の斎垣も越えぬべし恋しき人の見まくほしさに
に少し注目したい。
すでにネット上でいわれているように、この歌は『伊勢物語』第71段の
ちはやふる神の斎垣も越えぬべし大宮人の見まくほしさに
の「大宮人」を「恋しき人の」に変えたものである。
このころには定着していた本歌取り(元歌を匂わせて歌のイメージを
重層化させるテクニック。作者の腕の見せ所)とも言えない稚拙な歌だ。
まぁそこが『光る君へ』の道長らしい不器用さか。」
榎村寛之
『謎の平安前期 桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年』
中公新書 2023.12
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2023/12/102783.html
https://www.amazon.co.jp//dp/4121027833
も読んでみたくなりました。
第13回「進むべき道」
兼家がいよいよ老害表出!
権勢を誇った権力者の晩年の姿が哀れ!
晴明の狸ぶりが凄い!
兼家の奇行それに伴い兄弟其々の思惑が交差し突き進んでいく!
道隆は定子も入内させ子息伊周も得意満面!
まさか道長と姫彰子がそこに入って来て権力を二分し後々掌握してしまうとは思ってもいないだろう!
評議の場での道長の発言に聞き入って何度も感心する実資の表情が良いですね!
道長の二人の妻との関係も面白い!
明子と兼家との対面場面、残酷でいながら鬼気迫る!(呪詛の材料も手に入れる)
後々道長を支えまくる倫子と道長の関係性も素敵!
老いる親に対する二人の会話は素晴らしい!
だからこそまひろの倫子サロンへの女房就職は理由を付けて断るだろう!
しかし、後々倫子の娘である彰子付女房になるのはどう描いていくのか…これも楽しみですね(^_-)-☆
「枕草子」に出典のある宣孝の御嶽詣での派手な衣装を実際の視覚として観れて面白かったですねー!
今回の大河はこの様に古典の文献内の文章表現を視覚として考証陣が知恵と工夫を凝らして視覚的に表現して下さっているのが大そう楽しみで本当に愉しませていただいています!
味付けが現代風だが史実と創作が絶妙に交差していて今までで一番面白い大河です!
紀行は奈良の三笠山(御蓋山)の藤原氏の氏神を奉った春日大社!
絶頂の藤原氏の国宝級奉納が山盛り!
ここの財である伝義経奉納だが鎌倉末期製作であろう至極の大鎧である国宝赤糸威大鎧(竹虎雀飾)は、昔糸や紐も使うプラモデル(廃版)で一日かけて製作した事があり今も自宅に飾っています!
兼家がいよいよ老害表出!
権勢を誇った権力者の晩年の姿が哀れ!
晴明の狸ぶりが凄い!
兼家の奇行それに伴い兄弟其々の思惑が交差し突き進んでいく!
道隆は定子も入内させ子息伊周も得意満面!
まさか道長と姫彰子がそこに入って来て権力を二分し後々掌握してしまうとは思ってもいないだろう!
評議の場での道長の発言に聞き入って何度も感心する実資の表情が良いですね!
道長の二人の妻との関係も面白い!
明子と兼家との対面場面、残酷でいながら鬼気迫る!(呪詛の材料も手に入れる)
後々道長を支えまくる倫子と道長の関係性も素敵!
老いる親に対する二人の会話は素晴らしい!
だからこそまひろの倫子サロンへの女房就職は理由を付けて断るだろう!
しかし、後々倫子の娘である彰子付女房になるのはどう描いていくのか…これも楽しみですね(^_-)-☆
「枕草子」に出典のある宣孝の御嶽詣での派手な衣装を実際の視覚として観れて面白かったですねー!
今回の大河はこの様に古典の文献内の文章表現を視覚として考証陣が知恵と工夫を凝らして視覚的に表現して下さっているのが大そう楽しみで本当に愉しませていただいています!
味付けが現代風だが史実と創作が絶妙に交差していて今までで一番面白い大河です!
紀行は奈良の三笠山(御蓋山)の藤原氏の氏神を奉った春日大社!
絶頂の藤原氏の国宝級奉納が山盛り!
ここの財である伝義経奉納だが鎌倉末期製作であろう至極の大鎧である国宝赤糸威大鎧(竹虎雀飾)は、昔糸や紐も使うプラモデル(廃版)で一日かけて製作した事があり今も自宅に飾っています!
第14回「星落ちてなお」
兼家が亡くなり道隆の独裁政治が始まる。
子の伊周の得意満面さが鼻をつく・・・
兼家の扇で激しい呪詛を行う明子、その成し終えた時に異変が…
道長の優しい労わりある言葉に恨みに凝り固まっていた明子に変化が起こる。
ここはふと逆の状況であっても葵と光源氏のエピソードを思い起こしました!
喪中でも屋敷に女を集めて酒宴を行う道兼に愛想を尽かし娘と共に去る妻は、髭黒の北の方や夕霧の妻である雲居雁を彷彿とさせるし、今回の大河は時々描き方や登場人物の言動が源氏物語を思い起こさせるギミックが有りマニア心をくすぐってくれますね。
真面目だった道隆が権力の権化になり、挫折して捨て鉢な道兼が後に改心して真面目になろうとしても後にある自然の脅威には二人とも勝てない!
この時代は本当にドラマチック!
道隆の妻高階貴子主催の和歌の会の後、ききょう(清少納言)が自身の近況とこれからの生き方を胸を張って語る姿に現代女性を垣間見る想いがしました。
どちらも宮中に女房として出仕する様になり歴史に残る文学作品を残すわけだが、其々のその過程をどう描くか興味津々です!
今夜の回は道隆の政治に関する考え方と、まひろが文字を教え素直に学ぶ喜びを享受していた少女たねの父親の言葉から、どうしようもないこの時代の貧富の差を知る事になり今生活に困窮しながらも遣り甲斐を見付けて頑張っていたまひろに追い打ちをかける!
この時代の庶民については謎が多いですが、後の後白河院政期の「年中行事絵巻」や「信貴山縁起絵巻」「伴大納言絵巻(詞)」で視覚的に知る事が出来、考証陣も参考にしている事でしょう!
同じ時期にかの国宝「源氏物語絵巻」も創作され平安末期の文化の熟成と文化の享受が知れます!
紀行は道綱の母の蜻蛉日記と宇治
良くウロチョロしている宇治の景観の良さが出ていて又行きたくなりましたね(^_-)-☆
兼家が亡くなり道隆の独裁政治が始まる。
子の伊周の得意満面さが鼻をつく・・・
兼家の扇で激しい呪詛を行う明子、その成し終えた時に異変が…
道長の優しい労わりある言葉に恨みに凝り固まっていた明子に変化が起こる。
ここはふと逆の状況であっても葵と光源氏のエピソードを思い起こしました!
喪中でも屋敷に女を集めて酒宴を行う道兼に愛想を尽かし娘と共に去る妻は、髭黒の北の方や夕霧の妻である雲居雁を彷彿とさせるし、今回の大河は時々描き方や登場人物の言動が源氏物語を思い起こさせるギミックが有りマニア心をくすぐってくれますね。
真面目だった道隆が権力の権化になり、挫折して捨て鉢な道兼が後に改心して真面目になろうとしても後にある自然の脅威には二人とも勝てない!
この時代は本当にドラマチック!
道隆の妻高階貴子主催の和歌の会の後、ききょう(清少納言)が自身の近況とこれからの生き方を胸を張って語る姿に現代女性を垣間見る想いがしました。
どちらも宮中に女房として出仕する様になり歴史に残る文学作品を残すわけだが、其々のその過程をどう描くか興味津々です!
今夜の回は道隆の政治に関する考え方と、まひろが文字を教え素直に学ぶ喜びを享受していた少女たねの父親の言葉から、どうしようもないこの時代の貧富の差を知る事になり今生活に困窮しながらも遣り甲斐を見付けて頑張っていたまひろに追い打ちをかける!
この時代の庶民については謎が多いですが、後の後白河院政期の「年中行事絵巻」や「信貴山縁起絵巻」「伴大納言絵巻(詞)」で視覚的に知る事が出来、考証陣も参考にしている事でしょう!
同じ時期にかの国宝「源氏物語絵巻」も創作され平安末期の文化の熟成と文化の享受が知れます!
紀行は道綱の母の蜻蛉日記と宇治
良くウロチョロしている宇治の景観の良さが出ていて又行きたくなりましたね(^_-)-☆
第15回「おごれる者たち」
権力闘争に敗れた捨て鉢な道兼に道長が掛けた言葉は胸を打ちます!
此の後道兼は真摯な態度で勤めに励む様になって行きますが・・・
出世街道驀進中の伊周と真摯に政務に携わる道長の願い矢勝負は後々の二人の想いと結果を表現していて緊迫感と思いの深さを知れ面白かったですね!
どちらも光源氏のモデルと言われる一人です!
ついに後々一大文化サロンに発展する定子サロンにききょう(清少納言)登壇!
予告を観ると来週は定子と清少納言の有名な漢籍エピソード「香炉峰の雪」がもう描かれるようですね!
石山寺詣は石山寺縁起絵巻に描かれたまんまな、人々の詣での様子や、紫式部が石山寺で月を観て源氏物語の着想を得たと言う伝承をそれとなく描いていて面白かったですね!
道綱の母と偶然出会い蜻蛉日記に書かれた兼家の門エピソードと和歌の話、そして書く事で癒され救われたと言う話を聞く事で、生きがいを見つけられず壁にぶつかっているまひろの心に何かを響かせていました!
後々の源氏物語執筆の開始がどう描かれるか楽しみですね(^_-)-☆
終盤、ついに内裏にも吹き荒れる京に蔓延する疫病の魔の足音が忍び足でやってくる!
紀行はお馴染みの観音信仰石山詣の「石山寺」
平安時代から現代まで様々な紫式部ゆかりの絵画等の奉納が後を絶たず定期的に紫式部展を行っており春季は現在開催中で6/30まで!
権力闘争に敗れた捨て鉢な道兼に道長が掛けた言葉は胸を打ちます!
此の後道兼は真摯な態度で勤めに励む様になって行きますが・・・
出世街道驀進中の伊周と真摯に政務に携わる道長の願い矢勝負は後々の二人の想いと結果を表現していて緊迫感と思いの深さを知れ面白かったですね!
どちらも光源氏のモデルと言われる一人です!
ついに後々一大文化サロンに発展する定子サロンにききょう(清少納言)登壇!
予告を観ると来週は定子と清少納言の有名な漢籍エピソード「香炉峰の雪」がもう描かれるようですね!
石山寺詣は石山寺縁起絵巻に描かれたまんまな、人々の詣での様子や、紫式部が石山寺で月を観て源氏物語の着想を得たと言う伝承をそれとなく描いていて面白かったですね!
道綱の母と偶然出会い蜻蛉日記に書かれた兼家の門エピソードと和歌の話、そして書く事で癒され救われたと言う話を聞く事で、生きがいを見つけられず壁にぶつかっているまひろの心に何かを響かせていました!
後々の源氏物語執筆の開始がどう描かれるか楽しみですね(^_-)-☆
終盤、ついに内裏にも吹き荒れる京に蔓延する疫病の魔の足音が忍び足でやってくる!
紀行はお馴染みの観音信仰石山詣の「石山寺」
平安時代から現代まで様々な紫式部ゆかりの絵画等の奉納が後を絶たず定期的に紫式部展を行っており春季は現在開催中で6/30まで!
第16回「華の影」
定子サロンの華やかさ・・・行成の古今集の写しの美しい事・・・
更にのっけから枕草子漢籍エピソード「香炉峰の雪」を映像化!
その後、一条帝と定子に続き行成らも入っての雪遊びは美しくも長閑な映像!
雪まろばし(雪山づくり・雪遊び)は源氏物語の朝顔巻にも描かれており、朝顔の君に体よく振られその後雪の夜に目覚めて光源氏の読誦「とけて寝ぬねざめさびしき冬の夜に結ぼほれつる夢のみじかさ」をも思い出させます!
ついに刀伊の入寇で有名な大宰府で大活躍した隆家も隆家らしい言動で登場!
伊周の得意満面さは後の下向する運気と共にどんな顔をするのか楽しみでもあります!
内裏の雅やかさとは裏腹に民達は疫病に苦しめられ、まひろの幼い教え子も親子で命の火を消します!
医療現場の厳しさは先のコロナ禍を彷彿とさせ、博識で真摯な一条帝の民を想う思いとはかけ離れた道隆の国民を顧みない専横な独善的政治は、この頃ばかりで無く後々の御代においても様々な疫病や地震水害等の自然災害があろうが平安時代の雅で文化的な宮廷の贅沢を支える為税を搾り取って国民は苦しむ歴史的事実が目の前で繰り広げられる!
(今の世も似たり寄ったり?)
それにしても道隆役の井浦さんの演技は「福田村事件」と全く違った演技で権力に固執していて面白いですね!
道隆の心にある自分や明子以外の女性に想いを馳せる倫子・・・鋭いっ!
ここらへんも将来彰子サロンに出仕するまひろとの絡みがどう映像化されるか楽しみです!
今回の紀行は奈良興福寺と墨、延喜式もチラ見せ。
NHK「美の壺」や「新日本風土記」でも観た油煙墨(ゆえんぼく)の製作工程が少し観れます!
定子サロンの華やかさ・・・行成の古今集の写しの美しい事・・・
更にのっけから枕草子漢籍エピソード「香炉峰の雪」を映像化!
その後、一条帝と定子に続き行成らも入っての雪遊びは美しくも長閑な映像!
雪まろばし(雪山づくり・雪遊び)は源氏物語の朝顔巻にも描かれており、朝顔の君に体よく振られその後雪の夜に目覚めて光源氏の読誦「とけて寝ぬねざめさびしき冬の夜に結ぼほれつる夢のみじかさ」をも思い出させます!
ついに刀伊の入寇で有名な大宰府で大活躍した隆家も隆家らしい言動で登場!
伊周の得意満面さは後の下向する運気と共にどんな顔をするのか楽しみでもあります!
内裏の雅やかさとは裏腹に民達は疫病に苦しめられ、まひろの幼い教え子も親子で命の火を消します!
医療現場の厳しさは先のコロナ禍を彷彿とさせ、博識で真摯な一条帝の民を想う思いとはかけ離れた道隆の国民を顧みない専横な独善的政治は、この頃ばかりで無く後々の御代においても様々な疫病や地震水害等の自然災害があろうが平安時代の雅で文化的な宮廷の贅沢を支える為税を搾り取って国民は苦しむ歴史的事実が目の前で繰り広げられる!
(今の世も似たり寄ったり?)
それにしても道隆役の井浦さんの演技は「福田村事件」と全く違った演技で権力に固執していて面白いですね!
道隆の心にある自分や明子以外の女性に想いを馳せる倫子・・・鋭いっ!
ここらへんも将来彰子サロンに出仕するまひろとの絡みがどう映像化されるか楽しみです!
今回の紀行は奈良興福寺と墨、延喜式もチラ見せ。
NHK「美の壺」や「新日本風土記」でも観た油煙墨(ゆえんぼく)の製作工程が少し観れます!
第17回「うつろい」
酒好きの道隆も前回から症状が現れた「飲水病」=糖尿病には勝てず権力に固執する哀れな姿を見せ一条帝を困惑させる!
詮子の伊周嫌いの政治戦略と定子の伊周推しの政治戦略がぶつかり合う!
両者ともこの時代らしく後々女院として政治の世界に大きな影響を及ぼす!
道長の施策に金銭的援助を厭わない倫子も、この後も同じく大きく道長をバックアップして行きます!
それにしても倫子はいつも勘が鋭く衒いなく道長に聞いてみるところがイイですよね!
それをサラリと凌ぐ道長もしたたかだがやはり倫子の方が上手だろう!
今回も陣定(じんのさだめ)=陣議での実資言いたい事発言し、いい味出していましたね!
今回の紀行は京都祇園祭
平安時代末期に後白河院が作らせた現代で平安時代の習俗や行事を知る上で欠かせない「年中行事絵巻」のその様子を描いた祇園御霊会(祇園祭の元)の部分が紹介されていました!
時代・習俗考証においてこの絵巻の位置は大きいです!
この後出版されるNHK出版の大河ガイドムック後編は5/28発売予定!
完結編はその後・・・。
酒好きの道隆も前回から症状が現れた「飲水病」=糖尿病には勝てず権力に固執する哀れな姿を見せ一条帝を困惑させる!
詮子の伊周嫌いの政治戦略と定子の伊周推しの政治戦略がぶつかり合う!
両者ともこの時代らしく後々女院として政治の世界に大きな影響を及ぼす!
道長の施策に金銭的援助を厭わない倫子も、この後も同じく大きく道長をバックアップして行きます!
それにしても倫子はいつも勘が鋭く衒いなく道長に聞いてみるところがイイですよね!
それをサラリと凌ぐ道長もしたたかだがやはり倫子の方が上手だろう!
今回も陣定(じんのさだめ)=陣議での実資言いたい事発言し、いい味出していましたね!
今回の紀行は京都祇園祭
平安時代末期に後白河院が作らせた現代で平安時代の習俗や行事を知る上で欠かせない「年中行事絵巻」のその様子を描いた祇園御霊会(祇園祭の元)の部分が紹介されていました!
時代・習俗考証においてこの絵巻の位置は大きいです!
この後出版されるNHK出版の大河ガイドムック後編は5/28発売予定!
完結編はその後・・・。
第18回「岐路」
大宰府から戻った宣孝が得意げに話す宋の話を興味津々で聴くまひろはやはり学者肌!
宋の時代の科挙制度もチラっと話題になりまひろもワクワク!
心を改め善政を行おうとした道兼が志半ばで疫病で倒れ亡くなってしまいます!
宮中でも疫病が蔓延し、ここでライバルが伊周だけになり周りの人間が様々な思惑で噂し、意見を述べ、帝に進言する権力闘争が展開!
女院となった藤原詮子の迫力ある事!
まるで源氏物語の弘徽殿女御(太后)そのもの!
ドラマ終盤の想い出の場所であるなにがしの院風の廃邸でのまひろと道長の再会は、これまでの抱き合って再会を喜び合う立場ではない想いと、様々な事を経験し成長して逆に想いをぶつけたくても素直に出せないもどかしさが表現されていて素晴らしい脚本と演出だと思いました!
いよいよ伊周派VS道長派の権力闘争も佳境!
次回はその大きなターニングポイントである長徳の変が起り久々の花山(法)院登場!
紀行は京都石清水八幡宮と粟田口
貴重な栄花物語写本も登場!
道兼と石清水八幡宮や粟田の関りを紹介していて興味深かったですね!
大宰府から戻った宣孝が得意げに話す宋の話を興味津々で聴くまひろはやはり学者肌!
宋の時代の科挙制度もチラっと話題になりまひろもワクワク!
心を改め善政を行おうとした道兼が志半ばで疫病で倒れ亡くなってしまいます!
宮中でも疫病が蔓延し、ここでライバルが伊周だけになり周りの人間が様々な思惑で噂し、意見を述べ、帝に進言する権力闘争が展開!
女院となった藤原詮子の迫力ある事!
まるで源氏物語の弘徽殿女御(太后)そのもの!
ドラマ終盤の想い出の場所であるなにがしの院風の廃邸でのまひろと道長の再会は、これまでの抱き合って再会を喜び合う立場ではない想いと、様々な事を経験し成長して逆に想いをぶつけたくても素直に出せないもどかしさが表現されていて素晴らしい脚本と演出だと思いました!
いよいよ伊周派VS道長派の権力闘争も佳境!
次回はその大きなターニングポイントである長徳の変が起り久々の花山(法)院登場!
紀行は京都石清水八幡宮と粟田口
貴重な栄花物語写本も登場!
道兼と石清水八幡宮や粟田の関りを紹介していて興味深かったですね!
第19回「放たれた矢」
今回はめちゃくちゃ面白かった!
道長が関白職の推挙を辞した事!
一条帝が一目置いた事、陣定(じんのさだめ)での伊周の恥と引き籠り!
前回凄い迫力だった皇太后院詮子の道長の前で素直で可愛い姿はチャーミング!
公任の道長の手腕を立てて文化に勤しむカッコいい意向の表出!
斉信の参議に成れずちょっといじけた顔がお茶目!
行成の書の美しさを活用した女房への文(ふみ)作戦!
御堂関白記の開始!
中納言になって嬉しそうな実資!
道長の妻の一人明子の兄である前蔵人頭(帝の秘書長官)現参議源俊賢の世渡り上手と道長の人使いの巧さ!
元故左大臣の妻院の道長の正妻倫子へのユーモアのある帝王学伝授!
現実は交流の無かったききょう(清少納言)の推挙による定子サロンへの参内と一条帝との対面そして科挙の話題とその関連出典である白居易の新楽府を知っている一条帝!
その参内場面での源氏物語桐壺巻を彷彿とさせる廊下での鋲の嫌がらせと清少納言の堂々たる姿や帝と定子の艶っぽい退出場面を評する清少納言も面白い!
そのまひろ参内と一条帝とのやりとりの話を知った道長の感銘と想い(二人のソウルメイトとしてのつながりを感じる瞬間)!
これはこの先、為時の国司就任先の越前から戻ったまひろが彰子サロンで女房として就き彰子の知的成長に大きく貢献していくと見たのは小生だけでしょうか?
道長の意向による為時の「従五位下に叙す」の勅使の衝撃と赤い束帯の準備!
道長の政治手腕がいかんなく発揮された回でした!
又、その各場面で奏でられる音楽がロック・ジャズ・クラシック等多岐に富んでいて更に場面に合っていて楽しい!
しかしまひろの琵琶は他の曲や弾き方ないのか?
この後、花山法皇を射ると言う長徳の変後、伊周・隆家そして定子の転落が待っている!
やんちゃな隆家はこのままの役で大宰府での刀伊の入寇での活躍を番外編で観たいっ!
紀行は京都陽明文庫の国宝御堂関白記(道長自筆)と滋賀県高島町の巻筆
うーん雅!
今回はめちゃくちゃ面白かった!
道長が関白職の推挙を辞した事!
一条帝が一目置いた事、陣定(じんのさだめ)での伊周の恥と引き籠り!
前回凄い迫力だった皇太后院詮子の道長の前で素直で可愛い姿はチャーミング!
公任の道長の手腕を立てて文化に勤しむカッコいい意向の表出!
斉信の参議に成れずちょっといじけた顔がお茶目!
行成の書の美しさを活用した女房への文(ふみ)作戦!
御堂関白記の開始!
中納言になって嬉しそうな実資!
道長の妻の一人明子の兄である前蔵人頭(帝の秘書長官)現参議源俊賢の世渡り上手と道長の人使いの巧さ!
元故左大臣の妻院の道長の正妻倫子へのユーモアのある帝王学伝授!
現実は交流の無かったききょう(清少納言)の推挙による定子サロンへの参内と一条帝との対面そして科挙の話題とその関連出典である白居易の新楽府を知っている一条帝!
その参内場面での源氏物語桐壺巻を彷彿とさせる廊下での鋲の嫌がらせと清少納言の堂々たる姿や帝と定子の艶っぽい退出場面を評する清少納言も面白い!
そのまひろ参内と一条帝とのやりとりの話を知った道長の感銘と想い(二人のソウルメイトとしてのつながりを感じる瞬間)!
これはこの先、為時の国司就任先の越前から戻ったまひろが彰子サロンで女房として就き彰子の知的成長に大きく貢献していくと見たのは小生だけでしょうか?
道長の意向による為時の「従五位下に叙す」の勅使の衝撃と赤い束帯の準備!
道長の政治手腕がいかんなく発揮された回でした!
又、その各場面で奏でられる音楽がロック・ジャズ・クラシック等多岐に富んでいて更に場面に合っていて楽しい!
しかしまひろの琵琶は他の曲や弾き方ないのか?
この後、花山法皇を射ると言う長徳の変後、伊周・隆家そして定子の転落が待っている!
やんちゃな隆家はこのままの役で大宰府での刀伊の入寇での活躍を番外編で観たいっ!
紀行は京都陽明文庫の国宝御堂関白記(道長自筆)と滋賀県高島町の巻筆
うーん雅!
第20話「望みの先に」
死者も出た長徳の変での今回の童子の頭云々のグロイ話は描かなかったし、それ以前の伊周・隆家と道長の従者の激しい喧嘩等も描かれていないが一条帝の決断采配はお見事!!
更に詮子呪詛事件勃発し倫子大活躍!
検非違使長官実資良い動きしていました!
検非違使の伊周・隆家宅強制捜査もきちんと描いていました!
ドラマの脚本・演出はだいたい史実に基づいたこの実資の小右記を参考にしているものが多く実資の動きにも目が離せません!
為時の淡路守から越前守への鞍替え(レベルアップ)は為時が申文書いたのでなくまひろが書いたとの演出は道長との文の絡みも描きドラマとしてなかなか面白い!
ドラマではついに為時がまひろを呼び道長との関係を問い質す!
実直な為時の鋭い指摘と優しい心遣いが暖かい!
次回ついに清少納言が枕草子執筆開始!
紀行は検非違使の紹介で国宝伴大納言絵詞(絵巻)の部分を表示!
賀茂祭(葵祭)で下賀茂神社・上賀茂神社を紹介!
死者も出た長徳の変での今回の童子の頭云々のグロイ話は描かなかったし、それ以前の伊周・隆家と道長の従者の激しい喧嘩等も描かれていないが一条帝の決断采配はお見事!!
更に詮子呪詛事件勃発し倫子大活躍!
検非違使長官実資良い動きしていました!
検非違使の伊周・隆家宅強制捜査もきちんと描いていました!
ドラマの脚本・演出はだいたい史実に基づいたこの実資の小右記を参考にしているものが多く実資の動きにも目が離せません!
為時の淡路守から越前守への鞍替え(レベルアップ)は為時が申文書いたのでなくまひろが書いたとの演出は道長との文の絡みも描きドラマとしてなかなか面白い!
ドラマではついに為時がまひろを呼び道長との関係を問い質す!
実直な為時の鋭い指摘と優しい心遣いが暖かい!
次回ついに清少納言が枕草子執筆開始!
紀行は検非違使の紹介で国宝伴大納言絵詞(絵巻)の部分を表示!
賀茂祭(葵祭)で下賀茂神社・上賀茂神社を紹介!
第21回「旅立ち」
伊周の悲しい旅立ちと為時の不安と期待が入り混じった旅立ちを描く回!
道長とまひろの新たな転機を描く心の旅立ちでもある・・・。
道隆家の没落を描くが此の後出家した定子は還俗するし、伊周・隆家兄弟も都に戻って来る。
しかし、其々今までとは道が違っていくのもこれからの見どころ!
史実では接点がなかった筈のまひろと清少納言の交流はそれぞれの性格や個性が出ていてなかなか面白い!
まひろの提案で、あの有名な枕草子の冒頭が執筆され、そして春から夏・秋・冬と季節を描きながら四季について筆を走らせる少納言!
落ち込んで起き上がれない傷心の定子の心にほのかな光を与えそれを知る少納言の場面は鳥肌モノですね!
華やかなりし定子サロンの栄華を記録する随筆発現の場面を垣間見る事が出来感動の回でした!
そして久々の何某の院?での道長とまひろの逢瀬・・・。
其々の想いと相手の心を信じる想いが融合し見詰め合う二人は美しかったですね!
さすが恋愛ドラマの名手の脚本!
ついに越前へ
ここに来て、まひろに女性としての魅力を感じ始めている宣孝が面白い!
着任までの都からの旅を琵琶湖の船旅と陸路も描いていて視覚的資料としても抜群!
考証陣に宋人所作指導が入り宋人も現れこれから面白そうな展開です!
真面目過ぎる為時がどんな手腕を発揮するか?
また、まひろの出番?
いろいろと楽しみな越前編です!
紀行は枕草子写本紹介と伏見稲荷神社(小生も稲荷山山頂まで登りました!割とありますよ~!人が多いので早朝がお勧め!)と昔も今も人でいっぱいの清水寺!
伊周の悲しい旅立ちと為時の不安と期待が入り混じった旅立ちを描く回!
道長とまひろの新たな転機を描く心の旅立ちでもある・・・。
道隆家の没落を描くが此の後出家した定子は還俗するし、伊周・隆家兄弟も都に戻って来る。
しかし、其々今までとは道が違っていくのもこれからの見どころ!
史実では接点がなかった筈のまひろと清少納言の交流はそれぞれの性格や個性が出ていてなかなか面白い!
まひろの提案で、あの有名な枕草子の冒頭が執筆され、そして春から夏・秋・冬と季節を描きながら四季について筆を走らせる少納言!
落ち込んで起き上がれない傷心の定子の心にほのかな光を与えそれを知る少納言の場面は鳥肌モノですね!
華やかなりし定子サロンの栄華を記録する随筆発現の場面を垣間見る事が出来感動の回でした!
そして久々の何某の院?での道長とまひろの逢瀬・・・。
其々の想いと相手の心を信じる想いが融合し見詰め合う二人は美しかったですね!
さすが恋愛ドラマの名手の脚本!
ついに越前へ
ここに来て、まひろに女性としての魅力を感じ始めている宣孝が面白い!
着任までの都からの旅を琵琶湖の船旅と陸路も描いていて視覚的資料としても抜群!
考証陣に宋人所作指導が入り宋人も現れこれから面白そうな展開です!
真面目過ぎる為時がどんな手腕を発揮するか?
また、まひろの出番?
いろいろと楽しみな越前編です!
紀行は枕草子写本紹介と伏見稲荷神社(小生も稲荷山山頂まで登りました!割とありますよ~!人が多いので早朝がお勧め!)と昔も今も人でいっぱいの清水寺!
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
源氏物語で盛り上がろう 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-