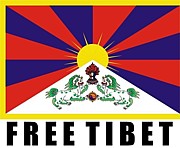中国は常に、そのチベット侵入と占領、チベットにおける弾圧的政策を正当化しようとして、チベットの伝統的社会の姿を最悪に描いてみせてきた。中国は、そのチベット軍事侵攻と占領を、チベット社会の「中世封建時代の農奴」と「奴隷」状態から「解放」したのだとみなしている。
伝統的チベット社会が―同時代のアジア諸国の多くと同じように―後進的で大いに改善の必要があったのは事実である。しかし、伝統的チベット社会を、中世ヨーロッパのような観点から「封建的」と呼ぶのは大きな誤りである。中国の侵入以前のチベットは、実際、当時のほとんどのアジア諸国よりもはるかに平等的だったのである。ヒュー・リチャードソンは、英領インド最後の、またインド独立後初代の代表として通算9年間チベットですごした人物だが、次のように書いた。「共産主義の著者といえども、[1949年以前の]チベットには貧富の大きな格差は存在しなかったということを認めざるをえない」(※12) 同様に、国際法曹委員会の法律調査委員会は、次のように指摘している。「中国の侵入以前はチベット人には人権が保証されていなかったという中国の主張は、チベットの生活の歪曲と誇張に基くものである」(※13)
社会的階級間移動と富の配分の観点から見れば、独立時代のチベットは、当時のアジア諸国の大多数に比較すれば優れていた。中国侵入以前のチベットの政策は、中国がわれわれに信じさせようとするような神政ではなかった。他方において、チベットの政治は、「チョーシ・スンレル(choesi-sungdrel)」、つまり憐れみ、道徳的高潔、平等という仏教教義に基く政治制度と呼ばれる。この制度に従って、政府は高い道徳基準に基づいて、親が子供に対するように、国民に対して愛と憐れみをもって奉仕しなければならない。この統治制度は、すべての感覚ある存在は菩提の種子を持ち、それゆえに尊重されねばならないという信仰に基く。
政治の精神的世俗的な指導者であるダライ・ラマは生まれ変わり探索の制度によって発見され、チベットの支配が世襲にならないよう保証されていた。13世、14世を含む大多数のダライ・ラマは、チベット遠隔地の平民の農民家庭出身だった。
ダライ・ラマ以下の行政職は、同数の僧侶と世俗の役人によって占められていた。世俗役人は世襲で職を得るが、僧侶の職は万人に開かれていた。僧侶役人の多数は非特権階級の出身だった。
さらに、チベットの僧院制度は、社会的階級移動の無制限の機会を提供した。チベットでは、僧院組織への参加は万人に開かれており、大多数の僧侶、特に階級を進んで最高の地位に昇る僧侶は低い身分の出身であり、しばしばカムやアムドの僻遠の村々から来ていた。これは僧院が万人に対して、学識によって僧侶としてのどんな地位にも昇れる平等の機会を与えたからである。よく知られているチベットの金言に次のような言葉がある。「もし母親の息子に知識があれば、ガンデン[チベット仏教のゲルク派の階層制度の最高位]の黄金の座は空いている」
中国のプロパガンダが執拗に「農奴」と呼ぶ農民たちは、法的身分を有したし、しばしば自分たちの権利を明記した文書を所持していたし、また法廷に持ち込むこともできた。農民は、彼らの主人を訴えて、より高い権威に対して裁定を求める権利を持っていたのである。
トゥンドゥプ・チュードゥン(Dhondup Choedon)夫人は独立時代のチベットの社会階層では最貧階級家庭の出身である。中国占領以前の時代の生活を回想して、彼女は次のように書いている。「私は中国人が現在農奴と呼ぶ階級に属しています…私の家族は六人でした…私の家は塀で囲まれた二階建てでした。一階には動物を飼っていました。ヤクが四頭、羊と山羊が27頭、驢馬が2頭おり、4ケル(0.37ヘクタール)半の土地を保有していました…生計を立てるのにまったく苦労しませんでした。私たちの地域に乞食はいませんでした」(※14)
チベットの全歴史を通して、農民を地主が虐待したり抑圧したりすることは、社会習慣ばかりでなく法律によって禁止されていた。7世紀のソンツェン・ガンポ王時代から始まって、多くのチベット支配者たちは、「仏陀の教えの十徳」(十条の道徳律)の仏教教義に基く法典を発布した。この特質は、支配者はその臣下に対して親のように行動しなければならないということである。これがソンツェン・ガンポ王の「16条一般道徳原則」(16条の掟)にも、また、14世紀にパグモ・ドゥパによって発布され、17世紀にダライ・ラマ5世によって改定された手続き及び刑罰の13条の掟にも反映されている。
法によって承認されている刑罰で、過去には手足切断や眼球摘出のような切断刑もあった。そのような刑罰は軽軽しく用いられることはなく、重犯の場合にのみ判決が下された。鞭打ちが主な刑罰だった。19世紀になっても、切断刑を科する力は理論上存在したが、実施されることはほとんど無かった。チベットでは死刑は禁止されていたし、肉体切断刑はラサの中央政府のみが科することができた。1898年にチベットは、国家反逆罪か国家に対する陰謀罪以外はそのような刑罰を廃止する法を制定した。ダライ・ラマ13世は、地主の虐待があった場合には、直接ダライ・ラマに訴える権利を全農民に与える法規を公布した。
すべての土地は国家に属し、国家は、国家に対して功績があった僧院や個人に対して地所を与えた。国家の方は、土地保有者から租税と奉仕を受けた。世俗の土地保有者は、地租を支払うか、または各世代から男性一人を政府役人として働くべく提供した。僧院は国家のために宗教的機能を果たし、またもっとも重要なことは、学校と大学、またチベット芸術や工芸、医術、文化の中心としての役目を果たした。チベットの教育の高度な中心機関としての僧院の役割は、チベットの伝統的な生活様式にとって重要な存在だった。僧院は、学生たちのためにすべての費用を負担し、彼らに無料で食事と宿舎を提供した。広大な地所を所有する僧院もあったし、寄付を投資する僧院もあった。しかしどちらも持たない僧院もあった。それらの僧院は、信者や後援者から個人的な寄付や寄進を受けた。これらの収入では、多数の僧侶の基本的な必要を満たすことがしばしば困難だった。収入を補うために、商売や金融業を行う僧院もあった。
チベットの土地の大多数は農民が所有しており、彼らは租税を直接国家に納めていた。そしてこれが、僧院や軍隊、地所を持たない役人たちに国家が配る食糧債の主要な源になった。ある者は労働で支払い、ある者は政府役人やある場合には僧院のために輸送の便を提供することを求められた。農民所有の土地は世襲相続された。農民はそれを他人に貸したり抵当に入れたりすることができた。農民が土地を取り上げられるのは、物納か労働で租税を支払わない場合に限られ、その負担も過度ではなかった。実際には農民は土地の自由保有権を有し、国へ収める租税は、現金よりむしろ物納で支払う地租の形をとっていた。
チベット人口のうちの少数―ほとんどはウ・ツァンの人々―は小作農だった。彼らは貴族や僧院の地所に土地を持ち、物納か、または家族の一人を召使や農業労働者として送り込むことで地主に地代を払っていた。これら小作農の中には農園の事務員として強力な地位に出世する者もいた。(このために、彼らは中国人から「封建貴族の手先」というレッテルを貼られた。)これら家族の他の者は完全な自由を有していた。彼らはどんな商売に就くこともできたし、どんな仕事でも、またどの僧院に入ることも、自分自身の土地で働くこともできた。彼らは小作農ではあったが、土地所有者の気まぐれで土地を立ち退かせられることはなかった。小作農の中には非常に裕福な者もいた。
ダライ・ラマ13世は、公用で旅行する役人が地方の土地保有農民から無料で輸送の便を要求できる制度を廃止して、馬、騾馬、ヤクの使用料を定めた。ダライ・ラマ十四世はさらに一歩進めて、将来は、政府の特別許可無しで輸送の便を要求することを禁止すると命じた。また、ダライ・ラマは輸送の料金を値上げした。(※15)
チャールズ・ベルや、ヒュー・リチャードソン、ハインリヒ・ハラーのように独立時代のチベットで生活し、働いていた外国人たちは、チベット人平民の平均的生活水準に強い印象を受けた。彼らの言うところによれば、多くのアジア諸国のそれよりも高かったのである。中国の侵入まで、チベットでは、飢饉や飢餓が耳に入ることはなかった。もちろん収穫不足や不作はあった。しかし、人々は地方行政府や僧院、貴族や富裕な農民の保有する緩衝在庫穀物を容易に借りることができた。
ダライ・ラマ14世が成年に達すると、根本的土地改革のための改革委員会を設立したが、中国共産主義者たちは、自分たちが出し抜かれることを恐れて、ダライ・ラマ法王がこの改革計画を実行するのを邪魔した。
1959年、インド亡命後に、ダライ・ラマはインドで政府を再び樹立して、一連の民主化改革に着手した。普通選挙により選出された国民の代表組織である亡命チベット議会(亡命チベット代表者議会)が設立された。1963年に、未来のチベットのための憲法の詳細な原案が公布された。強い反対にもかかわらずダライ・ラマは、国家の最高の利益になると思われる場合にチベット議会は、総議員数の三分の二の多数をもって、最高裁判所(亡命チベット最高司法委員会)との協議を経て、内閣を解任する権限を持つという条項を入れることを主張した。
1990年に、亡命チベット代表者議会(ATPD)の定員を12名から46名に増やすことで、さらなる民主化が行われた。この会議には、カロン(閣僚)選出のようなさらに合憲的権限が付与された。カロンは、以前はダライ・ラマによって直接指名されていたのである。亡命チベット最高司法委員会が、国民の政府に対する苦情に対処するために設立された。
2001年、チベット議会はダライ・ラマの助言のもとに亡命チベット憲法を修正して、亡命チベット人によるカロン・トリパ(内閣主席大臣)直接選挙の規定を設けた。
未来のチベットを見通して、ダライ・ラマは1992年2月に、将来におけるチベットの政治形態の指針と憲法の基本要点を発表したが、その中でダライ・ラマは、自分は「将来のチベット政府で何らかの役割を果たすことを望まない、ダライ・ラマの伝統的な政治的地位を求めないことは言うまでもない」と明確に述べた。ダライ・ラマは、将来のチベット政府は、成人参政権に基いて、国民によって選挙されることになるだろうと語った。
(※12) H.E..リチャードソン著『チベットとその歴史』(『Tibet and its History』)(オックスフォード大学出版 ロンドン 1962)
(※13) 『チベットと中華人民共和国』(『Tibet and the Chinese People's Republic』)チベット法律調査委員会による国際法曹委員会への報告(ジュネーブ 1960)
(※14) トゥンドゥプ・チュードゥン(Dhondup Choedon)著『赤旗人民公社での人生』(『Life int the Red Flag People's Commune』)(中央チベット政府情報局刊、ダラムサラ 1978)
(※15) ダライ・ラマ著『チベットわが祖国』(中公文庫)(My Land and My People)
伝統的チベット社会が―同時代のアジア諸国の多くと同じように―後進的で大いに改善の必要があったのは事実である。しかし、伝統的チベット社会を、中世ヨーロッパのような観点から「封建的」と呼ぶのは大きな誤りである。中国の侵入以前のチベットは、実際、当時のほとんどのアジア諸国よりもはるかに平等的だったのである。ヒュー・リチャードソンは、英領インド最後の、またインド独立後初代の代表として通算9年間チベットですごした人物だが、次のように書いた。「共産主義の著者といえども、[1949年以前の]チベットには貧富の大きな格差は存在しなかったということを認めざるをえない」(※12) 同様に、国際法曹委員会の法律調査委員会は、次のように指摘している。「中国の侵入以前はチベット人には人権が保証されていなかったという中国の主張は、チベットの生活の歪曲と誇張に基くものである」(※13)
社会的階級間移動と富の配分の観点から見れば、独立時代のチベットは、当時のアジア諸国の大多数に比較すれば優れていた。中国侵入以前のチベットの政策は、中国がわれわれに信じさせようとするような神政ではなかった。他方において、チベットの政治は、「チョーシ・スンレル(choesi-sungdrel)」、つまり憐れみ、道徳的高潔、平等という仏教教義に基く政治制度と呼ばれる。この制度に従って、政府は高い道徳基準に基づいて、親が子供に対するように、国民に対して愛と憐れみをもって奉仕しなければならない。この統治制度は、すべての感覚ある存在は菩提の種子を持ち、それゆえに尊重されねばならないという信仰に基く。
政治の精神的世俗的な指導者であるダライ・ラマは生まれ変わり探索の制度によって発見され、チベットの支配が世襲にならないよう保証されていた。13世、14世を含む大多数のダライ・ラマは、チベット遠隔地の平民の農民家庭出身だった。
ダライ・ラマ以下の行政職は、同数の僧侶と世俗の役人によって占められていた。世俗役人は世襲で職を得るが、僧侶の職は万人に開かれていた。僧侶役人の多数は非特権階級の出身だった。
さらに、チベットの僧院制度は、社会的階級移動の無制限の機会を提供した。チベットでは、僧院組織への参加は万人に開かれており、大多数の僧侶、特に階級を進んで最高の地位に昇る僧侶は低い身分の出身であり、しばしばカムやアムドの僻遠の村々から来ていた。これは僧院が万人に対して、学識によって僧侶としてのどんな地位にも昇れる平等の機会を与えたからである。よく知られているチベットの金言に次のような言葉がある。「もし母親の息子に知識があれば、ガンデン[チベット仏教のゲルク派の階層制度の最高位]の黄金の座は空いている」
中国のプロパガンダが執拗に「農奴」と呼ぶ農民たちは、法的身分を有したし、しばしば自分たちの権利を明記した文書を所持していたし、また法廷に持ち込むこともできた。農民は、彼らの主人を訴えて、より高い権威に対して裁定を求める権利を持っていたのである。
トゥンドゥプ・チュードゥン(Dhondup Choedon)夫人は独立時代のチベットの社会階層では最貧階級家庭の出身である。中国占領以前の時代の生活を回想して、彼女は次のように書いている。「私は中国人が現在農奴と呼ぶ階級に属しています…私の家族は六人でした…私の家は塀で囲まれた二階建てでした。一階には動物を飼っていました。ヤクが四頭、羊と山羊が27頭、驢馬が2頭おり、4ケル(0.37ヘクタール)半の土地を保有していました…生計を立てるのにまったく苦労しませんでした。私たちの地域に乞食はいませんでした」(※14)
チベットの全歴史を通して、農民を地主が虐待したり抑圧したりすることは、社会習慣ばかりでなく法律によって禁止されていた。7世紀のソンツェン・ガンポ王時代から始まって、多くのチベット支配者たちは、「仏陀の教えの十徳」(十条の道徳律)の仏教教義に基く法典を発布した。この特質は、支配者はその臣下に対して親のように行動しなければならないということである。これがソンツェン・ガンポ王の「16条一般道徳原則」(16条の掟)にも、また、14世紀にパグモ・ドゥパによって発布され、17世紀にダライ・ラマ5世によって改定された手続き及び刑罰の13条の掟にも反映されている。
法によって承認されている刑罰で、過去には手足切断や眼球摘出のような切断刑もあった。そのような刑罰は軽軽しく用いられることはなく、重犯の場合にのみ判決が下された。鞭打ちが主な刑罰だった。19世紀になっても、切断刑を科する力は理論上存在したが、実施されることはほとんど無かった。チベットでは死刑は禁止されていたし、肉体切断刑はラサの中央政府のみが科することができた。1898年にチベットは、国家反逆罪か国家に対する陰謀罪以外はそのような刑罰を廃止する法を制定した。ダライ・ラマ13世は、地主の虐待があった場合には、直接ダライ・ラマに訴える権利を全農民に与える法規を公布した。
すべての土地は国家に属し、国家は、国家に対して功績があった僧院や個人に対して地所を与えた。国家の方は、土地保有者から租税と奉仕を受けた。世俗の土地保有者は、地租を支払うか、または各世代から男性一人を政府役人として働くべく提供した。僧院は国家のために宗教的機能を果たし、またもっとも重要なことは、学校と大学、またチベット芸術や工芸、医術、文化の中心としての役目を果たした。チベットの教育の高度な中心機関としての僧院の役割は、チベットの伝統的な生活様式にとって重要な存在だった。僧院は、学生たちのためにすべての費用を負担し、彼らに無料で食事と宿舎を提供した。広大な地所を所有する僧院もあったし、寄付を投資する僧院もあった。しかしどちらも持たない僧院もあった。それらの僧院は、信者や後援者から個人的な寄付や寄進を受けた。これらの収入では、多数の僧侶の基本的な必要を満たすことがしばしば困難だった。収入を補うために、商売や金融業を行う僧院もあった。
チベットの土地の大多数は農民が所有しており、彼らは租税を直接国家に納めていた。そしてこれが、僧院や軍隊、地所を持たない役人たちに国家が配る食糧債の主要な源になった。ある者は労働で支払い、ある者は政府役人やある場合には僧院のために輸送の便を提供することを求められた。農民所有の土地は世襲相続された。農民はそれを他人に貸したり抵当に入れたりすることができた。農民が土地を取り上げられるのは、物納か労働で租税を支払わない場合に限られ、その負担も過度ではなかった。実際には農民は土地の自由保有権を有し、国へ収める租税は、現金よりむしろ物納で支払う地租の形をとっていた。
チベット人口のうちの少数―ほとんどはウ・ツァンの人々―は小作農だった。彼らは貴族や僧院の地所に土地を持ち、物納か、または家族の一人を召使や農業労働者として送り込むことで地主に地代を払っていた。これら小作農の中には農園の事務員として強力な地位に出世する者もいた。(このために、彼らは中国人から「封建貴族の手先」というレッテルを貼られた。)これら家族の他の者は完全な自由を有していた。彼らはどんな商売に就くこともできたし、どんな仕事でも、またどの僧院に入ることも、自分自身の土地で働くこともできた。彼らは小作農ではあったが、土地所有者の気まぐれで土地を立ち退かせられることはなかった。小作農の中には非常に裕福な者もいた。
ダライ・ラマ13世は、公用で旅行する役人が地方の土地保有農民から無料で輸送の便を要求できる制度を廃止して、馬、騾馬、ヤクの使用料を定めた。ダライ・ラマ十四世はさらに一歩進めて、将来は、政府の特別許可無しで輸送の便を要求することを禁止すると命じた。また、ダライ・ラマは輸送の料金を値上げした。(※15)
チャールズ・ベルや、ヒュー・リチャードソン、ハインリヒ・ハラーのように独立時代のチベットで生活し、働いていた外国人たちは、チベット人平民の平均的生活水準に強い印象を受けた。彼らの言うところによれば、多くのアジア諸国のそれよりも高かったのである。中国の侵入まで、チベットでは、飢饉や飢餓が耳に入ることはなかった。もちろん収穫不足や不作はあった。しかし、人々は地方行政府や僧院、貴族や富裕な農民の保有する緩衝在庫穀物を容易に借りることができた。
ダライ・ラマ14世が成年に達すると、根本的土地改革のための改革委員会を設立したが、中国共産主義者たちは、自分たちが出し抜かれることを恐れて、ダライ・ラマ法王がこの改革計画を実行するのを邪魔した。
1959年、インド亡命後に、ダライ・ラマはインドで政府を再び樹立して、一連の民主化改革に着手した。普通選挙により選出された国民の代表組織である亡命チベット議会(亡命チベット代表者議会)が設立された。1963年に、未来のチベットのための憲法の詳細な原案が公布された。強い反対にもかかわらずダライ・ラマは、国家の最高の利益になると思われる場合にチベット議会は、総議員数の三分の二の多数をもって、最高裁判所(亡命チベット最高司法委員会)との協議を経て、内閣を解任する権限を持つという条項を入れることを主張した。
1990年に、亡命チベット代表者議会(ATPD)の定員を12名から46名に増やすことで、さらなる民主化が行われた。この会議には、カロン(閣僚)選出のようなさらに合憲的権限が付与された。カロンは、以前はダライ・ラマによって直接指名されていたのである。亡命チベット最高司法委員会が、国民の政府に対する苦情に対処するために設立された。
2001年、チベット議会はダライ・ラマの助言のもとに亡命チベット憲法を修正して、亡命チベット人によるカロン・トリパ(内閣主席大臣)直接選挙の規定を設けた。
未来のチベットを見通して、ダライ・ラマは1992年2月に、将来におけるチベットの政治形態の指針と憲法の基本要点を発表したが、その中でダライ・ラマは、自分は「将来のチベット政府で何らかの役割を果たすことを望まない、ダライ・ラマの伝統的な政治的地位を求めないことは言うまでもない」と明確に述べた。ダライ・ラマは、将来のチベット政府は、成人参政権に基いて、国民によって選挙されることになるだろうと語った。
(※12) H.E..リチャードソン著『チベットとその歴史』(『Tibet and its History』)(オックスフォード大学出版 ロンドン 1962)
(※13) 『チベットと中華人民共和国』(『Tibet and the Chinese People's Republic』)チベット法律調査委員会による国際法曹委員会への報告(ジュネーブ 1960)
(※14) トゥンドゥプ・チュードゥン(Dhondup Choedon)著『赤旗人民公社での人生』(『Life int the Red Flag People's Commune』)(中央チベット政府情報局刊、ダラムサラ 1978)
(※15) ダライ・ラマ著『チベットわが祖国』(中公文庫)(My Land and My People)
|
|
|
|
|
|
|
|
【FREE TIBET】チベット 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
【FREE TIBET】チベットのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82539人
- 2位
- 酒好き
- 170703人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人