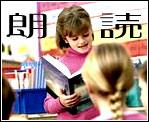|
|
|
|
コメント(5)
私見です。
朗読者はテキストを表現のための「素材」として扱うわけですが、抜粋・構成する場合はそこに抜粋・構成者の「バイアス」が必ずかかります。
朗読者は次のふたつのうちから選択をしなければならないと考えます。
1. できるだけバイアスをかけずにテキスト素材をそのまま扱う(作者の残したことばを尊重する)。
2. バイアスをかけることで別作品として表現する(抜粋・構成者が最終作者となる)。
作者が書きしるしたことばは、一連の「流れ」としてそこにあります。
作者は一本の線上にことばをならべることで、あるイメージを読者に伝えようと意図します。
したがって、ことばひとつ、センテンスひとつ抜いたり、書きくわえても、作者の「作品」ではなくなってしまうと考えます(私も作家のひとりとして)。
しかし、朗読は時間軸にそっておこなわれる表現行為ですから、どうしても時間的制約という「枠」があります。
私の場合、テキストを加工せずにそのまま使う場合には、ある部分をできるだけそっくりそのまま時間枠の制約内で抜きだすようにしています。
もうひとつの方法ですが、少し覚悟がいりますね。
私もよくやりますが。
まず、原テキストを「素材」として割り切ってしまう必要があります。
素材を抜粋・構成しなおすことは、まるで別の作品を作ると考えなければならないでしょう。
自分にあらたな構成者としての明確なコンセプト、表現目標が見えているなら、抜粋・構成もおもしろい作業になるでしょうし、表現対象者にも別作品として伝達することは可能だと思います。
群読作品を構成するときには、私はこの手法をよく使います。
例:現代朗読協会の特別朗読プログラム「Kenji」(抜粋)
⇒ http://jp.youtube.com/watch?v=wKMGBExoZVE
ここでは宮澤賢治の作品そのものを朗読することではなく、賢治のテキストを素材として再構成することで、「私が考える賢治という人そのもののあるイメージ」を中学生たちに伝えたくて、その目的にそって脚本構成しました。
朗読者はテキストを表現のための「素材」として扱うわけですが、抜粋・構成する場合はそこに抜粋・構成者の「バイアス」が必ずかかります。
朗読者は次のふたつのうちから選択をしなければならないと考えます。
1. できるだけバイアスをかけずにテキスト素材をそのまま扱う(作者の残したことばを尊重する)。
2. バイアスをかけることで別作品として表現する(抜粋・構成者が最終作者となる)。
作者が書きしるしたことばは、一連の「流れ」としてそこにあります。
作者は一本の線上にことばをならべることで、あるイメージを読者に伝えようと意図します。
したがって、ことばひとつ、センテンスひとつ抜いたり、書きくわえても、作者の「作品」ではなくなってしまうと考えます(私も作家のひとりとして)。
しかし、朗読は時間軸にそっておこなわれる表現行為ですから、どうしても時間的制約という「枠」があります。
私の場合、テキストを加工せずにそのまま使う場合には、ある部分をできるだけそっくりそのまま時間枠の制約内で抜きだすようにしています。
もうひとつの方法ですが、少し覚悟がいりますね。
私もよくやりますが。
まず、原テキストを「素材」として割り切ってしまう必要があります。
素材を抜粋・構成しなおすことは、まるで別の作品を作ると考えなければならないでしょう。
自分にあらたな構成者としての明確なコンセプト、表現目標が見えているなら、抜粋・構成もおもしろい作業になるでしょうし、表現対象者にも別作品として伝達することは可能だと思います。
群読作品を構成するときには、私はこの手法をよく使います。
例:現代朗読協会の特別朗読プログラム「Kenji」(抜粋)
⇒ http://jp.youtube.com/watch?v=wKMGBExoZVE
ここでは宮澤賢治の作品そのものを朗読することではなく、賢治のテキストを素材として再構成することで、「私が考える賢治という人そのもののあるイメージ」を中学生たちに伝えたくて、その目的にそって脚本構成しました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
朗読者 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-