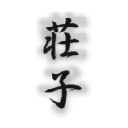━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━秋水篇━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(9)終と始
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯曰 河伯曰く。
然則我何爲乎 然らば則ち我は何をか爲さん。
何不爲乎 何をか爲さざらん。
吾辭受趣舍 吾の辞受趣舎(じじゅしゅしゃ)、
吾終柰何 吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。
北海若曰 北海若曰く。
以道観之 道を以てこれを観れば、
何貴何賤 何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。
是謂反衍 是、反衍(はんえん)と謂う。
无拘而志 拘(かか)わりて志すこと无(な)ければ、
與道大蹇 与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。
何少何多 何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。
是謂謝施 是、謝施(しゃせ)と謂う。
无一而行 一にして行(や)ること无(な)ければ、
與道參差 与(とも)に道と参差(しんし)たらん。
嚴乎若國之有君 厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。
其无私徳 其れ私徳无(な)し。
繇繇乎若祭之有社 繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社が有るが若くあれ。
其无私福 其れ私福无し。
泛泛乎 泛泛乎(はんはんこ)として
其若四方之无窮 其れ四方の窮まりが无きが若くあれ。
其无所畛域 其れ畛域(しんいき)する所无し。
兼懐萬物 万物を兼ねて懐(いだ)け。
其孰承翼 其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)る。
是謂无方 是(これ)无方(むほう)と謂う。
萬物一齊 万物は一にして斉(ひと)しく、
孰短孰長 孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とす。
道无終始 道に終始无し。
物有死生 物に死生有り。
不恃其成 其の成(せい)を恃(たの)まず、
一虚一満 一虚一満する
不位乎其形 其の形に位せず。
年不可擧 年は挙げるべからず。
時不可止 時は止めるべからず。
消息盈虚 消息や盈虚(えいきょ)にて、
終則有始 終われば則ち始まり有り。
是所以語大義之方 是(これ)が大義の方を語り、
論萬物之理也 万物の理を論じた所以(ゆえん)なり。
物之生也 物の生や、
若驟若馳 驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。
无動而不變 動いて変ぜざるは无(な)く
无時而不移 時として移らざるは无し。
何爲乎 何不爲乎 何をか為し、何をか為さざらん、
夫固將自化 夫(そ)れ固(もと)より将(まさ)に自ずと化さんとす。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
河伯はいった、「そうだとすると、私は何をしようか。何をしないでおこうか。自分の動作進退につて、私はいったいどうしたらよかろうか。」
北海若は答えた、「道の立場からみれば、何かを貴(とうと)いものとし何かを賤(しや)しいものとすることはない。この境地を反衍(はんえん/すなわち極まりない変化)という。お前の考えを固定させてはいけない、それでは道のはたらきと衝突することになるだろう。〔道の立場からすると、〕また何かを欠けたものとし何かを十分なものとすることもない。この境地を謝施(しゃた/すなわちとらわれのない随順)という。お前の行動を一定させてはいけない。それでは道のはたらきとそむいて離れることになるだろう。厳然とあたかも国家の君主のようにして、偏(かたよ)った恩恵を施すことがなく、おおらかにあたかも祭の中心の社神(しゃじん)のようにして、偏った福をくだすことがなく、ひろやかにあたかも四方の空間に限りがないようにして、どこにも区域を設けることがなく、万物をへだてなく包容して、特に何かを選んで助けたりはしない。この境地を無法(むほう/すなわち無限定の自由)という。万物は差別のない斉一(せいいつ)なものである。いずれが劣り、いずれがすぐれているということはない。道には終わりも始めもないが、個々の物には死があり生がある。個物としての完成を頼りとするわけにはいかない。あるときは欠(か)けあるときは満ちて、今のままの形で落ち着くことはないのだ。年の移りゆきはとめられないし、時の推移ははばめない。衰えたり栄えたり満ちたり欠けたりして、終わったと思うとまた始まるものである。以上のことがわかってこそ、すぐれた秩序のありかたを語ることができ、もろもろの存在の条理について論ずることができるのだ。物が生まれて存在するのは、ちょうど馬の駆けぬけるようなすばやさである。その動きにつれて変化し、時の流れとともに推移する。『何をしようか、何をしないでおこうか』などというが、そもそもすべてはもともと自然に変化しているのだ。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯は言った。
「それならば則ち、<我(わたし)>は何をしようか。
何をしないでいようか。
<吾(わたし)>の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
<吾(わたし)>は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
北海若は言った。
「道を以てこれを観れば、
何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。
これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。
狭いわくにとらわれて、心が目標を目ざして進み行くことがなければ、
同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
<一>にして(区別する)行為がなくなれば、
同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。
厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。
そこには私的な徳(恩恵)はない。
枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。
そこには私的な福(さいわい)はない。
(海の上で)浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
そこには境界線で区切られた所がない。
万物を一緒にあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。
そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。
これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。
万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
道には<終わり>も<始まり>もない。
物には<死>と<生>がある。
(だが、)そんな既成概念をあてにせず、
ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、
そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。
年の移り変りは(人の手で)動かすことはできない。
時の流れは(人の足で)止めることはできない。
消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、
<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。
これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、万物の道理を論じた理由だ。
物の<生>というのは、
まるで馬がかけるかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。
動くにつれて、変化しないものはなく、
時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。
『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、
それはもともと今将に(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(9)終と始
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯曰 河伯曰く。
然則我何爲乎 然らば則ち我は何をか爲さん。
何不爲乎 何をか爲さざらん。
吾辭受趣舍 吾の辞受趣舎(じじゅしゅしゃ)、
吾終柰何 吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。
北海若曰 北海若曰く。
以道観之 道を以てこれを観れば、
何貴何賤 何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。
是謂反衍 是、反衍(はんえん)と謂う。
无拘而志 拘(かか)わりて志すこと无(な)ければ、
與道大蹇 与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。
何少何多 何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。
是謂謝施 是、謝施(しゃせ)と謂う。
无一而行 一にして行(や)ること无(な)ければ、
與道參差 与(とも)に道と参差(しんし)たらん。
嚴乎若國之有君 厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。
其无私徳 其れ私徳无(な)し。
繇繇乎若祭之有社 繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社が有るが若くあれ。
其无私福 其れ私福无し。
泛泛乎 泛泛乎(はんはんこ)として
其若四方之无窮 其れ四方の窮まりが无きが若くあれ。
其无所畛域 其れ畛域(しんいき)する所无し。
兼懐萬物 万物を兼ねて懐(いだ)け。
其孰承翼 其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)る。
是謂无方 是(これ)无方(むほう)と謂う。
萬物一齊 万物は一にして斉(ひと)しく、
孰短孰長 孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とす。
道无終始 道に終始无し。
物有死生 物に死生有り。
不恃其成 其の成(せい)を恃(たの)まず、
一虚一満 一虚一満する
不位乎其形 其の形に位せず。
年不可擧 年は挙げるべからず。
時不可止 時は止めるべからず。
消息盈虚 消息や盈虚(えいきょ)にて、
終則有始 終われば則ち始まり有り。
是所以語大義之方 是(これ)が大義の方を語り、
論萬物之理也 万物の理を論じた所以(ゆえん)なり。
物之生也 物の生や、
若驟若馳 驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。
无動而不變 動いて変ぜざるは无(な)く
无時而不移 時として移らざるは无し。
何爲乎 何不爲乎 何をか為し、何をか為さざらん、
夫固將自化 夫(そ)れ固(もと)より将(まさ)に自ずと化さんとす。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
河伯はいった、「そうだとすると、私は何をしようか。何をしないでおこうか。自分の動作進退につて、私はいったいどうしたらよかろうか。」
北海若は答えた、「道の立場からみれば、何かを貴(とうと)いものとし何かを賤(しや)しいものとすることはない。この境地を反衍(はんえん/すなわち極まりない変化)という。お前の考えを固定させてはいけない、それでは道のはたらきと衝突することになるだろう。〔道の立場からすると、〕また何かを欠けたものとし何かを十分なものとすることもない。この境地を謝施(しゃた/すなわちとらわれのない随順)という。お前の行動を一定させてはいけない。それでは道のはたらきとそむいて離れることになるだろう。厳然とあたかも国家の君主のようにして、偏(かたよ)った恩恵を施すことがなく、おおらかにあたかも祭の中心の社神(しゃじん)のようにして、偏った福をくだすことがなく、ひろやかにあたかも四方の空間に限りがないようにして、どこにも区域を設けることがなく、万物をへだてなく包容して、特に何かを選んで助けたりはしない。この境地を無法(むほう/すなわち無限定の自由)という。万物は差別のない斉一(せいいつ)なものである。いずれが劣り、いずれがすぐれているということはない。道には終わりも始めもないが、個々の物には死があり生がある。個物としての完成を頼りとするわけにはいかない。あるときは欠(か)けあるときは満ちて、今のままの形で落ち着くことはないのだ。年の移りゆきはとめられないし、時の推移ははばめない。衰えたり栄えたり満ちたり欠けたりして、終わったと思うとまた始まるものである。以上のことがわかってこそ、すぐれた秩序のありかたを語ることができ、もろもろの存在の条理について論ずることができるのだ。物が生まれて存在するのは、ちょうど馬の駆けぬけるようなすばやさである。その動きにつれて変化し、時の流れとともに推移する。『何をしようか、何をしないでおこうか』などというが、そもそもすべてはもともと自然に変化しているのだ。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯は言った。
「それならば則ち、<我(わたし)>は何をしようか。
何をしないでいようか。
<吾(わたし)>の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
<吾(わたし)>は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
北海若は言った。
「道を以てこれを観れば、
何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。
これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。
狭いわくにとらわれて、心が目標を目ざして進み行くことがなければ、
同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
<一>にして(区別する)行為がなくなれば、
同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。
厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。
そこには私的な徳(恩恵)はない。
枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。
そこには私的な福(さいわい)はない。
(海の上で)浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
そこには境界線で区切られた所がない。
万物を一緒にあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。
そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。
これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。
万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
道には<終わり>も<始まり>もない。
物には<死>と<生>がある。
(だが、)そんな既成概念をあてにせず、
ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、
そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。
年の移り変りは(人の手で)動かすことはできない。
時の流れは(人の足で)止めることはできない。
消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、
<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。
これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、万物の道理を論じた理由だ。
物の<生>というのは、
まるで馬がかけるかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。
動くにつれて、変化しないものはなく、
時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。
『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、
それはもともと今将に(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(27)
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 河伯曰 ┃【河伯曰く。】
┃ 然則我何爲乎 ┃【然らば則ち我は何をか爲さん。】
┃ 何不爲乎 ┃【何をか爲さざらん。】
┃ 吾辭受趣舍 ┃【吾の辞受趣舎(じじゅしゅしゃ)、】
┃ 吾終柰何 ┃【吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。】
┗━━━━━━━━━┛
河伯は言った。
「それならば則ち、<我(わたし)>は何をしようか。
何をしないでいようか。
<吾(わたし)>の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
<吾(わたし)>は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【辭(辞)】は、もとの字は、「[左側の字](乱れた糸をさばく)+「辛(罪人に入れ墨をす
る刃物)」で「法廷で罪を論じて、みだれをさばくそのことば」をあらわします。「ことわ
る(いいわけをする。いいわけをのべて、受けとらない。)」
*【受】は、「爪(て)+又(て)+舟(音符)」で「Aの手からBの手に落とさないように
渡し、失わないようにうけとるさま」を示します。
*【趣】は、「走(はしる)+取(ぐっと指をちぢめてつかむこと)」で、「時間をちぢめてせ
かせかといくこと。」「おもむく(足ばやにいく。さっさとある方向へ向かう。)」
*【舎】は、「やどる・やどす(からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。)」
「おく・すてる(手をゆるめてはなしておく。すておく。はなす。)」
*【趣舎】は「進むこと、とまること。」「とること、すてること。」
*【柰(奈)何】は、手段・方法を尋ねるときのことば。「どうしたらよいか。」
◆通説では、【河伯曰く、然らば則ち我は何をか爲さん。何をか爲さざらん。吾が辞受趣舎
(じじゅしゅしゃ)、吾れ終(つい)に奈何(いかん)せん。】は〔河伯はいった、「そうだ
とすると、私は何をしようか。何をしないでおこうか。自分の動作進退につて、私はい
ったいどうしたらよかろうか。」〕としています。
◇【我】と【吾】とを使い分けて質問しているようです。
【河伯曰く。然らば則ち我は何をか爲さん。何をか爲さざらん。吾の辞受趣舎(じじゅ
しゅしゃ)、吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。】は〔河伯は言った。「それならば則
ち、<我(わたし)>は何をしようか。何をしないでいようか。<吾(わたし)>の辞し
たり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、<吾(わたし)>は最終的にどうとっ
たらよいのだろうか。」〕としました。
┃▼ 河伯曰 ┃【河伯曰く。】
┃ 然則我何爲乎 ┃【然らば則ち我は何をか爲さん。】
┃ 何不爲乎 ┃【何をか爲さざらん。】
┃ 吾辭受趣舍 ┃【吾の辞受趣舎(じじゅしゅしゃ)、】
┃ 吾終柰何 ┃【吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。】
┗━━━━━━━━━┛
河伯は言った。
「それならば則ち、<我(わたし)>は何をしようか。
何をしないでいようか。
<吾(わたし)>の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
<吾(わたし)>は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【辭(辞)】は、もとの字は、「[左側の字](乱れた糸をさばく)+「辛(罪人に入れ墨をす
る刃物)」で「法廷で罪を論じて、みだれをさばくそのことば」をあらわします。「ことわ
る(いいわけをする。いいわけをのべて、受けとらない。)」
*【受】は、「爪(て)+又(て)+舟(音符)」で「Aの手からBの手に落とさないように
渡し、失わないようにうけとるさま」を示します。
*【趣】は、「走(はしる)+取(ぐっと指をちぢめてつかむこと)」で、「時間をちぢめてせ
かせかといくこと。」「おもむく(足ばやにいく。さっさとある方向へ向かう。)」
*【舎】は、「やどる・やどす(からだをのばしてくつろぐ。やどをとって休む。)」
「おく・すてる(手をゆるめてはなしておく。すておく。はなす。)」
*【趣舎】は「進むこと、とまること。」「とること、すてること。」
*【柰(奈)何】は、手段・方法を尋ねるときのことば。「どうしたらよいか。」
◆通説では、【河伯曰く、然らば則ち我は何をか爲さん。何をか爲さざらん。吾が辞受趣舎
(じじゅしゅしゃ)、吾れ終(つい)に奈何(いかん)せん。】は〔河伯はいった、「そうだ
とすると、私は何をしようか。何をしないでおこうか。自分の動作進退につて、私はい
ったいどうしたらよかろうか。」〕としています。
◇【我】と【吾】とを使い分けて質問しているようです。
【河伯曰く。然らば則ち我は何をか爲さん。何をか爲さざらん。吾の辞受趣舎(じじゅ
しゅしゃ)、吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。】は〔河伯は言った。「それならば則
ち、<我(わたし)>は何をしようか。何をしないでいようか。<吾(わたし)>の辞し
たり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、<吾(わたし)>は最終的にどうとっ
たらよいのだろうか。」〕としました。
●通説では、次のようになっています。
河伯はいった、「そうだとすると、私は何をしようか。何をしないでおこうか。自分の動作進退につて、私はいったいどうしたらよかろうか。」
〇新解釈では、次のようになります。
河伯は言った。
「それならば則ち、<我(わたし)>は何をしようか。
何をしないでいようか。
<吾(わたし)>の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
<吾(わたし)>は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
【河伯曰】【河伯曰く。】
【然則我何爲乎】【然らば則ち我は何をか爲さん。】
【何不爲乎】【何をか爲さざらん。】
〔河伯は言った。「それならば則ち、<我>は何をしようか。何をしないでいようか。〕
──<我(わたし)>にできることは「言動」です。「然らば(それならば)」とは、「黙っているがいいと言うならば」ということなので、「言」は控えよと言われたととらえ、では「どういう行動をとればいいのか」と「動」について問いなおしたのでしょう。つまり、自分も是非「貴賤の門、大小の家を知ること」に至りたいと願ってのことでしょう。
【吾辭受趣舍】【吾の辞受趣舎(じじゅしゅしゃ)、】
【吾終柰何】【吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。】
私の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
私は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
──北海若の言葉と接する上で、総括的な<吾(わたし)>の態度をどうとったらいいのか、迷っているようです。北海若のことば(進言)を辞すべきか、受け入れるべきか、また河伯自身の知への探求をさらに進めるべきなのか、止めるべきなのか、最終的に<吾(わたし)>のとるべき態度をどう決めたらいいのかわからず質問をしたのでしょう。
河伯はいった、「そうだとすると、私は何をしようか。何をしないでおこうか。自分の動作進退につて、私はいったいどうしたらよかろうか。」
〇新解釈では、次のようになります。
河伯は言った。
「それならば則ち、<我(わたし)>は何をしようか。
何をしないでいようか。
<吾(わたし)>の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
<吾(わたし)>は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
【河伯曰】【河伯曰く。】
【然則我何爲乎】【然らば則ち我は何をか爲さん。】
【何不爲乎】【何をか爲さざらん。】
〔河伯は言った。「それならば則ち、<我>は何をしようか。何をしないでいようか。〕
──<我(わたし)>にできることは「言動」です。「然らば(それならば)」とは、「黙っているがいいと言うならば」ということなので、「言」は控えよと言われたととらえ、では「どういう行動をとればいいのか」と「動」について問いなおしたのでしょう。つまり、自分も是非「貴賤の門、大小の家を知ること」に至りたいと願ってのことでしょう。
【吾辭受趣舍】【吾の辞受趣舎(じじゅしゅしゃ)、】
【吾終柰何】【吾は終(つい)に奈何(いかん)せん。】
私の辞したり受けとったり、進めたり止めたりする態度を、
私は最終的にどうとったらよいのだろうか。」
──北海若の言葉と接する上で、総括的な<吾(わたし)>の態度をどうとったらいいのか、迷っているようです。北海若のことば(進言)を辞すべきか、受け入れるべきか、また河伯自身の知への探求をさらに進めるべきなのか、止めるべきなのか、最終的に<吾(わたし)>のとるべき態度をどう決めたらいいのかわからず質問をしたのでしょう。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 以道観之 ┃【道を以てこれを観れば、】
┃ 何貴何賤 ┃【何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。】
┃ 是謂反衍 ┃【是、反衍(はんえん)と謂う。】
┗━━━━━━━┛
北海若は言った。
「道を以てこれを観れば、
何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。
これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。
…………………………………………………………………………………………………………
*【何】は、「なに。」(疑問)「なにの・なんの。」「なんぞ (どうして)。」「いずれ・い
ずこ(どこ)。」(疑問)「なんぞ (どうしてそんなことがあろうか、ない。)」(反語)
*【反】は、「厂+又(て)」で、「布または薄い板を手で押して、そらせた姿。そったも
のはもとにかえり、また、薄い布や板はひらひらとひるがえるところから、かえる・ひ
るがえる」の意となったもの。
*【衍】は、「水+行」で、「水が長く横にのびるさま。」「のばす・のびる(のばし広げ
る。しきのばす。のび広がる。はびこる。)」
◆通説では、【北海若曰く、道を以てこれを観れば、何をか貴び何をか賤しまん。是を反
衍(はんえん)と謂う。】は〔北海若は答えた、「道の立場からみれば、何かを貴(とう
と)いものとし何かを賤(しや)しいものとすることはない。この境地を反衍(はんえん/
すなわち極まりない変化)という。〕としています。
◇【北海若曰く。道を以てこれを観れば、何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。是、反衍
(はんえん)と謂う。】は〔北海若は言った。「道を以てこれを観れば、何が<貴>であ
ろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。これを反衍(はんえん/反転
の広がり)という。〕としました。
┃▼ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 以道観之 ┃【道を以てこれを観れば、】
┃ 何貴何賤 ┃【何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。】
┃ 是謂反衍 ┃【是、反衍(はんえん)と謂う。】
┗━━━━━━━┛
北海若は言った。
「道を以てこれを観れば、
何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。
これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。
…………………………………………………………………………………………………………
*【何】は、「なに。」(疑問)「なにの・なんの。」「なんぞ (どうして)。」「いずれ・い
ずこ(どこ)。」(疑問)「なんぞ (どうしてそんなことがあろうか、ない。)」(反語)
*【反】は、「厂+又(て)」で、「布または薄い板を手で押して、そらせた姿。そったも
のはもとにかえり、また、薄い布や板はひらひらとひるがえるところから、かえる・ひ
るがえる」の意となったもの。
*【衍】は、「水+行」で、「水が長く横にのびるさま。」「のばす・のびる(のばし広げ
る。しきのばす。のび広がる。はびこる。)」
◆通説では、【北海若曰く、道を以てこれを観れば、何をか貴び何をか賤しまん。是を反
衍(はんえん)と謂う。】は〔北海若は答えた、「道の立場からみれば、何かを貴(とう
と)いものとし何かを賤(しや)しいものとすることはない。この境地を反衍(はんえん/
すなわち極まりない変化)という。〕としています。
◇【北海若曰く。道を以てこれを観れば、何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。是、反衍
(はんえん)と謂う。】は〔北海若は言った。「道を以てこれを観れば、何が<貴>であ
ろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。これを反衍(はんえん/反転
の広がり)という。〕としました。
●通説では、次のようになっています。
北海若は答えた、「道の立場からみれば、何かを貴(とうと)いものとし何かを賤(しや)しいものとすることはない。この境地を反衍(はんえん/すなわち極まりない変化)という。
〇新解釈では、次のようになります。
北海若は言った。
「道を以てこれを観れば、
何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。
これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【以道観之】【道を以てこれを観れば、】
【何貴何賤】【何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。】
〔北海若は言った。〕
〔「道を以てこれを観れば、〕
〔何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。〕
──北海若は「<貴賤>の門」のからくりについて説明しているものだと見なしました。最終的には、(7)で「道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。」と語っていたように、道にそった生き方ができれば「<貴賤>の区別はない」という境地に至ることでしょう。ところが、まだ道を体得する過程としては、最初は何らかのものを見定める時、あるものを<貴>とし、そうでないものを<賤>と判断することもあるのではないかと思われます。そこには「門」が仮にできるのです。ところが、そのあるものを別の角度、別の視点から見たならば、また違う「門」が仮にできるのです。<貴>だと思っていたものがそうではなく見え、同時に<賤>だと思っていたものが、そうではないと思えるということが起こり、別のものが<貴>とし、それに対するものが<賤>とする判断が起きているという見方が、次から次へと変わって起こるのだ…と言っているのではないでしょうか。つまり物の世界での「<貴賤>の門」は存在していても、ここだという視点が一定しているのではなく、いろんなところ、どんなところにでも門を立てることができるものの、それはすべて暫定的なものだということになる…と言っているようです。そうなると絶対的なものとしての「門」は存在しないに等しくなり、それと同時に、最終的に<貴賤>の区別はないという境地にはじめて至ることができるのだ…と言っているのではないでしょうか。
【是謂反衍】【是、反衍(はんえん)と謂う。】
〔これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。〕
──例えば、植物の中で食用と毒草という区分けが起き、食用は<貴>、毒草は<賤>だと判断することがあります。しかしこれは絶対的なものではありません。毒草から有用な薬が作られたり、食用も処理法や多飲で害になることがありますが、そうなると<貴>と<賤>の線引きはその立場が逆転することがあるのです。同様に、自分の中の喜怒哀楽の内、喜楽は<貴>、怒哀は<賤>という絶対的な線引きはできません。怒哀が<貴>、喜楽が<賤>になることだってあるからです。
このように<貴>だったものがひるがえって<賤>になったり、<賤>だったものがひるがえって<貴>になったりすることを「反衍(はんえん/反転のひろがり)」と呼ぶことができる…と言っているのではないでしょうか。
北海若は答えた、「道の立場からみれば、何かを貴(とうと)いものとし何かを賤(しや)しいものとすることはない。この境地を反衍(はんえん/すなわち極まりない変化)という。
〇新解釈では、次のようになります。
北海若は言った。
「道を以てこれを観れば、
何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。
これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【以道観之】【道を以てこれを観れば、】
【何貴何賤】【何ぞ貴とせんや、何ぞ賤とせんや。】
〔北海若は言った。〕
〔「道を以てこれを観れば、〕
〔何が<貴>であろうか、何が<賤>であろうか、わかったものではない。〕
──北海若は「<貴賤>の門」のからくりについて説明しているものだと見なしました。最終的には、(7)で「道を以てこれを観れば、物に貴賤なし。」と語っていたように、道にそった生き方ができれば「<貴賤>の区別はない」という境地に至ることでしょう。ところが、まだ道を体得する過程としては、最初は何らかのものを見定める時、あるものを<貴>とし、そうでないものを<賤>と判断することもあるのではないかと思われます。そこには「門」が仮にできるのです。ところが、そのあるものを別の角度、別の視点から見たならば、また違う「門」が仮にできるのです。<貴>だと思っていたものがそうではなく見え、同時に<賤>だと思っていたものが、そうではないと思えるということが起こり、別のものが<貴>とし、それに対するものが<賤>とする判断が起きているという見方が、次から次へと変わって起こるのだ…と言っているのではないでしょうか。つまり物の世界での「<貴賤>の門」は存在していても、ここだという視点が一定しているのではなく、いろんなところ、どんなところにでも門を立てることができるものの、それはすべて暫定的なものだということになる…と言っているようです。そうなると絶対的なものとしての「門」は存在しないに等しくなり、それと同時に、最終的に<貴賤>の区別はないという境地にはじめて至ることができるのだ…と言っているのではないでしょうか。
【是謂反衍】【是、反衍(はんえん)と謂う。】
〔これを反衍(はんえん/反転の広がり)という。〕
──例えば、植物の中で食用と毒草という区分けが起き、食用は<貴>、毒草は<賤>だと判断することがあります。しかしこれは絶対的なものではありません。毒草から有用な薬が作られたり、食用も処理法や多飲で害になることがありますが、そうなると<貴>と<賤>の線引きはその立場が逆転することがあるのです。同様に、自分の中の喜怒哀楽の内、喜楽は<貴>、怒哀は<賤>という絶対的な線引きはできません。怒哀が<貴>、喜楽が<賤>になることだってあるからです。
このように<貴>だったものがひるがえって<賤>になったり、<賤>だったものがひるがえって<貴>になったりすることを「反衍(はんえん/反転のひろがり)」と呼ぶことができる…と言っているのではないでしょうか。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 无拘而志 ┃【拘(とら)われて志すこと无(な)ければ、】
┃ 與道大蹇 ┃【与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。】
┗━━━━━━━┛
狭いわくにとらわれて、そして心が目標を目ざして進み行くことがなければ、
同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【拘】は、「手+句(狭いかぎ型のわくに包まれること) 。」で「せまいわくの中に押し
込めること。」「とらえる(せまいわく内にとらえて自由にさせないこと)。」「かかわ
る・とらわれる(せまいわくに縛られる) 。」
*【志】は、「心+士(之)」で、「心が目標を目ざして進み行くこと。」
*【與(与)】は、「ともに(いっしょに)。」
*【蹇】は、「足+寒(かわいてかたい、つっかかる、つかえるの略体)」で、「とどこお
る。」「すらすら進まない。」「動きがわるい。」
◆通説では【而】を「なんじ」としています。【與(与)】を読まず、無視しています。
【而(なんじ)の志を拘(束/しば)ることなかれ、道と大いに蹇(たが)わん。】は「お
前の考えを固定させてはいけない、それでは道のはたらきと衝突することになるだろ
う。」としています。
◇新解釈では、「而」は「なんじ」とはせず、あくまでも接続詞として解釈しました。
【拘(とら)われて志すこと无(な)ければ、与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。】は
「狭いわくにとらわれて、そして心が目標を目ざして進み行くことがなければ、同時
に、道に大きく突っかかることになるだろう。」としました。
┃▼ 无拘而志 ┃【拘(とら)われて志すこと无(な)ければ、】
┃ 與道大蹇 ┃【与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。】
┗━━━━━━━┛
狭いわくにとらわれて、そして心が目標を目ざして進み行くことがなければ、
同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【拘】は、「手+句(狭いかぎ型のわくに包まれること) 。」で「せまいわくの中に押し
込めること。」「とらえる(せまいわく内にとらえて自由にさせないこと)。」「かかわ
る・とらわれる(せまいわくに縛られる) 。」
*【志】は、「心+士(之)」で、「心が目標を目ざして進み行くこと。」
*【與(与)】は、「ともに(いっしょに)。」
*【蹇】は、「足+寒(かわいてかたい、つっかかる、つかえるの略体)」で、「とどこお
る。」「すらすら進まない。」「動きがわるい。」
◆通説では【而】を「なんじ」としています。【與(与)】を読まず、無視しています。
【而(なんじ)の志を拘(束/しば)ることなかれ、道と大いに蹇(たが)わん。】は「お
前の考えを固定させてはいけない、それでは道のはたらきと衝突することになるだろ
う。」としています。
◇新解釈では、「而」は「なんじ」とはせず、あくまでも接続詞として解釈しました。
【拘(とら)われて志すこと无(な)ければ、与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。】は
「狭いわくにとらわれて、そして心が目標を目ざして進み行くことがなければ、同時
に、道に大きく突っかかることになるだろう。」としました。
●通説では、次のようになっています。
お前の考えを固定させてはいけない、それでは道のはたらきと衝突することになるだろう。
〇新解釈では、次のようになります。
狭いわくにとらわれて、そして、心が目標を目ざして進み行くことがなければ、
同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。
【无拘而志】【拘(とら)われて、志すこと无(な)ければ、】
〔狭いわくにとらわれて、心が目標を目ざして進み行くことがなければ、〕
──私たちは、例えば<貴>とするものや<多>とするものは大事なものとして大切にします。そして、<賤>とするものや<少>とするものとは遠ざけようとしてないがしろにしてしまっているようです。そうすることは狭い枠にとらわれていることになるのです。そして、志(こころざし)、つまり自然にしていたら自由にめざして進もうとする心の目標があるにもかかわらず、そこに向おうとはしないことが起きてしまったならば、どうなるでしょうか。
【與道大蹇】【与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。】
〔同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。〕
──狭いわくにとらわれ、内なる声、心の目標に向かって志すことがなければ、それは同時に自由な心の動きにそってスムーズに進むことができずに、それこそ「道」に大きく突っかかることになるだろう…と言っています。
お前の考えを固定させてはいけない、それでは道のはたらきと衝突することになるだろう。
〇新解釈では、次のようになります。
狭いわくにとらわれて、そして、心が目標を目ざして進み行くことがなければ、
同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。
【无拘而志】【拘(とら)われて、志すこと无(な)ければ、】
〔狭いわくにとらわれて、心が目標を目ざして進み行くことがなければ、〕
──私たちは、例えば<貴>とするものや<多>とするものは大事なものとして大切にします。そして、<賤>とするものや<少>とするものとは遠ざけようとしてないがしろにしてしまっているようです。そうすることは狭い枠にとらわれていることになるのです。そして、志(こころざし)、つまり自然にしていたら自由にめざして進もうとする心の目標があるにもかかわらず、そこに向おうとはしないことが起きてしまったならば、どうなるでしょうか。
【與道大蹇】【与(とも)に道に大蹇(だいけん)たらん。】
〔同時に、道に大きく突っかかることになるだろう。〕
──狭いわくにとらわれ、内なる声、心の目標に向かって志すことがなければ、それは同時に自由な心の動きにそってスムーズに進むことができずに、それこそ「道」に大きく突っかかることになるだろう…と言っています。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 何少何多 ┃【何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。】
┃ 是謂謝施 ┃【是、謝施(しゃせ)と謂う。】
┗━━━━━━━┛
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謝】は、「言+射(はりつめた矢を手から離しているさま。矢をいれば、弓の緊張がと
けてゆるむ。)」で、「ことばにあらわすことによって、負担や緊張をといて気楽になる
こと。」「あやまる。」「ことわる。」「つげる(ことばを飾っていう。)」「勢いがぬけ
てさる。」「お礼またはおわびの気持ち。」
*【施】は、「[左と上の字](はた)+也(長いヘビ)」で、「吹き流しが長くのびるこ
と。」「ほどこす(手前の物を向こうへ押しやる。)」「平らにのばす。」「ほどこす
(技を展開する。計画を実際に行う。)」「のびる・のばす・うつる(長くのびる。のびて
うつっていく。)」
◆通説では、【謝施】を「しゃた/秊蛇」として意訳しています。【何をか少とし、何をか
多とせん。是れ謝施(しゃた/秊蛇)と謂う。】は、「〔道の立場からすると、〕また何か
を欠けたものとし何かを十分なものとすることもない。この境地を謝施(しゃた/すなわち
とらわれのない随順)という。」としています。
◇新解釈では、【謝施(しゃせ)】とはどういう意味か、少々難解ですが、あくまでも字源に
そって解釈しました。【何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。是、謝施(しゃせ)と謂う。】
は、「何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。これを謝
施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。」としました。
┃▼ 何少何多 ┃【何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。】
┃ 是謂謝施 ┃【是、謝施(しゃせ)と謂う。】
┗━━━━━━━┛
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謝】は、「言+射(はりつめた矢を手から離しているさま。矢をいれば、弓の緊張がと
けてゆるむ。)」で、「ことばにあらわすことによって、負担や緊張をといて気楽になる
こと。」「あやまる。」「ことわる。」「つげる(ことばを飾っていう。)」「勢いがぬけ
てさる。」「お礼またはおわびの気持ち。」
*【施】は、「[左と上の字](はた)+也(長いヘビ)」で、「吹き流しが長くのびるこ
と。」「ほどこす(手前の物を向こうへ押しやる。)」「平らにのばす。」「ほどこす
(技を展開する。計画を実際に行う。)」「のびる・のばす・うつる(長くのびる。のびて
うつっていく。)」
◆通説では、【謝施】を「しゃた/秊蛇」として意訳しています。【何をか少とし、何をか
多とせん。是れ謝施(しゃた/秊蛇)と謂う。】は、「〔道の立場からすると、〕また何か
を欠けたものとし何かを十分なものとすることもない。この境地を謝施(しゃた/すなわち
とらわれのない随順)という。」としています。
◇新解釈では、【謝施(しゃせ)】とはどういう意味か、少々難解ですが、あくまでも字源に
そって解釈しました。【何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。是、謝施(しゃせ)と謂う。】
は、「何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。これを謝
施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。」としました。
●通説では、次のようになっています。
〔道の立場からすると、〕また何かを欠けたものとし何かを十分なものとすることもない。この境地を謝施(しゃた/すなわちとらわれのない随順)という。
〇新解釈では、次のようになります。
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
【何少何多】【何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。】
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
──前に北海若自身の立場で説明したように、河伯と比べるならば<多(大)>となったり、天地と比べるなら<少(小)>となったりして、その評価は断定(絶対)的なものではなく暫定的なものであるが故に、最終的には何が<少(小)>になるか、何が<多(大)>になるか、わかったものではない…と言っているのだと思います。これが先に述べた「大小の家」のからくりに言及した言葉のようです。見る角度の違い、意識のピント合わせの違いによってその評価は変わるのです。
【是謂謝施】【是、謝施(しゃせ)と謂う。】
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
──「謝施(しゃせ)」と名付けたのはどうしてなのか想像してみます。人は常に物を把握するために、<多(大)>とか<少(小)>とか評価しては言葉で「つげて」は比べていることが多々あります。でもその評価は絶対的なものではありませんでしたね。
わかりやすく喩えで、ある一定量の粘土のかたまりを平らにのばしてみることを想像してみましょう。それは<多>とか<少>とか言えるでしょうか。結論から言えば、表面積は<多(大)>になりますが、厚さは<少(小)>になります。見る角度(視点)で違ってくるのです。でも一定量の粘土に変わりはありません。なのに評価されるのです。言葉で「つげること」も同様のことが言えそうです。言葉数(つげること)が<多>になっても、内容が希薄になって<少>と評価することになってしまうかもしれません。反対に言葉数(つげること)が<少>であっても、内容は充実していて<多>だと思える現象が起こるかもしれません。これを「謝施」と謂う…と言っているのでしょう。
〔道の立場からすると、〕また何かを欠けたものとし何かを十分なものとすることもない。この境地を謝施(しゃた/すなわちとらわれのない随順)という。
〇新解釈では、次のようになります。
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
【何少何多】【何ぞ少とせんや、何ぞ多とせんや。】
何が<少>であろうか、何が<多>であろうか、わかったものではない。
──前に北海若自身の立場で説明したように、河伯と比べるならば<多(大)>となったり、天地と比べるなら<少(小)>となったりして、その評価は断定(絶対)的なものではなく暫定的なものであるが故に、最終的には何が<少(小)>になるか、何が<多(大)>になるか、わかったものではない…と言っているのだと思います。これが先に述べた「大小の家」のからくりに言及した言葉のようです。見る角度の違い、意識のピント合わせの違いによってその評価は変わるのです。
【是謂謝施】【是、謝施(しゃせ)と謂う。】
これを謝施(しゃせ/つげることを平らにのばすこと)という。
──「謝施(しゃせ)」と名付けたのはどうしてなのか想像してみます。人は常に物を把握するために、<多(大)>とか<少(小)>とか評価しては言葉で「つげて」は比べていることが多々あります。でもその評価は絶対的なものではありませんでしたね。
わかりやすく喩えで、ある一定量の粘土のかたまりを平らにのばしてみることを想像してみましょう。それは<多>とか<少>とか言えるでしょうか。結論から言えば、表面積は<多(大)>になりますが、厚さは<少(小)>になります。見る角度(視点)で違ってくるのです。でも一定量の粘土に変わりはありません。なのに評価されるのです。言葉で「つげること」も同様のことが言えそうです。言葉数(つげること)が<多>になっても、内容が希薄になって<少>と評価することになってしまうかもしれません。反対に言葉数(つげること)が<少>であっても、内容は充実していて<多>だと思える現象が起こるかもしれません。これを「謝施」と謂う…と言っているのでしょう。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 无一而行 ┃【一にして行(や)ること无(な)ければ、】
┃ 與道參差 ┃【ともに道と参差(しんし)たらん。】
┗━━━━━━━┛
<一>にして(区別する)行為がなくなれば、
同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【行】は、十字路を描いた象形文字。「動いて動作する」意。「いく・ゆく(動いて進む
・動かして進める。)」「おこなう・やる(動いて事をする。うごかす。やらせる。)」
*【参】は、三つの玉のかんざしをきらめかせた女性の姿の象形文字。「まじわる (いく
つもいっしょに入りまじる。ちらちらする。)」「仲間入りする。」
*【差】は、「穂の形+左(そばから左手でささえる)」で、「穂を交差してささえると、
上端×型になり、そろわない。そのじぐざぐした姿。」
*【参差】(しんし)は、「長短入りまじっていっしょになるさま。」「並び連なるさま。」
◆通説では、ここでも【而】を「なんじ」と読んでいます。よって命令形にしています。
【参差】は【参】(まじわる)の意味を無視して「そむいて離れる」と意訳しています。
【而(なんじ)の行を一にすることなかれ、道と参差(しんし)たらん。】は、「お前の行
動を一定させてはいけない。それでは道のはたらきとそむいて離れることになるだろ
う。」としています。
◇新解釈では、【而】は接続詞とみなしました。【无(なし)】は【一】を否定しているので
はなく、【行】を否定しているものとして読みました。後から出てくる【无動而不變(動
いて変ぜざるは无く)】、【无時而不移(時として移らざるは无し)】と同じ読み方で統一
しました。【一にして行(や)ること无(な)ければ、ともに道と参差(しんし)たらん。】は
「<一>にして(区別する)行為がなくなれば、同時に、道と<長短>が入りまじった状
態のままで一緒になるだろう。」としました。
┃▼ 无一而行 ┃【一にして行(や)ること无(な)ければ、】
┃ 與道參差 ┃【ともに道と参差(しんし)たらん。】
┗━━━━━━━┛
<一>にして(区別する)行為がなくなれば、
同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。
…………………………………………………………………………………………………………
*【行】は、十字路を描いた象形文字。「動いて動作する」意。「いく・ゆく(動いて進む
・動かして進める。)」「おこなう・やる(動いて事をする。うごかす。やらせる。)」
*【参】は、三つの玉のかんざしをきらめかせた女性の姿の象形文字。「まじわる (いく
つもいっしょに入りまじる。ちらちらする。)」「仲間入りする。」
*【差】は、「穂の形+左(そばから左手でささえる)」で、「穂を交差してささえると、
上端×型になり、そろわない。そのじぐざぐした姿。」
*【参差】(しんし)は、「長短入りまじっていっしょになるさま。」「並び連なるさま。」
◆通説では、ここでも【而】を「なんじ」と読んでいます。よって命令形にしています。
【参差】は【参】(まじわる)の意味を無視して「そむいて離れる」と意訳しています。
【而(なんじ)の行を一にすることなかれ、道と参差(しんし)たらん。】は、「お前の行
動を一定させてはいけない。それでは道のはたらきとそむいて離れることになるだろ
う。」としています。
◇新解釈では、【而】は接続詞とみなしました。【无(なし)】は【一】を否定しているので
はなく、【行】を否定しているものとして読みました。後から出てくる【无動而不變(動
いて変ぜざるは无く)】、【无時而不移(時として移らざるは无し)】と同じ読み方で統一
しました。【一にして行(や)ること无(な)ければ、ともに道と参差(しんし)たらん。】は
「<一>にして(区別する)行為がなくなれば、同時に、道と<長短>が入りまじった状
態のままで一緒になるだろう。」としました。
●通説では、次のようになっています。
お前の行動を一定させてはいけない。それでは道のはたらきとそむいて離れることになるだろう。
〇新解釈では、次のようになります。
<一>にして(区別する)行為がなくなれば、
同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。
【无一而行】【一にして行(や)ること无(な)ければ、】
〔<一>にして(区別する)行為がなくなられば、〕
──ここの<一>は「一定にする」といった意味ではなく、「<一>となる(一体となる)」といった意味だと解釈しました。そして「行(や)ること」とは何か。それは「<貴賤>や<多少>といった区別する行為」ではないでしょうか。「世界と一体となって、区別する行為がなくなれば、」…と言っているのでしょう。
【與道參差】【ともに道と参差(しんし)たらん。】
〔同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。〕
──<一>にして区別する行為がなくなると、それと同時に、<長短><貴賤><多少>の違いも区別する行為に走らず、差があるものであってもそれが入りまじったままを自身の内部に許容する意識状態となり、道と一緒に歩みをともにすることができるようになるだろう…ということのようです。
お前の行動を一定させてはいけない。それでは道のはたらきとそむいて離れることになるだろう。
〇新解釈では、次のようになります。
<一>にして(区別する)行為がなくなれば、
同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。
【无一而行】【一にして行(や)ること无(な)ければ、】
〔<一>にして(区別する)行為がなくなられば、〕
──ここの<一>は「一定にする」といった意味ではなく、「<一>となる(一体となる)」といった意味だと解釈しました。そして「行(や)ること」とは何か。それは「<貴賤>や<多少>といった区別する行為」ではないでしょうか。「世界と一体となって、区別する行為がなくなれば、」…と言っているのでしょう。
【與道參差】【ともに道と参差(しんし)たらん。】
〔同時に、道と<長短>が入りまじった状態のままで一緒になるだろう。〕
──<一>にして区別する行為がなくなると、それと同時に、<長短><貴賤><多少>の違いも区別する行為に走らず、差があるものであってもそれが入りまじったままを自身の内部に許容する意識状態となり、道と一緒に歩みをともにすることができるようになるだろう…ということのようです。
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 嚴乎若國之有君 ┃【厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。】
┃ 其无私徳 ┃【其れ私徳无(な)し。】
┗━━━━━━━━━━┛
厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。
そこには私的な徳(恩恵)はない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【嚴(厳)】は、「口二つ(口やかましい)+[下の字](いかつくどっしりとした)」で「い
かついことばを使って口やかましくきびしく取り締まるること。」「きびしい。」「おご
そか。」
*【私】は、「ひとりだけの。」「かってな。」(対語「公」。)
*【徳】は、「本性。」「道徳。」「恩恵。」
◆通説では、【嚴】の字を付け加えて、【厳厳乎(げんげんこ)として国の君あるが若(ごと)
く、其れ私徳なし。】は「厳然とあたかも国家の君主のようにして、偏(かたよ)った恩
恵を施すことがなく、」としています。
◇【厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。其れ私徳无(な)し。】は、「厳
(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。そこには私的な徳(恩恵)はない。」
としました。
┃▼ 嚴乎若國之有君 ┃【厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。】
┃ 其无私徳 ┃【其れ私徳无(な)し。】
┗━━━━━━━━━━┛
厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。
そこには私的な徳(恩恵)はない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【嚴(厳)】は、「口二つ(口やかましい)+[下の字](いかつくどっしりとした)」で「い
かついことばを使って口やかましくきびしく取り締まるること。」「きびしい。」「おご
そか。」
*【私】は、「ひとりだけの。」「かってな。」(対語「公」。)
*【徳】は、「本性。」「道徳。」「恩恵。」
◆通説では、【嚴】の字を付け加えて、【厳厳乎(げんげんこ)として国の君あるが若(ごと)
く、其れ私徳なし。】は「厳然とあたかも国家の君主のようにして、偏(かたよ)った恩
恵を施すことがなく、」としています。
◇【厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。其れ私徳无(な)し。】は、「厳
(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。そこには私的な徳(恩恵)はない。」
としました。
●通説では、次のようになっています。
厳然とあたかも国家の君主のようにして、偏(かたよ)った恩恵を施すことがなく、
〇新解釈では、次のようになります。
厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。
そこには私的な徳(恩恵)はない。
【嚴乎若國之有君】【厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。】
〔厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。〕
──河伯が<吾>の態度はどのようにしたらいいのか尋ねたことに応えているようです。北海若は第一に「厳かに」…と言っています。その態度は威厳や風格があり、荘厳としたムードに包まれていような状態で、「まるで国の君主がいるがごとくあれ」と指標を与えてくれています。<わたし>という国をまとめるために、自身の内部に厳かな「君主」、「主人」が必要なのです。
【其无私徳】【其れ私徳无(な)し。】
〔そこには私的な徳(恩恵)はない。〕
──「君主」は自分勝手な態度はとりません。<わたし>という国をまとめ、秩序をもたらすために「私(わたくし)事」に振り回されることなく「公(おおやけ)事」を大事にします。<我>の中には「私的な<わたし>」、つまり何人もの<臣妾>が存在するのです。それらのことも細心の注意をはらいながらも、皆尊重されます。すると、それらは<わたし>という国のためには、<吾>という「主人」に従順に仕える必要があります。<わたし>という国がうまく治まるためには、個別の<私(わたし)>の徳(恩恵)を求めるようなことはないのだ…と言っているようです。
厳然とあたかも国家の君主のようにして、偏(かたよ)った恩恵を施すことがなく、
〇新解釈では、次のようになります。
厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。
そこには私的な徳(恩恵)はない。
【嚴乎若國之有君】【厳乎(げんこ)として国の君が有るが若(ごと)くあれ。】
〔厳(おごそ)かに、まるで国の君主がいるがごとくあれ。〕
──河伯が<吾>の態度はどのようにしたらいいのか尋ねたことに応えているようです。北海若は第一に「厳かに」…と言っています。その態度は威厳や風格があり、荘厳としたムードに包まれていような状態で、「まるで国の君主がいるがごとくあれ」と指標を与えてくれています。<わたし>という国をまとめるために、自身の内部に厳かな「君主」、「主人」が必要なのです。
【其无私徳】【其れ私徳无(な)し。】
〔そこには私的な徳(恩恵)はない。〕
──「君主」は自分勝手な態度はとりません。<わたし>という国をまとめ、秩序をもたらすために「私(わたくし)事」に振り回されることなく「公(おおやけ)事」を大事にします。<我>の中には「私的な<わたし>」、つまり何人もの<臣妾>が存在するのです。それらのことも細心の注意をはらいながらも、皆尊重されます。すると、それらは<わたし>という国のためには、<吾>という「主人」に従順に仕える必要があります。<わたし>という国がうまく治まるためには、個別の<私(わたし)>の徳(恩恵)を求めるようなことはないのだ…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 繇繇乎若祭之有社 ┃【繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社が有るが若くあれ。】
┃ 其无私福 ┃【其れ私福无し。】
┗━━━━━━━━━━━┛
枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。
そこには私的な福(さいわい)はない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【繇】は、「系+[左の字](こねて引きのばす)」で、「糸が細く長くのびること。枝葉
や道がのびる」意。「しげる。」「うた。」「ゆれうごく。」
*【祭】は、「肉+又(手)+示(祭壇)」で「肉のげがれを清めて供えること。」「まつり
(神霊をまつる儀式。)」
*【社】は、「示(祭壇)+土(地上につちを盛った姿。また、その土地の代表的な木を土地
のかたしろとしてたてたさま)」で、「土地の生産力をまつる土地神の祭り。」「やしろ
(もと、土の生産力をまつった土地の神。土地をまつった所。)」「その地の代表的な木
を、土地神のかたしろとしたもの。」
*【福】は、「示(祭壇)+畐(とくりに酒を豊かに満たしたさま)」で、「神の恵みが豊かな
こと。」「さいわい(神から恵まれた豊かさ。)」転じて「しあわせ。」
◆通説では、【繇繇乎】の【繇】は由の発音で読み、「悠悠乎」と同じ…としています。
【繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社あるが若く、其れ私福なし。】は「おおらかにあた
かも祭の中心の社神(しゃじん)のようにして、偏った福をくだすことがなく、」としてい
ます。
┃▼ 繇繇乎若祭之有社 ┃【繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社が有るが若くあれ。】
┃ 其无私福 ┃【其れ私福无し。】
┗━━━━━━━━━━━┛
枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。
そこには私的な福(さいわい)はない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【繇】は、「系+[左の字](こねて引きのばす)」で、「糸が細く長くのびること。枝葉
や道がのびる」意。「しげる。」「うた。」「ゆれうごく。」
*【祭】は、「肉+又(手)+示(祭壇)」で「肉のげがれを清めて供えること。」「まつり
(神霊をまつる儀式。)」
*【社】は、「示(祭壇)+土(地上につちを盛った姿。また、その土地の代表的な木を土地
のかたしろとしてたてたさま)」で、「土地の生産力をまつる土地神の祭り。」「やしろ
(もと、土の生産力をまつった土地の神。土地をまつった所。)」「その地の代表的な木
を、土地神のかたしろとしたもの。」
*【福】は、「示(祭壇)+畐(とくりに酒を豊かに満たしたさま)」で、「神の恵みが豊かな
こと。」「さいわい(神から恵まれた豊かさ。)」転じて「しあわせ。」
◆通説では、【繇繇乎】の【繇】は由の発音で読み、「悠悠乎」と同じ…としています。
【繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社あるが若く、其れ私福なし。】は「おおらかにあた
かも祭の中心の社神(しゃじん)のようにして、偏った福をくだすことがなく、」としてい
ます。
●通説では、次のようになっています。
おおらかにあたかも祭の中心の社神(しゃじん)のようにして、偏った福をくだすことがなく、
〇新解釈では、次のようになります。
枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。
そこには私的な福(さいわい)はない。
【繇繇乎若祭之有社】【繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社が有るが若くあれ。】
〔枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。〕
──「繇繇乎(ゆうゆうこ)として」とは、「木」に喩えて「のびのびと枝葉を伸ばすように」…と言っているようです。
「社(やしろ) 」は、神の来臨する所のことです。普通、土地を清めて祭壇を設け、神を祭った場所のことを指しますが、ここでは「その地の代表的な木を、土地神のかたしろとしたもの(神木)」と解釈しました。
神木は絶対に切り倒される心配はありません。その命が自然に途絶えるまで天寿を全うします。河伯の<吾>の態度として挙げられる第二のイメージは、「祭りの中心の社(神木)のように」…と言っています。
【其无私福】【其れ私福无し。】
〔そこには私的な福(さいわい)はない。〕
──北海若の言う「祭」は「天」を敬う態度で儀式めいたことを言っているのではなく、気持ちの持ち方と言った方が実感に近いのかもしれません。まるで「社(神木)」のごとく…と言っています。わが身(社)に天を降臨させるとなると、そこには私的な(<わたし>の)福(さいわい)はないのだ…と言っているようです。
おおらかにあたかも祭の中心の社神(しゃじん)のようにして、偏った福をくだすことがなく、
〇新解釈では、次のようになります。
枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。
そこには私的な福(さいわい)はない。
【繇繇乎若祭之有社】【繇繇乎(ゆうゆうこ)として祭の社が有るが若くあれ。】
〔枝葉をのびのびと伸ばすようにして、まるで祭の中心の社(神木)であるがごとくあれ。〕
──「繇繇乎(ゆうゆうこ)として」とは、「木」に喩えて「のびのびと枝葉を伸ばすように」…と言っているようです。
「社(やしろ) 」は、神の来臨する所のことです。普通、土地を清めて祭壇を設け、神を祭った場所のことを指しますが、ここでは「その地の代表的な木を、土地神のかたしろとしたもの(神木)」と解釈しました。
神木は絶対に切り倒される心配はありません。その命が自然に途絶えるまで天寿を全うします。河伯の<吾>の態度として挙げられる第二のイメージは、「祭りの中心の社(神木)のように」…と言っています。
【其无私福】【其れ私福无し。】
〔そこには私的な福(さいわい)はない。〕
──北海若の言う「祭」は「天」を敬う態度で儀式めいたことを言っているのではなく、気持ちの持ち方と言った方が実感に近いのかもしれません。まるで「社(神木)」のごとく…と言っています。わが身(社)に天を降臨させるとなると、そこには私的な(<わたし>の)福(さいわい)はないのだ…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 泛泛乎 ┃【泛泛乎(はんはんこ)として
┃ 其若四方之无窮 ┃ 其れ四方の窮まりが无きが若くあれ。】
┃ 其无所畛域 ┃【其れ畛域(しんいき)する所无し。】
┗━━━━━━━━━━━┛
〔海の上で〕浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
そこには境界線で区切られた所がない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【泛】は、「水+乏」で、「かぶさるように水面にうくこと。」「うかぶ・うかべる。」
「おおう・あまねし。」【泛泛】は「うかび漂うさま。」「いちめんにおおいかぶさるさ
ま。」
*【四方】は、「東西南北の四つの方角。」「あらゆる方角。」
*【窮】は、「穴(あな)+躬(かがむ・まげる)」「曲がりくねって先がつっかえたさま。」
「きわまる(ものことがぎりぎりのところまでいってつっかえる。いきづまってうごきが
とれない。)」「きわめる(ぎりぎりのところまでやり尽くす。つきつめる。さいごまで
見とどける。」「行きづまり。いちばん奥の所。はて。」
*【畛】は、「田+[右の字](びっしりつめる)」で「びっしり作物を植え田畑の間に残っ
たあぜ道。」
*【域】の「或」は、「戈(ほこ)+口(四角い範囲)」で「四角い場所をくぎって、武器で守
る」意。「或」が「有」に転用されるようになったので、「土+或」で「或」の原義をあ
らわすようになりました。「さかい(くぎり。くぎりの中。境界線で囲まれた土地。)」
◆通説では、【泛泛乎】はただ「ひろやかに」と訳しています。
【泛泛乎(はんはんこ)として其れ四方の窮りが无きが若く、其れ畛域(しんいき)する所
なし。】は「ひろやかにあたかも四方の空間に限りがないようにして、どこにも区域を
設けることがなく、」としています。
◇【泛泛乎】は「水」に関係した字を使っている所がミソだと思います。確かに「一面に
おおいかぶさる」という意味もあるので、「広々とした」イメージはありますが、ここ
では、あえて「〔海の上で〕浮かび漂うようにして」としました。
【泛泛乎(はんはんこ)として其れ四方の窮りが无きが若くあれ。其れ畛域(しんいき)
する所无し。】は「(海の上で)浮かび漂うようにして、まるで四方に限界がないかのご
とくあれ。そこには境界線で区切られた所がない。」としました。
┃▼ 泛泛乎 ┃【泛泛乎(はんはんこ)として
┃ 其若四方之无窮 ┃ 其れ四方の窮まりが无きが若くあれ。】
┃ 其无所畛域 ┃【其れ畛域(しんいき)する所无し。】
┗━━━━━━━━━━━┛
〔海の上で〕浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
そこには境界線で区切られた所がない。
…………………………………………………………………………………………………………
*【泛】は、「水+乏」で、「かぶさるように水面にうくこと。」「うかぶ・うかべる。」
「おおう・あまねし。」【泛泛】は「うかび漂うさま。」「いちめんにおおいかぶさるさ
ま。」
*【四方】は、「東西南北の四つの方角。」「あらゆる方角。」
*【窮】は、「穴(あな)+躬(かがむ・まげる)」「曲がりくねって先がつっかえたさま。」
「きわまる(ものことがぎりぎりのところまでいってつっかえる。いきづまってうごきが
とれない。)」「きわめる(ぎりぎりのところまでやり尽くす。つきつめる。さいごまで
見とどける。」「行きづまり。いちばん奥の所。はて。」
*【畛】は、「田+[右の字](びっしりつめる)」で「びっしり作物を植え田畑の間に残っ
たあぜ道。」
*【域】の「或」は、「戈(ほこ)+口(四角い範囲)」で「四角い場所をくぎって、武器で守
る」意。「或」が「有」に転用されるようになったので、「土+或」で「或」の原義をあ
らわすようになりました。「さかい(くぎり。くぎりの中。境界線で囲まれた土地。)」
◆通説では、【泛泛乎】はただ「ひろやかに」と訳しています。
【泛泛乎(はんはんこ)として其れ四方の窮りが无きが若く、其れ畛域(しんいき)する所
なし。】は「ひろやかにあたかも四方の空間に限りがないようにして、どこにも区域を
設けることがなく、」としています。
◇【泛泛乎】は「水」に関係した字を使っている所がミソだと思います。確かに「一面に
おおいかぶさる」という意味もあるので、「広々とした」イメージはありますが、ここ
では、あえて「〔海の上で〕浮かび漂うようにして」としました。
【泛泛乎(はんはんこ)として其れ四方の窮りが无きが若くあれ。其れ畛域(しんいき)
する所无し。】は「(海の上で)浮かび漂うようにして、まるで四方に限界がないかのご
とくあれ。そこには境界線で区切られた所がない。」としました。
●通説では、次のようになっています。
ひろやかにあたかも四方の空間に限りがないようにして、どこにも区域を設けることがなく、
〇新解釈では、次のようになります。
〔海の上で〕浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
そこには境界線で区切られた所がない。
【泛泛乎】【泛泛乎(はんはんこ)として】
【其若四方之无窮】【其れ四方の窮まりが无きが若くあれ。】
〔海の上で〕浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
──第三の<吾>の態度のイメージは、あたかも河川の決められた範囲の中で一定方向に流れていくようにではなく、大海原の真ん中で、「浮かび漂うように」して身を任せ、「まるでどの方向も果てがないかのごとく」、広大な水面の上を堪能しつつ、その気になれば進路は自由に決められるかのような状態であれ…と言っているようです。
実際の海の真ん中で、周りは果てしない状態に思える所で浮かび漂っていたら、水面を堪能するどころではなく、普通の人は気が遠くなって、下手すれば恐怖さえ覚えるかもしれませんね。
北海若は海の化身なので、海でもって話をしますが、海は海でも意識の海の話です。浮かんでいる意識の海の上で解放感に満たされ、何ものにも拘束されない自由を楽しめばいいのです。進路はなぜだか、自ずと決まってくるものなのです。決められた道筋はないのです。そこは漂っていても泳いでもいい世界なのです。そこで思いっきり遊ぶがいい……と言っているのかもしれませんね。
【其无所畛域】【其れ畛域(しんいき)する所无し。】
そこには境界線で区切られた所がない。
──陸の上を歩くなら、足跡が残り、あぜみち(畛)ができます。右と左、前と後ろといった具合に境界線によって区切られた方向が決まってきます。前後左右で、東西南北と結びつけられるのです。
ところが海(水)の上の進路には足跡は残りません。動けば波紋ができるかもしれませんが、すぐにかき消されてただの水面と戻ってしまいます。大海原の真ん中で、四方に果てがないということは、そこでは境界線で区切られた所がないのです。
これが意識の世界でも同じことが言えるのです。普通の人の意識状態は、<善悪>や<大小><貴賤>などといった境界線で区切られた区別をたよりに自分の進路を決めているのです。意識の陸の上を歩いているからです。あぜみちだらけなのです。自分の足跡を残したいとさえ思っているのです。ところが、意識の海の上では<善悪>や<大小><貴賤>などといった区別、境界線で区切られた所がないのです。足跡は残らずあぜみちはできない…と言っているようです。
ひろやかにあたかも四方の空間に限りがないようにして、どこにも区域を設けることがなく、
〇新解釈では、次のようになります。
〔海の上で〕浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
そこには境界線で区切られた所がない。
【泛泛乎】【泛泛乎(はんはんこ)として】
【其若四方之无窮】【其れ四方の窮まりが无きが若くあれ。】
〔海の上で〕浮かび漂うようにして、まるで四方に果てがないかのごとくあれ。
──第三の<吾>の態度のイメージは、あたかも河川の決められた範囲の中で一定方向に流れていくようにではなく、大海原の真ん中で、「浮かび漂うように」して身を任せ、「まるでどの方向も果てがないかのごとく」、広大な水面の上を堪能しつつ、その気になれば進路は自由に決められるかのような状態であれ…と言っているようです。
実際の海の真ん中で、周りは果てしない状態に思える所で浮かび漂っていたら、水面を堪能するどころではなく、普通の人は気が遠くなって、下手すれば恐怖さえ覚えるかもしれませんね。
北海若は海の化身なので、海でもって話をしますが、海は海でも意識の海の話です。浮かんでいる意識の海の上で解放感に満たされ、何ものにも拘束されない自由を楽しめばいいのです。進路はなぜだか、自ずと決まってくるものなのです。決められた道筋はないのです。そこは漂っていても泳いでもいい世界なのです。そこで思いっきり遊ぶがいい……と言っているのかもしれませんね。
【其无所畛域】【其れ畛域(しんいき)する所无し。】
そこには境界線で区切られた所がない。
──陸の上を歩くなら、足跡が残り、あぜみち(畛)ができます。右と左、前と後ろといった具合に境界線によって区切られた方向が決まってきます。前後左右で、東西南北と結びつけられるのです。
ところが海(水)の上の進路には足跡は残りません。動けば波紋ができるかもしれませんが、すぐにかき消されてただの水面と戻ってしまいます。大海原の真ん中で、四方に果てがないということは、そこでは境界線で区切られた所がないのです。
これが意識の世界でも同じことが言えるのです。普通の人の意識状態は、<善悪>や<大小><貴賤>などといった境界線で区切られた区別をたよりに自分の進路を決めているのです。意識の陸の上を歩いているからです。あぜみちだらけなのです。自分の足跡を残したいとさえ思っているのです。ところが、意識の海の上では<善悪>や<大小><貴賤>などといった区別、境界線で区切られた所がないのです。足跡は残らずあぜみちはできない…と言っているようです。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 兼懐萬物 ┃【万物を兼ねて懐(いだ)け。】
┃ 其孰承翼 ┃【其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)らん。】
┃ 是謂无方 ┃【是(これ)を无方(むほう)と謂う。】
┗━━━━━━━┛
万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。
そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。
これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。
…………………………………………………………………………………………………………
*【兼】は、「二本の禾(いね)+[(手)]で、「いっしょにあわせ持つさま。」「かねる(二つ
以上をいっしょにあわせる。)」
*【懐】は、「心+[右の字](ふところに入れて囲む)」で、「胸中やふところに入れて囲
む。中に囲んで大切にあたためる気持ち。」「いだく・ふところにする(胸中にかかえこ
む。)」「おもう(胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。)」
「なつく・なつける(ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。)」
*【孰】は、「いずれ(二つ以上のうち、どちらかを選ぶときに用いることば。どちら。)」
*【承】は、「人+[(りょうて)]+手」で、「人がひざまづいて、両手でささげうけるさ
ま。上へ持ちあげる」意。「うける。」「うけたまわる。」
*【翼】は、「つばさ」を描いた象形文字。「つばさ(二つで対をなしたつばさ。」また
「つばさのように左右二つにはり出したもの。」
*【方】は、「左右に柄の張り出したすき」を描いた象形文字。「かた。」「くらべる。」
◆通説では、【孰】を反語として否定形の意味と解釈してます。【承翼】は「しょうよく」
と読んで「選んで助ける」意としています。
【万物を兼(あわ) せ懐(いだ)く、其れ孰(いず)れをか承翼(しょうよく)せん。是れを無
方(むほう)と謂う。】は「万物をへだてなく包容して、特に何かを選んで助けたりはし
ない。この境地を無法(むほう/すなわち無限定の自由)という。」としています。
◇新解釈では、【承翼】は「翼を承(うけたまわ)らん」と読んで、「翼のように対になるよ
うにと承る」としました。
【万物を兼ねて懐(いだ)け。其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)らん。是(これ)を无方
(むほう)と謂う。】は「万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。そこ
では、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。これを无方(むほ
う/比べるものなしの状態)という。」としました。
┃▼ 兼懐萬物 ┃【万物を兼ねて懐(いだ)け。】
┃ 其孰承翼 ┃【其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)らん。】
┃ 是謂无方 ┃【是(これ)を无方(むほう)と謂う。】
┗━━━━━━━┛
万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。
そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。
これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。
…………………………………………………………………………………………………………
*【兼】は、「二本の禾(いね)+[(手)]で、「いっしょにあわせ持つさま。」「かねる(二つ
以上をいっしょにあわせる。)」
*【懐】は、「心+[右の字](ふところに入れて囲む)」で、「胸中やふところに入れて囲
む。中に囲んで大切にあたためる気持ち。」「いだく・ふところにする(胸中にかかえこ
む。)」「おもう(胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。)」
「なつく・なつける(ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。)」
*【孰】は、「いずれ(二つ以上のうち、どちらかを選ぶときに用いることば。どちら。)」
*【承】は、「人+[(りょうて)]+手」で、「人がひざまづいて、両手でささげうけるさ
ま。上へ持ちあげる」意。「うける。」「うけたまわる。」
*【翼】は、「つばさ」を描いた象形文字。「つばさ(二つで対をなしたつばさ。」また
「つばさのように左右二つにはり出したもの。」
*【方】は、「左右に柄の張り出したすき」を描いた象形文字。「かた。」「くらべる。」
◆通説では、【孰】を反語として否定形の意味と解釈してます。【承翼】は「しょうよく」
と読んで「選んで助ける」意としています。
【万物を兼(あわ) せ懐(いだ)く、其れ孰(いず)れをか承翼(しょうよく)せん。是れを無
方(むほう)と謂う。】は「万物をへだてなく包容して、特に何かを選んで助けたりはし
ない。この境地を無法(むほう/すなわち無限定の自由)という。」としています。
◇新解釈では、【承翼】は「翼を承(うけたまわ)らん」と読んで、「翼のように対になるよ
うにと承る」としました。
【万物を兼ねて懐(いだ)け。其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)らん。是(これ)を无方
(むほう)と謂う。】は「万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。そこ
では、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。これを无方(むほ
う/比べるものなしの状態)という。」としました。
●通説では、次のようになっています。
万物をへだてなく包容して、特に何かを選んで助けたりはしない。この境地を無法(むほう/すなわち無限定の自由)という。
〇新解釈では、次のようになります。
万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。
そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。
これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。
【兼懐萬物】【万物を兼ねて懐(いだ)け。】
【其孰承翼】【其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)る。】
〔万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。〕
〔そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。〕
──万物を、<善悪><長短>などの振り分け取捨選択をすることなく、両方を兼ねあわせてあるがままの状態で、胸中にしまいこみ、そこで無視することなく、意識的に大事に見守って大切にあたためよ…と言っています。
人間の肉体は翼を持てません。しかし、人間の意識は翼を持って自由に飛びまわることができると喩えることができるかもしれません。といっても、普通は飛びまわる意識は経験したことはないかもしれません。というのも<左右>どちらか片方の翼を持っているだけだからです。<善>や<大>や<貴>だけを追い求める意識は、片側の翼だけだと喩えることができるでしょう。何かが欠けている意識が内部から起こると、人はもっと何かが必要だと<多>をさらに求めるかもしれませんが、翼からの飢えの声は止むことがないでしょう。<右>だけ育った翼は、彼方の<多>ではなく、身近にある<左>を求めているのです。<悪>や<小>や<賤>などが<左>の翼の栄養になるのです。
<右>と同様に、<左>も胸中であたためなければならないのです。するとある日突然、<右>に見合った<左>を承ったなら、かつてない経験をすることになるのです。それは「飛べる」という自由を獲得するのです。これが翼の定めなのです。それは人為ではどうすることもできない、天からのプレゼントなのです。人為でできることは、<左>を求める声に応えて、それを阻害することなく胸中であたため続けることだけです。翼は<左右>そろって対になることによってバランスが保たれるだけではなく、「飛べる」のです。新しい意識の境地に至れるのです。
【是謂无方】【是(これ)を无方(むほう)と謂う。】
〔これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。〕
──<ポジティブ(陽極)>と<ネガティブ(陰極)>は対立するものではなく、対(ペア)になることができ、そこから第三の力を生み出すことができるということは周知のことと思います。「飛べる」という象徴だけではなく、新しいものを生み出す可能性を秘めているのです。大事なことは、<善>と<悪>も、<貴>も<賤>も、もともと「比べる(対立する)」ものではなかったという気づきなのだ…と言っているようです。必要なのは対(ペア)になることができるものだという認識を胸中であたため、両翼を体得するだけなのです。その状態を「无方」、つまり「比べる(対立する)ものなし」と名づけられる…と言っているようです。
万物をへだてなく包容して、特に何かを選んで助けたりはしない。この境地を無法(むほう/すなわち無限定の自由)という。
〇新解釈では、次のようになります。
万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。
そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。
これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。
【兼懐萬物】【万物を兼ねて懐(いだ)け。】
【其孰承翼】【其れ孰(いず)れか翼を承(うけたまわ)る。】
〔万物を一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためよ。〕
〔そこでは、どちらかを翼のように対になるようにと承ることになるだろう。〕
──万物を、<善悪><長短>などの振り分け取捨選択をすることなく、両方を兼ねあわせてあるがままの状態で、胸中にしまいこみ、そこで無視することなく、意識的に大事に見守って大切にあたためよ…と言っています。
人間の肉体は翼を持てません。しかし、人間の意識は翼を持って自由に飛びまわることができると喩えることができるかもしれません。といっても、普通は飛びまわる意識は経験したことはないかもしれません。というのも<左右>どちらか片方の翼を持っているだけだからです。<善>や<大>や<貴>だけを追い求める意識は、片側の翼だけだと喩えることができるでしょう。何かが欠けている意識が内部から起こると、人はもっと何かが必要だと<多>をさらに求めるかもしれませんが、翼からの飢えの声は止むことがないでしょう。<右>だけ育った翼は、彼方の<多>ではなく、身近にある<左>を求めているのです。<悪>や<小>や<賤>などが<左>の翼の栄養になるのです。
<右>と同様に、<左>も胸中であたためなければならないのです。するとある日突然、<右>に見合った<左>を承ったなら、かつてない経験をすることになるのです。それは「飛べる」という自由を獲得するのです。これが翼の定めなのです。それは人為ではどうすることもできない、天からのプレゼントなのです。人為でできることは、<左>を求める声に応えて、それを阻害することなく胸中であたため続けることだけです。翼は<左右>そろって対になることによってバランスが保たれるだけではなく、「飛べる」のです。新しい意識の境地に至れるのです。
【是謂无方】【是(これ)を无方(むほう)と謂う。】
〔これを无方(むほう/比べるものなしの状態)という。〕
──<ポジティブ(陽極)>と<ネガティブ(陰極)>は対立するものではなく、対(ペア)になることができ、そこから第三の力を生み出すことができるということは周知のことと思います。「飛べる」という象徴だけではなく、新しいものを生み出す可能性を秘めているのです。大事なことは、<善>と<悪>も、<貴>も<賤>も、もともと「比べる(対立する)」ものではなかったという気づきなのだ…と言っているようです。必要なのは対(ペア)になることができるものだという認識を胸中であたため、両翼を体得するだけなのです。その状態を「无方」、つまり「比べる(対立する)ものなし」と名づけられる…と言っているようです。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 萬物一齊 ┃【万物は一にして斉(ひと)しく、】
┃ 孰短孰長 ┃【孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とせん。】
┗━━━━━━━┛
万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【齊(斉)】は「◇印が三つそろったさま」を描いた象形文字。「ととのう・ひとしい。」
「過不足なくそろえて調和した状態。」
*【短】は「矢(短い直線)+豆(たかつき)」で、「矢とたかつきのように、比較的短い寸法
の物をあわせて、みじかいこと。」「たりない。不足する。」「能力・人格などのたりな
いところ。」
*【長】は、「老人がながい頭髪をなびかせてたつさま」を描いた象形文字。「ながい。」
「すぐれている。すぐれた点。」
◆通説では、【万物は一斉(いっせい)、孰(いず)れをか短とし孰れをか長とせん。】は「万
物は差別のない斉一(せいいつ)なものである。いずれが劣り、いずれがすぐれているとい
うことはない。」としています。
◇【万物は一にして斉(ひと)しく、孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とせん。】は「万物
は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、どちらかを<短>とし、どちらか
を<長>とできるだろうか。」としました。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 道无終始 ┃【道に終始无し。】
┃ 物有死生 ┃【物に死生有り。】
┗━━━━━━━┛
道には<終わり>も<始まり>もない。
物には<死>と<生>がある。
…………………………………………………………………………………………………………
◆通説では、【道に終始なく物に死生あり。】は「道には終わりも始めもないが、個々の物
には死があり生がある。」としています。
◇【道に終始无し。物に死生有り。】は「道には<終わり>も<始まり>もない。物には
<死>と<生>がある。」としました。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 不恃其成 ┃【其の成(せい)を恃(たの)まず、】
┃ 一虚一満 ┃【一虚一満する】
┃ 不位乎其形 ┃【其の形に位せず。】
┗━━━━━━━━┛
(だが、)そんな既成概念をあてにせず、
ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、
そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【成】は、「戈(ほこ)+丁(打ってまとめ固める)」で、「まとめあげる。」「つくろうと
したものがしあがる。できあがる。」「しあげる。」「すでにしあがった状態。」
*【恃】は、「心+寺(じっとまつ)」で、「あてにして待つこと。」「たのむ(何かをあてに
する)。」
*【形】は、「彡(模様)+井(四角いかた)」で、「いろいろな模様をなすわくどりやかたの
こと。」「かたち(外にあらわれた姿)。」「かた(物の外わく)。」「いろいろな模様をな
すわくどりやかたのこと。」
*【位】は、「立(人が両足で地上にしっかりたつ姿)+人」で、「人がある位置にしっかり
たつさま。」「くらいする(ポストにつく。」「あるべきポストにすわる。」
◆通説では、【其の成(せい)を恃(たの)まず、一虚一満して其の形に位せず。】は「個物
としての完成を頼りとするわけにはいかない。あるときは欠(か)けあるときは満ちて、
今のままの形で落ち着くことはないのだ。」としています。
◇【其の成を恃(たの)まず】とは何を意味しているのか、難解な箇所です。【成】とは「つ
くろうとしたものがしあがる。できあがる。」という意味とするなら通説のように「完成
」ということになるでしょう。「すでにしあがった状態。」という意味なら「既成」とい
うことになるでしょう。また【其の】は何を受けているのでしょうか。普通は【物には死
生がある。】という直前の文章を受けるものです。そこで、ここの文章は「物には死生が
あるという既成概念をあてにせず」と言っていると解釈しました。
【其の成(せい)を恃(たの)まず、一虚一満にして其の形に位せず。】は「その既成概念
をあてにせず、ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、そんな(外に
あらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。」としました。
┃▼ 萬物一齊 ┃【万物は一にして斉(ひと)しく、】
┃ 孰短孰長 ┃【孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とせん。】
┗━━━━━━━┛
万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
…………………………………………………………………………………………………………
*【齊(斉)】は「◇印が三つそろったさま」を描いた象形文字。「ととのう・ひとしい。」
「過不足なくそろえて調和した状態。」
*【短】は「矢(短い直線)+豆(たかつき)」で、「矢とたかつきのように、比較的短い寸法
の物をあわせて、みじかいこと。」「たりない。不足する。」「能力・人格などのたりな
いところ。」
*【長】は、「老人がながい頭髪をなびかせてたつさま」を描いた象形文字。「ながい。」
「すぐれている。すぐれた点。」
◆通説では、【万物は一斉(いっせい)、孰(いず)れをか短とし孰れをか長とせん。】は「万
物は差別のない斉一(せいいつ)なものである。いずれが劣り、いずれがすぐれているとい
うことはない。」としています。
◇【万物は一にして斉(ひと)しく、孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とせん。】は「万物
は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、どちらかを<短>とし、どちらか
を<長>とできるだろうか。」としました。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 道无終始 ┃【道に終始无し。】
┃ 物有死生 ┃【物に死生有り。】
┗━━━━━━━┛
道には<終わり>も<始まり>もない。
物には<死>と<生>がある。
…………………………………………………………………………………………………………
◆通説では、【道に終始なく物に死生あり。】は「道には終わりも始めもないが、個々の物
には死があり生がある。」としています。
◇【道に終始无し。物に死生有り。】は「道には<終わり>も<始まり>もない。物には
<死>と<生>がある。」としました。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 不恃其成 ┃【其の成(せい)を恃(たの)まず、】
┃ 一虚一満 ┃【一虚一満する】
┃ 不位乎其形 ┃【其の形に位せず。】
┗━━━━━━━━┛
(だが、)そんな既成概念をあてにせず、
ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、
そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【成】は、「戈(ほこ)+丁(打ってまとめ固める)」で、「まとめあげる。」「つくろうと
したものがしあがる。できあがる。」「しあげる。」「すでにしあがった状態。」
*【恃】は、「心+寺(じっとまつ)」で、「あてにして待つこと。」「たのむ(何かをあてに
する)。」
*【形】は、「彡(模様)+井(四角いかた)」で、「いろいろな模様をなすわくどりやかたの
こと。」「かたち(外にあらわれた姿)。」「かた(物の外わく)。」「いろいろな模様をな
すわくどりやかたのこと。」
*【位】は、「立(人が両足で地上にしっかりたつ姿)+人」で、「人がある位置にしっかり
たつさま。」「くらいする(ポストにつく。」「あるべきポストにすわる。」
◆通説では、【其の成(せい)を恃(たの)まず、一虚一満して其の形に位せず。】は「個物
としての完成を頼りとするわけにはいかない。あるときは欠(か)けあるときは満ちて、
今のままの形で落ち着くことはないのだ。」としています。
◇【其の成を恃(たの)まず】とは何を意味しているのか、難解な箇所です。【成】とは「つ
くろうとしたものがしあがる。できあがる。」という意味とするなら通説のように「完成
」ということになるでしょう。「すでにしあがった状態。」という意味なら「既成」とい
うことになるでしょう。また【其の】は何を受けているのでしょうか。普通は【物には死
生がある。】という直前の文章を受けるものです。そこで、ここの文章は「物には死生が
あるという既成概念をあてにせず」と言っていると解釈しました。
【其の成(せい)を恃(たの)まず、一虚一満にして其の形に位せず。】は「その既成概念
をあてにせず、ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、そんな(外に
あらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
万物は差別のない斉一(せいいつ)なものである。いずれが劣り、いずれがすぐれているということはない。道には終わりも始めもないが、個々の物には死があり生がある。個物としての完成を頼りとするわけにはいかない。あるときは欠(か)けあるときは満ちて、今のままの形で落ち着くことはないのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、、
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
道には<終>も<始>もない。
物には<死>と<生>がある。
そんな既成概念をあてにせず、
ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、
そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。
【萬物一齊】【万物は一にして斉(ひと)しく、】
【孰短孰長】【孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とせん。】
〔万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、〕
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
──万物は二元対立するなかで比べられるものがなくなった時、本来の<一>なのだと再認識することになるのかもしれません。<一>にして、過不足なく調和して、その価値はみな斉(ひと)しいのです。
二つの左右の翼は<一>になった時、その潜在能力が開花してはじめて飛べるのです。そこで改めて自己確認できるように尋ねています。その翼のどちらかを<短>とし、どちらかを<長>とすることができるだろうか?…と。翼に於いてはみな答えを知っています。片方を<短>とし、もう片方を<長>とできないということを。
万物の二つはみな翼と同じような仕組みで<一>をなしているのです。でも我々は<善悪><大小><多少><貴賤>などなどを簡単に<一>として受け入れられるでしょうか?
我々にできることは、先に述べてきたように、二つを一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためることだけです。実際の意識が「无方」の境地に至って、はじめて<一>となるのです。そこには<短>と<長>はなくなっているのです。
【道无終始】【道に終始无し。】
【物有死生】【物に死生有り。】
道には<終わり>も<始まり>もない。
物には<死>と<生>がある。
──道は<一>なる世界そのものなのです。<一>なるものに<終わり>も<始まり>もないのだ…と言っているのです。
ところが生物には<死>と<生>があることは誰でも認めるところでしょう。この運命には誰も逆らえません。人間も生物です。つまりこれは<終わり>と<始まり>があるということに等しいのでしょうか? そうなるとどこまでいっても人間は道と一体にはなれないということにならないでしょうか? それでは話が通りません。
【不恃其成】【其の成(せい)を恃(たの)まず、】
〔そんな既成概念をあてにせず、〕
──「物には<死>と<生>がある」というのは、既成事実、既成概念です。ところが、北海若は「そんな既成概念をあてにすることなく」…と言っているようです。<死>=<終わり>、<生>=<始まり>だと思われがちですが、実際は別のことなのです。一緒だというのが既成概念で、そんな考えはあてにするな…と言っているのです。
【一虚一満】【一虚一満する】
【不位乎其形】【其の形に位せず。】
〔あるときは空っぽ、またあるときは満ちあふれているといった、〕
〔そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。〕
──「空っぽ」という状態は、則ち「死」を予感させ、「満ちあふれている」という状態は、則ち「生」を予感させる言葉です。<死生>の違いは、ただ「空っぽ」か「満ちあふれているか」というその形(外にあらわれる姿)の違いにすぎないのだ…と言っているのではないでしょうか。「そんな形に位することはない」つまり「そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。」…と言っているようです。
人間は死生に支配される形(外にあらわれる姿)だけの存在なのでしょうか。それともここでは、形にはあらわれない内なる何かをももちあわせた存在なのだ…とほのめかしているのでしょうか。自分の居場所は形以外のところにありうるのか、このことは、もう少し後の展開で言及しているようです。
万物は差別のない斉一(せいいつ)なものである。いずれが劣り、いずれがすぐれているということはない。道には終わりも始めもないが、個々の物には死があり生がある。個物としての完成を頼りとするわけにはいかない。あるときは欠(か)けあるときは満ちて、今のままの形で落ち着くことはないのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、、
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
道には<終>も<始>もない。
物には<死>と<生>がある。
そんな既成概念をあてにせず、
ある時は空っぽ、またある時は満ちあふれているといった、
そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。
【萬物一齊】【万物は一にして斉(ひと)しく、】
【孰短孰長】【孰(いず)れをか短とし、孰れをか長とせん。】
〔万物は<一>にして過不足なくそろって調和しているのに、〕
どちらかを<短>とし、どちらかを<長>とできるだろうか。
──万物は二元対立するなかで比べられるものがなくなった時、本来の<一>なのだと再認識することになるのかもしれません。<一>にして、過不足なく調和して、その価値はみな斉(ひと)しいのです。
二つの左右の翼は<一>になった時、その潜在能力が開花してはじめて飛べるのです。そこで改めて自己確認できるように尋ねています。その翼のどちらかを<短>とし、どちらかを<長>とすることができるだろうか?…と。翼に於いてはみな答えを知っています。片方を<短>とし、もう片方を<長>とできないということを。
万物の二つはみな翼と同じような仕組みで<一>をなしているのです。でも我々は<善悪><大小><多少><貴賤>などなどを簡単に<一>として受け入れられるでしょうか?
我々にできることは、先に述べてきたように、二つを一緒に兼ねあわせ持って、胸中で大切にあたためることだけです。実際の意識が「无方」の境地に至って、はじめて<一>となるのです。そこには<短>と<長>はなくなっているのです。
【道无終始】【道に終始无し。】
【物有死生】【物に死生有り。】
道には<終わり>も<始まり>もない。
物には<死>と<生>がある。
──道は<一>なる世界そのものなのです。<一>なるものに<終わり>も<始まり>もないのだ…と言っているのです。
ところが生物には<死>と<生>があることは誰でも認めるところでしょう。この運命には誰も逆らえません。人間も生物です。つまりこれは<終わり>と<始まり>があるということに等しいのでしょうか? そうなるとどこまでいっても人間は道と一体にはなれないということにならないでしょうか? それでは話が通りません。
【不恃其成】【其の成(せい)を恃(たの)まず、】
〔そんな既成概念をあてにせず、〕
──「物には<死>と<生>がある」というのは、既成事実、既成概念です。ところが、北海若は「そんな既成概念をあてにすることなく」…と言っているようです。<死>=<終わり>、<生>=<始まり>だと思われがちですが、実際は別のことなのです。一緒だというのが既成概念で、そんな考えはあてにするな…と言っているのです。
【一虚一満】【一虚一満する】
【不位乎其形】【其の形に位せず。】
〔あるときは空っぽ、またあるときは満ちあふれているといった、〕
〔そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。〕
──「空っぽ」という状態は、則ち「死」を予感させ、「満ちあふれている」という状態は、則ち「生」を予感させる言葉です。<死生>の違いは、ただ「空っぽ」か「満ちあふれているか」というその形(外にあらわれる姿)の違いにすぎないのだ…と言っているのではないでしょうか。「そんな形に位することはない」つまり「そんな(外にあらわれる)形に(自分の居場所として)居ることはないのだ。」…と言っているようです。
人間は死生に支配される形(外にあらわれる姿)だけの存在なのでしょうか。それともここでは、形にはあらわれない内なる何かをももちあわせた存在なのだ…とほのめかしているのでしょうか。自分の居場所は形以外のところにありうるのか、このことは、もう少し後の展開で言及しているようです。
┏━━━━━━━┓
┃▼ 年不可擧 ┃【年は挙げるべからず。】
┃ 時不可止 ┃【時は止めるべからず。】
┃ 消息盈虚 ┃【消息や盈虚(えいきょ)にて、】
┃ 終則有始 ┃【終われば則ち始まり有り。】
┗━━━━━━━┛
年の移り変りは(人の手で)動かすことはできない。
時の流れをは(人の足で)止めることはできない。
消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、
<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【擧(挙)】は、「両手+両手+与(かみあったさま)」で、「手を同時にそろえ、力をあ
わせて動かすこと。」
*【止】は「足の形」を描いた象形文字。「足がじっとひと所にとまること。」
*【消息】は、「消えること生じること。」「栄枯盛衰のこと。」「時の移り変り。」
*【盈虚】(えいきょ)は、「みちることと欠けること。」
◆通説では、【年は挙(ふさ/歫)ぐべからず、時は止(とど)むべからず。消息盈虚、終れ
ば則ち有(ま/又)た始まる。】は「年の移りゆきはとめられないし、時の推移ははばめ
ない。衰えたり栄えたり満ちたり欠けたりして、終わったと思うとまた始まるものであ
る。」としています。
◇【年は挙げるべからず。時は止めるべからず。消息や盈虚(えいきょ)は、終われば則ち
始まり有り。】は「年の移り変りは(人の手で)動かすことはできない。時の流れは(人
の足で)止めることはできない。消えたり生じたり満ちたり欠けたりして、<終わり>
があれば則ち<始まり>があるのだ。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 是所以語大義之方 ┃【是(これ)が大義の方を語り、
┃ 論萬物之理也 ┃ 万物の理を論じた所以(ゆえん)なり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、
万物の道理を論じた理由だ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【所以…】は、「…するわけ・理由。…する手段。」
*【義】は、「羊(形のよいひつじ)+我(ぎざぎざとかどめのたったほこ。)」で、もと、
かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり
方。」
*【大義】は、「人として根本的な正しい筋道。」
*【方】は「しかた。やりかた。」「技術やわざ。」「不老長生の術。」「四角。」「人
として行うべきまっすぐな道。」
*【理】は、「玉+里(すじみちをつけた土地)」で「宝石の表面に透けて見えるすじめ。」
「ことわり(ものごとのすじみち。)」「条理。」「道理。」
◆通説では、未来のこととして解釈しています。
【是れ大義の方を語り、万物の理を論ずる所以(ゆえん)なり。】は「以上のことがわか
ってこそ、すぐれた秩序のありかたを語ることができ、もろもろの存在の条理について
論ずることができるのだ。」としています。
◇新解釈では、過去のことに対する理由として解釈しました。
【是(これ)が大義の方を語り、万物の理を論じた所以(ゆえん)なり。】は「これが、人
としての根本的な筋道のあり方を語り、万物の道理を論じた理由だ。」としました。
┃▼ 年不可擧 ┃【年は挙げるべからず。】
┃ 時不可止 ┃【時は止めるべからず。】
┃ 消息盈虚 ┃【消息や盈虚(えいきょ)にて、】
┃ 終則有始 ┃【終われば則ち始まり有り。】
┗━━━━━━━┛
年の移り変りは(人の手で)動かすことはできない。
時の流れをは(人の足で)止めることはできない。
消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、
<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【擧(挙)】は、「両手+両手+与(かみあったさま)」で、「手を同時にそろえ、力をあ
わせて動かすこと。」
*【止】は「足の形」を描いた象形文字。「足がじっとひと所にとまること。」
*【消息】は、「消えること生じること。」「栄枯盛衰のこと。」「時の移り変り。」
*【盈虚】(えいきょ)は、「みちることと欠けること。」
◆通説では、【年は挙(ふさ/歫)ぐべからず、時は止(とど)むべからず。消息盈虚、終れ
ば則ち有(ま/又)た始まる。】は「年の移りゆきはとめられないし、時の推移ははばめ
ない。衰えたり栄えたり満ちたり欠けたりして、終わったと思うとまた始まるものであ
る。」としています。
◇【年は挙げるべからず。時は止めるべからず。消息や盈虚(えいきょ)は、終われば則ち
始まり有り。】は「年の移り変りは(人の手で)動かすことはできない。時の流れは(人
の足で)止めることはできない。消えたり生じたり満ちたり欠けたりして、<終わり>
があれば則ち<始まり>があるのだ。」としました。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 是所以語大義之方 ┃【是(これ)が大義の方を語り、
┃ 論萬物之理也 ┃ 万物の理を論じた所以(ゆえん)なり。】
┗━━━━━━━━━━━┛
これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、
万物の道理を論じた理由だ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【所以…】は、「…するわけ・理由。…する手段。」
*【義】は、「羊(形のよいひつじ)+我(ぎざぎざとかどめのたったほこ。)」で、もと、
かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり
方。」
*【大義】は、「人として根本的な正しい筋道。」
*【方】は「しかた。やりかた。」「技術やわざ。」「不老長生の術。」「四角。」「人
として行うべきまっすぐな道。」
*【理】は、「玉+里(すじみちをつけた土地)」で「宝石の表面に透けて見えるすじめ。」
「ことわり(ものごとのすじみち。)」「条理。」「道理。」
◆通説では、未来のこととして解釈しています。
【是れ大義の方を語り、万物の理を論ずる所以(ゆえん)なり。】は「以上のことがわか
ってこそ、すぐれた秩序のありかたを語ることができ、もろもろの存在の条理について
論ずることができるのだ。」としています。
◇新解釈では、過去のことに対する理由として解釈しました。
【是(これ)が大義の方を語り、万物の理を論じた所以(ゆえん)なり。】は「これが、人
としての根本的な筋道のあり方を語り、万物の道理を論じた理由だ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
年の移りゆきはとめられないし、時の推移ははばめない。衰えたり栄えたり満ちたり欠けたりして、終わったと思うとまた始まるものである。以上のことがわかってこそ、すぐれた秩序のありかたを語ることができ、もろもろの存在の条理について論ずることができるのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
年の移り変りは(人の手で)動かすことができない。
時の流れは(人の足で)止めることができない。
消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、
<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。
これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、
万物の道理を論じた理由だ。
【年不可擧】【年は挙げるべからず。】
【時不可止】【時は止めるべからず。】
〔年の移り変りを(人の手で)動かすこともできなければ〕
〔時の流れを(人の足で)止めることもできない。〕
──年や時の流れは大自然のもと永遠に続いているものであって、人は手も足も出せないのです。一定のリズムがあり、それを人の手で遅くしたり速くしたり動かそうとしても不可能です。人の足で止めようとしても不可能です。人はそのことを十分知っていますが、気持ちは何とかしたいと願っていたりするものです。
【消息盈虚】【消息や盈虚(えいきょ)にて、】
【終則有始】【終われば則ち始まり有り。】
〔消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、〕
〔<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。〕
──<死生>を<終始>と同じだと考えている人にとっては、<始まり=生>があれば<終わり=死>があり、もう<始まり=生>はない…というのが一般的な既成概念です。でも、北海若はそうは言っていません。<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ…と言っています。<死>=<終わり>ではないと言っているようです。
【是所以語大義之方論萬物之理也】
【是(これ)が大義の方を語り、万物の理を論ずる所以(ゆえん)なり。】
〔これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、万物の道理を論ずる理由だ。〕
──「大義の方」(人としての根本的な筋道のあり方」)とは何を指しているのでしょうか。それは、「物には死生があるという既成概念をあてにしないようにすること」、また「形(外にあらわれるいっときの姿)に腰をするえないようにすること」ではないでしょうか。
「万物の理」(万物の道理)とは何を指しているのでしょうか。それは「年の移り変りを(人の手で)動かすことはできないし、時の流れを(人の足で)止めることはできないということ」ではないでしょうか。
なぜそんなことを語り、論じたのかという理由は、「<終わり>があれば則ちまた<始まり>がある」ということは、逆に言えばその途切れることのない連続は「<終わり>もなければ<始まり>もない」からだということではないでしょうか。つまり人の肉体の<死>は一区切りの<終わり>であっても、肉体以外の人間としては<終わり>ではなく、また<始まり>の新たな<生>があるということを示唆しているのではないでしょうか。それは連続しているがために本当の意味では<始まり>もないというのが万物の理に叶った概念ではないだろうか…と言っているのではないでしょうか。それは今までも何度か触れてきた、転生をほのめかしている言葉ではないかと推察できそうです。といっても、誰もそれを証明することはできませんので、ことばで断定できるようなことではありません。よって、ほのめかすことによって、ことばの行間に託したのではないでしょうか。
年の移りゆきはとめられないし、時の推移ははばめない。衰えたり栄えたり満ちたり欠けたりして、終わったと思うとまた始まるものである。以上のことがわかってこそ、すぐれた秩序のありかたを語ることができ、もろもろの存在の条理について論ずることができるのだ。
〇新解釈では、次のようになります。
年の移り変りは(人の手で)動かすことができない。
時の流れは(人の足で)止めることができない。
消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、
<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。
これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、
万物の道理を論じた理由だ。
【年不可擧】【年は挙げるべからず。】
【時不可止】【時は止めるべからず。】
〔年の移り変りを(人の手で)動かすこともできなければ〕
〔時の流れを(人の足で)止めることもできない。〕
──年や時の流れは大自然のもと永遠に続いているものであって、人は手も足も出せないのです。一定のリズムがあり、それを人の手で遅くしたり速くしたり動かそうとしても不可能です。人の足で止めようとしても不可能です。人はそのことを十分知っていますが、気持ちは何とかしたいと願っていたりするものです。
【消息盈虚】【消息や盈虚(えいきょ)にて、】
【終則有始】【終われば則ち始まり有り。】
〔消えたり生じたり、満ちたり欠けたりして、〕
〔<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ。〕
──<死生>を<終始>と同じだと考えている人にとっては、<始まり=生>があれば<終わり=死>があり、もう<始まり=生>はない…というのが一般的な既成概念です。でも、北海若はそうは言っていません。<終わり>があれば則ち<始まり>があるのだ…と言っています。<死>=<終わり>ではないと言っているようです。
【是所以語大義之方論萬物之理也】
【是(これ)が大義の方を語り、万物の理を論ずる所以(ゆえん)なり。】
〔これが、人としての根本的な筋道のあり方を語り、万物の道理を論ずる理由だ。〕
──「大義の方」(人としての根本的な筋道のあり方」)とは何を指しているのでしょうか。それは、「物には死生があるという既成概念をあてにしないようにすること」、また「形(外にあらわれるいっときの姿)に腰をするえないようにすること」ではないでしょうか。
「万物の理」(万物の道理)とは何を指しているのでしょうか。それは「年の移り変りを(人の手で)動かすことはできないし、時の流れを(人の足で)止めることはできないということ」ではないでしょうか。
なぜそんなことを語り、論じたのかという理由は、「<終わり>があれば則ちまた<始まり>がある」ということは、逆に言えばその途切れることのない連続は「<終わり>もなければ<始まり>もない」からだということではないでしょうか。つまり人の肉体の<死>は一区切りの<終わり>であっても、肉体以外の人間としては<終わり>ではなく、また<始まり>の新たな<生>があるということを示唆しているのではないでしょうか。それは連続しているがために本当の意味では<始まり>もないというのが万物の理に叶った概念ではないだろうか…と言っているのではないでしょうか。それは今までも何度か触れてきた、転生をほのめかしている言葉ではないかと推察できそうです。といっても、誰もそれを証明することはできませんので、ことばで断定できるようなことではありません。よって、ほのめかすことによって、ことばの行間に託したのではないでしょうか。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 物之生也 ┃【物の生や、】
┃ 若驟若馳 ┃【驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。】
┃ 无動而不變 ┃【動いて変ぜざるは无(な)く、】
┃ 无時而不移 ┃【時として移らざるは无し。】
┗━━━━━━━━┛
物の<生>というのは、
まるで馬がかけるかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。
(その)動くにつれて、変化しないものはなく、
時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【驟】は、「馬+聚(ぐっとひきしめる。つめる。)」で「はしる(馬がかけ足する。小ま
たではやがけする。)」
*【馳】は、「馬+也(横にのびる)」で「はせる(乗った車馬をはやくはしらせる。車馬に
乗ってはやくいく。」「はせる・はしる(横ざまにはいっていく。ものがさっと動いてい
く。)」
*【時】は、「とき(時間。時代。適当な時機。適時の。よいしおどきの。)」「うかがう
(よいしおどきをうかがう。)」
*【移】は、「禾(いね)+多」で、「稲の穂が風に吹かれて、横へ横へとなびくこと。」
「うつる・うつす(横にずれる。ずれて動く。位置や時間がしだいにずれていく。)」
◆通説では、【无…不〇】は、肯定の表現に変えています。
【物の生ずるや、驟(は)せるが若(ごと)く、馳(かけ)るが若く、動くとして変ぜざるは
なく、時として移らざるはなし。】は「物が生まれて存在するのは、ちょうど馬の駆け
ぬけるようなすばやさである。その動きにつれて変化し、時の流れとともに推移する。
」としています。
◇新解釈では、【无…不〇】は、万物は例外なくそうであるということを強調するために
二重否定の表現のままにしました。
【物の生や、驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。動いて変ぜざるは无
(な)く、時として移らざるは无し。】は「物の<生>というのは、まるで馬がかける
かのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやいものだ。動くにつれて、変化しないもの
はなく、時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。」としました。
┃▼ 物之生也 ┃【物の生や、】
┃ 若驟若馳 ┃【驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。】
┃ 无動而不變 ┃【動いて変ぜざるは无(な)く、】
┃ 无時而不移 ┃【時として移らざるは无し。】
┗━━━━━━━━┛
物の<生>というのは、
まるで馬がかけるかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。
(その)動くにつれて、変化しないものはなく、
時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【驟】は、「馬+聚(ぐっとひきしめる。つめる。)」で「はしる(馬がかけ足する。小ま
たではやがけする。)」
*【馳】は、「馬+也(横にのびる)」で「はせる(乗った車馬をはやくはしらせる。車馬に
乗ってはやくいく。」「はせる・はしる(横ざまにはいっていく。ものがさっと動いてい
く。)」
*【時】は、「とき(時間。時代。適当な時機。適時の。よいしおどきの。)」「うかがう
(よいしおどきをうかがう。)」
*【移】は、「禾(いね)+多」で、「稲の穂が風に吹かれて、横へ横へとなびくこと。」
「うつる・うつす(横にずれる。ずれて動く。位置や時間がしだいにずれていく。)」
◆通説では、【无…不〇】は、肯定の表現に変えています。
【物の生ずるや、驟(は)せるが若(ごと)く、馳(かけ)るが若く、動くとして変ぜざるは
なく、時として移らざるはなし。】は「物が生まれて存在するのは、ちょうど馬の駆け
ぬけるようなすばやさである。その動きにつれて変化し、時の流れとともに推移する。
」としています。
◇新解釈では、【无…不〇】は、万物は例外なくそうであるということを強調するために
二重否定の表現のままにしました。
【物の生や、驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。動いて変ぜざるは无
(な)く、時として移らざるは无し。】は「物の<生>というのは、まるで馬がかける
かのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやいものだ。動くにつれて、変化しないもの
はなく、時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
物が生まれて存在するのは、ちょうど馬の駆けぬけるようなすばやさである。その動きにつれて変化し、時の流れとともに推移する。
〇新解釈では、次のようになります。
物の<生>というのは、
まるで馬がはやがけするかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。
動くにつれて、変化しないものはなく、
時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。
【物之生也】【物の生や、】
【若驟若馳】【驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。】
〔物の<生>というのは、〕
〔まるで馬がかけるかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。〕
──我々は自分の<生>が、馬や車馬が走りゆくかのごとく、すばやく動いているものだと感じたことがあるでしょうか。普通に生を営んでいる状態ではほとんど動いているという自覚はないのではないでしょうか。過去を振り返ってみた時、動いていたのだなあというぐらいの感覚はあるかもしれませんが、すばやいという実感はないのではないでしょうか。
ところが、北海若はさっきと今とでさえ違っていて、既にすばやく動いているものだと認識しているようです。<生>の瞬間瞬間を意識して過ごしていたら、あっという間に過ぎ去っていくものだという感覚が伴うものなのかもしれません。
【无動而不變】【動いて変ぜざるは无(な)く、】
【无時而不移】【時として移らざるは无し。】
〔動くにつれて、変化しないものはなく、〕
〔時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。〕
──動いているということは、変化しないものはない…と言っています。さっきと今とはもう動いているのだとすると、ごくわずかでも確実に変化しているのです。否が応でも変化しないものはないのです。
一分前、一時間前、一日前、一週間前、一ヶ月前……時が流れるにしたがい、どんどんと移り変わっていることになります。時とともに、推移しないものはないのです。
過去を長いスパンで見るならば、変化や推移してきたことを認めることができるかもしれませんが、短いスパンだと変化を気にとめたことさえないかもしれません。どの程度を長いとし、どの程度を短いとするかは、個人によって違っていることでしょう。
何もすることもなくぼ〜としている時、時間の経過がとても長く感じます。忙しくあれこれしていると時間の経過はあっという間に感じます。ところが不思議なことに、後から思い出す時、何もしていなかった時間は短く感じ、あれこれしていた時間は長く感じます。何もしていなかった期間の自分の変化をあまり認めることができませんが、あれこれやってきた期間の自分の変化は大きかったと自覚するかもしれません。
変化や推移を自覚するには、意識的に行動した記憶の細かさの比較ができるかどうかにかかっていると言えるかもしれません。それによって、個人差ができてくるのでしょう。一年前と今の自分を比べた時には変化したことを認める人は多くいるでしょう。では一か月前ではどうでしょう。一週間前と変化したと認める人はいるでしょうか。一分や一秒前の自分と変化したと自覚できる人はまずいないでしょうね。それでも自然の摂理においては変化しないものはなく、推移しないものはない…と言っているようです。
物が生まれて存在するのは、ちょうど馬の駆けぬけるようなすばやさである。その動きにつれて変化し、時の流れとともに推移する。
〇新解釈では、次のようになります。
物の<生>というのは、
まるで馬がはやがけするかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。
動くにつれて、変化しないものはなく、
時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。
【物之生也】【物の生や、】
【若驟若馳】【驟(はし)るが若(ごと)く、馳(は)せるが若し。】
〔物の<生>というのは、〕
〔まるで馬がかけるかのごとく、車馬が馳せるかのごとくすばやく動くものだ。〕
──我々は自分の<生>が、馬や車馬が走りゆくかのごとく、すばやく動いているものだと感じたことがあるでしょうか。普通に生を営んでいる状態ではほとんど動いているという自覚はないのではないでしょうか。過去を振り返ってみた時、動いていたのだなあというぐらいの感覚はあるかもしれませんが、すばやいという実感はないのではないでしょうか。
ところが、北海若はさっきと今とでさえ違っていて、既にすばやく動いているものだと認識しているようです。<生>の瞬間瞬間を意識して過ごしていたら、あっという間に過ぎ去っていくものだという感覚が伴うものなのかもしれません。
【无動而不變】【動いて変ぜざるは无(な)く、】
【无時而不移】【時として移らざるは无し。】
〔動くにつれて、変化しないものはなく、〕
〔時が流れるにつれて、推移しないものはないのだ。〕
──動いているということは、変化しないものはない…と言っています。さっきと今とはもう動いているのだとすると、ごくわずかでも確実に変化しているのです。否が応でも変化しないものはないのです。
一分前、一時間前、一日前、一週間前、一ヶ月前……時が流れるにしたがい、どんどんと移り変わっていることになります。時とともに、推移しないものはないのです。
過去を長いスパンで見るならば、変化や推移してきたことを認めることができるかもしれませんが、短いスパンだと変化を気にとめたことさえないかもしれません。どの程度を長いとし、どの程度を短いとするかは、個人によって違っていることでしょう。
何もすることもなくぼ〜としている時、時間の経過がとても長く感じます。忙しくあれこれしていると時間の経過はあっという間に感じます。ところが不思議なことに、後から思い出す時、何もしていなかった時間は短く感じ、あれこれしていた時間は長く感じます。何もしていなかった期間の自分の変化をあまり認めることができませんが、あれこれやってきた期間の自分の変化は大きかったと自覚するかもしれません。
変化や推移を自覚するには、意識的に行動した記憶の細かさの比較ができるかどうかにかかっていると言えるかもしれません。それによって、個人差ができてくるのでしょう。一年前と今の自分を比べた時には変化したことを認める人は多くいるでしょう。では一か月前ではどうでしょう。一週間前と変化したと認める人はいるでしょうか。一分や一秒前の自分と変化したと自覚できる人はまずいないでしょうね。それでも自然の摂理においては変化しないものはなく、推移しないものはない…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 何爲乎 何不爲乎 ┃【何をか為し、何をか為さざらん、】
┃ 夫固將自化 ┃【夫(そ)れ固(もと)より将に自ら化さんとす。】
┗━━━━━━━━━━━┛
『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、
それはもともと今まさに(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【將】は、「まさに…せんとす(これから…しようとする。…しそうだ。)」「まさに
…ならんとす(ほぽ…に近い。)」
◆通説では、【將】は普通の未然の詞としては通じないとし、「以て」の意としています。
【何をか為し、何をか為さざらなん。夫れ固(もと)より将(もっ/以)て自(おのず)から
化すと。】は〔『何をしようか、何をしないでおこうか』などというが、そもそもすべ
てはもともと自然に変化しているのだ。」〕としています。
◇新解釈では、【将】はキーワードで、「今まさに…しようとしている」意としました。
【何をか為し、何をか為さざらなん、夫(そ)れ固(もと)より将に自ずと化さんとす。】
は〔『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、それはもともと今まさ
に(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」〕としました。
┃▼ 何爲乎 何不爲乎 ┃【何をか為し、何をか為さざらん、】
┃ 夫固將自化 ┃【夫(そ)れ固(もと)より将に自ら化さんとす。】
┗━━━━━━━━━━━┛
『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、
それはもともと今まさに(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【將】は、「まさに…せんとす(これから…しようとする。…しそうだ。)」「まさに
…ならんとす(ほぽ…に近い。)」
◆通説では、【將】は普通の未然の詞としては通じないとし、「以て」の意としています。
【何をか為し、何をか為さざらなん。夫れ固(もと)より将(もっ/以)て自(おのず)から
化すと。】は〔『何をしようか、何をしないでおこうか』などというが、そもそもすべ
てはもともと自然に変化しているのだ。」〕としています。
◇新解釈では、【将】はキーワードで、「今まさに…しようとしている」意としました。
【何をか為し、何をか為さざらなん、夫(そ)れ固(もと)より将に自ずと化さんとす。】
は〔『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、それはもともと今まさ
に(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」〕としました。
●通説では、次のようになっています。
『何をしようか、何をしないでおこうか』などというが、そもそもすべてはもともと自然に変化しているのだ。」
〇新解釈では、次のようになります。
『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、
それはもともと今まさに(この瞬間にも)自ら変化しようとしているものなのだ。」
【何爲乎 何不爲乎】【何をか為し、何をか為さざらん、】
【夫固將自化】【夫(そ)れ固(もと)より将に自ずと化さんとす。】
〔『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、〕
〔それはもともと今まさに(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」〕
──河伯が<我>の「(行)動」について尋ねたことに答えているようです。その「外部」の「する・しない」という<我>の行動は、<吾>の「内部」の必然性の変化に伴い、今まさにその瞬間瞬間に応じたかたちで、「自ずと」決定してゆくものなのだ…と言っているようです。
『何をしようか、何をしないでおこうか』などというが、そもそもすべてはもともと自然に変化しているのだ。」
〇新解釈では、次のようになります。
『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、
それはもともと今まさに(この瞬間にも)自ら変化しようとしているものなのだ。」
【何爲乎 何不爲乎】【何をか為し、何をか為さざらん、】
【夫固將自化】【夫(そ)れ固(もと)より将に自ずと化さんとす。】
〔『何をしようか。何をしないでいようか。』などと言うが、〕
〔それはもともと今まさに(この瞬間にも)自ずと変化しようとしているものなのだ。」〕
──河伯が<我>の「(行)動」について尋ねたことに答えているようです。その「外部」の「する・しない」という<我>の行動は、<吾>の「内部」の必然性の変化に伴い、今まさにその瞬間瞬間に応じたかたちで、「自ずと」決定してゆくものなのだ…と言っているようです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
荘子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75488人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196031人
- 3位
- 独り言
- 9044人