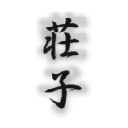━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━秋水篇━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(10)天と人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯曰 河伯曰く。
然則何貴於道邪 然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。
北海若曰 北海若曰く。
知道者 必達於理 道を知る者は、必ず理に達す。
達於理者 必明於權 理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。
明於權者 不以物害己 権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめず。
至徳者 火弗能熱 徳に至った者は、火も熱からしむること能(あた)わず、
水弗能溺 寒暑弗能害 水も溺(おぼ)らすこと能わず、寒暑も害すること能わず、
禽獣弗能賊 禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、
非謂其薄之也 其のこれを薄んじるを謂うに非ざるなり。
言察乎安危 寧於禍福 安危を察し、禍福に寧(やす)んじ、
謹於去就 去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、
莫之能害也 これを能(よ)く害するもの莫(な)きを言うなり。
故曰 天在内 人在外 故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、
徳在乎天 徳は天にありと。
知天人之行 天人の行を知り、
本乎天 位乎得 天に本(もと)づきて、得に位すれば、
蹢躅而屈伸 蹢躅(てきちょく)して屈伸し、
反要而語極 要に反(かえ)りて極を語らん。
曰 何謂天 何謂人 (河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。
北海若曰 北海若曰く。
牛馬四足 是謂天 牛馬の四足なる、これを天と謂う。
落馬首 穿牛鼻 是謂人 馬の首を落としめ、牛鼻を穿(うが)つ、これを人と謂う。
故曰 无以人滅天 故に曰く。人を以て天を滅ぼすなかれ。
无以故滅命 故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。
无以得殉名 得を以て名に殉(じゅん)することなかれと。
謹守而勿失 謹み守りて失うことなき、
是謂反其眞 是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
河伯はいった、「それでは、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若は答えた、「道をわきまえたものは、必ず物事の道理に通ずる。物事の道理に通じたものは、必ず臨機応変の処置に明るくなる。そして、臨機応変に明るいものは、外界の事物のために自分を害されることはない。最高の徳をそなえた人は、火も熱(あつ)がらせることができず、水も溺(おぼ)れさせることができず、寒さや暑さも害することはできず、禽獣も危害を加えられないというが、それは、彼が実際に火や水に近づいた結果がそうだということではない。安全と危険についてよく見きわめ、禍福のいずれにも心を動かされず、行動について慎重にして、それで何ものも彼を害することができないということである。そこで『天の自然は内面にひそんでいるが、人の作為は外面にあらわれる。徳(もちまえ)は天の自然の側にある。』といわれているが、この天然(てんねん)と人為とのありりかたをよくわきまえ、天然にもとづいてその徳(もちまえ)に身を落ちつけるなら、行きつ戻りつしながら周囲の変化のままに屈伸し、それでいて根本にたちかえって窮極の道を語ることができるであろう。」
〔河伯はまた〕いった、「どういうことを天の自然といい、またどういうことを人の作為というのだろう。」
北海若は答えた、「牛馬がそれぞれ四本の足でいるのは、それこそ天の自然である。馬の頭を綱でからめたり牛の鼻に輪をとおしたりするのは、それこそ人の作為である。だから『人のさかしらによって自然の働きを滅ぼしてはならぬ。ことさらなしわざで自然の命(さだめ)を滅ぼしてはならぬ。本来の徳(もちまえ)を名声のために犠牲にしてはならぬ、』といわれるいる。ただ慎んで〔自然の本来性を〕守ってそれからはずれないようにする、それこそ、真実の道にたちかえるということである。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。
ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。
バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるからだ。
徳(人間にそなわった本性)に至った者は、
火でもけっして熱がらせることはできず、
水でもけっして溺れさせることはできず、
寒さや暑さでもけっして害することができず、
鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、
そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。
安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、
禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、
進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。
故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、
徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。
<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、
<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、
少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、
極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」
(河伯は)言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」
北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。
馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。
故にこう言われている。
『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。
(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。
得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。
(以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、
これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、河伯と北海若(10)天と人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯曰 河伯曰く。
然則何貴於道邪 然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。
北海若曰 北海若曰く。
知道者 必達於理 道を知る者は、必ず理に達す。
達於理者 必明於權 理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。
明於權者 不以物害己 権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめず。
至徳者 火弗能熱 徳に至った者は、火も熱からしむること能(あた)わず、
水弗能溺 寒暑弗能害 水も溺(おぼ)らすこと能わず、寒暑も害すること能わず、
禽獣弗能賊 禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、
非謂其薄之也 其のこれを薄んじるを謂うに非ざるなり。
言察乎安危 寧於禍福 安危を察し、禍福に寧(やす)んじ、
謹於去就 去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、
莫之能害也 これを能(よ)く害するもの莫(な)きを言うなり。
故曰 天在内 人在外 故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、
徳在乎天 徳は天にありと。
知天人之行 天人の行を知り、
本乎天 位乎得 天に本(もと)づきて、得に位すれば、
蹢躅而屈伸 蹢躅(てきちょく)して屈伸し、
反要而語極 要に反(かえ)りて極を語らん。
曰 何謂天 何謂人 (河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。
北海若曰 北海若曰く。
牛馬四足 是謂天 牛馬の四足なる、これを天と謂う。
落馬首 穿牛鼻 是謂人 馬の首を落としめ、牛鼻を穿(うが)つ、これを人と謂う。
故曰 无以人滅天 故に曰く。人を以て天を滅ぼすなかれ。
无以故滅命 故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。
无以得殉名 得を以て名に殉(じゅん)することなかれと。
謹守而勿失 謹み守りて失うことなき、
是謂反其眞 是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽(金谷治 訳)
…………………………………………………………………………………………………………
河伯はいった、「それでは、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若は答えた、「道をわきまえたものは、必ず物事の道理に通ずる。物事の道理に通じたものは、必ず臨機応変の処置に明るくなる。そして、臨機応変に明るいものは、外界の事物のために自分を害されることはない。最高の徳をそなえた人は、火も熱(あつ)がらせることができず、水も溺(おぼ)れさせることができず、寒さや暑さも害することはできず、禽獣も危害を加えられないというが、それは、彼が実際に火や水に近づいた結果がそうだということではない。安全と危険についてよく見きわめ、禍福のいずれにも心を動かされず、行動について慎重にして、それで何ものも彼を害することができないということである。そこで『天の自然は内面にひそんでいるが、人の作為は外面にあらわれる。徳(もちまえ)は天の自然の側にある。』といわれているが、この天然(てんねん)と人為とのありりかたをよくわきまえ、天然にもとづいてその徳(もちまえ)に身を落ちつけるなら、行きつ戻りつしながら周囲の変化のままに屈伸し、それでいて根本にたちかえって窮極の道を語ることができるであろう。」
〔河伯はまた〕いった、「どういうことを天の自然といい、またどういうことを人の作為というのだろう。」
北海若は答えた、「牛馬がそれぞれ四本の足でいるのは、それこそ天の自然である。馬の頭を綱でからめたり牛の鼻に輪をとおしたりするのは、それこそ人の作為である。だから『人のさかしらによって自然の働きを滅ぼしてはならぬ。ことさらなしわざで自然の命(さだめ)を滅ぼしてはならぬ。本来の徳(もちまえ)を名声のために犠牲にしてはならぬ、』といわれるいる。ただ慎んで〔自然の本来性を〕守ってそれからはずれないようにする、それこそ、真実の道にたちかえるということである。」
…………………………………………………………………………………………………………
▽(吹黄 訳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。
ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。
バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるからだ。
徳(人間にそなわった本性)に至った者は、
火でもけっして熱がらせることはできず、
水でもけっして溺れさせることはできず、
寒さや暑さでもけっして害することができず、
鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、
そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。
安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、
禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、
進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。
故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、
徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。
<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、
<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、
少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、
極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」
(河伯は)言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」
北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。
馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。
故にこう言われている。
『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。
(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。
得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。
(以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、
これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
|
|
|
コメント(17)
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 河伯曰 ┃【河伯曰く。】
┃ 然則何貴於道邪 ┃【然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。】
┃ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 知道者 必達於理 ┃【道を知る者は、必ず理に達す。】
┃ 達於理者 必明於權 ┃【理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。】
┃ 明於權者 不以物害己 ┃【権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。
ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。
バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【達】は、「辵(すすむ)+羊(すらすらと子をうむ安産のシンボル)+大」で、「羊のお
産のようにすらすらととおすこと」をあらわします。「とおる・とおす(さしさわりな
く進む。すらすらととおす。また途中でつかえずにいきつく。)」「すらすらと理解す
る。」「すぐれていてなんでもこなす。」
*【理】は、「玉+里(すじみちをつけた土地)」で「宝石の表面に透けて見えるすじめ。」
「ことわり(ものごとのすじみち。」「条理。」「道理。」
*【権】は、「木+雚」でもと木の名。しかし、一般には「棒ばかりの重り」の意に用い、
「バランスに影響する重さ、重さにになう力」の意になります。「バランスをとってそろ
える」意を含みます。
*【害】は、「かぶせる物+口または古(あたま)」で「かぶせてじゃまをし進行をとめるこ
と」を示します。
◆通説では、【河伯曰わく、然らば則ち何ぞ道を貴ぶやと。北海若曰わく、道を知る者は、
必ず理に達す。理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。権に明らかなる者は、物を
以て己を害せしめず。】は〔河伯はいった、「それではどうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若は答えた、「道をわきまえたものは、必ず物事の道理に通ずる。物事の道理に通じ
たものは、必ず臨機応変の処置に明るくなる。そして、臨機応変に明るいものは、外界の
事物のために自分を害されることはない。〕としています。
◇【河伯曰く。然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。北海若曰く。道を知る者は、必ず理に達す。理
に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめ
ず。】は〔河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」北海若は
言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。ものごとの道理を
すんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。バランスをとることに
明るい者は、物によって己を害されることはなくなるのだ。〕としました。
┃▼ 河伯曰 ┃【河伯曰く。】
┃ 然則何貴於道邪 ┃【然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。】
┃ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 知道者 必達於理 ┃【道を知る者は、必ず理に達す。】
┃ 達於理者 必明於權 ┃【理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。】
┃ 明於權者 不以物害己 ┃【権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめず。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。
ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。
バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるからだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【達】は、「辵(すすむ)+羊(すらすらと子をうむ安産のシンボル)+大」で、「羊のお
産のようにすらすらととおすこと」をあらわします。「とおる・とおす(さしさわりな
く進む。すらすらととおす。また途中でつかえずにいきつく。)」「すらすらと理解す
る。」「すぐれていてなんでもこなす。」
*【理】は、「玉+里(すじみちをつけた土地)」で「宝石の表面に透けて見えるすじめ。」
「ことわり(ものごとのすじみち。」「条理。」「道理。」
*【権】は、「木+雚」でもと木の名。しかし、一般には「棒ばかりの重り」の意に用い、
「バランスに影響する重さ、重さにになう力」の意になります。「バランスをとってそろ
える」意を含みます。
*【害】は、「かぶせる物+口または古(あたま)」で「かぶせてじゃまをし進行をとめるこ
と」を示します。
◆通説では、【河伯曰わく、然らば則ち何ぞ道を貴ぶやと。北海若曰わく、道を知る者は、
必ず理に達す。理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。権に明らかなる者は、物を
以て己を害せしめず。】は〔河伯はいった、「それではどうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若は答えた、「道をわきまえたものは、必ず物事の道理に通ずる。物事の道理に通じ
たものは、必ず臨機応変の処置に明るくなる。そして、臨機応変に明るいものは、外界の
事物のために自分を害されることはない。〕としています。
◇【河伯曰く。然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。北海若曰く。道を知る者は、必ず理に達す。理
に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめ
ず。】は〔河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」北海若は
言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。ものごとの道理を
すんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。バランスをとることに
明るい者は、物によって己を害されることはなくなるのだ。〕としました。
●通説では、次のようになっています。
河伯はいった、「それでは、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若は答えた、「道をわきまえたものは、必ず物事の道理に通ずる。物事の道理に通じたものは、必ず臨機応変の処置に明るくなる。そして、臨機応変に明るいものは、外界の事物のために自分を害されることはない。
〇新解釈では、次のようになります。
河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。
ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。
バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるのだ。
【河伯曰】【河伯曰く。】
【然則何貴於道邪】【然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。】
〔河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」〕
──前に、北海若は「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。」と言っていました。それならば、<賤しむ>ことなく、どうして道を<貴ぶ>のか、河伯は疑問に思ったのでしょう。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【知道者 必達於理】【道を知る者は、必ず理に達す。】
〔北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。〕
──「道を知る者」というのは、どこかに行き着いた者のことではありません。常に今という一瞬一瞬を確実に一歩一歩意識的に歩いている者のことです。刻々と新たなものを知っていく者のことです。未知の領域に突入するのを歓迎している者のことです。
「理(ことわり)」とは「ものごとの筋道」です。「必ずものごとの道理(筋道)をすんなりと理解する」というのは、ものごとには原因と過程と結果という「筋道」があるということを理解することができる…と言っているのです。それも「必ず」そうなるというのです。それというのも、「今」の連続でなりたつ道を一歩一歩を意識的に歩いて知っているからです。ジグソーパズルの1ピースずつを残らず拾い上げ、つなげていって、最後に全体像を見ることができるようになるように、理解するのです。卵を温め、ヒナを誕生させ、成長を見守り、成鳥になり飛ぶことを筋道だって知り、理解するのです。また、道は必ず表があったら裏が存在するということを意識的にすんなりと理解するのだ…と言っているようです。
【達於理者 必明於權】【理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。】
〔ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。〕
──ものごとの筋道を理解する者は、必ず全身全霊で受け止めようとするようになるものです。意識が自由に飛翔ようになるために、両翼のバランスをとることに明るくなるとも言えそうです。ポジティブがあれば、ネガティブもあるのを受け入れます。つまり、両極のバランスをとることに明るくなるのです。<善悪><貴賤><大小><多少>など、どちらかに偏ることがなくなり、象徴として<男女>を共有する両性具有者のようだとも言えるかもしれません。
【明於權者 不以物害己】【権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめず。】
〔バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるのだ。〕
──バランスをとることに明るくなった者は、何事が身に起きても一喜一憂することがなくなるのです。そのことはつまり、物によって害されることがなくなり、自分の歩む道を阻止され、じゃまされることがなくなるのだ…と言っています。
道を貴ぶのは、つまるところ、自分の心が向かう方向へと何ものにも害されることなく、じゃまされることなく、自由に歩み続けることができるからだ…ということになるでしょうか。
河伯はいった、「それでは、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若は答えた、「道をわきまえたものは、必ず物事の道理に通ずる。物事の道理に通じたものは、必ず臨機応変の処置に明るくなる。そして、臨機応変に明るいものは、外界の事物のために自分を害されることはない。
〇新解釈では、次のようになります。
河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」
北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。
ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。
バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるのだ。
【河伯曰】【河伯曰く。】
【然則何貴於道邪】【然らば則ち何ぞ道を貴ぶや。】
〔河伯は言った。「それならば則ち、どうして道を貴ぶのだろうか。」〕
──前に、北海若は「道を以てこれを観れば、物に<貴賤>はない。」と言っていました。それならば、<賤しむ>ことなく、どうして道を<貴ぶ>のか、河伯は疑問に思ったのでしょう。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【知道者 必達於理】【道を知る者は、必ず理に達す。】
〔北海若はは言った。「道を知る者は、必ずものごとの道理をすんなりと理解する。〕
──「道を知る者」というのは、どこかに行き着いた者のことではありません。常に今という一瞬一瞬を確実に一歩一歩意識的に歩いている者のことです。刻々と新たなものを知っていく者のことです。未知の領域に突入するのを歓迎している者のことです。
「理(ことわり)」とは「ものごとの筋道」です。「必ずものごとの道理(筋道)をすんなりと理解する」というのは、ものごとには原因と過程と結果という「筋道」があるということを理解することができる…と言っているのです。それも「必ず」そうなるというのです。それというのも、「今」の連続でなりたつ道を一歩一歩を意識的に歩いて知っているからです。ジグソーパズルの1ピースずつを残らず拾い上げ、つなげていって、最後に全体像を見ることができるようになるように、理解するのです。卵を温め、ヒナを誕生させ、成長を見守り、成鳥になり飛ぶことを筋道だって知り、理解するのです。また、道は必ず表があったら裏が存在するということを意識的にすんなりと理解するのだ…と言っているようです。
【達於理者 必明於權】【理に達する者は、必ず権(けん)に明らかなり。】
〔ものごとの道理をすんなりと理解する者は、必ずバランスをとることに明るくなる。〕
──ものごとの筋道を理解する者は、必ず全身全霊で受け止めようとするようになるものです。意識が自由に飛翔ようになるために、両翼のバランスをとることに明るくなるとも言えそうです。ポジティブがあれば、ネガティブもあるのを受け入れます。つまり、両極のバランスをとることに明るくなるのです。<善悪><貴賤><大小><多少>など、どちらかに偏ることがなくなり、象徴として<男女>を共有する両性具有者のようだとも言えるかもしれません。
【明於權者 不以物害己】【権に明らかなる者は、物を以て己を害せしめず。】
〔バランスをとることに明るい者は、物によって己を害されることがなくなるのだ。〕
──バランスをとることに明るくなった者は、何事が身に起きても一喜一憂することがなくなるのです。そのことはつまり、物によって害されることがなくなり、自分の歩む道を阻止され、じゃまされることがなくなるのだ…と言っています。
道を貴ぶのは、つまるところ、自分の心が向かう方向へと何ものにも害されることなく、じゃまされることなく、自由に歩み続けることができるからだ…ということになるでしょうか。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 至徳者 ┃【徳に至った者は、】
┃ 火弗能熱 ┃【火も熱からしむること能(あた)わず、】
┃ 水弗能溺 ┃【水も溺(おぼ)らすこと能わず、】
┃ 寒暑弗能害 ┃【寒暑も害すること能わず、】
┃ 禽獣弗能賊 ┃【禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、】
┃ 非謂其薄之也 ┃【其のこれを薄んずるを謂うに非ざるなり。】
┗━━━━━━━━━┛
徳(人間にそなわった本性)に至った者は、
火でもけっして熱がらせることはできず、
水でもけっして溺れさせることはできず、
寒さや暑さでもけっして害することはできず、
鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、
そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【弗】は、「ひものたれた形+)(印(左右に切り分ける)」で、いやだめだとはらいのけて
強く否定する意。「ず(打ち消しをあらわすことば。」
*【禽獣】は、「とりやけもの。」
*【賊】の「戎」は、「戈(ほこ)+甲(かぶと)」で、「ほこやかぶとでおしつけること。」
【賊】は、「貝+戎」で、「凶器で傷つけて財貨をとること。」「そこなう(きずつける。
害を与える。無法なことをする。」
*【薄】は、「艸+溥(水がたいらに広がること)」で、「草木が間をあけずにせまって生え
ていること。」「間がせまれば、厚さが少なく、うすく平らである。」「うすんずる(軽ん
じる。)」
◆通説では、【至徳ある者は、火も熱からしむること能(あた)わず、水も溺(おぼ)らすこと
能わず、寒暑も害すること能わず、禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、其
のこれを薄(せま/迫)るを謂うには非ざるなり。】は「最高の徳をそなえた人は、火も熱
(あつ)がらせることができず、水も溺(おぼ)れさせることができず、寒さや暑さも害
することはできず、禽獣も危害を加えられないというが、それは、彼が実際に火や水に近
づいた結果がそうだということではない。」としています。
◇【徳に至った者は、火も熱からしむること能(あた)わず、水も溺(おぼ)らすこと能わず、
寒暑も害すること能わず、禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、其のこれを
薄んずるを謂うには非ざるなり。】は「徳(人間にそなわった本性)に至った者は、火でも
けっして熱がらせることはできず、水でもけっして溺れさせることはできず、寒さや暑さ
でもけっして害することができず、鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言う
が、そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。」としました。
┃▼ 至徳者 ┃【徳に至った者は、】
┃ 火弗能熱 ┃【火も熱からしむること能(あた)わず、】
┃ 水弗能溺 ┃【水も溺(おぼ)らすこと能わず、】
┃ 寒暑弗能害 ┃【寒暑も害すること能わず、】
┃ 禽獣弗能賊 ┃【禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、】
┃ 非謂其薄之也 ┃【其のこれを薄んずるを謂うに非ざるなり。】
┗━━━━━━━━━┛
徳(人間にそなわった本性)に至った者は、
火でもけっして熱がらせることはできず、
水でもけっして溺れさせることはできず、
寒さや暑さでもけっして害することはできず、
鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、
そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【弗】は、「ひものたれた形+)(印(左右に切り分ける)」で、いやだめだとはらいのけて
強く否定する意。「ず(打ち消しをあらわすことば。」
*【禽獣】は、「とりやけもの。」
*【賊】の「戎」は、「戈(ほこ)+甲(かぶと)」で、「ほこやかぶとでおしつけること。」
【賊】は、「貝+戎」で、「凶器で傷つけて財貨をとること。」「そこなう(きずつける。
害を与える。無法なことをする。」
*【薄】は、「艸+溥(水がたいらに広がること)」で、「草木が間をあけずにせまって生え
ていること。」「間がせまれば、厚さが少なく、うすく平らである。」「うすんずる(軽ん
じる。)」
◆通説では、【至徳ある者は、火も熱からしむること能(あた)わず、水も溺(おぼ)らすこと
能わず、寒暑も害すること能わず、禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、其
のこれを薄(せま/迫)るを謂うには非ざるなり。】は「最高の徳をそなえた人は、火も熱
(あつ)がらせることができず、水も溺(おぼ)れさせることができず、寒さや暑さも害
することはできず、禽獣も危害を加えられないというが、それは、彼が実際に火や水に近
づいた結果がそうだということではない。」としています。
◇【徳に至った者は、火も熱からしむること能(あた)わず、水も溺(おぼ)らすこと能わず、
寒暑も害すること能わず、禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、其のこれを
薄んずるを謂うには非ざるなり。】は「徳(人間にそなわった本性)に至った者は、火でも
けっして熱がらせることはできず、水でもけっして溺れさせることはできず、寒さや暑さ
でもけっして害することができず、鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言う
が、そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
最高の徳をそなえた人は、火も熱(あつ)がらせることができず、水も溺(おぼ)れさせることができず、寒さや暑さも害することはできず、禽獣も危害を加えられないというが、それは、彼が実際に火や水に近づいた結果がそうだということではない。
〇新解釈では、次のようになります。
徳(人間にそなわった本性)に至った者は、
火でもけっして熱がらせることはできず、
水でもけっして溺れさせることはできず、
寒さや暑さでもけっして害することができず、
鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、
そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。
【至徳者】【徳に至った者は、】
〔徳(人間にそなわった本性)に至った者は、〕
──「徳」というと、成長することによって後から身につける何か(道徳)のような印象があり、その「徳」にはランクのようなものがあり、「至徳」というと「至上(最高)の徳」のように思われるかもしれませんが、そうでしょうか。どうやら後の話からしても、少しニュアンスが違うように思います。「至徳」はシンプルに「徳に至った者」と言っているのではないでしょうか。「徳」は「人間にそなわった本性」で、その人間本来の可能性に至った者を「徳に至った者」と呼ぶのではないかと思います。
【火弗能熱】【火も熱からしむること能(あた)わず、】
【水弗能溺】【水も溺(おぼ)らすこと能わず、】
【寒暑弗能害】【寒暑も害すること能わず、】
〔火でもけっして熱がらせることはできず、〕
〔水でもけっして溺れさせることはできず、〕
〔寒さや暑さでもけっして害することはできず、〕
──『9、齧缺と王倪(2)』に登場した「至人」の描写に似たような下りがあります。
- - - - -
至った人は、精神的に不思議な力をもつことになるのだ。
大きな沢が焚(や)かれても、熱がらせることはできず、
黄河や漢水が凍っても、寒がらせることはできず、
疾走する雷が山を裂き、風が海を揺さぶろうとも、驚かせることはできない。
- - - - -
また、『大宗師篇』に「真人」について次のような下りがあります。
- - - - -
古えの「真人」は、一人きりになっても逆らわず、
成しても肩を張って威勢を示すことはない。
・・・このような者は、過失があっても悔やむことなく、
まさに的を射たことがあっても、得意になるようなこともない。
このような者は、高みに登っても怖れることなく、
水に入っても濡れることなく、火の中に入っても熱がることもない。
- - - - -
これら「至徳者」「至人」「真人」らは、みな「物によって己を害されることがなくなる」ということを、似かよった表現で形容されてきたようです。
【禽獣弗能賊】【禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、】
〔鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、〕
──野生動物が人を区別して危害を加えることがなくなることなどあるのでしょうか。
気療師の神沢瑞至(かんざわただし)さんという方をご存知でしょうか。彼は気の力だけで、動物をリラックスさせ横たわらせ寝かせることができる人なのです。草食動物の群れが何百頭いてもみな横たわらせます。凶暴なバイソンなども200頭まとめてです。それだけではなく、肉食動物のトラやオオカミやヒグマまでも、敵意を喪失させて危害を加えなくなるどころか、腹を見せて寝ころがるくらいリラックスさせる力があるのです。
(https://www.youtube.com/watch?v=A8VQqY5RoEQ)
このように気に敏感に反応する動物は、気配の違う人を襲う気力を失わされてしまうのか、はたまた自ら見分ける直観力を持っているのか、いずれにしても徳に至った人を傷つけることはけっしてしなくなる…ということもありえそうです。
【非謂其薄之也】【其のこれを薄んずるを謂うに非ざるなり。】
〔そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。〕
──これは、それらの外物に無頓着になって、高を括って軽んじていると言っているわけではない…と言っています。では、どうしてなのでしょうか。
最高の徳をそなえた人は、火も熱(あつ)がらせることができず、水も溺(おぼ)れさせることができず、寒さや暑さも害することはできず、禽獣も危害を加えられないというが、それは、彼が実際に火や水に近づいた結果がそうだということではない。
〇新解釈では、次のようになります。
徳(人間にそなわった本性)に至った者は、
火でもけっして熱がらせることはできず、
水でもけっして溺れさせることはできず、
寒さや暑さでもけっして害することができず、
鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、
そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。
【至徳者】【徳に至った者は、】
〔徳(人間にそなわった本性)に至った者は、〕
──「徳」というと、成長することによって後から身につける何か(道徳)のような印象があり、その「徳」にはランクのようなものがあり、「至徳」というと「至上(最高)の徳」のように思われるかもしれませんが、そうでしょうか。どうやら後の話からしても、少しニュアンスが違うように思います。「至徳」はシンプルに「徳に至った者」と言っているのではないでしょうか。「徳」は「人間にそなわった本性」で、その人間本来の可能性に至った者を「徳に至った者」と呼ぶのではないかと思います。
【火弗能熱】【火も熱からしむること能(あた)わず、】
【水弗能溺】【水も溺(おぼ)らすこと能わず、】
【寒暑弗能害】【寒暑も害すること能わず、】
〔火でもけっして熱がらせることはできず、〕
〔水でもけっして溺れさせることはできず、〕
〔寒さや暑さでもけっして害することはできず、〕
──『9、齧缺と王倪(2)』に登場した「至人」の描写に似たような下りがあります。
- - - - -
至った人は、精神的に不思議な力をもつことになるのだ。
大きな沢が焚(や)かれても、熱がらせることはできず、
黄河や漢水が凍っても、寒がらせることはできず、
疾走する雷が山を裂き、風が海を揺さぶろうとも、驚かせることはできない。
- - - - -
また、『大宗師篇』に「真人」について次のような下りがあります。
- - - - -
古えの「真人」は、一人きりになっても逆らわず、
成しても肩を張って威勢を示すことはない。
・・・このような者は、過失があっても悔やむことなく、
まさに的を射たことがあっても、得意になるようなこともない。
このような者は、高みに登っても怖れることなく、
水に入っても濡れることなく、火の中に入っても熱がることもない。
- - - - -
これら「至徳者」「至人」「真人」らは、みな「物によって己を害されることがなくなる」ということを、似かよった表現で形容されてきたようです。
【禽獣弗能賊】【禽獣(きんじゅう)も賊(そこな)うこと能わずとは、】
〔鳥や獣でもけっして傷つけることができない、と言うが、〕
──野生動物が人を区別して危害を加えることがなくなることなどあるのでしょうか。
気療師の神沢瑞至(かんざわただし)さんという方をご存知でしょうか。彼は気の力だけで、動物をリラックスさせ横たわらせ寝かせることができる人なのです。草食動物の群れが何百頭いてもみな横たわらせます。凶暴なバイソンなども200頭まとめてです。それだけではなく、肉食動物のトラやオオカミやヒグマまでも、敵意を喪失させて危害を加えなくなるどころか、腹を見せて寝ころがるくらいリラックスさせる力があるのです。
(https://www.youtube.com/watch?v=A8VQqY5RoEQ)
このように気に敏感に反応する動物は、気配の違う人を襲う気力を失わされてしまうのか、はたまた自ら見分ける直観力を持っているのか、いずれにしても徳に至った人を傷つけることはけっしてしなくなる…ということもありえそうです。
【非謂其薄之也】【其のこれを薄んずるを謂うに非ざるなり。】
〔そもそもこれらを軽んじていると言っているわけではないのだ。〕
──これは、それらの外物に無頓着になって、高を括って軽んじていると言っているわけではない…と言っています。では、どうしてなのでしょうか。
┏━━━━━━━━━┓
┃▼ 言察乎安危 ┃【安危を察し、】
┃ 寧於禍福 ┃【禍福に寧(やす)んじ、】
┃ 謹於去就 ┃【去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、】
┃ 莫之能害也 ┃【これを能(よ)く害するもの莫(な)きを言うなり。】
┗━━━━━━━━━┛
安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、
禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、
進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【察】は、何度も出てきましたが、「宀(いえ)+祭」で「家のすみずみまで、曇りなく清
めること。」転じて「曇りなく目をきかす」意に用います。「曇りなく目を光らせる。」
「曇りなくすみずみまで調べ考える。」
*【寧】は、「丂印(語気ののび出ようとして屈曲したさまで、やはりこちらに落ち着こう
という語気)+[宀(やね)+心+皿](家の中に食器を置き、心を落ち着けてやすんずる
さま)。」「やすらか・やすい(じっと落ち着いている。がさつかない。じっくりしててい
ねいな。)」「やすんずる(落ち着けて静かにさせる。安心させる。」
*【謹】は、「言+[キン](かわいた細かい土砂)」で、「細かく言動に気を配ること。」
「つつしむ(細かに気を配る。)」
*【去就】は、「ある地位から去ることと、とどまること。」「進むことと退くこと。」
「そむくことと、従がうこと。」
◆通説では、「謹む」を「慎む」と同義だとして「慎重に」と訳しています。【安危を察
し、禍福に寧(やす)んじ、去就(きょしゅう)に謹(つつし)みて、これを能(よ)く害する
もの莫(な)きを言うなり。】は「安全と危険についてよく見きわめ、禍福のいずれにも
心を動かされず、行動について慎重にして、それで何ものも彼を害することができない
ということである。」としています。
◇新解釈では、「謹む」は「慎む」とは違い、「細かく気を配る」意としました。【安危
を察し、禍福に寧(やす)んじ、去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、これを能(よ)く害
するもの莫(な)きを言うなり。】は「安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて
観察し、禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。」としました。
┃▼ 言察乎安危 ┃【安危を察し、】
┃ 寧於禍福 ┃【禍福に寧(やす)んじ、】
┃ 謹於去就 ┃【去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、】
┃ 莫之能害也 ┃【これを能(よ)く害するもの莫(な)きを言うなり。】
┗━━━━━━━━━┛
安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、
禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、
進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【察】は、何度も出てきましたが、「宀(いえ)+祭」で「家のすみずみまで、曇りなく清
めること。」転じて「曇りなく目をきかす」意に用います。「曇りなく目を光らせる。」
「曇りなくすみずみまで調べ考える。」
*【寧】は、「丂印(語気ののび出ようとして屈曲したさまで、やはりこちらに落ち着こう
という語気)+[宀(やね)+心+皿](家の中に食器を置き、心を落ち着けてやすんずる
さま)。」「やすらか・やすい(じっと落ち着いている。がさつかない。じっくりしててい
ねいな。)」「やすんずる(落ち着けて静かにさせる。安心させる。」
*【謹】は、「言+[キン](かわいた細かい土砂)」で、「細かく言動に気を配ること。」
「つつしむ(細かに気を配る。)」
*【去就】は、「ある地位から去ることと、とどまること。」「進むことと退くこと。」
「そむくことと、従がうこと。」
◆通説では、「謹む」を「慎む」と同義だとして「慎重に」と訳しています。【安危を察
し、禍福に寧(やす)んじ、去就(きょしゅう)に謹(つつし)みて、これを能(よ)く害する
もの莫(な)きを言うなり。】は「安全と危険についてよく見きわめ、禍福のいずれにも
心を動かされず、行動について慎重にして、それで何ものも彼を害することができない
ということである。」としています。
◇新解釈では、「謹む」は「慎む」とは違い、「細かく気を配る」意としました。【安危
を察し、禍福に寧(やす)んじ、去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、これを能(よ)く害
するもの莫(な)きを言うなり。】は「安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて
観察し、禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。」としました。
●通説では、次のようになっています。
安全と危険についてよく見きわめ、禍福のいずれにも心を動かされず、行動について慎重にして、それで何ものも彼を害することができないということである。
〇新解釈では、次のようになります。
安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、
禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、
進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。
【言察乎安危】【安危を察し、】
〔安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、〕
──安全と危険に気を回して観察するというのは、必ずしも安全なら進み、危険は避けて通るということではないようです。時には危険だと知りつつも進むこともありうるのです。そのための観察なのです。なにがどう危険なのか観察をもとにして心して、必要に応じて道を歩んでいくことになるのではないかと思います。
【寧於禍福】【禍福に寧(やす)んじ、】
〔禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、〕
──「禍福は糾える縄の如し」、「人間万事塞翁が馬」だということを肝に銘じているため、禍福に一喜一憂することなく、心を静かに動じることがないのだと思います。
【謹於去就】【去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、】
〔進退に細かく気を配ることによって、〕
──「去就(きょしゅう)に謹む」というのは「行動について慎重にする」ということとは少し違うように思います。「慎重に」となると、頭の中で考えることの方が勝り、危険や失敗をおそれて避けるあまり、行動については常にネガティブに規制をかけざるをえないイメージが伴います。
それでは新しい未知なることに半分もトライできないことになります。道はつねに新しく未知なることにあふれています。その中で行動の進退を決めていくには、すばやい判断力が求められます。危険や失敗の可能性もあるのですが、それでもたくましく歩を進めていくのです。それは無謀ではないのです。大知を得た人が凡人と違うのは、一度失敗したことは二度と繰り返すことがないという点です。そのため歩を進めるというのは、進めることもあれば積極的に退くことも選択する自由があるのです。それは慎重になるが故にブレーキをかけざるを得ない消極的な状態とはまるで違う行動です。進退をすばやく選択しながら「細心の注意」を怠らないのです。だから「慎重にする」のではなく「細かく気をくばる」…と言っているのです。
【莫之能害也】【これを能(よ)く害するもの莫(な)きを言うなり。】
〔それで彼を害することができないと言っているのだ。〕
──それによって、訪れるいかなる道も、何ものにも阻止されたり、じゃまされたり、傷つけられたりすることがなく、歩んでいけるようになると言える…と言っているのです。
安全と危険についてよく見きわめ、禍福のいずれにも心を動かされず、行動について慎重にして、それで何ものも彼を害することができないということである。
〇新解釈では、次のようになります。
安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、
禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、
進退に細かく気を配ることによって、
それで彼を害することができないと言っているのだ。
【言察乎安危】【安危を察し、】
〔安全と危険を曇りなくすみずみまで目を光らせて観察し、〕
──安全と危険に気を回して観察するというのは、必ずしも安全なら進み、危険は避けて通るということではないようです。時には危険だと知りつつも進むこともありうるのです。そのための観察なのです。なにがどう危険なのか観察をもとにして心して、必要に応じて道を歩んでいくことになるのではないかと思います。
【寧於禍福】【禍福に寧(やす)んじ、】
〔禍福に動じず心を落ち着けて静かにさせ、〕
──「禍福は糾える縄の如し」、「人間万事塞翁が馬」だということを肝に銘じているため、禍福に一喜一憂することなく、心を静かに動じることがないのだと思います。
【謹於去就】【去就(きょしゅう)に謹(つつし)んで、】
〔進退に細かく気を配ることによって、〕
──「去就(きょしゅう)に謹む」というのは「行動について慎重にする」ということとは少し違うように思います。「慎重に」となると、頭の中で考えることの方が勝り、危険や失敗をおそれて避けるあまり、行動については常にネガティブに規制をかけざるをえないイメージが伴います。
それでは新しい未知なることに半分もトライできないことになります。道はつねに新しく未知なることにあふれています。その中で行動の進退を決めていくには、すばやい判断力が求められます。危険や失敗の可能性もあるのですが、それでもたくましく歩を進めていくのです。それは無謀ではないのです。大知を得た人が凡人と違うのは、一度失敗したことは二度と繰り返すことがないという点です。そのため歩を進めるというのは、進めることもあれば積極的に退くことも選択する自由があるのです。それは慎重になるが故にブレーキをかけざるを得ない消極的な状態とはまるで違う行動です。進退をすばやく選択しながら「細心の注意」を怠らないのです。だから「慎重にする」のではなく「細かく気をくばる」…と言っているのです。
【莫之能害也】【これを能(よ)く害するもの莫(な)きを言うなり。】
〔それで彼を害することができないと言っているのだ。〕
──それによって、訪れるいかなる道も、何ものにも阻止されたり、じゃまされたり、傷つけられたりすることがなく、歩んでいけるようになると言える…と言っているのです。
┏━━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 故曰 天在内 人在外 ┃【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、】
┃ 徳在乎天 ┃【徳は天に在りと。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、
徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。
…………………………………………………………………………………………………………
◆通説では、【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、徳は天に在りと。】は〔そこで
『天の自然は内面にひそんでいるが、人の作為は外面にあらわれる。徳(もちまえ)は天
の自然の側にある。』といわれているが、〕としています。
◇【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、徳は天に在りと。】は、〔故にこう言う。
『<天>は内にあり、<人>は外にあり、徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』
と。〕としました。
┃▼ 故曰 天在内 人在外 ┃【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、】
┃ 徳在乎天 ┃【徳は天に在りと。】
┗━━━━━━━━━━━━━┛
故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、
徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。
…………………………………………………………………………………………………………
◆通説では、【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、徳は天に在りと。】は〔そこで
『天の自然は内面にひそんでいるが、人の作為は外面にあらわれる。徳(もちまえ)は天
の自然の側にある。』といわれているが、〕としています。
◇【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、徳は天に在りと。】は、〔故にこう言う。
『<天>は内にあり、<人>は外にあり、徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』
と。〕としました。
●通説では、次のようになっています。
そこで『天の自然は内面にひそんでいるが、人の作為は外面にあらわれる。徳(もちまえ)は天の自然の側にある。』といわれているが、
〇新解釈では、次のようになります。
故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、
徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。
【故曰 天在内 人在外】【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、】
【徳在乎天】【徳は天に在りと。】
〔故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、〕
〔徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。〕
──<天>と言えば、自分の「外」のはるかに離れた空間だと普通の人は考えているのではないでしょうか。それが、<天>は「内」にある…と言われて驚いた人もいるのではないでしょうか。さらには、<人>が「外」にある…と言われて、なお思考が追いつかない人もいるのではないでしょうか。
でも、なかには、<天>は「内」にある…と言われて、はっとして納得した人もいるはずです。<天>は宇宙とも言えます。宇宙には外宇宙と内宇宙があることを知っています。つまり<天>は「内界」にも存在しているのです。一方、<人>は「外界」に左右される存在です。つまり<人>は「外界」に属しているからです。これで、<人>は「外」にある…と言われても納得した人もいるかもしれませんね。
ところが、まだしっくりこない人もいるかもしれません。<人>だって「内」にも存在するのではないか、と。そこで次の言葉が続いているのです。徳(人にそなわった本性)は<天>にある…と言っています。<天>は「内」にあるのですから、つまり、徳(人にそなわった本性)は「内」に存在するということになります。ここで納得する人は増えたことでしょう。
ただし、わかったつもりになるのはまだ早いようです。徳(人にそなわった本性)をどれだけの人が認識し、意識をはっきりもって天に属するもの、天の法則にしたがっているものだと言えるかが問題です。
そこで『天の自然は内面にひそんでいるが、人の作為は外面にあらわれる。徳(もちまえ)は天の自然の側にある。』といわれているが、
〇新解釈では、次のようになります。
故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、
徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。
【故曰 天在内 人在外】【故に曰く、天は内に在り、人は外に在り、】
【徳在乎天】【徳は天に在りと。】
〔故にこう言う。『<天>は内にあり、<人>は外にあり、〕
〔徳(人にそなわった本性)は<天>にある。』と。〕
──<天>と言えば、自分の「外」のはるかに離れた空間だと普通の人は考えているのではないでしょうか。それが、<天>は「内」にある…と言われて驚いた人もいるのではないでしょうか。さらには、<人>が「外」にある…と言われて、なお思考が追いつかない人もいるのではないでしょうか。
でも、なかには、<天>は「内」にある…と言われて、はっとして納得した人もいるはずです。<天>は宇宙とも言えます。宇宙には外宇宙と内宇宙があることを知っています。つまり<天>は「内界」にも存在しているのです。一方、<人>は「外界」に左右される存在です。つまり<人>は「外界」に属しているからです。これで、<人>は「外」にある…と言われても納得した人もいるかもしれませんね。
ところが、まだしっくりこない人もいるかもしれません。<人>だって「内」にも存在するのではないか、と。そこで次の言葉が続いているのです。徳(人にそなわった本性)は<天>にある…と言っています。<天>は「内」にあるのですから、つまり、徳(人にそなわった本性)は「内」に存在するということになります。ここで納得する人は増えたことでしょう。
ただし、わかったつもりになるのはまだ早いようです。徳(人にそなわった本性)をどれだけの人が認識し、意識をはっきりもって天に属するもの、天の法則にしたがっているものだと言えるかが問題です。
┏━━━━━━━━━━┓
┃▼ 知天人之行 ┃【天人の行を知り、】
┃ 本乎天 位乎得 ┃【天に本(もと)づきて、得に位すれば、】
┃ 蹢躅而屈伸 ┃【蹢躅(てきちょく)して屈伸し、】
┃ 反要而語極 ┃【要を反(かえ)りみて極を語らん。】
┗━━━━━━━━━━┛
<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、
<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、
少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【行】は、「十字路」を描いた象形文字。
*【本】は、木の根の太い部分に─印や印をつけて、その部分を指し示した指示文字。
「太い根もとのこと。」「もと(太い木の根。転じて、物事の中心。)」「もと・はじめ
(ものごとのはじめ。おこりはじめ。また、もとで。)」
*【得】は、「彳(いく)+[貝+寸(て)](財貨を取得したさま)」で「いって物を手に入れる
こと。」「える(自分のものにする。)」「える(うまくあたる。つぼにはまる。)」
*【蹢】は、「足+啇(テキ)」の形声文字。「短い距離だけ進む。」「何歩か進む。」
*【躅】は、「足+蜀(くっついて離れない。とまる。)」「じっと立ちどまる。」
*【屈伸】は、「からだをかがめたり、のばしたりすること。」「伸び縮みすること。」
*【要】は、「こし。」「かなめ(要点の要。こしは人体のしめくくりの個所なので、かん
じんなかなめ)」
*【反】は、「かえる・かえす。」「ひるがえる・ひるがえす。」「かえりみる(我が身を
ふりかえって考える。)」
*【極】は、「木+亟(原字は二線の間に人を描き、人の頭の上から足先まで張り伸ばした
こと。)」で「端から端まで張ったしん柱。」「きわみ。」「きわめる・きわまる(やり
つくす。端までいきつく。このうえない。最高の段階。)」
◆通説では、【天人】は、真人、神人、至人などといった人を表していません。【天人の
行(道)を知り】は「この天然(てんねん)と人為とのありりかたをよくわきまえ」として
います。【蹢躅(てきちょく)して】はあしぶみして行きつ戻りつすること。ここでは、
周囲の外界の動きのままに従って、世俗とともに進退すること…と説明しています。
【天人の行(道)を知り、天に本(もと)づきて得(徳)に位すれば、蹢躅(てきちょく)して
屈伸し、要に反(かえ)りて極を語らん。】は[この天然(てんねん)と人為とのありりか
たをよくわきまえ、天然にもとづいてその徳(もちまえ)に身を落ちつけるなら、行きつ
戻りつしながら周囲の変化のままに屈伸し、それでいて根本にたちかえって窮極の道を
語ることができるであろう。」]としています。
◇新解釈では、【天人】は、真人、神人、至人などと同様に人を表していると解釈しまし
た。【蹢躅(てきちょく)して】は、「行きつ戻りつすること」ではなく、「少し進んで
は止まること」で「戻る」とは言っておらず、ましてや「世俗とともに進退すること」
ではないと解釈しました。【蹢躅(てきちょく)して屈伸し、要に反(かえ)りては極を語
らん。】とは、<人>が<天>とコラボしてとる行為と解釈しました。
【天人の行を知り、天に本(もと)づきて、得に位すれば、蹢躅(てきちょく)して屈伸し
要に反(かえ)りては極を語らん。】は〔<(天と人とが一体になった) 天人>はゆく道
を知り、<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るなら
ば、少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)の
ことを語ることになるだろう。」〕としました。
┃▼ 知天人之行 ┃【天人の行を知り、】
┃ 本乎天 位乎得 ┃【天に本(もと)づきて、得に位すれば、】
┃ 蹢躅而屈伸 ┃【蹢躅(てきちょく)して屈伸し、】
┃ 反要而語極 ┃【要を反(かえ)りみて極を語らん。】
┗━━━━━━━━━━┛
<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、
<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、
少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」
…………………………………………………………………………………………………………
*【行】は、「十字路」を描いた象形文字。
*【本】は、木の根の太い部分に─印や印をつけて、その部分を指し示した指示文字。
「太い根もとのこと。」「もと(太い木の根。転じて、物事の中心。)」「もと・はじめ
(ものごとのはじめ。おこりはじめ。また、もとで。)」
*【得】は、「彳(いく)+[貝+寸(て)](財貨を取得したさま)」で「いって物を手に入れる
こと。」「える(自分のものにする。)」「える(うまくあたる。つぼにはまる。)」
*【蹢】は、「足+啇(テキ)」の形声文字。「短い距離だけ進む。」「何歩か進む。」
*【躅】は、「足+蜀(くっついて離れない。とまる。)」「じっと立ちどまる。」
*【屈伸】は、「からだをかがめたり、のばしたりすること。」「伸び縮みすること。」
*【要】は、「こし。」「かなめ(要点の要。こしは人体のしめくくりの個所なので、かん
じんなかなめ)」
*【反】は、「かえる・かえす。」「ひるがえる・ひるがえす。」「かえりみる(我が身を
ふりかえって考える。)」
*【極】は、「木+亟(原字は二線の間に人を描き、人の頭の上から足先まで張り伸ばした
こと。)」で「端から端まで張ったしん柱。」「きわみ。」「きわめる・きわまる(やり
つくす。端までいきつく。このうえない。最高の段階。)」
◆通説では、【天人】は、真人、神人、至人などといった人を表していません。【天人の
行(道)を知り】は「この天然(てんねん)と人為とのありりかたをよくわきまえ」として
います。【蹢躅(てきちょく)して】はあしぶみして行きつ戻りつすること。ここでは、
周囲の外界の動きのままに従って、世俗とともに進退すること…と説明しています。
【天人の行(道)を知り、天に本(もと)づきて得(徳)に位すれば、蹢躅(てきちょく)して
屈伸し、要に反(かえ)りて極を語らん。】は[この天然(てんねん)と人為とのありりか
たをよくわきまえ、天然にもとづいてその徳(もちまえ)に身を落ちつけるなら、行きつ
戻りつしながら周囲の変化のままに屈伸し、それでいて根本にたちかえって窮極の道を
語ることができるであろう。」]としています。
◇新解釈では、【天人】は、真人、神人、至人などと同様に人を表していると解釈しまし
た。【蹢躅(てきちょく)して】は、「行きつ戻りつすること」ではなく、「少し進んで
は止まること」で「戻る」とは言っておらず、ましてや「世俗とともに進退すること」
ではないと解釈しました。【蹢躅(てきちょく)して屈伸し、要に反(かえ)りては極を語
らん。】とは、<人>が<天>とコラボしてとる行為と解釈しました。
【天人の行を知り、天に本(もと)づきて、得に位すれば、蹢躅(てきちょく)して屈伸し
要に反(かえ)りては極を語らん。】は〔<(天と人とが一体になった) 天人>はゆく道
を知り、<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るなら
ば、少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)の
ことを語ることになるだろう。」〕としました。
●通説では、次のようになっています。
この天然(てんねん)と人為とのありりかたをよくわきまえ、天然にもとづいてその徳(もちまえ)に身を落ちつけるなら、行きつ戻りつしながら周囲の変化のままに屈伸し、それでいて根本にたちかえって窮極の道を語ることができるであろう。」
〇新解釈では、次のようになります。
<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、
<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、
少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」
【知天人之行】【天人の行を知り、】
〔<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、〕
──<天人>は、<天>と<人>と区別しているのではなく、<天>と一体となった<人>のことを表しているのだと思います。
これは、ヒンドゥー教またはインド哲学におけるアートマン(意識の最も深い内側にある個の根源を意味する真我)は、ブラフマン(宇宙の根源)と同一(等価)であるとされている概念と近い感覚なのではないかと想像します。
「行」は、<天>の道と<人>の道とが交差する十字路のようになってできあがる道のことを表しているのではないかと思います。
そうした<天人>としてゆく道を知りながら…と言っているようですね。
【本乎天 位乎得】【天に本(もと)づきて、得に位すれば、】
〔<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、〕
──『19、河伯と北海若(9)終と始』の中では、「(外なる)形に位せず」と言っていましたが、ではどこに「位すればいいのか(自分の居場所として居ればいいのか)」という問題に、「(内なる)得に位すれば」と言っているようです。
では、「(内なる)得」とは、どんな所(境地)なのでしょうか。
『4、寓言(2)道は通じて<一>となる』においてこんな説明がありました。
- - - - -
不用のままに、諸々の庸(あるがまま)をそっくりな仮の宿として身をおくのだ。
庸(あるがまま)であると、その用(役に立つ必要な働き)をなす。
用(役に立つ必要な働き)をなすと、通(留まることがなく進めること)になる。
通(留まることがなく進めること)になると、得(まさにツボにはまること)となる。
得(まさにツボにはまること)となるように、<一つにまとめながら>向かうことが、
限りなく近いことだ。
- - - - -
おそらく、この話の中の「得」と関係しているものと思われます。ここでは、その前に、<天人>ともなると常に<天>に根ざしていることは当然のことのようです。そうした上で「得(ツボにはまった境地)」に、本来の自分が居るべき場所として居ることができれば…と言っているようです。
【蹢躅而屈伸】【蹢躅(てきちょく)して屈伸し、】
【反要而語極】【要を反(かえ)りみて極を語らん。】
〔少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、〕
〔我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」〕
──「蹢躅(てきちょく)」は、通説のように「行きつ戻りつ」ではなく、「少し進んでは止まる」といっているのがミソです。一般的な時計の秒針のように、一秒進んだら止まり、また一秒進んだら止まるといった意識状態ではないかと想像します。<天>は連続して動いています。動物など自然界においては、「止まる」ことなく進み続けていくのでしょうが、<天人>は進むことには逆らわず、ましてや戻ることなく進んでいるのですが「止まる」必要があるのです。それは意識の記憶に刻む必要があるからではないかと想像しています。
そのような進み方をしながら、「意識を屈伸させる」というのは、自分の意識を小さくしたり大きくしたりして、いろんな角度、尺度から身の丈を計っているのではないかと考えられます。伸び縮みすることで、内からと外からの視点をもつことになる…と言っているのでしょう。
「我が身の要(かなめ)」は頭にあるのではなく、<人>の中心、つまり内なる<天>の意志とでも言うような〔魂の〕中心にあり、それに常に意識の焦点を合わせるようにふりかえって考えてみては、「極」のことを語ることになる…と言っているようです。「極」とは、内なる中心から周辺に向かって派生する隅から隅までのあらゆる情報のことで、そこにも意識を届かせて語ることになる…と言っているようです。
この天然(てんねん)と人為とのありりかたをよくわきまえ、天然にもとづいてその徳(もちまえ)に身を落ちつけるなら、行きつ戻りつしながら周囲の変化のままに屈伸し、それでいて根本にたちかえって窮極の道を語ることができるであろう。」
〇新解釈では、次のようになります。
<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、
<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、
少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、
我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」
【知天人之行】【天人の行を知り、】
〔<(天と人とが一体になった)天人>のゆく道を知り、〕
──<天人>は、<天>と<人>と区別しているのではなく、<天>と一体となった<人>のことを表しているのだと思います。
これは、ヒンドゥー教またはインド哲学におけるアートマン(意識の最も深い内側にある個の根源を意味する真我)は、ブラフマン(宇宙の根源)と同一(等価)であるとされている概念と近い感覚なのではないかと想像します。
「行」は、<天>の道と<人>の道とが交差する十字路のようになってできあがる道のことを表しているのではないかと思います。
そうした<天人>としてゆく道を知りながら…と言っているようですね。
【本乎天 位乎得】【天に本(もと)づきて、得に位すれば、】
〔<天>に根ざして、得(ツボにはまった境地)に(自分の居場所として)居るならば、〕
──『19、河伯と北海若(9)終と始』の中では、「(外なる)形に位せず」と言っていましたが、ではどこに「位すればいいのか(自分の居場所として居ればいいのか)」という問題に、「(内なる)得に位すれば」と言っているようです。
では、「(内なる)得」とは、どんな所(境地)なのでしょうか。
『4、寓言(2)道は通じて<一>となる』においてこんな説明がありました。
- - - - -
不用のままに、諸々の庸(あるがまま)をそっくりな仮の宿として身をおくのだ。
庸(あるがまま)であると、その用(役に立つ必要な働き)をなす。
用(役に立つ必要な働き)をなすと、通(留まることがなく進めること)になる。
通(留まることがなく進めること)になると、得(まさにツボにはまること)となる。
得(まさにツボにはまること)となるように、<一つにまとめながら>向かうことが、
限りなく近いことだ。
- - - - -
おそらく、この話の中の「得」と関係しているものと思われます。ここでは、その前に、<天人>ともなると常に<天>に根ざしていることは当然のことのようです。そうした上で「得(ツボにはまった境地)」に、本来の自分が居るべき場所として居ることができれば…と言っているようです。
【蹢躅而屈伸】【蹢躅(てきちょく)して屈伸し、】
【反要而語極】【要を反(かえ)りみて極を語らん。】
〔少し進んでは立ち止まるのを繰り返しながら、意識を屈伸(伸び縮み)させて、〕
〔我が身の要(内なる天のかなめ)をふりかえって考えてみては、極(内なる天のきわみ)のことを語ることになるだろう。」〕
──「蹢躅(てきちょく)」は、通説のように「行きつ戻りつ」ではなく、「少し進んでは止まる」といっているのがミソです。一般的な時計の秒針のように、一秒進んだら止まり、また一秒進んだら止まるといった意識状態ではないかと想像します。<天>は連続して動いています。動物など自然界においては、「止まる」ことなく進み続けていくのでしょうが、<天人>は進むことには逆らわず、ましてや戻ることなく進んでいるのですが「止まる」必要があるのです。それは意識の記憶に刻む必要があるからではないかと想像しています。
そのような進み方をしながら、「意識を屈伸させる」というのは、自分の意識を小さくしたり大きくしたりして、いろんな角度、尺度から身の丈を計っているのではないかと考えられます。伸び縮みすることで、内からと外からの視点をもつことになる…と言っているのでしょう。
「我が身の要(かなめ)」は頭にあるのではなく、<人>の中心、つまり内なる<天>の意志とでも言うような〔魂の〕中心にあり、それに常に意識の焦点を合わせるようにふりかえって考えてみては、「極」のことを語ることになる…と言っているようです。「極」とは、内なる中心から周辺に向かって派生する隅から隅までのあらゆる情報のことで、そこにも意識を届かせて語ることになる…と言っているようです。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃▼ 曰 何謂天 何謂人 ┃【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。】
┃ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 牛馬四足 是謂天 ┃【牛馬の四足なる、これを天と謂う。】
┃ 落馬首 穿牛鼻 ┃【馬の首を落(らく)し、牛鼻を穿(うが)つ、】
┃ 是謂人 ┃【これを人と謂う。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
(河伯は)言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」
北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。
馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。
…………………………………………………………………………………………………………
*【落】は、「艸+洛」で「植物の葉がぽろりとおちること。」「おちる(つかえて止まっ
ていた物がぽろりとおちる。上から下へおちる。)」
*【穿】は、「穴(あな)+牙(きば)」で、「牙で穴をあけてとおすこと。」
◆通説では、【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。北海若曰く。牛馬の四足な
る、是れを天と謂う。馬首を落(から/絡)め、牛鼻を穿(うが)つ、是れを人と謂う。】は
〔〔河伯はまた〕いった、「どういうことを天の自然といい、またどういうことを人の作
為というのだろう。」北海若は答えた、「牛馬がそれぞれ四本の足でいるのは、それこそ
天の自然である。馬の頭を綱でからめたり牛の鼻に輪をとおしたりするのは、それこそ人
の作為である。〕としています。
◇【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。北海若曰く。牛馬の四足なる、是を天
と謂う。馬の首を落(らく)し、牛鼻を穿(うが)つ、是を人と謂う。】は〔(河伯は)
言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。北海若は言
った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に
穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。〕としました。
┃▼ 曰 何謂天 何謂人 ┃【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。】
┃ 北海若曰 ┃【北海若曰く。】
┃ 牛馬四足 是謂天 ┃【牛馬の四足なる、これを天と謂う。】
┃ 落馬首 穿牛鼻 ┃【馬の首を落(らく)し、牛鼻を穿(うが)つ、】
┃ 是謂人 ┃【これを人と謂う。】
┗━━━━━━━━━━━━┛
(河伯は)言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」
北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。
馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。
…………………………………………………………………………………………………………
*【落】は、「艸+洛」で「植物の葉がぽろりとおちること。」「おちる(つかえて止まっ
ていた物がぽろりとおちる。上から下へおちる。)」
*【穿】は、「穴(あな)+牙(きば)」で、「牙で穴をあけてとおすこと。」
◆通説では、【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。北海若曰く。牛馬の四足な
る、是れを天と謂う。馬首を落(から/絡)め、牛鼻を穿(うが)つ、是れを人と謂う。】は
〔〔河伯はまた〕いった、「どういうことを天の自然といい、またどういうことを人の作
為というのだろう。」北海若は答えた、「牛馬がそれぞれ四本の足でいるのは、それこそ
天の自然である。馬の頭を綱でからめたり牛の鼻に輪をとおしたりするのは、それこそ人
の作為である。〕としています。
◇【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。北海若曰く。牛馬の四足なる、是を天
と謂う。馬の首を落(らく)し、牛鼻を穿(うが)つ、是を人と謂う。】は〔(河伯は)
言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。北海若は言
った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に
穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。〕としました。
●通説では、次のようになっています。
〔河伯はまた〕いった、「どういうことを天の自然といい、またどういうことを人の作為というのだろう。」
北海若は答えた、「牛馬がそれぞれ四本の足でいるのは、それこそ天の自然である。馬の頭を綱でからめたり牛の鼻に輪をとおしたりするのは、それこそ人の作為である。
〇新解釈では、次のようになります。
(河伯は)言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」
北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。
馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。
【曰 何謂天 何謂人】【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。】
〔 (河伯は)言った。〕
〔「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」〕
──河伯は、それまでの北海若の説明だけでは、<天>と<人>の概念をつかみきれなかったのでしょうか、それを確かめるために質問したようです。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【牛馬四足 是謂天】【牛馬の四足なる、これを天と謂う。】
〔北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。〕
──<天>は「内」にあると言いながら、わかりやすくするために「外」のもので答えているようですね。「牛馬が四本足でいること」とは、与えられているままの自然の姿ということですね。「これを<天>と言う」としています。
そこから類推すると、<人>の中でも、生まれながらの自然の姿は<天>と言えるかもしれません。二本足であること、呼吸すること、食べること、排便すること、寝ること、歩くこと、手作業ができること、しゃべれること、考えれること、泣くこと、怒ること、笑うことなどの他、自由意志がもてるこも、先天的な状態、機能、能力は、みな<天>と言えるかもしれません。
【落馬首 穿牛鼻 是謂人】【馬の首を落(らく)し、牛鼻を穿(うが)つ、これを人と謂う。】
〔馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。〕
──一方、「馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと」とは、自然ではありえない人為で手を及ぼすことができる後天的な機能、能力のことですね。「これを<人>と言う」としています。
そこから類推すると、自分の内の潜在的な天性のもののほとんどに、後天的に手を加えることができるようですね。これらみな<人>と言えるかもしれません。
ここで、この説明の裏で、「無為自然」をモットーとする考えからしたら、<人>の作為は一切するべきではなく、<天>のままにしておくことをよしとすることを言っていると解釈する人がいると思うのですが、果してそうでしょうか。
<天>の中に「自由意志がもてること」が含まれているとしましたが、人為があったとしても、<天>を生かすも殺すもその<人>次第で、馬を移動手段として手なずけ乗りこなし、牛を農作業に使いこなすことも可能で、<人>と<天>とのコラボの実現を示唆しているものだとみなすことができないでしょうか。
そこで、<天>を損なうことなく生かすための秘訣を次に述べているのだと思います。
〔河伯はまた〕いった、「どういうことを天の自然といい、またどういうことを人の作為というのだろう。」
北海若は答えた、「牛馬がそれぞれ四本の足でいるのは、それこそ天の自然である。馬の頭を綱でからめたり牛の鼻に輪をとおしたりするのは、それこそ人の作為である。
〇新解釈では、次のようになります。
(河伯は)言った。「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」
北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。
馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。
【曰 何謂天 何謂人】【(河伯)曰く。何をか天と謂い、何をか人と謂う。】
〔 (河伯は)言った。〕
〔「どういうことを<天>と言い、どういうことを<人>と言うのか。」〕
──河伯は、それまでの北海若の説明だけでは、<天>と<人>の概念をつかみきれなかったのでしょうか、それを確かめるために質問したようです。
【北海若曰】【北海若曰く。】
【牛馬四足 是謂天】【牛馬の四足なる、これを天と謂う。】
〔北海若は言った。「牛馬が四本足でいること、これを<天>と言う。〕
──<天>は「内」にあると言いながら、わかりやすくするために「外」のもので答えているようですね。「牛馬が四本足でいること」とは、与えられているままの自然の姿ということですね。「これを<天>と言う」としています。
そこから類推すると、<人>の中でも、生まれながらの自然の姿は<天>と言えるかもしれません。二本足であること、呼吸すること、食べること、排便すること、寝ること、歩くこと、手作業ができること、しゃべれること、考えれること、泣くこと、怒ること、笑うことなどの他、自由意志がもてるこも、先天的な状態、機能、能力は、みな<天>と言えるかもしれません。
【落馬首 穿牛鼻 是謂人】【馬の首を落(らく)し、牛鼻を穿(うが)つ、これを人と謂う。】
〔馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと、これを<人>と言う。〕
──一方、「馬の首を落ち着かせ、牛の鼻に穴をあけ輪を通すこと」とは、自然ではありえない人為で手を及ぼすことができる後天的な機能、能力のことですね。「これを<人>と言う」としています。
そこから類推すると、自分の内の潜在的な天性のもののほとんどに、後天的に手を加えることができるようですね。これらみな<人>と言えるかもしれません。
ここで、この説明の裏で、「無為自然」をモットーとする考えからしたら、<人>の作為は一切するべきではなく、<天>のままにしておくことをよしとすることを言っていると解釈する人がいると思うのですが、果してそうでしょうか。
<天>の中に「自由意志がもてること」が含まれているとしましたが、人為があったとしても、<天>を生かすも殺すもその<人>次第で、馬を移動手段として手なずけ乗りこなし、牛を農作業に使いこなすことも可能で、<人>と<天>とのコラボの実現を示唆しているものだとみなすことができないでしょうか。
そこで、<天>を損なうことなく生かすための秘訣を次に述べているのだと思います。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 故曰 ┃【故に曰く。】
┃ 无以人滅天 ┃【人を以て天を滅ぼすなかれ。】
┃ 无以故滅命 ┃【故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。】
┃ 无以得殉名 ┃【得を以て名に殉(じゅん)することなかれと。】
┗━━━━━━━━┛
故にこう言われている。
『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。
(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。
得(ツボにはまる境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。
…………………………………………………………………………………………………………
*【滅】は、「水+烕(刃物で火種を切って火をけすこと)」で、「水をかけ火をけし、また
は見えなくすること。」「ほろぼす。」「きえる。」
*【故】は、「攴(動詞の記号)+古(かたくなった頭骨、または、かたいかぶと)」で、「か
たまって固定した事実になること。」
*【命】は、「A(あつめる。)+人+口」で、「人々を集めて口で意向を表明し伝えるさ
ま。」「みこと(神や目上の人からのさしず・いいつけ。お告げ。)」「天からの使命。」
「天からの運命。」「いのち(天から授かった生きる定め。」
*【殉】は、「歹(しぬ)+旬(十日にわたり、ひとめぐりすること)」で、「ぐるりと主君を
とりまいて死ぬこと。」「主君が死んだときにそれにしたがって臣下が死に、主君の死体
をとりまいてうめられる。」「したがう(命がけで他にしたがう。)」
◆通説では、【故】は事と同じ。ことさらなしわざ。…と説明しています。
【故に曰く。人を以て天を滅ぼすなかれ。故(こと)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。得
(徳)を以て名に殉(じゅん)することなかれと。】は〔だから『人のさかしらによって自
然の働きを滅ぼしてはならぬ。ことさらなしわざで自然の命(さだめ)を滅ぼしてはなら
ぬ。本来の徳(もちまえ)を名声のために犠牲にしてはならぬ、』といわれるいる。」〕
としています。
◇新解釈では、【故】は「かたまって固定した事実になること」という意から「固定概念」
としました。
【故に曰く。人を以て天を滅ぼすなかれ。故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。得を
以て名に殉(じゅん)することなかれと。】は「故にこう言われている。『<人>(の作
為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。(人の)固定概念によって、命(天からの使
命)を滅ぼすことなかれ。得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲に
なることなかれ。』と。」としました。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 謹守而勿失 ┃【謹み守りて失うことなき、】
┃ 是謂反其眞 ┃【是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。】
┗━━━━━━━━┛
(以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、
これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謹】は、「言+[キン](かわいた細かい土砂)」で、「細かく言動に気を配ること。」
「つつしむ(細かに気を配る。)」
*【守】は、「宀(やね)+寸(て)」で、「手で屋根の下に囲いこんでまもるさま。」「ま
もる(手中におさめて離さないようにする。)」「まもり(失わないように番をする。ま
た、その備え。)「まもる(心構えをいつまでもかえないで、保つ。また、まもって変え
ないみさお。)」
*【失】は、「手+乀印(よこへ引く)」で、「手中のものがするりと横へ抜け去ること。」
「うしなう(とり逃がす。するりとなくすること。なくしたもの。」「うしなう(やるべき
仕事や時期、道筋などを見のがす。)」
*【眞】は、「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさま。」「まこと
(うそや欠けめがない。充実している。)」「欠けめなく充実した状態。」
◆通説では、【謹み守りて失うことなき、是れを其の真(しん)に反(かえ)ると謂うと。】
は〔ただ慎んで〔自然の本来性を〕守ってそれからはずれないようにする、それこそ、
真実の道にたちかえるということである。」〕としています。
◇【謹み守りて失うことなき、是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。】は〔(以上のこ
とに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、これこそを、真(欠けめな
く充実した状態)にかえると言えるのだ。」〕としました。
┃▼ 故曰 ┃【故に曰く。】
┃ 无以人滅天 ┃【人を以て天を滅ぼすなかれ。】
┃ 无以故滅命 ┃【故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。】
┃ 无以得殉名 ┃【得を以て名に殉(じゅん)することなかれと。】
┗━━━━━━━━┛
故にこう言われている。
『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。
(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。
得(ツボにはまる境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。
…………………………………………………………………………………………………………
*【滅】は、「水+烕(刃物で火種を切って火をけすこと)」で、「水をかけ火をけし、また
は見えなくすること。」「ほろぼす。」「きえる。」
*【故】は、「攴(動詞の記号)+古(かたくなった頭骨、または、かたいかぶと)」で、「か
たまって固定した事実になること。」
*【命】は、「A(あつめる。)+人+口」で、「人々を集めて口で意向を表明し伝えるさ
ま。」「みこと(神や目上の人からのさしず・いいつけ。お告げ。)」「天からの使命。」
「天からの運命。」「いのち(天から授かった生きる定め。」
*【殉】は、「歹(しぬ)+旬(十日にわたり、ひとめぐりすること)」で、「ぐるりと主君を
とりまいて死ぬこと。」「主君が死んだときにそれにしたがって臣下が死に、主君の死体
をとりまいてうめられる。」「したがう(命がけで他にしたがう。)」
◆通説では、【故】は事と同じ。ことさらなしわざ。…と説明しています。
【故に曰く。人を以て天を滅ぼすなかれ。故(こと)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。得
(徳)を以て名に殉(じゅん)することなかれと。】は〔だから『人のさかしらによって自
然の働きを滅ぼしてはならぬ。ことさらなしわざで自然の命(さだめ)を滅ぼしてはなら
ぬ。本来の徳(もちまえ)を名声のために犠牲にしてはならぬ、』といわれるいる。」〕
としています。
◇新解釈では、【故】は「かたまって固定した事実になること」という意から「固定概念」
としました。
【故に曰く。人を以て天を滅ぼすなかれ。故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。得を
以て名に殉(じゅん)することなかれと。】は「故にこう言われている。『<人>(の作
為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。(人の)固定概念によって、命(天からの使
命)を滅ぼすことなかれ。得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲に
なることなかれ。』と。」としました。
┏━━━━━━━━┓
┃▼ 謹守而勿失 ┃【謹み守りて失うことなき、】
┃ 是謂反其眞 ┃【是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。】
┗━━━━━━━━┛
(以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、
これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。
…………………………………………………………………………………………………………
*【謹】は、「言+[キン](かわいた細かい土砂)」で、「細かく言動に気を配ること。」
「つつしむ(細かに気を配る。)」
*【守】は、「宀(やね)+寸(て)」で、「手で屋根の下に囲いこんでまもるさま。」「ま
もる(手中におさめて離さないようにする。)」「まもり(失わないように番をする。ま
た、その備え。)「まもる(心構えをいつまでもかえないで、保つ。また、まもって変え
ないみさお。)」
*【失】は、「手+乀印(よこへ引く)」で、「手中のものがするりと横へ抜け去ること。」
「うしなう(とり逃がす。するりとなくすること。なくしたもの。」「うしなう(やるべき
仕事や時期、道筋などを見のがす。)」
*【眞】は、「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさま。」「まこと
(うそや欠けめがない。充実している。)」「欠けめなく充実した状態。」
◆通説では、【謹み守りて失うことなき、是れを其の真(しん)に反(かえ)ると謂うと。】
は〔ただ慎んで〔自然の本来性を〕守ってそれからはずれないようにする、それこそ、
真実の道にたちかえるということである。」〕としています。
◇【謹み守りて失うことなき、是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。】は〔(以上のこ
とに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、これこそを、真(欠けめな
く充実した状態)にかえると言えるのだ。」〕としました。
●通説では、次のようになっています。
だから『人のさかしらによって自然の働きを滅ぼしてはならぬ。ことさらなしわざで自然の命(さだめ)を滅ぼしてはならぬ。本来の徳(もちまえ)を名声のために犠牲にしてはならぬ、』といわれるいる。ただ慎んで〔自然の本来性を〕守ってそれからはずれないようにする、それこそ、真実の道にたちかえるということである。」
〇新解釈では、次のようになります。
故にこう言われている。
『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。
(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。
得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。
(以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、
これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。」
【故曰】【故に曰く。】
〔故にこう言われている。〕
──<天>を生かすも殺すも<人>次第なのです。「だからこう言われている。」と、<天>を生かすための秘訣を述べています。
【无以人滅天】【人を以て天を滅ぼすなかれ。】
〔『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。〕
──<人>は時に、「角を矯(た)めて牛を殺す」ようなことをしているのです。「泣くこと」や「怒ること」は良くないと、感情を抑圧するようなこともあるのです。「徳性」を高めようと「道徳」によって、本来の「徳」を台無しにしていることもあるのです。このように、<人>の作為によって<天>を滅ぼす可能性があるため、そんなことがないように…と言っているのでしょう。
【无以故滅命】【故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。】
〔(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。〕
──「<人>は死によって終わる」という固定概念によって、幾度かの生のチャンスがあるかもしれない「命」の神秘を信じることができずに、今世の生において、「命(天から与えられている使命)」を果たせずに終わる可能性があるのです。だからそんなことがないように…と言っているのでしょう。
【无以得殉名】【得を以て名に殉(じゅん)することなかれと。】
〔得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。〕
──先に説明したように、「得」とは、不用→庸→用→通→「得」の過程を踏んで至る境地で、そこで他者からの名声を得ることになって有頂天になったとしたら、せっかくの「得」の境地も台無しになってしまう可能性があるのです。だから、そんなことにならないように…と言っているのでしょう。
【謹守而勿失】【謹み守りて失うことなき、】
【是謂反其眞】【是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。】
〔 (以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、〕
〔これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。〕
──以上の注意事項に細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、虚(からっぽ)になったり満ちたりする「外」の形に振り回されることなく、常に「内なる本性」は死生の定めを超えて継続し、「真(欠けめなく充実した状態)」にかえることができると言える…と言っているようです。
だから『人のさかしらによって自然の働きを滅ぼしてはならぬ。ことさらなしわざで自然の命(さだめ)を滅ぼしてはならぬ。本来の徳(もちまえ)を名声のために犠牲にしてはならぬ、』といわれるいる。ただ慎んで〔自然の本来性を〕守ってそれからはずれないようにする、それこそ、真実の道にたちかえるということである。」
〇新解釈では、次のようになります。
故にこう言われている。
『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。
(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。
得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。
(以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、
これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。」
【故曰】【故に曰く。】
〔故にこう言われている。〕
──<天>を生かすも殺すも<人>次第なのです。「だからこう言われている。」と、<天>を生かすための秘訣を述べています。
【无以人滅天】【人を以て天を滅ぼすなかれ。】
〔『<人>(の作為)によって、<天>を滅ぼすことなかれ。〕
──<人>は時に、「角を矯(た)めて牛を殺す」ようなことをしているのです。「泣くこと」や「怒ること」は良くないと、感情を抑圧するようなこともあるのです。「徳性」を高めようと「道徳」によって、本来の「徳」を台無しにしていることもあるのです。このように、<人>の作為によって<天>を滅ぼす可能性があるため、そんなことがないように…と言っているのでしょう。
【无以故滅命】【故(こ)を以て命(めい)を滅ぼすなかれ。】
〔(人の)固定概念によって、命(天からの使命)を滅ぼすことなかれ。〕
──「<人>は死によって終わる」という固定概念によって、幾度かの生のチャンスがあるかもしれない「命」の神秘を信じることができずに、今世の生において、「命(天から与えられている使命)」を果たせずに終わる可能性があるのです。だからそんなことがないように…と言っているのでしょう。
【无以得殉名】【得を以て名に殉(じゅん)することなかれと。】
〔得(ツボにはまった境地になること)によって、名声の犠牲になることなかれ。』と。〕
──先に説明したように、「得」とは、不用→庸→用→通→「得」の過程を踏んで至る境地で、そこで他者からの名声を得ることになって有頂天になったとしたら、せっかくの「得」の境地も台無しになってしまう可能性があるのです。だから、そんなことにならないように…と言っているのでしょう。
【謹守而勿失】【謹み守りて失うことなき、】
【是謂反其眞】【是、其の真(しん)に反(かえ)ると謂う。】
〔 (以上のことに)細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、〕
〔これこそを、真(欠けめなく充実した状態)にかえると言えるのだ。〕
──以上の注意事項に細かく気を配り、それを守り、見失うことがなければ、虚(からっぽ)になったり満ちたりする「外」の形に振り回されることなく、常に「内なる本性」は死生の定めを超えて継続し、「真(欠けめなく充実した状態)」にかえることができると言える…と言っているようです。
お知らせ
随分時間が経過しましたが、ついに荘子の本を出版発行することになりました。
題名は「タオの風 〜字源解釈による新説と自由展開で噛み砕く『荘子』斉物論篇〜」です。
投稿していた時のものを改訂、編集し直して、通説や定説といかに違うのかということも含めて、わかりやすく、また読みごたえのあるものになったと思っています。 本で通して読むと新しい発見もあるかもしれませんね。
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/17991488/?msockid=3b4514a95f946ea62e0106475e1f6f8c
アマゾン(なぜか画像がありません)
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E5%90%B9%E9%BB%84/dp/4434346679
他、Yahoo!ショッピング!、オンライン書店e-honなどなどにて販売いたしております。
「タオの風 吹黄」で検索してみてください。
長い文章は削れるところはできるだけ削りに削ったのですが、
それでも斉物論篇だけで、572ページにもなりました。
そのため、それ以降の様々な篇はまた後に発行することを計画しています。
出版社の方からは値段は3,500円(税抜)と提示されましたが、
できるだけ多くの人に読んでほしいと2,500円(税抜)にしました。
是非皆さん、読んでみてください。
レビュー、感想など書いていただけたら、なおうれしいです。
随分時間が経過しましたが、ついに荘子の本を出版発行することになりました。
題名は「タオの風 〜字源解釈による新説と自由展開で噛み砕く『荘子』斉物論篇〜」です。
投稿していた時のものを改訂、編集し直して、通説や定説といかに違うのかということも含めて、わかりやすく、また読みごたえのあるものになったと思っています。 本で通して読むと新しい発見もあるかもしれませんね。
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/17991488/?msockid=3b4514a95f946ea62e0106475e1f6f8c
アマゾン(なぜか画像がありません)
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E5%90%B9%E9%BB%84/dp/4434346679
他、Yahoo!ショッピング!、オンライン書店e-honなどなどにて販売いたしております。
「タオの風 吹黄」で検索してみてください。
長い文章は削れるところはできるだけ削りに削ったのですが、
それでも斉物論篇だけで、572ページにもなりました。
そのため、それ以降の様々な篇はまた後に発行することを計画しています。
出版社の方からは値段は3,500円(税抜)と提示されましたが、
できるだけ多くの人に読んでほしいと2,500円(税抜)にしました。
是非皆さん、読んでみてください。
レビュー、感想など書いていただけたら、なおうれしいです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
荘子 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
荘子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 写真を撮るのが好き
- 209382人
- 2位
- 福岡 ソフトバンクホークス
- 42915人
- 3位
- mixi バスケ部
- 38430人