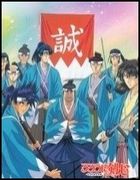↑間取り
残っている証言から、試衛館の間取りを想定してみました。
福地桜痴の証言による試衛館:
『前・中・後と小さな庭のある平屋建て。敷地は約100坪。
道場は30畳ばかりで、4畳半の玄関から廊下を行くと、8畳の茶の間兼周斎の隠居部屋。
その奥が、10畳か12畳の客間、廊下を右に折れると中庭があって、8畳の勇の書斎と、外に台所。台所に繋がって建て増ししたような細長い一室(食客部屋)があった。』
※これは某サイトより引用しました。
〜試衛館〜
試衛館(しえいかん)は、江戸時代後期に江戸市中にあった天然理心流の剣術道場である。天保10年(1839年)、近藤勇の養父である三代目:近藤周助(〜1867)が開業した。以降、四代目:近藤勇(1834〜1868)、佐藤彦五郎(1827〜1902)と引き継がれ、慶応3年まで存在した。この道場には新選組の中核をなす侍たちが顔を連ねており、門弟としては土方歳三・沖田総司・井上源三郎・山南敬助、食客としても、永倉新八・原田左之助・藤堂平助・斎藤一などがいた。
試衛館は江戸市谷甲良屋敷(現在の東京都新宿区市谷柳町25番地)にあり、同所に近藤勇邸があった。『佐藤彦五郎日記』の万延元年(1860年)の項には同場所において、斎藤弥九郎と交流試合を行ったとされている。市谷甲良屋敷は、屋敷町に隣接し、大棟梁甲良氏の拝領地で町人に賃貸してた賑やかな商店街であった。その商店街にあって、勇の養父・近藤周助の保証人である山田屋権兵衛の所有する蔵の裏手に試衛館は道場を間借りしていた。はあったと子孫の伝承に遺されている。「市谷柳町」は東京の新宿にあり、最近「都営大江戸線 牛込柳町駅」が出来ました。
市谷甲良屋敷は現在の市谷柳町25番地である(『東京府名所図会』、『牛込区史』)。一説に試衛館跡を現在の市谷甲良町1番地とする説があるが、この地には文政年間より明治10年代まで吉野元順という医師が代々「回春塾」という医塾を開業していた(『東京府学事開業調書』)。その他、試衛館を甲良町とする説を論じる作家がいるが、いずれも甲良町説を裏付ける史料を提示したことはない。
ちなみに現在の「市谷甲良町」は地名こそ市谷甲良屋敷から由来するが、当時は御先手同心組屋敷であり、現在の市谷甲良町に市谷甲良屋敷があった訳ではない。「甲良」とは人名からきたものであり、江戸時代、市谷甲良町は武家地であった。後半でもこの地に商人等が家屋を借りにきたという記録は公的資料として存在しない。民間史料である絵地図であっても同所で民間が借りたとされる記録は見当たらない。
平成16年(2004年)3月、東京都新宿区教育委員会が市谷甲良屋敷=市谷柳町25番地という史料を基に、歴史研究家、および地理学会員の助言を得て、「25番地のこのあたり」と記した碑を建立している。ただし、25番地内での詳細な位置、図面等は今後の研究課題である。
残っている証言から、試衛館の間取りを想定してみました。
福地桜痴の証言による試衛館:
『前・中・後と小さな庭のある平屋建て。敷地は約100坪。
道場は30畳ばかりで、4畳半の玄関から廊下を行くと、8畳の茶の間兼周斎の隠居部屋。
その奥が、10畳か12畳の客間、廊下を右に折れると中庭があって、8畳の勇の書斎と、外に台所。台所に繋がって建て増ししたような細長い一室(食客部屋)があった。』
※これは某サイトより引用しました。
〜試衛館〜
試衛館(しえいかん)は、江戸時代後期に江戸市中にあった天然理心流の剣術道場である。天保10年(1839年)、近藤勇の養父である三代目:近藤周助(〜1867)が開業した。以降、四代目:近藤勇(1834〜1868)、佐藤彦五郎(1827〜1902)と引き継がれ、慶応3年まで存在した。この道場には新選組の中核をなす侍たちが顔を連ねており、門弟としては土方歳三・沖田総司・井上源三郎・山南敬助、食客としても、永倉新八・原田左之助・藤堂平助・斎藤一などがいた。
試衛館は江戸市谷甲良屋敷(現在の東京都新宿区市谷柳町25番地)にあり、同所に近藤勇邸があった。『佐藤彦五郎日記』の万延元年(1860年)の項には同場所において、斎藤弥九郎と交流試合を行ったとされている。市谷甲良屋敷は、屋敷町に隣接し、大棟梁甲良氏の拝領地で町人に賃貸してた賑やかな商店街であった。その商店街にあって、勇の養父・近藤周助の保証人である山田屋権兵衛の所有する蔵の裏手に試衛館は道場を間借りしていた。はあったと子孫の伝承に遺されている。「市谷柳町」は東京の新宿にあり、最近「都営大江戸線 牛込柳町駅」が出来ました。
市谷甲良屋敷は現在の市谷柳町25番地である(『東京府名所図会』、『牛込区史』)。一説に試衛館跡を現在の市谷甲良町1番地とする説があるが、この地には文政年間より明治10年代まで吉野元順という医師が代々「回春塾」という医塾を開業していた(『東京府学事開業調書』)。その他、試衛館を甲良町とする説を論じる作家がいるが、いずれも甲良町説を裏付ける史料を提示したことはない。
ちなみに現在の「市谷甲良町」は地名こそ市谷甲良屋敷から由来するが、当時は御先手同心組屋敷であり、現在の市谷甲良町に市谷甲良屋敷があった訳ではない。「甲良」とは人名からきたものであり、江戸時代、市谷甲良町は武家地であった。後半でもこの地に商人等が家屋を借りにきたという記録は公的資料として存在しない。民間史料である絵地図であっても同所で民間が借りたとされる記録は見当たらない。
平成16年(2004年)3月、東京都新宿区教育委員会が市谷甲良屋敷=市谷柳町25番地という史料を基に、歴史研究家、および地理学会員の助言を得て、「25番地のこのあたり」と記した碑を建立している。ただし、25番地内での詳細な位置、図面等は今後の研究課題である。
|
|
|
|
コメント(1)
私も以前、試衛館の碑を見に行ったことがあります。たしか近藤勇の写真も碑の近くに掲示されていたと思いますが、どうも試衛館の正確な場所が今だにわからないようですね。「江戸切絵図」では武士の家は一軒一軒名が記されていたようですが、町人等の家はまとめて町名で示せれていたらしいですね。近藤勇の当時の身分は正式は武士ではなかったので町人と同様の扱いだったため試衛館も町名までしかわからないのですね。
福地桜痴は試衛館に出入りしていたようですね。近藤勇とは仲が良かったみたいですが、土方歳三とはあまり仲が良くなかったと聞いています。
因みに「甲良」とは幕府の作事方棟梁をつとめた甲良家の拝領屋敷が、そこにあったことから「甲良屋敷」と町名されたようですね。上述にあるように屋敷そのものがあったわけではないようですね。
福地桜痴は試衛館に出入りしていたようですね。近藤勇とは仲が良かったみたいですが、土方歳三とはあまり仲が良くなかったと聞いています。
因みに「甲良」とは幕府の作事方棟梁をつとめた甲良家の拝領屋敷が、そこにあったことから「甲良屋敷」と町名されたようですね。上述にあるように屋敷そのものがあったわけではないようですね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
〜〜新撰組〜〜 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
〜〜新撰組〜〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90061人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208318人
- 3位
- 酒好き
- 170698人