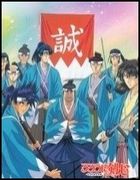〜佐幕〜
佐幕(さばく)は、動乱の幕末期によく使われた言葉で、「幕府を補佐する」の意。 しばしば倒幕派と対比するために佐幕派とも呼ばれる。
佐幕といっても、勤王・攘夷の志はあるものの、朝廷より大政を預かっている幕府あってこその尊王攘夷である、という考えを持つものもいた(尊皇佐幕)。
〜公武合体〜
公武合体(こうぶがったい)は、江戸時代後期に公家(朝廷)の伝統的権威と、武家(幕府)を結びつけて幕府権力の再構築をはかろうとした政策論をいう。公武合体論、公武合体運動、公武一和。
幕府権力の再強化や雄藩の政権への参加を目的とし、幕府は朝廷の伝統的権威と結び付き、尊皇攘夷(尊攘)運動を押さえ、幕藩体制の再編強化を図ろうとした。
江戸時代の幕藩体制において朝廷は政治的に規制され、朝廷内部の運営に制限されていた。一方で宗教的、儀礼的な秩序においては頂点に位置され、伝統的権威は保ち続けていた。江戸時代後期には地方の飢饉や都市部での打ち壊し、蝦夷地や長崎への異国船の来航などで将軍権威が揺らぎ、光格天皇の頃は朝廷権威の復興を望み、幕府との間に尊号一件が起こるなど折衝した。
1853年にアメリカ合衆国のマシュー・ペリーが国書を持って来日し通商を求めた。外国との条約締結を巡り幕府では朝廷に勅許を求めるべきであるとする意見が出され、鎖国政策を維持するか、開国するかにあたり朝廷の判断を仰ぐ事となった。
幕府では井伊直弼が大老に就任し、日米修好通商条約の締結、紀伊藩の徳川慶福(徳川家茂)を将軍後継に決定して将軍継嗣問題の解決を図るなど朝廷の意向を無視した強硬政治を行い、公武合体を求める孝明天皇は水戸藩はじめ御三家、御三卿などに対して戊午の密勅を下す。これに対して井伊は安政の大獄を行い一橋派や尊攘派の弾圧を行い、1860年(安政7)には井伊が暗殺される桜田門外の変が起こる。
尊皇攘夷運動の支柱である水戸学には朝廷権威により幕府専制を抑える思想があり、井伊が暗殺されると主に諸藩の下級武士を中心とする尊攘派の活動が激化した。京都では長州藩や薩摩藩など西南諸藩が公家と関係して政局に関与し、薩摩の島津久光は兵を率いて上洛し、尊皇攘夷派を取り締まり、朝廷に運動して公武合体を推進した。久光は勅使大原重徳とともに江戸へ赴き、一橋慶喜(徳川慶喜)の将軍後継職就任や、幕府に対して幕政改革などを要求する。
1861年(文久元)には、幕府による攘夷実行を条件に孝明天皇の妹の和宮を13代将軍家茂夫人として降嫁させることに成功した。徳川家茂と孝明天皇が死去すると効果を示さなくなり、京都では尊攘派が主流となり幕府に対して攘夷決行を求めた。
幕府は一橋慶喜が京都へ赴き、大政委任の確認させるなど運動するが、尊攘派は天皇の大和行幸による王政復古を目指す。朝廷では実力による尊攘派の一掃を図り、八月十八日の政変で薩摩藩が会津藩と結託して長州藩や尊攘派の公家らを追放し、公武合体派の一橋慶喜、京都守護職松平容保、松平慶永、土佐藩主山内豊信、宇和島藩主伊達宗城、島津久光らによる参与会議が成立する。
その後幕府により朝廷となった長州藩の征伐(幕長戦争)が行われるが、孝明天皇が死去すると長州は許され、秘密裏に薩摩と薩長同盟が結ばれる。土佐藩などの主張で幕府が朝廷に政権を返上し、諸侯会議により幕政改革を推進する公議政体論が主張され、15代将軍となった慶喜により大政奉還が行われるが、王政復古、小御所会議で討幕運動が主流となる。
〜尊皇論・尊王・勤王〜
?尊皇論
尊王論(そんのうろん)は、天皇、皇室を日本古来の血統を受け継ぐものとして崇拝する思想。尊王思想。
古代、日本に仏教が伝来し、中世に神仏習合が起こると、記紀神話に基づく皇室権威の絶対化が行われるようになる。
江戸時代には幕府は朱子学を支配原理として採用し、儒教思想が定着した。幕藩体制において朝廷は幕府の制約を受けていたが、権威的秩序、宗教的な頂点の存在として位置づけられた。江戸中期に国学がさかんになり、記紀や国史、神道などの研究が行われ、武士や豪農などの知識層へも広まる。また、天皇陵の修復や、藩祖を皇族に結びつける風潮も起こる。
幕政改革の混乱や、異国船の来航による対外的緊張など政治的混乱が起こると、幕府は秩序維持のため大政委任論に依存して朝廷権威を政治利用し、朝廷の権威が復興する。
幕末には、平田国学や水戸学などナショナリズムとして絶対化され、仏教を排斥する廃仏毀釈としても現れる。幕府が諸外国と条約を結び、鎖国体制を解いて開国を行うと、攘夷論と結合して尊王攘夷(尊攘)となり、幕政批判や討幕運動などへと展開していく素地のひとつとなり、明治以降の国体論や国家神道へも影響する。
また、江戸時代における儒教思想の日本への定着はすなわち、中華思想(華夷思想)の日本への定着を意味し、近代の皇国史観などに影響を与え、日本版中華思想ともいうべきものの下地となった。日本を指して「中国」と呼ぶなどの例は、それを示している。幕末に至って、従来は同じく中国思想であったものが日本化した攘夷論とむすびつき、幕府や幕藩体制を批判する先鋭な政治思想へと展開していく素地の一つとなる。
?尊王(そんのう)
皇帝や国王の権威を重視し、身分秩序を重んじる儒教思想。春秋時代に活発となった。この項で記述。
1を受けて日本の江戸時代に発展した思想。⇒尊皇論
?勤王(きんのう 勤皇とも言う)
天皇に忠義を尽くすこと。
尊皇攘夷論、尊王と類似する。
〜倒幕運動〜
倒幕運動(とうばくうんどう)は、主として江戸時代後期の幕末に、江戸幕府を打倒して政権打倒を目的とした幕末の政治運動を意味する。狭義では、武力で倒すことを目的とした討幕運動を指すが、広義では、軍事衝突を回避した政権移譲を目指す政治工作も含めて倒幕運動と呼ぶ。
鎌倉時代後期の後醍醐天皇や楠木正成、新田義貞らによる鎌倉幕府打倒運動(正中の変、元弘の乱)が存在し、1333年に鎌倉幕府が滅亡されると天皇親政である建武の新政が行われた。
江戸時代には日本の古典研究などを行う国学が発達し、外国船の来航が多発し、アメリカのマシュー・ペリーやロシアのプチャーチンらが来航して通商を求めると、幕府は条約締結に際して朝廷の勅許を求めたため、天皇、朝廷の伝統的権威が復興する。
幕府が諸外国と通商条約を締結して開国を行うと、在野の志士(活動家)たちは、水戸学の思想的影響のもと、名分論に基づき攘夷を断行しない幕府に対する倒幕論が形成された。幕府は朝廷権威に接近して権力の再構築を図る公武合体政策を行うが、公家の岩倉具視や、薩摩藩の西郷隆盛(吉之助)、大久保利通、小松帯刀、長州藩の桂小五郎(木戸孝允)、広沢真臣などの尊皇攘夷派らは、王政復古、武力討幕路線を構想する。
長州藩は没落して朝敵となるが、攘夷派であった孝明天皇の死去、薩長同盟で薩摩と長州が密約を結ぶと、15代将軍の徳川慶喜は大政奉還を行い公議政体構築を目指すが、王政復古のクーデターにより明治政府が成立、鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍が敗北し、徳川慶喜に対する追討令が出ると、法的には幕府機構は消滅しているものの武力討幕運動が盛んになる。
倒幕への経過
帝国主義時代に入った欧米列強の進出・侵略の手は東アジアにも迫り、中国ではイギリスとの間にアヘン戦争が起こり香港島が奪われ、日本ではラクスマンの来航(寛政4年(1792年))といった諸外国が通商を求める出来事や、フェートン号事件(文化5年(1808年))やゴローニン事件(文化8(1811年))といった摩擦・紛争が起こり始めた。江戸の天下泰平の世の中(鎖国体制下の社会)を乱されたくない・邪魔されたくないといった心情は、攘夷運動になっていった。
政権を担当する者・勢力はいつの世でもそうすることが多いが(そうなることが多いが)、黒船に象徴される圧倒的な武力を見せ付けられた幕府は、現実的な解として、開国を選択する。
孝明天皇も、攘夷の意志を示す。
江戸後期ごろ、日本の古典を研究する学問国学のなかから、“外来宗教伝来以前の日本人固有の考え方”という発想が起こった。良寛坊主が残した戒語のひとつ「好んで唐言葉を使う」によって表される社会の気分・雰囲気から生まれたものだと思われる。この発想で追求された“日本人固有”の行き着くところは天皇になり、外圧の高まりとともに尊皇思想も高ぶっていくことになった。政治の重心が、京都に移行する。
十四代将軍家茂の上洛の折、京都の治安悪化が懸念され浪士隊が結成される。その浪士隊のうち、京に残った派が新撰組結成。(のちに憲兵のような役割を果たす)
朝廷からの攘夷願いを無視できず、幕府は形式的な攘夷命令を諸藩に下す。
薩摩藩は、薩英戦争、長州藩は下関戦争を引き起こし、いづれも大敗する。
薩摩藩は、薩英戦争の経験から攘夷は不可能であると判断し、開国に論を変え、藩力の充実と先進技術の取得に努めることになった。長州藩は尊皇の思想が強く、下関戦争の後も藩論は攘夷で維持し、長州征伐を受けたりしていたが、1865年、日米修好通商条約に孝明天皇が勅許を出したことにより尊皇と攘夷は結びつかなくなり、攘夷の力が失われたところに、土佐藩の坂本龍馬らの仲介があって、薩摩藩と長州藩は和解、倒幕の密約を結ぶ。
黒船以来の国内の乱れ、また諸外国の現実を知り、幕府の統治能力の限界を思い知った西国雄藩は、倒幕の可能性を模索始める。
長州藩は、俗論党により途中「幕府恭順」姿勢を見せるも、その前後は反幕府という姿勢だった。
薩摩藩・土佐藩などは、当初は公武合体・徳川家を議長とする諸侯会議を目標としていたが、ある段階から幕府を見切り、それまでの敵の長州藩と手を結んだ。
1867年10月14日に密かに薩長に討幕の密勅がだされた。しかし、土佐藩主山内豊信らの進言・尽力により、同じ日に徳川慶喜は大政を奉還した。
佐幕(さばく)は、動乱の幕末期によく使われた言葉で、「幕府を補佐する」の意。 しばしば倒幕派と対比するために佐幕派とも呼ばれる。
佐幕といっても、勤王・攘夷の志はあるものの、朝廷より大政を預かっている幕府あってこその尊王攘夷である、という考えを持つものもいた(尊皇佐幕)。
〜公武合体〜
公武合体(こうぶがったい)は、江戸時代後期に公家(朝廷)の伝統的権威と、武家(幕府)を結びつけて幕府権力の再構築をはかろうとした政策論をいう。公武合体論、公武合体運動、公武一和。
幕府権力の再強化や雄藩の政権への参加を目的とし、幕府は朝廷の伝統的権威と結び付き、尊皇攘夷(尊攘)運動を押さえ、幕藩体制の再編強化を図ろうとした。
江戸時代の幕藩体制において朝廷は政治的に規制され、朝廷内部の運営に制限されていた。一方で宗教的、儀礼的な秩序においては頂点に位置され、伝統的権威は保ち続けていた。江戸時代後期には地方の飢饉や都市部での打ち壊し、蝦夷地や長崎への異国船の来航などで将軍権威が揺らぎ、光格天皇の頃は朝廷権威の復興を望み、幕府との間に尊号一件が起こるなど折衝した。
1853年にアメリカ合衆国のマシュー・ペリーが国書を持って来日し通商を求めた。外国との条約締結を巡り幕府では朝廷に勅許を求めるべきであるとする意見が出され、鎖国政策を維持するか、開国するかにあたり朝廷の判断を仰ぐ事となった。
幕府では井伊直弼が大老に就任し、日米修好通商条約の締結、紀伊藩の徳川慶福(徳川家茂)を将軍後継に決定して将軍継嗣問題の解決を図るなど朝廷の意向を無視した強硬政治を行い、公武合体を求める孝明天皇は水戸藩はじめ御三家、御三卿などに対して戊午の密勅を下す。これに対して井伊は安政の大獄を行い一橋派や尊攘派の弾圧を行い、1860年(安政7)には井伊が暗殺される桜田門外の変が起こる。
尊皇攘夷運動の支柱である水戸学には朝廷権威により幕府専制を抑える思想があり、井伊が暗殺されると主に諸藩の下級武士を中心とする尊攘派の活動が激化した。京都では長州藩や薩摩藩など西南諸藩が公家と関係して政局に関与し、薩摩の島津久光は兵を率いて上洛し、尊皇攘夷派を取り締まり、朝廷に運動して公武合体を推進した。久光は勅使大原重徳とともに江戸へ赴き、一橋慶喜(徳川慶喜)の将軍後継職就任や、幕府に対して幕政改革などを要求する。
1861年(文久元)には、幕府による攘夷実行を条件に孝明天皇の妹の和宮を13代将軍家茂夫人として降嫁させることに成功した。徳川家茂と孝明天皇が死去すると効果を示さなくなり、京都では尊攘派が主流となり幕府に対して攘夷決行を求めた。
幕府は一橋慶喜が京都へ赴き、大政委任の確認させるなど運動するが、尊攘派は天皇の大和行幸による王政復古を目指す。朝廷では実力による尊攘派の一掃を図り、八月十八日の政変で薩摩藩が会津藩と結託して長州藩や尊攘派の公家らを追放し、公武合体派の一橋慶喜、京都守護職松平容保、松平慶永、土佐藩主山内豊信、宇和島藩主伊達宗城、島津久光らによる参与会議が成立する。
その後幕府により朝廷となった長州藩の征伐(幕長戦争)が行われるが、孝明天皇が死去すると長州は許され、秘密裏に薩摩と薩長同盟が結ばれる。土佐藩などの主張で幕府が朝廷に政権を返上し、諸侯会議により幕政改革を推進する公議政体論が主張され、15代将軍となった慶喜により大政奉還が行われるが、王政復古、小御所会議で討幕運動が主流となる。
〜尊皇論・尊王・勤王〜
?尊皇論
尊王論(そんのうろん)は、天皇、皇室を日本古来の血統を受け継ぐものとして崇拝する思想。尊王思想。
古代、日本に仏教が伝来し、中世に神仏習合が起こると、記紀神話に基づく皇室権威の絶対化が行われるようになる。
江戸時代には幕府は朱子学を支配原理として採用し、儒教思想が定着した。幕藩体制において朝廷は幕府の制約を受けていたが、権威的秩序、宗教的な頂点の存在として位置づけられた。江戸中期に国学がさかんになり、記紀や国史、神道などの研究が行われ、武士や豪農などの知識層へも広まる。また、天皇陵の修復や、藩祖を皇族に結びつける風潮も起こる。
幕政改革の混乱や、異国船の来航による対外的緊張など政治的混乱が起こると、幕府は秩序維持のため大政委任論に依存して朝廷権威を政治利用し、朝廷の権威が復興する。
幕末には、平田国学や水戸学などナショナリズムとして絶対化され、仏教を排斥する廃仏毀釈としても現れる。幕府が諸外国と条約を結び、鎖国体制を解いて開国を行うと、攘夷論と結合して尊王攘夷(尊攘)となり、幕政批判や討幕運動などへと展開していく素地のひとつとなり、明治以降の国体論や国家神道へも影響する。
また、江戸時代における儒教思想の日本への定着はすなわち、中華思想(華夷思想)の日本への定着を意味し、近代の皇国史観などに影響を与え、日本版中華思想ともいうべきものの下地となった。日本を指して「中国」と呼ぶなどの例は、それを示している。幕末に至って、従来は同じく中国思想であったものが日本化した攘夷論とむすびつき、幕府や幕藩体制を批判する先鋭な政治思想へと展開していく素地の一つとなる。
?尊王(そんのう)
皇帝や国王の権威を重視し、身分秩序を重んじる儒教思想。春秋時代に活発となった。この項で記述。
1を受けて日本の江戸時代に発展した思想。⇒尊皇論
?勤王(きんのう 勤皇とも言う)
天皇に忠義を尽くすこと。
尊皇攘夷論、尊王と類似する。
〜倒幕運動〜
倒幕運動(とうばくうんどう)は、主として江戸時代後期の幕末に、江戸幕府を打倒して政権打倒を目的とした幕末の政治運動を意味する。狭義では、武力で倒すことを目的とした討幕運動を指すが、広義では、軍事衝突を回避した政権移譲を目指す政治工作も含めて倒幕運動と呼ぶ。
鎌倉時代後期の後醍醐天皇や楠木正成、新田義貞らによる鎌倉幕府打倒運動(正中の変、元弘の乱)が存在し、1333年に鎌倉幕府が滅亡されると天皇親政である建武の新政が行われた。
江戸時代には日本の古典研究などを行う国学が発達し、外国船の来航が多発し、アメリカのマシュー・ペリーやロシアのプチャーチンらが来航して通商を求めると、幕府は条約締結に際して朝廷の勅許を求めたため、天皇、朝廷の伝統的権威が復興する。
幕府が諸外国と通商条約を締結して開国を行うと、在野の志士(活動家)たちは、水戸学の思想的影響のもと、名分論に基づき攘夷を断行しない幕府に対する倒幕論が形成された。幕府は朝廷権威に接近して権力の再構築を図る公武合体政策を行うが、公家の岩倉具視や、薩摩藩の西郷隆盛(吉之助)、大久保利通、小松帯刀、長州藩の桂小五郎(木戸孝允)、広沢真臣などの尊皇攘夷派らは、王政復古、武力討幕路線を構想する。
長州藩は没落して朝敵となるが、攘夷派であった孝明天皇の死去、薩長同盟で薩摩と長州が密約を結ぶと、15代将軍の徳川慶喜は大政奉還を行い公議政体構築を目指すが、王政復古のクーデターにより明治政府が成立、鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍が敗北し、徳川慶喜に対する追討令が出ると、法的には幕府機構は消滅しているものの武力討幕運動が盛んになる。
倒幕への経過
帝国主義時代に入った欧米列強の進出・侵略の手は東アジアにも迫り、中国ではイギリスとの間にアヘン戦争が起こり香港島が奪われ、日本ではラクスマンの来航(寛政4年(1792年))といった諸外国が通商を求める出来事や、フェートン号事件(文化5年(1808年))やゴローニン事件(文化8(1811年))といった摩擦・紛争が起こり始めた。江戸の天下泰平の世の中(鎖国体制下の社会)を乱されたくない・邪魔されたくないといった心情は、攘夷運動になっていった。
政権を担当する者・勢力はいつの世でもそうすることが多いが(そうなることが多いが)、黒船に象徴される圧倒的な武力を見せ付けられた幕府は、現実的な解として、開国を選択する。
孝明天皇も、攘夷の意志を示す。
江戸後期ごろ、日本の古典を研究する学問国学のなかから、“外来宗教伝来以前の日本人固有の考え方”という発想が起こった。良寛坊主が残した戒語のひとつ「好んで唐言葉を使う」によって表される社会の気分・雰囲気から生まれたものだと思われる。この発想で追求された“日本人固有”の行き着くところは天皇になり、外圧の高まりとともに尊皇思想も高ぶっていくことになった。政治の重心が、京都に移行する。
十四代将軍家茂の上洛の折、京都の治安悪化が懸念され浪士隊が結成される。その浪士隊のうち、京に残った派が新撰組結成。(のちに憲兵のような役割を果たす)
朝廷からの攘夷願いを無視できず、幕府は形式的な攘夷命令を諸藩に下す。
薩摩藩は、薩英戦争、長州藩は下関戦争を引き起こし、いづれも大敗する。
薩摩藩は、薩英戦争の経験から攘夷は不可能であると判断し、開国に論を変え、藩力の充実と先進技術の取得に努めることになった。長州藩は尊皇の思想が強く、下関戦争の後も藩論は攘夷で維持し、長州征伐を受けたりしていたが、1865年、日米修好通商条約に孝明天皇が勅許を出したことにより尊皇と攘夷は結びつかなくなり、攘夷の力が失われたところに、土佐藩の坂本龍馬らの仲介があって、薩摩藩と長州藩は和解、倒幕の密約を結ぶ。
黒船以来の国内の乱れ、また諸外国の現実を知り、幕府の統治能力の限界を思い知った西国雄藩は、倒幕の可能性を模索始める。
長州藩は、俗論党により途中「幕府恭順」姿勢を見せるも、その前後は反幕府という姿勢だった。
薩摩藩・土佐藩などは、当初は公武合体・徳川家を議長とする諸侯会議を目標としていたが、ある段階から幕府を見切り、それまでの敵の長州藩と手を結んだ。
1867年10月14日に密かに薩長に討幕の密勅がだされた。しかし、土佐藩主山内豊信らの進言・尽力により、同じ日に徳川慶喜は大政を奉還した。
|
|
|
|
コメント(1)
その?
●尊皇思想(そんのうしそう)
皇室崇拝の思想。徳川時代、朱子学の大義名分論に基づく尊王斥覇=徳を以って治める王を尊び、力で支配する覇者を斥ける、という思想は、日本に於いては、国学および神道の研究の隆盛により万世一系の皇室が尊重されるべきことを教え、皇室崇拝の思想を広めた。尊皇論は、本来は幕府を否定するものではなかったが、幕末段階になって幕府の政治力が衰え、また経済の発展に伴って幕府体制の流通機構の矛盾が激しくなると、尊皇思想は下級武士、また地方の地主、豪農らを広く捉えた政治運動となり、攘夷論と結びついて尊皇攘夷運動へ発展していった。
●名分論(めいぶんろん)
大義名分論ともいう。中国哲学で名称と分限の一致を求め、国家社会の階級的秩序を確立しようとする儒家の思想を宋代の学者が強調。君臣の別をわきまえる封建社会の倫理的な支柱として、日本では江戸時代の初期、朱子学に基づいて観念的に主張され、「神皇正統記」「大日本史」など、国学や歴史編纂事業による復古思想の隆盛に影響を与えた。幕末までには次第に、朝廷と幕府の区別を主張し天皇に対する忠誠を求める尊王論へとすり替わり、幕府批判の政治論へと進んでいった。山形大弐はその著「柳木新論」で「天に二日なく、民に二王なし」と説いて、天皇・将軍という権威の両立を否定したために、幕政を批判する者として死罪に処せられた。この頃から名分論は幕府体制への批判となり、のちの尊皇攘夷運動の思想的背景となった。
●尊皇思想(そんのうしそう)
皇室崇拝の思想。徳川時代、朱子学の大義名分論に基づく尊王斥覇=徳を以って治める王を尊び、力で支配する覇者を斥ける、という思想は、日本に於いては、国学および神道の研究の隆盛により万世一系の皇室が尊重されるべきことを教え、皇室崇拝の思想を広めた。尊皇論は、本来は幕府を否定するものではなかったが、幕末段階になって幕府の政治力が衰え、また経済の発展に伴って幕府体制の流通機構の矛盾が激しくなると、尊皇思想は下級武士、また地方の地主、豪農らを広く捉えた政治運動となり、攘夷論と結びついて尊皇攘夷運動へ発展していった。
●名分論(めいぶんろん)
大義名分論ともいう。中国哲学で名称と分限の一致を求め、国家社会の階級的秩序を確立しようとする儒家の思想を宋代の学者が強調。君臣の別をわきまえる封建社会の倫理的な支柱として、日本では江戸時代の初期、朱子学に基づいて観念的に主張され、「神皇正統記」「大日本史」など、国学や歴史編纂事業による復古思想の隆盛に影響を与えた。幕末までには次第に、朝廷と幕府の区別を主張し天皇に対する忠誠を求める尊王論へとすり替わり、幕府批判の政治論へと進んでいった。山形大弐はその著「柳木新論」で「天に二日なく、民に二王なし」と説いて、天皇・将軍という権威の両立を否定したために、幕政を批判する者として死罪に処せられた。この頃から名分論は幕府体制への批判となり、のちの尊皇攘夷運動の思想的背景となった。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
〜〜新撰組〜〜 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
〜〜新撰組〜〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人