・森村泰昌、藤森照信、芸術新潮編集部『フリーダ・カーロのざわめき』(新潮社・とんぼの本)
2003年に雑誌『芸術新潮』の特集として組まれた内容を土台にした本書。
まずは冒頭の森村泰昌氏のフリーダ論からはじまる。
フリーダはその生きざまがひとの感動をさそう。
しかし、アーティストとしての森村氏は、それでもその人生よりもその絵のこそ存在価値があるのだと強調する。
それはいまでこそ奇異に響かないが、あの大壁画家かつ夫であったディエゴ・リベラ、そのディエゴにあれほど尊敬およびコンプレックスを抱いていたフリーダの作品が今日、ディエゴ以上の魅力ないし価値を与えられているのはなぜか、にするどく迫っている。
つまりスローガンやら啓蒙ということばからは縁遠く、フリーダの作品は、自分性に向き合っているということである。
ありのままを描くということ、それはメキシコがはらんでいる両義性といったものから派生しているのだともいえる。
異なった要素を融合させるのではなく、対立を対立として認めること。
対立しているものをそのまま描きこむこと。
なぜそれがユニークなのか、つまり、近代のオブセッションとは対立しているもの同士を融合させ、統合し、一歩うえの段階へと引っ張っていこうとしていたからである。
対立しているものをそのまま描くということは、それぞれがもともとはらんでいるちから、エネルギーをそのままのかたちで表しだすということを意味している。
だからフリーダの絵は生々しく、インパクトが強いのだ。
森村氏は自分の関心を12のトピックにまとめて描き出している。
1.家系図について:
家系図では、森村氏は、フリーダ自身は会ったことがないが、父方の祖母が意外と影響を与えているのではないかと考える。
今回、森村氏に指摘されるまで気がついたことがなかったが、この祖母は眉がつながり気味になっていて、いままではフリーダの眉のつながりはメキシコ性の象徴とされてきたが、じつはヨーロッパ性ともかかわっているのではないかという問いを出している。
2.ズボンとロングスカート:
フリーダは男っぽさと女らしさ、そのあいだを行き来した、いわゆるジェンダーのパイオニアではなかったのかという問い。
3.静物画:
フリーダにおける植物、および動物の意味。そのシンボルの意味。
4.眉:
眉毛というのは、男性性とも取れるが、森村氏は、あるいは心の髭であったのではないかという解釈をもつ。
5.抱きしめたい:
抱かれたいし、抱きしめたい、というフリーダの願望はその自然観、宇宙観、つまり合一したい、包み込まれたいという願望に裏打ちされているのではないかという考え。
6.反遠近法:
フリーダの絵画世界では一般に遠近感がとぼしく、稚拙ささえ感じさせる。しかし絵のなかの存在に序列をつけることなく、あるがままを描き出す、すべてが平等なのだという考えに支えられているらしい。
7.西洋的自我:
メキシコ性を押し出した自画像とはべつに、ヨーロッパ調の自画像もとくに初期には描かれ、以後、その種の作品を嫌悪したということではないので、ヨーロッパ性はべつに否定されていたわけではなかった。
8.祈りと革命:
フリーダの宗教性とその祈りとしての作品、および30年代、40年代、50年代のメキシコと国際政治は、きわめて複雑なものがあるゆえ、森村氏の見解のなかでももっともポレミックな箇所。政治の変転がめまぐるしく、かつ恣意的でもあったので、当然、フリーダの作品やらその生き方においても、ときとして矛盾が噴き出していることがある。
9.まなざし:
自分にむける苛酷なまなざしと他者にむける優しさのこもったまなざしの差異について。
10.フリーダとディエゴの愛憎劇:
近代人としての自覚を持ったはずのこの二人のあいだになにが交わされていたのかという実体にせまる。しかしフリーダには意外と人間関係の希薄さがあるらしい。
11.絵日記:
小品がすぐれているフリーダだけあって、インティメイトな絵日記には、フリーダの情緒がありのままに、しかしドラマティックに描き出されている。
12.永遠の現在:
フリーダはどこまで未来を信じられたのか。むしろ、永遠の現在としてときにすべてを捧げたのではないか。
第二章として、フリーダの人生が、そのときそのときのエピソードをひろいあげながら、読み物として編集部により構成されている。
フリーダの全体像をしるのにきわめて有益。
建築探偵として知られる藤森照信氏が、人気のたかいカサ・アスルではなく、サン・アンヘルのスタディオに迫る。
きわめてシンプルで、とくにこれといった魅力にとぼしいようにおもえるこのスタディオ。
しかし、設計者のフアン・オゴルマンは、20代にしてディエゴとフリーダに見込まれ、当時の最先端の建築スタイル、ル・コルビュジェの機能主義に基づいて建築されたもの。
したがって当時の文化が、この建物をすかしていろいろと見えてくる。
それはこのフアン・オゴルマン自身の生き方にも反映されていて、メキシコ大学の中央図書館の壁画やらメキシコ現代文化を語るときに欠かせないものであるが、その一方で、多くの矛盾やら苦しみにあえいだという構図が見えてきて、それはそのまま、メキシコでの知識人の運命とも関わってくるように思える。いつか、より調べ上げなければ。
この本は、コラムについても充実している。
死について、ファッションについて、あるいは料理について、マスコットについて。
このフリーダ生誕100周年をめぐっても、できるかぎりの叙述がさかれている。
近年、いわゆるフリーダグッズの氾濫には驚くべきものがある。そのごく一部でしかないだろうが、それでもいくつもいくつも、グッズが並べられていて、見ているだけでほほえましくなってくる。
フリーダ歴代恋人列伝として、およそ五人ほど男性が並べられている。
でも、フリーダの場合は女性に対しても愛をささげた場合がすくなくなかったはずであるから、もしかすると、不十分であったかもしれない。
ということで、多くの図版、絵画作品とともに写真、そのなかには本邦初お目見えのものもあり、すくなからぬテキストとあいまって、ニホンでフリーダ・カーロを愛するひとたちにとっては、これほど密度が濃い本が刊行されたことはありがたいと思う。
http://
2003年に雑誌『芸術新潮』の特集として組まれた内容を土台にした本書。
まずは冒頭の森村泰昌氏のフリーダ論からはじまる。
フリーダはその生きざまがひとの感動をさそう。
しかし、アーティストとしての森村氏は、それでもその人生よりもその絵のこそ存在価値があるのだと強調する。
それはいまでこそ奇異に響かないが、あの大壁画家かつ夫であったディエゴ・リベラ、そのディエゴにあれほど尊敬およびコンプレックスを抱いていたフリーダの作品が今日、ディエゴ以上の魅力ないし価値を与えられているのはなぜか、にするどく迫っている。
つまりスローガンやら啓蒙ということばからは縁遠く、フリーダの作品は、自分性に向き合っているということである。
ありのままを描くということ、それはメキシコがはらんでいる両義性といったものから派生しているのだともいえる。
異なった要素を融合させるのではなく、対立を対立として認めること。
対立しているものをそのまま描きこむこと。
なぜそれがユニークなのか、つまり、近代のオブセッションとは対立しているもの同士を融合させ、統合し、一歩うえの段階へと引っ張っていこうとしていたからである。
対立しているものをそのまま描くということは、それぞれがもともとはらんでいるちから、エネルギーをそのままのかたちで表しだすということを意味している。
だからフリーダの絵は生々しく、インパクトが強いのだ。
森村氏は自分の関心を12のトピックにまとめて描き出している。
1.家系図について:
家系図では、森村氏は、フリーダ自身は会ったことがないが、父方の祖母が意外と影響を与えているのではないかと考える。
今回、森村氏に指摘されるまで気がついたことがなかったが、この祖母は眉がつながり気味になっていて、いままではフリーダの眉のつながりはメキシコ性の象徴とされてきたが、じつはヨーロッパ性ともかかわっているのではないかという問いを出している。
2.ズボンとロングスカート:
フリーダは男っぽさと女らしさ、そのあいだを行き来した、いわゆるジェンダーのパイオニアではなかったのかという問い。
3.静物画:
フリーダにおける植物、および動物の意味。そのシンボルの意味。
4.眉:
眉毛というのは、男性性とも取れるが、森村氏は、あるいは心の髭であったのではないかという解釈をもつ。
5.抱きしめたい:
抱かれたいし、抱きしめたい、というフリーダの願望はその自然観、宇宙観、つまり合一したい、包み込まれたいという願望に裏打ちされているのではないかという考え。
6.反遠近法:
フリーダの絵画世界では一般に遠近感がとぼしく、稚拙ささえ感じさせる。しかし絵のなかの存在に序列をつけることなく、あるがままを描き出す、すべてが平等なのだという考えに支えられているらしい。
7.西洋的自我:
メキシコ性を押し出した自画像とはべつに、ヨーロッパ調の自画像もとくに初期には描かれ、以後、その種の作品を嫌悪したということではないので、ヨーロッパ性はべつに否定されていたわけではなかった。
8.祈りと革命:
フリーダの宗教性とその祈りとしての作品、および30年代、40年代、50年代のメキシコと国際政治は、きわめて複雑なものがあるゆえ、森村氏の見解のなかでももっともポレミックな箇所。政治の変転がめまぐるしく、かつ恣意的でもあったので、当然、フリーダの作品やらその生き方においても、ときとして矛盾が噴き出していることがある。
9.まなざし:
自分にむける苛酷なまなざしと他者にむける優しさのこもったまなざしの差異について。
10.フリーダとディエゴの愛憎劇:
近代人としての自覚を持ったはずのこの二人のあいだになにが交わされていたのかという実体にせまる。しかしフリーダには意外と人間関係の希薄さがあるらしい。
11.絵日記:
小品がすぐれているフリーダだけあって、インティメイトな絵日記には、フリーダの情緒がありのままに、しかしドラマティックに描き出されている。
12.永遠の現在:
フリーダはどこまで未来を信じられたのか。むしろ、永遠の現在としてときにすべてを捧げたのではないか。
第二章として、フリーダの人生が、そのときそのときのエピソードをひろいあげながら、読み物として編集部により構成されている。
フリーダの全体像をしるのにきわめて有益。
建築探偵として知られる藤森照信氏が、人気のたかいカサ・アスルではなく、サン・アンヘルのスタディオに迫る。
きわめてシンプルで、とくにこれといった魅力にとぼしいようにおもえるこのスタディオ。
しかし、設計者のフアン・オゴルマンは、20代にしてディエゴとフリーダに見込まれ、当時の最先端の建築スタイル、ル・コルビュジェの機能主義に基づいて建築されたもの。
したがって当時の文化が、この建物をすかしていろいろと見えてくる。
それはこのフアン・オゴルマン自身の生き方にも反映されていて、メキシコ大学の中央図書館の壁画やらメキシコ現代文化を語るときに欠かせないものであるが、その一方で、多くの矛盾やら苦しみにあえいだという構図が見えてきて、それはそのまま、メキシコでの知識人の運命とも関わってくるように思える。いつか、より調べ上げなければ。
この本は、コラムについても充実している。
死について、ファッションについて、あるいは料理について、マスコットについて。
このフリーダ生誕100周年をめぐっても、できるかぎりの叙述がさかれている。
近年、いわゆるフリーダグッズの氾濫には驚くべきものがある。そのごく一部でしかないだろうが、それでもいくつもいくつも、グッズが並べられていて、見ているだけでほほえましくなってくる。
フリーダ歴代恋人列伝として、およそ五人ほど男性が並べられている。
でも、フリーダの場合は女性に対しても愛をささげた場合がすくなくなかったはずであるから、もしかすると、不十分であったかもしれない。
ということで、多くの図版、絵画作品とともに写真、そのなかには本邦初お目見えのものもあり、すくなからぬテキストとあいまって、ニホンでフリーダ・カーロを愛するひとたちにとっては、これほど密度が濃い本が刊行されたことはありがたいと思う。
http://
|
|
|
|
コメント(8)
私も買いました。
フリーダも森村氏も好きなので見つけた時は嬉しかったです。
森村氏の眉毛の解釈には新たな発見をさせられました。
私も彼女の眉毛は民族衣裳同様、メキシコらしさの象徴かと思っていましたが、確かに家系図の絵を見るとドイツ人である祖母とそっくりですよね。
なぜ今まで気付かなかったのか?
それはフリーダについて知っているからだと思います。
フリーダの事を知らない人が見れば右上にいてる女性と女の子が同じ眉毛をしているという事は簡単に気付いたでしょう。
知識を入れずに絵を見るというのも必要かもしれませんね。
私の知人は今はマドンナが所有しているという、「私の誕生」を見て、「かっこいい」と言いました。
彼はフリーダに関する知識を全く入れずにあの絵を見たのですが、その彼があの絵を見て言った言葉が「かっこいい」だったので意外でしたが、それと同時に彼女の絵のすごさに驚きました。
彼女の人生を知ってこそ、自分の苦しみや痛みを隠すことなく絵に表現した彼女に対してかっこいいという感情も湧くのだと思っていましたが、バックグラウンドを知らない人があの絵を見てかっこいいと感じるなんて、フリーダの魅力は計り知れません。
なんか、まとまりのない文章になってしまいすみません。
フリーダも森村氏も好きなので見つけた時は嬉しかったです。
森村氏の眉毛の解釈には新たな発見をさせられました。
私も彼女の眉毛は民族衣裳同様、メキシコらしさの象徴かと思っていましたが、確かに家系図の絵を見るとドイツ人である祖母とそっくりですよね。
なぜ今まで気付かなかったのか?
それはフリーダについて知っているからだと思います。
フリーダの事を知らない人が見れば右上にいてる女性と女の子が同じ眉毛をしているという事は簡単に気付いたでしょう。
知識を入れずに絵を見るというのも必要かもしれませんね。
私の知人は今はマドンナが所有しているという、「私の誕生」を見て、「かっこいい」と言いました。
彼はフリーダに関する知識を全く入れずにあの絵を見たのですが、その彼があの絵を見て言った言葉が「かっこいい」だったので意外でしたが、それと同時に彼女の絵のすごさに驚きました。
彼女の人生を知ってこそ、自分の苦しみや痛みを隠すことなく絵に表現した彼女に対してかっこいいという感情も湧くのだと思っていましたが、バックグラウンドを知らない人があの絵を見てかっこいいと感じるなんて、フリーダの魅力は計り知れません。
なんか、まとまりのない文章になってしまいすみません。
eriさん、sonrieさん、ロージーさん、こんにちは。
この書籍の共著者である森村泰昌さんが、芸術選奨文部科学大臣賞にえらばれました。
当の個展「森村泰昌・美の教室、静聴せよ」をわたしは拝見することができなくて残念でしたが、この個展では、もちろんフリーダに当てられているところもあったわけです。
眉とひげ、に焦点があてられていたようです。
おそまきながら、この個展のフリーダに触れた部分を紹介しておきます。
「関連授業」なるものもあったんですね。
http://www.yaf.or.jp/yma/exhibition/2007/special/02_morimura/time.html
この書籍の共著者である森村泰昌さんが、芸術選奨文部科学大臣賞にえらばれました。
当の個展「森村泰昌・美の教室、静聴せよ」をわたしは拝見することができなくて残念でしたが、この個展では、もちろんフリーダに当てられているところもあったわけです。
眉とひげ、に焦点があてられていたようです。
おそまきながら、この個展のフリーダに触れた部分を紹介しておきます。
「関連授業」なるものもあったんですね。
http://www.yaf.or.jp/yma/exhibition/2007/special/02_morimura/time.html
関連本情報ということで。
岩波書店では「岩波アート・ライブラリー」と銘打って全十二巻のシリーズを今年刊行するのだとかいうお知らせがあります。
そのうちの一巻が「フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ」という構成になるんだそうです。
この原書、じつは1999年の刊行だとか。
最近、とみに研究がすすんでいるだけに、ちょっと気になります。
http://www.amazon.co.jp/Frida-Kahlo-Rivera-Pegasus-Library/dp/3791321641
ちなみに原書の目次はこんな具合だとか。
Childhood years in the Blue House
Frida-a rebel from the start
First brush with death
Diego Rivera
The dove and the elephant
Gringolandia-the years in America
The dark side of the relationship
The affair with Leo Trotsky
Kahlo's first New York exhibition
Kahlo and Surrealism
Divorce and remarriage
`Los Fridos' and `Los Dieguitos'
From wife to mother-from husband to child
Kahlo in terminal decline
Viva la vida-Kahlo's death
Diego without Frida
Endnotes
岩波書店では「岩波アート・ライブラリー」と銘打って全十二巻のシリーズを今年刊行するのだとかいうお知らせがあります。
そのうちの一巻が「フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ」という構成になるんだそうです。
この原書、じつは1999年の刊行だとか。
最近、とみに研究がすすんでいるだけに、ちょっと気になります。
http://www.amazon.co.jp/Frida-Kahlo-Rivera-Pegasus-Library/dp/3791321641
ちなみに原書の目次はこんな具合だとか。
Childhood years in the Blue House
Frida-a rebel from the start
First brush with death
Diego Rivera
The dove and the elephant
Gringolandia-the years in America
The dark side of the relationship
The affair with Leo Trotsky
Kahlo's first New York exhibition
Kahlo and Surrealism
Divorce and remarriage
`Los Fridos' and `Los Dieguitos'
From wife to mother-from husband to child
Kahlo in terminal decline
Viva la vida-Kahlo's death
Diego without Frida
Endnotes
岩波書店から出ましたね。
目次は繰り返しになりますが、参考までに加えておきます。
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/00/5/0089930.html
青い館での子ども時代
フリーダ―生まれつきの反逆児
死との最初の遭遇
ディエゴ・リベラ
鳩と象
グリンゴランディア―アメリカでの歳月
お先まっくらな2人の関係
レオン・トロツキーとの恋愛事件
多作な年(1937‐1938年)
ニューヨークでのカーロの最初の展覧会
カーロとシュルレアリスム
離婚と再婚
「ロス・フリードス」と「ロス・ディエギートス」
妻から母へ―夫から子どもへ
人生の暮れ方へ向うカーロ
ビバ・ラ・ビーダ、カーロの死
フリーダ亡き後のディエゴ
目次は繰り返しになりますが、参考までに加えておきます。
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/00/5/0089930.html
青い館での子ども時代
フリーダ―生まれつきの反逆児
死との最初の遭遇
ディエゴ・リベラ
鳩と象
グリンゴランディア―アメリカでの歳月
お先まっくらな2人の関係
レオン・トロツキーとの恋愛事件
多作な年(1937‐1938年)
ニューヨークでのカーロの最初の展覧会
カーロとシュルレアリスム
離婚と再婚
「ロス・フリードス」と「ロス・ディエギートス」
妻から母へ―夫から子どもへ
人生の暮れ方へ向うカーロ
ビバ・ラ・ビーダ、カーロの死
フリーダ亡き後のディエゴ
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
フリーダ・カーロ 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
フリーダ・カーロのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人
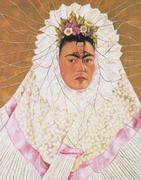










![[dir]食べ放題・バイキング](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/66/25/2346625_191s.jpg)












