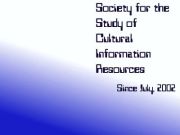諸般の事情により、休刊していたNewsletterを刊行することになりました。とりあえず、会長の挨拶ってことで、こんなことを書きました。
「春の息吹が感じられるようになりました。諸会員の皆様におかれましては、時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、当研究会の活動に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。また、昨年度は諸般の事情により、研究会の活動を全く行うことができずに、諸会員の皆様に大変なご迷惑をお掛けする結果となりました。この場を借りて、会長として深くお詫び申し上げる次第であります。
2002年7月の発会から、既に当研究会の活動も4年近い月日が経過しております。未だに会員数は、僅かに10名程度に止まる状況にあります。しかしながら、各種の会においては、非会員の方々にもご参加いただき、人数の少なさに負けない、常に領域を横断した活発な議論を実現していくことができました。ですが、そのような活動も、当初と比較して衰えを感じる状況にあり、私見では、今こそ組織目的やミッションなどの見直しを図る時期が到来したのだと実感しております。
発会当初から、当研究会の目的は、「学際研究領域としての文化情報学の確立」にありました。しかし、現実に組織行動を実践する際の問題意識は、まずもって、「どのようにして若手研究者に自由な発表の場所を持たせられるか」という点にありました。さらに、このような問題意識の源泉には、発会当初、「会員の大半を占める修士課程の大学院生が、学位を取得することをどれだけ支援できるのか」という現実的な課題があったことを、私自身も記憶しております。そして、そのような問題意識を基盤としながら、文化情報学研究会の組織活動は、その主眼を「若手研究者の育成」と「自由な討議」とすることにより、諸会員の合意形成と成果を創造してきたと言えるでしょう。
しかしながら、研究会を取り巻く環境は大きく変化しました。既に、会員の大半は修士号を取得し、当初の現実的な目標は達成されています。また、欧米では"inter-disciplinary"というナショナルな概念が衰退しており、研究会が掲げてきた「学際」という語は、既にしては死語となっているのが現状であります。さらに、新たな研究の基本スタンスとして、"cross-disciplinary"ないしは"trans-disciplinary"に代表されるボーダレスな領域横断概念が挙げられております。これは、従来の一国から様々な国に関わりあう「国際」的概念から、様々な国家がグローバリゼーションの波に翻弄されながら、その社会システムが融解し、諸国家を横断したグローバルな枠組みを志向せざるを得ない状況が、学問研究のレベルでも顕著になった証拠でもありましょう。
また、そのような動きに伴い、「生活発想を起点とした研究」ものに対する注目も必要となるわけですが、私見では、従来の研究会の動きは必ずしもそれを総合しきれていなかったのだと思っております。そして、そのようなことが背景となり、2004年頃からの研究会の活動が徐々に下火になり、既にワークショップなどの会を持つことの意味が疑問視されるようになった、ということにも繋がったのでしょう。
しかし、このような問題に対して、私は会長として有効なパラダイム・シフトを提唱するのが遅すぎました。また、昨年度は諸会員を取り巻く環境面の変化や、会長である私自身も大いに体調を崩してしまい、2005年2月19日に「2004年度最終ワークショップ」を横浜の関内において開催したのを最後に、組織的活動を1年ほど休止させる結果となってしまいました。ですが、昨年度に実施したワークショップは、参加者2名ということもあり、今後の文化情報学研究会の組織目的そのものを変えていかねばならない、ということを確認するのには大いに役立ちました。同時に、当初の組織規約などにも現実的な不都合が生じており、本格的なリエンジニアリングが必要であることを痛感させられ、組織を構成する諸々の枠組みを再構築することを確認しました。
そして、かのワークショップから早一年が経過しようとする2006年2月18日に、千葉商科大学において理事会を開催致しました。そこにおいては、規約を全面的に改定し、設立趣意書も新しいものを執筆させていただきました。さらに、発行を休止していたニューズレターを刊行し、新たな文化情報学研究会の一歩としたいと思っております。」
「春の息吹が感じられるようになりました。諸会員の皆様におかれましては、時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、当研究会の活動に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。また、昨年度は諸般の事情により、研究会の活動を全く行うことができずに、諸会員の皆様に大変なご迷惑をお掛けする結果となりました。この場を借りて、会長として深くお詫び申し上げる次第であります。
2002年7月の発会から、既に当研究会の活動も4年近い月日が経過しております。未だに会員数は、僅かに10名程度に止まる状況にあります。しかしながら、各種の会においては、非会員の方々にもご参加いただき、人数の少なさに負けない、常に領域を横断した活発な議論を実現していくことができました。ですが、そのような活動も、当初と比較して衰えを感じる状況にあり、私見では、今こそ組織目的やミッションなどの見直しを図る時期が到来したのだと実感しております。
発会当初から、当研究会の目的は、「学際研究領域としての文化情報学の確立」にありました。しかし、現実に組織行動を実践する際の問題意識は、まずもって、「どのようにして若手研究者に自由な発表の場所を持たせられるか」という点にありました。さらに、このような問題意識の源泉には、発会当初、「会員の大半を占める修士課程の大学院生が、学位を取得することをどれだけ支援できるのか」という現実的な課題があったことを、私自身も記憶しております。そして、そのような問題意識を基盤としながら、文化情報学研究会の組織活動は、その主眼を「若手研究者の育成」と「自由な討議」とすることにより、諸会員の合意形成と成果を創造してきたと言えるでしょう。
しかしながら、研究会を取り巻く環境は大きく変化しました。既に、会員の大半は修士号を取得し、当初の現実的な目標は達成されています。また、欧米では"inter-disciplinary"というナショナルな概念が衰退しており、研究会が掲げてきた「学際」という語は、既にしては死語となっているのが現状であります。さらに、新たな研究の基本スタンスとして、"cross-disciplinary"ないしは"trans-disciplinary"に代表されるボーダレスな領域横断概念が挙げられております。これは、従来の一国から様々な国に関わりあう「国際」的概念から、様々な国家がグローバリゼーションの波に翻弄されながら、その社会システムが融解し、諸国家を横断したグローバルな枠組みを志向せざるを得ない状況が、学問研究のレベルでも顕著になった証拠でもありましょう。
また、そのような動きに伴い、「生活発想を起点とした研究」ものに対する注目も必要となるわけですが、私見では、従来の研究会の動きは必ずしもそれを総合しきれていなかったのだと思っております。そして、そのようなことが背景となり、2004年頃からの研究会の活動が徐々に下火になり、既にワークショップなどの会を持つことの意味が疑問視されるようになった、ということにも繋がったのでしょう。
しかし、このような問題に対して、私は会長として有効なパラダイム・シフトを提唱するのが遅すぎました。また、昨年度は諸会員を取り巻く環境面の変化や、会長である私自身も大いに体調を崩してしまい、2005年2月19日に「2004年度最終ワークショップ」を横浜の関内において開催したのを最後に、組織的活動を1年ほど休止させる結果となってしまいました。ですが、昨年度に実施したワークショップは、参加者2名ということもあり、今後の文化情報学研究会の組織目的そのものを変えていかねばならない、ということを確認するのには大いに役立ちました。同時に、当初の組織規約などにも現実的な不都合が生じており、本格的なリエンジニアリングが必要であることを痛感させられ、組織を構成する諸々の枠組みを再構築することを確認しました。
そして、かのワークショップから早一年が経過しようとする2006年2月18日に、千葉商科大学において理事会を開催致しました。そこにおいては、規約を全面的に改定し、設立趣意書も新しいものを執筆させていただきました。さらに、発行を休止していたニューズレターを刊行し、新たな文化情報学研究会の一歩としたいと思っております。」
|
|
|
|
|
|
|
|
文化情報学研究会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
文化情報学研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82539人
- 2位
- 酒好き
- 170703人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人