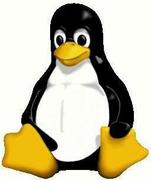IOPSについて調べておりまして
ITPROのサイトを拝見しました。
参考サイト
http://
IOPSの計算方法の記載があり、
以下計算に対する回答が記載されておりますが
どうして142IOPSになるかがよくわかっておりません。
お手数ですがご教示頂けますでしょうか。
変なご質問となりすみません。
仮に,4Kバイトのデータを書き込むために必要なデータ転送時間を1ミリ秒とする。
平均アクセス時間6ミリ秒のディスクにデータを4Kバイト単位で書き込むとする。
このディスクのIOPSは,「1/(6ミリ秒+1ミリ秒)=142IOPS」となる。
つまり,4Kバイトのデータを毎秒142回書き込めるディスクということになる。
ITPROのサイトを拝見しました。
参考サイト
http://
IOPSの計算方法の記載があり、
以下計算に対する回答が記載されておりますが
どうして142IOPSになるかがよくわかっておりません。
お手数ですがご教示頂けますでしょうか。
変なご質問となりすみません。
仮に,4Kバイトのデータを書き込むために必要なデータ転送時間を1ミリ秒とする。
平均アクセス時間6ミリ秒のディスクにデータを4Kバイト単位で書き込むとする。
このディスクのIOPSは,「1/(6ミリ秒+1ミリ秒)=142IOPS」となる。
つまり,4Kバイトのデータを毎秒142回書き込めるディスクということになる。
|
|
|
|
コメント(3)
>・・・どうして142IOPSになるか・・・
たぶん、そのリンクの計算では
一回あたりのランダムな平均アクセス(IO切り替えにかかる)時間は6ミリ秒(0.006s)で、一回のアクセスでの書き込みは4kバイトであり、4kバイトの書き込みには1ミリ秒かかる
ということは
一度のアクセスの際にかかる総時間は、0.006s+0.001s=0.007s
毎秒書き込める回数、つまりIOPSは
1/0.007=142.857142857142857142・・・
≒1.429×10^2
≒142(IOPS)
スペックを算出するときは、四捨五入や切り上げを安易にやると恣意的なオーバースペックを算出してしまうことにもなりかねないので、例えば少数点以下、あるいは有効桁数以下は切り捨てるほうがいいかもしれません
定義や計算ルールの詳細はIO装置の種類やその業界で決められていると思いますが詳しいことが知りたいなら装置の種類ごとにググるとわかるでしょう
サーバ一般でのIOPSの定義は
IOPS ≣ 一秒あたりの転送バイト数 ÷ 一度のIOアクセスで行う転送バイト数
であり、例えば、4Kバイトのデータを ”毎秒142回書き込める” ディスクのIOPSは、142 IOPSとなる
一定のバイト数の書き込みを行うときに、毎秒あたり最大何回それが可能かという回数ですよね
ディスクアクセスでIOPSを考えるのは”最近普及している高速のSSD”がランダムな物理アドレスに素早くアクセスできることを数値化するためでしょう
HDDのような磁気ディスクにシリンダやヘッドで書き込むときはランダムなアドレスの変化においては物理的運動に時間がかかりますが、それにl比べてSSDや半導体のRAMは物理アドレスのどこにでも同じように素早くアクセスできますので、ランダムアクセスでのIPOSを比較するとSSDのメリットがわかりやすくなります
このランダムなアドレス変化の速さを示すのがIOPSで、IOPSの数値が大きいほどランダムアクセスが早いということになります
たぶん、そのリンクの計算では
一回あたりのランダムな平均アクセス(IO切り替えにかかる)時間は6ミリ秒(0.006s)で、一回のアクセスでの書き込みは4kバイトであり、4kバイトの書き込みには1ミリ秒かかる
ということは
一度のアクセスの際にかかる総時間は、0.006s+0.001s=0.007s
毎秒書き込める回数、つまりIOPSは
1/0.007=142.857142857142857142・・・
≒1.429×10^2
≒142(IOPS)
スペックを算出するときは、四捨五入や切り上げを安易にやると恣意的なオーバースペックを算出してしまうことにもなりかねないので、例えば少数点以下、あるいは有効桁数以下は切り捨てるほうがいいかもしれません
定義や計算ルールの詳細はIO装置の種類やその業界で決められていると思いますが詳しいことが知りたいなら装置の種類ごとにググるとわかるでしょう
サーバ一般でのIOPSの定義は
IOPS ≣ 一秒あたりの転送バイト数 ÷ 一度のIOアクセスで行う転送バイト数
であり、例えば、4Kバイトのデータを ”毎秒142回書き込める” ディスクのIOPSは、142 IOPSとなる
一定のバイト数の書き込みを行うときに、毎秒あたり最大何回それが可能かという回数ですよね
ディスクアクセスでIOPSを考えるのは”最近普及している高速のSSD”がランダムな物理アドレスに素早くアクセスできることを数値化するためでしょう
HDDのような磁気ディスクにシリンダやヘッドで書き込むときはランダムなアドレスの変化においては物理的運動に時間がかかりますが、それにl比べてSSDや半導体のRAMは物理アドレスのどこにでも同じように素早くアクセスできますので、ランダムアクセスでのIPOSを比較するとSSDのメリットがわかりやすくなります
このランダムなアドレス変化の速さを示すのがIOPSで、IOPSの数値が大きいほどランダムアクセスが早いということになります
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
Linux 更新情報
Linuxのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90008人
- 2位
- 酒好き
- 170663人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人