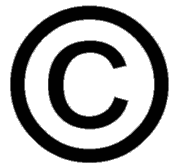著作権フリーライターのタイゾーといいます。お世話になります。「ピリ辛著作権相談室」(http://
JISの著作権問題について、ご存知でしょうか?JISは政府の大臣が制定して、国民が知るべき工業標準として公表されていますが、政府の辻褄合わせのために、JISに著作権があると称して、我々国民から高い金を巻き上げて、天下り団体を通じてJISの文書(規格票)を売りつけているという問題です。
下記にこの問題についてまとめたメモを掲載しますので、これをたたき台にして、自由に議論、意見交換できれば幸いです。
*************************************************************************************
経産省がJISの著作権についてデマ見解を発信中!
JIS=日本工業規格を御存知だろうか?国家規格の一つであり、「自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化する」工業標準である。わが国では、製品がJISの要求を満足していればJISに適合しているとして、国からお墨付きを得られることになっている。
このようなJISは経済産業大臣などの主務大臣が制定する工業標準であることから、法令、行政通達などと同様に、国民に広く知らしめるべきものである。ところが、経済産業省はこのJISには著作権があるとして、その内容が掲載されているJIS規格票を、天下り団体の財団法人日本規格協会を通じて高額な値段で我々国民に売りつけているのだ!
ことの発端は、日本工業標準調査会『21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書』(平成12年5月29日:http://
しかし、民間団体が原案を作成したJISについて著作権があるとする経産省の見解については、業界団体を中心に疑問が持たれていた。
この点、文化庁出身で著作権法研究者の鳥澤孝之氏は、「国家規格の著作権保護に関する考察 ―民間団体が関与した日本工業規格の制定を中心に―」知財管理 Vol.59 No.7 [2009.7]793-805頁(http://
この見解に対しては、経済産業省はこのたび、以下のような反論を行った(産業技術環境局基準認証ユニット(一橋大学イノベーション研究センター 江藤学編)『標準化実務入門(試作版)』(平成22年7月)184頁〔長谷亮輔執筆〕http://
1. 「著作権法第13条第2項(原文ママ。正しくは「第2号」。以下同様。)でいう告示とは、立法行為、司法行為、行政行為として権限のある者が作成し、その内容を公表することによって国民に知らしめ、また国民が自由に知るべきものであると性格づけることをいうものである。これに対して、JIS規格の官報への公示は規格の名称及び番号のみで、内容についてまで掲載されているわけではない。」
2. 「JIS規格の原文は、原案作成者や利害関係人などの民間団体において作成されているものである。著作権法第13条第2項の対象となるのは、官公庁自身が創作し国民に知らしめることが目的であるような場合に限定されるものであり、JIS規格のように利害関係者が原案を作成して申し出たり、原案を委託によって作成した者がいる場合には、著作権法第13条第2項を適用するのは不適当である」
しかし前者については、同号の告示等は官報の掲載内容に限定されるものではなく、また主務大臣が制定した工業標準の内容は本来国民に広く知らしめるべきものである。この点、経済産業省基準認証ユニット(日本工業標準調査会事務局)は制定又は改正されるJISの原稿を財団法人日本規格協会に回付し、同協会がその原稿に基づいてJIS規格票を印刷・発行し、同協会の窓口を通じて同規格票を販売・配布しているところである。このようにJISは経済産業省基準認証ユニットの監督の下に財団法人日本規格協会が発行する規格票を通じて公表され(日本規格協会編『JISハンドブック2008 56 標準化』(日本規格協会、2008年)1038頁)、JISの内容は官報に代わって規格票に掲載されていることから、官報で規格内容が省略されたことを著作権発生の根拠にすることはできない。また「現在有効な法令約7,400 件の中で、JIS規格を引用した法令は約360件(5%)もあ」るなど、「単なる技術標準としてだけでなく、行政制度とのつながりも深いものとなってい」るとの指摘がなされ(山中豊「事業仕分けと標準化」情報処理学会 情報規格調査会 NEWSLETTER No.85 (2010-03) 2-3頁:http://
後者については、法令、通達等の著作権が否定されるのは「公益的な見地から、国民に広く知らせ、かつ、自由に利用させるべき性質の著作物には、権利を認める結果としてその円滑な利用を阻害することとなるのを防ぐという観点から」であるところ(加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、平成18年)136頁)、JISの原案作成者が官公庁以外の者であることを理由に著作権の発生を認めれば、JISを利用する国民の生活や企業活動等に支障をきたし、国内に広く知らしめることを主要な機能とするJIS の役割を損なうことになる。なお原案作成者に著作権が認められない場合でも、原案を採用した主務大臣から補償金等を得て経済的利益を確保することは可能である。
なお国の機関の中でも国立国会図書館は「国立国会図書館 リサーチ・ナビ JIS規格:http://
このようなデマ見解を経産省が辻褄を合わせて発信し続ける理由としては、規格の国際協定である「貿易の技術的障害に関する協定(WTO/TBT協定):http://
WTO/TBT協定では、各国の国家規格は、国際規格であるISO(国際標準化機構)/IEC(国際電気標準会議) /ITU(国際電気通信連合)の規格に合わせて作成しないとWTO協定違反になる旨定めているが、国際規格の ISO/IECなどが規格のマニュアルである規格票のコピー、ネット送信などについて著作権を主張し、使用料を請求している(『ISO/IEC 専門業務用指針 第1部 専門業務の手順 第7版 英和対訳版』(2009年7月)32頁参照)。そのため、英語の規格票を日本語に翻訳するときには翻訳権が働き、わが国もISO/IEC/ITUの許諾を得て、経産省が国際規格をJISの原案として、審議会での審議・答申や主務大臣の制定を経て、利用していることから、JISの著作権を主張せざるを得ない立場に追い込まれている。この点、他の先進国で国家規格を作成する機関は、米国国家標準協会(ANSI)・カナダ標準委員会(SCC)・英国規格協会(BSI)・ドイツ標準協会(DIN)・フランス規格協会(AFNOR)のいずれも民間団体か、政府から独立した連邦公社となっており、また国際規格を作成するISO/IECも民間団体であり政府機関ではないことから、規格の著作権を主張することについて支障はない。
一方でわが国では、国家規格の作成機関を政府機関とすることに固執し続けている。すわなち、JISC事務局が経済産業省本省に置かれる平成13年の省庁再編前には、旧通商産業省工業技術院の付属機関(http://
平成13年の省庁再編の際には、工業技術院が独法化(産業技術総合研究所)することから、行政組織の減量・効率化の観点からJISCの位置づけが問題になったが、結局、中央省庁等改革大綱(http://
なお、情報工学研究者で東京工科大学学長だった高橋茂氏からは、日本の国家標準化機関も民営化しないと、国際競争力が危惧されるという指摘がなされていたが(高橋茂「情報技術標準化についての私見」情報処理学会 情報規格調査会 NEWSLETTER No.39 (1998-09)4-7頁:http://
政府は最近、知的財産戦略本部「知的財産推進計画2010」(2010年5月21日)(http://
JISの著作権問題について、ご存知でしょうか?JISは政府の大臣が制定して、国民が知るべき工業標準として公表されていますが、政府の辻褄合わせのために、JISに著作権があると称して、我々国民から高い金を巻き上げて、天下り団体を通じてJISの文書(規格票)を売りつけているという問題です。
下記にこの問題についてまとめたメモを掲載しますので、これをたたき台にして、自由に議論、意見交換できれば幸いです。
*************************************************************************************
経産省がJISの著作権についてデマ見解を発信中!
JIS=日本工業規格を御存知だろうか?国家規格の一つであり、「自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化する」工業標準である。わが国では、製品がJISの要求を満足していればJISに適合しているとして、国からお墨付きを得られることになっている。
このようなJISは経済産業大臣などの主務大臣が制定する工業標準であることから、法令、行政通達などと同様に、国民に広く知らしめるべきものである。ところが、経済産業省はこのJISには著作権があるとして、その内容が掲載されているJIS規格票を、天下り団体の財団法人日本規格協会を通じて高額な値段で我々国民に売りつけているのだ!
ことの発端は、日本工業標準調査会『21世紀に向けた標準化課題検討特別委員会報告書』(平成12年5月29日:http://
しかし、民間団体が原案を作成したJISについて著作権があるとする経産省の見解については、業界団体を中心に疑問が持たれていた。
この点、文化庁出身で著作権法研究者の鳥澤孝之氏は、「国家規格の著作権保護に関する考察 ―民間団体が関与した日本工業規格の制定を中心に―」知財管理 Vol.59 No.7 [2009.7]793-805頁(http://
この見解に対しては、経済産業省はこのたび、以下のような反論を行った(産業技術環境局基準認証ユニット(一橋大学イノベーション研究センター 江藤学編)『標準化実務入門(試作版)』(平成22年7月)184頁〔長谷亮輔執筆〕http://
1. 「著作権法第13条第2項(原文ママ。正しくは「第2号」。以下同様。)でいう告示とは、立法行為、司法行為、行政行為として権限のある者が作成し、その内容を公表することによって国民に知らしめ、また国民が自由に知るべきものであると性格づけることをいうものである。これに対して、JIS規格の官報への公示は規格の名称及び番号のみで、内容についてまで掲載されているわけではない。」
2. 「JIS規格の原文は、原案作成者や利害関係人などの民間団体において作成されているものである。著作権法第13条第2項の対象となるのは、官公庁自身が創作し国民に知らしめることが目的であるような場合に限定されるものであり、JIS規格のように利害関係者が原案を作成して申し出たり、原案を委託によって作成した者がいる場合には、著作権法第13条第2項を適用するのは不適当である」
しかし前者については、同号の告示等は官報の掲載内容に限定されるものではなく、また主務大臣が制定した工業標準の内容は本来国民に広く知らしめるべきものである。この点、経済産業省基準認証ユニット(日本工業標準調査会事務局)は制定又は改正されるJISの原稿を財団法人日本規格協会に回付し、同協会がその原稿に基づいてJIS規格票を印刷・発行し、同協会の窓口を通じて同規格票を販売・配布しているところである。このようにJISは経済産業省基準認証ユニットの監督の下に財団法人日本規格協会が発行する規格票を通じて公表され(日本規格協会編『JISハンドブック2008 56 標準化』(日本規格協会、2008年)1038頁)、JISの内容は官報に代わって規格票に掲載されていることから、官報で規格内容が省略されたことを著作権発生の根拠にすることはできない。また「現在有効な法令約7,400 件の中で、JIS規格を引用した法令は約360件(5%)もあ」るなど、「単なる技術標準としてだけでなく、行政制度とのつながりも深いものとなってい」るとの指摘がなされ(山中豊「事業仕分けと標準化」情報処理学会 情報規格調査会 NEWSLETTER No.85 (2010-03) 2-3頁:http://
後者については、法令、通達等の著作権が否定されるのは「公益的な見地から、国民に広く知らせ、かつ、自由に利用させるべき性質の著作物には、権利を認める結果としてその円滑な利用を阻害することとなるのを防ぐという観点から」であるところ(加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、平成18年)136頁)、JISの原案作成者が官公庁以外の者であることを理由に著作権の発生を認めれば、JISを利用する国民の生活や企業活動等に支障をきたし、国内に広く知らしめることを主要な機能とするJIS の役割を損なうことになる。なお原案作成者に著作権が認められない場合でも、原案を採用した主務大臣から補償金等を得て経済的利益を確保することは可能である。
なお国の機関の中でも国立国会図書館は「国立国会図書館 リサーチ・ナビ JIS規格:http://
このようなデマ見解を経産省が辻褄を合わせて発信し続ける理由としては、規格の国際協定である「貿易の技術的障害に関する協定(WTO/TBT協定):http://
WTO/TBT協定では、各国の国家規格は、国際規格であるISO(国際標準化機構)/IEC(国際電気標準会議) /ITU(国際電気通信連合)の規格に合わせて作成しないとWTO協定違反になる旨定めているが、国際規格の ISO/IECなどが規格のマニュアルである規格票のコピー、ネット送信などについて著作権を主張し、使用料を請求している(『ISO/IEC 専門業務用指針 第1部 専門業務の手順 第7版 英和対訳版』(2009年7月)32頁参照)。そのため、英語の規格票を日本語に翻訳するときには翻訳権が働き、わが国もISO/IEC/ITUの許諾を得て、経産省が国際規格をJISの原案として、審議会での審議・答申や主務大臣の制定を経て、利用していることから、JISの著作権を主張せざるを得ない立場に追い込まれている。この点、他の先進国で国家規格を作成する機関は、米国国家標準協会(ANSI)・カナダ標準委員会(SCC)・英国規格協会(BSI)・ドイツ標準協会(DIN)・フランス規格協会(AFNOR)のいずれも民間団体か、政府から独立した連邦公社となっており、また国際規格を作成するISO/IECも民間団体であり政府機関ではないことから、規格の著作権を主張することについて支障はない。
一方でわが国では、国家規格の作成機関を政府機関とすることに固執し続けている。すわなち、JISC事務局が経済産業省本省に置かれる平成13年の省庁再編前には、旧通商産業省工業技術院の付属機関(http://
平成13年の省庁再編の際には、工業技術院が独法化(産業技術総合研究所)することから、行政組織の減量・効率化の観点からJISCの位置づけが問題になったが、結局、中央省庁等改革大綱(http://
なお、情報工学研究者で東京工科大学学長だった高橋茂氏からは、日本の国家標準化機関も民営化しないと、国際競争力が危惧されるという指摘がなされていたが(高橋茂「情報技術標準化についての私見」情報処理学会 情報規格調査会 NEWSLETTER No.39 (1998-09)4-7頁:http://
政府は最近、知的財産戦略本部「知的財産推進計画2010」(2010年5月21日)(http://
|
|
|
|
コメント(4)
まゆちゃんさん
早速のレス、ありがとうございます。閲覧が中々できないはもちろんのこと、プリントアウトやダウンロードができないのは、困ったもんですねえ。しかも素人感覚で著作権を理由にされるのは、たまったものではないです。
政府側がそのようにする理由が何であれ、ユーザーに対する説明義務はあるでしょうね。民間ビジネスならともかく、政府機関が主体となって国民の税金を投入しているのですから。
「パンピーが束になってもどうにもならないでしょう」と諦めるのは、まだ早いです。政府(経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット)側が国際関係から辻褄あわせをしているのは、上記のとおりです。マスコミや世論にこのことを知らせば、是正される可能性はあります。
早速のレス、ありがとうございます。閲覧が中々できないはもちろんのこと、プリントアウトやダウンロードができないのは、困ったもんですねえ。しかも素人感覚で著作権を理由にされるのは、たまったものではないです。
政府側がそのようにする理由が何であれ、ユーザーに対する説明義務はあるでしょうね。民間ビジネスならともかく、政府機関が主体となって国民の税金を投入しているのですから。
「パンピーが束になってもどうにもならないでしょう」と諦めるのは、まだ早いです。政府(経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット)側が国際関係から辻褄あわせをしているのは、上記のとおりです。マスコミや世論にこのことを知らせば、是正される可能性はあります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
著作権 更新情報
-
最新のアンケート