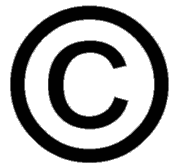著作権:「死後70年」に延長を 文芸家協会など要望−今日の話題:MSN毎日インタラクティブ
http://
9月22日に17団体が著作権保護期間の延長の要望を文化庁に提出するそうです。
著作者の死後50年という保護期間を20年延長することに、どのような意味があるのでしょうか?
http://
9月22日に17団体が著作権保護期間の延長の要望を文化庁に提出するそうです。
著作者の死後50年という保護期間を20年延長することに、どのような意味があるのでしょうか?
|
|
|
|
コメント(109)
>権利の行使をする気があるのに、権利を行使していないとい
>うのは具体的にはどのようなロジックでしょうか
権利を行使する気があるというのはどういう意味でしょう?
権利を行使していないと言う「状況」があるだけですね。具体的に意思については何か語られたことがあるのですか、とお尋ねしているわけですが。
誰もなにも言っていないのならば、ただ単に「権利を行使していない状況」であるだけで、意思に関しては忖度でしかないということです。
それをさして「何か言いたいことがあるなら行動に出るのが自然だ」と言うのは乱暴なこじつけです。
現状は、いいですか? 「権利を行使していないと言う状況である」だけです。意思については「わからない」といっているのです。
はっきりと意思がわからないのに、わたなべさんは勝手に「やる気がない」と忖度しているのだ、と言う指摘なんですが?
彼らがどういう意思かわかっているなら、その根拠を出してくださいと。そうお願いしています。なにせ、「その気がない」とおっしゃったのはわたなべさんなのですから、言いだしっぺに挙証責任があるはずですよね。
>うのは具体的にはどのようなロジックでしょうか
権利を行使する気があるというのはどういう意味でしょう?
権利を行使していないと言う「状況」があるだけですね。具体的に意思については何か語られたことがあるのですか、とお尋ねしているわけですが。
誰もなにも言っていないのならば、ただ単に「権利を行使していない状況」であるだけで、意思に関しては忖度でしかないということです。
それをさして「何か言いたいことがあるなら行動に出るのが自然だ」と言うのは乱暴なこじつけです。
現状は、いいですか? 「権利を行使していないと言う状況である」だけです。意思については「わからない」といっているのです。
はっきりと意思がわからないのに、わたなべさんは勝手に「やる気がない」と忖度しているのだ、と言う指摘なんですが?
彼らがどういう意思かわかっているなら、その根拠を出してくださいと。そうお願いしています。なにせ、「その気がない」とおっしゃったのはわたなべさんなのですから、言いだしっぺに挙証責任があるはずですよね。
不思議だなぁ、たさかさん。
以前、「黙認」をキーワードとした議論があったんですが、
その時は、「著作権者は黙認している」と言う主張をする人に対して、
一度として「その根拠は?」と言う質問をしなかったし、
そう言う主張をしている人に対して、
「真面目に議論する気がない」と言う批判もしなかった。
ましてや、挙証責任があるなんてことは言いもしていない。
今回、わたなべさんが同じ主張をしたとたんに、
「意思の根拠は?」「議論する気があるの」ですか。。。
しかも挙証責任なんて話まで出してきている。
私には、典型的なダブルスタンダードに見えますが、
議論をする姿勢として一貫しているとお考えでしょうか?
議論をする姿勢が一貫していなければ、他人に対して、
「真面目に議論する気があるのか?」と問うたり、
挙証責任を押し付けたりするのは変ではありませんか。
まぁ、私も、他人の意思を勝手に推定するのは嫌いなので、
「意思がない」のではなく「権利行使してない」だけだと思います。
その一方で、「搾取されている」と言うのも、
主観的な用語なので、なぜ「搾取」とまでいえるのか、
その部分のデータも必要だと考えていますけどね。
以前、「黙認」をキーワードとした議論があったんですが、
その時は、「著作権者は黙認している」と言う主張をする人に対して、
一度として「その根拠は?」と言う質問をしなかったし、
そう言う主張をしている人に対して、
「真面目に議論する気がない」と言う批判もしなかった。
ましてや、挙証責任があるなんてことは言いもしていない。
今回、わたなべさんが同じ主張をしたとたんに、
「意思の根拠は?」「議論する気があるの」ですか。。。
しかも挙証責任なんて話まで出してきている。
私には、典型的なダブルスタンダードに見えますが、
議論をする姿勢として一貫しているとお考えでしょうか?
議論をする姿勢が一貫していなければ、他人に対して、
「真面目に議論する気があるのか?」と問うたり、
挙証責任を押し付けたりするのは変ではありませんか。
まぁ、私も、他人の意思を勝手に推定するのは嫌いなので、
「意思がない」のではなく「権利行使してない」だけだと思います。
その一方で、「搾取されている」と言うのも、
主観的な用語なので、なぜ「搾取」とまでいえるのか、
その部分のデータも必要だと考えていますけどね。
「黙示の許諾」っつー奴ですな。
まぁ正直このトピックからはかなり外れる話になるので余談でしか無いですが……
同人誌即売会としては最大のものである「コミックマーケット」に企業として参加、もしくはそのカタログに広告を出している出版社というのはかなり存在する訳ですが、これら出版社は、コミケの参加サークルに対して「黙示の許諾」を行っている、と考えても良いように思えます。
他にもまぁあるわけですが、たとえばワンダーフェスティバルでは当日版権システムという奴が存在し、その当日のみ販売できるような著作権処理を行っているわけですが、今年の冬は「ちゅるやさん」というキャラクタが多数申請されたらしいです。
この「ちゅるやさん」、角川の小説とそのアニメ化作品の「涼宮ハルヒの憂鬱」の二次創作キャラクタとして生み出されたものです。これに対して角川はそのキャラクタの当日版権処理を行ったそうで、まぁこの辺伝聞にすぎないんですが、これらのことからも「黙示の許諾」がなりたつと可能性がありそうです。
これらは正直、現行法上、親告罪である事から成り立つある意味で「理想的な共犯関係」とも言える(まぁ共犯っつーのは間違いだとは思いますが……ちょっと他に言葉が見つからなかったもので)と思いますし、ある意味で「理想的な共生関係」でもあるように思えます。
そういう意味では、個人的には同人やってる人間としては誰にも気の毒がられる筋合いは無いように思えますし、著作権法の進む先は著作物のデッドコピー以外の二次的利用についてはかなり緩やかな制限に置かれるべきであると確信もしています。
ま、閑話休題でした。
#正直、なす氏に「気の毒」って言われる毎に極めて強い違和感を感じるのです。
まぁ正直このトピックからはかなり外れる話になるので余談でしか無いですが……
同人誌即売会としては最大のものである「コミックマーケット」に企業として参加、もしくはそのカタログに広告を出している出版社というのはかなり存在する訳ですが、これら出版社は、コミケの参加サークルに対して「黙示の許諾」を行っている、と考えても良いように思えます。
他にもまぁあるわけですが、たとえばワンダーフェスティバルでは当日版権システムという奴が存在し、その当日のみ販売できるような著作権処理を行っているわけですが、今年の冬は「ちゅるやさん」というキャラクタが多数申請されたらしいです。
この「ちゅるやさん」、角川の小説とそのアニメ化作品の「涼宮ハルヒの憂鬱」の二次創作キャラクタとして生み出されたものです。これに対して角川はそのキャラクタの当日版権処理を行ったそうで、まぁこの辺伝聞にすぎないんですが、これらのことからも「黙示の許諾」がなりたつと可能性がありそうです。
これらは正直、現行法上、親告罪である事から成り立つある意味で「理想的な共犯関係」とも言える(まぁ共犯っつーのは間違いだとは思いますが……ちょっと他に言葉が見つからなかったもので)と思いますし、ある意味で「理想的な共生関係」でもあるように思えます。
そういう意味では、個人的には同人やってる人間としては誰にも気の毒がられる筋合いは無いように思えますし、著作権法の進む先は著作物のデッドコピー以外の二次的利用についてはかなり緩やかな制限に置かれるべきであると確信もしています。
ま、閑話休題でした。
#正直、なす氏に「気の毒」って言われる毎に極めて強い違和感を感じるのです。
そりゃもちろん、「現行法上においての理想的関係」ですよ。
著作権法の改正については以前理想論を語ったつもりなのでパスですし、GPLやCCに「現行法上において」全ての著作権者が参加するはずはない以上、著作権の改正による強制なくして現行法上では「同人以上に理想的な共生関係」が得られるかどうかは疑問です。実際得られてませんし、フリーソフトウェア界隈でもかなり問題も多いのは周知の事実でしょう。プロプラとの関係や特許問題なんかもありますしね。
お互いに問題を抱えている部分がある以上、「気の毒」っていわれる筋合いはないと思いますし、逆に言えばこっちから「FSW界隈って気の毒だよね」と言ってしまうケースも十分あるでしょう。
著作権法の改正については以前理想論を語ったつもりなのでパスですし、GPLやCCに「現行法上において」全ての著作権者が参加するはずはない以上、著作権の改正による強制なくして現行法上では「同人以上に理想的な共生関係」が得られるかどうかは疑問です。実際得られてませんし、フリーソフトウェア界隈でもかなり問題も多いのは周知の事実でしょう。プロプラとの関係や特許問題なんかもありますしね。
お互いに問題を抱えている部分がある以上、「気の毒」っていわれる筋合いはないと思いますし、逆に言えばこっちから「FSW界隈って気の毒だよね」と言ってしまうケースも十分あるでしょう。
>>92
その通り。私は実際には同人とFSWが対立した構図になるなんて一つも考えていません。一応技術屋の端くれでもありますし。*だからこそ*「FSW界隈と比較して、同人は気の毒だ」と考えられる事に強い違和感があるんです。それはどちらかというと私から持ち出した話ではないと記憶していますが、違いましたか?
私個人としては、FSW界隈も、同人も別にかわいそうだとは思ってません。
あと、
>まぁ、20年延長されるってことは、同人さんのお子さんが親の財産を相続した結果、
>訴えられる可能性のある期間も延びるんですけどね。
時効を忘れてませんか?関係のある最大の期間でもおそらく20年だと思います。元著作権者の死去からの保護機関が20年延びたって、今回の件にはあんまり関係なさそうな気がします。
……死去したあとで、その死去された方の作品の同人を描く、というようなケースくらいかなぁ。その場合しかし、やっぱり「同人者の遺族」にはあまり(おそらくはぜんぜん?)関係ないような気がしますが。二次創作した当人がどうかって話はあるかもしれませんが。
その通り。私は実際には同人とFSWが対立した構図になるなんて一つも考えていません。一応技術屋の端くれでもありますし。*だからこそ*「FSW界隈と比較して、同人は気の毒だ」と考えられる事に強い違和感があるんです。それはどちらかというと私から持ち出した話ではないと記憶していますが、違いましたか?
私個人としては、FSW界隈も、同人も別にかわいそうだとは思ってません。
あと、
>まぁ、20年延長されるってことは、同人さんのお子さんが親の財産を相続した結果、
>訴えられる可能性のある期間も延びるんですけどね。
時効を忘れてませんか?関係のある最大の期間でもおそらく20年だと思います。元著作権者の死去からの保護機関が20年延びたって、今回の件にはあんまり関係なさそうな気がします。
……死去したあとで、その死去された方の作品の同人を描く、というようなケースくらいかなぁ。その場合しかし、やっぱり「同人者の遺族」にはあまり(おそらくはぜんぜん?)関係ないような気がしますが。二次創作した当人がどうかって話はあるかもしれませんが。
>>97
「感想」としている事については割愛。個人の自由である個人の感想は、
外部にそれをもらす限り、それをまた批判される事も
是認されねばならないとは思うけれど。この件に関してはさすがにオフトピックなので、これ以上このトピックでは続けません。失礼しました>皆様
>侵害し続けていますよね、存在している限り。
これはおかしい。侵害し続けているとすれば、新しく複製を行った場合か、翻案を行った場合と考えるべきだ。そうでなければ、例えば金品を不法行為によって詐取した場合の時効は、金品を全て返還してからスタートする事になる。
この場合、これは当然判例もある事であるはずだけれど、金品を詐取された事実を知ったときから3年、もしくは不法行為が行われた時点から20年で損害賠償請求の時効を迎える。
>(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
>第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
>損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
>不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5
>(消滅時効の進行等)
>第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.3
のであるから、敷衍して考えれば著作権法上の消滅時効はある著作物を複製した段階から始まると考えても良いし、もしくは私的複製を超えて複製しはじめたときから考えても良いかもしれない。「存在し続けているかぎり、侵害し続ける」などという事はこの国の法律上ありえないと思うのだが、どうでしょうか。
長い側に贔屓目に見ても、最後に複製物の譲渡を終えた瞬間を消滅時効の起算時刻と考えるのが一番長いし、一番短ければ消滅時効の起算時刻は「その著作物を複製し始めたとき」つまりは執筆開始時点、という事になるでしょう。その時から20年ですね。
刑事事件でそれ以上長い時効は死刑に相当する罪の場合の25年しかないです(これも非親告罪と考えてです)から、複製したものの最後の譲渡から20年が最大の時効と考えるのが妥当だと思います。
もちろん、書いてから延々と複製・頒布し続けていたなら別です。その場合は場合によっては、複製権の時効取得が援用できる可能性が出てきそうですが。そこまで行くとちょっと私の手には負えないですね。複製権の時効取得が「ありえる」という最高裁判決については、有名なポパイ事件があると思います。アレの場合はそもそもが著作権が消滅している、という判決なので、その事件に関しての時効取得の援用は理由が無い、とされたと思います。
「感想」としている事については割愛。個人の自由である個人の感想は、
外部にそれをもらす限り、それをまた批判される事も
是認されねばならないとは思うけれど。この件に関してはさすがにオフトピックなので、これ以上このトピックでは続けません。失礼しました>皆様
>侵害し続けていますよね、存在している限り。
これはおかしい。侵害し続けているとすれば、新しく複製を行った場合か、翻案を行った場合と考えるべきだ。そうでなければ、例えば金品を不法行為によって詐取した場合の時効は、金品を全て返還してからスタートする事になる。
この場合、これは当然判例もある事であるはずだけれど、金品を詐取された事実を知ったときから3年、もしくは不法行為が行われた時点から20年で損害賠償請求の時効を迎える。
>(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
>第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
>損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
>不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5
>(消滅時効の進行等)
>第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.3
のであるから、敷衍して考えれば著作権法上の消滅時効はある著作物を複製した段階から始まると考えても良いし、もしくは私的複製を超えて複製しはじめたときから考えても良いかもしれない。「存在し続けているかぎり、侵害し続ける」などという事はこの国の法律上ありえないと思うのだが、どうでしょうか。
長い側に贔屓目に見ても、最後に複製物の譲渡を終えた瞬間を消滅時効の起算時刻と考えるのが一番長いし、一番短ければ消滅時効の起算時刻は「その著作物を複製し始めたとき」つまりは執筆開始時点、という事になるでしょう。その時から20年ですね。
刑事事件でそれ以上長い時効は死刑に相当する罪の場合の25年しかないです(これも非親告罪と考えてです)から、複製したものの最後の譲渡から20年が最大の時効と考えるのが妥当だと思います。
もちろん、書いてから延々と複製・頒布し続けていたなら別です。その場合は場合によっては、複製権の時効取得が援用できる可能性が出てきそうですが。そこまで行くとちょっと私の手には負えないですね。複製権の時効取得が「ありえる」という最高裁判決については、有名なポパイ事件があると思います。アレの場合はそもそもが著作権が消滅している、という判決なので、その事件に関しての時効取得の援用は理由が無い、とされたと思います。
>遺品の整理などでの二次著作物の販売
そりゃその整理を行った人間の問題でしょう。それが新たな侵害を構成するとして、それはもともとの論点であるところの「同人さんのお子さんが親の財産を相続した結果、訴えられる可能性」なんてのには含むとも思えません。「情を知つて」頒布するのであれば問題はその整理を行う人間の問題ですし、少なくとも現行法上では「情を知つて」頒布していなければ著作権の侵害には当たりません。
ついでに言えば、時効済の複製物を譲渡したからといって何か問題は生じる気がしないんですが、どうなんでしょうか。さすがにこの辺の時効関連については識者の意見を待ちたいところです。
>二次著作物をもとにした三次著作物が作成された場合
そりゃ三次著作物(なんて言葉は実際には無いような気がしますが、まぁ二次著作物の二次著作物、って事ですよね)の著者の問題でしょう。
それに二次著作物の著者やその遺族が侵害の発生にかかわる意味が分かりませんが。どのようなケースを想定されておられますか?法的には二次著作物の二次著作物は一次著作物の二次著作物と考えてよいのでは無いでしょうか?
ああ、二次著作物としての独創性のある部分について、なす氏の言うところの「三次著作物」の著者を二次著作物の著者が訴える、という可能性があるのはわかりますが。
そりゃその整理を行った人間の問題でしょう。それが新たな侵害を構成するとして、それはもともとの論点であるところの「同人さんのお子さんが親の財産を相続した結果、訴えられる可能性」なんてのには含むとも思えません。「情を知つて」頒布するのであれば問題はその整理を行う人間の問題ですし、少なくとも現行法上では「情を知つて」頒布していなければ著作権の侵害には当たりません。
ついでに言えば、時効済の複製物を譲渡したからといって何か問題は生じる気がしないんですが、どうなんでしょうか。さすがにこの辺の時効関連については識者の意見を待ちたいところです。
>二次著作物をもとにした三次著作物が作成された場合
そりゃ三次著作物(なんて言葉は実際には無いような気がしますが、まぁ二次著作物の二次著作物、って事ですよね)の著者の問題でしょう。
それに二次著作物の著者やその遺族が侵害の発生にかかわる意味が分かりませんが。どのようなケースを想定されておられますか?法的には二次著作物の二次著作物は一次著作物の二次著作物と考えてよいのでは無いでしょうか?
ああ、二次著作物としての独創性のある部分について、なす氏の言うところの「三次著作物」の著者を二次著作物の著者が訴える、という可能性があるのはわかりますが。
>そりゃその整理を行った人間の問題でしょう。
遺品の整理って、著作権者のお子さんが行いませんか?
二次著作権を相続し、遺品の中にあった二次著作物を、
現金化して兄弟で分割する。
なんてのが典型的なケースだと思いますが。
死んだ二次著作者が、ましてや後年、
著名な漫画家になってたりすれば、
初期の世に出回ってない作品は莫大な利益を生みますし。
>少なくとも現行法上では「情を知つて」頒布していなければ
>著作権の侵害には当たりません。
二次著作権者なんですから、
「情を知って」と類推されるのでは?
三次著作権者が一次著作権者から訴えられる可能性は少ないでしょうが、
(少ない=まぁ、まずありえない。くらいの意味です。
ただ、その三次著作権者が二次著作物の元ネタ議論に
参加してたりすれば、情を知っているとみなされるでしょう。)
許諾を受けていない二次著作物を配布した結果、
三次著作物による被害を受ければ、
その被害に対する賠償義務は、二次著作権者にありますよね。
>時効済の複製物を譲渡したからといって
>何か問題は生じる気がしないんですが、どうなんでしょうか。
譲渡許諾を受けていない以上、二次著作物の譲渡行為は、
一次著作物の無許可での翻案・譲渡とみなされる。
よって、その譲渡行為を行った時点で、
一次著作物の著作権者の権利侵害を行ったことになる。
二次著作物制作時の時効は関係ない。
と言うのが、私の考えです。
そうでなければ、ミッキーマウスの人形を大量製造し、
3年(または10年)だか保管しておけば、
著作権侵害にならないことになります。
現在の運用と比較しても、
時効の考え方は間違っていると思います。
よって、関係するのは、
まさに議論の中核である「著作権の期間」でしょう。
遺品の整理って、著作権者のお子さんが行いませんか?
二次著作権を相続し、遺品の中にあった二次著作物を、
現金化して兄弟で分割する。
なんてのが典型的なケースだと思いますが。
死んだ二次著作者が、ましてや後年、
著名な漫画家になってたりすれば、
初期の世に出回ってない作品は莫大な利益を生みますし。
>少なくとも現行法上では「情を知つて」頒布していなければ
>著作権の侵害には当たりません。
二次著作権者なんですから、
「情を知って」と類推されるのでは?
三次著作権者が一次著作権者から訴えられる可能性は少ないでしょうが、
(少ない=まぁ、まずありえない。くらいの意味です。
ただ、その三次著作権者が二次著作物の元ネタ議論に
参加してたりすれば、情を知っているとみなされるでしょう。)
許諾を受けていない二次著作物を配布した結果、
三次著作物による被害を受ければ、
その被害に対する賠償義務は、二次著作権者にありますよね。
>時効済の複製物を譲渡したからといって
>何か問題は生じる気がしないんですが、どうなんでしょうか。
譲渡許諾を受けていない以上、二次著作物の譲渡行為は、
一次著作物の無許可での翻案・譲渡とみなされる。
よって、その譲渡行為を行った時点で、
一次著作物の著作権者の権利侵害を行ったことになる。
二次著作物制作時の時効は関係ない。
と言うのが、私の考えです。
そうでなければ、ミッキーマウスの人形を大量製造し、
3年(または10年)だか保管しておけば、
著作権侵害にならないことになります。
現在の運用と比較しても、
時効の考え方は間違っていると思います。
よって、関係するのは、
まさに議論の中核である「著作権の期間」でしょう。
>二次著作権を相続し、遺品の中にあった二次著作物を、
>現金化して兄弟で分割する。
これについて「情を知つて」いるかどうかはケースバイケースでしょう。本人が「この著作物は完全な一次著作物である」と考えていたら、実は二次著作物であった、という可能性は普通に考えられます。私も同人者ですが、私の作成するような同人誌の元ネタが何であるかなんて、親が知ってるとも思えませんし、回りの同人者も同様なケースが多いです。
#相続者が、相続した財産について無見識である、なんていくらでもある事例です。
>>少なくとも現行法上では「情を知つて」頒布していなければ
>>著作権の侵害には当たりません。
↑は上記、相続者についての文脈での説明であって、次の「二次著作物の二次著作物」では考慮にいれていませんでした。
これが次の文脈とあわせて書かれるのは強い違和感を感じますが、まぁ別段支障はないと思います。
>許諾を受けていない二次著作物を配布した結果、
>三次著作物による被害を受ければ、
>その被害に対する賠償義務は、二次著作権者にありますよね。
状況が良く分かりませんが整理を試みます。
便宜上二次著作物の二次著作物を三次著作物とします。
・三次著作物を頒布した
・その三次著作物の元になった二次著作物は「一次著作物である」と三次著作物の著者は考えていた(「情を知つて」頒布していなかった)
という状況でしょうか。
普通に三次著作者が一次著作者から賠償請求を受けて終わりだと思いますが、何故違うんでしょうか。
少なくとも三次著作者は二次著作物の二次著作物である事を知っているわけです。
とはいえ、そういう状況はまったく生まれないとは確かに思いませんが(そういう実例も知っていますが)、
その場合ほとんどの場合その二次著作物そのものが一次著作物から乖離しすぎていて、
「新たな一次著作物である」と解される場合がほとんどのような気がします。
(例:ふたばちゃんねるにおける「わはむすちょいあ」等)
まぁマイナーな著作物の二次著作物であれば考えられない事はない……だろうか。
それにしてもまぁ、一次著作者は二次著作者にも三次著作者にも損害賠償請求権があると考えて良いような気がします。
逆に三次著作者による被害の分については、一時著作者は二次著作者に損害賠償を請求する事はできないと考えて良いと思いますが。
>譲渡許諾を受けていない以上、二次著作物の譲渡行為は、
>一次著作物の無許可での翻案・譲渡とみなされる。
>よって、その譲渡行為を行った時点で、
>一次著作物の著作権者の権利侵害を行ったことになる。
時効を受ける事になるのがどのような行為であるか、というのが問題になるでしょう。
少なくとも、一次著作者が頒布を行っていたことそのものに対して時効の主張が出来ると
考えて良いわけですから、その場合は頒布物の残数が少なければ全てに時効の援用ができるような
気がします。また、一定期間の頒布を行っていた事に対して時効が成立する場合、
複製権・譲渡権全てについて時効取得を主張できる可能性を考慮に入れるべきでしょう。
>そうでなければ、ミッキーマウスの人形を大量製造し、
>3年(または10年)だか保管しておけば、
無理ですね。継続的に頒布を行っていなかった場合は譲渡権の時効取得の主張は出来ません。
したがって、いくつかのケースを検討しましたが、ほとんどの場合は、遺族などに関しては著作権の期間が20年延長されたとしても、関係ないと考えてよいと思います。
>現金化して兄弟で分割する。
これについて「情を知つて」いるかどうかはケースバイケースでしょう。本人が「この著作物は完全な一次著作物である」と考えていたら、実は二次著作物であった、という可能性は普通に考えられます。私も同人者ですが、私の作成するような同人誌の元ネタが何であるかなんて、親が知ってるとも思えませんし、回りの同人者も同様なケースが多いです。
#相続者が、相続した財産について無見識である、なんていくらでもある事例です。
>>少なくとも現行法上では「情を知つて」頒布していなければ
>>著作権の侵害には当たりません。
↑は上記、相続者についての文脈での説明であって、次の「二次著作物の二次著作物」では考慮にいれていませんでした。
これが次の文脈とあわせて書かれるのは強い違和感を感じますが、まぁ別段支障はないと思います。
>許諾を受けていない二次著作物を配布した結果、
>三次著作物による被害を受ければ、
>その被害に対する賠償義務は、二次著作権者にありますよね。
状況が良く分かりませんが整理を試みます。
便宜上二次著作物の二次著作物を三次著作物とします。
・三次著作物を頒布した
・その三次著作物の元になった二次著作物は「一次著作物である」と三次著作物の著者は考えていた(「情を知つて」頒布していなかった)
という状況でしょうか。
普通に三次著作者が一次著作者から賠償請求を受けて終わりだと思いますが、何故違うんでしょうか。
少なくとも三次著作者は二次著作物の二次著作物である事を知っているわけです。
とはいえ、そういう状況はまったく生まれないとは確かに思いませんが(そういう実例も知っていますが)、
その場合ほとんどの場合その二次著作物そのものが一次著作物から乖離しすぎていて、
「新たな一次著作物である」と解される場合がほとんどのような気がします。
(例:ふたばちゃんねるにおける「わはむすちょいあ」等)
まぁマイナーな著作物の二次著作物であれば考えられない事はない……だろうか。
それにしてもまぁ、一次著作者は二次著作者にも三次著作者にも損害賠償請求権があると考えて良いような気がします。
逆に三次著作者による被害の分については、一時著作者は二次著作者に損害賠償を請求する事はできないと考えて良いと思いますが。
>譲渡許諾を受けていない以上、二次著作物の譲渡行為は、
>一次著作物の無許可での翻案・譲渡とみなされる。
>よって、その譲渡行為を行った時点で、
>一次著作物の著作権者の権利侵害を行ったことになる。
時効を受ける事になるのがどのような行為であるか、というのが問題になるでしょう。
少なくとも、一次著作者が頒布を行っていたことそのものに対して時効の主張が出来ると
考えて良いわけですから、その場合は頒布物の残数が少なければ全てに時効の援用ができるような
気がします。また、一定期間の頒布を行っていた事に対して時効が成立する場合、
複製権・譲渡権全てについて時効取得を主張できる可能性を考慮に入れるべきでしょう。
>そうでなければ、ミッキーマウスの人形を大量製造し、
>3年(または10年)だか保管しておけば、
無理ですね。継続的に頒布を行っていなかった場合は譲渡権の時効取得の主張は出来ません。
したがって、いくつかのケースを検討しましたが、ほとんどの場合は、遺族などに関しては著作権の期間が20年延長されたとしても、関係ないと考えてよいと思います。
そんな馬鹿な。。。
ミッキーの複製物について、1件でも損害賠償請求せずに、
時効が成立したら、ミッキーの複製権が消滅???
>これについて「情を知つて」いるかどうかはケースバイケースでしょう。
そんなに甘いものでしょうか?
もしそれが成立するのであれば、二次「創作者」は、
パクったことを黙って、その権利を他者に譲れば、
新しい二次「著作権者」(権利を譲渡された側)は、
一切、著作権侵害に対する請求は免れると。
権利を譲渡された二次著作権者が権利を行使するのであれば、
それが他人の権利を侵害していないかを確認する義務はあると思います。
ましてや、その譲渡から3年だが10年だかが経過し、
民法上の時効が成立したら、一次著作権者は、
誰に対しても損害賠償が請求できなくなる?
素晴らしい法理論だと思います。
で、exさんは、ご自身の主張が認められるとお考えですか?
ぜひ、著作権にうるさくビジネスとしても儲かる、
ディズニーの著作物についてやってほしいものです。
>普通に三次著作者が一次著作者から賠償請求を受けて
>終わりだと思いますが、何故違うんでしょうか。
三次著作者は一次著作物に対しては善意の第三者ですよね。
「情を知らない」二次著作権者への請求ができないのに、
同じく「情を知らない」三次著作者への請求ができると言う
主張は矛盾をきたしています。
一次著作権者が三次著作権者への請求ができないのであれば、
その損害を生んだ切っ掛けである一次著作物を無断翻案した
二次著作権者へ請求の矛先を向けるのは、極めて自然です。
>また、一定期間の頒布を行っていた事に対して時効が成立する場合、
>複製権・譲渡権全てについて時効取得を
>主張できる可能性を考慮に入れるべきでしょう。
「主張できる可能性」だけなら100%ありますからね。
で、その主張が認められる可能性は?まぁ、まずないでしょう。
許諾は個別に行える行為です。
ある領布に対して、差し止め行為を行わず、
時効を迎えたとしても、
それ以外の複製や譲渡行為に対しては、権利者である以上、
全く問題ないわけです。
そもぞも、その領布が許諾を得ていたかどうかが、
第三者から不明である以上、「時効に見えた」としても、
本当に「時効」なのか、許諾があったのか不明です。
許諾があった場合は、複製権・譲渡権が有効であるのに、
許諾がなく時効を迎えると、複製権・譲渡権が無効になる。
このような頓珍漢な主張が本当に「認められる」とお考えですか?
>継続的に頒布を行っていなかった場合は
>譲渡権の時効取得の主張は出来ません。
何故ですか?複製権を侵害しているんですよ。
複製権侵害の場合は時効にはならないが、
領布行為(譲渡権侵害)の場合だけ時効になる、
その法的根拠をお持ちでしょうか?
私は、許諾行為と言うのは個別案件であると考えるので、
過去の権利侵害が無効になったとしても、
権利存続中の新たな権利侵害に対しての権利主張はできると考えます。
もし、exさんの法理論が通るなら、
現在、漫画家さんなら許容するような同人誌を領布しておいて、
譲渡権・複製権の時効を迎えた後、その漫画家さんと
ほとんど同じマンガを大量複製して、安く売りまくりますね。
そのマンガの譲渡権・複製権は時効で消えているんでしょ?
変なの・・・
ミッキーの複製物について、1件でも損害賠償請求せずに、
時効が成立したら、ミッキーの複製権が消滅???
>これについて「情を知つて」いるかどうかはケースバイケースでしょう。
そんなに甘いものでしょうか?
もしそれが成立するのであれば、二次「創作者」は、
パクったことを黙って、その権利を他者に譲れば、
新しい二次「著作権者」(権利を譲渡された側)は、
一切、著作権侵害に対する請求は免れると。
権利を譲渡された二次著作権者が権利を行使するのであれば、
それが他人の権利を侵害していないかを確認する義務はあると思います。
ましてや、その譲渡から3年だが10年だかが経過し、
民法上の時効が成立したら、一次著作権者は、
誰に対しても損害賠償が請求できなくなる?
素晴らしい法理論だと思います。
で、exさんは、ご自身の主張が認められるとお考えですか?
ぜひ、著作権にうるさくビジネスとしても儲かる、
ディズニーの著作物についてやってほしいものです。
>普通に三次著作者が一次著作者から賠償請求を受けて
>終わりだと思いますが、何故違うんでしょうか。
三次著作者は一次著作物に対しては善意の第三者ですよね。
「情を知らない」二次著作権者への請求ができないのに、
同じく「情を知らない」三次著作者への請求ができると言う
主張は矛盾をきたしています。
一次著作権者が三次著作権者への請求ができないのであれば、
その損害を生んだ切っ掛けである一次著作物を無断翻案した
二次著作権者へ請求の矛先を向けるのは、極めて自然です。
>また、一定期間の頒布を行っていた事に対して時効が成立する場合、
>複製権・譲渡権全てについて時効取得を
>主張できる可能性を考慮に入れるべきでしょう。
「主張できる可能性」だけなら100%ありますからね。
で、その主張が認められる可能性は?まぁ、まずないでしょう。
許諾は個別に行える行為です。
ある領布に対して、差し止め行為を行わず、
時効を迎えたとしても、
それ以外の複製や譲渡行為に対しては、権利者である以上、
全く問題ないわけです。
そもぞも、その領布が許諾を得ていたかどうかが、
第三者から不明である以上、「時効に見えた」としても、
本当に「時効」なのか、許諾があったのか不明です。
許諾があった場合は、複製権・譲渡権が有効であるのに、
許諾がなく時効を迎えると、複製権・譲渡権が無効になる。
このような頓珍漢な主張が本当に「認められる」とお考えですか?
>継続的に頒布を行っていなかった場合は
>譲渡権の時効取得の主張は出来ません。
何故ですか?複製権を侵害しているんですよ。
複製権侵害の場合は時効にはならないが、
領布行為(譲渡権侵害)の場合だけ時効になる、
その法的根拠をお持ちでしょうか?
私は、許諾行為と言うのは個別案件であると考えるので、
過去の権利侵害が無効になったとしても、
権利存続中の新たな権利侵害に対しての権利主張はできると考えます。
もし、exさんの法理論が通るなら、
現在、漫画家さんなら許容するような同人誌を領布しておいて、
譲渡権・複製権の時効を迎えた後、その漫画家さんと
ほとんど同じマンガを大量複製して、安く売りまくりますね。
そのマンガの譲渡権・複製権は時効で消えているんでしょ?
変なの・・・
ちなみに、同一二次著作物に対しても同じです。
ミッキーマウスの人形を大量生産しておき、
時効を迎えるまでは、つつましく、形だけ商売をします。
人通りの全くない路地裏とか、検索にひっかからないようにして、
ネットで時間限定で販売をするとかですね。
こうすれば、継続的に、ミッキーマウスの違法複製商品を
販売していた実績ができるので、やがて複製行為についても、
exさんが主張するところの領布についても、
時効が成立して、もはやディズニーは権利を失うことになります。
そして、時効成立後には、大々的に商売を始めればよい。
あとは、訴えられた時に「これまでの商売の実績です。」と
販売記録を見せれば良いんですね。
そうすれば、その後、そのディズニー違法コピー商品は、
違法ではなくなると。。。
インターネットが普及して10年は経ちますね。
初期から違法音楽データを流していた人たちに対して、
JASRACは時効理論で請求権を失うことになりますね。
そうすると、その楽曲をそのサイトでは使いたい放題?
複製権・譲渡権について時効理論が通用するなら、
公衆送信権についても適用できるでしょうから。。。
で、再確認ですが、そのような時効理論が
本当に通用するとお考えですか?
ミッキーマウスの人形を大量生産しておき、
時効を迎えるまでは、つつましく、形だけ商売をします。
人通りの全くない路地裏とか、検索にひっかからないようにして、
ネットで時間限定で販売をするとかですね。
こうすれば、継続的に、ミッキーマウスの違法複製商品を
販売していた実績ができるので、やがて複製行為についても、
exさんが主張するところの領布についても、
時効が成立して、もはやディズニーは権利を失うことになります。
そして、時効成立後には、大々的に商売を始めればよい。
あとは、訴えられた時に「これまでの商売の実績です。」と
販売記録を見せれば良いんですね。
そうすれば、その後、そのディズニー違法コピー商品は、
違法ではなくなると。。。
インターネットが普及して10年は経ちますね。
初期から違法音楽データを流していた人たちに対して、
JASRACは時効理論で請求権を失うことになりますね。
そうすると、その楽曲をそのサイトでは使いたい放題?
複製権・譲渡権について時効理論が通用するなら、
公衆送信権についても適用できるでしょうから。。。
で、再確認ですが、そのような時効理論が
本当に通用するとお考えですか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
著作権 更新情報
-
最新のアンケート