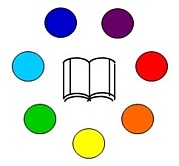当会にしては珍しく?、ビジネス書的な本が今回の課題本でした。その名も『イシューからはじめよ』。この本の記載に100%同意できるかといわれれば、そこには懐疑的になる方が多かった気がします。職場の現実や、生産性の定義などにも話が及びました。個人的に興味深かったトピックを以下に紹介します。
まずは、イシューの共有をいかに行うのか、という話です。(本当に導けるかは脇に置いといて)導出されたイシューには、何かしら革新的なものが多いと思うのですが、それを組織内でいかに意識共有して実行していくか。上下関係が基本の職場においては、「上から下へ」「下から上へ」どちらの場合でも、イシューが空中分解しがちになってしまう、という話です。これは(私も含め)ジャパニーズ・サラリマンなら誰もが頷いてしまう話だと思います。上でも下でもなく、「横から」という仕組みが必要なのかもしれません。しかしそれによって、自身の身は守れるのか。日曜劇場的な話ですね。
次は、イシューマトリクスにより導出された解の実現可能性です。「都市部なのに住居に虫が出て困る」という問題が出た際、まず実行する手段は「ブラッ○キャ○プ」等の駆除剤を置くこと。しかし、虫は徐々に耐性を付けていくため、効果は逓減し、置く個数を増やしていかないといけない。それどころか、相手が100%の耐性を身につけた暁には、別種の駆除剤を用意しなければならない。ところがそれに対しても耐性を……。と、これこそ「犬の道」と言えるのではないでしょうか。そこでイシューマトリクスにより「虫と共に生きる」という解が導出された際、我々はそれに従うべきか。いや、従うことができるか。解に必ずしも従えないイシューとして、環境問題なんかも挙げられると思います。この場合は、利害関心の異なる複数のアクターがいる状況での解の調整が「犬の道」へ着陸することとなります。おや、そうなると、上で挙げた「横から」の話と似てきますね。
そこで、私が読書会中に思いつきで述べた話になる訳です。すなわち、本書におけるイシューマトリクスは、二次関数的に言うとx軸y軸共に正の値である第1象限に限られていましたが、これに負の値も加味することで、第2〜4象限への広がりが生まれるのではないか、これにより先の虫の話や環境問題の解もマトリクス上に位置付けることができるのではないか、という話です。実はこの報告を書いている時に少しググったら、実際にマトリクスを第4象限まで含めて説明している画像を見つけたのですが、しかしそれは、本書における(0,0)の点を第3象限の最左下に置き換えただけで、本書におけるマトリクスと何ら変わりのないものでした。私がここで提案したのは、y軸における「解の質のマイナス値」=「基本的価値観からの踏み外し」、x軸における「イシュー度のマイナス値」=「条件からの離脱」といったものです。ま、あくまで思いつきですが。
あと面白かった論点としては、私は本書のキモを「時間だ」と何回も言ったところ、その時間を短縮し生産性を高めることそのものへの「不安」が挙げられた点でした。まさにその通りだと思います。本書の中にも「イシューに基づく仕事は人間の本能に無理を強いる仕事だ」的なことが書かれてありましたし、資本主義リアリズムの一端に触れた気がして心地よかったです笑。
今回の読書会を振り返ると、なにより初参加の方にお越しいただいたのが嬉しかったです。これに懲りず、またご一緒できるとありがたいです。では以下、当日言い足りなかったことなど何でもどうぞ〜。
まずは、イシューの共有をいかに行うのか、という話です。(本当に導けるかは脇に置いといて)導出されたイシューには、何かしら革新的なものが多いと思うのですが、それを組織内でいかに意識共有して実行していくか。上下関係が基本の職場においては、「上から下へ」「下から上へ」どちらの場合でも、イシューが空中分解しがちになってしまう、という話です。これは(私も含め)ジャパニーズ・サラリマンなら誰もが頷いてしまう話だと思います。上でも下でもなく、「横から」という仕組みが必要なのかもしれません。しかしそれによって、自身の身は守れるのか。日曜劇場的な話ですね。
次は、イシューマトリクスにより導出された解の実現可能性です。「都市部なのに住居に虫が出て困る」という問題が出た際、まず実行する手段は「ブラッ○キャ○プ」等の駆除剤を置くこと。しかし、虫は徐々に耐性を付けていくため、効果は逓減し、置く個数を増やしていかないといけない。それどころか、相手が100%の耐性を身につけた暁には、別種の駆除剤を用意しなければならない。ところがそれに対しても耐性を……。と、これこそ「犬の道」と言えるのではないでしょうか。そこでイシューマトリクスにより「虫と共に生きる」という解が導出された際、我々はそれに従うべきか。いや、従うことができるか。解に必ずしも従えないイシューとして、環境問題なんかも挙げられると思います。この場合は、利害関心の異なる複数のアクターがいる状況での解の調整が「犬の道」へ着陸することとなります。おや、そうなると、上で挙げた「横から」の話と似てきますね。
そこで、私が読書会中に思いつきで述べた話になる訳です。すなわち、本書におけるイシューマトリクスは、二次関数的に言うとx軸y軸共に正の値である第1象限に限られていましたが、これに負の値も加味することで、第2〜4象限への広がりが生まれるのではないか、これにより先の虫の話や環境問題の解もマトリクス上に位置付けることができるのではないか、という話です。実はこの報告を書いている時に少しググったら、実際にマトリクスを第4象限まで含めて説明している画像を見つけたのですが、しかしそれは、本書における(0,0)の点を第3象限の最左下に置き換えただけで、本書におけるマトリクスと何ら変わりのないものでした。私がここで提案したのは、y軸における「解の質のマイナス値」=「基本的価値観からの踏み外し」、x軸における「イシュー度のマイナス値」=「条件からの離脱」といったものです。ま、あくまで思いつきですが。
あと面白かった論点としては、私は本書のキモを「時間だ」と何回も言ったところ、その時間を短縮し生産性を高めることそのものへの「不安」が挙げられた点でした。まさにその通りだと思います。本書の中にも「イシューに基づく仕事は人間の本能に無理を強いる仕事だ」的なことが書かれてありましたし、資本主義リアリズムの一端に触れた気がして心地よかったです笑。
今回の読書会を振り返ると、なにより初参加の方にお越しいただいたのが嬉しかったです。これに懲りず、またご一緒できるとありがたいです。では以下、当日言い足りなかったことなど何でもどうぞ〜。
|
|
|
|
コメント(5)
今更ですが、イシュー本コメントです。
『基本的価値観からの踏み外し』『条件からの離脱』の話、とても面白かったです。そもそもの解の質の認識をぶっ壊す感じ。イイ!
虫との共存の例でいえば、虫を排除したいという顧客にとって、絶対認めたくないこと=虫と生きる、が根本の解決につながるという🤣なんというブーメラン技。
本書はビジネス本だったので、顧客からの評価をベースにした非常に狭い範囲の生産性について書いてありましたが
私は顧客(に都合の良い)満足度なんかよりも、長期的視野に立ち、より広い範囲な解決に繋がるような解が好きですし、それを示してくれる人がいてくれることの方が大事かと思います。
ゴキブリの侵入を防ぎたいという顧客のニーズに対し、受け入れろと諭すビジネスマン。これが当然として受け入れられる世の中が来たら、最高にクールですよね。
自分にとってのイシューは、誰にとって、何にとってのイシューか。まずそこから始めろや、と言いたいですね 笑
『基本的価値観からの踏み外し』『条件からの離脱』の話、とても面白かったです。そもそもの解の質の認識をぶっ壊す感じ。イイ!
虫との共存の例でいえば、虫を排除したいという顧客にとって、絶対認めたくないこと=虫と生きる、が根本の解決につながるという🤣なんというブーメラン技。
本書はビジネス本だったので、顧客からの評価をベースにした非常に狭い範囲の生産性について書いてありましたが
私は顧客(に都合の良い)満足度なんかよりも、長期的視野に立ち、より広い範囲な解決に繋がるような解が好きですし、それを示してくれる人がいてくれることの方が大事かと思います。
ゴキブリの侵入を防ぎたいという顧客のニーズに対し、受け入れろと諭すビジネスマン。これが当然として受け入れられる世の中が来たら、最高にクールですよね。
自分にとってのイシューは、誰にとって、何にとってのイシューか。まずそこから始めろや、と言いたいですね 笑
追記
私の前職でも、同様の話題が出てまして。
児童館とはどうあるべきか、というイシューに対し、『児童館なんてなくても、地域で支え合えるような世の中になればいいじゃない』と言い放ったヤベー上司がいましたよ笑
子供たちを取り巻く厳しい現状や問題が浮上したからこそ児童館は作られたのですから、児童館の来館者を増やすだの、より快適な設備を充実させるだの言うよりも、まずは子供に関わる問題を取り除くこと力を尽くし、100年後には立派に用済みとなって朽ち果てるのが児童館の使命だという。笑えますが、最高です。
子供たちに関わる問題は本当に様々で根が深く、そう易々と解決できるものではないと分かっています。が、目的地くらい遠くに設定したいですよね。
長文失礼しました〜(*☻-☻*)
私の前職でも、同様の話題が出てまして。
児童館とはどうあるべきか、というイシューに対し、『児童館なんてなくても、地域で支え合えるような世の中になればいいじゃない』と言い放ったヤベー上司がいましたよ笑
子供たちを取り巻く厳しい現状や問題が浮上したからこそ児童館は作られたのですから、児童館の来館者を増やすだの、より快適な設備を充実させるだの言うよりも、まずは子供に関わる問題を取り除くこと力を尽くし、100年後には立派に用済みとなって朽ち果てるのが児童館の使命だという。笑えますが、最高です。
子供たちに関わる問題は本当に様々で根が深く、そう易々と解決できるものではないと分かっています。が、目的地くらい遠くに設定したいですよね。
長文失礼しました〜(*☻-☻*)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|