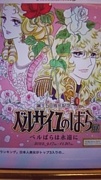賢い市民となるために不可欠なもの…それは教育
しかし現在の学校はというと麻薬に手を出したり、性犯罪をやらかしたり、殺人行為をする犯罪者の巣窟となっています…おまけに本来死刑にしなくてはならないのに罪が軽い
一方でモンスターペアレントなどの問題もあって教師の自殺もまた増えているのです……おまけに生徒には善悪の区別がつかない地上で最低の害獣でしかないなもたくさんいるようだし
今 行われてるのは教育でなく凶育です…この現実を変えるためにはまずは問題点をここで炙り出しましょう
追加……悲しいことに何者かの密告があったため、加害者の名前のかいた記事をいくつか消しました
しかし陰湿で卑怯な密告にもめげずにやっていきましょう
しかし現在の学校はというと麻薬に手を出したり、性犯罪をやらかしたり、殺人行為をする犯罪者の巣窟となっています…おまけに本来死刑にしなくてはならないのに罪が軽い
一方でモンスターペアレントなどの問題もあって教師の自殺もまた増えているのです……おまけに生徒には善悪の区別がつかない地上で最低の害獣でしかないなもたくさんいるようだし
今 行われてるのは教育でなく凶育です…この現実を変えるためにはまずは問題点をここで炙り出しましょう
追加……悲しいことに何者かの密告があったため、加害者の名前のかいた記事をいくつか消しました
しかし陰湿で卑怯な密告にもめげずにやっていきましょう
|
|
|
|
コメント(125)
小学校で跳び箱事故が頻発、一年で5000件超 着地に失敗して下半身不随になった生徒も
2018.09.16
1 名前:名無しさん@涙目です。(catv?) [SK]:2018/09/15(土) 23:31:34.16 ID:EkPU8dv20
何が起きたのか公表したがらず、十分な説明をすることもない。隠蔽が疑われるような学校対応は、いじめだけに限らない。授業や部活中の事故でも同様だ。
'17年5月11日、横浜市鶴見区の市立中学校で、中学2年生だった男子生徒、山下翔くん(15=仮名)が体育の授業中、高さ90センチの跳び箱から落下。胸から下が動かなくなった。
事故を受けて、市の学校保健審議会は「学校安全部会」を設置。原因を調査し、'18年6月、詳細調査報告書にまとめて再発防止策を提言している。これに対し、「個人の責任とも読めるため納得がいかない」という両親が取材に応じた。
報告書によると、翔くんは開脚跳びで5段の跳び箱を跳ぼうとしていた。ロイター板を踏み切ったとき、腰の位置が高くなり、跳び箱に手をついたが体勢が崩れた。そして、勢いをつけたまま、前方に敷かれていたマット(厚さ約20センチ)の上に頭から落ちてしまった。首は強制的にまげられる形になり、頸椎を脱臼。病院に救急搬送され、手術したが、足は動かないままだ。
日本スポーツ振興センターによると、'16年度中の「器械体操・新体操」での事故は1万2622件。このうち跳び箱運動は5046件と半数弱だ。小学校では、学校での事故で最も多いほど頻発している。
https://news.nifty.com/article/magazine/12148-088187/
2018.09.16
1 名前:名無しさん@涙目です。(catv?) [SK]:2018/09/15(土) 23:31:34.16 ID:EkPU8dv20
何が起きたのか公表したがらず、十分な説明をすることもない。隠蔽が疑われるような学校対応は、いじめだけに限らない。授業や部活中の事故でも同様だ。
'17年5月11日、横浜市鶴見区の市立中学校で、中学2年生だった男子生徒、山下翔くん(15=仮名)が体育の授業中、高さ90センチの跳び箱から落下。胸から下が動かなくなった。
事故を受けて、市の学校保健審議会は「学校安全部会」を設置。原因を調査し、'18年6月、詳細調査報告書にまとめて再発防止策を提言している。これに対し、「個人の責任とも読めるため納得がいかない」という両親が取材に応じた。
報告書によると、翔くんは開脚跳びで5段の跳び箱を跳ぼうとしていた。ロイター板を踏み切ったとき、腰の位置が高くなり、跳び箱に手をついたが体勢が崩れた。そして、勢いをつけたまま、前方に敷かれていたマット(厚さ約20センチ)の上に頭から落ちてしまった。首は強制的にまげられる形になり、頸椎を脱臼。病院に救急搬送され、手術したが、足は動かないままだ。
日本スポーツ振興センターによると、'16年度中の「器械体操・新体操」での事故は1万2622件。このうち跳び箱運動は5046件と半数弱だ。小学校では、学校での事故で最も多いほど頻発している。
https://news.nifty.com/article/magazine/12148-088187/
2017.12.13 Wed
司法における「ブラック校則」問題と、これからの政治の役割
荻上チキ・真下麻里子
ブラック校則をめぐる悲鳴
法や規則というものは、さまざまな背景を有する人が存在する社会において、その多様性を尊重し、個人の尊厳を守るために存在する。ルールを作るということは、社会秩序を守ることそれ自体が目的ではなく、ルールを制定するという手段によって、各個人の権利を守るものだ。ペナルティ等は、あくまでそのための一手段、それも最終手段にすぎない。しかし実際には、合理性が認められないルールが温存され、「ルールはルール」として人を不当に抑圧や排除をし、場合によっては懲罰を課すというような事態も起こりうる。
本稿は、最近インターネット上などで話題になっている「ブラック校則」について取り上げる。「ブラック校則」とは、子どもの健康や尊厳を損なうような、近代的な市民社会では許容されないような理不尽な学校内のルールのことを指す。
筆者らはtwitter上で「#ブラック校則」というハッシュタグを用い、「かつて子どもだった大人たち」を中心に、実際に経験した理不尽な校則の事例を収集した。そこに集まってきたのは、髪の毛の色や長さ、地毛証明、下着チェックなど、身だしなみに対する過度な制約や、水分補給の禁止、給食を食べ終わるまで放課後になっても居残りさせること、果ては学内恋愛の禁止や防寒対策の禁止まで、さまざまな事例だ。
これらの中には、「校則」として明示されているもののみならず、明示がなくても、学校の雰囲気として、あるいは校長や担任などの裁量によって、「当然のルール」として機能しているものも含まれている。
「ブラック校則」に関する話題は、最近報道されたひとつの事件に端を発している。その事件とは、生まれつき地毛の色素が薄いにもかかわらず、黒髪を強要されたことを苦痛に感じ、不登校になってしまったと訴える大阪府立高校の生徒が、府に対して損害賠償請求を行ったというものだ。
これは特異な事例というわけではなさそうだ。2017年4月、朝日新聞が行った調査報道によれば、東京の都立高校のうち、約6割の高校が、生徒が髪の毛を染めたりパーマをかけたりしていないかを確認するため、一部生徒に「地毛証明書」を提出させていることが分かっている。
地毛証明は、生徒の「黒くまっすぐな髪ではない」という身体的特徴に着目し、自己申告させるものであり、当該生徒が「他と異なる」ことをことさらに強調してしまう。「申告しなければならない生徒」の心情に対する配慮を著しく欠くものだ。同時に、本来生徒を守る立場にあるべき学校が、生徒に不当なレッテルを貼るにも等しく、からかいや排除を助長させる可能性からしても問題である。
校則は、これまで学校が子どもを「管理」するために活用されてきた。もちろん、すべての校則が不要であるわけではないし、学校にも広い裁量は必要だ。だが、校則が不当な抑圧や排除のツールとして機能し、子どもの人権を侵犯するようなケースがあるのであれば、それは是正されなくてはならない。
また、しばしば、厳しい校則が教育的効果と結びつけて論じられることがある。しかし、その効果は、個人の経験則にもとづくものが多く、学術研究等にもとづくものはきわめて少ないと感じる。子どもの人権に対して制約を課す以上は、適切な根拠にもとづく校則の運用が必要であり、これにもとづかないで行われる厳しい制約は見直されるべきだろう。
「社会に出たら理不尽なことがたくさんある、だから子どものうちから理不尽なことに慣れなければ、温室育ちでダメになる」という主張をよく聞く。この理屈にはいくつも問題がある。学校は、社会で適切に生きていくための能力を培う場所である。社会にはさまざまな理不尽があるが、そこで必要なのは、そうした理不尽さに慣れ、過剰適応し、疑問を抱かないようにすることではない。
本来必要なのは、理不尽さに疑問を抱き、そこから距離を取り、改善を求めるような力である。
司法における「ブラック校則」問題と、これからの政治の役割
荻上チキ・真下麻里子
ブラック校則をめぐる悲鳴
法や規則というものは、さまざまな背景を有する人が存在する社会において、その多様性を尊重し、個人の尊厳を守るために存在する。ルールを作るということは、社会秩序を守ることそれ自体が目的ではなく、ルールを制定するという手段によって、各個人の権利を守るものだ。ペナルティ等は、あくまでそのための一手段、それも最終手段にすぎない。しかし実際には、合理性が認められないルールが温存され、「ルールはルール」として人を不当に抑圧や排除をし、場合によっては懲罰を課すというような事態も起こりうる。
本稿は、最近インターネット上などで話題になっている「ブラック校則」について取り上げる。「ブラック校則」とは、子どもの健康や尊厳を損なうような、近代的な市民社会では許容されないような理不尽な学校内のルールのことを指す。
筆者らはtwitter上で「#ブラック校則」というハッシュタグを用い、「かつて子どもだった大人たち」を中心に、実際に経験した理不尽な校則の事例を収集した。そこに集まってきたのは、髪の毛の色や長さ、地毛証明、下着チェックなど、身だしなみに対する過度な制約や、水分補給の禁止、給食を食べ終わるまで放課後になっても居残りさせること、果ては学内恋愛の禁止や防寒対策の禁止まで、さまざまな事例だ。
これらの中には、「校則」として明示されているもののみならず、明示がなくても、学校の雰囲気として、あるいは校長や担任などの裁量によって、「当然のルール」として機能しているものも含まれている。
「ブラック校則」に関する話題は、最近報道されたひとつの事件に端を発している。その事件とは、生まれつき地毛の色素が薄いにもかかわらず、黒髪を強要されたことを苦痛に感じ、不登校になってしまったと訴える大阪府立高校の生徒が、府に対して損害賠償請求を行ったというものだ。
これは特異な事例というわけではなさそうだ。2017年4月、朝日新聞が行った調査報道によれば、東京の都立高校のうち、約6割の高校が、生徒が髪の毛を染めたりパーマをかけたりしていないかを確認するため、一部生徒に「地毛証明書」を提出させていることが分かっている。
地毛証明は、生徒の「黒くまっすぐな髪ではない」という身体的特徴に着目し、自己申告させるものであり、当該生徒が「他と異なる」ことをことさらに強調してしまう。「申告しなければならない生徒」の心情に対する配慮を著しく欠くものだ。同時に、本来生徒を守る立場にあるべき学校が、生徒に不当なレッテルを貼るにも等しく、からかいや排除を助長させる可能性からしても問題である。
校則は、これまで学校が子どもを「管理」するために活用されてきた。もちろん、すべての校則が不要であるわけではないし、学校にも広い裁量は必要だ。だが、校則が不当な抑圧や排除のツールとして機能し、子どもの人権を侵犯するようなケースがあるのであれば、それは是正されなくてはならない。
また、しばしば、厳しい校則が教育的効果と結びつけて論じられることがある。しかし、その効果は、個人の経験則にもとづくものが多く、学術研究等にもとづくものはきわめて少ないと感じる。子どもの人権に対して制約を課す以上は、適切な根拠にもとづく校則の運用が必要であり、これにもとづかないで行われる厳しい制約は見直されるべきだろう。
「社会に出たら理不尽なことがたくさんある、だから子どものうちから理不尽なことに慣れなければ、温室育ちでダメになる」という主張をよく聞く。この理屈にはいくつも問題がある。学校は、社会で適切に生きていくための能力を培う場所である。社会にはさまざまな理不尽があるが、そこで必要なのは、そうした理不尽さに慣れ、過剰適応し、疑問を抱かないようにすることではない。
本来必要なのは、理不尽さに疑問を抱き、そこから距離を取り、改善を求めるような力である。
大人の責任
2017年5月11日
 Toba Yoshiaki
Toba Yoshiaki  9:17 PM
9:17 PM
※※※5月11日(木)※※※
「モラルハザード」という言葉があります。 直訳すると「倫理観の欠如」、「道徳的危機」となります。
最近の子供達の様子を見て、「モラルハザード」の低下を嘆く声も聞かれますが、子供達は社会での立ち振る舞いや公衆道徳を知らない(大人にも目立ちますが)だけで、これは、我々大人の責任でもあります。
モラルハザードの低下は、子供ではなく我々大人の責任の問題で、子供達の生き生きとした行動を大切にしながら、上手に子供達に教えてやる大人の心配りが必要でしょう。
先日、ある新聞に掲載されていた年配読者からの次の様な投稿がありました。 その内容は、エレベータに乗り込んできた女子学生の傍若無人な振る舞いについてです。
「廻りに多くの乗客がいるにもかかわらず、大声で話しながら乗り込んできた女子学生に対して、我慢ならずにきつく注意したところとても気まずい雰囲気になった。
しかし、この女子学生達はエレベータを降りる時に、自分たちの非礼をきちんと詫びた。 社会の大人が先ず、姿勢を正し、子供達にきちんと教えなければならない事、言うべきことの大切さを、改めて知った。」というものでした。
私も、先日同じようなことを経験しただけに、思わず頷きました。 私の場合は、野洲駅でのことです。
電車に乗ろうと急いで駅のホームに上がったところ、券売機の前に中学生の長蛇の列があり通行を阻んでいました。 他の乗客も前へ進めません。
私は教員経験もありますので、「おーい、僕達、他の皆さんの邪魔になるから通り道を空けて。」と言いながら無事電車に乗ることができました。
でも、よく考えると、彼らは中学生の体育大会の帰りで、その切符を1人ひとりが買っていたんです。 先ず、ここが問題です。
少なくともこういう場合、引率教員が団体券を購入して、集団で行動させるべきです。 それができない場合でも、生徒達に公の施設である駅での行動に対する注意と指導をすべきです。
それが、この様な場合における教員の重要な仕事です。 この様なケースは、正に、教員の指導ができていないことに起因した子供たちのモラルハザードの欠如です。
大人が注意しておけば、防げたという典型的な実例です。 しかし、最近は「大人のモラルハザードの低いこと限りなし」です。
大人のモラルハザードに直球勝負。
2017年5月11日
※※※5月11日(木)※※※
「モラルハザード」という言葉があります。 直訳すると「倫理観の欠如」、「道徳的危機」となります。
最近の子供達の様子を見て、「モラルハザード」の低下を嘆く声も聞かれますが、子供達は社会での立ち振る舞いや公衆道徳を知らない(大人にも目立ちますが)だけで、これは、我々大人の責任でもあります。
モラルハザードの低下は、子供ではなく我々大人の責任の問題で、子供達の生き生きとした行動を大切にしながら、上手に子供達に教えてやる大人の心配りが必要でしょう。
先日、ある新聞に掲載されていた年配読者からの次の様な投稿がありました。 その内容は、エレベータに乗り込んできた女子学生の傍若無人な振る舞いについてです。
「廻りに多くの乗客がいるにもかかわらず、大声で話しながら乗り込んできた女子学生に対して、我慢ならずにきつく注意したところとても気まずい雰囲気になった。
しかし、この女子学生達はエレベータを降りる時に、自分たちの非礼をきちんと詫びた。 社会の大人が先ず、姿勢を正し、子供達にきちんと教えなければならない事、言うべきことの大切さを、改めて知った。」というものでした。
私も、先日同じようなことを経験しただけに、思わず頷きました。 私の場合は、野洲駅でのことです。
電車に乗ろうと急いで駅のホームに上がったところ、券売機の前に中学生の長蛇の列があり通行を阻んでいました。 他の乗客も前へ進めません。
私は教員経験もありますので、「おーい、僕達、他の皆さんの邪魔になるから通り道を空けて。」と言いながら無事電車に乗ることができました。
でも、よく考えると、彼らは中学生の体育大会の帰りで、その切符を1人ひとりが買っていたんです。 先ず、ここが問題です。
少なくともこういう場合、引率教員が団体券を購入して、集団で行動させるべきです。 それができない場合でも、生徒達に公の施設である駅での行動に対する注意と指導をすべきです。
それが、この様な場合における教員の重要な仕事です。 この様なケースは、正に、教員の指導ができていないことに起因した子供たちのモラルハザードの欠如です。
大人が注意しておけば、防げたという典型的な実例です。 しかし、最近は「大人のモラルハザードの低いこと限りなし」です。
大人のモラルハザードに直球勝負。
黒髪のファシズム
2017.11.07
大阪府立高校の頭髪指導問題に関する訴訟をきっかけに日本の頭髪指導の行き過ぎは海外でも批判の的に晒されてるらしい。
学校側では自毛が元々茶色の女子学生に対し黒染めを共用し、「例え金髪の外国人留学生であっても校則に従い黒に染めさせる」と言ったそうだ。
当該学生はパニックを起こして不登校になり、学校側は生徒名簿から氏名を削除していたらしい。
全くおかしな話だ。
そもそも、何故髪の毛が全員真っ黒でないといけないのか。
しかし、何故こうした話がおかしいのか一度考えてみる必要がある。
僕は今回の報道に触れて日本の学校の規範に関するある出来事を思い出した。
1980年代の後半だったと思う。
僕が住んでいた愛媛県の松山市はドイツのフライブルク市と姉妹都市提携を結ぶことになり、そのための視察としてフライブルク市の市会議員たちが松山市を訪問したことがあった。
僕はドイツ語の通訳として参加した。
市は歓迎行事としてドイツの議員団をある「優秀な」中学校へ招待することになった。その中学校は統制が取れている、あるいはお行儀が良いということで市でも一二を争う「模範校」だった。
学校では体育館に制服を着た生徒と吹奏楽団を配し議員団を待ったいた。ドイツ人も我々通訳もそのことを知らなかった。
体育館の入口が開くと先生の号令で制服を着た数百人の生徒たちが全員起立、号令一下、吹奏楽団がドイツ国歌を演奏し始め、生徒たちがドイツ語で歌い始める。
真正面の舞台には大きな日の丸とドイツ国旗、それをバックに全員不動の姿勢をとったままの生徒たちが無表情なままでドイツ国歌を歌っているのだ。
ドイツ人たちは体育館の入口から中へ入ろうとしない。
年配のドイツ人の議員の一人が「驚いた、これはまるでHJ(ヒトラー青年団)じゃないか!」と仲間に言った。
20名ほどいたドイツ人が入口から中へ入ろうとしないので僕たち通訳兼引率は全く困ってしまった。
歌が終わると先生の号令で一同が着席、膝に指を伸ばした手を置いて前を向いたまま微動だしない。
ドイツ人の議員たちはあからさまに不快というか異様なものを見ているといった表情だった。
しかし、生徒指導の先生はこうした統率を見せることが嬉しいのか、得意満面の笑顔で「どうですか、私たちの生徒たちは(素晴らしいでしょ?)」と言ってくる。
「市民からもお行儀の良さと校風は高く評価されている」と言って通訳してくれという。
議員団の団長は「イギリスではこういうのは少しは残っているかもしれないが、ドイツではない」と言ったのだが、先生たちはネガティブな意味だと分からず喜んでいる。団長は「ドイツではアルテモーディッシュだ」と言った。早い話は時代遅れという意味だ。
僕はそのことを先生に伝えたが、この答えには意外だったらしい。
「こういうのはドイツ人は一番嫌うのですよ」と僕は伝えたが最後まで伝わることはなかった。
これは極端な例だが僕は学校の統率による画一化された秩序の在り方が実に滑稽なものであり団長が言ったように前時代的なものであることを日本人として思い知ったわけである。
黒髪でなければならないという拘束は僕たちの学生時代から既に存在していた。それは髪を染める、パーマをかけるという行為が「不良少年」や「不良少女」がやる行為だと思われていたからである。
学校で画一化に反抗していた生徒たちは改造制服を着て髪の毛を染めたりパーマをあてていたりしていた。
「不良」といえば髪染めパーマが象徴となっていた。
学校は「不良」化を塞き止めるために校則を強化し、身体検査や頭髪検査を繁盛に行った。少しでも髪の毛が規定より長ければその場で髪を切られた。
TVでは非行問題を主題としたTVドラマ『積木くずし』がブームでここでも髪染めやパーマが非行の象徴であるかのような表象がなされていた。
学校は何が何でも彼らが規範とした秩序を守らなければならなかったのだ。
この頃から訳のわからない「頭髪証明書」とかが登場していた。
学校の秩序とは各々から個性を剥奪して全員が同じでなくてはならないというものである。
これはマイノリティを排除してゆく法則に基づいている。いわゆる「腐ったミカン」の論理だ。
マジョリティはあくまでも同じで揃っている側である。
僕が通っていた高校は男子校だったが、見事に秩序が崩壊していて校則に制帽を着用のことと記されていても誰ひとりとして制帽を被るものはいなかった。全校生徒で制帽を着用していたのは僕一人だった。帽子着用に関しては誰も守らないのでいつの間にか被らないことが普通になっていて、なし崩しで生徒指導部もそれを容認していた。
2017.11.07
大阪府立高校の頭髪指導問題に関する訴訟をきっかけに日本の頭髪指導の行き過ぎは海外でも批判の的に晒されてるらしい。
学校側では自毛が元々茶色の女子学生に対し黒染めを共用し、「例え金髪の外国人留学生であっても校則に従い黒に染めさせる」と言ったそうだ。
当該学生はパニックを起こして不登校になり、学校側は生徒名簿から氏名を削除していたらしい。
全くおかしな話だ。
そもそも、何故髪の毛が全員真っ黒でないといけないのか。
しかし、何故こうした話がおかしいのか一度考えてみる必要がある。
僕は今回の報道に触れて日本の学校の規範に関するある出来事を思い出した。
1980年代の後半だったと思う。
僕が住んでいた愛媛県の松山市はドイツのフライブルク市と姉妹都市提携を結ぶことになり、そのための視察としてフライブルク市の市会議員たちが松山市を訪問したことがあった。
僕はドイツ語の通訳として参加した。
市は歓迎行事としてドイツの議員団をある「優秀な」中学校へ招待することになった。その中学校は統制が取れている、あるいはお行儀が良いということで市でも一二を争う「模範校」だった。
学校では体育館に制服を着た生徒と吹奏楽団を配し議員団を待ったいた。ドイツ人も我々通訳もそのことを知らなかった。
体育館の入口が開くと先生の号令で制服を着た数百人の生徒たちが全員起立、号令一下、吹奏楽団がドイツ国歌を演奏し始め、生徒たちがドイツ語で歌い始める。
真正面の舞台には大きな日の丸とドイツ国旗、それをバックに全員不動の姿勢をとったままの生徒たちが無表情なままでドイツ国歌を歌っているのだ。
ドイツ人たちは体育館の入口から中へ入ろうとしない。
年配のドイツ人の議員の一人が「驚いた、これはまるでHJ(ヒトラー青年団)じゃないか!」と仲間に言った。
20名ほどいたドイツ人が入口から中へ入ろうとしないので僕たち通訳兼引率は全く困ってしまった。
歌が終わると先生の号令で一同が着席、膝に指を伸ばした手を置いて前を向いたまま微動だしない。
ドイツ人の議員たちはあからさまに不快というか異様なものを見ているといった表情だった。
しかし、生徒指導の先生はこうした統率を見せることが嬉しいのか、得意満面の笑顔で「どうですか、私たちの生徒たちは(素晴らしいでしょ?)」と言ってくる。
「市民からもお行儀の良さと校風は高く評価されている」と言って通訳してくれという。
議員団の団長は「イギリスではこういうのは少しは残っているかもしれないが、ドイツではない」と言ったのだが、先生たちはネガティブな意味だと分からず喜んでいる。団長は「ドイツではアルテモーディッシュだ」と言った。早い話は時代遅れという意味だ。
僕はそのことを先生に伝えたが、この答えには意外だったらしい。
「こういうのはドイツ人は一番嫌うのですよ」と僕は伝えたが最後まで伝わることはなかった。
これは極端な例だが僕は学校の統率による画一化された秩序の在り方が実に滑稽なものであり団長が言ったように前時代的なものであることを日本人として思い知ったわけである。
黒髪でなければならないという拘束は僕たちの学生時代から既に存在していた。それは髪を染める、パーマをかけるという行為が「不良少年」や「不良少女」がやる行為だと思われていたからである。
学校で画一化に反抗していた生徒たちは改造制服を着て髪の毛を染めたりパーマをあてていたりしていた。
「不良」といえば髪染めパーマが象徴となっていた。
学校は「不良」化を塞き止めるために校則を強化し、身体検査や頭髪検査を繁盛に行った。少しでも髪の毛が規定より長ければその場で髪を切られた。
TVでは非行問題を主題としたTVドラマ『積木くずし』がブームでここでも髪染めやパーマが非行の象徴であるかのような表象がなされていた。
学校は何が何でも彼らが規範とした秩序を守らなければならなかったのだ。
この頃から訳のわからない「頭髪証明書」とかが登場していた。
学校の秩序とは各々から個性を剥奪して全員が同じでなくてはならないというものである。
これはマイノリティを排除してゆく法則に基づいている。いわゆる「腐ったミカン」の論理だ。
マジョリティはあくまでも同じで揃っている側である。
僕が通っていた高校は男子校だったが、見事に秩序が崩壊していて校則に制帽を着用のことと記されていても誰ひとりとして制帽を被るものはいなかった。全校生徒で制帽を着用していたのは僕一人だった。帽子着用に関しては誰も守らないのでいつの間にか被らないことが普通になっていて、なし崩しで生徒指導部もそれを容認していた。
だから僕が制帽を着用するという校則に則った行動は逆に嘲笑の的となった。学生からも教師からも馬鹿にされたものだった。帽子を被っているというだけで集団に殴られたりもした。
僕は完全にマイノリティだったが、制帽着用は卒業までやめなかった。それは僕が学校の秩序に対して筋を通そうとした反抗だったからだ。
今から考えれば「不良少年」や「不良少女」と呼ばれた人たちの毛染めやパーマも学校の画一化する秩序に対するカウンター行動だったことがよく分かる。しかし、当時の感覚からすればそれは絶対に認められない行為であり断固排除されなければならない存在であった。
このように学校という空間では揃っていることが原則として重要で、それを侵すものは排除される。
2017年、既に30数年を経過した今、未だに学校は全員が揃っていなければならないという校則の価値観を守り通しているのだということに僕は驚きを禁じえない。
多様性を認めよう、国際化社会など日本がと言い始めて久しいが学校の現場では何も変わっていなかったのは如何にも日本らしい現象であると思う。
1980年代の後半に既にドイツ人から「アルテモーディッシュだ」と呼ばれていた価値観を更に30数年間守り通し、今もそれが続いている。
茶髪は1990年代頃に茶髪ブームが起きて髪を染める行為などは当たり前になって今日に至っている。
昨今、日本のファシズム化が進んでいることを危惧する声も聞かれるようになったが、未来を担う青少年を育てる教育現場が全員黒髪でなくてはならないと言っているのでは、既にファシズム化は完全に定着しているようなものだ。
「例え金髪の外国人留学生であっても校則に従い黒に染めさせる」
こうした原理主義的な考えが正義とされる社会において我々が国際社会に身を置く場所は残されていないだろう。
学校の先生たちはいったい何を守ろうとしているのだろうか?当人たちはそれすらも答えを出せないのではあるまいか。
ガラパゴス化は我々の身近で当たり前に思っているところに幾つでも見出すことができる。
日本人の常識は世界に通用すると考えるには世界が何歩も先を進んでいる。
これは戦前、戦後、我々日本人が今一度考え直さなくてはならない重要で深刻な問題である。
これが黒髪のファシズムなのだと。
執筆:永田喜嗣
僕は完全にマイノリティだったが、制帽着用は卒業までやめなかった。それは僕が学校の秩序に対して筋を通そうとした反抗だったからだ。
今から考えれば「不良少年」や「不良少女」と呼ばれた人たちの毛染めやパーマも学校の画一化する秩序に対するカウンター行動だったことがよく分かる。しかし、当時の感覚からすればそれは絶対に認められない行為であり断固排除されなければならない存在であった。
このように学校という空間では揃っていることが原則として重要で、それを侵すものは排除される。
2017年、既に30数年を経過した今、未だに学校は全員が揃っていなければならないという校則の価値観を守り通しているのだということに僕は驚きを禁じえない。
多様性を認めよう、国際化社会など日本がと言い始めて久しいが学校の現場では何も変わっていなかったのは如何にも日本らしい現象であると思う。
1980年代の後半に既にドイツ人から「アルテモーディッシュだ」と呼ばれていた価値観を更に30数年間守り通し、今もそれが続いている。
茶髪は1990年代頃に茶髪ブームが起きて髪を染める行為などは当たり前になって今日に至っている。
昨今、日本のファシズム化が進んでいることを危惧する声も聞かれるようになったが、未来を担う青少年を育てる教育現場が全員黒髪でなくてはならないと言っているのでは、既にファシズム化は完全に定着しているようなものだ。
「例え金髪の外国人留学生であっても校則に従い黒に染めさせる」
こうした原理主義的な考えが正義とされる社会において我々が国際社会に身を置く場所は残されていないだろう。
学校の先生たちはいったい何を守ろうとしているのだろうか?当人たちはそれすらも答えを出せないのではあるまいか。
ガラパゴス化は我々の身近で当たり前に思っているところに幾つでも見出すことができる。
日本人の常識は世界に通用すると考えるには世界が何歩も先を進んでいる。
これは戦前、戦後、我々日本人が今一度考え直さなくてはならない重要で深刻な問題である。
これが黒髪のファシズムなのだと。
執筆:永田喜嗣
教育委員会の裏は闇
2011.12.27
いかがでしょうか? こんな無茶苦茶な逮捕が許されて良いのでしょうか? 最近よく、
「体罰が出来なくなった。やるとすぐクビになる」
などと戸塚ヨットースクールのシンパみたいな教師がよく言いますわな。だけど、体罰で懲戒免職になる教員って北海道から沖縄まで何人いると思います? 毎年、ゼロという年が珍しくないんですよ(ただし公立学校に限る)。
しかも、生徒に骨折を負わせたとか、かない酷い体罰でも文書訓告とか戒告だったりするんですよ。兵庫県なんかそんな大甘の処分が以前は普通やったんですよ。女子生徒へのセクハラだと、流石に懲戒免職になる人はいますけどね。それでも年間10人程度とじゃなかったかと記憶してます。
流石に文部科学省の官僚も呆れて「甘すぎる」と言っていた程です。それに当然ですけど、これはあくまで教育委員会→文部科学省に報告が上がった一部の事例であって、実際は学校現場で不祥事が起きても内密にされていることが、殆どなんです。
第一、教育委員会に教師に不当な眼に遭ったと相談しても、教員籍の指導主事という職員が学校長と吊るんでウヤムヤにすることが多いんですわ。兵庫県下の教育委員会は特にそないです。
おまけに人を骨折させといて「文書訓告」って何やねん。僕の罪名は「右腕上腕部殴打」「頭突き」で暴行やて(途中から公務執妨害に罪名変更)。それで、逮捕されて20日間拘留。これ一体何やと思います。
ところで、兵庫県教育委員会事務局広報担当者が、問題のK市教育委員会に、
「ブログや記事にして”不当逮捕”やと言うのは止めてもらいたい」
と弁護士を通じて圧力掛けた意図を確認すると、
「そういう(圧力をかけた)事実はありません」
なんて報告した福田慎治生徒指導係長殿、貴方教育委員会に上がって来たばかりの時、随分助言してあげましたよね。
「角田さんのお陰で大分、仕事に慣れました」
と半年程経過した時、貴方の方から言わはりましたよね。忘れたとは言わせませんよ。それから、渡邊智明指導係長、獄中面会で弁護士から聴いたけど、
「東京都議会議員のブログにウチの職員に危害を加えるという犯行予告を書いた」
って出鱈目を弁護士に言うたでしょ! そんな嘘まで付いて人を陥れたいんですか!
まあ、大衆は皆さんを裁くでしょう。それが証拠に釈放されてから、「この犯罪者め!」なんて罵る人は誰もいませんでしたよ。それどころか、皆心配してくれて、法律に素人の取材対象者の人でも、
「それなら、角田さんが向こうを訴えることが出来るんじゃないですか」
とまで言っていますよ。嘆願署名集めると言ってくれた、親しい弁護士さんもいます。
この際ですよ。何処かの新興宗教同様、膿は出すだけ出そうやないですか。
「私は何も恐れない。ただ、大衆のみを恐れる」(三木武夫元首相)
2011.12.27
いかがでしょうか? こんな無茶苦茶な逮捕が許されて良いのでしょうか? 最近よく、
「体罰が出来なくなった。やるとすぐクビになる」
などと戸塚ヨットースクールのシンパみたいな教師がよく言いますわな。だけど、体罰で懲戒免職になる教員って北海道から沖縄まで何人いると思います? 毎年、ゼロという年が珍しくないんですよ(ただし公立学校に限る)。
しかも、生徒に骨折を負わせたとか、かない酷い体罰でも文書訓告とか戒告だったりするんですよ。兵庫県なんかそんな大甘の処分が以前は普通やったんですよ。女子生徒へのセクハラだと、流石に懲戒免職になる人はいますけどね。それでも年間10人程度とじゃなかったかと記憶してます。
流石に文部科学省の官僚も呆れて「甘すぎる」と言っていた程です。それに当然ですけど、これはあくまで教育委員会→文部科学省に報告が上がった一部の事例であって、実際は学校現場で不祥事が起きても内密にされていることが、殆どなんです。
第一、教育委員会に教師に不当な眼に遭ったと相談しても、教員籍の指導主事という職員が学校長と吊るんでウヤムヤにすることが多いんですわ。兵庫県下の教育委員会は特にそないです。
おまけに人を骨折させといて「文書訓告」って何やねん。僕の罪名は「右腕上腕部殴打」「頭突き」で暴行やて(途中から公務執妨害に罪名変更)。それで、逮捕されて20日間拘留。これ一体何やと思います。
ところで、兵庫県教育委員会事務局広報担当者が、問題のK市教育委員会に、
「ブログや記事にして”不当逮捕”やと言うのは止めてもらいたい」
と弁護士を通じて圧力掛けた意図を確認すると、
「そういう(圧力をかけた)事実はありません」
なんて報告した福田慎治生徒指導係長殿、貴方教育委員会に上がって来たばかりの時、随分助言してあげましたよね。
「角田さんのお陰で大分、仕事に慣れました」
と半年程経過した時、貴方の方から言わはりましたよね。忘れたとは言わせませんよ。それから、渡邊智明指導係長、獄中面会で弁護士から聴いたけど、
「東京都議会議員のブログにウチの職員に危害を加えるという犯行予告を書いた」
って出鱈目を弁護士に言うたでしょ! そんな嘘まで付いて人を陥れたいんですか!
まあ、大衆は皆さんを裁くでしょう。それが証拠に釈放されてから、「この犯罪者め!」なんて罵る人は誰もいませんでしたよ。それどころか、皆心配してくれて、法律に素人の取材対象者の人でも、
「それなら、角田さんが向こうを訴えることが出来るんじゃないですか」
とまで言っていますよ。嘆願署名集めると言ってくれた、親しい弁護士さんもいます。
この際ですよ。何処かの新興宗教同様、膿は出すだけ出そうやないですか。
「私は何も恐れない。ただ、大衆のみを恐れる」(三木武夫元首相)
友人からの情報です
教員採用半年で自殺、日記に残された言葉
長時間労働で精神的不安、睡眠恐怖も
2016年12月13日
福井新聞
自ら命を絶った嶋田友生さんの日記。2014年5月13日の欄には「いつになったらこの生活も終るのだろう」との表記があり、心身ともに追い込まれていた様子がうかがえる
疲れました。迷わくをかけてしまいすみません――。福井県若狭町の中学校の社会科教諭、嶋田友生(ともお)さん=当時(27)=は中学時代から毎日欠かさず付けていた日記にこう残し、自ら命を絶った。教員採用されてからわずか半年だった。長時間労働などにより精神的に追い込まれる教員は福井県内でも少なくない。教育現場からの「叫び」をリポートした。
時間外業務は月128〜161時間
友生さんは4年間の中学校学習支援員、講師を経て2014年4月、中学校教諭に採用された。1年生の担任を受け持つことが決まり迎えた入学式。同6日の日記には「21名の子どもたちを前にしてワクワクするとともに、不安もひしひしと感じた」と記した。
半年後の10月6日。初めて学校を休んだ。体調が悪そうな友生さんに母が病院に行くよう勧めたが「病院かあ。ぼちぼち行くわ」。昼すぎ、友生さんは学校に行くと告げて車で家を出た。母は毎夕、友生さんにメールをするのが日課だったが、この日は返信がこなかった。翌7日、母の実家で友生さんの車が見つかった。車中には練炭。友生さんは一酸化炭素中毒で死亡していた。
友生さんは、講師時の中学校と当時の勤務校との授業スタイルや指導方法の違いに悩んでいた様子だったという。友生さんの父・富士男さん(56)は「5月ごろから疲れた表情を見せるようになった」と振り返る。初任者研修の一環としての授業を10月中旬に行う予定だったが、この指導案作成にも苦労しており、口内炎ができたり、食欲が落ちたりと様子は悪化していった。亡くなる前日には頭を悩ませている様子で、「あかん。なかなかできん」と母に話していたという。
使用していたパソコンなどの記録から、4〜6月の時間外業務は月128〜161時間に上ると見られている。
友生さんの精神疾患と自殺に相当の因果関係があるとして今年9月6日、公務災害と認定された。6月ごろ、何らかの精神疾患を発症していたとされる。担当した村上昌寛弁護士によると、一般的な労災のケースでは申請から認定まで1年〜1年半程度かかるが、友生さんの場合は約9カ月で認定されたという。県内教員の認定は初ではないかといい、「勤務時間が非常に長いことが大きかった。日記には指導案が出来上がらないことなどから、寝ることに恐怖を感じていたような記述があり、悩みやストレスを発散する時間もなかったとみられる」と説明する。
富士男さんは「息子は精神的にも肉体的にも強い人間だったのに、なぜ……」と友生さんの死を今も受け入れられないでいる。「本当の原因が分からんから、息子に掛ける言葉も見つからない」。友生さんの遺骨は自宅に残されたままだ。
教員採用半年で自殺、日記に残された言葉
長時間労働で精神的不安、睡眠恐怖も
2016年12月13日
福井新聞
自ら命を絶った嶋田友生さんの日記。2014年5月13日の欄には「いつになったらこの生活も終るのだろう」との表記があり、心身ともに追い込まれていた様子がうかがえる
疲れました。迷わくをかけてしまいすみません――。福井県若狭町の中学校の社会科教諭、嶋田友生(ともお)さん=当時(27)=は中学時代から毎日欠かさず付けていた日記にこう残し、自ら命を絶った。教員採用されてからわずか半年だった。長時間労働などにより精神的に追い込まれる教員は福井県内でも少なくない。教育現場からの「叫び」をリポートした。
時間外業務は月128〜161時間
友生さんは4年間の中学校学習支援員、講師を経て2014年4月、中学校教諭に採用された。1年生の担任を受け持つことが決まり迎えた入学式。同6日の日記には「21名の子どもたちを前にしてワクワクするとともに、不安もひしひしと感じた」と記した。
半年後の10月6日。初めて学校を休んだ。体調が悪そうな友生さんに母が病院に行くよう勧めたが「病院かあ。ぼちぼち行くわ」。昼すぎ、友生さんは学校に行くと告げて車で家を出た。母は毎夕、友生さんにメールをするのが日課だったが、この日は返信がこなかった。翌7日、母の実家で友生さんの車が見つかった。車中には練炭。友生さんは一酸化炭素中毒で死亡していた。
友生さんは、講師時の中学校と当時の勤務校との授業スタイルや指導方法の違いに悩んでいた様子だったという。友生さんの父・富士男さん(56)は「5月ごろから疲れた表情を見せるようになった」と振り返る。初任者研修の一環としての授業を10月中旬に行う予定だったが、この指導案作成にも苦労しており、口内炎ができたり、食欲が落ちたりと様子は悪化していった。亡くなる前日には頭を悩ませている様子で、「あかん。なかなかできん」と母に話していたという。
使用していたパソコンなどの記録から、4〜6月の時間外業務は月128〜161時間に上ると見られている。
友生さんの精神疾患と自殺に相当の因果関係があるとして今年9月6日、公務災害と認定された。6月ごろ、何らかの精神疾患を発症していたとされる。担当した村上昌寛弁護士によると、一般的な労災のケースでは申請から認定まで1年〜1年半程度かかるが、友生さんの場合は約9カ月で認定されたという。県内教員の認定は初ではないかといい、「勤務時間が非常に長いことが大きかった。日記には指導案が出来上がらないことなどから、寝ることに恐怖を感じていたような記述があり、悩みやストレスを発散する時間もなかったとみられる」と説明する。
富士男さんは「息子は精神的にも肉体的にも強い人間だったのに、なぜ……」と友生さんの死を今も受け入れられないでいる。「本当の原因が分からんから、息子に掛ける言葉も見つからない」。友生さんの遺骨は自宅に残されたままだ。
危険ドラッグ、横浜の中学生8割「手に入れることができる」
中学生の8割以上が、危険ドラッグを「手に入れることができる」と思っていることが、横浜市教育委員会が行った調査から明らかになった。小中学生の4人に1人は、危険ドラッグに接する場面があるという認識を示し、薬物やたばこに比べ、飲酒は抵抗感が低い傾向にある。
生活・健康 / 小学生
2016.5.6 Fri 18:45
子ども調査
チャイルドシート、不使用時の致死率は13.4倍…警察庁
待機児童数、過去最少の1万6,772人…3年間で約29.7万人分拡大も
都内高校生の大学進学率、4年ぶりに上昇
編集部にメッセージを送る
中学生の8割以上が、危険ドラッグを「手に入れることができる」と思っていることが、横浜市教育委員会が行った調査から明らかになった。小中学生の4人に1人は、危険ドラッグに接する場面があるという認識を示した。また、薬物やたばこに比べ、飲酒は抵抗感が低い傾向にある。
横浜市教育委員会が行った「薬物・たばこ・酒」に関する意識調査は、横浜市立小学校5年生、横浜市立中学校2年生を対象に実施。調査時期は平成27年12月から平成28年2月まで。小学生1,659人、中学生3,248人に無記名方式調査票が配布され、そのうち36.7%にあたる1,801人から回答を得た。
「危険ドラッグ」「脱法ハーブ」などの言葉の認識率は、小学生で84.8%、中学生で97.4%。脱法ハーブを含む危険ドラッグや覚せい剤などの薬物について、どのような印象をもっているかを聞くと、小中学生ともに9割以上が「健康に悪い」「使用や所持は犯罪である」と回答した。
また、それらを使う人がいるのはどういう理由からだと思うかと質問すると、「インターネットなどに使ってみたいと思わせるような情報がのっている」「1回使っただけでは害がないなど、薬物使用の怖さについて誤った情報があふれている」「簡単に手に入るようになった」などが多かった。また、小学生の37.2%、中学生の38.4%が「自分の置かれている状況に不満があるから」と回答している。
薬物乱用に対して、小中学生の9割以上が「使うべきではないし、許されない」という考えを示した。危険ドラッグ等に接する場面があると思うかを聞くと、4人に1人が「ある」と認識。危険ドラッグ等の入手については、小学生の70.6%、中学生の84.9%が「簡単に手に入ると思う」または「少し苦労するが、なんとか手に入ると思う」と回答していた。
また、たばこ・酒についても調査しており、たばこを吸ってみたいと思ったことがある小学生は3.9%、中学生は6.6%だった。一方、酒を飲んでみたいと思ったことがある割合は、小学生で31.4%、中学生では44.3%にのぼった。薬物、たばこと異なり、興味がある回答が多いことがわかった。なお、20歳になる前からの飲酒・喫煙がきっかけとなって薬物乱用につながると思うかを聞くと、小中学生の65%以上が「あると思う」と答えている。
教育委員会では今回のアンケート結果から、子どもたちが「危険ドラッグ」を比較的身近にあるものととらえていることを踏まえ、既存の学習内容に加え、小学6年生から危険ドラッグについても正しい知識を定着させるための指導資料作成を進める。また、その前段階である小学5年生から「薬物・飲酒・喫煙」に関する学習ができるよう、新たな教材づくりも行うという。
《黄金崎綾乃》
中学生の8割以上が、危険ドラッグを「手に入れることができる」と思っていることが、横浜市教育委員会が行った調査から明らかになった。小中学生の4人に1人は、危険ドラッグに接する場面があるという認識を示し、薬物やたばこに比べ、飲酒は抵抗感が低い傾向にある。
生活・健康 / 小学生
2016.5.6 Fri 18:45
子ども調査
チャイルドシート、不使用時の致死率は13.4倍…警察庁
待機児童数、過去最少の1万6,772人…3年間で約29.7万人分拡大も
都内高校生の大学進学率、4年ぶりに上昇
編集部にメッセージを送る
中学生の8割以上が、危険ドラッグを「手に入れることができる」と思っていることが、横浜市教育委員会が行った調査から明らかになった。小中学生の4人に1人は、危険ドラッグに接する場面があるという認識を示した。また、薬物やたばこに比べ、飲酒は抵抗感が低い傾向にある。
横浜市教育委員会が行った「薬物・たばこ・酒」に関する意識調査は、横浜市立小学校5年生、横浜市立中学校2年生を対象に実施。調査時期は平成27年12月から平成28年2月まで。小学生1,659人、中学生3,248人に無記名方式調査票が配布され、そのうち36.7%にあたる1,801人から回答を得た。
「危険ドラッグ」「脱法ハーブ」などの言葉の認識率は、小学生で84.8%、中学生で97.4%。脱法ハーブを含む危険ドラッグや覚せい剤などの薬物について、どのような印象をもっているかを聞くと、小中学生ともに9割以上が「健康に悪い」「使用や所持は犯罪である」と回答した。
また、それらを使う人がいるのはどういう理由からだと思うかと質問すると、「インターネットなどに使ってみたいと思わせるような情報がのっている」「1回使っただけでは害がないなど、薬物使用の怖さについて誤った情報があふれている」「簡単に手に入るようになった」などが多かった。また、小学生の37.2%、中学生の38.4%が「自分の置かれている状況に不満があるから」と回答している。
薬物乱用に対して、小中学生の9割以上が「使うべきではないし、許されない」という考えを示した。危険ドラッグ等に接する場面があると思うかを聞くと、4人に1人が「ある」と認識。危険ドラッグ等の入手については、小学生の70.6%、中学生の84.9%が「簡単に手に入ると思う」または「少し苦労するが、なんとか手に入ると思う」と回答していた。
また、たばこ・酒についても調査しており、たばこを吸ってみたいと思ったことがある小学生は3.9%、中学生は6.6%だった。一方、酒を飲んでみたいと思ったことがある割合は、小学生で31.4%、中学生では44.3%にのぼった。薬物、たばこと異なり、興味がある回答が多いことがわかった。なお、20歳になる前からの飲酒・喫煙がきっかけとなって薬物乱用につながると思うかを聞くと、小中学生の65%以上が「あると思う」と答えている。
教育委員会では今回のアンケート結果から、子どもたちが「危険ドラッグ」を比較的身近にあるものととらえていることを踏まえ、既存の学習内容に加え、小学6年生から危険ドラッグについても正しい知識を定着させるための指導資料作成を進める。また、その前段階である小学5年生から「薬物・飲酒・喫煙」に関する学習ができるよう、新たな教材づくりも行うという。
《黄金崎綾乃》
神戸市須磨区の市立東須磨小学校の20代男性教員が、同僚の先輩教員4人に暴行や暴言などのいじめ行為を昨年から継続的に受けていたことが3日、関係者への取材で分かった。
加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリ「LINE(ライン)」で第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたという。
男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされている。担任していたクラスには急きょ臨時講師が配置されている。
関係者によると、加害側の教員は30〜40代の男性3人、女性1人。LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送るよう強要。男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりした。
また、コピー用紙の芯で尻をたたいて腫れさせ、「ボケ」「カス」といった暴言を頻繁に浴びせていた。男性教員は「羽交い締めにされ、激辛カレーを無理やり食べさせられたり、目にこすりつけられたりした」とも訴えているという。
一連の行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導。
市教育委員会には、7月に「人間関係のトラブル」などと報告したとされる。
9月になって市教委は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始めた。被害の内容や時期、回数など詳細を確認した上で処分を検討するもよう。
加害側の4人は10月に入って休んでおり、市教委は速やかに人事異動などで人員を補充する方針という。
男性教員側は、処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するという。
いじめの問題を巡っては、同市垂水区で市立中学3年の女子生徒がいじめを苦に自殺し、いじめについて証言した同級生らのメモが隠蔽(いんぺい)された問題を受け、市教委は9月30日に「組織風土改革のための有識者会議」から最終報告書の提出を受けたばかり。報告書は、いじめ防止対策推進法の趣旨を学び続ける▽いじめが絶対に許されない行為であると児童生徒に指導する−などと提言している。
被害に遭った男性教師(20代)がどのようないじめ行為を受けていたのでしょうか。
報じられた内容によると
・・羽交い締めにされ、激辛カレーを無理やり食べさせられたり、目にこすりつけられたりした
・LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送るよう強要
・コピー用紙の芯で尻をたたいて腫れさせた
・「ボケ」「カス」といった暴言を頻繁に浴びせていた
・男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼされた
・お酒を無理やり飲まされた
・仕事が残っているのに自宅まで送迎を強要
被害に遭った男性は、
東須磨小の20代の男性教師ということでした。
この男性教師は精神的に不安定になり、
今年9月から休暇による療養を余儀なくされているようです。
処分内容や職場の改善状況を踏まえ、
刑事告訴について検討するということです。
これだけ酷いことをされてきたのですし、
これからの教育のためにも、
刑事告訴で頑張って戦っていただきたいと思います。
まずは身体をゆっくり休めていただきたいです。
被害に遭った教師が20代男性教師だけではなく、
他にもいたということです。
加害側の教師は、別の20代男性教員1人と20代女性教員2人に対してもいじめ行為をしていたという事が明らかになりました。
女性教員へは、セクハラ行為があったほか、
男性教員には、ポンコツの意味で「ポンちゃん」とのあだ名を付けていたといいます。
4人の教師の名前は、柴田祐介、蔀俊(しとみたかし)、佐志田英和、長谷川雅代
加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリ「LINE(ライン)」で第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたという。
男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされている。担任していたクラスには急きょ臨時講師が配置されている。
関係者によると、加害側の教員は30〜40代の男性3人、女性1人。LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送るよう強要。男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりした。
また、コピー用紙の芯で尻をたたいて腫れさせ、「ボケ」「カス」といった暴言を頻繁に浴びせていた。男性教員は「羽交い締めにされ、激辛カレーを無理やり食べさせられたり、目にこすりつけられたりした」とも訴えているという。
一連の行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導。
市教育委員会には、7月に「人間関係のトラブル」などと報告したとされる。
9月になって市教委は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始めた。被害の内容や時期、回数など詳細を確認した上で処分を検討するもよう。
加害側の4人は10月に入って休んでおり、市教委は速やかに人事異動などで人員を補充する方針という。
男性教員側は、処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するという。
いじめの問題を巡っては、同市垂水区で市立中学3年の女子生徒がいじめを苦に自殺し、いじめについて証言した同級生らのメモが隠蔽(いんぺい)された問題を受け、市教委は9月30日に「組織風土改革のための有識者会議」から最終報告書の提出を受けたばかり。報告書は、いじめ防止対策推進法の趣旨を学び続ける▽いじめが絶対に許されない行為であると児童生徒に指導する−などと提言している。
被害に遭った男性教師(20代)がどのようないじめ行為を受けていたのでしょうか。
報じられた内容によると
・・羽交い締めにされ、激辛カレーを無理やり食べさせられたり、目にこすりつけられたりした
・LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送るよう強要
・コピー用紙の芯で尻をたたいて腫れさせた
・「ボケ」「カス」といった暴言を頻繁に浴びせていた
・男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼされた
・お酒を無理やり飲まされた
・仕事が残っているのに自宅まで送迎を強要
被害に遭った男性は、
東須磨小の20代の男性教師ということでした。
この男性教師は精神的に不安定になり、
今年9月から休暇による療養を余儀なくされているようです。
処分内容や職場の改善状況を踏まえ、
刑事告訴について検討するということです。
これだけ酷いことをされてきたのですし、
これからの教育のためにも、
刑事告訴で頑張って戦っていただきたいと思います。
まずは身体をゆっくり休めていただきたいです。
被害に遭った教師が20代男性教師だけではなく、
他にもいたということです。
加害側の教師は、別の20代男性教員1人と20代女性教員2人に対してもいじめ行為をしていたという事が明らかになりました。
女性教員へは、セクハラ行為があったほか、
男性教員には、ポンコツの意味で「ポンちゃん」とのあだ名を付けていたといいます。
4人の教師の名前は、柴田祐介、蔀俊(しとみたかし)、佐志田英和、長谷川雅代
神戸・教師いじめ女ボスは「女帝」と呼ばれ、前校長のお気に入り 児童にいじめ自慢の話まで
2019/10/ 8 12:45
印刷
神戸市立東須磨小学校で起きた「教師による教師へのいじめ」事件で、新たに事実がわかってきた。
加害4教師の中でリーダー格は40代女性教師だが、前任の校長が気に入った教員を自分の学校に招き入れる「神戸方式」のシステムでやってきた。この女性教師は現校長より長く学校にいて、「校内ですごい発言力を持つ、ある種女帝で、いじめの標的定めをやっていた」(市議会でいじめ問題を話し合う委員会の岡田ゆうじ市議)という話もある。
「校内ですごい発言力を持ち、いじめの標的定めを」
加害男性教師の1人は激辛カレーを食べさせるなどのいじめ行為を授業中、児童に「おもしろかった的な話をしていた」(卒業した元教え子)ともいう。
キャスターの立川志らく「メチャクチャですね。教え子に話すなんて、バカじゃないか」
市教育委員会は処分を検討しているが、教育評論家の石川幸夫さんによると、依願退職の可能性はあるが、「教員免許はく奪はない」そうだ。加害教師が後日、他の学校で教えることもあり得るらしい。
鴻上尚史(演出家)「暴行障害だ。刑事事件にしないと教員免許はく奪には至らないだろう」
志らく「まだ事実が全部はわからないが、こんな女帝とかがきたらたまらない。加害側の話(言い分)を聞きたい。教師を続けたいなら出てきて、反省してほしい」
堤達生(ベンチャーキャピタリスト)「校長の任命責任も重い」
学校は被害教師が休職したことで、学校は今月3日(2019年10月)に保護者説明会を開いたが、出席した保護者は「足を踏んだぐらいしか語られず、翌日に新聞でいじめの内容を知りました」という。
司会の国山ハセン「それが学校側の保身なのだろうな」
2019/10/ 8 12:45
印刷
神戸市立東須磨小学校で起きた「教師による教師へのいじめ」事件で、新たに事実がわかってきた。
加害4教師の中でリーダー格は40代女性教師だが、前任の校長が気に入った教員を自分の学校に招き入れる「神戸方式」のシステムでやってきた。この女性教師は現校長より長く学校にいて、「校内ですごい発言力を持つ、ある種女帝で、いじめの標的定めをやっていた」(市議会でいじめ問題を話し合う委員会の岡田ゆうじ市議)という話もある。
「校内ですごい発言力を持ち、いじめの標的定めを」
加害男性教師の1人は激辛カレーを食べさせるなどのいじめ行為を授業中、児童に「おもしろかった的な話をしていた」(卒業した元教え子)ともいう。
キャスターの立川志らく「メチャクチャですね。教え子に話すなんて、バカじゃないか」
市教育委員会は処分を検討しているが、教育評論家の石川幸夫さんによると、依願退職の可能性はあるが、「教員免許はく奪はない」そうだ。加害教師が後日、他の学校で教えることもあり得るらしい。
鴻上尚史(演出家)「暴行障害だ。刑事事件にしないと教員免許はく奪には至らないだろう」
志らく「まだ事実が全部はわからないが、こんな女帝とかがきたらたまらない。加害側の話(言い分)を聞きたい。教師を続けたいなら出てきて、反省してほしい」
堤達生(ベンチャーキャピタリスト)「校長の任命責任も重い」
学校は被害教師が休職したことで、学校は今月3日(2019年10月)に保護者説明会を開いたが、出席した保護者は「足を踏んだぐらいしか語られず、翌日に新聞でいじめの内容を知りました」という。
司会の国山ハセン「それが学校側の保身なのだろうな」
教員の天下り先
2014/12/13 2015/06/20
今回は教員の天下りについてお話ししようと思う。
その前に、「天下り」という言葉の定義について確認しよう。元々は、高級官僚が退職後に勤務官庁と関連の深い民間企業や民間企業や団体の高い地位につくことを指すが、最近では官僚だけでなく、民間企業の上位幹部が子会社の要職に就く際などにも用いられるようだ。
この定義に照らし合わせると、教員の場合は校長や教頭が退職して他の企業や団体の要職に就くことが、教員の天下りと言えるだろう。
まさか各都道府県の教育委員会が「わが県の校長たちの天下り先一覧」なんて公開しているはずもなく、あくまで伝聞や推測ではあるが、教員の天下り先と言われるのは、私立校の校長や教頭、専門学校や大学等の広報担当、生涯学習財団、学校給食会、体育協会など、教育委員会に関連する財団や協会等の理事や事務局長などである。
さて、この天下りという言葉、なんとなくネガティブなイメージをお持ちの方も多いと思う。私も天下りと聞くと、良く解らないが「ずるい」「悪習」という言葉が浮かんでくる。
では具体的に、天下りの何が悪くて、逆にどんなメリットがあるのだろうか。
天下りがどんな問題を生む恐れがあるかというと、第一には汚職と癒着である。元官僚が民間企業の要職に就くということは、その後輩が元いた官庁のポストを継ぐわけである。つまり「今度のあの仕事、うちの会社にやらせてくれよ」と、先輩が後輩に頼む恐れがあるということだ。実際に、こうした事件は過去にいくつも露見している。
第二に、天下り先を作るために不必要な特殊法人や独立行政法人が作られる恐れがある。
一方で、今までに得た経験や能力を生かすことができるというメリットもある。教員においては、学校という現場を知っているということが、再就職先で生かせることもあるだろう。
立場を悪用する者や、無駄な団体やポストがないか、私達一人一人も目を光らせる必要がありそうだ。
- 実情 天下り, 教員
2014/12/13 2015/06/20
今回は教員の天下りについてお話ししようと思う。
その前に、「天下り」という言葉の定義について確認しよう。元々は、高級官僚が退職後に勤務官庁と関連の深い民間企業や民間企業や団体の高い地位につくことを指すが、最近では官僚だけでなく、民間企業の上位幹部が子会社の要職に就く際などにも用いられるようだ。
この定義に照らし合わせると、教員の場合は校長や教頭が退職して他の企業や団体の要職に就くことが、教員の天下りと言えるだろう。
まさか各都道府県の教育委員会が「わが県の校長たちの天下り先一覧」なんて公開しているはずもなく、あくまで伝聞や推測ではあるが、教員の天下り先と言われるのは、私立校の校長や教頭、専門学校や大学等の広報担当、生涯学習財団、学校給食会、体育協会など、教育委員会に関連する財団や協会等の理事や事務局長などである。
さて、この天下りという言葉、なんとなくネガティブなイメージをお持ちの方も多いと思う。私も天下りと聞くと、良く解らないが「ずるい」「悪習」という言葉が浮かんでくる。
では具体的に、天下りの何が悪くて、逆にどんなメリットがあるのだろうか。
天下りがどんな問題を生む恐れがあるかというと、第一には汚職と癒着である。元官僚が民間企業の要職に就くということは、その後輩が元いた官庁のポストを継ぐわけである。つまり「今度のあの仕事、うちの会社にやらせてくれよ」と、先輩が後輩に頼む恐れがあるということだ。実際に、こうした事件は過去にいくつも露見している。
第二に、天下り先を作るために不必要な特殊法人や独立行政法人が作られる恐れがある。
一方で、今までに得た経験や能力を生かすことができるというメリットもある。教員においては、学校という現場を知っているということが、再就職先で生かせることもあるだろう。
立場を悪用する者や、無駄な団体やポストがないか、私達一人一人も目を光らせる必要がありそうだ。
- 実情 天下り, 教員
2019年5月30日 投稿者: inouebin
学校と教員が「変化を恐れる」4つの理由
1 横並び至上主義
世の中が刻々と変化しても、頑として変わらないまま旧い体質を堅持しているのが学校です。言い方を変えれば、世間の変化の行く末をじっくり見守っていて、変化には実に慎重な態度を貫いている…、というポジティブな捉え方をすることもできます。しかしどうやら現実はそうではない…。誰よりも先に「変化」して、もしもその「変化」が失敗…、つまり世間からの攻撃に晒されることを想定した場合、その責任は、当然に当時の管理職が負うのですから、できれば「変化」は、最初にチャレンジするのではなく、誰かがそれを行って成功したところのものから手をつける…、それが学校管理職の常套手段となります。地域にあまたある学校は、そうやってお互いがお互いの学校の出方を見合っています。そして教育委員会は、配下にある学校が、決定的な失敗を犯さぬように日々、監視と指導の手を緩めません。尖った思考、改革的野心のある管理職は、仮にいたとしても、彼らの牙は徐々に丸く削られ周囲と調和するように矯正されていくんです。高い志をもって管理職試験に合格し、校長として学校に着任しても、そういった上からの圧力や介入を受け続けて「イヤになった」「バカバカしくなった」といって早々に現場を去って行った校長を知っています。尖った思考と野心は、学校という超保守的な現場には相応しくないのですね。だから、こうしてどの学校も似たり寄ったりの横並び現象が起こるのです。
学校と教員が「変化を恐れる」4つの理由
1 横並び至上主義
世の中が刻々と変化しても、頑として変わらないまま旧い体質を堅持しているのが学校です。言い方を変えれば、世間の変化の行く末をじっくり見守っていて、変化には実に慎重な態度を貫いている…、というポジティブな捉え方をすることもできます。しかしどうやら現実はそうではない…。誰よりも先に「変化」して、もしもその「変化」が失敗…、つまり世間からの攻撃に晒されることを想定した場合、その責任は、当然に当時の管理職が負うのですから、できれば「変化」は、最初にチャレンジするのではなく、誰かがそれを行って成功したところのものから手をつける…、それが学校管理職の常套手段となります。地域にあまたある学校は、そうやってお互いがお互いの学校の出方を見合っています。そして教育委員会は、配下にある学校が、決定的な失敗を犯さぬように日々、監視と指導の手を緩めません。尖った思考、改革的野心のある管理職は、仮にいたとしても、彼らの牙は徐々に丸く削られ周囲と調和するように矯正されていくんです。高い志をもって管理職試験に合格し、校長として学校に着任しても、そういった上からの圧力や介入を受け続けて「イヤになった」「バカバカしくなった」といって早々に現場を去って行った校長を知っています。尖った思考と野心は、学校という超保守的な現場には相応しくないのですね。だから、こうしてどの学校も似たり寄ったりの横並び現象が起こるのです。
2 学校管理職の既得権益
学校管理職ともなれば、もう教育に関してはベテランですから、そして地域の特性についても十分に認知してますから、その教育の方針や手法に関してはどなたでも一家言もっているものです。しかし前述したように、決して管理職は尖ったりしません。野心をもって尖り続けた先輩諸氏が、その後の教育界でどのようになったのかを知っているからです。学校運営の王道(超保守)からはずれ、何か特別なことをしようとして、それが世間の不評を買った場合、それを行った(例えば)校長に対する教育委員会から評価は下落します。評価が下落した場合、定年した後の再就職先は、悲しいかな(というかそれが本来の姿、常識なのですが)自力で獲得するしかないんです。つまり…、体の良い「天下り先」を用意してもらえないわけです。体の良い「天下り先」…、それは例えば補助金や助成金を頼みに学校経営を行っているところの私学の中学や高校への校長職なんです。そして私学にとってもこの天下りの受け入れには都合の良い一面がありまして、学校(私学)が不測の事態に陥った場合に、教育委員会や学事課のバックアップを受けることができる…、つまり困ったときには公立学校並に行政当局が保護下に置いてくれる…、だから日頃から上部機関である教育委員会や学事課とは昵懇な関係でいたい…、そのためには進んで公立の元校長を私学の校長に迎え入れるんですね。こうやって私学といえども公立の学校と同じような現象…、つまり超保守的な横並び現象が起こりのですね。ちなみに体の良い天下り先の次なる候補…、それが大学の教員職です。大学、特に学生募集に苦慮している大学にとって元校長という肩書きは、とても使い勝手がいい…、想像すればすぐにわかりますが元校長の赴任していた学校(高校)には当然に後輩が配属されています。その後輩に対して自身が天下った先の大学の受験者を増やすよう、積極的にアプローチするんです。「頼むぞ、受けさせてくれよな!」と。後述しますが、教育委員会での教員の序列は絶対です。後輩は、たとえそれが理不尽な要求であったとしても、絶対にそれを快諾します。こうして大学と高校のズブズブの関係が「天下り」を契機に深化していくのです。こういった定年後の「おいしい生活」を捨ててまで尖った思考で校長職を、そして学校運営をしようとは思いませんよね。天下りって、決して国家役人だけの特権ではないんです。ちゃんと地方には地方の天下り文化というのがあって、それを脈々と、しかも人々の批判に晒されないような巧妙なカラクリで受け継がれているのです。そんな人々に、劇的な変化を求めることは…、できません。完全に彼らの既得権益が破壊されてしまうからです。
学校管理職ともなれば、もう教育に関してはベテランですから、そして地域の特性についても十分に認知してますから、その教育の方針や手法に関してはどなたでも一家言もっているものです。しかし前述したように、決して管理職は尖ったりしません。野心をもって尖り続けた先輩諸氏が、その後の教育界でどのようになったのかを知っているからです。学校運営の王道(超保守)からはずれ、何か特別なことをしようとして、それが世間の不評を買った場合、それを行った(例えば)校長に対する教育委員会から評価は下落します。評価が下落した場合、定年した後の再就職先は、悲しいかな(というかそれが本来の姿、常識なのですが)自力で獲得するしかないんです。つまり…、体の良い「天下り先」を用意してもらえないわけです。体の良い「天下り先」…、それは例えば補助金や助成金を頼みに学校経営を行っているところの私学の中学や高校への校長職なんです。そして私学にとってもこの天下りの受け入れには都合の良い一面がありまして、学校(私学)が不測の事態に陥った場合に、教育委員会や学事課のバックアップを受けることができる…、つまり困ったときには公立学校並に行政当局が保護下に置いてくれる…、だから日頃から上部機関である教育委員会や学事課とは昵懇な関係でいたい…、そのためには進んで公立の元校長を私学の校長に迎え入れるんですね。こうやって私学といえども公立の学校と同じような現象…、つまり超保守的な横並び現象が起こりのですね。ちなみに体の良い天下り先の次なる候補…、それが大学の教員職です。大学、特に学生募集に苦慮している大学にとって元校長という肩書きは、とても使い勝手がいい…、想像すればすぐにわかりますが元校長の赴任していた学校(高校)には当然に後輩が配属されています。その後輩に対して自身が天下った先の大学の受験者を増やすよう、積極的にアプローチするんです。「頼むぞ、受けさせてくれよな!」と。後述しますが、教育委員会での教員の序列は絶対です。後輩は、たとえそれが理不尽な要求であったとしても、絶対にそれを快諾します。こうして大学と高校のズブズブの関係が「天下り」を契機に深化していくのです。こういった定年後の「おいしい生活」を捨ててまで尖った思考で校長職を、そして学校運営をしようとは思いませんよね。天下りって、決して国家役人だけの特権ではないんです。ちゃんと地方には地方の天下り文化というのがあって、それを脈々と、しかも人々の批判に晒されないような巧妙なカラクリで受け継がれているのです。そんな人々に、劇的な変化を求めることは…、できません。完全に彼らの既得権益が破壊されてしまうからです。
3 前例踏襲主義
学校運営の指揮権は校長にあります。その校長をコントロール下に置いているのが、各地域の教育委員会です。この教育委員会に呼ばれると、多少の地域差は存在するでしょうが、まぁ〜、ほぼ同じような洗礼を受けるのだそうです。と、その洗礼を真面目に受け入れているところの管理職候補者は、だからそれが洗礼だとする認識はないのでしょうが、彼らは先輩教員に対する絶対服従…、そいうったヒエラルキーという伝統を、まずは注入されるのです。笑ってはいけないのですが、その伝統が日本という国の教育界には厳然と150年間も続いてきていて、それが理由で新しい時代の変化に鈍感になったと言っても過言ではないのですね。だって「絶対服従」ですよ。この時代に…、それって教育を実践する人間にとってはまるで思考停止を命じられているようなもので…、そうなんです。この思考停止状態が、実はとても重要な洗礼の儀式なんですね。つまり先輩の校長(前任者)が行ってきた学校運営を絶対に否定しないところから、新任の校長は学校運営を受け継ぎます。ということは、どんなに意味のない政策でも、そしてそのために現場がどんなに混乱していても、まずはそれを止めることはできない…、そんなカラクリになっています。よって現場の教員からすれば、無意味とも思える行事や仕事が次々と増えるだけで、そもそも「なんでこんなことしてるんだろう?」と疑問に感ている政策でも、その説明責任を果たすべき管理職は、人事異動でもう存在しないのです。でもそれを止められない。前任者を否定するような新規の政策を立ち上げようものなら、それこそ教育委員会のOB勢力から何を言われるかわかりませんからね。ちなみにこの教育委員会OB勢力は、実に強固な組織でして、現行の教育委員会を背後から操っていると言っても言い過ぎにはならないくらい、その影響力は絶大です。学校教育現場の「超保守的」な体質の権化であると言ってもいい存在ですね。この中から、これも笑っちゃいけないんですが、何年かに一度、リーダー格とも言える人材(元校長)なんかが、叙勲の対象になったりするんです。勤続○○年で地域の教育に貢献した…、なんていう理由で叙勲…、それを実現するべく、OB会はロビー活動に奔走します。ヒエラルキーを死守するために日本国に完全密着している教育委員会とその面々…、学校管理職が決して尖っていてはいけない理由と、であるからこそ学校の文化や制度は、まず変化し得ない…、ということがおわかりいただけましたか?
学校運営の指揮権は校長にあります。その校長をコントロール下に置いているのが、各地域の教育委員会です。この教育委員会に呼ばれると、多少の地域差は存在するでしょうが、まぁ〜、ほぼ同じような洗礼を受けるのだそうです。と、その洗礼を真面目に受け入れているところの管理職候補者は、だからそれが洗礼だとする認識はないのでしょうが、彼らは先輩教員に対する絶対服従…、そいうったヒエラルキーという伝統を、まずは注入されるのです。笑ってはいけないのですが、その伝統が日本という国の教育界には厳然と150年間も続いてきていて、それが理由で新しい時代の変化に鈍感になったと言っても過言ではないのですね。だって「絶対服従」ですよ。この時代に…、それって教育を実践する人間にとってはまるで思考停止を命じられているようなもので…、そうなんです。この思考停止状態が、実はとても重要な洗礼の儀式なんですね。つまり先輩の校長(前任者)が行ってきた学校運営を絶対に否定しないところから、新任の校長は学校運営を受け継ぎます。ということは、どんなに意味のない政策でも、そしてそのために現場がどんなに混乱していても、まずはそれを止めることはできない…、そんなカラクリになっています。よって現場の教員からすれば、無意味とも思える行事や仕事が次々と増えるだけで、そもそも「なんでこんなことしてるんだろう?」と疑問に感ている政策でも、その説明責任を果たすべき管理職は、人事異動でもう存在しないのです。でもそれを止められない。前任者を否定するような新規の政策を立ち上げようものなら、それこそ教育委員会のOB勢力から何を言われるかわかりませんからね。ちなみにこの教育委員会OB勢力は、実に強固な組織でして、現行の教育委員会を背後から操っていると言っても言い過ぎにはならないくらい、その影響力は絶大です。学校教育現場の「超保守的」な体質の権化であると言ってもいい存在ですね。この中から、これも笑っちゃいけないんですが、何年かに一度、リーダー格とも言える人材(元校長)なんかが、叙勲の対象になったりするんです。勤続○○年で地域の教育に貢献した…、なんていう理由で叙勲…、それを実現するべく、OB会はロビー活動に奔走します。ヒエラルキーを死守するために日本国に完全密着している教育委員会とその面々…、学校管理職が決して尖っていてはいけない理由と、であるからこそ学校の文化や制度は、まず変化し得ない…、ということがおわかりいただけましたか?
4 教員の側の確信的問題点
学校管理職に期待できなくても、学校現場にはそれなりに頑張っている教員もたくさんいます。これは事実です。しかしその頑張る方向性は、論理的に考えてみても「変化」をもたらすとは言えません。それはなぜか? 教員ほど学校と相性がいい人々はいないんです。「?」と思うかもしれませんが、教員を目指した時点で、その教員の学校に対する評価は肯定的です。「いや違う、自分はそんな学校の改革を目指して教職に就いたんだ!」とする御仁がいるとすれば、それはそれで心強いのですが、今のところ私の周囲にはそんな奇特な人物は現れません。ということは、教員を目指した時、少なからずその人々は現行の学校が「好き」なのであり、そんな「好き」な学校で働いてみたいという動機がもともと存在していた…、だから職場に対するネガティブな感情が湧きにくい…、ということは「変化」を求めない…、そういった構図になっていきます。では、なぜ彼ら教員は元々学校が「好き」だったのでしょうか? それはきっと自身の学生時代に学校で「いい思い」をしてきたからでしょう。スクールカースト的に言えば、学校の中ではもっとも安全で平和な地位です。カーストの最上位ではありません。最上位は、それはそれでかなり大変なんです。良くも悪くも自身のカラーを前面に出し続けて、周囲に影響力をもったところの存在でなければスクールカーストの最上位に存在することはできません。かと言って教員を目指す教員が、カーストの下位にい続けたとも考えにくいですね。下位の人々には学校という環境自体が苦痛でたまらなかったところの人々もきっとたくさんいますから、そんな中から教員を目指すことは考えにくいことです。つまり教員になろう、教員になりたいと考える人々は、スクールカーストの中位から上位で生活していた人々であったと考えられます。誰からも攻撃されず、それでいて誰も攻撃せず、体制に順応していれば自身に災いが降ってくることもないでしょう。それに教員との相性が良いのも、このカースト中位と上位なんです。だから日々は平和です。学校は楽しいです。教員に対する信頼も厚いでしょう。ただ一点、彼らの欠点をあげるとすれば…、それは「事なかれ主義」です。「長いものには巻かれろ」の精神です。事実、そうやって自身の青春を輝かしいものに演出してきたのですから、今更それを止めて「戦え!」「変革だ!」なんて言われても、彼らにはそんなことをする動機もなければ手法もありません。「事なかれ主義」がすっかり板についた状態での人生のスタートですから、そんな彼らに問題意識そのものをもってもらうことすら気の遠くなるような話なんですね。だから、彼らが主力となっているであろう教育現場から「変化」を期待することは…、ほとんどできません。
5 でも…、最近は…
教育委員会やそこで生産される学校管理職、そのOB、それに現行の学校現場を任されている教員…、どこを見ても新時代に相応しい学校改革や教育改革が生まれてくる気配はありません。だからといって国(文科省)の教育改革プランを待つ…、残念ながら、それでは日本の教育は周回遅れになってしまうでしょうし、なにしろ教員の働き方改革を早期に実現しなければ、教員のなり手がますます減ってきてしまいます。学校が働く場としても魅力的なものに「変革」しなければならないのです。そしてその「変革」は大胆なものでなければなりません。そういった意味で、首都圏(特に東京都)の教育委員会が、かつての求心力を失っている…、そんな情報を入手しました。教育委員会の「言うことをきかない」校長が出現し始めたのですね。そんな尖った校長が、果敢に学校改革の旗振り役を努めています。まだ、そのムーブメントは一部の学校でしか起こっていませんが、教育委員会のコントロールが良い意味で効かなくなってきているということは事実のようです。そしてそんな変化に敏感な一部教員も現れ始めました。彼ら教員は、学校と社会を有機的に結びつけなければこれからの学校は埋没していく…、そんな危機感から動き始めているのです。もはや教員の資質を育てる、そして教員の資質を担保するのは学校管理職や教育委員会ではありません。彼らの資質を育て担保するのは…、そうです、私たちの「社会」なんです。社会が教員を包摂して、彼らの変革に勇気を与えなければならないのです。そういった意味で、最近の教育界の動きは…、その動きは実に微妙ですが…、明るい兆しでもあると言えるのです。
学校管理職に期待できなくても、学校現場にはそれなりに頑張っている教員もたくさんいます。これは事実です。しかしその頑張る方向性は、論理的に考えてみても「変化」をもたらすとは言えません。それはなぜか? 教員ほど学校と相性がいい人々はいないんです。「?」と思うかもしれませんが、教員を目指した時点で、その教員の学校に対する評価は肯定的です。「いや違う、自分はそんな学校の改革を目指して教職に就いたんだ!」とする御仁がいるとすれば、それはそれで心強いのですが、今のところ私の周囲にはそんな奇特な人物は現れません。ということは、教員を目指した時、少なからずその人々は現行の学校が「好き」なのであり、そんな「好き」な学校で働いてみたいという動機がもともと存在していた…、だから職場に対するネガティブな感情が湧きにくい…、ということは「変化」を求めない…、そういった構図になっていきます。では、なぜ彼ら教員は元々学校が「好き」だったのでしょうか? それはきっと自身の学生時代に学校で「いい思い」をしてきたからでしょう。スクールカースト的に言えば、学校の中ではもっとも安全で平和な地位です。カーストの最上位ではありません。最上位は、それはそれでかなり大変なんです。良くも悪くも自身のカラーを前面に出し続けて、周囲に影響力をもったところの存在でなければスクールカーストの最上位に存在することはできません。かと言って教員を目指す教員が、カーストの下位にい続けたとも考えにくいですね。下位の人々には学校という環境自体が苦痛でたまらなかったところの人々もきっとたくさんいますから、そんな中から教員を目指すことは考えにくいことです。つまり教員になろう、教員になりたいと考える人々は、スクールカーストの中位から上位で生活していた人々であったと考えられます。誰からも攻撃されず、それでいて誰も攻撃せず、体制に順応していれば自身に災いが降ってくることもないでしょう。それに教員との相性が良いのも、このカースト中位と上位なんです。だから日々は平和です。学校は楽しいです。教員に対する信頼も厚いでしょう。ただ一点、彼らの欠点をあげるとすれば…、それは「事なかれ主義」です。「長いものには巻かれろ」の精神です。事実、そうやって自身の青春を輝かしいものに演出してきたのですから、今更それを止めて「戦え!」「変革だ!」なんて言われても、彼らにはそんなことをする動機もなければ手法もありません。「事なかれ主義」がすっかり板についた状態での人生のスタートですから、そんな彼らに問題意識そのものをもってもらうことすら気の遠くなるような話なんですね。だから、彼らが主力となっているであろう教育現場から「変化」を期待することは…、ほとんどできません。
5 でも…、最近は…
教育委員会やそこで生産される学校管理職、そのOB、それに現行の学校現場を任されている教員…、どこを見ても新時代に相応しい学校改革や教育改革が生まれてくる気配はありません。だからといって国(文科省)の教育改革プランを待つ…、残念ながら、それでは日本の教育は周回遅れになってしまうでしょうし、なにしろ教員の働き方改革を早期に実現しなければ、教員のなり手がますます減ってきてしまいます。学校が働く場としても魅力的なものに「変革」しなければならないのです。そしてその「変革」は大胆なものでなければなりません。そういった意味で、首都圏(特に東京都)の教育委員会が、かつての求心力を失っている…、そんな情報を入手しました。教育委員会の「言うことをきかない」校長が出現し始めたのですね。そんな尖った校長が、果敢に学校改革の旗振り役を努めています。まだ、そのムーブメントは一部の学校でしか起こっていませんが、教育委員会のコントロールが良い意味で効かなくなってきているということは事実のようです。そしてそんな変化に敏感な一部教員も現れ始めました。彼ら教員は、学校と社会を有機的に結びつけなければこれからの学校は埋没していく…、そんな危機感から動き始めているのです。もはや教員の資質を育てる、そして教員の資質を担保するのは学校管理職や教育委員会ではありません。彼らの資質を育て担保するのは…、そうです、私たちの「社会」なんです。社会が教員を包摂して、彼らの変革に勇気を与えなければならないのです。そういった意味で、最近の教育界の動きは…、その動きは実に微妙ですが…、明るい兆しでもあると言えるのです。
「ブラック校則」をめぐる闘争の歴史と現在
先ほど、改革の好ましい流れは長続きしないだろうと述べました。それは校則の歴史を顧みるに、一時的に見直しの機運が高まったとしても、「ブラック校則」はやがて姿形を変えて増殖を再開するだろうからです。「ブラック校則」は、近年に突如として姿を現したわけではありません。それは、つる草のようなマインド・ウィルス(ミーム)であって、日本社会に近代学校が誕生した150年前から蔓延しては駆除されることを繰り返してきました。とりわけ明治後期しかり、戦間・戦時期しかり、右傾の時代には「ブラック校則」が繁殖しやすいのです。
直近では管理主義教育の嵐が吹き荒れた1980年代が「ブラック校則」の最盛期でした。「校則・体罰・内申書」が管理主義教育の「三種の神器」と呼ばれていた時代です。80年代前半の学校はまさに「戦場」でした。現代の10倍以上にあたる1万人以上の児童・生徒が校内暴力で検挙・補導されており、生徒による「お礼参り」等を恐れて卒業式に警察官を配備した中学・高校も全国で900校を超えました。当時において「ブラック校則」は校内暴力の「原因」でもあり「結果」でもあったと言えます。当時は学校当局と暴走族などの学校外非行勢力との闘争状態があり、学校内の治安維持のために「ブラック校則」が用いられていました。厳しい校則で生徒の不規則行為を抑制し、規則から外れた生徒に指導を集中させて「公開処刑」にすることで、生徒の「荒れ」を未然防止するという管理主義的な治安維持戦略が採用されていたのです。他方、当時は全国の公立中学校の3分の1で男子生徒に対して頭髪丸刈りが強制されるなどしており、頭髪や服装の規制緩和を求める生徒たちのストライキや訴訟が頻発、学校側が生徒の抵抗を押さえ込むために規制強化をさらに押し進めていくことで、事態は泥沼化していました。そうした風向きが変わったのは今から30年前の1988年頃です。校内暴力が鎮静化するなかで、頭髪規則違反の生徒の写真を卒業アルバムから外したり、遅刻しそうになった生徒を校門に挟み圧死させるなどの振る舞いが社会問題化し、文部省(当時)が重い腰を上げて是正指導に乗り出したのです。それによって「男子は丸刈り、女子はおかっぱ(耳下10センチまで)」などの「ブラック校則」が生徒手帳から姿を消していきました。それから歳月が経過し、当時の記憶が風化するなかで、「ブラック校則」が再び増殖を始めたのは2000年代半ば頃ではないかと言われています。その動きは、子どもの学力低下の社会問題化、少年法の厳罰化、ニート・バッシングの広がりなど、子どもに対する包囲網が敷かれていくプロセスと軌を一にしています。日本社会の経済状況を見ても、当時は「失われた十年」と呼ばれる不況のなかで就職氷河期が続き、子どもたちの将来展望は暗澹としていました。新自由主義改革のさなかにあって「子どもの貧困」が社会問題化する少し前の話です。当時においてまだ「正体不明」であった子どもの荒れを強権によって封じ込めようとするなかで、休眠していた「ブラック校則」体制が各地で目を覚ましていったのかもしれません。
先ほど、改革の好ましい流れは長続きしないだろうと述べました。それは校則の歴史を顧みるに、一時的に見直しの機運が高まったとしても、「ブラック校則」はやがて姿形を変えて増殖を再開するだろうからです。「ブラック校則」は、近年に突如として姿を現したわけではありません。それは、つる草のようなマインド・ウィルス(ミーム)であって、日本社会に近代学校が誕生した150年前から蔓延しては駆除されることを繰り返してきました。とりわけ明治後期しかり、戦間・戦時期しかり、右傾の時代には「ブラック校則」が繁殖しやすいのです。
直近では管理主義教育の嵐が吹き荒れた1980年代が「ブラック校則」の最盛期でした。「校則・体罰・内申書」が管理主義教育の「三種の神器」と呼ばれていた時代です。80年代前半の学校はまさに「戦場」でした。現代の10倍以上にあたる1万人以上の児童・生徒が校内暴力で検挙・補導されており、生徒による「お礼参り」等を恐れて卒業式に警察官を配備した中学・高校も全国で900校を超えました。当時において「ブラック校則」は校内暴力の「原因」でもあり「結果」でもあったと言えます。当時は学校当局と暴走族などの学校外非行勢力との闘争状態があり、学校内の治安維持のために「ブラック校則」が用いられていました。厳しい校則で生徒の不規則行為を抑制し、規則から外れた生徒に指導を集中させて「公開処刑」にすることで、生徒の「荒れ」を未然防止するという管理主義的な治安維持戦略が採用されていたのです。他方、当時は全国の公立中学校の3分の1で男子生徒に対して頭髪丸刈りが強制されるなどしており、頭髪や服装の規制緩和を求める生徒たちのストライキや訴訟が頻発、学校側が生徒の抵抗を押さえ込むために規制強化をさらに押し進めていくことで、事態は泥沼化していました。そうした風向きが変わったのは今から30年前の1988年頃です。校内暴力が鎮静化するなかで、頭髪規則違反の生徒の写真を卒業アルバムから外したり、遅刻しそうになった生徒を校門に挟み圧死させるなどの振る舞いが社会問題化し、文部省(当時)が重い腰を上げて是正指導に乗り出したのです。それによって「男子は丸刈り、女子はおかっぱ(耳下10センチまで)」などの「ブラック校則」が生徒手帳から姿を消していきました。それから歳月が経過し、当時の記憶が風化するなかで、「ブラック校則」が再び増殖を始めたのは2000年代半ば頃ではないかと言われています。その動きは、子どもの学力低下の社会問題化、少年法の厳罰化、ニート・バッシングの広がりなど、子どもに対する包囲網が敷かれていくプロセスと軌を一にしています。日本社会の経済状況を見ても、当時は「失われた十年」と呼ばれる不況のなかで就職氷河期が続き、子どもたちの将来展望は暗澹としていました。新自由主義改革のさなかにあって「子どもの貧困」が社会問題化する少し前の話です。当時においてまだ「正体不明」であった子どもの荒れを強権によって封じ込めようとするなかで、休眠していた「ブラック校則」体制が各地で目を覚ましていったのかもしれません。
現代の「ブラック校則」は「丸刈り」や「運動中の水分補給の禁止」などといった80年代のそれと比べれば「ソフト」です。それはこれまでの市民運動が人権論と科学を武器に「ハード」な「ブラック校則」を追いつめ、ようやく根絶に近い状況までたどり着いたからに他なりません。ただ、「ソフト」になったということは、その分だけ問題化が難しくなったということでもあります。今日の「ブラック校則」追放運動で争われているのは、日焼け止めクリーム、眉剃り、置き勉などの禁止の是非であったり、下着の色、地毛証明、制服などの在り方です。
「茶色の地毛を黒髪に染髪させる」といったような、誰が見ても明らかな人権侵害事例は一部であって、ほとんどの校則は賛否の分かれる論点を内包しています。校則の一つひとつを権利論的・科学的にしっかりと吟味していく必要に迫られているのです。実際、冒頭で紹介した「置き勉」解禁運動では、保護者が「子どもに体重の1〜2割以上の荷物を背負わせることは有害」という科学的エビデンスを根拠にして、自分の子どもの荷物の重量が体重の25%に達することを指摘しました。下着の色を白のみに規制する校則の根拠として挙げられることの多い「色物の下着は透けて見えるから」という主張に対し、ツイッター上でランジェリーショップが「実は肌より淡い色のほうが透ける」という事実を写真付きで論証するといった草の根のレジスタンスも行われています。校則の内容をめぐる問い直しとともに、校則違反に対する制裁の在り方についても問い直しが進んでいます。ちょっとした校則違反を針小棒大にとらえて長時間にわたって指導したり、登校を禁止したり、全校集会で吊るし上げたりといった過剰な指導が、権利論的にも科学的にも妥当性を持たないことを論証しようという努力が「指導死」遺族などの手によって続けられているのです。
「茶色の地毛を黒髪に染髪させる」といったような、誰が見ても明らかな人権侵害事例は一部であって、ほとんどの校則は賛否の分かれる論点を内包しています。校則の一つひとつを権利論的・科学的にしっかりと吟味していく必要に迫られているのです。実際、冒頭で紹介した「置き勉」解禁運動では、保護者が「子どもに体重の1〜2割以上の荷物を背負わせることは有害」という科学的エビデンスを根拠にして、自分の子どもの荷物の重量が体重の25%に達することを指摘しました。下着の色を白のみに規制する校則の根拠として挙げられることの多い「色物の下着は透けて見えるから」という主張に対し、ツイッター上でランジェリーショップが「実は肌より淡い色のほうが透ける」という事実を写真付きで論証するといった草の根のレジスタンスも行われています。校則の内容をめぐる問い直しとともに、校則違反に対する制裁の在り方についても問い直しが進んでいます。ちょっとした校則違反を針小棒大にとらえて長時間にわたって指導したり、登校を禁止したり、全校集会で吊るし上げたりといった過剰な指導が、権利論的にも科学的にも妥当性を持たないことを論証しようという努力が「指導死」遺族などの手によって続けられているのです。
吹田市 職務放棄の教育長の月給は81万円
2020/05/12 13:03
いじめ被害の相談に来た、被害女児の両親に対して何の対応もせずに毎回門前払いをしてきた無能で職務放棄の吹田市教育委員会の教育長の月給が81万円。後藤市長は105万円。
納税者は「保育所や防犯カメラを増やしてほしい」等の、市民サービス等の向上を願って税金を納めている。
こいつらに贅沢をさせる為に納税しているわけではない。
そこを今一度考えろ、後藤!
貴様が応援していた堺市の竹山はあんなことになっているぞ。
ああいう人物を応援していたということは『類は友を呼ぶ』だ。
知り合いというほどの仲ではないが、私の知る年配の人間に豊〇市職員を経て豊〇市の教育委員をしていたという人物がいる。
この人は思考停止で論理的な会話が全くできない、社会問題を何も知らない、知ろうともしない、幼稚な屁理屈ばかり言う無知で面倒な人物だ。
こんな馬鹿でも豊〇市の職員に採用されて、教育委員も務めていた。
何故か? 親父のコネだ。
私の意見に対して、教育長は「失礼な。我々もちゃんと仕事をしているんだ。」と言いたいだろうが、明らかに労働内容と高額な報酬が見合わない。
本業が忙しくて教育委員会の会議等の用事に参加しなくとも、報酬は満額支給される。
『川崎市教育委員の俳優、会議4割欠席 「ドラマで多忙」
朝日新聞デジタル 3月1日(火)5時11分配信
俳優で川崎市教育委員N氏が、昨年開かれた25回の市教委の会議のうち、11回を欠席していたことが分かった。
N氏は朝日新聞の取材に「ドラマの仕事で忙しかった」などと説明している。委員には会議への出欠にかかわらず、月額27万9千円の報酬が支払われる。』
民間企業で月に81万円も貰おうと思ったら大変な労働だ。
何度も言うが、吹田市教育長 原田勝氏は教育現場の経験者か?何者だ?
2020/05/12 13:03
いじめ被害の相談に来た、被害女児の両親に対して何の対応もせずに毎回門前払いをしてきた無能で職務放棄の吹田市教育委員会の教育長の月給が81万円。後藤市長は105万円。
納税者は「保育所や防犯カメラを増やしてほしい」等の、市民サービス等の向上を願って税金を納めている。
こいつらに贅沢をさせる為に納税しているわけではない。
そこを今一度考えろ、後藤!
貴様が応援していた堺市の竹山はあんなことになっているぞ。
ああいう人物を応援していたということは『類は友を呼ぶ』だ。
知り合いというほどの仲ではないが、私の知る年配の人間に豊〇市職員を経て豊〇市の教育委員をしていたという人物がいる。
この人は思考停止で論理的な会話が全くできない、社会問題を何も知らない、知ろうともしない、幼稚な屁理屈ばかり言う無知で面倒な人物だ。
こんな馬鹿でも豊〇市の職員に採用されて、教育委員も務めていた。
何故か? 親父のコネだ。
私の意見に対して、教育長は「失礼な。我々もちゃんと仕事をしているんだ。」と言いたいだろうが、明らかに労働内容と高額な報酬が見合わない。
本業が忙しくて教育委員会の会議等の用事に参加しなくとも、報酬は満額支給される。
『川崎市教育委員の俳優、会議4割欠席 「ドラマで多忙」
朝日新聞デジタル 3月1日(火)5時11分配信
俳優で川崎市教育委員N氏が、昨年開かれた25回の市教委の会議のうち、11回を欠席していたことが分かった。
N氏は朝日新聞の取材に「ドラマの仕事で忙しかった」などと説明している。委員には会議への出欠にかかわらず、月額27万9千円の報酬が支払われる。』
民間企業で月に81万円も貰おうと思ったら大変な労働だ。
何度も言うが、吹田市教育長 原田勝氏は教育現場の経験者か?何者だ?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ベルばらと今の日本を考える 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-