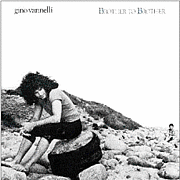ここは、毎月発売されるレコードコレクターズ誌に対して意見や感想を述べ合うトピックです。
レターズの電子版のつもりでトピ立てました。
特集、連載、編集者、ライターの方々へ等、何に対してでもかまいません。最新号はもちろんのこと、バックナンバーについてもOKです!
感動を伝えるのもよし、ワイワイ盛り上がるのもよし、熱く意見を戦わせるのもよし、傍観するのもよし(よしかよ!)。
レココレの編集者、ライター、読者、印刷会社?が三位一体(やっぱ、印刷会社入ってないやん)となって、さらに愛される雑誌になったらいいなと思います。
あなたのレター待ってます。
注)レターズ@ミクシィは私、ちんたろーJrが勝手に立てたトピックです。
レコードコレクターズ編集部とはな〜んの関係もありません。
レターズの電子版のつもりでトピ立てました。
特集、連載、編集者、ライターの方々へ等、何に対してでもかまいません。最新号はもちろんのこと、バックナンバーについてもOKです!
感動を伝えるのもよし、ワイワイ盛り上がるのもよし、熱く意見を戦わせるのもよし、傍観するのもよし(よしかよ!)。
レココレの編集者、ライター、読者、印刷会社?が三位一体(やっぱ、印刷会社入ってないやん)となって、さらに愛される雑誌になったらいいなと思います。
あなたのレター待ってます。
注)レターズ@ミクシィは私、ちんたろーJrが勝手に立てたトピックです。
レコードコレクターズ編集部とはな〜んの関係もありません。
|
|
|
|
コメント(138)
8月号の特集「英国ロック/ポップ名曲100選」を一通り読み終えました。
100曲中、ビートルズの曲が17曲ですか。予想してたとはいえ全体の約1/6というのはやはり凄い!おかげで過去のランキング企画と同じパターンで票割れを起こしてストーンズに1位の座を持っていかれちゃいましたね(笑)フーやキンクスにも抜かれちゃったよ、おい!
でも今回の特集、僕にとっての大きな収穫はあの時代の英国音楽のブリティッシュ・ビートとはまた違う一面が見れたということです。
‘ゴールドフィンガー’(73位)、‘サンダーバード’(100位)などの曲、トーネイドーズ(10位)のSF感覚、そしてジョン・レイトン(66位)がTV俳優でしかもジョー・ミークが絡んでたりして。そこに寺田編集長が書かれてた「SFチックな意匠」「映画/TV音楽とポップ音楽の距離」という言葉を合わせると、自分が知らなかったこの時代の英国音楽の特徴や面白さの一部がわかるような気がします。
今までは、「ビート」、「モッズ」というキーワードでしか語れなかったですが、ちょっと視野が広がった気がします。
今回は100曲揃えるのも楽そうだし、揃えてみようかな〜。
あっ、それにアルバム・ガイド(P38)にも面白そうな英国ロックアンソロジーが紹介されていましたね。
『British Rock'N'Roll Anthology 1956-64』
ボーナスが欲しい!(悲しき自営業)
100曲中、ビートルズの曲が17曲ですか。予想してたとはいえ全体の約1/6というのはやはり凄い!おかげで過去のランキング企画と同じパターンで票割れを起こしてストーンズに1位の座を持っていかれちゃいましたね(笑)フーやキンクスにも抜かれちゃったよ、おい!
でも今回の特集、僕にとっての大きな収穫はあの時代の英国音楽のブリティッシュ・ビートとはまた違う一面が見れたということです。
‘ゴールドフィンガー’(73位)、‘サンダーバード’(100位)などの曲、トーネイドーズ(10位)のSF感覚、そしてジョン・レイトン(66位)がTV俳優でしかもジョー・ミークが絡んでたりして。そこに寺田編集長が書かれてた「SFチックな意匠」「映画/TV音楽とポップ音楽の距離」という言葉を合わせると、自分が知らなかったこの時代の英国音楽の特徴や面白さの一部がわかるような気がします。
今までは、「ビート」、「モッズ」というキーワードでしか語れなかったですが、ちょっと視野が広がった気がします。
今回は100曲揃えるのも楽そうだし、揃えてみようかな〜。
あっ、それにアルバム・ガイド(P38)にも面白そうな英国ロックアンソロジーが紹介されていましたね。
『British Rock'N'Roll Anthology 1956-64』
ボーナスが欲しい!(悲しき自営業)
先月号(2009.10)から始まった連載『ビートルズ来日学』、面白いです。
『国際法的には、日航機の中は日本国内であり日本の法律が適用される。つまりビートルズは、日航412便「松島」に乗った瞬間?来日?したのだ。』
国際法とってたけど知らなんだ。それにしてもこの意気込みに圧倒されるではありませんか。リマスターされた音源聴くより、この連載読んでる方が楽しかったりして。
先週の『世界不思議発見』はビートルズ来日特集でした。そのなかで加藤茶へのインタビューがありました。
当初の予定では、ドリフターズの出演時間は20分あったそうですが、ビートルズの来日が近づくにつれ10分になり2分になり、そしてコンサート当日、本番前には「20秒でお願いします!」と言われたとか(笑)
『ビートルズ前座学』なんてのも成立しそうです。
『国際法的には、日航機の中は日本国内であり日本の法律が適用される。つまりビートルズは、日航412便「松島」に乗った瞬間?来日?したのだ。』
国際法とってたけど知らなんだ。それにしてもこの意気込みに圧倒されるではありませんか。リマスターされた音源聴くより、この連載読んでる方が楽しかったりして。
先週の『世界不思議発見』はビートルズ来日特集でした。そのなかで加藤茶へのインタビューがありました。
当初の予定では、ドリフターズの出演時間は20分あったそうですが、ビートルズの来日が近づくにつれ10分になり2分になり、そしてコンサート当日、本番前には「20秒でお願いします!」と言われたとか(笑)
『ビートルズ前座学』なんてのも成立しそうです。
トピックの削除に伴い、そこに書き込みいただいていた方のコメントをこちらに移動させることにしました。
内容はレココレ2010年2月号「リイシュー・アルバム・ベスト」に関してです。
********************************************************************
●つトム@ミクシィさん
「リイシュー・アルバム・ベスト特集号について
みなさんのベストとはどう違ってたでしょうか?
なんで, ビートルズのステレオ・ボックスや
リマスター盤群がランク・インしてないの?」
-----------------------------------------------------------
●Tomoさん
「普段アナログ盤をメインで聴いてるものとしては話題のビートルズのリマスターなどは笑止千万という気持ちが・・・・すいません。
アナログ盤をメインで聴いてるのが今時特殊というのは重々承知してますが、最新リマスターCD(モノ・ステレオ)を聴いても心が動きませんでした。
聴いてて音が痛くないですか?
昨今、中古レコ屋がバタバタと閉店してますが、何気にアナログが盛り返してるのも確かで。
アナログを扱っている中古屋は是非頑張ってもらいたいものです。」
-----------------------------------------------------------
●GRAさん
「毎年のベストものとセクションごとのランク付けなどを執拗に繰り返すこの雑誌の考えがいまだに理解出来ません。
それが働くのは何を買っていいのかわからないバイヤー達に対してだけでしょう。
評論が置き去りにされて、消費者ガイド・ブックとしての役割ならそれでもいいかもしれません。しかし良心的な消費者ガイド・ブックならダメな商品としてのリイシュー・アイテムもちゃんと指摘するべきでしょうけど、そんなものは最初から取り上げていない!と言われれば、「はー、そうですか。」になります。
購買欲をあおるだけの記事より、データ、およびもっと読んでいて思わずうなづきたくなるような記事の充実を求めます。」
**************************************************************
コメント移動に関して、トピックにコメントいただいてたTomoさん、GRAさんにご迷惑お掛けしましたこと、お詫びいたします。すみませんでした。
内容はレココレ2010年2月号「リイシュー・アルバム・ベスト」に関してです。
********************************************************************
●つトム@ミクシィさん
「リイシュー・アルバム・ベスト特集号について
みなさんのベストとはどう違ってたでしょうか?
なんで, ビートルズのステレオ・ボックスや
リマスター盤群がランク・インしてないの?」
-----------------------------------------------------------
●Tomoさん
「普段アナログ盤をメインで聴いてるものとしては話題のビートルズのリマスターなどは笑止千万という気持ちが・・・・すいません。
アナログ盤をメインで聴いてるのが今時特殊というのは重々承知してますが、最新リマスターCD(モノ・ステレオ)を聴いても心が動きませんでした。
聴いてて音が痛くないですか?
昨今、中古レコ屋がバタバタと閉店してますが、何気にアナログが盛り返してるのも確かで。
アナログを扱っている中古屋は是非頑張ってもらいたいものです。」
-----------------------------------------------------------
●GRAさん
「毎年のベストものとセクションごとのランク付けなどを執拗に繰り返すこの雑誌の考えがいまだに理解出来ません。
それが働くのは何を買っていいのかわからないバイヤー達に対してだけでしょう。
評論が置き去りにされて、消費者ガイド・ブックとしての役割ならそれでもいいかもしれません。しかし良心的な消費者ガイド・ブックならダメな商品としてのリイシュー・アイテムもちゃんと指摘するべきでしょうけど、そんなものは最初から取り上げていない!と言われれば、「はー、そうですか。」になります。
購買欲をあおるだけの記事より、データ、およびもっと読んでいて思わずうなづきたくなるような記事の充実を求めます。」
**************************************************************
コメント移動に関して、トピックにコメントいただいてたTomoさん、GRAさんにご迷惑お掛けしましたこと、お詫びいたします。すみませんでした。
2010年2月号
例によってランク付けのオン・パレードだが、単なる気まぐれでライター達が出した紹介ランクだと思えば何ともない。こちらにランクつけへの免疫がもう出来たということか。
この号で目立ったのは、ニール・ヤング特集での「また出ました。」のパターン、つまりセルロイド・ヒーロー先生の6ページに渡るおなじみの青春回想録、そしてブライアン・プレスリー先生のおなじみのギター・コード講座。これ何とかなりませんかね。レココレはランク付けのようなパターンの執拗な繰り返しが特色だが、彼等のそれも繰り返し地獄である。
ニール・ヤングは個人的にはあまり聞かないが、特に「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」についての最初の記事は深い洞察で、歌詞やヤング自身への思いと分析を論じており、ヤングに興味がなくとも著者の熱意には感嘆した。
次のベテラン・ライターの記事はいつも通り危綻のない語り口で、前者よりは淡白でもプロの書いた記事という気がした。
で三番目と四番目は既に述べたとおりだが、順に並べられたショーケースのようにその4者の優劣の際立ちが明らかである。ライター自身だけでなく、ヒーロー氏のような無理して結びつけたヤング論を書かせた編集部も人の選択から編集技術をもよく考えてもらいたい。
そのうちライターのベスト10をやるのはどうか?互選でもいいし、読者によるものでもいい。何か革命が起こるかもしれない。
レターズにあったアンケートの声、同じ苛立ちを感じている人たちがいたのが確認出来た。ただし掲載された声の80%は賞賛と感謝だったが。
ところでサイケ・ガレージ・バンドのガイド本が最近出たが、これまでこの手のガイドはレココレが2002年に出した特集くらいしかなく(以来その特集はそれきりっていううのもあるが)レココレのその目の付け所はよかった。
例によってランク付けのオン・パレードだが、単なる気まぐれでライター達が出した紹介ランクだと思えば何ともない。こちらにランクつけへの免疫がもう出来たということか。
この号で目立ったのは、ニール・ヤング特集での「また出ました。」のパターン、つまりセルロイド・ヒーロー先生の6ページに渡るおなじみの青春回想録、そしてブライアン・プレスリー先生のおなじみのギター・コード講座。これ何とかなりませんかね。レココレはランク付けのようなパターンの執拗な繰り返しが特色だが、彼等のそれも繰り返し地獄である。
ニール・ヤングは個人的にはあまり聞かないが、特に「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」についての最初の記事は深い洞察で、歌詞やヤング自身への思いと分析を論じており、ヤングに興味がなくとも著者の熱意には感嘆した。
次のベテラン・ライターの記事はいつも通り危綻のない語り口で、前者よりは淡白でもプロの書いた記事という気がした。
で三番目と四番目は既に述べたとおりだが、順に並べられたショーケースのようにその4者の優劣の際立ちが明らかである。ライター自身だけでなく、ヒーロー氏のような無理して結びつけたヤング論を書かせた編集部も人の選択から編集技術をもよく考えてもらいたい。
そのうちライターのベスト10をやるのはどうか?互選でもいいし、読者によるものでもいい。何か革命が起こるかもしれない。
レターズにあったアンケートの声、同じ苛立ちを感じている人たちがいたのが確認出来た。ただし掲載された声の80%は賞賛と感謝だったが。
ところでサイケ・ガレージ・バンドのガイド本が最近出たが、これまでこの手のガイドはレココレが2002年に出した特集くらいしかなく(以来その特集はそれきりっていううのもあるが)レココレのその目の付け所はよかった。
GRAさん
いつもながら鋭いご意見です。
>こちらにランクつけへの免疫がもう出来たということか。
単なる気まぐれという訳ではないでしょうが、結局は選者の趣向が反映されてるわけですから、読む方もそのつもりで読まなきゃいけないですね。個人的にはリイシュー・ベストなど1年を振り返るランキングに関してはその年の傾向などがわかる事もあり、嫌いではありません。
山口雅也さんの「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」についての最初の記事に関しては、全く同感です。
4ページある記事の中で「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」の歌詞に触れてるにはラストの半ページほどですが、そこにいくまでの考察が素晴らしかったと思います。<二項対立の世界の狭間で、漂泊(変化)し続ける孤独な船>という筆者がたどり着いたニール観が、僕の中にあったニール・ヤングに関する「もや」を吹き払ってくれた気がしました。
少し大げさですが山口さんの記事が僕を覚醒されてくれたかも。でもそれくらい素晴らしい記事だったと思います。
いつもながら鋭いご意見です。
>こちらにランクつけへの免疫がもう出来たということか。
単なる気まぐれという訳ではないでしょうが、結局は選者の趣向が反映されてるわけですから、読む方もそのつもりで読まなきゃいけないですね。個人的にはリイシュー・ベストなど1年を振り返るランキングに関してはその年の傾向などがわかる事もあり、嫌いではありません。
山口雅也さんの「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」についての最初の記事に関しては、全く同感です。
4ページある記事の中で「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ」の歌詞に触れてるにはラストの半ページほどですが、そこにいくまでの考察が素晴らしかったと思います。<二項対立の世界の狭間で、漂泊(変化)し続ける孤独な船>という筆者がたどり着いたニール観が、僕の中にあったニール・ヤングに関する「もや」を吹き払ってくれた気がしました。
少し大げさですが山口さんの記事が僕を覚醒されてくれたかも。でもそれくらい素晴らしい記事だったと思います。
2010年3月号
SSWのこの号、全部は読んでいないが丁寧に書かれたアルバムとアーティスト紹介がよかった。SSWというカテゴリーは地味な部類に入るだろうが、奥深そうでもある。
Crosby, Stills & Nashや、Buffalo SpringfieldからのSteve Stills、またByrdsの顔であるRoger McGuinnの1960年代〜1970年代のアルバムや紹介がなかったのが残念。同バンドからのNeil YoungやGram Parsonsだけがいつも語られ、中心であったStillsやMcGuinnがいつも脇に避けられていたのたのは昔からだが、今回も同じだった。
SSWのこの号、全部は読んでいないが丁寧に書かれたアルバムとアーティスト紹介がよかった。SSWというカテゴリーは地味な部類に入るだろうが、奥深そうでもある。
Crosby, Stills & Nashや、Buffalo SpringfieldからのSteve Stills、またByrdsの顔であるRoger McGuinnの1960年代〜1970年代のアルバムや紹介がなかったのが残念。同バンドからのNeil YoungやGram Parsonsだけがいつも語られ、中心であったStillsやMcGuinnがいつも脇に避けられていたのたのは昔からだが、今回も同じだった。
2010年5月号
リニューアルしたレココレの感想を1つ2つ。
やっぱり字が大きいと読みやすいですね。
新装レココレ読んでから、以前のものを読むと確かに読みにくい(笑)読みやすさは格段に上がってると思いました。これで老眼になっても安心か。あ、広告は昔のまんまでしたね。
ニュー・リリースを後ろに持ってきて、見やすさもアップしてるのも良かったです。こういうところは、これからも読者の声を聞いて柔軟に対応して欲しいです。
文字が大きくなったせいでアルバム・ガイドの曲目リストが犠牲になったのは残念。曲目を全てチェックしてたとは言いませんが、いろいろ参考にする事も多かったので。
復活してもらえませんかね〜。
編集後記にあった「情報の遅さ」に関しては、ある程度仕方の無いことだとは思います。ただ、誰もが全ての情報を即座に知り得るわけはなく、僕なんかバックナンバー読み返して数年前の情報を得ることもあるわけです(恥)それが古い情報だとしても、個人的には大切な情報です。だからこそ幅広い情報を丁寧に拾い上げてもらえればなぁと思います。
リニューアルしたレココレの感想を1つ2つ。
やっぱり字が大きいと読みやすいですね。
新装レココレ読んでから、以前のものを読むと確かに読みにくい(笑)読みやすさは格段に上がってると思いました。これで老眼になっても安心か。あ、広告は昔のまんまでしたね。
ニュー・リリースを後ろに持ってきて、見やすさもアップしてるのも良かったです。こういうところは、これからも読者の声を聞いて柔軟に対応して欲しいです。
文字が大きくなったせいでアルバム・ガイドの曲目リストが犠牲になったのは残念。曲目を全てチェックしてたとは言いませんが、いろいろ参考にする事も多かったので。
復活してもらえませんかね〜。
編集後記にあった「情報の遅さ」に関しては、ある程度仕方の無いことだとは思います。ただ、誰もが全ての情報を即座に知り得るわけはなく、僕なんかバックナンバー読み返して数年前の情報を得ることもあるわけです(恥)それが古い情報だとしても、個人的には大切な情報です。だからこそ幅広い情報を丁寧に拾い上げてもらえればなぁと思います。
8月号「日本のロック・フォーク・アルバム・ベスト100」の第一特集を読んだ。
その特集に流れるキー・ワードは「細野晴臣」と「パンタ」。
はっぴーえんどとティン・パン・アレーのシャワーを浴びたような感じだ。TVやラジオで何度も繰り返される商品名とメッセージと同じ執拗性をもつ。たとえばこれまで何度か採り上げられてきたおなじみのアルバムやアーティストがここであらためて登場し、しかも各選者のコラムにはっぴーえんどの同じジャケット写真が繰り返し並んでいるのは不気味でもある。
あと選者と評者達がかなりきばって書いている点も目立つ。同じ日本人同士ということで、歌っている内容を理解できる理由もあろうがかなり襟を正して各作品のコメントをつけているのに気が付いた。しかし同時に思ったのは選んだ作品を本当に好きだったり繰り返し聴いたのだろうかという疑問。また25枚も選び出すのに各人がかなり無理をしたのではないかという疑問。本当は10枚くらいが正直に出せる限度だったのではないかと思える。
だって日本だけのロック・フォークでしかも1960年代....というよりもほとんどが1970年代だが、25枚を出すのは大変な作業だったのではないか。
きばって書いているというのは次の意味不明な内容の結果にもつながる。わかる人にはわかるだろうが、もっと簡潔なわかりやすい言い方がある気がする。
第1位のはっぴーえんどの次の項(30ページ):
「奇妙でいびつで緊張関係にある楽曲が松本の詩世界とタイトル・パッケージのセンスでひとつの世界にまとまったワンダーランドであるこの作品の内容よりも俯瞰して見た「なんとなくのイメージ」の方が強烈な存在感を放ち、その後のチルドレンの「漠然とした70年代的サウンド」を生み出したのです。80年代における強烈な70年代パージによる情報断絶の影響は引き返せない音楽のデータ化により、今後「風街ろまん」というあるばむでなく「風をあつめて」という楽曲に引きつがれていくことになるのでしょうか。」
ただ同じ評者はポイントも突いている。:
「はっぴーえんどとティン・パン・アレー系がここまでチャートを独占するとは思いませんでした。これでは日本のロック史=細野晴臣の歴史みたいで、違和感を感じます。」
しかし60ページの39位での同評者の説明不足で”Oz Days Live”のアルバムについて読み手に理解させる配慮も欠ける。彼の文章ではこれはどういうアルバムかが全くわからないのだ。しかも....
「〜本当のアンダーグラウンドがここにある。CD化され多くの人に聞かれる必要などまったくない。これらのことは私が口承で伝えていくし、現物がレコードという物体で残っているの心配は無用。」
読者への放り出しと思い上がりと脳天気が同居したこのような書きっぷりは中学生の同人雑誌レベルである。
100枚も出ているのに次にほとんど選ばれなかったカテゴリーやアーティストを、これまでのランキングで必ず噴出する「今回はこれもなかった」のルーティーン的ノリであげていこう。
1.数多くのGS(選ばれたのはスパイダーズのみ)
2.売り上げははるかに100枚に選ばれているものよりあったと思われる「ニューミュージック系」、たとえば:
さだまさし
チューリップ
南こうせつ
イルカ(芸能界の長者番付一位だった。)
武田鉄矢
中島みゆき
アリス
などなど、音楽的な内容や質は別として、選ばれたのは陽水と吉田拓郎くらいしかなかった。理由はわからなくはないが。
3.いわゆる内田裕也派のロック・バンド群。せいぜいフラワー・トラベリン・バンドとフード・ブレインくらいで、ニューミュージック・マガジンが前面に立って応援していた1969年後半から1970年前半の頃が完全に風化しているのがわかる。要は21世紀になると英米のコピー・バンドは不要だということか。
4.その他:
矢沢栄吉
ダウンタウン・ブギー・ウギ・バンド
チャー
ゴダイゴ
桑名正晴
ヤマハ・ポプコン系列
関西系のバンド
ブルース系
1960年代のGS以前の日本人のロカビリーやロックのカバー
要は日本のその20年間のロック・フォークのほんの「ひとかけら」だけが選ばれたということだ。偏ったというよりも近視眼的な見方しか出来ない無理な企画と選者の人選は考え直した方がいい。とはいっても1980年代のは既にやっているし、J−POPもまた対象になるかもしれない。これはもう病気である。
しかしアーティストや選者を責めるつもりはなく、ある意味ではこのベスト100を楽しめなかった読者と同様、彼らも被害者かもしれない。
その特集に流れるキー・ワードは「細野晴臣」と「パンタ」。
はっぴーえんどとティン・パン・アレーのシャワーを浴びたような感じだ。TVやラジオで何度も繰り返される商品名とメッセージと同じ執拗性をもつ。たとえばこれまで何度か採り上げられてきたおなじみのアルバムやアーティストがここであらためて登場し、しかも各選者のコラムにはっぴーえんどの同じジャケット写真が繰り返し並んでいるのは不気味でもある。
あと選者と評者達がかなりきばって書いている点も目立つ。同じ日本人同士ということで、歌っている内容を理解できる理由もあろうがかなり襟を正して各作品のコメントをつけているのに気が付いた。しかし同時に思ったのは選んだ作品を本当に好きだったり繰り返し聴いたのだろうかという疑問。また25枚も選び出すのに各人がかなり無理をしたのではないかという疑問。本当は10枚くらいが正直に出せる限度だったのではないかと思える。
だって日本だけのロック・フォークでしかも1960年代....というよりもほとんどが1970年代だが、25枚を出すのは大変な作業だったのではないか。
きばって書いているというのは次の意味不明な内容の結果にもつながる。わかる人にはわかるだろうが、もっと簡潔なわかりやすい言い方がある気がする。
第1位のはっぴーえんどの次の項(30ページ):
「奇妙でいびつで緊張関係にある楽曲が松本の詩世界とタイトル・パッケージのセンスでひとつの世界にまとまったワンダーランドであるこの作品の内容よりも俯瞰して見た「なんとなくのイメージ」の方が強烈な存在感を放ち、その後のチルドレンの「漠然とした70年代的サウンド」を生み出したのです。80年代における強烈な70年代パージによる情報断絶の影響は引き返せない音楽のデータ化により、今後「風街ろまん」というあるばむでなく「風をあつめて」という楽曲に引きつがれていくことになるのでしょうか。」
ただ同じ評者はポイントも突いている。:
「はっぴーえんどとティン・パン・アレー系がここまでチャートを独占するとは思いませんでした。これでは日本のロック史=細野晴臣の歴史みたいで、違和感を感じます。」
しかし60ページの39位での同評者の説明不足で”Oz Days Live”のアルバムについて読み手に理解させる配慮も欠ける。彼の文章ではこれはどういうアルバムかが全くわからないのだ。しかも....
「〜本当のアンダーグラウンドがここにある。CD化され多くの人に聞かれる必要などまったくない。これらのことは私が口承で伝えていくし、現物がレコードという物体で残っているの心配は無用。」
読者への放り出しと思い上がりと脳天気が同居したこのような書きっぷりは中学生の同人雑誌レベルである。
100枚も出ているのに次にほとんど選ばれなかったカテゴリーやアーティストを、これまでのランキングで必ず噴出する「今回はこれもなかった」のルーティーン的ノリであげていこう。
1.数多くのGS(選ばれたのはスパイダーズのみ)
2.売り上げははるかに100枚に選ばれているものよりあったと思われる「ニューミュージック系」、たとえば:
さだまさし
チューリップ
南こうせつ
イルカ(芸能界の長者番付一位だった。)
武田鉄矢
中島みゆき
アリス
などなど、音楽的な内容や質は別として、選ばれたのは陽水と吉田拓郎くらいしかなかった。理由はわからなくはないが。
3.いわゆる内田裕也派のロック・バンド群。せいぜいフラワー・トラベリン・バンドとフード・ブレインくらいで、ニューミュージック・マガジンが前面に立って応援していた1969年後半から1970年前半の頃が完全に風化しているのがわかる。要は21世紀になると英米のコピー・バンドは不要だということか。
4.その他:
矢沢栄吉
ダウンタウン・ブギー・ウギ・バンド
チャー
ゴダイゴ
桑名正晴
ヤマハ・ポプコン系列
関西系のバンド
ブルース系
1960年代のGS以前の日本人のロカビリーやロックのカバー
要は日本のその20年間のロック・フォークのほんの「ひとかけら」だけが選ばれたということだ。偏ったというよりも近視眼的な見方しか出来ない無理な企画と選者の人選は考え直した方がいい。とはいっても1980年代のは既にやっているし、J−POPもまた対象になるかもしれない。これはもう病気である。
しかしアーティストや選者を責めるつもりはなく、ある意味ではこのベスト100を楽しめなかった読者と同様、彼らも被害者かもしれない。
レコード・コレクターズ誌の連載の中で白眉の面白さといったら洋楽マン列伝だと思う。なぜならこれは製作またはマーケッティングの現場からの生の声で、コレクターズ訪問とは違った観点から我々が見聞きするソフトの背景や歴史が証言されたものだからだ。輸入盤は別として国内製作、というか国内のレコード会社を通じて販売された商品がどのような経緯で広がって行ったか(あるいはしぼんでいったか)も明らかにされている。
連載が始まってから西洋文化の輸入の話が半分以上を占める大学教授のような元東芝のディレクター、1950年代から活躍していたビクターのディレクター等など、その中で際立っていたのはキング・レコードからアルファに移った寒梅賢さんの話だ。安田生命から、キング、アルファ、WEA、病院の夜間受付そして高校生の進路カウンセラーへの転進の自分の履歴を小気味いいテンポで語るその内容、ユーモア、新発見は、寒梅さんの人柄や担当レーベルとアーティスト、周囲の人たちを巻き込んだ一つの絵物語として展開されている。カーペンターズをめぐる悲哀かつ成功物語はいかに日本で最初は無視され、チャンスをつかみ、浸透(一時的ではない大事な効果だ)するかをあざやかに示してくれた。
A&Mのような一般受けする、でもロックのレーベルとしては地味な存在だった会社を軸にした展開も彼の話というか人柄を通じると輝いてくるのだ。おそらく他のレーベにはもっとセンセーショナルなアーティストやレーベルがあるが、語り手によってはごく普通の対象になり下がるであろう。
暗然とした点は専務として迎えられた大会社のWEAではバランス・シート確認と役員室でハンコ押しだけだったという下り。これは音楽業界に限らず、個性のある会社が投資会社を通じて売り買いされるようになった昨今、企業が言い換えれば二年先くらいの赤字黒字、つまり投資の元を取れたか否かだけが評価となる投機目的の対象にでしかなくなったつまらなさをよくあらわしている。(ちなみにWEAは先月あまり聞いたことのない投資会社に買収された。)もちろんメイジャーでも大コロンビアのクライブ・ディビスのような個性的な経営者もいたが、それはもう30年以上前の話である。
同じ連載のコマーシャル製作の現場と歴史のインタビューもそれなりに面白いが、コマーシャル用の音楽という限られたシーンの中での話で、やはりレーベルとそのアーティスト達、そして消費者をも巻き込んだマクロ的なこの仕掛け人シリーズから、より多くのおもしろい話が出てくることを期待する。
ミュージシャンだけにインタビューするだけが能じゃないことをこの雑誌は示してくれた。
連載が始まってから西洋文化の輸入の話が半分以上を占める大学教授のような元東芝のディレクター、1950年代から活躍していたビクターのディレクター等など、その中で際立っていたのはキング・レコードからアルファに移った寒梅賢さんの話だ。安田生命から、キング、アルファ、WEA、病院の夜間受付そして高校生の進路カウンセラーへの転進の自分の履歴を小気味いいテンポで語るその内容、ユーモア、新発見は、寒梅さんの人柄や担当レーベルとアーティスト、周囲の人たちを巻き込んだ一つの絵物語として展開されている。カーペンターズをめぐる悲哀かつ成功物語はいかに日本で最初は無視され、チャンスをつかみ、浸透(一時的ではない大事な効果だ)するかをあざやかに示してくれた。
A&Mのような一般受けする、でもロックのレーベルとしては地味な存在だった会社を軸にした展開も彼の話というか人柄を通じると輝いてくるのだ。おそらく他のレーベにはもっとセンセーショナルなアーティストやレーベルがあるが、語り手によってはごく普通の対象になり下がるであろう。
暗然とした点は専務として迎えられた大会社のWEAではバランス・シート確認と役員室でハンコ押しだけだったという下り。これは音楽業界に限らず、個性のある会社が投資会社を通じて売り買いされるようになった昨今、企業が言い換えれば二年先くらいの赤字黒字、つまり投資の元を取れたか否かだけが評価となる投機目的の対象にでしかなくなったつまらなさをよくあらわしている。(ちなみにWEAは先月あまり聞いたことのない投資会社に買収された。)もちろんメイジャーでも大コロンビアのクライブ・ディビスのような個性的な経営者もいたが、それはもう30年以上前の話である。
同じ連載のコマーシャル製作の現場と歴史のインタビューもそれなりに面白いが、コマーシャル用の音楽という限られたシーンの中での話で、やはりレーベルとそのアーティスト達、そして消費者をも巻き込んだマクロ的なこの仕掛け人シリーズから、より多くのおもしろい話が出てくることを期待する。
ミュージシャンだけにインタビューするだけが能じゃないことをこの雑誌は示してくれた。
ビートルズのベスト・ソング100はソロ時代まで含めて4年前にやっちゃいましたよ。忘れちゃいました?
http://musicmagazine.jp/rc/rc200807.html
http://musicmagazine.jp/rc/rc200808.html
http://musicmagazine.jp/rc/rc200809.html
読者投票で増刊号まで作っちゃった。
http://musicmagazine.jp/published/rcex-200811beatles.html
私はてっきりビートルズ→ストーンズときたから、次はディランだろうと仰ってるものと思っていました。
ディランの場合も第1位は読めちゃいますけど、2位以下は予想し難いんで、やってみたら案外面白いんじゃないかって気がします。
http://musicmagazine.jp/rc/rc200807.html
http://musicmagazine.jp/rc/rc200808.html
http://musicmagazine.jp/rc/rc200809.html
読者投票で増刊号まで作っちゃった。
http://musicmagazine.jp/published/rcex-200811beatles.html
私はてっきりビートルズ→ストーンズときたから、次はディランだろうと仰ってるものと思っていました。
ディランの場合も第1位は読めちゃいますけど、2位以下は予想し難いんで、やってみたら案外面白いんじゃないかって気がします。
ディランのキャリアにおけるプロテスト・ソングのウェイトって実はすごく小さいんですよね。
62年のデビュー・アルバムには一曲も無く、63年の2作目『フリーホイーリン』でも収録曲の半分以下。64年の3作目『時代は変わる』でようやく半分くらいがプロテスト・ソングになったけど、そこでフォークにはケリをつけちゃった。
つまりディランの50年のキャリアで彼がプロテスト・フォーク・シンガーだった時期は63〜64年のたった2年間なんです。
日本ではずっと遅れて60年代末にプロテスト・フォークの時代がやって来て、そこでディランが“神様”に祀り上げられたことから、プロテスト・フォークのイメージが強いんですよ。
62年のデビュー・アルバムには一曲も無く、63年の2作目『フリーホイーリン』でも収録曲の半分以下。64年の3作目『時代は変わる』でようやく半分くらいがプロテスト・ソングになったけど、そこでフォークにはケリをつけちゃった。
つまりディランの50年のキャリアで彼がプロテスト・フォーク・シンガーだった時期は63〜64年のたった2年間なんです。
日本ではずっと遅れて60年代末にプロテスト・フォークの時代がやって来て、そこでディランが“神様”に祀り上げられたことから、プロテスト・フォークのイメージが強いんですよ。
久々に来ましたが、静かなコミュになっていますね。さて最近レココレに関して想うことを書きます。
1.やはりレコード会社ディレクター列伝、コレクター訪問、ビートルズ来日学がいまだに面白いです。個人的にはランキングとナイアガラ系は未だに受け付けません。
2.歌詞を通じてアメリカを読む〜のは面白かったけど、歌詞は思っていた以上に重要で、かつ難しいというのがこのシリーズを通じて感じました。
3.ボックスものには全曲名を入れて、単発のCD紹介には曲名を省くのもボックスや雑誌の提供側からすると何となく理由はわかります。すべてがビジネスです。ただハコ物にはこれなら投資(購入)してもいいと思うものが幸か不幸か最近ありません。繰り返し出るビートルズに関しては「レット・イット・ビー」のDVD化が唯一の課題でしょうか。
4.以前にも書きましたが、ライターの人たちの個性とか知識、説得力がこの雑誌の今後の方向を決めると思います。
5.発売盤の紹介はやはり何かと役に立ちます。これまでこれがなかったら永久に出会えなかったものがたくさんありました。
1.やはりレコード会社ディレクター列伝、コレクター訪問、ビートルズ来日学がいまだに面白いです。個人的にはランキングとナイアガラ系は未だに受け付けません。
2.歌詞を通じてアメリカを読む〜のは面白かったけど、歌詞は思っていた以上に重要で、かつ難しいというのがこのシリーズを通じて感じました。
3.ボックスものには全曲名を入れて、単発のCD紹介には曲名を省くのもボックスや雑誌の提供側からすると何となく理由はわかります。すべてがビジネスです。ただハコ物にはこれなら投資(購入)してもいいと思うものが幸か不幸か最近ありません。繰り返し出るビートルズに関しては「レット・イット・ビー」のDVD化が唯一の課題でしょうか。
4.以前にも書きましたが、ライターの人たちの個性とか知識、説得力がこの雑誌の今後の方向を決めると思います。
5.発売盤の紹介はやはり何かと役に立ちます。これまでこれがなかったら永久に出会えなかったものがたくさんありました。
2015年1月号の読後感想を書きますと、つらい部分は箱物の詳細紹介でしょう。まず、当たり前だけど、そこには批評精神が入り込む隙がまったくない。なぜなら読者に買わせるのが目的だから。ここで資本主義の論理が成り立つわけだけど、もし生きておれば中村とうようさんの意見を聞きたいところです。
次にかなりのページを割かれている箱物の紹介は、消費者が広告を身銭を切って購入する形態になっている点でしょう。もしこれがメーカーからのレターメイルなら、所詮宣伝だからということで直ちに削除できるが、紙媒体の雑誌で、しかも800円なんぼの投資をしているのに、そのような形態の広告はちと厳しいものがあるのではないか?いやそのような記事紹介をしないとレココレを維持出来なくなり、他の面白い記事も今後読めなくなるのなら、これまた問題です。
それなら書店で好きな記事だけを立ち読みすればいいという意見もあるかもしれないが、それが出来ない立場なので悩ましい。
さらに自己矛盾を露呈すると、自分が興味あるアーティストの箱物特集だと、買う買わないは別として、抵抗なく読めてしまう矛盾。
もう一歩進めて考えると、こんなことは悩みに足らない問題なのかという気がしないでもないが、雑誌側からしてそれなりに力を入れている箱物特集は彼等が生き延びるための大きな手段でもあるからそれ相当の重要性をもっているはずだという仮説も成り立つ。
要はその他の記事がかなり面白く定期購読の価値があるからこそ、箱物紹介というのは厄介な議題ではなかろうか。
次にかなりのページを割かれている箱物の紹介は、消費者が広告を身銭を切って購入する形態になっている点でしょう。もしこれがメーカーからのレターメイルなら、所詮宣伝だからということで直ちに削除できるが、紙媒体の雑誌で、しかも800円なんぼの投資をしているのに、そのような形態の広告はちと厳しいものがあるのではないか?いやそのような記事紹介をしないとレココレを維持出来なくなり、他の面白い記事も今後読めなくなるのなら、これまた問題です。
それなら書店で好きな記事だけを立ち読みすればいいという意見もあるかもしれないが、それが出来ない立場なので悩ましい。
さらに自己矛盾を露呈すると、自分が興味あるアーティストの箱物特集だと、買う買わないは別として、抵抗なく読めてしまう矛盾。
もう一歩進めて考えると、こんなことは悩みに足らない問題なのかという気がしないでもないが、雑誌側からしてそれなりに力を入れている箱物特集は彼等が生き延びるための大きな手段でもあるからそれ相当の重要性をもっているはずだという仮説も成り立つ。
要はその他の記事がかなり面白く定期購読の価値があるからこそ、箱物紹介というのは厄介な議題ではなかろうか。
やはりレココレに感謝するのはディスク・レビューで読まなければそのままになってしま(って廃盤になる)うようなアルバムが紹介されている点でしょうか。あそこに出ているのはそれなりの水準以上のものであり、バランスをよく取っているし、一方で1アーティストか1シリーズを徹底的に紹介するところも見逃せない。
また書籍紹介もこれまでより多くなり、充実してきた。洋書紹介はその良心のひとつ。ディスク同様、読まなければ、その見落としたチャンスを後悔するような本もよくあります。
こうしてみると特集記事の良し悪しのムラが多く、その他連載物は比較的安定している傾向があります。
それと理由はわかりませんが、ビッグアーティストへの直接のインタビューがない。ポール・マッカートニーやボブ・ディラン、ミック・ジャガーなんて一回もないものね。¥のせいかな?海外誌のインタビュー記事ライセンスを買って掲載しても構わないと思うけど。ミュージック・ライフはかってやっていました。
また書籍紹介もこれまでより多くなり、充実してきた。洋書紹介はその良心のひとつ。ディスク同様、読まなければ、その見落としたチャンスを後悔するような本もよくあります。
こうしてみると特集記事の良し悪しのムラが多く、その他連載物は比較的安定している傾向があります。
それと理由はわかりませんが、ビッグアーティストへの直接のインタビューがない。ポール・マッカートニーやボブ・ディラン、ミック・ジャガーなんて一回もないものね。¥のせいかな?海外誌のインタビュー記事ライセンスを買って掲載しても構わないと思うけど。ミュージック・ライフはかってやっていました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
レコード・コレクターズ 更新情報
-
最新のアンケート
レコード・コレクターズのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- AOR Players' Community
- 1054人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82975人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 209206人