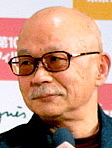|
|
|
|
コメント(4)
今、読んでいるのですが、特に阪本順治、北野武、黒沢清、青山真治などは、どんな作品でも評価していますね。
個人的に興味深いのは、「誰も知らない」(是枝裕和)を最高に評価している点で、
それは、自分は全く評価していないからなのですが、あるときは、その理論展開に大いに納得し、あるときは、そういった読者との齟齬を感じながら読んでいことが、評価への不満というより、自分の中でスリリングに感じられ、まさにこれこそ強度をもった評論ということなのでしょう。並の凡百の批評家なら猛烈に不快になって終わりですから。
なんか全然、作家も作品も聞いた事もないという作品がベストテンに選出されていて、
たとえば、「私は猫ストーカー」「ケンタとジュンとカヨちゃんの国」「ゲゲゲの女房」
「クローンは故郷をめざす」「ワルポロ」等々・・・何かすごい傑作らしいので、ぜひ見たいところですが、DVD等出ているのでしょうか。
山田洋次などは、氏の評価軸からするといつでもどんな作品でも仮想敵に設定されていて「たそがれ清兵衛」「武士の一分」などは、わりと評価する文章から始まっており、あっ、今回の作品、結構好きなのかなと思って読み進むと、最終的にはあっけなくひっくり返され、ああやっぱりね・・・となる。山田作品を批判する氏の筆致は、本当に生き生きしていて楽しそうですね。
2000年代は相米慎二の死から始まっているのだなと・・そのあと映画がどうなっていくのか・・といった点で見ているところもあるでしょうが、次から次へと出てくる愚作の山、作品の多種多様性・・まさに映画の底が抜けた状況では、一点からの評価などできず、何とか一作、一作に言葉を紡ごうとする氏の批評家としての誠実さは本当に素晴らしいと改めて思いますね。
個人的に興味深いのは、「誰も知らない」(是枝裕和)を最高に評価している点で、
それは、自分は全く評価していないからなのですが、あるときは、その理論展開に大いに納得し、あるときは、そういった読者との齟齬を感じながら読んでいことが、評価への不満というより、自分の中でスリリングに感じられ、まさにこれこそ強度をもった評論ということなのでしょう。並の凡百の批評家なら猛烈に不快になって終わりですから。
なんか全然、作家も作品も聞いた事もないという作品がベストテンに選出されていて、
たとえば、「私は猫ストーカー」「ケンタとジュンとカヨちゃんの国」「ゲゲゲの女房」
「クローンは故郷をめざす」「ワルポロ」等々・・・何かすごい傑作らしいので、ぜひ見たいところですが、DVD等出ているのでしょうか。
山田洋次などは、氏の評価軸からするといつでもどんな作品でも仮想敵に設定されていて「たそがれ清兵衛」「武士の一分」などは、わりと評価する文章から始まっており、あっ、今回の作品、結構好きなのかなと思って読み進むと、最終的にはあっけなくひっくり返され、ああやっぱりね・・・となる。山田作品を批判する氏の筆致は、本当に生き生きしていて楽しそうですね。
2000年代は相米慎二の死から始まっているのだなと・・そのあと映画がどうなっていくのか・・といった点で見ているところもあるでしょうが、次から次へと出てくる愚作の山、作品の多種多様性・・まさに映画の底が抜けた状況では、一点からの評価などできず、何とか一作、一作に言葉を紡ごうとする氏の批評家としての誠実さは本当に素晴らしいと改めて思いますね。
・・・などと私などが考えている間に素晴らしい書評が出ました。
画家/批評家の古谷利裕氏が新潮4月号に載せた批評です。
この本に興味のある方はぜひ立ち読みしてください。
古谷氏はここで、年間500本もの「日本映画」が作られているという現状に触れ、
もはや「映画」は35ミリフィルムで撮られたし商業映画だけとは限らない。
DVD、TV、ネットなど「映画」はハード面からしても変容を続けており、
そのために「映画」という言葉自体はもはや画一的な像を持ち得ない不断の更新を常に
続ける表現であるという現状認識を抑えた上で、では、山根氏の言う(こだわる)「日本映画」という「全体」を想定すること自体が可能なのか・・すなわちそのような現状に於いて「日本映画時評」が可能なのかという疑問を投げかける。
「様々な方向から波及する外的状況による切り崩しで、映画を映画として確定づける明確な輪郭は失われつつある
・・しかし、本書では、それでも映画は映画で有り続けなければならないのだということが「困難な時評を継続する」という行為によって主張されているように読める・・」
「時評を書くことは、作品を評価するというより映画を成立させ持続させようとする行為=運動で、それはいわば「映画をする」ことと言えよう」「・・ではどんなものであれば「映画」と呼び得るのか。おそらく著者は、それを探求するためにこそ映画を観つづけているのだ。(本書は)その過程を記録した膨大な思索ノートという意味合いももつ・・」
・・そうこの書物は不断の更新を続け変容を続ける映画という表現に言葉で何とかにじり寄ろうとする山根氏の思索の旅の記録なのであり、それは同時に実際にカメラを回さなくとも、山根氏自身の映画製作という運動なのである。
画家/批評家の古谷利裕氏が新潮4月号に載せた批評です。
この本に興味のある方はぜひ立ち読みしてください。
古谷氏はここで、年間500本もの「日本映画」が作られているという現状に触れ、
もはや「映画」は35ミリフィルムで撮られたし商業映画だけとは限らない。
DVD、TV、ネットなど「映画」はハード面からしても変容を続けており、
そのために「映画」という言葉自体はもはや画一的な像を持ち得ない不断の更新を常に
続ける表現であるという現状認識を抑えた上で、では、山根氏の言う(こだわる)「日本映画」という「全体」を想定すること自体が可能なのか・・すなわちそのような現状に於いて「日本映画時評」が可能なのかという疑問を投げかける。
「様々な方向から波及する外的状況による切り崩しで、映画を映画として確定づける明確な輪郭は失われつつある
・・しかし、本書では、それでも映画は映画で有り続けなければならないのだということが「困難な時評を継続する」という行為によって主張されているように読める・・」
「時評を書くことは、作品を評価するというより映画を成立させ持続させようとする行為=運動で、それはいわば「映画をする」ことと言えよう」「・・ではどんなものであれば「映画」と呼び得るのか。おそらく著者は、それを探求するためにこそ映画を観つづけているのだ。(本書は)その過程を記録した膨大な思索ノートという意味合いももつ・・」
・・そうこの書物は不断の更新を続け変容を続ける映画という表現に言葉で何とかにじり寄ろうとする山根氏の思索の旅の記録なのであり、それは同時に実際にカメラを回さなくとも、山根氏自身の映画製作という運動なのである。
>2. 古谷氏はここで、年間500本もの「日本映画」が作られているという現状に触れ…
若干話題は逸れますが、最新号の“日本映画時評”の冒頭で、山根さんも触れていました(↓)。
「全国映画館の入場者数とスクリーン数は前年より減少したが、日本映画の封切本数は増加している。日本映画製作者連盟の調べで、昨年、映画館で封切られた作品は441本(※本誌の封切一覧表には528本)。こうした状態は、周知のように、急に始まったわけではない。何年も前から進行している事態で、(中略)この時評でも何度か触れてきたが、あらためて話題にしたのは、量のあり方の微妙な変化が気になるからである。ごく単純にいえば、年々、膨大な量の内実が希薄になっているように感じられてならない。量のなかに質が結晶することは秀逸な作品の存在が証明しているが、量の総体において希薄さが深まっていると思われるのである…」(キネマ旬報2012年3月下旬号?1606)
ここでの「量の総体において希薄さが深まっている…」という箇所は、非常に気掛かりです。映画批評の世界にも、総じて通ずるように思えるからです。それはそうと、この『日本映画時評集成』は、この後《80年代編》、《90年代編》と続けて出版されるそうですが、久しぶりに興奮を覚えています。底が抜けた平場の映画批評の分野にとって、将来、きっと貴重な手本となるでしょうし、またそうなって欲しいものです…。
若干話題は逸れますが、最新号の“日本映画時評”の冒頭で、山根さんも触れていました(↓)。
「全国映画館の入場者数とスクリーン数は前年より減少したが、日本映画の封切本数は増加している。日本映画製作者連盟の調べで、昨年、映画館で封切られた作品は441本(※本誌の封切一覧表には528本)。こうした状態は、周知のように、急に始まったわけではない。何年も前から進行している事態で、(中略)この時評でも何度か触れてきたが、あらためて話題にしたのは、量のあり方の微妙な変化が気になるからである。ごく単純にいえば、年々、膨大な量の内実が希薄になっているように感じられてならない。量のなかに質が結晶することは秀逸な作品の存在が証明しているが、量の総体において希薄さが深まっていると思われるのである…」(キネマ旬報2012年3月下旬号?1606)
ここでの「量の総体において希薄さが深まっている…」という箇所は、非常に気掛かりです。映画批評の世界にも、総じて通ずるように思えるからです。それはそうと、この『日本映画時評集成』は、この後《80年代編》、《90年代編》と続けて出版されるそうですが、久しぶりに興奮を覚えています。底が抜けた平場の映画批評の分野にとって、将来、きっと貴重な手本となるでしょうし、またそうなって欲しいものです…。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
山根貞男ー映画批評の可能性ー 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
山根貞男ー映画批評の可能性ーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90055人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人