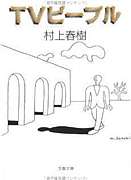僕が芝生を刈っていたのは十八か十九のころだから、もう十四年か十五年前のことになる。けっこう昔だ。
時々、十四年か十五年なんて昔というほどのことじゃないな、と考えることもある。ジム・モリソンが「ライト・マイ・ファイア」を唄ったり、ポール・マッカートニーが「ロング・アンド・ワインディング・ロード」を唄ったりしていた時代――少し前後するような気もするけれど、まあそんな時代だ――がそれほど昔のことだなんて、僕にはどうもうまく実感できないのだ。僕自身あの時代から比べてそれほど変っていないんじゃないかとも思う。
(本文より)
■収録
1982年8月 宝島
■初出
1983年5月 中国行きのスロウ・ボート
時々、十四年か十五年なんて昔というほどのことじゃないな、と考えることもある。ジム・モリソンが「ライト・マイ・ファイア」を唄ったり、ポール・マッカートニーが「ロング・アンド・ワインディング・ロード」を唄ったりしていた時代――少し前後するような気もするけれど、まあそんな時代だ――がそれほど昔のことだなんて、僕にはどうもうまく実感できないのだ。僕自身あの時代から比べてそれほど変っていないんじゃないかとも思う。
(本文より)
■収録
1982年8月 宝島
■初出
1983年5月 中国行きのスロウ・ボート
|
|
|
|
コメント(54)
> うりずんさん
コメントありがとうございます
私、今年は実家でのんびり過ごしていますよ。皆さんも年末年始はのんびりされているのかしら。それとも忙しい?
主人は地域が全然違うので、いろいろカルチャーショック受けてますよ(笑)
長くても大丈夫です
 むしろ私が携帯からしか投稿出来ずに泣く泣く文章を削って、複数回に分けて投稿したりしてるので…長いのはむしろ個人的に大歓迎です。
むしろ私が携帯からしか投稿出来ずに泣く泣く文章を削って、複数回に分けて投稿したりしてるので…長いのはむしろ個人的に大歓迎です。
余談ですが、以前某所で「風の歌を聴け」の読書会があった時に、日記三回分にわけて長文感想を書いて若干ひかれてしまったことがあります…。
感想文というか…ゼミのレジメみたいになってしまって…(笑)
それで、思い切りマニアックに語ってもいい場所としてここを作りましたので、もう存分に語って下さい(^o^)/
コメントありがとうございます
私、今年は実家でのんびり過ごしていますよ。皆さんも年末年始はのんびりされているのかしら。それとも忙しい?
主人は地域が全然違うので、いろいろカルチャーショック受けてますよ(笑)
長くても大丈夫です
余談ですが、以前某所で「風の歌を聴け」の読書会があった時に、日記三回分にわけて長文感想を書いて若干ひかれてしまったことがあります…。
感想文というか…ゼミのレジメみたいになってしまって…(笑)
それで、思い切りマニアックに語ってもいい場所としてここを作りましたので、もう存分に語って下さい(^o^)/
この「午後の最後の芝生」という短編は、三部作三冊目の「羊をめぐる冒険」と同年同月(1982年8月)に発表されています。村上春樹は長編を書く場合、集中して書くと自分でも書いていますから、同時に書きすすめたということは考えられず、おそらく「羊」のあとに「芝生」を、一気に楽しみながら書いたのかな?と想像しています。
登場人物は、この短編を読む人それぞれの解釈があると思いますが、僕的には都合7人います。ちょい役の芝刈り会社の社長、帰りに入ったドライブ・インの顔色の悪いウェイトレス、優しいマネージャーは重要ではないので省くと、4人ということになります。
『僕』『恋人』『依頼主の女性』『依頼主の娘』です。さらに、同時的に登場する人物は、『僕』と『依頼主の女性』の2人だけです。
この短編には、物語らしい物語はこれと言ってありません。33歳前後の現時点の『僕』が、14、5年前の『僕』の“記憶”を語っているだけです。
この短編は、四つの部分に分けて考えることができます。第一の部分は、語り始める前の現在の『僕』です。ここで現在の『僕』は、14、5年前というのはさほど昔ではなく、そのころからさして変わっていないと思っている自分を、「オーケー、僕は変わった。そして一四、五年というのは結構昔の話だ」と、無理に納得させています。そして、その記憶を小説として書くことの意味を見いだそうとしています。このくどくどと長い言いわけのような前置きは、初期の村上作品にいくつかあり、とくに処女作の「風の歌を聴け」の冒頭を想起させます。
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*
今、僕は語ろうと思う。
もちろん問題は何ひとつ解決していないし、語り終えた時点でもあるいは事態は全く同じということになるかもしれない。結局のところ、文章を書くことは自己療養の手段ではなく、自己療養へのささやかな試みに過ぎないからだ。
しかし、正直に語ることはひどく難しい。僕が正直になろうとすればするほど、正確な言葉は闇の奥深くへと沈みこんでいく。
弁解するつもりはない。少なくともここに語られていることは現在の僕におけるベストだ。つけ加えることは何もない。それでも僕はこんな風にも考えている。うまくいけばずっと先に、何年か何十年か先に、救済された自分を発見することができるかもしれない、と。そしてその時、像は平原に還り僕はより美しい言葉で世界を語り始めるだろう。
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*
このような前置きは、「午後の最後の芝生」においても重要な意味を持つものと思われます。かつて芝を刈っていた『僕』は、いまキャンプファイアーのまきみたいに、ぐったりとした子猫を集め、積み重ねる作業を試みようとしています。
うまくいくといいですね・・。
第二の部分は、『恋人』から別れの手紙を受け取った前後の状況説明です。『恋人』との遠距離恋愛。東京での『僕』の生活。一度だけ経験した、芝刈り仕事をした家の奥さんとのSEXと、隠喩としての“電話のベル”の記憶。『恋人』に対する後ろめたい想い。そして最後の芝刈りをするにいたった経緯。この段階では、『僕』は『恋人』を失ったことを、まだ大きなダメージとして感じていない。ただ、電話のベルが鳴っているのに、その電話に出られなかったことが、『恋人』と別れることになった原因かもしれない、という程度に思っただけだった。電話は、村上春樹のほかの小説でも、重要な隠喩として使われていますね。
第三の部分は、最後の芝生を刈りに行った家での出来事です。1968年、もしくは1969年7月14日、
ほれぼれするような見事な夏だ。空には古い思いでのように白い雲が浮かんでいた
という日に、FENが放送するロックとニュースを聴きながら、ライトバンを運転して、読売ランドの近くにある家に芝刈りに行きます。FNEのアナウンサーは、奇妙なイントネーションで、ヴェトナムの地名を連発していました。『僕』は、自ら好んで遠いところにある家の芝を刈ることを選び、マニアックなまでに丁寧に芝を刈ります。
つづきます↓
登場人物は、この短編を読む人それぞれの解釈があると思いますが、僕的には都合7人います。ちょい役の芝刈り会社の社長、帰りに入ったドライブ・インの顔色の悪いウェイトレス、優しいマネージャーは重要ではないので省くと、4人ということになります。
『僕』『恋人』『依頼主の女性』『依頼主の娘』です。さらに、同時的に登場する人物は、『僕』と『依頼主の女性』の2人だけです。
この短編には、物語らしい物語はこれと言ってありません。33歳前後の現時点の『僕』が、14、5年前の『僕』の“記憶”を語っているだけです。
この短編は、四つの部分に分けて考えることができます。第一の部分は、語り始める前の現在の『僕』です。ここで現在の『僕』は、14、5年前というのはさほど昔ではなく、そのころからさして変わっていないと思っている自分を、「オーケー、僕は変わった。そして一四、五年というのは結構昔の話だ」と、無理に納得させています。そして、その記憶を小説として書くことの意味を見いだそうとしています。このくどくどと長い言いわけのような前置きは、初期の村上作品にいくつかあり、とくに処女作の「風の歌を聴け」の冒頭を想起させます。
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*
今、僕は語ろうと思う。
もちろん問題は何ひとつ解決していないし、語り終えた時点でもあるいは事態は全く同じということになるかもしれない。結局のところ、文章を書くことは自己療養の手段ではなく、自己療養へのささやかな試みに過ぎないからだ。
しかし、正直に語ることはひどく難しい。僕が正直になろうとすればするほど、正確な言葉は闇の奥深くへと沈みこんでいく。
弁解するつもりはない。少なくともここに語られていることは現在の僕におけるベストだ。つけ加えることは何もない。それでも僕はこんな風にも考えている。うまくいけばずっと先に、何年か何十年か先に、救済された自分を発見することができるかもしれない、と。そしてその時、像は平原に還り僕はより美しい言葉で世界を語り始めるだろう。
*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・*
このような前置きは、「午後の最後の芝生」においても重要な意味を持つものと思われます。かつて芝を刈っていた『僕』は、いまキャンプファイアーのまきみたいに、ぐったりとした子猫を集め、積み重ねる作業を試みようとしています。
うまくいくといいですね・・。
第二の部分は、『恋人』から別れの手紙を受け取った前後の状況説明です。『恋人』との遠距離恋愛。東京での『僕』の生活。一度だけ経験した、芝刈り仕事をした家の奥さんとのSEXと、隠喩としての“電話のベル”の記憶。『恋人』に対する後ろめたい想い。そして最後の芝刈りをするにいたった経緯。この段階では、『僕』は『恋人』を失ったことを、まだ大きなダメージとして感じていない。ただ、電話のベルが鳴っているのに、その電話に出られなかったことが、『恋人』と別れることになった原因かもしれない、という程度に思っただけだった。電話は、村上春樹のほかの小説でも、重要な隠喩として使われていますね。
第三の部分は、最後の芝生を刈りに行った家での出来事です。1968年、もしくは1969年7月14日、
ほれぼれするような見事な夏だ。空には古い思いでのように白い雲が浮かんでいた
という日に、FENが放送するロックとニュースを聴きながら、ライトバンを運転して、読売ランドの近くにある家に芝刈りに行きます。FNEのアナウンサーは、奇妙なイントネーションで、ヴェトナムの地名を連発していました。『僕』は、自ら好んで遠いところにある家の芝を刈ることを選び、マニアックなまでに丁寧に芝を刈ります。
つづきます↓
目的の家は丘の中腹にあり、途中にある家々の庭の情景や聴こえてくるピアノの音などによって、裕福な住宅地を描写しています。目的の家は、こぢんまりとした家と書いていますが、決して小さな家ではないようです。しかも庭は広く、たぶん読売ランドができたときに始まった、宅地造成以前からあった古い家のように思えます。三度ベルを鳴らし、やっと出てきたおそろしく大きな中年の女に、「やんなよ」と言われ、丁寧に芝を刈り始めます。昼には、ハムとレタスときゅうりの、ぴりっと辛子のきいた美味しいサンドイッチをご馳走になり、十二時半に芝生に戻ります。そして二時二十分に仕事を終えたとき、「あなたのことは今でも好きです」と書かれた“恋人”の手紙の文章がよみがえってきます。
『僕』の芝刈りを気に入った女主人と、ビールを飲みながら刈られた芝を眺めます。女主人は「来月もまた来なよ」と『僕』に言うのですが、『僕』は学生であることを明かし、そろそろ勉強をしないと単位があぶないことを説明します。すると、しばらく『僕』の顔と足元を眺めた女主人は、視線を顔に戻し「学生なのかい?」と言い、「見てほしいものがある」と言います。そのようにして『僕』は、“異界への通路”のような淡い闇と時間がつくりだす古いものの臭いのする廊下を抜けて、二階への階段を上ってゆきます。女主人は、ワンピースのポケットから“鍵の束”を出し、大きな音を立ててドアの鍵を開けます。『僕』は、かなり詳細に『娘』の部屋を観察します。机の上に指を走らせてみると、一ヶ月分くらいの白い埃が指につき、カレンダーも六月のままであることに気が付きます。
一通り部屋を見終わると、ウオッカトニックを持ってきてくれた女主人は、「洋服ダンスを開けてみなよ」と言います。眠ってしまいたくなるような静かな夏の午後で、どこか遠くで電話のベルが鳴っています。ひと夏、デートのたびに違う服装ができるほどのたくさんの服を見て、引き出しの中も見終えると、「どう思う?」と女主人に訊かれ、「会ったこともないのにわかりませんよ」と『僕』は答えるのですが、「服を見れば大抵の女のことはわかるよ」と言われ、別れた恋人のことを考えます。しかし、たった半年前のことなのに、自分の恋人がどのような服を着ていたのか思い出せません。そして“自問‘します。
結局のところ、僕は彼女についていったい何を知っていたのだろう?
と。もちろん答えのない問いです。この答えのない自問は、「午後の最後の芝生」を理解する上で、重要なカギであると思われます。
女主人に問われ、娘の部屋や衣服から受けた印象を思いつくまま話しているうちに、光の海がつくりだしたほんのちょっとの歪みの中に、少しずつ忍び込んできた彼女(傍点)の存在を観じます。そして、この短編の核心の一つである、
「問題は・・・・・・彼女がいろんなことになじめないことです。自分の体やら、自分の考えていることやら、自分の求めていることやら、他人が要求していることやら・・・・・・そんなことにです」
という言葉が『僕』の口から出てくるのです。しかし『僕』には、それが誰から誰に向けられたものであるかがわからないのです。この言葉は、ほんとうに『僕』の口から出た言葉なのでしょうか?
さて、第四の部分は、眠気覚ましに入ったドライブ・インを出たあとの、車の中での想念です。疲れて運転するのを諦め、煙草に火をつけます。そして、なにもかもが遠い世界で起こった出来事のようで、まるで双眼鏡を反対にのぞいたように、いやに鮮明で不自然だったと観じます。『僕』はまた恋人からの手紙を想い出します。
「あなたは私にいろんなものを求めているのでしょうけど」と恋人は書いていた。「私は自分がなにかを求められているとはどうしても思えないのです」
僕の求めているのはきちんと芝を刈ることだけなんだ・・、
そうじゃないか(傍点)、と僕は声に出して言ってみた。
返事はなかった。
それ以来、僕は一度も芝を刈っていない。
この短編小説の主題は、もちろん『喪失』、もしくは『喪失感』です。ドライブ・インを出て、車の中ではじめて自分が失ったものの大きさ、重さに気が付き始めるのです。
それではのちほど、ゆっくりと四つの部分に分けたひとつひとつを、さらに掘り下げて考えてみたいと思います。
『僕』の芝刈りを気に入った女主人と、ビールを飲みながら刈られた芝を眺めます。女主人は「来月もまた来なよ」と『僕』に言うのですが、『僕』は学生であることを明かし、そろそろ勉強をしないと単位があぶないことを説明します。すると、しばらく『僕』の顔と足元を眺めた女主人は、視線を顔に戻し「学生なのかい?」と言い、「見てほしいものがある」と言います。そのようにして『僕』は、“異界への通路”のような淡い闇と時間がつくりだす古いものの臭いのする廊下を抜けて、二階への階段を上ってゆきます。女主人は、ワンピースのポケットから“鍵の束”を出し、大きな音を立ててドアの鍵を開けます。『僕』は、かなり詳細に『娘』の部屋を観察します。机の上に指を走らせてみると、一ヶ月分くらいの白い埃が指につき、カレンダーも六月のままであることに気が付きます。
一通り部屋を見終わると、ウオッカトニックを持ってきてくれた女主人は、「洋服ダンスを開けてみなよ」と言います。眠ってしまいたくなるような静かな夏の午後で、どこか遠くで電話のベルが鳴っています。ひと夏、デートのたびに違う服装ができるほどのたくさんの服を見て、引き出しの中も見終えると、「どう思う?」と女主人に訊かれ、「会ったこともないのにわかりませんよ」と『僕』は答えるのですが、「服を見れば大抵の女のことはわかるよ」と言われ、別れた恋人のことを考えます。しかし、たった半年前のことなのに、自分の恋人がどのような服を着ていたのか思い出せません。そして“自問‘します。
結局のところ、僕は彼女についていったい何を知っていたのだろう?
と。もちろん答えのない問いです。この答えのない自問は、「午後の最後の芝生」を理解する上で、重要なカギであると思われます。
女主人に問われ、娘の部屋や衣服から受けた印象を思いつくまま話しているうちに、光の海がつくりだしたほんのちょっとの歪みの中に、少しずつ忍び込んできた彼女(傍点)の存在を観じます。そして、この短編の核心の一つである、
「問題は・・・・・・彼女がいろんなことになじめないことです。自分の体やら、自分の考えていることやら、自分の求めていることやら、他人が要求していることやら・・・・・・そんなことにです」
という言葉が『僕』の口から出てくるのです。しかし『僕』には、それが誰から誰に向けられたものであるかがわからないのです。この言葉は、ほんとうに『僕』の口から出た言葉なのでしょうか?
さて、第四の部分は、眠気覚ましに入ったドライブ・インを出たあとの、車の中での想念です。疲れて運転するのを諦め、煙草に火をつけます。そして、なにもかもが遠い世界で起こった出来事のようで、まるで双眼鏡を反対にのぞいたように、いやに鮮明で不自然だったと観じます。『僕』はまた恋人からの手紙を想い出します。
「あなたは私にいろんなものを求めているのでしょうけど」と恋人は書いていた。「私は自分がなにかを求められているとはどうしても思えないのです」
僕の求めているのはきちんと芝を刈ることだけなんだ・・、
そうじゃないか(傍点)、と僕は声に出して言ってみた。
返事はなかった。
それ以来、僕は一度も芝を刈っていない。
この短編小説の主題は、もちろん『喪失』、もしくは『喪失感』です。ドライブ・インを出て、車の中ではじめて自分が失ったものの大きさ、重さに気が付き始めるのです。
それではのちほど、ゆっくりと四つの部分に分けたひとつひとつを、さらに掘り下げて考えてみたいと思います。
> うりずんさん
書き込みありがとうございます。とても興味深く読ませて頂いています。
年始でお忙しいこともあるでしょうし、ゆっくり書いて下さいね(^_^)
読みやすくてわかりやすい文章で助かります 私みたく私見を書き散らすのと違って(笑)
私みたく私見を書き散らすのと違って(笑)
今ちょうど「雑文集」を読んでいますが、ちょうど猫の比喩が出てきたので引用します。
良き物語を作るために小説家がなすべきことは、ごく簡単に言ってしまえば、結論を用意することではなく、仮説をただ丹念に積み重ねていくことだ。我々はそれらの仮説を、まるで眠っている猫を手にとるときのように、そっと持ち上げて運び(僕は「仮説」という言葉を使うたびに、いつもぐっすり眠り込んで猫たちの姿を思い浮かべる。温かく柔らかく湿った、意識のない猫)、物語というささやかな広場の真ん中に、ひとつまたひとつと積み上げていく。どれくらい有効に正しく猫=仮説を選びとり、どれくらい自然に巧みにそれを積み上げていけるか、それが小説家の力量になる。
これは2001年の文章ですが、見事に(?)呼応していて面白いですね。
雑文集自体も読み応えあるので、まだの方は是非
書き込みありがとうございます。とても興味深く読ませて頂いています。
年始でお忙しいこともあるでしょうし、ゆっくり書いて下さいね(^_^)
読みやすくてわかりやすい文章で助かります
今ちょうど「雑文集」を読んでいますが、ちょうど猫の比喩が出てきたので引用します。
良き物語を作るために小説家がなすべきことは、ごく簡単に言ってしまえば、結論を用意することではなく、仮説をただ丹念に積み重ねていくことだ。我々はそれらの仮説を、まるで眠っている猫を手にとるときのように、そっと持ち上げて運び(僕は「仮説」という言葉を使うたびに、いつもぐっすり眠り込んで猫たちの姿を思い浮かべる。温かく柔らかく湿った、意識のない猫)、物語というささやかな広場の真ん中に、ひとつまたひとつと積み上げていく。どれくらい有効に正しく猫=仮説を選びとり、どれくらい自然に巧みにそれを積み上げていけるか、それが小説家の力量になる。
これは2001年の文章ですが、見事に(?)呼応していて面白いですね。
雑文集自体も読み応えあるので、まだの方は是非
僕はこの「午後の最後の芝生」という短編を、便宜上四つに分けたのですが、まず第一の部分について考えてみたいと思います。
作中の『僕』は、18歳か19歳の頃に芝刈りのアルバイトをしていて、それはライト・マイ・ファイア(1967年・ドアーズ・ジム モリソン)やロング・アンド・ワィディング・ロード(1970年・ビートルズ・ポール マッカートニー)などの唄がヒットしていたころの記憶、という設定です。この時代設定は、作者自身が東京で学生だった頃と符合しますが、『僕』イコール作者?という問題に深入りすると長くなりますので、それは別の機会に譲りたいと思います。
ライト・マイ・ファイア
http://www.eigo21.com/03/pops/light.htm
ロング・アンド・ワィディング・ロード
http://www.eigo21.com/03/pops/zb03.htm
作者は、芝刈りをしていた時代を上記の唄が唄われていたころと設定しています。誰でも過去によく聞いた唄を再び聴いたり思い出したりすると、その唄が唄われていた時代背景までもが一緒に蘇ってくる経験したことがあると思います。では、なぜこの二つの唄なのか?歌詞を読んで見たところ、意味を見いだそうとすればできないというわけではないにせよ、さほどこの短編との深い結びつきがあるとも思えません。なにか示唆するものがあるのかもしれませんが、「ノルウェイの森」ほどの強い結びつきはないように思われます。出来るものなら、作者がなぜこの二つの唄を選んだのかを訊いてみたいところです。もちろんこの作者の作品には似合わないのですが、都はるみの演歌でも、伊東ゆかりの和製ポップスでも、60年代末期の頃を思い出す人もいるでしょう。
この短編小説は情報量が少ないのでなんとも言えませんが、じゃがいもうさぎさんが、のちの「ノルウェイの森」に繋がっているのではないかと指摘されたのは当を得ていると思います。この短編が書かれた1982年の時点では、まだ漠然としたものだったのでしょうが、この短編からも「ノルウェイの森」という物語に繋がる想いの原型が見られるような気がします。それでは、唄としてのノルウェイの森や、上記のふたつの唄が唄われた時代背景とはどういうものだったのでしょう。
60年代は政治の時代と言われています。とくに末期は、ヴェトナム戦争真っ盛りのころであり、日本政府がアメリカの戦争に、国民に隠すように協力していた時代でした。そういった時代の中で、ヴェトナム戦争に反対する運動があり、また学生たちも大学改革を求めて学園闘争が盛んになった時代でした。作者が学生だった早稲田大学も例外ではなく、キャンパスにはタテカンが立ち並び、校舎は学生に占拠され殺伐とした状況の中にありました。この状況の反映は、村上春樹の作品の至るところに見てとれます。ですから、「午後の最後の芝生」においても、直接的な表現はないものの、そういった時代背景を無視することはできないのではないか?と言うのが僕個人の感想です。
参考のために、下に学生運動を簡単に説明したものを貼り付けます。興味のある方は、ご覧ください。学生運動の是非や、活動家であったかノンポリであったかに関わらず、当時を学生として過ごした世代は、大なり小なりあの時代の影響を受けているものと、僕個人は思います。
日本の学生運動
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%AD%A6%E7%94%9F%E9%81%8B%E5%8B%95
記憶とは、とくにこの小説で語られている記憶とは、どのようなものなのでしょうか?一口に記憶と言っても様々なかたちがあります。楽しかった記憶、悲しい記憶、思い出したくもないような嫌な記憶。人それぞれ、誰もが数多くの記憶を抱えて生きています。あの頃は楽しかった、あの経験はいい思い出になったというような記憶は、楽しい思い出を回想しているだけで、まさに過去に終わったできごとです。それに対し、この小説の主人公が語っている記憶は、14、5年前という過去の出来事ではあっても、現在に大きな影を落としている記憶、と言うことができると思います。
そして『僕』は過去を回想し、小説に似た記憶を、あるいは記憶に似た小説を書くために、生暖かい子猫たちをキャンプファイアーの薪のように積み上げる作業に、真剣に向き合おうとします。
また多少時間がかかるかと思いますが、次は第二の部分を考えてみたいと思います。
作中の『僕』は、18歳か19歳の頃に芝刈りのアルバイトをしていて、それはライト・マイ・ファイア(1967年・ドアーズ・ジム モリソン)やロング・アンド・ワィディング・ロード(1970年・ビートルズ・ポール マッカートニー)などの唄がヒットしていたころの記憶、という設定です。この時代設定は、作者自身が東京で学生だった頃と符合しますが、『僕』イコール作者?という問題に深入りすると長くなりますので、それは別の機会に譲りたいと思います。
ライト・マイ・ファイア
http://www.eigo21.com/03/pops/light.htm
ロング・アンド・ワィディング・ロード
http://www.eigo21.com/03/pops/zb03.htm
作者は、芝刈りをしていた時代を上記の唄が唄われていたころと設定しています。誰でも過去によく聞いた唄を再び聴いたり思い出したりすると、その唄が唄われていた時代背景までもが一緒に蘇ってくる経験したことがあると思います。では、なぜこの二つの唄なのか?歌詞を読んで見たところ、意味を見いだそうとすればできないというわけではないにせよ、さほどこの短編との深い結びつきがあるとも思えません。なにか示唆するものがあるのかもしれませんが、「ノルウェイの森」ほどの強い結びつきはないように思われます。出来るものなら、作者がなぜこの二つの唄を選んだのかを訊いてみたいところです。もちろんこの作者の作品には似合わないのですが、都はるみの演歌でも、伊東ゆかりの和製ポップスでも、60年代末期の頃を思い出す人もいるでしょう。
この短編小説は情報量が少ないのでなんとも言えませんが、じゃがいもうさぎさんが、のちの「ノルウェイの森」に繋がっているのではないかと指摘されたのは当を得ていると思います。この短編が書かれた1982年の時点では、まだ漠然としたものだったのでしょうが、この短編からも「ノルウェイの森」という物語に繋がる想いの原型が見られるような気がします。それでは、唄としてのノルウェイの森や、上記のふたつの唄が唄われた時代背景とはどういうものだったのでしょう。
60年代は政治の時代と言われています。とくに末期は、ヴェトナム戦争真っ盛りのころであり、日本政府がアメリカの戦争に、国民に隠すように協力していた時代でした。そういった時代の中で、ヴェトナム戦争に反対する運動があり、また学生たちも大学改革を求めて学園闘争が盛んになった時代でした。作者が学生だった早稲田大学も例外ではなく、キャンパスにはタテカンが立ち並び、校舎は学生に占拠され殺伐とした状況の中にありました。この状況の反映は、村上春樹の作品の至るところに見てとれます。ですから、「午後の最後の芝生」においても、直接的な表現はないものの、そういった時代背景を無視することはできないのではないか?と言うのが僕個人の感想です。
参考のために、下に学生運動を簡単に説明したものを貼り付けます。興味のある方は、ご覧ください。学生運動の是非や、活動家であったかノンポリであったかに関わらず、当時を学生として過ごした世代は、大なり小なりあの時代の影響を受けているものと、僕個人は思います。
日本の学生運動
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%AD%A6%E7%94%9F%E9%81%8B%E5%8B%95
記憶とは、とくにこの小説で語られている記憶とは、どのようなものなのでしょうか?一口に記憶と言っても様々なかたちがあります。楽しかった記憶、悲しい記憶、思い出したくもないような嫌な記憶。人それぞれ、誰もが数多くの記憶を抱えて生きています。あの頃は楽しかった、あの経験はいい思い出になったというような記憶は、楽しい思い出を回想しているだけで、まさに過去に終わったできごとです。それに対し、この小説の主人公が語っている記憶は、14、5年前という過去の出来事ではあっても、現在に大きな影を落としている記憶、と言うことができると思います。
そして『僕』は過去を回想し、小説に似た記憶を、あるいは記憶に似た小説を書くために、生暖かい子猫たちをキャンプファイアーの薪のように積み上げる作業に、真剣に向き合おうとします。
また多少時間がかかるかと思いますが、次は第二の部分を考えてみたいと思います。
コメント、有難うございます。
なかなか次へ進むことができず、申し訳ありません。
時間を見つけては書いているのですが、まとめるのが難しいのです。
明日中には第二の部分を載せられると思います。
>学生運動の時代の話しなんですね。
そうですね。時代は学園闘争などの学生運動真っ盛りのころです。
主人公はノンポリのようですが、この時代はノンポリと活動家の
境が広く、ノンポリであっても集会に参加する学生は結構いました。
大学にもよりますが・・。
村上春樹自身は、けっこう学生運動と深く関わっていたということを
読んだことがありますが、僕には詳しいことはわかりません。
僕はじゃがいもうさぎ。さんのHNに。をつけるのを忘れていました。
申し訳ありませんでしたm(__)m
じゃがいもうさぎ。さんが紹介されている「雑文集」という本は、
多分僕は読んでいないと思います。
何年の出版で、出版社はどこでしょう?よろしければ教えてください。
次回日本へ行ったとき、是非買い求めたいと思います。
第二の部分です。
ひとつの小説を分析するとき、意図せずに重箱の隅をつつくような作業をしているような気分になることがあります。と言ってもごく些細なことで、この短編の価値を下げるわけではありません。例えば“スバルの1000CC”とか、“ラジエーターが故障するフォルクスワーゲン”(1973年のピンボール)といったたぐいのことです。もう一つ気になるところが第三の部分にあるのですが、それはあとまわしにして、芝刈りが意味するところを考えてみたいと思います。
この小説の中で、芝刈りをするという行為は何を意味しているのでしょうか。この短編の中からその意味を探る前に、作者は実際にこの芝刈りのアルバイトをしたのか?また作者は芝刈りそのものをしたことがあるのか?ということを考えてみたいと思います。作者のエッセイや旅行記などから、作者が学生だった当時まだ運転免許を持っていなかったことがわかりますから、この短編そのままのアルバイトをすることは不可能でした。そしてこの短編を書いた時点でも車に関する知識、もしくは興味は希薄だったことが想像できます。
当時フォルクスワーゲンといえば、空冷エンジンを積んだビートル(かぶとむし)のことです。ですから“1973年のピンボール”に書かれているような“ラジエーターが故障するフォルクスワーゲン”は存在しない車ということになりますし、“スバルの1000CC”というのも奇妙な印象を与えます。当時の学生の間では、スバルといえばスバル360のことで、“スバルの1000CC”という車はもちろんありましたが値段はずっと高く、しかも発売が1966年ですから、たとえ中古車としても学生がアルバイトで稼いだお金で買うには高すぎたのではないかと思います。それに比べ、スバル360は発売が1958年ですから、学生でも買えるくらいの年式が古い安い中古車がありました。
次に、作者は芝刈りをしたことがあるのか?という点について考えてみたいと思います。余談ですが、僕は春から秋にかけて「芝を刈らなければ」という強迫観念に囚われることが多く、我が家の庭の芝を刈るたびにこの短編のことを思い出しながら芝を刈っています。そういう芝刈りに対する脅迫観念があることも、この短編が好きな理由の一つかもしれません(笑)。強迫観念というおおげさな言葉を使ったのは理由があります。芝刈りは、月に一度ではなく週に一度はしなければならないものなのです。この短編に書かれているように、月一回の芝刈りでは「大抵の庭の芝はたっぷりと伸びている。まるで草むらみたいだ」という状態になってしまいます。とくに日本のような高温多湿の国では、雑草がはびこり芝は駆逐されてしまうのです。それこそ芝を刈っているのか雑草を刈っているのかわからないようになってしまいます。それは、ゴルフ場が芝以外の草を駆除する除草剤をまき、地下水を汚し問題になっていることでもわかります。
それでも作者は、芝刈りのまねごとくらいは何度かしたことはあるのだろう、ということは想像できます。というのは、作者は芝刈りについて「それからずっとかがんで仕事をするものだから、腰がすごく痛くなる。これは実際にやった人じゃなくちゃわからない。慣れるまでは階段の上り下りにも不自由するくらいだ」と書いているからです。これはまったくその通りで、芝刈りというのは結構しんどい仕事なのです。もっとも、芝刈りに関する話を人から聞き、聞いたことをアレンジして書いただけ、という可能性もありますが。
下に続きます↓
ひとつの小説を分析するとき、意図せずに重箱の隅をつつくような作業をしているような気分になることがあります。と言ってもごく些細なことで、この短編の価値を下げるわけではありません。例えば“スバルの1000CC”とか、“ラジエーターが故障するフォルクスワーゲン”(1973年のピンボール)といったたぐいのことです。もう一つ気になるところが第三の部分にあるのですが、それはあとまわしにして、芝刈りが意味するところを考えてみたいと思います。
この小説の中で、芝刈りをするという行為は何を意味しているのでしょうか。この短編の中からその意味を探る前に、作者は実際にこの芝刈りのアルバイトをしたのか?また作者は芝刈りそのものをしたことがあるのか?ということを考えてみたいと思います。作者のエッセイや旅行記などから、作者が学生だった当時まだ運転免許を持っていなかったことがわかりますから、この短編そのままのアルバイトをすることは不可能でした。そしてこの短編を書いた時点でも車に関する知識、もしくは興味は希薄だったことが想像できます。
当時フォルクスワーゲンといえば、空冷エンジンを積んだビートル(かぶとむし)のことです。ですから“1973年のピンボール”に書かれているような“ラジエーターが故障するフォルクスワーゲン”は存在しない車ということになりますし、“スバルの1000CC”というのも奇妙な印象を与えます。当時の学生の間では、スバルといえばスバル360のことで、“スバルの1000CC”という車はもちろんありましたが値段はずっと高く、しかも発売が1966年ですから、たとえ中古車としても学生がアルバイトで稼いだお金で買うには高すぎたのではないかと思います。それに比べ、スバル360は発売が1958年ですから、学生でも買えるくらいの年式が古い安い中古車がありました。
次に、作者は芝刈りをしたことがあるのか?という点について考えてみたいと思います。余談ですが、僕は春から秋にかけて「芝を刈らなければ」という強迫観念に囚われることが多く、我が家の庭の芝を刈るたびにこの短編のことを思い出しながら芝を刈っています。そういう芝刈りに対する脅迫観念があることも、この短編が好きな理由の一つかもしれません(笑)。強迫観念というおおげさな言葉を使ったのは理由があります。芝刈りは、月に一度ではなく週に一度はしなければならないものなのです。この短編に書かれているように、月一回の芝刈りでは「大抵の庭の芝はたっぷりと伸びている。まるで草むらみたいだ」という状態になってしまいます。とくに日本のような高温多湿の国では、雑草がはびこり芝は駆逐されてしまうのです。それこそ芝を刈っているのか雑草を刈っているのかわからないようになってしまいます。それは、ゴルフ場が芝以外の草を駆除する除草剤をまき、地下水を汚し問題になっていることでもわかります。
それでも作者は、芝刈りのまねごとくらいは何度かしたことはあるのだろう、ということは想像できます。というのは、作者は芝刈りについて「それからずっとかがんで仕事をするものだから、腰がすごく痛くなる。これは実際にやった人じゃなくちゃわからない。慣れるまでは階段の上り下りにも不自由するくらいだ」と書いているからです。これはまったくその通りで、芝刈りというのは結構しんどい仕事なのです。もっとも、芝刈りに関する話を人から聞き、聞いたことをアレンジして書いただけ、という可能性もありますが。
下に続きます↓
あらためて書く必要はないと思いますが、芝刈りという行為は、この短編全体を象徴するメタファーであると思います。要するに14〜5年前、『僕』は芝刈り的生き方(自己完結的世界)を自ら求めていたということです。『僕』は大学の学生課で芝刈りの仕事を見つけ、何人かの学生と一緒に芝刈りを始めますが、きつい仕事なのでみんなすぐに辞めてしまいます。そして『僕』はこう書いています。
仕事はきつかったが、給料は悪くなかった。それにあまり他人と口をきかなくて済む。僕向きだ。
そして、芝刈りが“僕向き”である理由をこう書いています。
実際僕はすごく評判がよかった。丁寧な仕事をしたせいだ。大抵のアルバイトは大型の電動芝刈り機でざっと芝を刈ると、残りの部分はかなりいい加減にやってしまう。それなら時間も早く済むし、体も疲れない。僕のやり方はまったく逆だ。機械はいい加減に使って、手仕事に時間をかける。(中略)僕はべつに評判を良くするためにこんなに丁寧な仕事をしたわけではない。信じてもらえないかもしれないけど、ただ単に芝生を刈るのが好きだったのだ。(後略)
効率の悪い、遠くにある家の芝刈りを引き受けた理由も以下のように書いています。
べつにたいした理由はない。遠くまで行くのが好きなのだ。遠くの庭で遠くの芝を刈るのが好きなのだ。遠くの道の遠くの風景を眺めるのが好きなのだ。でもそんな風に説明したって、たぶん誰もわかってくれないだろう。
『僕』は、誰かにわかってもらおうと意思すらないようです。そして、見落としてはならないこのような一節があります。ずっと遠くの街に住む恋人との二週間をのぞいた、東京での学生生活についての記述です。
彼女と会う二週間ばかりをのぞけば、僕の人生はおそろしく単調なものだった。たまに大学に行って講義を受け、なんとか人なみの単位は取った。それから一人で映画を見たり、わけもなく街をぶらぶらしたり、仲の良い女ともだちとセックス抜きのデートをしたりした。何人もで集まったり騒いだりするのが苦手だったせいで、まわりでは物静かな人間だと思われていた。(後略)
以上のことから想像するのですが、『僕』は東京の大学に進学することに憧れていたわけではなさそうですし、とくに東京での暮らしに新鮮さを感じてもいなさそうです。「風の歌を聴け」であったか「73年のピンボール」であったか忘れましたが、希望の大学などはなく、大学でさえあればどこでもよかったという気持ちを、この短編の『僕』も持っているようです。そして友達をたくさんつくり、学生生活を楽しもうという気もなく、ひとり自分の中に閉じこもり、休みに街へ帰り、恋人と過ごすときだけが生き生きとした気持ちになれたようです。そんな『僕』にとって、誰とも話す必要のない芝刈りの仕事は、まさに“僕向き”(自己完結的)の仕事だったわけです。それは当時の彼の生き方を象徴しており、へその緒が取れない嬰児のように、まだ“街”(故郷)を引きずっていたのだろうと思います。
異論は当然あるでしょうが、“恋人”は恋人が象徴し、その存在の背後にある“街”と『僕』の幼児期から思春期(高校卒業)までの過去のメタファーであると思います。しかし『僕』は、芝刈りをした家の奥さんとのセックスのときに聞こえた“電話”に出ることができなかったのです。その“電話”は、『僕』の思春期までの過去からの電話という隠喩であると僕は解釈しています。『僕』は、過去へはもう戻れないことを、どこかで自覚し始めているのだと思いますが、みなさんはどのようにお考えでしょうか。
次は、この短編の核心である第三の部分について書きたいと思います。
仕事はきつかったが、給料は悪くなかった。それにあまり他人と口をきかなくて済む。僕向きだ。
そして、芝刈りが“僕向き”である理由をこう書いています。
実際僕はすごく評判がよかった。丁寧な仕事をしたせいだ。大抵のアルバイトは大型の電動芝刈り機でざっと芝を刈ると、残りの部分はかなりいい加減にやってしまう。それなら時間も早く済むし、体も疲れない。僕のやり方はまったく逆だ。機械はいい加減に使って、手仕事に時間をかける。(中略)僕はべつに評判を良くするためにこんなに丁寧な仕事をしたわけではない。信じてもらえないかもしれないけど、ただ単に芝生を刈るのが好きだったのだ。(後略)
効率の悪い、遠くにある家の芝刈りを引き受けた理由も以下のように書いています。
べつにたいした理由はない。遠くまで行くのが好きなのだ。遠くの庭で遠くの芝を刈るのが好きなのだ。遠くの道の遠くの風景を眺めるのが好きなのだ。でもそんな風に説明したって、たぶん誰もわかってくれないだろう。
『僕』は、誰かにわかってもらおうと意思すらないようです。そして、見落としてはならないこのような一節があります。ずっと遠くの街に住む恋人との二週間をのぞいた、東京での学生生活についての記述です。
彼女と会う二週間ばかりをのぞけば、僕の人生はおそろしく単調なものだった。たまに大学に行って講義を受け、なんとか人なみの単位は取った。それから一人で映画を見たり、わけもなく街をぶらぶらしたり、仲の良い女ともだちとセックス抜きのデートをしたりした。何人もで集まったり騒いだりするのが苦手だったせいで、まわりでは物静かな人間だと思われていた。(後略)
以上のことから想像するのですが、『僕』は東京の大学に進学することに憧れていたわけではなさそうですし、とくに東京での暮らしに新鮮さを感じてもいなさそうです。「風の歌を聴け」であったか「73年のピンボール」であったか忘れましたが、希望の大学などはなく、大学でさえあればどこでもよかったという気持ちを、この短編の『僕』も持っているようです。そして友達をたくさんつくり、学生生活を楽しもうという気もなく、ひとり自分の中に閉じこもり、休みに街へ帰り、恋人と過ごすときだけが生き生きとした気持ちになれたようです。そんな『僕』にとって、誰とも話す必要のない芝刈りの仕事は、まさに“僕向き”(自己完結的)の仕事だったわけです。それは当時の彼の生き方を象徴しており、へその緒が取れない嬰児のように、まだ“街”(故郷)を引きずっていたのだろうと思います。
異論は当然あるでしょうが、“恋人”は恋人が象徴し、その存在の背後にある“街”と『僕』の幼児期から思春期(高校卒業)までの過去のメタファーであると思います。しかし『僕』は、芝刈りをした家の奥さんとのセックスのときに聞こえた“電話”に出ることができなかったのです。その“電話”は、『僕』の思春期までの過去からの電話という隠喩であると僕は解釈しています。『僕』は、過去へはもう戻れないことを、どこかで自覚し始めているのだと思いますが、みなさんはどのようにお考えでしょうか。
次は、この短編の核心である第三の部分について書きたいと思います。
第三の部分です。
まず始めに、記憶を回想するという行為について考えておきたいと思います。前にも書きましたが、ここで想い起す記憶とは、たんなる過去の時点で完結している思い出ではなく、回想する主体に現在に至るまでなんらかの影響を与えている、言ってみればある種の重さを持った記憶です。そのような記憶を回想する場合、往々にして回想する主体の、その記憶に対する解釈というものが含まれる場合があります。ですから、実際に過去に起きた事柄そのままとは限らず、その解釈は回想する時点で加えられたものというより、14〜5年前から意識的無意識的に少しずつ行われてきたものかもしれません。
だからと言って僕は、『僕』が自分の都合の良いように過去を捻じ曲げてきたと言うつもりではありません。『僕』はそれなりに真剣に自分の過去の総括を試みてきたように思えますし、それが子猫を積み上げる試みを始めた時点での、『僕』にとっての“真実”なのでしょう。そして、村上春樹の小説を読むに際して頭に入れておきたいことに、彼自身が「ノルウェイの森」は彼の作品の中で唯一のリアルな小説であると書いていることです。ということは、「ノルウェイの森」以外の小説はリアルではない、ということが言えます。僕自身は、「ノルウェイの森」でさえリアルな小説とは思えないのですが・・。それに、恋愛小説ですらないとも思っています。
芝刈りが三人の喪失感を持った登場人物を結びつけます。雇い主の女性は、丁寧に芝を刈る『僕』に好感を持ちサンドイッチやビールをご馳走してくれます。芝刈りを終えた後、ビールを飲みながら女主人は「来月もまた来なよ」と『僕』に言います。『僕』は、自分は学生でそろそろ勉強をしないと単位が取れないので、今日が最後の仕事であることを説明します。すると女主人は、
≪彼女はしばらく僕の顔を見てから、足もとを眺め、それから顔を見た。
「学生なのかい」≫
と言って、『僕』が芝刈りの職人ではなく学生であることに興味を持ち、見てほしいものがあると家の中へ誘います。
僕の感想は、ここから皆さんの感想と少し違ってきます。というのは、僕は依頼主の家の娘は生きていると思っているのです。というか、生きていてほしいという願望に過ぎないのですが、僕には依頼主の女性や娘の部屋から死を感じられないのです。そして娘が生きているのではないかというかすかな根拠として、以下の一節があります。心もとないほど小さな希望で、まさに藁をもつかむ程度の根拠です(笑)。『僕』は芝刈りを始める前に芝刈り機や熊手を運びます。
≪僕が道具を運んでいるあいだ、彼女は玄関に靴を十足ばかり並べてぼろきれでほこりを払っていた。靴は全部女もので、小さなサイズと特大のサイズの二種類だった。≫
特大のサイズの靴は、もちろん女主人のものでしょう。そして、小さなサイズのものは娘の靴だと思われます(娘は母親に似ず、大女ではなかったのでしょう)。娘が死んだとして、部屋をそのままにしておくということは、女主人がそれを受け入れることができず、茫然と酒に頼ってひと月を過ごしてきたと解釈できます。しかし、なぜ靴の手入れまでするのでしょう?それは、いつ娘が帰って来ても良いように、という気持ちからだと僕は解釈しているのですが、みなさんはどのように思われるのでしょうか?
≪家の中は相変わらずしんとしていた。夏の午後の光の洪水の中から突然屋内に入ると、瞼の奥がちくちくと痛んだ。家の中には水でといたような淡い闇が漂っていた。何十年も前からそこに住みついてしまっているような感じの闇だ。べつに暗いというわけではなく、淡い闇だった。中略
廊下にはいろんな臭いがした。どの臭いも覚えのある匂いだった。時間がつくりだす匂いだ。時間が作りだし、そしてまたいつか時間が消し去っていく匂いだ。古い洋服や古い家具や、古い本や、古い生活の匂いだ。≫
まず始めに、記憶を回想するという行為について考えておきたいと思います。前にも書きましたが、ここで想い起す記憶とは、たんなる過去の時点で完結している思い出ではなく、回想する主体に現在に至るまでなんらかの影響を与えている、言ってみればある種の重さを持った記憶です。そのような記憶を回想する場合、往々にして回想する主体の、その記憶に対する解釈というものが含まれる場合があります。ですから、実際に過去に起きた事柄そのままとは限らず、その解釈は回想する時点で加えられたものというより、14〜5年前から意識的無意識的に少しずつ行われてきたものかもしれません。
だからと言って僕は、『僕』が自分の都合の良いように過去を捻じ曲げてきたと言うつもりではありません。『僕』はそれなりに真剣に自分の過去の総括を試みてきたように思えますし、それが子猫を積み上げる試みを始めた時点での、『僕』にとっての“真実”なのでしょう。そして、村上春樹の小説を読むに際して頭に入れておきたいことに、彼自身が「ノルウェイの森」は彼の作品の中で唯一のリアルな小説であると書いていることです。ということは、「ノルウェイの森」以外の小説はリアルではない、ということが言えます。僕自身は、「ノルウェイの森」でさえリアルな小説とは思えないのですが・・。それに、恋愛小説ですらないとも思っています。
芝刈りが三人の喪失感を持った登場人物を結びつけます。雇い主の女性は、丁寧に芝を刈る『僕』に好感を持ちサンドイッチやビールをご馳走してくれます。芝刈りを終えた後、ビールを飲みながら女主人は「来月もまた来なよ」と『僕』に言います。『僕』は、自分は学生でそろそろ勉強をしないと単位が取れないので、今日が最後の仕事であることを説明します。すると女主人は、
≪彼女はしばらく僕の顔を見てから、足もとを眺め、それから顔を見た。
「学生なのかい」≫
と言って、『僕』が芝刈りの職人ではなく学生であることに興味を持ち、見てほしいものがあると家の中へ誘います。
僕の感想は、ここから皆さんの感想と少し違ってきます。というのは、僕は依頼主の家の娘は生きていると思っているのです。というか、生きていてほしいという願望に過ぎないのですが、僕には依頼主の女性や娘の部屋から死を感じられないのです。そして娘が生きているのではないかというかすかな根拠として、以下の一節があります。心もとないほど小さな希望で、まさに藁をもつかむ程度の根拠です(笑)。『僕』は芝刈りを始める前に芝刈り機や熊手を運びます。
≪僕が道具を運んでいるあいだ、彼女は玄関に靴を十足ばかり並べてぼろきれでほこりを払っていた。靴は全部女もので、小さなサイズと特大のサイズの二種類だった。≫
特大のサイズの靴は、もちろん女主人のものでしょう。そして、小さなサイズのものは娘の靴だと思われます(娘は母親に似ず、大女ではなかったのでしょう)。娘が死んだとして、部屋をそのままにしておくということは、女主人がそれを受け入れることができず、茫然と酒に頼ってひと月を過ごしてきたと解釈できます。しかし、なぜ靴の手入れまでするのでしょう?それは、いつ娘が帰って来ても良いように、という気持ちからだと僕は解釈しているのですが、みなさんはどのように思われるのでしょうか?
≪家の中は相変わらずしんとしていた。夏の午後の光の洪水の中から突然屋内に入ると、瞼の奥がちくちくと痛んだ。家の中には水でといたような淡い闇が漂っていた。何十年も前からそこに住みついてしまっているような感じの闇だ。べつに暗いというわけではなく、淡い闇だった。中略
廊下にはいろんな臭いがした。どの臭いも覚えのある匂いだった。時間がつくりだす匂いだ。時間が作りだし、そしてまたいつか時間が消し去っていく匂いだ。古い洋服や古い家具や、古い本や、古い生活の匂いだ。≫
僕は、この淡い闇や時間がつくりだす古いものの臭いのする廊下を、“あちら側”に抜ける通路のようなものであると解釈しています。この廊下はのちの「ダンスダンスダンス」の闇への通路であるエレヴェーターや、「ねじまき鳥クロニクル」の井戸、そして「1Q84」の高速道路の非常階段の原型ではないかと想像しているのですが、みなさんはいかがお考えでしょうか?ですから僕の解釈では、『僕』は女主人と共にその通路を通って“あちら側”へと向かうわけです。そして女主人はワンピースのポケットから鍵の束を出し、大きな音を立てて娘の部屋のドアを開けます。この鍵について、僕は長年疑問に思っていたのですが、死んだにせよ生きているにせよ、なぜ娘の部屋に鍵をかけておかなければならないのでしょう?普通なら、家の戸締りさえしっかりとすれば、それぞれの部屋にいちいち鍵をかける必要はないはずです。これは僕にとって、長年の解けない謎でした。
今回このように分析を始めてこの短編を何度も読み返したり、三部作をなん十回目かわかりませんがもう一度読みなおしヒントをさがしていて思ったのですが、この娘の部屋は異界の一部なのではないかということです。もちろんこじつけに過ぎないのかもしれませんが、そう考えてみると前後の作品との関連で、この短編の意味がよくわかるような気がするのです。母親である女主人は出て行った娘を理解したいため、幾度となく娘の部屋に入り時を過ごしたのだろうと想像します。そうしているうちに、光の海がつくりだしたほんのちょっとした歪みの中から娘が現れたのではないでしょうか。そのような体験をしたあと、彼女は娘の部屋に鍵をかけ酒びたりになったのではないかとも思うのです。なにしろこの短編は、読者に多くの情報を与えてくれませんから、理解しがたい部分を想像で補う以外ありません(笑)。
娘の部屋に入り、まず『僕』は典型的なティーンエイジャーの女の子の部屋という印象を持ちます。この“典型的なティーンエイジャーの女の子の部屋”という記述には、多少の違和感を持ちます。というのは、その後の部屋の記述からはとても典型的なティーンエイジャーの女の子の部屋とは思えないのです。僕は学生だった頃、同級生や部活で一緒だった女の子の部屋に行ったことがあるのですが(もちろん何人かで)、その女の子たちの部屋は、このいなくなった娘の部屋よりはるかに華やかで、ぬいぐるみやスターの写真やらポスターがあり、男兄弟しかいない僕の目から見るとかなりまぶしく感じたものです(笑)。そして女主人から「どう思う?」と感想を訊かれたとき、「学校は女子大か短大」と答えていますが、僕には“典型的な”早稲田の女子学生の部屋に思えるのです。作者がこの娘の部屋の様子を書くとき、思い浮かべたのは陽子さんの学生時代の部屋だったのではないかと想像したりしています。
それでは、娘の部屋でどのようなことが起きたのでしょうか。女主人は、洋服ダンスを開けて見るように言い、さらに引出しまで開けさせます。そして『僕』が見終えると、彼女はベッドに腰かけたまま窓の外を見ています。一呼吸おいて、彼女は「どう思う?」と訊き、さらに窓に目をやったまま「彼女についてさ」と言います(彼女に傍点)。このくだりは、何を物語っているのでしょう。思うにこの母親にとって娘は、大事に育て自分の言うことを素直に聞く良い娘だったのでしょう。『僕』が見た部屋や洋服の記述からも、なにもかもが清潔できちんとした娘だったことがわかります。少なくとも母親である女主人はそう信じていたのだと思います。ところがある日、娘はなんらかの理由で突然のように母親にそむき始めます。良い娘だと信じていた母親にとっては、まさに青天の霹靂だったことでしょう。そのような経緯のあとで娘は出て行ってしまった。母が娘を、娘が母をお互いに愛していることは疑いのないことだと思います。それだけに母親は『僕』の言葉から(『僕』を見ることができず視線をそらし)、わずかでも娘を理解する糸口を、アルコールで朦朧とした意識のなかで探していたのではないかと思います。
「どう思う?」と訊かれ、『僕』は「とても感じのいいきちんとした人みたいですね」と答え、そして「あまり押しつけがましくないし、かといって性格が弱いわけでもない・・」と言います。女主人は「続けなよ」と促します。『僕』は「それ以上はわかりませんよ」と応じるのですが、女主人は「だいたい合ってるよ」と無表情に言います。
今回このように分析を始めてこの短編を何度も読み返したり、三部作をなん十回目かわかりませんがもう一度読みなおしヒントをさがしていて思ったのですが、この娘の部屋は異界の一部なのではないかということです。もちろんこじつけに過ぎないのかもしれませんが、そう考えてみると前後の作品との関連で、この短編の意味がよくわかるような気がするのです。母親である女主人は出て行った娘を理解したいため、幾度となく娘の部屋に入り時を過ごしたのだろうと想像します。そうしているうちに、光の海がつくりだしたほんのちょっとした歪みの中から娘が現れたのではないでしょうか。そのような体験をしたあと、彼女は娘の部屋に鍵をかけ酒びたりになったのではないかとも思うのです。なにしろこの短編は、読者に多くの情報を与えてくれませんから、理解しがたい部分を想像で補う以外ありません(笑)。
娘の部屋に入り、まず『僕』は典型的なティーンエイジャーの女の子の部屋という印象を持ちます。この“典型的なティーンエイジャーの女の子の部屋”という記述には、多少の違和感を持ちます。というのは、その後の部屋の記述からはとても典型的なティーンエイジャーの女の子の部屋とは思えないのです。僕は学生だった頃、同級生や部活で一緒だった女の子の部屋に行ったことがあるのですが(もちろん何人かで)、その女の子たちの部屋は、このいなくなった娘の部屋よりはるかに華やかで、ぬいぐるみやスターの写真やらポスターがあり、男兄弟しかいない僕の目から見るとかなりまぶしく感じたものです(笑)。そして女主人から「どう思う?」と感想を訊かれたとき、「学校は女子大か短大」と答えていますが、僕には“典型的な”早稲田の女子学生の部屋に思えるのです。作者がこの娘の部屋の様子を書くとき、思い浮かべたのは陽子さんの学生時代の部屋だったのではないかと想像したりしています。
それでは、娘の部屋でどのようなことが起きたのでしょうか。女主人は、洋服ダンスを開けて見るように言い、さらに引出しまで開けさせます。そして『僕』が見終えると、彼女はベッドに腰かけたまま窓の外を見ています。一呼吸おいて、彼女は「どう思う?」と訊き、さらに窓に目をやったまま「彼女についてさ」と言います(彼女に傍点)。このくだりは、何を物語っているのでしょう。思うにこの母親にとって娘は、大事に育て自分の言うことを素直に聞く良い娘だったのでしょう。『僕』が見た部屋や洋服の記述からも、なにもかもが清潔できちんとした娘だったことがわかります。少なくとも母親である女主人はそう信じていたのだと思います。ところがある日、娘はなんらかの理由で突然のように母親にそむき始めます。良い娘だと信じていた母親にとっては、まさに青天の霹靂だったことでしょう。そのような経緯のあとで娘は出て行ってしまった。母が娘を、娘が母をお互いに愛していることは疑いのないことだと思います。それだけに母親は『僕』の言葉から(『僕』を見ることができず視線をそらし)、わずかでも娘を理解する糸口を、アルコールで朦朧とした意識のなかで探していたのではないかと思います。
「どう思う?」と訊かれ、『僕』は「とても感じのいいきちんとした人みたいですね」と答え、そして「あまり押しつけがましくないし、かといって性格が弱いわけでもない・・」と言います。女主人は「続けなよ」と促します。『僕』は「それ以上はわかりませんよ」と応じるのですが、女主人は「だいたい合ってるよ」と無表情に言います。
≪彼女(傍点)の存在が少しずつ部屋の中に忍び込んでいるような気がした。彼女(傍点)はぼんやりとした白い影のようだった。顔も手も足も、何もない。光の海がつくりだしたほんのちょっとした歪みの中に彼女はいた。≫
『僕』は「ボーイフレンドはいます」と言い、その後に、
≪「問題は……彼女がいろんなものになじめないことです。自分の体やら、自分の考えていることやら、自分の求めていることやら、他人が要求していることやら……そんなことにです」
「そうだね」としばらくあとで女は言った。「あんたの言うことはわかるよ」
僕にはわからなかった。僕のことばが意味していることはわかった。しかしそれが誰から誰に向けられたものであるかがわからなかった。≫
という、この短編の核心部分が続きます。先に、喪失感を持った登場人物を三人と書きましたが、この家の娘が死んだのではなく生きていると解釈すれば、この“異界”である部屋では母、娘、『僕』の想念が交差しているのだと思います。それでは、この言葉は誰から誰に向けて語られたのでしょうか?この言葉は、光の海がつくりだしたほんのちょっとした歪みの中にいる娘が、『僕』の口を通して母親に言った言葉ではないかと思うのです。現実の世界で娘がどこにいるにせよ、娘は母にそむき家を出たことに強い罪悪感と後悔の念を持ち、なんとしても自分をわかってもらいたいというその強い想念が、時空を超えて娘の想いを『僕』と母がいる場に運んだのだろうと思うのです。その言葉を聞き、女主人は「そうだね・・、あんたの言うことはわかるよ」と、『僕』を通して娘に言ったのだろうと思います。
ですから、『僕』には誰から誰に向けられた言葉なのかがわからなかったのです。部屋を一通り見たあと、『僕』はこの部屋の持ち主の姿を想像してみますが、別れた恋人の顔しか浮かんできません。そして洋服ダンスを引出しまで開けてみたあとで、女主人に「服を見れば大抵の女のことはわかるよ」と言われ、恋人のことを考えて見ますが、ほんの半年前に会った恋人がどのような服を着ていたかさえ思い出せないのです。結局のところ、この言葉は娘が母と自分自身に向かって言ったと同時に、母と自分をつなぐ役目をしてくれている『僕』にも向けて言った言葉ではないでしょうか。
≪結局のところ、僕は彼女についていったい何を知っていたのだろう?≫
第二の部分のおしまいに、“恋人”が意味するものは、『僕』の幼児期から思春期に至る過去と“街”のメタファーであると書きました。永遠に引き延ばされたアドレッセンス。居心地のいいモラトリアムの時代。アイデンティティの確立からの逃避。そのような曖昧さの中からの芝刈り的生き方。
『僕』は「ボーイフレンドはいます」と言い、その後に、
≪「問題は……彼女がいろんなものになじめないことです。自分の体やら、自分の考えていることやら、自分の求めていることやら、他人が要求していることやら……そんなことにです」
「そうだね」としばらくあとで女は言った。「あんたの言うことはわかるよ」
僕にはわからなかった。僕のことばが意味していることはわかった。しかしそれが誰から誰に向けられたものであるかがわからなかった。≫
という、この短編の核心部分が続きます。先に、喪失感を持った登場人物を三人と書きましたが、この家の娘が死んだのではなく生きていると解釈すれば、この“異界”である部屋では母、娘、『僕』の想念が交差しているのだと思います。それでは、この言葉は誰から誰に向けて語られたのでしょうか?この言葉は、光の海がつくりだしたほんのちょっとした歪みの中にいる娘が、『僕』の口を通して母親に言った言葉ではないかと思うのです。現実の世界で娘がどこにいるにせよ、娘は母にそむき家を出たことに強い罪悪感と後悔の念を持ち、なんとしても自分をわかってもらいたいというその強い想念が、時空を超えて娘の想いを『僕』と母がいる場に運んだのだろうと思うのです。その言葉を聞き、女主人は「そうだね・・、あんたの言うことはわかるよ」と、『僕』を通して娘に言ったのだろうと思います。
ですから、『僕』には誰から誰に向けられた言葉なのかがわからなかったのです。部屋を一通り見たあと、『僕』はこの部屋の持ち主の姿を想像してみますが、別れた恋人の顔しか浮かんできません。そして洋服ダンスを引出しまで開けてみたあとで、女主人に「服を見れば大抵の女のことはわかるよ」と言われ、恋人のことを考えて見ますが、ほんの半年前に会った恋人がどのような服を着ていたかさえ思い出せないのです。結局のところ、この言葉は娘が母と自分自身に向かって言ったと同時に、母と自分をつなぐ役目をしてくれている『僕』にも向けて言った言葉ではないでしょうか。
≪結局のところ、僕は彼女についていったい何を知っていたのだろう?≫
第二の部分のおしまいに、“恋人”が意味するものは、『僕』の幼児期から思春期に至る過去と“街”のメタファーであると書きました。永遠に引き延ばされたアドレッセンス。居心地のいいモラトリアムの時代。アイデンティティの確立からの逃避。そのような曖昧さの中からの芝刈り的生き方。
部屋を出て階段を降りるときの主語は“我々”です。この短編に出てくる唯一の一人称複数形なのですが、強引な意味づけをすれば、娘の部屋である種の精神の交感をしたことにより生じた共同意識を表しているのかもしれません。もしそうであるならば、三人がそれぞれのカタルシスを得たことを、“我々”という一人称複数で表したのかな?とも思えます。もっとも『僕』のほんとうのカタルシスは、さらに長い年月の先に先延ばしされるのですが・・。
玄関のドアを開けた時、『僕』は本当にほっとします。淡い闇に包まれた廊下を通り、“異界”から現実の世界に戻ってきたのです。女主人はチップとして一万円を『僕』に渡します。1968・9年の一万円というのは、チップとしては信じられないほどの額です。何しろ新卒のサラリーマンの初任給が四万円前後の時代ですから。女主人は「芝生がすごく綺麗に刈れてたからさ、嬉しかったんだよ」と言いましたが、ほんとうは「娘のことを教えてくれたからさ、嬉しかったんだよ」と言いたかったのではないでしょうか。それでなければ、芝刈りのチップとしては一万円はあまりにも多すぎます。
さて、娘はどこに行ったのでしょう?母親と修復しがたい仲違いをして、自分を理解してくれている伯父さん叔母さんのところに身を寄せているのかもしれませんし、友達のところにいるのかもしれません。しかし僕にはそう思えないのです。作者はわざわざ『僕』に買ったばかりのトランジスタ・ラジオを運ばせ、きれいにFMのステレオ放送が入るのに、中波のFENをかけロックンロールを聴き、アナウンサーに奇妙なイントネーションでヴェトナムの地名を連発させています。作者がモノラルでしか受信できないFENにこだわるには、それなりの意図があってのことと思われます。その目的は言うまでもなく、時代背景をそこにはっきりと書き込みたかったからではないでしょうか。以上のような理由で、娘は自分の大学(早稲田?)の学生に占拠された校舎の中か、運動家が集まるどこかのアジトにいるのではないかと思います。というのは当時、おとなしそうな彼(彼女)が突然のように学生運動に加わり、何日も何週間も家に帰らなくなったということは珍しくなかったからです。
本当に長くなってしまいました。第四の部分を書き終え次第、また載せたいと思います。
玄関のドアを開けた時、『僕』は本当にほっとします。淡い闇に包まれた廊下を通り、“異界”から現実の世界に戻ってきたのです。女主人はチップとして一万円を『僕』に渡します。1968・9年の一万円というのは、チップとしては信じられないほどの額です。何しろ新卒のサラリーマンの初任給が四万円前後の時代ですから。女主人は「芝生がすごく綺麗に刈れてたからさ、嬉しかったんだよ」と言いましたが、ほんとうは「娘のことを教えてくれたからさ、嬉しかったんだよ」と言いたかったのではないでしょうか。それでなければ、芝刈りのチップとしては一万円はあまりにも多すぎます。
さて、娘はどこに行ったのでしょう?母親と修復しがたい仲違いをして、自分を理解してくれている伯父さん叔母さんのところに身を寄せているのかもしれませんし、友達のところにいるのかもしれません。しかし僕にはそう思えないのです。作者はわざわざ『僕』に買ったばかりのトランジスタ・ラジオを運ばせ、きれいにFMのステレオ放送が入るのに、中波のFENをかけロックンロールを聴き、アナウンサーに奇妙なイントネーションでヴェトナムの地名を連発させています。作者がモノラルでしか受信できないFENにこだわるには、それなりの意図があってのことと思われます。その目的は言うまでもなく、時代背景をそこにはっきりと書き込みたかったからではないでしょうか。以上のような理由で、娘は自分の大学(早稲田?)の学生に占拠された校舎の中か、運動家が集まるどこかのアジトにいるのではないかと思います。というのは当時、おとなしそうな彼(彼女)が突然のように学生運動に加わり、何日も何週間も家に帰らなくなったということは珍しくなかったからです。
本当に長くなってしまいました。第四の部分を書き終え次第、また載せたいと思います。
毎回、丁寧な考察に「なるほど」と思いながら読ませて頂いています。
娘の生死は作中で言及されていませんから、読者の掘り下げ方で色んな解釈が出来るんですね。私はもうノルウェイのイメージをかなり引きずって読んでいたので、自殺したとしか思ってませんでした。
ただ、ご指摘のあった箇所についてはちょっと捉え方がちがいました。
まず娘が生きているとするなら、その娘の部屋に今日会ったばかりの男を入れるだろうか?ってことなんです。
これは私が女だから特にそう感じるんだと思います。
私が娘側だとして、自分がいないうちに母がそういうことをしてたらすっごく嫌だし、母親側としても、普段鍵まで掛けている娘の部屋に男を入れるって、ちょっと抵抗あるんじゃないかなぁ…
生きているとしたら、やはりノルウェイの亜美寮みたいな場所にいるとか、なにかしらギリギリな場所に追い込まれているように思います。
靴に関しては、私も上手く説明は出来ませんが、母親の気持ちはわかる気がします。
ちょっと一旦切りますね(すみません)
娘の生死は作中で言及されていませんから、読者の掘り下げ方で色んな解釈が出来るんですね。私はもうノルウェイのイメージをかなり引きずって読んでいたので、自殺したとしか思ってませんでした。
ただ、ご指摘のあった箇所についてはちょっと捉え方がちがいました。
まず娘が生きているとするなら、その娘の部屋に今日会ったばかりの男を入れるだろうか?ってことなんです。
これは私が女だから特にそう感じるんだと思います。
私が娘側だとして、自分がいないうちに母がそういうことをしてたらすっごく嫌だし、母親側としても、普段鍵まで掛けている娘の部屋に男を入れるって、ちょっと抵抗あるんじゃないかなぁ…
生きているとしたら、やはりノルウェイの亜美寮みたいな場所にいるとか、なにかしらギリギリな場所に追い込まれているように思います。
靴に関しては、私も上手く説明は出来ませんが、母親の気持ちはわかる気がします。
ちょっと一旦切りますね(すみません)
慣れないスマホで書き込んでるので休み休み書いてます(笑)すみません。
あっと、先に断っておきますが、あくまで私の感じ方なので、他の解釈を否定するのではありません(^_^;)
読む人によって感じ方が違ってくるのは当たり前ですから。
靴についてなんですけど、多分これも私が女で主婦だからなんでしょうね〜。靴を綺麗にしている=死んだ人の靴は綺麗にしない=生きている、とは言い切れないんじゃないかなと。
娘が生きていて帰ってくる希望があるなら、部屋も掃除しておかしくないですし。
部屋に鍵を掛けて掃除もされていないことから、多分普段は立ち入らない開かずの間になっているのかなと。
だから部屋にある服や鞄は手に取ることもないし、もし部屋に靴があればやはりそれにも触らないでしょう。
いわば娘の部屋は、うりずんさんの仰った通り、異界になっているのです。
そのような異界を作り出すのは、ただの家出少女には出来ないことなんじゃないかと思うのですが。
ただの家出だったら、むしろちゃんと掃除してそう(主婦目線。笑)
靴が綺麗にされていたのは、たぶんそれが玄関にあったからだしょう。或いは下駄箱かな?
異界の物には抵抗があっても、こちらの世界の物にはまだ抵抗が無いというか…
逆に玄関の掃除をしようとした時に、埃だらけの娘の靴だけ避ける方が不自然な感じがします。
死んだからって、その人の持ち物は邪険に出来ませんよね。
だけど部屋は思いが強すぎると言うか…うーん、上手く言えないんですが…
玄関にある靴は綺麗にするけど部屋には入れない、って微妙な葛藤が、私には「娘の不可解な自殺」を印象付けさせるのです。
本当にグダグダな説明?でスミマセン(汗)
変な横槍入れちゃいましたが、気にせず続きを書いて下さいね。楽しみにしてます!
あっと、先に断っておきますが、あくまで私の感じ方なので、他の解釈を否定するのではありません(^_^;)
読む人によって感じ方が違ってくるのは当たり前ですから。
靴についてなんですけど、多分これも私が女で主婦だからなんでしょうね〜。靴を綺麗にしている=死んだ人の靴は綺麗にしない=生きている、とは言い切れないんじゃないかなと。
娘が生きていて帰ってくる希望があるなら、部屋も掃除しておかしくないですし。
部屋に鍵を掛けて掃除もされていないことから、多分普段は立ち入らない開かずの間になっているのかなと。
だから部屋にある服や鞄は手に取ることもないし、もし部屋に靴があればやはりそれにも触らないでしょう。
いわば娘の部屋は、うりずんさんの仰った通り、異界になっているのです。
そのような異界を作り出すのは、ただの家出少女には出来ないことなんじゃないかと思うのですが。
ただの家出だったら、むしろちゃんと掃除してそう(主婦目線。笑)
靴が綺麗にされていたのは、たぶんそれが玄関にあったからだしょう。或いは下駄箱かな?
異界の物には抵抗があっても、こちらの世界の物にはまだ抵抗が無いというか…
逆に玄関の掃除をしようとした時に、埃だらけの娘の靴だけ避ける方が不自然な感じがします。
死んだからって、その人の持ち物は邪険に出来ませんよね。
だけど部屋は思いが強すぎると言うか…うーん、上手く言えないんですが…
玄関にある靴は綺麗にするけど部屋には入れない、って微妙な葛藤が、私には「娘の不可解な自殺」を印象付けさせるのです。
本当にグダグダな説明?でスミマセン(汗)
変な横槍入れちゃいましたが、気にせず続きを書いて下さいね。楽しみにしてます!
何度も追加してスミマセン(汗)
娘の不在が闘争によるものといううりずんさんの読みはとても興味深いですね。
私はその時代をリアルに知らないので、全く想定出来ませんでした。
でも言われてみれば、大事に品よく大人しく育ててきた箱入り娘が闘争によって人が変わってしまったとしたら、ショックや失望からそうなってもおかしくないのかも…
正直言って、私にはその安保闘争とかその一連の流れが上手く理解出来ないんですよね。
日本中の学生達が一斉に同じ思想を持ち、政治的な激しい活動をするっていうのが。
私の世代はバブルを知らない無気力世代と言われたりして、努力は実らないし不況だし未来なんて下り坂、がんばっても無駄だから自分のためにお金と時間使おうぜって雰囲気なんですよね。。。
そういう空気の中で育つと、闘争とかセクトとかが別の世界の話のように聞こえてしまって。
ジェネレーションギャップてすねぇ。
娘の不在が闘争によるものといううりずんさんの読みはとても興味深いですね。
私はその時代をリアルに知らないので、全く想定出来ませんでした。
でも言われてみれば、大事に品よく大人しく育ててきた箱入り娘が闘争によって人が変わってしまったとしたら、ショックや失望からそうなってもおかしくないのかも…
正直言って、私にはその安保闘争とかその一連の流れが上手く理解出来ないんですよね。
日本中の学生達が一斉に同じ思想を持ち、政治的な激しい活動をするっていうのが。
私の世代はバブルを知らない無気力世代と言われたりして、努力は実らないし不況だし未来なんて下り坂、がんばっても無駄だから自分のためにお金と時間使おうぜって雰囲気なんですよね。。。
そういう空気の中で育つと、闘争とかセクトとかが別の世界の話のように聞こえてしまって。
ジェネレーションギャップてすねぇ。
じゃがいもうさぎ。さん、INOさん、みなさん。
前にも書きましたように、この短編から得られる情報はとても少なく、理解しがたい部分は読者の想像によって補う以外手はありません。場合によってはそれぞれの読者が、この物語を発展させて違う物語をつくってしまうことも可能ですが・・(笑)。
娘についてですが、僕は初めてこの短編を読んだときから、娘の死はまったく考えませんでした。というより、娘は死んだのだろうか?という疑問さえ持たずに、母親との深刻な問題によって家を出たのだろうと思っていました。まあ、生きていてほしいという僕の願望があり、夫に死なれ、さらに娘に死なれたのでは、このくすの木のような大女があまりにも可哀そうです。僕は思うのですが、もしこの家の娘が死んだのだとしたら、この短編はとても奥行きの狭いものになってしまうのではないでしょうか。
議論するつもりはまったくありませんが、じゃがいもうさぎ。さんにいただいたコメントに、僕なりの考えを書かせていただきます。もう一度書きますが、決してじゃがいもうさぎ。さんの意見を否定するつもりではありません。
>私が娘側だとして、自分がいないうちに母がそういうことをしてたらすっごく嫌だし、母親側としても、普段鍵まで掛けている娘の部屋に男を入れるって、ちょっと抵抗あるんじゃないかなぁ…
これは母と娘の断絶が、どのようなかたちでどの程度深刻であるかによると思います。修復しがたいほどの深刻な問題と深さであるとして、にもかかわらずお互いの意識下において、親子の愛情がその関係の修復を強く欲しているとすれば、見知らぬ男に部屋どころか服や下着を見られることは、さほどの問題ではないのかもしれません。もちろん人にもよりますしその状況にもよると思いますが、その見知らぬ男が母と娘の間の“配電盤”の役目をしてくれるのだとしたら、部屋や服を見られることはさしたる問題ではないのかもしれません。
>娘が生きていて帰ってくる希望があるなら、部屋も掃除しておかしくないですし。
その希望は、『僕』が現れたことによって初めて持つことができたのではないでしょうか。前にも書きましたように、母親は娘を理解しようと幾度となく娘の部屋に入ったのでしょう。何度目かに娘の想念が、光の海がつくりだしたほんのちょっとした歪みの中から、娘の形をとって現われたのだと思います。そのあり得ない、信じがたい出来事を経験して以来、母親は部屋に鍵をかけ開かずの間にしたのだと思います。ですから、見も知らない“学生”である『僕』を娘の部屋に入れたのは、母親の藁をもつかむ気持からではないか?と先に書きました。
>靴が綺麗にされていたのは、たぶんそれが玄関にあったからだしょう。或いは下駄箱かな?
>異界の物には抵抗があっても、こちらの世界の物にはまだ抵抗が無いというか…
そのとおりだと思います。というか、靴を綺麗にすることによって娘を待つ気持ちを奮い立たせているとも考えられます。象徴的な意味で、娘の靴を磨くことは娘に対する愛情の証として大事なことだったのかもしれません。
>大事に品よく大人しく育ててきた箱入り娘が闘争によって人が変わってしまったとしたら、ショックや失望からそうなってもおかしくないのかも…
当時、学生運動にのめり込んでいった学生と、その親との確執は深刻なものがあり、男女にかかわらずそのような例はいくらでもありました。第一の部分で60年代の学生運動について書いたのも、多少なりとも参考になればという気持ちからでした。僕のようなノンポリ学生でさえ、好むと好まざるとに関わりなくそのような闘争の場に巻き込まれたり、またその運動にシンパシーを感じていましたから。少なくとも68年の秋までは、多くの一般学生及び多衆は学生運動に好意を寄せていたと思います。それが崩れ、ノンポリ学生や一般大衆と学生運動の乖離が始まったのは、69年の東大安田講堂の闘争の頃からだったと思います。
それでは、第四の部分を書き終えたらまた載せます。
前にも書きましたように、この短編から得られる情報はとても少なく、理解しがたい部分は読者の想像によって補う以外手はありません。場合によってはそれぞれの読者が、この物語を発展させて違う物語をつくってしまうことも可能ですが・・(笑)。
娘についてですが、僕は初めてこの短編を読んだときから、娘の死はまったく考えませんでした。というより、娘は死んだのだろうか?という疑問さえ持たずに、母親との深刻な問題によって家を出たのだろうと思っていました。まあ、生きていてほしいという僕の願望があり、夫に死なれ、さらに娘に死なれたのでは、このくすの木のような大女があまりにも可哀そうです。僕は思うのですが、もしこの家の娘が死んだのだとしたら、この短編はとても奥行きの狭いものになってしまうのではないでしょうか。
議論するつもりはまったくありませんが、じゃがいもうさぎ。さんにいただいたコメントに、僕なりの考えを書かせていただきます。もう一度書きますが、決してじゃがいもうさぎ。さんの意見を否定するつもりではありません。
>私が娘側だとして、自分がいないうちに母がそういうことをしてたらすっごく嫌だし、母親側としても、普段鍵まで掛けている娘の部屋に男を入れるって、ちょっと抵抗あるんじゃないかなぁ…
これは母と娘の断絶が、どのようなかたちでどの程度深刻であるかによると思います。修復しがたいほどの深刻な問題と深さであるとして、にもかかわらずお互いの意識下において、親子の愛情がその関係の修復を強く欲しているとすれば、見知らぬ男に部屋どころか服や下着を見られることは、さほどの問題ではないのかもしれません。もちろん人にもよりますしその状況にもよると思いますが、その見知らぬ男が母と娘の間の“配電盤”の役目をしてくれるのだとしたら、部屋や服を見られることはさしたる問題ではないのかもしれません。
>娘が生きていて帰ってくる希望があるなら、部屋も掃除しておかしくないですし。
その希望は、『僕』が現れたことによって初めて持つことができたのではないでしょうか。前にも書きましたように、母親は娘を理解しようと幾度となく娘の部屋に入ったのでしょう。何度目かに娘の想念が、光の海がつくりだしたほんのちょっとした歪みの中から、娘の形をとって現われたのだと思います。そのあり得ない、信じがたい出来事を経験して以来、母親は部屋に鍵をかけ開かずの間にしたのだと思います。ですから、見も知らない“学生”である『僕』を娘の部屋に入れたのは、母親の藁をもつかむ気持からではないか?と先に書きました。
>靴が綺麗にされていたのは、たぶんそれが玄関にあったからだしょう。或いは下駄箱かな?
>異界の物には抵抗があっても、こちらの世界の物にはまだ抵抗が無いというか…
そのとおりだと思います。というか、靴を綺麗にすることによって娘を待つ気持ちを奮い立たせているとも考えられます。象徴的な意味で、娘の靴を磨くことは娘に対する愛情の証として大事なことだったのかもしれません。
>大事に品よく大人しく育ててきた箱入り娘が闘争によって人が変わってしまったとしたら、ショックや失望からそうなってもおかしくないのかも…
当時、学生運動にのめり込んでいった学生と、その親との確執は深刻なものがあり、男女にかかわらずそのような例はいくらでもありました。第一の部分で60年代の学生運動について書いたのも、多少なりとも参考になればという気持ちからでした。僕のようなノンポリ学生でさえ、好むと好まざるとに関わりなくそのような闘争の場に巻き込まれたり、またその運動にシンパシーを感じていましたから。少なくとも68年の秋までは、多くの一般学生及び多衆は学生運動に好意を寄せていたと思います。それが崩れ、ノンポリ学生や一般大衆と学生運動の乖離が始まったのは、69年の東大安田講堂の闘争の頃からだったと思います。
それでは、第四の部分を書き終えたらまた載せます。
じゃがいもうさぎ。さん、INOさん、みんさん、こんにちは。
実は先週、思いもよらないことが起きてしまいました。
酷使し続けたデスクトップが、突然ストライキをおこし
起動しなくなってしまいました。
復旧を試みてみましたが、僕の手には負えないようなので
専門家を頼んでいるところなのですが、いつ来てくれることやら(苦)
いまは、旅行用のノートでアクセスしているのですが、最悪なことに
書いていた第四の部分のバックアップをしていなかったので、書いたことを
思い出しながらなんとか格好をつけることができました。
さらに、この「午後の最後の芝生」が村上春樹の小説群のなかに
占める位置について書き始めていたのですが、それも書き終えた段階で
載せさせていただこうと思っています。
実は先週、思いもよらないことが起きてしまいました。
酷使し続けたデスクトップが、突然ストライキをおこし
起動しなくなってしまいました。
復旧を試みてみましたが、僕の手には負えないようなので
専門家を頼んでいるところなのですが、いつ来てくれることやら(苦)
いまは、旅行用のノートでアクセスしているのですが、最悪なことに
書いていた第四の部分のバックアップをしていなかったので、書いたことを
思い出しながらなんとか格好をつけることができました。
さらに、この「午後の最後の芝生」が村上春樹の小説群のなかに
占める位置について書き始めていたのですが、それも書き終えた段階で
載せさせていただこうと思っています。
第四の部分です。
芝刈り仕事のあと、『僕』はドライブインでまどろみ、出た後も車の中で物思いにふけります。いろんな細々とした疲れが『僕』に向かって押し寄せてきて、運転するのをあきらめ煙草をもう一本吸います。ここで読み手の僕は、ちょっと待てよと思わざるを得ません。19歳の『僕』に押し寄せてきた細々とした疲れとはどういうことでしょう?たとえ恋人に振られたからといって、これでは人生に疲れた中年のおっさんのようです(笑)。本来なら元気いっぱいであるはずの19歳の青年が持つ疲れとは、芝刈りという肉体労働や、無理に飲まされたアルコールのせいであるとは思えません。そこには、もっと深い心の奥底から湧き上がってきた諸々の疲れがあるはずです。それがどのような疲れなのか、情報の少ないこの短編の中から、いくつかヒントを探してみたいと思います。
≪素晴らしい天気だった。女の子と二人で夏の小旅行に出かけるには最高の日よりだ。僕は冷やりとした海と熱い砂浜のことを考えた。それからエアー・コンディショナーのきいた小さな部屋とぱりっとしたブルーのシーツのことを考えた。それだけだった。それ以外には何も考えつけなかった。砂浜とブルーのシーツが交互に頭に浮かんだ。≫
小説家という人々は、当然ながら考えに考えた末に使う言葉を選ぶと言います。村上春樹自身も、句読点を打つ場所についてさえ、推敲を重ねた末に打つという意味のことをどこかに書いていました。とするならば、上の文章には興味深い点があるのではないでしょうか。ここで作者は、“恋人”ではなく“女の子”という言葉を使っています。『僕』が夢想する夏の小旅行の相手は、とくに“恋人”とではなくても不特定の“女の子”でよく、小旅行の目的の第一は“冷やりとした海と熱い砂浜”、そして“エアー・コンディショナーのきいた小さな部屋とぱりっとしたブルーのシーツ”に重点が置かれています。そして“それ以外には何も考えつけなかった。砂浜とブルーのシーツが交互に頭に浮かんだ。”と書いています。つまり、この夢想の中に“恋人”が占める場所はなく、『僕』の意識の中には不特定の“女の子”という、夏の小旅行に必要な従属的な存在があるにすぎないようにも取れます。もちろん従属的な存在といっても、もし小旅行に行くとしたら相手は“恋人”ということになるのでしょうけど。
この短編の最初から“恋人”に関する記述を拾い読みしてみたのですが、『僕』の“恋人”に対する記憶が書かれているに過ぎず、“恋人”がどのような人であるかその人物像に関する記述は一切ありません。それどころか、
≪僕が彼女をほんとうに好きだったのかどうか、これは今となってはよくわからない。≫
と書き、芝刈りを終えたあと、絨毯のようになめらかに刈れた芝を見て満足のいく出来だったと自画自賛し、その直後“恋人”からの手紙に書かれていたことが頭をよぎります。
≪「あなたのことは今でもとても好きです」中略。「やさしくてとても立派な人だと思っています。でもある時、それだけじゃ足りないんじゃないかという気がしたんです。中略。あと何年かたったらもっとうまく説明できるかもしれない。でも何年かたったあとでは、たぶん説明する必要もなくなってしまうんでしょうね」
人と人との関係は、求め合い与え合うものです。それが男女の関係、ましてや遠距離恋愛であればなおさらのことでしょう。ところが芝刈りを終えたそのときに、“恋人”からの手紙の重要な一節が頭をよぎったにもかかわらず、『僕』は自省の念すら持つことなく水道で顔を洗い道具類の片づけをし、女主人とビールを飲みながら芝生を眺めます。生きた生身の女性である“恋人”は、常に確かなものを求め日々成長してゆきます。故郷であるかもしれない『僕』の街すら、日々変わってゆくのです。時とともにものごとは流れ変わってゆくにもかかわらず、『僕』はそれに気がつかないかのように“芝刈り的自己完結的生き方”に埋没して過ごしてきたようです。さらにもう一度第三の部分で言及した、この短編の核心部分を振り返ってみたいと思います。
下に続く↓
芝刈り仕事のあと、『僕』はドライブインでまどろみ、出た後も車の中で物思いにふけります。いろんな細々とした疲れが『僕』に向かって押し寄せてきて、運転するのをあきらめ煙草をもう一本吸います。ここで読み手の僕は、ちょっと待てよと思わざるを得ません。19歳の『僕』に押し寄せてきた細々とした疲れとはどういうことでしょう?たとえ恋人に振られたからといって、これでは人生に疲れた中年のおっさんのようです(笑)。本来なら元気いっぱいであるはずの19歳の青年が持つ疲れとは、芝刈りという肉体労働や、無理に飲まされたアルコールのせいであるとは思えません。そこには、もっと深い心の奥底から湧き上がってきた諸々の疲れがあるはずです。それがどのような疲れなのか、情報の少ないこの短編の中から、いくつかヒントを探してみたいと思います。
≪素晴らしい天気だった。女の子と二人で夏の小旅行に出かけるには最高の日よりだ。僕は冷やりとした海と熱い砂浜のことを考えた。それからエアー・コンディショナーのきいた小さな部屋とぱりっとしたブルーのシーツのことを考えた。それだけだった。それ以外には何も考えつけなかった。砂浜とブルーのシーツが交互に頭に浮かんだ。≫
小説家という人々は、当然ながら考えに考えた末に使う言葉を選ぶと言います。村上春樹自身も、句読点を打つ場所についてさえ、推敲を重ねた末に打つという意味のことをどこかに書いていました。とするならば、上の文章には興味深い点があるのではないでしょうか。ここで作者は、“恋人”ではなく“女の子”という言葉を使っています。『僕』が夢想する夏の小旅行の相手は、とくに“恋人”とではなくても不特定の“女の子”でよく、小旅行の目的の第一は“冷やりとした海と熱い砂浜”、そして“エアー・コンディショナーのきいた小さな部屋とぱりっとしたブルーのシーツ”に重点が置かれています。そして“それ以外には何も考えつけなかった。砂浜とブルーのシーツが交互に頭に浮かんだ。”と書いています。つまり、この夢想の中に“恋人”が占める場所はなく、『僕』の意識の中には不特定の“女の子”という、夏の小旅行に必要な従属的な存在があるにすぎないようにも取れます。もちろん従属的な存在といっても、もし小旅行に行くとしたら相手は“恋人”ということになるのでしょうけど。
この短編の最初から“恋人”に関する記述を拾い読みしてみたのですが、『僕』の“恋人”に対する記憶が書かれているに過ぎず、“恋人”がどのような人であるかその人物像に関する記述は一切ありません。それどころか、
≪僕が彼女をほんとうに好きだったのかどうか、これは今となってはよくわからない。≫
と書き、芝刈りを終えたあと、絨毯のようになめらかに刈れた芝を見て満足のいく出来だったと自画自賛し、その直後“恋人”からの手紙に書かれていたことが頭をよぎります。
≪「あなたのことは今でもとても好きです」中略。「やさしくてとても立派な人だと思っています。でもある時、それだけじゃ足りないんじゃないかという気がしたんです。中略。あと何年かたったらもっとうまく説明できるかもしれない。でも何年かたったあとでは、たぶん説明する必要もなくなってしまうんでしょうね」
人と人との関係は、求め合い与え合うものです。それが男女の関係、ましてや遠距離恋愛であればなおさらのことでしょう。ところが芝刈りを終えたそのときに、“恋人”からの手紙の重要な一節が頭をよぎったにもかかわらず、『僕』は自省の念すら持つことなく水道で顔を洗い道具類の片づけをし、女主人とビールを飲みながら芝生を眺めます。生きた生身の女性である“恋人”は、常に確かなものを求め日々成長してゆきます。故郷であるかもしれない『僕』の街すら、日々変わってゆくのです。時とともにものごとは流れ変わってゆくにもかかわらず、『僕』はそれに気がつかないかのように“芝刈り的自己完結的生き方”に埋没して過ごしてきたようです。さらにもう一度第三の部分で言及した、この短編の核心部分を振り返ってみたいと思います。
下に続く↓
≪僕は恋人のことを考えた。そして彼女がどんな服を着ていたか思い出してみた。まるで思いだせなかった。僕が彼女について思い出せることは全部漠然としたイメージだった。僕が彼女のスカートを思い出そうとするとブラウスが消え失せ、僕が帽子を思い出そうとすると、彼女の顔は誰かべつの女の子の顔になっていた。ほんの半年前のことなのに何ひとつ思い出せなかった。結局のところ、僕は彼女についていったい何を知っていたのだろう?≫
“恋人”の立場になってみれば、ひどい話です。これでは“恋人”に振られても仕方ありません。結局のところ『僕』は、生身の女性である“恋人”を愛するという次元とは別の、彼女に代表される変わることのないはずの“過去”にしがみついていたものと思われます。
≪彼女(傍点)の存在が少しずつ部屋の中に忍び込んでいるような気がした。彼女(傍点)はぼんやりとした白い影のようだった。顔も手も足も、何もない。光の海が作り出したほんのちょっとした歪みの中に彼女(傍点なし)はいた。僕はウォッカ・トニックをもう一杯飲んだ。≫
この文章の中に、彼女という単語が三回でてきます。最初の二度は傍点付きで、三番目の彼女は傍点がありません。この二回の傍点付き“彼女”と傍点なしの“彼女”は、作者がある意図を持って区別をつけたものに違いありません。思うに、二度の傍点付きの“彼女”は部屋の主で、その娘の存在を感じているうちに、“娘”から“恋人”へとその存在が『僕』の中ですり替わって行ったのではないでしょうか。そして核心の部分の言葉へと向かいます。
≪前略。「問題は……彼女がいろんなものになじめないことです。自分の体やら、自分の考えていることやら、自分の求めていることやら、他人が要求していることやら……そんなことにです」≫
『僕』は、この言葉の意味していることはわかるが、それが誰から誰に向けられた言葉なのかがわかりません。そして≪僕はとても疲れていて、眠りたかった。眠ってしまえば、いろんなことがはっきりするような気がした。≫という思いにとらわれます。たとえはっきりしても、自分が楽になれるとは思えないことを知っていながら・・。これは逃避以外のなにものでもありません。自分は“芝刈り的”生き方に逃げ、たとえ楽になれなくとも他力本願的な解決を望んでいるようにも思えます。このとき『僕』は、漠然とながら、部屋の主である娘の存在を通して、“恋人”の求めていたことや自分の置かれたすべての状況を理解したのだと思います。そして、そのことをドライブインから出たあと、車の中ではっきりと認識するのです。
“恋人”の立場になってみれば、ひどい話です。これでは“恋人”に振られても仕方ありません。結局のところ『僕』は、生身の女性である“恋人”を愛するという次元とは別の、彼女に代表される変わることのないはずの“過去”にしがみついていたものと思われます。
≪彼女(傍点)の存在が少しずつ部屋の中に忍び込んでいるような気がした。彼女(傍点)はぼんやりとした白い影のようだった。顔も手も足も、何もない。光の海が作り出したほんのちょっとした歪みの中に彼女(傍点なし)はいた。僕はウォッカ・トニックをもう一杯飲んだ。≫
この文章の中に、彼女という単語が三回でてきます。最初の二度は傍点付きで、三番目の彼女は傍点がありません。この二回の傍点付き“彼女”と傍点なしの“彼女”は、作者がある意図を持って区別をつけたものに違いありません。思うに、二度の傍点付きの“彼女”は部屋の主で、その娘の存在を感じているうちに、“娘”から“恋人”へとその存在が『僕』の中ですり替わって行ったのではないでしょうか。そして核心の部分の言葉へと向かいます。
≪前略。「問題は……彼女がいろんなものになじめないことです。自分の体やら、自分の考えていることやら、自分の求めていることやら、他人が要求していることやら……そんなことにです」≫
『僕』は、この言葉の意味していることはわかるが、それが誰から誰に向けられた言葉なのかがわかりません。そして≪僕はとても疲れていて、眠りたかった。眠ってしまえば、いろんなことがはっきりするような気がした。≫という思いにとらわれます。たとえはっきりしても、自分が楽になれるとは思えないことを知っていながら・・。これは逃避以外のなにものでもありません。自分は“芝刈り的”生き方に逃げ、たとえ楽になれなくとも他力本願的な解決を望んでいるようにも思えます。このとき『僕』は、漠然とながら、部屋の主である娘の存在を通して、“恋人”の求めていたことや自分の置かれたすべての状況を理解したのだと思います。そして、そのことをドライブインから出たあと、車の中ではっきりと認識するのです。
≪何もかもが遠い世界で起こった出来事みたいな気がした。双眼鏡を反対にのぞいた時みたいに、いやに鮮明で不自然だった。≫
この双眼鏡の比喩は、確か別の作品でも使っていたようにも思います。『僕』が気付き始めた現実は、自らのアイデンティティーの確立をせまっているのですが、それはどこか遠い世界で起きたことのようで、しかも嫌に鮮明で不自然なもののように見えたのです。
≪「あなたは私にいろんなものを求めているのでしょうけど」と恋人は書いていた。「私は自分が何かを求められているとはどうしても思えないのです」≫
“恋人”は、人と人との関係は求め合い与え合うものだと教えているのです。しかし『僕』は、
≪僕が求めているのはきちんと芝を刈ることだけなんだ、と僕は思う。最初に機械で芝を刈り、くまででかきあつめ、それから芝刈ばさみできちんと揃える―――それだけなんだ。僕にはそれができる。そうするべきだと感じているからだ。
そうじゃないか(傍点)、と僕は声に出して言ってみた。
返事はなかった。≫
負け犬のようにそう思い、そうじゃないかと声に出して言ってみます。誰も返事をしてくれないことも、誰も『僕』のこのような生き方を理解してくれないことも、すでに『僕』自信が気付いているのです。ここにあるのは、“恋人”を失っただけではなく、その“恋人”の背後にある幼児期からの想い出、友達、海や砂浜を含むすべての自分を抱擁し保護してくれた過去なのではないかと思います。
≪それ以来、僕は一度も芝を刈っていない。後略≫
芝刈りをやめた後も、『僕』のアイデンティティー確立の試みは長くかかったようです。そしていま、ぐったりとした柔らかい子猫たちを積み重ね、小説という形で読者との対話の試みを始めようとしているのです。
≪記憶というのは小説に似ている。あるいは小説というのは記憶に似ている。中略。
どれだけきちんとした形に整えようと努力してみても、文脈はあっちに行ったりこっちに行ったりして、最後には文脈ですらなくなってしまう。なんだかまるでぐったりした子猫を何匹か積みかさねたみたいだ。生あたたかくて、しかも不安定だ。そんなものが商品になるなんて―――商品だよ―――すごく恥ずかしいことだと僕はときどき思う。本当に顔が赤らむことだってある。僕が顔を赤らめると、世界中が顔を赤らめる。≫
以上が、僕が理解した19歳の青年に向かってきた細々とした疲れです。
このあとに、この短編小説が村上春樹の作品群の中で占める位置について書いたのですが、思い出しながら書き、書き終えたら載せようと思います。
この双眼鏡の比喩は、確か別の作品でも使っていたようにも思います。『僕』が気付き始めた現実は、自らのアイデンティティーの確立をせまっているのですが、それはどこか遠い世界で起きたことのようで、しかも嫌に鮮明で不自然なもののように見えたのです。
≪「あなたは私にいろんなものを求めているのでしょうけど」と恋人は書いていた。「私は自分が何かを求められているとはどうしても思えないのです」≫
“恋人”は、人と人との関係は求め合い与え合うものだと教えているのです。しかし『僕』は、
≪僕が求めているのはきちんと芝を刈ることだけなんだ、と僕は思う。最初に機械で芝を刈り、くまででかきあつめ、それから芝刈ばさみできちんと揃える―――それだけなんだ。僕にはそれができる。そうするべきだと感じているからだ。
そうじゃないか(傍点)、と僕は声に出して言ってみた。
返事はなかった。≫
負け犬のようにそう思い、そうじゃないかと声に出して言ってみます。誰も返事をしてくれないことも、誰も『僕』のこのような生き方を理解してくれないことも、すでに『僕』自信が気付いているのです。ここにあるのは、“恋人”を失っただけではなく、その“恋人”の背後にある幼児期からの想い出、友達、海や砂浜を含むすべての自分を抱擁し保護してくれた過去なのではないかと思います。
≪それ以来、僕は一度も芝を刈っていない。後略≫
芝刈りをやめた後も、『僕』のアイデンティティー確立の試みは長くかかったようです。そしていま、ぐったりとした柔らかい子猫たちを積み重ね、小説という形で読者との対話の試みを始めようとしているのです。
≪記憶というのは小説に似ている。あるいは小説というのは記憶に似ている。中略。
どれだけきちんとした形に整えようと努力してみても、文脈はあっちに行ったりこっちに行ったりして、最後には文脈ですらなくなってしまう。なんだかまるでぐったりした子猫を何匹か積みかさねたみたいだ。生あたたかくて、しかも不安定だ。そんなものが商品になるなんて―――商品だよ―――すごく恥ずかしいことだと僕はときどき思う。本当に顔が赤らむことだってある。僕が顔を赤らめると、世界中が顔を赤らめる。≫
以上が、僕が理解した19歳の青年に向かってきた細々とした疲れです。
このあとに、この短編小説が村上春樹の作品群の中で占める位置について書いたのですが、思い出しながら書き、書き終えたら載せようと思います。
作品の位置づけ。
今回、この「午後の最後の芝生」を注意して読み、さらに三部作を含む周辺の作品群を読み直して思ったのですが、「午後の最後の芝生」という短編は、「中国行きのスロウ・ボート」とともに、その後の村上春樹の膨大な作品群の中で非常に重要な位置を占める作品だと、今更ながら思いました。
この作品が重要であることを書く前に、ふたつお断りしておきたいことがあります。そのひとつは、第三の部分で“我々”という一人称複数を、この短編中で唯一の使用例だと書きましたが僕の記憶違いで、128ページ(文庫本)で既に使われていましたので、二回目でした。
ふたつめは、村上春樹を読むにあたって、60年代後半にという時代背景を知っている必要があるかどうかについてですが、作品の普遍性ということからすると必ずしも知っている必要はないのかもしれません。しかし、作者はいくつかの作品の中で、登場人物に自分が通過してきた時代について語らせています。たとえば「国境の南、太陽の西」で、≪僕らは六〇年代後半から七〇年前半にかけての、熾烈な学園闘争の時代を生きた世代だった。中略。ごくおおまかに言うならそれは、戦後の一時期に存在した理想主義を呑み込んで貪っていくより高度な、より複雑でより洗練された資本主義の論理に対して唱えられたノオだった。後略≫と、主人公に言わせています。またそのような時代の中で、「蛍」や「ノルウェイの森」の主人公である『僕』や直子が、どのような想いで過ごしていたのかをイメージする大きな助けになるのではないでしょうか!?
さて、今回「午後の最後の芝生」を改めて読んで思ったことですが、この短編に記されたエピソード(マテリアル)を、作者は三部作のどこかで使おうと思っていたのではないかということです。ところが三部作のどこにも、このエピソードを使わなければならない必然性を見いだせなかった。そこで、作者は三部作では語りきれなかった何らかの想いをこの短編集に託すために、「羊をめぐる冒険」のあとすぐに書き始めたのではないかと想像するのです。作者は誰かとの対談で、「午後の最後の芝生」を書いた直後、この作品は長編に発展させることができると思った。しかし、時間が過ぎて見るとそうはならなかった。ということを言っていたように記憶しています。とはいうものの、この作品の主人公は「ねじまき鳥クロニクル」の主人公、“岡田亨”として再登場します。もちろん「午後の最後の芝生」の主人公そのままが“岡田亨”ではないにせよ、イメージとして作者は『僕』を、いつか別の作品に登場させるため意識の中であたため続けていたのではないかと思います。
下へ続く↓
今回、この「午後の最後の芝生」を注意して読み、さらに三部作を含む周辺の作品群を読み直して思ったのですが、「午後の最後の芝生」という短編は、「中国行きのスロウ・ボート」とともに、その後の村上春樹の膨大な作品群の中で非常に重要な位置を占める作品だと、今更ながら思いました。
この作品が重要であることを書く前に、ふたつお断りしておきたいことがあります。そのひとつは、第三の部分で“我々”という一人称複数を、この短編中で唯一の使用例だと書きましたが僕の記憶違いで、128ページ(文庫本)で既に使われていましたので、二回目でした。
ふたつめは、村上春樹を読むにあたって、60年代後半にという時代背景を知っている必要があるかどうかについてですが、作品の普遍性ということからすると必ずしも知っている必要はないのかもしれません。しかし、作者はいくつかの作品の中で、登場人物に自分が通過してきた時代について語らせています。たとえば「国境の南、太陽の西」で、≪僕らは六〇年代後半から七〇年前半にかけての、熾烈な学園闘争の時代を生きた世代だった。中略。ごくおおまかに言うならそれは、戦後の一時期に存在した理想主義を呑み込んで貪っていくより高度な、より複雑でより洗練された資本主義の論理に対して唱えられたノオだった。後略≫と、主人公に言わせています。またそのような時代の中で、「蛍」や「ノルウェイの森」の主人公である『僕』や直子が、どのような想いで過ごしていたのかをイメージする大きな助けになるのではないでしょうか!?
さて、今回「午後の最後の芝生」を改めて読んで思ったことですが、この短編に記されたエピソード(マテリアル)を、作者は三部作のどこかで使おうと思っていたのではないかということです。ところが三部作のどこにも、このエピソードを使わなければならない必然性を見いだせなかった。そこで、作者は三部作では語りきれなかった何らかの想いをこの短編集に託すために、「羊をめぐる冒険」のあとすぐに書き始めたのではないかと想像するのです。作者は誰かとの対談で、「午後の最後の芝生」を書いた直後、この作品は長編に発展させることができると思った。しかし、時間が過ぎて見るとそうはならなかった。ということを言っていたように記憶しています。とはいうものの、この作品の主人公は「ねじまき鳥クロニクル」の主人公、“岡田亨”として再登場します。もちろん「午後の最後の芝生」の主人公そのままが“岡田亨”ではないにせよ、イメージとして作者は『僕』を、いつか別の作品に登場させるため意識の中であたため続けていたのではないかと思います。
下へ続く↓
村上春樹は言葉に対し非常に強い不信感を持っている、ということをどこかで読んだ記憶があります。これは、60年代後半を学生として過ごした者なら、個人差はあっても多かれ少なかれ持っているのだろうと思います。それは、語られていた言葉がある時期を過ぎると、あとかたもなく胡散霧消してしまったからです。その経緯は、「ノルウェイの森」に描写されている通りです。言葉に不信感を抱きながらも、また≪完璧な文章なんて存在しない≫という想いを持ちながらも、≪像は平原に還り僕はより美しい言葉で世界を語り始めるだろう≫という希望を捨てず、≪ぐったりとしていて、とてもやわらかい≫子猫たちを積み重ねるように、村上春樹は小説を書き始めたのです。これは、「風の歌を聴け」から「1Q84」に至るまで、村上春樹の作品に通低しているものだと思います。その子猫たちを積み重ねるようにして、作者は常に二つの世界を書き始め、ときにそれは『僕』と『鼠』という形であったり、「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」のような社会の中を生きる『私』と脳内世界の『僕』であったりしますが、この作法も「1Q84」に至るまで一貫しています。
そして子猫をより分けあちら側とこちら側の世界を描き、小指のない女の子(消えてしまう登場人物という文脈で)を初めとして登場人物があちら側に行ってしまい、キキや芝刈り仕事の雇い主の娘のように、あちら側からのメッセージを送らせたりします。ただ「ねじまき鳥クロニクル」以降、「スプートニクの恋人」あたりから様相は変わってきます。消えた女の子(すみれ)がこちら側の世界に戻ってくるようになったのです。なにはともあれ、村上春樹世界がその後発展してゆく多くの萌芽と思えるのもが、この短い短編「午後の最後の芝生」には見てとれると思います。
以上長くなりましたが、読んでくださった方がいたとしたら、お礼申し上げます。
そして子猫をより分けあちら側とこちら側の世界を描き、小指のない女の子(消えてしまう登場人物という文脈で)を初めとして登場人物があちら側に行ってしまい、キキや芝刈り仕事の雇い主の娘のように、あちら側からのメッセージを送らせたりします。ただ「ねじまき鳥クロニクル」以降、「スプートニクの恋人」あたりから様相は変わってきます。消えた女の子(すみれ)がこちら側の世界に戻ってくるようになったのです。なにはともあれ、村上春樹世界がその後発展してゆく多くの萌芽と思えるのもが、この短い短編「午後の最後の芝生」には見てとれると思います。
以上長くなりましたが、読んでくださった方がいたとしたら、お礼申し上げます。
うりずんさん、長文お疲れ様でした!!
とても読みごたえありで、私の学生時代の卒論よりずっとよくまとまってて、本当に大作ですね。
また後で改めて頭から読んでみます。そしてこの作品もまた読み返したくなりました。
長文で皆さんに呆れられないかとのことですが、私も昔全く同じこと考えてました。
某読書会のお題だった風の歌を聴けで、みんな何行かの書き込みくらいなのに、私だけ日記三ページに渡って長々と解釈を書いてしまいました…。
ちょっとやりすぎたかなーと後になって反省してみたり。
なので、好きなことを好きなだけ書ける場所を自分で作ったんです。
どんなに長い春樹トークをしても大丈夫なように。笑
今は諸事情であんまりネットに出てこられないのですが、こうやって参加者の皆様のアツい書き込みで場が盛り上がってくれると本当に嬉しいです(*^^*)
遠慮せずどんどん書き込みにきて下さいね。
お疲れ様でした&ありがとうございました(^_^)v
とても読みごたえありで、私の学生時代の卒論よりずっとよくまとまってて、本当に大作ですね。
また後で改めて頭から読んでみます。そしてこの作品もまた読み返したくなりました。
長文で皆さんに呆れられないかとのことですが、私も昔全く同じこと考えてました。
某読書会のお題だった風の歌を聴けで、みんな何行かの書き込みくらいなのに、私だけ日記三ページに渡って長々と解釈を書いてしまいました…。
ちょっとやりすぎたかなーと後になって反省してみたり。
なので、好きなことを好きなだけ書ける場所を自分で作ったんです。
どんなに長い春樹トークをしても大丈夫なように。笑
今は諸事情であんまりネットに出てこられないのですが、こうやって参加者の皆様のアツい書き込みで場が盛り上がってくれると本当に嬉しいです(*^^*)
遠慮せずどんどん書き込みにきて下さいね。
お疲れ様でした&ありがとうございました(^_^)v
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
村上春樹∽短編小説 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
村上春樹∽短編小説のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人